和漢三才圖會 卷第五十一 魚類 江海無鱗魚 寺島良安
書き下し及び注記 © 2007-2023 藪野直史
(原型最終校訂 2007年 9月27日)
(原型一部訂正 2008年 6月 8日)
(原型最終訂正 2021年 6月 6日)
(再校訂・修正・追補開始2023年 9月18日 午後4:15)
(再校訂・修正・追補終了2023年10月 3日 午前6:45)
[やぶちゃん注:本ページは以前にブログに記載した私の構想している「和漢三才圖會」中の水族の部分の電子化プロジェクトの第二弾である。底本・凡例・電子化に際しての方針等々については、「和漢三才圖會 卷第四十六 介甲部 寺島良安」の冒頭注の凡例を参照されたい。なお、本巻では本文中に有意な縦罫が単一項目の途中に多く現われるので、途中の縦罫のみは実際の罫線ですべて入れることとした。なお、本巻の冒頭には目次がなく、「卷第五十 河湖無鱗魚」の頭に巻五十と一緒に掲げられているため、ここでは本ページ相当の項目部分のみを抽出して(冒頭の総目録標題名と巻五十河湖無鱗魚の目録は省略。折り返し丁中央の縦罫の「目録」標題は再現した)最初に置く。目次の項目の読みはママ(該当項のルビ以外に下に書かれたものを一字空けで示した。なお、本文との表記の異同も認められるが、注記はしていない)。なお、原文では横に三列の罫があり、縦に以下の順番に書かれている。項目名の後に私の同定した和名等を[ ]で表示した。また、良安は、「目次」では(うおへん)を持つ漢字を総て「𩵋」とするが、一般的な正字の(うおへん)「魚」としたことを謂い添えておく。【二〇二三年九月十八日追記】私のサイトの古層に属する十五、六年前の作品群で、当時はユニコードが使用出来ず、漢字の正字不全が多く、生物の学名を斜体にしていないなど、不満な箇所が多くある。今回、意を決して全面的に再校訂を行い、修正及び注の追加を行うこととした。幾つかのリンクは機能していないが、事実、そこにその記載や引用などがあったことの証しとして、一部は敢えて残すこととした。さても……サイト版九巻全部を終えるには、かなり、かかりそうである。【二〇二三年十月三日追記】なお、本巻の再校訂版の全終了公開は、二〇〇六年五月十八日のニフティのブログ・アクセス解析開始以来、私のブログ「Blog鬼火~日々の迷走」が、昨夜の午後八時前に、2,010,000アクセスを突破した記念として公開することとした。]
■和漢三才圖會 無鱗魚 卷ノ五十目録 ○ 一
[やぶちゃん注:「○」と「一」のスペースはママ。くどいが、この目録自体は卷之五十の頭にあるため、以上の折り返し丁中央の縦罫の「目録」標題は「卷ノ五十」となっている。誤りではないので注意されたい。]
卷之五十一
江海無鱗魚
《改ページ》
鯨(くぢら) [クジラ]
鱣(ふか) [チョウザメ/サメ]
鱘(かぢとをし) [ハシナガチョウザメ/カジキ]
鮪(しび) はつ [チョウザメ/マグロ]
堅魚(かつを) [カツオ]
鮠(なめいを) [スナメリ]
海豚(いるか) [イルカ]
河豚(ふぐ) [フグ]
鰐(わに) [ワニ]
鮫(さめ) [サメ]
皮剥魚(かははぎ) [カワハギ]
馬鮫(さはら) さごし [サワラ]
文鰩(とびいを) [トビウオ]
[やぶちゃん字注:「鰩」の字は(つくり)は現在の簡体字「鳐」のそれに近いが、最も下の部分は「止」のように見える奇体な字体である。正字で示した。]
華臍魚(あんごう) [アンコウ]
海鷂魚(ゑい) こめ ゑざれ [エイ]
鯧(まなかつを) [マナガツオ]
魴(かゝみいを) まといを [イトヒキアジ]
嫗背魚(うぼせ) [イボダイ]
仁良岐(にらぎ) [ヒイラギ]
鰈(かれい) かれゑひ [カレイ]
牛舌魚(うしのした) [ウシノシタ]
鰺(あぢ) [アジ]
楂魚(うきゝ) まんぼう [マンボウ]
海鰻(はむ) はも [ハモ]
《改ページ》
■和漢三才圖會 無鱗魚 卷五十目録 ○ 二
[やぶちゃん注:「○」と「一」のスペースはママ。]
阿名呉魚(あなご) [アナゴ]
鱭(たちいを)
[やぶちゃん注:実際には、本項は、以下の本文では、ここには入らず、本巻無鱗魚の最後、「舩留魚」の後に置かれている。「目録」の最後に改めて比定した魚種とともに再掲しておく。]
玉筋魚(いかなご) かますこ [イカナゴ]
鱠殘魚(しろいを) [シラウオ]
鱊(ちりめんこあい) [(チリメンジャコ=イワシ類等の稚魚を主体とした乾燥食品として食用に耐え得る魚類稚魚の総称)]
章魚(たこ) [タコ]
石距(てなかだこ) [テナガタコ]
望潮魚(いひたこ) [イイダコ]
烏賊魚(いか) [イカ]
柔魚(たちいか) するめいか [スルメイカ]
海䑕(とらご) [ナマコ]
[やぶちゃん注:「䑕」は「鼠」の異体字。]
海䖳(くらげ) [クラゲ]
綳魚(すゝめいを) うみすゝめ [ハリセンボン・ウミスズメ]
鰕(ゑび) [エビ]
紅鰕(いせゑひ) かまくらゑび [イセエビ]
海糠魚(あみ) [アミ(他種混入)]
鰕姑(しやこ) しやくなげ [シャコ]
海馬(かいば) [タツノオトシゴ]
舩留魚(ふなとめ) [コバンザメ]
[やぶちゃん注:先に記したように、本文では、最後に以下の項が入る。
鱭(たちいを) [トゲウナギ/タチウオ]
魚之用《改ページ》
鱗(うろこ) [鱗(うろこ)]
鰓(あぎと) ゑら [鰓(えら)]
魚丁(かしらほね) [鯛の鯛(タイのタイ)=烏口骨及び肩甲骨]
鰭(はた) ひれ [鰭(ひれ)]
腴(つちすり) [腹部(つちずり/すなづり)]
鯝(いをのわた) [腸と浮袋を主体とした内臓全般]
[やぶちゃん注:本文では、この間に、
鰾(にべ) [鰾(うきぶくろ)]
が入る。]
鯁(いをのほね) [骨]
䱊(いをのこ) [卵(はらご/はららご)]
炙(やきもの) [焼き物]
𦞦(あつもの) 羹(同) [汁の多い魚介類の煮物・スープ]
[やぶちゃん字注:(同)の「同」は「羹」のルビ位置に小さくある。前のルビの「あつもの」に「同じ」の意。]
※(いりもの) [汁の少ない魚介類の煮物]
[やぶちゃん字注:※=「𩽌」の(つくり)から「山」を除去した「雋」とする字体。]
膾(なます) [膾]
魚軒(さしみ) [刺身]
鮓(すし) [熟れ鮓]
蒲鉾(かまぼこ) [蒲鉾]
魚醢(しゝひしを) 南蠻漬 [魚醤・南蛮漬]
鱁鮧(しほから) [塩辛]
鰾(にべ)
[やぶちゃん注:先に記したように、本文では、ここにはない。]
腌(しをもの) 鹽引 [塩漬]
鮿(ひもの) 未乾魚(なまび) [干物・生乾し]
魥(めざし) [目刺]
肴(さかな) [酒肴]
□本文
■和漢三才圖會 江海無鱗魚 卷ノ五十一 ○一
和漢三才圖會卷第五十一
魚類【江海中無鱗魚】
くじら
鯨【音擎】
唐音キン
䲔【本字】 海鰌
勇魚【万葉集訓
伊佐奈
古呼魚皆曰奈】
雄曰鯨雌曰鯢
【和名久知良】
[やぶちゃん字注:以上六行は、前三行の下に入る。]
三才圖會云鯨海中大魚也其大橫海吞舟穴處海底出
穴則水溢謂之鯨潮或曰出則潮下入則潮上其出入有
節大者長千里小者數丈一生數万子嘗以五六月就岸
生子至七八月導率其子還大海中皷浪成雷濆沫成雨
水族驚畏莫敢當者然其死也有彗星應之雄者爲鯨雌
《改ページ》
者爲鯢或曰死於沙上得之者皆無目俗言其目化爲朋〔→明〕
月珠
古今詩話云海岸有獸名蒲牢聲如鐘而性畏鯨鯨躍輒
鳴故鑄鐘作蒲牢形其上爲鯨形
藻塩 潮ふく鯨のいきとみゆる哉沖に村立夕立の雲
△其狀畧似鰌故名海鰌肥圓長與周等其色蒼黑而無
鱗鼻上骨髙起項上頸前有吹潮之穴口𤄃下唇長於
上唇而出于頷前舌亦長廣其大鯨有三十三尋【約十六丈
余】所謂長千里者甚妄也
齒 大如屐齒之尖齗白切片之名蕪骨
眼 繊近于口吻而下鳥〔→烏〕珠如水精之磨而軟
鬛 出口中兩邊其數有三百六莖純黒色名筬削磨則
美潤長自三四尺至丈餘廣五六寸厚五六分工匠用
之作笄揥及尺秤之類
鬐 外黒内白色名達波長自八九尺至丈餘廣四五尺
《改ページ》
■和漢三才圖會 江海無鱗魚 卷ノ五十一 ○二
骨 近肉圓骨名法師骨此亦漁家採油也
筯 赤黃色太徑三寸許細割破之浸泔水取去油氣用
之今爲唐弓弦以打木綿
[やぶちゃん注:「弓」は原本では「グリフウィキ」のこれ。「弓」の異体字。]
大小膓 長五十条許故名百尋煑食之能治久泄
陰莖 名多計里大者一丈其雌陰戸及乳房亦兼備
尾 有岐黒色尾之上圓肥處名尾脛其味極美不可言
糞 有黑白其白者希焉泛水上如白泡采得晒乾似蛇
骨治痘瘡紫黒下䧟燒之薫煙有効
皮 黑皮與赤肉之交有白脂熬之油最多凡方三寸厚
一尺皮可得油一升
凡鯨有六種性喜嗜鰯不敵于諸魚海舶若觸尾鬐則必
覆冬自北行南春自南去北肥州五島平戸邊節分前
後爲盛紀州熊野浦仲冬爲盛捕之刺鯨鉾呼曰森用
樫木作柄鉾頭着繩繫舩柱其鉾中鯨則脫柄入肉隨
鯨動作深入肉中不㧞〔=拔〕鉾柄雖脫着繩故不失【此外森之製數
《改ページ》
品有】掌一舩進退人呼曰羽指被長袖短袗宛如軍配近
頃遠用大繩網〔→綱〕豫繫之擲森故百無一失
世美 鯨六種中爲最上大者十余丈其子鯨二三丈許
大抵十三尋者全體取油得二百斛七尋者油得四十
斛惟八尋者油少漸十斛許
座頭 大者不過四五丈鬐長丈許一片黑一片白其肚
皮層層作畦如編竹呼名簀子皮背有方二尺許疣鰭
似琵琶形彷彿瞽者負琶故名座頭非盲魚也其余與
世美同爾雖中森鉾能遁去但子持鯨易得先使兒鯨
防殺之半死則母鯨不忍去以身掩子時可殺得後又
捕子鯨蓋用今大網〔→綱〕則座頭亦不能遁去
長須 形色似世美此又背有疣鬐大者十丈許常沈水
底而浮者稀矣故難得
鰮鯨 毎逐鰮來其大者不過二三丈肉薄脂少故漁人
不好殺之
《改ページ》
■和漢三才圖會 江海無鱗魚 卷ノ五十一 ○三
真甲 有大牙如犢牛角此亦好逐鰮來脂少故不好殺
之西海希有而紀勢総常之海有之其牙類象牙猪牙
切磋作噐或造人牙齒以爲入齒
小鯨 淡黒或灰白色鬛白長一尺五六寸廣三寸許厚
二三分呼曰白鬚各類其大鯨大者不過一二丈
有魚虎者其齒鰭如剱鉾【詳有鱗魚之下】數十毎在鯨口傍衝頰
腮其聲聞于外久而鯨困迷開口時魚虎入口中嚙切
其舌根既喰盡出去鯨乃斃謂之魚虎切偶有之浦人
𫉬之海中無雙大魚爲纔小魚絶命矣
凡截鯨刀宜用生鐵也鋼鐵却不佳蓋鯨全體可食可取
油用其齒鬛鰭可爲噐寔此本朝寳貨之類乎中華亦
有之不如日本之多而見之者希故鯨不載諸本草雖
出于三才圖會其說憶見耳
*
和漢三才圖會卷第五十一
魚類【江海の中〔の〕無鱗魚。】
くじら
鯨【音、擎〔(けい)〕。】
唐音キン
䲔〔(けい)〕【本字。】 海鰌
勇魚(いさな)【「万葉集」に「伊佐奈」と訓ず。古へ、呼びて、魚を皆、「奈」と曰ふ。】
雄を「鯨」と曰ひ、雌を「鯢〔(げい)〕」と曰ふ。
【和名、「久知良」。】
「三才圖會」に云はく、『鯨は、海中の大魚なり。其の大いさ、海に橫たはり、舟を吞み、海底に穴處〔(けつしよ)〕す。穴を出づるに、則ち、水、溢〔(あ)〕ふる。之を「鯨潮〔(げいてう)〕」と謂ふ。或いは、曰ふ、「出づる時は[やぶちゃん注:「時」は送り仮名の中にある。]、則ち、潮〔(しほ)〕、下り、入るる時は、則ち、潮、上る。其の出入、節、有り、と。大なる者、長さ千里、小なる者、數丈。一たび、數万〔(すまん)〕の子を生む。甞〔(かつ):常に。〕て、五、六月を以て、岸に就きて、子を生む。七、八月に至りて、其の子を導-率(みちび)き、大海中に還る。浪を皷〔(こ)〕して、雷を成し、沫(あは)を濆(は)き、雨を成す。水族、驚畏〔(きやうい)〕し、敢て當たる者、莫し。然して、其の死ぬるや、彗星、有りて、之れに應ず。雄なる者、「鯨」と爲し、雌なる者、「鯢〔(げい)〕」と爲す。或る人[やぶちゃん注:「人」は送り仮名にある。]の曰はく、「沙上に死する之れを得る〔(とき)〕は、皆、目、無し。俗に言ふ、『其の目、化して、「明月珠」と爲る。』と。』と。
「古今詩話」に云はく、『海岸に、獸〔じう〕、有り。「蒲牢〔(ほらう〕」と名づく。聲、鐘ごとくして、性、鯨を畏る。鯨、躍れば、輒〔(すなは)〕ち、鳴く。故に鐘を鑄〔(い)〕るに、「蒲牢」の形を作り、其の上に「鯨」の形を爲〔(つく)〕る。』と。
「藻塩」 潮〔(うしほ)〕ふく鯨〔(いさな)〕のいきとみゆる哉〔(かな)〕沖に村立〔(むらた)〕つ夕立の雲
△其の狀〔(かたち)〕、畧〔(ほぼ)〕、「鰌〔(どぜう)〕」に似る。故に「海鰌〔(かいしう)〕」と名づく。肥えて、圓〔(まろ)〕く、長さと、周(めぐ)りと、等し。其の色、蒼黑にして、無鱗。鼻の上の骨、髙く起こり、項〔(うなじ)〕の上・頸〔(くび)〕の前に、潮〔(しほ)〕を吹く穴、有り。口、𤄃〔(ひろ)〕く、下唇、上唇より、長く、頷〔(おとがひ):下顎。〕の前に出でて、舌も亦、長く、廣し。其の大なる鯨、三十三尋(ひろ)有り【約[やぶちゃん注:換算。]するに、十六丈余。】。所謂〔(いはゆ)〕る、長さ、千里と云ふ[やぶちゃん字注:「云」は送りがなの中にあり。]は、甚だ、妄〔(まう)〕なり。
齒 大にして、屐(あしだ)の齒の尖りたるがごとし。齗(はぐき)、白し。之れを切片〔(きわわけ)〕て、「蕪(かぶら)骨」と名づく。
眼〔(まなこ)〕 繊(ほそ)く、口吻に近く、而して、下がる。烏珠〔(ぬばたま):瞳・〕は、水精の磨きたるがごとくにして、軟かなり。
鬛(ひれ〔→ひげ〕) 口中の兩邊に出づ。其の數、三百六莖、有り。純黒色なり。「筬(をさ)」と名づく。削り磨けば、則ち、美しく潤ほひ、長さ三、四尺より、丈餘に至る。廣さ、五、六寸、厚さ五、六分。工匠、之れを用ひて、笄-揥(かんざし)、及び、尺-秤(ものさし)の類に作る。
鬐〔(ひれ)〕 外、黑く、内、白色にして、「達波〔(たつぱ)〕」と名づく。長さ、八、九尺より、丈餘に至る。廣さ四、五尺。
骨 肉に近き圓き骨を「法師骨」と名づく。此れも亦、漁家、油を採るなり。
筯〔(すぢ)〕 赤黃色、太-徑(ふと)さ、三寸ばかり。細かに、之れを割〔(さ)〕き破り、泔水(しろみづ〔:米の研ぎ汁。〕)に浸し、油氣〔(あぶらけ)〕を取り去り、之れを用ひて、今、唐弓〔(たうゆみ)〕の弦(つる)と爲し、以つて、木綿(きわた)を打つ。
大小膓 長さ、五十丈〔:百五十一・五メートル。〕ばかり。故に「百尋(ひろ)」と名づく。之れを、煑〔(に)〕、食ひて、能く「久泄」を治す。
陰莖 「多計里〔(たけり)〕」と名づく。大いなる者、一丈。其れ、雌の陰戸及び乳房、亦、兼備す。
尾 岐〔(また)〕、有り。黑色。尾の上、圓く肥えたる處を「尾脛(〔を〕はばき)」と名づく。其の味、極美、言ふべからず。
糞 黑、白、有り。其の白き者、希れなり。水上に泛〔(ただよ)〕ふ白き泡(あは)のごとし。采〔=採〕り得て、晒し乾して、蛇骨に似たり。痘瘡の紫黑下䧟〔(しこくげかん)〕を治するに、之れを燒き、煙を薫ず。効、有り。
皮 黑皮と赤肉の交(あは)ひ、白き脂〔(あぶら)〕、有り。之れを熬〔(い)り〕て、油、最も多し。凡そ方三寸にして厚さ一尺の皮、油一升を得べし。
凡そ、鯨に、六種、有り。性、喜(この)んで鰯を嗜〔(この)〕んで、諸魚に敵せず。海舶、若し、尾鬐に觸るる時は、[やぶちゃん字注:「時」は送りがなの中にある。]則ち、必ず、覆(くつが)へる。冬は、北より、南に行き、春は、南よりして、北に去る。肥州〔=肥前〕五島・平戸の邊は、節分の前後、盛りと爲し、紀州〔=紀伊〕熊野浦は、仲冬〔:陰暦十一月。〕を盛りと爲して、之れを捕るに、鯨を刺(つ)く鉾〔(ほこ)〕を呼びて「森(もり)」[やぶちゃん注:木製の「銛」。]と曰ふ。樫〔(かし)〕の木を用ひ、柄と作り、鉾の頭に、繩を着けて、舩〔=船〕の柱に繫ぐなり。其の鉾、鯨に中〔(あた)〕れば、則ち、柄、脫けて、肉に入り、鯨の動作に隨ひて、深く、肉の中に入りて、拔けず。鉾の柄、脫〔(ぬ)〕くると雖も、繩を着くる故、失はず【此の外に「森」の製、數品〔(すひん)〕、有り。】。一舩〔(ひとふね)〕の進退を掌(つかさど)る人、呼んで「羽指(〔は〕ざ)し」と曰ふ。長き袖、短き袗〔(ひとへ)〕を被りて、宛(さなが)ら、軍配のごとし。近頃は、遠く大繩(ふとなは)の綱を用ひて、豫(○あらかじ)[やぶちゃん字注:この「○」の意味、不明。]め、之れを繫ぎ、「森」を擲(う)つ。故に、百に、一失、無し。
世美 鯨六種の中、最上たり。大なる者、十余丈、其の子鯨は、二、三丈ばかり。大抵、十三尋の者、全體、油を取れば、二百斛〔こく〕を得、七尋の者は、油四十斛を得、惟だ八尋の者は、油、少なし。漸く、十斛許〔(ばか)〕り。
座頭 大なる者、四、五丈に過ぎず、鬐、長さ、丈ばかり。一片は黑く、一片は白し。其の肚皮〔(はらかは)〕、層層として畦〔(うね)〕を作り、竹を編〔める〕ごとし。呼びて「簀の子皮〔(すのこがは)〕」と名づく。背に、方二尺ばかりの疣鰭〔(いぼひれ)〕有り、琵琶の形に似たり。瞽者〔(こしや):盲人〕の負ふ琶〔=琵琶〕に彷-彿(さもに)たり。故に「座頭」と名づく。盲魚には非ざるなり。其の余、「世美」と同じきのみ。森鉾〔もりほこ)〕に中〔(あた)〕ると雖も、能く遁げ去る。但し、子持ち鯨は得易し。先づ、兒鯨をして、殺す時は、之れを防ぎ、半死にせしめ〔れば〕、[やぶちゃん字注:「時」は送りかなの中にある。]則ち、母鯨、去るに忍びず、身を以つて、子を掩〔(おほ)〕ふ時、殺し得つべし。後、又、子鯨を捕ふ。蓋し、今の大綱を用すれば、則ち、座頭、亦、能く遁〔(のが)れ〕去らず。
長須(ながす) 形・色、「世美」に似たり。此れも又、背、疣鬐〔(いぼひれ)〕有り。大なる者、十丈ばかり。常に水底に沈めて〔→みて〕、浮く者、稀れなり。故に得難し。
鰮鯨(いはしくじら) 毎〔(つね)〕に鰮を逐ひ來〔(きた)〕る。其の大なる者、二、三丈に過ぎず、肉、薄く、脂、少なき故に、漁人、好んで〔は〕、之れを殺さず。
真甲(まつかう) 大なる牙、有り。犢牛(こてい〔:子牛。〕)の角のごとし。此れも亦、好んで鰮を逐ひ來る。脂、少〔なく〕、故に好みて〔は〕之れを殺さず。西海に希れに有りて、紀〔=紀伊〕・勢〔=伊勢〕・総〔=上総〕・常〔=常陸〕の海に、之れ、有り。其の牙、象牙・猪の牙(き)に類す。切磋して、噐〔(うつは)〕に作り、或いは、人の牙齒に造り、以つて、入齒と爲す。
小鯨〔(こくじら)〕 淡(うす)黑く、或いは、灰白色。鬛〔(ひげ)〕白く、長さ、一尺五、六寸、廣さ、三寸ばかり、厚さ、二、三分。呼んで「白鬚〔(しらひげ)〕」と曰ふ。各〔(おのおの)〕、其の大鯨に類す。大なる者、一、二丈に過ぎず。
「魚虎(しやちほこ)」と云ふ者有り[やぶちゃん注:「云」は送りがなにある。]。其の齒・鰭(ひれ)、剱鉾〔(けんぼこ)〕のごとし【「有鱗魚」の下に詳〔(くは)〕し。】。數十〔(すじふ)〕毎〔(つね)〕に鯨の口の傍らに在りて、頰・腮〔(あぎと):あご〕を衝〔(つ)〕く。其の聲、外に聞こゆ。久しくして、鯨、困迷して、口を開く時、魚虎、口〔の〕中に入り、其の舌を、嚙み切り、根、既に喰ひ盡して、出で去る。鯨は、乃〔(すなは)ち〕、斃〔(し)〕す。之れを「魚虎切(しやちぎり)」と謂ふ。偶々、之れ有りて、浦人、之れを獲る。海中の無雙の大魚、纔〔(わづ)〕かの小魚の爲に命を絶つ。
凡そ、鯨を截〔(き)〕る刀、宜しく、生鐵(なまかね)を用ふべし。鋼鐵(あか〔が〕ね)は、却つて、佳(よ)からず。蓋し、鯨、全體、食して可〔にて〕、油を取るに〔も〕用〔にもす〕べし。其の齒・鬛・鰭、噐に爲〔(つく)〕るべし。寔〔(まこと)〕に、此れ、本朝の寳貨の類〔(たぐひ)〕ならんか。中華にも亦、之れ、有りて〔も〕、日本の多きごとくならず、之れを見る者、希れなる故、鯨は、諸本草に載せず。「三才圖會」に出だすと雖も、其の說、憶見のみ。
[やぶちゃん注:分類は多岐にわたる。半可通の私が妙に不完全に叙述するよりも専門家に委ねよう。サイト“AQUAHEAT”「イルカ・クジラの分類表」が最もよい。
・「海底に穴處す」トンデモ誤り。クジラに巣はない。生涯、遊泳し続ける。睡眠しながら泳ぐことも可能であるが、最近、ある種のクジラ類が、何頭もが、海中に垂直に立って、睡眠を取る画像を見た。
・「三才圖會」は、本書が範とした中国の百科全書。一六〇七年に明の王圻(おうき)によって編せられた。しかし、この内容は、良安によって本項の末尾で、「憶測に過ぎない」と手酷く叩かれることとなる。
・「古今詩話」は、東洋文庫版後注によれば、『八巻。明の稽留山樵撰。』、とのみある。
・「節、有り」は、「リズムがある・一定の時間周期がある」ということ(実際には勿論、潮汐現象のことをこう解している)。
・「皷して」の「皷」は「鼓」の俗字。「打って」の意。
・「其の死ぬるや、彗星、有りて、之れに應ず」の民俗は不明であるが、「淮南子」(えなんじ)「覧冥篇」に「鯨魚死而慧星出」(鯨魚、死して、彗星、出づ)とある。彗星は凶兆であるから、大いなるものの死の齎(もたら)す恐怖の類感的イメージか。
・「明月珠」は「真珠」の別称。
・「蒲牢」は、龍の九種の子の一種とし、班固の「西都賦注」に、「鯨」が「蒲牢」を撃つに、「蒲牢」が大いに鳴いた、と記す。但し、小学館「日本国語大辞典」には、『想像上の海獣の名。鯨に襲われると大声を発するとされるので、その首をかたどって鐘のかざりにつけ、撞木を鯨にみたてて、鐘の音が大きいのを願う。また、そのかざりや、そのかざりをつけた鐘。転じて、ひろく鐘のこと』とある。これが現実の如何なる生物(モデル生物)を指すかは、ずっと考察中なのであるが、やはり、鰭脚類か、カイギュウ目の海産哺乳類の可能性が高いような気がする。
・『鐘を鑄るに、「蒲牢」の形を作り、其の上に「鯨」の形を爲る」について。梵鐘は別に「鯨鐘」・「華鯨」・「巨鯨」等とも呼ばれる。梵鐘の頂上にある部分を一般に「竜頭」(りゅうず)と呼ぶが、これは俗称で、本来は「蒲牢」と言った。前記の言い伝えに基づいて、「打てば、大いに鳴る。」の意から造形された。『上に「鯨」の形を爲る』は、竜頭の上にということであろうが、私はそのような多重形状の梵鐘の記載には、今のところ出会っていないし、そのような梵鐘も見たことがない。一般には、撞木を「鯨」に喩えるのではなかろうか。その方が、「蒲牢」の話にぴったりくるように思われるからである。
・「藻塩」は「藻塩草」で、戦国時代の連歌師宗碩(そうせき)の歌学書。連歌創作のための資料として、「万葉集」・「源氏物語」・「古事記」・「奥義抄」などを引用した、歌作のための実用書。私は「藻塩草」を所持していないので校合できないが、東洋文庫版では、以下のように原典との第三句目の異同を記している。
潮(うしほ)ふく鯨のいきとみゆるかな沖にひとむら夕立ちの雲
また、それよりも先行する正徹(しょうてつ)の「草根集」に極めて類似した和歌をネット検索で見出したので、参考までに掲げておく。
潮ふく鯨のいきと見えぬへし興(おき)にひとむらくたる夕立
(潮ふく鯨のいきと見えぬべし沖にひとむらくだる夕立)
・「鰌に似る」? か? しかし、この冒頭の絵を見ていると、あーら、不思議! 似てるわ!
・「三十三尋」の「尋」は両手を広げた長さ、約一・八メートルなので、約五十九・四メートル(後の丈[一丈=三・〇三メートル]換算でも約五十センチメートル)。これは「千里」に文句を言う良安の言葉を借りると、それでも「妄なり」で、ちょっと長すぎる(当初、「三~十三尋」で穏当かと思ったが、底本では、良く見ると、「三」と「十三」の間に熟語を示す「-」がある)。
・「屐」は下駄。
・「蕪骨」は、ここでは「齒」と記されるが、少なくとも、現在の「蕪骨」は、「氷頭(ひず)」とも言い、鯨の頭部上顎を、縦に走っている骨の中の軟骨部分を言う。細く削って、乾燥し、粕漬等にする。九州地方で「松浦漬」と称する。
・「水精」は水晶。「水精」で「すいしょう」とも訓じる。
・「鬛」の字に原本は御覧の通り、『ヒレ』とルビがある。確かに、これは、「魚の顎脇の小鰭(こびれ)」という意味があり、この場合の叙述とも齟齬はないが、本来の意味の「ひげ」とする方が、直後の鬐(ひれ)とも区別し易い。東洋文庫版でも『ひげ』とルビしている。
・「筬」は、本来は「織機の経糸(たていと)を通す櫛状の道具」を指す。昔の一般的な「竹筬」(たけおさ)は、竹で出来た薄い小片を、櫛の歯のように列ね、長方形の框(わく)に入れたもので、その形状が「鯨の髭」と似ていたためであろう。
・「久泄」は、慢性の下痢。ただの消化不良から、潰瘍性大腸炎まで含む。
・「尾脛」は、現在の「オノミ」を指す。「はばき」とは、「脛巾」・「行纏」・「脛衣」等と書く、旅装として、脛に巻きつけるものを指すか。後世の「脚絆」(きゃはん)に当るが、形状が鯨の尾の形に似ている。
・「唐弓」繰綿(くりわた)を打って、不純物を取り去り柔らかくするための道具。弓のように木に弦を張ったもので、古くは、牛の筋を弦として用いたが、後は鯨を用いるようになった。「わたゆみ」「わたうちゆみ」とも言う。
・「百尋」は、現在も「鯨の腸」の異名。ちなみに百尋は百八十メートルに相当する。この呼称は、満更、嘘ではあるまい思って調べてみると、マッコウクジラの腸の長さは実に二百三十メートルという記録がある。看板に偽りなし!
・「糞」は、「龍涎香」(アンバーグリス:Amburgris)を指している。マッコウクジラに特有な大腸内の蠟状の体内結石で、動物性香料として有名である。その生成過程については、核部分にダイオウイカの顎板(カラストンビ)が見つかることから、何らかのイカの成分が関係しているとも言われているが、科学的解明は全くなされていない。重さ五十グラムから五キログラムで、捕獲したマッコウクジラの腸内から直接採取されたり、叙述の通り、海上を浮遊していたり、海岸に打ち上げられたりしたものが利用される。形状には変異が多く(「蛇骨」というのは複数のイカの顎板の突出したものを言うか)、色も琥珀に似た黄色を帯びた灰色・灰白色・黒色等、それぞれgolden・grey・black等の等級がある(goldenが最上とされる)。中国や中世ヨーロッパに於いては、媚薬として流行したが、この結石から精油した龍涎香は、一般に他の香水と合わせた時、主成分のテルペノイド(Terpenoid:二重結合を二つ持つ炭化水素イソプレン(soprene)の重合した化合物)であるアンブレイン ambrein の酸化作用によって、すぐれた芳香効果を示す。
・「痘瘡の紫黑下䧟」は、痘瘡に罹患した後に出来る窪んだあばたを指す。それにしても金と同等に取引された龍涎香をこんな症状に用いるとは、太っ腹じゃのう!
・「黑皮と赤肉の交ひ、白き脂有り」の全体が、現在のクジラのベーコン! 大好き! 言っとくと、美味しいのは、毒々しく着色されない生ベーコンだよ!
・「鯨に、六種、有り」とあるが、現在の大きな分類では、ヒゲクジラ類三科、ハクジラ類十三科で総種数は八十種を越えるとする。但し、本邦の海域内であれば、この数字は問題ないであろう。
・「羽指」は、「はざし」と読む。日本での捕鯨は、遠く縄文期(貝塚からの小鯨の骨の出土や土器の装飾紋に見られる骨の使用等から)やアイヌらによるオホーツク沿岸捕鯨まで遡るが、近世初期の古式捕鯨である網取式捕鯨の漁法に於いて、「羽指」という花形的職能が定着したように思われる。即ち、山上に「山見(やまみ)」という見張り場を設け、鯨の到来を確認すると、狼煙(のろし)などで、その種類や方角を報ずる。それを受けて「勢子(せこ)船」・「網船」・「持双(もっそう)船」が出船し、「網船」が鯨の先に網を降ろし、「勢子船」でその網に鯨を追い込む。クジラが網に絡まったところで、銛を撃ち込み、弱ったところを見計らって、「羽指」が、口に鼻切包丁(刃渡り三十センチメートル程の軟鉄製で、素手による整形が可能)を銜えて飛び込み、刺さった銛の繩を手掛かりにして、鯨に、攀じ登る。そうして、両の鼻の穴に切り込みを入れ、太綱を通し、それを二艘の「持双船」に渡して、鯨を挟み込んで、陸に運び、解体した(以上、網取式捕鯨については主にサイト「久則庵」の“WHALES”中の「日本の古式捕鯨(網取り式捕鯨)」を参照した)。
・「長袖短袗」は、袖が長く丈は短い単衣(ひとえ)。
・「近頃は遠く」は、「最近では遠く沖まで出て」という意味であろう。
・「世美」は鯨偶蹄目セミクジラ科セミクジラ属セミクジラ Eubalaena japonica 。文字通り、背びれがなく背が美しいことからの命名。ちなみに冒頭掲げられる「海鰌」の名も実は、このセミクジラに与えられてある。
・「斛」は約百八十リットル。一斛=十斗=百升。
・「座頭」は鯨偶蹄目ナガスクジラ科ザトウクジラ属ザトウクジラ Megaptera novaeangliae 。英名の humpback whale (「せむしの鯨」の意)といい、本叙述の和名由来といい、私も知らずに使ってきたが、これらは忌々しき差別名称の最たるものであろう。
・「瞽者」の読みは、一応、正式な音読みとして「こしや(こしゃ)」にしたが、東洋文庫版では『ごぜ』とルビしている。島崎藤村の小説「旧主人」でも、こう書いて「ごぜ」と読んではいる。但し、「ごぜ」は「瞽女」で、女性のそうした障碍者の芸能者を特定して指す語であったから、私は「こしゃ」でよいと思う。
・「先づ、兒鯨をして、殺す時は、之れを防ぎ、半死にせしむれば、則ち、母鯨、去るに忍びず、身を以つて、子を掩ふ時、殺し得つべし。後、又、子鯨を捕ふ。」の部分は、訓読に苦しんだ。原本では訓点は、一部、不審な箇所(返り点の「下二」)も含めて、
*
先ツ使下二兒鯨一防キ二殺ス寸ハ之ヲ一半死上則母鯨不レ忍レレ去ニ以レ身テ掩フレ子ヲ時可シ二殺得エツ一後又捕フ二子鯨ヲ一
*
である。後半部は問題ないが、前半部がちゃんと読めない。「鯨」の左下には明らかに返り点「下二」とあるが、これでは機能しない。因みに、東洋文庫版では、ここを以下のように訳している。
《引用開始》
ただし子持ち鯨は捕獲しやすい。まず児(こ)鯨を攻めて半死の目に合わすと母鯨は去るに忍びず、身をもって子をかばい掩(おお)う。そのときに殺すことができ、そのあと子鯨も捕える。
《引用終了》
基本的には、私も、概ね、このような意味と理解して、書き下したつもりではある。
・「長須」は鯨偶蹄目ヒゲクジラ亜目ナガスクジラ科ナガスクジラ属ナガスクジラ Balaenoptera physalus (同属シロナガスクジラ Balaenoptera musculus は、遊泳速度が速く、死骸が沈むことから、近世までの捕鯨の対象とはなっていない。大きさからいっても、ここでは、外して考えるべきであろうと私は思う)。
・「鰯鯨」はナガスクジラ属イワシクジラ Balaenoptera borealis 。
・「真甲」は鯨偶蹄目 Whippomorpha 亜目 Cetacea 下目ハクジラ小目マッコウクジラ科マッコウクジラ属マッコウクジラ Physeter macrocephalus 。「マッコウ」は多くの文献が「抹香」と書くところから、先に記した本種特有の龍涎香が、モクレン科のシキミ Illicium anisatum の葉を粉にした「抹香」の香りと似ていることに由来する。
・「小鯨」は「コクジラ」・「チゴクジラ」等の異名を持つ小型種であるコククジラ科或いはナガスクジラ科のコククジラ属コククジラ Eschrichtius robustus を指すかとも思われるが、良安先生! 「各其の大鯨に類す」では、全種の小鯨となって、独立条として出す以上は、あんまりで御座りませか?! そもそも、「コク」に「克」の字が当てられているのは、古くから近代まで、「児童鯨」「小鯨」という和名が、一般名詞の「小鯨」と混同されたことから、区別するためだったんでげすよ?! ……まあ、しかし、先生も、ここまで各種を叙述して下すったんだから、「目鯨立てる」のは、やめておきやしょうか。
・「魚虎」は、とりあえずクジラ目ハクジラ亜目マイルカ科シャチ属に属する Orcinus orca と同定してよいであろう。仲間外れにされて、可哀そうなので、良安の割注にもある「卷四十九 魚類 江海有鱗魚」の独立項の「魚虎」(先般、終わった二〇二三年改訂版のもの)を転写しておく。
* * *
■和漢三才圖會 江海有鱗 卷ノ四十九 ○二十
[やぶちゃん注:冒頭の鯡の項の最終三行及び後半の人魚の項前部は省略。]
しやちほこ
魚虎
イユイ フウ
土奴魚 鱐【音速】
【俗用鱐字未詳
鱐乃乾魚之字】
【俗云奢知保古】
[やぶちゃん字注:以上四行は、前三行下に入る。]
本綱魚虎生南海中其頭如虎背皮如猬有刺着人如蛇
咬亦有變爲虎者又云大如斗身有刺如猬能化爲豪豬
此亦魚虎也
△按西南海有之其大者六七尺形畧如老鰤而肥有刺
鬐其刺利如釼其鱗長而腹下有翅身赤黒色離水則
黃黒白斑有齒食諸魚世相傳曰鯨食鰯及小魚不食
大魚有約束故魚虎毎在鯨口傍守之若食大魚則乍
《改ページ》
入口嚙斷鯨之舌根鯨至斃故鯨畏之諸魚皆然矣惟
鱣鱘能制魚虎而已如入網則忽囓破出去故漁者取
之者稀焉初冬有出于汀邊矣蓋以猛魚得虎名爾猶
有蟲蠅蝎虎之名非必變爲虎者【本草有變爲虎者之有字以可考】
鱣鱘鯉逆上龍門化竜亦然矣
城樓屋棟瓦作置龍頭魚身之形謂之魚虎【未知其據】蓋置嗤
吻於殿脊以辟火災者有所以【嗤〔→蚩〕吻詳于龍下】
*
しやちほこ
魚虎
イユイ フウ
土奴魚 鱐〔(しゆく)〕【音、速。】
【俗に「鱐」の字を用ふるは、未だ、詳らかならず。鱐、乃〔(すなは)〕ち、「乾魚」の字〔なり〕。】
【俗に「奢知保古〔(しやちほこ)〕」と云ふ。】
「本綱」に『魚虎、南海中に生ず。其の頭〔(かしら)〕、虎のごとく、背の皮に猬〔=蝟=彙:はりねずみ〕のごとくなる刺〔(とげ)〕有りて、人に着けば、蛇の咬むがごとし。亦、變じて、虎と爲る者、有り。又、云ふ、大いさ、斗〔:柄杓〕のごとく、身に、刺、有りて、猬のごとし。能く化〔(け)〕して豪-豬(やまあらし)と爲〔(な)〕る。此れも亦、魚虎なり。』と。
△按ずるに、西南海に、之れ、有り。其の大なる者、六、七尺。形、畧〔(ほぼ)〕、「老鰤〔(おいしぶり)〕」のごとくして、肥えて、刺鬐〔(とげひれ)〕有り。其の刺、利きこと、釼〔(つるぎ)〕のごとし。其の鱗、長くして、腹の下に、翅〔(はね)〕、有り。身、赤黒色。水を離〔(はな)るれば〕、則ち、黃黒、白斑なり。齒、有りて、諸魚を食ふ。世に相傳へて曰く、『鯨は、鰯、及び、小魚を食ふも、大魚を食はざるの約束、有り。故に、魚虎は、毎〔(つね)〕に、鯨の口の傍らに在りて、之れを守る。若〔(も)〕し、大魚を食はば、則ち、乍〔(たちま)〕ち、口に入り、鯨の舌の根を嚙〔(か)み〕斷〔(た)ち〕、鯨は斃〔(し)〕するに至る。故に、鯨、之れを畏る。諸魚、皆、然り。惟だ、鱣〔(ふか)〕・鱘〔(かぢとをし)〕、能く、魚虎を制すのみ。如〔(も)〕し、網に入らば、則ち、忽ち、囓み破りて、出で去る。故に漁者、之れを取る者、稀れなり。初冬、汀-邊〔(みぎは)〕に出づること、有り。』と。蓋し、猛魚なるを以つて、「虎」の名を得《うる》のみ。猶ほ、蟲に蠅-虎(はいとりぐも)・蝎-虎(いもり〔→やもり〕)の名有るがごとし。必〔ずしも〕、變じて虎と爲る者に非ず。【「本草」〔=「本草綱目」〕に『變じて、虎と爲る者、有る』と云ふの「有」の字、以つて、考ふべし。[やぶちゃん注:「云」は送り仮名にある。]】鱣(ふか)・鱘(かぢとをし)・鯉(こひ)、龍門に逆(さ)か上(のぼ)りて竜に化すと云ふも亦、然り。[やぶちゃん注:「云」は送り仮名にある。]
城樓の屋-棟(やね)して、瓦に、龍頭魚身の形を作り置く。之れを「魚虎(しやちほこ)」と謂ふ【未だ、其の據〔(きよ)〕を知らず。】。蓋し、「嗤吻(しふん)」を殿脊〔(でんせき):屋形の屋根〕に置き、以つて火災を辟〔=避〕くと云ふは、所-以(ゆへ[やぶちゃん注:ママ。])有り【「蚩吻」は「龍」の下に詳らかなり。】
[やぶちゃん注:「本草綱目」の記す「魚虎」は、化生するところは架空の生物であるが、刺の描写や大きさは、カサゴ亜目オニオコゼ科オニオコゼ属オニオコゼ Inimicus japonicus を筆頭としたカサゴ目の毒刺を有するグループを想定し得るが(「和漢三才圖會 卷第四十八 魚類 河湖有鱗魚」の「䲍」(おこじ:オコゼ)も必ず参照されたい)、後の良安の記すものは、とりあえずクジラ目ハクジラ亜目マイルカ科シャチ属シャチ Orcinus orca と同定してよいであろう。シャチと言えば、私は今でも鮮やかに覚えている、少年時代の漫画学習百科の「海のふしぎ」の巻に、サングラスをかけた小さなシャチが、おだやかな顔をしたクジラを襲っているイラストを……。ちょっとした参考書にも、シャチは攻撃的で、自分よりも大きなシロナガスクジラを襲ったり、凶暴なホホジロザメ等と闘い、そこから「海のギャング」と呼ばれる、と書かれていたものだ。英名もKiller whale、学名はローマ神話の『死の神「オルクス」に属する者』、或いは「死者の王国の者」という意味でもある。しかし。実際には、肉食性ではあるが、他のクジラやイルカに比べ、同種間にあっては、攻撃的ではないし、多くの水族館でショーの対象となって、人間との相性も悪くない(私は芸はさせないが、子供たちと交感(セラピー)するバンクーバーのオルカが極めて自然で印象的だった)。背面、黒、腹面、白、両目上方に「アイ・パッチ」と呼ぶ白紋があるお洒落な姿、ブリーチング(海面に激しく体を打ちつけるジャンピング)やスパイ・ホッピング(頭部を海面に出して索敵・警戒するような仕草)、数十頭の集団で生活する社会性、エコロケーションによる相互連絡やチームワークによる狩猟、じゃれ合う遊戯行動等、少しばかり、ちっぽけな彼等が、人間の目に付き過ぎたせいかもしれないな。本項の叙述も殆んど、「切り裂きジャック」並みの悪行三昧だ。良安が教訓染みて終えているので、私も一つ、これで締めよう。『出るシャチはブリーチング』。
・「鱐【音、速。】」とあるが、「鱐」の音は、示した通り、「シュク」である。「速」は「ソク」で「シュク」と言う音はない。不審である。「鱐」は「ほしうお・ひもの・乾魚」或いは「魚のあぶら」を意味する。これも、良安、わざわざそう記しているように、何となく、不審である。これは、実は実際のシャチの実物を全く見ていない彼の弱みが聴き書きを必死で書き込んだ痕跡のように、私には思われるのである。
・「猬」は哺乳綱モグラ目(食虫目)ハリネズミ科 Erinaceidaeのハリネズミ類。
・「豪豬」はネズミ目(齧歯目)ヤマアラシ上科ヤマアラシ科アメリカヤマアラシ科 Erethizontidaeの地上性のヤマアラシ類。
・「老鰤」スズキ目アジ亜目アジ科ブリ Seriola quinqueradiata の大型個体。一応、訓読みしておいた。
・「刺鬐、有り。其の刺、利きこと、釼のごとし」はセビレの形状を言うものと考えてよい。シャチの♂は、成長するにつれて、セビレ、及び、ムナビレ(=「腹の下に翅」)が特に目立つようになる。
・「水を離れば、則ち黃黒、白斑なり」とは、水から上がってしまうと、体色の黄身を黄色い部分や黒い部分に白い斑点が現れる、という意味であるが、これはパッチを誤解(聴き取りの誤認)したものと思われ、やはり、良安は不十分にして偽りの多い知ったか振りの半可通の話を無批判に記した可能性が高いように思われる。
・「魚虎は、毎に。鯨の口の傍らに在りて、之れを守る。……」これは、実際、クジラを襲うことのあるシャチへの根拠のない妄想説のように思われるのだが、よく見ると、「口の傍らに在りて」及び「口に入り」というのは、クジラに付着しているコバンザメ類(スズキ目Perciformesコバンザメ亜目コバンザメ科Echeneidae)の行動を見、クジラの死亡個体の口腔内からコバンザメを発見した際に(サメやクジラの口腔内を出入りするコバンザメを私は映像で見たことがある。但し、死亡個体の口腔内に有意に彼等を発見し得るかどうかは知らないのであるが)それが「鯨の舌の根を嚙み斷」ったと誤認し、それが実際のクジラに攻撃行動をとるシャチと混同されて生じた伝説ではあるまいか。識者の意見を伺いたいものである。なお、後掲される「舩留魚」(ふなとめ=コバンザメ)の項も参照されたい。
・「鱣」分類学上、フカは軟骨魚綱板鰓亜綱Elasmobranchiiに属するサメと同義。後掲される「鱣」の項、参照。
・「鱘」カジキのこと。カジキはスズキ目メカジキ科 Xiphiidae 、及び、マカジキ科 Istiophoridae の二科に属する魚の総称。後掲される「鱘」の項、参照。
・「蠅虎」節足動物門クモ綱クモ目ハエトリグモ科シラヒゲハエトリグモ属シラヒゲハエトリ Menemerus confusu 等に代表される(ハエトリグモ科の種和名は慣習として接尾語のクモを外す)のハエトリグモ類。「蠅狐」「蠅取蜘蛛」とも。次の「蝎虎」と同様、中国語(現在も通用)。私の数少ない大好きな「虫」の一つである。
・「蝎虎」現代中国語では蠍座を「蝎虎座」と呼び、「とかげ座」と訳している。爬虫綱有鱗目トカゲ亜目 Lacertilia のトカゲである。また、ヤモリは「壁虎」で近いし、ネット上には蝎虎を爬虫綱有鱗目トカゲ亜目ヤモリ下目ヤモリ科 Gekkonidae に属するヤモリ類を言うとする記載が多い。ここで良安は、両生綱有尾目イモリ亜目イモリ科 Salamandridae の「イモリ」とルビを振るが、現代中国語では「蠑螈」で、イモリを蝎虎とする記載はネット上には見当たらない。ヤモリは上位タクソンでトカゲに属し、更にイモリの形状はヤモリに似、日本の古典で、イモリとヤモリを一緒くたに語る(イモリとヤモリの双方向同一物表現)ものを、複数、見たことがある。決定打は、実は「和漢三才圖会」の卷四十五にあった。ここに良安は「蠑螈」(ゐもり)=イモリと、「守宮」(やもり)=ヤモリを、二項、続けて、記載しており、その「守宮」の項の図下の冒頭の異名の列挙に『蝘蜓(えんてい) 壁宮 壁虎 蝎虎』と記している。序でに言えば、その「守宮」の本文中で良安は、
*
守宮【今云屋守】蠑螈【今云井守】一類二種而所在與色異耳守宮不多淫相傳蛙黽變爲守宮
守宮(やもり)【今、屋守と云ふ。】蠑螈(いもり)【今、井守と云ふ。】一類二種にして、所在と色と、異なるのみ。守宮(やもり)は多淫ならず、相傳ふに、蛙-黽(あまがへる)、變じて、守宮と爲る、と。
*
と記し(ちなみに「多淫ならず」は、前項の「蠑螈」(イモリ)についての記載の『性、淫らにして能く交(つる)む』とあるのを受ける)、イモリもヤモリも棲むところと色が違うだけで同じだあなと、のたもうておる訳で――ここはもう、ヤモリでキマリ!
・「鱣・鱘・鯉、龍門に逆か上りて竜に化す」この「登龍門」の魚の正体については、「鱣」や「鯉」、種々の項で、私の考えを語ってきた。結論だけを言う。チョウザメ目チョウザメ科 Acipenseridaeのチョウザメ類が龍門を登る魚の正体である。後掲される「鮪」の項の「王鮪」の注を参照されたい。
・「蚩吻」は「和漢三才圖會」の卷四十五の「龍」の項の解説に割注を含めてたった八文字(全く以つて「詳」ではない!)、以下のようにある。
*
蚩吻好吞【殿脊之獸】
蚩吻は吞むことを好む【殿脊の獸。】。
*
「殿脊」は「でんせき」と読み、「屋形の屋根」の意。いやはや、これでは困るな。大寺院の甍の両端に、まさに鯱(しゃちほこ)のような形のものを御覧になった記憶がある方は多いだろう。これは「鴟尾(しび)」と呼称することも、芥川龍之介の「羅生門」でお馴染みだ。文字の意味は「鳶の尻尾」なのであるが、これは実は、「蚩尾」で、良安が判じ物のように示した通り、龍の九匹の子供の内の一匹が「蚩吻」(しふん)と称する酒飲みの龍であり、それが屋根を守ると、古くから信じられたようなのである。派手に酒を吹き出して、消火してくれるスプリンクラーのようなものか? いや、待てよ! 中国酒はアルコール度数が高いから逆にジャンジャン燃えるんでないの!?!
なお、以上の注は冒頭の「鯨」の項の「魚虎」の注として作成したものを改訂増補したものである。向うの「魚虎」の記述と一部の注を以下に付しておく。
*
魚虎〔(しやち)〕と云ふ者、有り。其の齒・鰭(ひれ)、剱鉾〔(けんぼこ)〕のごとし【「有鱗魚」の下に詳し。】。數十〔(すじふ)〕、毎〔(つね)〕に、鯨の口の傍らに在りて、頰・腮〔(あぎと):あご〕を衝〔(つ)〕く。其の聲、外に聞こゆ。久しくして、鯨、困迷して口を開く時、魚虎、口中に入り、其の舌を嚙み切り、根、既に喰ひ盡して出で去る。鯨は乃〔(すなは)〕ち、斃〔(し)=死〕す。之れを「魚虎切り」と謂ふ。偶々、之れ、有りて、浦人〔(うらびと)〕、之れを獲る。海中の無雙の大魚、纔〔(わづ)〕かの小魚の爲に、命を絕つ。
*
・「剱鉾」は、剣(つるぎ)や鉾(ほこ)と読んで問題ないが、魚虎の派手さからは、京都祇園御霊会の、神輿渡御の際の先導を務める悪霊払いの呪具たる「剱鉾」を指している可能性もある。「剱鉾」の画像はグーグル画像検索「祇園祭 剣鉾」をリンクさせておく。]
* * *
以上の「鯨」の項の再改訂は、なかなか時間がかかった。]
***
ふか
鱣【音天】
テン
黃魚 蠟魚
玉版魚
【俗云布可】
【和名抄爲鰻鱺之訓者非
也】
[やぶちゃん字注:以上五行は、前三行の下に入る。]
本綱鱣海中無鱗大魚也狀似鱘其色灰白其背有骨甲
三行鼻長有鬚口近頷下其尾有岐其出也以三月逆水
而上其居也在磯石湍流之間其食也張口接物聽其自
入食而不飮蟹魚多誤入之其行也在水底去地數寸漁
人以小鈎數百沉而取之一鈎着身動而護痛諸鈎皆着
之船遊數日待其困憊方敢掣取之其小者近百斤大者
長一三丈至一二千斤其氣甚鯹其脂與肉層層相間肉
色白脂色黃如蠟故名之其脊骨及鼻并鬐與鰓皆脆軟
可食其肚及子盬藏亦佳其鰾亦可作膠
肉【甘平有小毒】 多食生熱痰發瘡疥【和蕎麦食人失音】忌荊芥
《改ページ》
■和漢三才圖會 江海無鱗魚 卷ノ五十一 ○四
△按鱣小者二三尺大者二三丈狀畧類守宮蟲而頭扁
圓嘴尖眼大口在頷下而𤄃大有齒牙而堅利背有三
骨甲尾有岐鰭亦硬無鱗皮厚灰白色如鮫之沙小者
肉潔白味稍美故魚市所出皆不過三四尺其大者好
取人嚙如有人出手足於舷者鱣跳浮囓切去海舶最
畏之胎生產於口嘗見胎魚其子既備鱣形名天以豆
留古【一名奈宇佐宇】鱣類有數種其肉爲𩵟膾食之或爲魚餅
以僞海鰻蒲鉾
白目鱣 小者二三尺大者二三丈背灰白腹白齒大其
眼色白好嚙人其肉味美
牛鱣 大抵三尺許狀類白目鱣灰皂色無齒
猫鱣 大三四尺頭形似猫扁身有虎斑文有齒味不佳
加世鱣 大三四尺及一丈灰黑色口小而齒細有耳其
眼有耳端此鱣在海中不爲害俗取膽爲疳眼藥
坂田鱣 大二三尺頭圓匾似團扇身挟長似團扇柄而
《改ページ》
灰黑色
*
ふか
鱣【音、天。】
テン
黃魚 蠟魚
玉版魚
【俗に「布可」と云ふ。】
【「和名抄」に「鰻鱺」の訓を爲すは、非なり。】
「本綱」に、『鱣は、海中無鱗の大魚なり。狀〔(かたち)〕、「鱘」に似、其の色、灰白。其の背に、有骨の甲、三行(〔み)〕くだり)、有り。鼻、長く、鬚、有り。口、頷〔(あぎと)〕の下に近く、其の尾、岐〔(また)〕、有り。其の出づるや、三月を以つて、水に逆(さから)〔ひ〕て上り、其〔れ〕、居〔(を)〕るや、磯石湍流〔(そせきたんりう)〕の間に在り。其〔れ〕、食ふや、口を張り、物を接し、其の自ら入るを聽きて、食つて、飮まず。蟹・魚、多く、誤りて、之れに入る。其〔れ〕、行くや、水底に在り、地を去ること、數寸。漁人、小さき鈎(つり〔ばり〕)數百を以つて、沉めて、之れを取る。一鈎〔(ひとはり)〕、身に着き、動きて、痛みを護〔(まも)〕る〔に〕、諸鈎、皆、之れに着けり。船、遊ぶこと數日〔(すじつ)〕、其の困-憊(つか)れたるを待ちて、方〔(まさ)〕に、敢へて、之れを掣(う)ち取る。其の小さき者は、百斤〔(きん)〕に近し。大なる者は、長さ一、三丈、一~二千斤に至る。其の氣〔(かざ)〕、甚だ、鯹〔=腥〕さし。其の脂〔(あぶら)〕と肉と、層層として、相間(〔あひ〕まじは)つて、肉色、白く、脂の色、黃にして、蠟のごとし。故に、之れを〔「蠟魚」と〕名づく。其の脊の骨、及び鼻、并びに、鬐〔(ひれ)〕と、鰓〔(あぎと)〕と、皆、脆く、軟にして、食ふべし。其の肚〔(はら)〕、及び、子、盬藏(しほ〔〕づけ)にして、亦、佳なり。其の鰾(にべ)も亦、膠〔(にかは)〕に作るべし。
肉【甘、平にして、小毒、有り。】 多く食へば、熱痰を生ず。瘡疥〔(さうかい)〕を發し【蕎麦に和して食へば、人をして、失音せしむ。】、荊芥〔(けいがい)〕を忌む。』と。
△按ずるに、鱣は、小なる者、二、三尺、大なる者、二、三丈。狀〔(かた)〕ち、畧〔(ほぼ)〕、「守宮蟲〔(いもり)〕」に類して、頭〔(かしら)〕、扁たく、圓〔(まろ)〕く、嘴〔(くちばし)〕、尖り、眼〔(まなこ)〕、大きく、口、頷〔(おとがひ)〕の下に在りて、𤄃〔(ひろ)〕く、大〔にして〕、齒牙、有りて、堅く、利〔(り)なり:鋭利である。〕。背に、三の骨甲、有り。尾に、岐〔(また)〕、有り。鰭も亦、硬し。鱗、無く、皮、厚く、灰白色、鮫の沙のごとし。小さき者は、肉、潔白にして、味、やや美なり。故に、魚市に出づる所は、皆、三、四尺に過ぎず。其の大なる者は、好んで、人を取りて、嚙〔(く)〕ふ。如〔(も)〕し、人、手足を舷(ふなばた)に出だす者、有れば、鱣、跳(と)び浮きて、囓み切り、去る。海舶に、最も、之れを畏る。胎生にして、口より、產む。嘗つて、胎(はらみ)魚を見〔るに〕、其の子、既に、鱣の形を備なふ。「天-以-豆-留-古(でい〔つるこ〕)」と名づく【一名、「奈-宇-佐-宇〔(なうさう)〕」。】。鱣の類、數種、有り。其の肉、𩵟(さしみ)・膾(なます)と爲す。之れを食ふに、或いは、魚-餅(かまぼこ)と爲し、以て「海-鰻(はも)」の蒲鉾に僞〔(いつは)〕る。
白目鱣 小なる者、二、三尺、大なる者、二、三丈、背、灰白、腹、白く、齒、大にして、其の眼〔(まなこ)〕の色、白し。好んで、人を嚙む。其の肉、味、美なり。
牛鱣(うしふか) 大抵、三尺ばかり。狀、「白目鱣」に類して、灰皂〔=黑〕色。齒、無し。
猫鱣 大いさ、三、四尺。頭の形、猫に似、扁たく、身、虎斑〔(とらふ)〕の文〔(もん)〕、有り。齒、有り。味、佳からず。
加世鱣 大いさ三、四尺〔より〕、一丈に及ぶ。灰黑色、口、小さくして、齒、細く、耳、有り。其の眼、耳の端に有り。此の鱣、海中に在りて、害を爲さず、俗、膽〔(きも)〕を取りて、疳眼〔(かんがん)〕の藥と爲す。
坂田鱣 大いさ、二、三尺。頭、圓く、匾〔(ひら)たく〕、團-扇(うちは)に似、身、挟〔(せば)〕く、長〔く〕、團扇の柄に似て、灰黑色なり。
[やぶちゃん注:「フカ」と「サメ」と古名としての「ワニ」は、総て、軟骨魚綱板鰓亜綱 Elasmobranchii に属する魚類の中で、原則として、鰓裂が体側に開くものの総称である(後述するカスザメ目 Squatiniformes の鰓孔は腹側から側面に開いている)。即ち、「フカ」は「サメ」と生物学的には同義であるが、民俗的には、それぞれの地域で、厳然とした二分法がある(実際、本巻でも、後に「鮫」を別項目として立てている。なお、「鰐」が、その直前に項目としてあるが、これは珍しく正真正銘の爬虫綱ワニ目 Crocodilia のワニであることが、挿絵で判然とする)。ところが、関東では、大きな鮫を「フカ」と呼ぶのに対して、関西以南では、逆に、小さな鮫を「フカ」、大きなものを「サメ」と呼称するとか、関西では「フカ」、関東では「サメ」が鮫類の呼称として優勢であるとか、また、一般には、大型のものや、「人食い鮫」に相当するような攻撃性の強いものを「フカ」と呼称するであるとか、その内実と名は、現代でも一定してはいない。
・「和名抄」は、正しくは「倭(「和」とも表記)名類聚鈔(「抄」とも表記)」で、平安中期に源順(したごう)によって編せられた辞書。以下、注は略す。
・『「鰻鱺」の訓』国立国会図書館デジタルコレクションの万文七(一六六七)年の版本のここを見ると、巻十九の「鱗介部第三十」の「龍魚類第二百三十六」に、
*
鱣魚(むなき) 「文字集略」云はく、『鱣【音、「天」。和名「無奈木」。】は、黃魚、銳〔き〕頭〔(かしら)〕にして、口、頸〔(あご)〕下に在る者なり。「本草」に云はく、『䱇魚【上の音、「善」。和名、上に同じ。】、一名、「鰌䱇」【上の音、「秋」。】、一名、「鯆魮」【「甫」「毘」の二音。】一名、※1[やぶちゃん注:「※1」=「魚」+「尖」。]䰲【「※2」[やぶちゃん注:「※2」=(上)「尖」+(下)「鳥」。]「軋」の二音。】「爾雅注」に云はく、『鱓は蛇に似たり【今、按ずるに、「鱓」は卽ち、「䱇」の字なり。』と。
*
を指して良安は批判していると考えてよい。因みに、実は、この後のここに、「卷十九」の「鱗介部第三十」の「龍竜魚類第二百三十六」には、
*
鰻鱺魚(はしかみいを)「本草」に云はく、『鰻鱺【「蛮」「縲」の二音。和名「波之加美伊乎」】は[やぶちゃん注:以下、欠]。』と。
*
という別項がある。しかし、この「鰻鱺魚」(はじかみうお)というのは、実は、かのオオサンショウウオの古名とされるので、この批判との関係性は認められない。私が気になるのは、良安が「和名類聚鈔」には示されない「鰻鱺」という漢字表記を示している点にある。「鰻鱺」は、「廣漢和辭典」の「鰻」の字義の「うなぎ」の後に、朱駿声の「説文通訓定声」から引いて、「今俗に鰻鱺と曰ふは、是なり」と、この熟語が現われるので、この「鰻鱺」とは漢語に於いては「うなぎ」を指すものであることは間違いないのではあるが。
・「綱目」は「本草綱目」で明の李時珍の薬物書。全五十二巻。一五九六年頃の刊行。巻頭の巻一、及び、二は、序例(総論)、巻三、及び、四は百病主治として各病症に合わせた薬方を示し、巻五以降が薬物各論で、それぞれの起源に基づいた分類がなされている。収録薬種は千八百九十二種、図版一一〇九枚、処方一万千九十六種にのぼる。以下、多く引用されるので注は、ここのみとする。
・「鱘」は、東洋文庫版は『かじき」と訓じている。確かに、次の項目が「かぢとをし」でカジキマグロであり、見出しも本字、「鱘」である。また、次項解説の同じ「本草綱目」でも、「鱣」に似ている、とも記述されてはいる。しかし、私は、これは、「鱘」のもう一つの意味である「チョウザメ」を指しているのではあるまいかという疑念が拭いきれない。時珍は「登龍門」(あれは、本来は「チョウザメ」であったものが、「コイ」に代えられたものとも言う。私は、かねがねこの説を支持したいと思っていた)の故事等で、中国人に、より一般的な硬骨魚である条鰭亜綱チョウザメ目チョウザメ科 Acipenseridae との類似を、時珍は、まず、示したかったのではないか? いや、それどころか、この「鱣」の叙述に現われるその形状・生態は、この時珍の叙述の最後まで(「其の肚、及び、子、盬藏にして、亦、佳なり」なんて、キャビアそのものじゃないか?!)、驚くほどチョウザメに酷似するように感ぜられないだろうか? 識者の見解を待つ。
・「磯石湍流」の「湍流」は、本来、「河川の早瀬」を言う。岩礁性、若しくは、石礫の海底で、海流の流れが早いところを言うのであろう。
・「斤」・「丈」は、時珍の生きた明代で、一斤は五百九十六・八グラム、一丈は三・一メートルであった。
・「鰾」の「にべ」という読みは、本来、スズキ目ニベ科ニベ Nibea mitsukurii の浮袋から作られた接着力の強い膠(にかわ)を指す(「愛着を示さない・愛想がない」の意味の「にべもない」の語源)。そこから、広く浮袋を「にべ」と呼称している。他にコイ・ウナギ、そしてサメなどの浮袋からも生成された。「和漢三才圖會 卷第四十九 魚類 江海有鱗魚」の「鮸」の項を参照。
・「熱痰」は、黄色の痰を吐き、顔面が赤味を帯びている症状を言う。
・「瘡疥」は、広く吹き出物から発疹等の種々の皮膚疾患全般を言う。
・「荊芥」は、シソ科のケイガイ Schizonepeta tenuifolia の花穂、及び、その茎枝で、漢方薬として、風邪や出血性疾患や皮膚病に効果があるとする。
・「守宮蟲に類して」? か? しかし、またしても、「鯨」の項の悪夢の再来である。この冒頭の絵を見ていると、ちょっと、イモリに似てるかもという気が、しないでもないんである……。
・「嚙ふ」は、ここでは、或いは、「くはふ」と訓読しているかも知れぬが、私は、「人食いザメ」のニュアンスを出した〱思ったのである。
・「胎生にして、口より、產む」とあるが、口から子を産むマウスブリーダー習性(産むように見えるアジアアロワナ Scleropages formosus 等の条鰭綱アロワナ目アロワナ亜目アロワナ科 Osteoglossidae や、スズキ目キノボリウオ亜目のチョコレートグラミー Sphaerichthys osphromenoides のような)をサメが持っているというのは、私はちょっと聞いたことがない。これは何かの勘違いであろう。これに関しての解釈は、後掲の「鮫」の後注を参照されたい。
・「奈宇佐宇」は、ここでは幼体のフカを呼称する語であるが、小型のサメは、捕獲時に、比較的、暴れずに、おとなしいことから、「脳の回りが遅い」という長崎方言でつけられたという説がある。現在、「ノウソウ」と呼称するものとしては、ドチザメ科ホシザメ属シロザメ Mustelus griseus や、ネズミザメ目オナガザメ科オナガザメ属マオナガ Alopias vulpinus 辺りが同定候補となるか。
・「海鰻」は、条鰭綱ウナギ目アナゴ亜目ハモ科ハモ属ハモ Muraenesox cinereus (現行の本邦での近縁種は、スズハモ Muraenesox bagio ・ハシナガアナゴ(ハシナガハモ)属ハシナガハモ Oxyconger leptognathus ・ワタクズハモ属ワタクズハモ Gavialiceps taiwanensis )。
・「白目鱣」は、その名称から、取り敢えず、メジロザメ目メジロザメ科メジロザメ属 Carcharhinus を挙げておくが、この叙述自体からは、メジロザメ属に同定し得る決定打は見出せない。確かに、このメジロザメ目 Carcharhiniformes には、かなり攻撃的な種が含まれる。一般に知られる人への危険度では、ホオジロザメ Carcharodon carcharias(ネズミザメ目 Lamniformes )、オオメジロザメ Carcharhinus leucas や、イタチザメ Galeocerdo cuvier が挙がるが、後者の二種は、ともにメジロザメ目ではある。しかし、メジロザメ目総体を人間を好んで襲うという言うのにも、やや躊躇を感じる。
・「牛鱣」の呼称と類似する、現在ウシザメと呼ばれる種は、前項に掲げたメジロザメ目オオメジロザメ Carcharhinus leucas である。沖繩周辺での生育が確認されている。但し、歯は勿論あって、長く三角形に近い。
・「猫鱣」は、ネコザメ Heterodontus japonicus 、又は、シマネコザメ Heterodontus zabra 。これは、また思い出すなあ、小学校時代の漫画学習百科を。サザエを噛み割るその名こそ、マイナーなれど、人ぞ知る、「サザエワリ」とは、我が名なり! と言った風情、妙に色気のある流し目のネコザメのイラストだった……。お蔭で私は「サザエワリ」という名を早くから知っていたのであった。
・「加世鱣」は、その叙述と発音の近似性からカスザメ目カスザメ科カスザメ Squatina japonica (又は、胸鰭の先端の角度が、やや大きい近縁種コロザメ Squatina nebulosa )ではなかろうかと思われる。眼病薬という記載は探り得なかったが、若し、本種がカスザメであれば、本種の皮は、古くより、刀剣の柄(つか)に滑り止めとして巻いたことで知られる。なお、冒頭に述べたように、本種は、サメの中では変り種で、鰓孔は完全な体側ではなく、腹側から側面に開いている。もう一つ、付け加えておくと、サメの尾鰭は、上葉が下葉よりも長いのだが、カスザメは下葉が発達し、ほぼ上下同長である。
・「疳眼」は、角膜乾燥症・結膜アレルギーによる眼病を言う。
・「坂田鱣」は、当初、エイ目サカタザメ亜目サカタザメ科サカタザメ属サカタザメ Rhinobatos schlelii に同定していたのだが、変更の経緯は後掲される「海鷂魚」(エイ)の「窓引鱝」(マドヒキエイ)の後注も参照されたいが、この――体が円い――頭部が団扇に似ている――身から(尾にかけてととってよい)狭く長く団扇の柄に似ている――という特徴は、実は、サカタザメよりも、より、エイ目ウチワザメ科ウチワザメ属ウチワザメ Platyrhina sinensis に酷似するからである。サカタザメ類に似るが、はっきりと体が丸いのが、この種の特徴であり、坂田鱣は、丸いというよりも、尖(とん)がっているというのが最初の視認印象であること、現在のウチワザメは、まさしく「団扇鮫」と表記すること、後の「海鷂魚」の「窓引鱝」が、サカタザメ Rhinobatos schlelii 、又は、コモンサカタザメ Rhinobatos hynnicephalus と同定されるように感じられることから、本種は、
エイ目ウチワザメ科ウチワザメ属ウチワザメ Platyrhina sinensis
に同定変更した。更に付け加えると、後掲する「海鷂魚」(エイ)の図を参照されたい。これは一般的なエイのフォルムで想定するアカエイでもヒラタエイでもなく、ウチワザメではなかろうか?]
***
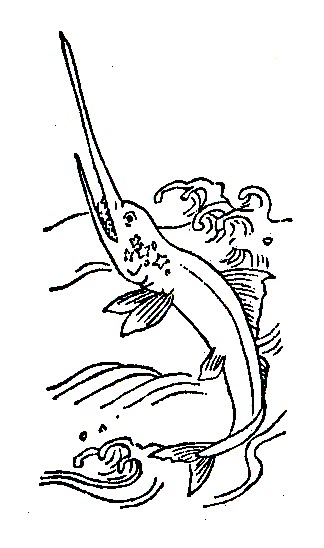
かぢとをし
鱘【音尋】
ツイン
鱏【音尋】 碧魚
【俗云加知止乎之】
[やぶちゃん字注:以上二行は、前三行の下に入る。]
本綱鱘鱣屬也岫居長者丈餘至春始出而浮陽見日則
目眩其狀如鱣而背上無甲其色青碧腹下色白其鼻長
與身等口在頷下食而不飮頰下有青班〔→斑〕紋如梅花狀尾
有岐如丙肉色純白味亞於鱣鬐骨不脆又云其頭大哆
口似銕兠〔=兜〕鍪其肉【甘平有毒】作鮓雖珍亦不益人
本草必讀云鱘目小如豆鼻傍肉作直𮈔名爲鹿頭肉【言味
美也】鰾亦作膠鱣鱘二魚皆能化龍
△按鱘嘴尖利如鐵海舶値之則可突拔故俗呼名柁通
*
かぢをとし
鱘【音、尋。】
ツイン
鱏【音、尋。】 碧魚
【俗に「加知止乎之」と云ふ。】
「本綱」に、『鱘は、「鱣〔(ふか)〕」の屬なり。岫居〔(しうきよ)〕し、長き者、丈餘。春に至りて、始めて出でて、陽〔(ひ)〕に浮き〔→くも〕、日〔(ひ)〕を見れば、則ち、目眩(くる)めり。其の狀〔(かたち)〕、「鱣(ふか)」のごとくにして、背の上に、甲、無く、其の色、青碧、腹の下の色、白し。其の鼻、長し。身と等(ひと)し。口、頷〔(あぎと)〕の下に在り。食ひて飮まず。頰の下に、青〔き〕斑〔(まだら)〕の紋、有り。梅花の狀のごとし。尾、岐〔(また)〕有りて、「丙」のごとく、肉色、純白(ましろ)く、味、「鱣」に亞(つ)ぐ。鬐骨〔(ひれぼね)〕、脆(もろ)からず。又、云ふ、其の頭〔(かしら)〕、大-哆(おほ)きなる口、銕-兜-鍪(かなかぶと)に似たり。其の肉【甘、平、毒有り。】、鮓〔(すし)〕に作る、珍と雖も、亦、人に益あらず。』と。
「本草必讀」に云ふ、『鱘は、目、小にして、豆のごとし。鼻の傍らの肉、「直-𮈔(はながつほ〔→を〕)に作る。名づけて「鹿頭肉〔(ろくとうにく)〕」と爲す【言ふ、「味、美なり。」と。】。「鰾(にべ)」も亦、膠〔(にかは)〕に作る。「鱣」・「鱘」の二魚、皆、能く龍と化す。』と。
△按ずるに、「鱘」は、嘴、尖(とが)りて、利〔にして〕、鐵のごとし。海舶、之れに値〔(あ)=遇〕へば、則ち、突(つ)き拔(ぬ)くべし。故に、俗に呼んで、「柁通(かぢとをし[やぶちゃん注:ママ。])」と名づく。
[やぶちゃん注:「本草綱目」の「鱘魚」の項を、良安は、恣意的に取捨選択して、海産のカジキに読み替えようとしているのが、手に取るように理解出来る。実は、これは「集解」の途中からで、『(藏器曰)鱘生江中背如龍長一二丈(時珍曰)出江淮黃河遼海深水處亦鱣屬也』の最後の三文字以降から引用しているである。この「鱘」も、そしてその属であるとする「鱣」も、「本草綱目」では、どちらも、明らかに、河川を遥かに遡上する魚である。且つ、実は次の「鮪」の項に良安が引用している『月令云季春天子薦鮪於寢廟故有王鮪之稱郭璞云大者名王鮪【其小者名叔鮪更小者者鮥子】』は、「本草綱目」の「鱘魚」の項の冒頭、「釈名」に「時珍曰」として記す内容なのである。良安先生、そうした齟齬を隠しきれずに、遂に「鮪」の自己の記載では『「本綱」に、鱘・鮪、以つて、一物と爲すは、未だ、精(くは)しからず』と記さざるを得なくなったわけである(次項及び注参照)。では、「鱘」は何か。これについては、本ページを読まれた「釜石キャビア株式会社」というところで、チョウザメに係わるお仕事に従事しておられるY氏から、二〇〇八年六月六日、この「かじとうし」の絵は、長江に生息するハシナガチョウザメであると考えらるというメールを頂戴した(リンク先は私のブログ記事)。以下に、メール本文の一部を引用する。
◇〔引用開始〕
「かじとうし」の絵、長江に生息します、ハシナガチョウザメと考えられます。チョウザメの仲間の中では特異な姿をしており、口に歯がはえております(チョウザメ類には歯が無い)。現在、長江でも絶滅したと考えられ、わずかな尾数を中国政府が保護飼育しております。添付図は中国のハシナガチョウザメの切手でございます。
◇〔引用終了〕
私は本ページで「鱣」・「鱘」・「鮪」にチョウザメの影を感じてきてはいたのであったが、メールを頂いた当初は、これは良安がオリジナルに描いたのだから、幾ら何でも当然、海産のスズキ目メカジキ科 Xiphiidae 及びマカジキ科 Istiophoridae の二科に属する魚(カジキマグロとは通称で正式和名ではない)の絵であるだろうと思っていたのだが、そのように言われて、よく見ると、これは時珍の「本草綱目」の「鱘魚」の叙述に従って、頬に星の模様まで入れて描いた想像図、カジキの実見描画ではなかったのである。これは、もう、間違いなく、Y氏の指摘された、英名“ Chinese swordfish ”、硬骨魚綱条鰭亜綱軟質区チョウザメ目ヘラチョウザメ科ハシナガチョウザメ属の異形種であるハシナガチョウザメ(古くはシナヘラチョウザメと呼称した) Psephurus gladius の叙述と考えてよい。Y氏から提供して戴いた中国切手の画像も以下に示す。まさにチョウ! 極似じゃないか!

私は、何時か、このY氏を釜石に訪ねし、親しくお逢いしたく思っていた。しかし、二〇一一年の大震災で被災され、ネットで調べても、「釜石キャビア株式会社」はサイトがなくなっていた。痛恨の極みであった。どこかで、再起され、チョウザメを飼育されておられることを心から祈っている……。
話を良安の附記に戻す。良安が確信犯で、無理矢理、同定しようと試みた種を同定しておこう。
カジキは、スズキ目メカジキ科 Xiphiidae 、及び、バショウカジキ科 Istiophoridae の二科に属する魚の総称(カジキマグロとは通称であって、正式和名ではない)。日本近海の種を挙げるならば、
メカジキ科メカジキ属メカジキ Xiphias gladius
バショウカジキ科マカジキ属マカジキ Tetrapturus audax
バショウカジキ科バショウカジキ属バショウカジキ Istiophorus platypterus
バショウカジキ科フウライカジキ属フウライカジキ Tetrapturus angustirostris
バショウカジキ科シロカジキ属シロカジキ Makaira indica
バショウカジキ科クロカジキ属クロカジキ Makaira mazara
の六種でよろしいか。名の由来は、本篇末尾の記載通り、「舵木通し」(かじきどおし)の略である。因みに、この中でも、バショウカジキは、帆に似た体高より大きな背鰭(これが芭蕉の葉に似ることからの命名)を持ち、全魚類中、最速の、時速百二十キロメートルの遊泳速度の保持者である。この大きな背鰭は、高速遊泳時の急ブレーキの役割を持つとも言われる。
・「岫居」の「岫」は、本来、「山の岫(くき:洞穴)」のことを指す。従って、ここでは、河川や海底の洞窟に棲み、という意となる。
・『「丙」のごとく』とは、「丙」という字のような形をしている、という意。
・「本草必讀」という書は、東洋文庫版の後注には『「本草綱目類纂必読」か。十二巻』とのみあるだけである。中国の爲何鎭(いかちん)なる人物の撰になる「本草綱目」の注釈書であるらしい。
・「直𮈔」、及び、後の「鹿頭肉」は、不明である。ここでの「はながつを」なるルビ自体が(「鹿頭肉」とのイメージの甚だしいギャップとともに)大いに怪しい気がする(そもそも、カジキの頬肉から鰹節を作り、それを、また、わざわざ「花鰹」にしたもの等というのは、如何にも非実利的で迂遠で胡散臭いではないか……と言いつつ、今、ネット上で非売品ながら、「鰹節」ならぬ「サメ節」の現物を見てしまった。確かに鰹だけじゃあない、何でも「節」は作れる訳だな)。前記の如く、原本も確認出来ないので、全くお手上げである。何かご存知の方は、御一報願いたい。
・「鰾」の「にべ」という読みは、本来、スズキ目ニベ科ニベ属ニベ Nibea mitsukurii の浮袋から作られた接着力の強い膠を指す(「愛着を示さない・愛想がない」の意味の「にべもない」の語源)。そこから、広く浮袋を「にべ」と呼称している。他にコイ・ウナギ、そしてサメなどの浮袋からも製造された。
・「鱣・鱘の二魚、皆、能く、龍と化す」は大いに気になる。魚偏の漢字の字義は、時代的地域的に大きな変異や諸説があり、その複雑多岐に亙る錯綜は、とても私の手におえるものではないのであるが、ここでどうしても気になるのは、「鱣」の項で私が言った「登龍門」の故事の魚類同定とのシンクロである。原義的には「鱣」は「コイの一種」ともされるのだ。そうして、現今、「鱘」は、中国語では、そうさ、チョウザメ目チョウザメ科 Acipenseridae のチョウザメ類を指すのである!]
***
■和漢三才圖會 江海無鱗魚 卷ノ五十一 ○五
しび
はつ
鮪【音委】
ヲイ
王鮪【其大者
【和名之比
或云波豆】
叔鮪【其小者
俗云目黒】
鮥子【更小者
俗云目鹿】
[やぶちゃん字注:以上七行は、前四行の下に入る。]
本綱鮪與鱘爲一物月令云季春天子薦鮪於寢廟故有
王鮪之稱郭璞云大者名王鮪【其小者名叔鮪更小者名鮥子】
△按鮪亦鱣屬鱘之類也本綱鱘鮪以爲一物者未精矣
鱘青碧色鼻長與身等鮪頭畧大鼻雖長不甚口有頷
下兩頰腮如銕兠鍪頰下有青斑死後眼出血背腹有
鬣無鱗【如有些細鱗】蒼黒色肚白如傅雲母尾有岐硬上大
中圓下小其大者一丈余小者六七尺肉肥淡赤色背
上肉有黒血肉兩條【俗曰血合】可去之其頭有力乘暖浮見
日目眩其來也成羣漁人熬取油其肉爲膾爲炙味稍
《改ページ》
佳
宇豆和【一名茶袋】 小鮪一尺以下者作胾以芥醋食味甚佳
目鹿 二尺以下小鮪亦可爲胾
目黑 三尺以下者多爲𩸆【凡宇豆和目黒共爲𩸆則通俗名目黒】
末黑 三四尺以上者至此時形畧扁色亦稍黒爲𩸆冬
月民間賞之亞于鰤又鮮肉作脯※〔→贗=贋〕鰹節
[やぶちゃん注:※=「贗」-「亻」。]
波豆 四五尺以上者與鮪無異惟腹鬐【鮪黃赤色波豆蒼黒】異身
其𩸆和州人嗜食之以一枚爲馬一駄
*
しび
はつ
鮪【音、委。】
ヲイ
王鮪〔(わういう)〕【其の大き者なり。和名、「之比〔(しび)〕」、或いは、「波豆〔(はつ)〕」と云ふ。】
叔鮪〔(しゆくいう)〕【其の小さき者は、俗に「目黒〔(めぐろ)〕」と云ふ。】
鮥子〔(くわいし)〕【更に小さき者は、俗に「目鹿〔(めじか)〕」と云ふ。】
「本綱」に、『鮪と鱘と、一物と爲す。「月令(がつりやう)」に云ふ、『季春、天子に〔→「に」は衍字、もしくは「は」の誤り〕、鮪を寢廟に薦(すゝ)む。』と。故に「王鮪」の稱、有り。郭璞〔(かくはく)〕が云はく、『大なる者を「王鮪」と名づく。』と【其の小さき者を「叔鮪」と名づく。更に小さき者を「鮥子〔(らくし)〕」と名づく。】。』と。
△按ずるに、鮪(しび)も亦、「鱣〔(ふか)〕」の屬にして、「鱘(かぢとをし)」の類なり。「本綱」に、「鱘」・「鮪」、以つて、一物と爲すは、未だ、精(くは)しからず。鱘は青碧色、鼻、長くして、身と等し。鮪は、頭、畧(ち)と、大きく、鼻、長しと雖も、甚〔(はなはだ)し〕からず。口、頷〔(あぎと)〕の下に有り。兩の頰・腮〔(あぎと)〕、銕-兠-鍪(かなかぶと)のごとし。頰の下、青斑、有り。死して後、眼に血を出だす。背・腹に鬐〔(ひれ)〕有りて、鱗、無し【些〔(いささ)〕か細〔かなる〕鱗、有るがごとし。】。蒼黒色。肚〔(はら)〕、白にして、雲母(きらゝ)を傅(つ〔(=着〕)くるがごとし。尾に、岐〔(また)〕有り。硬く、上〔は〕大、中〔は〕圓〔(まろ)〕く、下〔は〕小さし。其の大なる者、一丈余、小さき者、六、七尺。肉、肥えて、淡赤色。背の上の肉、黒き血肉、兩條(ふたすぢ)有り【俗に「血合〔(ちあひ)〕」と曰ふ。】。之れを去(す)つべし。其の頭〔(かしら)〕、力、有り、暖に乘じて浮く。〔→浮くに、〕日〔(ひ):太陽。〕を見、目、眩(くる)めく。其の來〔(きた)〕るや、羣〔(むれ)〕を成す。漁人、熬(い)りて、油を取り、其の肉、膾(さしみ)と爲す。炙(やきもの)に爲して、味、稍〔(やや)〕佳なり。
宇豆和【一名、「茶袋」。】 小さき鮪の一尺以下の者。胾(さしみ)に作り、芥醋(からしず)を以つて、食ふ。味、甚だ、佳なり。
目鹿(めじか) 二尺以下の小さき鮪。亦、胾に爲すべし。
目黑(めぐろ) 三尺以下の者。多くは𩸆(ひしほ)と爲す【凡そ、「宇豆和」・「目黑」、共に、𩸆(しほもの)と爲し、則ち、通俗して、「目黑」と名づく。】。
末黑(まぐろ) 三、四尺以上の者。此の時に至りて、形、畧(ち)と、扁たく、色も亦、稍〔(やや)〕黑し。𩸆と爲し、冬月、民間、之れを賞す。「鰤〔(ぶり)〕」に亞(つ)ぐ。又、鮮(あたら)しき肉、脯(ふし)に作り、鰹節に※〔贗=贋=似〕(にせ)る。
[やぶちゃん注:「※」=「贗」-「亻」。]
波豆(はつ) 四、五尺以上の者。鮪と異なること、無し。惟だ、腹の鬐〔(ひれ)〕【「鮪」は黃赤色、「波豆」は蒼黒。】、異なるのみ。其の𩸆(しほもの)を、和州〔=大和:奈良。〕の人、之れを嗜(す)きて、食ふ。一枚を以つて、馬一駄と爲す。
[やぶちゃん注:スズキ目サバ亜目サバ科マグロ属 Thunnus 。本邦産種は、
クロマグロ Thunnus orientalis (大西洋産クロマグロは、現在、別種タイセイヨウクロマグロ Thunnus thynnus とする)
ミナミマグロ Thunnus maccoyii
メバチマグロ Thunnus obesus
キハダマグロ Thunnus albacares
ビンナガマグロ Thunnus alalunga
コシナガ Thunnus tonggol
の六種を挙げれば、よいであろう。
・「しび」は、現在、主に関西・四国・九州南部の西日本でのキハダマグロ Thunnus albacares の呼称であるが、「古事記」の清寧天皇の条(古事記歌謡一〇八番歌)の平群志毘臣(へぐりのしびおみ)と袁祁命(おけのみこと)の、女を争った歌垣に、
*
潮瀨(しほせ)の波折(なを)りを見れば遊び來る鮪(しび)が端手(はたで)に妻立てり見ゆ
○やぶちゃん訳:海の早瀬の波が幾重にも立っている辺りを見ていると、泳ぎ来たった鮪(平群志毘臣を指す)の傍らに、魚の分際で、連れの女が寄り添っているのが見えるよ。
*
と現われ、「万葉集」でも二例あり、巻六の九三八番歌、山部赤人の神亀三年九月十五日(グレゴリオ暦換算七二六年十月十九日)、播磨国印南野行幸の従駕歌である長歌、
*
やすみしし 我が大君の 神(かむ)ながら 高(たか)知らせる 印南野(いなみの)の 大海(おふみ)の原の 荒拷(あらたへ)の 藤井の浦に 鮪(しび)釣ると 海人舟(あまねふね)騷ぎ 鹽燒くと 人ぞさはにある 浦を良(よ)み うべも釣はす 濱を良み うべも潮燒く あり通(がよ)ひ 見(め)さくも著(しる)し 淸き白濱
○やぶちゃん訳
我らが大君が、神としてお治めになる印南野の大海原、その藤井の浦で、鮪を釣ろうと、漁師の船が発ち騒ぎ、藻塩を焼こうと、人が賑わう。浦が良い故、尤もなことながら、鮪を釣るのだ。浜が良い故、尤もなことながら、藻塩を焼くのだ。大君が、足繁く、お通ひになり、ご覧になられる、その訳も、もうはっきりしているではないか、この清く美しい白浜よ!
*
及び、巻十九の四二一八番歌、大伴家持、越中在任中の和歌、
*
鮪(しび)突くと海人(あま)の燭(とも)せる漁火(いさりび)の秀(ほ)にか出ださむ我が下思(したも)ひを
○やぶちゃん訳
鮪を突こうと、漁師が灯している漁り火のように、はっきりと告げ知らせてしまおうか、この私の、秘めた思いを。
*
に現われることから、一般的な鮪が、非常に古くから「シビ」と呼称されていたことが分かる。なお、私は、この「古事記」や「万葉集」に現われた「シビ」はキハダマグロ Thunnus albacares ではないかと思っている。その理由は古事記歌謡一〇八番歌の「早瀨」は、海中にあって、比較的浅瀬に相当する場所であること、赤人の歌のシチュエーションが、内湾であり、家持の歌の漁が、夜であることから、これらの「シビ」は回遊性のマグロではなく、根付きのマグロである可能性が高いと考えるからである。表層近くを遊泳し、根付きの生態を持っているという特徴を最もよく示すのはキハダマグロであるという私見である。識者の意見を俟つ。
・「はつ」という呼称は、現在でも大阪の市場でキハダマグロの成魚の呼称として用いられており、上方落語の「菊江仏壇」にも「ハツの付け焼き」として鮪が登場する。
・「月令」は「礼記」(らいき)の第六篇で、一年の行事・天文・暦について書かれたものである。
・「季春、天子に、鮪を寢廟に薦(すゝ)む」は、古代中国に於いて、魚類を豊饒の祈りの供物としたことを示す。「月令」の季冬の月の条に、
*
命漁師始漁。天子親往。乃嘗魚。先薦寢廟。
漁師に命じて、始めて漁せしむ。天子、親(みづか)ら往き、乃(すなは)ち、魚を嘗(な)む。先づ、寝廟に薦む。
*
とあり、また、良安が引く季春の月の条には、
*
天子始乘舟。薦鮪于寢廟。乃爲麥祈實。
天子、始めて、舟に乘り、鮪(い)を、寝廟に薦め、乃ち、麥の爲に實りを祈る。
*
とある。この「寢廟」とは、祖霊を祭る建物を言う語である。
・「王鮪」――ここまで来て、はたと、気なる。古代中国にあって、祭儀の例祭の重要な供物とするようなものが、海産のマグロであるというのは如何にも不自然である。この「鮪」は、マグロではないのではないか? 「王」と名づくような巨大魚であり、黄河に棲息する淡水産の魚と言えば、これはもう、チョウザメ目チョウザメ科 Acipenseridae のチョウザメ類しかいないと私は思うのである。しかし、「廣漢和辭典」でも「鮪」は「シビ」で、マグロである……ところが、ここに来て、有力な情報を得た。それはまた、先般より私が拘っている「登龍門」の原種の同定とも関わる嬉しい内容であった。さて、『月刊しにか』(一九九五年九月号)の加納喜光氏の「漢字動物苑(6)チョウザメ」の中に、以下の記載が現われるからである。
《引用開始》
鯉が魚の王とされる以前はチョウザメが魚の王だった。『詩経』では婚礼や饗宴に用いられるめでたい魚とされている。春になると時期を違わずに黄河に出現すると、古代人は考えた。そのため、春一番のチョウザメを宇宙のリズムのシンボルとして宗廟に供え、季節祭を執り行った。以上のことは『周礼』や『礼記』に見える。
チョウザメが鯉に地位を譲るに当たって、登竜門の故事が利用されたふしがある。この故事の主役は実はチョウザメなのであった。竜門は黄河の中流にある山峡で、禹が山を穿ち水を通したという伝説がある。ここは急流になっているという。登竜門の故事を記した最古の文献は『淮南子』の高誘(後漢の人)の注釈である。[やぶちゃん注:以下が、その引用。原文では全体が二字下げ。一部の漢字を正字化した。]
鱣は大魚、長さは丈餘なり。細鱗黃首、白身短頭。口は腹下に在り。鮪(い)は大魚、また長さ丈餘なり。仲春二月、河西より上り、龍門を過ぐるを得れば、すなわち龍となる。
ここに出る鮪もチョウザメの一種である。[やぶちゃん注:一部を省略した。以下、中略。]
チョウザメを表す漢字と現存する種(五種ある)とを対照して同定する作業は困難だが、筆者は次のように考えている。鱣を最も大型のダウリアチョウザメ、鮪をカラチョウザメ、鱏(じん)[やぶちゃん注:原文では(つくり)が「譚」の(つくり)であるが、これが正字と思われる。]をハシナガチョウザメに当てる。鰉は鱣の別名、鱘や※[やぶちゃん注:※=僭の(にんべん)を「魚」に換える。]は鱏の別名とする。他の二種についてははっきりしない。[やぶちゃん注:後略。]
《引用終了》
ここで加納氏が引用する「淮南子」(高誘注)の該当箇所をネット検索した結果、一つだけ台灣のサイトに発見出来た(「《詩經·碩人》賞析」)。以下に該当原文を掲げる(喜光氏の引用部の前半部である)。
*
《淮南子·氾論訓》高誘注:“鱣、大魚、長丈餘、細鱗、黃首白身、短頭、口在腹下。鮪、大魚、亦長丈餘。”
*
なお、加納氏が後半で掲げるチョウザメの学名は、ダウリアチョウザメ Huso dauricus 、カラチョウザメ Acipenser sinensis 、ハシナガチョウザメ
Psephurus gladius である(現生種は二科三十六種に及ぶ。但し、一部の種は絶滅種である可能性が高い)。さて、以上の叙述を綜合して考えると、本項の「本草綱目」の引用に現われる「鮪」はマグロではなく、チョウザメであると明言してよい。このことは自明の方も多いのかもしれない。しかし、例えば、東洋文版現代語訳に対して私が大きな不満を持つのは、そのような注記が全く見られないことである。注とは真実を解明しないまでも、その探求への喚起となるものでなくては、付ける意味はないと、私は、常々、思っているのである。……それにしても、私がマグロの字義論等しているうちに、中国に多量の本物のマグロが流れて、国内のマグロ供給が脅かされている昨今は、皮肉といえば皮肉な話ではある。
・「郭璞」は、晋の学者で、驚天動地の博物学書「山海経」の最初の注釈者として有名。
・「未だ、精しからず」とは、「どうもよく分からない(=今一つ納得出来ない)」という意味である。良安先生、当然なのだ。「鱣」も「鱘」も「鮪」も、ここでは、総て、チョウザメを指しているのだから。
・「其の頭、力、有り」は、「力」の意味がよく意味が分からないが、通常、メバチマグロが海の中層を遊泳する(キハダマグロは表層近く)ことや、高速遊泳魚(最高時速百六十キロメートル)を前提としての言葉のようにも思える。
・「宇豆和」という呼称は、現在のマグロ属には用いられてはいないようである。因みに、伊豆地方や、沼津で、サバ科ソウダガツオ属のマルソウダガツオ Auxis rochei (一部の情報ではヒラソウダガツオ Auxis thazard とも)を「うずわ」と呼んでいることが、ネット上で確認出来た。
・「胾」は、「切り身・ししむら・大きく切った肉片」の意。
・「目鹿」については、クロマグロ Thunnus orientalis の四十センチメートルから一メートル前後の成魚の前段階のものを「メジマグロ」と、現在、呼称している。これに於いては、「雌鹿鮪」(めじかまぐろ)の略で、眼の周囲の肉が、鹿肉のように美味であったことからの命名とも、眼が、鼻先近くにあるのを、「目近(めじか)」と呼んだからだとも言われる。しかし一方で、やはり現在、前項のマルソウダガツオ Auxis rochei を別名で「めじか」と呼ぶ地方もある。
・「目黑」は、眼が黒々としているから「目黒」「メグロ」、それが訛って「マグロ」となったとする語源由来の一説にはある(別な説では、海で、その背部が、小山のように真っ黒に見えるところから「背黒」「セグロ」、それが「真黒」「マグロ」と訛ったとする)。しかし、メグロマグロとは、如何にも言いにくく、なんとなく紛らわしい。呼称としては、さても、生き残りそうもないように私には思われる。「メグロはやっぱりマグロに限る」。
・「𩸆(しほもの)」は、前後の叙述から、本来、マグロの調理法としては、刺身以上に、この「しおもの」、或いは、「ひしお」、則ち、「塩漬け」にしたものの方が一般的であったことを知る。これは、所謂、醤油や魚醤に漬け込んだもの(ヅケ)も含まれる。ヨーロッパでも現在、鮪は塩漬けが圧倒的に一般的である。但し、何度か、伊豆で購入したが、塩が強過ぎ、今一であった。
・「末黑」及び「波豆」は、ずばりクロマグロとしてよいであろう。最大長は三メートルを超える個体もある。
・「脯」は、本来は、「薄く裂いて塩漬けにした肉」を指す。この「ふし」という読みは、鰹節に合わせた「節」の当て読みであろう。
・「のみ」は、「身」という字を副助詞として読んだが、私の知る限り、このような訓読法は見たことがない。「身、其の𩸆を……」と読むことも考えたが、文意が通じない。単純に「耳」の誤字なのかも知れない。]
***
かつを
鰹
鰹【俗以堅魚二字爲鰹
蓋鰹乃鮦大
者非是也此
魚脯極堅硬
可削用故俗
呼曰堅魚
堅魚】
[やぶちゃん注:最後のダブっている「堅魚」は衍字であろう。]
【和名加豆乎】[やぶちゃん字注:以上八行は、前二行の下に入る。]
△按鮪之屬也狀似目黑而圓肥頭大嘴尖無鱗蒼黒色
有光膩腹白如雲母泥背有硬鰭到尾端兩片似鋸齒
《改ページ》
■和漢三才圖會 江海無鱗魚 卷ノ五十一 ○六
尾有岐其肉深紅味甘温背上兩邊肉中有黒血肉一
條【謂之血合其味不如正肉】釣之不用餌以牛角或鯨牙一瞬釣數
百關東殊多有
縷鰹 皮上縱有白縷三四條爲胾和芥醋未醬食甚佳
名之真鰹作節爲極上
橫輪 皮上橫有白斑四五條大一尺五七寸尾極細故
又名尾纎作節亞縷鰹作𩸆味甚佳俗呼曰須宇麻
餅鰹 形色同鰹而肉粘頗如飴生𩸆共味不佳
鰹節 鰹肉乾脯者也漁人造之鮮魚去頭尾出膓爲兩
片去中骨復割兩片肉作兩三條以煮熟取出曝乾則
堅硬而色赤如松節【故名鰹節】本邦日用之佳肴調和五味
之徧〔=偏〕一日不可欠者也土佐之產爲上【俗呼稱投出節】紀州熊
野次之阿州勢州又次之【以鮪脯僞之雖肥大味杳劣】
煮取 造鰹節時取其液滯者収之黒紫色味甘美
鰹醢【俗云太太木】 肉耑及小骨敲和爲醢紀州【熊野】勢州【桑名】遠
《改ページ》
州【荒井】之者爲上相州【小田原】次之奥州【棚倉】之醢色白味佳
酒盗 鰹膓爲醢出於阿波者得名爲肴則酒益勸故名
山家 いらこ崎に鰹釣舟ならひ浮きてはかちの濱にうかひてそ寄
西行
*
かつを
鰹
鰹【俗に「堅」「魚」の二字を以つて、「鰹」と爲す。蓋し、「鰹」は、乃〔(すなは)〕ち、「鮦」〔(とう)〕の大なる者〔にして〕、是に非ざるなり。此の魚の脯〔(ほじし)〕、極めて堅硬、削用すべし。故に俗に呼びて、「堅魚」と曰ふ。】
【和名、「加豆乎」。】
△按ずるに、鮪の屬なり。狀〔(かたち)〕、「目黑〔(まぐろ)〕」に似て、圓〔(まろ)〕く、肥え、頭〔(かしら)〕、大〔なり〕。嘴〔(くちばし)〕、尖りて、鱗、無し。蒼黒色。光る膩〔(あぶら)〕、有り。腹、白く、雲母泥(きらゝ〔でい〕)のごとく、背に、硬き鰭、有り。尾の端に到るまで、兩片、鋸齒〔(のこぎりのは)〕に似たり。尾に、岐〔(また)〕、有り。其の肉、深紅、味、甘く、温〔たり〕。背の上、兩邊〔の〕肉中、黑血肉〔(くろちのにく)〕、一條、有り【之れを「血合〔(ちあひ)〕」と謂ひ、其の味、正肉にしかず。】。之れを釣るに、餌を用ひずして、牛角、或いは、鯨の牙を以つて、一瞬に、數百〔(すひやく)〕を釣る。關東、殊に、多く、有り。
縷(すぢ)鰹 皮の上に、縱(たつ〔=たて〕)に、白き縷〔(すぢ)〕、三、四條、有り。胾(さしみ)と爲し、芥醋〔(からしず)〕・未醬〔(みそ):味噌。〕に和して食ふ、甚だ、佳し。之れを「真鰹(まがつを)」と名づく。節に作りて、極上と爲す。
橫輪(よこわ) 皮の上、橫に、白斑、四、五條、有り。大いさ、一尺五、七寸、尾、極めて細き故、又、「尾纎(〔を〕ほぞ)」と名づく。節に作り、「縷鰹〔(すぢがつを〕」に亞〔(つ)〕ぐ。𩸆〔(ひしほ)〕に作り、味、甚だ、佳〔なり〕。俗に呼んで、「須宇麻〔(すうま)〕」と曰ふ。
餠(もち)鰹 形色、鰹に同じくして、肉、粘(ねば)る。頗〔(すこぶ)〕る、飴(あめ)のごとし。生・𩸆とも、味、佳ならず。
鰹節(ぶし) 鰹の肉を乾-脯(ほし)たる者なり。漁人、之れを造るに、鮮〔(あたら)〕しき魚、頭・尾を去り、膓〔(わた)〕を出だし、兩片と爲し、中骨〔(なかぼね)〕を去り、復〔(ま)〕た、兩片の肉を割〔(さ)〕き、兩三條と作〔(な)〕し、以つて、煮熟〔:十分に煮込む〕し、取〔り〕出〔(いだ)〕し、曝し乾せば、則ち、堅-硬〔(かた)〕くして、色、赤きこと、松の節のごとし【故に「鰹節」と名づく。】。本邦日用の佳肴〔(かかう)〕、五味の徧〔(かたより)〕を調和す。一日も欠(か)くべからざる者なり。土佐の產を上と爲す【俗に呼びて「投出節〔(なげだしぶし)〕」と稱す。】。紀州熊野、之れに次ぐ。阿州〔=阿波〕・勢州〔=伊勢〕、又、之れに次ぐ【鮪脯〔(まぐろのほじし)〕を以つて、之れを僞〔(いつは)〕る。肥大と雖も、味、杳(はるか)に劣れり。】。
煮取(にとり) 鰹節を造る時、其の液(しる)、滯〔(とどこほ)〕る者を、取りて、之れを収む。黒紫色、味、甘美〔なり〕。
鰹醢(たゝき)【俗に「太太木」と云ふ。】 肉の耑(はし=端)及び小骨、敲(たゝ)き、和して、醢(しほから)と爲す。紀州【熊野。】・勢州【桑名。】・遠州【荒井。】の者、上と爲し、相州【小田原。】、之れに次ぐ。奥州【棚倉。】の醢〔(しほから)〕、色、白くして、味、佳し。
酒盗(しゆとう[やぶちゃん注:ママ。「しゆたう」が正しい。]) 鰹の膓(わた)を醢(しほから)と爲す。阿波より出づる者、名を得。肴〔(さかな)〕と爲し、則ち、酒、益々、勸む。故に名づく。
「山家」 いらこ崎に鰹釣舟ならび浮きてはがちの濱にうかびてぞ寄る
西行
[種としてのカツオ Katsuwonus pelamis は、スズキ目サバ亜目サバ科カツオ属の一属一種である。但し、同定に際しては、以下の五種辺りを「カツオ」の仲間として認識しておく必要があろうかとは思われる。
サバ科ハガツオ属ハガツオ Sarda orientalis
サバ科スマ属スマ Euthynnus affinis
サバ科イソマグロ属イソマグロ Gymnosarda unicolor(本種には「マグロ」の名がつくが、分類学上は、「ハガツオ」に近縁で、魚体も、「カツオ」から、そう離れていないので、挙げておきたい)
サバ科ソウダガツオ属ヒラソウダガツオ Auxis thazard
サバ科ソウダガツオ属マルソウダガツオ Auxis rochei
である。
・「鰹」は、中国では大鰻(おおうなぎ)を指し、「鮦」は、「鰹(かつお)」と「鱧(はも)」を指す漢字で、良安は「鰹」の本字は、ハモや類似したウナギや、それらの大型化したもの(オオウナギ)だと言いたいのであろう。ちなみにハモ Muraenesox cinereus は、ウナギ目アナゴ亜目ハモ科 Muraenesocidae である。ウナギはウナギ目ウナギ科 lidae に属する魚の総称であるが、オオウナギという呼称は大型のウナギ一般を指す場合と、種としてのオオウナギ Anguilla marmorata を指す場合があるので要注意だが、ここでは、一般名詞としてとってよい。
・「鮪の屬」という判断は、現在の分類学上からも、マグロもカツオもスズキ目サバ科 Scombridae である点で、一致している。
・「鱗無し」は、同族のマグロ類との大きな相違点である。カツオには胸甲部や側線等の一部を除いて、実際に鱗がないのに対し、マグロ類は全体が鱗で覆われ(但し、高速遊泳の抵抗にならないよう、表面に、比較的、平板に分布している)、特に胸甲部や側線の鱗は、一層、大きくなっている。
・「光る膩」は、背部の青みがかった油を流したような(角度によって、やや虹色に耀く)部分を指しているか。
・「雲母泥」は、層状のケイ酸塩鉱物の結晶である雲母を粉末にしたものを、半液状の他の顔料と合わせた顔料の名であろう。
・「縷鰹」(すじがつを)はカツオ Katsuwonus pelamis である。現在、魚類にあっては、体軸に沿って横に走る縞を「縱縞」と呼ぶが、それが本件でも通用するかどうかが問題となる。しかし、次の小項目の呼称が「橫輪」(「輪」である以上、これは、「魚体を一周する」の意味である)であることに着目すれば、これはクリアされていると判断する。なお、この縦縞は、生時には、殆ど見られないもので、死後に現れるとよく言われるが、実際には、次項で述べる横縞同様、生時にあっても、興奮すると、出現する斑紋であるようだ。なお、この縦縞がカツオ Katsuwonus pelamis では腹部に現れ、ハガツオ Sarda orientalis では、背部に現れるので、容易に識別が出来る。
・「横輪」は、恐らく、カツオ Katsuwonus pelamis の中型の大きさのものを言っているか。この横縞は、実は、カツオに一般的に見られるもので、既に述べた通り、通常は目立たないが、興奮すると、浮き出してくるという(四条から十条程度)。この横縞は死ぬと消え、代わりに前項で示した縦縞がはっきり現れるという。
・「餅鰹」もカツオ Katsuwonus pelamis で、死後硬直するまでの新鮮なカツオ(従って、身が柔らかく、餅のような食感がある)のことを指すか、若しくは、「味、佳ならず」という叙述からは、身がカツオより柔らかく、時間が経つと独特の薬品のような臭いを発するハガツオ Sarda orientalis を指している可能性もある。前者は、静岡県西部で、現在も「モチガツオ」と呼称し、殆どが地元で消費されると聞く。
・「五味」は、甘・酸・鹹・苦・辛の総称。
・「投出節」については、これ(投出節)自体を探索している静岡の鰹節店「柳屋本店」のサイト中の、雑話の中の、『第二話 江戸時代の名物「かつお」』に譲る(現在は当該ページは消失している模様)。現在、高知県では、少なくともこの呼称では、伝承されていないと思われる。「なげだしぶし」と読んでよいであろう。
・「煮取」は、「にんべん」公式サイトの「鰹節の歴史」のページに、「堅魚煎汁」と書いて「カツオノイロリ」と読みを附し、鰹節が誕生する以前から貴重な調味料として使われてきたことが記されてある。現在では「煎汁(せんじ)」や「エキス」と呼ばれているらしい。鰹の煮汁を、数日とろみが出るまで煮込み上げた液で、鹿児島枕崎等で「かつおせんじ」若しくは「かつおせんじエキス」という商品名で現在も出回っているようである。私がよくお世話になっている「MANAしんぶん」の「タレとツユとダシの言葉について」というページに、「古事類苑」「飮食部四」の「料理下」の「だし」「生垂」「煮貫」の部分を引用してある。原典を所持していないが、これは、この呼称や使用法の参考になるので、そのままコピー引用させて戴いた(構文にエラーがあるのか、右クリック・コピーとHTML上の表示には齟齬があり、コピーの方が正しいと判断した。傍点「〇」部分は下線に換えた。推測するに〔 〕が書編巻名、[ ]がHP編者の注、{ }が本文の割注と思われる。『〔厨事類記〕寒汁實{○中略}』の「{○中略}」の「〇」の意味は不明)。
《引用開始》
○だし
〔倭訓栞 中編十三多〕だし 垂汁の義、又煮出の義、
〔屠龍工随筆〕鰹ぶしを味に用る事、いつよりありつるとも志らず、古へには沙汰もなきことなりけり、然而延喜式大膳式に、鰹の汁幾*[木ヘン+盃ツクリ=はい]と出文、宇治拾遺物語に、みせんといふもの見えたるは、文字いかに書ともしれざれども、事のさま、今いふ水出しの様におもはれたり、
〔一話一言 二十一〕煎汁
薩摩より出る鰹煎汁を、外の國にては ニトリといふ、薩摩にては センといふ、和名抄に煎汁とあれば古語なりと、忍池子の話、{九月初三}
〔料理物語 なまだれだし〕だしは かつほのよきところをかきて、一升あらば水一升五合入、せんじあぢをすひ見候て、あまみよきほどにあげてよし、過候てもあしく候、二番もせんじつかひ候、精進のだしは かんへう 昆布{やきても入}ほしたで、もちごめ、{ふくろに入に候}ほしかぶら、干大根、右之之内取合よし、
〔厨事類記〕寒汁實{○中略}
或説云、寒汁ニ鯉味噌ヲ供ス、コヒノミヲヲロシテ、サラニモリテマイラス、 ダシ汁{或説イロリニテアルベシ、或説ワタイリノシル云々、}にてアフベシ、
○生垂
〔料理物語 なまだれだし〕
生垂(なまだれ)は 味噌一升に水三升入、もみたてふくろにてたれ申候也、
垂味噌(たれみそ) みそ一升に水三升五合入、せんじ三升ほどになりたる時、ふくろに入たれ申候也、
○煮貫
〔料理物語 なまだれだし〕煮貫(にぬき) なまだれにかつほを入、せんじこしたるもの也、
〔料理物語 萬聞書〕煮貫は 味噌五合、水一升五合、かつほ二ふし入せんじ、ふくろに入たれ候、汲返し汲返三辺こしてよし、
《引用終了》
・「鰹醢」は、現在の「鰹のタタキ」とは異なり、文字通り、包丁で細かく叩いて塩蔵した塩辛である。本来「たたき(叩き・敲き)」は「たたき塩辛」であって、魚や鳥獣の肉等を庖丁でたたく調理法を指し、自然に、それを保存食として塩辛と成したようである。現在は、あの「鰹のタタキ」が席捲してしまい、この呼称では、塩辛としては生き残っていないようである。ちなみに、現在の鰹のタタキの作り方については、かつて自分のブログに「鰹のたたきという幸福」で、僕のこだわりを記載した。ご笑覧あれ。
・「荒井」は、現在の静岡県新居町(あらいちょう)新居(グーグル・マップ・データ。以下、無指示は同じ)。但し、ここは関所があったために、人口に膾炙していたことから挙げられた名であって、実際に、鰹が多く陸揚げされたのは、漁港として栄えた新居の東直近の対岸の舞阪(静岡県浜松市西区舞阪町(まいさかちょう)舞阪)であったと考えるべきであろう(現在も、そうである)。
・「棚倉」は、現在の福島県南東部東白川郡棚倉町棚倉。内陸に位置するが、ここを支配していた棚倉藩は、飛び地として港湾地である平潟を領地とし、そこが言わば藩の表玄関の役割を持っていた。更に、仙台・三陸・松前の物産がこの平潟に集積した。サイト「平潟港の歴史」の「平潟港で交易された商品」によれば、平潟港の棚倉藩運上規定の「荷物出投」(物品税)が課せられた海産物の筆頭に鰹が挙げられている。さればこその、「棚倉の鰹の塩辛」なのであろう。
・「酒盗」は、ウィキペディア等の記載を見ると、どうもこの「和漢三才圖會」の記述が最も古いものであるらしい。「鰹の塩辛」とも呼称されるが、塩辛との決定的な違いは、加工時の長期熟成(一年)にある。因みに、実は酒盗は、加熱によって、コクが増す。「酒盗たれ」(酒盗を細かく刻んで酒炒りしたもの)と称して調味料になる。旨い。お試しあれ。
・「いらこ崎……」の歌は西行の「山家集」(治承二(一一七八)年頃、、西行五十歳代後半に原型が成立したとされる)には、詞書とともに、次のように記されてある。
*
沖の方より、風のあしきとて、鰹と申す魚(いを)釣りける舟どもの歸りけるに
伊良湖崎に鰹釣り舟並び浮きて北西風(はがち)の波に浮かびつつぞ寄る
○やぶちゃん訳
沖の方から、「風が良くない。」と、鰹と申します魚を釣る、何艘もの舟が、陸(おか)へと、帰ってきたのを詠むに、
伊良湖崎に鰹釣りの舟が一斉に並んで浮き、北西風(はがち)に立つ波に揺られながら、浜辺をさして寄ってくることよ。
*
とあり、下の句の第四句に、本文の「濵」→「波」の異同が見られる。なお、「西行法師家集」には、
*
伊良湖崎に鰹釣る舟並び浮き遙けき浪に浮かれてぞ寄る
*
という類型歌が見え、意味から見ても、「波」が正しい。なお、「はがち」であるが、小学館「日本国語大辞典」によれば、語源説は、『吹き放つ義のハガツ(放)から』とするが、引用元を幸田露伴の「音幻論」とし、私には、ちょっと、眉唾に思えなくもない(幸田露伴は今一つ好きになれない作家であるから)。]
***
なめいを
鮠【音危】
クイ
鮰魚 鱯魚
𩸄魚 ※魚
[やぶちゃん字注:※=「魚」+「賴」。「グリフウィキ」のこれ。]
【俗云奈女魚】
【和名抄訓
波江謬也】
[やぶちゃん字注:以上五行は、前三行の下に入る。]
本綱鮠生江淮間無鱗魚亦鱘之屬而頭尾鬐共似鱘惟
鼻短爾口亦在頷下骨不柔脆腹似鮎背有肉鬐
肉【甘平】不可合野猪野雞食令人生癩
△按鮠狀似鱣亦如鮎而身圓其大者長至一三丈灰色
無眼但頭上有二穴而吹潮其尾似鯨尾肉味亦畧如
鯨脂多熬取燈油
*
なめいを
鮠【音、危。】
クイ
鮰魚 鱯魚
𩸄魚〔(くわぎよ)〕 ※魚〔(らいぎよ)〕
[やぶちゃん字注:※=「魚」+「賴」。「グリフウィキ」のこれ。]
【俗に奈女魚と云ふ。】
【「和名抄」に「波江」と訓ずるは、謬りなり。】
「本綱」に『鮠は、江淮の間に生ず。無鱗魚。亦、鱘〔(かじき)〕の屬にして、頭〔(かしら)〕・尾・鬐、共に鱘に似る。惟だ、鼻、短きのみ。口も亦、頷〔(おとがひ)〕の下に在り。骨、柔-脆(もろ)からず。腹、鮎(なまづ)に似て、背に、肉鬐〔(にくひれ)〕、有り。肉【甘、平。】野-猪(いのしし)・野-雞(きじ)と、合はせて食ふべからず。人を〔して〕癩〔(らい)〕を生ずる〔→生ぜしむ〕。』
△按ずるに、鮠は、狀〔(かたち)〕、鱣(ふか)に似て、亦、鮎(なまづ)のごとくにして、身、圓〔(まろ)〕く、其の大なる者、長さ一、三丈に至り、灰色、眼〔(まなこ)〕、無く、但だ、頭〔(かしら)〕の上に、二穴、有りて、潮を吹く。其の尾、鯨の尾に似て、肉味は、亦、畧〔(ほぼ)〕、鯨のごとく、脂、多し。熬りて、燈油を取る。
[やぶちゃん注:これは勿論、現在の淡水魚の鮠(はや)、「和名抄」の意味する異名「ハエ」・「ハヤ」で、何度も述べた、複数の種を含むところの「はや」の一種で、狭義に一部地方の異名とするウグイ Tribolodon hakonensis とするところの、それらでは、毛頭、有り得ない(この際、単体記事で示せる私の「大和本草卷之十三 魚之上 ウグヒ (ウグイ)」をリンクさせておく。そこの私の注の冒頭で、恐らくは、最も漏れのない「ハヤ・ハヨ」の全貌を指示出来ていると思うからである)「それでは、一体、何であるか? まず、「本草綱目」と良安の叙述に於いて、「鮠」が同じものを指しているかどうかが問題となるが、良安は注意深く、「鱘」と同族を示す「鱣」を示し、「鮎」を中国語の意味として「なまづ」と訓じている点で、同一の生物を語っていると見てよい。そうなると、両者の語る内容を総合して種同定してよいと考えられる。
まず、「本草綱目」から見よう。「江淮」とは、長江(揚子江)と淮水(河南省に発し東シナ海に注ぐ中国第三の大河)を指す。この生息域(淡水域主体)の限定は大きい。鱗がなく、鱘の同属で、全体が鱘に似ているが、鼻が短い、とする。この「鱘」は、取り敢えず、良安の解釈によれば、カジキである。但し、私は先に記した通り、これをチョウザメ目チョウザメ科 Acipenseridae のチョウザメ類とする解を捨てられない(なお、冒頭にある「鮰魚」という名称は、まさに、現代中国で、揚子江に棲息するチョウザメに与えられている)。しかし、その、どちらでも、形態的説明は齟齬しないとも私は思うのである。口が顎の下にあって、骨格はしっかりして、腹部が鯰のように(「白くふくよかである」と解してよい)、背部に盛り上がった肉のような鰭を具えている、とする。
次に良安の見解を見る。まず、形状は鱣に似ている、とする。ここでの「鱣」は良安の言だから、「フカ」を指して言っている(しかし、それが中国の書からの孫引きならば、やはり、私のこだわるチョウザメの解となる。先に述べた通り、それでも齟齬しない)。時珍の叙述をそのまま引いたかと思われるような鯰との形状類似を言い、そこで「身、圓く」とする。この「丸い」というのは、魚体の正中線上での断面の形状を言っている(挿絵からも歴然)。大型個体は三~九メートルとするが、成体の大型個体が、こんなに差があるのは、如何にも不自然である。概して良安の度量衡サイズは、他の項目でもオーバー気味であるから、この体長は同定素材としては使えない。体色は灰色で、目がなく――これは好意的には、「目がごく小さい」こと、「眼として認識し得る部分がない」というを示していると考えることが可能だが……)、頭部上に二つの孔(不審。噴気孔は一つしかない。最後に検証する)があって、潮を吹き上げ、尾は鯨にており、肉の味も、殆んど、鯨に等しくて、脂分が多いとし、煎って燈油を採取する、とする。
さて、ここで本項冒頭の本種の和名に着目しよう。「なめいを」とは、「舐める魚」であり、「海底の砂を舐めるようにして泳ぐ魚」、則ち、この魚は、「浅海域の砂泥地を砂を擦るように遊泳する生物」であることを示している――もう、とっくにお分かりであろう、本種はクジラ目ハクジラ亜目ネズミイルカ科スナメリ属 Neophocaena に属する小型イルカ、スナメリ(和名の漢字表記は「砂滑」)の名称と合致する・また、次項が、「海豚魚(いるか)」であることも強い親和性を認めることが出来るのである。
そこで、実際のスナメリと本叙述を比較してみると、日本を棲息域の北限とし、淡水である中国の揚子江にも棲息する(現在は「江豚」と呼称。但し、現在の中国では絶滅危機状態にある)=「江淮の間に生ず」。スナメリには背鰭が、殆んどないものの、皮膚が盛り上がった隆起=「背に、肉鬐、有り」であり、口吻部は、殆んど発達していない(=「鼻、短き」)、成体個体は、全身に明るい灰色を呈している(=「灰色」)。その他のクジラ類の特徴は、いちいち挙げて検証するには及ぶまい(本邦に於いて過去にスナメリの食用や採油の事実も確認済みである。因みに、最体長は二メートル弱である。また、この背部正中線に沿って、首の後方から肛門付近にまで存在する、黒い粒状紋のある隆起(高さ二~三センチメートル)が、スナメリ識別の最大の特徴である)。はっきり示そう。本種は
クジラ目ハクジラ亜目ネズミイルカ科スナメリ属スナメリ Neophocaena phocaenoides
である。
・「人をして、癩を生ぜしむ」は甚だしい誤りである。「癩」は現在は「ハンセン病」と呼称せねばならない。抗酸菌(マイコバクテリウム属 Mycobacterium に属する細菌の総称。他に結核菌・非結核性抗酸菌が属す)の一種である「らい菌」( Mycobacterium leprae )の末梢神経細胞内寄生によって惹起される感染症。感染力は低いが、その外見上の組織病変が多様で激しいことから、洋の東西を問わず、「業病」「天刑病」という誤った認識・偏見の中で、今現在まで、不当な患者差別が行われてきている(一九九六年に悪法「らい予防法」が廃止されても、それは終わっていない)。歴史的に差別感を強く示す「癩病」という呼称の使用は解消されるべきと私は考えるが、何故か、菌名の方は「らい菌」のままである。おかしなことだ。「ハンセン菌」でよい(但し、再三述べてきたように、「言葉狩り」をしても意識の変革なしに、差別は、なくならない)。ハンセン病への正しい理解を以って本記載は批判的に読まれたい。但し、ここで言う「癩」は、ハンセン病以外の広い意味での皮膚病変をも含むものであろうことは押さえておく必要はあろう。
・「頭の上に、二穴、有り」とあるが、噴気口(鼻孔)は一穴である。但し、噴気孔の後ろに僅かな陥没が見られるだけで、この噴気孔は海中で閉じている際には、実は、殆んど判らないのだ。されば、良安は実物個体を見ることなく、全くの聴き書きで誤認(或いは、騙されて)し、「頭の上に穴二つ」と認識した。而して――この挿絵の頭部の目にしか見えない黒いごく小さな二点は――実は――噴気孔を描いたもの――と読まざるを得ないのである。これは、挿絵だけを見ていると、違和感をそれほど感じない――しかし――トンデモ博物画であることが暴露されるのである!]
***
《改ページ》
■和漢三才圖會 江海無鱗魚 卷ノ五十一 ○七
いるか
海豚魚
ハアイトヲンイユイ
海豨 江豚
江豬 水豬
鱀【音志】 䱐鯆
[やぶちゃん字注:「鱀」は、正確には、「既」は「既」。]
𩽝【音讒】 鯆【音 】
[やぶちゃん字注:「鯆」の割注の「音」の漢字は欠字。]
【和名伊留可】[やぶちゃん字注:以上五行は、前三行の下に入る。]
本綱海豚魚狀大如數百斤豬形色青黒如鮎有雌雄有
兩乳類人數枚同行一浮一沒謂之拜風其骨硬其肉肥
不中食其膏最多和石灰艌舩良也味【鹹腥】如水牛肉
生海中曰海豚候風潮出沒其鼻在腦上作聲噴水直上
百數爲羣其子如蠡魚子數萬隨母而行人取子繫水中
其母自來就而取之
生江中曰江豚小於海豚出没水上舟人候之占風其中
有肉脂㸃燈照樗蒲【博奕※也】卽明讀書工作卽暗俗言懶
[やぶちゃん字注:「※」=「塞」の「土」を「石」に換える。]
婦所化也
△按海豚西國多有狀似豚眼細狹亦如豚齒細小背有
《改ページ》
刺鬛兩鰭如足尾有岐硬漁人不好采如得之投岸棄
之有聲此鳴鼻乎
*
いるか
海豚魚
ハアイトヲンイユイ
海豨〔(かいき)〕 江豚
江豬〔(こうちよ)〕 水豬
鱀【音、志】 䱐鯆
[やぶちゃん字注:「鱀」は、正確には、「既」は「既」。]
𩽝【音讒】 鯆【音、 】
[やぶちゃん字注:「鯆」の割注の「音」の漢字は欠字。]
【和名、「伊留可」。】
[やぶちゃん字注:以上五行は、前三行の下に入る。]
「本綱」に、『海豚魚は、狀〔(かたち)〕・大〔いさ〕、數百斤の豬〔(ゐのこ)=豚〕の形のごとし。色、青黒にして、鮎(なまづ)のごとし。雌雄、有り。兩乳、有りて、人に類す。數枚〔=匹〕同行〔して〕、一〔つは〕浮〔き〕、一〔つは〕没〔す〕。之れを「拝風」と謂ふ。其の骨、硬く、其の肉、肥え、食ふに、中〔(あた)〕らず。其の膏〔(あぶら)〕、最も多し。石灰に和して、舩を艌(つくろ:=繕)ふに良し。味【鹹、腥。】、水牛の肉のごとし。海中に生ずるを「海豚」と曰ふ。風〔と〕潮〔(しほ)〕を候〔(うかが)〕ひて、出沒す。其の鼻、腦の上に在り、聲を作〔(な)〕し、水を噴き、直(たゞち)に上〔(あげ)〕る。百數、羣を爲す。其の子、蠡〔(れい)〕の魚の子のごとし。數萬〔(すまん)〕、母に隨ひて、行く。人、子を取りて、水中に繫(つな)げば、其の母、自〔(おのづか)〕ら、來〔(きた)〕る。就いて〔は〕、之れを取る。
江中に生ずるを「江豚」と曰ふ。「海豚」より、小さし。水の上に出没す。舟人、之れを候ひて、風を、占なふ。其の中に、肉脂〔(にくあぶら)〕、有り。燈に點じて、樗蒲(ちよぼ)【博奕〔(ばくえき)〕の※〔=塞:場所。〕なり。】を照らさば、卽ち、明なり。讀書・工作を照せば、卽ち、暗し。俗に言ふ、「懶婦の化する所なり。」と。』と。
[やぶちゃん字注:「※」=「塞」の「土」を「石」に換えたもの。]
△按ずるに、海豚は西國に多く有り。狀、豚に似て、眼、細く狹く、亦、豚のごとし。齒、細く小さく、背に刺鬛〔(とげひれ)〕有り。兩鰭、足のごとく、尾に岐有りて硬し。漁人、好んで〔は〕采らず。之を得れば、岸に投じて之を棄つ。聲有り、此れ鼻を鳴らすか。
[やぶちゃん注:イルカはクジラ目ハクジラ亜目 Odontoceti に属する水生哺乳動物の中で、比較的小型の種類を呼ぶ通称である。「海豚」・「江豚」について、時珍は、その大きさによる(後者が有意に小さい)と記述されるが、現代中国に於いては、「江豚」は、前項の「鮠」=クジラ目ハクジラ亜目ネズミイルカ科スナメリ属スナメリ Neophocaena phocaenoides を指す。
・「豨」は、大きな豚。
・「鯆【音、 】」の「鯆」は音が「フ」で、漢語では、鯨偶蹄目 Whippomorpha 亜目 Cetacea 下目ハクジラ小目ヨウスコウカワイルカ科ヨウスコウカワイルカ属ヨウスコウカワイルカ Lipotes vexillifer を指す語である。昨年暮れ、ひっそりと、揚子江固有種にして一科一属一種のヨウスコウカワイルカLipotes vexillifer(中国名・揚子江河海豚、別称・長江女神)の公的な絶滅宣言がなされた。先日、二〇〇七年八月八日、中国人専門家からは、「国際自然保護連合の絶滅の定義は、五十年間、自然界で、一度も発見されなければ、絶滅と判定する、と明記されている。一九九七年に十三頭が確認され、そのわずか九年後の二〇〇六年に行われた大規模調査の結果だけで絶滅と判定することはできない。」と疑義がなされたが、そんなこっちゃあないんだ! 見つけて救ってこそなんぼのもんじゃ! こんな反論するくらいなら、専門家なら一匹でも探して来いよ!)。汚染し、そうして、女神に見放された長江よ……その水に繋がるガイアよ、僕らは一体、何処へ行ってしまおうとしているのだろう……]
・「鱀魚」は、漢方系の記載によれば、「鱧魚」・「烏魚」とも言い、タイワンドジョウ科カムルチー Channa argus を指すとする。これが、所謂、カムルーチ=「ライギョ」(雷魚)を指す語とすれば、形状の極めて似たタイワンドジョウ Channa maculata も同定候補として挙げておくべきであろう。
・「樗蒲」は本邦では「かりうち」とも言い、楕円形の平たい木片を、一方を白、一方を黒く塗ったもの四枚を用い、それを投げて、出た面の組合せで勝負を競う博打の一種を指す。朝鮮では「ユッ」と言う。これとほぼ同じものが、骸子の代りに現在でも用いられているという。また、「樗」は、ミツバウツギ科のゴンズイ Euscaphis japonica 、「蒲」は、ヤナギ科のカワヤナギ Salix gilgiana で、ともに骸子の材料に用いられた木である。さて、この割注の「※」「※」は「塞」の「土」を「石」に換えたものだが、こんな漢字は知らない。「塞」の異体字にも見られない。さて、これに就いては、東洋文庫版では、「塞」の誤字と取ったらしく、「塞」の字で起してあり、『ばしょ』(=場所・賭博場)のルビを振る。確かに一見すると、それで意味が通るのではあるが、私は、これは――「賽」(=「骸子」(さいころ))の誤字――ではないかと思うのである。偶然であるが、「塞」は「賽」に通じる字で、従って、東洋文庫版のように「塞」でもよいが、これは場所を指しているのではなく、「賽」=「骰子」、さらには、「骸子賭博と言う遊戯そのもの」を指して注しているのだと思う。さればこそ、後に「讀書・工作」と対照並列すると言えると思うのである。
・「懶婦」は「怠ける女・不精な女」の意(別に「蟋蟀」(こおろぎ)の別名でもある)。]
***
ふぐ
ふくへ
ふくと
河豚
ホウ トヲン
吹吐魚 嗔魚〔(しんぎよ)〕
鮭【䲅同】 鯸鮐
鯸䱌 鰗鮧
氣包魚
【和名布久
一云布久閉】
[やぶちゃん字注:以上六行は、前五行の下に入る。]
本綱河豚魚江淮河海皆有之狀如蝌斗大者尺餘背青
白有黃縷無鱗無腮無膽目能開闔觸物卽嗔怒腹張如
氣毬浮起【故名之氣包魚】腹下白而不光率以三頭相從爲一部
春月珍賞之其腹腴味最美呼爲西施乳【凡魚之無鱗無腮無膽有聲目
能睫者者皆有毒】此魚備毒品狀故人畏之其肝及子有大毒然有
二種其色炎黒有文㸃者名斑魚毒最甚【凡煮之忌煤灰落中】此魚
挿樹立便乾枯【狗膽塗其樹復當榮盛】雖小而獺及大魚不敢啖之
則不惟毒人又能毒物也食之一日内不可服湯藥【荊芥大忌】
《改ページ》
■和漢三才圖會 江海無鱗魚 卷ノ五十一 ○八
中其毒者以槐花【微炒】乾臙脂【等分爲末】水調灌之大妙
△按河豚魚雖河之名河中無之在江海耳【對海豚江豚名河豚名
乎】狀如上說自頭至尾腹背有小鬛如刺其尾無岐而
細肉白味【淡】脆美而不飽大骨兩邊有赤血肉又腸胃
後傍大骨有如胡蝶形者青白色投水如動此物有大
毒殺人【猫犬亦食作斃】
鯖鯸 皮薄柔而有滑背黃白斑腹白頭畧方其眼大而
腹背無刺鬛其肚不甚脹微似鯖故名煮食炙食無毒
名護屋鯸 背黃赤有白㸃無刺鬛腹白味不美惟剥皮
乾之名皮鯸夏月爲臛食之凡鯸九月至二月出冬月
最賞之故夏以皮鯸代之
鮮鯸能洗浄腸血食之不中毒冬月争喫也和漢共然焉
其味以異于他也又食之擧家皆死者予亦見之胒〔→昵〕暫
時口味賭身命矣與※〔=密〕媱者趣一也
[やぶちゃん字注:「※」は「密」の「必」を「發」の(はつがしら)に代えたもの。「密」の異体字に酷似したものがあるので、訓読では「密」に代えた。]
*
ふぐ
ふくべ
ふくと
河豚
ホウ トヲン
吹吐魚 嗔魚
鮭〔(けい)〕【䲅〔(き)〕と同じ。】 鯸鮐〔(こうたい)〕
鯸䱌〔(こうい)〕 鰗鮧〔(こい)〕
氣包魚〔(きはうぎよ)〕
【和名、「布久」。一に「布久閉」と云ふ。】
「本綱」に『河豚魚は、江淮河海、皆、之れ、有り。狀〔(かたち)〕、蝌斗(かへるのこ)のごとく、大なる者、尺餘。背、青白にして、黃なる縷(すぢ)有り。鱗、無く、腮〔(あぎと)〕、無く、膽〔(きも)〕無く、目、能く、開闔〔(かいかふ)=開閉〕す。物に觸るれば、卽ち、嗔-怒(いか)りて、腹、張〔りて〕、氣-毬(まり)の浮き起こるがごとし【故に、之れを「氣包魚」と名づく。】。腹の下、白くして、光らず。率〔(おほ)〕むね、三頭を以つて、相〔あひ〕從ふ。〔→從ひ、〕一部と爲す。春月、之れを珍賞す。其の腹の腴(つちすり)の味、最も美なり。呼びて「西施乳」と爲す【凡そ、魚の、鱗、無く、腮、無く、膽、無く、聲、有り、目、能く睫(またゝ)く者、皆、毒、有り。】。此の魚、毒品〔(どくひん)〕の狀を備(そな)ふ。故に、人、之れを畏る。其の肝、及び、子に、大毒、有り。然〔(しか)〕も、二種、有りて、其の色、炎黑〔にして〕、文㸃〔(もんてん)〕有る者を「斑魚」と名づく。毒、最も甚だし【凡て、之れを煮るに、煤〔(すす)〕・灰の中に落つることを忌む。】。此の魚、樹に挿さば、立処〔(たちどころ)〕に[やぶちゃん字注:「処」は送り仮名にある。]便〔(すなは)〕ち、乾〔(かは)き〕枯〔(か)〕る【狗の膽を、其の樹に塗らば、復〔(また)〕、當〔(まさ)〕に榮盛〔:復活。〕すべし。】。小さしと雖も、獺(かはうそ)、及び、大魚、敢へて、之れを啖〔(くら)〕はず。則〔ち〕、惟〔(ただ)〕、人を毒するのみならずして、又、能く、物を、毒す。之れを食らひたる一日の内は、湯藥〔(たうやく)〕を服すべからず【荊芥〔(けいがい)〕は、大いに忌む。】。其の毒に中〔(あた)〕る者は、槐花〔(かいくわ)〕を以つて【微〔(わづ)〕かに炒〔(い)〕る。】、乾臙脂(〔ほし〕ゑんじ)と【等分に末と爲す。】水に調して、之れを灌〔(そそ):飲む。〕ぐ。大いに妙なり。』と。
△按ずるに、河豚魚は、河の名を得ると雖も、河の中には、之れ、無く、江海に在るのみ【「海豚(いるか)」・「江豚〔(かはいるか)〕」に對して、「河豚」と名づくか。】。狀、上の說のごとく、頭より、尾に至るまで、腹・背に、小さき鬛〔(ひれ)〕、有り。刺(はり)のごとし。其の尾に、岐〔(また)〕、無くして、細し。肉、白く、味【淡。】、脆く、美にして、飽かず。大骨の兩邊に、赤〔き〕血肉、有り。又、腸・胃の後(しりへ)、大骨に傍(そ)ふて、胡蝶の形のごとくなる者、有り、青白色、水に投じて、動くごとし。此の物、大毒、有り、人を殺す【猫・犬も亦、食へば、作〔(たちま)〕ち、斃〔(たふ)〕す。】。
鯖鯸(さばふぐ) 皮、薄く、柔かにして、滑(ぬめ)り、有り。背に、黃白の斑〔(まだら)あり〕、腹、白く、頭〔(かしら)〕、畧〔(ちと)〕、方〔(はう)〕なり。其の眼〔(まなこ)〕、大にして、腹・背に、刺鬛、無し。其の肚〔(はら)〕、甚だ〔は〕、脹(ふく)れず。微(やや)「鯖」に似たる故に、名づく。煮て食ひ、炙り食ひ、毒、無し。
名護屋鯸 背、黃赤にして、白㸃、有り。刺鬛、無く、腹、白く、味、美ならず。惟〔(ただ)〕、皮を剥(は)ぎて、之れを乾かす。「皮鯸〔ひふぐ)〕」と名づく。夏月、臛〔(あつもの)〕と爲し、之れを食ふ。凡て、鯸は、九月より、二月に至るまで、出でて、冬月、最も、之れを賞す。故に、夏は、「皮鯸」を以つて、之れに代〔(か)〕ふ。
鮮(あたら)しき鯸、能く、腸〔(はらわた)〕・血を洗浄し、之れを食ひて、毒に中〔(あた)〕らず。冬月、争い[やぶちゃん字注:漢字も送りがなもママ。]喫〔(くら)〕ふや、和漢ともに、然り。其の味、他に異なるを以つてなり。又、之れを食ひて、擧家〔→家を擧げて〕、皆、死する者、予、亦、之れを見る。暫時の口味〔(こうみ)〕に昵(なづ)んで、身命〔(しんみやう)〕を賭(かけもの)とする〔は〕、密-媱(まをとこす)る者と、趣〔(おもむき)〕は、一〔(いつ)〕なり。
[やぶちゃん注:フグ目フグ科 Tetraodontidae。本邦でフグ目(カワハギ科・ハリセンボン科・マンボウ科等を含む)は三亜目九科百一属で、現生種は三百五十七種を数えるとする(幾つかの違った数値があるが、ここではウィキの「フグ目」の数値を最新のものとしておく)。内、名にし負うフグ亜目(ハコフグ上科は含まない)は、現生種百五十四種、而して、その内のフグ科で日本近海に棲息する種は七属五十三種(ここは「WEB魚図鑑」の「フグ科」に拠った)、さらに、所謂、流通上での「フグ」で、一九八三年に旧厚生省によって食用として許可された種は全二十二種である(「東京都保健医療局」の中の「食用のふぐの種類とその可食部位(その1)」で、その二十二種の標準和名(学名は添えられていない)と可食部位のリストが見られる。但し、そこでは、カワハギ科・マンボウ科は含まれない。ハコフグは含まれている)。
・「蝌斗」は「蝌蚪(かと)」で、蛙の幼体の御玉杓子(オタマジャクシ)のこと。
・「腴(つちすり)」(土摩り)は、「下腹部の肥えて脂ののった柔らかな肉」を言う。他に「すなづり」とも呼ぶが、これは「砂摩り」で、同義、或いは、魚の腹の下の脂ののった腹鰭の周辺部分を指す。
・「西施乳」に就いては、多くの記事が、人口に膾炙する「臥薪嘗胆」の越王勾踐・呉王夫差の逸話を引き、傾城西施を、有毒のフグと結び付けている。確かに宝暦六(一七五六)年の新井白蛾の随筆「牛馬問」にも、『腹中の膵を西施乳といふ。これは西施が美にして國を亂るるを、この魚の味、美にして、毒あるに、比すなるべし。』と記す。――しかし、果してそうか? 本来は、無毒なフグの精巣を指して言ったはずの、この言葉が、ここで「膵」(内臓)となっているように、更には、フグそのものを指すように変化したと考えられるが、私は「西施乳」は、素直に、絶世の美女たる白く豊満たる西施の乳房(その液体としての乳では断固として「ない」と思う)を料理として食ったような旨さ(カニバリズム、何するものぞ! 人類の歴史にあってカニバリズムは、自然な行為であるとさえ私は思っている。但し、組成から言って旨いとは思えないが)、中国人の最も好きな豚肉ほどに旨い(ブタは獣類では牛など、何するものぞ! 飛び抜けてうまいと私は思っている。事実、豚肉の生ミンチは、飛んでもなく旨いらしい。但し、無菌豚やSPE豚(Specific Pathogen Free=特定疾患不在豚)でもない限り、死に至るような重篤な症状さえ引き起こすE型肝炎や、有鉤条虫 Taeniarhynchus saginatus 感染症や嚢虫症のリスクは覚悟されたい)という、まさに究極の表現であると確信するのである。ことさらに、その毒性と結び付けるには及ばない、と私は言いたいのだ。如何にも、雨に西施がねぶの花、で、あんまり可愛そうじゃあねえか!(乳房を食われるのも残酷だがね)
・「毒品の狀を備ふ」とは、「毒を持った魚としての特徴を総て完備している」という意味である。
さても、「毒」である。テトロドトキシン tetrodotoxin(C11H17O8N3)、その強力な毒性によって、ウェブ上でも、専門家を含め、記載ページは多い。故に薀蓄を垂れるのも気が引けるのだが、最低限の注記はやはり、極めて危険な毒物である以上、私なりに注記が必要であると考える。致死量は二~三ミリグラム、一般に青酸カリの千倍以上、或いは、五百倍、又は、経口摂取で八百五十倍などと記載されてある(ヒトの青酸カリの致死量自体が、その青酸カリの精製度の差や、個人差によってブレるので、この致死倍率の数値の相違を云々するのは、余り、意味のあることではないと私は思う。従って毒物では定番のまことしやかなマウス・ユニットの説明も省く)。毒性を持つ部位や、その含有量が、種・生息場所・時期・各個体によって著しく異なることや、その作用が神経伝達に関わるイオン・チャンネル(ナトリウム・チャンネル)の遮断による神経麻痺・筋肉麻痺であることや、その毒性起源が、食物連鎖による海洋細菌( Staphyloccus ・ Bacillus ・ Micrococcus ・ Alteromonas ・Acinetobacter ・ Vibrio 属の細菌が、既に単離されている)由来であることなども、三十六年程前から判明してきた。更に最近では、「毒を以つて毒を制す」で、その生理作用を利用した、アルツハイマー病・パーキンソン症候群等の難治性疾患の治療薬や、鎮痛薬としての新薬開発が、そこから始まろうとしてもいる。昔、大好きだった化学の先生のために、構造式の見られるページも入れちゃおう!
・「其の肝、及び、子に、大毒、有り」は周知の通り。肉に毒性を持つものもあり、くれぐれも素人料理は禁物である。かつて私の父は、昔、よくあの悩ましいキス釣りの外道のクサフグ Takifugu niphobles を一時、後生大事に持って帰っては、母に味噌汁仕立てにさせて、「旨いぞ。何故、食わん!」としきりに言ったものだ。一切れ食って、確かに旨いとは思った(クサフグは、実際、旨い)が、中学一年生ながら、翌日、図書館で調べてみれば、卵巣・肝臓・腸が猛毒、次いで皮膚・筋肉・精巣は弱毒とあるのを確認した。それからは決まって、「食え」と言う父と、喧嘩となったものだ。そのうち、父は、海釣りから、鮎のドブ釣に鮮やかに転向したので、目出度く「擧家皆死」せずに済んだ。クサフグは、一部の評者によれば、最強の毒フグとされるのであるから、これ、笑い話ではない。因みに、本項最後の「腸・胃の後、大骨に傍ふて、胡蝶の形のごとくなる者、有り、青白色、水に投じて、動く」ように見えるものが、まさに、猛毒の肝臓を指しているものと思われる。……しかし私は実は、大分の臼杵で、フグの肚を、佐渡でフグの卵巣の粕漬けを、どちらも食している。まず、臼杵、これは所謂、公然の秘密という部類の話で、臼杵(調べてみると大分ではというべきらしい。これは伝統的な当地の食い方で、勿論立派な違法行為である。ある種の書き込み等には、まことしやかに、「キモを食べていいという条例が現地にある」等と書かれているが、それは真っ赤な嘘である)では、どのフグ料理店も、数日、水に晒して、血抜きした「てんこ盛り」のキモを(私の食べた店では、即物的に正しく激しく「てんこ盛り」で、なんと食い切れずに残した)醤油に混ぜて、厚切りのフグを頂くのであり、石川県の方法(こちらのものは条例によって認められた合法的な製品だが、異様に塩辛くて多くは食えないと聞く。こちらは残念ながら未だ未食である)と同ルーツと思われる佐渡(★訂正(二〇〇七年十月二十日附)のものは、これ、新潟県が、ただ一人、製造を公式に認可している須田訓雄氏による合法的な製品である)のものは、「はららご」としては、あっさりとしており、伝えられる石川のもののような塩辛さも全くなく、美味しかった。(★追記(二〇〇七年十月二十日附)先週、友人に頼んで石川県の正規合法商品たる「ふぐの子ぬか漬」を入手、食した。確かに塩辛い。塩辛いが、基(もとい)! この塩辛さの彼方に、含んだ口中、一時の後、一粒一粒に凝縮している旨味が、じんわり広がってゆく。これは、恐らく数少ない珍味中の珍味と言ってよい。佐渡の粕漬に比すと、ずっと塩分濃度が高くなるが、これは全く違った味わいである。比較するものではない。ただ、粒立ちの舌触りの美事さは、石川のものに軍配が上がる(私が、今回、食したのはこちらの製品)。
フグ中毒死で忘れられないのは、食通の歌舞伎役者八代目坂東三津五郎(昭和五〇(一九七五)一月十六日没)だ。高校二年生だったが、新聞に載った、その最期の言葉の皮肉とともに、よく覚えている。京都の行きつけの料亭で、フグのキモを板前に無理強いして作らせ、招待した友人三人が連れであったが、怖がって食わず、「なんでこんなに旨いもんを。」と四人前を全部一人で食った(これが一人前しか食っていなかったら、死なずに済んだとも聞く)。その後、奥方に電話して、「今、旨いものを食ったんだ、何だと思う? 天にも登るような気持ちだよ。」と言ったそうだ(記憶であり、細部は少し違うかもしれない)。そうして、文字通り、天に登っちゃったわけであるから、忘れようが、これ、ない。
・「炎黒」がよく分からない。「炎」は「紅蓮」で、濃い紅色がかった黒い色という意味か。
・「斑魚」は、「文㸃」から推すならば、時珍が最強毒種とするのは、フグの食用最高級品種たる胸鰭付近の黒い紋が特徴のトラフグ Takifugu rubripes と見てよいか(この学名属名、和名由来で、可愛いね!)。
・「之れを煮るに、煤〔(すす)〕・灰の中に落つることを忌む」意味不明。可食部でも、煤や灰の中に落ちた場合、そこに残っていた毒素が強力に変化するとでも思ったものか? 識者の御教授を乞うものである。
・「能く、物を、毒す」とは、「あらゆる生物(動植物全て)に対して、毒性を有する。」の意。
・「荊芥」は、シソ科キク上目シソ目シソ科イヌハッカ属ケイガイ Schizonepeta tenuifolia の花穂、及び、その茎枝で、漢方薬名でもある。風邪や出血性疾患や皮膚病に効果があるとする。
・「槐花」は、マメ目マメ科マメ亜科エンジュ属マメ科エンジュ Styphnolobium japonicum の花・蕾から生成された漢方薬。出血性疾患に用い、降圧及び毛細血管透過性低下作用を持つ。
・「乾臙脂」は、別名、「花没薬」(はなもつやく)とか、「紫鉱」(しこう)と呼ばれる、半翅目ラックカイガラムシ科ケリア属ラックカイガラムシ Laccifer lacca の分泌物から生成された漢方薬。抗菌・止血作用を持つ。――しかし、残念ながら、これらにテトロドトキシンの解毒効果はない。テトロドトキシンの解毒剤は、現在も、ない。
・「河豚魚は、河の名を得ると雖も、河の中には、之れ、無く、江海に在るのみ」と良安は綴るが、これは誤り。「河豚」は、現行では「目河豚」として、揚子江や黄河の淡水域にも遡上する海産のメフグ Takifugu obscurus (河口等と淡水域に適応しているフグは、他にも、タイ・スリランカ・インドネシアなどに分布するミドリフグ Tetraodon nigroviridis や、東南アジア産のハチノジフグ Tetraodon biocellatus 等、結構、いる)に与えられているからである。「豚」の方は、興奮時の膨らんだ状態や、捕捉された際に挙げる鳴き声が豚のそれに似ているから!――そうして、ここが肝心!――それは――豚肉ほどに窮極に旨いから!――なのだ! と私は勝手に思っている。鳴き声については、嘗つて、中学生の頃、富山の雨晴海岸の岩礁の浅瀬で蟹突きをしていて、クサフグに、脇腹の肉をしたたかに噛まれたという稀有の体験を持つほどの私の経験では、フグは「ギュウー!」か「キュウー!」か「グゥウ!」と鳴く。私が噛まれたのは、恐らく子供を襲われると思った親が、捨て身で守るために、防御攻撃をかけたのであろうと思われる(実際にその時、私は視野に幼魚がいるのを現認している)。しかし、あの上下の強烈な板歯で、直径七、八ミリメートルの、円形に、したたかに、深々と噛み抉られた私を想像してみるがいい。何が私を憂鬱させたかが、お前には分かるだろう……と梶井を気取りたくなる程、痛い恥ずかしい思い出ではあった。釣って指を噛まれた話や、生きたトラフグを調理中、噛まれて、指を骨折した等という話は聞くが、海水浴中に噛まれた話を、残念ながら、僕は僕以外、知らないのである。
・「鯖鯸」は、最近まで、サバフグ一種とされていたものが、一九八三年、
シロサバフグ Lagocephalus wheeleri
クロサバフグ Lagocephalus gloveri
ドクサバフグ Lagocephalus lunaris
の三種に分けられた。本項は、無毒のシロサバフグである、でなくてはならない。クロサバフグもドクサバフグも有毒である。クロサバフグの日本近海個体は無毒とされるが、南シナ海産個体の内臓からは、毒が検出されているし、そもそも何故、長く一種とされてきたかを考えれば、この三者、よく似ているのである。要注意だ!
・「名護屋鯸」は、現在、コモンフグ Takifugu poecilonotus と、ナシフグ Takifugu vermicularis の二種を指しているとされる。これらは、現在は、良安の記載に反して、トラフグに次いで、美味で安価との評判である。両者とも、しっかり、有毒ではある。なお、瀬戸内海では、この二種の交雑種が報告されてもいる。但し、ネット上の別な情報では、これはショウサイフグ Fugu vermicularis を一般的に指すと断言するものもある(これも刺身が旨いとされるが、しっかり、やっぱり、有毒種ではある)。因みに、この命名は恐らく高い確率で「尾張名古屋」に引っ掛けた、まかり間違えると命の「終り」であろうかと私には思われる。
・「臛」の「あつもの」とは、スープ、若しくは、ゼラチン質の固形化した煮凝り(にこごり)を指すが、後者であろう。
・「暫時の口味に昵んで、身命を賭とする、密媱(まをとこす)る者と、趣は、一なり」「仮初(かりそめ)のフグの食味に、心、奪われて、命を賭けるなどということは、間男(夫のある女と他の男が肉体関係を持つこと)することと、その内実に於いて、全く同じである。」だが、その教訓に反論しておこう。そうか、じゃあ、清廉潔白で不倫もしない良安さんよ(そもそも、君は、既婚者か? 未婚者か? 実は彼のプライベートはよく判っていないのだ。というより、この突然の異様な教訓にこそ、寺島良安のトラウマや、秘密が隠れているのかも知れない。いや、それを言ったら、僕のこの注のある部分だって、同なじなんだな)、これだけフグの旨味と、この禁誡を力説した君は、決してフグを食なかったし、不倫もしなかったんだな!? え? ♪ふふふ♪]
***
わに
鰐【音諤】
クワアヽ
鱷【同字】
【和名和仁】
[やぶちゃん字注:以上二行は、前三行下に入る。]
和名抄云鰐形似蜥蜴而大水潜吞人卽浮
說文云鰐食人魚一生百卵及成形則有爲蛇爲龜爲蛟
者其亦靈
三才圖會云鰐南海有之四足似鼉長二丈餘喙三尺長
尾而利齒虎及龍渡水鰐以尾擊之皆中斷如象之用鼻
徃徃取人其多處大爲民害亦能食人既飽則浮在水上
若昏醉之狀土人伺其醉殺之
春雨 よの中は鰐一口もをそろしや夢にさめよと思ふ斗そ
△按鰐狀灰白色頭圓扁足如蜥蜴而前三指後一指偃
額大眼尖喙稍長口甚𤄃牙齒利如刄上下齒有各二
《改ページ》
■和漢三才圖會 江海無鱗魚 卷ノ五十一 ○九
層牙上下相貫交嚙物無不斷切者故諺曰稱鰐之一
口也無鱗背上有黒刺鬛而有沙尾長似鱝尾其尾足
掌之甲皆黒色小者一二尺大者二三丈
社頭拜殿懸鐵鉦以布繩敲之形圓扁如二鉦合成有大
口頗象鰐頭俗謂之鰐口其來由未詳古有神駕鰐之
事據于此乎
建同魚 大明一統志云眞臘國有建同魚四足無鱗鼻
如象吸水上噴髙五六丈是亦鰐之別種乎
*
わに
鰐【音、諤。】
クワアヽ
鱷〔(がく)〕【同字。】
【和名、「和仁」。】
「和名抄」に云はく、『鰐は、形、蜥蜴(とかげ)に似て、大にして、水に潜(くゞ)りて、人を吞む時は、卽ち、浮く[やぶちゃん注:「時」は送り仮名にある。]。』と。「說文」に云はく、『鰐、人を食ふ魚なり。一たび、百の卵を生む。形を成すに及びては、則ち、蛇と爲り、龜と爲り、蛟(みづち)と爲る者、有り。其れ亦、靈〔(れい)〕なり。』と。
「三才圖會」に云はく、『鰐は、南海に、之れ、有り。四足、鼉〔(だ)〕に似、長さ、二丈餘。喙〔(くちばし)〕、三尺。長き尾にして、利〔(するど)〕き齒、あり。虎、及び、龍、水を渡れば、鰐、尾を以つて、之れを擊つに、皆、中(―[やぶちゃん注:右に、かくダッシュ状の記号があるが、意味不明。])に斷(を)れる。象の、鼻を用ひるがごとし。徃徃にして、人を取る。其の多き處は、大〔きに〕民の害を爲し、亦、能く人を食ふ。既に飽く時は、則ち、浮かんで、水上に在り[やぶちゃん注:「時」は送り仮名にある。]。昏醉〔(こんすゐ)〕せる狀(さま)のごとし。土人、其の醉へるを伺ひて、之れを殺す。』と。
「春雨」 世の中は鰐一口もをそろしや夢にさめよと思ふ斗(ばかり)ぞ
△按ずるに、鰐の狀〔(かたち)〕、灰白色にして、頭〔(かしら)〕、圓〔(まろ)〕く、扁たく、足、蜥蜴〔(とかげ)〕のごとくにして、前に、三指、後に、一指〔あり〕。偃〔(ふし)〕たる額〔(ひたひ)〕、大なる眼〔(まなこ)〕、尖りたる喙〔(くちばし)〕の、やや長く、口、甚だ、𤄃く、牙齒、利(と)きこと、刄(やいば)のごとし。上下の齒、各々、二層、有り。牙の上下、相〔(あひ)〕貫〔き〕、交〔はりて〕、物を嚙む。斷ち切らずと云ふ者〔(もの)〕、無し[やぶちゃん字注:「云」は送りがなにある。]。故に諺に曰はく、「鰐の一口」と稱す。鱗、無く、背上に、黒き刺鬛〔(とげひれ)〕、有りて、沙〔:粒状の突起。〕有り。尾、長くして、鱝(ゑい)の尾に似る。其の尾・足、掌の甲、皆、黒色。小さき者は、一、二尺、大なる者、二、三丈。
社頭、拜殿に、鐵鉦〔(てつがね)〕を懸けて、布繩〔(ぬのなは)〕を以つて、之れを、敲〔(たた)〕く。形、圓く、扁たく、二鉦〔(ふたかね)〕を合成〔(いひな)〕すがごとし。大なる口、有り。頗〔(すこぶ)〕る、鰐の頭に象〔(かたど)〕る。俗に、之れを「鰐口〔(わにぐち)〕」と謂ふ。其の來由〔=由来〕、未だ、詳らかならず。古へ、神、鰐に駕〔(が)する〕の事、有り、此れに據〔(よ)〕るか。
建同魚 「大明一統志」に云はく、『眞臘國〔(しんらふこく)〕に、建同魚、有り。四足にして、鱗、無し。鼻、象のごとく、水を吸ひ上げて、噴(ふ)くこと、髙さ、五、六丈。』と。是れ亦、鰐の別種か。
[やぶちゃん注:爬虫綱ワニ目Crocodiliaに属する動物の総称。現生種は正鰐亜目 Eusuchia のみで、アリゲーター科 Alligatoridae、クロコダイル科 Crocodylidae、ガビアル科 Gavialidaeの三科分類が一般的で、現生種は二十三種。ガビアル科 Gavialidae はインドガビアル Gavialis gangeticus の現生種は一属一種である(但し、科として独立させずにクロコダイル科とする考え方もある)。頭部を上から見た際、喙(口先)が丸みがかっているものがアリゲーター科で、細く尖っているものがクロコダイル科である。更に、閉じた口を横から見た際、下顎の第四歯が上顎の穴に収まっているものがアリゲーター科で、牙の如く外に突出しているものがクロコダイル科。ガアビル科インドガビアルは、喙が細長い吻となっているので、誤りようがない(インドガアビルの成体の♂は鼻が大きく膨らんでおり、♀と容易に区別出来るが、他のワニでは、外見上の雌雄の判別は出来ない)。
・「一たび百の卵を生む」は誇張。科によって異なるが、通常、十~五十個である。
・「靈」は、「人知を超えた不思議な働き・玄妙な原理」の意。
・「鼉」はアリゲーター属ヨウスコウアリゲーター Alligator sinensis (お洒落じゃないね、この和名。ヨウスコウワニか、チョウコウワニの方がいい)。なお、東洋文庫版では、これに『すっぽん』のルビを振るが、甚だしい誤りである。「鼈」と見前違えたに過ぎない初歩的ミスである。
・「說文」は「說文解字」で、漢字の構成理論である六書(りくしょ)に従い、その原義を論ずることを体系的に試みた最初の字書。後漢の許慎の著。但し、東洋文庫版後注によると、この部分、良安が記すような記述は「倭名類聚鈔」にはなく、これは「説文」の「𧊜」(わに)の説明であるとする。まず「倭名類聚鈔」の「卷第十九」「鱗介部第三十」の「龍魚類第二百三十六」の「鰐」の条は以下の通りである(今回は原文と訓読文を並置する。国立国会図書館デジタルコレクションの漢文七(一六六七)年刊本の当該項を視認した)。
*
鰐(ワニ) 麻果切韻云鰐【音萼和名和仁】似鱉有四足喙長三尺甚利齒虎及大鹿渡水鰐擊之皆中断。[やぶちゃん注:「鱉」(ベツ)は「スッポン」・「簑亀」(背中に藻を生やした亀)を指す「鼈」と同字。]
鰐(わに) 「麻果切韻」に云はく、『鰐【音、萼。和名、「和仁」。】。鱉に似て、四足、有り、喙、長く、三尺。甚だ利(するど)き齒あり。虎、及び、大鹿、水を渡る時、鰐、之れを擊ちて、皆、中に断(だん)ず。』と。
*
一見してお分かりのように、これは良安が直後に引く「説文」の内容とほぼ一致する(良安の記述の「龍」は「大鹿」の字の読み違いか、写本の誤りであろう)。更に、「説文」の解説は以下の通り(「廣漢和辭典」の「鱉」の字義の例文にある。恣意的に正字化し、私の訓読を添えた)。
*
鱉佀蜥易。長一丈、水潛、吞人卽浮。出日南也。从虫屰聲。
鱉〔(わに)〕は、蜥易〔=蜥蜴〕に佀〔=似〕る。長さ一丈、水に潛(もぐ)り、人を吞めば、卽ち、浮ぶ。日南に出づるなり。「虫」に从〔=從〕ひ、「屰」の聲。
*
最後の部分は解字である。「廣漢和辭典」によれば、「𧊜」は、「鰐」と同一語異体字とある。従って、「説文」には「鰐」の別項はないと思われる。では気になるのが、彼が「説文」からとした、この引用文の出所である。東洋文庫もそれを記していない。識者の教えを乞う。この文字列で検索すると、最初の三件は私の電子記事という為体(たいたらく)だ!
・「春雨」は、三島由紀夫も称揚した上田秋成の幻想小説集「春雨物語」を指すと思うのが普通である(東洋文庫版もそうとっている)が、次項のような次第で、実はこれは別な書物を指している可能性がある。
・「世の中は……」(「をそろし」はママ)の和歌は調査中であるが、これは「春雨物語」の中には所収していない可能性が高い(「岩波古典文学大系 索引」で、この和歌は掲載されていない)。
・「前に三指、後に一指」は正しい表現ではない。そもそもワニの指は前肢が五本で、後肢は四本である。これはそのキッチュさが大好きな「熱川バナナワニ園」で得た貴重な知識である。
・「偃たる額」の「偃」の字を私は「ふス」と読んだ。これは扁平で地べたに伏せた(うつぶせになった)頭部を示すものとして違和感がない。東洋文庫版では、ここを『出ばった額』と訳しているが、そもそも「偃」にそのような意味はない。但し、「堰」の別義で、土を盛り、流れをせき止めるの意味の敷衍ならばとれないことはないが、やや強引である。
・「鰐の一口」は「鬼の一口」と同じとする見解が多い。だとすれば、「処理の仕方が驚くべき素早さで、しかも確実である。」という意味と、文字通り、「ひどく恐ろしい目に遭うこと」の意味となる。
・「鱝」は「海鷂魚」として後掲される軟骨魚綱板鰓亜綱 Elasmobranchii のエイ類である。
・「鰐口」については川崎市教育委員会HPの指定文化財紹介ページ「青銅製鰐口(市民ミュージアム)の概説が言うべきことを洩らさない非常に優れたものなので、以下に引用する。
《引用開始》
鰐口は梵音具(打ち鳴らして音を出すための仏具)の1つで、多くは鋳銅(銅の鋳物)製であるが、まれに鋳鉄製や金銅(銅に鍍金を施したもの)製のものもみられる。通常は神社や仏閣の軒先に懸けられ、礼拝する際にその前に垂らされた「鉦の緒」と呼ばれる布縄で打ち鳴らすもので、今日でも一般によく知られている。その形態は偏平円形で、左右に「目」と呼ばれる円筒形が張り出す。また、下方に「口」が開き、上緑部2箇所には懸垂のための「耳」を付した独特なものである。
「鰐口」という呼称は、正応6年(1293)銘をもつ宮城大高山神社蔵の作例の銘文中に記されるのが初見である。それ以前の鰐口の銘文には「金口」とか「金鼓」といった呼称がみられることから、古くはこのように呼ばれていたのが、鎌倉時代末頃以降、「鰐口」と称されるようになったものと考えられている。江戸時代中期の医家、寺島良安はその著『和漢三才図会』(正徳3年〈1713〉自序)のなかで「口を裂くの形、たまたま鰐の首に似たるが故にこれを名づくるか」と推察しているが、実際に堂宇に懸けられた鰐口を仰ぎみる時、このように考えることは十分にうなずける。
鰐口の現存遺例は室町時代以降の作例が多く、それ以前のものは少ない。平安時代の作例には、長野松本市出土の長保3年(1001)銘鰐口(東京国立博物館保管)の他、愛媛奈良原経塚出土の平安時代後期に推定される例があるにすぎない。
鰐口の祖形には、韓国の「禁口」と呼ばれる鳴物が考えられているが、鉦鼓を2つ重ねたとする見方や鐃との関連も考えられている。[やぶちゃん注:以下略。]
《引用開始》
ここで、この執筆者が引いている「和漢三才圖會」の叙述は、本項の鰐口の部分ではなく、「卷第十九」の「神祭附リ佛供ノ噐」の「鰐口」の項の叙述である。序でなので、該当部を以下にテクスト化しておく(体裁は本頁の書式に従った)。【2023年9月追記】実はここで電子化していたことを忘れて、ブログ・カテゴリ「和漢三才図会抄」で、全く別個に『「和漢三才圖會」卷第十九「神祭」の内の「鰐口」』として電子化注してしまった。ボケの始まりか。そっちの画像の方が大きい。
*
■和漢三才圖會 神祭 備噐 卷ノ十九 ○ 三
[やぶちゃん注:冒頭の「高麗狗」後半六行及び「神楽鈴子」の項は省略。]
わにくち 俗云和尓久和〔→知〕
鰐口
△按鰐口以鐵鑄之形圓扁而半裂如鰐吻懸之社頭従
上垂下布繩【長六七尺】俗名鉦緒而𭆤〔=參〕詣人必先取繩敲其
鐵靣〔=面〕未知其據恐是好事者本於鉦鼓而欲令異其音
裂口形偶似鰐首故名之乎
*
わにぐち 【俗に「和尓久知」と云ふ。】
鰐口
△按ずるに、鰐口は、鐵を以て、之れを鑄〔(い)〕る。形、圓くして扁たく、半ばは、裂けて、鰐の吻のごとし。之れを、社頭に懸けて、上より布繩を垂-下〔(たら)〕し【長さ六、七尺。】、俗に、「鉦緒(かねのを)」と名づく。參詣人、必ず、先づ、繩を取りて、其の鐵靣を敲く。未だ、其の據〔(よりどころ)〕を知らず。恐らくは、是れ、好事(こうず)者の、鉦鼓に本づきて、其の音を異ならしめんと欲し、口を裂く〔→裂くに、〕形、偶々(たまたま)鰐の首に似たる故に、之れを名づくか。
*
・「古へ、神、鰐に駕するの事、有り」とは、人口に膾炙する海幸彦山幸彦兄弟の神話中の出来事を指しているか。兄海佐知毘古(うみさちびこ)の名は海の漁師の意味で、彼の正しい神名は火照命(ほでりのみこと)で、山佐知毘古の方は火遠理(ほをりの)命という。兄弟は、ある日、猟具を交換し、山幸彦は魚釣りに出掛けたが、兄に借りた釣針を失くしてしまう。失くした釣針を求めて、綿津見神(わたつみのかみ=海神)の宮殿に赴き、そこで豊玉比売(とよたまひめ)と契った火照命は、三年経って、自分がここに来た理由と兄火照命の仕打ちを語る。豊玉比売の父海神は鯛の喉から件の釣り針を発見、それを兄に返す際の呪文と潮の潮汐を自在に操る秘密兵器「塩盈珠(しほみつたま)」・「塩乾珠(しほふるたま)」を手渡す。そうして火照命の葦原中国(あしはらのなかつくに)への帰還のシーンとなるのであるが、そこに「和邇魚(わに)」が登場する。「古事記」の該当箇所を引用する。
*
鹽盈珠、鹽乾珠、幷せて兩個(ふたつ)を授けて、卽ち、悉くに和-邇-魚(わに)どもを召〔(まね)〕び集めて、問ひて曰ひけらく、[やぶちゃん注:以下は綿津見神の台詞。]
「今、天津日高(あまつひこ)の御子、虛-空-津-日-高(そらつひこ)、上(うは)つ國に出-幸(い)でまさむと爲(し)たまふ。誰(たれ)は幾日(いくひか)に送り奉りて、覆-奏(かへりごとまを)すぞ。」
といひき。故、各己(おのおの)が身の尋長(ひろたけ)の隨(まにま)に、日を限りて白(まを=曰)す中に、一-尋-和-邇(ひとひろわに)白(まを)しけらく、
「僕(あ)は、一日(ひとひ)に送りて、卽ち、還り來む。」
とまをしき。故に、爾〔(ここ)〕に其の一尋和邇に、
「然(しか)らば、汝(なれ)、送り奉れ。若(も)し、海中(わたなか)を渡る時、な惶-畏(かしこ)ませまつりそ。」
と告(の)りて、卽ち、其の和邇の頸に載せて、送り出しき。
故(かれ)、期(ちぎ)りしが如(ごと)、一日の内に送り奉りき。
其の和邇、返らむとせし時、佩(は)かせる紐-小-刀(ひもかたな)を解きて、其の頸に著けて、返したまひき。故、其の一尋和邇は、今に佐-比-持-神(さひもちのかみ)と謂ふ。[やぶちゃん注:以下略。]
*
しかし、現在、この「和邇」は、無論、ワニではなく、サメとするのが定説である。しかし、良安がここで想起したのが、この神話であったとすれば、所謂、爬虫類のワニが、当時は本神話の登場生物として広く信じられていたということを示すとも、とれようか。
・「大明一統志」は、明の英宗の勅で李賢らによって撰せられた中国全土と周辺地域の総合的地理書。九十巻。天順五(一四六一)年に完成。
・「真臘國」は「旧唐書」に、
*
眞臘國、在林邑西北、本扶南之屬國、崑崙之類。
眞臘國は、林邑の西北に在り、扶南の屬國にして、崑崙の類なり。
*
とある。渡邉明彦という方のアンコール遺跡群の記事のカンボジアの歴史についての記載によれば、『紀元前後、メコン川下流のデルタ地帯から沿岸地帯を領有する扶南国があり、メコン川中流にはクメール族の真臘国があった。真臘は3、4世紀頃から南下をはじめ、扶南を吸収合併していった。7世紀にはほぼ現在のカンボジアと同じ領土を有していた。』とあり、現在のカンボジア王国と同定してよい。
・「建同魚」が分からない。ワニでは毛頭あるまい。「隋書」の「卷八十二 列傳第四十七」にも「南蠻海中有魚名建同、四足、無鱗、其鼻如象、吸水上噴、高五六十尺。」と、ここと同様の記述がある。当初ジュゴン Dugong dugon を想定してみたが、叙述としっくりこない。何方かの鮮やかな同定を期待する。]
***
さめ
鮫【音交】
キヤ◦ウ
沙魚 鰒【音剥】
溜魚 䱜【音錯】
【和名佐米】
[やぶちゃん字注:以上三行は、前三行下に入る。]
本綱鮫東南海皆有之有數種形稍異而皮一等青目赤
頰背上有鬛腹下有翅大者尾長數尺能傷人皮皆有沙
如真珠可飾刀靶又堪揩木如木賊也其子隨母行驚卽
從口入腹中其肉【甘平】作膾及鮓味美補五藏功亞于鯽
鹿沙【一名白沙】 其背有珠文如鹿而堅彊者能變鹿也
虎沙【一名胡沙】 背有斑文如虎而堅彊
鋸沙【一名挺鮥〔→頷〕魚又鱕䱜】 鼻前有骨如斧斤能擊物壞舟
春雨 よの中は鰐一口も恐しや梦に鮫よとおもふ斗そ
△按鮫形狀畧如上說但灰黒色無鱗魚也鈎得後以急
擲岸頭則魚困痛忿恚而皮上黒沙起脹堅硬如真珠
刀鉾不能裁之工人以竹帚頻洗之成白珠脊有一大
粒其大如薏苡仁其周※〔=匝〕七八粒亦大而圍魁粒共似[やぶちゃん字注:※=「匝」の中が「帀」。「グリフウィキ」のこれ。「匝」(ソウ/めぐる)の異体字。]
九曜星次次二三座亦然似玉蜀黍子者飾欛甚良其
粒粒大小兼備者價最貴重也若魁粒䧟〔=陷〕或歪者鑿去
之更以鹿角作成魁粒繫入亦難曉矣而欛鮫皆用異
國之產本朝之鮫全體粒粒平等止可爲鞘鮫
聖多默太泥占城之產爲最上咬𠺕吧暹羅阿媽港次之
《改ページ》
■和漢三才圖會 江海無鱗魚 卷ノ五十一 又九
[やぶちゃん注:「又九」という異例な表示は、補綴による追加若しくは齟齬を後になって書き換えた結果であろう。]
南京鮫幅廣鮫等下品也此外交趾東〔→柬〕埔寨有數品而
鞘鮫亦多來焉
縐鮫 巖石鮫 發斑鮫 虎鮫 麑鮫 海子鮫 白
倍志鮫 加伊羅介鮫等不悉記之
本朝之鮫亦有數種 駿州大愛鮫 同國蒲原小愛鮫
常州愛古呂 紀州脊古呂 松前菊登知等不遑記
之凡鮫和漢同物異品因土地之差乎不獨鮫而草木
鳥獸皆有異同
*
さめ
鮫【音、交。】
キヤ◦ウ
沙魚 鰒【音、剥。】
溜魚 䱜【音、錯。】
【和名、「佐米」。】
「本綱」に、『鮫は、東南海、皆、之れ、有り。數種、有りて、形、稍〔(やや)〕、異にして、而〔(しか)れども〕皮は、一等なり。青き目、赤き頰、背の上に、鬛〔(ひれ)〕、有り、腹の下に、翅〔(はね)〕、有り。大なる者、尾の長さ、數尺。能く人を傷〔(きず)つく〕る。皮に、皆、沙、有り。真珠のごとく、刀の靶(つか)〔=欛〕を飾るべし。又、木を揩(こす)るに、堪へたり。木賊〔(とくさ)〕のごとし。其の子、母に隨ひて、行く。驚く時は、卽ち、口より、腹中に入る[やぶちゃん字注:「時」は送りがなにある。]。其の肉【甘、平。】、膾〔(なます)〕、及び、鮓〔(すし)〕に作る。味、美にして、五藏〔=臟〕を補ふ。功、「鯽〔(ふな)〕」に亞〔(つ)〕ぐ。
鹿沙〔(ろくさ)〕【一名、「白沙」。】 其の背に、珠文、有り、鹿のごとくにして、堅彊〔(けんきやう=堅強〕なる者、能く鹿に變ずるなり。
虎沙【一名、「胡沙」。】 背に、斑文、有り、虎のごとくして、堅彊。
鋸沙〔(きよさ)〕【一名、「挺頷魚〔(ていがんぎよ)〕」。又、鱕䱜〔(ばんしやく)〕。】 鼻の前に、骨、有りて、斧-斤〔(をの/まさかり)〕ごとくして、能く物を擊ち、舟を壞(くづ)す。』と。
「春雨」 よの中は鰐一口〔(わにひとくち)〕も恐しや梦〔(ゆめ)〕に鮫〔(さめ)〕よとおもふ斗〔(ばかり)〕ぞ
△按ずるに、鮫の形狀、畧〔ほぼ)〕、上の說のごとし。但し、灰黑色の鱗無き魚なり。鈎〔(つ)り〕得て後、以つて、急に、岸頭に擲(なげう)ちては〔→ちれば〕、則ち、魚、困-痛(くる)しみ、忿-恚(いか)りて、皮の上〔の〕黒沙、起-脹〔(きちゃう):起きて膨れ上がって。〕して、堅-硬なること、真珠のごとく、刀・鉾、之れを裁(た)つこと、能はず。工人、竹-帚(さゝら)を以つて、頻〔(しき)〕りに、之れを洗ひ、白珠と成す。脊に、一大粒、有り、其の大いさ、薏苡仁〔(よくいにん)〕のごとく、其の周-匝(めぐ)りに七、八粒、亦、大にして、魁-粒(をやつぶ[やぶちゃん注:ママ。])を圍(かこ)む。共に九曜〔(くえう)〕の星に似て、次次は二、三座〔をなして〕、亦、然り。玉-蜀-黍-子(なんばんきびのみ)に似たる者、欛(つか)を飾るに、甚だ、良し。其の粒粒、大小兼備する者、價〔(あたひ)〕、最も貴-重(たか)し。若し、魁粒、䧟(をちい)り、或いは、歪(なゝ)めなるは、之れを鑿〔(けづ)〕り去り、更に、鹿角を以つて、魁粒を作り成し、繫ぎ入る。亦、曉〔(あか)〕し難し。欛鮫〔(つかざめ)〕、皆、異國の產を用ふ。本朝の鮫は、全體の粒粒、平等にして、止(た)ゞ、鞘鮫(さや〔ざめ〕)と爲すべし。
聖多默(サントメ)・太泥(〔パ〕タニ)・占城(チヤンパン)の產、最上と爲す。咬𠺕吧(ジヤガタラ)・暹羅(シヤム)・阿媽港(アマカハ)、之れに次ぐ。「南京鮫」・「幅廣(はゞびろ)鮫」等(―[やぶちゃん注:このルビ位置のダッシュ状の記号、意味不明。「トウ」か。])は下品なり。此の外、交趾(カフチ)・柬埔寨(カボヂヤ)、數品〔(すひん)〕有り、鞘鮫も亦、多く來〔(きた)〕る。
「縐鮫(ちりめんざめ)」・「巖石(がんせき)鮫」・「發斑(はつぱ)鮫」・「虎鮫」・「麑(かのこ)鮫」・「海子(うみこ)鮫」・「白倍志(しろへし)鮫」・「加伊羅介(かいらけ)鮫」等あり。悉く〔は〕、之れを記さず。
本朝の鮫、亦、數種、有り。 駿州の「大愛(あい)鮫」・同國蒲原(かんばら)の「小愛鮫」・常州の「愛古呂(あいころ)」・紀州の「脊古呂(せごろ)」・松前の「菊登知(〔きく〕とぢ)」等、之れを記すに遑(いとま)あらず。凡そ、鮫、和漢同物にして、異品は、土地の差(ちが)ひに因るか。獨り、鮫のみならず、草木鳥獸、皆、異同、有り。
[やぶちゃん注:サメとは、軟骨魚綱板鰓亜綱 Elasmobranchii に属する魚類の中で、原則として鰓裂が体の側面に開くものを呼称する(前項の「鱣」の注で細述済であるが、カスザメ目やサカタザメのような例外がある)。現生種数は二〇二〇年現在で、世界中に九目三十六科百六属五百五十三種、日本近海には九目三十四科六十四属百三十種を数える。「フカ」と「サメ」の同義性と民俗学的差別化は、やはり「鱣」の注を参照されたい。
・「皮は一等なり」とは、多くの種類があるが、以下に記すような特性を持った皮膚は、その全てのサメに同「一」に「等」しくあるという意味である。
・「沙」は、本項のキー・ワードであるし、実はサメ自体の特性の重要なファクターでもあるのだ。まず、この「沙」は、サメの皮膚が砂のように粒子状で、ざらざらしていること(厳密には、生体の場合、尾から頭の方に向かって触れた時にそう感じる)を表現している語である。この、ざらついた皮膚は「楯鱗(じゅんりん)」と呼ばれる顕微鏡的な鱗から構成されており、それは表皮の上皮細胞と、骨・筋肉などを形成する「間葉細胞」が向かい合い、その間に「エナメル質」と「象牙質」が形成されるという、エナメル質・象牙質・骨様組織の三つ巴の精緻堅固な組織構造を持っている。そうして、これは、まさに、我々の「歯」と全く同じ構造なのである。従って、サメの鱗は別名を「皮歯(ひし)」と呼ぶ。勿論、サメのあの歯も、その皮膚が口中に陥入し、変形して進化したものであると考えられているのである。
・「木を揩(こす)る」という良安の読みには疑義がある。原文は「堪揩木」であるが、これは「揩木に堪へたり」と読むべきではなかろうか。そうして、「揩木」は「すりこぎ」と訓読すべきではないだろうか。所謂、鮫皮で作った「おろし金」である。
・「木賊のごとし」とは、古来、「砥草」とも表記するトクサ植物門トクサ科トクサ Equisetum hyemale の茎を煮て、乾燥させたものを、鑢(やすり)として、柘櫛(つげぐし)の研磨等に用いたことに由来する。
・「其の子、母に隨ひて、行く。驚く時は、卽ち、口より、腹中に入る」について、また、語らねばならなくなった。これに類似した記載は「鱣」の項にも、「胎生にして、口より、產む」等と現われている。そこで述べた通り、私は、口から子を産むマウス・ブリーダー習性のように見えるアジアアロワナ Scleropages formosus 等の条鰭綱アロワナ目アロワナ亜目アロワナ科 Osteoglossidae や、スズキ目キノボリウオ亜目のチョコレートグラミー Sphaerichthys osphromenoides のような)をサメが持っているというのは、聞いたことがない。これは何かの勘違いであろう。では何か。すぐに考えられるものは、「母親に随ってゆく」という表現から、スズキ目コバンザメ科 Echeneidae のコバンザメ類の誤認である。彼らは、硬骨魚類であるが、コバンイタダキの異名を頂戴するだけに、そのちゃっかり吸着する習性からも、吸着対象の魚の「子」と誤認されやすい。実際、サメに吸着しているのは、画像で何度も見た。タイノエ Rhexanella verrucosa のような口腔内寄生する甲殻類のような寄生性生物の吸着があるかどうかは知らないが(サメ類のようなあんなに大きな魚体で、鋭い歯が並ぶ中に、安穏と鎮座していられるだろうか? 私は、ちょっと考えにくい気がするのだが)、彼らは時に、サメの口腔内にも吸着する。但し、コバンザメもタイノエも、時に、宿主に食べられてしまうことが、大いに、あるらしい。但し、以上、私自身、コバンザメ説を決定打とは考えていない。一つの仮説として捉えて頂きたい。
・「膾、及び、鮓に作る」は、我々には奇異に思えるが、現に広島県山間部の備北地域や、山陰の一部では、今も「ワニ(サメ)料理」が根強い人気を持っている。代謝の結果、生ずるアンモニアが、腐敗を防ぐという逆説も、目から鱗(いや、見た目は「無鱗」だったね)だ。軟骨エキスやら、深海鮫エキスやら、キッチュな健康有効成分も、続々、報告、商品化されている。それは、もしかすると、古くて、新しい食材なのかも知れない。
・「鯽」はフナを指す(外には「イカ」も指すこともある)。フナはコイ亜科フナ属 Carassius の魚の総称。しかし、漢方に詳しくない私としては、フナに、こんな豪勢な効能があるなんて(おせち料理に入ってるのは、そのせいかなあ?)、加えてナンバー・ツーがサメだったとは、お釈迦様でもご存知あるめえよ!
・「鹿沙」は、……ここからはあんまり踏み込みたくないんだな、だって、そもそも海産無脊椎動物が好きな私は、逆に、魚類の同定が大の苦手なのである(何故か、無脊椎動物ほどに、身体的特徴に興味が湧かないのである)。しかし、力技で進まないと先には行けないし(この巻の私の期待は、最後に頭足類やナマコを始めとする偏愛する無脊椎動物がやってくるからなんだな、実は)。よし! ネズミザメ上目メジロザメ目ドチザメ科ホシザメ属ホシザメ Mustelus manazo はどうだ! 古くから日本で食用に供してきた種であり、背部に、地味ながら、鹿の子模様の「白」い斑点もあるぜ! 御批判は熱烈歓迎!
・「虎沙」は、ネズミザメ上目メジロザメ目トラザメ科トラザメ属トラザメ Scyliorhinus torazame でよかろう。
・「鋸沙」は、ノコギリザメ目ノコギリザメ科 Pristiophoridae に属する、鋸状の吻部をもつ魚の総称(二属五種)であるが、日本近海ならば、ノコギリザメ Pristiophorus japonicus 一種のみである。
・「春雨」と和歌は前項「鰐」と同一なので、そちらの注を参照されたい。但し、一部表記の違いが見られる。それにしても、良安先生、気に入ったぜ!「覺(醒)め」を「鮫」に懸けた洒落の和歌を引くのは!
・「白珠」以下、延々と続くサメの皮革細工の話、どうも違和感があった。サメの皮から、こんな真珠様の模様が鑑賞に耐え得る程に加工され得るものならば、現在もそれは残っていて、鮫皮の高級装飾品(この手間は安くはあるまい)として知られているはずであろうと思ったからであった。しかし、ネットで検索してみたところ、まずは、外国産のエイの皮で、こうした加工品が現在もあることが判った。そこで再検索をかけると、ズバリ! 画像付きで、文字通り、目から鱗、だがね! 輸入雑貨業者のHPの「最高級スティングレイ(エイ革製品、エイ皮製品)」のページだ。侮るなかれ! 金儲けをするなら、これくらいの薀蓄は垂れたいものだ。それが客への当り前のマナーである。中国で、このエイが『泳ぐ宝石』、『天眼』(神の目)と崇拝されてきたという民俗、その『スターマーク』は、一匹から、一つしか、採取できないこと、『ビーズを敷き詰めたような』形状、『カウレザー(牛革)30年、スティングレイ(エイ革製品、エイ皮製品)100年』と称される最高強度……もうこのページが、そのまんま、ここの部分注になっていると言える。このスティングレイを一般に、何故、「ガルーシャ」(Galuchat)と呼ぶのかが、フランスのルイ十五世から一介のエイ皮鞘職人ジャン・クロード・ガルーシャ(Jean-Claude Galuchat に辿り着くところなんざ、薀蓄の薀蓄たる醍醐味だ! さて、この中の『ちょとした雑学』で挙げられている、本エイ皮素材となる二種は、アカエイ科アカエイ属 Dasyatis である。その一つ、 Dasyatis bleekery は Stingray leather、今一つの、Dasyatis brevicaudata は Smooth Stingray という英名を持っているらしい(前者はロシアのサイトでの確認であるので、やや疑問はある)。最後に復唱、「目から鱏(エイ)」!
・「薏苡仁」この「よくいにん」とは、単子葉植物綱イネ目イネ科ジュズダマ属ジュズダマ変種ハトムギ Coix lacryma-jobi var. ma-yuen の黒褐色の果皮を除き、精白したものを用いた漢方薬の名である。グーグル画像検索「薏苡仁」をリンクさせておく。
・「周-匝」の「匝」は原文字注で記したように、「匝」の中が「帀」となっているのだが、実は中が「帀」となっている漢字が「匝」の正字なのであり、意味は「周」と同じ「めぐり」の意味で、畳語なのである。
・「九曜の星」はインドの暦法に端を発する星の名。実在する星である七曜星(日・月・火・水・木・金・土)に、黄道上に存在して見えないとして想定した、暗黒の星である「羅睺」(らごう)と、彗星である「計都」(けいと)の二星を加えた名称。陰陽道に於いて、人の生年にこれらを配し、吉凶を占うようになった。他に実在する「プレアデス星団」や、「北斗七星」に対して、また「カシオペア座」の呼称としても用いられる。
・「次次は、二、三座をなして、亦、然り」とは、中央の大きな親粒(「魁粒」)の周囲に九曜星をなぞらえるように、七つから八つの、やや小さな粒が並んだものが、更に、二つから三つ、星座のように(というよりも単に複数のものが集まっているいるように見える状態を「座」と呼んでいるのであろう)、次々と、しっかり並んでいる、という意味である。「最高級スティングレイ(エイ革製品、エイ皮製品)」の最初の右の画像を見るに若くはない。スティングレイ! 欲しくなった! そもそも僕の世代にとって、この言葉の響きは、確実に「スティングレー」なのだ! そうだ、「海底大戦争 スティングレイ」だよ!(“Stingray”は後に大ヒット作「サンダーバード」を生み出すことになるジェリー・アンダーソンらが一九六二年に製作したイギリスの特撮マリオネット・ドラマである)。
・「玉蜀黍子」はトウモロコシの実。
・「欛」は刀剣の柄。私が解説するよりも、「備前長船刀剣博物館」の「柄巻師」のページがビジュアル的にも最適。ここでも、サメでなく、エイであることが示されている。
・「曉」は判字と判読に迷ったが、これを動詞として読んでいるのだから「あかつき」から「明かす」、「本物か贋物かを明らかにする」の意味でとり、「あかシ」と読んだ。
・「欛鮫」は刀剣の柄用の鮫の皮の意味であるが、前述の通り、実際にはサメでなく、エイである。
・「聖多默(サントメ)」は、インド東岸のコロマンデル地方の別称(この附近。グーグル・マップ・データ)この地にポルトガルの宣教師セント・トーマスが来たとの故事からの地名とする。木綿の産地で、このサントメから渡来した縞の綿織物ということで「桟留縞(さんとめじま)」、あるいは「唐桟」(「桟」は「桟留」の略)と呼んだ。鮫や鹿の皮も「桟留革」と呼称したようである。
・「太泥(パタニ)」は、現在のタイ王国パッターニー県(マレー半島グーグル・マップ・データ)に十四~十九世紀にかけて存在したマレー人王朝にして、その都。マレー半島東海岸のパタニは、南シナ海有数の貿易港であった。
・「占城(チヤンパン)」は、チャンパ王国で、現在のベトナム中部沿海地方にあった。国域は当該ウィキで確認されたい。
・「咬𠺕吧(ジヤガタラ)」は、現在のインドネシアのジャカルタ(グーグル・マップ・データ)の古称である。
・「暹羅(シヤム)」は、現在のタイ王国。
・「阿媽港(アマカハ)」は、現在のマカオで、「澳門」・「阿馬港」・「亜媽港」等と表記した。
・「南京鮫」同定不能。これはしかし、欛用の鮫皮の商品名であろうと思われ、従って、やはり、サメではなく、エイである。
・「幅廣鮫」同前。しかし、これが「羽広」であれば、鱏(えい)の一種である舶来の鮫皮の一つ、である(「日本国語大辞典」)。以下、「沖縄・八重山探偵団」というブログに「羽広」に関わる探索が載るのを発見した(この方の民俗学的考察は魅力的だ)。それによれば、「鮫皮精鑒録」という書物に、
「羽廣の鮫は親つぶ青く地粒大小あり郭索(がさつく)気味なり」
(羽広のサメの皮は、大きなつぶが青く、地皮についた粒には、大小があって、手触りは、がさつく傾向がある」[やぶちゃん注:以上は該当ブログの筆者の現代語訳。]
そうして、この鮫皮は、サメではなく、エイのものであることを述べ、『羽を広げたように見えるエイの姿を、「羽広」と呼んだのであった』と記している。多分、これに間違いないだろう。前の「南京鮫」も、その「鮫皮精鑒録」や「鮫皮精義」等と言うマニアックな専門古書を辺りを紐解けば出てきそうだ(でも、此の注でそこまでしてやる気は残念ながら、私には、ない)。
・「交趾(カフチ)」は、「交阯」とも書く。前漢から唐にかけての中国の郡名。現在のベトナム北部ソンコイ川流域地域で、後にこの地域が独立してからも、この呼称を用いた。当該ウィキを見られたい。ちなみに紛らわしい「コーチシナ」(交趾支那)という呼び名は、フランス統治下のベトナム南部に対する呼称である。
・「柬埔寨(カボヂヤ)」は現在のカンボジア王国。
・「鞘鮫」は「欛鮫」同様、江戸期には、こうした商品としての名が普通に使われていた(恐らく業界内では現在も)。「皮革ハンドブック」(日本皮革技術協会編)によれば、『1711年、この一年間の唐船・蘭船による、皮革の輸入取引は58回を数え、その取引量を拾い出して合計すると、牛革が6765枚、鹿皮が99544枚、その他の皮革4326枚、そして鞘鮫が1091枚、柄鮫が25625本、海鮫が700本となり重要な輸入品目の一つであった。」(「レザークラフト ハンズたかおか」のサイト内からの孫引。一七一一年は江戸中期、正徳元年で徳川家宣の頃)である。
・「縐鮫」(チリメンザメ)は同定不能。但し、これも文の続きと、その如何にもな名称から考えると、異国産のサメの名前と言うより、「南京鮫」や「幅廣鮫」同様、欛用の鮫皮の商品名であろうと思われ、従って素材はサメでなくエイである可能性が高い。
・「巖石鮫」(ガンセキザメ)同定不能。「縐鮫」注に同じ。
・「發斑鮫」(ハッパザメ)以下、同前。
・「虎鮫」(トラザメ)本邦の実際のサメならば、「トラザメ」は先に「虎沙」で注したネズミザメ上目メジロザメ目トラザメ科トラザメ属トラザメ Scyliorhinus torazame である。が、これも同前で、欛用の鮫皮の名称であろうから、エイも含まれるか。
・「麑鮫」(カノコザメ)これも本邦の実際のサメならば、この名称は現在、仙台地方で用いられ、ネズミザメ上目メジロザメ目ドチザメ科ホシザメ属ホシザメ Mustelus manazo を指している。が、これも同前で、欛用の鮫皮の名称であろうから、エイも含まれるであろう。
・「海子鮫」(ウミコザメ)同定不能。「縐鮫」注に同じ。
・「白倍志鮫」(シロヘシザメ)同前。
・「加伊羅介鮫」(カイラケザメ/カイラゲザメ)前の七件を欛用の鮫皮と推論した理由は、実はこの「カイラケ(ゲ)ザメ」なる呼称が、まさに「著名な鮫皮の名称の一つ」だからである。後に、鮫皮全体を、その共通の文様から「梅花皮鮫(かいらぎざめ)」と称したようである。なお、これについては、イバラエイ Urogymnus asperrimus に種同定している資料があった。
・「駿州の大愛鮫」(ダイ/オオアイザメ)は駿河(現在の静岡県中部と東部・伊豆半島及び伊豆諸島を含む)であることから、トラザメの一種で、伊豆半島周辺海域固有種であるイズハナトラザメ Scyliorhinus tokube を同定候補として、まず、挙げておきたい。但し、「愛鮫」となると、現在、深海ザメの一種としてアイザメ科 Centrophoridae 科の数種も挙がってくる。アイザメ Centrophorus atromarginatus 、ニアウカンザメ Centrophorus niaukang 、モミジザメ Centrophorus sqamosus 、タロウザメ Centrophorus acus 、ゲンロクザメ Centrophorus tessellatus 等である。生態画像を見るに、感覚的にはタロウザメなんか、匂う気はしたが、果して深海ザメを容易に漁獲出来たかどうか、ちょっと疑問……。
・「同國蒲原の小愛鮫」(コアイザメ)の蒲原は、静岡県の中部の庵原(いはら)郡に位置していた町であるが、現在は静岡市に編入合併して、清水区の一部(飛地)となっている(ここ。グーグル・マップ・データ)。前記「大愛鮫」の中に同定種がいることを祈るのみ。モミジサメなんか可愛いけど……。
・「常州の愛古呂」(アイコロ)常州は、常陸で、現在の茨城県北東部。これは頭の「愛」のアイザメよりも、寧ろ、後の「古呂」が、カスザメ目カスザメ科のコロザメ Squatina nebulosa を連想させるようには思われる。
・「紀州の脊古呂」(セゴロ)これは前項と同種か、その仲間の紀伊地方での呼び名と思われ、従って同定候補も同じコロザメとしておく。
・「松前の菊登知」キクトヂ 同定不能。ただ、その「きくとぢ」という印象的な呼称が気になる。松前にこの痕跡は残っていないか? そもそもこれは「菊綴ぢ」であろう。「菊綴じ」とは、水干や直垂(ひたたれ)等の縫目に綴じ付けた紐の呼称で、本来は絹製で、その結んだ紐の先をほぐして菊花のように細工したところから名づけられた。さて、これは後に皮紐製のものが登場してくるのだが、そこで用いられたのが鮫皮である。これは、エイ由来が殆んどとされる「欛鮫」等とは違って、サメ由来だったのかも知れない。もし、松前の方が、ここをお読みになった際には、是非、郷里でお聴きになってみてもらいたい。あなたのメールをお待ちしている♡【2008年6月8日改稿】本件について、「鱘」の同定でも御助言を頂戴した、釜石キャビア株式会社というところでチョウザメに係わるお仕事に従事しておられるY氏から、貴重な情報を頂戴した。以下に引用する。
《引用開始》
「松前の菊登知」とはチョウザメのことでございます。水干の袖等を留める、放射状の糸綴を「菊綴」と呼びますが、この放射状の装飾が、チョウザメの背の鱗に似ていることから「菊綴鮫(きくとぢ)」とも呼ばれていました。松前は最近でもチョウザメが捕獲される地域でございます。
《引用終了》
この情報に、私は、まさに、目から「鱗」だった。実は、それは、エイでもサメでもなく、チョウザメだった――更には「逆」だった――「絹製」の「水干や直垂等の縫目に綴じ付けた」「紐の先をほぐして菊花のように細工した」その模様がチョウザメの鱗と似ていたのであった――加えて驚天動地・無知蒙昧というか、現在も「松前の菊登知」は捕獲されているのだった!――本件については、もう少し詳しい情報をお願いしたところ、お忙しい中、すぐに次のようなメールを頂戴した。
◇〔引用開始〕
日本において、忘れ去れてしまった魚、その利用の文化と言う観点から、「菊綴」をいろいろと調べていました。その、中心地は北海道であり、その文化はアイヌ民族が中心で、文字を持たない民族であるため、その資料数は限定されています。アイヌ語でチョウザメを「ユベ」と呼び、北海道の地名に「ユベ」の名のつく場所は、チョウザメが捕獲、又は関係のある場所とされています。日本近海では、大きく2種類のチョウザメが捕獲されますが、「菊登知」とされるチョウザメは、 Acipenser medirostris mikadoi と言うチョウザメです。 mikadoi は「帝」の意と聞いております。小河川にも産卵遡上する、特殊なチョウザメでございます。重くて恐縮ですが、菊登知の鱗を利用した刀剣の写真を添付します。この、5月末に北海道大学のグループが、日本近海で捕獲される菊登知を、十数年がかりで収集し、餌付けした親魚から採卵、孵化に成功しております。寺島良安先生も、生きたチョウザメは見たことはなかったと思いますが、確かにチョウザメは日本においても、知られていた魚であったと考えられます。本州では、付近の海で捕獲された菊登知が、大洗水族館で、飼育展示されています。
《引用終了》
Y氏のチョウザメへの思いは、確かな日本の、いや、地球の自然の保全へと繋がる暖かい「智」であると、私は思う。Y氏の文章の真摯な温もりを味わって戴きたく、そのまま転載した。また、送って頂いた「菊綴」の写真も御紹介させて戴く。
ここでY氏が述べておられるのは、硬骨魚綱条鰭亜綱軟質区チョウザメ目チョウザメ科チョウザメ亜科チョウザメ属のチョウザメ(和名をミカドチョウザメとするものもあるが氏の呼称を支持する) Acipenser medirostris mikadoi である。そうして、「菊綴」なる存在は多様に変化してゆく。今度はフィード・バックして、「菊綴」に似たチョウザメの鱗が、刀剣の鞘の「菊綴」文様に逆利用されるたのだった――私は、「智」と「物」が、自然と人事の間を変化自在に行き来した良き時代をしみじみ感じるのである。なお、後日、この私の注記とY氏の写真は、ある学術論文に引用掲載された。]
***
かはゝぎ 【正字未詳】
皮剥魚
△按此魚形狀甚醜而頭似方頭魚狀畧似鮫全體薄扁
灰白色無鱗皮厚有沙口極小鰓鰭亦小背上有鬛腹
《改ページ》
下有翅背中目上有一刺尾無岐從尾末剥皮乃皮裏
青而肉潔白炙食【淡甘】味美傳云用皮擦錢瘡能治春
夏京師希見之蓋此鮫之屬乎
*
かはゝぎ 【正字は未だ詳らかならず。】
皮剥魚
△按ずるに、此の魚、形狀甚だ醜くして、頭は方-頭-魚(くずな)に似、狀、畧ぼ、鮫に似、全體薄く扁たく、灰白色、鱗無し。皮厚く、沙有り。口、極めて小さく、鰓鰭〔(さいき)〕、亦た小さく、背の上に鬛〔(ひれ)〕有り。腹の下に翅〔(はね)〕有り。背、目の上に中〔(あた)〕りて一刺有り。尾、岐無く、尾の末より皮を剥ぎなば、乃ち皮の裏、青くして、肉、潔白なり。炙り食ふ【淡、甘。】。味、美なり。傳へて云ふ、皮を用ひて、錢瘡〔(ぜにかさ)〕を擦〔(す)〕れば、能く治す〔と〕。春・夏、京師〔(けいじ)〕〔に〕、希に之を見る。蓋し此れ鮫の屬か。
[やぶちゃん注:フグ目カワハギ科カワハギ属或いはカワハギ Stephanolepis cirrhifer である。その表皮の形状に引かれてか、良安は、最後に鮫の仲間であろうかと誤認している。と言うより、この絵、カワハギじゃあ、ねえ!
・「方頭魚」と書き、かつ「クズナ」とルビが振られている以上、これはスズキ目キツネアマダイ科アマダイ属 Brachiostegus に属する魚の異名である。但し、「方頭魚」はカサゴ目ホウボウ科カナガシラ Lepidotrigla microptera の異名でもあるが、「京師」(京都)の話が後半に出る辺りから考えても(「西京焼き」で有名な「グジ」は「アマダイ」の異名である)、前者を指すと考えてよいだろう。しかし、アカアマダイBranchiostegus japonicus 、キアマダイ Branchiostegus auratus 、シロアマダイ Branchiostegus alubus や、カナガシラ同士は良く似ていると思うのだが、正直、カワハギはどちらにも似ていない。冒頭の絵はアマダイっぽくは見えるが、京にいた良安が、アマダイを知らぬ筈はないし、無鱗魚に入れよう筈も、これ、ない。本記載は、やはり、カワハギである。
・「沙、有り」は、鮫同様、表皮が砂のようにざらついていることを示す。
・「腹の下に、翅、有り」と「目の上に中りて、一刺、有り」は、これなら、カワハギ属に極めて特徴的な部分で、背びれの第一条が太く短い棘となっている(特異的に癒合した腹鰭も同様で、前者の「翅」はそれを指して言っているものと思われる)。ちなみに、背鰭の第二軟条が糸状に細く伸びているのは♂である。
・「錢瘡」は、一般に「田虫(たむし)」と呼ばれる体部白癬を指す。主にカビの仲間である白癬菌属 Trichophyton 、小胞子菌属 Microsporum 、表皮菌属 Epidermophyto といった皮膚糸状菌が病原体である。感染すると、縁がピンク色の輪状(銭型)でやや盛り上がった皮疹が形成される。
さて、聞いた話じゃ、カワハギは、このところ、深刻な大発生をしているエチゼンクラゲ Nemopilema nomurai の天敵だそうで、集団で、エチゼンクラゲを襲撃するという(考えてみれば、クラゲ食のマンボウもフグ目だもんなあ)。そこから、同じ天敵のアジやカワハギ釣をやめて……とは、ならないんだな……逆に漁師は、エチゼンクラゲを餌に、更にカワハギを多量に漁獲するというわけだ……目の前にぶら下がった餌しか見えないのは……カワハギばかりではないのだ……。最後に一言。かつて多量のカワハギを江の島で父が釣り、母が刺し身にしたのだが、よく言われる苦玉(胆嚢)を捌く途中で、潰してしまった。洗い流したけれども、その大皿の上の数多のカワハギの刺し身は、空しく、食われずに残された。身の味が落ちるどころではない。真面目に、苦くて食えなくなってしまうので、ご用心!]
***
さはら
さごし
馬鮫
マアヽキヤ゚ウ
鰢鮫 章鮌
鰆【音春】
【俗云佐波良】
青箭魚【其小者
俗云佐古之】
[やぶちゃん字注:以上五行は、前四行下に入る。]
南産志云馬鮫魚青斑色無鱗有齒【一名章鮌】小者曰青箭
△按馬鮫魚頭尖眼大鰓硬無鱗青色背有青斑圓紋又
無背文有之肚白鬐硬刺尾有岐尾耑有刺鬛如大鋸
齒其大者三尺許春月盛出故俗用鰆字形狹長故稱
狹腹狹腰乎其小者尺許色最青並肉白【甘、温。】脂多味
厚美膾炙※腌皆佳
[やぶちゃん字注:※=「月」+「雋」。]
洋鰆 馬鮫之極大者長五六尺味劣
■和漢三才圖會 江海無鱗魚 卷ノ五十一 ○十
唐墨 馬鮫之䱊也其胞多子形如刀豆莢而大乾之褐
色微似唐墨故名之土州阿州讃州多出之味【甘微澁】美
然不如於鰡䱊之唐墨
*
さはら
さごし
馬鮫
マアヽ キヤ゚ウ
鰢鮫〔(ばかう)〕 章鮌〔(しやうこん)〕
鰆【音、春。】
【俗に佐波良と云ふ。】
青箭魚〔(せいせんぎよ)〕【其の小者。】
【俗に「佐古之」と云ふ。】
「南産志」に云ふ、『馬鮫魚は青斑色、鱗、無く、齒、有り【一名、「章鮌」。】。小さき者を「青箭」と曰ふ。』
△按ずるに、馬鮫魚は、頭〔(かしら)〕、尖り、眼〔(まなこ)〕、大きく、鰓〔(あぎと)〕、硬く、鱗、無し。青色。背に、青〔き〕斑〔(まだら)の〕圓紋、有り。又、背〔の〕文、之れ、無きも、有り。肚〔(はら)〕、白く、鬐〔(ひれ)〕に、硬き刺、有り。尾、岐〔(また)〕、有り、尾耑〔=端〕(をさき)に、刺鬛〔(とげひれ)〕有りて、大鋸〔(〔おほ〕のこぎり〕の齒のごとし。其の大なる者、三尺許〔(ばかり)、春月、盛んに、出づ。故に、俗に、「鰆」の字を用ふ。形、狹〔(せば)〕く、長し。故に「狹腹(さはら)」・「狹腰(さごし)」と稱すか。其の小さき者、尺ばかり、色、最も青く、並びに、肉、白く【甘、温。】、脂〔(あぶら)〕、多く、味、厚く、美なり。膾(なます)・炙(やきもの)・※(いりもの)・腌(しほもの)、皆、佳し。
[やぶちゃん字注:※=「月」+「雋」。]
洋鰆(をきさはら[やぶちゃん注:ママ。]) 馬鮫の、極めて大なる者、長さ五、六尺、味、劣れり。
唐墨(からすみ) 馬鮫の〔(こ)〕なり。其の胞、子、多く、形、刀豆莢(なたまめざや)のごとくして、大〔なり〕。之れを、乾かして、褐色、微〔(わづ)〕かに、唐墨に似たる故に、之れを名づく。土州・阿州・讃州より、多く、之れを出だす。味【甘、微澁。】、美□〔→なり〕。然れども、「鰡䱊(ぼらのこ)」の唐墨には、如かず。
[やぶちゃん注:スズキ目サバ科サワラ Scomberomorus niphonius 。出世魚として知られる。成長するに従って、
サゴシ(西日本)・サゴチ(関東)
↓
ナギ
↓
サワラ
或いは、
サワラゴ
↓
グッテラ
↓
サゴシ
↓
サワラ
と呼ぶ。
・「南産志」は、明の何喬遠(かきょうえん)撰になる現在の福建省地方の地誌・物産誌である「閩書」(びんしょ)の中の二巻。
・「青箭」の「箭」(せん)は「弓矢」のことを言う。その魚体に相応しい命名である。
・「※2」(※2=「月」+「雋」)の「いりもの」とは、食材の水分がなくなるまで炒ったものを言う。
・「沖鰆」は、サワラの大型個体の呼称と考えてよいと思われる。現在は、あの獰猛で名高い「バラクーダ」(英名: barracuda )=スズキ目カマス科カマス属オニカマス Sphyraena barracuda 、及び、その仲間を、異名や、切り身の商品名で、「オキサワラ」と呼んでもいる。実際、サワラよりも大きくなるようである。同種は西日本・沖縄・小笠原諸島に棲息している。
・「唐墨」は一般には長崎名産として、、ボラ目ボラ科ボラ属ボラMugil cephalusの卵巣の塩漬けしたものを、酒につけ、さらに乾燥させたもので珍味として名高いが、現在でも、香川県では、サワラの卵巣から、カラスミを製造しており、ボラに比して、味は濃厚、と謳っている。台湾では「烏魚子」(ボラ卵使用)、ヨーロッパでは同様のものを、フランスでは「ブタルグ」(Boutargue)、イタリア(サルジニア島)では「ボッタルガ」(Bottarga)、スペインでは「ウエバ(卵)のサラソン」(魚類の塩漬けの乾燥品)等と称して、味わう。ヨーロッパのそれらは、マグロ・スズキ・メルルーサ等の多彩な魚卵が使用されている。一言だけ。さっと炙るのが、本カラスミを味わう、何よりのコツである。
・「䱊」は「はらご」「はららご」で、「魚の卵」を言う語。
・「刀豆莢」の「刀豆」はナマメ科ナタマメ Canavalia gladiate で、その莢は四十センチメートルにも達する。ちなみに、「福神漬け」の中に入っているプラナリアみたような形をした中空のものは、この莢を輪切りにして漬け込んだもので、あれが多いほど、高級な「福神漬け」なのだそうだ。更に付け加えると、このナタマメの豆には、シアン配糖体の一種であるアミグダリン amygdalin が含まれており、実が熟すと、その分解過程で、微量ながら、青酸が発生するため、ナタマメの解説には実は有毒である(脱線序でに、シアン配糖体アミダグリンとは懐かしい。吉永春子氏は一九九六年年講談社刊の「謎の毒薬」で、かの冤罪事件「帝銀事件」の毒物の正体として、これを挙げておられた)。
・「土州・阿州・讃州」は、順に、土佐・阿波・讃岐。]
***
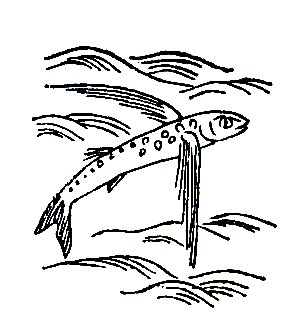
とびいを
ひいご
文鰩【音姚】
ウヱン ヤ゚ウ
【音飛】 飛魚
【俗云止比魚
【又云比以古】
[やぶちゃん字注:以上三行は、前四行の下に入る。]
本綱文鰩大者尺許狀如鯉有翅與尾齋羣飛海上其身
[やぶちゃん注:は(つくり)は「鳐」のそれであるが、本文ともに正字で示した。]
蒼文白首赤喙常以夜飛肉【甘酸】食之已狂又宜妊婦
△按飛魚西海多背蒼腹灰白色三四月群飛其飛也離
水上尺許可一段而没水復飛薩摩最多作鮿送他邦
*
とびいを
ひいご
文鰩【音、姚。】
ウヱン ヤ゚ウ
※�【音、飛。】 飛魚
【俗に「止比魚」と云ふ。】
【又、「比以古」と云ふ。】
「本綱」に、『文鰩は、大なる者、尺ばかり。狀〔(かたち)〕、鯉のごとく、翅〔(はね)〕有り、尾と齋〔(ひと)〕し。海上に羣飛す。其の身、蒼き文、白き首〔(かうべ)〕、赤き喙〔(くちばし)〕。常に、夜を以つて、飛ぶ。肉【甘、酸。】、之れを食へば狂を已(や)む。又、妊婦に宜(よろ)し。』と。
△按ずるに、飛魚は西海に多し。背、蒼く、腹、灰白色。三、四月、群飛す。其れ、飛ぶや、水上を離るること、尺許〔(ばかり)〕にして、一段ばかりにして、水に没し、復た、飛ぶ。薩摩に、最も、多し。鮿(ひもの)に作り、他邦に送る。
[やぶちゃん注:ダツ目トビウオ科 Exocoetidae 。現生種は約五十種、日本近海でも約三十種を数える。
・「鯉」はコイ属コイ Cyprinus carpio (僕はこの「カルピオ」という響きが大好き!)のコイ以外は指さないが、似ていない。形態上の変異が少ないと感じるが故に、魚そのものに興味が持てないという私が、それでも「似ていない」と言うんだから、似てない!
・「水上を離るること、尺ばかり」は、度量衡オーバー気味の良安にしては、遠慮し過ぎ。実際には、滑空時の高さは三メートルに及び、飛距離は百~三百メートルが平均的な記載であるが、五百メートルを越えて飛翔できるとするもの、高さ十メートル(!)・飛距離四百メートル・時速七十キロメートルで飛翔したという記録がある、とする記事もある。私も、ここでは、良安になりそうになるが、きっと大洋では、マグロやシイラに追われた彼らが、まさに必死になって飛翔するとき、我々の想像を絶する最長不倒距離を、今、この時も、知られずに更新しているに違いないと思うのである。
トビウオ類は、西日本や日本海側では「アゴ」と呼び、よく賞味される。干した「アゴ焼き」や「アゴだし」は私の家の常備品である(「アゴだし」は醬油の強い濃厚さや、白だしの鼻につくお上品さに辟易している私には、必需品である)。かつて四十六年前、同僚教師らと一緒に訪ねた、神津島で、「くさや」の店を訪れた時、漬け場も見せてくれた、そこの主人は、「一番旨いのは、ムロアジじゃあなくて、トビウオだな。」とぼそっと言い、特に選んでくれた一匹を買って、即、民宿で焼いてもらった。民宿の主人や奥方は、気持ちよく、何も言わずに焼いてくれたのだが、同じツアーで同宿したOL二人はその焼いた臭いに、悪鬼のごとき顔となった。しかし、僕にとって,実は,初めての「くさや体験」であったのだが、その後に食ったくさやの中でも、あれほどの旨さを感じたことは、今もって、ない。
脱線だが、最後にその折りの思い出を語ろう。僕は神津島では、夜な夜な酔っては、民宿のすぐ前の墓場に行った。いや、槐多の「悪魔の舌」では、残念ながら、ないのだ。大きな木に抱かれるように、花々に飾られた幻想的な夜の墓場を見に行ったのだ。先祖崇敬と供養の習慣が厳然として残っていた。女達は、毎日毎朝、墓に色とりどりの南国の切花を抱えるほどに供える。最早、無縁仏となった墓にさえだ。そこでは、人はかつてのように、今も祖霊と、文字通り、華やかに交感するのだ。私の半生の中でたった一度だけの、美しい親しみに満ちた夜の墓場との出会いだった――
・「一段許にして」は、漠然とした「一段落して」の意味では、勿論、ない。「段」は距離の単位で、六間、約十一メートルである。ここでも、良安、異例に、しょぼい。まあ、高度が三十センチメートルじゃあ、この程度かな。]
***
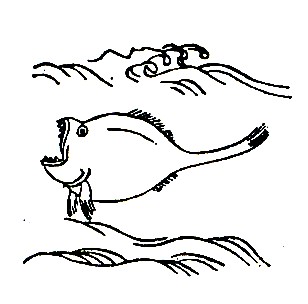
あんごう
華臍魚
ハアヽ ツユイ イユイ
老婆魚 綬魚
琵琶魚
【俗云阿牟古宇】
[やぶちゃん注:この三行は、前の三行の下にある。]
泉州府志云華臍魚腹在帶如帔子生附其上故名綬魚
其形如科斗而大者如盤呉都賦云此魚無鱗而形似琵
琶故又名琵琶魚
△按此東海皆多有西南海少十月初出最賞之三月以
後稍希夏秋全無之狀團偏如盤肉厚肚大背黒腹白
眼鼻向上口𤄃大而鬛鬐短弱骨亦極軟尾無岐而長
爲臛食之味【淡甘平】惟去胃與頭余皆可食以爲上饌割
之有法呼曰鈞切其法以繩貫下唇懸于屋梁入水於
口可五六升水自口溢爲度先切頸喉外皮而次剥周
身皮還割鬐及肉采膽割腸及骨以刀刺胃袋則畜〔→蓄〕水
《改ページ》
■和漢三才圖會 江海無鱗魚 卷ノ五十一 ○十一
迸出若不如法割之則肉不離皮骨
*
あんごう
華臍魚
ハアヽ ツユイ イユイ
老婆魚 綬魚〔(しうぎよ)〕
琵琶魚
【俗に「阿牟古宇」と云ふ。】
「泉州府志」に云はく、『華臍魚は、腹に、帶、在りて、帔〔(ひ)〕 のごとし。子、生じて、其の上に、附く。故に「綬魚」と名づく。其の形、蝌斗〔(かと)〕のごとくして、大なる者、盤〔(ばん:大皿。)〕のごとし。「呉都賦」に云ふ、『此の魚、鱗、無くして、形、琵琶に似たる故に、又、「琵琶魚」と名づく。』と。
△按ずるに、此れ、東海に、皆、多く、有り。西南海には、少なし。十月、初めて出でて、最も之れを賞す。三月以後、稍〔(やや)〕、希(まれ)なり。夏・秋、全く、之れ、無し。狀〔(かたち)〕、團〔(まろ)〕く、偏たく、盤のごとし。肉、厚く、肚〔(はら)〕、大、背、黑く、腹白く、眼・鼻、上に向き、口、𤄃く、大にして、鬛-鬐〔(ひれ)〕短かく、弱し。骨、亦、極めて、軟にして、尾、岐〔(また)〕、無くして、長し。臛(しる)と爲して、之れを食ふ。味【淡甘、平。】、惟〔
(ただ)〕、胃と、頭とを、去り、余は、皆、食ふべし。以つて、上饌と爲す。之れを割〔(さ)〕くに、法、有り。呼んで、「鈞切(つるしぎり)」と曰ふ。其の法、繩を以つて、下唇を貫き、屋-梁(やね)に懸け、水を、口より、入るること、五、六升ばかり。水、口より溢(あふ)れるを、度〔(ど)〕と爲す。先づ、頸-喉〔(のど)〕の外皮を切りて、次に、周身〔(しうしん)〕の皮を剥ぎ、還りて、鬐〔ひれ〕、及び、肉を割き、膽〔(きも)〕を采り、腸、及び、骨を割き、刀を以つて、胃を刺せば、袋、則ち、蓄水、迸〔(ほとば)〕しり出づ。若し、法のごとくならずして、之れを割けば、則ち、肉、皮骨〔(ひこつ)〕を離れず。
[やぶちゃん注:アンコウ目 Lophiiformes 。アンコウは、分類がやや複雑で科まで言うのは厳しい。HP「釣絶! 魚ゲノム」の「アンコウ目一覧表」を参照されたい。
・「泉州府志」は、南宋の嘉定年間(一二〇八年~一二二四年)年に李芳子が起筆したとされる(別説あり)、現在の福建省にあった泉州府の地誌・物産誌。
・「帔」は、服のすそ、裳裾(もすそ)。これは次項で説明するチョウチンアンコウの仲間の皮膚が、ゼラチン状で、剥離しやすい様子を説明しているものと思われる。
・「子、生じて、其の上に、附く」は興味深い叙述である。本記述のアンコウはチョウチンアンコウ亜目 Ceratioidei の内、ヒレナガチョウチンアンコウ科 Caulophrynidae に属するもの、又は、ミツクリエナガチョウチンアンコウ科 Ceratiidae のミツクリエナガチョウチンアンコウ Cryptopsaras ouesii や、ビワアンコウ Ceratias holboelli 等(これにオニアンコウ科 Linophrynidae を加える説もあるが、どうも寄生♂はこの科では見つかっていないようだ)に属するものが同定候補となる。何故なら、周知の通り(この話は、昔は、驚天動地の雑学の秘密兵器であったが、最近は、トリビア流行りで知れ渡ってしまい、授業で話しても、知ってらあという顔をされるようになってしまった)、上に挙げたアンコウ類は(総てのアンコウが、このライフサイクルを持つと思っている人がいるが、それは間違い)、極端な性的二形で、♂が極端に小さく(例えば、ミツクリエナガチョウチンアンコウでは平均、♂は僅か二センチメートルであるに対して、♀は四十センチメートル。ある記事では、♂は♀の六十分の一ともする)、しかも♂が♀の腹部に寄生するということである。しかも、♂は♀の腹部や体後部に噛みつくと同時に、癒合を促進する酵素の分泌を開始し、その結果、皮膚は勿論、血管も繋がり、♂は眼を初めとして、外見上、悉く、退化してしまい、遂には♀の体の一部、奇妙な突起物にしか見えなくなる(但し、勿論、精巣はしっかりと機能しているわけで、この時、当該個体は雌雄同体となったと考えてよい。因みに、この寄生オスの変異過程の途中でも、寄生された♀は他の♂へのフェロモン放出による♂に対する誘引行動をやめず、二匹目の♂を、更に、ぶら下げる♀も稀ではないようだ)。本件についての歴史的発見や生物学的詳細は、そのチャートを含め、目からアンコウの♂が出るほどに秀抜な「チョウチンアンコウの深海生活」(サイト「水産雑学コラム」内)内)で吊るし切り風にブスっとトドメの一発だ! ちなみに、このミツクリエナガチョウチンアンコウ、魚類和名の最長不倒距離とも言われるが、それより博物学フリークには懐かしい名前に出会えて嬉しくなる。漢字に直せば、「箕作柄長提灯鮟鱇」、そこで奉名されているのは最初の東京帝国大学生物学教授にして、日本海洋生物学発祥の地である三崎臨海研究所の創立者、箕作佳吉(みつくりかきち)先生の姓だからだ。
さて、ここで、参考にした上記の叙述の中で、長年、私が疑問に思っていることを述べておきたい。この筆者は、最後の「吊るし切り」の項の冒頭で、教科書にもしばしば載る、加藤楸邨の有名な
鮟鱇の骨まで凍(い)ててぶちきらる
を引用されている。多くの句解説では、これに、歳時記、宜しく「吊るし切り」の説明を載せるのであるが、私は、このアンコウは「吊るし切り」ではないと思うのである。ここでは、捌く者が、「骨まで凍て」たかのようなアンコウを、出刃包丁で「骨まで」断ち割るように(若しくは、事実、断ち割って)、ざっくり「ぶちきらる」のである。そこにこの、バツン! という音が聴こえてくるような慄っとする素敵なリアリズムが生じるのである。ところが「吊るし切り」では、このように「ぶちきらる」というダイナミズムは、どう考えても生じないと思うのである(私は「吊るし切り」自体、テレビの映像でしか見たことがなく、実見はしていないが)。いや、もし、これが楸邨が実見した「吊るし切り」の場面なのだとしたら……残念ながら、その瞬間、本句の魔力は、減衰する。いっかな私も、この句を素直に読んで「吊るし切り」をイメージ出来ないからである。それはきっと、多くの人に納得して頂けるものと信ずるのである。則ち、私は、本句で「吊るし切り」の解説の冒頭を飾ることには疑義があるのである。反論をお待ちする。因みに、大型でないアンコウは、やや手間取るものの、勿論、俎の上で調理できる。良安が最後に言う言葉は、必ずしも、真ではないのである。私は実はアンコウ鍋が大好きなのである。
・「綬」は、官位を示すしるしとしての紐、或いは、印を結びつけた紐、または礼服(らいふく)着用の時に胸の下に垂らした帯などを指す。
・「蝌斗」は「蝌蚪」で「おたまじゃくし~♪ (゜゜)~
・「呉都賦」は晋の左思の連作「三都賦」の一篇。晋に先行する三国時代の国のそれぞれの都の情勢・物産・制度等を描いた「蜀都賦」・「吳都賦」・「魏都賦」からなる。発表当時から、名文の誉れ高く、貴族や富豪が先を競って書写したため、洛陽は紙不足となり、紙の値段も高騰した(「晋書」文苑伝)。所謂、「洛陽紙價貴」、「洛陽の紙価を高からしむ」の故事となった文章である。
「△」以下の良安の記述は、食用種のアンコウについての記載であるから、
アンコウ(クツアンコウ)Lophiomus setigerus
キアンコウ(ホンアンコウ)Lophius litilon
を挙げておけばよいであろう。
・「惟だ胃と頭とを去り」とあるが、「胃」はアンコウの「七つ道具」と呼ぶところの、「トモ」(鰭)・「ヌノ」(卵巣)・「キモ」(肝臓)・「水袋」(胃袋)・「エラ」(鰓)・「柳肉」(身及び頬肉)、「皮」にしっかり入るので、去っちゃダメ! 「頭」は、削ぎ落とした後の頭骨部分を指すのであろうが、これも、しっかり、出汁をとるために必要だぞ
! 良安先生のアンコウ鍋、ちょっと味に不満がありそうだな。
・「鈞切」は、ゼラチン状で捌きにくいアンコウを調理するための独特の「吊るし切り」で、茨城の「大洗ホテル」のYouTubeの『大洗ホテル「鮟鱇(あんこう)吊るし切り」 2,222回目』がよかろう。ちなみに、この動画では見られないが、最後に胃を刺すのだが、これはパフォーマンスではない。これで最後に包丁を洗うというプラグマティックな意味があるのである。
・「度と爲す」とは、「丁度いい頃合いとして、水を入れるのをやめる。」という意。
・「頸喉」は二字で「のど」と訓読しているか。東洋文庫版訳でもそうルビを振っている。]
***
【針有鋸齒而在尾
根際能左右振螫
人欲捕之可抓目
際陷處不然則所
螫大※1〔→痛〕甚者至死】
[やぶちゃん字注:以上の四行の割注は特異的に以下の図のすぐ上部に罫線なしである。国立国会図書館デジタルコレクションで私の底本と同一の版本のここを見られたい。「※1」は非常に奇体な字体で、通常の部分要素合成で示すことが出来ない。恐らく「痛」の字の篆書体(「人文学オープンデータ共同利用センター」の『「痛」(U+75DB) 篆書字体データセット』のこちらを参照されたい)の(つくり)部分に近いものと思われる。敢えて表現すると、《(まだれ)の上部に「コ」を左払いに接合し、その下に「冉]の全ての外への出っ張りを、全部、はずし、右中央の横画をも取とり払ったものを組み合わせた字体》である。]
ゑひ
こめ
ゑざれ
海鷂魚
ハアイ セウ イユイ
[やぶちゃん注:「鷂」の字の(へん)は「揺」の(つくり)であるが、正字で示した。本文も同じ。]
鱝【音忿】 荷魚
卲陽魚 鯆魮
蕃蹹魚
【和名古米】
【鱏訓衣比謬
也鱏乃鱘也】
[やぶちゃん字注:以上六行は、前四行の下に入る。]
本綱海鷂魚海中頗多江湖亦時有之狀如盤及荷葉大
者圍七八尺無足無鱗背青腹白口在腹下目在額上尾
長有節螫人甚毒皮色肉味同鮎肉内皆骨節節聯比脆
軟可食肉【甘鹹平有小毒】常有風濤則乘風飛於海上逢物則以
尾撥而食之【魚掉尾曰鱍音鉢】
△按鱝形狀如上說大者皮有沙如鮫以可飾刀鞘其口
甚下【大𢷽〔=概〕可稱𮌚〔=胸〕處乎謂在腹下者過矣】大者丈余煎肝取燈油
赤鱝 卽真鱝也其肉赤俗傳云煑食止瀉痢其膽治小
兒雀目屢試有効未言本草但不多食可矣
《改ページ》
鷂鱝 喙尖色黒有肉翅頗似鳶鷂之形故名鳶鱝本名
海鷂魚亦𢷛〔=據〕此乎其肉脆味美
窓引鱝 狀薄扁而尾細長如挽窓戸繩故名之其肉骨
畧硬味劣
牛鱝 黒色肉白肥味最不美
*
【針に、鋸齒、有りて、尾〔の〕根の際〔(きは)〕に在り。能く左右に振りて、人を螫〔(さ)〕す。之れを捕へんと欲〔せば〕、目の際の陷處〔(おちいるところ)〕を抓(つか)むべし。然らずんば、則-所〔(たちどころ)〕にして螫〔され〕、大いに痛み、甚〔だしき〕は死に至る。】
ゑひ
こめ
ゑざれ
海鷂魚
ハアイ ヤ゜ウ イユイ
鱝【音、忿。】 荷魚
卲陽魚〔(せうやうぎよ)〕 鯆魮〔(ほひ)〕
蕃蹹魚
【和名、「古米」。】
【「鱏」を「衣比〔(えひ)〕」と訓ずるは、謬〔(まちが)〕ひなり。「鱏」は、乃〔(すなは)〕ち、「鱘(かぢとをし)」なり。】
「本綱」に、『海鷂魚〔(かいえうぎよ)〕は、海中に、頗〔(すこぶ)〕る、多し。江湖にも亦、時に、之れ、有り。狀〔(かたち)〕、盤、及び、荷葉〔(かえふ)〕のごとく、大なる者は、圍〔(めぐり)〕、七、八尺。足、無く、鱗、無く、背、青く、腹、白く、口は、腹下に在り、目は、額の上に在り。尾は、長くして、節〔(ふし)〕、有り、人を螫す。甚だ、毒あり。皮の色、肉の味、「鮎(なまづ)」に同じ。肉の内、皆、骨、節節〔(ふしぶし)〕、聯-比(つらな)り、脆く、軟〔(やはらか)〕にして、食ふべし。肉【甘鹹、平。小毒、有り。】常に、風の濤〔(なみ)〕、有れば、則ち、風に乘じて、海上に飛びて、物に逢へば、則ち、尾を撥(はね)て、之れを、食らふ【魚、尾を掉〔(う)〕つを、「鱍」と曰ふ。音、鉢。】。』と。
△按ずるに、鱝は、形狀、上の說のごとし。大なる者、皮に、沙、有りて、鮫のごとし。以つて、刀〔の〕鞘〔(さや)〕を飾るべし。其の口、甚だ、下(ひき)く【大𢷽〔(おおむね)〕、「胸」と稱すべき處か。「腹下に在り。」と謂ふは過ぎたり。】。大なる者、丈余。肝を煎〔(せん)〕じて、燈油を取る。
赤(あか)鱝 卽ち、真鱝〔(まえい)〕なり。其の肉、赤し。俗に傳へて云ふ、「煑〔て〕食〔ふに〕、瀉痢を止め、其の膽〔(きも)は〕、小兒の雀目(すずめもく)を治す。」〔と〕。屢々、試み、効、有り。未だ、本草〔:諸本草書。〕に言はず。但し、多食はせずして〔→せざるが〕可なり。
鷂鱝(とびゑひ) 喙〔(くちばし)〕、尖り、色、黒く、肉の翅〔(はね)〕、有り。頗る、「鳶(とび)」・「鷂(はいたか)」の形に似たる。故に「鳶鱝〔(とびえい)〕」と名づく。本(もと)、「海鷂魚」と名づくは、亦、此れに據〔(よ)〕るか。其の肉、脆く、味、美なり。
窓引(まどひき)鱝 狀、薄く扁たく、尾、細く長く、窓の戸を挽(ひ)く繩のごとくなる故に之を名づく。其の肉の骨、畧ぼ硬く、味、劣れり。
牛鱝 黑色、肉白く肥え、味、最も美ならず。
[やぶちゃん注:「ゑひ」だが、歴史的仮名遣は「えい」が正しい。エイとは、軟骨魚綱板鰓亜綱に属する魚類の中で、鰓裂が体の下面に開くものを便宜的に総称する用語である。「鮫」の項で述べたように、サメは原則として、鰓裂が体側に開く(但し、カスザメ目 Squatiniformes の鰓孔は腹側から側面に開いている)。本項の図について一言。先に「鱣」(フカ)の注末で述べたように、これは、一般的なエイのフォルムで想定するアカエイ Dasyatis sp. でもなく、体幹がよく隆起するヒラタエイ Urolophus aurantiacus でもない。全体に強い丸みを持って団扇(うちわ)型であること、背面に有意な棘突起らしきものが、体の正中線に沿うように尾部まで続くところから、私は、
エイ上目サカタザメ目ウチワザメ科ウチワザメ属ウチワザメ Platyrhina sinensis
ではないかと考えている。但し、勿論、それを掲げてあっても、何らの問題はない。「ウチワザメ」は「ザメ」とつくが、エイ目であるからである。
まずは毒である。タンパク毒であるが、一般の海洋生物毒同様、研究が進んでいない。最近では、オーストラリアの自然保護運動家として知られたステファン・ロバート・アーウィンStephen Robert Irwin氏がグレートバリアリーフのアカエイDasyatis sp.で命を落としている(私はYouTubeで、その指された際の動画を見た。詳細は彼についてのWikipediaを参照されたい)。
因みに、冒頭の図中上部の割注については、東洋文庫版後注に、『この説明は、杏林堂版にはない。』とある。私の底本としている一九九八年刊の大空社版CD-ROM「和漢三才図会」も東洋文庫版が底本とした五書肆名連記版であろう(底本明記が、このCD-ROMにはない)。この異同は良安による本書改稿の結果と考えられるが、本項は、その冒頭の図中割注といい、不可解な字体の使用(「※」)といい、やや訓点も、他と、ちょっと異なる気がする(対句法や、他に見ない連続性等々)。少なくとも本項の叙述の際、良安、何かあったのかな? と余計な詮索をしたくなる程に、かなり奇異な感じを受けることを述べておく。
・「目の際の陷處」とは、眼の後ろにある一対ある「噴水孔」を指す。鰓に水を送る役目をする一方で、捕食時などに、同時に吸い込んでしまった水や、砂を排出する機能があるので、こう名付けているものであろう。
・「鱘」と良安が言う時、それはスズキ目メカジキ科 Xiphiidae 及びマカジキ科 Istiophoridae の二科に属するカジキを指している。本頁中の「鱘」の後注を参照のこと。
・「江湖にも亦、時に、之れ、有り」気水域に入り込める海産種や、東南アジアには淡水エイが知られている。なお、最近の流行りの鑑賞用淡水産エイの多くは南米産で、ポタモトリゴン属 Potamotrygon が多い。
・「荷葉」はスイレン目ハス科ハス Nelumbo nucifera の葉のこと。
・「鮎」はナマズ目ナマズ科 Siluridae の魚類の総称。
・「大なる者、皮に、沙、有りて、鮫のごとし。以つて、刀鞘、飾るべし」は「鮫」の項の後注「白玉」を、必ず、参照されたい。これは実は「鮫」の注ではなく、このエイの注というべきものであるからである。画像もある。
・「赤鱝」アカエイ 本属は種数が多いが、とりあえずアカエイ Dasyatis akajei 挙げておく。
・「雀目」は一般に「夜盲症」の中古の古名で、ビタミンAの不足によるものとされた。但し、現在、夜盲症の中には、遺伝的な由来による網膜色素変性症(因みに、私がブログで浦沢直樹作「プルートゥ」の挿話「ノース2号の巻」に関わる評論「ノース2号論ノート」で盲目の音楽家ダンカンの病因として同定したものも、この病気である)である場合もあることを知っておく必要があろう。サメの肝臓には多量のビタミンAが含まれることが知られており、同グループのエイでも同様と思われ、効果はあるであろう。また、「多食はせ」ざるが「可なり」(食べ過ぎるのは良くない)というのは、まさにビタミンAの過剰摂取症(下痢等の食中毒様症状・倦怠感・皮膚剥離障害等、女性の場合は子供への催奇形性リスク有り)を警告している優れた部分である。
・「鷂鱝」トビエイ イトマキエイ属 Mobula 、ウシバナトビエイ属 Rhinoptera 、オニイトマキエイ属 Manta 、マダラトビエイ属 Aetobatus を挙げておけばよいであろう。最近、有明海の貝類の甚大な不漁は、ナルトビエイ Aetobatus flagellum の進出と、その捕食行動にあるとする番組や論文を見た。駆除も盛んだ。しかし、彼らが北進してきたのは、地球温暖化のせいだ。彼らの棲息域が広がったのは、彼らのせいでは、ない。況や、彼らが僕らに果敢に挑戦してきたのでも、さらさらないということを忘れずにいたい。
・「鳶・鷂」の「鳶」はタカ目タカ科トビ属トビ Milvus migrans 。「鷂」はタカ科ハイタカ属ハイタカ Accipiter nisus で、ハイタカ属オオタカ Accipiter gentilis と同属である。♂は背面が灰色で、腹面に栗褐色の横縞があるのに対して、♀は背面が灰褐色で、腹面の横縞は、オスよりも細かい。本邦の民俗社会では、古くは「ハイタカ」は、現在のハイタカの♀を指す呼称で、♂は「コノリ」と別称されていた。
・「窓引鱝」マドヒキエイは、私には、「窓引」なるものが如何なる形状のものであるか、分からない。ただ、本文の最後に「繩のごとく」とあるので、これを、最もスリムで、尾部が、縄状に細いエイ目サカタザメ亜目サカタザメ科サカタザメ属サカタザメ Rhinobatos schlelii 、又は、コモンサカタザメRhinobatos hynnicephalu に同定したくなる。ところが、既に良安は、本頁の「鱣」の項で「坂田鱣」(さかたぶか)なるものを挙げてしまっているのである。これをどう考えるべきか。「鱣」の「坂田鱣」を再考してみよう。
*
坂田鱣 大いさ二、三尺。頭、圓く匾〔( ひらたく)〕、團扇(うちは)に似、身、挟く長〔く〕、團扇の柄に似て、灰黑色なり。
*
体が円い、頭部が団扇に似ている、身から(尾にかけてととってよい)狭く長く団扇の柄に似ている特徴は、実はサカタザメよりも、よりエイ目ウチワザメ科ウチワザメ属ウチワザメ Platyrhina sinensis に近似する。サカタザメ類に似るが、体が丸いのが、この種の特徴であり、坂田鱣には「圓く」の記述があること、現在のウチワザメは、まさに「団扇鮫」と表記することから、「坂田鱣」の先の同定をウチワザメ Platyrhina sinensis に変更し、本種の方をサカタザメ Rhinobatos schlelii 、又は、コモンサカタザメ Rhinobatos hynnicephalu に同定することとする。
・「牛鱝」トビエイ目アカエイ科アカエイ属ウシエイ Dasyatis ushiei であろう。これはかなりの大型種であり、そこからの命名であろう。横幅が一~一・八メートルに達する。頭部上面の前額部分も、もっこりと、突き出しており、ウシの顔に似ていなくもない。]
***
まなかつを
鯧【音昌】
チヤン
鯧鯸 䱽魚
[やぶちゃん字注:「䱽」の(つくり)は正確には「倉」。】
昌鼠
【俗云末奈
加豆乎】
[やぶちゃん字注:以上四行は、前三行の下に入る。]
本綱鯧生南海四五月出之形似鯿腦上突起連背身圓
肉厚白如鱖肉只有一脊骨治之以葱薑缶之以粳米其
骨亦軟而可食【甘平】或云鯧游於水群魚隨之食其涎沫
有類於娼故名之腹中子有毒令人下痢
三才圖會云鯧縮項扁身似魴而扁鱗細色白
《改ページ》
■和漢三才圖會 江海無鱗魚 卷ノ五十一 ○十二
△按鯧形狀如上說攝泉播最多東北海無之大一尺
余白色帶青作魚軒最美也然有微青臭氣炙食亦佳
或作鮓作糟漬惟不宜煑食但雖有鱗細白而如無
*
まながつを
鯧【音、昌。】
チヤン
鯧鯸〔(しやうかう)〕 䱽魚
昌鼠
【俗に「末奈加豆乎」と云ふ。】
「本綱」に、『鯧は、南海に生ず。四、五月、之れ、出づ。形、鯿(かゞみうを)に似る。腦の上、突き起こり、背に連なり、身、圓〔(まろ)〕く、肉、厚く、白く、「鱖(あさじ)」の肉のごとし。只〔(ただ)〕一〔(いつ)〕の脊(せ)骨、有り。之れを治〔(ととのふ)〕るに、葱・薑〔=生姜〕を以てし、之れを缶るに、粳(うるち)米を以つてすれば、其の骨も亦、軟にして、食ふべし【甘、平。】。或は云ふ、「鯧、水に游〔ぶに〕、群魚、之れに隨ひて、其の涎沫(よだれ)を食せんと、娼に類すること、有り。故に、之れを名づく。腹中の子、毒、有り。人をして、下痢せしむ。』と。
「三才圖會」に云はく、『鯧は、縮(みぢか)き項(うなじ)、扁〔(ひら)〕たき身、魴(かゞみうを)に似て、扁たく、鱗、細く、色、白し。』と。
△按ずるに、鯧は、形狀、上の說のごとし。攝〔=摂津〕・泉〔=和泉〕・播〔=播磨〕、最も多し。東北海、之れ、無く、大いさ、一尺余、白色に青を帶ぶ。魚-軒(さしみ)に作りて、最も美なり。然れども、微かに青臭き氣〔(かざ)〕、有り。炙り食〔ひて〕亦、佳なり。或いは、鮓〔(すし)〕に作り、糟漬に作る。惟だ、煑て、食〔ふ〕を宜しからず〔とす〕。但し、鱗有りと雖も、細かに、白くして、無きがごとし。
[やぶちゃん注:イボダイ亜目マナガツオ科マナガツオ属マナガツオ Pampus argenteus 。東シナ海や中国広域にまで広げて考えるならば、コウライマナガツオ Pampus echinogaster 、シナマナガツオ Pampus chinensis も挙げておくべきか。現在の市場に現れるものは、以上の三種である。マナガツオの名称由来については、「本朝食鑑」に、京では、カツオが手に入らなかったことから、カツオと同漁期に、瀬戸内から入ってくる、この生鮮魚を膾となして、鰹の「生(なま)」に学び擬えたが故に、「学鰹(まなびがつを)」と言い、それが、「まながつお」となったという説(これは「まな」に「生」の意味がない以上、安易な恣意的な無理強いした文字反転である気がするし、そもそも「学びなぞらえる」という語句は私には妙に言い訳染みた感じでしっくりこない)、マナは「真名」で、この魚の身がよくしまっていることから、これが正真正銘の堅い魚=鰹=真魚鰹=まなかつお、となったとする説などがある。
・「鯿」(カガミウオ)はスズキ亜目アジ科イトヒキアジ属アジ科イトヒキアジ Alectis ciliaris の異名。後の「魴」も、和名ではカサゴ目ホウボウ科ホウボウ属ホウボウ Chelidonichthys spinosus を意味するが、カガミダイ(更にはマナガツオ自体をも)も指す。但し、これらは、共に中国の本草書中の用字である以上、良安のルビとは別な種を同定すべきであると考える。「鯿」は現在、中国では、コイ科の Rasborinus 属の一種を指すのではないかと思われ(和名は、恐らく、ない。読めない中国語サイトの学名一覧からの勝手な推測ではあるが)、「魴」を持つ魚としては、「団頭魴」があり、これは武昌魚、コイ科クセノキプリス亜科メガロブラマ属ダントウボウ Megarobrama amblycephala であるとする。但し、「団頭魴」=「魴」とは私には思われない。中国語に堪能な方の御助力を求めるものである。
・「鱖」(アサジ)と本邦で呼称するものは淡水魚であるコイ科クセノポリス亜科 Oxygastrinae ハス属オイカワ Zacco platypus である(通称では、同種の♂を「アサジ」、♀を「シラハエ」と称する)。体長十五センチメートル程で、甘露煮・唐揚・天麩羅・南蛮漬などで食用にされるが、肉は厚くなく、本記載には適合しない。これは「本草綱目」の叙述であるから、ここでも良安のルビに惑わされず、中国名での「鱖」を優先して考えねばならない。現在、本字で示されるのは、観賞用淡水魚であるケツギョ科ケツギョ属ケツギョ Siniperca chuatsi である。こちらについては、ぷりぷりとした白身の高級魚として中華料理で有名だ。取り敢えず、こちらに同定しておく。
・「缶る」「缶」は音「フウ・フ」(「カン」ではない)で、訓は「ほとぎ・もたい」で「口をすぼんだ素焼きの器」を指し、これは本来は、酒などを注ぎ入れる器であるが、そこから「酒で煮る」の意としたい。東洋文庫版の『あぶれば』という訳では、以下の意味が通じない。
・「娼に類すること有り」は、「娼婦に似たところがある」という意味だが、分かったような分からないような、変な由来説明である。この部分、私には何だか妙に読後感が悪い。
・「腹中の子、毒、有り」とあるが、マナガツオの卵巣に毒はない。ただ興味深いのは、同じマナガツオ科 Stromateidae に属する、エボダイに似た南アメリカ産のゴマシズ Stromateus brasiliensis や、ホシゴマシズ Stromateus stellatus の身から、近年、摂取量によっては、下痢を引き起こす可能性のある脂質成分ジアシルグリセリルエーテル(Diacyl glyceryl ether:DAGE)が検出されていることだ。この手のワックス中毒は、最近クロース・アップされてきた。でもね、その手のワックスを含む魚類の刺身は、ちょっと食べるには、安全で、旨いんだよなぁ……(と、口ごもっておく)。
・「魚軒」は正真正銘の「刺身」の意。「軒」という字には、大きく切った肉片という意味がある。
・「惟だ、煑て、食〔ふ〕を宜しからず〔とす〕」は、「但し、煮て食うには適していない。」という意味であるが、「食」の送り仮名は「ムレ」のような字で、訓読出来ない。意味からは「惟だ、煮て食はむには、宜しからず」であろうか。]
***
かゝみうを
まといを
魴【音房】
ハン
鯿
【俗云鏡魚
又云的魚】
【鯿魴共本草入有鱗魚
之類今改出于無鱗下】
[やぶちゃん字注:以上五行は、前四行の下に入る。]
本綱魴小頭縮項穹脊闊腹扁身細鱗其色青白腹内有
肪性宜活水其狀方其身扁故名之作鱠味最腴美作𦎟〔=羹〕
臛食【甘温】宜人功與鯽同疳痢人勿食
火燒鯿 頭尾俱似魴而脊骨更隆上有赤鬛連尾如蝙
蝠之翼黒質赤章色如烔𤋱〔=熏〕故名
△按魴鯧二物形狀相似而其所說亦難別惟三才圖會
所圖以能別矣蓋魴自項至尾有鬐而有一條𮈔〔=絲〕鬛宜
炙食色白於鯧
*
かゞみうを
まといを
魴【音、房。】
ハン
鯿〔(はん)〕
【俗に「鏡魚」と云ひ、又、「的魚」と云ふ。】
【鯿と魴、共に「本草」〔=「本草綱目」〕に「有鱗魚」の類に入る。今、改めて、「無鱗」の下に出だす。】
「本綱」に『魴は、小さき頭、縮みたる項〔(うなじ)〕、穹(たか)き脊、闊(ひろ)き腹、扁〔(ひら)〕たき身、細かなる鱗、其の色、青白く、腹の内に、肪〔(あぶら)〕有り。性、活水に宜〔(よろ)〕し。其の狀〔(かたち)〕、方〔(はう)〕にして、其の身、扁き故に、之れを名づく。鱠〔=膾(なます)〕に作り、味、最も腴美〔(ゆび)〕なり。𦎟臛〔(かうかく)〕に作〔(な)〕して食ふに【甘、温。】、人に宜〔(よろ)〕し。功、「鯽〔(ふな)=鮒〕」と同じ。疳痢の人、食すること勿れ。
火燒鯿〔(くわせうはん)〕 頭・尾、俱に、「魴」に似て、脊骨、更に隆(たか)し。上に、赤き鬛〔(ひれ)〕有りて、尾に連なり、蝙蝠(かはもり)の翼のごとし。黒質に赤章、色、烔-𤋱(ふす)ぶる〔が〕ごとし。故に名づく。』と。
△按ずるに、魴・鯧〔(まながつを)〕の二物、形狀、相似て、其の說く所、亦、別し難し。惟〔(ただ)〕、「三才圖會」に圖する所を以つて、能く別〔(わか)〕つ。蓋し、魴は、項より、尾に至りて、鬐〔(ひれ)〕、有りて、一條の𮈔〔(いとひれ)〕、有り。炙り食ひて、宜〔(よろ)〕し。色、鯧より、白し。
[やぶちゃん注:カガミウオはアジ科イトヒキアジ Alectis ciliaris の異名。但し、冒頭の異名で「鯿」を掲げてしまい、さらに、本文中でも、良安自身が、魴・鯧の区別について、「其の說く所、亦、別し難し。」(その「本草綱目」の説明が、また、よく分からない)と記すのは、「本草綱目」記載の種と、良安の同定する種とが、大きく齟齬しているからに他ならない。それについては、前項「鯧」(マナガツオ)の「鯿」の私の後注を参照されたい。
・「的魚」は、気になる。これは別種(しかし形状にイトヒキアジとの類似性が認められる)のマトウダイ目マトウダイ科のマトウダイ Zeus faber を指しているのかもしれない。ちなみにマトウダイの英名も Targetfish である。
・「魴」この「本草綱目」中の「魴」はイトヒアジではなく、淡水魚の一種であろう。その証拠に、棲息域についての記載がない。さらに海産にしては、「活水に宜し」(勢いよい流れている水の中で棲息することを好む)という表現も、やや不自然である。そこで、国会図書館の「本草綱目」の該当部分を見てみると、良安が引用部の頭をカットしていることが分かった。そこには「魴魚處處有之。漢沔尤多。」とある。これは「魴魚は處處に、之れ、有り。漢沔(かんべん)に、尤も多し。」で、「漢沔」とは沔水(べんすい)のことで、陜西省から湖北省を東南流する漢水の上流を言う。即ち、これが淡水魚であることをはっきりと示しているのである。恐らく良安は、それが、彼が記載しようとしている海産のイトヒキアジと適合しないために、わざと排除したものと思われるのである。これじゃあ、「其の說く所、亦、別し難し」に決まってるじゃあ、あ~りませんか、良安先生!?
・「腴美」の「腴」は、「下腹部の脂(あぶら)ののった肥えて軟らかな肉」のことを指すので、脂のっていて柔らかく美味しい、という意味であろう。
・「𦎟臛」は二字で「スープ」の意(この二つは「有菜曰羹、無菜曰臛」等と具の有無によって分けるとも言う)。
・「鯽」は、「鮫」の項にも前出しているが、漢方系の記載などを参考にし、本文で示したようにコイ亜科フナ属 Carassius に一応、同定しておく。漢方では、鮒は、下痢止めや、ビタミンAによる体力回復の効果が認められるとする。
・「疳痢」は、栄養不良による痩身と下痢症状が複合した状態を指す。
・「火燒鯿」は、「本草綱目」の個別記載である以上、やはり「鯿」の同族の淡水魚であろう。この特徴は、かなり明確である。中国産淡水魚の専門家の指摘を待つ。
・「蝙蝠(かはもり)」はコウモリ。脊椎動物亜門哺乳綱コウモリ目(=翼手目)Chiroptera。
・「黒質に赤章」は、「下地の色が黒で、それ赤い円形の紋がある」という意味である。
・「烔-熏(ふすぶる)ごとし」の「烔」は、「熱い」という意味、「熏」は「煙でいぶす」意。良安は合わせて、「ふすぶ」(「いぶす」の古語)と読んでいるように思われる(但し、「ふすぶる」というルビは「熏」の横にのみついている)。高温の煙でいぶしたように黒い、ということであろうか。もし、この字が(「火」+{「口」に中に左に接する「コ」})であれば、それは「烟」の俗字であり、文字通り、「熏」との畳語にはなる(東洋文庫版は、そのように解して「烟薫」と活字化している)。
・「一條の𮈔鬛、有り」は、良安の本種同定がイトヒキアジであることを示す特徴である。イトヒキアジの幼体は背鰭(尻鰭も)の鰭条が糸状に伸びるのである(但し、成長とともに短くなる)。]
***
うぼぜ 正字未詳
嫗背魚 【俗云宇保世】
【此魚僂畧似嫗背故俗曰
嫗背魚又訛爲宇保世乎】
△按宇保世形似鯧而小腦上突起連脊如瘤疣極細鱗
色白光如傅雲母九十月攝泉紀播出之二三寸至五
六寸炙食作鮓亦佳
*
うぼぜ 正字、未だ、詳らかならず。
嫗背魚 【俗に「宇保世」と云ふ。】
【此の魚、僂〔にして〕、畧〔(ほぼ)〕嫗が背に似る。故に俗に嫗背魚と曰ふ。又、訛りて宇保世と爲るか。】
△按ずるに、宇保世は、形、鯧〔(まながつを)〕に似て小さく、腦の上、突起〔し〕、脊に連なり、瘤疣(こぶ〔いぼ〕)のごとし。極めて細き鱗、色白く光り、雲母(きらゝ)を傅(つ)くるがごとし。九~十月、攝〔=摂津〕・泉〔=和泉〕・紀〔=紀伊〕・播〔=播磨〕に、之を出だす。二~三寸〔より〕、五~六寸に至る。炙り食ひ、鮓〔(すし)〕に作り、亦、佳し。
[やぶちゃん注:イボダイ亜目イボダイ科イボダイ属イボダイ Psenopsis anomala 。本種の同定はすっきりくる。まず、西日本にあって本種はボウセ(徳島)・ボゼ(三重)ウボセ(和歌山)と呼称され(他にウオゼ・オシズ・シズ)――澁澤敬三「日本魚名の研究」(一九五九年刊)によれば、これはその可愛らしさからの、とある港の遊女名由来とする。ああっ! 「先生」の「靜(しづ)」さんがこんなところに!――等)、関西圏では、これらの名称由来について、背が曲がっているように見えるので「媼背(うばぜ)」の転訛であるとする説を多くの解説が紹介する。また、関東圏では、本種を「エボダイ」と呼称するが、「えぼ」とは「疣(いぼ)」のことであり、その形状、及び、良安の形容と完全に一致はする。
・「僂」(音「ロウ」)は「せむし・佝僂(くる)」。脊椎後彎(背中全体の弓状歪曲)の病態をいう。明白な差別言辞である。
・「傅くる」の「傅」(音「フ」)は、「付く・くっつく」の意。]
***
にらぎ 正字未考
仁良岐魚
△按仁良岐狀似宇保世而小色青白其頸有一刺八九
《改ページ》
■和漢三才圖會 江海無鱗魚 卷ノ五十一 ○十三
月出之攝泉多有之大一二寸爲醢爲糟漬俱香味甘
美
*
にらぎ 正字は未考
仁良岐魚
△按ずるに、仁良岐は、狀〔(かたち)〕、「宇保世〔(うぼぜ)〕」に似て小さく、色、青白く、其の頸、一刺〔(ひとはり)〕、有り。八、九月、之れ、出づ。攝〔=摂津〕・泉〔=和泉〕、多く、之れ、有り。大いさ、一、二寸。醢〔(ししびしほ):塩辛。〕と爲し、糟漬と爲し〔て〕、俱に香〔(かぐは)〕しく、味、甘美なり。
[やぶちゃん注:ヒイラギ科Leiognathidaeのヒイラギの仲間を指すと考えてよい。ヒイラギ属 Leiognathus の分類は混乱しており、特定種を指すことが出來ない。この「にらぎ」という呼称に、最も近似した地方名は高知の名物料理でもある「ニロギ」である(この「ニロギ料理」には、小型種であるオキヒイラギ Leiognathus rivulatus を用いることが多く、一般的なヒイラギ Leiognathus nuchalis は、現地では「ウチヒイラギ」と呼称されるとも言う)。因みに、この名の由来は、モクセイ属ヒイラギ Osmanthus heterophyllus の葉のように、脊鰭と尻鰭に棘があることに由来すると考えてよいようだが、本来、植物のヒイラギが、古語の「ひひらく」(ひりひり痛む)由来のものであるとすれば、この「にらぎ」というのは、このヒイラギの仲間に与えられた、何か別系統の呼称の転訛とも考えられる。識者の指摘を俟つ。
若い頃、父と、よく、キス釣に行くと、これが外道でかかったものだ(私が中高の六年間を過した富山県高岡市伏木では、これを「ギンダイ」と呼称していた)。生魚は、表皮に持つ独特の粘液(しかし、この粘液が鮮度を保つとも言われる)、しっかり痛い棘、下方に突出する奇体な口吻……父はよく、これを吸い物や味噌汁にしていたが、私は、何故だか、妙に『女』を感じさせるこの魚に、ある種の意味不明な生理的嫌悪感さえ抱いていた……しかし、大人になって酒の肴として、千葉産の干物の「ギラ」なるものの旨さを知り、それがヒイラギの小物の素揚げであることを見て、恩讐は鮮やかに彼方へと去ったのであった。ギラは、旨い。]
***
かれゑひ
かれい
鰈【音蝶】
魪【音介】比目魚
鰜【音兼】鞋底魚
魼【音去】奴屩魚
婢簁魚
【和名加良衣比
又云加禮比】
[やぶちゃん字注:以上六行は、前三行に入る。]
本綱鰈狀如牛脾及女人鞋底細鱗紫白色兩片相合乃
得行其合處半邊平而無鱗口近腹下各一目相並而行
故名比目魚劉淵林以爲王餘魚蓋不然【王餘魚乃今云白魚】
肉【甘平】 益氣力
△按倭名抄亦用王餘魚【訓加良衣比】謬也【王餘魚乃膾殘也】鰈形似
魴而扁頭小口尖黑紫有細鱗裏白滑其兩眼相去甚
近向上而相比故名比目魚乎然本草引爾雅云鰈一
目而不比不行故兩片相合乃得行之說非也不知別
《改ページ》
一物有乎否大者二三尺其種類多可炙可※其肉白
[やぶちゃん字注:※=「月」+「雋」。]
柔甘美味厚脾虛痞滿者不宜食
蒸鰈 出於若狹及越前大尺許者以鹽水蒸令半熟取
出陰乾數日而炙食如有些鯘氣而亦味美也
星鰈【一名甘鰈】 裏白皮有黒㸃者其大者尺余小者五六寸
石鰈 表黒皮鰭兩邊有黒片石子者味勝大者尺許
瓶子鰈 形團大而背鱗中有丸文秋冬出於播州明石
大者尺半其味美爲最上
白水鰈【一名霜月鰈又云藻鰈】 仲冬多出大者不過六七寸形狹
小而肉薄軟子亦雖滿腹味不佳
目板鰈 表裏無鱗畧狹長
木葉鰈 大一寸許作脯炙食香美出於泉州異物志所
謂箬葉魚者乃是矣
*
かれゑひ
かれい
鰈【音、蝶。】
魪【音、介。】比目魚〔(ひもくぎよ)〕
鰜【音、兼。】鞋底魚〔(あいていぎよ)〕
魼【音、去。】奴屩魚〔(どきやくぎよ)〕
婢簁魚〔(ひしぎよ)〕
【和名、「加良衣比」、又、「加禮比」と云ふ。】
「本綱」に、『鰈は、狀〔(かたち)〕、牛の脾〔:脾臓。〕、及び、女人の鞋〔(けい)=靴〕底のごとし。細鱗、紫白色。兩片、相合〔(あひあ)ひ〕て、乃〔(すなは)〕ち、行くことを得。其の合ふ處、半邊〔(はんぺん)は〕、平らにして、鱗、無し。口、腹の下に近く、各々〔(おのおの)〕、一目、相〔(あひ)〕並〔(び)〕て行く。故に「比目魚」と名づく。劉淵林〔(りうゑんりん)〕、以つて、「王餘魚」と爲す。蓋し、然らず。【王餘魚〔は〕、乃ち、今、云ふ、「白魚」なり。】
肉【甘、平。】 氣力を益す。』と。
△按ずるに、「倭名抄」にも亦、「王餘魚」を用ふ【「加良衣比」と訓ず。】〔は〕、謬〔(あやま)〕りなり【「王餘魚」は、乃ち、「膾殘(しろうを)」なり。】。鰈の形、「魴(かゞみうを)」に似て、扁たく、頭〔(かしら)〕、小さく、口、尖り、黑紫、細かなる鱗、有り。裏、白く、滑らか。其の兩眼、相去ること、甚だ近く、上に向きて、相比(なら)ぶ。故に「比目魚」と名づくか。然るに、「本草」〔=「本草綱目」〕に「爾雅〔(じが)〕」を引きて云はく、『鰈は、一目を比(なら)べずして、行かず。故に、兩片、相合ひて、乃ち、行くことを得の說、非なり。知らず、別に、一物、有るか否か。』と。大なる者、二。三尺、其の種類。多し。炙るべし、※(い)〔=熬〕るべし。其の肉、白く、柔かく、甘く、美なり。味、厚し。脾虛痞滿〔(ひきよひまん)〕の者、食ふに宜しからず。
[やぶちゃん字注:※=「月」+「雋」。]
蒸(むし)鰈 若狹、及び、越前より、出〔づ〕る。大いさ、尺許〔(ばかり)〕の者、鹽水を以つて、蒸して、半熟〔せ〕しめ、取り出〔だ〕し、陰乾〔(かげぼし)〕すること、數日〔(すじつ)〕にして、炙り食〔ふに〕、些〔(すこ)〕し鯘(さか)りたる氣(かざ)有るごとくして、而〔(し)〕も亦、味、美なり。
星(ほし)鰈【一名、「甘鰈」。】 裏の白皮に、黒㸃、有る者。其の大なる者、尺余。小さき者、五、六寸。
石鰈(いしかれ〔ひ〕) 表の黒皮・鰭の兩邊に、黑片の石子有る者、味、勝〔(すぐ)〕れり。大なる者、尺ばかり。
瓶子(へいし)鰈 形、團〔(まろ)〕く、大にして、背〔の〕鱗の中、丸文〔(まるきもん)〕、有り。秋冬、播州明石より、出づ。大なる者、尺半。其の味、美〔にして〕、最上と爲す。
白水(しろみづ)鰈【一名、「霜月鰈」。又、「藻鰈」と云ふ。】 仲冬、多く出づ。大なる者、六、七寸に過ぎず。形、狹小〔(さしやう)に〕して、肉、薄く、軟〔かし〕。子、亦、腹に滿つと雖も、味、佳ならず。
目板(めいた)鰈 表裏、鱗、無く、畧〔(ほぼ)〕、狹長〔(さなが)なり〕。
木葉(このは)鰈 大いさ、一寸許。・脯〔(ほじし):干物。〕に作り、炙り食ふ。香、美なり。泉州より、出づ。「異物志」に、所謂、「箬葉魚〔(じやくえふぎよ)〕」と云ふは、乃ち、是か。[やぶちゃん注:「云」は送り仮名にある。]
[やぶちゃん注:カレイ目カレイ科 Pleuronectidae 、及び、カレイ亜目ヒラメ科 Paralichthyidae 。記載内容から、良安はカレイとヒラメを区別していない。
・「屩」は「靴の中敷」を意味する。形状からであろう。
・「簁」は「竹製の籠」、若しくは、「篩(ふるい)」を言う語。カレイの表皮の模様からであろう。
・『劉淵林、以つて王餘魚と爲す」は、「文選」に所収する左思の「呉都賦」の、
*
「雙則比目、片則王餘。」
○書き下し文
雙は、則ち、比目。片は、則ち、王餘(わうよ)。
○やぶちゃん訳
両の目を並び持つ魚は「比目(ひもく)」と言い、片目しか持たない魚は「王餘」と言う。
*
に北宋の徽宗の時、中書侍郎を務めた劉淵林がそれに注した、
*
「比目魚、東海所出。王餘魚、其身半也。俗云、越王鱠魚未盡、因以殘半棄水中爲魚、遂無其一面、故曰王餘也。」
○書き下し文
比目魚は、東海に出づる所のものなり。王餘魚は、其の身、半なり。俗に云ふ、『越王、鱠(なます)せる魚(うを)を、未だ盡くさざるに、因りて以うて、殘れる半を、水中に棄つるに、魚と爲る。遂に、其の一面、無し。故に「王餘」と曰ふなり。』と。
○やぶちゃん訳
「比目魚」は東海に産するものである。「王餘魚」は、その魚体が、丁度、半分しかない。俗に伝えるところでは、『越王が、膾(なます)にした魚を食べ尽くさないうちに(呉王が奇襲をかけてきたため)、その残りの半身(はんみ)を水中に棄てたところ、それが生きたまま、魚となった。しかし、それは、丁度、その魚体の半分がなかった。故に、「王の余した魚」と名づけたのである。』と。
*
を指す。
・「白魚」の同定だが、白魚は現代中国では淡水魚の Anabarilius 属に与えられているようであり、日本のシラウオでもシロウオでもないようである。但し、キュウリウオ目Osmeriformesシラウオ科 Salangidaeに属するシラウオは、東アジアの淡水域に広く分布しており、本件の越王の故事にも、その半透明で骨格や内臓が透けて見える点などを考慮すると、ピッタリきそうな気もしなくはない(恰も、鱗を剝ぎ取って、半身にしたかのような錯覚は心情的には判る)。孰れにせよ、「本草綱目」の「白魚」について、私には、これ以上の同定は不可能である。
・「膾殘」――そこで満を持して、これを、考える。良安は、これに「しろうを」のルビを振っているが、果して、これは現在の「シロウオ」であるか否かである。まず、彼がここでこう言う場合、それは本邦産の「白魚」ということになる。更に、この時代に「シロウオ」と「シラウオ」という呼称や種が、厳密に区別されていたとは私には思われない(少なくとも「カレイ」も「ヒラメ」も一緒くたにする良安は、極めて近似した形状を持つこの二種を生態学的に区別出来ていたと信ずることは極めて困難である)。結論から言えば、これは、
○キュウリウオ目 Osmeriformes シラウオ科シラウオ属シラウオ Salangichthys microdon
であって、
☓ハゼ亜目 Gobioidei ハゼ科 Gobiidae ゴビオネルス亜科 Gobionellinae シロウオ属シロウオ Leucopsarion petersii
ではないと私は考えている。本件については、後出する「鱠殘魚」(シラウオ)の私の後注を参照されたい。
・「爾雅」は、類語や字解を載せる最古の字書。作者成立年代ともに、未詳である。
・「知らず、別に、一物、有るか否かと」は、言わば、「比翼の鳥」のように――二匹が合体していないと、どちらも全く行動ができない生物――というものが、この世に別に存在するかどうかは分からない、と言う意味。今まで、鮮やかに「謬」と言い放ってきた良安先生らしくないよ! いや、流石にこんな生物は、いないだろ?! これぞという生物種がいたら是非とも御教授戴きたい。言っとくけど、チョウチンアンコウの雌雄やチューブ・ワームの共生なんかに広げるのは――なし――だからね。《★追記(二〇〇七年十月七日):正直、何だか「絶対いない」と言い切ってしまってから、ずっと胸の辺りに、何やら、引っかかっていた。生物界に人間的常識は必ずしも通用しないとどこかで思っていたことは、事実である。下等動物の中には、もしかすると、極めてそれに近い生物が存在しはしまいか? という疑義が膨らんでいた。一昨日の通勤で、黄色くなった筒井康隆の「私説博物誌」(昭和五五(一九八〇)年新潮文庫刊)を再読していたら、いた! 「比翼鳥」型生物が、いたのだ! その名もフタゴムシ、扁形動物門単生綱多後吸盤目(筒井は多後口目と記載するが、古称であろう)に属する種で、コイ・フナに寄生するフタゴムシ Eudiplozoon nipponicum 、及び、ウグイ属に寄生する同種の仲間 Eudiplozoon sp. の二種が本邦での報告例である。彼らは雌雄同体で、当該魚類の鰓に寄生し、吸血する。本種による寄生魚類の貧血症が水産関係の論文に発表されているのも確認した。以下、筒井の記述を引用する。
《引用開始》
『幼虫は、卵からかえった時は、〇・二五ミリくらいの大きさで、水の中を泳いで魚の鰓にたどりつく。もし、一〇時間以内にたどりつかないと、そのまま死んでしまうそうだ。鰓に寄生した幼虫は成長して、一ミリぐらいの大きさになる。これはデボルバと呼ばれ、以前はフタゴムシとは別の種類の寄生虫であろうと思われていたらしい。
この虫には雌雄の区別はなく、同じからだをしている。生殖器が成熟すると、二匹の虫が互いにからだをねじってカットのような[やぶちゃん注:図(カット)を指すが、著作権上の問題から省略する。その代わり、サイト「水産食品の寄生虫検索データベース」のこちらを参照されたい。写真有り。]状態になり、くっつきあう。それぞれが背中に小さな突起と、腹に吸盤を持っているので、吸盤で相手の突起をしっかりとつかんでしまうのだ。その恰好のまま一生、といってもたったの一ヶ月あまりであるが、魚の鰓に吸着して生き続けるのである。なぜそんないやらしい恰好のままでと不思議に思い、二、三の本を読んでみたが理由は書かれていない。相手にめぐりあう機会が少ないからではないかと思って父に訊(たず)ねてみたが、そうではあるまいということである。ど助平だからというのでもないらしい。つまりセックスが好きで好きでしかたがないからやり続けているのではないのだ。そういうみっともない状態でいることが生きのびる上に欠かせないからである。というのはこのフタゴムシ、二匹をはなすと死んでしまうのである。いわば命がけで相手にしがみついているというわけだ。』
*
一生交尾した状態で過すので、これを「終生交尾」(!)というのだそうである。強烈な生物学用語ではないか! 幼生期の一時期を除いて、ペアリングし、離れれば、ともに死ぬというのであれば、これは間違いなく――『比翼の鳥のように、そのように二匹が合体していないとどちらも全く行動(吸着寄生自体が一つの生態行動である)が出来ない生物』――に等しいと言ってよい。私の早とちりを素直に認め、ここに追記するものである。★追記の追伸(同):因みに、この引用部の後は、例の筒井氏独特の人間の男女が常に交尾しているというSF・ショート・ショート風のおとぼけエッセイとなるのであるが、どうして、以上の生物学的記載は頗る真面目なのである。何てったって、彼の父君は本書の「あとがき」で「あの」日高敏隆(!)が逢うやビビって学者としての自信をなくしたと記すほどの、元大阪天王寺動物園園長でもあった京大動物学教室出身の動物学者筒井嘉隆氏なのである。膝下敬白
・「脾虛痞滿」の「脾虛」は、消化器系、及び、循環器系全般の機能低下によって引き起こされる諸症状を言い、「痞滿」は胸がつかえて塞がったような苦しい症状、若しくは、脇腹が、しくしく痛んだり、ぎゅっと縛られるような痛みの症状を言う。
・「蒸鰈」(ムシガレイ)は、その製法から叙述しているが(短時間で蒸して陰干しする「蒸鰈」と、内臓を除去して天日干しする「干鰈」は、種ではなく、カレイの保存加工処理の二法であるが、ここでは、種名称との混同が見られる)、取り敢えず、現在の呼称では、カレイ科ムシガレイ Eopsetta grigorjewi を指す。これは本来、「虫鰈」で、目のある側に虫食いのような六つの円紋を持つことからの命名である。但し、若狭を産と記述する点や、干物として美味とするところからは、別種のヤナギムシガレイ Tanakius kitaharai も有力な同定候補(寧ろ、こちらを第一とすべきかとも思われる)であろう。
・「鯘りたる氣」の「鯘」は通常「あざる」と訓じ、「魚肉等が傷む・腐敗する」という意味で、「さかル」の読みは不審である。新鮮さから「離(さか)る」の意か。どちらにせよ、やや饐(す)えたような生臭い匂いがある、ということではあろう。
・「星鰈」ホシガレイ(アマガレイ)は「裏の白皮」という謂いが気になるが、マツカワ属ホシガレイ Verasper variegatus と同定してよいだろう。本種は背鰭・尻鰭に黒い円紋を持つ(同属のマツカワ Verasper moseri では、この紋が、帯状に、細長く流れてしまう。但し、現在でもマツカワとホシガレイは区別されずに流通するケースがある)。
・「石鰈」はイシガレイ Kareius bicoloratus 。「石子」(いしこ)は、小さな石状の突起を言う。表側(眼のある上側)の側線附近に、硬い石状の骨板が二、三列、並んでいる。それが名称の由来でもある。
・「瓶子鰈」(ヘイシガレイ)というこの呼称は、現在は廃れているようである(しかし、私は、確かに、どこかで聞いたことがことがあるのだが)。「瓶子」は、壷で、口縁部が細くすぼまった比較的小型のもので、主に酒器として用いられた。神社のお神酒を入れる白い壺をイメージされるとよい。さて、本種の同定のヒントは「播州明石」であろう。現在の明石で「最上」のカレイとされるものを最有力候補と考えてよい。漁協や釣り人のサイトを縦覧すると、これは恐らく、大分県の「城下鰈」などで知られる高級種マコガレイ Limanda yokohamae であろうことが、見えてくる(見分けの難しい同属のマガレイ Limanda herzensteini も加えておこう)。
・「白水鰈」シロミズガレイ(シモツキガレイ・モガレイ)で、これらの名称の内、「霜月鰈」は、「東京湾に冬季に入ってくるカレイ」を言う冬の季語として、また、浜名湖で、十一月に湾内に入ってくる前記の「マコガレイ」や「イシガレイ」の異名呼称として、「モガレイ」は「マコガレイ」の別称として立派に生きている。何となく、「城下鰈」も「白水鰈」に音が類似する。そもそも、この叙述にある腹に満ちた子が、魚卵=真子で「マコガレイ」の由来である。これは全くの推測であるが、旧暦の霜月=仲冬(現在の十二月下旬)頃は抱卵期の後期に当たって、身は美味くないのではなかろうか。因みに、一月以降、マコガレイは釣果が無くなり、総じて、春のカレイは、小振りとなる。以上から、本種は前項同様、マコガレイ、及び、マガレイに同定しておく。
・「目板鰈」メイタガレイは、メイタガレイPleuronichthys cornutus 、及び、ナガレメイタガレイ Pleuronichthys sp. )。ちなみに「メイタ」の由来は、接近して突出する眼と眼の間の前後に、棘状の突起があり、そこから「目痛」と呼ぶようになったとのことである。
・「木葉鰈」キノハガレイは、ガンゾウビラメ Pseudorhombus cinnamoneus、及び、タマガンゾウビラメ Pseudorhombus pentophthalmus 。関西の流通系で「木葉鰈(コノハガレイ)」がガンゾウビラメの干物の名称として生きている(私には後者のタマガンゾウビラメを干した「デベラ」(四国や広島県での地方異名)の方が親しい。どこで訊いたか忘れたのだが)。
・「異物志」は「嶺南異物志」。東洋文庫版後注によれば、孟琯(もうかん)撰になる嶺南地方の珍奇な生物について記述したもの、とある。唐代の作のようである。台湾のサイト「中國飲酒詩」の「随園食單補證」の「比目魚」の頁に『《異物志》:「一名箬葉魚,俗呼鞋底魚。」』とある。
・「箬葉魚」の「箬」の字は「竹の皮や熊笹」を意味する。]
***
《改ページ》
■和漢三才圖會 江海無鱗魚 卷ノ五十一 ○十四
うしのした
牛舌魚
△按牛舌魚形畧類鰈而薄狹長色亦淡赤黒細鱗無尾
大者一尺許眼有背口如巴紋肉與鰈同味稍淡
馬舌魚 似牛舌而腹白而表兩邊黒色味亦相似二種
共肉薄爲下品乃鰈之屬也
*
うしのした
牛舌魚
△按ずるに、「牛の舌魚」は、形、畧〔(ほぼ)〕、鰈〔(かれひ)〕に類して、薄(うす)く、狹〔(せば)〕く、長く、色も亦、淡き赤黒にして、細〔き〕鱗、尾、無く、大なる者、一尺許〔(ばかり)〕。眼〔(まなこ)〕、背に有り。口、巴紋〔(ともゑもん)〕のごとく、肉、鰈と同じ。味、稍〔(やや)〕淡し。
馬の舌魚 「牛の舌」に似て、腹、白にして、表の兩邊、黒色。味も亦、相〔(あひ)〕似たり。二種共、肉、薄くして、下品たり。乃〔(すなは)ち〕、鰈の屬なり。
[やぶちゃん注:所謂シタビラメと呼ばれるカレイ目ウシノシタ科 Cynoglossidae の魚類の総称。本邦産は十八種を数え、それぞれが似ているために分類が難しい。本記載の種としては、その体色から、
イヌノシタ属アカシタビラメ Cynoglossus joyneri
或いは、
イヌノシタ Cynoglossus robustus
コウライアカシタビラメ
Cynoglossus abbreviatus
を比定候補としておく、因みに、市場で「アカシタビラメ」として売られるものの多くは後者の「イヌノシタ」であるとされる。「イヌノシタ」じゃ、売れないもんな。また、アカシタビラメとの区別がつきにくく、且つ漁獲量も多い、
タイワンシタビラメ属クロウシノシタ Paraplagusia japonica
加えて、鰓の部分が有意に黒い、
オオシタビラメ属オオシタビラメ Arelia bilineata
等をも挙げておく。
・「馬舌魚」はウシノシタ科の別称であるが、本記載では、体色の黒が強調されているので、背鰭・尻鰭が黒い点からは、上記の、
タイワンシタビラメ属クロウシノシタ Paraplagusia japonica
が挙げられ、次いで、やはり上記の、
オオシタビラメ属オオシタビラメ Arelia bilineata
も候補としてよいと思う。「ウマノシタ」という呼称で、「ツルマキ」、即ち、
ウシノシタ亜目ササウシノシタ科シマウシノシタ属シマウシノシタ Zebrias zebrinus
を指すという叙述をあちこちで見かけるが、もし、シマウシノシタであれば、良安は、その縞に、必ずm言及するはずであり、私は、とらない。ちなみに、この連中は、動きが鈍いのか、中学時代、この私が(!)富山の雨晴海岸の浅瀬の岩場で十八センチメートル大のセトウシノシタ Pseudaesopia japonica を手製のヤスで捕獲したことがある。ちなみに「鰒」(フグ)の注に記したクサフグに食われたのも、この時のことである。]
***
あぢ
鰺【音騷】
ツア゜ウ
鱢【同】
【和名阿遲】
和名抄載崔禹錫食經云鰺似鯼而尾白刺相次者也
《改ページ》
△按鰺無鱗魚背青腹微白小者二三寸大者尺餘形似
鯖而背後兩邊相對自鰓下至尾末硬鰭如白刺如鱗
其肉中黒血肉綿綿成條性喜成群游好海糠食自春
末至秋末多采之作鮓煑炙膾共味甘美其品類甚多
棘髙鰺 大三四寸皮厚刺硬作𩸆最爲下品
室鰺 多出於播州室津故名之形似鰺而畧圓有白刺
眼大冬月作𩸆東海亦多出味脆不佳爲下品
目髙鰺 喙長兩眼之間廣又目大而口小者名目太鰺
島鰺 似鰺而畧扁有横文尾耑有刺鬛三四月出
滅托鰺 似鰺而稍扁尾前帶黃無刺鰭
*
あぢ
鰺【音、騒。】
ツア゜ウ
鱢【同じ。】
【和名、「阿遲」。】
「和名抄」に崔禹錫〔(さいうしやく)〕が「食經〔(しよくけい)〕」を載せて云はく、『鰺は、「鯼(ぐち)」に似て、尾に、白き刺〔(はり)〕、相《あひ》次ぐ者なり。』と。
△按ずるに、鰺は、無鱗魚〔なり〕。背、青く、腹、微〔(かす)かに〕白し。小さき者、二、三寸、大なる者、尺餘。形、鯖に似て、背の後、兩邊に相〔(あひ)〕對して、鰓〔の〕下より、尾末に至るまで、硬き鰭、白き刺のごとくの〔もの〕、鱗のごとし。其の肉〔の〕中に、黑き血肉、あり。綿綿として、條を成す。性、喜んで群を成し、游(ゆ)く。海-糠(あみ)を、好みて、食ふ。春の末より、秋の末に至るまで、多く、之れを采る。鮓〔(すし)〕に作り、煑・炙・膾ともに、味、甘美なり。其の品類、甚だ、多し。
棘髙(いらたか)鰺 大いさ、三、四寸、皮、厚く、刺、硬し。𩸆(しほもの:塩漬。〕に作〔(な)し)すも〕、最も下品なり。
室(むろ)鰺 多く、播州室津〔(むろつ)〕に出づ。故に之れを名づく。形、鰺に似て、畧〔(ほぼ)〕、圓〔(まろ)〕く、白〔き〕刺、有り。眼〔(まなこ)〕、大なり。冬月、𩸆(しほもの)と作〔(な)〕す。東海、亦、多く出づ。味、脆〔(もろ)〕く、佳ならず。下品なり。
目髙鰺 喙〔(くちばし)〕長く、兩眼の間、廣し。又、目、大にして、口、小さき者、「目太鰺〔(めぶとあじ)〕」と名づく。
島鰺 鰺に似て、畧、扁たく、橫文〔(わうもん)〕、有り。尾の耑〔=端〕に刺鬛〔(とげひれ)〕有り。三、四月に出づ。
滅托(めつたく)鰺 鰺に似て、稍〔(やや)〕扁たく、尾の前、黃を帶ぶ。刺鰭、無し。
[やぶちゃん注:スズキ亞目アジ科 Carangidae の魚類の総称。本邦には五十種以上が棲息する。
・『崔禹錫が「食經」』の「食經」は「崔禹錫食經」で唐の崔禹錫撰になる食物本草書。前掲の「倭名類聚鈔」に多く引用されるが、現在は散佚。後代の引用から、時節の食の禁忌・食い合わせ・飲用水の選び方等を記した総論部と、一品ごとに味覚・毒の有無・主治や効能を記した各論部から構成されていたと推測されている。
・「鱢」は、本来は「なまぐさい」の意味であるが、国字としては「あじ」と読む。
・「鯼」は、既出のスズキ目ニベ科ニベ属ニベ Nibea mitsukurii 、又は、同科の「イシモチ」=シログチ属シログチ Argyrosomus argentatus を指す。底本で良安は「クチ」とルビを振っているが、これはイシモチの俗名(または方言名)である「グチ」であろう。
・「背の後、兩邊に相對して、鰓下より、尾末に至るまで、硬き鰭、白き刺のごとくのもの、鱗のごとし。」は、所謂、「ゼイゴ」部位を指している。ゼイゴは、体側中央から尾柄に並ぶギザギザの刺条の硬い鱗を指し(学術的には「稜鱗」と呼称する)、これはアジ類の持つ大きな特徴となっている。従って、良安が、これを最初に細密に記述しているのは、誠に正しい。大槻文彦「言海」の「あぢ」の項には「ぜんご」とあり、「竹筴」の字を当て、最後には鰺の別名として「竹筴魚」を挙げている。ちなみに「竹筴(ちくさく)」とは占いに用いる筮竹のことである。
・「海-糠」は、エビ亜綱エビ下網フクロエビ上目アミ目 Mysidae に属する小型のエビに似た甲殻類の総称。エビ類とは異なると認識されている。その差異は、アミ類が胸脚に、「はさみ」を持たない、尾節後脚の付け根に身体の傾きを認知する平衡胞を持つ、♀は、胸部に保育嚢を持つ等によってエビ類とは明確に区別されている。
・「棘髙鰺」イラタカアジ 私の御用達の「真名真魚辞典」によれば、明和六(一七六九)年跋の松岡玄達(恕庵)著の「食療正要」に『行者壓日(ギョウジャアジ)有り、一名、衣棘達葛壓日(イラタカアジ)、尼崎に出つ。身極めて扁大、硬鱗、頭に至る。皮青色、腹下銀光、尾箭鏃(やじり)に似たり。』とある、とする。「イラタカ」は「いらたか念珠」のことであろう。「最多角」・「伊良太加」・「刺高」とも書く。角(かど)のある百八の珠を用いた数珠(じゅず)で、修験者(行者)が使用する。通常は、数珠を揉む時には、音を立ててはならないとされているが、能でお馴染みの如く、修験道では、「悪魔祓い」の意味で、読経や祈禱の際に、この数珠を両手で激しく上下に揉んで、音を立てる。「いらたか」とは,「角が多い」の意だという説もあるが、一般には、揉み摺る音の、高く聞こえることに由来するとされ、梵語の「阿唎吒迦」(ありたか)の音を転じて名附けたと説く。しかし、ここまでだ。「ギョウジャアジ」も「イラタカアジ」も現在は用いられていない俗名のようである。「食療正要」の『身、極めて扁大』以下の叙述から、Web上の数多の写真を見つつ、取り敢えず、カイワリ属カイワリ Kaiwarinus equula 、イトヒラアジ属イトヒラアジ Carangichthys dinema 、ヨロイアジ属ヨロイアジ Carangoides armatus や、同属のリュウキュウヨロイアジ Carangoides hedlandensis 等を自信なげに掲げるのみである(ヨロイアジ属は、その頭部の硬い形状に惹かれるが、南日本という分布域からいってやや無理があるかとは思う)。
・「室鰺」ムロアジ ムロアジ属ムロアジ Decapterus muroadsi 。ムロアジは「群れアジ」の転訛とも言う(但し、「あぢ」そのものが、「小さなものが沢山群れる」という意味を持っているとも言う)。なお、森浩一氏は、播磨灘がアジの産地ではなく、現在の兵庫県淡路市室津(グーグル・マップ・データ)で、アジが特産であった記載が、江戸期の諸書にも見えないことから、この良安が示すような命名由来には疑問を呈しておられる(神奈川水総研「アジ」参照)。
・「目髙鰺」「メダカアジ」は、先に後の「目太鰺」を同定してみて、さて、「兩眼の間、廣し」というこちらの叙述にぴったりするものはやっぱり、マアジ属マアジ Trachurus japonicus かなと思った。そもそも、この列挙の中に、良安が正真正銘の凛々しいマアジを挙げていないというのは不自然ではなかろうか。搦め手からの苦し紛れの同定ではあるが。
・「目太鰺」「メブトアジ」は、目が大きく目立つところが名の由来とするメアジ属メアジ Selar crumenophthalmus であろう。
・「島鰺」「シマアジ」はシマアジ属シマアジ Pseudocaranx dentex 。本種の和名の「島」は伊豆七島を指す。今や、アジ類では高級種となってしまった。
・「滅托鰺」「メッタクアジ」は、マアジの中でも、沖で回遊する通称「クロアジ」に対する、強い内湾性を示す黄色がかった個体群である「キアジ」を指しているのではなかろうか(但し、「刺鰭なし」が合わないが)。
・食に就いて一言。何より「なめろう」だ。何匹でも食べられる。刺身にすればいいのにと言われる程の(しかし刺身は、はっきり言って一定量を食うと何でも飽きるものである)生きのいいアジを「なめろう」で食うのぐらい、贅沢な味わいは、ない。]
***
《参考1》→
《参考2》→
[やぶちゃん図注:本図はどう見ても、マンボウではなく、エイ(美事な大型個体のアカエイ Dasyatis sp. の仲間か)である。既に挙がった「海鷂魚」の項の絵が《参考1》である。これは一般的なエイのフォルムで想定するアカエイでもヒラタエイでもなく、エイ目ウチワザメ科ウチワザメ属ウチワザメ Platyrhina sinensis ではないかという考察は「海鷂魚」の注でも書いたが、控えめなこれより、いっそ「海鷂魚」には、この「楂魚」の図を使え! と言いたくなるぐらいだ。ところが、よく見ると、この「楂魚」の図、尾部を除くと、マンボウの本体の形に似ていないだろうか? 試みに、外形部を残して、周囲の鰭状部分と尾部を消去し、外側に背鰭と尻鰭を書き加え、両者の変形した尾部(これは尾鰭ではないとされる)をやや太い線で結び、目と口、胸鰭、体側のへこみを示す小さなギザギザを入れてみた《参考2》。これって、チョーへたっぴいだけど、確かにマンボウになるじゃない? 良安先生、隠し絵とは、おちゃめなんだから!(生まれて初めて画像編集機能を用いたので稚拙なのは許してね❤)]
うきゝ
まんほう
楂魚
滿方魚【正字未詳】
【俗云宇岐木】
[やぶちゃん字注:以上二行は前三行下に入る。]
《改ページ》
■和漢三才圖會 江海無鱗魚 卷ノ五十一 ○十四
△按楂魚奥州常州海上有之狀類鱝而方故名滿方魚
大者方一二丈厚一二尺周緣稍薄灰白色肉白骨硬
味不佳性魯鈍不知死浮游人以長把留則留如楂故
名割背取白腸長丈余【名百尋】作䱒或糟漬或曝乾食之
*
うきゝ
まんぼう
楂魚
滿方魚【正字、未だ、詳かならず。】
【俗に「宇岐木」と云ふ。】
△按ずるに、楂魚は、奥州・常州〔=常陸〕の海上に、之れ、有り。狀〔(かたち)〕、鱝〔(えい)〕に類して、方〔(はう)〕にして、故に「滿方魚」と名づく。大なる者は、方一、二丈、厚さ一、二尺。周緣、稍〔(やや)〕薄く、灰白色。肉、白く、骨、硬く、味、佳ならず。性、魯鈍にして、死を知らずして、浮游す。人、長き杷(さらへ)を以つて、留〔(とど)〕むれば、則ち、留〔(とど)〕まる。楂(うきゝ)のごとし。故に名づく。背を割〔さ)〕き、白き腸(わた)を取る。長さ、丈余【「百尋〔(ひやくひろ)〕」と名づく。】。�䱒〔(しほもの:「𩸆」に同じ。塩漬。)〕に作〔(な)〕し、或いは、糟漬にし、或いは、曝(さら)し乾(ほ)し、之れを食ふ。
[やぶちゃん注:フグ亜目マンボウ科マンボウ Mola mola 。他にマンボウ科にはヤリマンボウ属ヤリマンボウ Masturus lanceolatus 、及び、クサビフグ属クサビフグ Ranzania laevis がおり、三属三種のみである。良安は「鱝に類して方にして」と記しているから、実際にマンボウを実見することも、また図画を見ることもなかったのであろう。だからこそ、冒頭のような誤った絵となったのである。ちなみに、学名の mola とは、ラテン語で「碾き臼」の意味である。でも、マンボウに相応しい、いい響きだな ❤~モラ~モラ~❤ なお、アカマンボウ目アカマンボウ科アカマンボウ属アカマンボウ Lampris guttatus は形が似ているので、和名に「マンボウ」が附いているが、マンボウとは全く縁がないので注意されたい。アカマンボウに就いては、私の『栗本丹洲自筆巻子本(国立国会図書館所蔵・第1軸)「魚譜」始動 / マンダイ (アカマンボウ)』の私の注を見られたい。また、「栗本丹洲 単品軸装「斑車魚」(マンボウ)」も参考になろう。
・「死を知らずして、浮游す」とは、後述されるような捕獲の死の危険をも自覚せずにぷかぷか浮いているということを言う まさに❤~モラ~モラ~❤
・「杷」とは「さらい」と言い、穀物を集めたりするのに用いる熊手状の道具 モラちゃん! 危険がアブナイよ!
・「楂」は音「サ」、筏(いかだ)のこと。
・「百尋」という呼称はクジラの小腸にも用いる(良安は「鯨」の項でちゃんと挙げている)。ちなみにクジラの百尋は百八十メートルにも相当する。クジラは個体自体の大きさが半端じゃないから、この呼称は満更、嘘ではあるまい思って調べてみると、マッコウクジラの腸の長さはなんと二百三十メートルという記録がある。いやはや、これはバッチリ、モノホンの百尋! では、マンボウなんか見たこともないし(きっと食ったこともない)良安は一丈余(約三メートル強)だと書いているが……でも、実際にマンボウの腸が百尋あるかどうか、知りたくない?……さても世の中には素敵な仲間がいるもの! マンボウの百尋は大型個体で二十一メートルだそうだ。サイト「生き物NAVI」の「マンボウの腸の長さがすごい!腸の食べ方は?」でお楽しみあれ! ❤~モラ~モラ~❤
でも、モラちゃん、悪いけどm身も百尋も食ったことある。いや、旨いんだな、これが! だってさ、フグの仲間だもんね! ごめんね❤~モラ~モラ~❤]
***
はむ
はも
海鰻
ハアイ マン
慈鰻鱺 狗魚
【和名波無
俗云波毛
唐音之畧歟】
【俗用鱧甚非
鱧乃八目鰻】
[やぶちゃん字注:以上六行は、前四行の下に入る。]
本綱海鰻鱺生東海中類鰻鱺而大也
△按海鰻鱺西南海多【當唐東海】東北全無之形似鰻鱺而
大背有鬛連尾青黒色淺於鰻鱺無鱗腹白牙齒長短
相並中道亦小齒數十相連大抵尺半二尺許肉白不
脆割之連皮傳〔→傅〕醬油炙食脂少於鰻鱺味美
蒲鉾 以海鰻肉擂擣爲魚餅粘于竹狀似蒲穗而如鉾
《改ページ》
故名之或粘板片炙亦佳爲肴中之珍【以他魚爲蒲鉾或多用鱣僞之
味劣】
風海鰻【俗云五牟岐里】 海鰻十頭相聨作白鮝形如片板者夏
秋賞之繊刻之和酒醬代膾甚可矣本綱註鰻鱺云乾
者名風鰻者蓋是矣【鰻鱺之乾者未知其好悪】
鮦鮃【正字未詳假字音用】 海鰻之大者四五尺許出於讃州味劣
於尋常者
凡海鰻之肝腸亦可煑食或作醢佳其膽苦不可食有如
白袋者乾之可以磨唐弓絃【唐弓者打和木綿者】
[やぶちゃん注:「弓」は二ヶ所とも異体字のこれ(「グリフウィキ」)だが、「弓」とした。]
一種有海宇奈岐【是亦可用海鰻鱺字】 有江海之鰻鱺色稍淺味
亦劣
*
はむ
はも
海鰻
ハアイ マン
慈鰻鱺〔(じまんれい)〕 狗魚
【和名、「波無」。俗に「波毛」と云ふ。唐音の畧か。】
【俗に「鱧」を用ふるは、甚だ、非なり。「鱧」は、乃〔(すなは)〕ち、「八目鰻」なり。】
「本綱」に、『海鰻鱺は、東海中に生ず。鰻-鱺(うなぎ)の類〔(るゐ)〕にして、大なり。』と。
△按ずるに、海鰻鱺は、西南海に、多し【唐〔(もろこし)〕の東海に當る。】。東北には、全く、之れ、無し。形、鰻-鱺(うなぎ)に似て、大きく、背に、鬛、有りて、尾に連なる。青黒色、鰻鱺より、淺し。鱗、無く、腹、白く、牙齒、長短、相〔(あひ)〕並び、中道にも亦、小齒、數十、相連なる。大抵、尺半、二尺ばかり。肉、白く、脆〔(もろ)〕からず。之れを割(さ)いて、皮を連ね、醬油を傅〔(つ)け)〕て炙り食ふ。脂〔(あぶら)〕、少なく、鰻鱺より、味、美なり。
蒲鉾(かまぼこ) 海鰻の肉を以つて、擂(す)り擣(つ)きて、魚餅〔(ぎよべい)〕と爲して、竹に粘(つ)くる。狀〔(かた)〕ち、蒲(がま)の穂(ほ)に似て、鉾〔(ほこ)〕のごとし。故に、之れを名づく。或いは、板片〔(へぎいた)〕に粘〔(ねん)〕して、炙るに、亦、佳し。肴中〔(かうちゆう)〕の珍なり【他魚を以つて、蒲鉾と爲〔すに〕、或いは、鱣〔(ふか)〕を多用し、之れを僞〔(いつは)〕る。味、劣れり。】。
風海鰻(ごんきり)【俗に「五牟岐里」と云ふ。】 海-鰻〔(はも)〕十頭、相聨(つら)ねて、白鮝(しらほし)と作〔(な)〕す。形、片板(へぎいた)のごとき者、夏・秋、之れを賞す。繊(ほそ)く之れを刻みて、酒醬〔(さけひしほ)〕に和して、膾〔(なます)〕に代〔(か)〕ふ。甚だ、可〔(よ)〕し。「本綱」〔=「本草綱目」〕、鰻-鱺〔(まんれい)〕を註して云はく、『乾〔しし〕者を「風鰻」と名づく。』と云ふは[やぶちゃん注:「云」は送り仮名にある。]、蓋し、是れか【鰻-鱺〔(うなぎ)〕の乾〔しし〕者、未だ、其の好悪〔(よしあし)〕を知らず。】。
鮦鮃(とうへい)【正字、未だ、詳らかならず。字の音を假りて用ふ。】 海鰻の大なる者、四、五尺ばかり。讃州〔=讃岐〕に出づ。味、尋常の者に劣れり。
凡そ、海鰻(はも)の肝・腸、亦、煑食ふべし。或いは、醢(なしもの)〔:塩辛。〕に作〔(な)すに〕、佳し。其の膽〔(きも)〕、苦くして食ふべからず。白き袋のごとき者、有り。之れを乾〔か〕して、以つて、唐弓〔(とうゆみ)〕の絃〔(つる)〕を磨(みが)くべし【唐弓は木綿を打ち和〔(やは)ら〕ぐる者なり。】。
一種、「海宇奈岐」、有り【是も亦、「海鰻鱺」の字を用ふべし。】。江海に有る〔ところ〕の鰻鱺よりは、色、稍〔(やや)〕、淺く、味も亦、劣れり。
[やぶちゃん注:ウナギ目アナゴ亜目ハモ科ハモ属ハモ Muraenesox cinereus 。本邦の近縁種として同属スズハモ Muraenesox bagio 、ハシナガハモ科ハシナガハモ(ハシアナアナゴ属とも) Oxyconger leptognathus 、ワタクズハモ Gavialiceps taiwanensis を挙げておく。但し、ワタクズハモは分布が沖縄諸島から台湾までの南方の上、深海種で、良安の認識域外であるから、ここでは除外した方がよい。
・「鱺」の単漢字は「廣漢和辭典」に、「おおなまず」=「鱧」、とする。
・「唐音の畧か」とは、冒頭にある中国音「ハアイ マン」を略した呼び名か、という意味である。但し、これは偶然であろうと思われる。寧ろ、「嚙・食(は)む」・「齒を持つ魚」の転訛とする方が、正しいように感ぜられる。
・「鱧は、乃ち、八目鰻なり」とあるが、「廣漢和辭典」によれば、中国では、「鱧」は、第一に「大鯰(オオナマズ)」を指し(前掲通り、ここで「鱺」と同字とする)、第二、に「ヤツメウナギ」(無顎口綱ヤツメウナギ目ヤツメウナギ科 Petromyzontidae の魚類の総称)を指す。
・「鰻鱺」は正真正銘のウナギ Anguilla japonica 。時珍が「海鰻」と漢名を記してしまったのは仕方がないが、素人でも、比較すれば、これがそれほど近縁種でないことは知れる。その辺りを、ハモ料理は京の良安には、親しいものであったはずだから、ここは、果敢にその別種なることを主張すべきであったと思う。
・「中道にも亦」とは、前述の如く、長く発達した口吻(顎部)内部には、犬歯状の鋭い歯が並んでおり、さらに「その内側にもまた」、細かい歯が並んでいるハモの特異な歯列を表現している。先に「ハモ」中国音説があったが、それよりも、この漁獲に際して危険な歯に由来する「嚙(は)む」の転訛とする方が、やはり、しっくりくるのである。
・「風海鰻」は、本叙述によれば、保存食としての「風干しのハモ」を指す言葉のようであるが、現在は「ごんぎり」(長崎)・「五寸切」と書いて、ハモ自体の別称とされている。
・「片板」は、「折(へ)ぎ板」で、杉や檜等を薄く削って作った板のことで、「へぐ」は「剥ぐ・折ぐ」で、「薄く削りとる」の意。前の「板片」は転倒しているが、同義と見て、同じ訓を添えておいた。
・「酒醬」とは、酒・梅干・塩等を混ぜ合わせて作った調味料で、魚や鶏肉などの下味に用いる。
・「未だ其の好惡を知らず」は、良安先生、「正直、ウナギの干物なんざ。食ったことがないので、旨いか。不味いか分からぬ。」と言いたいのである。
・「鮦鮃」トウヘイ これは現在のスズハモ Muraenesox bagio の呼称である(但し、ウナギ目アナゴ科クロアナゴ Conger japonicus を西日本に於いてこう呼称するという情報もあるし、ハモとスズハモを一緒くたにする地方や市場もあると聞く)。良安が困惑しているこの「トウヘイ」という音については、「唐兵」と書き、スズハモの硬い肋骨が、秦の始皇帝陵等で有名な兵馬俑の鎧の如く見えるからという記載を見かけた。うーん、「唐兵」自体は留保するにしても、幾らなんでも兵馬俑の存在自体が人口に膾炙する年代を考えると(兵馬俑自体が途轍もなく古くとも多くの日本人がそれを知るのは途轍もなく新しい)、語源由来としては眉唾っぽい。
・「白き袋」とは「浮き袋」のことであろう。ちなみに、これは「鱧笛」と称して、鱧料理の珍味。京で食したことがあるが、きゅっとした食感がたまらなくいいものである。
・「唐弓」綿打ちをする道具としての竹製の綿弓。形状はまさしく小型の弓そのもので、指で弦を弾(はじ)いて、綿を打ち、繊維をほぐす。
・「海宇奈岐」現在も「ウミウナギ」という呼称は、
ハモの別称
として用いられるが、他に、
ウナギ亜目アナゴ科クロアナゴ亜科クロアナゴ属マアナゴ Conger myriaster
を言う地方名でもあり、さらに伊豆半島にあっては、広く
ウナギ目ウツボ亜目ウツボ科 Muraenidae のウツボ類
を指す。但し、良安の叙述は、
正真正銘のウナギ Anguilla japonica
を指しているようにも思われる。何故なら、同種の成体個体でも、海の内湾に棲息するものもあるからである。]
***
■和漢三才圖會 江海無鱗魚 卷ノ五十一 ○十四
あなご 正字未詳
阿名呉
△按阿奈古[やぶちゃん注:ママ。]狀似海鰻而色淺於海鰻不潤從項至尾有
小白㸃星者兩邊相連各百有餘其味【甘平】脂少不
美漁人炙之僞鰻鱺
*
あなご 正字、未だ、詳らかならず。
阿名呉
△按ずるに、阿奈古は、狀〔(かたち)〕、海鰻〔(はも)〕に似て、海鰻より、色、淺し。潤〔(うるほ)〕はず。項〔(うなじ)〕より、尾に至りて、小さき白㸃の星のごとくなる者、有り。兩邊に相〔(あひ)〕連なること、各〔(おのおの)〕、百有餘。其の味【甘、平。】、脂〔(あぶ)〕ら、少なくして、美ならず。漁人、之れを炙り、鰻-鱺〔(うなぎ)〕に僞〔(いつは)〕る。
[やぶちゃん注:本種は、その頭部、及び、側線上部の白点(側線孔)の列という特徴、及び、食用流通種という観点から、ウナギ目アナゴ亜目アナゴ科 Congroidei のマアナゴ Conger myriasterCongroidei としておくが、実際にはアナゴ科は本邦産だけでど十五属二十七種を数え、分類の難しいグループとされる。
・「海鰻」は前項「海鰻」のアナゴ亜目ハモ科ハモ属ハモMuraenesox cinereus 。
・「潤はず」とは、前の色の説明と考えられるので、ハモのような潤いに満ちた茶褐色の輝きが体表面に見られず、くすんだ褐色であることを表現しているか。
・「鰻鱺」は、前項「海鰻」の叙述を見ても分かるように、良安が正真正銘のウナギ Anguilla japonica を指す際に用いる語である。]
***
いかなこ
かますこ
玉筯魚
俗云以加奈古
又名加末須古
[やぶちゃん字注:以上二行は、前三行下に入る。]
三才圖會云玉筯魚身圓如筯微黒無鱗兩目㸃黒至菜
花開時有子而肥俗謂之菜花玉筯
《改ページ》
△按其大一二寸無鱗白色脊微青似梭子魚之形然本
是別種春末腹在鮞凡春分時攝州一谷始多取之立
夏播州明石浦鹿瀬盛取之夏至前後讃州八島及下
關取之【自一谷次第至西海】其翌日更無之亦一異也【其盛出時泝浪如山
一網幾千万難測量】初春偶有之者大三四寸背青腹白蓋此舊
魚也盛時以布網取之用潮水※之脂多浮于釜中扱
[やぶちゃん字注:「※」=「月」+「雋」。]
取爲燈油與鯨鰯油相並矣所𤎅魚亦黃而脂尙有之
【甘溫微毒】以送四方爲賤民食其利用廣大亞于鯨鰯
*
いかなご
かますご
玉筯魚
俗に「以加奈古」と云ふ。又、「加末須古」と名づく。
「三才圖會」に云はく、『玉筯魚は、身、圓〔(まろ)〕く、筯(はし)のごとし。微〔(すこ)し〕黑くして、鱗、無し。兩目㸃は黒し。菜花、開(さ)く時に至り、子、有りて、肥〔(こ)〕ゆ。俗に、之れを、「菜花玉筯〔(さいくわぎよくきん)〕」と謂ふ。』と。
△按ずるに、其の大いさ、一、二寸、鱗、無く、白色。脊(せすぢ)、微し、青〔なり〕。梭-子-魚(かます)の形に似たり。然れども、本〔(もと)〕は是れ、別種にして、春の末、腹に鮞(こ)、在り。凡そ、春分の時、攝州一の谷に、始めて、多く、之れを取る。立夏、播州明石の浦の鹿瀨(しゝがせ)にて、盛んに、之れを取る。夏至の前後、讃州八島、及び、下関(しものせき)に、之れを取る【一の谷より、次第に、西海に至る。】。其の翌日、更に、之れ、無きも亦、一異なり【其の盛んに出でし時、泝浪〔(せきらう)〕して、山のごとく、一網にして、幾千万、測-量〔(はか)〕り難し。】。初春、偶々〔(たまたま)〕、之れ、有る者、大いさ、三、四寸、背、青く、腹、白し。蓋し此れ、舊-魚(ふるせ)なり。盛りの時、布網を以つて、之れを取る。潮水を用ひて、之れを※(い)る〔に〕、脂〔(あぶら)〕、多く、釜中〔(かまなか)〕に浮く。扱(すく)ひ取りて、燈油と爲す。鯨・鰯の油と相〔(あひ)〕並ぶ。𤎅〔(い)〕る所の魚、亦、黃にして、脂、尙を〔→尙ほ〕、之れ、有り【甘、溫。微毒。】。以つて、四方に送る。賤民の食と爲す。其の利用、廣大なること、鯨・鰯に亞〔(つ)〕ぐ。[やぶちゃん字注:※=「月」+「雋」。]
[やぶちゃん注:スズキ目ワニギス亜目イカナゴ科イカナゴ属イカナゴ Ammodytes personatus 。この稚魚が、カマス類(サバ亜目カマス科カマス属 Sphyraena )の稚魚に似ていることから、「カマスゴ」とも言うが、これには別に、名産地摂津から「叺(かます)」(「蒲簀(かます)」の意。古くは植物の「ガマ」で作った。藁莚(わらむしろ)を二つ折りにし、縁を縫い閉じた袋)に入れて諸国に送ったことからとも言われる。稚魚は、地方により、「カナギ」(南日本での呼称。「カナ」は「極めて細いこと」、「ギ」は「魚」を示す接尾語という。なお、この呼称は、現地ではニシン目キビナゴ科キビナゴ属キビナゴ Spratelloides gracilis にも用いられる)・「コオナゴ(小女子)」・「シンコ(新子)」・「シャシャラナゴ(「玄孫子=曾孫子」であろう)」と呼び、成長したものを「メロウド(女郎人)」・「フルセ(古背。本記載にも登場する)」と呼んだりする。
・「筯」は、音で「チョ」または「ジョ」と読み、ここでは、「箸」のことである。因みに、この字には、今、一つ、『貝の名。はまぐりの類。殻の中に蟹を宿して、死ぬまで離れない。』(「廣漢和辭典」)という意味がある(南朝斉から梁にかけての文学者任昉(じんぼう 四六〇年~五〇八年)の「述異記」を引用している)。これはハマグリ属 Meretrix と、それに寄生するカクレガニ科 Pinnotheridae のピンノ類を指していよう。
・「目點」とは眼球の光彩部を指すと思われる。
・「菜花」は言わずもがなだが、フウチョウソウ目アブラナ科アブラナ属 Brassica 。
・「梭子魚」は先に示したサバ亜目カマス科カマス属の総称であるが、本邦で「カマス」と呼ぶ場合は、アカカマス Sphyraena pinguis であることが多い。
・「鮞」は、「はらご・はららご・魚の卵」を指す。
・「明石の浦の鹿瀬」は、「イカナゴの釘煮(くぎに)」発祥の地のようである(以下、個人サイト内の「いかなご釘煮のルーツは?」(複数の投稿者によるものの内、「紫苑」さんの記事)よりの孫引きである。但し、改行をすべて省略した)。
《引用開始》
1935年、神戸市垂水区塩屋町の「魚友」松本信子に、ジェームス山の別荘地に住んでいたお客様より「いかなごを佃煮にしてくれないか」と依頼されました。そこで醤油・砂糖(キザラ)・生姜を使用して、試行錯誤のうえ炊き上げました。その後その住人が近所の方々に配るなどするうちに評判になり、「魚友」の店頭にも置くようになりました。それまでは、「いかなご」といえば「釜揚げ」と、それを天日干した「かなぎちりめん」がほとんどでした。1960年代頃になって、神戸市垂水漁協の組合長により「くぎ煮」(出来上がりが「さびた古釘」のよう)と名付けられました。それとともに、神戸市垂水区の各家庭でも炊くようになり、盛んになってきました。いまでは、関西の春の風物詩のひとつに挙げられるようになりました。
《引用終了》
私は一九五七年生まれ。「釘煮」という命名は、どうやら私より、やや若いらしい。
・「泝浪」の「泝」は、「流れに逆らって登る」が原義であるから、「海の波に逆らって泳ぐほどに、群れをなして、山の如く」という意味であろう。
・「燈油と爲す」という事跡については、まとまった記載を知りえないが、先の「いかなご釘煮のルーツは?」の別な箇所に、「MANA・なかじま」氏の投稿に以下の記載があった。
《引用開始》
一時期に大漁に水揚げされるシンコの処理には常に頭を悩ませていて、生食など食用に向けられるのは地元のわずかの消費のみで、鯨油や鰯油の代替材料として魚脂を抽出して燈油用に使われたり、塩漬け発酵ののち魚醤としてイカナゴしょう油の存在は、香川や兵庫地区の特産品として中世以前にまで遡れるそうです。(以下略)
《引用終了》
この「鯨油や鰯油の代替材料」とされた歴史年代は不明であるが、良安の最後の「其の利用、廣大なること、鯨・鰯に亞ぐ。」という謂いからも、相当、古くから燈油として用いられていたと考えてよいようである。
それにしても、どうもこの良安の記載、気になることがある。このイカナゴの漁獲地域記載の、
一の谷→播州明石の浦→讃州八島→下関
の順番(勿論、それは、事実を順に書いたのであろうが)、直後の分かりきった「一の谷より、次第に西海に至る。」という割注、そうして、盛んに繁栄していたイカナゴの群れが、夏至の後、一日にして、全く、姿を消してしまうのは、一大奇異であると記すこと、「其の盛んに出でし時、泝浪山のごとく、一網にして、幾千万、測量り難し。」と最後に、ご丁寧に、またしても、その盛時の栄華を回想する。――もうお分かりであろう、これ、「盛者必衰の理」を著わした良安版「平家物語」のパロディに見えてくるのである。]
***
しろいを
鱠殘魚
クワイ ツアン イユイ
王餘魚 銀魚
【俗云白魚】
[やぶちゃん字注:以上二行は前三行下に入る。]
本綱膾殘魚大者四五寸身圓如筯潔白如銀無鱗若已
鱠之魚但目有兩黒㸃爾小者曝乾以貨四方清明前有
《改ページ》
■和漢三才圖會 江海無鱗魚 卷ノ五十一 ○十七
子甚美清明後子出而痩但可作鮓腊耳【博物志云呉王食魚膾棄其殘
餘於江化爲此魚故名或作越王或作僧寶誌皆傳〔→傅〕會也不足致辨】肉作羹食健胃
本草必讀云鱠殘魚色青離水色變則白矣
△按鱠殘魚生江海交伊勢志摩參河肥後備前多出攝
播亦有之凡立春初出人賞之二三月腹有子味稍劣
焉生帶青色離水則白煑之則益潔白頭尾尖而身扁
有鬐無皮骨煮食軟甘美供上饌或以竹串貫眼相聯
曝乾作魥【俗云目佐之】一種有氷魚【河湖無鱗魚下有之】
*
しろいを
鱠殘魚
クワイ ツアン イユイ
王餘魚 銀魚
【俗に「白魚」と云ふ。】
「本綱」に、『膾殘魚は、大なる者、四、五寸、身、圓〔(まろ)〕く、筯〔(いかなご)〕のごとく、潔白なること、銀のごとく、鱗、無く、已〔(すで)〕に鱠〔(なます)〕にする魚のごとし。但し、目に、兩黒㸃有りし、のみ。小なる者、曝〔(さら)〕し乾して、以つて、四方に貨〔(う)=売〕る。清明の前、子、有りて、甚だ、美なり。清明の後は、子、出でて、痩せ、但だ、鮓腊〔(させき)〕に作るのみ【「博物志」に云ふ、『呉王、魚〔の〕膾を食し、其の殘餘を、江に棄つ。化して此の魚と爲る。故に名づく。』と。或いは、越王に作り、或いは、僧寶誌に作る。皆、傅會〔(ふかい)〕なり。辨を致すに足らず。】。肉、羹〔(あつもの)〕に作りて食すに、胃を健やかにす。』と。
「本草必讀」に云ふ、『鱠殘魚は、色、青く、水を離〔るれば〕、色、變じて、則ち、白し。』と。
△按ずるに、鱠殘魚は、江海の交(あはひ)に生ず。伊勢・志摩・參河〔(みかは)=愛知〕・肥後・備前に、多く、出づ。攝〔=摂津〕・播〔=播磨〕、亦、之れ、有り。凡そ、立春の初めに出づ。人、之れを賞す。二、三月、腹に、子、有り、味、稍〔やや)〕、劣れり。生〔(なま)〕は青色を帶び、水を離れては、則ち、白し。之れを煮れば、則ち、益々、潔白なり。頭・尾、尖りて、身、扁〔(ひらた)〕く、鬐〔(ひれ)〕、有り。皮・骨、無く、煮食へば、軟にして、甘美なり。上饌に供す。或いは、竹串を以つて、眼〔(め)〕を貫き、相〔(あひ)〕聯〔=連〕ね、曝し乾して、「魥(めざし)」と作〔(な)〕す【俗に「目佐之」と云ふ。】。一種、「氷魚〔(ひを)〕」、有り【「河湖無鱗魚」の下に、之れ、有り。】。
[やぶちゃん注:「鰈」の項でも問題にしたが、本種は、
キュウリウオ目 Osmeriformes シラウオ科シラウオ属シラウオ Salangichthys microdon
と同定したい。まず、本項目の「本草綱目」の言う「膾殘魚」は、シラウオの分布域が中国に及んでいるのに対して、ハゼ亜目ハゼ科ゴビオネルス亜科 Gobionellinae シロウオ属シロウオ Leucopsarion petersii の分布が、日本及び朝鮮半島に限定されている点、その大きさを十二~十五センチメートルとしている点(現在の本邦の成魚のシラウオは十センチメートル程度、シロウオの方は、一回り小さく、六センチメートル)、「銀のごとく」という表現が、現代中国語のシラウオを指す「銀魚」と一致する点、そうして、本邦で多くの書が「膾殘魚」をシラウオの異名としている点で、間違いなくシラウオである。次に、良安が語るものがシラウオであるかどうかであるが、生時に青色を帯びているという表現は、微かに褐色ががったシロウオではなく、透明度の高いシラウオを指すと考えられる点、頭部と尾部が尖っているというのは、シロウオよりも有意にシラウオの特徴を示す表現である点(私だったらシロウオの頭と尾を尖っているとはまず表現しない)、シラウオは背鰭の後方に脂鰭があるのがシロウオとの大きな相違点であるが、シロウオの方はさらに背鰭は一つしかなく、腹鰭も極めて小さい(実は、ハゼ科の魚は、背鰭が二つあること、腹鰭が、吸盤状に発達していることが特徴)点の、以上、三点からも、シラウオと同定するものである。それでは、ハゼ亜目ハゼ科ゴビオネルス亜科シロウオ Leucopsarion petersii は? という疑問が起こるのだが、最終的に、私は、やはり、良安はシラウオとシロウオを分別するに至っていないというのが現在のところの感想である(シラウオとシロウオの相違については、例えば、以下のページを参照されたい)。なお、以下に本邦の三属四種を掲げておく。
シラウオ属シラウオ Salangichthys microdon
イシカワシラウオ Salangichthys ishikawae
アリアケシラウオ属アリアケシラウオ Salanx ariakensis
ヒメシラウオ属アリアケヒメシラウオ Neosalanx reganius
である。
・「筯」は「玉筯魚」(いかなご)の後注を参照。
・「鱠」は「なます」と読んで、「こまかく切った魚の生肉」、即ち、刺身(それらを酢に漬ける加工品は本邦での謂いである)。
・「清明」は二十四節気の一つ。旧暦の三月、春分後十五日目、現在の四月上旬。
・「鮓腊」は、「なれ鮨」や「ほじし」(干物)。
・「博物志」は晋の張華が撰した本草・博物書であったが、散佚し、後代に諸書の引用から集書したものが残る。
・「呉王、魚膾を食し……」の該当部分は以下の通り。
*
吳王、江行食鱠。有餘、棄於中流。化爲魚。今、魚中有名吳王鱠餘者。長數寸、大者、如箸。猶有鱠形。
○やぶちゃん訓読
吳王、江(かう)に行(ゆ)きて、鱠(なます)を食ふ。餘る有りて、中流に棄(す)つ。化して、魚と爲る。今、魚中に「吳王鱠餘者(ごわうかいよしや)」との名、有り。長さ、數寸、大なる者、箸のごとし。猶ほ、鱠の形に、有るごとし。
○やぶちゃん訳
呉王が、長江に行って、刺身を食った。余ったので、流れの中に棄てた。それが、化して、魚となった。今、魚類の中に、「呉王鱠余者」(呉王の刺身の余りもの)と言う魚名がある。長さは、数寸で、大きなものは、箸のようである。今も、実に、なお、刺身の形のままであるようである。
*
但し、私の引用したのは、李時珍の引用した版本とは異なるものと思われる。
・「僧寶誌」は宝誌和尚(四一八年~五一四年)で、中国の南北朝時代の伝説的な風狂・神異の僧侶。梁の武帝が、画家に命じて、彼の肖像を描かせようとした折り、顔が真ん中から裂け、その下から十二面観音の尊顔が現われ、それがまた、自在に変化したため、遂に描くことが出来なかったという逸話で知られるが、まさに、その場面を彫った京都西住寺にある平安時代作のナタ彫りの宝誌和尚立像(グーグル画像検索「京都西住寺 宝誌和尚立像」)。私の大好きな仏像である。一度、ご覧あれ!
・「皆、傅會なり。辨を致すに足らず」の「傅會」は、「牽強付会」の「付会」と同義と思われ、「そんな好い加減に、何人にも、こじつけてきた、刺身が生き魚になるなんぞという話は、どれが正しいかなどと、まともに論ずべき価値は、ない!」と良安先生のプラグマティクな拘りが判る発言だ。
・「羹」は、肉に野菜を混ぜて作った吸い物。スープ。
・「本草必讀」という書は、東洋文庫版の後注には『「本草綱目類纂必読」か。十二巻』とのみあるだけである。中国の爲何鎭(いかちん)なる人物の撰になる「本草綱目」の注釈書であるらしい。
・「魥」は、「ひもの・ほしうお・魚を竹に刺して乾かしたもの」を言う語。
・「氷魚……」の「氷魚」は現在、「ひお」もしくは「ひうお」と呼び、キュウリウオ上科アユ科アユ属アユ Plecoglossus altivelis altivelis の稚魚のことを呼称する(従って、良安のシロウオの「一種」という表現は、当然、誤りである)。芭蕉の膳所(ぜぜ)での句にも現れる。
霰せば網代の氷魚を煮て出さん
「和漢三才圖會 卷第五十 魚類 河湖無鱗魚 寺島良安」の掉尾の「ひを 𩵖」を見られたい。]
***
ちりめんこあい
鱊【音聿】
キヱツ
春魚
【俗云縐小鰷】
[やぶちゃん字注:以上二行は、前三行下に入る。]
本綱鱊小魚也大如針一斤千頭春月自岩穴中隨水流
出狀似初化魚苗取收曝乾爲※名鵞毛※其細如毛食
[やぶちゃん字注:「※」=「月」+「廷」。]
以薑醋味同蝦米【甘温】或云此鱧魚苗也
△按鱊魚春月攝播多取之最細小不過寸身圓潔白而
似索麪之屑目有兩黒㸃熬之縬縬如縐線故名縐小
鰷熬之食味【甘】如饙曝乾亦佳也實非鰷子此鰡苗也
鰮子 同時出大寸許畧扁白而帶微黒色是亦稱小鰷
熬之不脆味劣
*
ちりめんこあい
鱊【音、聿〔(いつ)〕。】
キヱウ
春魚
【俗に「縐(ちりめん)小鰷〔(こあい)〕」と云ふ。】
「本綱」に、『鱊は、小魚なり。大いさ、針のごとく、一斤〔:約六百グラム。〕〔に〕、千頭〔あり〕。春月、岩穴の中より、水の流れを〔→流れに〕、隨ひ、出づ。狀〔(かたち)〕、初めて化する魚苗〔(ぎよべう)〕に似たり。取り收め、曝〔(さら)〕し乾して、※〔(ほじし)〕と爲す。「鵞毛※〔(がもうてい)〕」と名づく。其の細きこと、毛のごとし。食ふに、薑醋〔(しやうがず)=生姜酢〕を以つてす。味、蝦米〔:干しエビ。〕に同じ【甘、温。】。或る人の云はく[やぶちゃん注:「人」は送りがなにある。]、「此れ、「鱧-魚(やつめうなぎ)」の苗〔(べう):稚魚。〕なり。』と。[やぶちゃん字注:※=「月」+「廷」。]
△按ずるに、鱊魚は、春月、攝〔=摂津〕・播〔=播磨〕に、多く、之れを取る。最も細小にして、寸を過ぎず。身、圓〔(まろ)〕く、潔白にして、索麪〔(さうめん)〕の屑(くづ)に似たり。目に、兩黑點、有り。之れを熬〔(い)〕れば、縬縬〔(しゆくしゆく)〕として、縐-線(ちゞみ)のごとし。故に「縐(ちりめん)小鰷〔(こあゆ)〕」と名づく。之れを、熬りて、食ふ。味【甘。】、饙(こはめし)のごとし。曝し乾して亦、佳なり。實は、「鰷」の子に非ず、此れ、「鰡(えぶな)」の苗なり。
鰮(いわし)の子 同時に出づ。大いさ、寸ばかり。畧〔(ほぼ)〕、扁たく、白くして、微〔(わづ)かに〕黑色を帶ぶ。是れも亦、「小鰷」と稱す。之れを熬る。脆〔(もろ)〕からず、味、劣れり。
[やぶちゃん注:現在、これに類似した「チリメンジャコ」は加工食品の名称として用いられるが、良安は明確に生体を指して呼称しているので、イワシ類等の稚魚を主体とした乾燥食品として食用に耐え得る魚類稚魚の総称、ととっておく。種としてはイワシ類(カタクチイワシ・マイワシ・ウルメイワシ等)やシロウオ・シラウオ・イカナゴ・アユ等の稚魚と広範囲に示すしか、ない。しかし、雑魚だからと、不当に軽々しく待遇するのは不敬である。そこで、以下、「チリメンジャコの学名」を列挙することとする。
ニシン上目ニシン目ニシン亜目カタクチイワシ科カタクチイワシ属カタクチイワシ亜科カタクチイワシ Engraulis japonica
ニシン目ニシン科マイワシ属マイワシ Sardinops melanostictus
ニシン目ニシン科ウルメイワシ属ウルメイワシ Etrumeus micropus
キュウリウオ目シラウオ科シラウオ属シラウオ Salangichthys microdon
同科シラウオ属イシカワシラウオ Salangichthys ishikawae
同科アリアケシラウオ属アリアケシラウオ Salanx ariakensis
同科ヒメシラウオ属アリアケヒメシラウオ Neosalanx reganius
ハゼ亜目ハゼ科ゴビオネルス亜科シロウオ属シロウオ Leucopsarion petersii
スズキ目ワニギス亜目イカナゴ科イカナゴ属イカナゴ Ammodytes personatus
キュウリウオ上科アユ科アユ属アユ Plecoglossus altivelis altivelis
同科アユ属リュウキュウアユ Plecoglossus altivelis ryukyuensis
もっといるだろうが、この程度に留める。
・「縐小鰷」の「縐」は、「ちぢみ」(麻や葛で作った細やかな皺のある織物)を意味する。「小鰷」の「鰷」は、訓で、川魚のコイ科ウグイ亜科ウグイT ribolodon hakonensis (通称異名で「ハヤ」・「ハエ」があるが、私は絶対に使用しない「はや」という魚種は存在せず、複数の川魚を指すことは、既に何度も述べた)を指し、音も「チョウ・ジョウ・ショウ」で、「あい」又は「あゆ」という読みは、不審。東洋文庫版は良安の記載の中のこれに『こあゆ」とルビを振るが、私は冒頭に現われる「ちりめんこあい」の読みを尊重したい。良安は一貫して「鰷」にルビを振っていない。私が「こあい」という訓に拘るのは、これはキュウリウオ上科アユ科アユとは異なるものであることを明白に示したいからで、「こあい」というのは「子鮎」ではなく、「小さな細い魚」の謂いではなかろうかと思うからである。例えば、関西では、「イワシの塩物」を「小相」(こあい)と称するようであるし(「チリメンジャコ」は薄塩で炊き上げるから「塩物」と言ってよいはずである)、関西方言の「こまい」(小さい)等からの転訛の可能性もあろうと思うからである。
・「魚苗」は「卵から孵ったばかりの幼魚」を言うが、ここはそれが大きな群れをなしている状態を指しているようにも読める。
・「※」[※=「月」+「廷」]は「まっすぐな干し肉」のことを言う。
・「鵞毛※」がカモ目カモ科カモ亜科ガン族ガチョウ Anser anser の毛のように白くて、軽い干物、ということであろう。この「鵞」を「白鳥」、カモ科ハクチョウ亜科 Cygninae のハクチョウ類とする解説を、多く目にする。確かに中文のウィキペディアの「ハクチョウ」は「天鵝」とする。しかし、私は「廣漢和辭典」の記載を優先しておく。
・「鱧魚」を「ヤツメウナギ」と訓じているが、これは前出の「鱧」(ハモ)の項で取り上げたように、中国は、第一に「大鯰」(オオナマズ)を指し、第二に無顎口綱ヤツメウナギ目ヤツメウナギ科 Petromyzontidae の魚類の総称である「ヤツメウナギ」を指すからである。
・「索麪」の「麪」は「麺」の正字。素麺。「そうめん」は「さくめん」の音便変化したもの。
・「目に、兩黒㸃、有り」とは、眼球の光彩部を指して言っているものと思われる。
・「縬縬」の「縬」は「縮」で、「みるみる縮むさま」を言い、次の「縐」と同字として、「ちぢみあや(しじらあや)」の意味も持つ。
・「縐線」は、もしかすると、「折り目の細かいちぢみ」を意味する「縐絺」(しゅうち/せんち)の誤字かもしれない。但し、これで中文検索をかけると、幾つかの繊維関連のサイトが上がってくる。中国語ちんぷかんの私には、これが、限界。
・「饙」は、本来は、「一度炊いて、もう一度、蒸しを加えた飯」、又は、「半蒸しの飯」を言うが、ここでは「コワメシ」のルビを振っているので、餅米(粳米)を蒸した「おこわ」のことを言っていると採る。
・「鰷」は東洋文庫版は、既に述べたのと同じく、これに『あゆ』とルビを振るが、これは先に言った通り、コイ科ウグイ亜科ウグイその他の「はや」類を指す。従って、ここは、「はや」「はえ」と訓ずるのが穏当である。しかし、文脈上、「縐小鰷」を明白に「ちりめんこあい」と私が読んできたことからは、これを私は「あい」と読まねばならぬとも言える(いや、ルビが振られていなければ、そう読む方が「自然」であろう。寧ろ、「あゆ」と読む方が「不自然」である)。ところが、それでは、私の冒頭の考察が正しいとして、この「鰷」が特定の種を示さないものとなってしまい、ここで「鰡」(えぶな=ボラ)という特定種と対峙させる意味が、全く無化されてしまうこととなる。良安は、当然、この「鰷」を以つて特定種を示していることは言を俟たない。とすれば、私は、字面通り、「はや」「はえ」と訓じておくべきであると思う。良安は既に「ちりめんこあい」が「縐小鰷」という字を用い、更にハイブリッドに「こあい」と発音しながら、「こあい」は「子鮎」では、勿論、なく(但し、チリメンジャコの素材にはアユの稚魚は含まれる)、しかも、それが、本来の「鰷」の字が示すウグイ(「はや」「はえ」)とも無縁であることを認識していたのであろうと思われるのだ(但し、その正体を以下で「鰡」=ボラとのみ特定してしまったことには疑義があるが)。だからこそ、これは本来の限定されたウグイ(「はや」「はえ」)ではないのだということを良安は明記したのだと解釈しておく。
・「鰡」はボラ目ボラ科ボラ属ボラ Mugil cephalus の稚魚であるが、チリメンジャコの素材としては、あり得るが、一般的ではないと思う。良安の時代は、ボラの稚魚が優勢だったのか、それとも、ただの良安の勘違いか、最早、知るすべはない。
・「鰮の子」は、文字通りならば、マイワシの子ということだが、注冒頭に掲げたようなイワシ類全般を指している。
その昔、私が数ある国内の海岸生物図鑑の中で(私はとりあえず低学年向のもの以外は概ね購入している)最も高く評価する一冊、菅野徹氏(奇しくも私が今勤務している高等学校のずっと昔の『英語』(!)の先生であった)の小学館の「海べの生物」のシラスボシ中の混入生物種を仕分けた表に心躍らせたのが懐かしい。と……ネットを探ってみると、やっぱり楽しい奇特な人々はいるもんだ! チリメンモンスター名鑑! ズバリ! サイト名「チリモン図鑑」! 楽しいなあ♡ ご覧あれ!]
***
たこ
章魚
チヤン イユイ
𠑃魚 章擧
鮹【延喜式用此字】
海蛸子
【和名太古】
[やぶちゃん字注:以上四行は、前三行の下に入る。]
本綱章魚生南海形如烏賊而大八足身上有肉採鮮者
薑醋食之味如水母【甘鹹寒】
△按和名抄云海蛸子【和名太古】貌似人裸而圓頭者也長丈
餘者謂海肌子蛸正作鮹【延喜式等皆用鮹字】蓋本草綱目鮹別
《改ページ》
此一種非章魚屬也
章魚狀似烏賊而大八足疣多其疣凹纍纍色白帶微赤
煑之變深赤色頭圓而白眼口在頸與足之交無腹而
膓在頭中八腿交股之中間白皮中有如雙小鳥者褐
色其狀一如鴉一如鳶也章魚頭似嚢而肉薄但足肉
厚味亦美然硬於鮑而老齒不堪食惟先以柔策數敲
之後煑之則肉軟以薑醋食之酒水等分以文火煮半
日許加醬油再煮則軟脆甘美倍常俗謂之關東煮
凡取章魚以繩絆壺投水中則久而章魚自入也無大小
壺一箇章魚一頭北海乃大者多有一二丈許長足若
人及犬猿誤對之則足疣吮着皮膚無不殺也鮹性好
芋入田圃掘芋食其行也怒目踏八足立行其頭如浮
屠狀故俗稱章魚坊主最難死惟打兩眼中間則死
又云章魚若飢則食己足故五足六足者亦間有
*
たこ
章魚
チヤン イユイ
𠑃魚 章擧
鮹【「延喜式」は、此の字を用ふ。】
海蛸子〔(かいせうし)〕
【和名、太古。】
「本綱」に、『章魚は、南海に生ず。形、烏賊〔(いか)〕のごとくにして、大〔(おほき)〕く、八足。身の上に、肉、有り。鮮(あたら)しき者を採りて、薑醋(しやうがず)〔=生姜酢〕にて、之れを食ふ。味、水母〔(くらげ)〕のごとし【甘鹹、寒。】。』と。
△按ずるに、「和名抄」に云ふ、『海蛸子【和名、「太古」。】、貌〔(かほ)〕、人の裸(はだか)に似て、圓頭〔(ゑんとう)〕なる者なり。長さ、丈餘の者、「海肌子〔(かいきし)〕」と謂ふ。蛸は、正〔(まさ)〕に「鮹」に作る【「延喜式」等は、皆、「鮹」の字を用ふ。】。』と。蓋し、「本草綱目」に、「鮹」、別に、此れ、一種〔とす〕。章魚の屬に非ず。
章魚は、狀〔(かた)〕ち、烏賊に似て、大きく、八足、疣(いぼ)、多く、其の疣、凹(なかくぼ)にして纍纍〔=累累〕たり。色白く、微赤を帶ぶ。之を煮れば、深赤色に變ず。頭、圓くして白く、眼・口、頸と足の交(あはひ)に在り。腹、無くして、膓〔(はらわた)〕、頭〔(かしら)〕の中に在り。八つの腿〔(もも)〕の交股〔(かうこ)〕の中間は白く、皮の中に、雙(つがい[やぶちゃん字注:ママ。])の小鳥のごとき者、有り。褐(きぐろ)色にして、其の狀〔(かたち)〕、一〔(いつ)〕は鴉のごとく、一は鳶のごとし。章魚の頭は、嚢(ふくろ)に似て、肉、薄し。但し、足の肉、厚〔く〕して、味、亦、美なり。然れども、鮑(あはび)より硬〔く〕して、老いたる齒にては、食ふに、堪へず。惟〔(ただ)〕、先づ、柔-策(むち)を以つて、數々〔(たびたび)〕、之れを敲きて後、之れを煑れば、則ち、肉、軟かなり。薑醋を以つて、之れを食ふ。酒・水、等分にして、文火〔(とろび)〕を以つて煮ること、半日許〔(ばか)〕り、醬油を加へて、再び、煮れば、則ち、軟脆〔(なんぜい)〕にして、甘美、常に倍す。俗に、之れを、「關東煮」と謂ふ。
凡そ、章魚を取るに、繩を以つて、壺を絆(くゝ)り、水中に投ずれば、則ち、久しくして、章魚、自〔(みづか)〕ら、入るなり。大小と無く、壺一箇に、章魚一頭あり。北海には、乃〔(すなは)〕ち、大なる者、多く有り。一、二丈ばかりの長き足〔にて〕、若〔(も)〕し、人、及び、犬・猿、誤りて、之れに對すれば、則ち、足の疣、皮膚に吮着〔(せんちやく)=吸着〕して、殺さざると云ふこと、無し[やぶちゃん字注:「云」は送り仮名にある。]。鮹、性、芋を好(す)き、田圃に入り、芋を掘りて、食ふ。其の行(あり)くことや、目を怒(いか)らし、八足を踏みて、立行〔(りつかう)〕す。其の頭〔(かしら)〕、浮屠(ふと)の狀〔(かたち)〕のごとし。故に、俗に「章魚(たこ)坊主」と稱す。最も、死し難し。惟だ、兩眼の中間を打つ時は、則ち、死す[やぶちゃん注:「時」は送りがなにある。]。又、云ふ、「章魚、若〔(も)〕し、飢〔(うう)〕れば、則ち、己〔(おの)〕が足を、食ふ。故に、五足・六足の者も亦、間(まゝ)有り。
[やぶちゃん注:軟体動物門頭足綱八腕形上目タコ目(八腕目) マダコ(無触毛)亜目マダコ科マダコ亜科マダコ属マダコ亜属マダコ Octopus (Octopus) vulgaris 、及び、マダコ科ミズダコ属ミズダコ Enteroctopus dofleini の二種は、その典型的形状と、本邦に於いて、原則的に、前者が南(能登半島・茨城以南)を、後者が北(日本海及び茨城沖以南)をカバーする食用代表種という点で同定としては堅い。さらに、分布域も形状もミズダコに似ており、流通量も多い、マダコ科 Paroctopus 属ヤナギダコ Paroctopus conispadiceus も加えておく。「章魚」の「章」は、「印章」の意味で、吸盤からの連想であろう。なお、良安は、タコの墨について、後続のタコ類でも、一切、記載していない代わりに、後に掲げる「烏賊魚」(イカ)の項の中では「イカ墨」について語っている。変則的であるが、「タコ墨」に就いては、その「烏賊魚」の「墨」の注を是非、参照して頂きたい。
・「延喜式」は、「養老律令」の施行細則を記載した古代の法典。
・「海蛸子」の「蛸」という字は、本来、「蠨蛸(しょうそう)」は蜘蛛の一種である、よく家屋の中で見かける大型のアシダカグモ Heteropoda venatoria を指す。古人はタコを「海の蜘蛛」と見たのであろう。現在の「蛸」という用字は、この「海蛸子」の前後が省略されたものと思われる。面白いのは、「蛸」の別義にある「螵蛸(ひょうしょう)」・「蜱蛸(ひしょう)」で、オオジガフグリ(カマキリの卵塊)を指すとする。この呼称、不学にして知らなんだ。「フグリ」は金玉(睾丸)で、まさに、あの形態を言い得て妙であるが、「オオジガ」は何だろう? 「大爺がフグリ」か? 「お爺が金玉」か! これまた言い得て妙?!
・『「本草綱目」に、「鮹」、別に此れ一種とす』については、まず「本草綱目」を見よう。
*
[集解]藏器曰、『出江湖。形似馬鞭、尾有兩岐、如鞭鞘。故名。』。
([集解]藏器曰はく、『江湖に出づ。形、馬の鞭に似、尾に、兩岐、有りて、鞭鞘(べんせう)のごとし。故に名づく。』と。)
*
更に「廣漢和辭典」の「鮹」の項の字義の第一に「魚の名」とし、この「本草綱目」の引用(一部に省略があるが)に先立って以下の引用がある(書き下し文に直し、一部に読みを施した)。
*
〔廣韻〕鮹は、海魚。形、鞭鞘(べんせう)のごとし。〔集韻〕鮹は、海魚の名。形は、鞭旒(べんりう)のごとし。
*
「鞭鞘」は、中国語で「鞭の先につける細い革紐」のことで、「鞭旒」は、「細長く旗が棚引くようなタイプの鞭」を言うか。以上から「鮹」は海産(時珍は淡水産とするが)で、魚体が鞭状で、有意に細長い(時珍は、その尾部が、二叉の鞘状になるとする)ものということになる。その形状は、トゲウオ目ヨウジウオ科ヨウジウオ属 Syngnathus か、若しくは、時珍の言う尾鰭の形状から、同じトゲウオ目ヨウジウオ亜目ヤガラ科ヤガラ属 Fistularia 等を強く想起させる。本プロジェクトの底本を出版している「長野電波技術研究所」の「本草綱目」の同定ページでは、「鮹魚」をコウライシタビラメ Cynoglossus abbreviatus と同定しているのだが、形状が違い過ぎる。ともかく、中国博物学書の「鮹」は、確かに「章魚」=タコ目(八腕目)Octopoda でないことは確かである。
・「疣」は勿論、「吸盤」を指す。ここでは当然、タコとイカの吸盤構造の違いを述べておく必要があろう。タコの吸盤は、文字通り、吸い付くところの「吸盤」で、球状の一部が円柱状になって、その中央部分に窪みがあり、そこの圧力を減らして対象に吸着する。それに対して、イカの吸盤は、柄が付いたカップのような形状で、その縁にキチン質の刺(とげ)の付いたリング(これを「イカリング」とは言わないので注意)が嵌っており、それが対象を噛んで(それぞれの刺が引っかかって)保持する。一般に頭足類の雌雄判別で、♂の吸盤は、成長するに従って、大きく不揃いとなる等と言われるが、これは、必ずしも、確実にそうとは言えない。
・「頭」は勿論、生物学的には「胴」である。ここでは、当り前のことながら、タコの体制を述べておかなくてはならない。一般に「頭」と呼ぶ部分が「胴」であり(ここに「腸」=消化器官もしっかりある)、良安が述べるように、その「胴」と「足」の間に漏斗・眼、そして足に広がる高度な神経系を統御する神経叢、口を含む頭部があり、「足」=腕足が、放射状に、それに付随する(但し、口器は腕足の中央部に開口しているから、上から「胴」+「頭」+「足」という図式もインパクトがあるが、「胴」+周りに「腕足」が生えた「頭」+「口」の方がよりショッキングであり、より正しいと言えるのではあるまいか)。
先に「疣」の注で、雌雄判別について述べたが、以下も、頭足類の場合、必ず語っておかねばならない重要な特徴である。♂の判別は交接腕の有無にある。まず足の数え方から。頭足類は胴にある漏斗(総排出口。海水を噴出して推進したり、排泄したりするためのパイプで、漫画では「口」になる部分だが、言うなら、あれは「口」ではなくて「肛門」である)を正面に持ってきて、胴全体を上にし、それぞれの腕を左右から番号で、例えば、右なら、時計回りに「右Ⅱ腕」というふうに呼ぶ(但し、イカ類では左右のⅢ腕とⅣ腕の間に有意に長い採餌用の捕食腕があり、それを特に「触腕」と言って区別して呼称する)。さて、タコ類では、右の第Ⅲ腕が、イカ類では、右、又は、左、或いは、その両方の第Ⅳ腕が「交接腕」となる。では「交接腕」とは何か? それぞれの番号の腕を見ると、♀では、先端まで普通に吸盤があるだけであるが、♂は、先の部分が溝(若しくはスプーン状・叉状等様々)になっていて、吸盤がない。この部分を持つ腕を特に「交接腕」と言い、その先端こそが、「精莢(せいきょう)」と呼ばれる頭足類の不思議なオスの生殖器官(「ペニス」相当)である。♂のタコは、♀を見つけて発情すると、やおら、自分の精巣にmこの第Ⅲ腕を入れ込んで、精子の入った袋である「精嚢」を、この先端部分の溝に挟みこんで、取り出す。それを♀の体表の卵巣のそばに、突き刺し(この時、♀は相当に痛いらしい)、その後、♂は、自らその先端部を切断してしまうのである。万事順調に行けば、精嚢は次第に膨張し、最後に破裂し、目出度く受精する。ちなみに、十九世紀初頭のフランスの有名な博物学者キュビエは、♀のマダコ亜目アミダコ科アミダコ属アミダコ Ocythoe tuberculata を解剖中、この「精莢」を見つけ、「寄生虫だ!」と早合点して、ご丁寧に「百疣虫」=ヘクトコチルス・オクトポイディス Hectocotylus Octpodis という学名までつけてしまった。現在も、その勘違いに敬意を表して、この「交接腕」のことを「ヘクトコチルス」と呼んでいる。
・「皮の中に、雙(つがい)」(「つがひ」が正しい)「の小鳥のごとき者有り」とは、まさに、通称、「カラストンビ」と呼ばれる「顎板(がくばん)」を指す。スズメ目カラス科カラス属 Corvus の嘴は、一般に、太く短く真直ぐであるが、タカ目タカ科トビ属のトビ Milvus migrans のそれは、鉤(かぎ)のように曲っている。頭足類の口には、この「顎板」と呼ばれる口器があり、それが、丁度、カラスとトビ(トンビ)のそれぞれの嘴のように、一方は、比較的真直ぐで、もう一方が鉤方に湾曲している。そこから頭足類の顎板を「烏鳶(カラストンビ)」と呼ぶようになった。この二つ顎板で食いちぎられた餌は、その内側にある「口球」という器官に送り込まれ、そこにある「おろしがね」状の「歯舌」で磨り潰される。なお、この顎板、鯨類・鳥類・魚類の食性研究者にとって、食われた頭足類の種の同定になくてはならない(というより、最後は、これしか残らない)ものなのだ。見よ! 「国立博物館」公式サイト内の「頭足類の顎板による種査定に関するマニュアル」を!
・「文火」に就いては、種々の和文献もあるが、さるブログ上に、中国のドラマの一場面で『「文火(wenhuo)って何?」「文火も知らないの? 慢火(manhuo)のことよ」』という会話があったが、中国語では「慢火」とは「弱火」、ちなみに「強火」は「武火」とも言うとあった。
・「關東煮」は現在、「おでん」の異名(というよりも古名)である。「とろ火」で半日、更に醤油をさして、再び、煮込むとなれば、まさに相当に濃い出し汁の「関東炊き(かんとだき)」(この読みはそれが関西に伝わった際に訛ったもの)と言える。
・「壺」言わずと知れた蛸壺による漁法。ウィキペディアは、まさにツボを押さえて、コンパクトに纏まっている。私の好きな芭蕉の句(句のリンクは伊藤洋氏の美事な「芭蕉DB」)を掲げてるのも、好きさ♡
蛸壺やはかなき夢を夏の月 はせを
・「北海には、乃ち大なる者、多く有り」は、体長三メートル・体重四十キログラムを超える個体もいるという、世界最大種のマダコ科ミズダコ属ミズダコ Enteroctopus dofleini をおいてほかにない(北米では同種で体長五メートルの記録があるという)。
・「性、芋を好き、田圃に入り、芋を掘りて食ふ」は、かなり人口に膾炙した話であるが、残念ながら、私はこれは、一種の「噂話」「都市伝説」であると考えている。しかし、タコが、夜、陸まで上がってきてダイコン・ジャガイモ・スイカ・トマトを盗み食いするという話を信じている人は、結構、いる、のである。事実、私は千葉県の漁民が真剣にそう語るのを直に聴いたことがある。また、一九八〇年中央公論社刊の西丸震哉著「動物紳士録」等では西丸氏自身の実見談として記されている(農林水産省の研究者であった頃の釜石での話として出てくる。しかし、この人、知る人ぞ知る、人魂を捕獲しようとしたり、女の幽霊にストーカーされたり、人を呪うことが出来るなどとのたまわってしまう人物である。いや、その方面の世界にいる時の私は、実はフリークともいえるファンなのだが)。実際に全国各地でタコが畠や田んぼに入り込んでいるのを見たという話が古くからあるのだが、生態学的にはタコが海を有意に離れて積極的な生活活動をとることは不可能である。心霊写真どころじゃあなく、実際にそうした誠に興味深い生物学的生態画像が頻繁に見受けられるのであれば、当然、それが識者によって、学術的に、好事家によって、面白く、写真に撮られるのが道理である。しかし、私は一度として、そのような決定的な写真を見たことがない(タコ……じゃあない、イカさまの見え見え捏造写真なら、一度だけ見たことがあるが、余程、撮影の手際の悪いフェイクだったらしく、可哀想に、タコは上皮がすっかり白っぽくなり、芋の葉陰に、ぐったり横たわっていた)。これだけ携帯が広がっている昨今、何故、タコ上陸写真が何故、流行らない?!? 冗談じゃあ、ない! 信じている素朴な人間がいる以上、私は「ある」と真面目に語る御仁は、それを証明する義務があると言っているのである。たとえば、岩礁帯の汀で、カニ等を捕捉しようと、岩上に、たまさか、上がったのを見たり、漁獲された後に逃げ出したタコが、畠や路上で蠢くのを誤認した可能性が高い(タコは「海の忍者」と言われるが、海中での体色体表変化による擬態や、目くらましの墨以外にも、数十センチメートルの大型の個体が、蓋をしたはずの水槽や、運搬用パケットの極めて狭い数センチメートルの隙間等から容易に逃走することが出来ることは、頓に知られている)。さらに、タコは雑食性で、なお且つ、極めて好奇心が強い。海面に浮いたトマトやスイカに抱きつき食おうとすることは十分考えられ(クロダイはサツマイモ・スイカ・ミカン等を食う)、さらに意地悪く見れば、これはヒトの芋泥棒の偽装だったり、「蛸研究会」の以下のページにあるような(西丸氏の上記の記事も載る)、禁漁期にタコを密猟し、それを芋畑に隠しているのを見つけられ、咄嗟にタコの芋食いをでっち上げた等々といった辺りこそが、この伝説の正体ではないかと思われるのである。いや、タコが芋掘りをするシーンは、是非、見たいぞ! 信望者の方は、是非、実写フィルムを! 海中からのおどろどろしきタコ上陸→農道を「目を怒らし、八足を踏みて立行す」るタコの勇姿→腕足を驚天動地の巧みさで操りながら器用に地中のジャガイモを掘り出すことに成功するタコ→「ウルトラQ」の「南海の怒り」のスダールよろしく、気がついた住民の総攻撃をものともせず、悠々と海の淵へと帰還するタコ……だ(円谷英二は、あの撮影で、海水から出したタコが、突けど、触れど、一向に思うように動かず、すぐ弱って死んでしまって往生し(洒落じゃないよ)、「生き物はこりごりだ」と言ったと聴く)。
・「浮屠」は「浮図」とも書く仏教用語。本来は梵語のbuddha(=仏陀)の漢訳であったが、転じて「僧侶」の意に用いた。
・「兩眼の中間」――誰でも脳をぶち割られれば、死ぬ。タコは眼球の周縁部分に大きな神経叢(「脳」と言ってよい)を持っている。
・「若し、飢れば、則ち、己が足を食ふ」は、都市伝説では、一応、ない。まず、タコには蜥蜴(とかげ)の「尻尾切り」と同じ防御機能としての自切行動がある。タコはウツボ等の天敵に襲われると、噛み付かれた足を自切して、逃げる。もげた足は、後に再生する。そうしてタコは、自分の足をもいで、食うことも、まれにあるらしい。但し、それはタコの場合、水族館等で狭い水槽に何匹も住まわせたりすることで、ノイローゼに罹ったタコのする異常行動であるらしい(タコは一般に交尾期以外は排他的で孤独相を好む)。いや、そんなことをする前に、だいたいの病んだイカ・タコは、墨を吐き尽くして弱って死んでしまうことの方が圧倒的に多い。頭足類は、概ね、非常に神経質で、水槽のガラスを叩く音や、円形回遊式でない水槽内では、ストレスを起こして人並みのノイローゼになってしまう(これまた、その前に、壁やガラスに胴頂部が激突損傷し、弱って死んでしまうことが多い)。円形水槽も水槽の絶対数も少なかった以前の水族館では、イカ・タコは飼育しにくい動物の筆頭に挙がっていたものである。それにしてもノイローゼに罹るイカ・タコとは、彼らが人間並みなのか? いやいや、それとも、我々の方が、イカ・タコ並みなのか? さてもどっちだろう?
足の数が少ないことを見たら、その逆も話したくなるな。タコは英語でオクトパス“octpus”だが、これは、ラテン名オクトプスに由来し、ギリシャ語の“octo”「八本の」と“pous”「足」の合成語である。しかし、突然変異で七本とか、十数本足のタコが稀に見つかる。現在までに記録に残された最多例は、昭和三二(一九五七)年八月、三重県鳥羽市答志島沖合で、漁師の中村勘三郎氏によって捕獲されたもので、実に八十五本足であった。これは恐らく世界一の記録である。今も標本として残されている。私は一九七一年の富山の伏木中学校の関西修学旅行の途中、今のバリバリの建物からは想像も出来な~い、冷た~い~ぼ~ろぼろのお化け屋敷みたよ~な暗~い鳥羽水族館の一室で、これを、見た。いや、慄っとした。
そうしてトリはやはり、私の私淑する萩原朔太郎の、そして、その詩の中でもいっとう好きなこの一篇に登場してもらわねばなるまい(昭和一四(一九三九年刊の散文詩集「宿命」より。底本は筑摩書房版「定本萩原朔太郎全集」を用いた)。
*
死なない蛸 萩原朔太郞
或る水族館の水槽で、ひさしい間、飢ゑた蛸が飼はれてゐた。地下の薄暗い岩の影で、靑ざめた玻璃天井の光線が、いつも悲しげに漂つてゐた。
だれも人人は、その薄暗い水槽を忘れてゐた。もう久しい以前に、蛸は死んだと思はれてゐた。そして腐つた海水だけが、埃つぽい日ざしの中で、いつも硝子窓の槽にたまつてゐた。
けれども動物は死ななかつた。蛸は岩影にかくれて居たのだ。そして彼が目を覺した時、不幸な、忘れられた槽の中で、幾日も幾日も、おそろしい飢饑を忍ばねばならなかつた。どこにも餌食がなく、食物が全く盡きてしまつた時、彼は自分の足をもいで食つた。まづその一本を。それから次の一本を。それから、最後に、それがすつかりおしまひになつた時、今度は胴を裏がへして、内臟の一部を食ひはじめた。少しづつ他の一部から一部へと。順順に。
かくして蛸は、彼の身體全體を食ひつくしてしまつた。外皮から、腦髓から、胃袋から。どこもかしこも、すべて殘る隈なく。完全に。
或る朝、ふと番人がそこに來た時、水槽の中は空つぽになつてゐた。曇つた埃つぽい硝子の中で、藍色の透き通つた潮水(しほみづ)と、なよなよした海草とが動いてゐた。そしてどこの岩の隅隅にも、もはや生物の姿は見えなかつた。蛸は實際に、すつかり消滅してしまつたのである。
けれども蛸は死ななかつた。彼が消えてしまつた後ですらも、尙ほ且つ永遠に
*
なお本注記に当たっては、私自身がかつて生徒のために書き下ろした「藪だこのひとりごと」を参考にした。「たこ焼き」の話など、興味のある方は、是非、お読みあれ!]
***
てなかたこ 石鮔
【俗云手長鮹】
石距
本綱石距亦章魚之類身小而足長入鹽燒食極美也
△按蛇入江海變石距人有見其半變者故多食則食傷
*
てながだこ 石鮔
【俗に「手長鮹」と云ふ。】
石距
「本綱」に、『石距〔(てながだこ)〕は亦、章魚(たこ)の類〔にして〕、身、小にして、足、長し。鹽を入れ、燒き食ふ。極美なり。』と。
△按ずるに、蛇(くちなは)、江海に入りて、石距に變ず。人、其の半〔(なかば)〕、變〔(へん)〕なるを、見たる者、有り。故に、多く食へば、則ち、食傷〔(しよくしやう):食あたり。〕す。
[やぶちゃん注:マダコ科マダコ属テナガダコ Octopus minor である。全長七十センチメートルに達し、腕部は胴の五倍を越える。韓国で踊り食い(「サンナクチ」)されるのは本種である(「在大韓民国日本国大使館」公式サイト内の、『「ナクチ」と「蛸」と「違い」の話 』という面白いコラムがある)。本叙述の中にもあるように、古くから蛇が蛸に変ずることはかなり古くから信じられており、結果、「テナガダコ」という呼称を妖怪とするweb上の記述さえもある始末だ。これについて、南方熊楠はその「蛇に関する民俗と伝説」(大正六(一九一七)年)の「十 蛇の変化」の中で、例の立て板にゲロ、じゃあなかった水の名調子で、以下のように記す(底本は平凡社版「南方熊楠選集1」を用いた。〔 〕の読みは私が加えたもの)。
*
西土にも蛇が修役を積んで竜となる説なきにあらず。古欧州人は蛇が他の蛇を食えば竜と化(な)ると信じた(ハズリットの『諸信および民俗』)。ハクストハウセン説に、トランスカウカシア辺で伝えたは、蛇中にも貴族ありて人に見られずに二十五歳経(た)たば竜となり、諸多の動物や人を紿(あざむ)き殺すため、その頭を何にでも変じ得、さて六十年間人に見られず犯されずば、ユクハ(ペルシア名)となり、全形をどんな人また畜にも変じ得、と。天文元年の著なる『塵添壒嚢抄〔じんてんあいのうしょう〕』八に、蛇が竜になるを論じ、ついでに蛇また鰻に化(な)ると言い、『本草綱目』にも、水蛇が鱧(はも)という魚に化るとあるは形の似たるより謬ったのだ。文禄五年筆『義残後覚』四に、四国遍路の途上船頭が奇事を見せんというゆえ、蘆原にある空船に乗り見れば、六、七尺長き大蛇水中にて異様に旋(まわ)る、半時ほど旋りて胴中炮烙(ほうろく)の大きさに膨れ、また舞う内に後先(あとさき)おのおの二に裂けて四となり、また舞い続けて八となり、すなわち蛸(たこ)と化(な)りて沖に游(およ)ぎ去ったと見ゆ。例の『和漢三才図会』や『北越奇談』、『甲子夜話』などにも、蛇、蛸に化る話あり。こんな話は西洋になけれど、一八九九年に出たコンスタンチンの『熱帯の性質(ラ・ナチュール・トロピカル)』に、古ギリシアのアポロン神に殺された大蛇ピゾンが多足の竜ヒドラに化ったというは、蛇が蛸になるを誇張したのであろうとあるは、日本の話を聞いて智慧つけたのかそれとも彼の手製か、いずれに致せ蛸と蛇とは似た物と見えるらしい。
ただに形の似たばかりでなく、蛸類中、貝蛸(かいだこ)オシメエ・トレモクトプス等諸属にあっては、雄の一足非常に長くなり、身を離れても活動し雌に接して子を孕ます。往時学者これを特種の虫と想い、別に学名を附けた。その足切れ去った跡へは新しい足が生える。古ギリシア人は日本人と同じく蛸飢うれば自分の足を食うと信じたるを、プリニウスそは海鰻(はも)に吃い去らるるのだと駁撃(ばくげき)した。しかし宗祇『諸国物語』に、ある人いわく、市店に売る蛸、百が中に二つ三つ足七つあるものあり、これすなわち蛇の化するものなり。これを食う時は大いに人を損ずと、怖るべしと見え、『中陵漫録』に、若狭小浜の蛇、梅雨時章魚(たこ)に化す。常のものと少し異なるところあるを人見分けて食らわず、と言える。『本草啓蒙』に、一種足長蛸、形章魚(たこ)に同じくして足最(いと)長し、食えば必ず酔い、また斑(ぶち)を発す。雲州でクチナワダコと言い、雲州と讃州でこは蛇の化けるところという。蛇化のこと若州に多し。筑前では飯蛸(いいだこ)の九足あるは蛇化と言う。八足の正中(まんなか)に一足あるを言うと記せるごとき、どうもわが邦にも交合に先だって一足が特に長くなり、体を離れてなお蠕動(ぜんどう)する、いわゆる交接用の足(トクユチルス[やぶちゃん注:ママ。「章魚」で注した「ヘクトコチルス」のこと。]、第十二図)が大いに発達活動して蛇に肖(に)た蛸あり。それを見謬って蛇が蛸に化(な)るといったらしい。キュヴィエーいわく、欧州東南の海に蛸類多きゆえに、古ギリシア人蛸を観察せる事すこぶるつまびらかで、今日といえども西欧学者の知らぬ事ども多し、と。わが邦またこの類多く、これを捕るを業とする人多ければ、この蛇が蛸に化る話なども、例の一笑に附せず、静かに討究されたいことじゃ。それから蛸と同類で、現世界には化石となってのみ蹟(あと)を留むるアンモナイツは、漢名石蛇というほど蟠(ま)いた蛇に酷(よく)似おる。したがって、アイルランド人はその国にこの化石出づるを、パトリック尊者が国中の蛇をことごとく呪して石となし、永くこれを除き去った明証と誇る由(タイラー『原始人文篇(プリミチヴ・カルチュール)』一巻一〇章)。一昨年三月号一六三頁にその図あり。
↑第十二図 貝蛸の雄の交合用の足まさに離れ去らんとするところ
↑石蛇[やぶちゃん注:引用文末が指示している「アンモナイツ」の図。これは前年に発表した熊楠の「田原藤太竜宮入りの譚」の第二十二図である。頭足綱†アンモナイト亜綱Ammonoidea のアンモナイト(英名:Ammonite)である。]
*
ここで熊楠は「貝蛸オシメエ・トレモクトプス等諸属」と記すが、これは「貝蛸・オシメエ・トレモクトプス等」の三並列の意と思われる。即ち、頭足類である貝蛸=アオイガイ属 Argonauta ・オシメエ属・ムラサキダコ属 Tremoctopus 等の多くの属に、という意味である。しかし「オシメエ」という属は八腕類には見当たらない(御教授を乞う)。なお、上記の論文の正字の原稿(上掲のものとはかなり違う)を元にしたものが、国立国会図書館デジタルコレクションの渋沢敬三編「南方熊楠全集」(乾元社一九五一年刊)の「第一卷 十二支考 Ⅰ」のここ(同章の第二段落の『古い歐洲人は蛇が他の蛇を食へば龍と化ると信じた(ハズリットの諸信及俚傳一)。……』以下が相当する)から視認出来るので、見られたい。
さても。この「和漢三才圖會」電子化プロジェクトの最初の動機は、南方熊楠の幼年期の本書の暗誦筆記である。「藪」に「熊」は、これ、いい取り合わせじゃあねえか!
熊楠に拘って、彼が挙げる文献の幾つかを見ていこう。
まず、文禄五(一五九六)年の世間話集「義残後覚」巻四に現れる蛇から蛸への変化の様子であるが、ここは、今回(二〇二三年の再改訂)、国立国会図書館デジタルコレクションの「續史籍集覽」第七冊(近藤瓶城編・昭和五(一九三〇)年近藤出版部刊)の当該部「大蛸の事」で、前半のパート(大蛇と大蛸の戦い)も含め、全部を視認して電子化した。但し、「し」の「志」の字の崩しや、「ハ」のカタカナ、踊り字「〱」「〲」は正字化し、読み易さを考えて、段落や記号を追加して、読みは私が推定で歴史的仮名遣によって( )で補った。また、漢字が少なく、却って読み難いことから、《 》で推定で正字漢字を私が添えた。
*
大蛸の事
爰に、丹後のくにゝ竒妙なる松あり。一はう《方》は、さうかい《滄海》、まんまんとして、きわ[やぶちゃん注:ママ。]も、なし。みきは《汀》のかたは、青りん、がゝと、そびえて、苔(こけ)、なめらかなり。[やぶちゃん注:「青林」では、以下の「峨々と聳えて」呼応が可笑しい。「青」は「碧」で、「りん」は「けん」で「嶮」、「青緑色の岩山」か?]
このいはほの上に、彌々(いよいよ)、うへにありて、えだ葉、うみのうへゝ、なげかけたり。
これ、いかんと、申(まふす)に、ちかきころの事なるは、六月なかばに、大蛇の、山よりいでゝ、この松に、まとひつきて、こう《甲》をほして、あそべり。
そのたけは、十五、六ひろも、ありぬべし。[やぶちゃん注:「十五、六」尋は、二十七~二十八・八メートル。]
まなこ・くちぎはの、すさまじさは、ものにたとへんかた、なし。
かゝる所に、海中より、大なみ、こなみ、けだてゝ《蹴立てて》、きほひきたるもの、あり。
「なになるらん。」
と、見ければ、そのあたまは、一けん四はう《方》を、まろめたるほどなる、たこの八(やつ)の手を、うちかけ、うちかけ、大なみ、こなみ、おしきつて、このいはほのかたへ、きたりて、大じやを、
「きつ」
と、みて、いかにして、是をとるべき、きしよく《氣色》なり。[やぶちゃん注:「一」間は約一・八二メートル。]
大じやは、また、このたこをみて、とつてのむべきけしき《氣色》なり。
兩はう《方》、たがひに、『ねらひあひけるがな』にと思ひけるやらん。
たこは、すこし、しりぞくやうに見えけるが、大じやは、とびかゝるきしよくにて、かしらを、さしのべ、手をいだすところを、たこの、
「へたへた」
と、てを、いだして、じやを、まきけり。
じやは、たこのあたまを、くらいつかんと、手をのぶる。
しかれども、じやは、この松を、五まとひほど、まとふ。
たこは、又、じやを、八ツのてにて、
「ひたひた」
と、まく。
虵(じや)は、たこを、まきあげんとす。
たこは、じやを、うみへ引(ひき)おとさんとす。
たこのちからや、つよかりけん、松ともに、下へ引(ひき)おとし、海へ、つゐに、大じやを引こみける。
なかにては、じやを、なにとしたるも、しらず。
松は、このとき、ね《根》を、かへしてけり。
しかれども、かたえだのかたなる、ねの、いさゝか、いはにとり付(つき)て、大木となりて、枝葉さかへけり。
よのなかに、たこといふもの、大なるは有(ある)といへども、かゝる大じやを、まきこむほどのたこは、つゐに[やぶちゃん注:ママ。]わがてう《朝》にて、きゝをよばず[やぶちゃん注:ママ。]。
ある人のいはく、
「ふねに『あやかし』といふものゝつくときは、かいしき、ふねが、うごかずして、なにともならず、めいわくす事、あり。その『あやかし』といふは、此たこなり。」
と、いへり。[やぶちゃん注:「かいしき」「怪しき」で「怪しいことに」の意か。]
龍虎のせうぶ[やぶちゃん注:ママ。「勝負」。]は、あり、と、むかしより、いへども、たこと、大じやの勝負は、まことに珍しき物がたりなれば、こゝに記すなり。
また、四こくへんろしたる人のいはく、
「四こくのうちにて、雨のはれまに、みきはのかたへ、いでゝ、
『空のけしき、いかゞあるべし。』
と同行(どうぎやう)とも、みる所に、あけ舟に乘りたる船頭の、
『なう、たび人たち、はやく、おはせよ。きとくなる事を、みせん。』[やぶちゃん注:「なう」。呼びかけ。「さあ!」。]
といふほどに、蘆はらを、二、三げんがあひだ、ふみ分(わけ)て、舟にのりてみれば、ながき、六、七尺もあるらんと、みえける「大くちなわ」[やぶちゃん注:ママ。以下同じ。]の、水中にて、
『きりきり』
と、まふ《舞ふ》事、よのつね、ならず。
半時ばかり、まふてければ、筒中(どうなか)とおぼしきところ、ほうろくの大きさに、まろく、ふくれ、
『ふしぎや。』
と見る所に、又、
『きりきり』
まふほどに、しばらくありて、あとさき、二ツづゝに、さけたり。
みれば、四ツになりけり。
それより、又、まふ事、やゝしばらくありて、四ツの手をさけて、八ツになりたり。
めだゝき[やぶちゃん注:「瞬き」に同じ。]する内に、このくちなわ、蛸となりにけり。
そのゝち、沖をさして、およぎゆきしなり。
人々、
『さても、ふしぎなる事を、みつるものかな。かゝることもあるならいかや。』
とて、よくよく、みおきて、ものかたりにしたりけり。
*
その前に挙げる「北越奇談」であるが、私は二〇一七年九月に同書の電子化注を終えているのであるが、いっかな、見出せないでいる。これは、ちょっとおかしい。しかし、これを熊楠の勘違いとしつつ、良心的に「北越」地方の「奇談」と読み替えるならば、ズバり、ある。私の「怪奇談集」の最初の電子化注の中の「佐渡怪談藻鹽草 蛇蛸に變ぜし事」である。さらに、北越から東北まで広げると、「谷の響 二の卷 三 蛇章魚に化す」が、それに当該する。特に後者は、私の真相推理説が、結構、気に入っている。見られたい。
次は、文政四(一八二一)年から二十年間を費やして書かれた博覧の平戸藩主松浦(まつら)静山の随筆「甲子夜話」。その正編巻七十六の十一にある。これは蛇の蛸と化すフォークロアの優れた記載と検証であり、熊楠も、この記事に多くを拠っていると思われる。今回の二〇二三年の新改訂に合せて、ブログ・カテゴリ「甲子夜話」で、「フライング単発 甲子夜話卷之七十六 11 蛇、鮹に變じ、蟾蜍、魚となる」として公開しておいたので、そちらを見られたい。
次は、「宗祇諸国物語」であるが、これは同書の巻之一「無足の蛇 七手の蛸」の後半に現われる。宗祇が肥後の宇土長浜の連歌数寄の荻生房高(おぎうふさたか)のもとを訪ね、うららかな一日、共に磯をそぞろに名所を訪ねるうち、不思議な蛇を見出す。これは、独立したブログ・カテゴリ『「宗祇諸國物語」 附やぶちゃん注【完】』で二〇一六年に全電子化注を終えている。「宗祇諸國物語 附やぶちゃん注 無足の蛇 七手の蛸」が当該話である。見られたい。
続いて、文政九(一八二六)年の佐藤成裕「中陵漫録」のそれは、国立国会図書館デジタルコレクションの昭和四(一九二九)年日本随筆大成刊行会刊の『日本隨筆大成』第三期第二巻の当該部を用いて、正字で示した。読点を増やし、( )は私の補った読みである。
*
○蛇化二章魚一〔蛇章魚に化す〕
藷蕷(やまいも)、鰻鱺〔うなぎ〕に化す事、疑ひなし。鰻鱺、藷蕷、化すこと、「龍宮船」に見えたり。又、若州小浜の蛇は、五月、梅雨(つゆ)の時、海邊(うみべ)に出(いで)て章魚(たこ)に化す。此邊(このあたり)の人、常に見て、しる處なり。常に章魚より、少し、異(ことな)る處あるが、人、見分(みわけ)て、是を食せず、と云(いふ)。
*
南方熊楠の後追いに終わるのも、如何にも癪である。この際、もう少し、オリジナルに引こう。
伴蒿蹊(ばんこうけい)の「閑田耕筆」から。底本は国立国会図書館デジタルコレクションの『日本隨筆大成」卷九(昭和二(一九二七)年刊)の当該部を用いた。読点を追加した。このカタカナのルビは底本のもので、ひらがなのそれは私が添えたものである。
○章魚(タコ)の内に、あるひは[やぶちゃん注:ママ。]蛇に化するもの有(ある)といふ。ある人の話に、越前にて大巖(おほいはほ)にふれて尾を裂(サキ)たるが、つひに、脚(あし)に成りたり。其間(そのかん)、時をうつせしと、いへりし。又、使(つかは)し僕(しもべ)も彼國の者にて、是は、山より、小蛇、あまた下り來て、水際(みづギハ)に漬(ヒタ)り、小石にふれ、漸々(ぜんぜん)に、化して、水に入(いり)たりと、いひき。彼邊(かのあたり)にては、折々、有(ある)事ならし。
*
――サアサア!――最後に控けえしは! 曲亭馬琴の「兎園小説」也! 報告者は、江戸時代のUFOのような奇体な乗り物の漂着事件で今にブレイクしている、『曲亭馬琴「兎園小説」(正編) うつろ舟の蠻女』と同じく、親馬鹿馬琴の息子で、医師の琴嶺舎である(実際には、馬琴の代筆部分が多い)。元は、ここに全電子化を置いていたが、「兎園小説」は、その「兎園小説拾遺」に至る全続集全篇の電子化注を、昨年、完遂しているので、最も完備させた『曲亭馬琴「兎園小説」(正編) 蛇化して爲ㇾ蛸』をリンクさせておく。]
***
いひたこ
望潮魚
鱆魚【共出于
閩書】
【俗云飯鮹】
[やぶちゃん字注:以上三行は、前二行下に入る。]
△按望潮魚狀類章魚而小凡五六寸許其頭如鳥印〔→卵〕頭
中滿白肉煮食其肉粒粒如蒸飯味亦然故名飯鮹足
亦軟美正二月盛出播州髙砂之產頭中之飯多攝泉
《改ページ》
■和漢三才圖會 江海無鱗魚 卷ノ五十一 ○十九
之產無飯者亦相半至季春則魚瘦而無飯余月全無
東北海亦曾無之取之繫榮螺空貝投之則久而鱆入
貝此鱆亦頭與股中間如鳶鴉者有之
貝鮹 大如鱆魚而無飯毎一頭生貝中其貝白狀似秋
海棠葉形日本紀私記云貝鮹【和名加比太古】是矣【詳于貝類之下】
蜘蛛鮹 似蛸而最小頭如雀卵加州越州有之播州明
石取之乾送四方以似蜘蛛名之和名抄所謂小鮹魚
【知比佐木太古】是矣
*
いひだこ
望潮魚
鱆魚〔(しやうぎよ)〕【共に「閩書〔(びんしよ)〕」出づ。】
【俗に「飯鮹」と云ふ。】
△按ずるに、望潮魚は、狀〔(かたち)〕、章魚〔(たこ)〕の類にして、小さく、凡そ五、六寸ばかり。其の頭〔(かしら)〕、鳥〔の〕卵〔(たまご)〕のごとく、頭〔の〕中に、白き肉を滿つ〔→滿たす〕。煮て食ふ。其の肉、粒粒〔として〕、蒸飯(〔むし〕めし)のごとく、味も亦、然り。故に「飯鮹」と名づく。足、亦、軟にして、美なり。正・二月、盛んに出づ。播州髙砂の產は、頭〔の〕中の飯、多し、と。摂〔=摂津〕・泉〔=和泉〕の產、飯、無き者、亦、相〔(あひ)〕半ばす。季春〔:三月。〕に至りて、則ち、魚、瘦(やせ)て、飯、無し。余月は、全く、無く、東北海には亦、曾て、之れ、無し。之れを取るに、榮-螺-空-貝(さゞいがら)を繫(つな)ぎて、之れを投ずれば、則ち、久しくして、鱆、貝に入る。此の鱆も亦、頭と股との中間に、鳶・鴉のごとくなる者、之れ、有り。
貝鮹(かひだこ) 大いさ、鱆魚〔(いひだこ)〕のごとくにして、飯、無し。毎〔(つねに)〕一頭、貝〔の〕中に生ず。其の貝、白く、狀、秋海棠の葉の形に、似たり。「日本紀」の「私の記」に云ふ「貝鮹」【和名、「加比太古」。】、是れか。【貝類の下に詳〔(くは)し〕。】
蜘蛛鮹(くもだこ) 蛸に似て、最も小さく、頭、雀の卵のごとく、加州〔=加賀〕・越州〔=越前・越中・越後〕に、之れ、有り。播州明石に之れを取る。乾かして、四方に送る。蜘蛛に似たるを以つて、之れを名づく。「和名抄」に所謂、「小鮹魚」【「知比佐木太古〔(ちひさきたこ)〕」。】、是れか。
[やぶちゃん注:イイダコ Octopus ocellatus 。全長約五~二十センチメートルという小振りである以外は、マダコに似ているが、両眼の間に一箇所の長方形に似た模様があること、更に、腕の付根の眼球に近い辺りに丸い金色に縁取られた二箇所の紋が特徴となる。♀の胴の内部の小さな米粒形のものは、勿論、肉ではなく、卵塊である。一匹の♀は凡そ二百から六百粒の卵を持つという。産み付けられた卵塊は、植物のフジの花が垂れ下がるのに似ることから、「海藤花(かいとうげ)」と呼ばれるが、これは一般には、タコ類の卵を広く呼び、古くは「すぼし」にし、後に「塩漬け」「麹塩漬け」にし、兵庫県明石市の名産として、今に知られる。
・「閩書」は、明の何喬遠(かきょうえん)撰になる閩(福州・泉州・厦門等の現在の福建省辺りを指す)の地誌。
・「播州髙砂」は、現在の兵庫県高砂市。
・「之れを取るに」とあるが、イイダコの漁法としてよく知られているのは、白い物に対して敏感に反応する習性を利用したもので、白ければ、オールマイティで、餌としては、辣韮(ラッキョウ)に始まり、陶器・豚の脂身・葱などを、釣り糸の先に結わえて、底引きをする。良安のようなサザエ等の貝殻(これは斧足類でも可能である)を用いるやり方は、大阪で寛政一一(一七九九)年に出た「日本山海名產圖會」に、アカニシを用いた方法が、「○漁捕(ぎよほ)は、長さ、七、八間のふとき縄に、細き縄の一尋許りなるを、いくらもならび付けて、其の端(はし)每に、赤螺(あかにし)の壳(から)を括りつけて、水中に投(たう)す。潮(しほ)のさしひきに、波、動く時は 海底に住みて、穴を求(もと)る[やぶちゃん注:ママ。「もとむ」の脱字であろう。]が故に、かの赤螺に隱る。これを、ひきあぐるに、貝の動けば、尚、底深く入りて、引き取るに用捨なし。」と示されている。私は「日本山海名產圖會」の全篇をブログで正規表現・図入りで電子化注を二〇二一年に終えているが、当該部は、「日本山海名産図会 第四巻 蛸・飯鮹」の一節であるので、見られたい。
・「貝鮹」は、私の電子テクスト「和漢三才圖會 卷第四十七 介貝部 寺島良安」のラストの「貝鮹」の項を参照されたい。
・『「日本紀」の「私の記」』とは、平安期に書かれたり、なされたりした「日本書紀」についての注釈研究・講筵の記録を指す。これが、どの部分を指すのかは不明だが、「日本書紀」には、菟道貝鮹皇女(うじのかいたこのひめみこ:「菟道磯津貝皇女」「静貝王)」とも書く) という女性が出てくる。おまけに、この人、聖徳太子の妃である。古代史は苦手でね、これぐらいにしてボロが出ないようにしよう。
・「蜘蛛鮹」についてであるが、これは現在のクモダコ Octopus longispadiceus ではなく、前述の全く同じイイダコを指していると考える。根拠の一つは、現在の明石で主に食用として捕獲されるタコは、マダコ・イイダコ・テナガダコの三種であること、クモダコは全国的に見ても一般的な種ではない点、更に、以下に引用する地元での識者の実際的観察によって最早明らかであると思う(明石淡路フェリー株式会社「明石海峡タコだより vol.6 蜘蛛ダコって?」より(二〇二三年現在、消失している)。『でも、時折「クモダコ」という呼び名も耳にする。昆虫のクモのようなタコを探しても、別の種類が目に付くわけでもない。どうやら、胴に黒い筋が入り、金色の丸印を模様とするイイダコがそれらしい。真冬に胴の中ぎっしりと飯粒のような卵を持っていないものをクモダコと呼び分けたのではないだろうか』とある。これくらい安心して同定出来ると、気持ち、いいね!
***
いか
烏賊魚
ウヽ ツヱツ イユイ[やぶちゃん字注:「ツヱツ」の最後の「ッ」は有意に小さく、且つ右に寄せて書かれている。]
鰞鱡 烏鰂
墨魚 纜魚
【和名以加】[やぶちゃん字注:以上三行は、前三行の下に入る。]
本綱烏賊魚狀若革嚢無鱗有鬚黒皮白肉大者如蒲扇
口在腹下八足聚生于口旁其兩鬚如帶甚長背上有一
《改ページ》
骨厚三四分狀如小舟而兩頭尖輕虛而白脆重重有紋
以指甲可刮爲末名海螵蛸亦鏤之爲鈿飾又腹中血及
膽正如墨可以書字但逾年則迹滅惟存空紙爾此魚遇
風波則以鬚下矴或粘石如纜故名纜魚性嗜鳥〔→烏〕毎自浮
水上飛鳥〔→烏〕見之以爲死而啄之乃卷取入水而食之因名
烏賊過小滿則形小也又云此是本𪇰鳥所化今其口腹
具存猶頗相似【𪇰似鶂見于水禽部】
肉【酸、平。】 益氣强志 其墨能治心痛【以醋服之】
海螵蛸 烏賊骨能治婦人血閉不足症【炙黃入藥味鹹微溫】唾血
下血又止瘡多膿汁不燥
三才圖會云烏賊腹中有墨見人及大魚常吐墨方數尺
以混其身人反以是知取之
△按烏賊形狀如上攝漁人以銅作烏賊形其鬚皆爲鈎
真烏賊見之自來則罹鈎蓋此見巳〔→己〕輩而慕乎嫉乎
烏賊亦頸之交有如鳶鴉者
*
いか
烏賊魚
ウヽ ツヱツ イユイ
鰞鱡〔(うそく)〕 烏鰂〔(うそく)〕
墨魚 纜魚〔(らんぎよ)〕
【和名、「以加」。】
[やぶちゃん字注:以上三行は、前三行の下に入る。]
「本綱」に、『烏賊魚は、狀〔(かたち)〕、革嚢のごとく、鱗、無し。鬚、有り。黑き皮、白き肉。大なる者は、蒲扇のごとし。口、腹の下に在り。八つの足、口の旁に聚〔(あつま)〕り生ず。其の兩鬚、帶のごとく、甚だ、長し。背の上に、一骨、有り。厚さ三、四分、狀、小舟のごとくにして、兩頭、尖り、輕虛にして、白く、脆し。重重〔(かさねがさね)〕に、紋、有り。指の甲(つめ)を以つて、刮(こそ)げて、末〔(まつ)〕と爲すべし。「海螵蛸(いかのかう)」と名づく。亦、之れを鏤(ちりば)め、鈿飾〔(でんしよく)〕と爲す。又、腹中の血、及び、膽〔(きも)〕、正〔(まさ)〕しく、墨のごとし。以つて、字を書くべし。但し、年を逾(こ)ゆれば、則ち、迹(あと)滅(き)へて、惟だ、空紙〔:白紙。〕を存するのみ。此の魚、風波に遇ふときは、則ち、鬚を以つて、矴(いかり)を下す。或いは、石に粘(つ)いて纜(ともづな)のごとし。故に「纜魚〔(らんぎよ)〕」と名づく。性、烏を嗜(す)く。毎〔(つね)〕に、自らを、水上に浮く。飛〔ぶ〕烏、之れを見て、以つて死にたりと爲して、之れを啄(ついば)むを、乃〔(すなは)〕ち、卷き取りて、水に入れて、之れを食ふ。因りて「烏賊」と名〔(なづ)〕く。小滿を過ぐれば、則ち、形、小に〔なる〕なり。又、云ふ、此れは、是れ、本〔(も)〕と、鳥の化する所、今、其の口・腹、具さに存して、猶ほ頗る相似たり【𪇰は鶂に似たり。「水禽部」を見よ。】。』と。
肉【酸、平。】 氣を益し、志を强くす。 其の墨は、能く、心痛を治す【醋を以つて、之れを服す。】
海螵蛸(いかのかう) 烏賊〔の〕骨、能く、婦人の血閉・不足の症を治す【炙り、黃にして、藥に入る。味、鹹、微〔(すこ)〕し溫。】唾血〔:唾液や痰に血が混じること。〕・下血、又、瘡〔(かさ)〕多く、膿〔の〕汁、燥(かは)かざるを止む。
「三才圖會」に云ふ、『烏賊は、腹の中に、墨、有り。人及び大魚に見〔(まみえ)〕ば、常に墨を吐くこと、方〔(はう)〕數尺、以つて、其の身を混ず。人、反りて、是れを以つて知りて、之れを取る。』と。
△按ずるに、烏賊の形狀、上のごとし。漁人、銅を以つて、烏賊の形(なり)に作り、其の鬚を皆、鈎(つりばり)と爲す。真の烏賊、之れを見て、自〔(おのづか)〕ら來り、則ち、鈎に罹(かゝ)る。蓋し、此れ、己が輩〔(うから)〕を見て、慕(した)ふか、嫉〔(そね)〕むか。
烏賊にも亦、頸の交(あはひ)に、鳶・鴉のごとき者、有り。
[やぶちゃん注:イカは軟体動物門 Mollusca 頭足綱 Cephalopoda 十腕形上目 Decapodiformes に属する生物の総称。目レベルでは、コウイカ目 Sepiida ・ダンゴイカ目 Sepiolida ・トグロコウイカ目 Spirulida ・ツツイカ目 Teuthida に大別され、三十を越える科に分かれるが、実際に本邦で食用に供される種類は、その殆んどが、
コウイカ目コウイカ科 Sepiidae
ツツイカ目ヤリイカ下目(閉眼下目) Myopsida ヤリイカ科(ジンドウイカ科) Loliginidae
ツツイカ目スルメイカ下目(開眼下目) Oegopsida アカイカ科 Ommastrephidae
の三科に含まれ、それ以外では、
ツツイカ目スルメイカ亜目ホタルイカモドキ科 Enoploteuthidae ホタルイカ属ホタルイカ Watasenia scintillans
ツツイカ目スルメイカ下目ソデイカ科 Thysanoteuthidae ソデイカ属ソデイカ Thysanoteuthis rhombus
ツツイカ目スルメイカ下目テカギイカ科 Gonatidae ドスイカ属ドスイカ Berryteuthis magister
ダンゴイカ目ダンゴイカ科ダンゴイカ亜科 Sepiolinae ミミイカ属 ミミイカ Euprymna morsei
等が挙げられよう。
・「鬚」現代のイラストなどで、脚の一対を鬚に描くものが、しばしば見られ、時珍は、イカの脚を四対八足とするので、位置的に見ると、左右の第Ⅳ腕を、かく呼称しているかとも思ったが、後の良安の記載に、イカ釣りの方法が書かれおり、そこからは、長大な捕食腕である触腕としか私には思われない。
・「蒲扇」は、ガマやビンロウの葉で作った団扇。
・「輕虛」は、ふわふわとして中身のないさま。
・「海螵蛸」は学術的には「甲」或いは「軟甲」と呼ぶ。これはまさに頭足類が貝類と同じグループに属することの証しと言ってよい。即ち、貝類の貝殻に相当する体勢の支持器官としての、言わば、「背骨」のように見える物が「イカの甲」なのである。あまり活発な遊泳を行わないコウイカ類では、炭酸カルシウムの結晶からなる多孔質の構造からなる文字通りの「甲」を成し、この甲から生じる浮力を利用している。本件で言うのは、勿論、これである。対して、活発な遊泳運動をするツツイカ類では、運動性能を高めるために完全にスリムになって、半透明の鳥の羽根状の「軟甲」になっている。ツツイカ目のヤリイカ科アオリイカは、外見はコウイカに似るが、「甲」は舟形ながら、薄く半透明で軽量である。これは、言わば、「甲」と「軟甲」双方の利点を合わせた効果を持っている。即ち、相応の浮力もあり、スルメイカほどではないにしても、かなり速い遊泳力も持ち合わせているのである。
・「婦人の血閉・不足の症」は月経不通・生理不順を言う。但し、イカの甲の成分である炭酸カルシウムは一般には止血効果がある。「海螵蛸」は海産の生薬では、かなりポピュラーなものであるらしい。
・「鈿飾」は、螺鈿細工の補助材料、又は、その代替材料とするということであろうか。軟甲は英語で Cuttlebone と呼ばれ、現在でも金属を用いた装飾品の加工時に、型取りの材料や、磨き粉として用いられているようである。
・「墨」については、嘗つて私は、ブログの「蛸の墨またはペプタイド蛋白」で語ったことがある。但し、その主要部分はタコの墨についてであった。但し、良安は何故か、タコの墨について語っていなかったために、墨について語る機会もなく、また、ブログ記載時の、ある疑問が今も解けていない。そこではタコとイカの墨の違いも述べているので、一部加筆して、イカ、引用する。
*
「イカスミ」は料理に使用するが、タコの墨は「タコスミ」とも、まず、言わず、料理素材として用いられることがないことが気になった。ネット検索をかけると、タコの墨には、旨味成分がなく、更に、摂餌する甲殻類や貝類を麻痺させ、天敵のウツボの感覚器官をも麻痺させるペプタイド蛋白が含まれているから、と概ねのサイトが記している。
では、それは麻痺性貝毒ということになるのであろうか(イカ・タコの頭足類は広い意味で貝類と称して良い)。一般に、麻痺性貝毒の原因種はアレキサンドリウム属 Alexandrium のプランクトンということになっているが、タコの、そのペプタイド蛋白なるものは、如何なる由来なのか? 墨だけに限定的に含まれている以上、これはタコ本来の分泌物と考える方が自然であるように思われる。
ただ、そもそもタコの墨は、イカ同様に敵からの逃避行動時に用いられる「煙幕」という共通性(知られているように、その使用法は違う。イカは粘性の高い墨で、自己の擬態物を作って、ダミーを作り、逃げるのであるのに対して、タコの粘性の低い水溶性の墨は、素直な視界を晦ます「煙幕」なのである[やぶちゃん注:「三才圖阿會」の墨の効能記載は、イカというよりも、タコのそれである。])から考えても、ここに積極的な「ペプタイド蛋白」による撃退機能を附加させる必然性は、果してあったのであろうか。進化の過程で、この麻痺性の毒が、有効に働いて、高度化されば、それは積極的な攻撃機能として転化してもおかしくないように思われる。しかし、タコの墨で苦しみ悶えるイセエビとか、弱って容易に口を開けてしまう二枚貝、阿呆のように戸惑ったウツボの映像等というのは、私は、残念ながら、見たことがない。また、タコには墨があるために、天敵の捕食率が極端に下がっているのだという話も、聞かない。
更に、このペプタイド蛋白とは何だ? 化学の先生にも尋ねてみたが、ペプタイドとペプチドは peptid という綴りの読みの違いでしかないそうだ。しかし、その先生(女性)に言わせれば、「蛋白」という語尾自体が不審なのだそうだ。そもそも、ペプチドはタンパク質が最終段階のアミノ酸になる直前に当たる代謝物質なのであって、アミノ酸が数個から数十個繋がっている状態を指すのであってみれば、この物言いはおかしなことになる。彼女は、「その繋がりが、もっと長いということを言っているのかも知れない。」と最後に呟いたが、僕も、煙幕が張られているようで、どうもすっきりとしなかった。いやいや、調べるうちに、逆に蛸壺に嵌ってしまったわい。
*
なお、イカの墨から作った顔料は、実在する。よく言うところの色名であるセピア sepia が、それであり、sepia はラテン語で「コウイカ」を指す。ギリシャ・ローマ時代から使用されており、巨匠レンブラントが愛用したことから「レンブラント・インク」とも呼ばれる。但し、実際の「レンブラント・インク」は暗褐色で、現在で言うところの「セピア色」とは、このインクが、経年変化して、色褪せた薄い褐色になった状態の色調に由来している。薄くはなるが、実際には、消えない。良安が言い、信じられているところの、「消える文字」というのは、この褪色効果を、大袈裟に語っているに過ぎないのであろう。なお、この墨から液晶が作られたとよく聞くが、これは誤りと思われる。液晶製造初期に於いて、イカの肝臓から採取されたコレステロールから作られた「コレステリック液晶」(グラデーション様に表示される寒暖計等)のことが誤って伝えられたものと思われる。
・「小滿」は二十四節気の一つ。小満は「四月中気」とも言い、この小満を含む、新月から次の新月の直前の月が、「旧暦の四月」と定められる。現在の五月二十一日頃に当たる。
・「𪇰」は、音「ホク」又は「ハク」又は「ホウ」又は「ボウ」。水鳥の名。
・「鶂」は、「鶃」が本字。音は「ゲキ」・「ギヤク」または「ゲイ」。水鳥の名。割注は「卷第四十一 水禽部」の「鷁」を指している。ここに「𪇰」・「鶂」の記載が現われる。本原型を終えてから後、「禽部」の総てをブログで電子化注した。「和漢三才圖會第四十一 水禽類 鷁(げき)〔?〕」がそれであるが、原型では、『叙述からみると、ペリカン目ウ科 Phalacrocoracidae の一種か、勘繰れば、同科の種のアルビノとも考え「ウ」であろうかとも思われるが、風媒で受精するとか、口から子供を吐いて生むとか、更に舳先に据えた龍頭鷁首(りゅうとうげきしゅ:特に平安人が好んだ、これらの鳥を、舳先に据えた二艘組みの船の名を指す)に、まさに龍とともにシンボライズされているところからも、これは「想像上の霊鳥」と解しておくのがよかろう』と書いたのは、我ながら、正しかったと、思う。]
***
《改ページ》
■和漢三才圖會 江海無鱗魚 卷ノ五十一 ○十九
たちいか
するめいか
柔魚
明鮝【鹽乾者俗云須留女】
脯鮝【淡乾者】
【俗云太知以加
又云鮝以加】
[やぶちゃん字注:以上四行は、前三行下に入る。]
本綱柔魚與烏賊相似但無骨爾
△按柔魚同烏賊而身長大乾之爲鮝出於肥州五島者
肉厚大味勝微炙食【裂食則佳切則味劣】或不炙細刻代膾皆甘
美柔魚骨亦似舟形而薄玲瓏似蠟紙【無骨者不審】又章魚
膞乾爲鮝【名乾章魚而不稱須留女】古者是亦謂須留女乎【和名抄小蛸魚
訓須留女】
障泥烏賊 大於真烏賊四周有肉緣狀似障泥【阿乎里以加】
是亦爲鮝佳
龜甲烏賊 背隆而肉厚故名之
針烏賊 似真烏賊而骨耑顯尻碑手如針鋒故名
《改ページ》
瑣管烏賊 身狹長如竹筒故名尺八烏賊
雛烏賊 烏賊小者其大一寸余頭中有飯者亦有之【又名
比之保以加】骨亦小攝州播州采之味美蓋此自一種非烏
賊子也【烏賊處處多有此者何少有乎】
*
たちいか
するめいか
柔魚
明-鮝(するめ)【鹽乾しの者は、俗に「須留女」と云ふ。】
脯鮝〔(ほしやう)〕【淡く乾す者。】
【俗に「太知以加」と云ふ。又は、「鮝(するめ)以加」と云ふ。】
「本綱」に、『柔魚は、烏賊と相〔(あひ)〕似たり。但〔し〕、骨、無きのみ。』と。
△按ずるに、柔魚は、烏賊に同じくして、身、長く、大きく、之れを乾かして「鮝(するめ)」と爲す。肥州〔=肥前〕五島より出づる者、肉、厚く、大にして、味、勝れり。微〔(やや)〕炙り、食ふ【裂きて、食へば、則ち、佳し。切れば、則ち、味、劣れり。】或いは、炙らずして、細かに刻みて、膾〔(なます)〕に代〔(か)〕ふ。皆、甘く、美なり。柔魚(たちいか)の骨(こう[やぶちゃん字注:ママ。])は亦、舟の形に似て、薄く、玲-瓏(すきとほ)り、蠟紙〔(らうがみ)〕に似る【『骨、無き。』と云ふは、不審。[やぶちゃん注:「云」は送り仮名にある。]】又、章魚(たこ)を、膞(ひつぱ)り、乾(ほ)して「鮝(ひだこ)」と爲す【「乾章魚(ひだこ)」と名づく。「須留女」と稱さず。】。古(いにしへ)は、是れも亦、「須留女」と謂ふか【「和名抄」に「小蛸魚」、「須留女」と訓ず。】。
障泥烏賊(あをりいか[やぶちゃん注:ママ。]) 「真烏賊」より、大にして、四周に、肉〔の〕緣〔(ふち)〕、有り。狀〔(かた)〕ち、障-泥(あをり)に似たり【「阿乎里以加」。】。是れも亦、鮝(するめ)と爲〔して〕佳し。
龜甲烏賊 背、隆(たか)くして、肉厚、故に、之れを名づく。
針(はり)烏賊 「真烏賊」に似て、骨の耑〔=端〕に尻を顯はし、手に碑〔(たつ)〕る針鋒〔(しんぽう)=針先〕のごとし。故に、名づく。
瑣管烏賊(しやくはちいか) 身、狹く、長く、竹の筒(つゝ)のごとし。故に「尺八烏賊」と名づく。
雛烏賊(ひないか) 烏賊の小さき者。其の大いさ、一寸余。頭〔(かしら)〕の中に、飯、有る者も亦、之れ、有り【又、「比之保以加〔(ひしほいか)〕」と名づく。】。骨も亦、小さし。攝州〔=摂津〕・播州〔=播磨〕に、之れを采る。味、美なり。蓋し、此れ、自〔(おのづか)〕ら一種なり。烏賊の子に非ず【烏賊、處處、多く有りて〔→有るに〕、此れは何ぞ、少〔なく〕有るか。】
[やぶちゃん注:ツツイカ目スルメイカ亜目アカイカ科スルメイカ亜科スルメイカ Todarodes pacificus である(但し、良安が不審がっているように、「本草綱目」の「柔魚」は「骨がない」と言い切っていることから、こちらは、典型的な軟甲を持つ他のツツイカ類を指している可能性が高い)。良安の、ここでのスルメイカの甲の記載は、誠に正確で、オリジナリティのある美事なものである(前項「烏賊魚」の「海螵蛸」注を参照のこと)。「スルメイカ」の「スルメ」の語源については、海中に「墨を吐く群れ」→「スミムレ」→「スルメ」という説が知られるようだ。良安が「和名抄」から引用している事実は、一見、これを補強するように見えないことはない。今一つの語源として、本種を「スルメ」(干し烏賊)にすることが多かったから、という噴飯もののトートロジーが平然と記されているのも見かける。そういうのは「イカ」ンながら、真の語源説とは言わないと思うんだなぁ。
さて、ところが、ここに興味深い事実がある。昨今、各地で稲の品種を記した古代の木簡(種もみの俵に付けた名札と考えられる)が出土しており、そこに以下のような名称が出て来るという。
*
石川県金沢市畝田ナベタ遺跡 「酒流女」「須※女」と記載した木簡(九~十世紀)[やぶちゃん字注:「※」=「流」-(さんずい)。]
石川県金沢市西念・南新保遺跡 「須留女」と記載した木簡(八~九世紀)
奈良県香芝市下田東遺跡 「小須流女」という品種を記載した木簡(九世紀初頭)
*
これらは、皆、「するめ」と読み、下田東遺跡の「小須流女」は、その改良品種らしいと言う。これを報じた『朝日新聞』の記事(二〇〇七年五月一日附)では、『「するめ」の「する」は「早い」、「め」は「芽」を示す』とある。そこで、スルメイカを指す「するめ」の場合の「め」が、一般に用いられる小動植物を示す接尾語であるとすれば、海中にあって、その軟甲を駆使して巧みに「素早く動く生き物」とも取れるし、この「め」を、そのまま「芽」、若しくは、ワカメ・アラメ等の「め」に相当する海産食用になる「海藻」状のもの(よく干した「スルメ」の足や薄い胴、若しくは、裂いた「スルメ」はそのように見えませんか?)を指すとは読めまいか? 勿論、これは、全く国語学の嫌いな僕の、今日の勝手な思いつきに過ぎない。ご批判は潔くお受けする。
・「鮝」の字は、「鯗」の俗字であり、「ひもの・ほしうお」を指す(特にニベ科シログチ属イシモチ Argyrosomus argentatus の干物を指す場合もある)。但し、国字としては「鱶」(ふか)を指す。
・「障泥烏賊」ツツイカ目開眼(ヤリイカ)亜目ヤリイカ科ヤリイカ亜科アオリイカ Sepiotenthis lessoniana 。「障泥」(あふり(あおり))とは、「馬の胴の両側に泥除けとして垂らす馬具」を言い、アオリイカの丸みを帯びた胴体の縁に沿ってある、半円形の鰭との類似からの呼称。「バショウイカ」(芭蕉烏賊)とも呼ばれる。
・「真烏賊」(マイカ)ここで良安は、突如として、「真烏賊」という語を用いている(前項の「烏賊」でも、良安は種名として「真烏賊」という語は用いていない)。が、ここでアオリイカという個別種と対比して語る以上、これは特定種を指すと考えねばならない。現在、市場で「マイカ」という流通名は、コウイカ目コウイカ科コウイカ属コウイカ Sepia esculenta に用いられており、良安が、西日本で多量に捕獲される代表的な本種を意識していないはずはないと私は思う。
・「龜甲烏賊」(キッコウイカ)このような呼称は現在、生き残っていない。市場での和名と形状から類推するしかないが、形態と呼称の類似からは、まず、「モンゴウイカ」という通称の方が有名なコウイカ目コウイカ科コウイカ属 Acanthosepion 亜属カミナリイカSepia (Acanthosepion) lycidas が念頭に登る。文句なしの巨大種であり、英名 Kisslip cuttlefish が示す通り、胴(外套膜背面部)に「キス・マーク」のような紋がある(「ぼうずコンニャクの市場魚類図鑑」の同種のページの二枚目の写真を参照されたい)。これを「亀甲紋」ととったとしても、それほど違和感はない。これが同定候補一番であろうが、私は、もう一種、挙げておきたい欲求にかられる。ツツイカ目開眼亜目の大型種で、極めて特徴的な幅広の亀甲型(と私には見えないことはない)形態を持つソデイカ科ソデイカ属ソデイカ Thysanoteuthis rhombus は如何だろうか? ソデイカは地方名・市場名で「タルイカ」・「オオトビイカ」・「セイイカ」、はたまた「ロケット」等という名も拝名している(「セイイカ」の「セイ」は「勢」で男性の生殖器のことであろう。「背、隆くして、肉厚」と称してもグッときちゃうゼ!)。グーグル画像検索「ソデイカ」を見られたいが、胴体部がカメの甲羅と言っても、おかしくないからである。
・「針烏賊」現行の標準和名では、コウイカ目コウイカ科ハリイカ(コウイカモドキ) Sepia (Platysepia) madokai を指すが、市場名としては、先に出したコウイカと混同されており、コウイカ(もしくは他のコウイカ類)を「ハリイカ」と呼称する地方もある。コウイカのグループは、甲の胴頂方向の頭部が、有意に尖っており、生体を触っても、それが棘のように感じられるのである。
・「瑣管烏賊」(シャクハチイカ)ツツイカ目ヤリイカ亜目ヤリイカ科ヤリイカ亜科ヤリイカ属ヤリイカ Heterololigo bleekeri の地方名として残存する。
・「雛烏賊」ヒナイカ(「ヒシオイカ」という異名もあるがこれは、現在は死語と思われる)はコウイカ目ヒメイカ科ヒメイカ Idiosepius paradoxus と考えてよい。というよりも、奥谷喬司先生の「WEB版世界原色イカ類図鑑」によれば、この標準和名ヒメイカの原名(!)がヒナイカなのであるから、正統なる同定であると思っている。ツツイカ目ヤリイカ科のジンドウイカ属 Loliolus も、「コイカ」「ヒイカ」等の小型種を示す異名を持つが、ここでの「一寸余」に比して、有意に大き過ぎる。但し、良安が産地の局地性を不審に思っているのは、逆に不審と言わざるを得ない。本種は、三陸以南の藻場等に、ごく普通に棲息しているからである。]
***
とらご
海鼠
ハアイ チユイ
土肉【文選】海參
海男子【五雜組】
沙噀 沙蒜
塗筍【寧波府志】
【和名 古
俗云止良古】
[やぶちゃん字注:以上六行は、前三行下に入る。]
和名抄載食經云海鼠似蛭而大者也
食物本草曰海參生東南海中其形如蠶色黒身多㿔㿔
一種長五六寸表裏俱潔味極鮮美功擅補益殽品中最
珍者也一種長二三寸者割開腹内多沙雖刮剔難盡味
亦差短今北人有以驢馬之陰莖贋爲狀味雖畧同形帶
微扁者是也
《改ページ》
■和漢三才圖會 江海無鱗魚 卷ノ五十一 ○二十一
五雜組云海參遼東海濵有之一名海男子其狀如男子
勢其性温補足敵人參故曰海參石華文選註云土肉正
黒長五寸大如小兒臀有腹無口目有三十足可炙食
寧波府志云沙噀塊然一物如牛馬腸臓形長可五六寸
許胖軟【胖半軆肉也】如水蟲無首無尾無目無皮骨但能蠕動
觸之則縮小如桃栗徐復擁脹土人以沙盆揉去其涎腥
雜五辣煑之脆美爲上味
△按海鼠中華海中無之見遼東日本熬海鼠未見生者
故所載於諸書皆熬海鼠也剰文選之土肉入本草綱
目恠類獸之下焉惟寧波府志所言詳也寧波去日本
不甚遠近年以來日本渡海舶多以寧波爲湊海鼠亦
少移至乎於今唐舩來長崎時必多買熬海鼠去也
本朝自神代既有之舊事紀云彥火瓊瓊杵尊時諸魚
皆仕奉曰之而海鼠不曰爾天鈿賣命以細小刀折其
口故於今海鼠口折是也處處海中皆有之奥州松前
《改ページ》
津輕爲上其大者尺有餘尾州和田參州栅島相州三
浦武州本木讃州小豆島皆得名大抵五七寸無骨鱗
無尾鰭背圓淺青色又有帶黃者畧以似虎彪名虎兒
全體疣多滑軟其腹扁白色常在水中擴身而薄扁能
游行水庭如物觸則橫縮至離水則如半片胡瓜其口
折而無齒鰓其目切而無珠光共如小刀痕冬月盛出
春月終盡夏月全無也
肉【甘鹹寒】類鰒而有香氣帶黃者最佳爲鱠以薑醋食之煮
食亦良或攬砂數振篩則肉軟老人亦易喫
海鼠膓 腹中有黃膓三條淹〔→腌〕之爲醬者也香美不可言
冬春爲珍肴色如琥珀者爲上品黃中黒白相交者爲
下品過正月則味變甚鹹不堪食其膓中有赤黃色如
糊者名海鼠子亦佳
熬海鼠 鮮者去膓熬之則鹹汁自出而焦黒取出候冷
曝乾所謂如小兒臀或如男勢者是也出於奥州金花
《改ページ》
■和漢三才圖會 江海無鱗魚 卷ノ五十一 ○二十二
山海邊者帶金色名金海鼠爲極上 又熬之毎十箇
懸張二小柱而如梯之形者名串海鼠處處皆有之共
使時一日漫水煮熟則肥脹味甘美
凡海鼠性忌稻藁如犯之則體解如泥又鼹鼠畏海鼠以
串海鼠柱椓于花園鼹不敢入
老海鼠【和名保夜】 出于介甲類
海兔【宇美宇佐岐】 似海鼠而腹黃色大者一尺二三寸豫州
海邊有之人不敢食俗傳云誤突殺之則黒血流出乃
忽雨屢試亦然
*
とらご
海鼠
ハアイ チユイ
土肉〔(どにく)〕【「文選」。】海參
海男子【「五雜組」。】
沙噀〔(さそん)〕 沙蒜〔(ささん)〕
塗筍〔(とじゆん)〕【「寧波府志」。】
【和名は、「古」。俗に「止良古」と云ふ。】
「和名抄」に「食經」を載せて云はく、『海鼠は、蛭〔(ひる)〕に似て、大なる者なり。「食物本草」に曰く、『海參は、東南海の中に生ず。其の形、蠶(かいこ)のごとし。色、黒く、身に㿔㿔〔(ぶつぶつ)〕、多く、一種、長さ五、六寸、表裏、俱に潔〔(きよ)く〕、味、極〔く〕鮮美〔なり〕。功〔=効〕、補益を擅(ほしいまゝ)にし、殽〔=肴〕-品〔(さかな)〕の中の最も珍なる者なり。一種、長さ二、三寸なる者、腹内を割り開けば、沙、多く、刮〔(か)き〕、剔〔(のぞ)〕くと雖も、盡き難し。味も亦、差(やゝ)短〔(みじか)〕し。今、北人、驢馬の陰莖(へのこ)を以て、贋(にせ)て、狀〔(かたち)〕を爲〔(つ)〕くる有り。味、畧〔(ほぼ)〕同じと雖も、形、微〔(すこ)〕し、扁〔(ひらた)〕たきを帶ぶる者、是れなり。』と。
「五雜組」に云ふ、『海參は、遼東の海濵に、之れ、有り。一名、「海男子」。其の狀、男子の勢(へのこ)のごとし。其の性、温補、人參に敵するに足り、故に「海參」と曰ふ。』と。石華が「文選」の註に云はくふ、『土肉は、正黒にして、長さ五寸、大いさ、小兒の臀〔(しり)〕のごとく、腹、有りて、口・目、無く、三十の足、有り。炙り食ふべし。』と。
「寧波府志」に云ふ、『沙噀は、塊然たる一物〔なり〕。牛馬の腸-臓〔(はらわた)〕の形のごとくにして、長さ五、六寸許〔(ばかり)〕ばかりなるべし。胖軟〔(はんなん)〕なり【「胖」は「半軆〔(はんみ)〕の肉」なり。】。水蟲のごとく、首〔(かうべ)〕、無く、尾、無く、目、無く、皮・骨、無く、但だ、能く、蠕動(うじつ)く。之れに觸(さは)れば、則ち、縮-小(し〔→ち〕ゞ)まり、桃・栗のごとく、徐(そろそろ)と、復た、擁-脹(ふくれ)る。土人、沙盆〔:砂を盛った鉢。〕を以つて、其の涎腥〔(ぜんせい)〕を揉み去り、五辣〔(ごらつ)〕を雜〔(まぜ)〕て、之れを煑れば、脆美、上味たり。』と。
△按ずるに、海鼠(なまこ)は、中-華(もろこし)の海中に、之れ、無く、遼東、日本の「熬-海-鼠(いりこ)」を見て、未だ、生〔(なま)〕なる者を見ず。故に、諸書に載する所、皆、「熬海鼠」なり。剰(あま〔つ〕さ)へ、「文選」の「土肉」を、「本草綱目」、「恠類獸」の下に入る。惟〔(ただ)〕、「寧波府志」言ふ所、詳〔(つまびら)かなり〕。寧波(ニンハウ)は、日本を去ること、甚しく〔は〕遠からず、近年以來、日本渡海の舶〔(ふね)の〕多くは、寧波を以つて、湊と爲す。海鼠も亦、少し、移り至るか。今に於いて、唐舩〔(からぶね)〕、長崎に來〔(きた)〕る時[やぶちゃん注:「時」は送りがなにある。]、必ず、多く、熬海鼠を買ひて、去(い)ぬるなり。
本朝には、神代より、既に、之れ、有り。「舊事紀〔(くじき)〕」に云はく、『彦-火-瓊-瓊-杵-尊(〔ひこほの〕に〔に〕ぎのみこと)の時、諸魚、皆、「仕へ奉らん。」と曰〔(まう)〕す。之れ、而〔(しか)〕るに、海鼠、曰〔(い)〕はざるのみ。天-鈿-賣-命(〔あめ〕のうずめのみこと)、細き小刀を以つて、其の口を坼(くじ)く。故〔(かれ)〕、今、海鼠の口、折(さけ)たる〔は〕、是れなり。』と。處處〔の〕海中に、皆、之れ、有り。奥州松前・津輕を上と爲す。其の大なる者、尺有餘。尾州〔=尾張〕の和田・參州〔=三河〕の栅島(さくの〔しま〕)・相州〔=相模〕の三浦、武州〔=武蔵〕の本木・讃州〔=讃岐〕の小豆島(しやうどしま)、皆、名を得。大抵、五、七寸、骨・鱗、無く、尾・鰭。、無く、背、圓〔(まろ)〕く、淺青色、又、黃を帶びる者、有り。畧〔(ほぼ)〕、虎-彪(とらふ)に似たるを以つて、「虎兒(とらご)」と名づく。全體、疣(いぼ)、多く、滑軟なり。其の腹、扁〔(ひらた)〕く、白色。常に水中に在りて、身を擴(ひろ)げて、薄く、扁く、能く、水庭〔=水底〕を游行す。如〔(も)〕し、物に觸〔(ふる)〕る時は[やぶちゃん字注:「時」は送りがなにある。]、則ち、橫に縮まる。水を離るるに至りては、則ち、半片〔(かたひら)〕の胡瓜(きうり)のごとし。其の口、坼(さ)けて、齒・鰓〔(あぎと)〕、無く、其の目、切れて、珠の光、無し。共に小刀の痕(きづ)のごとし。冬月、盛んに出づるに、春月終り、盡く。夏月、全く、無し。
肉【甘鹹、寒。】鰒〔(あはび)〕に類して、香氣〔(かうき)〕、有り。黃を帶びたる者、最も佳し。鱠〔(なます)〕と爲し、薑醋〔(しやうがず):生姜酢〕を以つて、之れを食ふ。煮て食ふも亦、良し。或いは、砂にて、攬〔(ま)〕ぜ、數(しばしば)、振(ふ)り篩(ふる)へば、則ち、肉、軟にして、老人も亦、喫し易し。
海-鼠-膓(このわた)は、腹中に黃なる膓〔(はらわた)〕、三條、有り。之れを腌〔(しほもの):塩漬け。〕とし、醬〔(ひしほ)〕と爲〔(な)〕る者なり。香美〔(かうび)〕、言ふべからず。冬・春、珍肴〔(ちんかう)〕と爲す。色、琥珀のごとくなる者を、上品と爲す。黃なる中に、黑・白、相〔(あひ)〕交る者、下品と爲す。正月を過〔ぐ〕れば、則ち、味、變じて、甚だ、鹹〔(しほから)〕く、食ふに堪へず。其の膓〔(わた)〕の中、赤黃色、有りて、糊(のり)のごとき者を、「海-鼠-子(このこ)」と名づく。亦、佳〔なり〕。
熬-海-鼠(いりこ)は、鮮〔(あたら)〕しき者、膓を去り、之れを熬る時は[やぶちゃん注:「時」は送りがなにある。]、則ち、鹹汁〔(しほからきしる)〕は、自〔(おのづか〕ら出でて、焦〔(こ)げて〕黑くなり、取り出〔(いだ)〕し、冷〔(ひゆ)〕るを候〔(まち)〕て、曝し、乾す。所謂、小兒の臀〔(しり)〕、或いは、男勢〔(へのこ)〕のごとしと云ふ者、是れなり。奥州金花山の海邊に出づる者、金色を帶ぶ。「金海鼠〔(きんこ)〕」と名づく。極上と爲す。 又、之れを熬り、毎十箇、二つの小柱に懸〔け〕張りて、梯(はしご)の形のごとくなる者、「串海鼠(くしこ)」と名づく。處處、皆、之れ、有り。共に使ふに、一日、水に漫(ほとはか)して、煮熟すれば、則ち、肥脹にして、味、甘美なり。
凡そ、海鼠の性、稻藁(いなわら)を忌む。如〔(も)〕し、之れを犯せば、則ち、體、解けて、泥のごとし。又、鼴-鼠(うくろもち)、海鼠を畏る。串海鼠の柱を以つて、花園に椓(くいう=杭打)てば、鼴、敢へて入らず。
老-海-鼠(ほや)【和名、「保夜」。】 介甲類に出づ。
海兔(うみうさぎ)【「宇美宇佐岐」。】 海鼠に似て、腹、黃色。大なる者、一尺二、三寸。豫州〔=伊予〕の海邊に、之れ、有り。人、敢へて食はず。俗に傳へて云ふ、「誤りて、之れを突き殺せば、則ち、黑血、流〔れ〕出で、乃〔(すなは)〕ち、忽ち、雨ふる。屢々、試む。亦、然り。
[やぶちゃん注:私の偏愛するナマコちゃんに遂に辿り着いた! では、まず最初は、軽く遊びましょう! 私のブログの「帰ってきた臨海博士やぶちゃん」の「ナマコ・クイズ」に挑戦! ちゃんと自律的に答えるんだよ。調べちゃ、ダメ! 誰ですか? 先にこの解答篇をクリックしようとしてるのは!? 言っとくけど、半端じゃなく難しいよ。
棘皮動物門 Echinodermata ナマコ綱 Echinoidea である。現在、六目に分類されるが、以下には、深海からの採取に限られる指手目 Dactylochirotida を除いた五目を挙げ、さらに阪急コミュニケーションズ二〇〇三年刊の本川達雄他著「ナマコガイドブック」に所載される科を列挙、同時に同書巻末にあるナマコ写真図鑑部分に所載する四十九種を漏れなく掲げた。これによって、本邦産の嘱目可能な主要な種を学術的にほぼ完全に押さえられると信ずるからである。同書の内容を一覧化したに過ぎないが、それでも私のこの記載は、現在Web上に存在する最も新らしい知見に基づく国産主要ナマコ類の最新の学名附き分類表であると自負するものである。
*
樹手目 Dendrochirotida
ジイガゼキンコ科 Psolidae
マツカサキンコ属ジイガゼキンコ Psolus squamatus
グミモドキ科 Phyllophoridae
ハマキナマコ属ハマキナマコ Phyrella fragilis
スクレロダクティラ科 Sclerodactylidae
イシコ属イシコ Eupentacta chromhjelmi
ムラサキグミモドキ属ムラサキグミモドキ Afrocucumis africana
キンコ科 Cucumariinae
キンコ属キンコ Cucumaria frondosa var. japonica
グミ属グミ Pseudocunus echinatus
楯手目 Aspidochchrotida
クロナマコ科 Holothuriidae
クリイロナマコ属クリイロナマコ Actinopyga mauritiana
ゲクリイロナマコ Actinopyga echinites
オオクリイロナマコ Actinopyga echinites sp.
Personothuria 属クロエリナマコ Personothuria graeffei
グミ属グミ Pseudocunus echinatus
ジャノメナマコ属フタスジナマコ Bohadschia bivittata
チズナマコ Bohadschia vitiensis
ジャノメナマコ Bohadschia argus
ニセジャノメナマコ Bohadschia sp.
クロナマコ属クロナマコ Holothuria (Halodeima) atra
アカミシキリ Holothuria (Halodeima) edulis
チビナマコ Holothuria (Platyperona) difficilis
イソナマコ Holothuria (Lessonothuria) pardalis
クロホシアカナマコ Holothuria (Semperothuria) cinerascens
テツイロナマコHolothuria (Selenkothuria) moebii
リュウキュウフジナマコ Holothuria (Thymiosycia) hilla
ミナミフジナマコ Holothuria (Thymiosycia) arenicola
イサミナマコ Holothuria (Thymiosycia) impatiens
フジナマコ Holothuria (Thymiosycia) decorata
トラフナマコ Holothuria (Mertensiothuria) pervicax
ニセトラフナマコ Holothuria (Mertensiothuria) leucospilpta
ニセクロナマコ Holothuria (Mertensiothuria) leucospilpta
モグラナマコHolothuria (Mertensiothuria) sp.
ハネジナマコ Holothuria (Metriatyla) scabra
イシナマコ Holothuria (Microthele) nobilis
シカクナマコ科 Stichopodidae
バイカナマコ属バイカナマコ Thelenota ananas
アデヤカバイカナマコ Thelenota anax
オキナマコ属オキナマコ Parastichopus nigripunctatus
シカクナマコ属シカクナマコ Stichopus chloronotus
オニイボナマコ Stichopus horrens
ムチイボナマコpseudhorrens
アカオニナマコ Stichopus ohshimae
ヨコスジオオナマコ Stichopus hermanni
タマナマコ Stichopus variegatus
マナマコ属マナマコ Apostichopus armata
アカナマコ Apostichopus japonicus
ミツマタナマコ科 Synalloctdae
ソコナマコ属ゴマフソコナマコ Batyplotes moseleyi
板足目 Elasipodida
カンテンナマコ科 loetomogonidae
カンテンナマコ属ヒメカンテンナマコ Laetomogone maculata
隠足目 Molpadida
カウディナ科 Caudinidae
シロナマコ属シロナマコ Paracaudina chilensis
無足目Apodida
イカリナマコ科 Synaptidae
Opheodesoma 属(?)クレナイオオイカリナマコ Opheodesoma(?) sp.
オオイカリナマコ属オオイカリナマコ Synapta maculata
トゲオオイカリナマコ Euapta godeffroyi
クルマナマコ科 Chiridotidae
クルマナマコ属ミナミクルマナマコ Chiridata sp.
ムラサキクルマナマコ属ムラサキクルマナマコ Polycheira fusca
ヒモイカリナマコ属ヒモイカリナマコ Patinapta ooplax
*
・「文選」は、中国南北朝時代の南朝・梁の昭明太子によって編纂された全三十巻の書物。周から梁までの文章・詩・論文を集めたもの。奈良・平安朝の日本に於いては、貴族階級の必読書とされた。
・「五雜組」は、明の謝肇淛(しゃちょうせい)の十六巻からなる随筆集であるが、殆んど百科全書的内容を持ち、日本では江戸時代に愛読された。書名は五色の糸でよった組紐のこと。
・「寧波府志」は明の張時徹らの撰になる浙江省寧波府の地誌。
・「食經」は「崔禹錫食經」で、唐の崔禹錫撰になる食物本草書。前掲の「倭名類聚鈔」に多く引用されるが、現在は散佚。後代の引用から、時節の食の禁忌・食い合わせ・飲用水の選び方等を記した総論部と、一品ごとに味覚・毒の有無・主治や効能を記した各論部から構成されていたと推測される。
・「食物本草」は、明の汪頴(おうえい)撰になる、通常の食物となるものに限った本草書。
・「㿔㿔」の「㿔」は、「小さなできもの・腫れ物」を指す。背部の多数の突起を言っている。
・「補益」とは、食物補給による栄養状態の改善を言う。
・「温補」とは、健康な人体にとって必要な温度まで高める力を補うという意味であろう。
・『石華が「文選」の註に云ふ……』以下については、東洋文庫版は以下の注を記す。『『文選』の郭璞(かくはく)の「江賦」に、江中の珍しい変わった生物としてあげられたものの説明の一つであるが、石華については、「石華は石に附いて生じる。肉は啖(くら)うに中(あ)てる」とあり、〔その同じ「江賦」の:やぶちゃん補注〕土肉の説明が『臨海水土物志』[やぶちゃん注:隋の沈瑩(しんえい)撰。]を引用したこの文である。〔「江賦」の記載に於ける:やぶちゃん補注〕石華と土肉は別もので、どちらも江中の生物。良安は石華を人名と思ったのであろうか。』とあるのだが、この編者注で、ちょっと気になるのは、どちらも『江中』の生物であると言っている点である。即ち、どちらも「江」=淡水域であるということを編者は指摘しているように、私には判断されるのである(中国語にあっては「江」は「長江」が第一義であり、「海の入江」の意を本来的には主には持たないはずである)。従って、東洋文庫版編者は「石華」は勿論、「土肉」さえも、ナマコとは全く異なった生物として同定していると言えるのである(淡水産のナマコは存在しない。淡水への適応が、本来的にナマコにはないのである)。しかし、「土肉」は「廣漢和辭典」にあっても、明確に中国にあって「なまこ」とされている(同辞典の字義に引用されている「文選」の六臣注の中で、「蚌蛤之類」とあるにはあるが、ナマコをその形態から軟体動物の一種と考えるのは極めて自然であり、決定的な異種とするには当たらないと私は思う)。さすれば、「土肉」は「ナマコ」と考えてよい。次に気になるのは「石華」の正体である。まず、書きぶりから見て、良安は、東洋文庫版注が言うように、「石華」を「土肉」について解説した人名(まどろっこしいが、「文選」注に引用された郭璞の注の中の、更に引用元の人物名ということになる)と誤っていると考えてよい。しかし、そんな考証は私には大切に思えない。「生き物」を扱っているのだから、それより何より、「石華」を考察することの方が大切であると思うのだ。そこで、まず、ここで問題となっている郭璞の注に立ち戻ろう。「石華」と「土肉」の該当部分は、中国語ウィキペディアの「昭明文選 卷12」から容易に見出せる(一部の漢字を正字化した)。
*
王珧〔姚〕海月,土肉石華。[やぶちゃん注:「江賦」本文。〔姚〕は「珧」の補正字であることを示す。以下、注。]
郭璞山海經注曰:珧,亦蚌屬也。臨海水土物志曰:海月,大如鏡,白色,正圓,常死海邊,其柱如搔頭大,中食。又曰:土肉,正黑,如小兒臂大,長五寸,中有腹,無口目,有三十足,炙食。又曰:石華,附石生,肉中啖。
王珧〔=姚〕・海月、土肉・石華。
○やぶちゃんの訓読
郭璞が「山海經」注に曰はく、『珧は亦、蚌の屬なり。』と。「臨海水土物志」に曰はく、『海月は、大いさ、鏡のごとく、白色、正圓、常に海邊に死し、其の柱、搔頭の大いさのごとく、食ふに中(あ)つ。』と。又、曰はく、『土肉は、正黑、小兒の臂(ひじ)の大いさのごとく、長さ五寸、中に腹、有り。口・目、無く、三十の足、有り。炙りて食ふ。』と。又、曰く、『石華は、石に附きて生じ、肉、啖(く)ふに中つ。』と。
*
脱線をすると、止めどもなくなるのであるが、「王珧〔=姚〕」は「和漢三才圖會 卷第四十七 介貝部 寺島良安」の「王珧」でタイラギ、「海月」は、同じく「海鏡」で、カガミガイ、又は、マドガイである(「海鏡」は、記載が、美事に一致する。それぞれの学名については、該当項の注を参照されたい)。「土肉」は、その記載からみても、間違いなくナマコである。では、「石華」は何か? 極めて少ない記載ながら、私はこれを海藻類と同定してみたい欲求にかられる(勿論、「肉」と言っている点から、海藻様に付着するサンゴやコケムシや定在性のゴカイ類のような環形動物、及び、ホヤ類も選択肢には、当然、挙がるのだが、「肉は啖(くら)ふに中(あ)つ。」という食用に供するという点からは、定在性ゴカイのエラコ Pseudopotamilla occelata か、ホヤ類に限られようとは思う)。すると、「石花」という名称が浮かび上がるのだ。「大和本草」の「卷之八草之四」の「心太(ふと)」の条に(ブログで「大和本草卷之八 草之四 海藻類 心太 (ココロフト=トコロテン)」を電子化注してある)、「閩書」(明の何喬遠撰)を引いて「石花菜ハ海石ノ上ニ生ス。性ハ寒、夏月ニ煮テ之ヲ凍(こほり)ト成ス」とする。即ち、「石華」とは、一つの可能性として、紅色植物門紅藻綱テングサ目テングサ科マクサ Gelidium crinale 等に代表されるテングサ類ではなかろうかと思われてくるのである。
・「胖軟」の「胖」は、下の割注に、「胖は半軆の肉なり」とあるように、本来は、祭儀に於いて、「生贄として裂かれた肉類の半身」を指すが、それでは意味が通じないから、ごり押し敷衍するなら、「生贄に捧げる軟らかな獣類の肉を半分に切ったような形態の肉である」と解釈するしかないが、ここは、割注を無視し、「胖」の、もう一つの意味であるところの、「肥え太る」の意味で取り、「ゆったりと肥え軟らかな肉である」の意味に取るべきであろう。
・「涎腥」は、生臭い粘り気のある粘液。
・「五辣」は、辣韮(ラッキョウ)・韮(ニラ)・葱(ネギ)・蒜(ノビルやニンニクの類)・薑(ショウガ)。
・「熬海鼠」の「いりこ」という呼称は、現在は、「イワシ類を塩水で茹でて干した煮干(にぼし)」のことを言うが、本来は、実は、本邦では、非常に古くから、ナマコの腸を除去し、塩水で煮て、完全に乾燥させたものを指して言った。平城京跡から出土した木簡や「延喜式」に、能登国の調として記されている。「延喜式」の同じ能登の調には後述されるコノワタやクチコも載り、非常に古い時代から、ナマコの各種加工が行われていたことを示している。昭和三七(一九六二)年内田老鶴圃刊の大島廣先生の「ナマコとウニ」(本書は私の最初の博物学電子テクスト「仙臺きんこの記 芝蘭堂大槻玄澤(磐水)」の冒頭注に記したように、実は私が博物学書テクスト化を志す動機となった書で、私の座右の銘に相応しい名著である)。には、明治二九(一八九六)年の調査になる農商務省報告に、各地方に於けるイリコの製法がいちいち詳述されており、それらを綜合した標準製法が示されているとする(以下、同書からの孫引だが、カタカナを平仮名に直し、〔 〕で読み・意味を加え、適宜濁点を補った)。
*
「捕獲の海鼠は盤中に投じ、之に潮水を湛〔たた〕へ、而して脱腸器を使用して糞穴より沙腸を抜出し、能く腹中を掃除すべし。是に於て、一度潮水にて洗滌し、而して大釜に海水を沸騰せしめ、海鼠の大小を区別し、各其大小に応じて煮熟の度を定め、大は一時間、小は五十分時間位とす。其間釜中に浮む泡沫を抄〔すく〕ひ取るべし。然らざれば海鼠の身に附着し色沢を損するなり。既に時間の適度に至れば之を簀上〔さくじやう:すのこの上〕に取出し、冷定〔れいてい(?):完全に冷えること。〕を竢〔まつ=待〕て簀箱〔すばこ〕の中に排列し、火力を以て之を燻乾〔くんかん:いぶして干すこと。〕すべし。尤〔もつとも〕晴天の日は簀箱の儘交々〔かはるがはる〕空気に曝し、其湿気を発散せしむべし。而して凡〔およそ〕一週間を経て叺〔かます〕等に収め、密封放置し、五六日許りを経て再び之を取出し、簀箱等に排列して曝乾〔ばつかん〕するときは充分に乾燥することを得べし。抑〔そもそ〕も実質緻密のものを乾燥するには一度密封して空気の侵入を防遏〔ばうあつ:防ぎとどめること。〕するときは、中心の湿気外皮に滲出〔しんしゆつ:にじみ出ること。〕し、物体の内外自から其乾湿を平均するものなり。殊に海鼠の如き実質の緻密なるものは、中心の湿気発散極めて遅緩なれば、一度密蔵して其乾湿を平均せしめ、而して空気に晒し、湿気を発散せしむるを良とす。已に七八分乾燥せし頃を窺ひ、清水一斗蓬葉〔よもぎば〕三五匁の割合を以て製したる其蓬汁にて再び煮ること凡そ三十分間許にして之を乾すべし」
*
まことに孫引ならぬ孫の手のように勘所を押さえた記述である。なお、最後の「蓬汁」で煮るのは、大島先生によると、『ヨモギ汁の鞣酸(たんにん)と鉄鍋とが作用して黒色の鞣酸鉄(たんにんてつ)を生じ、着色の役割をするものである』と後述されておられる。
・「少し移り至るか」は面白い考察である。即ち、船舶の往来によってナマコが生体として移入した可能性を示唆しているのである。その当否は別として、生態系への外来種の無意識的人為移入の視点を持っていた良安先生は、ナウい。是非、お弟子にして欲しい!
・「恠類獸」の「恠」は「怪」の俗字。「見慣れない不思議な生き物」の意。
・「舊事紀」は「先代舊事本紀」。聖徳太子と蘇我馬子によって編せられたとするが、平安初期に作られた偽書。「古事記」・「日本書紀」・「古語拾遺」を切り張りしつつ、独自の創作を加えたものと思われる。その以下の引用は、より正統な「古事記」から引くのがよいと思われるので、以下に引用する(書き下し文及び訳は上代の苦手な私の仕儀につき、ご注意あれ。過去形で訓読するのが一般的であるが、敢えて現在形で臨場感を出した)。
*
於是送猿田毘古神而、還到、乃悉追聚鰭廣物鰭狹物、以問言、汝者天神御子仕奉耶、之時、諸魚皆、仕奉、白。之中、海鼠不白。爾天宇受賣命謂海鼠云、此口乎、不答之口、而以紐小刀拆其口。故、於今海鼠口拆也。
○やぶちゃんの訓読文
是に於いて、猿田毘古神(さるたひこのみこと)を送りて、還り到りて、乃(すなは)ち、悉く、鰭(はた)の廣物(ひろもの)・鰭の狹物(さもの)を、追ひ聚(あつ)め、以つて、問ひて言(のたまは)く、
「汝(な)は、天つ神の御子に仕へ奉らむや。」
と。
之の時、諸々(もろもろ)の魚、皆、
「仕へ奉らむ。」
と白(まを)す。
この中(うち)、海-鼠(こ)のみ、白さず。
爾(ここ)に、天宇受賣命(あめのうずめのみこと)、海鼠(こ)に謂ひて云(のたまは)く、
「此の口や、答へざるの口。」
と。
而して、紐小刀(ひもかたな)を以つて、其の口を拆(さ)く。
故に、今に於いて、海鼠(こ)の口、拆くるなり。
○やぶちゃん訳
天宇受売命は、ここで、天孫降臨の先導を務めてくれた猿田毘古神を送って帰って来て、即座に、海中の、大小、あらゆる魚たちを、悉く、呼び集めて、訊(たず)ねてねて言った。
「お前達は、天つ神の御子に従順に仕え奉るか?」
と。
すると、魚どもは、皆、
「お仕へ奉りまする。」
と申し上げる。
と、しかし、その中で、海鼠だけは、答えようとしない。
ここに天宇受売命は、海鼠に向かって言った。
「この口は、答えぬ口なのね。それじゃあ、こんな口は、いらないわ。」
と。
そして、飾り紐の付いた小刀で、その海鼠の口を裂いた。
故を以つて、今に至るまで、海鼠の口は裂けているのである。
*
以上は、古来からの大神であったサルタヒコさえ、天孫の膝下に下り、そこにダメ押しとしての畜生(衆生)のシンボルたる総魚類の従属を示して、それに従おうとしなかった海鼠が、原罪への処罰として、口を切られ、その反スティグマは、永遠に消えない程に恐ろしいのだ、と語っているのであろう。私には生理的に厭な話である。この「切られた口」なるものは、ナマコの口部を取り巻く十~三十本の触手(因みに、これは、管足が巨大に変形したものである)を示すのだが、和漢の多くの観察者は、「海鼠には口はない」と言っているではないか。「古事記」のこの女神による海鼠制裁事件は、大いに冤罪の可能性がある。とっくに時効ではあるが、ナマコたちよ、名誉回復のための訴訟には、いつでも私が特別弁護人になってあげる!
・「海鼠膓」(このわた)について、前掲書の大島廣「ナマコとウニ」には次のように記される)。
*
このわたの収量は、ナマコ三七五キログラムに対して、約十四リットル、これに二~三割の食塩を加え、熟成し、水分を去ると製品の歩留(ぶどま)りは更に七割ぐらいに減る。
*
最近の記載では二キログラムから牛乳瓶一本とあるが、この差は、さて何かしらん、怪しい匂いがするなあ。ナマコの腸が急に最近になって大きくなったとでも言うんかい? ――いやいや、そんなことより私が激しくムッとくるのは、ナマコの習性を悪用(?)した公然たるコノワタ作りなのだ。ナマコはストレス(環境悪化・化学的または物理的刺激・捕食動物による攻撃等)を受けると、口部の触手から腸、腸に分布する腸血洞(栄養吸収や運搬に関わる組織と考えられている)や、呼吸樹(肺に相当)の一部も身ぐるみならぬ、ハラワタぐるみ、吐き出してしまう。これを吐臓現象(内臓吐出)と言う。吐き出した着ぐるみだけとなったナマコは、砂に潜って、凝っとしている。環境によって異なるが、およそ二ヶ月で、失われた臓器は再生するのだ。そこでだ、「大阪水研」公式サイト内のこのページを見よ(実はリンクを付けるのも虫唾が走るぐらい厭なのだが)。そこにさりげなく書かれた、『これを利用して売れない大きすぎるマナマコを水槽で飼育し、驚かせて内蔵だけを吐き出させます。内臓は2週間ほどで薄い膜でできた腸を再生するので、生命に別状はありません。この腸管の塩辛をコノワタといいます。』……私はナマコが好物で、よく丸のままを買って調理するが、最近、「活ナマコ」と称したものを割いてみると、体内がすっかりくっきり何もないという驚天動地を味わうことがあるのだ。まさに、この処置を受けた弱ったものを、そのまま再生も待たずに早期に平然と出荷しているのだ! これは、おぞましい詐欺行為以外の何ものでもない! 勿論、内臓の多くは遺棄される(試みに、呼吸樹、触手、神経環・石灰環を含む口部周縁・珍味となるはずの卵巣を、それぞれ食してみたことがあるが、如何とも言い難い。おやめになった方が無難であろう)。それでも、やっぱり、腸は、楽しみだ。コノワタを自分で作るわけではないが、切断せぬように腸から細心の注意を払って、砂を、扱いて除去し、軽く塩と酒を振って、少し置いて食べるのは、正当な権利であり、気持ちの中の贅沢であり、私は美味と感じる。勿論、吐臓にヒントを得た漁人の知恵は知恵として、積極的ではないが、評価できる。この小ざかしい技法は、かなり以前から行われていた。前掲書大島氏の「ナマコとウニ」には次のように記す。
*
ナマコ類が、失われた内臓を再生することは、実験的に証明されたことだが、この性質を利用して、ナマコを殺さずにその腸を採取する方法が、愛知県知多郡豊浜町漁業組合と知多郡水産組合との協力によって考案され、秘法として実施されているという。その方法は次の通りである。まず集めたナマコを活簀(いけす)に入れ、一二時間放置して腸管の中の砂泥をことごとく排出させる。次に数十個づつ分けて桶(おけ)に入れ、別に一~二個を取ってその腸を取出し、圧搾(あっさく)してその液汁を絞って取り、これをほかのナマコに呼吸させる。すると、これが刺戟となって、ことごとくのナマコがその腸を全部、肛門から排出する。このように、生理的な自裁(じさい)によって失われた消化管は、八週間を経て完全に再生するという(磯野泰二)。
*
確かにナマコは、内臓どころか、本体自体をも再生出来る。実際に、ミクロネシアでナマコ食をする民族たちは、食うための前半分を切り、後部の半身を海に返す(前後は推測。前半分の場合、実験的には再生に失敗するケースが高いそうである)。再生力の強いナマコは、本体部を再生し、また一匹になるのだ。そしてそれは、小国寡民の島嶼にあっては、頗る自然の理にかなった正しい仕儀であったと言ってよい。しかし、私が憤るのは、それを、この飽食大国日本の漁業の公的な組織が、さも当然の如く記す無神経さなのである。そんな中で、着ぐるみだけで、内臓のないナマコを「活ナマコ」として売買することは、立派な詐欺である。それを取り締まるどころか、逆に、生命ニ別状ハアリマセン、だと?――ど外道が! てめえらには、ハシゴ状神経系さえも、ねエ! というドーベルマン刑事風の捨てセリフが僕の指弾の中身なのである。
春潮に肝吐き盡くす海鼠哉 藪野唯至
・「武州の本木」不詳。海辺に近い場所では、現在は見当たらない。
・「腸三條」という表現は、必ずしも誤りとは言えない。勿論、腸は完全な一本の管として、口部から総排泄腔へと繋がって存在しているが、これが最も一般に食用に供されるマナマコ属マナマコ Apostichopus armata や、イリコ材料として古くから使われていたシカクナマコ属シカクナマコ Stichopus chloronotus (従ってコノワタの材料としても一般的であったと考えてよい)は、他種に比して、有意に長い腸管を持っているため、口から体幹に沿って後部へと走る腸が、途中で再び、前方に向かって折れ曲がり、更に後方へと、再度、曲って、S字型を呈する(これは実際の市販のマナマコを調理すれば容易に観察出来る)ため、まさに「三条」に見えるのである。因みに、ナマコの中には、普通に、体幹中央部に沿ったシンプルな一本の腸を持つものもあり、この回折した腸というのは、消化しにくい植物質摂餌を主とする堆積物捕食者である楯手目の種に主に明瞭な特徴である。実に彼らは二十四時間継続的に多量の砂と一緒に、その中の僅かな可食物を食い続けているのである。
・「海鼠子」(くちこ)について、前掲書大島廣「ナマコとウニ」には次のように記す。
*
紐(ひも)状の生殖線[やぶちゃん注:「腺」の誤字。]を海鼠鮞(このこ)という。これを乾したものを俗に
*
「口子(クチコ)」・「干口子(ヒグチコ)」は、その製品が、三味線の撥(バチ)に似ているので「バチコ」とも言う。コノワタ以上に珍味とされ、まさに撥大のぺらぺら一枚が軽く五千円を越える(ナマコ数十キロから一枚しか出来ないという記述を見かけたが、「数十キロ」はコノワタで騙された感じの私にはクエスチョンだな)。今夏(二〇〇七年)、私は遂に連れ合いと義父母と一緒に行った実家のある名古屋の高級料理店でこれを食した。掛け値なし、自慢なし、誇張なし――大枚払って食してみる価値は、確かに、ある。
・「金海鼠」は、樹手目キンコ科キンコ Cucumaria frondosa var. japonica である。これは是非とも、記念すべき私の最初の博物学電子テクスト「仙臺きんこの記 芝蘭堂大槻玄澤(磐水)」をお訪ね下され! ページ丸ごと、キンコ!
・「串海鼠」について、前掲書大島廣「ナマコとウニ」に以下のように記す。
*
串(くし)に貫いて梯子(はしご)のような形にしたものは、筆者も沖繩本島のハネジイリコで初めて見たのだが(第二十五図[やぶちゃん注:大島先生の著作権は継続中なので省略。])、古くは広く行われた方法らしく、いろいろな書物にこれを見ることができる。
「串に刺し、柿の如くして乾したるを
「毎十箇懸張二小柱而如梯之形者名
「凡(およそ)串(くし)に貫(つらぬ)くものは
「海上人復有以牛革譌作之ノ語アリ。此即八重山串子(ヤエヤマクシコ)ト俗称スルモノニシテ、味甚薄劣下品ノモノナリ」(栗本瑞見)
この最後の記事は贋物(にせもの)の追加である。[やぶちゃん注:以下略。]
*
最後のものは、私が「海鼠 附録 雨虎(海鹿) 栗本丹洲 (「栗氏千蟲譜」卷八より)」で電子テクスト化した中に現われるもの。そちらも是非、御参照の程! さても贋物と言えば、良安の「食物本草」の引用には、ナマコの偽物として「驢馬の陰莖」によるものがあると記している。驢馬一頭を犠牲にしてまで……それは、何か、あんまりで、まさに「海鼠哀史」ではないか。
・「鼴鼠」は、哺乳綱モグラ目モグラ科 Talpidae のモグラのこと。日本には四属七種が棲息している。古くは「うころもち」(宇古呂毛知:「本草和名」)・「うごろもち」と呼称した。江戸期には「むくらもち」や「もぐらもち」の呼び方が定着、現在の「もぐら」になった。
・「老海鼠」は、食用とする脊索動物門尾索動物亜門海鞘綱(=ホヤ綱)壁性目(=側性ホヤ目)褶鰓(しゅうさい)亜目ピウラ科(マボヤ科)マボヤ Halocynthia roretzi 、若しくは、アカボヤ Halocynthia Aurantium としておく。「和漢三才圖會 卷第四十七 介貝部 寺島良安」の同項参照。
・「海兔」は軟体動物門腹足綱後鰓目無楯亜目 Anaspidea アメフラシ科アメフラシ属 Aplysia を指している。
愛するキュビエ管や、摩訶不思議な結合組織(キャッチ・アパレータス:catch apparatus)、まさに綺羅星の如き骨片等、多くを語りえなかった怨みは大きいが、注であることに我慢して、九回する腸が伸びきってコノワタにされるような哀しみを噛み締めることと致そう……]
***
くらけ
海䖳
ハアイ シヱヽ
水母 石鏡
樗蒲魚
【俗云久良介】
【和名抄用海
月二字非】
本綱海䖳形渾然凝結其色紅紫無口眼腹下有物如懸
《改ページ》
絮羣蝦附之咂其涎沫浮汎如飛爲潮所擁則蝦去而䖳
不得歸人因割取之常以蝦爲目蝦動䖳沈猶蛩蛩之與
駏驉也其最厚者謂之䖳頭味【鹹温】更勝生熟皆可食以
[やぶちゃん字注:「驉」は厳密には「虚」は「虛」であるが、表示出来ない。]
薑醋進之茄柴灰和鹽水淹之良又浸以石灰礬水去其
血汁其色遂白
△按海䖳形圓上面扁也故上面曰平【比良】下面有物如耳
[やぶちゃん注:「面」の字は総て「グリフウィキ」のこれであるが、同前。]
又如足曰臓其大者徑三尺厚一尺許無鱗骨頭目惟
如口者有腹下八九十月以攩綱〔→網〕取之和鹽水淹之取
鉤栗葉微焙碓碎共漬之夏毎日冬三日一度換水使
時用灰能揉洗浄去臭氣味【甘鹹】脆美代魚膾備前之
仲之〔→仲正〕
產爲上 夫木 我戀は海の月をそ待渡るくらけも骨に逢世在やと
肥前水母【又名唐水母】 一物異製也其製明礬和鹽揉合漬
之令色黃白使時能洗浄去礬氣肥前之產最佳故名
其味淡嚼之有聲
水海 色白形圓如水泡之凝結魚鰕附之隨潮如飛
《改ページ》
■和漢三才圖會 江海無鱗魚 卷ノ五十一 ○二十三
味不佳且有毒漁人不取之
*
くらげ
海䖳
ハアイ シヱヽ
水母 石鏡
樗蒲魚〔(ちよぼぎよ)〕
【俗に「久良介」と云ふ。】
【「和名抄」に「海月」の二字を用ふは、非なり。】
「本綱」に『海䖳〔(かいた/かいだ)〕は、形ち、渾然として凝結し、其の色、紅紫、口・眼、無く、腹の下に、物、有り。絮〔(しよ):綿〕を懸〔けたるが〕ごとし。羣蝦〔(むれえび)〕、之れに附きて、其の涎沫〔(よだれ)〕を咂(す)〔=吸〕ふ。浮汎〔(ふはん)すること〕、飛ぶがごとく、潮の爲に擁〔(よう)せ〕らるれば、則ち、蝦、去りて、䖳、歸るを得ず。人、因りて、割〔(わ)け〕て、之れを取る。常に、蝦を以つて、目と爲す。蝦、動けば、䖳、沈む。猶を〔→ほ〕蛩蛩〔(きようきよう)〕の駏驉〔(きよきよ)〕とのごとし。其の最も厚き者、之れを「䖳頭」と謂ふ。味【鹹、温。】、更に勝れり。生・熟〔=煮熟〕、皆、食ふべし。薑醋〔(しやうがず):生姜酢。〕を以つて、之れを進む。茄柴の灰、鹽水に和して、之れを淹〔(い)〕れて、良し。又、浸すに、石灰・礬水〔(ばんすゐ)〕を以つて、其の血汁〔(けつじふ)〕を去れば、其の色、遂に白し。』と。
△按ずるに、海䖳は、形、圓〔(まろ)〕く、上面、扁(ひら)たし。故に、上面を「平」【比良。】と曰ふ。下面に、物、有りて、耳のごとく、又、足のごとし。「臓〔(はらわた)〕」と曰ふ。其の大なる者、徑〔(わた)〕り三尺、厚さ一尺ばかり。鱗・骨・頭・目、無し。惟〔(ただ)〕、口のごとくなる者、腹の下に有り。八・九・十月、攩網(すくひたま)を以つて、之れを取る。鹽水に和して、之れを淹〔(しほもの)とす〕。鉤-栗(くぬのき)の葉を取り、微〔(やや)〕、焙〔(あぶ)〕り、碓〔(うす)〕にて碎きて、之れを共に漬ける。夏、毎日、冬、三日に一度、水を換ふ。使ふ時、灰を用ひて、能く揉み、洗浄して、臭氣(くさみ)を去る。味【甘鹹。】、脆く、美なり。魚膾〔(うをなます)〕に代〔(か)〕ふ。備前の產、上と爲す。
仲正
「夫木」 我戀は海の月をぞ待ち渡るくらげも骨に逢ふせありやと
肥前水母【又、「唐水母」と名づく。】 一物〔にして〕、異製なり。其の製、明礬〔(みやうばん)〕に、鹽を和して、揉み合はせ、之れを漬ける。色、黃白ならしめ、使ふ時、能く洗浄し、礬〔の〕氣を去る。肥前の產、最も佳し。故に名づく。其の味、淡く、之れを嚼〔(か)〕むに、聲〔(おと)〕、有り。
水海(みずくらげ) 色、白にして、形、圓く、水の泡(あは)の凝(こ)り結(むす)ぶがごとし。魚・鰕、之れに附き、潮に隨ひて、飛ぶがごとし。味、佳ならず、且つ、毒、有り。漁人、之れを取らず。
[やぶちゃん注:現在、クラゲと呼称する場合、狭義には、
刺胞動物門 Cnidaria と有櫛(ゆうしつ)動物門 Ctenophora の異なった二種の生物集団
を挙げるのが一般的である。有櫛動物門は、所謂、刺胞を持たないクラゲである。但し、後鰓類のミノウミウシ亜目 Aeolidina のミノウミウシ類と同様に、摂餌したヒドロクラゲ類の刺胞を消化せずに盗刺胞して自己防衛機能として持つ有櫛動物門有触手綱フウセンクラゲ目フウセンクラゲモドキ科フウセンクラゲモドキ属フウセンクラゲモドキ Haeckelia rubra は例外である。当然、しっかり刺すので、要注意である(因みに、アオミノウミウシの盗刺胞については、嘗つてブログに書いた。痛恨の右腕遠位端骨折のあの日の忘れがたい思い出である)。
しかし、良安の言う「クラゲ」とは、以上の二門以外に、
プランクトンとしてのクラゲ様生物
をも指していると言ってよい。即ち、
浮遊性・寒天状物質によって構成された生体や、「クラゲ」という名を負っている種群を総称する
と考えてよい。そうして、その方がプランクトンたるクラゲという、実は生態学的には前掲の二門に限定するよりも、より正確な生物学的認識に至ることが出来ると私は考えるのである。そこから、まず、
軟体動物門腹足綱ハダカゾウクラゲ上科ゾウクラゲ科のゾウクラゲ Carinaria cristata 等を含むグループ
が追加候補となろう(ゾウクラゲを挙げるなら、同様に貝殻を全く持たないハダカカメガイ(クリオネ)Clione limacina limacina 等を含む後鰓亜綱裸殻翼足目 Gymnosomata のグループも挙げるべきであると考える御仁も居よう。如何にも正論であるが、そうすると、止めどなく大小様々なプランクトンを検証しなくてはならないこととなるので、ここは名にし負うゾウクラゲだけで我慢して頂きたい)。更に、言わば、浮遊性のホヤの仲間と言うべき、脊索動物門尾索動物亜門タリア綱サルパ目サルパ科のサルパ類や、タリア綱ウミタル亜綱ウミタル目ウミタル科 Doliolidae ウミタル類モマタ、良安が見たなら、間違いなく「クラゲ」と認識する(いや、海洋生物関連の記述を見ると、現代生物学でも、プランクトンとしてのクラゲの範疇には、サルパやウミタルが正式に「クラゲ」として認知されているのである)。そこで、以上のグループを目のタクソンまで(一部は亜目まで)表示して、以下に私の考える広義の「クラゲ」を示す(ゾウクラゲは異足目なんて無粋で淋しいタクソンなので、属まで記載した)。何でナマコみたいに科までやらないかって? 二〇〇〇年TBSブリタニカ刊の並河洋「クラゲガイドブック」巻末の「日本産クラゲリスト」の科を数えてみると、刺胞動物門だけで六十五を越えている。「和漢三才圖會」クラゲの注としては、カツオノエボシやボウズニラの触手並みに冗長になってしまうんだ。悪しからず。それでも名数フリークの方のために、二〇〇六年技術評論社刊の久保田信他監修「クラゲのふしぎ」によれば、現生種の場合(同書四十五ページの表3及び表4に「計」を追加した)、
○刺胞動物門クラゲ類の目、科、種の数
鉢クラゲ類 立方クラゲ類 ヒドロクラゲ類 計
目 4 1 11 16
科 22 2 106 130
種 200 20 2700 2920
○有櫛動物門2綱の目、科、種の数
有触手綱 有触手綱 計
目 6 1 7
科 20 1 21
種 93 50 143
因みに、引用書で、は続いて、現在までに最もクラゲの種が豊富な海域として和歌山県田辺湾(南方熊楠先生の故郷!)での調査結果が記されている。その総種数は、実に百四十八種である。
刺胞動物門 Cnidaria
ヒドロ虫綱 Hydrozoa
花クラゲ目 Anthomedusae
軟クラゲ目 Leptomedusae
淡水クラゲ目 Limnomedusae
レングクラゲ目 Laingiomedusae
硬クラゲ目 Trachymedusae
剛クラゲ目 Narcomedusae
盤クラゲ目 Chondrophora
管クラゲ目 Siphonohora
鍾泳亜目 Calycophorae
嚢泳亜目 Cystonectae
胞泳亜目 Physonctae
箱虫綱 Cubozoa
立方クラゲ目 Cubomedusae
鉢虫綱 Scyphozoa
十文字クラゲ目 Stauromedusae
(*このナガアサガオクラゲ科 Cleistocarpidae (シャンデリアクラゲの仲間である北海道に棲息する寒帯系のウチダシャンデリアクラゲ Manania uchidai 等)・アサガオクラゲ科 Haliclystidae (ムシクラゲ Stenoscyphus inabei 等)・ジュウモンジクラゲ科 Kishinouyeidae (ジュウモンジクラゲ Kishinouyea nagatensis 等)の三科からなる十文字クラゲ類は、十文字クラゲ綱 Staurozoa として独立させる説もあるが、孰れにせよ、本族の属する種は、柄によって海草や海藻等に固着し、プラヌラ幼生でさえも泳ぐことがなく、終生、水中を漂うことがない。従って、これは何とクラゲでありながら、良安の記載からは「クラゲ」と見なされないクラゲということになろうかとも思われる。いや! このクラゲは生態から見ても狭義のプランクトンでさえ、ないのだ!
冠クラゲ目 Coronatae
旗口クラゲ科 Semaeostomeae
根口クラゲ目 Rhizostomeae
羽クラゲ目 Pteromedusae
有櫛動物門 Ctenophora
無触手綱 Nudatentaculata
ウリクラゲ目 Beroida
有触手綱 Tentaculata
オビクラゲ目 Cestida
フウセンクラゲ目 Cydippida
カブトクラゲ目 Lobata
軟体動物門 Mollusca
腹足綱 Gastropoda
前鰓亜綱 Prosobranchia
異足目 Heteropoda
ゾウクラゲ科Carindariidae
カエデゾウクラゲ属 Caradiopoda
ゾウクラゲ属 Carinaria
ゾウクラゲ Carinaria cristata 等
コノハゾウクラゲ属 Pterosoma
脊索動物門 Chordata
尾索動物亜門 Urochordata
サルパ綱(タリア)綱 Thaliacea
筋体(ウミタル)亜綱 Myosomata
環筋(ウミタル)目 Cyclomyaria
ダンキン目 Desmomyaria
ハンキン目 Hemimyaria
サルパ目 Salpida
・「樗蒲」(ちょぼ)は本邦では「かりうち」とも言い、楕円形の平たい木片を、一方を白、一方を黒く塗ったもの四枚を用い、それを投げて、出た面の組合せで勝負を競う博打の一種を指す。朝鮮では「ユッ」と言う、これとほぼ同じものが、骸子の代りに現在でも用いられているという。また、「樗」はミツバウツギ科のゴンズイ Euscaphis japonica 、「蒲」はヤナギ科のカワヤナギ Salix gilgiana で、ともに、骸子の材料に用いられた木である。
・『「海月」の二字を用ふは非なり』とは、良安が「海月」を、既に巻四十七の「介貝部」で、「海鏡」(斧足類のマルスダレガイ科カガミガイか、ナミマガシワ科マドガイ)に同定しているからである。
・「渾然」とは、全く差や違和感がなく、一つのまとまりになっているさま、もしくは角や窪みのないさまを言う。まさに、クラゲのためにあるような語である。
・「腹の下に、物、有り。絮を懸ごとし」は、主として鉢クラゲ類で目立つ口腕、及び、一部の種の、その口腕の附属器を指しているのであろう。当然、その他の縁弁を含む傘縁触手や、有櫛動物の場合の触手も含んでいると考えてよい。
・「羣蝦、之れに附きて」は、まず、挿絵みないで、想起したのは、エビの方ではなくて、鉢虫綱根口クラゲ目イボクラゲ科エビクラゲ属エビクラゲ Netrostoma setouchianum だろう。ここで共生するエビは、特定種のエビではないようである(ただ、研究されていないだけで、特定種かも知れない)が、好んで、鉢虫・ヒドロ虫類、及び、クシクラゲ類・サルパ類に寄生するエビとなれば、
節足動物門大顎亜門甲殻綱エビ亜綱エビ下綱フクロエビ上目端脚目(ヨコエビ目)クラゲノミ亜目 Hyperiidea に属するクラゲノミHyperiame medusarum や、オオタルマワシ Phronima stebbingi 、クラゲノミ亜目のウミノミ類辺りが挙げられよう。
・「浮汎」の「汎」は、やはり浮かぶこと。
・「潮の爲に擁せらるれば」は、原文の「所」を受身で読む。「擁」は、「かかえる・覆う」の意であるから、「潮流に包まれると」の意。
・「割〔(わけ)〕て」の部分を、東洋文庫版は「捕って割(さ)く」と訳している。しかし、それでは語順がおかしい。私は、この部分の前後に記されるエビとクラゲの共生論を前提としての語と捉え、クラゲの眼となっているエビがいなくなって航行不能に陥ったクラゲを、即ち、エビとクラゲを「分けた」(別れた)ところで、容易に捕獲する、の意味でとる。
・「猶ほ蛩蛩の駏驉とのごとし」「蛩蛩と駏驉のように仲がよい・一心同体である・離れては存在しない・生きてゆけない」といった意味である。この二種の生物は、「山海経」及びその注に登場する架空の獣名である。以下に「山海経」の「海外北経」から引用する(私が中文電子テクストで重宝している中国の方のサイト「翰廬」の「山海經海經新釋卷三」より。●はママ)。
*
北海内有獸,其狀如馬,名曰騊駼。有獸焉,其名曰駮,狀如白馬,鋸牙,食虎豹。有素獸焉,狀如馬,名曰蛩蛩。有青獸焉,狀如虎,名曰羅羅。
*
その「蛩蛩」についての注は、
郭璞云:「即蛩蛩鉅虛也,一走百里,見穆天子傳(卷一);音邛。」珂案:周書王會篇云:「獨鹿邛邛,善走也。」孔晁注:「獨鹿,西方之戎也;邛邛,獸,似距虛,負●而走也。」實則邛邛、距虛乃是一物,即爾雅釋地所記「邛邛岠虛」也。呂氏春秋不廣篇云:「北方有獸,名曰蹶,鼠前而兔後,趨則跲,走則顛,常爲蛩蛩距虛取甘草以與之。蹶有患害也,蛩蛩距虛必負而走。」是猶比肩之獸也。
*
この二匹は同なじだと言ってみたり、頭がネズミで、下半身が兎の、蹶(ケツ)なんて奴に養われていると言ったり、蛩蛩と距虚は、常に伴って走ると言ってみたり……何だかよく分かんない~! しかし、この、一説に白い馬に似ているという幻獣の蛩蛩と、その同類であるとする駏驉が、比翼の鳥や、連理の枝と同義的に用いられているのは、韓愈の詩「醉留東野」(私の愛する漢詩サイト「詩詞世界 碇豊長の漢詩」を参考にした)に、
*
願得終始如駏蛩
願はくは 終始 駏蛩(きよきよう)のごとくあらんことを得ん
○やぶちゃん訳
友たる孟東野(孟郊)君と私が どうかいつまでも蛩蛩と駏驉のように一心同体であることを望む
*
とあることからも分かる(当該ページの同詩句の注を、是非、参照されたい)。
しかしながら、勿論、良安が考えたように、エビがクラゲの眼の代わりなわけでもなく、クラゲも、それが去ることで、捕獲=死の憂き目に逢うわけでもない。サンゴとゾーザンテラ(褐虫藻) zooxanthella のように一蓮托生のものに、こ蛩蛩と駏驉の比喩は使いたいものだ。
・「䖳頭」時珍の記載ということを考慮するならば、最大級の種としての鉢虫綱根口クラゲ目ビゼンクラゲ科エチゼンクラゲ属エチゼンクラゲ Nemopilema nomurai に同定してよいであろう。傘径2m・体重200㎏に達する個体もある。厳密な意味で種としての最大種は、並河洋「クラゲガイドブック」によれば、鉢虫綱旗口クラゲ目ユウレイクラゲ科ユウレイクラゲ属キタユウレイクラゲ Cyanea capillata の北方(バルチック海等)種で、現在までの確認個体は傘径二・五メートル、全長は四十メートルにも達する。
・「茄柴」を東洋文庫版は『茄子の木』と訳している。「廣漢和辭典」によれば、「茄」は、まず、「蓮の茎・蓮」を指すとある。蓮の茎や根茎を乾したものを指している可能性もあるように思われる。
・「淹れて」を東洋文庫版は『淹(しおづけ)にして』と訳している。しかし、本字に「塩漬け」の意味はない。良安がよく用いる「塩漬け」の意味の「腌」の衍字と取るのならば、そのように注記するべきであるが、注記もなく、「淹」の字をそのまま用いて、「しおづけ」とルビしている。さらに原文は送り仮名を「テ」しか送っていない。もし良安が本字をそのように読んでいるとするならば、彼の書き癖からいって「シテ」又は「ニシテ」とルビを振ると思われる。勿論、この部分の叙述から、その意味としては、「塩漬け」でよいのあるが、私はここは「淹(いれ)て」と普通に訓読する。
・「石灰・礬水」の「礬水」は、「どうさ」と当て字読みし、「膠(にかわ)とミョウバンを水に溶かした液体のことを指す。一般には、和紙や絹地の表面に薄く引いて、墨や絵具等が滲むのを防ぐ効果を持つ顔料である。しかし、ここでは単に明礬(ミョウバン)=硫酸アルミニウムカリウム12水和物 AlK(SO4)2・12H2Oの水溶液を指していると考えられる。「石灰」は、消石灰=水酸化カルシウムCa(OH)2である。
・「鉤栗」は、東洋文庫版で『くぬぎ』とルビしている。このような処理法を遂に発見し得なかったが、取り敢えず、ブナ目ブナ科コナラ属クヌギ Quercus acutissima に同定しておく。
・「夫木和歌抄」延慶三(一三一〇)年頃に成立した藤原長清撰になる私撰和歌集。動植物を詠んだ珍しいタイプの和歌も多く採録されている。この和歌は、原文の作者名「仲正」を「仲之」と誤まっている。源仲正(仲政とも書く)は平安末期の武士、酒呑童子や土蜘蛛退治で有名なゴーストバスター源頼光の曾孫である。即ち、ひいじいさんの霊的パワーは彼の息子、鵺(ぬえ)退治の源頼政に隔世遺伝してしまい、仲正の存在はその狭間ですっかり忘れ去られている。しかし歌人としてはこの和歌に表れているような、まことにユーモラスな歌風を持つ。当該歌と思われるものは「夫木和歌抄」巻二十七雑九にあるが、以下の通り、正しくは「海の月」が「浦の月」、「くらげもほね(骨)に」が「くらげのほね(骨)も」、「「逢ふせ(瀨)」が「逢ふ夜」である。二首を比較しやすいように漢字仮名を一致させて並べてみる。
(原典)我が戀は浦の月をぞ待ちわたるくらげのほねに逢ふ夜ありやと
(引用)我が戀は海の月をぞ待ちわたるくらげもほねに逢ふ瀨ありやと
この二首の和歌を試みに訳してみる(私は和歌は苦手であるので、解釈の不味さはご容赦願いたい)。
(原典)やぶちゃん訳:私の恋は、浦に上ぼる遅い月をひたすら待ち続けるようなもの……意地悪くも、その上ぼる月が水面に映ったかと見紛う、海月(くらげ)……その海月の骨に出逢う夜が、世が、時がやって来るのであろうか? いや、それは海月に骨がないように、私の恋は、決して成就することなどないに違いない……
(引用)やぶちゃん訳:私の恋は、海に上る遅い月をひたすら待ち続けるようなもの……意地悪くもその上ぼる月が水面に映ったかと見紛う、海月……その海月が、かつて抜かれてしまった骨に出逢う瀨が、流れが、時がやって来るのであろうか? いや、もともと骨を持たぬ海月には永遠に骨は還ってこない……同じように私の恋は、決して成就することなどないに違いない……
良安の方は、クラゲを歌の中で強調するために、恣意的に「海」「瀨」というより強い縁語に換えられており、係助詞「も」の使用によって、更に捩れた意味合いを暗示するかのように読めるよう改変されている。即ち、これは勿論、和歌引用の際の誤りではなく、パロディ作家仲正の歌の更なる狂歌化なのだ。さればこそ、良安は、わざと「仲正」を「仲之」として本歌を架空の作品として示したのかも知れない。
・「肥前水母」(ヒゼンクラゲ)良安はこれを塩クラゲの製法違いとしているが、既に横綱エチゼンクラゲに土俵入りしてもらっている以上、やはり種としてのヒゼンクラゲにも控えてもらおう。
ところが、その前に片付けておかなくてはならない事柄がある。私は実は、若い頃、永い間、肥前(佐賀県と長崎県の一部)や備前(岡山県と兵庫県の一部)といった漁獲された旧国名からついた和名が極めて似ているため、この鉢虫綱根口クラゲ目ビゼンクラゲ科ビゼンクラゲ属ヒゼンクラゲ Rhopilema hispidum という種と、同属異種のビゼンクラゲ Rhopilema esculenta という種が、同一のクラゲの和名異名であると思っていた(事実、前掲の二冊の、かなり新しいクラゲの出版物でも、索引にはビゼンクラゲしか載らない)。次に、少し経って、ヒゼンクラゲというのは、ビゼンクラゲに極めて類似したスナイロクラゲ Rhopilema asamushiのシノニムではないかとも疑った。ところが、レッド・データ・リスト等を検索する内、実際には、この三種はすべて同属の別種であるという記載があり、また、多くの観察者の記載や画像を見るに、私も、これらは異なった種であろうという印象を持つに至った。即ち、クラゲ加工業者の間で「白(シロクラゲ)」と呼称されるヒゼンクラゲ Rhopilema hispidum は有明海固有種であり、私がシノニムを疑ったスナイロクラゲは、その分布域が、九州から陸奥湾に広く分布するという記述だけで、最早、同一ではあり得ず、また、ビゼンクラゲ Rhopilema esculenta は、業者が「赤(アカクラゲ)」と呼称するように、傘が有意に褐色を帯びており(但し、ヒゼンクラゲでも傘に紅斑点があるものがあり、その方が「塩クラゲ」にするには上質とされるらしい)、見るからに異なったクラゲに見えるのである。今後のアイソザイム分析が楽しみである。
更に付け加えておくと、現在、大量発生で問題になっている ビゼンクラゲ科エチゼンクラゲ属エチゼンクラゲ Nemopilema nomurai については、実は、日本では過去に塩クラゲ加工の歴史はなかった、というのも眼からクラゲであった。恐らく、昔はあんまり来なかったんじゃないか? はい、江戸博物書の注であっても、やっぱり温暖化の問題は避けて通れませんね。
更に追伸。「唐水母」(とうくらげ)という名称は、今の異名としては残っていない。ところが「唐海月」という語ならば、井原西鶴の「好色一代女」卷五の冒頭「石垣戀崩」に『おそらく我等百十九軒の茶屋いづれへまゐつても。蜆やなど吸物唐海月ばかりで酒飮だ事はない。』と出て来る(近世物は苦手なので注釈書が手元にないので、これまでである)。しかし、これは、もしかすると、もともとは、中国製の加工食品としての塩クラゲを言う言葉ではなかったか。その製法が、江戸期に日本に伝わり、肥前で作られたものに、この呼称が残ったとは言えまいか? あ! されば、そのルーツはまさにエチゼンクラゲ製であったかも知れないぞ?!
・「水海(みづくらげ)」鉢虫綱旗口クラゲ目ミズクラゲ科 Ulmaridae の主な日本産の種を挙げておく。
ミズクラゲ科 Ulmaridae
ミズクラゲ亜科 Aureliinae
ミズクラゲ属ミズクラゲ Aurelia aurita
キタミズクラゲ Aurelia limbata
アマガサクラゲ亜科 Ulmarinae
アマガサクラゲ属アマガサクラゲ Parumbrosa polylobata
サムクラゲ Phacellophora camtschatica
解せぬのは「毒」。いや、ミズクラゲだって毒があるなんてことは百も承知。問題は、何で良安先生、ここに至るまで刺胞毒のことを、一切記述せず、よりによって、刺胞毒の弱いミズクラゲの個別項目で「毒、有り」なの? って感じ。可能性の一つとして、アマガサクラゲ等の刺胞毒の強い白色系のクラゲの情報が、ここに紛れ込んでいるのかも知れないが(でも、アマガサクラゲは深海性ですぜ?)、それにしても、「毒」はどうも、「食」の「毒」のように読めてしまい……更に更に、私の疑問は、こんがらがって、ヒドロ虫綱管クラゲ目ボウズニラ Rhizophysa eysenhardti か、ヒドロ虫綱クダクラゲ目嚢泳亜目カツオノエボシ科カツオノエボシ属カツオノエボシ Physalia physalis の触手に刺され、アナフラキシー・ショック状態だわん! 本当はクラゲは、刺胞毒の話が、一番、好きなのに! キライ! 良安センセ!]
***
すゝめうを 海牛
うみすゝめ
綳魚 【俗云雀魚】
食物本草云綳魚形似河豚而小背青有斑紋無鱗尾不
岐腹白有刺戟人手亦善嗔嗔則腹脹大圓緊如泡仰浮
水靣〔=面〕
日本紀齋明帝時於雲州北海濵魚死而積厚三尺許其
大如鮐雀喙針鱗鱗長數寸是雀入於海爲魚也名曰雀
魚
△按雀魚今亦處處有之狀類雀而首短額有一小角嘴
尖如鳥無足有四鰭尾向上背腹方有四稜無鱗如鮫
皮而有龜甲紋灰白色大不過三四寸世人未食之或
《改ページ》
用海牛字未知其據又日本紀所謂者與今雀魚異
*
すゞめうを 海牛
うみすゞめ
綳魚 【俗に「雀魚」と云ふ。】
「食物本草」に云ふ、『綳魚〔(はうぎよ)〕は、形、河豚に似て、小〔さく〕、背、青く、斑紋、有り。鱗、無し、尾、岐〔(また)〕、あらず、腹、白くして、刺〔(とげ)〕、有り、人の手を戟(つ)く。亦、善く嗔〔(いか)〕る。嗔れば、則ち、腹、脹れ、大いに圓緊〔(ゑんきん)〕にして、泡のごとし。仰ぎて、水面に浮く。』と。
「日本紀」に、『齋明帝の時、雲州〔=出雲〕北海の濵に於いて、魚、死して、積むこと、厚さ三尺ばかり、其の大いさ、「鮐〔(ふぐ)〕」のごとく、雀の喙〔(くちばし)〕、針の鱗、あり。鱗の長さ、數寸〔(すすん)〕、是れ、雀、海に入りて、魚と爲るなり。名づけて「雀魚」と曰ふ。』と。
△按ずるに、雀魚は、今、亦、處處、之れ、有り。狀〔(かたち)〕、雀の類にして、首〔(かうべ)〕、短く、額に、一〔(いつ)〕の、小さき角、有り。嘴〔(きちばし)〕、尖り、鳥のごとく、足、無く、四〔(よつ)〕の鰭(ひれ)、有り。尾、上に向ひて、背・腹の方にして、四つ、稜(かど)、有り。鱗、無くして、鮫皮のごとくにして、龜甲の紋、有り。灰白色。大いさ、三、四寸に過ぎず。世人、未だ、之れを食はず。或いは、「海牛」の字を用ふ。未だ、其の據〔(よることろ)〕を知らず。又、「日本紀」に謂ふ所の者は、今の「雀魚」と〔は〕異なり。
[やぶちゃん注:良安が最後に相違を明示している通り、ここで引用された「食物本草」及び「日本紀」の記述しているのは
フグ目ハリセンボン科ハリセンボン Diodon holocanthus
若しくは、その同属種である、
ネズミフグ Diodon hystrix
ヒトヅラハリセンボン Diodon liturosus
又は、同じハリセンボン科の、
イシガキフグ属イシガキフグ Chilomycterus reticulates
等を指しており、良安が記述し挿絵としているものは、眼上棘の記載に不審はあるものの(後述)、同フグ目の、
ハコフグ科コンゴウフグ属ウミスズメ Lactoria diaphana
若しくは、その近縁種である同属の、
シマウミスズメ Lactoria fornasini
コンゴウフグ Lactoria cornuta
等を指していると考えて間違いない。
・「食物本草」は、元の李杲(りこう 一一八〇年~一二五一年:医師。金元四大家の一人。張元素について医学を学んだ。号の東垣(とうえん)の号でも有名。脾胃を補うのを治病の根本としたので、「補土派」「温補派」などと呼ばれた。また、朱震亨と併称して「李朱医学」と称される。「脾胃論」ほか、多くの著作がある)編とされる本草の中から食物だけを抽出し、その薬効等を論じたもので、「本草綱目」の李時珍が注したものが知られ、良安の引用も時珍のものである。国立国会図書館デジタルコレクションで崇禎一一(一六三八)年翁小麓刊(版本)の当該部分(右丁六行目。ここでは先に字下げで時珍が注を附した(△部)後に、本文が出る形式である)が視認出来る。
・「綳魚」の「綳」=「繃」で、「たばねる」の意。これはまさにハリセンボンの通常時、怒張していない時の棘を状態を指し示している。
・「圓緊」は、まさにフグが丸くパンパンに膨れ上がる様子を、如実に示す語である。
・「日本紀」は「日本書紀」。斉明天皇の在位は六五五年から六六一年まで。該当部分を示す。
*
斉明天皇四年[やぶちゃん注:六五八年。以下、中略。]、出雲國言。於北海濱魚死而積。厚三尺許。其大如鮐。雀喙針鱗。鱗長數寸。俗曰。雀入於海化而爲魚。名曰雀魚。[やぶちゃん注:後略。]
*
・「北海の濵」については、現在、出雲市の北東部(旧平田市の北西部)に十六島湾(うっぷるいわん)に面した北浜村が嘗つてはあった。「ひなたGPS」のこちらの戦前の地図の方を参照されたい。因みに、この特異な湾名・地名の読みは、古代朝鮮語起源であると言われる。
・「世人、未だ、之れを食はず」とあるが、現在は食用とする(ハコフグ類の旨さは五島列島の「カトッポ」等、珍味の呼び声高いが、残念なことに私は未だ食したことがない。「カトッポ」は、ハコフグを背開きして内臓を除去し、その「ハコ」に、キモと麦味噌と刻んだ玉葱・生姜ものを混ぜて詰めて焼いたもので、内側の体壁の身をこそいで和えて食うらしい。こうしてシュミレーションしているだけで唾が出てくる)。食用状況については「ウミスズメ 市場魚貝類図鑑」によく纏まっているので、参照されたい。ちなみにハコフグ類は体内にテトロドトキシンを持たないが、そのほとんどが体表の粘液にパフトキシン pahutoxin というかなり強い魚毒(赤血球破壊作用)を持っている。多くの記載は、人体に影響がなく、焼くことによって無毒化するとするが、この毒素は内臓部分にも、微量ながら含まれているという記載もある(毒成分の記載は、やはり正確であるべきだと思う。最後の記述が正しいとすれば、体表粘液のみとしている記載は、たとえ人体に無害であっても、明記すべきであると私は考える。更に附け加えておくと、この毒、本人=本魚にも作用してしまうらしい。海水魚飼育関係の記載に、パフトキシンを分泌したハコフグ自身が死んでしまったとある。但し、これ、パフトキシンを分泌したストレスによって生じたもので、毒自体は主死因でないと言えれば、の話だ)。
・「或いは、「海牛」の字を用ふ。未だ、其の據を知らず」(この魚に「海牛」の字を当てる場合がある。しかし、未だにそのように呼称する根拠は不明である)と良安は言うのだが、そもそもウミスズメには、良安が、前で記述する「額に、一の小さき角、有り」という記載に反して、両眼の前方に張り出した棘が一対(眼上棘という。また、腹側隆起の後端からは、同様の腰骨棘一対が出る)がある。接写でウミスズメの面長(おもなが)の頭部を見ていると、その両棘と、突き出した口吻全体は、鳥というよりも、角のある牛に、かなり似ていると私は思う。因みに、同属のコンゴウフグでは、この眼上棘と腰骨棘が強烈に長くなって、そのフォルムはシュールでさえある。グーグル画像検索「コンゴウフグ」をリンクさせておしまいと致す。]
***
ゑび 海老【俗】
鰕【音霞】 【和名衣比】
ヒアヽ
本綱鰕凡江湖出者大而色白溪池出者小而色青皆磔
鬚鍼鼻背有斷節尾有硬鱗多足而好躍其腸屬腦其子
在腹外凡有數種米鰕糠※〔=鰕〕【以精粗名】青鰕白鰕【以色名之】泥鰕海
[やぶちゃん字注:「※」=「𩵋」+(「鰕」-「魚」の右半分を「殳」に代えた「鰕」の異体字。訓読では「鰕」に代えた。次行の頭も同じ。]
※【以出產名】梅鰕【以梅雨時有名之】有天鰕其蟲大如蟻秋社後羣堕
水中化爲鰕凡鰕之大者蒸曝去殻謂之鰕米食以薑醋
所珍凡蝦〔=鰕〕類【甘温有小毒】水田及溝渠者有毒【小兒及雞狗食鰕脚屈弱】
△按鰕處處有之其品類亦多不可悉記
真鰕 大二三寸皮薄而白手足鬚共短細煮之淡赤色
味甘美有河海之交江戸芝鰕是也
《改ページ》
■和漢三才圖會 江海無鱗魚 卷ノ五十一 ○二十四
車鰕 大四五寸皮厚而節隆有褐白色橫文煮之變紅
形曲如車輪故名自夏出秋冬盛味最甘美爲上品
手長鰕【一名川鰕】 大二三寸兩手肥長有螯其雌者形相似
而手小無螯腹下抱多子煮之正紅色
白狹鰕 大二三寸白色煮之亦不赤
川鰕 大一寸許褐色冬月江池取之與蘿蔔同煮食味
甘美又爲彈塗魚餌可也
尻引鰕 大一寸余頭尾短其背微扁煑之不赤雜肴中
混來是爲鰕中之下品
*
ゑび 海老【俗。】
鰕【音、霞。】 【和名は「衣比」。】
ヒアヽ
「本綱」に、『鰕は、凡そ、江湖に出づる者、大にして、色、白し。溪池に出づる者、小にして、色、青し。皆、磔鬚〔(たくしゆ)〕、鉞鼻〔(ゑつび)〕、背に、斷節、有り、尾に、硬き鱗、有り。多き足にして、躍るを、好みて、其の腸、腦に屬(つゞ)く。其の子、腹の外に在り。凡そ、數種〔(すしゆ)〕、有り。米鰕〔(こめえび)〕・糠鰕〔(ぬかえび)〕【精・粗を以つて名づく。】。青鰕・白鰕【色を以つて、之れを名づく。】。泥鰕・海鰕【出產を以つて名づく。】。梅鰕〔(うめえび)〕【梅雨(つゆ)の時、有るを以つて、之れを名づく。】。天鰕〔(てんえび)〕、有り。其の蟲の大いさ、蟻のごとく、秋社〔(しうしや)〕の後、羣れて、水中に堕ち、化して、鰕と爲る。凡そ、鰕の大なるは、蒸〔し〕曝〔(さら)し〕、殻を去りて、之れを「鰕米〔(こめえび)〕と謂ふ。食ふに、薑醋〔(しやうがず):生姜酢。〕を以つて〔し〕、珍とする所なり。凡そ、蝦の類【甘、温。小毒、有り。】、水田、及び、溝-渠(みぞ)の者には、毒、有り【小兒、及び、雞〔(にはとり)〕・狗〔(いぬ)〕、鰕を食ひ、脚〔(あし)〕、屈〔(かが)まり〕弱〔る〕。】。』と。
△按ずるに、鰕は、處處、之れ、有り。其の品類、亦、多し。悉く記すべからず。
真鰕(まゑび) 大いさ、二、三寸。皮、薄くして白く、手・足・鬚、共に、短く、細く、之れを煮れば、淡赤色。味、甘美。河海の交(あはひ)に有り。江戸芝の鰕、是れなり。
車鰕 大いさ、四、五寸。皮、厚くして、節、隆(たか)く、褐白(きぐろ)色の橫文、有り。之れを煮れば、紅に變ず。形、曲(かゞま)り、車輪のごとし。故に名づく。夏より出でて、秋・冬、盛んに、〔→盛んに出づ。〕味、最も甘美。上品たり。
手長(てなが)鰕【一名、「川鰕」。】 大いさ、二、三寸。兩の手、肥えて、長く、螯(はさみ)、有り。其の雌(めす)は、形、相〔(あひ)〕似て、手、小さく、螯(はさみ)、無し。腹の下に、多き子を抱く。之れを煮れば、正紅色〔となる〕。
白狹(しらさ)鰕 大いさ、二、三寸。白色。之れを煮て亦、赤からず。
川鰕〔(かはえび)〕 大いさ、一寸許〔(ばかり)〕。褐色。冬月、江池に、之れを取る。蘿蔔〔(だいこん)〕と同じく〔:共に〕煮て、食ふ。味、甘美。又、彈-塗-魚(はぜ)の餌と爲して、可なり。
尻引鰕 大いさ、一寸余。頭・尾、短く、其の背、微〔(やや)〕扁たく、之れを煑て、赤からず。雜-肴(ざこ)の中に混(まぜ〔→まぢり〕)て來〔(きた)〕る。是れ、鰕〔の〕中の下品たり。
[やぶちゃん注:基本は、現在の節足動物門 Arthropoda 甲殻亜門 Crustacea 軟甲(エビ)綱 Malacostraca ホンエビ上目 Eucarida 十脚(エビ)目 Decapoda に属する生物の内、異尾(ヤドカリ)下目 Anomura ( Anomala )と短尾(カニ)下目 Brachyura を除いた生物群の総称である「エビ」類についての総論である。但し、多くの人が「エビ」と誤認している、アミ(糠蝦・醤蝦)類、則ち、軟甲綱真軟甲亜綱フクロエビ上目アミ目 Mysida に属する小型甲殻類も、良安は、やはり現代の大多数の人と同様、「エビ」と認識していると読めるので、注意されたい。項目冒頭の和訓「ゑび」と、本文内の「ゑび」もママ。
・「磔鬚」の「磔」は、「裂く」の意味を取って、「裂けた細い鬚(ひげ)」の意味と取りたい。東洋文庫版は『はりひげ』とルビを振るが、ややごまかしの感がある。
・「鉞鼻」の「鉞」は、武器の「まさかり」の意味であるが(東洋文庫版では『おの』とルビを振る)、所謂、金太郎の背負う斧、古い大きい鉞とは私には思われない。この「鉞」は、本来、天子が征伐を命じる際に将軍に手渡したもので、「大漢和辭典」の図版を見ると、長い槍の頭部に、横に半円の歯(所謂、「マサカリ」部分)が附属して出ている。また、後に儀仗に用いられたとも記されており、これは長い尖がった槍のようなものをイメージすべきではないか。その方が又、エビの頭部先端の飛び出た棘を表わすに頗る自然であると思われるからである。
・「其の腸、腦に屬(つゞ)く」というのは、エビの腸管が背部にあり、それが頭胸甲に続いているために、このように表現したものと思われる。俗に言う「背ワタ」が、腸であることは、エビ類の摂餌後の「背ワタ」の色の変化を見れば、古い時代でも十分に理解されたのではないかと私は推測する。
・「米鰕」は「糠蝦」を小型のエビ類や、エビではないが、一見、エビに見えるアミ類と見るならば、それに比較して、やや大きな中型のエビ類を指すと考えてよいわけだが(「米」の意味は後述の「鰕米」の注を参照)、「米」という字を含むエビとしては、現代中国の分類表では、抱卵亜目コエビ下目ヌマエビ科 Atydae =「匙指虾科」(「蝦」「鰕」の異体字)の属名に「米虾属」があり、つけられている(維基百科の「米虾属」を参照)が、これは、本邦の抱卵亜目コエビ下目ヌマエビ科ヒメヌマエビ亜科ヒメヌマエビ属 Caridina (日本産ヌマエビ類でも約二十種の内、半分が本属であり、南西諸島で種類が多い)の中文名である。以下、「天鰕」まで、「本草綱目」の記載である点に留意しながら、同定考察を行った。
・「糠鰕」は、現代中国語では、生のアミ(エビ亜綱フクロエビ上目アミ目 Mysidacea に属する小型甲殻類を指す(再度、言うが、このアミ類は真正の「エビ」ではない)。特に、その中のアミ科 Mysidae に属する種の総称)を言う。なお、本邦には、真正の「エビ」である「糠鰕」、抱卵亜目ヌマエビ科ヌカエビ Paratya compressa improvisa がいる。但し、この本邦の「ヌカエビ」は日本固有種で、近畿以北の本州北部のみに分布する純淡水生の「エビ」であるから、「本草綱目」の同定としては、無効となる。
・「青鰕」は、漢方で、後掲されるコエビ下目テナガエビ上科テナガエビ科テナガエビ亜科テナガエビ属テナガエビ Macrobrachium nipponense を指すとする記述があったが、大陸産テナガエビが、果たして本種と全く同種であるかどうかは、やや疑問である。なお、本邦では幾つかの種の異名としてあるものの、どうも、中国のそれと合いそうな種はいない。
・「白鰕」は、現代中国では、流通での通称和名バナメイエビ Litopenaeus vannamei に用いられるが、本種はメキシコからペルーの太平洋東岸に原産するエビで、中国産は現代の養殖物であるから、違う(因みに、本種の中国産冷凍エビから、二〇〇三年の日本で基準値を遥かに越える抗生物質クロルテトラサイクリン chlortetracycline が検出され、回収される騒ぎが記憶にある。私はペルーのホテルで食べたが、大味で、旨いとは思わなかった)。私は、これは蘇州近くの無錫にある太湖の名産「太湖三白」(銀魚・白魚・白蝦)に数えられる「白蝦」で、テナガエビ科のトサカスジエビ属の Exopalaemon modestus (和名不詳)ではないかと思う。
・「泥鰕」については、「『東方広東語辞典』にみえる不適切な記述」に『川エビの一種;学名を Metapenaeus ensis という.』という記述の訂正案として、『ヨシエビ.シラサエビ;香港で目にする“基圍蝦”の代表種の広東省湛江周辺での言い方.』と記されている。ヨシエビは、根鰓亜目クルマエビ科ヨシエビ属ヨシエビ Metapenaeus ensis であり、シラサエビは後述するように、抱卵亜目オキエビ科シラエビ Pasiphaea japonica である可能性が高い。これで終わりかと思いきや、検索をかけると、ところがどっこい、台湾海洋大学甲殻類標本のリストでは、ヤドカリ下目ハサミシャコエビ科 Laomediidae に「泥蝦科」の名前が見出される。ダメ押しで、本邦では抱卵亜目エビジャコ科クロザコエビ属クロザコエビに「泥鰕」の別名が与えられてあった……実に、この同定戦、「泥」試合の様相を呈してきた。
・「海鰕」は一見、叙述からも、海産のエビ類全般でいいようにも思えるが、狭義の「海蝦」は、どうも、クルマエビ科クルマエビ属コウライエビ(「タイショウエビ」の異名の方が違和感がない) Penaeus chinensis を指しているらしい。ここでは、日中同じ可能性が高い、同定比定出来た稀有のケースとなった。
・「梅鰕」これは同定不可能と思われたが、一つの候補として、本邦では、まさに梅雨の時期に漁期が盛んとなるのが、先に示し、後にも出る、テナガエビ Macrobrachium nipponense であることから、同属の一種である可能性が浮上してくる。但し、前と同じく、時珍の指しているのと同一種とするには、私は疑問がある。
・「天鰕」については、まず、宋の洪容斎「夷堅志」に、蟻が蝦に変じる話が載るとある(肝冷斎氏の個人サイト「肝冷斎雑志」のこのページの平成一八(二〇〇六)年五月十六日の記事を参照)。その「夷堅志」叙述の末尾で、「始験其骸為蟻所食而復堕蝦類云。」(始めて、その骸の蟻の食らふ所と為り、復た蝦類に堕せることを験す、と云ふ。)の部分を、肝冷斎氏(この人は全く私の知らない方である。法律関係のお仕事とお見受けする)は『やっと、その老人の死骸がありんこに食われて、その(肉を食べた)ありんこが再びえびの類に化けた、ということが証明されたのだ、とおっしゃっていた。』と訳され、その後、良安が「和漢三才図会」に引用した「本草綱目」を引用して、『謝亮大さん[やぶちゃん注:この蟻の蝦への変生を目撃した実在した政治家。]は「証明された」とか何とか言ってますが、地域は少し違いますがおそらくコレですね』と述べられている。読んで頂ければ分かる通り、このエピソード自体はエビ捕りを生業としていた老人の遺体を食った蟻が川に入ってエビとなるという、一種の因果応報譚であって、本件の叙述の補強材料とは言えないのであるが、肝冷斎氏の言うように、この末尾部分は、そのように四百六十年後(!)の時珍の記述と、呼応するように読めないことは、ない。
極めつけは南宋の周去非が書いた「嶺外代答」の「天蛾」の一節(中国語サイトより引用。注を省略し、一部の字を改めた)だ。
*
253 天蝦
南方有飛蟲,有翅如飛蛾,其尾如蟋蟀,色白,身長似小鰕然。夏秋之間,晩飛蔽天,墮水,人以長竹竿橫江面,使風約之,如萍之聚。早乃棹舟搏取,縷肥肉,合以爲鮓,味頗美。然此夜墮水,次早卽取乃可用,稍遲一夕,已脫而化矣。
○やぶちゃん書き下し文
南方に、飛蟲、有り。翅、有りて、蛾の飛ぶがごとく、其の尾は、蟋蟀(しつしゆ)のごとし。色、白く、身、長くして、小鰕然として、似たり。夏秋の間、晩に飛んで、天を蔽ひ、水に墮つ。人、以つて、長き竹竿(ちくかん)を江面に橫へ、風をして、之れを約さしめ、萍(へう)の聚(しう)のごとし。早や、乃(すなは)ち、舟に棹さして搏(う)ち取り、縷(る)・肥肉、合せ以つて、鮓(すし)と爲す。味、頗る美なり。然るに、此れ、夜、水に墮つ。次いで、早く、卽ち、取り、乃ち、用ふべし。やや遲れて、一夕には、已に脫して、化せり。
○やぶちゃんの勝手訳
南方に飛ぶ虫がいる。蛾が飛ぶように飛べる羽があって、その尾はコオロギのようである。色は白く、体形は長く、まさに小エビ然として、似ている。夏と秋の頃、夕暮れに空を覆うように飛び、水に落ちる。人は、長い竹竿を、川の水面に横たえて、風に従って、これらを一つ所に集めたその様は、浮き草の集まったものに似ている。即座に、舟を操って、すくい捕り、細い糸筋のような部分[やぶちゃん注:羽の部分を指すか。]と、肥えた肉部分[やぶちゃん注:ただの旨味のある肉という意味かも知れない。]を合わせて、「なれずし」にする。味は、極めて良い。しかし、これはその夜に水に落ちたものを、翌日、すぐに、掬い取り、食べねばならない。少しでも遅れてしまえば、既に脱皮して、別なものへと化してしまう。
*
これは何? イナゴ(イナゴ科 Catantopidae )みたようなもんじゃないかなあとも思ってみるのだが、イナゴなら、甚大な被害を及ぼす飛蝗の仲間(但し、中国では「蝗」はイナゴを指さず、トノサマバッタや、サバクトビバッタ Schistocerca gregaria を指す)として痛いほど知られていたはずだから、このような奇天烈な化生を記す必要なないしなぁ。また、空を覆うほど群舞し、水面に落下し、それが浮き草の様だ、さても命短く一夜にして化生する……となれば、梶井の「桜の木の下には」だぁ。しかし、たとえば、あの本体のこまいモンカゲロウ科 Ephemeridae の仲間――あの梶井基次郎の「櫻の木の下には」のウスバガゲロウ(ウスバカゲロウ科 Myrmeleontidae )は羽化を渓流の中からとしている以上、大いなる誤りなのである――が「頗る美なり」とは、ちょっと、いや、大いに思えないしなぁ……だいたい、この叙述、名前には天「蝦」とあるが、エビになると明確に本文では言っていないし、その形は「蝦」然としているけれども、味が「蝦」と同じだとも言っていない……遂に「天蝦」そのものに行き会えたのに、ここにきて消化不良になっちゃったなぁ……う~ん、確かにこの手の奇食系のものは、食べ過ぎると、腹、こわすよなぁ……
・「秋社」は、雜節の一つで、秋の社日(しゃにち:産土神(うぶすなしん:生まれた土地の守護神)を祀る日)。秋分に最も近い戊の日(前後同日数の場合は前の方の戊の日)が社日となる。この日、土地神に初穂を供えて収穫を感謝する。
・「鰕米」は「干蝦」(ほしえび)の別称。「米」は、狭義に於いて、「穀類の実の部分の外皮を取り外した部分」を指し、エビの殻を外したものと同義的と言えば、言える。その場合、穀類を狭義の米とせず、豆類も含めて考えれば、ミミクリーとして無理がない。
・「水田、及び、溝渠の者には、毒、有り」は、チュウゴクモクズガニ Eriocheir sinensis 等、淡水産甲殻類に寄生するベルツ肺吸虫 Paragonimus pulmonalis 、或いは、ウエステルマン肺吸虫 Paragonimus westermainii の感染を言ったものか(但し、これらは、淡水産エビからの感染は考えにくい)。割注の症状は、明らかに、エビの形状が、大まかに淡水ガニの親戚のような感じからの類感表現で、考察に値するとも思われないが、これらの肺臓ジストマが肺気腫や気胸を起させる時の病態は、激しい咳き込みや胸痛を示すと思われ、強ち類感とも言えぬかもしれないが。
・「真鰕」「マエビ」「シバエビ」根鰓亜目クルマエビ科ヨシエビ属シバエビ Metapenaeus joyneri に同定する。「マエビ」という呼称はシバエビの地方名として残るところもあるが、「真海老」ということで、流通では、次項の大型高級種のクルマエビの別名としても用いられてしまっている。
・「車鰕」根鰓亜目クルマエビ科クルマエビ属クルマエビ Marsupenaeus japonicus 、及び、その近縁種。
・「手長鰕」「テナガエビ」「カワエビ」抱卵亜目コエビ下目テナガエビ上科テナガエビ科テナガエビ亜科テナガエビ属テナガエビ Macrobrachium nipponense 、ヒラテテナガエビ(ヤマトテナガエビ) Macrobrachium japonicum 、ミナミテナガエビ Macrobrachium formosense の三種が本土種。南西諸島では、これに加えて、さらに六種がいる。テナガエビは別名「カワエビ」とも呼ばれ、そのために混同される後述の「カワエビ」=スジエビ Palaemon paucidens とは、名前だけでなく、互いの種の若い個体自体が、極めて似ている。両者は、しかし、テナガエビの目の後ろにある特有の棘(肝上棘)で区別出来る。長く発達した鋏脚(これは第二歩脚が肥大したものであって、両鋏脚の内側に一対の小さな第一鋏脚が観察出来る)は、良安の述べる通り、♀、及び、若年個体では、細く短い。
・「白狹鰕」「シラサエビ」この呼称で、現在、呼ばれるものとしては、海産のクルマエビ科ヨシエビ属モエビ Metapenaeus moyebi 、及び、淡水産のテナガエビ科スジエビ Palaemon paucidens があるようであるが、後者は、居酒屋で「カワエビ」の空揚げとしてよく出るもので、赤くなるから、この記載に反する。しかし、前者がアスタキサンチン astaxanthin を含まず、赤くならないかどうかは、ネットのフレーズ検索で調べたが、判らなかった。赤くならないことを私が知っており、更に、この名称に最も近似するものとしては、抱卵亜目オキエビ科シラエビ Pasiphaea japonica が挙げられる。
・「川鰕」「カワエビ」はテナガエビ亜科スジエビ Palaemon paucidens 。無論、淡水生。
・「彈塗魚」は「跳鯊」で、スズキ目ハゼ亜目ハゼ科トビハゼ属 Periophthalmus に分類されるハゼの総称であるが、本件では、特に、その中のトビハゼ Periophthalmus modestus を指すと考えてよい。トビハゼは海産であるが、現在でも海産の魚類の釣り餌として淡水エビであるスジエビ Palaemon paucidens は多く利用されている。
・「尻引鰕」このような呼称は現在、見当たらない。叙述の雑魚に交じるという表現から、これを海産と考えてよいならば、テッポウエビ上科モエビ科 Hippolytidae の多様な種、及び、その幼体と捉えてよいようにも思われるが、前の注に「シラサエビ」同様、この種の中の、どの種がアスタキサンチンを含まず、赤くならないかについては、やはり遺憾ながら判らない。また、現在、流通に於いて、「コエビ」と総称される根鰓亜目クルマエビ科アカエビ属アカエビ Metapenaeopsis barbaraz 、同属トラエビ Metapenaeopsis acclivis 、同属キシエビ Metapenaeopsis dalei 、クルマエビ科サルエビ属サルエビ Trachysalambria curvirostris 等の集合群体に絞ることも考えられるが、これらは、どれも赤くなるようである。エビの専門家のご教授を乞うものである。]
***
いせゑび
かまくらゑび
紅鰕
鰝【音浩】 海鰕
【俗云伊勢鰕
又云鎌倉鰕】
[やぶちゃん字注:以上三行は、前三行下に入る。]
本綱紅鰕乃海鰕也皮殻嫩紅色前足有鉗者色如朱長
《改ページ》
一尺許其肉可爲鱠鬚可作簪杖大者七八尺至一丈
五色鰕 閩中有之長尺餘彼人兩兩乾之謂之對鰕
仲正
夫木 今は我世をうみにすむ老ゑひのもくつか下にかゝまりそ
をる
△按紅鰕勢州相州多有之紫黒煮之正赤色口有四鬚
鬚長過一二尺根有硬刺殻有如鋸沙者而尖手足有
節掌指如毛尾端如花葩是稱海老以爲賀祝之肴或
謂有榮螺變成紅鰕而半螺半鰕者人徃徃見之蓋悉
不然也紅鰕腹中有子則是亦山芋變鰻之類矣
*
いせゑび
かまくらゑび
紅鰕
鰝【音、浩。】 海鰕
【俗に「伊勢鰕」と云ふ。又、「鎌倉鰕」と云ふ。】
「本綱」に、『紅鰕は、乃〔(すなは)〕ち、海鰕なり。皮殻、嫩(の〔ん〕)に〔して〕、紅色なり。前足に鉗〔(はさみ)〕有る者は、色、朱のごとく、長さ、一尺許〔(ばかり)〕。其の肉、鱠〔(なます)〕と爲すべし。鬚、簪杖〔(しんぢやう)〕に作るべし。大なる者、七、八尺〔より〕、一丈に至る。
五色鰕 閩中〔(びんちう):福建省中部。〕に、之れ、有り。長さ尺餘。彼〔(か)〕の人、兩〔(ふた)〕つ兩〔(づ)〕つ、之れを乾かし、之れを「對鰕〔(ついか)〕」と謂ふ。』と。
仲正
「夫木」 今は我世をうみにすむ老ゑびのもくづが下にかゞまりぞをる
△按ずるに、紅鰕は、勢州〔=伊勢〕・相州〔=相模〕、多く、之れ有り。紫黒〔(むらさきぐろ)〕く、之れを煮れば、正赤色。口に、四の鬚、有り。鬚、長くして、一、二尺に過ぐ。根に、硬き刺、有り、殻に鋸-沙(をがくづ)のごとくなる者、有りて、尖り、手足に、節〔(ふし)〕、有り。掌〔(て)の〕指は毛のごとく、尾の端、花-葩(はなびら)のごとし。是れ、「海老」と稱して、以つて賀祝の肴と爲す。或る人[やぶちゃん注:「人」は送り仮名にある。]、謂ふ、「榮螺の變じて、紅鰕と成り、半螺・半鰕なる者、有りて、人、徃徃、之れを見る。」〔と〕。蓋し、悉く〔は〕、然らざるなり。紅鰕の腹中に、子、有ることは、則ち、是も亦、「山芋、鰻に變ずる。」の類〔(たぐひ)〕か。
[やぶちゃん注:代表種である、
抱卵亜目イセエビ下目イセエビ上科イセエビ科イセエビ Panulirus japonicus
の外、本邦産種をのみ挙げるならば、
カノコイセエビ Panulirus longipes
シマイセエビ Panulirus penicillatus
ケブカイセエビ Panulirus homarus
ゴシキエビ Panulirus versicolor
ニシキエビ Panulirus ornatusP
等である。「本草綱目」の記載も、同科の仲間を指すものとして、全く違和感がない。
・「鎌倉鰕」例外を注記するならば、カマクラエビは、関東に於いて、イセエビ Panulirus japonicus を指すが、和歌山南部ではイセエビ下目セミエビ科ゾウリエビ属ゾウリエビPariibacus japonicus を指すという(「串本高田食品株式会社」の以下のページ)。正直、これは初耳。
・「嫩に紅色たり」は、「嫩緑」が新緑の意味であり、「嫩」(中国音“nèn”。そこから音に〔ん〕を補ってみた)には別に見た目のよいさまという意味もあるから、「生き生きとした鮮やかな美しい赤である」という意味か。「薄い」という意味もあるが、イセエビではピンとこない。因みに、東洋文庫版では、『わかわかしい紅色』と訳す。
・「簪杖」「かんざし」の本体の柄の部分を指すか。
・「五色鰕」はズバり、ゴシキエビ Panulirus versicolor ととってよいであろう。古くから、下のように観賞用に剥製にされてきたものらしい。
・「對鰕」これは「喜」の字を二つシンメトリックに並べることに繋がるような慣わしであろうか。因みに、現代中国では、クルマエビ科 Penaeidae に「対虾科」(「虾」は「蝦」の異体字で「エビ」の意)の名が付けられており、単に「對蝦」と言った場合は、クルマエビ科クルマエビ属コウライエビ(異名タイショウエビ) Penaeus chinensis を指す。
・「今は我世をうみにすむ老ゑびのもくづが下にかゞまりぞをる」勝手訳すると、「今、私は、世の中に倦まれて、疲れ果ててしまい、海に住んでいる老いた海老が、哀れ、藻屑の下(もと)で、腰もすっかり老い屈まって居るのと同じように、最早、惨めに隠棲しております。」。
・「半螺・半鰕なる者、有り」私は、これは、サザエ類の殻に入ったヤドカリの仲間を伊勢海老の幼体と誤認したものと思う。ヤドカリ科 Diogenidae のオニヤドカリ属 Aniculus や、ヤドカリ属 Dardanus には相当に巨大で、鋏脚も立派な種や個体がおり、充分、誤認し得ると思うからである。
・「蓋し悉く然らざるなり……」について。彼は「巻九十六 蔓草類」の「萆薢」(ひかい・ところ)=ヤマイモの項では、「山芋、鰻に變ずる。」について全く語っていないし、「卷五十 河湖無鱗魚」の「鰻鱺」(うなぎ)=ウナギの項では、「又有薯蕷久所濕浸而變化鰻鱺者自非情成有情者是亦不必盡然也」(又、「薯蕷(やまのいも)、久しく濕浸されて、變じて、鰻鱺に化する者、有り。」〔と〕。非情より、有情と成ること、是れ亦、必しも盡〔(こと)〕ごとく然るには、あらざるなり。)と述べる。この口調は、本件の最後の口調と極めて類似している。いわば、イセエビの腹の中に子があることは(観察によって明白で、彼らは通常は卵生である)、従って、このイセエビがサザエに変化するということもまた、『山芋が鰻に変化する』という類いの俗説と同じ、如何にも稀な、いや、信じがたい化生(けしょう)の類いなのではなかろうか、と批判して言っているのである。ここで我々は、良安が、このような、当時、信じられた自然発生説的俗信に対して、冷静な自然観察者として、かなり懐疑的な視点を保持していたことを読み取るべきであると私は思うのである。]
***
あみ 糠鰕【本綱】
あめじやこ
海糠魚 【和名阿美
俗云阿女】
△按和名抄之海糠本草之糠鰕一物而鰕中細小者而
非鰕苗本自此一種終不長者也爲※爲醢味甚美
[やぶちゃん字注:※=「月」+「雋」。]
《改ページ》
■和漢三才圖會 江海無鱗魚 卷ノ五十一 ○二十五
夏糠鰕 自立夏至立秋出其大者不過四五分色白帶
微赤備前海上多以布綱〔→網〕取之作醢名糠鰕鹽辛
秋糠鰕 九十月盛出其大六七分色白頭與尾正紅豊
前中津多取之備前亦少有之
*
あみ 糠鰕【「本綱」〔=「本草綱目」〕。】
あめじやこ
海糠魚 【和名、「阿美」。俗に「阿女」と云ふ。】
△按ずるに、「和名抄」の「海糠」、「本草」〔=「本草綱目」〕の「糠鰕」、一物にして、鰕の中の細小なる者、而も鰕苗〔(かべう)〕に非ず。本(もと)より、此の一種、終〔(つひ)〕に長ぜざる者なり。※(いりもの)に爲し、醢(しほから)に爲して、味、甚だ、美なり。[やぶちゃん字注:※=「月」+「雋」。]
夏糠鰕(あみ[やぶちゃん注:三字へのルビ。]) 立夏より、立秋に至りて、出づ。其の大なる者、四、五分に過ぎず。色、白くして、微赤を帶ぶ。備前〔の〕海上に多し。布網を以つて、之れを取る。醢〔(しほから)〕に作り、「糠鰕鹽辛(あみしほから)」と名づく。
秋糠鰕 九、十月、盛んに出づ。其の大いさ、六、七分。色、白。頭と尾と、正紅。豊前中津〔:現在の大分県中津市(グーグル・マップ・データ)。〕に、多く、之れを取る。備前にも亦、少し、之れ、有り。
[やぶちゃん注:まずは、前掲の「蝦」の項の「糠鰕」を参照されたい。その上で、現在、狭義の「アミ」は、エビ亜綱フクロエビ上目アミ目 Mysidacea に属する小型甲殻類の中でも、アミ科 Mysidae に属する種を総称する呼称とされる。例えば、本邦産の「アミ」の正統的な種を挙げるとすれば、汽水域に生息するイサザアミ Neomysis intermedia であろう。本項の後に掲げられる「夏糠鰕」に就いて、取り敢えず、これに同定しておくが、ここに異種としての本物の「エビ」であるホンエビ上目オキアミ目 Euphausiacea も当然、含まれてくると考えねばならない。「秋糠鰕」は、後述するように、完全に本物のエビとしての異種であるからである。
・「鰕苗」の「苗」とは、この場合、「生まれたばかりの動物」を指す。総体としての「エビ幼体個体(群)」を言う。
・「秋糠鰕」は、根鰓亜目サクラエビ上科サクラエビ科アキアミ Acetes japonicus である。現在言うところの「アミ」ではなく、一般的な意味での正統な「エビ」である、ということだ。現在、「アミ」と「エビ」は異なるものと認識されている。その明確な相違点としては、エビ類と異なって、脚の先は鋏状にならない、♂が腹部に育児嚢を持つ、尾節の付け根に一対の球状器官(平衡胞)を持つこと等が挙げられる。……しかしね、やっぱり素直な観察眼からは、これを「エビ」でなく「アミ」だと平然と言いのける輩には、違和感を覚えるがね、私は。アミだってエビだよ、ね、良安先生❤]
***
しやこ 青龍鰕
しやくなげ 【俗云志也古
鰕姑 又云尺奈外】
ヒヤアヽ タウ
閩書載開元遺事云鰕姑狀如蜈蚣尾如僧帽泉人謂之
青龍
△按鰕姑狀類鰕而扁頭尾相等有鬚手足多背有細節
灰白色帶碧攝泉雜肴中亦混來而熬食其肉少而味
不佳相傳云治婦人血閉消瘢痕
於久里加牟木里 鰕姑頭中之小石【如鮸頭之石乎】能治五淋
《改ページ》
通小便蠻人秘藥也然未見有石者
*
しやこ 青龍鰕
しやくなげ 【俗に「志也古」と云ふ。又、「尺奈外」と云ふ。】
鰕姑
ヒヤアヽ タウ
「閩書」に「開元遺事」を載せて云ふ、『鰕姑は、狀〔(かたち)〕、蜈蚣〔(むかで)〕のごとく、尾、僧帽のごとし。泉人〔:福建省泉州の人。〕、之れ、「青龍」と謂ふ。』と。
△按ずるに、鰕姑は、狀、鰕の類にして、扁たく、頭・尾、相〔(あひ)〕等し。鬚、有り、手足、多く、背に、細節、有り。灰白色、碧を帶ぶ。攝〔=摂津〕・泉〔=和泉〕の雜肴(ざこう[やぶちゃん注:ママ。正しい歴史的仮名遣は「ざかう」。])の中、亦、混(まじ)り來る。熬り食ふ。其の肉、少なくして、味、佳からず。相〔あひ〕傳へて云ふ、「婦人の血閉を治す。瘢痕を消す。」と。
於久里加牟木里〔(おくりかんきり)〕 鰕姑〔の〕頭〔(かしら)の〕中の小石【鮸〔(にべ)〕の頭の石のごときか。】。能く五淋を治す、小便を通ず、蠻人の秘藥なり。然れども、未だ、石、有る者を見ず。
[やぶちゃん注:私はシャコが大好きだ。小さな時から食うのも、観察するのも(元来、「寿司屋で子供が好きなのはシャコである」ことを、僕は、真理として譲る気がない)。この「蜈蚣(ムカデ)に似ている」と言われ、私が六年住んだ富山では、鮓種(すしねた)にさえならずに、浜に、おぞましく、山のように死骸を打ち捨てられ、東京湾漂流死体の内臓を食い荒らしては、怒濤の如く、「そこ」から飛び出してくるというカニバルな彼等――しかし、僕は、無性に、好きだ。何故かって? それこそ……「僕に似ているから」……かも知れんな。ふふふ♪
軟甲綱口脚(トゲエビ)亜綱口脚(シャコ)目単楯亜目シャコ上科シャコ科シャコ属シャコ Oratosquilla oratoria
江戸期には「ャクナギ」とか、「シャクナゲ」と呼称されていた。これはシャコを茹でた際、紫褐色に変わって、それが「石楠花」、ビワモドキ亜綱ツツジ目ツツジ科ツツジ属 Rhododendron シャクナゲ亜属 Hymenanthes 無鱗片シャクナゲ節のシャクナゲ類(約百四十種を擁する)の花の色に似ていたところから付けられ、それが短縮されて「シャコ」と呼ばれるようになったとされる。花の色から言うと、一般的には、赤紫色か、白のホンシャクナゲ Rhododendron metternichii var. hondoense であろうか。「青龍蝦」は、現在でも、シャコの別名として生き残っている。(ここでやぶ、ギャル風の装束で、何故か「羅和辞典」を持って登場。)
それよか~さぁ! この学名、面白くない~? Oratosquilla oratoria
の属名と種小名にある“ Orato ”及び“ oratoria ”ってさぁ、「オラトリオ」じゃ~ん!(“ squilla ”ってえのはさぁ、“ scilla ”と同じで、「葱」や「蟹」の意味なわけ~。エビ・カニって言うんだから、気にしないの~) ラテン語で“ Orato ”つ~のはさ、「雄弁」とか「祈禱」の、“ oratorie ”なら、「演説風に」とか「雄弁に」だし~、“ oratorium ”となるとさ、「祈禱室」・「礼拝堂」なの。シャコが盛んに、忙しく、鋏脚やら、歩脚を動かす動作から雄弁な「演説」? ノン、ノン! 頻りに礼を繰返すみたいだから「祈禱・礼拝」とかイメージしたのかもよ~? わけわかんない、なんとかつー、中国の本にも「僧帽」(いやん! これマジ、良安ちゃんの絵、中国の歴史の映画に出てくる、あのお坊さんの変テコな帽子に、クリソツよ!)とかに擬えてるし~! あとさ~あ、“ Oratus ”っーのは、「乞い願うこと」って書いてあるわけ! これって、さあ、やっぱ、シャコちゃんがさあ、あのお辞儀するみたいな動きすんの、言ってんのかもよ~?! チョー面白いじゃ~ん!(退場。以下、ずっと普通のやぶちゃんに戻る。)
・「閩書」は、明の何喬遠(かきょうえん)撰になる閩(福州・泉州・厦門等の現在の福建省辺りを指す)の地誌。
・「開元遺事」は、正しくは「開元天寶遺事」で、五代の王仁裕(八八〇年~九五六年)の編。四巻。仁裕は初め、蜀に仕えて翰林学士となったが、蜀の滅亡後は長く長安に住み、民間に伝わる唐の玄宗の時の遺事記を辿って記した。史実と云うよりは、小説に近いものである。「開元天寶」は唐の第六代玄宗の治世(七一三年~七五六年)を、その主要年号の開元(二十九年間)と天宝(十五年間)に因んでこのように呼ぶ。唐の極盛期であるとともに、中国古代文化のピークを迎えた時代に当たる。
・「蜈蚣」は節足動物門大顎亜門唇脚(ムカデ)綱 Chilopoda のムカデ類を指す。私のブログ版の「和漢三才圖會卷第五十四 濕生類 蜈蚣(むかで)」を参照。
・「婦人の血閉」は月経不通を言う。
・「於久里加牟木里」は、ザリガニ Cambaroides japonicus (これは抱卵亜目 Pleocyemata ザリガニ下目 Astacidea の中の本邦北方固有種である極めて厳密な意味での「ザリガニ」である)の胃石(胃の中にできる結石)である。「長崎大学」公式サイト内の「長崎薬学史の研究」のページの中の、「薬品応手録」(解説によれば、シーボルト Philipp Franz von Siebold が、門人高良斎(こうりょうさい)に和訳させて印刷し、訪問した地での医師への手土産としたものと推測されている書。ヨーロッパで常用されている薬草と、その代用品に加えて、多少の新薬を収載しているとする)に掲載されている、とし、同ページ製作者が以下のような解説を附している(元のページは表形式。私が便宜上、『オクリカンクリ(刺蛄石)』と二重括弧で括ったものが、本書へのシーボルトの薬品記載)。
*
『オクリカンクリ(刺蛄石)』ザリガニの胃に生じた結石。炭酸カルシウム、リン酸カルシウム、キチン質からなる。胃酸中和剤。シーボルトがよく用いた薬とされている。[やぶちゃん注:下線、やぶちゃん。]
*
さて、同サイトには、別に、「蘭方口伝(シーボルト験方録)」(筆者未詳。危険を冒してシーボルトの門人であった邦人がシーボルトの処方を書き記したもの)があって(二〇〇八年一月現在、当該ページは消失)、そこにも、『14. 収酸剤(吸酸剤,胃散を中和する薬)』〔この( )内は、ページ製作者の注と思われる〕として、以下のような「おくりかんきり」の記載があり、
*
蛄石(オクリカンクリ,ザリガニの結石)
*
とあって、その直後に、やはり、ページ製作者による注と思われる以下の文章が出現する。以下の文章は、「ママ」である。
*
吸酸剤は胃の酸を中和する制酸剤である。ここで興味深いのは「ら蛄石(オクリカンキリとも呼ばれる)」で,これはザリガニの胃の中にできる結石である。小児のひきつけ,胃痛,下痢止めの効があるとされ,シーボルト来日以前から輸入されている。[やぶちゃん注:下線、やぶちゃん。]
*
長々と引用したのは、「おくりかんきり」の効能に興味があるから、では、ない。この下線を引いた表記の微妙な違いである。特に、最後の解説中の「ら蛄石」の平仮名の「ら」は不審である。そもそも、前者の「薬品応手録」の『刺蛄石』という表記から、後者の解説部の『ら蛄石』を考えると、これは、後者の本文記載『蛄石』が本来、『●蛄石』という三文字の熟語あったものを、頭の一字をページ編者が脱落させてしまったのではなかろうか。さらにその直後に解説では、脱字させなかったものの、今度は当該の『●』の字を当時のワープロで変換出来ないまま(もしくは変換ミスのまま)『ら』としてしまったと思われる。さて、ワープロの「ら」から変換出来る漢字で(これは思いの外、少ない。常用字では「羅・螺・等・裸・良」ぐらいなものだ)、「薬品応手録」の「刺」から容易に類推出来るのは、「喇叭」(らっぱ)の「喇」(ら)である。「喇蛄」を検索すると、ウィキの「ザリガニ」に、江戸期の表記として引っ掛かり、そうしてここには冒頭、「蝲蛄」という漢字表記が示されている。そこで「蝲蛄石」で検索をかけてみると、来た来た! 中国語の簡体字の漢方サイトなので、一部の漢字を日本の字体に補正して、以下に引用する。
《引用開始》
蝲蛄石
【拼音名】 Là Gū Shí
【別名】東北蝲蛄[東北螯虾]、蝲蛄[やぶちゃん注:「虾」は「蝦」「鰕」の異体字。]
【来源】甲殻綱蝲蛄科東北蝲蛄 Cambaroides dauricus(Pallas);朝鮮蝲蛄 C. similis (Koelbel);蝲蛄 C. schrenskii (Kessler),以体内的碳酸鈣石入薬。
【生境分布】東北。
【功能主治】止血,止瀉,利小便,壮筋骨。主治刀傷出血,小儿軟骨,瀉痢,心腹刺痛等。
【用法用量】 1~2銭,外用適量。
【備注】蝲蛄是肺蛭的中間宿主。
【摘録】《全国中草薬彙編》
《引用終了》
素晴らしい! 最初に登場する「東北蝲蛄」とは、ニホンザリガニ属マンシュウザリガニ Cambaroides dauricus であり、「朝鮮蝲蛄」は、ズバり、チョウセンザリガニ Cambaroides similis で、ここで単に「蝲蛄」とするのは、シュレンクザリガニ Cambaroides schrenckii である。実に、二力士、ザリガニ類の本家以外の揃い踏みだ! 「碳酸鈣」は、炭酸カルシウムCaCO3の中国語表記、何より凄いのは、ちゃんと、私の大好きな寄生虫「肺蛭」(カンテツ)ちゃん♡=肺吸虫=肺臓ジストマ=ベルツ肺吸虫 Paragonimus pulmonalis 、及び、ウエステルマン肺吸虫 Paragonimus westermainii の危険を注記していることである!(私は実は寄生虫フリークでもあるのである)
閑話休題! 私の高校国語教師の授業のように、脱線し過ぎて、本題を忘れていた。シャコに戻る。それぞれの漢字を見て欲しい。シャコを、良安は「鰕姑」と書くが、通常は「蝦蛄」と表記する(実際、良安は「鰕」の項で「蝦」の字を混在させている)。オクリカンキリを示す漢語は、ザリガニの体内の石ということで、「蝲蛄」石である。
蝦蛄
と
蝲蛄
この二つの熟語、余りにも似てはいないか? おまけに「蝦蛄」は「シャコ」で、「蝲蛄」の音は「ラッコ」である。勿論、脱皮するシャコに、オクリカンキリがあっても不思議ではないが(多分あるのであろうが、微細なのかも知れない)、さても私が言いたいのは、この部分の記述は、良安が「蝦」という字と「蝲」という字を同字として見間違え(この二つは恐らく崩し字で書くと見間違い易いのではあるまいか)、蘭語のオクリカンキリが、シャコと漢訳語で、「同じ字」を書くのなら、シャコこそが、謎の薬物オクリカンキリの産出生物の正体なのだと思った結果の誤記述ではないかと思われるのである。……だらだらと牛の涎のように考察してきた。いや、既に分明のことやも知れぬ。識者の御指摘を俟つものである。
しかし、最後に、やっぱり、オクリカンキリの総括は欲しい。「東京人形倶楽部あかさたな漫筆14P」に、写真入りで以下のような素晴らしい記載がある。
《引用開始》
[やぶちゃん注:前略。]大槻玄沢『蘭説弁惑』(1799)は蘭学を学ぶ門人の質問への答えを記録したものであるが、巻之上で「おくりかんきり」に触れている。「是は此邦にても津軽松前の地に産する「さりかに」といふものゝ腹中に出来る癖石なり。「おくり」とは目のこと也。「かんきり」は「かんける」といふ間違にて蝦の事也。目といひしは形の似タルより名付づけたる也。」と答えている。オクリカンケリはラテン語 oculi cancri で、意味は玄沢の言う通りである。ザリガニが脱皮準備のために胃に蓄える炭酸カルシウムで、米粒大のもの。磨り潰して粉状にして万能薬として用いる。西洋では狂犬病、ペスト、利尿、水腫に効果があるとされた。また丸のままで、虫歯の詰め物としても充填された。さらに、目に入れ、眼病にも使われた。逆に眼を傷つけたことだろう。あるいは、痛くて涙が出て症状が緩和されるのを期待していたのだろうか。「しゃり」(舎利)を持つ蟹だから「ザリガニ」だとする民間語源もあるくらいだが、子供時代のザリガニ経験ではオクリカンキリは見たことがなかった。松浦武四郎「おきのいし」(1855)にはヲクリカンキリは虻田に豊富に産すると記されている。柴田哲孝「オクリカンキリの効用」(『週刊日本の天然記念物 動物編』10ニホンザリガニ、小学館、2002.8.29、p.25)参照。
《引用終了》
こんなに完璧で気持ちのいい素敵な解説には、私の弛緩した注では、そうそう書くことは出来そうもない。引用の筆者の観察の中で、見たことがない、という語が、良安の疑義に不思議にシンクロしてくるではないか。実は、私も、ここ大船、アメリカザリガニ発祥の地で、筆者に負けないであろう「ご幼少の砌りのアメリカザリガニ体験」をしてきたのだが、残念ながら見たことがないが、ザリガニの飼育家のページ等には、当たり前のことのように、水槽に落ちているとか、書いてあるようだ。やはり愛する観察者の勝利か?
……ところが、ここまで、コンダケ、苦労して、ふと、「広辞苑」で「オクリカンキリ」を引いたら、ちゃんと「蝲蛄」の字を掲げて、ザリガニのことも、何もかも、書いてありやがんの! あぅ、昨夜からの努力は全く報われぬのか!(そもそもネットの検索に頼って、面白い結果に有頂天になり、堅実に辞書を引かなかった私が、単純に馬鹿であっただけなのだが)癪だけど引く! ちなみに私の所持する書籍版「広辞苑」の第二版補訂版(一九七六年刊)と、同じく所持する電子版の第五版(一九九八年版)の記載は異なる。面白いから、並べてみる。序でに、参照見出しの「胃石」もね。これが二十二年の輝かしい生物学の進歩の結果なわけだ(と最後まで癪だから皮肉る)。
*
○「広辞苑」第二版補訂版
オクリ‐カンキリ【 oculi cancri ラテン】(「カニの眼」の意)アメリカザリガニの体内から採る結石様のもので、蘭方で一種の利尿剤とされた。蝲蛄(らっこ)石。→胃石(いせき)
い‐せき【胃石】ヰ‥
ザリガニ・カニ類の胃の中にある、円板形の分泌物の塊。白色、直径約5ミリメートル。炭酸カルシウムから成り、二個あって、食物をくだくのに役立つ。昔はオクリ‐カンキリ(oculi cancri ラテン カニの眼の意)といって、利尿剤とした。ざりがにいし。
●「広辞苑」第五版
オクリ‐カンキリ【 oculi cancri ラテン】(「カニの眼」の意)ザリガニ類の胃石(いせき)。炭酸石灰・燐酸石灰より成り、蘭方で利尿剤とされた。蝲蛄(ざりがに)石。→胃石
い‐せき【胃石】ヰ‥
①ザリガニ・カニ類の胃の中にある、円板形の結石。炭酸カルシウムから成り、2個ある。食物をくだくのに役立つとされるが、脱皮の際カルシウムが過剰に捨てられるのを防止する。ざりがにいし。
②経口摂取したものに胃液が作用し、胃内で固形物となったもの。毛髪石・柿胃石の類。
*
・「鮸の頭の石」の「ニベ」は、スズキ亜目ニベ科ニベ Nibea mitsukurii 。ニベは別名「イシモチ」とも呼ばれるが、これは、頭部に大きな耳石を持つからである(以下は「WEB魚類図鑑」の「耳石Otolith」のページを主に参考にして記載した)。硬骨魚類には内耳があって人間と同様な一対の三半規管を持っている。前後・左右・水平に直交するリング状の管の中に、それぞれ「扁平石」( sagitta )・「礫石」( lapillus )・「星状石」( asteriscus )と呼称する石がある。この内、扁平石が最も大きく、通常、「耳石」というと「扁平石」を指す。これらの石は、毛状の組織の上に乗っており、石の微細な移動が伝達され、個体の平衡や外界の水流変化による他個体の行動・外敵の襲来を統御・認知する。耳石の主成分は、オクリカンキリと同じく炭酸カルシウムで、年周輪を形成することが多く、この輪紋をその魚の年齢を調べるのに使うことはよく知られている。
・「五淋」は尿路障害で、石淋(尿路結石。排尿障害や強い痛みを伴うことが多いもの)・気淋(ストレスによる神経性の頻尿)・膏淋(尿の濁り)・労淋(過労・性交過多に伴う排尿異常)・熱淋(痛みが激しく時に出血を伴う急性尿路感染症)を言う。]
***
かいば 水馬
海馬 【俗用字音】
ハアイ マアヽ
本綱海馬其身如鰕首如馬背傴僂有竹節紋長二三寸
其喙垂下漁人捕得不以啖食暴乾以雌雄爲對婦人難
產手持之卽如羊之易産也【帶之於身亦可】雌者黃色雄者青色
△按海馬偶混于雜肴中有之安産之功人皆所識也
*
かいば 水馬
海馬 【俗に字音を用ふ。】
ハアイ マアヽ
「本綱」に、『海馬は、其の身、鰕のごとく、首、馬のごとく、背、傴僂〔(うろう)〕、竹節の紋、有り。長さ二、三寸、其の喙〔(くちばし)〕、垂下す。漁人、捕-得(〔とり〕え)ても、以つて、啖-食〔(くら)〕はず、暴〔=曝〕〔(さら)し〕乾し、雌雄を以つて、對(つい)と爲す。婦人、難產の手に、之れを持てば、卽ち、羊の産、易〔(やす)〕きがごとし【之れを、身に帶びても亦、可〔なり〕。】。雌は黃色、雄は青色。』と。
△按ずるに、海馬は、偶々、雜肴〔(ざこう)〕の中に混りて、之れ、有り。安産の功、人、皆、識る所なり。
[やぶちゃん注:条鰭綱トゲウオ目ヨウジウオ亜目ヨウジウオ科タツノオトシゴ亜科 タツノオトシゴ属 Hippocampus。本邦産は、
タツノオトシゴ Hippocampus coronatus
ハナタツ Hippocampus sindonis
イバラタツ Hippocampus histrix
サンゴタツ Hippocampus japonicus
タカクラタツ Hippocampus takakurai
オオウミウマ Hippocampus keloggi
クロウミウマ Hippocampus kuda
Hippocampus severnis(和名なし)
の八種とされてきたが、最近、
ピグミーシーホース Hippocampus bargabanti
が、小笠原や沖縄で確認され、また、通称、「ジャパニーズピグミーシーホース」なる未確認種も二〇一八年には、
ハチジョウタツ Hippocampus japapigu
と和名が決定されているので、全十種となり、恐らく、さらに増える可能性があろう。
・「傴僂」は「背をかがめる」こと。差別用語としての「せむし」の意もあるが、ここは本来の意味でよいであろう。
・「其の喙、垂下す」とあるが、タツノオトシゴ類は、頭部が、体幹に対して直角に曲っており、全身を直立させて、頭部を前に突き出して遊泳している。肉食で、動物性プランクトンを摂餌するが、その際、パイプ状の吻を、下から上に素早く振り上げ、ターゲットを瞬時に吸引する。
・「羊の産、易きがごとし」について、幾つかの牧畜家の記述を読むと、一般にヒツジ(ウシ科ヤギ亜科ヒツジ属ヒツジ Ovis aries )の出産には、難産は少ないようではある。
・「雌は黃色、雄は青色」は誤り。体色は種のみでなく、個体間でも変異が多い。雌雄の区別は腹部を見、直立した腹部の下方に尻鰭が現認でき、腹部全体が有意に膨らんでいるのが♀ある。
・「安産の功」について。タツノオトシゴ類は♂が「出産する」ことは、現在、小学生にもよく知られている。♂には、腹部に育児嚢があり、♀は交尾時に輸卵管を♂の育児嚢に挿入、その中に産卵する。♂がそれを保育し、約二週間ほどすると、親と同じ形をした数十から数百匹の子供を、♂が、かなり苦しそうな動きをしながら「出産する」のである。幾つかの説が、このタツノオトシゴの生態から「安産のお守り」となったという説を載せる。しかし、私は「和漢三才圖會 巻第四十七 介貝部」の「貝子」(タカラガイ)の項の注で述べたように、タツノオトシゴが胎児(もしくは妊婦の姿そのもの)と似ているからではないかと考えている(但し、「それは近代生物学以降のことだろう」と言われると沈黙せざるを得ないことも承知している)。フレーザーの言うところの類感呪術の一つである。その生態としての♂の育児嚢からの出産から生まれた風習という説は、考えとしては誠に面白いが、古人がそこまでの観察と認識から用いたとは、残念ながら私には思えないのである。但し、それを全否定できない要素としては、ここで雌雄をセットで御守としている点である。但し、これに対しても受卵前の雌雄、若しくは個体(雌雄の判別のところで述べたが、受卵前の♂は腹部のラインがすっきりとスマート、逆に♀は有意に膨らんでいる。加えて、受卵し、保育する♂も有意に膨らむ)が丁度、出産の前と後とのミミクリーであるとの見解を私は持っている。いや、その最初の発案者たる呪術師はもしかすると、水槽にタツノオトシゴを飼育し、その雌雄の生態(但し極めて高い確率で♂と♀を取り違えていたと思われるが)を仔細に観察していたのかも知れぬ。しかし、何故に、彼、若しくは、彼女(巫女かも知れぬ)はタツノオトシゴを飼育していたのであろうか?……タツノオトシゴを見る巫女……何だか僕はヒッポカムポス( Hippocampos :ギリシア神話に登場する半馬半魚の海馬)なロマンを感じ始めたようだ。]
***
[やぶちゃん図注:図の右上に「背」とし、左やや下に「腹」とし、それぞれの方向からの魚体を描いてあるが、よく見て頂きたい。良安は「背」と「腹」を誤まっている。腹ビレも描き落としており、良安が果たして実物を見て描いたのかどうか疑わしい。しかし、本文「頭の裏」という確信に満ちた記載や、「其の異形を惡」むという語調は、忌まわしい魚体に対する彼の生理的嫌悪感の現われであり、それ故の誤認と、とれなくもない。]
ふなとめ 正字未詳
舩留魚 【俗云不奈止女】
《改ページ》
■和漢三才圖會 江海無鱗魚 卷ノ五十一 ○二十六
△按舩留魚鱣之屬狀似鯒而尾末纎無岐偃頭眼小灰
白色無鱗頭裏扁有小刻如金小判之象而下喙尖畧
長有小鬛自頭連尾小者長尺半大者三四尺毎以頭
小刻附海舶板用鐵梃亦不離也掩籃待自離去取之
希有出魚市人惡其異形無食之者
*
ふなとめ 正字、未だ、詳らかならず。
舩留魚 【俗に「不奈止女」と云ふ。】
△按ずるに、舩留魚は鱣(ふか)の屬、狀〔(かた)〕ち、鯒(こち)に似て、尾の末、纎〔(ほそ)〕く、岐〔(また)〕、無し。偃頭〔(えんとう)〕。眼〔(まなこ)〕、小さく、灰白色。鱗、無く、頭〔(かしら)〕の裏、扁たく、小〔さき〕刻〔(きざ)〕、有り、金〔(かね)の〕小判の象〔(かたち)〕のごとくにして、下〔の〕喙〔(くちばし)〕、尖りて、畧〔(やや)〕、長し。小鬛〔(こひれ)〕有りて、頭より、尾に連なり、小さき者、長さ尺半、大なる者、三、四尺。毎〔(つね)〕に、頭の小〔さき〕刻を以つて、海舶の板に附きて、鐵梃〔(かなてこ)〕を用ひても亦、離れざるなり。籃〔(かご)〕を掩〔(おほ)ひ〕て、自〔(おのづ)〕から離-去〔(はな)るる〕を待ちて、之れを、取る。希〔(まれ)〕に魚市に出づること有り、人、其の異形を惡〔(にく)〕んで、之れを食ふ者、無し。
[やぶちゃん注:スズキ目コバンザメ亜目コバンザメ科 Echeneidae で四属八種で、コバンザメ属 Echeneis 、スジコバン属 Phtheirichthys 、ナガコバン属Remora 、シロコバン属 Remorina である。彼らは、歴とした硬骨魚の正統主流派であるスズキ目であって、軟骨魚類の「鱣の屬」=フカ=サメ類ではない。ただ、この時代から「サメ」呼ばわり(サメ=フカの仲間と認識)していたことが、この良安の叙述から窺われ、本種のコバンイタダキへの改名に反対していた魚類学者田中茂穂の『東京附近でコバンザメと云ふのは形が多少鮫に似てゐる爲である。此魚は鮫類とは著く違つてゐる爲に、わざわざコバンイタヾキと云ふ名稱を付けたのは教科書を作った學者達である。然し私はコバンザメと言つた方が如何にもいゝやうに感ずる。相當智識のある人ならば此魚を鮫と思ふ人はいない故、そんな取越苦勞は不要である。是に類似したことが他の動物にもあるが、徒に不器用な改名は私は採らないのである。』[注:「コバンザメ-WEB魚図鑑」からの孫引きであるが(現在、その解説は消えている)、表記の一部に問題があるため、恣意的に補正してある。下線部、やぶちゃん。])の謂いには、やや疑問が生じる。実際、田中は東京附近での通称名の標準和名化であることを示唆しているが、この時代の良安でさえ、「鱣の屬」と言っている。私は「サメ」でもないのに「サメ」は、ないと思う。標準和名は、その名を聞いてある程度の実体とのかけ離れることのない連想が可能である名前がよいと思っている(最低限、誤まった情報を類推させてはいけないということである。但し、既に人々に定着してしまっているものを、強いて変えることに拘るものでもないが、良安に従うなら、「コバンブカ」でもいことになろう)。頭頂部に小判型の吸着器を「頂き」、寄生種の運動エネルギーや餌のお零れをちゃっかり「頂戴する」魚のイメージとして、私は「コバンイタダキ」の和名をこそ鮮やかに支持するものである。この吸着器官は第一背鰭の変形したものと考えられている。また、寄生行動をとるのは、比較的若い個体で、成長すると、自由遊泳するものが多いという。また、寄生生活をしている個体の胃からは、寄生種に寄生している甲殻類が見つかっており、ちゃっかり者のコバンイタダキではなく、相利共生の側面も否定出来ないとも思われる(但し、寄生種である本家のサメ等に食われることもあると聞く)。
・「鯒」は、カサゴ目コチ亜目 Platycephaloidei の魚類の総称である(この場合は、私はスズキ目ネズッポ亜目 Callionymoidei の民間の総称通称である「コチ」呼称群を考慮する必要はないと思う)。特に、ここでは、本邦の典型的な大型種コチ亜目 Platycephaloidei のマゴチや、近縁種のヨシノゴチ(どちらもPlatycephalus sp. 。嘗つては、と同一種とされていたが、研究の進展により、現在は別種とされる。学名未認定。)を良安は想定していると考えてよいであろう。
・「偃頭」は本ページの「鰐」の注で考察したように、「扁平で地べた・水底に伏せた(うつ伏せになった)頭部」を示すもの。東洋文庫版は、ここでは『鰐』とは、うって変わって、妙な訳をせず、『(頭が伏せたような形になっていること)』と極めて素直である。
・「之を食ふ者、無し」とあるが、伝え聞くところでは、漁師料理にして、旨いとする。私は、残念なことに食したことはない。しかし、御用達の「ぼうずコンニャクの市場魚類図鑑」の「コバンザメ」( Echeneis naucrates )には、「コバンザメノ刺身」の条によれば、『外見からは想像できない美しい血合いと身に混在する脂。近縁とされるスギよりも身質は上だと考えている。舌に触れると微かに脂の溶ける感じがして、最初から甘い。そこに適度に締まった身の心地よい食感。魚らしいうま味は後から来るのだけど、うまいなーと独りごちてしまいそうだ』とあり、他に、『コバンザメのセビチェ』と『コバンザメの煮つけ』が載り、孰れも旨いと解説されておられる。食ってみたい!]
***
たちいを
鱭
鮆 鮤
鱴 魛
鰽 望魚
【俗云太刀魚】
[やぶちゃん字注:以上四行は、前二行の下に入る。]
本綱鱭生江湖中常以三月始出狀狹而長薄如削木片
細鱗白色吻上有二硬鬚腮下有長鬛如麥𦬆〔=芒〕腹下有硬
角刺快利若刀腹後近尾有短鬛肉中多細刺煎炙或作
鮓食皆美烹煮不如蓋此魚飮而不食鱣鮪食而不飮
△按鱭生江海中然言生於江湖者非也八九月與鰯同
《改ページ》
時盛出泉州播州特多其大者三四尺小者一二尺似
海鰻而薄扁青色上帶白如塗雲母是乃脂也甞無鱗
然言有細鱗者非也其眼圓大而吻腮及臍下硬鬛皆
如本草之說刮去白脂而可熬可炙其肉白脆味美也
小骨橫于脊如箆櫛
*
たちいを
鱭
鮆 鮤
鱴 魛
鰽 望魚
【俗に「太刀魚(たちいを)」と云ふ。】
「本綱」に『鱭〔(し/せい)〕は、江湖の中に生じ、常に三月を以つて、始めて出づ。狀〔(かたち)〕、狹〔(せば)〕くして、長く、薄きこと、削りたる木の片(へぎ)のごとし。細〔か〕なる鱗、白色にして、吻の上、二〔(ふたつ)〕の、硬き鬚、有り。腮〔(あぎと)〕の下に、長き鬛〔(ひれ)〕有り、麥の芒〔(のぎ)〕のごとし。腹の下に、硬き角-刺(〔かど〕ばり)有り、快利なること、刀〔(かたた)〕のごとし。腹の後、尾に近く、短き鬛、有り。肉の中〔(うち)〕、細〔き〕刺〔(はり)〕、多し。煎〔り〕、炙〔り〕、或いは、鮓〔(すし)〕に作りて、食ふ。皆、美なり。烹-煮(に)なば、如〔(し)〕かず。蓋し、此の魚は、飮みて、食はず。鱣・鮪は、食ひて、飮まず。』と。
△按ずるに、鱭〔(たちいを)〕は、江海の中に生ず。然るに、「江湖に生ず」と言ふは、非なり。八、九月、鰯と同時に盛んに出づ。泉州〔=和泉〕・播州〔=播磨〕、特に多し。其の大なる者、三、四尺、小なる者、一、二尺。海鰻(はむ)に、似て、薄く、扁たく、青色なる上に、白を帶びて、雲母(きらゝ)を塗るがごとし。是れ、乃〔(すなは)〕ち、脂なり。甞〔(かつ)〕て、鱗、無し、然るに、「細き鱗、有り」と言ふは、非なり。其の眼〔(まなこ)〕、圓〔(まろ)〕く、大にして、吻・腮、及び、臍の下〔の〕、硬き鬛、皆、「本草」の說のごとし。白脂を刮(こそ)げて、去りて、熬るべし、炙るべし。其の肉、白、脆〔(もろ)〕く、味、美なり。小骨、脊〔(せぼね)〕に橫〔(よこた)〕へて〔→橫たはりて〕、箆櫛(たうぐし[やぶちゃん注:ママ。「箆」の音は「ヘイ」である。寧ろ、「へらぐし」と読みたい。或いは「唐櫛」を当て訓したものとも思われるが。])のごとし。
[やぶちゃん注:良安が強烈な齟齬を感じている通り、本項には、全く異なった二種が示されている。即ち、「本草綱目」の言う淡水魚と、良安がこれに同定しようとした、
スズキ目サバ亜目タチウオ科タチウオTrichiurus lepturus
である。
それ以外にも、冒頭に掲げている他の漢字では、最初の「鮆」は、
ニシン目ニシン亜目カタクチイワシ科エツ亜科エツ属エツ Coilia nasus
を指し、「鮤」が、同様に、
エツ
若しくは、
タチウオ
又は、
ダツ目ダツ亜目ダツ上科ダツ科 Belonidae のダツ類
を指し、而して「鱴」及び「魛」が、
エツ
又は、
タチウオ
を、「鰽」が、
タチウオ
若しくは、
ニシン科ニシン亜科ニシン属ニシン Clupea pallasii
及び、
ニシン科ヒラ属ヒラ Llisha elongate
を指す等、完全に錯綜しているのだ。
さて。「本草綱目」の言う淡水魚……は、何かって? もったいぶったね。では、言おう。これは魚類が苦手な僕の暴虎馮河、乏しい知識からの無謀にして無茶な同定であることは、ご了承願おう。「本草綱目」の言う淡水魚は、
条鰭綱スズキ目トゲウナギ亜目トゲウナギ科 Mastacembelidae
のトゲウナギ類に同定したいのである。但し、彼等に対しては、現在、スズキ目 Persiformes ではなく、日本にもいるタウナギ Monopterus albus (五百七十万年以上前に大陸の個体群から分岐したと推定されている)に代表されるタウナギ目 Synbranchiformes とする新知見による新しい分類が行われ、現在は、
条鰭綱タウナギ目トゲウナギ亜目トゲウナギ科 Mastacembelidae
となっている。彼等は Spiny eel (トゲだらけのウナギ)の英名を持ち、最近は「スパイニーイール」或いは「スピニイール」と呼ばれる売れっ子の熱帯性淡水魚類である。「ウナギ」とあるが、体型が似るだけで全く関係がない。以下にウィキの「トゲウナギ科」の記述を一部引く。「本草綱目」の記載と、お比べ頂きたい。『体は細長く、各ひれはウナギのように融合せず分離している。また、背びれの前方に名前の由来となった短いトゲが一列に並んでいる。 頭部は尖った三角形のような形状で、口の先端には鼻孔がヒゲのように発達した器官があり、これを動かして餌を探す行動が見られる。15cm程度の小型の種類から1mに達する大型種までおり、色彩や模様も多様』で、分布はアジアとアフリカに渡って』棲息している。『いずれも観賞魚として流通しており、砂に潜る性質や人間によく馴れることからアクアリストに人気がある』とある。
本件での良安の誤算は、彼自身が、『其の眼、圓く、大にして、吻・腮、及び、臍の下〔の〕、硬き鬛、皆、「本草」の說のごとし』という叙述の部分的な一致を以って、異種の生物として切り捨てることが出来なかった点にある。「本草綱目」への信頼過剰が齎した悲劇である。本項は総ての魚類の掉尾なだけに、ちょっぴり残念な気がする。
昔、小学館の「魚貝の図鑑」の終りの囲み記事で、何故か特別に、このトゲウナギの獰猛そうな図が田圃のような中に描かれ、「痛い」という言葉が最後にある解説文が忘れられなかった。僕はいつもこの絵を見ながら、『田圃にこんなトゲだらけの、狂暴なウナギがいるのだったら、田圃に入るのはゼッタイいやだ。』と思ったものだった。僕は、今回、この項の「本草綱目」の叙述を通勤の湘南電車の中で読みながら、思わず、あの絵が浮かんできて、「トゲウナギだ!」と呟いてしまった。向かいに立っていたOLが、如何にもトゲトゲしい怪訝な顔をしたのが、面白くも、怖かった……。
・「鱣・鮪」も、私のこだわりの部分。どちらも、フカでもなければ、マグロでもありません! チョウザメ目チョウザメ科 Acipenseridae のチョウザメ類! 詳しくは、本ページの「鮪」の「王鮪」の注を参照されたい。これは、私の自信の注、目から鱗、間違いなしです!
・「鰯」はニシン目ニシン科マイワシ Sardinops melanostictus 、及び、それに似た形態の魚類を総称する。
・「海鰻」は 条鰭綱ウナギ目アナゴ亜目ハモ科ハモ属ハモ Muraenesox cinereus (近縁種は同属スズハモMuraenesox bagio・アシナガハモ(ハシナガアナゴ)属ハシナガハモ Oxyconger leptognathus ・ワタクズハモ属ワタクズハモ Gavialiceps taiwanensis )。因みに、ハモ料理は、京都のフル・コースも食べたが、何より旨かったのは、とある高級天ぷら店の「天ぷら」であった。
・「箆櫛」は「梳き櫛」。「唐櫛」と言った場合、近世の竹製で、歯の非常に細かく密なものを言う。]
***
附
魚之用
[やぶちゃん注:標題の「附」はつけたり」と訓ずる。以下、魚体各部の最後の「䱊」まで、最初の「鱗」のみ最後の二行が頁頭まで上がって「鱗」の図の左部分にだけ縦罫が現われるほかは、総て上部に図があり、横罫、その中央部に右から、読み→項目名【字音】(「魚丁」にはなし。)→中国音が入り、その下部に解説があり、各項目の間は縦罫で仕切られている。以下、煩いので、以上の字配置の注については省略し、中央部と下部の間は行空けとした。]
いろくつ
うろこ
鱗【音鄰】
リン
○鱗【和名以呂久都俗云宇呂古】魚甲也
文字集略云龍魚之屬衣曰
鱗時珍曰鱗㔂也魚産於水
故鱗似粼鳥產於林故羽似
葉獸產於山故毛似草魚行
上水鳥飛上風凡鱗物以龍爲長蓋龍有八十一鱗具九
九陽數鯉有三十六鱗備六六陰數
*
いろくづ
うろこ
鱗【音は鄰。】
リン
○鱗【和名、「以呂久都」。俗に「宇呂古」と云ふ。】は、「魚の甲」なり。「文字集略」に云はく、『龍魚の屬、衣〔(ころも)〕を「鱗」と曰ふ。』と。時珍が曰はく、『鱗は㔂なり。魚は水に産する。故に鱗、粼(すはま)に似る。鳥は林に產する。故に羽、葉に似る。獸は、山に產する。故に毛、草に似る。魚は、行きて、水に上〔(の)〕り、鳥は、飛びて、風に上〔(の)〕る。凡そ、鱗ある物、龍を以つて、長〔(をさ)〕と爲す。蓋し、龍に、八十一の鱗、有りて、九九の陽數を具(そな)ふ。鯉に、三十六の鱗、有りて、六六の陰數を備ふ。』と。
[やぶちゃん注:「鱗」の字は、篆書体では「米」が「炎」となる。則ち、この(つくり)の「粦」は、本来、「鬼火」の意味である(!)。魚の体で、「鬼火の如くほの白く光るもの」の意である。「いろくづ」や「うろこ」の「いろ・うろ」は、「魚」の「うを」・「いを」→「うろ」・「いろ」へと転じたとも、「いろ」は、「平坦な部分から何かが少し飛び出た状態」や、「ある物体に触れた際のざらざらした感触」を意味するとも言う。
・「文字集略」は、梁の阮孝の撰した字書。
・「時珍」は良安が「和漢三才圖會」の一番の記述の拠り所とする本邦の本草書のバイブルであった「本草綱目」の著者李時珍。明代の医師にして本草学者。この記述は「本草綱目」の「鱗部 魚鱗」に記す内容。
・「㔂」は「粼」に同じで、本来は、「水が清く透き通って水底の連なる石が美しく見えるさま」を言う。「すはま」という良安による訓は「州浜・洲浜」であり、「曲線を描いて洲が出入りして形成された水際」を言う。時珍の原義と良安の理解は微妙に違うように思われる。なお、以下の記述は、一種の共感呪術的解釈である。
・「九九の陽數」「九」は陰陽説にあって、十進法での最大にして神聖なる天の陽気をシンボライズする陽数(奇数)である。それが重なる重陽、九月九日の「重陽の節句」に見るように、最も縁起のよい神聖な最大のパワーのシンボルとしての数列なのである。
・「六六の陰數」私は以前から、陰陽説にあって何故、「八」ではなくて「六」が陰数を代表するのか分からなかった。今回も、色々、調べては見たものの、納得がいかない。いかないが、注は書かざるを得ない。しかし、ここで考え直さねばならないと思ったのは、数の連続のみならず、その連環性と、形而上学的属性の理解の修正であるように思われる。難しいことを言ってるんじゃあ、ない。私がずっとどこかで感じてきた、陰数が悪く、陽数が正しい、という単純な阿呆な理解を捨てねばならないということである。易学においても(ということは「易経」にそう書いてあるからで、根拠は最早、不明なのかなあ?)、九が、六つ集まった卦(け)を「乾」(けん)とし、天を示す。一方、六が、六つ集まった卦が「坤」(こん)で、地を示す。天と地、世界の総体を「乾坤」と呼ぶから、「六」と「九」は、神聖なる連動上の密接な関係を持つらしい。さすれば、ここで暗示される「登龍門」(この話、実際にはコイではなく、チョウザメ科のチョウザメ類である。本ページの「鱣」の注を見よ)の劇的な変化に象徴されるように、陰数六(若しくは、その6×6=36という最大の陰数)の持つパワーには、その本体の世界を陽気に転ずる力が実は逆接的に内在するということなのではないだろうか? 俟于生半解凡俗者於中國哲學碩學御叱咤!]
***
《改ページ》
■和漢三才圖會 江海無鱗魚 卷ノ五十一 ○二十七
あぎと
えら
腮【音䰄】
シヤイ
○腮【和名阿木止俗云惠良】唐韻云魚
頰也字彙云魚頰中骨也
[やぶちゃん字注:実際には「阿木止」の「止」の字は「木」との間に半角分の空欄があり、ポイントがやや落ちて右下に書かれている。意図不明なので従わなかった。]
*
あぎと
えら
鰓【音、䰄〔(サイ)〕。】
[やぶちゃん字注:「䰄」には「シ」の音もあるが、それは魚の腮(えら)」を指さず、「恐れる」の意である。]
シヤイ
○鰓【和名、「阿木止」。俗に「惠良」と云ふ。】は、「唐韻」に云はく、『魚の頰(ほゝ)なり。』と。「字彙」に云はく、『魚の頰の中の骨なり。』と。
[やぶちゃん注:「鰓」の音を表わす「思」(本来の音が「シ」で、「サイ」はその変化した音とする)は、「顋」となると、「顎」(あご)の意味になる。魚の「えら」は「あご」である。「えらが張った顔」と言うもんなあ。
・「唐韻」は、唐の孫愐(そんめん)によって編纂された、「切韻」(隋の陸法言によって作られた作詩のための韻書)の補正本。
・「字彙」は、明の梅膺祚(ばいようそ)によって編纂された漢字字典。本文の十二支の巻に加えて、首巻と巻末があり、合わせて十四巻。親字数三万三千百七十九字。字典として初めて、現在のように、漢字が画数順に二百十四の部首順に分けられ、各部首内で総画数順に配列されてあるものである。
・「魚の頰の中の骨なり」発生過程に於いて、咽頭部側壁に膨らみが生じ、それに対応して、外胚葉に窪みが現われ、それらが、互いに癒合して鰓列が開口し、同時に、鰓弓も形成される。その鰓弓外側の後部には、多数の鰓弁が二列に並び、呼吸器としての機能を持つに至る。分かりきったことではあるが、エラは骨ではなく、内臓であり、肺である。]
***
かしらほね
魚丁
イユイ テイン
○魚丁【和名抄以乎乃加之良乃保祢】爾雅
云魚枕謂之丁在魚頭骨中
形似篆書丁字者也
*
かしらぼね
魚丁
イユイ テイン
○魚丁【「和名抄」、「以乎乃加之良乃保祢」〔(いをのかしらのほね)〕。】は、「爾雅」に云はく、『魚の枕、之れを「丁」と謂ふ。魚頭の骨の中に在り。形ち、篆書の「丁」の字に似たる者なり。』と。
[やぶちゃん注:魚の頭骨は、複雑で特徴的な形をしているが、これは言うところの「鯛の鯛」を指しているのではなかろうか(厳密には頭部とは言い難い気もするが)。魚の鰓蓋(さいがい)の下方部分にある烏口(うこう)骨と肩甲骨とが癒合した構造部分が、魚のように見えることから「鯛中鯛」(マダイ等のこれが、また、その本体に似ているため)、「タイのタイ」と言う。その昔は、わざわざ好事家小児科医の大西彬の「鯛のタイ」(一九九一年草思社刊)なんぞを物好きにも買ったもんだが、今じゃ、ほれ、解説も、さまざまな「鯛の鯛」もこんな風に簡単に見られる。隔世の感、甚だしきかな、オタクも軽くなっちまったもんだわい。
・「和名抄」は、正しくは「倭(和とも表記)名類聚鈔(抄とも表記)」で、平安時代中期に源順(したごう)によって編せられた辞書。
・「爾雅」は、中国古代の字書。現在の伝本は全十九篇。著者・成立年代未詳。周公旦、或いは、孔子作などと伝えられる。分類と解釈を伴った語彙集の体裁を持つ書である。]
***
はた
ひれ
鰭【音耆】
○鰭【和名波太俗云比禮】文選注云魚
背上鬛也鬛【音獵】字彙云魚龍
額旁小鬐也馬領毛亦曰鬛
○魩【音末】魚尾也或名丙
*
はた
ひれ
鰭【音、耆〔(き)〕。】
○鰭【和名、「波太〔(はた)〕」。俗に「比禮」と云ふ。】は、「文選」注に云はく、『魚の背(せずぢ)の上の鬛〔(ひれ)〕なり。鬛【音、獵〔(れふ)〕。】。』と。「字彙」に云はく、『魚龍の額の旁〔(かたはら)〕の小〔さき〕鬐〔(せびれ)〕なり。馬の領(ゑり)の毛も亦、鬛(たてがみ)と曰ふ。』と。
○魩(いをのを)【音、末。】 魚の尾なり。或いは「丙」と名づく。
[やぶちゃん注:最初に三つのヒレを示す漢字を「廣漢和辭典」を参考にしながら整理しておく。
「鰭」は、音は「キ」又は「ギ」。訓は「ひれ・はた」で、純粋に広く魚のヒレを示す語。
「鬛」は、音は「レフ(リョウ)」で、①「鬛鬛」は「髪の毛が逆立つさま」。②ひげ。あごひげ。③髪。毛。④馬のたてがみ。⑤魚のアゴ(=鰓)の脇の小ビレ。⑥鳥の頭の毛。⑦蛇の鱗。⑧箒。⑨松葉、とあるから、馬の鬣(たてがみ)の意味の方が先行し、後に魚の胸鰭を指すようになった語。
「鬐」は、音は「キ」又は「ギ」。①馬のたてがみ。②魚の背鰭。③虹の曲っている部分。④次第に尽きる(現象を示す動詞の用法である)、とあるから、馬の鬣(たてがみ)の意味が原義で、ミミクリーから、魚の背鰭を指すようになった語。
孰れも、使い分けが面白い。
・『「文選」注』の「文選」(もんぜん)は、中国南北朝時代の南朝梁の昭明太子によって編纂された全三十巻の書物。周から梁までの文章・詩・論文を集めたもの。奈良・平安朝の日本に於いては貴族階級の必読書とされた。通常、単に『「文選」注』と言った場合、唐の李善注を指すことが多い。
・「領」は「馬の首筋」。
・「丙」については、「爾雅」釋魚に「魚尾、謂之丙」とある。魚の尾の形とこの漢字の字体の類似からであろう。]
***
《改ページ》
つちすり
腴【音臾】
スエ゜ウ
○俗作𦚤 【和名豆知須里】魚腹下肥
[やぶちゃん字注:「腴」「𦚤」は、実際には、ともに、最終画の右払いが、前の画を左上方で貫いている。]
處也禮少儀云進魚冬右腴
夏右鰭凡魚冬時陽氣在下
肥美在腹夏則陽氣在上肥
美在脊也
*
つちすり
腴【音、臾〔(ゆ)〕。】
スエ゜ウ
○俗に𦚤に作る【和名、「豆知須里」。】。魚の腹の下の肥えたる處なり。「禮〔記〕」の少儀に云はく、『魚を進むるに、冬は、腴を、右にす。夏は、鰭を、右にす。』と。凡(すべ)て、魚は、冬時は陽氣、下に在り、肥美、腹に在り。夏は、則ち、陽氣、上に在りて、肥美、脊に在ればなり。
[やぶちゃん注:「腴」の原義は「肥」で、「下腹部や滋味が肥える」の意である。そこから、「下腹部の肥えて脂ののった軟らかい肉」のことを指すようになり、魚の場合は、「つちす(ず)り(土摺り・土摩り)」・「すな(砂)す(ず)り」の部分を言うようになった。
・『「禮」の少儀』の「禮」は五経の一つである「礼記」(らいき)。周から漢にかけての儒学者が記した、儀式や儀礼に関する記述を、前漢の戴聖らが編纂したものとされる。全四十九篇からなり、その中の第十七篇の「少儀」は、そこまでの重要な儀式制度に比して、比較的重要度の低い儀礼について論じたもの。その十に、「羞濡魚者進尾。冬右腴、夏右鰭。」とある。以下の陰陽の気の説明はよく分からぬ。この手の漢方系の話は、聴いても納得出来そうな合理的根拠が窺えないことが多いので、あんまり分かりたくもないのが、本音である。]
***
いをのわた
鯝【音故】
クウ
○鯝【訓以乎乃和多】魚肚中腸也又
曰乙
○脬【和名以乎乃布江】魚腹中脬也
諸魚之白脬其中空如泡故
又曰鰾
*
いをのわた
鯝【音、故。】
クウ
○鯝【「以乎乃和多」と訓ず。】は、魚の肚〔(はら)の〕中〔(うち)〕の腸〔(はらわた)〕なり。又、「乙」と曰ふ。
○脬(ふえ)【和名、「以乎乃布江」。】は、魚の腹中の脬〔(うきぶくろ)〕なり。諸魚の白〔き〕脬、其れ、中空にて、泡のごとくなる故に、又、「鰾〔へう)〕」と曰ふ。
[やぶちゃん注:ここでは魚の内臓を乱暴にも一緒くたに論じている。
・「乙」には、確かに「魚のはらわた」の意味がある(一説に「魚のあごの骨」とも)。「廣漢和辭典」の引用が面白い(書き下しには一部に読点・記号と読みを増やした)。
*
〔爾雅、釋魚〕魚腸、謂之乙。其腸似篆書乙字。
(魚腸、之れを「乙」と謂ふ。其の腸〔(はらわた)〕、篆書の「乙」字に似たり)。
〔禮記、内則〕魚去乙。(魚、乙を去る。)
〔禮記鄭玄注〕乙、魚體中害人者名也。今東海鰫魚有骨、名乙。在目旁狀如篆乙。食之鯁人、不可出。
(乙は、魚の體の中(うち)、人を害する者の名なり。今、東海の鰫魚〔(ようぎよ)〕、骨、有り、「乙」と名づく。目の旁(かたはら)に在り、狀(かたち)、篆の「乙」のごとし。之れを食へば、人、鯁〔(かう/きやう)〕し、出だすべからず。)
*
「礼記」の「内則」は家庭内の儀礼を記した部分で、ここは魚の調理法を述べているようで、特に「骨を取り去る」ことを述べている。また、「鰫魚」は中国で「四大家魚」の一つに数えるコイ科の大型魚ハクレン属コクレン Hypophthalmichthys nobilis を指す。「鯁」はズバり、「骨が喉に刺さる」の意である。しかし、この文から考えると、古くは、各器官の内臓を一緒くたにするばかりか、骨をさえ、区別しないで考えていたとも読める興味深い部分ではある。
・「脬」は音「ハウ(ホウ)」又は「ヘウ(ヒョウ)」。詳しくは、次項「鰾」の注を参照。
・「諸魚の白脬、其れ、中空にて」とあるが、厳密には誤り。詳しくは次項「鰾」の注を参照。
・「鰾」は、音「ヘウ(ヒョウ)」又は「ベウ(ビョウ)」。詳しくは次項「鰾」の注を参照。]
***
にべ
鰾【音飄】
○鰾【和名仁倍】本綱諸魚之白脬
其中空如泡故曰鰾可治爲
膠【一名䲂膠】諸鰾皆可爲膠而海
漁多以石首魚鰾作之粘物
甚固此乃工匠日用之物也
*
にべ
鰾【音、飄。】
○鰾【和名、「仁倍」。】「本綱」に、『諸魚の白き脬(ふえ)、其れ、中空、泡のごとくなる故、「鰾」と曰ふ。治〔(をさ)〕めて、膠(にかは)と爲すべし【一名、「䲂膠〔(せんかう)〕」。】。諸〔(もろもろ)の〕鰾、皆、膠に爲すべし。海漁、多く、石-首-魚(ぐち)の鰾を以つて、之を作る。物に粘〔(つけ)〕て、甚だ、固(かた)し。此れ、乃〔(すなは)〕ち、工匠、日用の物なり。』と。
[やぶちゃん注:だから言ったじゃないの、良安先生! だぶっちゃったでしょうが! 私も注が書きにくいでしゅ!
・「鰾」は、音「ヘウ(ヒョウ)」又は「ベウ(ビョウ)」で、「へ」「うきぶくろ」「ははら」「魚胞」など言う。その鰾を煮て膠をとることが多かった魚種スズキ亜目ニベ科ニベ属ニベ Nibea mitsukurii を指す場合もある。
・「脬」は音「ハウ(ホウ)」又は「ヘウ(ヒョウ)」で、「廣漢和辭典」には「ゆばりぶくろ」「膀胱」とのみある。しかし、似てないとは言えないな。これを何故、日本で「ふえ」と呼称するかが(「和名抄」に載るというからかなり古い時代からの呼称である)、前から不思議だったのだが、その語源には、今回もまた至り得なかった。
・「中空」とあるが、厳密には誤り。普段は深海に住みながら、時に浅海まで移動する深海性の硬骨魚の一種には、通常の硬骨魚のようなガス調節が急激な水圧変化に追いつかないため、鰾に比重の低い脂質(ワックス:高級脂肪酸とアルコールのエステル、グリセリドや、パラフィンなど)を詰め込んでいる種がある。例えば、スズキ目サバ亜目クロタチカマス科バラムツ属バラムツ Ruvettus pretiosus 、クロタチカマス科アブラソコムツ属アブラソコムツ Lepidocybium flavobrunneum 、マトウダイ目オオメマトウダイ科オオメマトウダイ属オオメマトウダイ Allocyttus verrucosus 等で、変わったところでは、たしか、「生きた化石」として知られる「ゴンベッサ」(コモロ諸島の地方名で「役に立たない」の意。不味いのである)=シーラカンス亜綱シーラカンス目ラティメリア科ラティメリア属ラティメリア・カルムナエ(第一発見種の現生シーラカンス)Latimeria chalumnae もそうだった(詰まっていたのは、日本での最初の解剖個体だったはずだから二種の内、こちらの種を挙げておく)。こういった脂質を持つ魚は、当然、筋肉にも、それらのワックスを多く含有し、一定量以上を食べると、下痢や腹痛、皮脂漏症(皮膚から脂が漏れ出す症状)を引き起こすことがあるため、流通・食用が禁止されている。なんて脱線をするのは、当然、コノ手のワックス魚を食ったことがあることを吹聴したいから。中でも、カサゴ目ギンダラ科ギンダラ属アブラボウズ Erilepis zonifer の刺身は、悪いね、それ、マジ! 旨いんだなぁ、これが! 無論、達人の調理師が許容量内で捌いて呉れたものを食した。
・「膠」なるものを、私は、不幸にして用いたことがないし、見たこともないぞ……でも絵描きの父は画材として持ってたんだろうけどなあ(今は鮎のドブ釣り命で絵の一枚も描かない)。家に的の俵まである和弓命の伯父も「にべ弓」(古くは弓作りには欠かせない材料であった)に拘ってたりするんかなあ(うちの藪野一族はフリーク系が多い。私ばかりではないのだよ……]
***
《改ページ》
のぎ
いをのほね
鯁【音梗】
ケン
○鯁【和名乃木】魚骨謂之刺
又食𩵋骨留咽中曰鯁【骾同】
直言難受如骨之咈咽
*
のぎ
いをのほね
鯁【音、梗。】
ケン
○鯁【和名、「乃木」。】は、魚の骨、之れを「刺」と謂ふ。又、魚を食ひて、骨の咽〔(のんど)〕の中に留まるを、「鯁」と曰ふ【「骾」、同じ。】。直言〔(ぢきげん)〕して受け難きは、「骨の咽に咈(た)つ」ごとし。
[やぶちゃん注:「鯁」は音「カウ(コウ)」又は「キヤウ(キョウ)」で、元来は「魚の骨」の意。以上の通り、後で「骨が喉に刺さる」の意となり、「災い」「患い」の意でも用いられる。なお、「鯝」の「乙」の注も参照されたい。
・「直言して受け難きは、骨の咽に咈つごとし」とは、「直言されても、それを素直に受け入れ難いのは、『骨が喉に刺さった』ようなものだ。」の意味だが、そういう故事成句は不学にして知らない。「鯁言」という熟語には、「正しい意見を遠慮せずに言うこと、若しくは、その意見」といった意味があるので、そこから良安が敷衍して述べたものか。いや、良安先生、ここでも何だかヘン、やっぱり、これを記述している時、何かそんなことがあったのかしら? やぶちゃん、とっても心配!]
***
いをのこ
䱊【音米】
鮞【音而】䲑【音移】○本綱凡魚皆冬
月孕子至春末夏初則於湍
水草際生子有牡魚隨之洒
尿白蓋其子數日卽化出謂
之魚苗最易長大
*
いをのこ
䱊【音、米。】
鮞【音、而。】䲑【音、移。】○「本綱」に、『凡そ、魚、皆、冬月は、子を孕む。春の末・夏の初めに至りて、則ち、湍水〔の〕草の際〔(きは)〕に於いて、子を生む。牡魚、有りて、之れに隨ひ、尿白を洒(そゝ)ひで、其の子を蓋(おほ)ふ。數日〔(すじつ)〕にして、卽ち、化〔し〕出づる。之、「魚苗〔(ぎよべう)〕」と謂ふ。最も、長大なり易し。』
[やぶちゃん注:「䱊」は、音「ベイ」又は「マイ」、「はらご・はららご・魚の卵」を言う。「鮞」は、音「ジ」、或いは「ニ」、又は「ジク」或いは「ニク」で、「䲑」は音「ギ」(本文では「移」とするので音は「イ」となるが、不審)で、どちらも、やはり「魚の卵」を指す。
・「湍水」は、「渦巻く流れ・早瀬」を言う。時珍の記述であるから、これは淡水魚の産卵を言ったものととるべきである。だから「草の際」が納得出来るのである。
・「魚苗……」は、「魚苗」は、一般に「卵から孵ったばかりの幼魚」を言うが、ここは以上のように、晩春・初夏に早瀬の水草に♀が産卵し、それにオスが正確に放精するタイプの魚類の子ふどもは、大変、大きく成長すると限定的に言っているように読める。……そういうタイプの魚類の同定ですか? ……少し疲れました。――「下ノ畑ニオリマス」――「隨分、御機嫌やう」――]
***
[やぶちゃん注:以下、魚介類の調理法の項。その最後(本巻最後)まで、図は、ない。幾つかの項目で、項目名の下部範囲を終えた説明の一部の後ろが頁頭一字下げ位置まで上がっている(原文翻刻の内、一字下げになっている行は、その部分)。上部に、読み→項目名(「臛」(あつもの)の項は異例で、更に下段に同じ大きさで「羹」の項目が来る)→【字音】(字音は一部項目には、なし)→中国音(一部項目には、なし)が入り、その下部に解説があり、各項目の間は縦罫で仕切られている。横罫は一切ない。以下、煩わしいので、以上の字配置の字注については省略し、項目名と解説の間は行空けのみとした。]
やきもの
炙【音庶】
○炙【和名阿布利毛乃】「說文」字从肉火凡肉置火中曰
炮【和名豆々三夜木】爇之曰燔【音煩】近火曰炙以微火温
曰𤇯【音恩】炙居外和禮謂江海魚前腴河湖魚前
脊背居頭於人左蓋禮記所謂進魚冬右腴夏右鰭與此
[やぶちゃん字注:底本ではこの行のみ、一番上まで上がって一字空けでない。新条目を立てるのではない(本文が前行より続いている)のに、こうなるのは極めて珍しい。]
有少異
*
やきもの
炙【音、庶〔(しよ)〕。】
○炙〔(しや)〕は【和名、「阿布利毛乃〔(あぶりもの)〕」。】、「說文」に、『字、「肉」〔と〕「火」に从〔=從〕ふ。』と。凡そ、肉、火の中に置くを「炮〔(はう)〕」と曰ひ【和名、「豆々三夜木〔(つつみやき)〕」。】、之れを爇(や)〔=燒〕くを、「燔〔(はん)〕」と曰ひ【音、煩。】、火に近づくるを「炙」と曰ひ、微火〔(とろび)〕を以つて、温(あたゝむるを「𤇯」〔(おん)〕と曰ふ【音、恩。】。炙は、外に居(す)ふ。和禮に謂ふ、「江海の魚は、腴(つちずり)を前にし、河湖の魚は、脊背〔(せきはい)〕を前にして、頭〔(かしら)〕を人の左に居ふ。」と。蓋し、「禮記〔(らいき)〕」に謂ふ所、『魚、進むるに、冬は、腴〔(すなずり)〕を右に、夏は、鰭(ひれ)を右にす。』と。此れと、少異、有り。
[やぶちゃん注:「炙」の上部は「月」=「肉」、即ち、「肉」を「火」の上にのせた形で、「あぶる」の意となる。
・「說文」は「說文解字」で、漢字の構成理論である六書(りくしょ)に従い、その原義を論ずることを体系的に試みた最初の字書。後漢の許慎の著。
・「肉、火に从ふ」とは、「肉」が「火」と関連する、「肉」が「火」に就く、即ち、「肉を火の上にかざして焼くの意味である。」という解字である。
・「炮」の原義は、「獣の毛を取らずに丸焼きにすること」で、そこから、物に包んで丸焼きにする意味となった。
・「燔」の原義は、「柴などを焚いて、天に火の粉を上げながら、肉を焼く」の意で、言わずもがな、天の神々に贄(にえ)を捧げる燔餐(はんさん)の祭儀に由来する。
・「𤇯」は、「衣(ころも)を乾かすためや、ぬくめるため、火で暖めるように、とろ火で物をあぶる」の意。別に、「埋め焼く」の意もある。
・「炙は、外に居ふ」は、「配膳の際の全体の中での位置」を言う。
・「和禮に謂ふ」は、「日本のマナーでは」の意。寛永一九(一六四二)年の秘伝伝受の日付を持つ四条流の料理書「料理切形祕傳抄」では『魚を板に据(すえ)て人の前に出(いだ)すには、海魚(うみうを)は、腹を人の方へなし、川魚は背(せな)を人の方へむけて出す物也。同かしらの向(むけ)やうは人の左の方へむけべし。ちいさき魚は、かしらを人の方へ、むくるものなり』とある。
・「腴」は前項の「腴」を参照。
・「禮記」は五経の一書。周から漢にかけての儒学者が記した儀式や儀礼に関する記述を、前漢の戴聖らが編纂したとされる。全四十九篇からなり、その中の第十七篇の「少儀」は、そこまでの重要な儀式制度に比して、比較的、重要度の低い儀礼について論じたものである。その十に『羞濡魚者進尾。冬右腴、夏右鰭。』とある。「腴」の本文を参照されたい。]
***
あつもの 同
𦞦【臛同】 羹【音耕】
○臛羹【共訓阿豆毛乃】王逸云有菜曰羹無
菜曰臛師古云羹與𦞦烹煑異齋調
和不同非關有菜無菜也徐氏云羹
以菜爲主臛以肉爲主【𡭗 〔=尓〕毛乃】以魚肉諸物和羹謂之骨
董羹
*
あつもの 同
𦞦【臛と同じ。】 羹【音、耕。】
○臛〔(かく)〕・羹〔(かう)〕は【共に「阿豆毛乃〔(あつもの)〕」と訓ず。】、王逸が云はく、『菜、有るを、「羹」と曰ひ、菜、無きを、「臛」と曰ふ。』と。師古が云はく、『「羹」と「臛」と、烹煑〔(はうしや)〕・齋〔(とき)〕、異なりて、調和、同じからず。菜、有る、菜、無きに、關(あづか)るに非ざるなり。』と。徐氏が云はく、『羹、菜を以つて、主と爲し、臛、肉を以つて、主と爲す【尓毛乃〔(にもの)〕。】。魚肉、諸物を以つて、羹に和(ま)ぜる、之れを「骨董羹〔(こつとうかん)〕」と謂ふ。』と。
[やぶちゃん注:「臛」は音「カク・コク」で、「肉のあつもの(スープ)」の意(他に、「香気が蒸し上る」の意あり)。「臛」は音「コク・カク」で、「肉のあつもの(スープ)」。「羹」は「羔」が「子羊」を示し、「美」は、もと、「鼎」の象形から簡略化された字で、音は現代仮名遣で「コウ・キョウ・ロウ・カン」で、現代日本で一般に用いられる「羊羹」の「かん」という音は、唐音で特殊な読みで、「スープ」を意味する「羹湯」(こうとう)のように、通常の熟語では、「こう」の読みが普通。「廣漢和辭典」には、「五味を調和させた吸い物」「肉に野菜を混ぜて作った吸い物」とし、字義からも、この後の王逸の解釈としっくりくる。
・「王逸が云はく」の引用は、後漢の王逸による「楚辭」の注釈書(現存最古の「楚辭」の注釈書である)の「楚辞章句」の「招魂」中の「露鷄臛蠵」の注に現れる。
・「師古が云はく」の引用は、東洋文庫版注によれば、初唐の訓詁学者である顔師古の撰になる経典解釈と字義字音書である「匡謬正俗」(きょうびゅうせいぞく)に載るとする。
・「烹煮」は、どちらも「にる」の意で、微妙な煮方の異なりを言うか。
・「齋」は、仏教上の「齋・非時」のような限定的な意味合いではなく、そうした「あつもの」を出す際の、時期的な、若しくは場面的・儀礼的な、料理の出す順等での、時と場合の相違を示しているか。東洋文庫版は『烹煮する齋(時と場合)が異なっていて』と「烹」と「煮」を、そうした違いの意味での別漢字と取っているかのようにも読める。碩学の御意見を埃つ。
・「調和、同じからず」は、「混ぜ合わせる内容物の相違をも、両字の区別には含まれていること」を示す。即ち、後述する如く、単に、菜の有る・無し等というような単純なものではなく、「烹煮」「齋」「調和」の総てに於いて、厳然たる相違が両者にはあることを言う。だったら、それを具体的に書けよ、って言いたいがね。
・「徐氏が云はく」は、東洋文庫版注によれば、南唐の徐鍇(じょかい)撰の「說文」の最古の解釈書「說文繫傳」に載るとする。
・「骨董羹」は、有体(ありてい)に言ってしまえば、「ごった煮」のことである。]
***
いりもの
※【音淺】
[やぶちゃん字注:※=「月」+「雋」。]
○※【和名以利毛乃】少汁也曹子建七啓所謂※漢
南之鳴鶉是也
[やぶちゃん注:※2=「確」の「石」を「月」に換える。]
*
いりもの
※【音、淺。】
[やぶちゃん字注:※=「月」+「雋」。]
○※は【和名、「以利毛乃〔(いりもの)〕」。】、汁、少なき𦞦なり。曹子建〔が〕「七啓」に謂ふ所、『漢南の鳴鶉〔(めいじゆん)〕を※〔(い)る〕。』〔とは〕、是れなり。
[やぶちゃん字注:※=「確」の「石」を「月」に換える。]
[やぶちゃん注:「※」は音「セン・スイ」、「肉」に、「鳥肉が肥えて柔らかいこと」を意味する「雋」を加えた字で、「汁の少ないあつもの(スープ)」とする。
・『曹子建が「七啓」』は、魏の曹植の、父曹操を讃えるための美文「七啓」。全体像は「漢籍リポジトリ」の「曹子建集卷第九」のガイド・ナンバー[009-5a]で確認されたい。当該部分は同所の六行目に現われる。]
***
なます
膾【鱠同】
○鱠【和名奈萬須】細切肉也本綱生魚劊切而成故
謂膾凡魚之鮮活者薄切洗浄血鮏沃以蒜薑
醋等五味食之近夜勿食不消成積【不可同瓜食也】論
語膾不厭細曲禮云膾炙處外
*
なます
膾【鱠と同じ。】
○鱠は【和名、「奈萬須〔(なます)〕」。】は、細く切〔りたる〕肉なり。「本綱」に、『生(なま)魚、劊(た)ち切りて、成す。故に「膾」と謂ふ。凡そ魚の鮮-活(あたら)しき者、薄く切りて、血-鮏(〔ち〕なまぐさ)きを洗浄〔して〕、沃〔(すす)〕ぐ。蒜〔(にんにく)〕・薑〔(しやうが):生姜。〕・醋〔(す)〕等の五味を以つて、之れを食ふ。夜に近くは、食ふこと、勿れ。消せずして、積〔(しやく)〕と成る【瓜と同〔じくして〕食ふべからざるなり。】。』と。「論語」に、『膾は、細きを厭〔(いと)〕はず。』と。〔「禮記」〕「曲禮」に云はく、『膾・炙(やきもの)は、外に處(す)ふ。』と。
[やぶちゃん注:「膾」は音「クワイ(カイ)・ケ」、「會」は「合わせる」で、「細かく切った生の魚肉に、酢を合わせた膾」の意を示す。
・「五味」は、「甘・酸・鹹・苦・辛」の総称。
・「消せずして、積と成る」は「消化することが出来ずに、腹にもたれる」の意。
・『「論語」に……」は、同書「鄕黨第十」にある言葉。少し長いが、孔子の食への「こだわり」が窺える面白い章なので、以下に全文引用する(所持する明治書院一九六〇年刊吉田賢抗「新釈漢文大系1 論語」を参考底本とした)。
*
食不厭精。膾不厭細。食饐而餲、魚餒而肉敗不食。食惡不食。臭惡不食。失飪不食。不時不食。割不正不食。不得其裳醬不食。肉雖多、不使勝食氣。惟酒無量、不及亂。沽酒市脯不食。不撤薑食、不多食。祭於公不宿肉。祭肉不出三日。出三日、不食之矣。食不語。寢不言。雖疏食菜羹瓜祭、必齊如也。
○やぶちゃんの書き下し文
食(し)は、精(しら)げるを厭はず。膾は、細きを厭はず。食の饐(い)して、曷(あい)し、魚(うお)の、餒(たい)して、肉の敗(はい)したるは、食らはず。色の惡しきは食らはず。臭ひの惡しきは、食らはず。飪(じん)を失したるは、食らはず。時ならざるは、食らはず。割(きりめ)、正しからざれば、食らはず。其の醬(しやう)を得ざれば、食らはず。肉は多しと雖も、食(し)の氣に勝(か)たしめず。惟(ただ)、酒は、量、無しとするも、亂(みだ)りに及ばず。沽酒(こしゆ)・市脯(しほ)は、食らはず。薑(はじかみ)を撤(す)てずして食らふも、多くは、食らはず。公(おほやけ)に祭(まつり)すれば、肉を宿せず。祭の肉は、三日を出ださず。三日を出づれば、之れを食らはず。食らふに、語らず。寢(い)ぬるに、言はず。疏食(そし)・菜羹(さいこう)・瓜(くわ)と雖も、祭るに、必ず、齊如(さいじよ)たり。
○やぶちゃん訳:孔子さまは、飯は精白された白米をお好みになるが、必ずしもそれにこだわったわけではなく、未精米のものでもお嫌いにはならない。膾(なます)は、肉類を細かく切ってあるものを、お好みになる。飯が饐(す)えて臭いがしたり、味が変わっていたり、また、魚が傷んでいたり、肉が腐っていたりすれば、お食べにならない。色の悪いものは、お食べにならない。臭いの悪いものは、お食べにならない。生煮えや、煮過ぎ等、煮加減が悪ければ、お食べにならない。季節外れのものは、お食べにならない。肉の切り方が正しくなければ、お食べにならない。肉や魚は、それに適したソースや醤油が一緒に出なければ、お食べにならない。肉は多くお食べになるとしても、その時の飯の量以上にお摂(と)りになることはない。飲酒の量は、お決めになっていないが、酔って取り乱すほどには、お飲みにならない。自分でお作りになる酒以外の、町で買った酒や、自分で作られる干肉以外の、市場で売られている干肉は、お食べにならない。ツマに添えられたり、一緒に漬け込まれたりした生姜は、捨てずに、お食べになるが、沢山は、お食べにならない。主君の先祖の祭祀の執行を助けた際に下賜される肉は、その日の夜を越すことなく、食べきる。自分の家の先祖の祭祀に用いた肉は、三日以上は残さず、三日を越えてしまうと、お食べにならなかった。食事をする際には、相手とは、お語りにならず、おやすみになっている際には寝言をおっしゃらない。粗末な飯・野菜の汁・瓜のごときものであっても、必ず、神へのお供えをする(お初を執(と)る)ことを忘れず、その時には、たとえ、そのようなつまらない僅かなものであっても、一貫して、恭しく、厳粛にして、誠実な態度で、心をこめてお祭することをお忘れにならない。
*
現代語訳には敬語と、概ね現在時制を用いて、生きた孔子について語るような雰囲気を出してみた。
・「曲禮」は「禮記」(らいき:五経の一書。周から漢にかけての儒学者が記した儀式や儀礼に関する記述を、前漢の戴聖らが編纂したとされる。全四十九篇)の中の第一及び第二篇が「曲禮」の上・下で、五礼(吉・凶・賓・軍・嘉)に就いて総説する。その第一篇「曲禮 上」に「膾炙處外、醯醬處内、蔥渫處末、酒漿處右。」とある。]
***
さしみ
𩵋軒
胾【音恣】○禮記注純肉切曰胾肉柔故胾右居
又云肉塊細切爲膾大切爲軒
△按鱠胾相似而有異鱠細切而和萊菔栗
薑蓼等之五味沃之以醋食之胾【俗云左之美】純肉牒調別
《改ページ》
■和漢三才圖會 魚之用 卷ノ五十一 ○二十九
用熬酒山蓼或生薑醋食之異國牛羊猪豕麋鹿皆有
軒本朝亦上古皆食獸肉天武天皇四年詔曰自今以
後莫食牛馬犬猿鷄之完犯此者罪之以外不在禁制
而後諸獸肉不得食且以爲穢神社最忌之今稱肉者
魚鳥而已魚肉薄切曰【※1※2同】
[やぶちゃん字注:「※1」=「蝶」の「虫」を「月」に換える。※2=「月」+(「弃」の下部「廾」を「木」に換える)。]
*
さしみ
魚軒
胾【音、恣〔(し)〕。】○「禮記」注に、『純肉、切りたるを、「胾」と曰ふ。肉は柔なり。故に、胾は、右に居〔(す)〕ふ。』と。又、云ふ、『肉塊、細く切るを「膾〔(なます)〕」と爲し、大に切りたるを、「軒〔(さしみ)〕」と爲す。』と。
△按ずるに、鱠(なます)と胾(さしみ)は相〔あひ〕似て、異、有り。鱠は、細く切りて、萊-菔(だいこん)・栗・薑〔:生姜。〕・蓼〔(たで)〕等の五味に和して、之れに沃〔(そそ)〕ぐに、醋〔(す)〕を以つて〔し〕、之れを食ふ。胾は【俗に「左之美」と云ふ。】、純肉、牒(つく)り調へ、別に熬酒〔(いりざけ)〕・山-蓼〔(わさび)〕、或いは、生薑醋〔(しやうがず):生姜酢。〕を用ひて、之れを食ふ。異國には、牛・羊・猪・豕〔(いのこ):豚。〕・麋〔(なれしか)〕・鹿、皆、軒(さしみ)、有り。本朝にも亦、上古、皆、獸肉を食ふ。天武天皇四年、詔〔(みことの)〕りして曰はく、『今より以後、牛・馬・犬・猿・鷄の完(しゝ)を、食ふ莫かれ。此れを犯す者、之れを罪(つみと)はん。以(こ)の外は、禁制に在らず。』と。而後、諸獸〔の〕肉、食ふことを得ず。且つ、以つて、「穢(けが)れ」と爲す。神社、最も、之れを忌む。今、「肉」と稱する者は、魚・鳥のみ。魚肉、薄く切るを「※1(つく)る」と曰ふ【「※2」、同じ。】。
[やぶちゃん字注:※1=「蝶」の「虫」を「月」に換える。※2=「月」+(「弃」の下部「廾」を「木」に換える)。]
[やぶちゃん注:「魚軒」の「軒」は、「大きく切った獣肉」を言い、以下の「禮記」の記載にあっても、我々の想起する「刺身」とは異なるものと考えるべきである。即ち、中国での「魚軒」や「胾」は、魚の肉の大きく四角に切った「物」という素材としての加工途中の食材を指し(それに熱を加えても、恐らく「胾」と呼んだと思われる)、生食する刺身という「料理名」とは違うように感じられる。中国では、本来、如何なる動物の肉も、普通は食さない。
・「胾」は、音「シ」、切り身。「大きく切った肉片」の意。
・『「禮記」注』は「禮記」の宋の呉曽祺(ごそうき)による注釈書「禮記菁華錄」の「曲禮上第一」の「凡進食之禮。左殽右胾。」の注などを指すか。そこに「肉帶骨曰殽。純肉切曰胾。骨剛故左肉柔故右。」とある。「曲禮」は五礼(吉・凶・賓・軍・嘉)について総説した章で「礼記」第一篇がその「曲禮上」、第二篇が「曲禮下」である。
・『肉塊、細く切るを、「膾」と爲し、大に切りたるを、「軒」と爲す。』は、「禮記」の第十二内則篇(家内の儀礼について記す)に『肉腥細者爲膾、大者爲軒。』とある。
・「五味」は、甘・酸・鹹・苦・辛の総称。
・「熬酒」とは、調味料の一種。一説に、酒・梅干・鰹節・味醂少々を加えて煮詰めるとも言い、文化文政期の調合法としては、「酒二盃・醤油半盃・大梅五つ・鰹節沢山」ともある。醤油にとって代わられるまでは、かなりポピュラーな調味料であったらしい。
・「麋」は、音は「ビ・ミ」、広義の「大鹿」(大型の鹿類の意)以外に、現代中国語では、種として、偶蹄目反芻亜目シカ科ノロ亜科Capreolinae のヘラジカ属ヘラジカ Alces alces 、及び、シカ亜科シフゾウ属シフゾウ Elaphurus davidianus が相当するものの、古い中国でのそれであるから、ここは大型のシカ科 Cervidaeのシカ類としておくのが、無難である。
・「天武天皇四年、詔りして曰く……」以下は、「日本書紀」天武五(六七五年)四月十七日に発せられた肉食禁止令で、四月一日から九月三十日までの限定期間、魚の稚魚の保護及び五畜(牛・馬・犬・日本猿・鶏)の肉食を禁止する内容である。以下に示す。これは、「涅槃経」が主旨の核心であるとされるが、仏教伝来から百年にしての宗教的禁制、これが後に思わぬ酷い人間の差別を生むルーツとなったことを忘れてはならない。
*
庚寅詔諸國曰、自今以後、制諸漁獵者、莫造檻阱及施機槍等類。亦四月朔以後九月三十日以前、莫置比滿沙伎理梁。且莫食牛馬犬猿雞之宍、以外不在禁例。若有犯者罪之。
○やぶちゃんの書き下し文
庚寅、諸國に詔(みことの)りして曰く、『今より以後、諸漁獵者を制して、檻を造り阱(あなほ)り、及び、機槍(ふむはなち)等の類ひを施す莫かれ。亦、四月朔以後、九月三十日以前に、比滿沙伎理(ひみさきり)の梁(やな)を置くこと、莫かれ。且つ、牛・馬・犬・猿・雞の宍(しし)を食ふこと、莫かれ。以外は、禁の例に在らず。若(も)し犯す者、有らば、之れを罪せむ。』と。
○やぶちゃん訳
庚寅(かのえとら)の日、諸国に詔りして宣はれた。
「向後、総ての漁猟する者に制限を加える。檻や穽(落し穴)・機械仕掛けの槍等の罠は、一切、造ってはならない。また、四月一日から九月三十日日までの期間は、目の細かい梁(やな)を仕掛けてはならない。且つ、牛・馬・犬・猿・鶏の肉を食ってはならない。この凡例以外のものは禁止としない。もし、これを犯す者が有れば、これを罰する。』と。
・「※1」[※1=「蝶」の「虫」を「月」に換える]は、音「チョウ・ショウ・ジョウ」(現代仮名遣)で、「薄く大きく切った肉片」又は「細切れの肉」を指す。
・「※2」[※2=「月」+(「弃」の下部「廾」を「木」に換える)]は音も意味も不明。東洋文庫版にもルビがない。]
***
すし
鮓【音査】
鮨【音支】𩷒【䰼同】𩻢【鲝同】○本綱釋名云鮓【和名須之】醖也以
盬糝醖釀而成也諸魚皆可爲之大者曰鮓小
者曰𩷒【南人曰𩷒北人曰鮓】凡鮓發瘡疥鮓内有髪害人
鮓不熟者損人脾胃諸無鱗魚鮓尤不益人不可合豆
藿麥醬蜂蜜食令人消渇及霍乱
[やぶちゃん注:「乱」はママ。]
△按釀鮓法盬少糝壓之一夜拭淨水氣用冷飯藏于桶
如糟漬法而春冬四五日夏秋一二日熟凡江州鮒濃
州鰷和州吉野鰷【名釣瓶鮓】城州宇治鰻鱺【名宇治丸】攝州福島
小鰡【名雀鮓】和州今井鯖皆得名者也一種有杮鮓者鯛
鯧鮑章魚烏賊※等魽〔=蚶〕加之以紫蘓〔=蘇〕筍木耳釀之最爲
《改ページ》
上品【凡鮓得蓼山椒味美】
[やぶちゃん字注:「釀」は原本では、孰れも、(なべぶた)の下が「人」を二つ並べた字体。「䰼」は原本では、(つくり)は「今」。「𩻢」は原本では、上部は「巫」の一画目がない。東洋文庫版を採用した。「鲝」は原本では、下部が正字の「魚」。「※」=「蝶」の「虫」を「月」に換える。「蘓」の「魚」は「𩵋」。]
*
すし
鮓【音、査。】
鮨【音、支。】・𩷒〔(しん)〕【䰼〔(しん)〕、同じ。】・𩻢〔(さ)〕【鲝〔(さ)〕、同じ。】。○「本綱」、「釋名」に云ふ、『鮓は【和名、「須之」。】醖〔(うん):醗酵させる。〕なり。盬を以つて、糝(まぶ)し、醖-釀(かも)して成るなり。諸魚、皆、之れを爲〔(つく)〕るべし。大なる者、「鮓」と曰ひ、小なる者、「𩷒」と曰ふ【南人は、「𩷒」と曰ひ、北人は、「鮓」と曰ふ。】。凡そ、鮓は、瘡疥〔(さうかい)〕を發す。鮓の内に、髪、有れば、人を害す。鮓、熟せざる者は、人の脾胃〔(ひゐ)〕を損ず。諸無鱗魚の鮓は、尤も、人に益あらず。豆の藿(は)・麥醬〔(ばくしやう)〕・蜂蜜と合せて食ふべからず。人をして消渇、及び、霍乱せしむ。』と。
△按ずるに、鮓を釀〔(つく)〕る法は、盬、少し、糝(まぶ)して、之れを壓(を[やぶちゃん注:ママ。])すこと、一夜、水氣〔(みづけ)〕を拭淨〔(しよくじやう)〕して、冷飯を用ひて、桶に藏〔(をさ)〕むること、糟漬〔(かすづけ)〕の法のごとくにして、春・冬は、四、五日、夏・秋は一、二日にして熟(な)る。凡そ、江州〔=近江〕の鮒、濃州〔=美濃〕の鰷〔(あゆ)〕、和州〔=大和〕吉野の鰷【「釣瓶(つるべ)鮓」と名づく。】、城州〔=山城〕宇治の鰻鱺(うなぎ)【「宇治丸」と名づく。】、攝州〔=攝津〕福島の小鰡(ゑぶな)【「雀鮓」と名づく。】、和州今井の鯖、皆、名を得る者なり。一種、「杮鮓(こけらずし)」と云ふ者、有り[やぶちゃん注:「云」は送りがなにある。]。鯛・鯧(まながつを)・鮑(あはび)・章魚(たこ)・烏賊(いか)・蚶(あかゞい[やぶちゃん注:ママ。])等、※(つくり)て、之れを加ふるに、紫蘇・筍(たけのこ)・木-耳(きくらげ)を以つて、之れを釀〔(つく)〕る。最も上品たり【凡そ、鮓、蓼・山椒を得れば、味、美なり。】。』と。
[やぶちゃん字注:「釀」は原本では、孰れも、(なべぶた)の下が「人」を二つ並べた字体。「䰼」は原本では、(つくり)は「今」。「𩻢」は原本では、上部は「巫」の一画目がない。東洋文庫版を採用した。「鲝」は原本では、下部が正字の「魚」。「※」=「蝶」の「虫」を「月」に換える。「蘓」の「魚」は「𩵋」。]
[やぶちゃん注:「鮓」は音「サ・シャ」(現代仮名遣)で、本来は、酢に漬けた、又は、塩や糟に漬けた魚を言う語である(別に「クラゲ」の意味もある)。中国も、本書の時代の日本も、「鮓」と書いた場合は、以上に列挙されるような、所謂、「熟れ鮓(なれずし)」を指し、良安の記載も、そのようなコンセプトで語られており、現在の我々に馴染みの早鮨(はやずし)=握り寿司のニュアンスは全くないので、本書の魚貝部の「鮓」はみなそれであることに注意されたい。
・「瘡疥」は、広く、吹き出物から、強い発疹等の種々の皮膚疾患全般を言う。
・「豆藿」は、「黄帝内経素門」の中の臓気法時論篇に「五菜」(他にナス・ニラ・ニンニク・ネギを数える)の一つとして挙げらている「豆叶」(とうと)である。これは、広く、良安がルビを振るように「豆類の葉」を指すが、中国語サイト(簡体字)の「古代“五菜”述略」等によれば、特にエンドウマメ(マメ目マメ科マメ亜科エンドウ属エンドウ Pisum sativum 、若しくは、その仲間)の葉を指しているとあった。くどいが、これは、「豆」でも「莢」でもなく、エンドウの「若い苗」や「茎葉(けいよう)」と呼ばれる「蔓(つる)の先の柔らかな部分」、所謂、「豆苗」(とうみょう)を指すと思われる。「豆藿」という語は、他に、広く「蔬菜」を指す語でもあるが、全ての野菜と鮨の食い合わせが悪いというのはいくらなんでも、不自然に思われる。
・「麥醬」は、大豆を使用せず、小麦と塩から造った醤油で、江戸時代には盛んに用いられた(現在は規格上、大豆を用いないものに「醤油」は命名出来ないため「白たまり」と称している)。
・「消渇」は、口が渇き、多飲多尿を示す症状で、私の持病である糖尿病を指すと思われる。
・「霍乱」は、激しい嘔吐・下痢・腹痛を訴える症状。
・「江州の鮒」は近江の「鮒鮓」。琵琶湖固有種であるコイ亜科フナ属ニゴロブナ Carassius auratus grandoculis の♀を用いる。私の大好物であるので、特に現在の製法を、種々の記載を総合して述べる。卵を持った♀の鱗を完全に取り去り、腹開きにして、卵巣以外の全ての内臓を除去する。腮の部分から、腹腔内に塩を詰め、更に塩をたっぷりと用いて桶に並べ、三ヶ月から一年ほど、漬ける。漬かったフナを、水洗いして、適度に塩抜きをした後、暫く、置く。その後、塩をまぶした飯を混ぜたものを、腮から詰めたものを、再度、桶に御飯と交互に重ね詰めして、密封する。それを、最低でも四ヶ月から最長二年程度まで、漬け込み、醗酵・熟成を促す。最短でも、生きた鮒の水揚げから、七ヶ月は要する、スロー・フードである。私から一言。付着している飯は捨ててはいけない。頭部は、この飯と一緒に、細かく叩くとよい。素(す)の飯も、頭と和えた飯も、共に惜しみつつ、鮒鮓を食った後日、余韻の酒のあてに、はたまた、名残りの茶漬に用いて、文句なく美味である。
・「濃州の鰷」は、「鮎の熟れ鮓」。長良川の鵜飼漁で捕れたアユ(キュウリウオ上科アユ科アユ属アユ Plecoglossus altivelis altivelis )を用いた熟れ鮓。古くから幕府への献上品であった。現存する。ここで用いられている「鰷」は、本来は、訓でコイ科ウグイ亜科ウグイ Tribolodon hakonensis (ごく狭義の異名で「ハヤ」・「ハエ」。広義の複数種のそれは、何度も述べたので、ここでは略す)を指し、音も「チョウ・ジョウ・ショウ」(現代仮名遣)で、「鮎」又は「あゆ」という読みとは結びつかないのであるが、明治三四(一九〇一)年頃の出版になる、田中芳男編纂・藤野富之助補輯の「水産名彙」にアユの読みがあり(「真名真魚字典」)、ここは、その加工食品の歴史から見て、当然、アユ以外には考えられない。私は、実は本巻の前項「鱠殘魚 しろいを」の注で取上げた「氷魚(ひを)」の注で、この字の読みには、疑義を出している。参照されたい。なお、アユの「熟れ鮓」は「今昔物語集」(登場箇所も知っており面白いが、余りに汚いのでここに引用したくない。巻三十一の第三十二、この直前の三十一も、同じように懐かしく、グロいというか、ゲロい話だ。みんなが知っているよ、ほら、「太刀帯の陣」の魚売りの婆さんだよ、知らない? いいや、みんな高校一年生の時に読んでるさ)等にも登場しており、平安期以前、相当古い時代から、加工品としてあったと思われる。
・「釣瓶鮓」は「義經千本櫻」三段目「すしやの段」で有名なであるが、惜しくもこの「鮎鮓」は現存しない。芝居のモデルとなったとされる釣瓶鮓「弥助」は、昔ながらの桶(釣瓶)作りの職人がいなくなり、流通のスピードに追いつけなくなったとして、昭和六三(一九八八)年に製造を中止している。釣瓶鮓の由来は、その鮓桶が井戸の釣瓶に似ていたことからで、現在も「弥助」には、明治期の桶が残る。釣瓶鮓は、アユを開いて、水洗いし、塩漬にし、その後、腹に飯を詰め、それを先の桶に並べて押しをかけ、熟成させたものである。
・「宇治丸」という宇治川で捕れる鰻を用いた料理名は、室町時代の記述に現れるらしいが、それ炙り物で、鮓ではない。文政一三(一八三〇)年刊の喜多村節信(ときのぶ)の「嬉遊笑覧」には、「鰻の鮓」という記述が出て来る。これはどうもウナギ目ウナギ科ウナギ Anguilla japonica の酒漬けであるらしいが、それ以上のことは不明である。生ウナギの熟れ鮓は、べろべろになった皮とか……う~、流石の私も、ちょっと引いちゃうかも。炙ったものを、漬け込んだものではあるまいか。
・「小鰡」は、ボラ目ボラ科のボラ Mugil cephalus の別名、又は、幼魚を指す。
・「雀鮓」は現在、「小鯛の雀鮓」として知られるが、古くは「浪花江鮒」(なにわえぶな)と呼んだ「ボラの稚魚」を用いた。ボラを背割りにして、内臓を除去して、干し、そこに御飯を詰めて熟成させた熟れ鮓である。飯の詰め方と醗酵により、腹部が膨満し、形が雀に似ることから名づけられたと言われる。江戸の早い時期に既に摂津の名産であった。元祖雀鮓と思しき「鮨萬」の「歴史」を見られたい。それによれば、承応二(一六五三)年の創業とあるから、このまさに「鮨萬」のページに記されている「今宮心中」(正徳元(一七一一)年)で、この雀鮓を台詞に取り上げた近松門左衛門(当時、近松五十九歳)その人が生まれた年でんがな。
・「和州今井の鯖」は、現在の奈良県橿原市今井町に於いて、古く、祭事や祝い事の際に食されたサバ(スズキ目サバ科サバ属 Scomber )の熟れ鮓。熟れ鮓としては現存していない模様である。
・「杮鮓」(こけらずし)は、現在伝わるものは、鮓飯と素材を重ね合わせた箱鮨であるが、良安の叙述は、層状の鮓のようには見えず、それらの素材を混ぜ合わせて醗酵・熟成させたもののように読み取れるが、この「杮」(こけら)という名称は、鮓飯の上に良安が挙げたような素材の薄切りの具を並べたさまが、柿葺(こけらぶき)、即ち、薄い裂いた木片で葺いた屋根の如く見えたことからの命名である可能性が強く(切ったそれらの素材の形が、手斧(ちょうな)で木を薄く削った削り屑である「こけら」(杮)に似ているからともとれる)、良安の時代には、既にこのような並べた四角い形状をしており、それが当たり前に認識されていた(故に形状の仔細な描写は不要と考えた。良安は京都人である)とも考えられないこともない。なお、そのような箱鮨としての「柿鮓」の製法の詳細については、歌舞伎座のメールマガジン「江戸食文化紀行」の「No.22 すし――押しずし――」のページ等が詳しい。]
***
かまぼこ
蒲鉾
魚餠○造法刮取海鰻肉擣千杵和盬酒各少
許再擣令如餠粘着竹枝炙之如蒲草穗又似
鉾故名或有粘杉板者用方頭魚緋魚藻魚鮸
等無毒魚作蒲鉾其肉稍脆故加鷄卯〔→卵〕汁令粘之病人
食之無損又有以鱣者此魚家僞于海鰻肉者味不佳
*
かまぼこ
蒲鉾
魚餠〔(ぎよべい)〕○造る法。海-鰻(はも)の肉を刮(こそ)げ取り、擣〔(つ)〕くこと、千杵〔(きね)〕、盬・酒、各々、少しばかり和して、再たび、擣きて、餠〔(もち)〕のごとくならしめ、竹の枝に粘着して、之れを炙〔(あぶ)〕る。蒲-草〔(がま)〕の穗のごとし。又、鉾に似る。故に名づく。或いは、杉板に粘(つ)くる者、有り。方-頭-魚(くずな)・緋-魚(あご)・藻魚(も〔いを)〕)・鮸(ぐち)等の、無毒の魚を用ひて、蒲鉾に作る。其の肉、やや、脆〔(もろ)〕し。故に、鷄-卵(たまご)の汁を加へて、之れを粘(ねば)らしむ。病人、之れを食ひて、損、無し。又、鱣(ふか)を以つて、する者、有り。此れ、魚家(いをや)、海-鰻(はも)の肉に僞〔(いつは)〕るは、之〔(これ)[やぶちゃん字注:「之」は送り仮名にある。]〕、味、佳からず。
[やぶちゃん注:蒲鉾の原材料としては、現在は、タラ目タラ亜目タラ科スケトウダラ Theragra chalcogramma の利用量が多いが、そもそも、蒲鉾は、白身の魚であれば、雑魚でもサメでも、広く素材とし得る。
・「海鰻」は、ウナギ目アナゴ亜目ハモ科ハモ属 Muraenesox cinereus 、及び、その亜種を指す。前掲同項を参照されたい。
・「方頭魚」は、スズキ目キツネアマダイ科アマダイ属 Brachiostegus を指すと考えてよい。現在も「クズナ」の別称を持つ。「皮剥魚」の後注を参照されたい。
・「緋魚」については、東洋文庫版はルビを『あゆ』とする。しかし、アユを蒲鉾の材料とするのは奇異であるし、アユの別名に「緋魚」というのは聞かない。これは東洋文庫版の編者が、原文の振りがなである「コ」を「ユ」と読み誤ったのである。即ち、これは「アコ」と書かれているのであり、「アゴ」で、トビウオのことである。トビウオは「緋魚」の別名を持つ。これは、ダツ目トビウオ科 Exocoetidae のトビウオ類を指している。そうして確かに、トビウオは、立派に蒲鉾の材料となっているのである。前掲「文鰩」(とびいを)の項も参照されたい。
・「藻魚」は、海藻の繁茂する沿岸域に棲息する魚を指す語で、メバル・ハタ・ベラ・カサゴなど、多種を広く含む。
・「鮸」は、「イシモチ」とも呼ばれるスズキ目ニベ科シログチ属シログチ Argyrosomus argentatus を指す。
・「鱣」は、広くサメ類を指す。前掲「鱣」の項参照。]
***
しゝひしほ
魚醢
イユイ ハアイ
○陶氏云肉醬魚醬皆呼爲醢【和名之々比之保】毛氏
禮記注云凡作醢者必先膊乾其肉莝之雜以
粱麯及盬以美酒塗置甄中百日卽成
南蠻漬法 醋酒等分一沸入燒盬少許盛甄以鮮魚肉
※入其中經一晝夜味極美復次加入亦佳雖極暑五
七日不鮾以代鱠軒良方也
[やぶちゃん字注:※=「蝶」の「虫」を「月」に換える。]
*
しゝびしほ
魚醢
イユイ ハアイ
○陶氏が云はく、『肉醬・魚醬、皆、呼びて「醢〔(かい)〕」と爲す【和名、「之々比之保〔(ししびしほ)〕」。】。』と。毛氏が「禮記」注に云はく、『凡そ、醢を作るには、必ず、先づ、其の肉を、膊(は)り乾し、之れを莝〔(さ)し:切り。〕、粱-麯(かうじ)、及び、盬を以つて、雜〔(まぜ)〕るに、美酒を以つて、塗り、甄中〔(けんちう):陶器の中。〕に置く。百日にして卽ち、成る。』と。
南蠻漬(なんばんづけ)の法 醋・酒、等分、一沸〔(ひとわかし)〕して、燒盬を少しばかり入れ、甄に盛り、鮮魚の肉を以つて、※(つく)りて其の中に入れ、一晝夜を經て、味、極美なり。復た、次に加へ入〔(いる)〕るも亦、佳し。極暑と雖も、五、七日は鮾(〔く〕さ)からず。以つて、鱠(なます)・軒(さしみ)に代〔(かは)〕る良方なり。[やぶちゃん字注:※=「蝶」の「虫」を「月」に換える。]
[やぶちゃん注:「醢」は音「カイ」、(つくり)の部分は、「肉を手に取って勧める」意を示す。そこから、干肉を刻んで塩・麹と混ぜ合わせ、酒に漬け込んで熟成させた「しおから」「ししびしお」を指す(別に「人を殺して塩漬けにする刑罰」をも指す。なお、そのように処刑された「ししびしお」は、当然、食べられたのである。かの私の好きな暴虎馮河の小路も食われた)。ただ、ここで言う、特に前半の「魚醬」は、所謂、現在の「うおびしお」=「しょっつる」=「ナンプラー」に繋がるものを、私は、強く感じている。
・「陶氏」は陶弘景。六朝時代の南朝梁の本草学者。彼の撰した「本草経集注」の中に、『醬多以豆作、純麥者少。今此當是豆者、亦以久久者彌好。又有肉醬・魚醬、皆呼爲醢、不入藥用也。』とある(以下の繁体字ページ参照)。
・「毛氏」は、一般に「毛詩」と別称される「詩經」に、伝(=注釈)を施した前漢の訓詁学の一派であった毛亨(もうこう)・毛萇(もうちょう)を指す。その注釈に、後に後漢の鄭玄(じょうげん)が、更に箋注を施しているため、良安は別に、「禮記」に注釈を施したことがある鄭玄と「詩經」の古注釈者達を混同錯誤してしまったものと思われる。
・『「禮記」注に云ふ』は「周禮」天官の鄭玄による注にある『作醢及臡者、必先膊乾其肉、乃後莝之、雜以梁麴及鹽、漬以美酒、塗置瓶中百日責成矣。』からの引用である。]
***
しほから
なしもの
鱁鮧
トヲン イヽ
○鱁鮧【俗云之保加良】唐韻云盬藏魚腸也漢武逐夷
至海上見漁人造魚膓于坑中取而食之遂命
此名言因逐夷而得是矣
*
しほから
なしもの
鱁鮧
トヲン イヽ
○鱁鮧〔(ちくい)〕【俗に「之保加良〔(しほから)〕」と云ふ。】「唐韻」に云はく、『盬藏(づけ)魚の腸なり。』と。漢武〔:漢の武帝。〕、夷〔(えびす)〕を逐ひ、海上に至り、漁人、魚の膓(わた)を坑〔(あな)〕の中に造るを見る。取りて之れを食ひて、遂に此の名を命ず。言ふ心は、夷を逐〔(お)〕ふに因りて、是を得たる〔となり〕。[やぶちゃん字注:「心」は送りがなにある。]
[やぶちゃん注:「廣漢和辭典」には『鱁鮧(チクイ)は、魚の名。また、しおから』とある。魚名を特定出来る要素はない。この「鱁」「鮧」には、ちらちらアユの意味が見え隠れ、それにウルカ(アユの内臓や卵や白子等を用いた塩辛)の影がさらに透けると、そのような同定の誘惑にも駆られるが(実際に、そのような解釈を下している文献があるのだが)、「海上」とあることや、「鮧」がオオナマズやナマズの意味を中国で持っている(「鮎」は中国では、アユではなく、ナマズを指すことは最近では広く知られるようになった)ことなどから、アユでは、ない。本件のエピソードについては、「斉民要術」(せいみんようじゅつ)の第八巻の「作醬等法第七十」の注等に載る。「斉民要術」は北魏の賈思勰(かしきょう)が著した中国最古の総合農学書である。以下に、その注を引く。
*
作鱁法
昔漢武帝逐夷至於海濱、聞有香氣而不見物。令人推求、乃是漁父造魚腸於坑中、以至土覆之、香氣上達。取而食之、以爲滋味。逐夷得此物、因名之、蓋魚腸醬也。 取石首魚、魦魚、鯔魚三種腸・肚・胞・齊淨洗、空著白鹽、令小倚鹹、内器中、密封、置日中。夏二十日、春秋五十日、冬百日、乃好熟。食時下薑、酢等。
*
・「唐韻」は、唐の孫愐(そんめん)によって編纂された、「切韻」(隋の陸法言によって作られた作詩のための韻書)の補正本。]
***
《改ページ》
■和漢三才圖會 魚之用 卷ノ五十一 ○三十
しほもの
𩸆【音謁】
ヱツ
腌醃䱒【並同】○盬漬𩵋也【俗云之保毛乃】煑食之時急欲
去盬者漬冷水柹〔=柿〕澁汁少加入則盬氣速去
淡𩸆【俗云阿末之保】 盬微止經一夜者味甚佳
盬引 冬月取鮭鰡等鮮者拔去鰓及鯝滿盬於腹中裹
藁苞倒懸于檐待盬汁埀盡解之復固裹而春夏食之
*
しほもの
𩸆【音、謁。】
ヱツ
腌〔(えふ)〕・醃〔(えん)〕・䱒〔(えふ)〕【並びに同じ。】○盬漬の魚なり【俗に「之保毛乃」と云ふ。】。之れを煑食ふ時、急〔ぎ〕盬を去らんと欲せば、冷水に漬〔(ひた)〕して、柹澁〔(かきしぶ)〕の汁、少し、加へ入れば、則ち、盬氣、速(はや)く去る。
淡𩸆(あまじほ)【俗に「阿末之保」と云ふ。】 盬、微〔(わづか)〕にして、止(た)ゞ一夜を經(ふ)る者、味、甚だ、佳し。
盬引(しほびき) 冬月、鮭(さけ)・鰡(ぼら)等の鮮(あたら)しき者を取りて、鰓(えら)、及び、鯝(わた)を拔き去り、盬を、腹中に滿ち、藁苞(わらづと)に裹(つゝ)み、倒〔(さかさま)〕に檐〔(のき)〕に懸けて、盬汁、埀〔=垂〕れ盡くるを待ち、之れを解きて、復た、固く裹みて、春・夏、之れを食ふ。
[やぶちゃん注:元来、前掲の「腌」・「醃」の同義字にある「奄」は、「淹」(ひたす)の意で、「酢漬の肉」を指す字であった。それが、後に「塩漬の魚」の意となったのである。
・「柿澁」の主成分はカキタンニンで、これはタンニン( tannin )が、数多く結合した構造を持ち、強力なタンパク質凝固作用を持っている。
・「鮭」は、多くのサケ科の種を指すが、ここではズバリ、サケ目サケ科サケ属サケ Oncorhynchus keta で代表してもらってよかろう。
・「鰡」は、ボラ目ボラ科のボラ Mugil cephalus 。]
***
ひもの
鮿【音摺】
チツ
薧【音考】鯗【音想】乾魚○漢書師古注不着盬而乾魚
曰鮿禮記謂之薧凡物乾陳者皆謂之薧羅願
云諸魚薧皆爲鯗【俗云干物】
未乾魚 膊鮮魚和微盬乾之半濕者謂之未乾【奈末比】味
與淡盬魚同美
*
ひもの
鮿【音、摺〔(せふ)〕。】
チツ
薧〔(かう)〕【音、考。】・鯗〔(さう)〕・【音、想。】・乾魚○「漢書」師古が注に、『盬を着けずして、魚を乾かすを「鮿〔(てふ)〕」と曰ふ。』と。「禮記」に、『之れを「薧」と謂ふ。凡そ、物、乾(ほ)して陳(ひさ)しき者、皆、之れを「薧」と謂ふ』と。羅願が云はく、『諸魚の薧、皆、「鯗」と爲す【俗に「干物」と云ふ。】。』と。
未乾魚(なまびの〔いを〕) 鮮魚(なまいを)を膊(ひら)いて[やぶちゃん字注:ママ。]、微〔(わづか)な〕盬に和して、之れを乾し、半ば濕(し)める者、之れを「未-乾(なまび)」と謂ふ【奈末比。】。味、淡盬(あまじほ)の魚と同じく、美なり。
[やぶちゃん注:「鮿」は音「チョウ」(現代仮名遣)、「婢鮿魚」となると、タナゴ(但し、これは、中国語での意味として「廣漢和辭典」に挙げられているので、本邦固有種であるコイ目コイ科タナゴ亜科タナゴ属タナゴ Acheilognathus melanogaster とは異なる種であるので注意)であるが、一般名詞では、「塩を付けないで乾かした魚」を指す。
・『「漢書」師古が注』初唐の訓詁学者である顔師古の、「漢書」卷九十一「貨殖傳」第六十一の注に、以下のようにある。『師古曰「鮿、膊魚也、卽今不著鹽而乾者也。』。
・「羅願」は宋代の博物学者。東洋文庫版割注によると、以下の引用は、漢代の字書である「爾雅」を彼が補綴した「爾雅翼」からのもの。]
***
めさし
魥【音怯】
法魚○魥【俗云目左之】字書云以竹貫魚爲乾也
△按白魚氷魚等十頭相連爲魥
有鰷鮒之類鮮者不着盬㷶乾者雖極暑耐久
*
めざし
魥【音、怯〔(けふ)〕。】
「法魚」。○魥【俗に「目左之」と云ふ。】は、字書に云はく、『竹を以つて、魚を貫きて、乾すことを爲すなり』。と。
△按ずるに、白魚〔(しろいを)〕・氷魚(ひを)等、十頭、相〔(あひ)〕連ねて「魥」と爲す。鰷・鮒の類、鮮〔(あたら)〕しき者、盬を着けずして、㷶乾〔(びかん)せる〕者、有り。極暑と雖も、久〔(ひさ)しき〕に、耐ふ。
[やぶちゃん字注:※=「備」の(つくり)の下に(れっか)。]
[やぶちゃん注:「魥」は、音「ゴウ・キョウ・コウ」(現代仮名遣)で、「ひもの・干魚・魚を竹に刺して乾かしたもの」の意。
・「法魚」何故か知らぬが、「魚の干物」の意がある。
・「字書」は一般名詞。漢字を分類した辞典の意。
・「白魚」は、取り敢えず、キュウリウオ目シラウオ科に属するシラウオと同定しておく。詳細は前掲の「鱠殘魚」の冒頭注を参照のこと。……う~ん、しかし、あのちんまいシラウオを目刺しにするのは、ちょっと、やりたくないな。
・「氷魚」はキュウリウオ上科アユ科アユ Plecoglossus altivelis altivelis の稚魚のことを呼称する。前項同様、「鱠殘魚」、及び、その注の中で翻刻した「氷魚」を参照のこと。
・「鰷」は、取り敢えず、アユの成魚ととっておくが、「氷魚」の後に、すぐ良安がこれを掲げているのを見る限り、「鱠殘魚」の注で取上げた「氷魚」で、私が疑義を提示している不審が、またぞろ湧き上がって来る。「鰷」は良安にとって本当にアユだったのであろうか? と。大体、中型の魚類は、目刺しに出来はするが、ちょっと、今度は、大きくて、逆に目刺しにしたくはない。但し、アユは、稚魚も成魚も乾しても旨い。
・「鮒」はコイ亜科フナ属 Carassius 。]
***
さかな
肴【音爻】
ヤ゜ウ
殽【同】○禮記注云肉帶骨曰肴骨剛故肴左居
唐韻云非糓〔=穀〕而食皆謂之肴
《改ページ》
△按肴【訓左加奈】酒魚也凡吃酒時間少啖之以爲酒媒者也
與禮記注所言不當也如遇漁舟乞買魚者謂肴則甚
恚不與謂魚則與之言肴乃些少之物也漁者特重向
來之祝辭也
*
さかな
肴【音、爻〔(かう)〕。】
ヤ゜ウ
殽〔(かう)〕【同じ。】○「禮記」注に云ふ、『肉、骨を帶〔(おぶ)〕るを「肴」と曰ふ。骨、剛き故に、肴は、左に居〔(す)〕ふ。』と。「唐韻」に云はく、『糓に非ずして食ふ、皆、之れを「肴」と謂ふ。』と。
△按ずるに、肴は【「左加奈(さかな)」と訓ず。】、「酒魚(さかな)」なり。凡そ、酒を吃〔(きつ)〕する時、間(まゝ)、少し、之れを啖〔(く)〕ひて、以つて、酒の媒(なかだち)を爲す者なり。「禮記」の注に言ふ所、當らざるなり。如〔(も)〕し、漁舟に遇ひて、魚を買はんことを乞はば、「肴。」と謂へば、則ち、甚だ、恚(いか)りて、與へず。「魚。」と謂はば、則ち、之れに與ふ。言ふ心は、肴は、乃〔(すなは)〕ち、「些少の物」なり。漁者は、特に向來〔(きやうらい)〕の祝辭を重じればなり。[やぶちゃん字注:「心」は送り仮名にある。]
[やぶちゃん注:「肴」は音「コウ・ギョウ」(現代仮名遣)、「爻」は、「組み合わせる」の意で、「組み合わせた肉・ご馳走・骨付きの肉」の意。「煮たり、又は、焼いたりした獣・鳥・魚の骨付きの肉」の意が、転じて、広く、穀類以外の副食物(おかず)を言う。良安が如何にももっともらしく言う、酒を飲む時に添えて食べる料理の意は、国訓によって初めて生じたもの(但し、日本語の「さかな」という語の語源としては、正しいと思われる)。原字にはない意味であるから、良安の批評は根本的には誤りである。
・『「禮記」注』は礼記(五経の一つ。周から漢にかけての儒学者が記した儀式や儀礼に関する記述を前漢の戴聖らが編纂したとする。全四十九篇から成る)の呉曾祺による注釈書「礼記菁華録」(らいきせいかろく)の「曲禮上第一」の『凡進食之禮、左殽右胾。』の注などを指すか。そこに『肉帶骨曰殽。純肉切曰胾。骨剛故左肉柔故右。』とある。「曲禮」は五礼(吉・凶・賓・軍・嘉)について総説した章で「禮記」第一篇が、その「曲禮上」で、第二篇が「曲禮下」である。
・「唐韻」は、唐の孫愐(そんめん)によって編纂された、「切韻」(隋の陸法言によって作られた作詩のための韻書)の補正本。
・「漁者は特に向來の祝辭を重じればなり」の「向來」は「過去から現在まで」、「従来」の意。従って、「漁師と言うものは、特に古くからの縁起担ぎの言祝(ことほ)ぎを重んじ、気にするものだからである。」の意。]