
鈴木しづ子句抄――雑誌発表句・未発表句を中心にしたやぶちゃん琴線句集 ⇒縦書版へ
[やぶちゃん注:鈴木しづ子の句集『春雷』及び『指環』を中心とした抄出は、既に「やぶちゃん版鈴木しづ子句集」で二百十七句を行ったが(二〇〇五年七月公開・二〇一〇年八月改訂)、現在は川村蘭太氏の労作「しづ子 娼婦と呼ばれた俳人を追って」(新潮社二〇一一年一月刊)によって、しづ子の現存する総ての句を読むことが出来るようになった。私は鈴木しづ子の俳句の足跡を編年で拾い読みし乍ら、私なりにしづ子の句を辿ってみたい欲望に駆られた。そこで、ブログ・カテゴリに「鈴木しづ子」を創始し、『春雷』及び『指環』に含まれなかった雑誌発表句や初公開の多量の未発表句を中心として、幾つかのしづ子のエポックの句や、私の琴線に触れるものを編年形式で抄出、私の浅い読みを添えながらそれを試みた。それを一先ず終え、ここに一括HP版を公開する(ブログ版に多少の追加と訂正を加えた)。引用の底本は上記「しづ子 娼婦と呼ばれた俳人を追って」の巻末にある「鈴木しづ子 全句」を元とする。但し、「鈴木しづ子句集」の冒頭注で語った通り、私の勝手な思い込みから、漢字を概ね正字表記に変えて示すことをお断りしておく(但し、実際には底本でも正字表記が多い)。まずは何より、川村氏の「しづ子 娼婦と呼ばれた俳人を追って」という稀有の感性と洞察に貫かれたそれをお読みになることを、そしてその全句をお読みになることを、お薦めする。――あなたのしづ子は、私のしづ子ではないであろうから――【二〇一一年二月二十六日】【二〇一八年七月一日追記:本日、古書店「古書 古群洞」樣の『樹海』(第五巻二号から第六巻六号/揃十五冊/昭和二五(一九五〇)年から翌年にかけて発行)のこちらの商品見本画像で、鈴木しづ子の句の掲載部分の幾つかを拝見出来たが、そこでは漢字が総て正字化されていることが判った。私の恣意的な漢字の正字化の仕儀がまずは正しいことが立証された。ここに「古書 古群洞」様に御礼申し上げる。なお、今回、七年前に未処理であった一部の漢字を正字化した。 藪野直史】]
鈴木しづ子句抄
〇鈴木しづ子 最初期句 七句
まず、彼女の最初期の句を見たい。
* * *
秋空に校庭高くけやきの木
五年 鈴木しづ子
(『樹海』昭和十二(一九三七)年十一月号 「子供の俳句」欄)
*
秋空に赤くもえたつ夕燒雲
尋四 鈴木しづ子
(『樹海』昭和十三(一九三八)年一月号 「子供の俳句」欄)
*
雲の外靑葉若葉がそよいでいる
五年 鈴木靜子
(『樹海』昭和十三(一九三八)年六月号 「子供の俳句」欄)
[やぶちゃん注:「いる」はママ。]
以上の三句が底本の巻頭に並ぶ。これらが我々が知り得る、そして初めて我々が目にする鈴木しづ子の最も古い(若い時の)句群なのである。
彼女の生涯が謎に満ちていること、彼女が実年齢より八歳前後若い年齢として振る舞っていたのは周知の通りであるが、ここで吃驚するのは、彼女がその最初から年齢を確信犯で詐称して登場していることである。川村氏の精査により、彼女の生年は大正八(一九一九)年六月九日であることが判明している。従って実はこの最初の尋常小学校五年と自らクレジットした句はしづ子十八歳の、後の二句は二十歳の折りの投句なのである。まず、そこに彼女の奇妙な現実世界への仮象の「投企」を私は強く感じるのである。敢えて言うなら、最初の句の「五年」は――嘘――ではない。しかし、それは尋常小学校「五年」ではなく、私立淑徳高等女学校「五年」という意味でならば、である。ここに「子供」の詐称への後ろめたさの含羞を読もうとすれば、読めないことはない、としづ子を弁護しておこう。
その句柄は一見、如何にも衒いのない素直な、いや、俳句を捻ったことのあるものなら、子供らしいと微苦笑、謂わば一笑に附すもののようにも見える。しかし、どうであろう、私には、ここに既にしづ子の、後年に冴え切ってゆく「視線」のこだわりが強く感じられるのである。
同一俳誌八ヶ月の間に、彼女は一貫した対象と空(虚空)との明確なパースペクティヴのモチーフにこだわった、この三句を示し続けているという点に於いて、である。考えても見るがいい、これが素人なら、毎回、新規な対象に色気を移して、さまざまにつまみ食いするように詠むのが常であろう。中学の頃に俳句にかぶれた私も、やはりそうだったことを告白する。そうして、乏しい詩力をずらしては誤魔化そうとするのが普通なのだ。私は、ここ「子供の俳句」欄に、敢えてこうした連作とも思える、当時のしづ子の、「実感」「実視」にこだわった感覚の表現体を、自信をもって投げ入れる――そんな風なしづ子を見る思いがするのである。
*
ゆかた着てならびゆく背の母をこゆ
靑芒の一つ折れしがふかれてゐる
(『樹海』昭和十八(一九四三)年)
しづ子が愛した母への心的複合(コンプレクス)は非常に複雑である。それは川村氏の著作に譲るが、何よりここでしづ子は、一気に当時の実年齢二十四歳になって詠んでいることに着目したい。
先の句を詠んだ「十歳の少女」が、五年で十四も成長するのだ。
色っぽい浴衣を着て、母の背を越えた女は、もはや艶麗な大人の「女」のそれである。十五や十六出はあり得ない。
それはあたかもロバート・ネイサンの「ジェニーの肖像」のようではないか。
そして二句目では、まるで尾崎放哉の句のような、早過ぎる諦観の老いた眼つきの印象さえ、私には感じられる。その「折れた靑芒」の揺れる彼方には、戦争のおどろおどろしい黒雲さえ見え隠れするではないか。
*
春雷はいつかやみたり夜著に更ふ
木下闇蜘蛛しろがねの糸ふけり
(「石楠」昭和十九(一九四四)年)
この二句のシーンにいるのも、もう、間違いなく妖艶な大人の女である。大人であることを知ってしまった女の意識が横溢している。十代後半の少女の句ではあり得ない。彼女には『樹海』への登場の初期に於いては、意図的な年令詐称の意志はなかったと思っている。
この前後から戦後の昭和二十一(一九四六)年一月迄の「石楠」に投句掲載された残りの十句は、その総てが第一句集『春雷』に採録されている。私は、この二句を自選から外したしづ子の俳句への「覚悟」と「真摯」さに胸打たれる思いがする。「春雷」の句は恐らく、句集の題である「春雷」とのバランスの中で深考の末に削ったものと思われるが、後者は私なら残す。「春雷」の中にあったなら、間違いなく私は琴線句として選ぶ。それを削った彼女の「精進」を、私は思うのである。
以上の七句と、そして句集『春雷』を合わせたものが、現在知られるしづ子の、『春雷』以前の全句作ということになる。
◯鈴木しづ子 二十七歳 昭和二十一(一九四六)年から 九句
敗戦――恋人の戦死の報――しづ子の戦後が始まる。
昭和二十一(一九四六)年の発表句は句集『春雷』を除くと、総数二十一句に過ぎない。尚且つ、その中には『春雷』に採録されたダブりが五句含まれるので、それを除くと十六句となる。続く昭和二十二(一九四七)年からは第二句集『指環』へ採録されたものが出現し始めるが、何故か、彼女は昭和二十一年の作品を『指環』に一句も採録していない。以上の十六句から七句を選んだ。
*
旅ごころさそふふみをばさみだれに
(「現代俳句」昭和二十一(一九四六)年九月号)
「現代俳句」は石田波郷が編集に当たった画期的な綜合雑誌で、これはその創刊号でもある。しづ子のメジャー・デヴュー五句の内の一句。――エトランジェが手紙をなめて背後の五月雨へとフォーカス・インする。――波郷は当時三十三歳、翌年十一月には現代俳句協会を創立するなど、戦後の俳壇の再建に精力的に活動していが、また丁度この頃、宿痾となった肺結核に既に罹患していたものと思われる。
*
梅林によするこころや昃る帶
(『樹海』昭和二十一(一九四九)年九月号)
「昃る」は「かげる」と読む。――梅林――高速度撮影でパン――ティルト・ダウン――手前に和服の女の後姿がイン、その帯で止まる――初春の淡い夕陽が帯に影を作り――背後の梅林が静かに暮れなずむ……。
*
このてぶりうれしくひひな飾りけり
(『樹海』昭和二十一(一九四九)年九月号)
ここでもアップの雛人形の手振りから、それを愛おしく手に取って雛壇に飾る女の手へとズーム・アウトしてゆく、彼女独特の遠近法が美しい。
*
よるの萩おもひそめたることども書く
(『樹海』昭和二十一(一九四九)年十二月号)
「一つ家に遊女も寝たり萩と月」の確信犯インスパイア。これはしづ子の実景であると同時に、市振の宿の芭蕉の部屋の、その襖を隔てた隣室の、遊女の思いへのタイム・スリップでもある。
*
秋葵みづをこえたる少女の脚
(『樹海』昭和二十一(一九四九)年十二月号)
「秋葵」は双子葉植物綱アオイ目アオイ科トロロアオイ属オクラ。勿論、ここでは「あきあおい」と読んでいる。周年開花するが、初夏から初秋までが頻繁な開花時期で、季語も夏。五~七センチの黄色若しくはクリーム色で中央が赤い花をつける。通常のオクラの開花は夜から早朝の夜間で、昼頃には凋んでしまう。花の印象は可憐な少女に合わすにすこぶる相応しい。これは静止した水溜りか。映像は総てその水面の映像である。――秋葵の花――水面、揺れて――飛び越える少女の脚――水面、揺れて……
*
鳳仙花なみだぐみたるふたつの眸
(『樹海』昭和二十一(一九四九)年十二月号)
鳳仙花の接写から涙を溜めた女の双眸の組写真である。しづ子が写真や映画を撮っていたら、きっと素晴らしい映像を残してくれていたろうにと、彼女の句を読むにつけ思う……。
*
蜻蛉の高ゆくひとつ廠をこゆ
(『樹海』昭和二十一(一九四九)年十二月号)
「蜻蛉」は私としては「せいれい」ではなく「とんぼう」と読みたい。「廠」は恐らく「工廠」で、旧陸海軍に所属し、その兵器・弾薬等を製造修理した軍需工場、所謂、砲兵工廠と思われる。これもしづ子のパースペクティヴの妙味が感じられる佳句である。
*
ぬれあがる葉あかり引くや夕夜
秋さだか兩の睫毛はしとりけり
(「小徑」昭和二十一(一九四九)年七・八・九・十・十一・十二月合併号)
一句目の「夕夜」は「ゆふべよる」と読ませるか。見かけない語であるが、夕暮から夜への時間的経過を表現するものととれば違和感を私は感じない。句柄も静謐で悪くない。二句目もいい。「しとりけり」は「湿とりけり」の謂い。――実はこの二句は底本である「全句」には所収されていない。私は本選句を行うに当たって、まず底本とした「全句」を編年で順に鑑賞・抄出し、その後に本文「しづ子 娼婦と呼ばれた俳人を追って」の当該年に当たるパートを読むようにした。これは川村氏の鑑賞に私の選句が左右されないようにするためである。私は飽くまで私の感性と解釈で詠み進めたいと思ったからである。ところが、そうやって読み進めたところ、本文でこの句にぶつかった。川村氏が何故、この二句を「全句」に入れなかったのかは分からないが、氏の叙述によれば、これは確かに彼女の句である。川村氏がこれを発見した経緯と、驚きのしづ子の「若菜集」ばりの定型恋愛詩、その男性名で書かれた詩がしづ子の作品であることを明かした氏の卓抜な推理は、同書百三十八ページ以降の『幻の詩句集「小径」』をお読み頂きたい。
◯鈴木しづ子 昭和二十二(一九四七)年から 六句
昭和二十二(一九四七)年の発表句は総数五十句、そのうち句集『指環』に採録されたものが十一句(一句、改作されているものがあるが、それは別な句ととって数えてなかった。最初に掲げたのがその句である)含まれるので、それを除くと三十九句となる。以上から句を選んだ。
*
あをむ月吻ふれしむる玻璃のはだ
(『樹海』昭和二十二(一九四七)年一月号)
「吻」は「くち」。本句は『指環』に、
月蒼む吻ふれしむる玻璃のはだ
の句形で載るが、私は表記やリズムも含めた詩想に於いて動態で畳み掛ける後者よりも、この初期形の方を、愛するものである。
*
日ざしきし非をさとさるる秋の壁
(『樹海』昭和二十二(一九四七)年二・三月号)
私はこの句に不思議なもの――禅機とでも言うべきものを感ずる。「非」の哲学的瞑想と言ってもよい。少なくとも私にはここに具体な情景や写生の解説を浮かべて矮小化する解釈は埒外なのである。
*
眉ひくや秋蛾はばたく鏡の面
(「黒檜」昭和二十二(一九四七)年五月号)
「面」は「おも」か「も」か。しづ子の用字としては「おも」か。シュールレアリスム風のワン・ショット。「鵙」という標題での五句の巻頭句。標題はその中の「鵙高音花壺の水すてるとき」に由来するが、この「眉ひくや」句の鮮烈さに、続く他の句はかすんでしまう。
*
冬雁のむらだちゆくや過去は過去
(「俳句研究」昭和二十二(一九四七)年五月号)
「紺リボン」という標題での五句の巻頭句。これもメジャー誌をターゲットとした、下五で斬新に突き放す野心的な作である。ただ、やや巧んだ後味が残る。好きな句だが、しづ子が『指環』に採らなかった気持ちは分かる気がする。この頃の『俳句研究』は恐らく改造社社員であった山本健吉の編集になるものであろう。
*
背信や寒をはなやぐちまたの燈
(「俳句研究」昭和二十二(一九四七)年五月号)
同じく「紺リボン」標題の二句目。こちらは前句とは逆に、上五で中七下五の風景を扇情的に浸潤させる効果を狙った。やはりやや狙う意図が見えてしまう句である。しかし、韻律が流麗で私好みである。
*
アマリリス娼婦に似たる氣のうごき
(「俳句研究」昭和二十二(一九四七)年八月号)
標題「春嵐」十句の第四句。これは別段、うまい句ではない。ではないが、しづ子にとってエポック・メーキングな句であるように思われる。この「氣」は作者しづ子自身に確信犯的に投影されているからである。しづ子には、句集『指環』所収の、
娼婦またよきか熟れたる柿
という有名な句があるが、それに遥かに先行する、伏線の如き句として私には映るからである。この知られた句は初出が昭和二十五(一九五〇)年四月号『俳句研究』で、実は句形が『指環』とは微妙に異なっている。以下に掲げる。
娼婦またよきかな熟れし柿食うぶ
本句は実に、これより凡そ三年前の句であり、『春雷』と『指環』という大きな変身をする、その狭間にある本句は、やはり銘記されるべき句であろう。因みに、この「氣」は底本が正字なのである。更に言えば、実はここに掲載された十句全部が正字表記なのである。これは私が恣意的にしづ子の句を正字化していることへの、一つの正当性を証するものとして掲げたい。一首の変化を狙ったものとも思われるけれども、そうした意識の切り替えをスムースに出来るのは、彼女の原意識に正字の感覚が定着しているからにほかないらないのである。標題は、最後の第十句目、
春嵐饐えし男體われに觸る
である。「男體」は「だんたい」と音読みさせるか。面白いが、無理のある句である。この時期、しづ子は「愛憎」「敵意」「本能」「節操」といった哲学的概念語や尋常性を失った語彙衝突の語句を挿入することで詩想を変革出来ると安易に思っていた感を私は受けるのである。但し、それは概念ではなく、切実な現実であったのかもしれないのだが……
……しづさん、私は誤っていなかったね……
鈴木しづ子の現存する最後の自筆句稿に当たるのは昭和二十七(一九三二)年九月十五日附、その前が同年九月九日附のものである。その表記を見ると、後者では「団扇」を「團扇」、「売らじ」を「賣らじ」、「鶏頭」を「雞頭」、「点ずる」を「點ずる」、「油蝉」を「油蟬」、「醤油」を「醬油」、「灯」を「燈」、「美観」を「美觀」、「虫」を「蟲」と表記している。最終稿でも「虫」を「蟲」、「昼」を「晝」、「台風」を「颱風」(しづ子の好んで用いた語でこの表記は以前から一貫している)、「数」を「數」、「蝉」を「蟬」、「躯」を「軀」、「団扇」を「團扇」(但し、一句のみで他の五句では「団扇」とする)と表記している。これらからしづ子の詩想にあっては、昭和二十七(一九三二)年の時点にあってさえ圧倒的に正字のイメージが優位性を保持して奔流していたことが立証されると言ってよい。
……しづさん、私が貴女の選句集を、そして、ここでの選句をすべて正字化していること、許して頂けますね……
◯鈴木しづ子 二十九歳 昭和二十三(一九四八)年から 二十四句
昭和二十三(一九四八)年の発表句は総数九十三句、そのうち句集『指環』に採録されたものが三十九句に及び、それを除くと五十三句となる。この年は『「しづ子」伝説元年』であると言える。
*
婚約
婚約や白萩の花咲きつゞき
月光の濱に足跡つけずゆく
秋薔薇署名おこなふ布の端し
秋燈悲し愛情の片鱗さへみえず
秋蛾堕つ初戀の男慕はしからず
(『樹海』昭和二十三(一九四八)年一月号)
表記はすべてママ(「燈」「戀」)。川村蘭太「しづ子 娼婦と呼ばれた俳人を追って」の巻末略年譜によれば、しづ子はこの年の十二月に当時彼女が勤務していた東芝車輛の「関」姓の同僚男性と結納を交わしているが、早くも翌年にはこの男との結婚生活を解消、とある。しかし、この「婚約」を標題とする五句連作の「婚約」相手は「関」なる人物であるとは思われない。この「婚約」とは後掲する「雪崩」句群の冒頭の「この夜ひそかに結婚す」という謂いと同じく、愛する男に身を捧げたことを意味していよう。問題なのは、その愛情が早回しの映画のように、たった五句の中で急激な右肩下がりを示すということである。これらは前年の秋の一連の出来事と考えてよいようだが、不思議な転落の詩集ではないか。川村氏の探求によって、このしづ子の愛した人物は、池田政夫という『樹海』同人、しづ子より五歳年下の東京商科大学(現一橋大学)学生であったことが分かっている。
*
欲るこころ手袋の指黑に觸るる
(『樹海』昭和二十三(一九四八)年三月号)
「黒」は「黑」としたが、「觸」はママ。かのスキャンダルを産んだ句は、その登場からして不幸であった。表記の通り、とんでもない誤植で始まった。勿論、これは
欲るこころ手袋の指器に觸るる
であるが、川村氏によれば、その正誤表示さえなされずに、突如、翌四月号『樹海』誌上で、主宰にして彼女の師である松村巨湫の選評の中で、誤植を言わずに「器に觸るる」として評されることとなる。『樹海』の主要同人の中では早期にその誤植が認知されていたもののようではあるが、一瞥の「黑」は強烈である。それが「器」と訂されたとしても、見てしまった人々にとって、その「器」はまがまがしい「黑い器」なのであった。私はこの句について語ることを欲しない。いまわしいまでのこの句への波状的な誤解の洪水が、俳人鈴木しづ子の運命を否応なく数奇に向けて変質させてしまった。それは全く以て彼女の責任ではない。――後のしづ子がその張られたレッテルを、逆に強力な武器として使用したことは、完全な正当行為であり、それを本末転倒に指弾したり、阿呆臭い道徳的な説教でもって批判するなどということは許されないのだ。――涎を垂らした自称俳人ニンフォマニアどもの、見当違いの恣意的な曲解誤読の堆積の山が総ての元凶である。それは私には、京大俳句事件で特高がやった、とんでもなく滑稽なイデオロギー的牽強付会誤釈なんぞより、遥かに致命的で罪深いものであったとさえ言えると考えている。
*
對決
ダンサーになろか凍夜の驛間步く
霙るる槇最後のおもひ逢ひにゆく
春近し親しくなりて名を呼び合ふ
春火桶甘へし聲に吾がおどろく
對決やじんじん昇る器の蒸氣
(『樹海』昭和二十三(一九四八)年四月号)
本「對決」句群全五句の内、「ダンサーになろか」「霙るる槇」「對決や」は『指環』に所収されるが、これは五枚の組み映像、急緩急、薬缶がじんじんと蒸気を噴き上げる「對決」のカタストロフへ至る一つのストーリーを形成していると言ってよい。これは五句セットで読まれるべきものである。初句がしづ子の著名句として知られるが、私は最終句がいっとう好きだ。「器」の用字は先の邪読スカベンジャーどもへ投げ与えた、しづ子の軽蔑に満ちた一擲の腐肉である。
*
雪崩
山の殘雪この夜ひそかに結婚す
雪崩るるとくちづけのまなこしづかに閉づ
山はひそかに雪ふらせゐる懺悔かな
春雪の不貞の面て擲ち給へ
けんらんと燈しみだるる泪冷ゆ
(『樹海』昭和二十三(一九四八)年五月号)
これは全体が、日野草城が昭和九(一九三四)年の『俳句研究』に発表した、自身の新婚初夜の連作「ミヤコホテル」をインスパイアしたものであるが、雪山のロケーションが音を吸収し、静謐にして遥かに広がる純白の山小屋の窓外景、室内の映像はタルコフスキイの「鏡」のように素晴らしい。これも最後の三句が『指環』に採られているが、これもやはり五句セットで初めて真の心情が伝わる組句である。時期的に見ても前年冬か初春、愛人池田政夫との体験に基づくものであろう。しづ子がこの冒頭二句を『指環』から外したのは、『指環』刊行時には、既にこの時のリアルな映像を出来ることなら忘れたいと感じていたから、かも知れない。
*
好きなものは玻璃薔薇雨驛指春雷
(『樹海』昭和二十三(一九四八)年六月号)
標題「好きなものは」の五句の掉尾。「驛」はママ。しづ子の句としては最も人口に膾炙しているものの一つ。尾崎放哉の「咳をしても一人」と同じで、後にも先にもやった者ののみが正当な唯一の「作家」であり、唯一の「作品」で有り続ける見本である。玻璃――薔薇――雨――驛――指――春雷――その個別な象徴関係を精神分析することも、有機的綜合解釈をすることも――総てはしづ子から皮肉な笑みを返されるだけである。なお、この号にはもう一つ「道程」という十句句群があるが、この句群は「懷疑」「戀の淸算」「戀夫」「浮氣男」「死の肯定」「肉感」「情痴」といった伝統的俳句用語から大胆に外れた語句を意識的に散りばめた野心作乍ら、十句全部を総覧すると明白な作為が見え透いてしまい、その結果、一句の重みが不可避的に著しく減じられ、いずれにも等価な瑕疵が感じられてしまう(逆に言えばそれぞれを単独で鑑賞した際には違った印象を与えるかも知れないということではある)。
*
ほろろ山吹婚約者を持ちながらひとを愛してしまつた
(『樹海』昭和二十三(一九四八)年七月号)
この号の発表句は「意識」という標題の十一句であるが、内、八句を『指環』に採っている。採られなかった一句がこれで、しづ子にしては珍しい自由律であるから当然の落選である。直前が、
であるが、それでも初句字余りの範囲内であり、現代のどこぞの若手女流俳人の句の中に置いてもしっくりして、六十年以上も前の句であると気づく人は恐らく少ないであろう。それに反して本句は句群にあって形式も詩想も極端に外れている。しかし、だからこそここで採りたくもなるのである。私はもともと自由律から俳句に入ったから、こうした句形に全く抵抗感がないのである。
*
薔薇の夜や深く剪りたる指の爪
(『樹海』昭和二十三(一九四八)年七月号)
前句と同じく『指環』に採られなかった、もう一句なのであるが、これをしづ子が採らなかったことが意外である。私にはこれは如何にもしづ子らしい句であり、如何にも『指環』の世界に相応しい句であると思うのだが。……いや、余りにも隙がないほどにぴったりし過ぎた、あたかも予定調和のようなものを感じさせるところこそが、しづ子の癇に障ったのかも、知れないな……
*
まぐはひのしづかなるあめ居とりまく
(『樹海』昭和二十三(一九四八)年八月号)
遂に確信犯の、勝手に造られた「しづ子」像を逆手にした、しづ子の俳壇への復讐が始まる。総表題は「過程」で十句。『指環』に採録。しかし、何と美しい句であろう。そもそも「まぐはふ」という古語自体、愛する者同士が「目交はふ」で、目を見つめ合うことを語源とする。単漢字の「居」が――あたかもイサナキとイサナミが廻った「天の御柱」のように句を求心的に「とりまく」――そしてしづ子は男と「しづかなる」「目交はひ」の中にいる――遠心的な外延の「あめ」がその世界を通奏低音で静かに「とりまく」――この句、いや、この歌――私にとっては永遠に神聖で美しい――
*
裸か身や股の血脈あをく引き
(『樹海』昭和二十三(一九四八)年八月号)
前句と同じ「過程」の一句。『指環』に採録。誘惑的な確信犯にも見えるが(「引き」という能動態がそれを更に刺激する)、私には、エロス以前に、大腿部内股のクロース・アップと浮いた真っ蒼な静脈の、マッド・サイエンティストの手術のような(と言ってしまえば実はサディズムのエロスのシンボルとなってしまうのだが)慄っとする青ざめたモノクロームの美を見る。――しづ子版「アンダルシアの犬」――主演もしづ子自身――なお、「過程」句群の他の句は(底本を読んで頂きたいが)、
山吹散る二度目の女ではわたしは厭だ
という直情径行以外は比較的抑制された句柄であって、この二句から敷衍想像されるような強烈なものではないことを附言しておく。
*
花柘榴左肋膜病にけり
(『樹海』昭和二十三(一九四八)年九月号)
しづ子に肺結核の兆候があった可能性を示唆する一句である。あくまで可能性に過ぎない。肋膜炎は結核性が最も多いが、非結核性の菌やウィルスによるものもあるからである。
*
風鈴や果してわれは父の子か
(『樹海』昭和二十三(一九四八)年十一月号)
しづ子が深く思慕した母綾子は昭和二十一(一九四九)年五月十五日に亡くなっているが、この句は、さんざん綾子を苦しめた父俊雄が正にこの昭和二十三(一九四八)年十一月に、母綾子の生前から関係があった女性と再婚することへの、強烈な抵抗感に基づく呪詛の句である。
◯鈴木しづ子 三十歳 昭和二十四(一九四九)年から 三句
この年は、『樹海』一月号に二句、三月号に十一句が掲載されたのみで計十三句。四月号以降はしづ子は完全に沈黙を守る。関某との結婚生活がどこで切れたかは不明であるが、私はこの年の春頃と推測している(なお、川村氏の精査によって戸籍に変更がなく、これは事実婚であったことが分かっている)。この年の末頃か、しづ子は住み慣れた東京から岐阜(まずは岐阜在の叔母を頼った)へと転居している。
*
關といふ姓の感じや寒櫻
林檎剝くややにそだつる妻ごころ
(『樹海』昭和二十四(一九四九)年一月号)
二句目は新妻の句として微笑ましいが、一句目は妙に改まった余所行きの「寒櫻」が、全体にややクールな印象を残し、私には既にしてある影を感じさせる。
*
はこぶ箸のこる悔恨かすかにも
(『樹海』昭和二十四(一九四九)年二月号)
冒頭に記した通り、「かすか」に「のこる」だけだったはずの「悔恨」は増殖して膨れ上がり、この結婚生活はあっという間に瓦解する。
◯鈴木しづ子 三十一歳 昭和二十五(一九五〇)年から 二十二句
しづ子の実像に眩しいハレーションがかかり始める。「しづ子」伝説の第二期ともいうべき世界が起動し始める。俳句も再起動し、年間の発表句は全五十九句、その内、『指環』に採録されたものは二十二句である。
*
花吹雪岐阜へ來て棲むからだかな
黑人と踊る手さきやさくら散る
(『樹海』昭和二十五(一九五〇)年二月号)
『指環』採録句。「最後の審判」のように黒人の黒い手としづ子の白い手――早いターンの二人きりの尽きるともないダンス――そこに歌舞伎の舞台の如き沢山の桜吹雪――芝居がかっていながら、強烈なリアリズムと若い律動がある名句である。標題「流転」四句の冒頭二句。
*
指環
冬の夜の指環の指や妻たりし
左中指かたみの指環凍てにけり
玉三つならべ指環の凍てにけり
手袋の指に指環を愛でにけり
をんな持ちならざる指環指凍ゆ
凍つる夜の吻ふれしむる指環かな
過去の冬あたへられたる指環かな
指環凍つみづから破る戀の果
(『樹海』昭和二十五(一九五〇)年二月号)
これは彼女の第二句集の題名『指環』と同じ標題でありながら、実は最終句のみが『指環』に採られたのみである。時系列から言うとこの指環を送った人物は、短い結婚生活であった関某かと私は当初思ったのだが、その場合、二句目の「かたみの指環」で躓く。「みづから破る戀の果」からは先に示した関に先行する愛人池田政夫かとも思われるが、やはり「かたみ」がそぐわない。この指環に対する強いフェティシズムには、えも言われるぬしづ子の執念が感じられる。これについて、川村氏は「しづ子 娼婦と呼ばれた俳人を追って」の中で、実はしづ子には向島の工場で製図工として働いていた昭和十四(一九三九)年二十歳の頃、二人で秘かに契った婚約者がいたが、彼は戦死した事実を明らかにし(氏名や戦死の時期等は不詳。競馬の騎手であったとも言う)、『しづ子が真に愛した相手は、戦死した婚約者であった気がする』とされ、またこの「をんな持ちならざる」振りの大きい男物の指環の元の持ち主として『最も自然なのは、戦死した婚約者ということになろう』と記しておられる。私も、この句群の句柄をほぼ総て説明し得るものは、その戦死した婚約者しかいないと思う。そうしてそう腑に落ちた時、これらの句群はいやさらに輝きを増すと言ってよい。
*
寒の夜の流離の指環愛でにけり
遊び女としてのたつきや黃水仙
(『樹海』昭和二十五(一九五〇)年三・四月号)
標題「黃水仙」の四句の最後の二句。後者が第二期の伝説「娼婦しづ子」を初めて読者の鼻先に突きつけた問題の句である。最終兵器「しづ子」が起動した。
賣春や鷄卵にある掌の溫み
菊白し得たる代償ふところに
娼婦またよきかな熟れし柿食うぶ
(「俳句研究」昭和二十五(一九五〇)年四月号)
先にも記した通り、『指環』所収は、
娼婦またよきか熟れたる柿
で、句形が微妙に異なっている。
しづ子は、前月に続き、メジャー誌も用いてスキャンダラスな都市伝説(アーバン・レジェンド)を世間に播種し感染させる。意味深な標題――「代償」――その全六句の掉尾に「娼婦またよきかな」――この新鋭の、裏切られた俳壇に強迫的な脅威を与えるために秘かに製造された――娼婦型最終兵器「しづ子」は――満を持して岐阜にて配備されたのである――
*
霙けり人より貰ふ錢の額
(『樹海』昭和二十五(一九五〇)年五月号)
ここまで来ると、もはや娼婦句ではなく、路通や乞食井月の風情に古化してくる。前掲句と合わせても4句のみ、「しづ子」娼婦伝説の証左は(それらしい素振り仄めかしや仕草の匂わせの確信犯の句は確かに多くあるが)たったこの程度なのだ。恐らく増殖した妄想の中で、しづ子の句は体よく「娼婦句」として奇形的解釈が行われ、今もいまわしい「伝説」の再生産が行われているのだと私は思う(ただそれをやはりしづ子はほくそ笑んで黙って蔑視ばかりなのであるが)。私がこの四句をお示ししたのは、ある意味、それにケリをつける時がきたということを感じているからである。――あなたが更に、あなたのしづ子を傷つけない、ためにである――
*
斯くまでの氣持の老けやたんぽぽ黃
春盡や全裸のかひな輕く曲げる
情慾や亂雲とみにかたち變へ
身の變轉あかつきを降る春霞
(『樹海』昭和二十五(一九五〇)年六月号)
彼女の印象的な下五「たんぽぽ黃」の四句連作の後に掲げた三句が続いた全七句群。私は『指環』に採らなかった「春盡や」の句が不思議に健康で美しく高い位置に感じられ、次いで「情慾や」から「身の變轉」でもて余し、持ち崩した身体へと映像が変質、最後に、いや、身はまだしも「斯くまでの氣持の老け」をとこそ初めて実感する、しづ子の哀しい姿体が見えるのである。底本によれば、この号でしづ子の具体的な住所が誌面に公開されている。但し、これは必ずしもしづ子の自律的な意志によるものではないであろう。編集上の同人情報記載であった可能性の方が私には高いように思われる。彼女は自身の住所は知られたくなかったはずだと思う。
*
句作七年十指の爪の小さきこと
(『樹海』昭和二十五(一九五〇)年八月号)
演じられた「子供の俳句」三句の先行を除けば、しづ子の『樹海』初投句は、先に示した『樹海』昭和十八(一九四三)年十月号の、
ゆかた着てならびゆく背の母をこゆ
で、七年前になる。
*
明星に思ひ返せどまがふなし
(『樹海』昭和二十五(一九五〇)年十一月号)
標題「まがふなし」で五句。川村氏は「しづ子 娼婦と呼ばれた俳人を追って」の本文で、この号に松村巨湫は「しづ子のこと」という一文を寄せているが、この長文の評は、実はしづ子自身からの依頼で書いたものであることを後に巨湫自身が明らかにしているとし、そこで『師のこのしづ子評は難解であると共にかなり不思議な文章で』『そこに謎が潜んでいる気がしてならない』と記されている。二〇〇九年八月河出書房新社刊の「KAWADE道の手帖」の「鈴木しづ子」に所収するそれを再読してみた。これはしづ子評としては飛び切りオリジナルなもので、しづ子を語る上では避けて通れない必須評論なのであるが、しかし違った意味で飛び切り難解にして異常な文章なのである。――「〇〇性」「〇〇的」「〇〇化」の連発――傍点の乱打――俳句詩想を示すための哲学的で難解、というより、奇怪奇景な印象を与える「語維」「靭性」「撓性」「抒懐」「抒懐度」「象性」「嚮向的規制論理」といった造語らしきものもふんだんに含まれる尋常ならざる語群――またそこで開陳される彼の俳句詩想の一部は、すぐ後の文で無化されたり、訂正されたり、その外延を野放図に広げたりしていて、これがまた如何にも読みにくい印象を強めているのである。そして――ここに奇妙な性的表現に続く、やや意味不明な文脈が二箇所、出現する。一つは本句を評釈した部分に現れる。
『「まがふなし」はその思慕――かれ自身にも気づかれないリビドー――の存在を無意識のうちにも摑みえたよろこびであり、そこから未来に向かって世界をひらきゆかんとする決意である。』
(「決意」に傍点。「かれ」とはしづ子のことである。巨湫はしづ子を語る際に「かれ」と表現する。これにも私は奇妙なこだわりを感じる)で、今一つは、しづ子の「すべて夜おそき飯はむ秋簾」の句を激賞する中で(残念ながら私は別段この句をよいとは思わない)、古来の風雅理念である「寂び」を批判する文脈に現れる、
『ひとによって生み出され、にじみ出て来たものを、後とからしきりと反芻しているのが能楽だ。世にもかけがえのない愛人のそれでないかぎり、分泌物質を嗜尚することに私は堪えがたい。』
(「反芻」「能楽」に傍点)という叙述である。「性」に関わる表現はしづ子を評するに避けられないから、私はそれを以て「奇妙な性的表現」と言っている、のではない。
掲げた前者は一見、特に変ではないように見えるかもしれないが、よく読むと如何にもおかしいのだ。『かれ自身にも気づかれないリビドー』という受身・可能否定形の使用の意味の不鮮明さ。更に、そもそもが無意識下の性衝動の核部分を言うリビドーは、自身に気づくことは出来ないからリビドーなのである。従って、そ『の存在を無意識のうちにも摑みえたよろこび』とい謂いは精神分析学的には矛盾した言説(ディスクール)なのである。それどころか、それが一気に『そこから未来に向かって世界をひらきゆかんとする決意』にダイレクトに繋がるというのは文学的な措辞としては恰好いいけれども、何を言わんとしているのかが実は全く伝わってこない、やはり「変な意味」で「性」的な解釈なのだ(言っておくが実は私は、この「明星に思ひ返せどまがふなし」の句をも私の琴線句としては、採らない。巨湫の言うような、ある強靭な強さをこの句に私も感じはするが、しかし「私の琴線」には触れてこないのである。それだけは断っておく。ただしづ子自身がこの句にこだわった事実に於いてこの句はしづ子のエポック・メーキングの句であることは確かであり、そのようなものとしてこの難解な象徴句は今後も議論されねばならない)。――私はこの巨湫の奇妙なもの謂いには、まさに巨湫の援用しているフロイトの「言い間違え」理論によって解釈し得るのではあるまいかという予感がしている。巨湫は、しづ子との間にある、ある性的な秘密を隠している――しかしそれは巨湫のリビドーに直結しているが故に、こうした言い間違いとして不思議な影をその評釈に投射してしまったのだ――という私の野狐分析である。今は残念ながら詳細なその分析を立証する資料もなく、している暇もないので、これ以上は語らないこととする。しかし、私のその一見、性的な牽強付会とも批評されそうな解釈は、後者の巨湫の叙述に至って、解釈可能性の有意な高まりを感じさせはしないだろうか? この文章を「変」に感じない人は、最早、いないであろう。だって俳句の「寂び」を語る中で、
『世にもかけがえのない愛人の』『分泌物質』であるなら、それが汗であり、経血であり、精液であったとしてもそれを私は慈雨のように『嗜尚する』であろう
と巨湫は言い放っているのである。――これは確かに川村氏の言を俟つまでもなく、異様で奇怪な『かなり不思議な文章で』『そこに謎が潜んでいる気が』、確かにしてくるのである。
◯鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十六(一九五一)年一月から六月の発表句から 七句
本記載を一月から六月に区切ったのは、この六月より、しづ子には多量の未発表句稿が存在するからである。一応、時系列を意識してしづ子の句を見たいと思っているので、ここに区切りを作った。
*
月の夜の蹴られて水に沈む石
(『樹海』昭和二十六(一九五一)年一月号)
しづ子得意のパースペクティヴと水面の波紋が孤独に美しい詠唱である。
*
戰況や白き花在る枯れの中
(「俳句往来」昭和二十六(一九五一)年二月号)
「戰況」とは朝鮮戦争を指す。本句の作句時期は投稿から考えて二か月程前に遡ると考えられるが、前年一九五〇年十月には中国軍が参戦して戦況は泥沼化、十一月、国連軍は十月に進攻制圧した平壌を放棄して三十八度線近くまで潰走を始め、中朝軍は十二月五日に平壌を奪回、この年の一月四日にはソウルを再度奪回している。川村氏の年譜によればこの前年十月頃には恋人となったGI(米軍軍人の俗称で《government
issue》(官給品)の略。潤沢な官給品を支給されたことによるとされる)と同棲を始めており、彼はこの五月に朝鮮に出兵しているから、しづ子にとってその「戰況」は切実であった。なお、この『俳句往来』の前号(一月号)にはしづ子をモデルにした柳澤湫二なる人物(『樹海』同人。本名不詳)の小説「なめくじ」が掲載されている。私は未見であるが「しづ子 娼婦と呼ばれた俳人を追って」の二百九十一~二百九十二ページに、川村氏によって驚天動地のその内容が要約されている。要約でも扇情的で妙に粘着質の印象を持った何だか厭な通俗作品であることを感じさせるが、先に川村氏が指摘し、私も仮定した巨湫としづ子との秘かな関係をも匂わせる内容ではある。
*
星凍てたり東京に棲む理由なし
山沿ひに小雪來るらあし此の縣のみ
曲りきて伊吹颪を流るるなり
花椿いまだに拔けぬ妻の癖
(『樹海』昭和二十六(一九五一)年三月号)
二年前の東京から岐阜への移住、ダンサーを生業としながら以後、同県内を転々とするに至ったしづ子の流転走馬灯のような十句から。――「曲りきて」「流るる」のはしづ子自身であることが、如何にも荒涼として哀しい。
*
雪は紙片の如く白めりヒロポン缺く
(『樹海』昭和二十六(一九五一)年五月号)
これはしづ子のヤクではなく、恐らく恋人のGIのものではあるまいか。当時の読者はしかし、しづ子の「転落の詩集」をここで確信したに違いない。いや、それもしづ子の確信犯でもあろう――。
*
花散り初むきのふ曉け方みたる夢
(『樹海』昭和二十六(一九五一)年六月号)
……しづさん……あなたの見たその夢……そっと聴かせて下さい……
◯鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十六(一九五一)年六月八日附句稿百句から 十九句
――最初に、これらの手書き句稿を一字一字丹念に読み解き、我々に与えてくれた川村蘭太氏の労苦に心から謝意を表するものである。――
それにしても詠み溜めたものではあるが、一日の便で百句は強烈である。
而してそのうち、『指環』に採られた句は「風鈴や枕に伏してしくしく涕く」「ひまわりを植ゑて娼家の散在す」「夏草と溝の流れと娼婦の宿」のたった三句に過ぎない(採録状況も川村氏の底本の記載に従っている)。
五月雨の流れどほしの木木の膚
短夜の夢の白さや水枕
風鈴に甘くして飮む水藥
ひと在らぬ夜るの風鈴鳴りにけり
炎日の葉の影を踏み家に入る
日は宙に徑にまごつく遠蛙
春畫賣る汗に濁りし老婆の眼
黑人兵の本能強し夏銀河
五月雨に掌を出してみる葉の隣り
ややありて雫をはらふ濃靑の葉
蟻の體にジユツと當てたる煙草の火
指置くや決して指には觸れぬ蟻
指はさむ暴れどほしの翅もつ蟻
五月雨の湖を燈して渡りけり
生臭く半生の星かかげけり
天の河少女の頃も死を慾りし
濃山吹すなほにあゆむ少年犯
汗白む少年犯の膝頭
コスモスに肯きかねることありけり
「ややありて」の「濃靑」は「こあを」と読む。ダークブルー。「五月雨の」の句の「湖を燈して」は「うみをともして」と読んでいよう。しづ子の句の素晴らしさはその独特の映像表現にあると私は思う。キネマの第一世代の真骨頂とも言うべきか。その時間のモンタージュは凡百のカメラマンを蒼白たらしめるに足ると言ってもよい。
「木木の膚」を本流の如く漲り落ちる「五月雨」を「流れどほしの」とアップどころではない接写レンズで撮る――
「短夜の夢の白さや水枕」三鬼の「水枕ガバリと寒い海がある」をインスパイア、熱にうかされた眩暈を幻のままに「夢の白さや」と詠んで、あの不透明な白々とした「水枕」をクロース・アップ――
「風鈴」(アップ)――「水藥」の壜(アップ)――「甘くして飮む」唇(アップ)のカット・バック――たった一人の五月の暗い居室にチリンと鳴る孤独な「風鈴」――
路上。焦げ付くような「炎日」に焼き付けられた「葉の影」。女の足がそれを踏みしだいて、そして家の闇へと吸い込まれてゆく孤独なその後ろ姿――
感光するフィルムは辛うじて「日は宙に」ある映像を見せて、カメラは急激にパンして人気のないぎらついた小「徑」を俯瞰、そこ「にまごつく遠蛙」(「遠蛙」は「とほかはづ」であろう)を広角で映し出す――
「春畫賣」りの「老婆の」黄色く「濁」った「眼」そして粘つくようにしたたる「汗」――
「黑人兵の」句は伝説のしづ子ならではの句である。「黑人兵」「本能」「強し」「夏銀河」の総ての語が強靭で尚且つ、批評を許さぬ有機的なソリッドな合体として、読者に迫る。下五で宇宙にスケールを飛ばすのも上手い。その句の具体なイメージを遥かに遠くに措いてしまって、私はこの句が好きである。
以下、三句を選んだ「蟻」の句は、十句連作である。是非、底本で鑑賞されたい。炎天下のしづ子と蟻のハレーション気味の映像は、忘れ難い強烈な印象を残す。
「生臭く半生の星かかげけり」は先行する、謎めいた句「明星に思ひ返せどまがふなし」に響き合うように私は感じる。
「少女の頃も死を慾」(「慾」はママ)したしづ子の眼は、「少年犯」の共犯ででもあるかのような「少女」の視線と、そして母の慈愛に満ちた双眸とでもって、見守っている(この「少年犯」の句も四句連作)。
「コスモスに肯きかねることありけり」は翌月の『樹海』(昭和二十六(一九五一)年七月号)に載る、知られた「コスモスなどやさしく吹けば死ねないよ」の原型と言えよう。――因みにコスモスの花言葉は――乙女の真心・愛――である。
◯鈴木しづ子 三十二歳 『樹海』昭和二十六(一九五一)年七月号の発表句二十一句から 七句
標題「夏みかん」総句数二十一。異例の多さである。――かの名唱の二句が初出する。『指環』所収句は十四句。
*
まみゆべし梅雨朝燒けの飛行場
頒ち持つかたみの品や靑嵐
俳句の病いである。
この句を戦中の句だと言えば、人々は誰もが涙し、英霊を思う――正しい制作年を示して「戦中」だと言えば、しづ子とその上の同時代人は一瞬にして顔を曇らし、胡散臭い視線を送る――作者は鈴木しづ子という、と発すれば、しづ子の名を何処かで聞いたことのある者は、したり顔に妙な笑いをして肯んずる――
俳句の病いである。
この冒頭二句は『指環』に所収する。
*
夏みかん酸つぱしいまさら純潔など
いまさら句評など前途下車無効しづ子の純潔――
言うまでもなく『指環』所収。
*
燈の薔薇はもつとはなやげ斯かるとき
「燈の薔薇」が今一つこなれない――次の句を並べれば、それは元来が詩語でなく、安っぽい即物ででもあるかもしれない――しかし、それは問題ではない――これも俳句の病である――しかし、だから、いい。
『指環』所収。
*
燈の笠に寒のあまおとつたふなり
凡庸とも言われようが悪くない。しかし、前句と並べば、否応なしに前句の印象を完全な写生句に引き下げてしまうのである。だから『指環』に採らなかったか。
*
コスモスなどやさしく吹けば死ねないよ
先日、私はこの名句をインスパイアさせてもらって、
と、やらかさせてもらった。
『指環』所収。
*
倖うすき頤持つや蘭寒み
ゴッホの「病める子」だ――
『指環』所収。
◯鈴木しづ子 三十二歳 『樹海』昭和二十六(一九五一)年八月号の発表句十八句
この号の掲載句は昭和二十六(一九五一)年六月八日附句稿百句の中から撰されたものである。『指環』所収句は九句。その掲載句十八句を総て順に掲げる。
拭ふ汗東京の土踏むことなし
搖れてゐる炎天の葉をみとめけり
風鈴や枕に伏してしくしく涕く
風鈴に甘くして飮む水藥
炎天のポストは橋のむかふ側
夏草と溝の流れと娼婦の宿
掌の金や嘲笑に似て蛙鳴く
生溫く牛乳飮むや娼家の隅
暦日やみづから堕ちて向日葵黃
高き葉の隔日に照る梅雨なりけり
蟻の體にジユツと當てたる煙草の火
指觸れしより蟻のまた速きこと
指はさむ暴れどほしの翅もつ蟻
生臭く半生の星かかげけり
濃山吹くすなほにあゆむ少年犯
ひと在らぬ踏切わたる美濃の秋
霙るる葉居のなかほどを燈しけり
冴返る劍山深く水に沈み
因みに、この選句は百句句稿の順に正しく並んでいる。
この内、しづ子によって『指環』に採録された九句だけを、以下に抽出してみよう。
搖れてゐる炎天の葉をみとめけり
風鈴や枕に伏してしくしく涕く
炎天のポストは橋のむかふ側
夏草と溝の流れと娼婦の宿
暦日やみづから堕ちて向日葵黃
蟻の體にジユツと當てたる煙草の火
ひと在らぬ踏切わたる美濃の秋
霙るる葉居のなかほどを燈しけり
冴返る劍山深く水に沈み
最後に、先に私が六月八日附句稿百句で私の琴線句として掲げた十九句を示し、本号での採否を見る。〇が掲載句、×がこの時には巨湫が採らなかった句である。なお、この号に掲載された句群を私は今初めて見ていることをお断りしておく。
× 五月雨の流れどほしの木木の膚
× 短夜の夢の白さや水枕
〇 風鈴に甘くして飮む水藥
× ひと在らぬ夜るの風鈴鳴りにけり
× 炎日の葉の影を踏み家に入る
× 日は宙に徑にまごつく遠蛙
× 春畫賣る汗に濁りし老婆の眼
× 黑人兵の本能強し夏銀河
× 五月雨に掌を出してみる葉の隣り
× ややありて雫をはらふ濃靑の葉
〇 蟻の體にジユツと當てたる煙草の火
× 指置くや決して指には觸れぬ蟻
〇 指はさむ暴れどほしの翅もつ蟻
× 五月雨の湖を燈して渡りけり
〇 生臭く半生の星かかげけり
私の詩想と俳人巨湫の詩想を殊更に比較しようというのではない。しかし、私の感覚と巨湫の撰のずれには、「しづ子」という仮象された存在証明の恐ろしいまでの「ずれ」を見ることが出来よう。それは決して無駄なことではないと私は思うのである。
最後に。実は六月八日附句稿百句の中に、一句だけ『樹海』に採られなかったのに『指環』に所収されている句があるのである。それは句稿で「夏草と溝の流れと娼婦の宿」のすぐ前にある、
夏草と溝の流れと娼婦の宿
である。これが『指環』に採られた経緯は分からないが、極めて高い確率でしづ子自身の自選であると考えた方がよかろう。
「しづ子娼婦俳人伝説」を堅固なものにするに、これは相応しい句ではある。
この句――しづ子若しくは「しづ子」にとっては――必要な句であったのだ。
そのようなものとして、私たちはこの一句を、もう一度、読み返してみる必要がありそうだ。――
◯鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十六(一九五一)年六月十九日附句稿五十句から十句及び『樹海』昭和二十六(一九五一)年八月号全三句
巨湫はこの五十句から『樹海』昭和二十六(一九五一)年八月号には次の三句を撰しているに過ぎない。
向日葵に便りなければ憂しと書く
朝鮮へ書く梅雨の降り激ちけり
梅雨明の水があつまる木のうしろ
但し、句稿では三句目初句が「梅雨明け」であるから、脱字であろう。「激ちけり」は「たぎちけり」。上代からの古語「たぎつ」はしづ子の好きな動詞である。この五十句、全体にしづ子らしい勢いがなく、淋しい。これは「朝鮮に書く」の句で分かるように、恋人のGIが朝鮮戦線へ派兵された(川村氏の年譜によれば同年五月頃)心痛と寂寥によるものであろう。後の二句は私も採る。以下、私の撰。
夢さめて夢なつかしむ蚊遣香
朝鮮へ書く梅雨の降り激ちけり
向日葵に妥協妥協とつぶやき步く
麥は黃にキヤバレー女に戀などなし
ことごとく玉葱くさる籠の中
梅雨明けの水があつまる木のうしろ
あじさゐの葉先が觸れてゐる水面
まがふなし花のあぢさゐ掌もてゆすり
死ぬことをかつて絶れし曉けの雲
最後の句は「かつて絶れし」という過去形が意味深長であるが、それが詮索助長性を軽率に惹く分、逆に句の瑕疵となってしまっている。「キヤバレー女」の自己侮蔑からもお分かり戴けるように、全体に自棄の印象、濃厚である。
◯鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十六(一九五一)年八月二十四日附句稿六十九句から三十二句及び『樹海』昭和二十六(一九五一)年十月号の発表句三句
『樹海』昭和二十六(一九五一)年十月号には次の三句が載る。
乳房持つ犬に蹤けられ夕燒雲
朝顏のつねに日蔭の花も咲く
大阪や來泊てて覺めし夾竹桃
私は馬鹿なのか、最後の句が読めない。尚且つ、この句、底本の八月二十四日附句稿六十九句には含まれておらず、また底本末尾に配された年月日不明の句稿にも含まれていない。これは、底本に初めて示された大量未発表句稿には散逸した部分があることを示唆している。少なくとも、この八月二十四日附句稿は六十九句以上あったと考えてよい。一句目「乳房持つ」は『指環』所収句であり、私の琴線句の一句である。以下、私の撰。
好きことの電報來たる天の河
明星にまがふかたなき軀と識りぬ
還り來て得し病かな鳳仙花
看とること曉およぶ水中花
風鈴の瞼とづれば鳴りにけり
乳房持つ犬に蹤けられ夕燒雲
雪はげし妻たりし頃みごもりしこと
雪はげし吾のみのほか知らず過ぐ
雪はげし葬るべく意をかためしこと
雪はげし月を經ずして葬りしこと
激つ雪自ら葬りおほせけり
雪はげし葬りて性別さへ頒たず
蘭の葉の三月寒し離婚せり
火蛾舞へば妻たりしこと悔ゆるや切
その名さへうとみけるかな燈蛾堕つ
黑人の妻たるべきか蚊遣火堕つ
ふたたび妻たるべきか舞ふ燈蛾
火蛾の舞ひ人種異る手と手合はす
まつかうに西日きたれる殘暑かな
桐一葉かつて十七のお下げ髮
桐一葉西日の中に落ちにけり
蟬かしまし飮酒喫煙おぼえしこと
雉啼くや遠き過去やら近きそれ
流れ星ひんぱんに戀を奪いしこと
遠花火音より早く失せにけり
樹の下にいちじく吸ふや白痴のごとく
祭笛吹き了りなば情ささげむ
祭笛ふくとき若さ恥ぢにけり
花の木瓜寒むざむ浮氣してみよか
凍みる戸を怒りと共に閉ぢ來しなり
「好きことの」の「好きこと」とは朝鮮戦役からの恋人の日本への帰国を指す。川村氏の年譜によれば、この年の八月頃、恋人のGIが佐世保に戻った。句稿は佐世保での再会の喜びを連句する。
――しかしその喜びは暗転する――彼はヒロポン中毒者になって帰ってきたのであった。「明星に」から「風鈴の」の句群はしづ子の、その愕然たる思いを伝えて哀しい。川村氏の年譜によれば、同八月中の出来事として、この恋人の米兵はその後、埼玉県朝霧基地に移動し、『横浜から米国へ帰国する』ことと決し、この『恋人に会うために一泊二日で岐阜より上京』した旨の記載がある。
「激つ雪」を含む「雪はげし」連作は勿論、橋本多佳子の昭和二十六年六月一日発行の句集『紅絲』に所収する「雪はげし抱かれて息のつまりしこと」の如何にもな本歌取りではある。しかし、私たちはここにしづ子の悲しい堕胎の思い出をここに知ることになる。これは架空の句では読みえない。恋人の絶望的な病いの中で、伝説の「しづ子」を演技をする余裕など彼女にはなかったはずだ。いや、これは伝説以前の「妻」であった時の体験である。――その「妻」の相手は正式な結婚をし、すぐに冷えきった「関」姓の人物か、それとも――などという詮索はこの際、私には不要である。伝説の中の「しづ子」が垣間見せた真実のしづ子の聖痕(スティグマ)を、私は全身で、受けとめる――
川村氏の年譜では月は示されていないが、この秘密の堕胎連作の直後の「蘭の葉の」の句によって、しづ子が生涯で一度だけ正式な「妻」であった、「関」姓の夫との離婚が(少なくともこの堕胎事件はしづ子一人の秘密であって、少なくとも夫側からの離婚の直接理由であるようには読めない)、昭和二十四(一九四九)年三月であったと考えてよい。
「火蛾舞へば」「その名さへ」も多佳子の「火蛾捨身瀆(よご)れ瀆れて大切子」等の火蛾句に似る。しかし「火蛾捨身」の句は多佳子の昭和三十二年の句であるから、そのインスパイアではないのである。そして、しづ子の詠みの方が遙かに切実であることに気づく。
薬中になった病んだ彼を健気に看病するしづ子をなめた彼女の背後からのショット――「黑人の妻たるべきか」「ふたたび妻たるべきか」と逡巡するしづ子の顔の眼をターゲットとした前方からのあおりのショット――しづ子の白い手が布団から出た彼の黒い手をとって「手と手合はす」アップ――枕辺のランプにコンコンとぶつかる「舞ふ燈蛾」――「蚊遣火」のアップ――「火蛾の舞」ふアップ――蚊遣の灰がポトリと「堕つ」――
「まつかうに西日きたれる殘暑かな」は、しづ子らしい強靭な句である。しづ子は何か、ある覚悟をしたとき、強烈な眩しい強い句を産む。この句は私には、そのような一瞬の時間を切り出した句として映る。私は久女じゃないが大の「虛子嫌ひ」である。「桐一葉」とともに、しづ子の可愛い八重歯が、虚子の太腿にがっしと嚙みついているようで、快い。
秘かな堕胎告白もそうであるが、「桐一葉かつて十七のお下げ髮」や「蟬かしまし飮酒喫煙おぼえしこと」「流れ星ひんぱんに戀を奪いしこと」と、この句稿では病んだ恋人の実景と過去が、文字通り、「遠き過去やら近きそれ」といった感じで目まぐるしくフラッシュ・バックする。
「遠花火音より早く失せにけり」はこうして単独で読むと、写生句である。写生を伝家の宝刀とされる方には、しづ子もやるじゃないか、と言わせるかも知れない。それが私の言う『俳句の病い』なのだ。是非、底本をお読みあれ。これは「樹の下に」「祭笛」などと同じく十二句続く遠花火と祭りの句群の中にあって、何ものでもない『儚い一瞬の恋情の遠花火』であることがお分かりになるであろう。底本の「全句」をお読みあれ。私はあくまで川村蘭太氏の労作「しづ子 娼婦と呼ばれた俳人を追って」(新潮社二〇一一年1月刊)の販促をお手伝いをするものである。なお、この「祭笛」の句――「祭笛吹くとき頭かしげける」という句もこの十二句の中にあるのだが――も橋本多佳子の「祭笛吹くとき男佳(よ)かりける」「祭笛うしろ姿のひた吹ける」のインスパイアである。一見、如何にもな剽窃のごとく見えるのであるが、ここには仕掛けがある。多佳子のこの句はやはり句集『紅絲』に所収するのであるが、「祭笛」と標題するこの句群には『戦後はじめて京都祇園祭を観る』とあって、この笛吹く男は多佳子の恋人でもなんでもない。ところが、この多佳子の句をまずスタートとして、しづ子のこれらの句群を読むと、鮮やかに一人の祭笛を吹く青年とそれを熱い眼で見つめる女の姿が――晴れの祭りの一夜のあやうい恋の物語が映像化される寸法になっているのだ。これを私は安易なインスパイアと呼ぶべきではないと思う。これは多佳子の句によって確信犯的に創られた別な事件、平行世界のもう一つの祝祭的神話、トワイライト・ゾーンの一話なのである。――そうした視点から見ていると、もう一つの不思議な映像が私には見える――ここで祭りの笛を吹いているのは一体誰なのか?――それは祭りで見知った行きずりの男――などでは――ない――この「祭笛」を「頭をかしげ」で吹いている「若さを恥ぢ」る「惚れ惚れ」とするような「情をささげ」んとするのは――巫女であり――しづ子自身なのではあるまいか?……私は多佳子の句も好きである。しづ子もそうだった。先輩俳人として尊敬もしていたであろう。しかし、これみよがしな「雪はげし」と「蟬かしまし飮酒喫煙おぼえしこと」「流れ星ひんぱんに戀を奪いしこと」などの、これでもかといった詩語や句柄の意識的模倣を見ると、これはもうインスパイアというよりは――上流階級の才媛多佳子の、あくまでポジティヴな純愛思慕調の「雪はげし」や、久女由来のあくまで観念的でしかない冒瀆的語感に対する――ネガティヴでしかも強烈なリアリズムに基づく「堕ちた」しづ子が挑戦状を突きつけた対決の句――に見えてくるのである。――これらの句群は、多佳子の句群には「俳句」としては到底及ばないと評されるのであろうし、退屈な公的「俳句史」にも残らない句ではあろう。しかし、私には――私の「俳句」の意識の中では――立派に多佳子に拮抗する作品として、永遠に記憶されるのである。
「花の木瓜寒むざむ浮氣してみよか」祭りの後か――伝説の「しづ子」のモノローグ――
しかし――
“La fete est finie.”――
「祭りは終わった」――
バーン!!!――
「凍みる戸」は「怒りと共に閉ぢ」られる――
これが句稿の最終句である――
〇「俳句往来」昭和二十六(一九五一)年十月号から一句
この掲載句十句はすべて昭和二十五年十一月号から昭和二十六年七月号の『樹海』からの採録であるが、私が先に琴線句としたものは、『樹海』昭和二十六年一月号の次の一句のみである。
月の夜の蹴られて水に沈む石
◯鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十六(一九五一)年九月五日附句稿二十四句から三句及び『樹海』昭和二十六(一九五一)年十月号の発表句から六句
凍蝶に蹤きて日陰を出でにけり
霧の洋復るなくして流るべし
袞々と國土へだつる霧の洋
『樹海』昭和二十六(一九五一)年十月号には九句が載る。私の琴線句前二句が揚がっている。奇妙なのは「霧の洋」が、
霧の洋復るなくして渡るべきか
となっている点で、これは巨湫の朱とは考えにくい。心情が全く異なるからである。これはリアルな人事句で、「復るなくして渡るべきか」は、もう日本には帰らない覚悟で、彼(恋人のGI)の祖国アメリカへ渡るべきか、というしづ子の『強い近未来への逡巡』を言う。しかし「流るべし」は、逡巡を超えて――渡る、だけじゃないんだ、そこからまた流れて行かなくちゃならないかも知れない、いいえ、それも私なんだわ――という『既に決した未来を透徹した覚悟』の謂いである。しづ子の詩語としての助動詞「べし」はそれほど確定的な意思を示す。私は断然、「流るべし」を採る。
なお、『樹海』には、
靑蘆の天かがよへり情死もよく
渦卷く爐火白ばくるること狎らされたり
をんな中かるたの男を輕蔑す
の三句が最後に載るが、これは二十四句稿には入っていない(「爐火」は「ろくわ(ろか)」と読む)。これも実際にはこの句稿は二十五句以上あったことを示唆するものである。先の「霧の洋復るなくして渡るべきか」というのはその中にあった可能性が考えられる。その場合、現存句稿の後ろだけではなく、中間部も散佚したものと考えられる。現存句稿と比べるとこの前後の句稿がちゃんと残っており、順に『樹海』に掲載されているからである。
「凍蝶に蹤きて日陰を出でにけり」は、直接には橋本多佳子の昭和二十六年六月一日発行の句集『紅絲』冒頭を飾る「凍蝶抄」の、
凍蝶に指ふるゝまでちかづきぬ
等のインスパイアに見えるが、私は実はこの多佳子の句自体が杉田久女の、
蝶追うて春山深く迷ひけり
のインスパイアであると思っている。それは久女の句としづ子を並べて見たときにはっきりする。
蝶追うて春山深く迷ひけり
凍蝶に蹤きて日陰を出でにけり
それは正しい本歌取りで、久女の原句が古い総天然色の画像なら、しづ子のそれはエッジの鋭いモノクロームなのである。しづ子は多佳子の本歌取りを見破り、しづ子流のそれをしてみせたのである。
「霧の洋復るなくして流るべし」「袞々と國土へだつる霧の洋」の二句は、一読、山口誓子の名吟「海に出て木枯歸るところなし」を連想させる(「洋」は「うみ」と読ませるのであろう)。これらに寺山修司の、
凍蝶とぶ祖國悲しき海のそと
や、有名な、
マッチ擦るつかのま海に霧ふかし身捨つるほどの祖國はありや
を並べてみると、寺山の薄っぺらさが際立つ。しかし、その気障さ加減が、「しづ子」伝説と同じで、寺山の虚数的魅力でもある。私は寺山が好きである。私も彼と同じように何処かで魂の剽窃ばかりの人生だからである。
最後に。最後の「かるた」の句について少し補足する。若い読者には理解し難いと思われるが、かるたというのは近代に於いては数少ない男女の直接的な人体接触を含んだ危うい交流の場であったことを認識しておく必要がある。それを知らないとこの句をまたぞろ「しづ子」伝説で曲解する羽目に陥る。以下は私の「こゝろ」の「先生の遺書 八十九」に附した注の一部である。
*
OCTOPUS氏のHPにある「競技かるたのページ」の論文から一部を引用する(アラビア数字を漢数字に変更してある)。『十畳の客間と八畳の中の間とを打抜きて、広間の十個処に真鍮の燭台を据ゑ、五十目掛の蝋燭は沖の漁火の如く燃えたるに、間毎の天井に白銀鍍の空気ラムプを点したれば、四辺は真昼より明に、人顔も眩きまでに輝き遍れり。三十人に余んぬる若き男女は二分に輪作りて、今を盛と歌留多遊びを為るなりけり。(*一)』〔『*一 尾崎紅葉「金色夜叉」(昭和四十四年十一月新潮文庫)より引用』という注記記載がある〕。『尾崎紅葉(一八六八~一九〇三)のベストセラー小説「金色夜叉」(明治三十~三十五
年連載、未完)の中には明治当時のかるた会の模様が述べられている。娯楽の少なかった当時、かるたというのは格好の男女の出会いの場であったと想像される。実際、後のクイーン渡辺令恵の祖父母も、昭和五(一九三〇)年頃ではあるが、かるたが縁で出会ったとのことである(*二)』〔『*二 渡辺令恵「競技かるたの魅力」(「百人一首の文化史」平成十年十二月すずさわ書店)』という注記記載がある〕。『当時のかるたの試合は、今日で言う所のちらし取り、あるいは二組に分かれての源平戦が主流であった。「金色夜叉」に描かれたかるたの試合は、どうやらちらし取りであったように思われる』(以上は同HP内の「三.競技かるたの夜明け」の冒頭「かるた会のあけぼの」より引用)。『黒岩涙香が開催した明治三十七(一九〇四)年の第一回かるた大会の案内には「男女御誘合」とあり(*一)、当初かるた会は女性に大きく門戸を開いていた。だが、男尊女卑の傾向が著しかった時代で』あったため、明治四十一・四十二(一九〇八・一九〇九)年頃に至って『かるたが世間に認知されるようになると、男女が交わって競技を行なう点が非難の的となる。「若い男女が入り乱れになつて、手と手を重ねたり、引手繰事(ひったくりっこ)をしたり、口の利き様もお互ひに慣れ慣れしくなり作法も乱れて居る」(*二)と、山脇房子は明治四十二(一九〇九)年一月に指摘している。「今の若い男女は平常は隔てられて居て、いざかるたとでもなると、又極端に走りますからいけない」と、山脇は「風俗上衛生上の害を避ける為め」にテーブルの上での競技をも提案している。またその一方で、「相手が女では、バカバカしくて本気になって取れン」(*三)であるとか、「荒くれ男を向ふに廻して戦を挑むような女は嫌ひだ」「婦人は須らく男子に柔順で、繊弱優雅なるを愛する」(*四)などといった男性選手の言い分もあった。その結果、黒岩涙香としては当初の「平等意思」(*五)に反するとしながらも、東京かるた会は明治四十一(一九〇八)年二月、傘下の各会と同盟規約を結ぶこととなる。その内容は「同盟各会の会員は勿論東京かるた会の出席者は素行不良ならざる男子たること」「同盟各会其他競技席上には婦人及素行不良と認めらるる男子の入場を拒絶すること」(*六)といったもので、これにより明治四十二(一九〇九)年二月の五周年大会以降女流選手の大会参加は認められなくなる』。『しかし、完全に女性が閉め出されていたかというと、そうではなく、仙台では女流大会が開催されており、昭和二(一九二七)年の第1回大会では藤原勝子が優勝している。東京や山梨、筑波などでも同様の大会が開かれている(*七)』とある。因みに『かるた会が再び女流選手に門戸を開いたのは昭和九(一九三四)年一月五日の第二十二回全国大会からであった』(以下略。以上の引用部の注記は以下の通り。『*一 「萬朝報」明治三十七年二月十一日』・『*二 山脇房子「風紀上より見たる歌留多遊び」(明治四十二年一月「婦人画報」)以下引用は同記事』・『*三 「朝日新聞」昭和三十年一月五日「女のはな息」』・『*四*八 「かるた界 第八巻第二号」昭和九年十二月 東京かるた会』・『*五*六 東京かるた会編「かるたの話(かるた大観)」(大正十四年十二月 東京図案印刷)』・『*七 「かるたチャンピオン 九十五年のあゆみ」平成十一年一月 全日本かるた協会』。以上は同HP内の「五.かるた黄金時代」の「女流選手のあゆみ」より引用)。ここで明治四十年代初頭に公的なかるた会が『男女が交わって競技を行なう点が非難の的とな』ったこと自体が、実はそれ以前、男女の手が触れあたりする私的な男女の正月のかるた取りが、密やかにそうした男女の交感の場でもあったことを図らずも物語っていると言えよう。
*
〇「俳句往来」昭和二十六(一九五一)年十一月号から三句
「美濃へ」の標題で四十九句。句集『指環』の中核を形成する代表作群が並ぶ。底本には冒頭に川村氏の「すべて句集『指環』から再録」とあるのであるが、これは不審である。何故なら、『指環』の発刊は翌昭和二十七年一月一日であるからである。これは「に再録」の誤りではないかと思ったのだが、以下に見るように川村氏は本誌掲載句と『指環』掲載句とを校訂されており、その二箇所の注で「『指環』の元句は」と表現されており、更に掲げた一句「子を欲りぬ」については、「『指環』になし」とある。ないということは、この「俳句往来」の原稿には少なくともこの句が含まれており、句集『指環』と同一稿ではないといういうことになる。若しくは句集『指環』準備稿なるものが存在し、『指環』発刊直前の「俳句往来」本号にはその一部が示された、ところが実際の決定稿ではそこから「子を欲りぬ」の句が外された、ということではないか。
かくまでの氣持の老けやたんぽぽ黃
歸る步やまづ火をおこすべしとのみ
以上は二句は『指環』では、
斯くまでの氣持の老けやたんぽぽ黃
歸る步やまず火をおこすべしとのみ
である。後者は歴史的仮名遣ならば「まづ」が正しい。『指環』では、歴史的仮名遣と斬新な口語が激しく混在して使用されているが、一句の中ではほぼ統一されている。しづ子はこの句に、『指環』では、現代仮名遣・文語表現を採用したということになる(「氣」「歸」の正字化は私の仕儀である)。
子を欲りぬとは氣まぐれか夏の虹
本句は『指環』に所収ない。そしてこの「氣」はママで、私の仕儀ではない。先の「かくまでの」句は底本では「氣持」は「気持」である。正字の観点から見ると、この四十九句には正字が殆ど使用されていない。はっきりしたものは「體」「縣」と、この「氣」だけである。「體」はしづ子の好きな字体であり、正字という意識は彼女にはない。「縣」は住所表示に長く使用されてきただけに、これも意識的な正字感覚はないはずだ。だとすれば、この句だけが「氣」と、はっきり正字使用を意識しているということになる。不思議である。この四十九句の選句は、実は我々の知らないつぎはぎされた(だから正字の本句が混在する)原『指環』稿なるものがあったことを示唆するものではないだろうか。
◯鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十六(一九五一)年九月二十八日附句稿百五句から二十八句及び『樹海』昭和二十六(一九五一)年十二月号の発表句全七句
百五句の大量句稿から見る。これは青春の回想吟であり、それはあたかも時系列に沿って創られ、並べられたかのようにシークエンスが編集されている。最初の十一句は纏めて採る。
*
彈き初めの翏を競へり戀きそふ
獲し戀ぞ花の鷄頭艶然と
翏と戀競ひしことぞ掌の胡桃
野分の葉うばひし戀のつまらなく
この二句に現れる「翏」は不審。「翏」は高く飛ぶ、その形容及び、遠くから吹きすさぶ風の音の意で名詞の意を持たない。これは「琴」ではあるまいか? 「彈き初め」が説明出来、「こと」と「こひ」の響き合う語感もよい。「獲し戀ぞ」の「鷄」は川村氏によって補われたもの。原句は「獲し戀ぞ花の頭艶然と」であるらしい。
情識りぬ旅の山肌明け易く
蹤きゆきし十九の夏の旅初め
蟬はげし馴初めの得ざりし男の手
蟬はげし夫ならぬ手を識りゐしこと
祕めごとや額の汗の美しく
祕めごとの知る人ぞなし葉鷄頭
蟬は樹に吾が手與へし人ぞ亡し
稻田燈蒼し人亡しと思へばなほ
「祕めごとの知る人ぞなし葉鷄頭」も原句は「祕めごとの知る人ぞなし葉頭」であるらしい。川村氏の補った「葉鷄頭」で採った。ここまでの句群を一連のものとすれば、彼を奪い得た数え「十九の夏」というは、しづ子が後に戦死する許嫁と出逢った頃に同定されているのに一致する。最後の句では既に彼は死んでいる。やはりこの「男」は彼であろう。なお、この後には黒人の恋人との海水浴の四句が続く。
*
木枯や胸乳隆くして獨り
この前にも自分の豊かな胸を謳う三句あるが、その、
乳ゆたかなれど孤獨や木枯しに
の推敲稿である。
*
ちちははの戀の生れ處や曼珠沙華
しづ子の父俊雄と母綾子は従妹同士であった。――因みに私の両親も従妹同士である。――そして、母の死後、そこに隠された独身の頃の謎の母の自殺未遂、それが「ちちははの戀の生れ處」となった事実を知った。私には本句が特別な感慨を以て響いてくる所以である。俳句の感動とは恐らく――そういうシンクロニティにあると私は思っている。
*
いなづまに長女と生まれてまづはよし
いなづまに早世の次女の貌忘る
いなづまにもつともすこやかなる三女
天の河つねに悲戀は姉娘
學びけり少女の心いつぱいに
しづ子、本名鈴木鎭子は大正八(一九一九)年六月九日東京市神田区三河町で父鈴木俊雄・母綾子の長女として生まれた。彼女の誕生からのコマ落としの五句連作。初句の「いなづまに」と「まづは」の言辞の持つ意味は、川村蘭太「しづ子 娼婦と呼ばれた俳人を追って」の六十四ページに明晰に語られている。「もつとも」は底本「もっとも」、同じく「いつぱい」も「いっぱい」。
*
稻妻に父憶ふとき汚れけり
つねの世も女人は哀し曼珠沙華
稻妻や母のわだちぞ踏むまじく
以前に記したが、さんざん綾子を苦しめた父俊雄は昭和二十三(一九四八)年十一月に母綾子の生前から関係があった女性と再婚した。第一句のような強烈な抵抗感に基づく呪詛句がこの前に六句ほどある。この昭和二十六(一九五一)年の冬には、しづ子は昭和二十一(一九四九)年五月に亡くなっている母綾子の墓を愛知県犬山市の寺に、新たに建立している。
*
蟬のこゑもつとも高し滅びる前
「もつとも」「滅びる」はママ。
*
降る雪やわがをとこ名のむかしの詩
川村氏の「しづ子 娼婦と呼ばれた俳人を追って」の『幻の詩句集「小径」』で推理のキーとなった句。
*
雜草に紙片吹き寄る空工場
これは、しづ子の、プロレタリア俳句への答えという感じがする。
*
稻妻に希ひし破婚爲しにけり
私は以前、関との離婚は昭和二十四(一九四九)年三月とした。この句は「稻妻」で秋である。しかし、矛盾しない。「稻妻に希ひし」で過去形であってそれは寒雷でも春雷でもよいのであり、そもそも先行句を見れば一目瞭然、「稻妻」は彼女にとって季語である以上に、彼女の人生の時空間を支配する哲学的な詩語なのである。しづ子は季語に縛られていないのである。
*
逝く夏の葉分けの風のゆくえかな
巧まぬ佳品である。風の囁きが聴こえる――
*
うつせみや吾が手與へし人失せて × ①
大阪へ五時間で着く晩夏かな 〇5指⑥
新涼の喫泉小さくあふるる驛 ×
木枯や胸乳隆くして獨り 〇1 ②
雪こんこん死びとの如き男の手 〇2指③
そだちつつ颱風ちかよりつつあると 〇3 ④
刻すでに颱風圏内花黃なり 〇4 ⑤
以上が『樹海』昭和二十六(一九五一)年十二月号の発表句全七句である。下に附した記号は、「〇」が昭和二十六(一九五一)年九月二十八日附句稿百五句に所収する句、「×」は所収しない句である。「〇」の下の番号は句稿の方で、早く現れる順に番号を振った(今までの句稿は順序に狂いがないが、ここでは大きく食い違うのが気になる)。この内、『指環』に採られた句にはその下に「指」を附した。「うつせみや吾が手與へし人失せて」は明らかに「蟬は樹に吾が手與へし人ぞ亡し」の句の別稿である。巨湫の朱が入ったものとも思われるし、「新涼の」の明らかな句稿喪失からも、例によって句稿の複数脱落の可能性も疑われる。但し、感触的にはここは巨湫の朱という感じが強い。だとすればと仮定した上で一番下に句稿の方で早く現れる順に〇付数字の番号を振った(やっぱりこの句順は不思議である)。なお、この「木枯や」の句の左には、川村氏の『※巨湫の句か?』という注が附されているが、不審。上で見た通り、句稿にもこの句は入っている。また、この掲載句に言及した「しづ子 娼婦と呼ばれた俳人を追って」三百六ページでも、この不思議な注については言及されていない。
◯鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十六(一九五一)年十一月二十三日附句稿四十五句から句及び『樹海』昭和二十七(一九五二)年一月号の発表句全五句
この昭和二十七(一九五二)年一月一日、随筆社より第二句集『指環』が刊行される。句稿から見る。
*
東京に來てすぐ歸り九月盡
秋の雨ふた日ひと夜の朝霧町
出京や秋の外套片手に持ち
玻璃むかふ秋の雨降る迷ひごと
竝び立つ霧の埠頭の人の中
霧曉けの人去らしむる埠頭かな
共に往き一人復りぬ秋海棠
右頰に秋の日享くる離京かな
薬に侵された恋人の黒人兵がアメリカへ帰ってゆくのを見送る、そのスカルプティング・イン・タイムの八つのシークエンス。私はこの組句を――哀しくも美しいと思う――
*
秋櫻うつすら想ふ死のてだて
四ヶ月前の「コスモスなどやさしく吹けば死ねないよ」を自解するような句である。いや、四ヶ月前は「死ねないよ」という呟きだった――今は「死のてだて」を「うつすら想ふ」しづ子であった――
*
山の子がはにかみて出す掌の木の實
しづ子の女らしい優しさが珍しく素直に示された美句である。
*
雪粉粉わつと叫びて狂ひたく
鐡路凍つ體投ぐること有り得べく
発狂願望と自殺願望とが――ルナティクに舞う粉雪と――触れなばびっと張り付いて皮膚がべろりと剥けそうな凍ったレールに――オーバー・ラップする――
*
責むるには哀しかりけり鰯雲
これは無論、加藤楸邨の主観俳句の名句「鰯雲人に告ぐべきことならず」のインスパイアなのであるが、如何にもますらをぶりの男系句である楸邨に、相聞でしづ子は美しく返したのだ。
鰯雲人に告ぐべきことならず
責むるには哀しかりけり鰯雲
この美事な鏡像構造を見よ。この句は決して句屑の中に埋もらせるべきものでもなく、また軽々に扱うべきものでもないと私は思う。
*
右頰に秋の日享くる離京かな
山の湯に肩まで浸る十月盡
右の上秋の水きて流れけり
ひややかにうなじの黑子吹かれけり
木に倚れば頰に擦れ合ふ黃ばみし葉
以上が『樹海』昭和二十七(一九五二)年一月号発表句全五句。冒頭の句は単独で切り離された時、しづ子の思いは全く読者に伝わらないことがお分かり頂けるはずである。三句目は句稿から、「石」の誤植。『樹海』の誤植か底本の誤植かは不明だが、『樹海』の誤植とすれば、句誌としては話にならない致命的な酷い誤植である。「器」を「黑」として訂正もせず、その「器」を勝手に「磁器」から「男性生殖器」に読み替える愚劣なスカベンジャーどもの姿が垣間見える――
◯鈴木しづ子 三十二歳 『樹海』昭和二十七(一九五二)年二月号の発表句全七句
雪粉粉いのち粗末に醉ひにけり
粉雪舞ふ晝の褥を延べにけり
寒の夜やくれないうすき造花の葩
ほつそりと佇つや野分の草の中
山の子が山駈けめぐる秋は好し
佇つ前を貨車が過ぎゆく鰯雲
雪のあとすこし雪つく木木の膚
今までにない不思議な現象がここにある。それはこれが前の『樹海』一月号に続いて昭和二十六(一九五一)年十一月二十三日附句稿四十五句から再び採句されたものだからである。実は次の句稿は六日後の十一月二十九日附句稿が現存するが、ここからこの二月号には全く採られていない。勿論、これは『樹海』の編集が二箇月前の十五日に締切を迎えるものであるために(「しづ子 娼婦と呼ばれた俳人を追って」二五八ページにある川村氏の調査によるが、実際には十六日以降の句稿でも二箇月後の号に載っているものもあり、その辺は臨機応変であったようである)、後者の句稿が間に合わなかったという物理的理由によるものであることは容易に想定出来るのであるが、大量投句を始めた几帳面なしづ子がこの編集のリミットを知らなかったはずはなく、このような遅れた投句をせざるを得なかったしづ子側の状況を推し量るべきではなかろうか。それは母綾子の新たな墓の建立ではなかったか。実際、十一月二十三日附句稿の一部には「母の墓建てむと」という句稿では例外的に標題が附く。
――にしても――私は不思議な静謐感をこの七句に感じる。「造花の葩」(「葩」は「花」である)のキッチュな原色だけを着色したモノクロ画面が前後左右にマルチで映し出される。私はこの七句の一句さえも昭和二十六(一九五一)年十一月二十三日附句稿四十五句からは琴線句として選ばなかったのに――しかし、巨湫によって再度選ばれたこの七句は――撰せられてソリッドに並べられた途端に――不思議な輝きを発しているではないか。これも『俳句の病い』、否、『俳句の魔法』であろう――私はこれらの句をタイピングしながら、本当に不思議の感に打たれているのである――
◯鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十六(一九五一)年十一月二十九日附句稿百三句から二十一句
この大量句稿も不思議な現象を見せている。ここから『樹海』二月号には全く採られていないということは前に述べたが、実は、それどころではなく、この句稿からは『樹海』の如何なる号にも一句も採られていないのである。これはどういうことか? 私はこの百三句を総てボツとした巨湫を想定出来ないわけではない。しかし――総ては謎である――まずは「母の墓建てむと」の標題の手前までの句から七句採る。
みなそこは冬のはじめの草と石
冬枯れの崖くだりゆく足場かな
冬雲や自惚れとそをいふべきか
花槐歌人なれども嫌ふ叔母
醉漢や雪の片々眼にとらへ
雪粉粉麻藥に狂ふ漢の眼
一瞬や殺意めきたる薔薇紅し
雪はげし汝れに言ふべきことは死ね
最初の二句は写生句であるが、しかし、やはりしず子の心象風景が、そこにオーバー・ラップする。水底には草と石が溺死している。水底ははしづ子の冥府である。冬枯れの崖の下降の足場のぐらつきは、そのまましづ子人生の転落の危うさを象徴する。その心象風景が次の「冬雲」に投影され、そこでは既に写生を失って「露悪的な自惚れ」のしづ子の内的な虚空を描き出している。
「花槐」に登場する叔母はアララギ派の歌人であった鈴木朝子である。川村蘭太氏の「しづ子 娼婦と呼ばれた俳人を追って」のしづ子の評伝部分は、このしづ子の父敏雄の妹の歌集や叙述を主軸にして展開している。特にしづ子の少女期から青年期にかけては、この朝子との関係が謎めいた鈴木しづ子の心理を推定し得る唯一の第一級資料となっている。詳しくは当該書をお読みあれ。
「雪粉粉」直前の「酔漢や」に「雪の片々眼にとらへ」の描写が、この酔漢が黒人であることを暗に示しているように思われる。米兵相手のダンス・ホールのダンサーだった彼女のリアル・タイムの実景であろうが、それはアメリカへ帰ってしまった薬に冒された黒人兵の恋人の回想へと直結している。
「一瞬」「殺意」「めきたる」「薔薇」の語の選びと、自動描法(オートマチスム)めいた接合がいい。
「雪はげし」またしても橋本多佳子への確信犯句である。伊東静雄の「水中花」(昭和十二(一九三七)年作)のインスパイアでもある。しづさん、美味しいところばかり、ちょっと贅沢ですぞ――
*
以下、「母の墓建てむと」の標題以降、句稿最後までから十四句。
此の金や不淨ならざる枯れ簫々
犬の眼に唯一瞬の野火映る
ここは死の斷崖という冬の月
秋の蛾の人の如くに玻璃を打つ
どこからか昨夜の秋蛾のきたりけり
二夜來ていのちをはりし秋蛾かな
秋の蛾に玻璃は閉ぢられゐたるまま
蘆は枯れ言はずに濟ます事と事
冬田中二三樹が立つ墓どころ
慾情すればもつそり起きる阿片患者のぎらつく汗
木の芽たくまし國際結婚興味なく
雪崩の記憶戀變へるたび好き詩生れ
狂戀の琴の師匠や花ひひらぎ
ひひらぎや戀に狂へど巧む藝
渦なせど冬のみなそこ何も無し
「此の金や」には、伝説の「しづ子」を否定するしづ子の姿がある。彼女はあくまでダンサーであり、娼婦ではない、矜持を我々はこの句に見なくてはならない。
「犬の眼に」森山大道の画質の荒く、それでいてエッジの鋭いモノクロ写真を見るようである。しづ子は接写の妙を弁えた鬼才である。
「死の斷崖という」場所は随所にあろう。しかしこのしづ子が立つのは何処でもない彼女心象の中の「死の斷崖」である。そこに心の臓を貫くような尖った凍てた「冬の月」が永遠に掛かっている――。
「秋蛾」の連句はうまい、これは橋本多佳子の例の『紅絲』の中にある「秋蛾」という標題句群を意識しているのかも知れないが、多佳子の「秋蛾」が「沼水に捨てし秋蛾のそれぞれ浮く」というクールな突き離し一句にのみ現れるのに対して、ホラー映画のように霊的な秋蛾を四カットで撮りきったしづ子の手腕は尋常な技ではない――この蛾は蛇笏が芥川龍之介の魂を「秋の螢」になぞらえたように、しづ子の愛する死者たちの魂である――
「冬田中」は単なる嘱目吟にも見えるが、遠く標題「母の墓建てむと」の句と読む。
「慾情すれば」の「阿片患者」は実景ではなく、大陸の清末の歴史的夢想句のように私には読める。勿論、そこには、この八月に朝鮮戦争から戻った薬中となり果てた恋人をダブらせて、ではあるが。いずれにせよ、どぎつい「しづ子」の伝説の強化剤の一句ではある。
「木の芽たくまし」を読むと、後日、しづ子がアメリカに亡き恋人の面影を追って行き、そのまま失踪したという伝説は信じ難いという気が私にはしている。現実のしづ子は完全な自暴自棄に投身するような弱い女ではない。打ち砕かれ切り倒され焼かれても「たくまし」く「木の芽」を吹く女である。
「雪崩の記憶」は前掲した『樹海』昭和二十三(一九四八)年五月号の「雪崩」句群に響き合う句である。
「狂戀の琴の師匠や花ひひらぎ」と「ひひらぎや戀に狂へど巧む藝」によって、先に掲げた昭和二十六(一九五一)年九月二十八日附句稿百五句の中の、「彈き初めの翏を競へり戀きそふ」と「翏と戀競ひしことぞ掌の胡桃」が、
彈き初めの琴を競へり戀きそふ
琴と戀競ひしことぞ掌の胡桃
であるという確信を私は強く持つ。
私はこの句稿の抄出で第一句に、「みなそこは冬のはじめの草と石」を採った。それにこの、句稿の最後から三番目にある句を並べて見よう。
みなそこは冬のはじめの草と石
渦なせど冬のみなそこ何も無し
――初冬の遺骸の草と石の映像は――タルコフスキイの「ストーカー」の水底の移動撮影のように動きながら――真冬には何もかもがなくなってゆくのである――
◯鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十六(一九五一)年十二月十一日附句稿九十二句から九句
この句稿の冒頭四句は川村氏によって改作の旨の注記が附されている。しづ子には改作を示すだけの思いがこれらの句にはあったと思われる。尚且つ内三句は直前の、結果的に選句されなかった大量句群の中の句である。――もしかすると、ここにこそ先の句稿が選句対象とならなかった理由を探ることが出来るのかもしれない。先の十一月二十九日附句稿群がしづ子自身にとって不満足であったか若しくは投句後、何らかの事態の変化や再考によって選句されてはまずいと彼女が判断するに至った句が混じっていたために、その投句原稿総てを次号の選句対象から外してくれるように、この十二月十一日附句稿の添え書きか何かで巨湫に依頼した可能性である。でなければ、たった十二日後に送られてきた大量句稿の冒頭に、先の句稿の四句の改作をして配するということは普通ならしないように思われるからである。――たとえばそれは、彼女の肉親に関わる句なのではなかったろうか? 実際に句稿の中には先に引いた例の歌人の叔母の句が二句及び再婚で嫌悪するに至った父の句が三句存在する。また、先に掲げた「此の金や不淨ならざる枯れ簫々」も伝説を信ずる読者には弁解染みた浅いものを感じさせ、句柄も真実のしづ子自身を語るに汲々としている印象が強く、しづ子が愛した母への追悼句としては不敬とも言える。私が感じるのはその程度であるが、その他にも公開をされたくないと感じた句があるのかも知れない。――勿論、選句対象からそれらを指示して外してもらうことも可能であるが、しづ子の性格からして、それはあり得ない気がする。そもそもそんな仕儀は選句する師に対する礼を失することになるからである。以上、私の全くの推理であるが――彼女はそのために十一月二十九日附句稿総てを諦め、纏めて葬ったのではなかったか?――但し、この仮定には難点がある。それは、これ以降の公開されている投句稿は最早、『樹海』掲載句と連動しなくなってゆくからである。恐ろしいまでの大量句稿群が波状的神経症的に巨湫のもとに送られてくることになるからである。――それは『樹海』の採句限界を無視した、しづ子の確信犯のように私には見える。――彼女は次第に『樹海』という世界から幽体離脱してゆき、師巨湫個人へ深々と礼をしながらも、絞り出した全句を素手で力任せに師の顔面に擲っているように感じられるのである。――
取り敢えず、以下にその改作句四句を掲げておく。
冬の燈に自信なくして坐しにけり
雪粉粉わつと叫びて狂ひたし
誘はれて否と言へざり蒲は穗に
竹吹けり伊吹颪をはばむなく
それぞれの原句と所在を示す。「誘はれて」の下五の「■」は川村氏の判読不能の字を示すものである。
冬燈下自信失くして坐しにけり
(昭和二十六(一九五一)年十一月二十九日附句稿)
雪粉粉わつと叫びて狂ひたく
(昭和二十六(一九五一)年十一月二十三日附句稿)
誘はれて否と言へざる蒲は穗■
(昭和二十六(一九五一)年十一月二十九日附句稿)
竹吹かる伊吹颪をはばむなく
(昭和二十六(一九五一)年十一月二十九日附句稿)
この内、私が先に選んだのは「雪粉粉わつと叫びて狂ひたく」であるが、私の好みから言えば改作の「狂ひたし」がいい。にしても――この改作は、内的欲求からの改作という感じはまるでない。やはりおかしい。
*
色ならば母を譬へて寒き紫
枯れの月いづれ此の土地離かるべし
人の子の手を引き戾る枯野かな
雷去りておのが髮膚にほひけり
風邪癒えて妙に空きある木木のひま
句稿には「母の墓たつ」と「昭和十八年六月、はじめて樹海句會に出席して」の標題を持つ句群を含むが、私には妙にリズムがぎこちなく、普段のしづ子らしい語彙のひらめきも感じられない。心づくのは以上の三句のみである。『樹海』昭和二十七(一九五二)年三月号には、この十二月十一日附句稿九十二句から十一句が採られている。私の採った「色ならば」「枯れの月」「雷去りて」の三句はその中にある。なお、そこには、
きっぱりと冬の木が立つ風茜
が載るが、句稿では
さつぱりと冬の木が立つ風茜
である。
◯鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十六(一九五一)年十二月十九日附句稿百五句から二十一句
幸福な子の手の中の凧の糸
人の子のそれぞれ在るや柿赤く
人の子のことばきたなく柿熟れたり
最初の句は「幸福な子」が説明的で陳腐であると酷評されるところであろうが、この句の眼目は「子の手の中の凧の糸」をマイクロ・カメラで捉える、そばの「それぞれ在る」ところの凧を持てぬ「ことばきたな」い「人の子の」「貧しい子」、そして「不幸な子」であった、「不幸な子」あり続けているしづ子自身にある。則ち、「幸福な子」ならざる己に繋がる外延の「不幸な子」にこそ、この「凧の糸」は遠心的に結びついているのである。
*
雪踏むや師い在す限りの體と識るべく
これが最早この大量句稿が「投句稿」ではなく、巨湫へ向けての――おかしな言い方ながら、一方通行の交換日記――であることをこの句が証明しているように思われる。
*
春寒くリボン吹かるる不幸な子
最初に掲げた「幸福な」をこの句に並べれば、それで憂鬱は完成する――
*
そは見果てぬ夢か煖爐にくべる薪
タルコフスキイの「鏡」の、あのシーンではないか!――しづ子に「鏡」を見せたかった!――
*
堕胎兒が三歳となるああ四月の■の箸
下五の「■」は川村氏の判読不能の字を示す。しかし、二〇〇九年八月河出書房新社刊の『KAWADE道の手帖』の「鈴木しづ子」に所収する底本の作者川村蘭太氏の「鈴木しづ子追跡」では、氏はこの句を、
堕胎児が三歳となるああ正月の繕の箸
と完全表記されている(底本表記に従った)。「繕の箸」というのは如何にもおかしいから、これは「膳の箸」で、そうなると「三歳となる」と「ああ」という感慨からは特別な料理の「膳」、数え年で年をとる「正月」のお節料理の「膳」が如何にも相応しくなる。従って私は、この句は、
堕胎兒が三歳となるああ正月の膳の箸
がしづ子の決定稿であったのではないかと推測する。昭和二十六(一九五一)年八月二十四日附句稿に現れる秘かなしづ子の堕胎連作の注で私は、「関」姓の夫との離婚が(但し、少なくともこの堕胎事件はしづ子一人の秘密であって、少なくとも夫側からの離婚の直接理由であるようには読めない)、昭和二十四(一九四九)年三月であったと考えた。堕胎がそれよりもやや遡るとして、出産予定が昭和二十五年の初春と仮定すれば、この句が書かれたのが投句と変わらぬ実際の昭和二十六年の十二月であったなら(句稿冒頭から冬の句が続くのでそれで間違いないと思う)、翌昭和二十七年の正月には、この子は産まれていれば確かに数えで三歳となっていたことになる。この句によってしづ子の秘かな悲しい、あの堕胎の連句は事実を詠んだものであったと考えてよいと思う。
*
ケリーを憶ふ二句
一瞬や麻藥に狎れし眼と認む
霧深き中すでに汝は病者の眼
横濱に人と訣れし濃霧かな
離るるや港よこはま濃霧き街
さよならケリーそして近づく降誕祭
+
火絶え絶えやるせなきものケリーの眼
頭振りて記憶の眼をば消さんずる
爐火さむざむ變らぬなさけつづくべし
++
見えざれど濃霧たちたる洋中とぞ
濃霧き中見返ることぞ忘るるな
吾が名呼はば洋上の霧うすらぐべし
「ケリーを憶ふ二句」という標題句群から。この年の八月に帰国した米黒人兵の恋人の名が初めて句に読み込まれる。次々回の句稿では「ケリー・クラツケ」というフル・ネームで登場する(但し、彼の訃報で)のであるが、川村氏は、この名は本名とは考えにくいという結論を示されている。ネイティヴの方も加わった考証で、川村氏はこれによって他の本文箇所ではしづ子の恋人を単にGIと呼称されている。詳細は川村氏の本文二百六十八ページをお読み戴きたい。「二句」というのは「ケリー」の名を詠み込んだ句が二句ということを意味しており、実際には私の判断で以上の十一句を「ケリーを憶ふ」と詠んですべて採録した(「+」の間に五句、「++」の間に一句あるが私にはケリーの映像が見えないので排除した)。「離るるや」と「濃霧き中」の「濃霧き」は、二箇所で錯字をすることは考えにくいから、これで「きりこき」と読ませているものと考えられる。「吾が名呼はば」の「呼はば」はママ。
*
おさげ髮の鏡の吾や寂しき貌
これは風邪を引いたしづ子が、病床で五月蠅い髪を久しぶりにお下げに結った折りの句であるが、私などは三十二歳の「おさげ髮」のしづ子が「鏡の」中に立って、そこに写る「おさげ髮の」「寂しき貌」の十代の「吾」が姿が映っているという映像を思わずしてしまう――逆転したドリアン・グレイ――この後の句稿末尾の方に配された鏡二句(「破れ鏡とぞ」は句稿最終句)を示して、この句稿の採録を終わる。
秋風や破片の鏡棄てがたく
破れ鏡とぞ人の言もて譬ふれば
◯鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十六(一九五一)年十二月二十四日附句稿九十六句から二十三句
現存する昭和二十六(一九五一)年最後の句稿である。
*
人の子の雪の日曜吾も遊ぶ
雪合戰に額打たれし顰むるなく
好きな子を敵に取られし雪合戰
この體在學最後の年や雪合戰
雪合戰の雪つけてきし幼な髮
しばし待て雪にしめりし髮乾す間
句稿の冒頭から「雪」「積雪」の語句が示され、「雪の縣道事故」「ラツセル車」が詠まれ、雪の詠まれぬ句は一句もない。その十六句目が「人の子の」の句であり、次の句から雪合戦連作が実に十五句、掲げた「雪合戰の」句まで続く。これは、ご覧の通り、岐阜のある大雪の日の知り合いの子らの雪合戦の嘱目吟に始まるのだが、その中間部、子らの雪合戦のフラッシュ・バックの映像が、何としづ子自身の少女期へと変容し始めるという不思議な連作である。子らの歓声のSEと雪玉のアップの句が続いて「好きな子を」の句の辺りから時間が巻き戻されている。次の「この體」は既に雪合戦をしている少女しづ子自身の映像である。「幼な髮」とあるが、これは「雪合戰」と「髮」のみが「幼な」い、しかし「體」は女である高等女学校「在學最後の年」の「雪合戰」の追憶である。休み時間の雪合戦から教室に戻った女子生徒は次の時間の、若き国語教師に目線で――「雪合戰の雪」に濡れてしまった「幼な髮」の「しめ」ってしまったこの黒「髮」を「乾す」少しの「間」だけ「しばし待」って――と媚を送っているのではあるまいか? 私の雪合戦句群の解釈は牽強付会か? そうかな? この「しばし待て」に続く以下の六句をご覧あれ。
師を好きて好きて卒業したりしこと
戀初めの國文の師よ雪は葉に
雪は葉に高師卒へたる師の講義
雪の椿折りて靑年少女の戀
戀初めの戀失せしめし卒業せり
雪は佳し宗教教育享けしき體
「雪は佳し」の次からは現在時制に戻っている――その二句目には「年了るナイトクラブは雪の中」とある――しづ子は昭和十三(一九三八)年十九歳で私立淑徳高等女学校を卒業している――三十二歳の「雪の中」の「ナイトクラブ」の、ダンサーを身過ぎとする疲れた面持ちの女が回想する――十九の蒼き春の雪の思い出……私はこれらの句に個人的にある胸の痛みを感じてしまうのだ……
*
吹雪く玻璃たがひ背ける黑人白人
雪を來し色魔の如き唇のうるみ
米兵たちを冷徹に観察するしづ子の眼である。
*
明日の體はあるひは轟く雪崩の下
聞きしこと屍美しき雪の中
死果たさず見返りみかへり雪を來しこと
現は死ねない記憶の雪崩背に轟き
こころの體失せしのちにも雪かがよふ
以上は連続する五句。しづ子と「雪崩」は『樹海』昭和二十三(一九四八)年五月号に載る「雪崩」句群以来、しづ子の好きな詩語であり、そこには秘めたエロス(生=性)のエクスタシーの「記憶」が内包されているものだが、それをここではタナトス(死)のそれに変換して、雪崩自殺願望とその未遂という稀有のエピソードに物語化してゆく。……因みに、雪崩自殺なぞはそう簡単に出来るものではないのです……雪山の遭難でも雪解け頃に見つかればいいですがね……そうでなければ動物に腐肉を裂かれ……そりゃあ見るも無残な……断裂した遺体を晒すことになりますよ、おやめなさい、しづさん……
*
傲然と雪墜りケリーとなら死ねる
この句は「こころの體」の次の句であるが、「ケリー」の名を掲げていることと、前のシークエンスの自殺願望のエピソードに一区切りがついての「となら死ねる」と口をついて出た感懐と捉え、一句独立させた。この句稿では「ケリー」の名を詠み込んだものはこの一句だけである。そうして――そうして彼女がここでケリーを詠み込んだのには――ダンサー――舞姫――踊り巫女としてのしづ子の超自然的な予感が働いたのではなかったかと私は思うのだ――彼女は――この昭和二十六(一九五一)年十二月二十四日から昭和二十七(一九五二)年一月二日(次の大量句稿の日附)までの十日間の間に――ケリー・クラッケの訃報を受け取ったのではなかったろうか?――次の大量句稿の冒頭は彼の訃報から始まるからである――
*
そは抗ひ共産ごころすこし湧く
最後の方から三句。「共産ごころ」とは面白い語彙だ。しづ子の型に囚われない句屑蒐集は健在である。因みに、昭和二十六(一九五一)年十月に日本共産党は第五回全国協議会に於いて「日本の解放と民主的変革を、平和の手段によって達成し得ると考えるのは間違いである」との「五十一年綱領」を採択し、軍事闘争路線に基づく組織整備を進めた年である。しづ子の言う「共産ごころ」は、そのようなものとして解釈した時、俄然、しづ子にふさわしい句となるのである。
*
雪の昏れ燈さずにをく好みけり
「雪の昏れ」も一句を映像に撮りたい願望を刺激する言いっぱなしの主観句で、しづ子らしい。しづ子の句はしづ子というピアノ線の上で危うい琴線を奏でるものである。彼女の真似をしても、下手なヴァイオリンの耐え切れぬ騒音になるばかりである。
*
胸張ればいつさいは
「胸張れば」の句は句稿の最終句である。もし、ケリーの訃報がこの句稿やその前の十二月十九日附句稿以前に齎されていたとしたら――私はしづ子にこれだけ膨大な句稿を巨湫に送るエネルギーはなかったと思う。私はしづ子は優れたステップをドゥエンデによって生み出す霊力は持っていても、感情を抑制して巧妙な自己韜晦を演ずることなどは、いっかな出来ない人間だと思う。ケリーの死を慟哭一声も挙げずに、翌年の新年の句稿でそれを溜めておいて「演ずる」ことが出来るような卑劣な女ではない。だから私はケリー・クラッケの訃報をしづ子が受け取ったのは、この昭和二十六(一九五一)年十二月二十四日から元日までの九日間(訃報の当日に句稿を書く余裕は私ならないから日附である二日は外す)でなくてはならないと考えるのである(但し、この句稿最後に脱落があり、そこにケリー訃報の句があった可能性を排除は出来ない。しかし、新年の句稿冒頭の慟哭句は二番煎じとは私には思われないのである)。以前の鈴木しづ子に関わる記載ではこのケリーの訃報の報知やその遺品のしづ子への送付を昭和二十六年中としているものが多く、それに対する私の以前からの疑義にこだわって延々と述べてきた。――しかし実は、今気がついたのだが、既にそれには片がついているようである。最新のしづ子の年譜である川村蘭太氏「しづ子 娼婦と呼ばれた俳人を追って」の巻末の略年譜では、はっきりと年譜最後の昭和二十七(一九五二)年の欄の最初に、『元日、三重の伊勢神宮へ二年参り。帰宅し恋人のGIの訃報を受け取る。』と記されていたからである。これに気付かずに無駄なお喋りをしてきた私自身の愚かさを嘆くと同時に――いや、しづ子に「演技」など、やっぱりなかったのだ――という深い安堵が落ちた――私はそれだけで無性に嬉しかった――
◯鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年一月二日附句稿百五句より ケリー・クラッケ悼亡悲傷句群全二十一句
同句稿の巻頭二十一句を漏れなく採った。後半の数句は必ずしも亡きケリー・クラッケへの追悼哀傷に留まらないものを――しづ子が最も愛した第二次世界大戦で戦死した日本人の恋人への感傷の遡及を――感じるけれども、それはしづ子の愛の喪失という中で心傷(トラウマ)としての聖痕(スティグマ)として渾然一体のものであるから、私は敢えてそこまで採ることにした。「ケリー・クラッケ悼亡悲傷句群」とは私が仮に附した標題である。「■」は川村氏の判読不能の字を示す。
霧の洋渡り渡りきし訃報手に
霧五千海里ケリー・クラツケへだたり死す
訃報掌に霧もむら立つ體のほとり
こころの墓霧立ちのぼる人の死へ■
霧濃き中哀感そそる死びとの眼
地の果や霧に隱れし七つ星
嚙めば血潮は熱くとどろくかひなかな
かばね置く霧をへだてし東のかた
霧うすうす立ちてとどかぬものは距離
すべて總てがみをさめなりし霧月夜
霧月夜髮ふれしめし記憶もつ
黑人の哀しさ言ひし霧葉かな
圍ひなす霧中叫び得ざりしか
霧立てばこころしづかに狂ふ日つづく
葉の上に滴りしも愛の終止符
霧徐々に人の體とらへけり
屍すでに抵抗はなし霧濃き中
悲劇はこの世だけでいいスクリーンの白雪
まぼろしの霧の手袋片手に持つ
霧去りしこころの裡の水漬く屍
一つの屍茫々霧をへだてけり
次の一月十一日附大量句稿には「押繪羽子板」や「元旦の燈」が詠み込まれているが、新年の句はこの句稿にはない。総て「年の内」の句であり、「大晦日」を詠み込んだ句一句、末に並ぶのは「年越」句群五句である。恐らく、一月一日にケリー・クラッケの訃報を受け取ったしづ子は既に準備していたもっと後に送るつもりだった年内の投句稿の頭に、これらのケリー・クラッケ悼亡悲傷句群の衝撃を詠んだ句を急遽追加して、衝動的に巨湫に送ったものであろう(但し、一句だけこの後に追悼句と思われる「霧もむら立つ人死なしめしこころの裡」が混入している)。これを松の内に受け取る巨湫の気持ちなんぞを考えるゆとりなど、しづ子にはなかった――だからこそしづ子らしい――いや、巨湫にだけは――この慟哭のシャウトを聴かせたかった――聴くべき義務がある――としづ子は思ったのかも、知れない。
――この元日はしづ子にとってアンビバレントな日でもあった。――
この日、しづ子の真の意志とは無関係に、鳴り物入りで予告されていた第二句集『指環』が、随筆社から刊行されているのである。
ともかくも彼女にとって第二の人生を選択出来た、かも知れない、この句集出版の喜びも――このケリーの死によって、舞台の模造の雪片のように、儚く吹き散ってしまったかのように私には思われる――
◯鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年一月二日附句稿百五句の内 前掲ケリー・クラッケ悼亡悲傷句群全二十一句を除く残り八十四句より十一句
この頃や人の死つづく黃水仙
この句は先のケリー・クラッケ悼亡悲傷句群の最後と私がとった「一つの屍茫々霧をへだてけり」から三句目にあるが、この静寂と弛緩はケリー・クラッケ悼亡悲傷句群以前の句と私はとる。――黄水仙の花言葉は――私のもとへ帰って――愛に応えて――である。
*
人の子のお手玉縫ふて大晦日
私が冒頭のケリー・クラッケ悼亡悲傷句群を除く本句稿の下限を昭和二十六(一九五一)年十二月三十一日とする根拠の句である。
*
霧もむら立つ人死なしめしこころの裡
これが私にとって戸惑う句である。ケリー・クラッケ悼亡悲傷句群の「こころの墓霧立ちのぼる人の死へ■」の類型句であることは間違いなく、ケリーの死を、愛する者を守るべきであった自分を「死なしめし」と表現したものであろう。本句はしかし突如、日常の句家柄の間に挟まって登場する。言い訳がましいが私は、しづ子が投句句稿を清書する内に、「こころの墓霧立ちのぼる人の死へ■」の句を推敲し、ここに改稿を挿入したものという如何にも苦しい仮説でも立てるしかあるまいか。――しかし実際には私は、強引に見えるかも知れないが、「この頃や人の死つづく」と感じていたしづ子の、本句はケリーの死以前に死にかけたケリーやあらゆるしづ子の愛した死者たちに対するレクイエムとして詠んだ句だ、とおめでたくも信じているということを告白しておく。そしてこの句の十句後に続く三句を見てほしい。
霧もむら立つ麻藥求めてやまざりし
霧もむら立つ生きる屍とはうべなるかな
霧もむら立つ人と契らば末遂ぐべし
これは、「死んだケリーの回想」ではない――「霧もむら立つ」中から浮かび上がってくるあの人、「麻藥求めてやま」なかった、さもありなん、伝え聞けば今や祖国アメリカで「生きる屍と」なってしまったというケリー、でもそのケリーと私は契ったのだ! 「契らば末遂ぐべし」! 「ケリーとなら死ねる」! ――という一連の句群である。最後の句は文字通り、この前の句稿の「傲然と雪墜りケリーとなら死ねる」にジョイントする。則ち、「霧もむら立つ」という詩語はしづ子の中で、ケリーの訃報を受ける以前に、醸成し使用していた語彙なのである。さすれば、「霧もむら立つ人死なしめしこころの裡」がケリー訃報以前の句であったとしてもなんらおかしくない、というのが私の見解である。
*
寒雲に忌むや啄木と一茶殊のほか
寒雲に忌むやたつき貧しきことの詩
二人の詩人を詠み込んだ贅沢と、しづ子の句想を考える上で面白い句である。彼女は経済的貧困を訴えることを主眼とした詩を、それが期待する憐みや同情を忌み嫌い、生理的に嫌悪したということである。確かに、その反転画像にこそしづ子のポーズがあることに我々は気づく。
*
小説より詩へ俳句へわが三轉のひやこき手
……しづさん……あなたの詩は読みました……小説、読みたかったな……
*
吹雪く夜や裏返しをく壞れし時計
雪の中犬が動かす箱の蓋
時計は別れる際にもらったケリーの腕時計であろうか。なんだかヒッチコックのワン・シーンのようだ。こうしたモンタージュや編集は、まさにしづ子の真骨頂である。映像処理の観点からしづ子の俳句をヴィジュアル化してみる人は出てこないかな、きっと面白いと思うのだけれど。
◯鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年一月十一日附句稿百五句より八句
これだけの句数ながら、やはり全体に著しく力がない。拍子もぎこちなく、語彙の輝きも著しく減衰している。ケリーの死の心痛が伝わってくる。
*
迎年の死戰に生きし生命かな
「逝きし人に、かつては」という標題の冒頭句。ケリーへのレクイエムとして重厚できりっとした名句である。
*
暴れしあと月の有明死の如し
髮なびくここ月明の有明海
珍しい羈旅回想吟が現れる。有明海を詠み込んだ四句の内の二句。しづ子は過去に台風の直後の有明海を訪れている。
*
上流へ約八町の枯日かな
冬映えの木曾のみなそこ透る石
これも小さな旅。十数句続く木曽川での吟。何度も訪れているようで、句群の中には初夏の景を回想して詠じている。しづ子の好きな場所であったことが分かる。昭和二十六(一九五一)年十一月二十九日附句稿で採った「みなそこは冬のはじめの草と石」も木曽川と思われる。
*
ことし靑葉の頃こそ行かむ桃太郎の出生地
……しづさん、愛知県犬山市
*
頸根つく伊勢のかがり火凍てにけり
離るればあかつき闇のかがり火凍つ
川村氏略年譜にある、この元日の三重の伊勢神宮参拝を裏付ける句である。川村氏ははっきりと二年参りとしているから、しづ子は大晦日から出掛けていることになる。そして――この帰宅した元日に、しづ子はケリーの訃報を手にした――。「離るれば」は句稿の掉尾である。
◯鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年一月二十日附句稿二百十二句より (1) 二十一句
生理期の吾が頤を寒しと見る
炭つぐや吾が生理期の指纎う
生理期の吾が手冷やこき限りなり
「生理期」句全三句。こうした表明が文学的に忌避されることが当然の社会は未成熟というべきである。ホモ・サピエンスにとって、
生=性
であり、
性=生理
であり、
生理=生の実在
の認識であると言ってよい。そもそも、その最初期に女性のメンスを「生理」と日本語で表現した人間は、実にそうした真理を押さえていたとも言えないだろうか?――「纎う」は「しなう」(歴史的仮名遣では「しなふ」)で、個人的にはこの句がいっとう上手いと思う。
*
示されし盲腸すでに一個のもの
ついさっきまで肉体の一部であったものを厳粛に見つめるしづ子である。私の共感する一句である。
*
靑春は女人に短し寒菊黃
しづ子の著名な「たんぽぽ黃」でもそうだが、しづ子の句は、シナリオに於けるある技法と同じ効果を狙っている。一般に脚本家はカメラの指示をしてはいけないというのがカメラマンに対する一種の礼儀である。しかし、やはり作家の中にここはアップで撮って欲しい場面は必ずある。その場合の一つの「合法的な」手法に、対象を格助詞の「の」で繋げながらアップにしたい対象物を最後に持ってきて体言止めにするというのがある。しづ子はそうした技を生得的に身につけていると言える。読む者は「寒菊黃」は「寒菊」の黄色い花びら接写せずにはいられないからだ。
*
東京の雪か雪つけ本きたる
受取りし吾が手冷やこし詩の本
送られきし雪にしめりし句集の本
紙の上吾が詩ならぶ雪明かり
二句目の「詩」は「うた」と読ませるか。しづ子が自身の第二句集『指環』を手にした際の句であるが、そこには何らの浮き立つ思いは感じられない。寧ろ、総てが雪の冷気の中にある――しづ子の『指環』は既にして――雪の上に書かれた儚い絵文字なのであった――
*
霧の燈よおほかたの過去忘れたり
菊の雨むかしはむかしの詩もてり
先の「紙の上」の後、二句を挟んである句。これがわずか三十二歳にして第二句集を手にしたしづ子の正直な冷めた感懐であった。それはケリーの死が共時的なかったとしても――私は余り変わらぬしづ子の思いであったと思う。
*
冬芽立つ吾が戰前の戀憶ふ
かの雪の深き記憶や子どもごころにも
いまは昔雪に死したる人あまた
たしか吾が幼稚園の頃かの大雪
先の「菊の雨」に続く一句。『指環』という余所行きになって派手な衣装を纏わされた句集から、しづ子は『春雷』以前の、純情な乙女の時分に、少女の頃へと意識を遡る。それは伝説の「しづ子」の句集『指環』へのかすかな――自嘲――ででもあったかも知れない。この句の雪は「あの日」の雪である。次の句。
二・二六事件の雪と較ぶる癖雪積れば
――しかし、我々は気づいてしまう――しづ子は「しづ子」を最早、演じ続けねばならぬ宿命を背負ってしまったのだ……昭和十一(一九三六)年二月二十六日……この時、事実は彼女は幼稚園児ではなかった……淑徳高等女学校に通う十七の乙女であった……それにしても、この句の十三句後にしづ子は「この雪やかの大雪の日につづく」と詠んでいる……しづ子の戦後は戦前と直結していた……しづ子の戦後は永遠に終わらなかった……いや……今も……終わってはいない……
*
雪積むや東京を戀ふこころ持つ
追憶がしづ子を刺激した……しづ子の懐かしい東京への憧れが少し首をもたげた……
*
氣の強さ丑年生れ柚子は黃に
一葉の死せし歳過ぐ冷やこき手
誕生日東京に雪在る無しや
脈寒く二十七年經てきし手
「氣の強さ」の句は「丑年生まれ」が必ずしも作者と限定して読めないような流れでは作られている。因みに、しづ子は大正八(一九一九)年六月九日生まれで、生年の干支は己未である。しかし続く「一葉の死せし」でそれが限定される。樋口一葉は満二十四歳で亡くなっているから、この時、満で三十二歳のしづ子とは八歳違う。三十二歳で「一葉の死」んだ二十四歳を「過ぐ」とは、恥ずかしくて逆立ちしても言わないであろう。大正の丑年生まれは、乙丑の大正十四(一九二五)年である。――そしてしづ子の妹正子は大正十四年一月二〇日に生まれている。――正子は、この昭和二十七(一九五二)年一月二十日で満「二十七」歳、「一葉の死せし歳過ぐ」歳であったと言ってよい。――しづ子は妹の年齢を詐称していたのである。――それも「誕生日東京に雪在る無しや」と言い得る――一月二十日という誕生日――さえも――まるで――しづ子はマルセル・デュシャン!――
◯鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年一月二十日附句稿二百十二句より (2) 伊勢参宮志摩鳥羽遊覧句群七十数句から十句
この句稿中には七十数句に及ぶ、直近の伊勢参宮と伊勢志摩鳥羽遊覧の羈旅嘱目吟が並ぶ。しづ子にしては珍しく歌枕を散りばめ、ほとんどが素朴な写生句である。おそらく吟行帳にリアル・タイムに記したものをそのまま引き写したもののように見える。私がその句群の最初と最後(岐阜着)と考える句と他数句を示す(「御酒享けし」の「双」は正字にしなかった)。
初詣での人の中なる伊勢路かな
二つの宮へだて在すや白椿
御酒享けし双手冷え冷え裹みけり
冬の苑のみなそこ深く鯉呼べり
暴れあとの波立ち寒し夫婦岩
初日の出待つ掌の中の石一つ
鳥去りにし霧のふなばた冷えにけり
冬晴れやかちどきに似し波がしら
立てばここ驛は月下の陸の果
正月の旅をへにけり手の疲れ
「立てばここ」の「驛」は鳥羽駅、「陸」の読みは「くが」であろう。これだけの句を吟じて夜行で来て夜行で帰る二日の旅でこの膨大な句を記せば――これは確かに「手の疲れ」が目から鱗――しかし――久々の旅情を得て帰宅したしづ子を待っていたのは――愛するケリーの訃報であった――
◯鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年一月二十日附句稿二百十二句より (3) 伊勢参宮志摩鳥羽遊覧句群後から三句
炭火はぜはつと思ふや指纎う
菊さむしなきがらを見ぬ人の死へ
貌そむけ笑ひこらへし雪の松
伊勢志摩から戻った彼女は風邪を惹いて寝込んだ。勿論、そこにはケリーの死という衝撃も作用している。この部分の句は勿論、全体にトーンが低く、しづ子独特の生=性のエネルギが感じられない。それでも生きねばらぬ……笑わなければ……
◯鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年一月二十三日附句稿百四句より (1) ケリー・クラッケ・メモリアム・テキサス句群
ケリー・クラッケ・メモリアム・テキサス句群とは私のつけたもの。句稿の冒頭七句。総て採る。
テキサスの雪を言ひしが逝きしなり
テキサスの雪に埋もれし生家ときく
テキサスの雪に母をき逝きしなり
テキサスの雪に還りてより死せり
雪ふれりテキサスに置く一人の墓
魂還れテキサス想ひ哀しめり
◯鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年一月二十三日附句稿百四句より (2) 音楽句二句(音源リンク附)
雪深しラ・モローチヤを聽く眠りしな
この夜の爐火アンネンポルカ愉しく聽く
「ラ・モローチヤ」スペイン語《La morocha》は「小麦色の娘」の意。一九〇五年に発表されたエンリケ・サボリド作曲アンヘル・ビジョルド作詞になる著名なタンゴ。――ここで実際に聴きながら――しづ子の句を味わっては――いかがです?
「アンネンポルカ」《Annen-Polka》はヨハン・シュトラウス二世、一八五二年の作品。曲名は一般にはオーストリア皇帝フェルディナント一世の皇后マリア・アンナ《Maria
Anna von Savoyen》に捧げられたことによるとされるが、一説には彼が音楽家を志すことに反対した父シュトラウス一世に隠れて、こっそりと音楽修行をさせてくれた母アンナ・シュトライム《Anna
Streim》に感謝と愛情を込めて捧げられたとする説もある。――これは彼女を強引に支配した父俊雄と正反対であり、そんなワンマンな男の妻として苦労の中で死んでいった、しづ子の最愛の母綾子のことをも連想させる。尚且つ、この母アンナについてはその出自に諸説があり、宿屋の娘・料理店の娘・居酒屋の娘とも、先祖はスペインのジプシー(ロマ族)であるとか、いや、スペイン王国の貴族の末裔等々、様々に取りざたされている、まさにしづ子好みの女性であるとも言える。――ここで実際に聴きながら――しづ子の句を味わっては――いかがです?
◯鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年一月二十三日附句稿百四句より (3) 十句
霙るる葉此の國厭ふやむかたなし
ここまで読み進めてきた私には、やはり、その切実さの重量に於いてしづ子は寺山修司を遙かに凌駕していると思う。
*
射たれて死すといふマタ・ハリを讀む白薔薇に
上海へこころはしるや槻芽立つ
東洋といふ語の魅力槻芽立つ
讀む雪の十九世紀の血を憶ふ
「マタ・ハリ」芸名《 Mata Hari 》は本名《 Margaretha Geertruida Zelle 》マルガレータ・ヘールトロイダ・ツェレ(一八七六年~一九一七年)。パリのムーラン‐ルージュの人気ダンサー(高級娼婦の肩書を記すものもある)。マレー系オランダ人(「マタ・ハリ」はマレー語で「太陽」の意)。第一次世界大戦中、ドイツのスパイの嫌疑をかけられてフランス軍に捕縛、一九一七年十月十五日、バンセンヌの要塞で銃殺刑に処せれた。以後、女スパイの代名詞となるが、現在は冤罪に近いと考えられている。

「槻」は「つき」で欅の別名。私の想像であるが、しづ子は読むマタ・ハリの評伝から、東洋のマタ・ハリ川島芳子を連想しているのではあるまいか。そこで彼女は「美的裝束をして街を闊步した詩人」(梶井基次郎「檸檬」)になった――続く幾つかの句では、この今の状況下にあって、日本人として生まれたことへの嫌悪と忌避を露わにしている――
*
あらためて指紋とらるる霙るる燈
あはれ指紋すべての娼婦とられたり
ダンサーも娼婦のうちか雪解の葉
警察より戾る雪解の徑と橋
紙貼りて休業つづく一月盡
正月明け、何らかの違法営業行為や事件によって、しづ子が専属ダンサーとして勤めていたダンス・ホールが検挙されたのであろう。確かに彼女の勤めていたのは実質的にはダンス・ホールを表看板とした、半ば公然たる売春営業も行う店であったのであろう。但し、川村氏も子細に調査されておられるが、そうした慰安婦と、客を呼び込むためのホール・ダンサーは求人に於いても職務に於いても、厳密に分けられていた。何より、これらの句群を素直に読むなら、この事件を冷徹にドキュメントしているカメラマンしづ子が、娼婦でないことは一目瞭然である。手入れによって警察に一斉検挙されて、十把一絡げで否応なく連行されてしまったしづ子――指紋を採られる接待婦(売春婦)たちを見ているしづ子――そこで一律娼婦扱いで犯罪者の如くしづ子の指紋をも採ろうとする警官に対し、抗議するしづ子――しかし、所詮同じ穴の貉どもと罵倒され「ダンサーも娼婦のうちか」と溜息をつき、接待婦たちと一緒に釈放され、雪解の道を帰ってゆくしづ子……営業停止を受けた、人気のない、寒々としたダンス・ホール、その入り口の、休業の張り紙(ズーム・イン)……一月晦日の寒風が、剥がれかけた、それをパタパタと煽る……
◯鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年一月二十八日附句稿百句より (1) 二十句
雪の上雜魚を洗ひし水抛る
腥い水が、それも雑魚を洗った水が、バッと撒かれ、ヴァージン・スノーを瀆す――
*
こんこんと救はれ難き雪ふれり
常人にはカタルシス(浄化)であり、禊である、時空の経過と忘却のはずの、こんこんと降る雪も――今や、しづ子にとっては「救はれ難き」もの降れり――なのであった――
*
雪解けの書きてきたりし詐稱の名
詐称してきた名は何か? それは句集『指環』という「鈴木しづ子」という「女」の詐称ではなかったか? 「書きてきたりし」の「きたりし」は――もうそろそろやめにしよう、という感慨であり、「雪解けの」はダイレクトに下五「詐稱の名」を修飾する。――冷たい雪でデコラティヴしてきた詐称の名は、もうお仕舞いにしよう――ものとしづ子に戻るの――雪解けだわ……もし、そうだとすれば――しづ子は我々の前から永遠にその姿を消し去る凡そ九ヶ月も前に――私には、その「覚悟」が出来ていたものと見える――
*
この一夜遠謀失せし北斗凍つ
私はこの句を前の「雪解けの」句の同詩想のものと読む。実際に前句の三句後にある。「この一夜」自ら望んだ訳ではなく、しかし拒みもしなかった――『指環』の――娼婦の――転落の――エロティカルな――俳人「しづ子」――その「遠謀」に対して求心的にも遠心的にも――全天回転軸たる冷然とした北斗の如く、きっぱりと――冷徹にして厳然たる「ケリ」をつけるのよ、今夜――という覚悟として、である――
*
澄む穹や意氣地なき子も凧あげて
私は凧を揚げたことがない。揚がった凧を見上げた至福の思い出がない。ただ唯一の記憶がある。幼稚園の頃だ。新聞紙の長い脚を附けた奴凧をずるずると地面に牽きながら泣いている私の記憶――
*
生物の如く枯枝の日すさる
一方の井桁に置きし凍瓶
夏雲や以南の航路ゆるされず
風の中爪立ちて見るしんめかな
國若し寒さ中なる新芽吹く
冴返る唇紅がつく紙の面
小返る剃りて變へたる眉の形り
掌の上や悲喜失せしめし椿の葩
星とぶやいつさい棄ててはばかるなし
頭あぐれば星は星の光りもつ
屋の上を戀猫通る鏡中
大寒の甍の面や雨の跡
命沙汰持ちしことあり露けき手
われと吾が鼾おぼえし餘寒かな
蕗の薹吾ら一族失せにけり
私には――今の、ある心的状況下にある私には、というのが正しい文法だ――この句稿群に激しく共感するし、やはり、まさにここで、しづ子には大きな心理的な変化が起こっているとしか思われない。それ程に、使用語彙や詩想に、本来のしづ子のキレが鮮やかに戻ってきているのだ。
〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年一月二十八日附句稿百句より (2) 十三句
倶樂部在り春の雪ふる水ほとり
ひとごゑやストーブ燃えし四つの隅
品定めはじまるらしき雪ちらつく
品定めさるるに狎れし雪ちらつく
雪ちらつくみだらに了る品定め
倶樂部の奥寐室在るや雪ちらつく
ことさらに寒き寐室人を招ず
踊り場に靴がころがる雪夜なり
玻璃透りて雪がちらつく脱げし靴
靴脱げしジルバ續くや雪ちらつく
うす絹やハバネラ踊る雪ちらつく
連続する十一句を採った。今後、当たり前のことを二度とは言わぬ――
――「鈴木しづ子は娼婦ではない。ダンサーである。」――
しづ子の勤めるダンス・ホール――だから四隅にストーブ――しかし、今日の客の米兵はあたしとダンスを踊る奴は、いそうもないわ、あの眼――早くも接待婦の品定めが始まった――生と性に疲れて、ホステスの女たちは、もうすっかりその忌まわしい獣の視線に狎れきってる――みんなペアで奥へ行っちゃった――さて! じゃあ、雪のちらつく今夜は――しづ子の、誰もいないオン・ステージ――たった一人のジルバとハバネラ――
*
天暗く若死に以て星流る
春めく夜囘想の星失せしめぬ
……詮索はやめよう……しづ子だけの回想を……そっとしておこう……
〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年二月五日附句稿百五句より (1) 五句
ケリー・クラツケ亡し葡萄の種を地に吐く
「葡萄の種を地に吐く」のはしづ子なのだが、私にはそれがケリーに変貌する。その地に吐かれた葡萄の種は、みるみる蔓を延ばし、実をたわわにつける――私はこのしづ子=ケリーに、キリストを見る――
*
米人を父にもつ子ら雛まつり
雛の燈や黑人の子らよく育ち
雛まつるおほかたは父わからぬ子
このしづ子が訪ねている場所は、児童養護施設かそれに準じた宗教的な保護施設ではないか。米黒人兵と邦人女性との間に出来た私生児の子らを見つめるしづ子の眼。私は六年後昭和三十四(一九五九)年に創られる今井正監督の「キクとイサム」(大東映画)を思い出さずにはおれない。そのしづ子の限りなく優しい視線を、ここに読まずにはおれない。ここにはまた――遂にこうした子らの母になれなかったしづ子――いや、この子たちみんなの母にならんとするしづ子の――思いが裏打ちされているのではあるまいか。
因みに、この句稿投稿の前日、昭和二十七(一九五二)年二月四日午前零時、しづ子は岐阜駅で師巨湫と数分間の再会を果たしている。それは句集『指環』出版記念会出席の確認を巨湫がしづ子からとりつけるためのものだったとされている。しかし川村氏はこの束の間の邂逅にこそ、しづ子と巨湫の秘密が隠れており、しづ子の永遠の失踪の序曲の開始を意味する調弦があると推理されている。その文章の緻密さと冴えは、是非とも原書をお読みあれ。
〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年二月五日附句稿百五句より (2) さくら散る幼きときの羽化の夢
さくら散る幼きときの羽化の夢
これはもう――私好みの句――
〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年二月五日附句稿百五句より (3) 二句
もつとも奥營倉置くや冬めく葉
衛兵のマフラの白さ距て見る
これは昔、同棲していたケリーとの追想吟か。ケリーの朝鮮からの帰還後では季節が合わないし、こうしたことを体験する時間的余裕はなかったものと思われる。昔、何かの重い規律違反で営倉入りの懲罰を受けた彼に会いにゆき、基地でMPに拒絶された一コマか。若しくは、たまたま親しくなった当時のGIのエピソードででもあったのかも知れない。たった二句で物語を語る、しづ子の稀有の天分である。仮想の組み写真としても私は、書斎に飾りたいぐらい好きだ。
〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年二月五日附句稿百五句より (3) 四句
戀果てやさくら吹雪を羨しとも
思ひここに在らず櫻は花のまま落ちて
俤や浮きて流るる櫻の葩
ケリー・クラツケ亡し淀む水面に浮く櫻
時折り、しづ子に去来するケリー・クラッケ追懐句群の一つ。
〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年二月七日附句稿百六句より 七句
本句稿には豊川稲荷・豊橋・富士(愛知県側からの眺望)・知多の羈旅吟を多く含むが、残念ながらそれらに佳句は少ない。
*
みづ色の春の雪舞ふ衣なりき
句稿巻頭。昭和二七一月二十六日松村巨湫宛鈴木しづ子葉書。『お葉書有難うございました。お目にかかるのを楽しみにしてをります。水色の外套を着てホームの中程にをりますからさがして下さい。お氣をつけて行ってらしゃいませ。 二十六日 巨湫先生 しづ子』(川村蘭太「しづ子 娼婦と呼ばれた俳人を追って」三百三十七ページ所収)。先に記した昭和二十七(一九五二)年二月四日の岐阜駅での師巨湫との再会の句である。
*
春冷えの影長くして壺圓し
水仙ひらくひたすら圓き壺の中
銅版画のような印象を与える、清冽な陰影と質感である。
*
莫迦莫迦し蟬放たしむ指のひま
理屈には倦みし蟬ごゑじつと聽く
うち伏せばみなそこ浸る蟬のこゑ
蟬のこゑ木曾のみなそこ透りけり
蟬のこゑおのがいやはて想ひけり
私は蟬の句が好きなのである。
〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年二月十二日附句稿九十九句より (1) 五句
炎日はかなしからずや飛機の影
「飛機」はぎりぎりの用法であるが「機影」という語がある以上、無理とは言えない。これと「炎日」「影」の三つのエレメントに、「かなしからずや」という強烈な感性をぶつけてつげ義春の「ねじ式」の一コマであっておかしくない句である。
*
經だたればいっさい喜劇柘榴咲く
人間一人死して喜劇の柘榴咲く
地の上半ば食みたる柘榴打つ
小氣味よく刳りて棄てし柘榴の實
「いっさい」はママとした。この句群に放哉の「柘榴が口あけたたはけた戀だ」と三鬼の「露人ワシコフ叫びて石榴打ち落す」を紛れ混ませたい欲求に駆られる。それでしづ子の憂鬱は完成する――
〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年二月十二日附句稿九十九句より (2) 師巨湫刹那邂逅句群 二十一句
先に述べたが繰り返す。昭和二十七(一九五二)年二月四日午前零時、しづ子は岐阜駅で師巨湫と数分間の再会を果たしている。それは句集『指環』出版記念会出席の確認を巨湫がしづ子からとりつけるためのものだったとされている。しかし川村氏はこの束の間の邂逅にこそ、しづ子と巨湫の秘密が隠れており、しづ子の永遠の失踪の序曲の開始を意味する調弦があると推理されている。その文章の緻密さと冴えは、是非とも原書をお読みあれ。以下、その謎の師との刹那の邂逅を詠じたと私が判断する句稿末尾の句群、二十一句を総て掲げる。なお、しづ子と巨湫のこの再会は、巨湫の『樹海』昭和二十七年三月号の「内外抄」に載せた行動記録によれば『見違へる程きれいになつたしづ子と一分間ばかり逢った』とあり、川村氏は当時の時刻表を精査し、巨湫の乗った「銀河」の岐阜駅着が〇時十五分、〇時十七発で、正味二分間であったことを示しておられる。
通りまする師にまみゆべし驛霙る
如月の終車で着きし星きらめく
待つひまのをりをり雪を散らす穹
しろじろとミルクとかれし雪夜なり
みじろがず寒さ耐えしむ瞼うち
胸ぬちの貨車が過ぎゆく寒さかな
三たびほど雪夜の汽車を見過せり
星霽れの列車到りて止まりけり
雪が散るむかふの穹に星在りぬ
如月の星のきらめきまみえけり
窓に倚り星の明りに人さがす
雪つけど觸るるべからず御師の眉
再會を約す二月の星なりけり
雪の夜の御手に觸れたる握手かな
御手はづす如月の星きらめけり
距てゆく雪の明り貌とみし
如月を夜更けて歸る星在らぬ
間道を車驅けしむ霜夜の燈
い寐やらぬ一夜あかつき寒みけり
い寐やらぬ一夜霜の曉けにけり
俤は霜と白みて曉けにけり
――冒頭、師を待つしづ子、七句――国鉄岐阜駅。――「水色の外套を着てホームの中程に」師を待つしづ子。――霙が雪に変わる。――
――刹那の師との再会そして慌ただしい別れ、七句……一時、雪がやんだ……空の一角に星が見える――列車がゆっくりと入ってきて止まる……もう一度、見上げよう……雪が散る……でも……そう、確かに……私にはあの星が見える……あの「むかふの穹に」あの星は……在る……その「如月の星のきらめき」の中……私はこれから愛する、あの師と「まみえ」る……「窓に倚」って……あの「星の明りに」あの「人さがす」……先生……先生の眉に雪がついてる……でも「觸」れてはいけないの……そして……私は私の……秘密の覚悟を先生に告げた……そうして……そうして句集『指環』出版記念会の「再會を約」して……二月の私と先生……二人だけの秘密のあの星の下で……雪の夜……最後の握手だ……先生の暖かい手……いつまでも握っていたい手……でも、これが最後……握った手を「はづ」した……これもあの宿命の「如月の星」の「きらめ」く下のこと……
――別れての余韻、六句……暗闇へ消えてゆく汽車のテール・ランプ……その「雪の明り」の中に……先生の「貌」が「俤」となって浮かんだ……「如月を夜更けて歸る」私には、もうさっきの……あの「星」は……ない……もう、すっかり終わってしまった……それは……私が望んだ終わりの曲……「間道を車驅け」らせる……「霜夜の燈」が走馬灯のように背後へと消え去ってゆく……以前の私に私がさよならするように……帰宅して……「寐」むれぬ「一夜」「あかつき」が来た……とても……とても寒い……私の新しい夜「曉け」が……それは先生の「俤」をホワイト・アウトする……びっしりと強く真っ白に降り敷いた「霜の曉け」だった……
私はこの句群に現れる星を実際の星として見ていない。私はこの星を、『樹海』昭和二十五(一九五〇)年十一月号に載った、
明星に思ひ返せどまがふなし
の星であり、この星は、先に示した師巨湫との秘密の換喩であると感じている。
しかし、実際にしづ子は一瞬の雲間に実際の星の輝きを見、それをあの「秘密の星」と見たのかも知れない。さればこそやはり、その星は「そこに在る」のだ。最後に株式会社アストロアーツHP「AstroArts 星空ガイド」で再現された当日の午前零時の星座表を示しておきたいと思う。
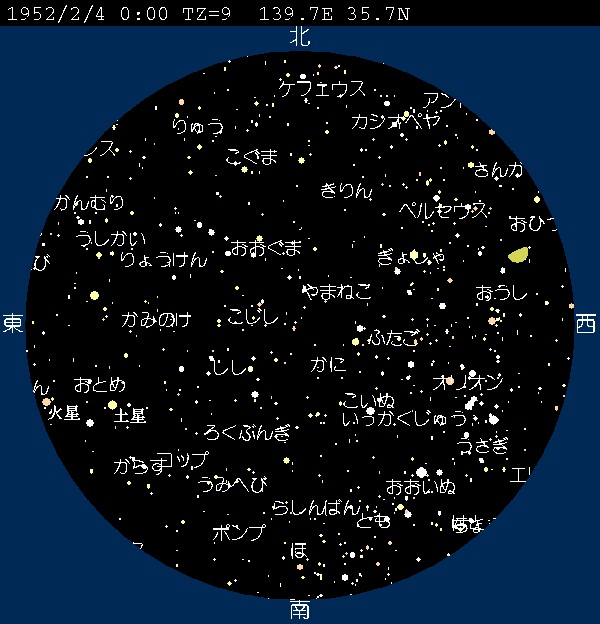
――ここにしづ子と巨湫の秘密の星は確かに「そこに在る」――
〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年二月十六日附句稿八十七句より 十九句
もう居ない此の世の人へ柘榴咲く
先の謎めいた意味深き再会を受けるなら、「もう居ない此の世の人」とは師巨湫その人であろう。
*
湯上りの冷ゆることなき十指かな
溫かき十指伸ばせば揃ひけり
放哉の「爪切つたゆびが十本ある」を想起させる句である。しづ子は恐らく放哉を、俳句を始めた早い時期からディグしていたと考えている。
*
月光らふいのち曝して惜しむなし
しづ子はしばしば「光げ」で「かげ」と読ませており、これは「影ろふ」の「かげ」で、「かげろふ」は光がちらつく、ひらめくの意である。ここでも「つき/かげらふ」と読んでいる可能性が高いのであるが、私は敢えて「つき/きらふ」という読みの可能性を感じる。同じく「きらめく」の意としてではあるが、但し、そのような動詞はないから造語ではある。しかし、音数律は保てる。本句の覚悟には、私は字余りが似合わない気がするのである。た句群の後半にも、
死してもよき常のおもひや月光らふ
とあり、上五は字余りである。しかしこれも「つき/かげらふ」と読むとなると、初句と下五で字余りとなり、如何にもリズムが悪い。私はやはり「つき/きらふ」と読みたい。
*
好き人でありしとおもふ時鳥
先の「もう居ない此の世の人」の句から六句目にあり、私はこの「好き人でありし」人も巨湫を指すと読む。さすれば、これは「よきひと」と「すきびと」の掛詞として機能するように私には読めるのである。
*
片親の憶ひは深し星祭り
七夕のメリンス帶をしめてもらふ
親憶ふ梅雨の簾を垂れしめぬ
とどむるは涼しき髮の母姿
これは明らかな追想吟であり、しづ子は傍観者ではなく、画題の七夕の少女はしづ子自身であり、「涼しき髮の母姿」はしづ子の母綾子としか私には読めぬ。「片親」とは、土木業者で留守がちであった父俊雄、母綾子を裏切り続けた(としづ子が感じ続けた)父俊雄を拒絶した成人のしづ子の感懐から仮想された思いととる。しかし同時にその少女の頃、実は大好きだった不在がちな父を、しづ子は愛していた。そのアンビバレントな表現が「親憶ふ」ではないか。しかもなお、今のしづ子の追想には母の孤独な「母姿」が浮かび上がるしかなかったのである。
*
酒嘔きて戀情も嘔く月凍る
宿酔句群九句の掉尾。
*
ひとつづつ節分の豆嚙みて碎く
ゆゑあるが如く節分待ちきしなり
節分句群の内の二句。節分の習慣からこの句は大きな意味を持つ。昭和二十七(一九五二)年の節分を、しづ子は「ゆゑある」が故に待っていたのである。――それは自身の半生を「ひとつづつ」一歳ずつ、覚悟を以て「嚙みて碎く」覚悟ではなかったか。――
*
雛の夜のたがひ引き合ふ喧嘩の髮
泣きじやくる負かされし手の雛あられ
混血の幼きものよ桃の花
連続する雛祭り三句。二月五日附句稿でも同じ句群を揚げたが、これも同じ場面を詠んだものである可能性が高い。しかし私は、しづ子は頻繁にこうした混血の児童や孤児を保護した施設を訪ねていたのではなかろうかという気がしている。そこには亡き黒人兵ケリーへの思いが裏打ちされていたには違いないが、私はしづ子の失踪の彼方の一つに(若しくはしづ子のこの後の将来設計の一つの選択肢にと言ってもよい)、こうしたかの「サンダース・ホーム」のような児童養護施設を想定し得るような気がしてならないのである。
*
雪ちらつく水のほとりのアースの線
吹雪かれて切れしを繼なぐアースの線
これはもしかすると直前にソリッドにある飛騨の温泉での嘱目吟であるのかも知れない。温泉の電気器具のアース線が、しづ子の眼に止まった。私の深読みであろうが、しづ子のこのアース線への視線がひどく気になる。地に総てを流して、総ての電気を流して感電することを避けるためのアース線――あらゆるリスクを回避する地にむすぼれた線――これはしづ子の決意と同じではなかったのか?!
*
ひとあらぬ體ぬちめぐる霧笛かな
ナ行音を配した空疎な殺伐とした本句を以て、本句稿の抄出の最後とする。
〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年二月二十一日附句稿九十四句より 五句
濃しといふ女帝いたゞく國の霧
葉の上に春の露をく貴族の死
句稿巻頭句二句。この投句の十五日前の二月六日、イギリスでエリザベス二世がイギリス連邦(イギリス王国十六箇国)女王元首にしてイギリス国教会首長に就任している。彼女はしづ子より七歳年下で、満二十七歳での即位であるが、これはしづ子が詐称した年齢にほぼ等しい。後の句は一句目とは無縁な本邦の貴族の死かも知れないが、組句ととるなら、同じく二月六日の夜、冠状動脈血栓症で急逝したエリザベス二世の父イギリス王ジョージ六世ととることも可能である。五十六歳であった。
*
露けさの吾が室が待つすべての夜
本句群の前半は、既句の改案がひどく目立つ。孤独な自室に戻るというシチュエーションも既出モチーフであるが、これは一読、下五が鋭い。
*
リトマス紙はさむ餘寒の指のひま
雪の日のリトマス試驗のこと憶ふ
この二句、聊か気になる句ではある。現在でも妊娠検査にリトマス試験が有効がどうかを問う質問がネット上に散在する。勿論、リトマス試験紙では分からないのだが、今でさえ、そのような認識があるとすれば、しづ子の持つリトマス紙は、そのようなものとして示されているととられても致し方あるまい。但し、二句目では、この「リトマス試驗」が過去の事実として扱われており、これが女学校当時の雪の白き景色の中の化学の実験での、鮮やかに色の赤く、青く変わる様の不思議を追懐して素朴に詠んだとしても決して可笑しくはない。しかし、例えば、仮に前の一句のみが撰されれば、これはもう、私の言う『俳句の病い』を逆手にとったとも、しづ子「伝説」への確信犯の思わせ振りの句とも言えよう。
*
寒き夜の卵割らしむものの角
下五「ものの角」の喝破にしづ子らしさがある。いい句だ。
〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年二月二十六日附句稿百七十三句より 十二句
のこぎりの刃形りのふちをもつ冬葉
「刃形り」は「はなり」と読ませるのであろう。ハ行音を効果的に用いて、一見した際の視覚的な印象の韻律の悪さが、詠むことで美事な定型句に変貌する。しづ子の句にはこうした仕掛けもある。
*
見えぬ浪のおとのひねもす菊咲けり
本句群に多数見られる知多での羈旅吟の一句。浪を直接見せずに、時空に日がな一日充満するSEとし、菊をアップにする。
*
鳰を見るひとにをしふることもなく
芭蕉の「五月雨に鳰の浮巣を見にゆかん」をインスパイアするに、鳰(歴史的仮名遣では「にほ」)の音に「にを」を掛けた諧謔性の割には、元の句の浮き立つような風狂のときめきの諧謔が、「をしふることもなく」の言辞によって急速に醒めてゆく。そこを狙った部分を買いたい。私は好きな句である。
*
博徒らし日向まぶしく人待つか
ハレーション気味の映像と、「博徒」のイメージの反社会性・孤立性が句全体の渇きや埃っぽさを強化しつつ、それを見るしづ子の「らし」と「待つか」という推測と疑問文が、逆に博徒としづ子の遠心的紐帯となって立ち現れる。
*
吾が簷に月のひかりの氷柱もち
「簷」はしづ子の好んで用いる字で、私は一貫して「のき」と読むことにしている。「月光」もしづ子偏愛の詩句で、「吾が」が既にして現実のしづ子の住む家のそれにあらざる――しづ子の孤独な心の軒下に冷厳ときっぱりと垂れ下る月光自体が凍てた哀しき氷柱が――私には――見える。
*
蝶よかのたむろなす花まで行け
「蝶よ」は萩原朔太郎のように「てふてふよ」と読みたい。「たむろなす花」の語の選びが美事な俳諧となっている。「てふてふよ/かのたむろなす/はなまでゆけ」の方が、「てふよかの/たむろなすはな/までゆけ」の下五の腰砕けの字足らずよりも遙かに至上の厳命として強靭に響くからである。
*
冬がきて必殺の獨樂放ちけり
子らの遊びを見るしづ子の眼はいつも母性に満ちた優しさに溢れている。少年の「必殺」の声が、独楽のブン! と飛ぶ音とともに聴こえてくる――
*
器中一夜浸せし春の貝
これも漢字マジックである。――「うつはなかひとよひたせしはるのかひ」――総ての詰屈な感じが和訓となる時、えも言われぬ快いハ行音を意識した調べとなって伝わってくる。デッサン画のそれに淡い貝の色を水彩で少し色を塗ったところだ――。ところが……しづ子を鵜の目鷹の目で垂涎して舌なめずりするエロ俳爺いにとっては「器」「中」「夜」「侵」「春」「貝」の文字の色が猥雑に反転する。そもそもが、しづ子でない女流俳人の句であれば、これをそのようなあぶな絵として誰一人見ないはずである。これが「しづ子」の「不幸」である。しかし伝説の「しづ子」の内には「幸」は不要なのである。――「しづ子」の不幸は「しづ子」の「功」――「しづ子」の不幸は「しづ子」の子――「しづ子」としづ子は似て非なり――「しづ子」はしづ子ぢやありません――
*
笑ひたき夢の記憶よ白木蓮
「しづ子」は笑うことも許されない。余りにも「しづ子」は深刻過ぎる。本当のしづ子の笑顔は、あの昭和二十三(一九三八)年の木曾川犬山橋河原で撮った叔母と妹夫婦との写真のように、健康で美しいのに――
*
ふつと氣が變りしときの鵙高音
これは鵙の地鳴きを詠んで素晴らしい。私なら一番に歳時記に採る。私は歳時記を認めないがね。
*
寒浪の去にし陸をば哀しめり
上句に「寒浪」を被せる十九句の掉尾。「陸」は「くが」と読みたい。如何にもな垂直的語句交換で苦吟しているが、響きといい、力といい、詩想といい、最後に至って美事にアウフヘーベンしていると私は思う。
*
吾がものとおもひこそすれ紙の雛
失礼――私は雛人形が好きなのである。私には子はないが、御殿附きの七段飾りを毎年飾るのである。
〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年二月二十六日附句稿百九十七句より 三句
吾が忌みしよべの秋蛾のあほむき死す
私は如何なる海産無脊椎動物をも忌まわしく思わない代わりに、殆どの陸生昆虫類を忌避する。しかし、しづ子と同じ程度には、彼らの死に哀れを感じる点に於いて、しづ子と感応するものである。
*
いまぞ識る歳時記による虎※笛
底本では「※」=「木」+「尤」であるが、このような漢字はない。これは「虎落笛」の誤字であろう。この句は「虎落笛」を結局、使わないしづ子がいて、それ故に「歳時記による」詩語が無効であることを、しづ子は言っているのである。歳時記を『俳句の病い』として一番忌まわしく思う人間である私が、如何にもな歳時記風に「虎落笛」を書いてみようと思う。私は歳時記なるものがあるとすれば、それぞれの個人の歳時記を、自分自身のみが納得する歳時記を創るべきだと思っている。以下の説明の後半部は、そんな「虎落笛」の歳時記を目指してみた。にしても――虎落笛の名句は少ないね――
〇虎落笛 〔読み〕もがりぶえ 〔季節〕仲冬を主に三冬(十二月を主に十一月から一月の期間)
冬の寒風が竹の切り株・柵・竹垣及び建物や戸板・窓、現代なら電柱・電線・看板などに激しく吹き当たって時に高く時に低くヒューヒュー、蕭々と鳴ることを言う。物理学的にはエオルス音《Aeolian Tone》と呼び、主に柱状物体の風下左右両側に、カルマン渦という逆向きの渦風がつぎつぎと発生しては離れていく、その際の円柱表面での振動が空気中を伝わって音となったものを言う。鞭の音もこれである。「エオルス」はギリシャ神話の風の神の名。「もがる」の語源は不詳。一説に「刺(とげ)」を意味する「棘(いが)」の動詞化した「いがる」が「んがる」「むがる」「もがる」と転訛したとする説や、幼児が欲しいものをねだって駄々を捏ねて泣き叫ぶ様子を形容したものに由来という説があるようである。私はてっきり貴人の遺体を一定期間保存して再生を図る「殯(もがり)」を語源とするのかと思いきや、無縁であるようだ(こちらは「喪上がり」が語源に仮定されている)。「もがり」「もがる」という古語の動詞は「虎落る」以外に「強請る」などとも書き、①異議申し立てをする、逆らう。②言い掛かりをつけて金品を巻き上げる、所謂、ゆすりたかりの行為を言うが、丁度、唇を尖らして笛を鳴らすようにする嘯く動作が、不平・不満を述べることに通ずることによるものであろう。さすれば「もがりぶえ」という自然現象への呼称はそれよりも後の成立であると考えられる。「虎落」は、本来は軍営にあって竹を組んで柵とした矢来としたものを言い、中国で、通常の木ではなく竹で組んだそれは虎もよじ登れないことに基づく虎避けの柵、従って当て字である。後には竹を立て並べた紺屋などの物干しをも指すようになった。小学校五年生の頃、TBSで昭和四十二(一九六七)年十月十七日~翌一九六八年一月九日の火曜夜九時から九時三十分に放映されていた「木下恵介アワー」の江原真二郎のドラマ「もがり笛」は、もうすっかりストーリーを忘れたものの、各回の最後にもがり笛を読み込んだ俳句か和歌がテロップとともに示されていたのを覚えている。それが僕の「虎落笛」の初見だった。僕の年齢では早い方だろう。亡き母も私も好きなドラマだった。ドラマ様々だ。その後のこと、時代劇の「子連れ狼」で、名人が相手の首筋の動脈を上手く斬った際、血を吹き出しながら音が鳴る、それを虎落笛と呼ぶ、という話柄があった。果してその呼称が江戸期の事実であったかどうかは知らない。知らないが、私は授業でしばしばそれを語った程には、危ない気に入った話ではあった。音韻のおどろおどろしさでは、いい詩語ではあるが、私は使ったことはない。
虎落笛眠に落ちる子供かな 高浜虚子
虎落笛子供遊べる声消えて 高浜虚子
一汁一菜垣根が奏づ虎落笛 中村草田男
夕づつの光りぬ呆きぬ虎落笛 阿波野青畝
モガリ笛いく夜もがらせ花ニ逢はん 檀一雄
いじわるな叔母逝き母に虎落笛 金子兜太
ふたたびを俺達は死ぬ虎落笛 鈴木六林男
もがり笛よがりのこゑもまぎれけり 加藤郁乎
もがり笛風の又三郎やあーい 上田五千石
樹には樹の哀しみのありもがり笛 木下夕爾
*
その一つややこしくして冬の季語
しづ子には歳時記がいらない。ということは季語がいらないということである。しづ子は季語とされる詩語を季語として用いていない。しづ子の季語はしづ子の感性が独自に、その句の中でのみ規定される。そもそも、いみじくもこの世に存在するあらゆる言葉は季詞ならざるはなし、と言ったのは芭蕉である。因みに私も、季語を意識したことはない。
〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年三月四日附句稿三百五句より十二句
春愁の紙風船に息を詰め
春の夜の紙風船を疊めば反る
春の夜の天井觸るる紙風船
ぼんぼりに燈が入るころの双つ雛
火めぐりの灰を馴らしてただそれのみ
日永さの目立つばかりのなんてん葉
春燈下肉商人の指を缺く
空箱に絲など容れて春めくか
くりかへす子をとろ遊び夏はじめ
玻璃の面の蜘蛛は平たき餘寒かな
蟬しぐれ人を追ひ死すこともある
喪の家の沈丁匂ふ柵のうち
膨大な句稿であるが、アンビバレンツがなく、力の抜けた平板な句が多い。そうしたダルな雰囲気の中の垣間見た視線の、私の琴線が以上の十二句。最後の「喪の家の」は、句稿の掉尾で、柵の中に沈丁花を植えた或る棲み古した家を舞台に、家人が病いとなり、医師が向かい、死の家となる、アッシャー家の没落風の十七句連作の終曲句。連作としては興味をそそるが、一個の句としてはどれも今一つ。
〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年三月五日附句稿二百十六句より七句
前句稿の翌日附のものであるから、やはり雰囲気は変わらない。しかし、東大寺二月堂の修二会のお水取り前の雰囲気、岐阜県羽島郡笠松町の笠松競馬場の三月競馬、美濃・木曾路・中仙道の春景色といった羈旅吟行を並べ、寒竹を切る十六句などをひたすら詠じたりして、詩想の停滞を必死に打開しようとしている感じがする。一茶は嫌いと言っていたしづ子だが、子らを詠んだ一茶風の句群が私には光って見えた。因みに、原本のものとも判読の誤りとも区別し難いが、「みふそこ」×→「みなそこ」〇、「かふ」×→「かな」〇、「糖」×→「糠」〇など、底本のこの部分、かなり誤字と思われる箇所が多い。
*
仲良しになつて夕燒け濃かりけり
蟬生れてこころの平和放すまじ
花桃やよくぞさへづる子らのくち
それし手の毬がころがるたんぽぽ黃
春晝のいつかやみたる手毬唄
冷やし水喇叭飮みして遊びに去る
斜め日や詠ふに難き梅の花
〇鈴木しづ子 三十二歳 『樹海』昭和二十七(一九五二)年四月号掲載句全十一句
昭和二十七(一九五二)年三月四日附句稿及び三月五日附句稿を元にして選句された『樹海』昭和二十七(一九五二)年四月号掲載句全十一句を掲げておく。珍しく私の撰とかなりダブった(参考までに私の選んだ句の下に〇を附した)。
春愁の紙風船に息を詰め 〇
火めぐりの灰を馴らしてたゞそれのみ 〇
日永さの目立つばかりのなんてん葉 〇
空箱に絲など容れて春めくか 〇
啓蟄の藪を透して見るひかり
くりかへす子をとろ遊び夏はじめ 〇
やすかれと希ふばかりの霧笛かな
踏めば消ゆむかしの都の奈良の雪
仲良しになつて夕燒け濃かりけり 〇
手をのべてスタンド燈す黃水仙
蟬しぐれ人を追ひ死すこともある 〇
「踏めば消ゆ」と「仲良しに」の句は三月五日附句稿から。それ以外はその前の三月四日附句稿に基づく。なお、これ以降の『樹海』の掲載句には、このように、最新の投句稿と、これ以前の句稿からの混合採句がしばしば見られるようになる。
〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年三月八日附句稿二百十六句より(1) 四句
忌むかぎり狂ふ燈蛾と人の貌
凄絶な語彙選択の勝利だ。
*
吹かれつつ春日の中のひとりかな
春冷えの吾が室ならぬ中にゐる
春林の徑たゆるまで行くべしと
杉田久女の、「蝶追うて春山深く迷ひけり」がオーバ・ラップする。だが、もうこれは、インスパイアではない。――久女のそれは、私にとっては、句よりも後年の映画、ロバート・アルドリッチ監督の「何がジェーンに起こったか?」(一九六二年アメリカ)のベティ・デイヴィス演じるジェーン・ハドスンが、ラスト・シーンで海岸で踊る姿を髣髴とさせる。久女が後年、精神を病んだように。――しかし、しづ子の春日の中の姿は、毅然としているのだ。彼女は春の林の中にいる。そこは「吾が室ならぬ中」でありながら、しかもしづ子が「ひとり」屹立する地平である。しかししづ子はその春林の「徑たゆる」地平の果てを目指す覚悟なのだ。則ち、しづ子は「迷」ってはいないのだ。しづ子はきっぱりとした明晰にして冷徹な覚悟の中で、春の林を突き抜けて「ひとり」「行くべし」と言い切る。――私はこれらの句に恐ろしいまでのしづこの覚悟を見る――それはKの破滅への、死(タナトス)の「覚悟」を、では、ない――しづ子の生(エロス)の、強靭な激り、のそれを、である――
〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年三月八日附句稿二百十六句より(2) 一句
耳覆うすべもなかりし霧笛引く
回想のケリー・クラッケ訣別句であろう。これはもう、ジュリアン・デュヴィヴィエ監督の「ペペ・ル・モコ(望郷)」(一九三七年フランス)のエンディング――しかし、しづ子の神話では人物が交換する――しづ子はギャビーじゃない――しづ子は――ジャン・ギャバン演じるペペなのだ――
〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年三月八日附句稿二百十六句より(3) 四句
手にとればなにもなかりし熱砂かな
掌の熱砂砂漠もたざる國に生れ
思を凝らし熱砂の砂漠描かしむ
熱砂敷く沙漠ありせばありとせば
句稿の中に突如現れる沙漠の砂の句四句である。最初の三句は連続で現れ、二句挟んで最後の句が出る。私はこれをケリー・クラッケ追悼句群の一つと見る。この頃、ケリーの母からケリーを埋葬した地の砂がしづ子に送られて来たのではなかったか?(川村氏らの著作によって、この前後にケリーの遺品がケリーの母から送られてきたことは確かである) また、昭和二十七(一九五二)年一月二十三日附句稿百四句にあるケリー・クラッケ・メモリアム・テキサス句群から、ケリーの故郷はテキサス州にあったことは確実である。ところがテキサスというと、たいして西部劇の洗礼を受けていない私などでも「パリ、テキサス」などで今も砂漠のイメージが強いのだが(脱線だが――私がかつて勤務したとある学校では「学校内の僻地」という意味で、平然と教員さえ校内で最も離れた特別教室を「テキサス」と呼称していた。私はそれに強い違和感を覚えた。生徒に、「それじゃあそこをネパール、東北、と呼ぶことにしたらどうだい?」、「うちの姉妹校で訪問して来たアメリカの高校生にテキサス出身の学生がいて、何故、テキサスなのかと質問されたら、あそこはカントリーだからさ、と言えるわけだ?」と挑発もした。教員がその呼称を用いるのはやめるべきだと職員会議で意見も述べたが、同僚からは鼻でせせら笑われただけだった。多分、今も相変わらず用いられていることであろう。それが我々日本人の人権感覚のお粗末な正体なのである――)、実は沙漠地帯はテキサス州の十%足らずしかなく、かなり地域が限定されるのである。チワワ砂漠と称するこのテキサス州南西部国境域周辺の――メキシコや南部のデキシーと西部開拓時代の人種混合した文化の、不法入国者が絶えず、現在でもアメリカでは極めて経済的に厳しいこの地域の――どこかに、ケリーの故里はあったのではあるまいか? ケリーがどんな人物であったか、僕らは最早、追跡できそうもない。しかし、私は、私なりにケリー・クラッケを私の中にブロマイドを創る。そうして、しづ子が愛したケリーを、私も愛する。――でなければ、しづ子のケリー・クラッケ句群を語る権利はない――いや、そもそも、しづ子の句を語る資格はない、と、私は本気で思うからである。
〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年三月八日附句稿二百十六句より(4) 三句
雪の夜の更けゆくばかり女人の居
居めぐりの昏れゆくほどの雪の增え
欝々と穹は在りけり雪怺へ
実はこの句は数句の前がある連作句で、その前の句群では、しづ子の家にある人物が訪れ、しづ子が聞きたくもない愚痴や嫌味を言い放題にして、雪の中をその人物が帰ってゆくまでが描かれている。その後の、一人になった後の三句(最後の句は翌朝か。若しくは全く異なる詩想に基づくものかも知れないが「欝々と」が明らかに前の連作を引きづって読めるところから敢えて採った)。「怺へ」は「こらへ」で、堪えるの意。煩瑣な下劣な日常の、如何にも愚劣極まりない事柄が、しづ子の孤独をいやにも掻き立てるさまが、如実に伝わってくる。「欝」の字はママ。
〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年三月八日附句稿二百十六句より(5) 十句
春の日の草履袋を振りつつ振りつつ
ランドセルがたごと櫻とつても綺麗
下校時櫻折つてはいけません
先生に言ひつけよつと晝櫻
先生と踏切りを越え晝櫻
驅けて驅けて下校の櫻吹雪かしむ
晝櫻町角に言ふさようなら
簷に葉に春日さんさん坊やはいくつ
復習はもう済みました晝櫻
お八つ頂戴さくらが散つて散つてきて
新春の陽射し、桜並木の中を駆けてゆく子ら、しづ子の優しい視線に満ちた句群である。これは連作として読むとき初めて、彼女の限りない慈悲の眼が、分かってくる。これは単独句では決して伝わらない。今、私は、しづ子の俳句は独自の連作句法の観点から、再評価されなければならないとしみじみ思う。ここは総て表記をママでとった。「復習は」の「済みました」は当時の小学生の気持ちになり(新字体表記を公用とする「当用漢字表」の公示は昭和二十一(一九四六)年十一月十六日)、正字にしなかった。以下、百三十六を残すが、私の琴線に触れるものは、残念ながら、ない。
〇鈴木しづ子 三十二歳 『樹海』昭和二十七(一九五二)年五月号掲載句全十二句
ことごとく人失せしめし霜の石 (三月八日附)
地に置くも置かぬも古葉としての形り (三月八日附)
地の薪のいぶるかぎりをいぶらしむ (三月八日附)
春の日の草履袋を振りつつ振りつつ (三月八日附)
ランドセルがたごと櫻とつても綺麗 (三月八日附)
驅けて驅けて下校の櫻吹雪かしむ (三月八日附)
いさぎよく切られてしまふ寒の竹 (三月五日附)
寒過ぎの氷が混じる落し水 (三月五日附)
この菊は半ばひらきてやみたるなり (三月一日附)
埋火のいまもひたひた燃えてあらむ (三月一日附)
疑へば疑はしくも簷氷柱 (三月一日附)
あるだけの卵をゆでる春の晝 (三月一日附)
各句の後に示したのが、採られた句稿の日附である(総て昭和二十七(一九五二)年)。前の私の撰した子らの句群と、そこから抽出してしまったここでの三句の印象の違いは明らかであろう。組写真のスラーな連続が断ち切られ、最早、モンタージュでさえなくなった、ばらばらの痩せた句になってしまっている。
〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年三月十一日附句稿百六句より(1) 五句
母の日の甘藍の皮剝がし次ぎ
「甘藍」は恐らく韻律からいって「かんらん」と読ませている。キャベツのこと。中国語名由来。
*
寐る四肢のうづきは悲し毛布觸れ
いのちよし薰風の竹立つかぎり
これは何らかの高熱を発する病床での吟と、その回復期の一句ではあるまいか。私は若き日に山水を飲んでA型肝炎に感染し、高熱とγGTP二〇〇〇という肝機能振り切れ状態を体験したが、その時、横臥している敷布団に触れている部分と、毛布の掛布団が触れている四肢が、千山を押し付けられたかのようにうづいたのを忘れられない。
*
花を見るそれでも夢をもつてゐる
「しづ子」伝説には、こんな素直な句はあってはならないのに違いない。巨湫は遂にこの句は採っていない。しかし、彼が真にしづ子を語らんと欲せば、失踪後も、急句稿からあたかも投句され続けているかのように『樹海』に句を掲載し続けた巨湫にして、私は最後にはこの句を採らぬのはおかしい思う。いや、葬られずに残っていたことだけでも巨湫に感謝すべきか。
*
水仙やあかつき點す雨の音
水仙は室内の生け花一輪がいい。でなくては「雨の音」が生きない。「あかつき點す」は、暁の真っ暗な室内に白く浮かんだ水仙の花を、燈火に喩えて点(とも)しているのである。
〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年三月十一日附句稿百六句より(2) 亡き母へのレキエム句群より十五句
終焉や地に影おく林檎の木
花林檎かつては疎開つづかしめ
花林檎双親つとに失せにけり
銀漢や失せて總ては戰爭中
母死なせし林檎花もつ北の方
花林檎咄嗟の泪もたざりけり
雪解けの續く限りや明里町
冬苔やおのが識りゐし一つの死
踏切や母には難き炎天下
出生を忌むがばかりに寒牡丹
夏蟬やむかし母には冷たかり
濡れ初めの石の面てや冬の苔
春雨にひとしく濡るる石の面
母死なせし靑き冬苔濡るる中
枯れの面や綾子之墓と母に書けり
「終焉や」に始まる三十数句に及ぶ亡き母へのレクイエム連作から。これらから、しづ子は母の逝去の地をこの句稿直近に訪ねていることは確実であると思われる。
「花林檎かつては疎開つづかしめ」はしづ子の「しづ子」のための句。年齢詐称のためには、「しづ子」は戦中に疎開をしていなくてはならない年齢であった。但し、「疎開」という言辞そのものが更に虚構であって、川村蘭太氏の「しづ子 娼婦と呼ばれた俳人を追って」によれば、昭和十六(一九四二)年の夏に母綾子が病に倒れ、その転地療養のために一家で福井県福井市に転居している。そして更に虚偽があって、この時、しづ子は一人、東京に残ったのである。
「花林檎双親つとに失せにけり」も事実ではない。しづ子の母綾子は昭和二十一(一九四六)年五月十五日に亡くなっているが、父俊雄は、この時、未だ健在である。以前にも記した通り、さんざん綾子を苦しめた父俊雄が、昭和二十三(一九四八)年に、母綾子の生前から関係があった女性と再婚したことに対して激しい嫌悪感情を持っており、しづ子にとってかつて尊敬した父は、今や完全に死んだ存在であったのである。林檎の花の花言葉は「名声」「選択」「評判」「選ばれた恋」である。
「雪解けの續く限りや明里町」川村氏の略年譜では綾子の逝去の地を「福井県福井市明王町」と記すが、この句の「明里町」が正しいものと思われる。現在の北陸本線福井駅の西方二キロ弱の現在の福井競輪場近くに位置する小さな町である。
「出生を忌むがばかりに寒牡丹」の主語はしづ子自身であろうか。とすれば、愛する母と同じように、愛に恵まれなかった自分の出生への呪詛となる。寒牡丹の花言葉は「高貴」。
〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年三月十一日附句稿百六句より(3) 虫二句
この星の浮塵子の如く家郷なし
「浮塵子」は「うんか」と読む。カメムシ目ヨコバイ亜目Homopteraに属するセジロウンカSogatella furcifera、トビイロウンカNilaparvata lugens、ヒメトビウンカ Laodelphax stratella などの総称。稲の害虫とされ、時に大繁殖し、それが大群を成すことから「雲霞の如き」という語が生まれ、通称名となった。但し、「ウンカ」という和名の種はいない。なお、あまり認識されていないが、彼らはヒトを刺す。吸血するわけではないが、人によっては激しい炎症を起こす。侮らない方がよい。
*
吾が指のてんたう蟲の越えし節
しづ子には昆虫や蛛形類の句が多いが、その接し方は鬼城より遙かに西欧近代的個人としてクールである。それが一種の気障な作為性を感じさせることもあれば、逆に斬新な心象として読む者をして激しく共感させることもある。因みに私はこのイメージ・フィルムのような一句が好きだ。
〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年三月十一日附句稿百六句より(4) 三句
それのみの鷄頭起つや茜中
鷄頭花憎しみさへも失せゆけり
鷄頭花父を一人の男とも
父へのアンビバレントな感覚が変容してゆく。川村蘭太氏の「しづ子 娼婦と呼ばれた俳人を追って」によれば、しづ子は父俊雄にとって自慢の娘であり、顔つきや性格的にもしづ子は父と似ていると言う。青春期のしづ子は、そうした父を寧ろ自慢にしていたらしい。また、その理想に応えるべく、父の命に従って進路を選んでもいる。しかし、先に述べた通り、その後、ワンマンでさんざん母綾子を苦しめた父俊雄が、昭和二十三(一九四八)年に母綾子の生前から関係があった女性と再婚したことに対して激しい嫌悪感情を持つようになった。それがここに至って、何を理由とするか不明であるが(もしかするとそれはしづ子にも不明であったのかも知れない。この「鶏頭」の実景にこそ、その隠された深層心理が潜んでいるとも言える)、大きな変化を示している。この三連句の鶏頭の句を並べた時、父への「憎しみさへも失せゆけ」る感覚を経て、『所詮、父の性格は変わらない、私と同じだもの』といった諦めの感情と、幾多のすれ違ってきた愛憎の異性らをそこに並べた時、しづ子は「父を一人の男とも」捉えることが出来るようになったのである。そこでしづ子は、この父との関係に、毅然とした決断力に富んだ父と同様、きっぱりと敢然と一つのケリをつけているのである。因みに鶏頭の花言葉は「お洒落」「風変わり」「感情的」「個性」「色あせぬ恋」「情愛」である。
〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年三月十一日附句稿百六句より(4) 一句
梅一枝不連續線海より耒
「不連續線」は前線のことであるが、湿気を含んだ海風に揺れる梅の枝に、不連続という語感が心理的傾きを添え、更に「來」の俗字「耒」の一画目の物理的傾斜がダメ押しする。
〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年三月十一日附句稿百六句より(5) 四句
月光げの紙をつらねし玻璃の疵
玻璃の面の月光げの疵びびと伸び
指細くなりしおもひの指環かな
その疵の因をおもふや月の玻璃
「月光げ」は「つきかげ」で、しづ子の好きな表記。この硝子の罅に張った紙の連なりと月影の映像が、私の偏愛を唆るが、この三句目に出現する「指環」四句目の「その疵の因をおもふや」が直結すると(この四句は体裁から連作である)、この「指環」はケリーからプレゼントされたものであり、ケリーとの愛の巣であったここで、とあるトラブルからどちらかが何かを投げ、それが窓硝子に罅を入れた。それを、指環とともに思い出しているとしか読めない。因みにしづ子の第二句集の題名にもなった『指環』について、川村氏はケリーから贈られた指環と思っていたが、研究される中で、戦死した青年から贈られたものであろうという最終的推論に至っておられる。私もそれを肯んずるものではあるが、ここでの指環は、これが密接な意味連関を持った連句である以上、ケリーの贈ったものとしか読めない。私はしづ子は二つの指環をしていたのではないかと思われる。戦死した青年の形見の男物のごっつい指環と――やはり亡きケリーの形見の指環と――
〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年三月十一日附句稿百六句より(6) 一句
蝶翔ちて日はななめ射す羽目の面
この句は直前の三句から、引っ越した後のがらんとした板敷の間がイメージされるようになっている。
〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年三月十二日附句稿百十句より 四句
髮編みて三月ある日家を出づ
しづ子は二十一歳の昭和十五(一九四〇)年、深川の家を出、家族と離れて蒲田の矢口にあった岡本工作機械製作所設計課トレース工として入社、その武蔵新田にあった社員寮に入っている(川村氏の調査による)。恐らくこの句はその折りの回想句であろう。また、川村氏はこの前年に後に戦死する許嫁と出逢ったものと推定されている。しづ子の、ノラのような果断な性格を髣髴とさせる句である。
*
外す步や土の面のいぬふぐり
本句稿では、全体に亙っていぬふぐりを詠んだ句が多い。その中で、私の琴線に触れたのは、この一句。
*
白梅や衣觸れの鋭き乳の先
「鋭き」は「とき」と読ませているのであろう。私ならしづ子の代表句に採りたくなる句である。
*
春日中牛にしたはれゐたりけり
しづ子の句には、かなり頻繁に旅中吟が現れる。「しづ子」を伝説化させる人々は、そうしたこのスナップのような、どこかほっとして、笑顔で佇んでいるしづ子を決して欲しないのだ。それは師巨湫を含めてである。彼らは総てが現実のしづ子を抹殺した共犯者である。伝説の「しづ子」像をひたすら堅固にするためにのみ句を選び、そうして堕天使のモチーフに更なる虚構の絵具を塗りたくってゆくのだ。それが、しづ子の不幸であった。
〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年三月二十日附句稿百十句より 六十三句
ひしめくジヤズひしめく衣のおのがすそ
嫉視中おのがたつきぞ保たしめ
ひしめくジヤズ渦卷く嫉視花は紙
痛きほどテケツにぎりし掌の裡ぞ
ダンサーを生業とするしづ子のカット・バック。「テケツ」はチケットのこと。当時、しづ子が勤めていたダンス・ホールは戦前からのダンス一曲につき一チケットをダンサーに払うチケット制がまだ残っていたものらしい。詳しくは川村蘭太「しづ子 娼婦と呼ばれた俳人を追って」の二五四ページを参照されたい。この句稿、まずはダンサーの軽妙なステップやジャズやボレロやキャリオカで賑やかに幕開きする。そこで舞うしづ子は、中でも売れっ子だ。他のダンサーや慰安婦らの、カット・バックの中には、そうした女たちの独特の視線が配されている。
*
歸り耒つ三月さむき吾が居の燈
そんな仕事から引けて帰った一人のしづ子は、理髪店に行き、春日中の野辺を歩く。ここまではこの句稿が投ぜられた三月の同時制であると私は詠む……ところが……その春風が……遠い若き日の春の風となって……しづ子に吹いてくるのだ……
*
固き餠黴の餠燒き神田つ子
鈴木鎭子は大正八(一九一九)年六月九日、東京市神田區三河町二丁目二十三番地(現在の千代田区内神田一丁目と神田司町二丁目付近)に生まれた(川村蘭太「しづ子 娼婦と呼ばれた俳人を追って」六二ページによる)。この句を初めとして、以下、句稿は走馬灯のようにしづ子の出生から現在までを総攬し始めるのである。
*
生まれにけり大正最後の雪の中
震災を知らざる生まれ繪燈籠
黑髮や雪の一月生れにけり
しづ子が「しづ子」のために、数少ない積極的な共犯正犯となった事柄――それは年令詐称である。この最早、句として撰してもらうことなど微塵も考えていない大量投句――私はこれをしづ子の巨湫への壮大な叙事詩の外形をとったラブ・レターにして、同時に渾身の抒情的遺書と認識しているのだが――そこにあっても、これだけは巨湫個人に対してさえも、是が非でもなされなければならない「若さ」の絶対の演出であった。そこに私はしづ子の女としての弱さを感じるのであるが、それはまた私にはほっとするものでもあるのである。しづ子の年令詐称を鬼の首を取ったようにしづ子批評に持ち出す下劣漢どもに言いたいのは、だったら女性作家も女優も女は誰も彼も生年を必ず公表せよと訴えるがいい。こんなことは下らぬことだ。問題は、しづ子が実在する妹正子の年齢を美事に詐称している構造にあるのだ。川村氏はまさにそうした詐称の構造論から語って極めて有益な論を展開されておられる。「しづ子 娼婦と呼ばれた俳人を追って」を是非、お読み頂きたい。ここでは事実のみを述べておく。先に示した通り、鈴木鎭子は大正八(一九一九)年六月九日生まれであり、「大正最後の雪の中」「の一月生れ」ではない、関東大「震災を知らざる生まれ」どころではなく、震災当時四歳で、明らかに震災の記憶をはっきりと保持している年齢に達していたと言ってよいのだ。「大正最後の雪の中」「の一月生れ」で関東大「震災を知らざる生まれ」であったのは、彼女の妹正子であった。正子は大正十四(一九二五)年一月二十日に東京市下谷區(現在の台東区)で出生しているのである。
*
震災や母は妻たり二十一
ここには微妙な年令詐称をしても、愛する亡き母にだけは嘘をつけないしづ子が見える。鎭子の母綾子(明治三十(一八九七)年生まれ)は彼女を産んだ時が二十二歳、震災時では綾子は二十六歳、正子を産んだのは翌年であるから二十七歳である。いや、戦前は寧ろ数えで言うのが普通だから、綾子の年齢は「二十三」であろう。さすれば、しづ子は愛する母をも若く美しい「二十一」に詐称した、せずにはおられなかったのだ、とも言えまいか。
*
繪燈籠濱町育ちとませつつも
深川にみとせの夏をおくりけり
花美しき傳通院に母校をく
*
浜町――深川――大川――両国――芥川龍之介……伝通院――こゝろ――夏目漱石……しづ子は龍之介の例えば亡くなった父母と夭折の姉(しづ子には三つ違いの五歳で夭折した妹光子がいる)を描いた「點鬼簿」を――漱石の「こゝろ」の同名の「靜」の生き方を――どう読んだのであろう。とっても――とっても彼女に聞いてみたい願望に駆られるのである。
*
吾がすでに喫煙識りゐて花は八重
エスケープ亦愉しくて花は八重
不良性多分にもちて花は八重
謹愼といふこと強ひられつつに花
退校の極どさ保ちつつに花
花は八重不良女學生とは異ふ
學生として交るや一つ思想
花は八重思想の危機を吾ももちし
學園の思想の危機を吾ももちし
春燈下をんな學生混へつつ
高女卒とは名のみばかりに八重櫻
淑徳高等女学校時代の十四歳(昭和八(一九三三)年)から十九歳(昭和十三(一九三八)年)の回想吟。「すでに喫煙識りゐ」、「エスケープ亦愉しく」、「不良性多分にも」った、「謹愼」処分も食らって、危うく「退校の極どさ」さえ実感したお墨付きの「不良女學生」――であったとしたら――私を例の「しづ子」として更に更に伝説化なさるに、巨湫先生、都合が大層宜しゅう御座いましょう? でもね、先生、そんな「不良女學生とは異」って御座いましたの、私は――と正座したしづ子がきっと前を向いて答えている――が見える。そして――軍靴の足音が響く中にあって、しづ子も危ぶまれる危険「思想」としての社会主義にシンパサイズされるしづ子――「春燈下」の細胞の学習会で目を輝かせているしづ子――が見える。そこに佇立しているのは、インテリゲンチアとしての凛々しい乙女である。しかし、父俊雄としづ子自身の強い希望であったにも拘わらず、しづ子は女子大への進学に失敗、昭和十三年の秋頃、製図学校に入学する。最後の句にはその、阻まれた進路への哀しさが現れた後ろ姿が見える。ただ――確実に言えることは、ここでしづ子が女子大に合格していたら――後の俳人鈴木しづ子は決して生れなかった、ということである。いや、当時も今もごろついている俳句を捻る誰彼と同じような才媛と評される作家の一人にはなっていたかも知れない。しかし、それは平均的な陳腐な才媛作家群の中に哀しくも埋没して、決して浮上するような句を残すことはなかった。我々はこの「高女卒とは名のみばかりに八重櫻」の淋しいうしろ姿にこそ、鎭子の、否、しづ子としての旅立ちを見なくてはならないのである。
*
以下、私のある思いから先の末尾の「高女卒とは名のみばかりに八重櫻」の次の句から句稿最後までの三十九句を残らず(一句も省略せず)順に掲げる。「*」を入れず、「――」「……」で私の勝手な解釈を附す。
水の邊の墨田風起つ夜の櫻
風起ちて花は夜を咲き向島
――ここにはマジックがある。昭和十三(一九三八)年春の十九歳のしづ子を点景とする「八重櫻」は「墨田」と「向島」の妖艶な夜桜に変容し、その梶井基次郎の「櫻の木の下には」のような屍の精力が――十九の処女を一瞬にして三十の女にするのである――
東京の花を待たずに離り耒し
早春の風吹く美濃に耒初めけり
三月盡來初めし土地に家を探す
職を得て土地に棲みつく櫻かな
――お分かりのようにこれは女学校時代から二十代をスポイルして昭和二十四(一九四九)年の春の、府中から岐阜への転居へとタイム・スリップしている。しづ子の事蹟を知らぬ者には、女学校生が一気に転落してゆくように読めるところがマジックである。私は「要注意」などと教師臭いことを言っているのでは、ない。再度申し上げるが、この句稿は最早、巨湫に「撰せられる」ことなど微塵も意識していないのだ――これらは総て、弟子しづ子の巨湫という野狐禪師への、命を懸けた公案の掛け合いなのだ――そもそもこの私の「しづ子琴線句」選を読まれる方は川村蘭太氏の「しづ子 娼婦と呼ばれた俳人を追って」を読まずんばならず、読んでおられるとならば、私のこの分かり切った屋上屋の解説自体、不要なはずである。
街娼とかよふ爲しごと花は夜を
夜櫻や土地に耒初めて錢は無く
夜櫻や救ひたまふか異邦人
夜櫻や代償と得し錢一貨
錢一貨握りにぎりて花は夜を
い寐やらぬ一夜の花のホテルかな
ホテルの夜十指の爪を燈に濡らす
花の夜や爪は光りておのがいろ
はからずも花ぞひらける一夜かな
はじめての夜るの櫻とひらきけり
はじめての人の背にある春燈かな
おのおのの貌は忘れて花は夜々
夜櫻やこころの鏡曇り次ぎ
麻痺つづく一つこころと花は夜々
――私は如何にも無謀と言われるかもしれないが、以上の十四句を連合した『娼婦変身仮想句群』として読んだ。作句内時制はしづ子がダンサーとなった昭和二十五(一九五〇)年頃か。冒頭の句はれっきとした全うなダンサーであるしづ子が「街娼とかよふ」――街娼と変わりゃしない「爲しごと」じゃ、と後ろ指刺されることへの深い傷心の表現であり――だったら私、娼婦になったつもりで――あだ「花は夜を」生きる伝説の「しづ子」を、句の中で演じてみよう――それがこの、しづ子の魂胆ではなかったか?
……夜櫻の私…………
……「舞姫」のように……
……初めての土地に来て……一銭の錢もない……
……そんな私を救ってくれたのは……
……かのエリスと同じき……
……異国の肌え黒き人だった……
……代償として受けたのは錢一貨……
……その錢一貨……見つめる私……
……これが……私の価い……私の価値……
……それをギュツと握りに握って……
……あだ花は夜を生きるの……
……一夜の花のホテルの一室
……男に抱かれながら……
……十指の爪を燈に翳して……見る……
……その濡れたような十本の指……見つめる私……
……花の夜やうつりにけりな爪は光り……
……そはまごうなきおのがいろ……
……はからずも花ぞひらける一夜にて……
……はじめての夜の櫻とひらく……
……はじめて買われた人の……その黒い背(そびら)を手前に……
……春の夜の淋しい燈火が……見える……
……こと終えて……おのおのの貌は……もう忘れましょう……
……あだ花はまた別な夜々へ舞い散る……
でも、そんなこと! とっても堪えられない! 私のこころの鏡は曇りに曇る! 麻痺、麻痺だわ! 私の一つのこころは、麻痺するの! そんなのはあり得ない! 私は娼婦じゃない! ダンサーよ! 舞姫なの!――私は「夜櫻やこころの鏡曇り次ぎ」「麻痺つづく一つこころと花は夜々」の二句をそう読む。一言だけ言っておくと、例えばしづ子は一文無しで岐阜に「落ちて」来たわけでは全くない。また、川村氏の現地調査でも、しづ子を知る人々の語る印象は、決して悪くない。寧ろ好感を以て語られていると言ってよい。彼女が、よもや、そうした『賤しき限りなる業に墮ち』(森鷗外「舞姫」)ていたなどという事実は――「しづ子」の匂わされた句以外には、実はどこにも存在しないというのが真実なのである。なお、私のこの仮想には当然、愛したケリー・クラッケの印象を入り込ませたことを断っておく。
――そしてこれらが夢想句群である証左が以下の句となる。ここでしづ子は現実に戻る。そうして『娼婦でないダンサーのしづ子』が、冷厳に辛辣に同僚の慰安婦たちを活写するのである。
キヤバレーに得し一つ職花は夜々
脚組むや紙のはなびらふらす花
女たちうすぎたなくも脚を組み
女たち顎突きだして煙草喫ひ
女たち一つ煙草を喫ひおくり
女たち自國語ならぬことば識り
女たちくちびる厚く吻ふくみ
女たち乳を隱して膚かくさず
女たち燈明り蔭に吻をすひ
女たちおほかたひまに酒を飮み
女たち猜むおもひを露はにも
花は夜々ジエーンと名づけられつつに
賣れつ子といはるるほどに花は夜々
一身に猜みあつめし胸の汗
猜まるること極まりて職を抛つ
――「猜む」は「そねむ」と個人的には読みたいが、最後の句の「猜まるる」は明らかに「ねたまるる」であろう。しづ子はとあるダンス・ホールではジェーンという愛称で呼ばれていたか。最後の五句に現れるダンサーとしての自信と矜持は一抹の卑下も感じられない。しづ子は堂々と挑戦的に「女たち」の前で美事にステップを踏んでいるではないか。
戰ひは吾らに嚴し愛ぞ斷つ
距つなばそれもよかりし海の霧
海の霧戰死ならざる死と知りて
――ケリー・クラッケとの同棲――ケリーの朝鮮出兵――ヒロポン中毒者としての日本への帰還と、慌ただしい帰国――そして故郷テキサスからのケリーの訃報――
――以上、珍しく多量の句を選んだ本句群は、私にはその全体が一読忘れ難い有機的な融合体として意識されるのである。
〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年三月二十四日附句稿百十句より 三句
三月ある日句數二百と詠ひつつ
川村氏も指摘されているが、しづ子は矢数俳諧を意識しているようには見える。見えるが――しかし、やっぱり、いいや、そうじゃない! 西鶴のやらかしたそれは愚劣な橋下と同じく俳諧の政治的独擅場へ躍り出るためでしかなかったが、しづ子のそれは、師松村巨湫への公案の機銃掃射としてであって、何らの名声が意識されていない点に於いて、矢数俳諧を超えて、我々を迎撃するのだ。尾崎放哉も井原西鶴も顔色無し、だ。何故なら、それは最早、消閑の具としての俳句を超越しているからである。西欧的近代的個人? 糞喰らえ! このしづ子の糞は、鋼鉄のカチ糞として我々の脳天を――確実に一気に――打ち破る!
*
囀りや床の面に撒く石鹼水
私はフロイトを小学生の時から愛読したとんでもない汎性論の影響下にあった人間である。例えばこれを精神分析学的に解釈したい気持ちを抑えられないと同時に、しかし今、その分析をも総て私は無効にするであろうことも確実である。而してこの映像はタルコフスキイのワン・シークエンスである。タルコフスキイもフロイトを認めない。私もこの年になって、フロイトよりもユング、いや、ユングなんぞの怪しげな似非神秘主義も超えて芥川龍之介の「杜子春」の鐵冠子に惹かれていると言おう――「さえづりやゆかのもにまくせつけんすゐ」――これはもう、タルコフスキイの撮った神聖な映像――そのものではないか――
*
槻芽立つ師とかよはするふみぞもち
「槻(つき)」は欅を指し、しづ子の大好きな詩語である。この句こそ、多量の修行の如き句稿の確信犯の真理を現前させている――と私は思う。
〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年三月二十四日附句稿二百十九句より(1) 六句
昃ろへば蝶翔たしむる玻璃の柵
いづれ指觸るるにあらず蝶は翔ち
蝶の軀の入いるにやすく玻璃のひま
玻璃透きて蝶は遠のくばかりなり
蝶翔ちて指とどかするすべもなし
ガラス窓にうっかり囚われた迷い来った蝶は、やさしいしづ子の手で自由を得て翔んでゆく――その自分のような蝶に、しづ子は、少しだけ触れてみたかった……でも……
激つ浪憶ひは距つばかりなり
その魂のデイスタンスは――恋の不在を――厭がおうにも、しづ子に思い出させるのであった――
*
古来、蝶は人の魂であった……
〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年三月二十四日附句稿二百十九句より(2) 十句
目つむれば琴の六段指はじき
琴憶ふ雪つむ宵に在りにけり
花桃や琴絲支ふ指ぞ伸べ
琴爪や彈きやみ溫みかよひつつ
琴千鳥彈きやみ明りせつなけれ
歳月は還るよしなし琴の爪
雪の日の琴絲支ふ指の先
琴絲支ふ指ぞ切るほどむかし琴
經だつれど身に添ふわざぞ琴六段
琴句群二つを接合した。しづ子は若き日に琴を習い、得意としたことは先の昭和二十六(一九五一)年九月二十八日附句稿百五句の冒頭四句からも明らかである。箏曲にあって六段(伝八橋検校作)は、六段に始まり六段に終わると言われる基礎にして完成の域をも示す重要な曲である。二世吉沢検校作の千鳥の曲は六段に並ぶ古箏曲の名曲とされ、古雅と斬新な内容を併せ持つエポック・メーキングな名作である。ここでのしづ子の謂いには、ダンサーとなった今でも、琴を弾ける自分に対する強い矜持があることが窺がわれる。しかもこれは回想吟とは思われず、直近の何かの機会に琴を弾いているのである。この場が私には興味をそそるのである。因みにこの冒頭々の前には、
早春の奈良線に人あふれけり
とある。これがこれらの琴の句と無縁ではないように私には思われる。「千鳥」は普通、独奏しないのである。しづ子と奈良と琴――そして尺八の伴奏者――ここに私はしづ子の失踪の謎を解く鍵が隠されているようにも思えるのである。
〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年三月二十四日附句稿二百十九句より(3) 五句
祈りはなし春夜きらめく一つ星
まがふとも靑炎ゆるべし一つ星
春星に狂ひつくさば果てはまた
星炎えや水漬く屍と曝すとも
星を読み込んだ連作句十二句の内。巻頭と掉尾はその句群の最初と最後。これらは二年前の「明星に思ひ返せどまがふなし」にダイレクトに共鳴する句群であるが、ここでは既に『祈る』ことは棄てられ、情念の炎と化した星は蒼白き滅びの光となったしづ子の『生』=「一つ星」は、狂気も死さえも辞することなく、暗闇の中に『在る』――
*
沙羅双樹父母は無かりし吾が十八
勿論、偽りである(しづ子の母の死はしづ子二十七歳、父は健在)。しづ子十八歳――満ならば昭和十二(一九三七)年であるが、私はしづ子の意識は数えであると考えるから、昭和十一(一九三六)年がそれであると考える。この時にしづ子には何かがあった。それは親族に纏わる何らかの出来事であり、それはしづ子にとってある種の精神的な死と再生のイニシエーションに相当するものであったのではないか。でなくてはブッダ涅槃の「沙羅双樹」と「父母」の不在と「十八」を結びつける意味がない。少なくとも、しづ子がそのような「しづ子」伝説を仮想させることを意図して置いた一句であることは間違いない。
〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年三月二十四日附句稿二百十九句より(4) 詩心句群 二十一句
詩絶えのちかづくおもひ爪は燈に
半歳とつづかぬ詩心爪長く
戀うたを削りけづりて爪は燈に
詩稿いくたび煙と化せし炭火中
詩一冬竹の高葉の吹き徹し
詩絶えの懼るにあらず竹は吹き
寒浪のすさるに似たり詩心いま
愛しむや盛りし詩心失せゆくに
半歳の詩心華麗にして了る
爪は燈につづる詩心翳ぞ濃く
蝶翔ちて吾が頭は輕し一過の思
詩のことたつきのことと爪は燈に
爪は燈に十とそろへてつつがなし
たつき憂し兩立かくも爲し難く
破綻眼に見ゆるばかりに春南風
たつきか詩か三月さむき火の燃えて
春北風たつきぞあらざる詩はなし
春北風やたつきぞ守り徹すべし
春北風やたつき敗るるとも詩は
ひひらぎや詩倖せにこの體在り
春南風詩とたつきと頭にからげ
「詩心」を詠み込んだ一連の句群を二十一句連続で採った。川村氏はこれを若き日のしづ子が詩から訣別した回想句として捉えられている。そして、そこで川村氏は新発見の森田洋平なる男性名の定型詩を示されている。その詩は「しづ子 娼婦と呼ばれた俳人を追って」百四十頁を参照されたい。昭和二十一(一九四六)年の小冊子『子徑』に載る詩である。そうして私も確かに「半歳の詩心華麗にして了る」の句までは、そのように――近代詩から俳句に遷移したしづ子の句と十全に読めると言おう。だが、そこから後半の句は、私には実は現在時制で感じられるのである。後半の句では「詩」は音数律から言って「うた」と訓じているようにしか読めない。そして、句群の季節は明らかにこの句稿の季節そのものである。だとすれば、少なくともこの句群の後半は、過去の回想吟ではなく、「たつき」=「生」と両立し得る「詩」=詩歌=俳句を意味しているようにしか私には読めないのである。さすれば、そこには「俳句」と「たつき」たるダンサー、いや、これからしづ子が選び取らんとしている何らかの「たつき」=「生」と、「詩」=俳句の覚悟の訣別の謂いとしか読めないのである。しづ子は、この時、既に俳句を棄てる覚悟をしている、と私は読むのである。この句群の後はきっぱりとして、「詩」を語彙から棄てている。そして、彼女の好きだった木曾川の砂地を歩むしづ子が十数句詠まれて終わるのだ――
陽炎や砂地つきなば還るべし
しづ子は――好きだった木曾の河原の砂地を走ってゆく――タルコフスキイの「僕の村は戦場だった」のラスト・シーンでイワンと妹が走ってゆく川岸のように――好きだったその『抒情の文学=詩=俳句』の世界の、絶えて尽きたところで――「もう、帰りましょう」――と、しづ子は覚悟しているのではなかったか?――この二日後、第二句集『指環』が刊行される――
〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年三月三十日附句稿百五十六句より(1) 四句
本句稿の日付は極めて意味深いものである。何故なら、これは何と、しづ子が神田神保町西神田倶楽部で催された自身の第二句集『指環』の出版記念会に出席した当日の日附だからである。これはどこでしたためられたものなのか? この日附に拘るとすれば、年譜的事実からは出版会の後、その日の夜宿泊したところの品川の宿で書かれたということになるが、それは如何にも考えにくい。とすれば、答えは一つしかない。すなわち、この句稿は出版会に出席するために岐阜を立った、三月二十九日の夜までに記され(前日出発については川村蘭太氏の「しづ子 娼婦と呼ばれた俳人を追って」の三〇八ページに確定的考証が示されている)、三十日の朝、東京で投函されものだということである。川村氏は直接持参して巨湫に手渡した可能性を同ページで示唆されているが、いずれにせよ、私はその仕儀に、毅然としたしづ子のある覚悟が見えるように思えるのである。
『指環』出版が実は、必ずしも彼女の意に沿ったものではないことは、川村蘭太氏の驚くべき精査によって最早、明らかである。『指環』によって「鈴木しづ子」なる伝説の城は、師巨湫を始めとする「異端の娼婦俳人しづ子」を求める有象無象の俳人らの共同正犯によって完膚なきまでに外堀を埋められたのだった。
無数の猥雑な『独身者によって略奪された花嫁』しづ子――しかし、それであって『さえも』――しづ子は、
「みなさん、ごきげんよう、さようなら」
という鮮やかな一言の肉声を最後に投げかけて――その姿を永遠に消し去ったである――
*
降りやみの濡れ葉いろなす土おもて
指にぎる草秀しほるるばかりなり
吹きやみの夕べ黝ずむ葉のおもて
毬さがす夕べ明りの草の中
この句稿は庭の草取りの情景群に始まるが、その草取りは草取りの持つ「生」や「活」の属性を全く感じさせない。雨後の庭であるが、抜く草の穂は最早既にしおれている――そして、あっという間に夕闇が迫る――最後に採った句では、しづ子は少女に戻っている――しかし夕闇は果てしなく濃い――タルコフスキイの「鏡」のラスト・シーンのようにカメラは情景を、否、そこに独り立つ少女のしづ子を映して――愛おしむようにゆっくりと叢の中へとフェイド・アウトしてゆく――
〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年三月三十日附句稿百五十六句より(2) 一句
おはじき玉ガラス缺けつつ草萌え耒
『それからまた、
〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年三月三十日附句稿百五十六句より(3) 一句
霧たてばおのれならざる思の狂ひ
ハリー・クラッケ追悼句群の一句。人影は霧の中へ――そして中七の「おのれならざる」の思惟――下五の「しのくるひ」が読む者に対して――詠むしづ子の胸の裂ける思いを――ざっくりと――突き立てる――
〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年三月三十日附句稿百五十六句より(4) 十二句
一つ死のぬぐふあたはぬ霧笛かな
一つの死月のコスモス地を匍ひ
一つ思やつねたたしむる月夜霧
霧たてばおのれならざる思の狂ひ
めぐる思や霧の朝霞は曉けにけり
霧笛起つ抱き深さのかひな裡
一つ思と乳房くるまば霧たつか
霧たてばかたちなきものかい抱く
霧衣うつし身の肩冷えにけり
かひな觸る想ひのみかは霧衣
悲しめば吾が體一つの霧笛かな
霧たてば見えざるこゑに體こそ投げ
先に挙げた「霧たてばおのれならざる思の狂ひ」の前後に存在する、ハリー・クラッケ追悼句群の推敲・改稿句を拾ってみた。ここにはしづ子の連想法の特異性がよく示されている。特に「一つの死」が「一つの思」という通音で意味が変容してゆく過程は面白い。漢字も音数律から特異な読みで変化を持たせようとしているのが分かる。しかし――しかし――その絵の真ん中には――濃い霧の中に立ち尽くすしかない孤独なしづ子が独り立っているだけ――なのである――
〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年三月三十日附句稿百五十六句より(5) 一句
いづれは體土還るとも曼珠沙華
「體」は「たい」であろう。「とも」という接続助詞が「曼珠沙華」の瞬時に燃え立つ女の強い情念を引き出す。これは文字で書いた時初めて、背をすっくと伸ばした古武士のようなしづ子が髣髴としてくる視覚的な効果を持った句である。
〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年三月三十日附句稿百五十六句より(6) 四句
かよちやんは眞赤なセーター双つ子の
きみちやんはチェツカの外套双つ子の
和男に詩朗たちきやんは否進學す
徑でこぼこけんちやんゆきちやん一年生
幼稚園の修業式を詠ったものと思われる句群から子らの名を詠み込んだものを採った。この子らはしづ子の住んでいた近隣の子らであろう(直後に「進学す肉商ひの親ありて」がある)。きっとよくこの子らとしづ子は遊んでやったのであろう。でなければ、名をこんなに親しげには詠み込まない。先に「寒雲に忌むや啄木と一茶殊のほか」と詠んだしづ子であるが、双子の連作や絶対リアリズムの最後の句、そして何より、総て違った子らの名を詠み込んでいるところに、作句の新規一転などという小賢しい作為などではない、しづ子の眼差しの限りない母性的優しさを隠しようもないではないか。三句目は、「たきちゃん」ともう呼ばれるのは小学生なんだから「否(いや)」という意味で採れなくもないが、そうした荒い省略法はこの期のしづ子には見られないし、前後の素直な詠からしても、これは「皆」の誤りかと思われる。
〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年三月三十日附句稿百五十六句より(7) 十二句
花吹雪東京に夢果てにけり
熟れ柿や汝があこがるる東京とは
花吹雪東京の詩削りつつ
美濃は好し春は水邊に詩の生まれ
美濃は好し夏は水邊に語らふも
美濃は好し秋は水邊に髮を梳き
美濃は好し冬は水邊に指濡らし
棲みつけば離るがさだめ歸り花
歸り花棲み古りてより離り耒し
一つ土地棄ててきたりし歸り花
その昔府中の霧を夜々燈し
離るれば府中の霧の歸り花
連続した十二句。私はこれらが一体となって不思議な定型詩として響いてくる。それは例えば次のように――
花吹雪
東京に夢
果てにけり
汝(な)に問はん
「熟れ柿や
汝があこがるる
東京とは」と――
吾(あ)は答ふ
「花吹雪
東京の詩
削りつつ」と――
ああ
美濃は好し――
春は水邊に詩の生まれ
夏は水邊に語らふも
秋は水邊に髮を梳き
冬は水邊に指濡らし
なれど――
棲みつけば
歸り花
棲み古りてより
離り耒し
一つ土地は
棄ててきたりし
その昔
府中の霧を
夜々燈し
離るれば
府中の霧の
歸り花――
それは不思議に、限りない郷愁と漂泊の、伊東靜雄の詩の一節のような響きを以て、私の心に流れるエレジーなのである――
――そして忘れてはいけない――
――この句稿は――
――しづ子が神田神保町西神田倶楽部で催された自身の第二句集『指環』の出版記念会に出席した当日の日附であることを――
――冒頭の私の問答はしづ子と他者ではない――
――しづ子としづ子の公案なのである――
〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年三月三十日附句稿百五十六句より(8) 三句
古葉光げ土面しめりてゐたりけり
よべ濡れの古葉ひかりの土面かな
花ちかく朝はしめれる土面かな
本句稿抄出冒頭の「降りやみの濡れ葉いろなす土おもて」の推敲句が後半に再び現れる。これはしづ子がどうしても、この句稿で――特にこの日の日附の句稿で――どうしても摑みたかった句境だったのだ――と私は思うのである。
〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年三月三十日附句稿百五十六句より(9) 五句
朝鴉河西善藏在らざるなり
情炎の河西文學蚊帳をゑがき
靑蚊帳や讀みすて文の一つ痴話
蚊帳靑し痴語といふには哀しくて
一つ文情痴はめぐる誘蛾燈
しづ子の文学体験を考察する上で、貴重な句群と言える(「河西」は「葛西」のしづ子の誤り)。次の同年四月十五日附大量投句稿でも、しづ子は太宰に傾倒したことをやはり詠んでいるが、川村氏は「しづ子 娼婦と呼ばれた俳人を追って」の九十六頁でこの「朝鴉」の句を引き、太宰に先行する典型的な破滅型の、この赤裸々な私小説作家葛西善蔵の意識の中にあった一種の『開き直り』と、しづ子の『指環』による「しづ子」伝説形成への、しづ子自身の『開き直り』との共通性を見出し、『それはひとえに、しづ子が目指した俳句そのものに、私小説的なる源泉をみていたからであろう』と記しておられる。至当な評言である。残念ながら私は葛西の作品を若い時に数作読んだぎりで、ここでこれ以上の語るものを持たないし、実は掲げた五句総てが私にはどれも意味が判然としないのである。ただ二句目とそこから展開連想される三句については気になるところではある。ネット上での検索から、アルコール中毒症状を呈するようになってから彼が書いた「弱者」という作品の中で、まさに前幻覚症状ともいうべき、強迫的な追跡妄想の表現が蚊帳に関わって現れているのを見出した。本句の「蚊帳」とは無関係かも知れないが、引用しておく(引用元は個人のサイト「御酒之寝言屋頁」の「御酒の話(2)」の「葛西善蔵の酒」。但し、漢字を正字化し、一部の読みを排除した。「…」はママ)。
*
自分はその狹い植え込みの中に、動く黑い姿を認めた。ゾウーとした感じにうたれた。…兎に角にさう云ふ黑い影が、毎晩のやうに私を脅かす。閉めておいた筈の雨戸が開放されてあり、閉めてゐた筈の障子が開いてをつて、漠然とした黑い影が蚊帳の外に立たれるには
*
〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年三月三十日附句稿百五十六句より(10) 五句
花の雨明日のこの刻在らざる居
春降りや金曜にもつジヤズタイム
春降りや刻いつぱいのジヤズ了る
沈丁やととのへ成りし旅のこと
旅立ちの夜るの沈丁にほふなり
川村氏は「しづ子 娼婦と呼ばれた俳人を追って」の三〇九頁でしづ子が上京するために乗った列車を、三月三十日の東海道本線急行の岐阜発〇時五二分東京行と推定されている。すると、「花の雨」の句はその前々日、三月二十八日の零時前後の作と考えられる(因みに二十九日の天気も川村氏は当日の「岐阜タイムス」の予報の記事を引用して、ここ数日の「花の雨」の事実を確認しておられる)。昭和二十七(一九五二)年三月二十八日は金曜日であった。「春降りや」の二句は、ダンサーとして勤めているクラブのその花金の閉店時間一杯までの勤務の活写であり、最後の二句(句稿掉尾の二句である)は翌日三月二十九日の景、特に最後の句は既に二十九日の夜に入ってから、まさに家を出るその「旅立ち」の詠である。私はそれを彼女は岐阜駅へと向かう途次で投函したと思う。
――これは私の感覚でしかないのだが――私がしづ子なら――この句稿を師巨湫に手渡しにはしたくないと思うのである。今までの郵送投句(それは師との一対一の文字通り修行であり参禅であった)の例外行為というだけでなく、これを私はしづ子にとって極めて特別な意味を持つ句稿と捉えているから、猶更に今まで通りの郵送で送りたいのである。
――しづ子がこの二十九日の土曜一日をかけて書いた一つの人生の区切りとしての――しづ子の新たな孤独の夜の果ての「旅立ち」としての――この清書した絞り出した公案の答えを――
――姿を他人に見せる最後となる旅の当日の句稿を――
私なら絶対に愛する師(男)に――しかも「しづ子」見たさに鵜の目鷹の目で群がっている男どもの前で――ある表情の意味を読み取られるような感じで――この最後の覚悟の大事な遺書の一部を手渡しにするようなことは――決してしたくはないからである――
――因みに沈丁花の花言葉は――「栄光」――「不死」――「不滅」である――
〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年四月十五日附句稿二百十七句より(1) 於神田神保町西神田倶楽部 鈴木しづ子第二句集『指環』出版記念会 感懐句群 二十九句
帶京の夜の花とはなりにけり
氣疲れや飯をくるめしとろろ汁
湯の音も絶えてしまひぬ旅の膳
旅の夜や海苔がくるみし熱き飯
品川の宿の夜櫻海苔の膳
靑海苔や泊り短く發ちにけり
花の穹感激もなく雲流れ
紅茶冷えよくしやべる男だな
それと見し性の異ひや夜の紅茶
よはひ覆ふすべもなかりし夫人かな
眼鏡してオレンジジュースひややかに
ソーダ水眼鏡の奥に性をよむ
醫學者や眼鏡ひかりて夜の紅茶
花一日人らつどひてくだらなく
東京に靑穹を見し花ちかく
眼鏡せし夫人のこころ解せぬなり
眼鏡して蔑すみゐるにちがひなし
恃むなし離京の汽車に目つむれば
東京の花のひらきや愛着はなし
花いまだおもしろからぬ離京かな
ともかくも義理を果たせし櫻かな
*
ソーダ水上目づかひに見られつつ
*
ソーダ水眼鏡透りし伏目の眸
眼鏡して夫人はちらよ見たりけり
*
帶京や神田籠りの花の穹
花の街目的もなく鞄提げ
東京は汗ばむほどの櫻かな
*
眼鏡せし夫人をうとみつづけたり
眼鏡せし夫人の方は眸をやらず
昭和二十七(一九五二)年三月三十日に神田神保町西神田倶楽部にて催された鈴木しづ子第二句集『指環』出版記念会に出席したしづ子の感懐句と思われる句をほぼ総て拾った。「*」を挟んだ後ろの七句は、それぞれ少し後の方に思い出したように登場するものであるが(「*」は断続点に打った)、最初の二十一句は句稿の冒頭から総て連続する。――これらはその時の、さめた――「冷めた」であり「覚めた」であり「醒めた」であり「褪めた」である――しづ子の総てだったのだ――
〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年四月十五日附句稿二百十七句より(2) 一句
手の裡の夜店戾りの鏡かな
しづ子の淋しい瞳――しづ子の掌の中の小さな丸い手鏡の中――春の夜の夜店のアセチレンの匂いとともに……
〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年四月十五日附句稿二百十七句より(3) 一句
夫に仕ふ一人女人や夕牡丹
これも私は実は、出版記念会の感懐句群の一句と思っている。しかし……しかし――何故か、この句はしづ子が余りに可哀相な気がするのだ――だから私はこれをここに別掲しておきたいのだ。
〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年四月十五日附句稿二百十七句より(4) 一句
遊び女と徹し切れざる十指かな
〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年四月十五日附句稿二百十七句より(5) 一句
春風裡はらわた裂きて蛇死せり
〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年四月十五日附句稿二百十七句より(6) 二句
かつては防空壕さくらはなびら散りて吹き
吹く櫻要なき壕の穴ならび
ここまで暗い心性の私の特異な抄出であるから、断っておくと、決して暗く沈んだ句柄が並んでいる訳ではない。東京から帰ったしづ子は、春の野に出でて、大好きな木曽川の岸辺に佇んで、その息吹きを多様に素直に詠っている。
防空壕をこのような景色として日常的に知っている世代は、多分、私辺りが最後だろう。この句を映像化さえ出来ない人々が半数を占めるような時代になった事実には、何か不思議な感懐が私の胸を打つ。防空壕―戦争という直喩以前に、この情景が見えないのだから。二句目下五は動詞の連用形ではなく、「穴ならび」という名詞で読むべきであろう。
〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年四月十五日附句稿二百十七句より(7) 一句
玻璃の面や春のあかつきの鐘の音
〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年四月十五日附句稿二百十七句より(8) 三句
月明のみなそこ沈む死を想ふ
希まば死つまさき近むきりぎしに
花散りぬ眸の隅笑ふ看とり女は
連続の三句。突如、入水夢幻句が現れる。落花の如く川面に散るしづ子の眸の隅に一瞬映るみとり女の不気味な笑い――
〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年四月十五日附句稿二百十七句より(9) 三句
瞬間の死にあらざればむしろ否
桃は濃し母のごとくに死ぬるなめ
死なば死ね地の底を匍ふ人のこゑ
これらの句の前後や句稿の後半には肋膜を疑う句や発熱、病臥、慰めを言う医師がしばしば詠まれ、以上のような死を直接に詠む句、知多半島河和と思しい小旅行を「最后の旅かもしれず」などと意味深長に謳うなど、しづ子の結核罹患の可能性への不安を濃厚に感じさせる句が並ぶ(但し、私はしづ子が事実、結核に罹患していた可能性には懐疑的である)。二句目の「死ぬるなめ」は不審。「死ぬるなり」「死ぬるなれ」若しくは「死ぬるなる」(連体中止法)の誤記か? 考えにくいが「死ぬるなんめり」の「ん」無表記の「り」の脱字か?
しづ子はこの頃から、先の入水無幻のような自殺願望を示す句を創り始める。本句稿のの後半でも「もはや飽みたり生きること」「不意に死を得る」「死は最良のさだめとか」のいった表現が用いられている。知られた「しづ子」伝説の一つに、巨湫も口にしているしづ子自殺説があるが――これは無論、私の願望でもあるのであるが――私は「瞬間の死にあらざればむしろ否」というこの句に現れた凄絶ながらきっぱりとした覚悟から、しづ子は自殺してはいないと感ずるものである。
〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年四月十五日附句稿二百十七句より(10) 七句
國ごころ花の蘇枋は濃かりけり
蘇枋咲き封建ごころつづくなり
自由欲し花の蘇枋は降りて咲き
日本といふ國なつてはをらずきぼしの芽
蘇枋濃しむかし還るか國ごころ
蘇枋濃し共産ごころも一つの思
ややこしき政治なるかな蘇枋濃し
底本では「蘇栃」とあるが、しづ子自身の誤記か底本の誤植かは分からないが、「蘇枋」の誤り(「蘇栃」と書く植物はない)。私の判断ですべて訂した。「蘇枋」は「すはう(すおう)」で、バラ目マメ(ジャケツイバラ)科ジャケツイバラ亜科ジャケツイバラ属スオウ
Caesalpinia sappan 若しくは同ハナズオウ属ハナズオウ Cercis chinensis こと。四月、葉が出る前に黄や桃・赤紫・白色の小さな蝶形の花が固まって咲く。「濃し」とあるから後者のハナズオウ赤紫のものかと思われる。花言葉は「豊かな生涯」。
これらの珍しく強い政治性を孕んだしづ子の社会性俳句は、この句稿の日附から、警察予備隊から保安隊への再編の時期との関連を強く感じさせる。以下、ウィキの「警察予備隊」によれば、この日附の十三日後の昭和二十七(一九五二)年四月二十八日、サンフランシスコ講和条約が発効し、ポツダム命令は原則一八〇日以内に失効するはずであったが、ポツダム命令に含まれた警察予備隊令については同年五月二十七日の改正によって「当分の間、法律としての効力を有する」ものとされた。しかし政府は、軍事力を保有する法的根拠の明確化と体制整備を図るために海上警備隊を統合する保安庁構想の下に保安庁法を成立させ、同年八月一日に保安庁を発足、『警察予備隊は後の防衛省の内部部局に相当する「本部」、陸上幕僚監部に相当する「総隊」、陸上自衛隊に相当する「管区隊以下の部隊等」に分けられ、本部と総隊はそれぞれ保安庁内部部局と第一幕僚監部への移行と同時に廃止されたが、部隊等は』『警察予備隊」の名称のまま保安庁の下部組織として』数か月存続、同年十月十五日、後の自衛隊となる保安隊が発足することになる。なお、若い読者のために言っておくと、日本共産党は戦後、「人民の軍隊」による自国防衛の必要性を訴え、一九八〇年代までは、アメリカに従属した自衛隊を解消した上で、改憲をも視野に入れた自衛組織による武装中立策をとっており、非武装や護憲ではなかったし、昭和三十(一九五五)年七月の第六回全国協議会(六全協)で武装闘争路線の放棄を決議するまでは、中国革命に倣った社会主義革命のための武装闘争を長い間、綱領としていた。このサンフランシスコ講和条約によって一九五〇年から続いていたレッドパージは解除されたが、公職追放や解職・免職となった人々の殆どは現職復帰は出来なかった。
〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年四月十五日附句稿二百十七句より(11) 一句
うす醉ひの氏に手觸られて春の宵
『指環』出版記念会か、その後の二次会の回想吟か。定かではない。句稿の最後の方に、ぽつんと現れる句である。二次会は神保町の喫茶店「きやんどる」であった(位置を変えて現存)。
〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年四月十五日附句稿二百十七句より(12) 二句
借りて棲む蠶屋の隅や文學論
ここに少女期太宰文學神とあほぎ
太宰治は処女短編集『晩年』を昭和十一(一九三六)年六月に刊行、翌年には内縁の妻小山初代とのカルモチンによる自殺未遂を起こして一年間執筆を断っているが、しづ子は昭和十一年六月当時十七歳、淑徳高等女学校二年であった。川村氏はしづ子の年齢詐称との問題から、少女期の太宰文学との出会いを微妙に留保されているが、私は素直にこの時の体験としてよいと思っている。ここで年齢詐称は必ずしも露見するとは言えず、既にこの時、しづ子にはそうした気遣いは不要になっていたと私は思うからである。但し、前者の句の「借りて棲む」という謂いは、しづ子が単身東京に残った昭和十六(一九四一)年(しづ子二十二歳)以降、戦後直後を詠んでいる可能性が高いとは思うし、それが太宰が女性に人気を博すのとシンクロしているとは言える。
〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年五月六日附句稿七十七句より(1) 一句
死にどころこころゑがくや春の雲
〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年五月六日附句稿七十七句より(2) 三句
形りあらば
五月雨や執念絶つにすべはなし
山形の砂の面てや蠅生る
一句目は難解である。「なりあらばつち/なげうつものを/わがししん」ととりあえず詠みたい。「なげうつ」を音数律で「なりあらば/つちうつものを/わがししん」とも読めるが、採らない。――実体があるものならば、この固い「現実の土」の面へ、投げうって、こなごなに完膚なきまでにうち砕いてしまいたい、私の詩心――。二句目。しづ子の投句は決して書き溜めた古句想ではないことが分かる。そして「執念」は今も、ある――。三句目。安倍公房の「砂の女」の反転。――砂の山は擂鉢状に逆に屹立している――その崩れる砂――砂――砂――そこから這い出してくる蛆――蛆――蛆――そこから羽化する蠅――蠅――蠅――無数の蠅――それはしづ子というどっこい生きてる
〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年五月二十二日附句稿十七句より 一句
倚る樹膚かなしきときは雲を見る
◯鈴木しづ子 三十二歳 『樹海』昭和二十七(一九五二)年六月号掲載句全四句 貝殻
この全四句には表記通り、掉尾の句から「貝殻」という標題が附けられているが、以下に私が投句稿の日附を( )で示したように、この「貝殻」というのは巨湫による恣意的な仮想標題であり、句群としての集合性は実は全くない。『樹海』だけを我々が読むと、これらの句を「貝殻」という連続したソリッドな有機体として読み誤ることになる。そこは大いに注意しなくてはならない点であると私は思う。
貝殻
この星や浮塵子の如く家郷なし (三月十一日附)
眞對へば陸が近づく花菜の黃 (四月十五日附)
人の子や親しめば柿柚子など呉れ (一月 二日附)
秋風裡掌に容れし貝殻散らす
なお、この標題とされた掉尾の句――私はこの句が好きだ――は、大量投句稿の中に見出すことが出来ない。「秋風裡」はしづ子の好きなフレーズであったと思われ、前年の昭和二十六年十一月二十九日附投句稿に、
秋風裡女體の息を想ふこと
があり、同じく書き溜めた前年の句柄と思われる、季節外れの昭和二十七年三月三十日附投句稿にも、
秋風焜爐の■に炭碎き
(「■」は底本の判読不能を示す記号)が、また、大量投句稿の日附不明の部にも、
秋風裡わさびきかせの鮨を喰ふ
がある。これらから、しづ子には現在知られる大量投句稿以外に散佚してしまった句稿群が存在することが分かる。それは、最早、俳句に何の関心も持たない子孫によって、誰かの亡き父や祖父のがらくたと一緒に、今もどこかの筐底に紙魚に喰われつつあるのであろう……
〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年六月六日附句稿二十四句より 六句
木蓮の花の搖らぎや轉轍音
足ふめばこころ妖めく銀砂かな
醉い果ての月の蒼さを哀しめり
夏蟬や病ならざる一つの死
逝く春の薔薇吹く風に棲み古れり
蠅打ちてけふのおのれの在りにけり
二句目「妖めく」は「なまめく」と読む。またこの下五は底本「銀砂かふ」であるが、底本の判読では、しばしば「な」の草書体を「ふ」と誤読しておられ、明白であるここも、勝手ながら訂した。三句目「醉い」はママ。しづ子の誕生日は六月九日。ここまでがしづ子の満三十二歳の句。句稿最後に配された「蠅打ちて」の句はそれを意識しているように感ぜられる。
〇鈴木しづ子 三十三歳 昭和二十七(一九五二)年六月十五日附句稿五百四十六句より(1) 四句
恐るべき膨大な数の句稿である。この前の二本(五月二十二日附・六月六日附)の句稿は極端に少なく、その前も七十七句、その前の四月十五日附句稿の中間部からは肺に関わる体調の不良や病臥を詠んでいたが、ここにきてしづ子の体調(少なくとも肉体的な)がやや快方へ向いてきた印象が句柄からも持てるように思われる。
*
惜春や衣みどりや双つ肩
句稿巻頭。きりりとした決意は、虚子の赤裸々な「春風や闘志いだきて丘に立つ」なんぞよりずっと映像的で嫌みがない。
*
春蟬や湯の面に落とす指の布
しづ子独特の美事なクロース・アップのカメラ・ワークが戻ってきた。私は凡夫であるから有名な法師温泉の高峰三枝子の広告写真を思い出す。いいや、私は実際に誰もいない法師温泉で独特の春蟬の鳴く二日間を実際に過ごしたことがある。だからこの句がリアルに感ぜられるのである。
*
春晝の溝うつくしく流れけり
『雨が二階家の方からかゝつて來た。音ばかりして草も濡らさず、裾があつて、路を通ふやうである。
*
わが十指花栗の香にまみれけり
栗の花の匂いには、男性の前立腺から分泌するスペルミンC10H26N4というポリアミンが含まれている。栗の花はしばしば精液の匂いと同じだとされる。私に高校生の時、このことをちょっとはにかんだ笑顔で教えてくれたのは、理科の先生でも、ませた友人でも、なかった。私の母であった。
〇鈴木しづ子 三十三歳 昭和二十七(一九五二)年六月十五日附句稿五百四十六句より(2) 六句
ガーベラの朱が搖れます氣欝症
ガーベラの花言葉は「希望」・「常に前進」・「辛抱強さ」、特に赤は「神秘」・「燃える神秘の愛」で、愛の告白やプロポーズに使われる。面白いことに現代のフラワーセラピーでは「赤いガーベラは低血圧・頭痛・眩暈に効くとある。
*
冬もルムバ火の鳥めきて踊りけり
ウィキの「ルンバ」によれば、『キューバの伝統的な Rumba はキューバに奴隷として連れられてきたアフリカ人によるもの。アフリカの神々に捧げるサンテリアなどの黒人宗教音楽から派生したキューバの郷土娯楽音楽』とある。ここにきて、踊り巫女しづ子も健在である。中七「火の鳥めきて」が利いている。
*
壁越しの怒聲五月雨強む夜
この頃、しづ子は長屋かアパートのような貸家に住まっていたらしく、しばしば壁越しのこうした、隣人の生活句が現れる。しづ子の聴覚的な面白さのある句であるが、そこにはそうした現実社会とは実は半ば切れたような、仄かな一種の遁世者の「隣りは何をする人ぞ」といった冷めた意識も感じられる。
*
戰なし夏が近づく垣間の燈
恋人ケリーの精神を病ませ、遂に死に至らしめた朝鮮戦争は、前年からの休戦協定の模索の中、この昭和二十七(一九五二)年一月には実質的な休戦状態に入っていた。但し、その結果として同一月十八日には軍事的に余裕をもった韓国が李承晩ラインを宣言、竹島や対馬の領有を宣言して連合国占領下の日本への圧力を強め始めてもいたのだが。
*
まざまざとことば交はしぬ夏の夢
しづ子が交わした相手は誰だったのか――戦死した初恋の相手か――亡きハリー・クラッケか――二度と逢わぬことを秘かに覚悟した、そしてこの句稿を読む師巨湫か――いや、これを読んでいる、そう、あなたかも知れない――しづ子の句とは――そういう不思議な魅惑を、持っているのである――
*
水中花かなしき時も花たもつ
水中花 伊東靜雄
水中花と言つて夏の夜店に子供達のために賣る品がある。木のうすい/\削片を細く壓搾してつくつたものだ。そのまゝでは何の變哲もないのだが、一度水中に投ずればそれは赤靑紫、色うつくしいさまざまの花の姿にひらいて、哀れに華やいでコツプの水のなかなどに凝としづまつてゐる。都會そだちの人のなかには瓦斯燈に照しだされたあの人工の花の印象をわすれずにゐるひともあるだらう。
今歳水無月のなどかくは美しき。
軒端を見れば息吹のごとく
萌えいでにける釣しのぶ。
忍ぶべき昔はなくて
何をか吾の嘆きてあらむ。
六月の夜と晝のあはひに
萬象のこれは自ら光る明るさの時刻。
遂ひ逢はざりし人の面影
一莖の葵の花の前に立て。
堪へがたければわれ空に投げうつ水中花。
金魚の影もそこに閃きつ。
すべてのものは吾にむかひて
死ねといふ、
わが水無月のなどかくはうつくしき。
〇鈴木しづ子 三十三歳 昭和二十七(一九五二)年六月十五日附句稿五百四十六句より(3) 一句
蕾薔薇莖はふかぶか水に沈め
しづ子の好きな「蕾」と「薔薇」と「水」。冒頭の四字はイマージュの画面に確信犯のくさかんむりの漢字による強靭な視覚的効果を与え、「沈め」という連用中止法も利いている。
〇鈴木しづ子 三十三歳 昭和二十七(一九五二)年六月十五日附句稿五百四十六句より(4) 北海道追懐句群十七句
石狩の林檎をかじりをはりたり
死に難しかくもしたたる蝦夷の夏
北海の浪のしぶきや夏の航
蝦夷の地へこころ走るや山邊の燈
生きるべし蝦夷はまつたき夏みどり
北海を渡るこの體ぞ胸熱し
折り待てる鈴蘭萎ふこともなし
逆卷ける浪に投げけり一莖を
海渡る髮にかざせし鈴蘭かな
鈴蘭やわが二十代けんらんと
石狩の夕燒けに染む十指かな
陸見え來指に落とせし煙草の火
旅の體に蝦夷の夕燒け濃かりけり
旅果てり蝦夷の角卷見ることなく
夕べ濃きひと日の蝦夷を離りたり
樺太は識らず夏めく白夜かな
石炭の蝦夷に來て泊つ靑菜汁
北海道追懐句群。しづ子は実は北海道に住んだことがある。しかしそれは大正一四(一九二五)年、しづ子六歳の時のことで、これらはその遙か四半世紀も前の回想吟なのである。あなたは六歳の記憶をこれだけのパワーを以て詠えますか? 私には出来ない。
「折り待てる」の句の「萎ふ」は「しなふ」であろうが、通常は「しなぶ」で「しなびる」の意である。
「鈴蘭や」の句は、北海道の追懐ではなく前句の「鈴蘭」に触発された感懐句であろうが、連続性を認めて採った。
「陸見え來」や「夕べ濃き」の句柄は不思議である。これはあたかも大人になった、若しくは句稿を投じた近々に一日だけ北海道を訪れたかのような句柄である。夢想句かも知れないし、事実、実はしづ子はこの頃、何らかの理由で北海道を再訪していたのかも知れない。謎である。一つだけ、私が気になることがある。それはこの前の年、昭和二十六(一九五一)年に黒澤明監督の「白痴」――ドストエフスキイの「白痴」を北海道に移して脚色――が公開されている点である。しづ子はこの映画を見て、この想像を絶したタイム・スリップの大ジャンプ句群を美事に成し遂げたのではなかったろうか? さすれば、私は、私の大好きな原節子演じる美しい角巻姿(以下の注を参照)の那須妙子に、しづ子はシンクロニティしたはずである。これらの一見、現在形北海道実景句は、悲劇のヒロイン那須妙子――ナスターシャになったしづ子の演技ではなかったか?――と夢想するのである。
「旅果てり」の句の「見ることなく」は底本では「見ることふく」であるが、草書体「な」の誤読と判断して訂した。「角卷」とは「かくまき」と読み、北国で女性が外出する際に身に纏った防寒着の名称である。サイト「北海道人」の「角巻ものがたり」によれば、『大きめの四角い毛織物で、三角に折って背中から羽織るように着た。ショールとも違う、すっぽりと体が入るくらいの大きさで、色は茶や赤、紺などさまざま。四角形のふちには房があり、歩くとさらさら揺れた』。このファッションは明治期から現われ、昭和三十年代には姿を消したとあり、『この角巻は、北海道だけの風俗ではなく、東北地方や北陸地方など、北国に広くひろがった冬の風物詩だった。』ルーツは赤ゲットにあり、『女性にとってみれば、ショールやマントのようにまとえ、和服でも洋服でも合わせることができ、しかも断然に温かい角巻は、実用性とファッション性を兼ね備えたものだった』とあり、この記者は『かつて母の角巻に包まれて幸せだった子供たちの姿も、もう見ることはできない』と結んでおられる。――角巻――如何にもしづ子に似合いそうではないか――
川村蘭太氏の「しづ子 娼婦と呼ばれた俳人を追って」によれば、しづ子の父俊雄の渡道は、大正末から昭和初年で、陸軍のシベリア測量班としての出兵のための訓練を受けるためであったと推定されている。『俊雄は、家族に自分の勇姿を見せたかったのだろう』とあり、『家族で棲む北海道。叔母の朝子も祖母たちもしづ子の手を握って、北海の風景に見とれていたのだろうか。鈴木家にとって、それは一番の至福の時であった。』しかし、川村氏は続けて言う。『しづ子が当時の子供時代に戻ってこの俳句を詠んでいる。家族の前から姿を消す覚悟の上で作句している。哀れである。巨湫もかつての恋人も知らない、家族との思い出である。』――しづ子の人生の楽園は、もう二十五年以上も前の霧の彼方へ、とっくに消えていたのであった――
〇鈴木しづ子 三十三歳 昭和二十七(一九五二)年六月十五日附句稿五百四十六句より(5) 二十八句
大輪の朝顏ゑがく種袋
好きだね。俳諧本来の諧謔とアイロニーが写生に生きているではないか。
*
父の如まさに落日在りにけり
詠んだ者勝ち。いいじゃないか。
*
惜春や壁にかたむくマリアの像
悪くない。初五が嵌まり過ぎて少し観念に堕ちるか。
*
尾張路や自轉車に積む荷の芒
いいね! 子規も褒めそうな。
*
煤煙のながれゆく方冬鷗
底本「ふがれゆく」。訂した。長回しのゆっくりとパンするカメラがいい。
*
またしてもぽつかり割れて夜の胡桃
三鬼の「夜の桃」を意識しながらも、女らしくインスパイアしたクロッキー風の佳品。
*
胡桃燒くわれに一つの宿命あり
ファム・ファータル――その名はしづ子――
*
秋白く追ひつめられてゆく思かな
声に出して詠むとこの句の美しさが、分かる。
*
雲下りて十藥白し美濃の果て
「十藥」は「どくだみ」。霧のような雲と一緒にゆっくりとティルト・ダウンして、ドクダミをアップ――急速にバックして広角で美濃の全景をアオリで撮る。
*
たんぽぽや■美と知多が圍ふ海
この底本の「■美」は「渥美」でしょう。
*
死してありよべはなやぎし螢どち
詩語の選びと表記が絶妙である。特に下五の「どち」が上手い。
*
酒を嘔く泪ぎらつく月の前
雲間の月土曜日曜いとま得ず
あてどふく働きつづく月の西に
疲れし體西方よりの月に佇つ
この日頃なりはひたたず梅雨めく雲
月朱し醉ふほどに酒飮まされて
「嘔」は底本では「※」=「口」+(「偪」-「亻」-「田」+《「田」の位置に》「匹」)であるが、「嘔」と判断した。珍しくポーズのない、しづ子の生活に疲れた句群である。この後にも仕事で飲んで嘔吐する句が続く。
*
蠅の屍に蠅が寄りきて離れざる
いいね――慄然とするエッチングだ――
*
不思議にも荒れざる膚や夏の貌
夏ちかづく素顏の膚や小麦いろ
堕ちきれず寒月は地にびつしりと
しづ子はやっぱり小麦色のぴんとした健康な女である。しづ子は堕ちない。
*
石を蹴るときは悲哀のこころあり
『あるひは(つまづく石でもあれば私はそこでころびたい)』(尾形亀之助「障子のある家」巻頭)
*
とほからず行く上海や夏の海
夢の銀河鉄道『「しづ子」伝説号』は大陸行の片道船便も用意されています――どうぞ、ご自由に――上海バンスキングと参りましょうか――
*
腋毛濃しさんさんと湧く雲間の陽
私はこの句が好きで好きでたまらない――
*
氷■中突きて散らさむ五體かな
鴉群る■漠に置けりおのが屍を
この二つの句、判読不能字の存在故にこそ魅力的である。
*
人買ひに買はるるもよし夕鴉
しづ子のしづ子による「しづ子」伝説は「オルレアンの噂」の域にまで達していたのですね――
*
うべなふや薔薇くれなゐの花ことば
底本「うべふふ」。訂した。句鑑賞に花言葉を添えるのを、自分ながら胡散臭く思う部分が私にはあるが、それでもこれは添えずにはおくまい。赤い薔薇は「愛情」「情熱」「熱烈な恋」、中でも濃い赤の薔薇は実は「内気な恥じらい」である。しづ子がうべなうのはこっちだと私は思う。
〇鈴木しづ子 三十三歳 昭和二十七(一九五二)年六月十五日附句稿五百四十六句より(6) 八句
冷藏庫あがなひし折倖せに
冷藏庫の扉閉ぢつつ笑みしことなど
人還るおもひに棲めり食む氷菓
冷藏庫の扉開けては閉ぢにけり
過ぎ失せし愛の記念や冷藏庫
死によりて斷たれし愛や氷菓美し
嚙む氷菓うべなひ難き一つの死
國際愛とは氷菓にほどく厚き紙
「冷藏庫あがなひし折倖せに」の「あがなひし折」は底本では「あがなふし」、「嚙む氷菓うべなひ難き一つの死」の「うべなひ難き」は底本では「うべふひ難き」。訂した。冷蔵庫と氷菓を詠んだ十七句に及ぶハリー・クラッケ追悼句群の一つから。昭和二十二年頃から売り出された冷蔵庫はとんでもない高級品であった。川村氏によれば、しづ子がGIのハリーと同棲したのは昭和二五(一九五〇)年十月頃からと推定され、翌年五月頃には朝鮮戦争に彼が出兵、八月にヒロポン中毒なって帰日、即座にアメリカに帰国した。しづ子の一瞬の「倖せ」を思い出させる冷蔵庫と氷菓(自家製製造器によるアイスクリームかシャーベットであろうか)――哀しい「記念」(かたみ)であった――
〇鈴木しづ子 三十三歳 昭和二十七(一九五二)年六月十五日附句稿五百四十六句より(7) 不思議ながじゆまる句群より十句
かりそめにあらざる契りがじゆまる葉
がじゆまるの葉の滴りも小豆島
海荒れの雲のうごきや南の國
海流に沿ふて流すやがじゆまる葉
たがひ持つがじゆまる葉の靑さかな
かりそめの言の不吉さがじゆまる葉
裂きて持つがじゆまる葉よ離るまじ
古りけり吾手に残るがじゆまる葉
指に折る書より出でしがじゆまる葉
片割れのがじゆまる葉よ夕べ濃く
哀戀や裂けば破るるがじゆまる葉
不思議な句群である。「がじゆまる」を詠み込んだ連続する十七句から。そもそもこの「がじゆまるの葉の滴りも小豆島」を示さなければ、ここにある句群を小豆島だと思う読者は皆無である。今なら普通に沖繩の詠と誰もが読む。「南の國」「海流に」は正に沖繩に、「がじゆまる」の生い茂るそこにふさわしい。岐阜から見れば小豆島は南で、温暖な島国ではあるし、瀬戸内海も海流は流れる――と言われていも、やはり「がじゆまる」と「小豆島」は意外中の意外、私にはオーパーツである。だいたいガジュマルは日本では主に南西諸島にしか自生しない。小豆島は温かいが、ガジュマルが生えているとは思われない。何らかの植物園内なら考えられるが、この昭和二十七年代にそうした施設があったのか? いや、オリーブの島ならガジュマルも生えるか、ともかく小豆島に現在若しくは過去にガジュマルの木があるかあったか、御存知の方、御一報頂けると幸いである。ネット上の検索では見当たらなかった。
そして次は、このシチュエーションの謎だ。
――私は――あの「がじゆまる」の木の下に、恋人と一緒に佇んだのを思い出す――
――そこで私たち二人は葉を何枚か千切り――そのうちの一枚の葉を二つに千切って――それぞれに裂いて持つた「片割れのがじゆまる葉」、その「がじゆまる葉よ離るまじ」と――確かにそこで永遠の愛を契ったのだった――
――二人して歩んだ美しい砂浜――私たちはそこで何枚かの「がじゆまるの葉」を流して戯れたりした――楽しかったあの日――
――でも、ふと呟いた言葉の中に「かりそめの言の不吉さ」が混じっていた――
――それは今や本当になってしまったわ――
――あの時の「がじゆまる」の葉――それが今、私の手の中にある――すっかり古びてしまったけれど――大好きな本の栞にしていたの――
――ああ、私の哀しい恋――
――もう、あなたは、いない――
ピッ……
――「裂けば破るるがじゆまる葉」――
この「がじゆまる」の木は現に生えている。「葉」だけではない。でなければ「たがひ持つがじゆまる葉の靑さかな」とは詠まない。不吉な言上げは、これを呟いたのがどちらかかは分からない。ともかくもそれは二人の思いもしなかった離別や死別を暗示させるものであったということである。しづ子はこの「がじゆまる葉」連禱十七句の最後に――その「がじゆまる葉」を裂いて粉々にしてしまう――夕暮である――
最後に。この相手は誰か。――恋人・旅行・南国・離別、そして現在もしづ子の中に深い思慕の情が現存する――私はハリー・クラッケしかいないと思う。
〇鈴木しづ子 三十三歳 昭和二十七(一九五二)年六月十五日附句稿五百四十六句より(8) 二句
貞女とは秋をきらめくダリアの緋
烙印を押されてしまひぬダリアの緋に
この二句に共通するのは、少なくとも意味深長な解釈を許すのはダリアの花言葉「栄華」「華麗」そして「移り気」以外にはない。しづ子はやはり花言葉に精通していると私は思う。本邦での花言葉の普及はネット上の情報によれば、昭和初期に発売された小学生相手の趣味の本に、既に花言葉の解説が掲載されているとあり、花言葉の流行はかなり早いと考えてよい。
〇鈴木しづ子 三十三歳 昭和二十七(一九五二)年六月十五日附句稿五百四十六句より(9) 二句
わが神は魔なり黑髮かく長く
神よりも魔親しも身ほとり風光る
一句目の中七は底本では「魔ふり黑髮」であるが、訂した。
〇鈴木しづ子 三十三歳 昭和二十七(一九五二)年六月十五日附句稿五百四十六句より(10) ハリー・クラッケ哀傷句群全三十六句
テキサスの春を傳へてあますなし
人の母老いけり梅雨の月薄く
旅費送るともいはれつつ春の雪
テキサスの花むらさきに文重し
米語におもふことばの崩れ月梅雨めく
月梅雨めくなりゆきなりといふ觀かた
異つ國のことば習ふやアマリリス
レベツカと讀みし署名や梅雨燈下
うつしゑや雪消え山そびらにし
人の母の情に涕きぬ梅雨燈下
人の母にまみゆることや春の雪
春の雪うつしゑをもてまみえけり
耐えしめずうつしゑに見し人の墓
習ひのごと十字を切りぬ梅雨燈下
墓碑の面の名は讀めざりき雪被き
梅雨激ちケリー・クラツケ在らざるなり
信ぜざるべからず梅雨の降り激ち
梅雨の降りとどめを刺されし如くにて
激つ降り人のうつしゑ棄てにけり
夕星やうべなひ難き見えざる死
梅雨燈下海■りきし文と品
梅雨の燈やおののきほどく文の端し
やうやくに返事したたむ牡丹かな
英字にて署名をはるや梅雨激つ
花椿たがひかよはす文あらぬ
鬼灯や人のことには觸れず書く
テキサスまで送るべき文夏薊
夏薊週餘ののちに届くべし
靑葉濃き木曾のうつしゑ送りけり
梅雨の燈や緣者あらざることも似て
老い先は短かからむといふを讀む
人の母のうつしゑを見ていねがたき
蔦の葉や老いの身が言ふ金のこと
蔦の葉や子を喪ひしことの文
文を見て涕かされしことからむ蔦
からむ蔦それもこれも運命かな
ハリー・クラッケ哀傷句群とは私の仮題である。私がそう判断する連続する全三十六句を総て採った。この連作には注も不要、如何なる俳句的批評も無効である。このハリーの母レベッカ母さんの、雪を被ったケリーの墓の写真を、送られてきたケリーの遺品を、胸に抱いて涙するしづ子に共感しない者は(そんな輩は私はいないと信ずるが)、しづ子自体を語る資格が全くない。遙かなテキサスのレベッカの映像さえ見える。それは、しづ子がこのレベッカに実母綾子を完全に重ね合わせているからに他ならない。SEは終始、頭上に降り、身の周囲をたぎるように流れ落つる雨音である。
(雨音。)
――燈下に送られてきたケリーの生前最後の写真に見入るしづ子――
――泣きながらゆっくりと、細かく、ケリーの写真を破るしづ子の手――
――燈火のしづ子、哭く――
(雨音、激しくなる。F・O・)
「墓碑の面の」の下五「雪被き」は「ゆきかずき」と読んでいよう。
〇鈴木しづ子 三十三歳 昭和二十七(一九五二)年六月十五日附句稿五百四十六句より(11) 二句
書きつつにおのれ涕く夜の燈蛾かな
燈蛾捉へたり手に持つものと壁のひま
二十七句に及ぶ、手紙をしたためる夜の句群から。ケリーの母レベッカへの返信と思われる。
〇鈴木しづ子 三十三歳 昭和二十七(一九五二)年六月十五日附句稿五百四十六句より(12) 三句
鳳仙花むかしわが詩やさしくて
鳳仙花まことは弱き女人にて
鳳仙花まことの姿知らしめず
ホウセンカの花言葉は「快活」「私に触れないで」「せっかち」である。
〇鈴木しづ子 三十三歳 昭和二十七(一九五二)年六月十五日附句稿五百四十六句より(13) 一句
水中花故郷は遠くなるばかり
〇鈴木しづ子 三十三歳 昭和二十七(一九五二)年六月十五日附句稿五百四十六句より(14) 十四句
ひとごとと聞きながしつつ柿の花
おのが言おのれに還るや柿の花
世の人の眼の確かさよ柿の花
評さるる吾はここにあり柿の花
わが詩はわが詩なりに柿の花
香水やいつはりは亦美しく
香水やいつはりは亦難くして
香水や狎るれば僞言恥づるなく
告げ得ざる師へのいくつか梅雨めく雲
わが詩にいつはりありや梅雨めく雲
讀むひとの意の異りや梅雨燒けて
詩の意の曲げらるること梅雨燒けて
辯ぜざれば梅雨の夕雲朱かりき
離りきて師ぞしろしめす梅雨の雲
これは句集『指環』の齎した「しづ子」伝説へのしづ子の――半ば諦めた半ば尻を捲った――一つの感懐である――
〇鈴木しづ子 三十三歳 昭和二十七(一九五二)年六月十五日附句稿五百四十六句より(15) 掉尾三句
指あはれ汗とインクといづれが濃き
とどまればあふるるほどの暑さかな
百姓の夕べ歸や雲と水
この三句、名吟であると私は思う――語りつくした後の名吟である――
〇鈴木しづ子 三十三歳 昭和二十七(一九五二)年六月十五日附句稿百六十五句より四句
梅雨降れり混血の子がうようよと
父にもち黑人兵を死なしめし
雪美しき國への帰化を希ふとか
ゆく雲や妻を愛せば帰化ならむ
「梅雨降れり」の「混血の子が」は底本「混血のるが」であるが、以上のように独断で変えた。上五も何だか座りが悪い。「父に持つ」ではありまいか。「父にもち」の句の「死なしめし」は底本「死ふしめし」。訂した。以前、しづ子が頻繁にこうした混血の児童や孤児を保護した施設を仕事の合間に訪れていたように思うと書いたが、やはりそれを感じさせるもので、生活句の中にぽんと放り込まれた連続する二句である。
後の二句も連続する二句であるが、これもおや? っと感じさせる句である。この「雪美しき國」は日本、ダンス・ホールで「日本人のワイフを愛しているから帰化しようと思う」としづ子に語りかけているのはクラブへやってきたGIということになろうか。
この句稿、冒頭で勤め先の集団性病検診の景を詠んだり、「靑蔦」や「梅雨」「セル」の多量連作句が並び、見た感じがそれら「蔦」「梅雨」「セル」の文字が恰も総譜の通奏低音のように見えたりもするのだが、残念ながら私の琴線に触れてくるものはなかった。
〇鈴木しづ子 三十三歳 昭和二十七(一九五二)年六月十七日附句稿「白痴」句群六十二句より十五句
この句稿は一見一読、ともかく強烈である。私が差別的ニュアンスをも避けずに敢えて全句を「白痴」句群としたのは、この全句が重い知的障碍を持った近隣の知れる女性を詠んだ完全な六十二句連作で、途中の一句と最後の五句を除いて総ての句に「白痴」が用いられているからで、この六句も、一句は牡丹の前に佇んだその娘からの散った牡丹の花へのティルト・ダウン、以下に総て採った最後の五句も娘が眼前から去った後の余韻句として詠まれているからである。そこでしづ子は、この『狂人の娘』を「白痴」の語を連打して一見、残酷悲惨冷徹に描いているように見えながら、その実、この『狂人の娘』の中に、まさに女人としての哀しき『人生の狂人の娘』たるしづ子自身を見つめていることがはっきりと分かってくる。私の選句はそれを伝えるに不十分である。底本によって全句の通読をお薦めするものである。
せつなけれこころ白痴に媚態せる
白痴にてこころ深げに形りに佇つ
白痴佇てり夕燒けは血の如くして
白痴佇てり親あれば髮美しく
白痴佇つやつねひらかれてうごかぬ眼
昏れがての雲のうつろひ白痴佇てり
白痴佇てり吾とひとしき女體もて
白痴失せぬ雲の夕燒け消えしより
せつなけれこころ白痴に髮黑く
白痴の眼牡丹の一點を捉へたり
白痴にて女人の步みたもちつつ
生きるべし梅雨の夕燒けしたたる如
梅雨燒けや五體そろへばありがたき
梅雨燒けぬこころゑがける祈りの手
この刻や生ひしひしと梅雨燒けぬ
泪しておのれに言ふや梅雨燒けぬ
二句目「白痴にてこころ深げに形りに佇つ」は底本では「こころ深けに」。独断で濁音化した。下五は「なりにたつ」と読んでいよう。
冒頭にも述べた通り、この最後の五句が差別的な「白痴」をメタなレベルへと引き上げてゆく。「夕燒け」の生々しい生き血の「したたる如」「生きるべし」――生きよ――と叫び、「五體そろへばありがたき」と感じているのは『狂人の娘』へであると同時に、しづ子自身への強烈なエールである。「こころゑがける祈りの手」は『狂人の娘』の艶めかしく美しい白い祈りの手であった映像が手へフレーム・アップして、再びティルト・アップするとそれはしづ子である。「この刻や生ひしひしと」「泪しておのれに言ふ」言葉は――あの子は私――というしづ子のモノローグなのである――
――僕が小学生だった時、通学路のすぐ脇に一軒の旧家があった。いつもその縁側には朝も夕も年中同じ白木綿の寝巻を羽織った、燃え立っているいるかのように真っ黒な髪の毛の、その髪のまた、恐ろしく豊かな、四~五歳ほど私よりか上と思われる小太りの少女が座っていた。学校には行っていなかった。通る時に皆で彼女のことを覗いたりすると、彼女は必ず嚙み付くように「なんダヨ!」と奇妙なアクセントで、ねめつけながら僕らを怒鳴ったものだった。――私は今も――何故だか彼女の顔を忘れられない。彼女は今、どうしているのだろう――彼女は――私の幽かな心の疼きとともに、時々浮かんでくる『永遠の少女』なのである――
〇鈴木しづ子 三十三歳 昭和二十七(一九五二)年六月二十日附句稿二百五十一句より 十三句
二百五十一句としたが、実際にはこの句稿はもっと多い。途中に編者による丸々四ページ分の『判読不能』注記があるからである。底本の本文に画像で示されている一部句稿を見るに、一枚宛八句表記であるから、単純にこれで計算しても四枚で三十二句、この句稿は実際には二百八十句を有に越える句稿である。それに加えて、この句稿は保存状態が悪かったのか、異様に判読不能字も多い(判読不能字を含む句は実に二十七句に及ぶ)。また編者に失礼ながら、誤読と思われる字も、また多い。
菊は地に天に勝利のピストル音
冒頭の「ピストル」連作の一句。これらの一連の句は昭和十一(一九三六)年の山口誓子の著名な句「ピストルがプールの固き面にひびき」に触発されたものであろう。他の句柄から小学校か何かの秋の運動会の何メートル走かの種目競技の嘱目吟であるが、この句だけを取り出すと総てが役割を変じて不思議なおどろおどろしさを醸し出すではないか。一種の天狗俳諧、俳句のマジックである。面白い。そうした読みを断固拒絶なさるなら、俳句を棄てたがいい、と私は本気で忠告する。定型俳句の物理的論理的限界性を見据えずに花鳥諷詠だの伝統俳句だのとほざく輩は私の知己ではない。
*
蛇死して子供あそべり夏旱
蛇死すと步を早めつつ徑をそれ
「蛇死して」は底本では「蛇死してる供あそべり夏旱」であるが、独断で変更した。
以下は、私がかつて卒論で鑑賞した尾崎放哉の句鑑賞の一つを用いた。しづ子の句はこの「蛇が殺されて居る」の近親句である。
蛇が殺されて居る炎天をまたいで通る
炎天下、蛇が殺されて横たわっている、つぶされて、生臭い体液を土ににじませて。それを避けることも出来ない細道なのか、それともあえてその凄惨な現場をまたごうとする不思議な心理か。
惨殺された蛇の屍をまたぐのを、「炎天をまたいで通る」と表現したところに一種ぞっとするような俳諧味がある。太陽のギラギラした直射、埃っぽい乾燥感のなかにあって、ただ蛇から流れ出た血だまりだけが、湿り気をもって、生々しく迫ってくる。
私はこの句を読むにつけ、芥川龍之介が大正六(一九一七)年の『中央公論』に連載した「偸盗」の第一章の冒頭を思い出す。夏の蒸し暑い不潔な朱雀綾小路の、「車の輪にひかれた、小さな
『むし暑く夏霞のたなびいた空が、息をひそめたやうに、家々の上を掩ひかぶさつた、七月の或日ざかりである。男の足をとめた辻には、枝の疎な、ひよろ長い葉柳が一本、この頃
下手な解釈を下すより、芥川のこの一文の示すところが、放哉の――そしてしづ子のこれら句の持つ生理的実感を如実に伝えているではないか。
*
爆擊下炎日の河流れつき
ハリーの朝鮮戦争での体験を聞き書きした間接体験の句と読めなくもないが、前に「夏盛る東京をのみ記憶とし」とし、後に「望郷や瓦■の草の吹きつぎて」とあるから、しづ子の空襲体験に基づくものと読みたい。但し、季節が異なることから所謂、知られた昭和二十(一九四五)年三月十日のような大規模な東京大空襲での体験ではないと思われる。東京は本土初空襲であるドーリットル空襲(ドーリットル中佐指揮のB-25中型爆撃機編隊十六機による)による昭和十七(一九四二)年四月十七日以降、実に百回を有に越える空襲を受けているが、しづ子はその間、岡本工作機械製作所設計課トレース工として日吉工場に勤務していた。東京の衛星都市で工場群も多かった神奈川も昭和二十年五月二十九日の横浜大空襲等、大きな爆撃を受けている。
*
吾らが手一夜の爐火を絶やしめず
この句の前後には愛する相手を詠った句が並ぶ。例えば前の方には「雪こんこん吾らが愛に國境なし」「薔薇白く國際愛を得て棲めり」とあるから、ハリー・クラッケの追悼句群と捉えてまずは間違いないのであるが、実はこの句の前にあるような「雪崩」「雪」となると、これは前に掲げた『樹海』昭和二十三(一九四八)年五月号の「山の殘雪この夜ひそかに結婚す」「雪崩るるとくちづけのまなこしづかに閉づ」「春雪の不貞の面て擲ち給へ」の「雪崩」句群の頃の愛人『樹海』同人池田政夫の思い出へと変容しているようにも読まれる。もうこの頃には、しづ子にとって愛した男たちはすべてが遥か彼方の有機的な複合体として意識されていたのかも知れない。私はそれでいいと思う。実は私の過去への意識もしづ子のそれに近いからである。
*
銀漢や軍備を希ふ言多し
銀漢や戰忌む言胸えぐり
しづ子の時々ふっと胸を突いて出る社会性俳句。前に述べた通り、この時期、保安隊の発足が叫ばれ、再軍備化が進みつつあった。しづ子は賛成反対の二つの声を実に冷徹に謳いあげている。そこにはそのどちらにも組しない、組出来ない、そのどちらにも、邪な思いと嘘がある、と知ってるから、と呟くように。
*
驛柵の畫きて月下の道はじまる
萩原朔太郎「定本靑猫」より。
停車場之圖
無限に遠くまで續いてゐる、この長い長い柵の寂しさ。人氣のない構内では、貨車が靜かに眠つて居るし、屋根を越えて空の向うに、遠いパノラマの郷愁がひろがつて居る。これこそ詩人の出發する、最初の悲しい停車場である。
*
驛の井の蓋なきままに夏盛る
巧まぬ美事な写生である。
*
二十代ははや落莫と冬に入る
「二十心已朽」(李賀「贈陳商」)――二十にして心已に朽ちたり――歩こう、預言者――
〇鈴木しづ子 三十三歳 昭和二十七(一九五二)年六月二十三日附句稿百七十一句より(1) 一句
月光やかすめてすぎし殺意めき
初五はしづ子の好みからいって「つきかげや」と訓じているものと思われる。こういう猟奇句、私は大好きである。
〇鈴木しづ子 三十三歳 昭和二十七(一九五二)年六月二十三日附句稿百七十一句より(2) 一句
春雷といひてきこえのこころよし
しづ子の第一句集の題名は『春雷』、第二句集『指環』の名吟に「好きなものは玻璃薔薇雨驛指春雷」があるが、しづ子には実は文字として以上に、正に「いひて」、言葉として発した聴覚としての響きに対する偏愛があることを忘れてはならない、則ち、しづ子の句は読む以上に聴く俳句であることを我々はもっとディグする必要があるのである。
〇鈴木しづ子 三十三歳 昭和二十七(一九五二)年六月二十三日附句稿百七十一句より(3) 三句
指ふれのさくらはなびらとどましむ
底本中七「さくらはふびら」。訂した。
*
指に選る書はさむべき銀杏木葉
下五は「ぎんなんば」と読んでいるか。
*
八車の花の吹かれや母とほし
「八車」は花期から考えてバラ目ユキノシタ科ヤグルマソウ Rodgersia podophylla であろう。句柄にもに円錐状のあの白い花がよく似合う。但し、通常は「矢車」と書く。
〇鈴木しづ子 三十三歳 昭和二十七(一九五二)年六月二十三日附句稿百七十一句より(4) 三句
塔白き熱さまよひの夢なりし
白塔と蟻と熱砂と夢に病む
夢に病みて月美しき蝦夷の夏
「夢に病みて」の中七は底本「月美しさ」。独断で変えた。この辺り、死の翳りを潜ませたような不思議な夢の句が続くが、そこに師巨湫を憶う妙な句が挟まったり、「夢に病みて」からは幼少期の北海道の思い出がフラッシュ・バックしたような「札幌」「蝦夷」「アカシヤ」を詠み込んだ句が十句ほど続いたりもしている。
〇鈴木しづ子 三十三歳 昭和二十七(一九五二)年六月二十三日附句稿百七十一句より(5) 四句
千代女をのてかしはとしとする花火
千代女より久せ多住ると遠花火
白露やむかしはかかる詩でよく
夫失せの千代女の詩は露をいふ
珍しく加賀千代女の名を詠み込んだ句群から。但し、最初の二句は失礼ながら判読の誤りとしか思われない意味不明の文字列である。原本を見たい気持ちが髣髴として湧き起こる。後ろの二句は千代女の「露はまた露とこたえて初しぐれ」などを念頭に置くか。
〇鈴木しづ子 三十三歳 昭和二十七(一九五二)年六月二十三日附句稿百七十一句より(6) 「指環」改作 三十一句
本句稿の最後は『「指環」改作』と標題を附した三十一句からなる。句集刊行後半年にして改作句をこれだけ纏めて師に示すこと自体、私は異例のことと感じる。総てを見て行きたいが、「改作」と言いながら、厳密に校合したわけではないが改作の直接の原句が『指環』に見当たらない句が半分以上ある、というのが私の印象である。恐らくは『指環』で用いたところの過去のイメージのストックから、今作った句であるけれども『指環』に載せるならこっちを載せたかったと思う句が含まれているのではなかろうか。原句と思われるものを三字下げで示した。この句稿は変である。ともかくお読み頂こう。
*
「指環」改作
葉の松の年のはじめの黝みどり
原句なし。『指環』の新年の句は冒頭の
にひとしのつよ風も好し希ふこと
であるが、この改作には見えない。「黝みどり」は「あをみどり」と読む。
*
玻璃の面や凍みるほどにも疵走る
月蒼む吻ふれしむる玻璃のはだ
たんたんと降る月光げよ玻璃きづつく
原句は二句とも巧みな「捻じれ」が表現されているが、改作は物理学の実験みたようでつまらない。
*
早春のリボンはためく髮の先
春さむく髮に結ひたるリボンの紺
改作は凡庸なカメラマンのブレまくった写真。原句のスローモーションとアップと色彩に及ぶべくもない。
*
梅雨降りの激ぎちきたるやゼネスト日
雲ながれゼネストつづく熟れいちじく
やはり原句に軍配。噎せ返るようなゼネストの雰囲気が「熟れいちじく」の饐えたアップと美事に一致する。
*
ラケットの握りななめや靑葉光げ
テニスする午前七時の若葉かな
これは比較すれば改作句の方が動的でいいが、原句改作何れも凡庸な句であることに変わりがない。
*
うべなへば頭べ吹かるる秋芒
穗の芒こころそまざることもきく
どちらもよい。これは二句並べてしづ子の内心が確かに伝わるところの句であると言おう。
*
秋燈下履歴つづりてはばかるなし
秋燈下こまかくつづるわが履歴
これは無論、改作句に軍配。
*
春雷のそれきり起たず籠り宿
これと似ているものに、
默々と小包つくる春の雷
があるが、これは改作というより、連作の別シーンである。
*
潮の渦解けしのちにて潮流る
*
なにゆゑのあがきぞががんぼ玻璃をうち
ががんぼや雨の吹きつけ玻璃の面
ががんぼのあがきつつや玻璃のあめ
とび入りし玻璃のががんぼ騷々し
ががんぼのいきて息づく玻璃面かな
ががんぼの在らずなりたる玻璃の面
『指環』にががんぼの句は一句もない。但し、これと同じシチュエーションを蛾で読んだ連作は大量投句稿の中にはある。「ががんぼのいきて息づく玻璃面かな」の下五は底本「玻璃面かふ」。訂した。
*
じゅんじゅんと冬夜の蒸氣昇らしめ
對決やじんじん昇る器の蒸氣
これなどは最大最悪の改悪句にしか見えぬ。
*
懺悔めく冬夜の雨のいたりけり
*
みじろげばたがひの衣霧じめり
*
理性葉つ一夜の霧の妖めきに
「理性葉つ」はママ。意味不明。判読の誤りであろう。
*
たたずむは女人とおもふ蟲の闇
*
東京も北多摩べりのカンナかな
往還にカンナ花もつ病不可
カンナ花せいめい永し朝夕通る
何となく東京への懐かしさから地名を詠み込んだものの、これも駄句に堕してしまった。
*
雪崩るると衣あたらしき双の膝
*
居ごもりの蘇枋の濃かりけり
蘇枋濃しせつないまでに好きになつたいま
それにしてここまで改悪の駄句が並ぶと、これは一体どういうつもりで『改作』と名打ったのか――如何にも不思議の感にとらわれてしまう。この句群は何だか――やっぱり変である。
*
見上げれば星炎えいづる梅雨のひま
底本「梅雨のひき」。独断で変更した。
*
黑人うたごゑつづく花ふれり
黑人と踊る手さきやさくら散る
哀しい改悪のダメ押しである。
*
燈の柿のころがりてゐて娼家かな
ひまはりを植えて娼家の散在す
夏草と溝の流れと娼婦の宿
上五がやや不審であるが、悪くない。
*
移りて美濃の夕燒け濃かりけり
底本「美濃」は「美農」。訂した。
*
はずさるる汗の耳輪の靑びかり
*
疲るるなき十指の爪の汗じめり
この句は、もしかすると『指環』の掉尾、
朝鮮へ書く梅雨の降り激ちけり
の改作のつもりなのかも知れない。しかし、ケリーへの恋文を書くというよりも、つい先日の昭和二十七(一九五二)年六月十五日附投句稿の、ケリーの母レベッカへの返信を書くしづ子の映像にこそ、この類型イメージは沢にある。
*
まみゆると大赤に踏む梅雨の上
まみゆべし梅雨朝燒けの飛行場
「朝燒け」を「大赤」と言うのだろうか? 識者の御教授を乞う。
*
古し品をかたみとおもふ靑嵐
頒ち持つかたみの品や靑嵐
これが句稿の掉尾でもある。この最後の句が『指環』の改作句であることはご覧の通りだ。やはり、しづ子はこの凡庸な改悪句三十一句を、何故か分からないが『「指環」改作』と標題して巨湫に示したかったことが分かる。――私はあまりのことに――この句群は何らかの暗号なのではないか? この句をどうにかして配列すると何かの別なメッセージが浮かび上がってくるのではないか?――などと――今も疑っているのである――
〇鈴木しづ子 三十三歳 昭和二十七(一九五二)年六月二十四日附句稿百五十七句より(1) 四句
なにゆえに花にあめ降る石は白く
芭蕉を意識して贅沢な句であるが、字余りの下五に座り心地の悪さが残る。
*
わが眼より玻璃裏側を蟲の匍ふ
蜂の飛翔をなぜか哀しき眼もて追ふ
蜂が巣をしづ子の家のすぐそばに作ったらしい。刺されること怖がったしづ子は窓に金網を張った。二十数句に及ぶ連作から。
*
ダイナてふこの颱風を捲かれ
「捲かれ」は「まきつかれ」と読むか(そう読んでも私には「たいふうをまきつかれ」という破格文法は腑に落ちないのだが)。ただ私がこの句を採った理由は、しづ子の大量投句稿が正しくアップ・トゥ・ディトな、『現存在吟』であるということを示したかったからである。ダイナ台風は昭和二十七(一九五二)年の台風第二号で
六月二十日に発生している。国際名“Dinah”。六月二十三日に静岡県浜名湖付近に上陸、死者六十五人を出しているが、ネット上で検索すると、翌月の「アサヒグラフ」一九五二年七月十六日号は「台風ダイナ岐阜県下を襲う」という特集を組んでおり(標題のみで記事は未見)、しづ子のいた岐阜はその被害が甚大であったことを容易に想像させる。岐阜市の公式の大水害記録にも、二十三日のクレジットで、
ダイナ台風・台風規模中型・最大風速NNE10.8・最大瞬間風速 N12.2・岐阜県内の主な被害(死者1・負傷者29・床上浸水460・堤防決壊128・岐阜市水稲被害500ha
という記載が見える。
この句稿の日附に注意されたい。同年六月二十四日、ダイナ上陸の翌日である。この句は句稿の六十九句目、ほぼ全句の中央に位置している。やはり、しづ子は決してストックした句を易々と投句していたのでは、なかったのだ。正に強烈な「修行」として、日々時々刻々と精進していたのだということが、私にはここで改めて実感されたのである。俳句を消閑の具とするあなたには馬鹿馬鹿しいことかも知れない。私には、しかし、重大である。
〇鈴木しづ子 三十三歳 昭和二十七(一九五二)年六月二十四日附句稿百五十七句より(2) 西瓜七句
指はじきはじき西瓜の品さだめ
わが選りしにし西瓜の重み掌を替え持つ
識らざれば言はるるままの西瓜得て
西瓜得て黃昏のみち急ぎけり
西瓜割る燈しの下に板を据え
夜の西瓜かつと割るや刃の兩側
刃をあつるべく定まらぬ西瓜の位置
しづ子の誤字であろう、総ての句の「西瓜」は総て「西爪」。総て「西瓜」に訂した。「指はじき」の中「はじき西瓜の」は底本「はいき」。独断で「じ」の誤読と判断して訂した。「わが選りしにし」の「選りしにし」は誤字か誤読が疑われるが、「選りにし」の謂いであろう。「識らざれば」の下五は「西爪を得ふ」である。これは「得て」か「得し」か「得る」などが疑われるが、「累」の変体仮名「る」は実は最も「ふ」に近い。但し、次句の上五との一致から独断で「得て」とした。
私はこの西瓜連作、とっても好きだ。
〇鈴木しづ子 三十三歳 昭和二十七(一九五二)年六月二十四日附句稿百五十七句より(3) 一句
還らざることの確かさ蚊追香
「蚊追香」は見慣れない表記だが「かやりかう(かやりこう)」と読みたい。私は好きな句だ。
〇鈴木しづ子 三十三歳 昭和二十七(一九五二)年六月二十四日附句稿百五十七句より(4) 二句
美しく悲しきはなし星祭
七夕ややつぱり母の戀しくて
七夕は星祭りとも言う。しかし、「美しく悲しきはなし」とは、牽牛淑女のことであろうか? そうかも知れない。皆、そう読むかも知れない。しかし、私はこの句を読んだ瞬間、これは、もしや宮澤賢治の「銀河鉄道の夜」を詠んだ句ではなかろうかと夢想したものである。
〇鈴木しづ子 三十三歳 昭和二十七(一九五二)年六月二十四日附句稿百五十七句より(5) 五句
駐留軍キャムプへかよふ棗の實
タイプ打って必死の夏を過ごしけり
タイプ打つ W に當つる汗の指
夏葉吹き英文タイプにミス多く
タイプでは生活たたず棗嚙む
しづ子が岐阜へ来たのは昭和二十四(一九四九)年であるから、その後の二年間の夏の時期に、しづ子は進駐軍のキャンプでタイピストとして働いていたことがあるか、働こうとして米軍基地でタイプを習っていたことが、これらの句から推定される。川村氏は「しづ子 娼婦と呼ばれた俳人を追って」の二七〇頁で、ケリーとの交際の中でその機会を得たのかも知れないが、しづ子が米軍基地に勤務した形跡は見当たらず、しづ子がかつて『女子大学の入試に失敗したように、その夢もまた果たせなかったのかもしれない。この句が、ダンサーになる以前のものか、その後の句なのかは定かではない。だが哀れな心境ではある』と記されている。特に「タイプ打つ
W に當つる汗の指」は、しづ子の真骨頂であるカメラのアップが素晴らしい私の大好きな句で、二〇〇九年八月河出書房新社刊の『KAWADE道の手帖』の「鈴木しづ子」のエッセイで俳人の土肥あき子氏がこの句を鑑賞し、『浮遊した双手をわが身に引き寄せるように、タイプライターの上で悪戦苦闘するしづ子』の映像を語り、『しづ子の人生にもっとも大きな影を背負った、運命の指がそこにある』と語られている。この「Wを打てば」という文章、しづ子への評の中でも頗る名品であると私は思う。
〇鈴木しづ子 三十三歳 昭和二十七(一九五二)年六月二十四日附句稿百五十七句より(6) 一句
萬綠の岩に腰をきトマト喰めり
十数句のしづ子の好きな木曽川の渓流での句の中の一つ。巧まぬ画面の色彩の面白さが利いて、更に、ほっと一息ついているしづ子の美しいフル・ショットと笑顔が、見える。
〇鈴木しづ子 三十三歳 昭和二十七(一九五二)年六月二十七日附句稿百三十二句より(1) ケリー・フラッシュ・バック五句
八月を夢美しく病みゐけり
またたくは葉月をはりの遠燈し
短夜の夢はただよふ筑紫の野
汗わきつぐくらがり中のぎらつく眸
けんらんたる夏夜の夢の中に病む
これらの句は前年の夏の句と推定される。「筑紫の野」とあるのは、ケリーが朝鮮戦線から佐世保へ生還したことと関連するが、しづ子が佐世保へ向かった事実は確認されていないから、これは一種の想像句と読みたい。川村氏は「しづ子 娼婦と呼ばれた俳人を追って」でしづ子が慕った歌人の叔母朝子が敗戦後に中国から引き揚げた際の上陸地が佐世保であること、また同時期には『父俊雄が熊谷組福岡支店長代理として、同じ九州の福岡に義母と共に暮らしている。しづ子にとっては、この九州の地は因縁深いものがあ』ったと記されている(同書二七八頁)ことから、これはこの佐世保からのケリー帰還の連絡を受けたしづ子があくがれる心で詠んだものと思われるのである。――しかし、既に記したようにケリーはヒロポン中毒者となっていた――これらの句の「病みゐたり」「ぎらつく眸」「夢の中に病む」のは間違いなくケリーである。そしてこの映像は、佐世保から埼玉県朝霧へと移送されたケリーと面会した、しづ子の実感に基づくものである。病んだままにアメリカへ帰国し故郷テキサスで死んだケリーの面影は、幾度となく、こうして、しづ子の心のスクリーンにフラッシュ・バックするのである――
〇鈴木しづ子 三十三歳 昭和二十七(一九五二)年六月二十七日附句稿百三十二句より(2) 一句
揚花火女人の肩に似て崩る
〇鈴木しづ子 三十三歳 昭和二十七(一九五二)年六月二十七日附句稿百三十二句より(3) 五句
いなづまがくつきり摑む壺の形り
涼風の居のくらがりに人を招ず
野莓やみるみる暗む空の雲
雲下りて十藥暗し疾風起り
まつたくの沖の暗みや花茨
しづ子のモンタージュの感性上の上手さがこれらの句にはよく出ている。「涼風の」の句は不思議に凄みがある。最後の句は後に続く句から、しばしばしづ子が好んで行った知多半島の嘱目であり、その前の二句もその折りの句である可能性が高いと私は思う。因みに私の祖父藪野種雄は東邦電力の発電所技師として知多半島の根元にあった名古屋発電所の建造起動に携わり、後に知多南端の河和の町で肺結核のために亡くなった。祖父の遺稿はここに。私にとっても因縁の地である。
〇鈴木しづ子 三十三歳 昭和二十七(一九五二)年六月二十七日附句稿百三十二句より(4) 四句
醉ふを欲る一夜の酒や雨の沙羅
かかる夜は醉ふれ崩れむ雨の沙羅
花沙羅に雨はすばやくあがりけり
こころなき一夜の降りや沙羅双樹
「かかる夜は」の中七「醉ふれ崩れむ」は不審。
これらの沙羅句群、声を出して詠むと、不思議に響きがよい。しづ子は句を創作する時、きっと音読しつつ詠むことを心掛けていたと私は確信している。
〇鈴木しづ子 三十三歳 昭和二十七(一九五二)年六月二十七日附句稿百三十二句より(5) 一句
秋風裡片言を以て母を呼ぶ
限りない哀切が中七の字余りで利いている。
〇鈴木しづ子 三十三歳 昭和二十七(一九五二)年六月二十七日附句稿百三十二句より(6) 十二句
花桐や絶ちし交はりそのままに
花桐やこころかよはぬ叔母と姪
花桐や死すとも逢ふを欲らざるなり
花桐やこころ否める女人の貌
花桐や三十年をアララギ派
肉親に蔑まれつつ夏を棲む
花桐や作家としては慕はしき
花桐や作家にあらず人として
肉親のあらそひつづく梅雨の月
花桐や言はるることも一應は
封建制そのものにして桐に棲む
肉親らしからざる情桐の花
「花桐や三十年をアララギ派」は底本では「花桐や三十年をア■■ギ派」。句稿最後に配されたアララギ派の歌人であった岐阜在住の叔母山田朝子との訣別句群十数句から。「肉親らしからざる情桐の花」は掉尾。川村氏は「しづ子 娼婦と呼ばれた俳人を追って」に「その後の叔母と父」という項を設けておられ、その中で芭蕉の「我宿のさびしさ思へ桐一葉」を引用、『その葉は衰亡の兆しを表わしても』おり、『しづ子はこの<桐の花>の優雅な佇まいを、奇気位の高い当時の言葉でいえば、封建的と見立てている。彼女は古くから詠まれているこの<桐の花>を、古いモラル、そして自身の意思が通じない象徴として捉えている』と解釈されている。これらの句群を総攬した時、確かに川村氏の謂いは強い説得力を以て私に響いた。そして――しづ子の失踪の覚悟は――既にカウント・ダウンに入っていたものと思われるのである。
◯鈴木しづ子 三十三歳 『樹海』昭和二十七(一九五二)年七月号掲載句全五句
既に『樹海』前号から始まった巨湫による、膨大な既投句稿からのパッチ・ワーク的な恣意的選句がはっきりと見えてくる。句の後に投句稿のクレジットを示したが、その抄出は逆時系列、五句の中の季の連関性や流れも糞もない、むしろ、しづ子の持っている連作性や句間の有機的連合を解体し、わざわざランダムにしてあるとしか思われない。また、この五句が私には――勿論、私は私の選句眼が一般に通用するようなものだとも思ってはいないけれども――それにしてもこの掲載句は、どれも決して多量投句群の中で光っている佳品であるとは到底、感じられないのである。私は前号とこの号辺りに、後の、しづ子失踪後に始まる巨湫の確信犯的犯罪の源泉があるように思われてならない。
蠅打ちてけふのおのれの在りにけり (六月 六日附)
眉引くやことしの春は雨多く (五月 六日附)
轉業かうすき雲ゆく花の穹 (四月 十五日附)
事もちし花のコスモスいますがれ (三月 三十日附)
沙羅双樹富しことなし貧もまた (三月二十八日附)
〇鈴木しづ子 三十三歳 昭和二十七(一九五二)年七月二日附句稿百五十八句より(1) 一句
蹴りつつに家へ近づく實梅かな
アナタニハ ソンナ經驗ハ アリマセヌカ ナイトナラバ アナタハ幼年期ヲ 慘メタラシク拒絶シテ 愚劣ナル大人ニ強イテ成ラントスル淋シイ人デスネ サウシテ サウシテ此ノ句ハシヅ子ニ別ナ過去ヲ引キ出サセル情景トナルノデスヨ――次ヲ御覽アレ――
〇鈴木しづ子 三十三歳 昭和二十七(一九五二)年七月二日附句稿百五十八句より(2) 八句
とりいだせし扇風機にも過去嚴と
とりいだせし扇風機にて戀哀れ
扇風機の奢りにありぬひとりの居
扇風機にもつともちかく貌をさらす
扇風機に眞對ふ貌の細の眸
夫という言とひしめく靑梅と
實梅落つ素直に享くる人の愛
死す如く眠りおちゆく扇風機
先の「過ぎ失せし愛の記念や冷藏庫」ほどではないが、しづ子の恋句には電気製品という極めて現代的な対象によって追懐されるという際立った特徴がある。それもこの昭和二十年代には、冷蔵庫や扇風機を普通に持っていた上流階級に属する俳人誰彼であっても、こうした自慢げに見える句は流石に嫌味になるから遠慮して決して作るまい。これらの句は、言わば、そうした階級意識を持った「遠慮」――その実、厳然としてある貧富の差の目線――更にしづ子のようなダンサーを蔑む彼らの視線――「しづ子」伝説に涎を垂らす鵜の目鷹の目猥褻卑猥な自称俳人の男たち――といった有象無象の優位感を持ったしづ子の周囲の輩に対する、しづ子独特の、一つの冷めた報復であるように感じられる。扇風機の真正面に目を細めて髪を靡かせて無言でいるしづ子は――「ワレワレハ宇宙人ダ」ではない――「お前たちこそ人の心を踏みにじって屁とも思わない宇宙人ではないか」と私に語りかけてくる――
〇鈴木しづ子 三十三歳 昭和二十七(一九五二)年七月二日附句稿百五十八句より(3) 六句
夫ならぬ夫と哀しむ林檎剝く
林檎酸くむかしおのれの還るなし
林檎酸く假定の中にをくおのれ
狂ほしく一黑人の愛の手の
林檎剝くや人を愛せしことも過去
林檎剝けばむかしのおのれ稚な妻
〇鈴木しづ子 三十三歳 昭和二十七(一九五二)年七月二日附句稿百五十八句より(4) 蟻三句
蟻の眼に水のかがよひ美しき
子の指がねらひし蟻のすべてを殺す
夜の蟻迷ふかぎりを迷はしむ
『指環』の掉尾から三つ目「蟻の體にジユツと當てたる煙草の火」で知られるが、しづ子には蟻の句が断然多い。そんな中でこの蟻の眼に」のような俯瞰ショットでなく、水に落ちた蟻の目線で詠んだものは珍しい。「この指が」の句、ずっと昔読んだ漫画に、少年が巣に戻る蟻を親指で悉く潰し続け、母に呼ばれて、家へ帰るのだが、最終コマは笑顔で走ってゆく少年の前方からのアオリのショットで、その背後の天空から巨大な手が親指を向けて降りてくる――というのがあった。この句は、少なくとも蟻からのアオリの映像が見える――「頑是無い」子供の無邪気な殺意の「愛くるしい」」表情が――見える。「夜の蟻」はそのシチュエーションと語彙の選択、厳然たる写生性がオリジナルで面白い。――えっ? 大丈夫、御安心なさい――この前の句でしづ子は「土に還さしむ」と詠んでいますから――
〇鈴木しづ子 三十三歳 昭和二十七(一九五二)年七月二日附句稿百五十八句より(5) 一句
戀遠しひらけば日仐みづいろに
「仐」は「傘」のこと。
どこぞのちゃらちゃらした現代の女流俳人に似ても似つかぬ超軽量の類似句を見たことがある――
〇鈴木しづ子 三十三歳 昭和二十七(一九五二)年七月五日附句稿二百七十四句より(1) 二句?
野に戾ればふと
體のうちのうづくなり
二句目は底本では「うづくるり」。一瞬、すわ、しづ子の自由律かと眼を見張ったのだが、これはどうも、
野に戾ればふと體のうちのうづくなり
上五の大幅な字余りという連続したもののように思われる。ちょっと残念。
〇鈴木しづ子 三十三歳 昭和二十七(一九五二)年七月五日附句稿二百七十四句より(2) 一句
牡丹得て人のごとくに吻づける
ある日――独居の家に高価な牡丹の花を買(こ)うて戻る――活けた牡丹に対坐して冷えた夕餉を摂るしづ子の牡丹(一部の句には芍薬ともある)句群三十四句より。
〇鈴木しづ子 三十三歳 昭和二十七(一九五二)年七月五日附句稿二百七十四句より(3) 一句
雷雨の夜壺の白花に詩感なし
と詠みつつ、雷鳴と雷雨を詠んだ連作句群三十数句から。しづ子の句作はそれ自体が一つの生死の連続体への公案の答えであると私はしみじみ思うのである。
〇鈴木しづ子 三十三歳 昭和二十七(一九五二)年七月五日附句稿二百七十四句より(4) 一句
擦るマツチ戰いの前と後を生
この句から始まる「擦るマツチ」「マツチ擦る」「擦りしマツチ」句群が十一句続く。下五は「いく」と読ませるか。この句は、この連作中に「いくさ前の生活おもふや擦るマツチ」という句があることから、第二次世界大戦の前後のしづ子自身の生き様を一瞬の儚いマッチの炎の点灯と消滅の中に見てとっているのだということが分かる。
〇鈴木しづ子 三十三歳 昭和二十七(一九五二)年七月五日附句稿二百七十四句より(5) 七句
出生を忌むばかりにてちろろ蟲
これを最後とおもふ朝顏あきかぜに
露萬朶吾に死ぬ日の■然と
露萬や美濃に訣るる墓の前
美濃■る日の近づきや露育つ
離るべきおもひの強み露育つ
白露や逢ふが別れと誰が言ひし
判読不能字を含みながら、全体に不吉な句群である。既に岐阜を去り、失踪を決意したしづ子の社会的な死の末期の眼でもあろうか――
〇鈴木しづ子 三十三歳 昭和二十七(一九五二)年七月五日附句稿二百七十四句より(6) 二句
北海の流る五月の髮なりき
封建性そのものの貌蝦暑し
ここに再び「鈴木しづ子 三十三歳 昭和二十七(一九五二)年六月十五日附句稿五百四十六句より(4) 北海道追懐句群十七句」で示した北海道追懐句が数句現れる。詳しくは先行する当該部の私の注を参照されたい。「封建性そのものの貌蝦暑し」(「蝦」はこれで「えぞ」と読ませるか、若しくは単純な脱字であろう)は父俊雄の「顏」と読む。
〇鈴木しづ子 三十三歳 昭和二十七(一九五二)年七月五日附句稿二百七十四句より(7) 一句
戀の蝶たがひ觸れつつとほのきぬ
〇鈴木しづ子 三十三歳 昭和二十七(一九五二)年七月五日附句稿二百七十四句より(8) 一句
梅雨めく雲爲さば爲べきこといくつ
〇鈴木しづ子 三十三歳 昭和二十七(一九五二)年七月五日附句稿二百七十四句より(9) 三句
死を誘ひ死をはばみては秋櫻
わが生をとどむるものやコスモスなど
コスモスなど搖れやすければ死ただよふ
かつてしづ子が拘ってきた「コスモスなどやさしく吹けど死ねないよ」という「公案」への――今の一つの――しづ子の答えであった――
〇鈴木しづ子 三十三歳 昭和二十七(一九五二)年七月五日附句稿二百七十四句より(10) 四句
驛へ驛へ學生つづく猛り鵙
おほかたの思想かたむく落花かな
統ぶるすべざる思想捲散る
學生やこころ一途に夏の雲
「おほかたの」の下五は底本「落花かふ」。訂した。学生運動の初期の映像である。しづ子も戦前の若き日にそうした集会に出たらしき「春燈下をんな學生混へつつ」という句を見た。しづ子は眼前のこの学生たちを、やや距離を置いて見ているようには見えるが、最後に掲げた句などには、やはりそこには一種の心情上の共感が感じられる。しづ子は決してクールな傍観者ではない。ただそこには常に現実から彼女が学び取ったところの、絶対善や自由の謳歌への疑義、相対的な現実世界の持つ胡散臭さを嗅ぎ取っているようにも私には感じられるのである。
〇鈴木しづ子 三十三歳 昭和二十七(一九五二)年七月五日附句稿二百七十四句より(11) 一句
贈り人失せて日仐は靑し戀もまた
掉尾日傘十句から。ケリーからのプレゼントであったのだろう。
――仕舞われていたお気に入りの水色の日傘を今年もまた包みから出してさしてみる――
――一年前は彼はまだ、生きていた――
――けれど今年はもう――
――あの人は永遠に冥界の霧の彼方へ消えていってしまった――
――燦々と降り注ぐ陽光――
――もう私しか帰ってこない住まいへ――
――くるっ――くるっ――
――と傘を回してみる――
――くるっ――くるっ――
――みずいろの日傘としづ子――
――しづ子独り――
〇鈴木しづ子 三十三歳 昭和二十七(一九五二)年七月六日附句稿五十六句より 十二句
許せかし醉ふてみだれし月の前
涼風や鼻尾をはさむ足の指
涼しさのえりあしみせし髮の形り
蚊遣香の渦のからみを色にたどり
素足の膚鼻尾濕りの色にじむ
夏降りの臙脂濕りの鼻尾の面
あまおとの殼つたひけり蝸牛
晩そ夏の膚をさらすや湯の濕り
錯亂の頭の一角や紅蝙蝠
蚊遣香の渦たどりゆく錯覺す
炎天の輓馬に蹤きてゆくほかなし
炎天の輓馬と吾と徑岐る
今……二〇一一年十二月三十一日午後九時半過ぎ……しづさん……残すところ、千百数句……今年最後の、私のあなたの句の選句です……ありがとう、しづさん……
〇鈴木しづ子 三十三歳 昭和二十七(一九五二)年七月二十四日附句稿百五十八句より(1) 迎え火二句
迎え火のほむらをかばふ掌の圍ひ
迎え火の燃えて盡きしにかがまれる
「迎え火」の「え」はママ。私は昨夏、初めて母の迎え火をした。このしづ子の姿は私自身である。
〇鈴木しづ子 三十三歳 昭和二十七(一九五二)年七月二十四日附句稿百五十八句より(2) 螢三句
その一つ吾に近づく螢の火
螢火のあまたの中に佇ちつくす
螢火の失せしを探す母戀ふ如
〇鈴木しづ子 三十三歳 昭和二十七(一九五二)年七月二十四日附句稿百五十八句より(3) 二句
炎天下鐵條網の端し崩れ
炎天下首輪くひこむ犬の首
これはもう遙かに森山大道に先んじている。
〇鈴木しづ子 三十三歳 昭和二十七(一九五二)年七月二十四日附句稿百五十八句より(4) 動物詠九句
金魚の屍迅き流れの川に葬る
近よれば幼き貌の冷やし馬
絶望にも徹し切れざる飛燕かな
蛇にして全身をもて遁れゆけり
跼み癖つねに地上の蟻殺す
蝙蝠を見し夜不吉に爪を切る
我が苦惱馬臭はげしき炎天下
炎晝の鳩降り下る石疊
蟬鳴く中見せ物小舍の紙はためき
「跼み癖」は「かがみぐせ」と読む。これらはしづ子の好むクロース・アップ手法がどれも効果的に利いた佳品である。特に私は「蛇にして全身をもて遁れゆけり」の厳しい描写力と無駄のない語彙選びに打たれる。
〇鈴木しづ子 三十三歳 昭和二十七(一九五二)年七月二十四日附句稿百五十八句より(5) 一句
鐵臭や故郷はとほき春の雷
〇鈴木しづ子 三十三歳 昭和二十七(一九五二)年七月二十四日附句稿百五十八句より(6) 一句
祕して言はずわがクローバーの四つの葉
花言葉では通常の三つ葉のクローバーの一枚の葉には「希望」「信仰」「愛情」の意味があるとされ、特に四つ葉のクローバーには人口に膾炙するように「幸福」の意が込められる。川村氏は「しづ子 娼婦と呼ばれた俳人を追って」の三五三~三五四頁で、この句を特に取り上げてしづ子の謎に迫っておられる。詳細は当該書をお読み戴きたいが、元『樹海』同人であった矢澤尾上(おのえ)氏は、その評論「俳人・鈴木しづ子――その知られざる生涯と作品」(『俳句研究』昭和六十二(一九八七)年八月号)で、自身が『指環』特装本限定三十部の第一冊を所蔵していること、それがもと巨湫の所蔵本であったこと、氏に巨湫から形見として渡されたこと、そして、その見返しには『この一冊はしづ子さんの所有だったのです。「まがふなし」もしづ子さんのもとめにより私がかきました』という添え書きがなされていることなどを述べられている(「まがふなし」は『樹海』昭和二十五(一九五〇)年十一月号に載った、しづ子の「明星に思ひ返へせどまごふなし」を指す)。ところが、その巨湫遺愛の『指環』には、『デパートの包紙で丁寧に上覆いされている』『四ツ葉のクローバーがはさ』み込まれてある、とある。川村氏はこの事実と本句から、しづ子自殺説への否定的見解を展開されている。氏は『この<クローバー>の句には、大きな謎が隠されている。直訳すれば、しづ子は巨湫に、この<四つの葉>に託した意味を、<秘して言はず>に別れていることになる』と語られる。そしてクローバーの花言葉を示し、普通に考えるならば、しづ子は『これらの花言葉総ての願いを巨湫に託した』、それは言わずもがなのはずの『師巨湫への愛』だとするならば、しかし『であれば彼女は何も巨湫に対して秘密にすることはない』はずである。だのに敢えてここで「祕して言はず」と詠んだのは何故か? 川村氏は言う。ここには言わずもがなではない、『そうではない二人だけの暗黙の何かが』潜ませてあり、それは正に『しづ子自身に向けての思いではなかったのか。その意味を知っているからこそ、巨湫はこの四つ葉を大切に保管していたのではなかろうか』。そこから更に氏は花言葉の「信仰」に着目、しづ子の失踪の彼方に、尼僧となったしづ子の姿を措定されておられる。その当否は当該書をお読みになったあなたが判断されたいが、私もしづ子は自殺していないという立場に立つ点に於いて、川村氏に同感であり、この句の孕んだ「希望」の秘密が、一本の葦として私自身にも強く意識されるのである。
――「希望」「信仰」「愛情」そして「幸福」――
――昨年の秋、私はアリスを散歩させながら、必死になって四つ葉のクローバーを探した――そうして見つけたそれを病床の母に贈った――母は最期の日まで――病床に押し花にしたそれを飾っていた……
〇鈴木しづ子 三十三歳 昭和二十七(一九五二)年七月二十七日附句稿百三十七句より(1) 一句
冷夏にて空襲の夢を見る
これはしづ子の中でも新傾向若しくは自由律の、しづ子にして珍しいその短律と断じてよく、そのような句としても総ての語彙とその衝突が慄然として成功している。私なら本句をしづ子の自由律代表句として残したい。
〇鈴木しづ子 三十三歳 昭和二十七(一九五二)年七月二十七日附句稿百三十七句より(2) 五句
石光りて炎熱の地に一物なし
見事なる蟬の一つを兄に欲る
誇らかに蟬を示せる弟の前
炎日の宙に指もて渦を描き
炎晝の町にて方角失へり
どれもハレーション気味の映像が素晴らしい。最後の句は句稿掉尾。
〇鈴木しづ子 三十三歳 昭和二十七(一九五二)年七月三十一日附句稿十句より 一句
螢狩のありし地上に螢死す
〇鈴木しづ子 三十三歳 昭和二十七(一九五二)年八月十八日附句稿十四句より 一句
ひと在らぬ半ば開きの氷庫の扉
ケリーとの愛の巣の思い出の品――タルコフスキイの「鏡」の1ショットである――
さて、ここに現在、川村氏の所持する大量投句稿に紛れ込んでいた一通の巨湫宛のしづ子書簡がある。川村氏は「しづ子 娼婦と呼ばれた俳人を追って」の中でそれが写真入りで紹介されているが、そこには以下のように記されている(写真画像から改行も再現してテクスト化した)。
曆の上ではもう立秋になりましたが、
毎日あつい日がつづいてをります。
ご氣元[やぶちゃん注:ママ。]如何でいらつしやいますか。
本年中に家をかはることになりさう
ですが、只今のところ、よその[やぶちゃん字注:「他」と書いて末梢。]県に行
くのか、またこの那加町内でかはるのか、
未だはつきりいたしません。かはり
ましたら何れにいたしましても
ご通知申上げます故、それ迠は
お手殘[やぶちゃん注:ママ。]下さいませぬよう。
御身体お大切に。
八月九日 しづ子
巨湫先生
川村氏は封筒の消印が判読不能であるが、差出先から、この投句稿の九日前の昭和二十七年八月九日と推測されている。「お手殘」は「お手紙」の誤記と考えられるから、ここでしづ子は巨湫からの来信さえも遂に遮断したことが判明する。しづ子の失踪の毅然たる準備は着々と確実に進められていたことが分かるのである。
〇鈴木しづ子 三十三歳 昭和二十七(一九五二)年八月二十四日附句稿五十五句より(1) 二句
劇藥の劇と銘うちまがふなし
密封する藥を持ちいつでも死ねる
劇薬を抽斗の奥に仕舞い込んだしづ子――それを透視するしづ子――その連作五句から。
最初の句は当然の如く、巨湫との謎の感応(秘められた官能というべきかも知れない)句
明星に思ひ返せどまがふなし
と響き合うように作られている。思い出さずにはおかせない、といった風に……こんなものを句稿として送られた巨湫はたまったものではないな……
――そうか? たまったものではないのは当然だ!
――たまったものではなかろうということをしづ子は十全に知っていて――
――しづ子は確信犯でこれを投句しているのだ――
――これを送られるべき――これを是が非でも当然読まねばならない義務が巨湫の側にあったからこそ――
――しづ子は――
――後妻との凡庸な生活人をぬくぬくと生きる巨湫にとって道義的に許されざる――
――選句されるべくもない赤裸々な自死志向句を詠み、送りつけたのではなかったか?……
――いや――それも恩讐の彼方であった――
――しづ子の句は今や――公案への答えである――
――幻の人生そのものを捨象するための――
――たかが/されど俳句――なのであった――
〇鈴木しづ子 三十三歳 昭和二十七(一九五二)年八月二十四日附句稿五十五句より(2) 九(十)句
犬の屍のがつと血を吐く炎暑の地
狙った感じだが下五の響きとイメージが私には今一つ弱い気がする。
*
カルメンは煙草女工わたしは紡績女工ニツキ嚙む
新涼の紡績會社の門くぐる
しづ子が紡績女工であったという事実はない。この句はそうした事実を云々する材料というより、自身を「ノラ」を越えて、カルメンに比している部分にこそしづ子の真骨頂を詠むべきである。前句はもう自由律の長律に近い。
*
天とほくキヤレン颱風をそれにけり
美しく颱風をいふ女人の名
国土交通省関東地方整備局江戸川河川事務所のHPの「川について知る」の中に「台風の名前は外国人女性!?」という頁があり、そこに、現在は一般に発生順で番号を振って呼称する(近年は実際にはすべてに名前が付けられているが、通常のメディアでは全く使用されていない)のにかつてはどうして英語名で台風が呼ばれたのかという点について述べており、それは昭和二十二(一九四七)年から昭和二十七(一九五二)年までの六年間、日本がアメリカの占領下にあったため、アメリカ本土のハリケーンに倣って、日本の台風に女性の英語名を付けることが『強要されていた』とあり、この間に発生したカスリーン(一九四七)・アイオン(一九四八)・キティ(一九四九)・ジェーン(一九五〇)・ルース(一九五一)などの『台風名は番号ではなく、英語名が正式名』なのだとある。私は『強要されていた』というのには、正直、吃驚している。これは公機関の記事である。
*
標札てふものもちこことなしちらつく雪
祭幟はためくこころうつろなる刻に
祭幟抗ふ如くはためけり白露や若ければこそ死を希ふ
前の二句は明らかな破調を狙った新傾向である。三句目はママ。「祭幟」は「まつりばた」と読んでいるか。三句目はその極限の思い切った長吟かと期待したのだけれど、よくみるとこれは「祭幟抗ふ如くはためけり」「白露や若ければこそ死を希ふ」で完全定型である。ちょっと残念。
*
白露や人を追ひ死すこともよく
「人」はケリーであろうが……しづさん……そう、「あの人」を苛めてはいけませんよ……
〇鈴木しづ子 三十三歳 昭和二十七(一九五二)年八月二十九日附句稿百八句より(1) 自死暗示二十句
夏を過しつ死といふことがめあてにて
いつでも死ねるグラヂオラスは咲きのぼり
死ぬるべきの藥ぞ箱裏む
劇藥の劇と銘うち暑氣極む
こん致死量の吾にあやまたさることを
步一步死へ近づき暑氣極む
秋たちぬ情死希いしことはむかし
雪はげし共に死すべく誓ひしことし
人死して降りしきるなり牡丹雪
雪霏々と愛は濃くなるばかりなり
雪霏々と吾らが一人死なせけり
吾らが愛雪くれないの染まむほど
雪こんこんおのが致死量まがふなし
月涼したんたんとして死を待てば
死にどこおろここゑがくや月に雲
ひつそりと死なむコスモス地を匍ひ
おのが死してのちの世を想ふ
死に神誘ふにあらず月澄みて
秋燈下粉末白く毒含む
夏らんらんいつでも死ねる藥を持ち
表記の不審なものもあるがすべてママである。
……しづさん……もういいでしょう……この頃から、巨湫はすっかりあなたが自死するかも知れないと思っていますよ……実際に彼は『樹海』同人の主だった者に、あなたの自殺の可能性を仄めかしてもいますから……しかし、ね……私は……しづさん……あなたは自殺なんかしていないね……それは私の願望なんぞを遙かに超えたものとして……不思議な確信に近い実感として……今もある、のですよ……
〇鈴木しづ子 三十三歳 昭和二十七(一九五二)年八月二十九日附句稿百八句より(2) 一句
ふつふつと湧きてやまざる素顏の行
私が何度も言ってきたことだ――しづ子にとって――この投句は、平然としたしづ子の生(なま)の「素顏の」正しく「行」(ぎょう)なのだ――
〇鈴木しづ子 三十三歳 昭和二十七(一九五二)年八月三十日附句稿百一句より 三句
競泳に負けて歸れる徑の草
競泳に負けて歸りて少年無口なり
たくましくして水泳の黑パンツ
知れる少年の競泳の敗北連作九句から。いいシチュエーションなのに今一つ。私は読みながら、西東三鬼の昭和十一年の名作「算術の少年しのび泣けり夏
」を超えるあなたの一句を望んでいたのに。でも――きっとそれは――あなたが女――母性を持った女――だからなのかも知れないね――ふと見ると、次の句稿(八月三十一日附)の冒頭にも「水泳にひたすら託す少年の夢」「皆泳ぎを得意とするや飯を喰む」と詠んでおられる――よく読むと、あなたの句には少年の内外を総て包む愛が、確かにあるものね――三鬼のそれは、泣く少年を固定カメラでじっくりと撮ろうという、カメラマンの、監督の、実は「芸術」を伝家の宝刀とする理不尽なもの――なのかも知れないね――
〇鈴木しづ子 三十三歳 昭和二十七(一九五二)年八月三十日附句稿五十五句より(1) 一句
餉のあとのととのひなるや法師蟬
これはしづ子の未発表の「たかが」一句であるが、私にはしかし並々ならぬ力量を感じさせる一句である。
〇鈴木しづ子 三十三歳 昭和二十七(一九五二)年八月三十日附句稿五十五句より(2) 空飛ぶ円盤二句/天文少年二句
夏の夜や少年が見し「空飛ぶ円盤」
空飛ぶ円盤見てこと告げむと駈けて來たり
夏の夜の天文學の本をかかへ
夏の夜の少年が言ふ天文學
空飛ぶ円盤を詠み込んだ俳句の嚆矢として掲げたい。尚且つ、この句はそれを奇を衒う語彙として使用しているのでもない点で、おそらく稀有の美しい――星空の下(もと)の少年としづ子の――「空飛ぶ円盤」俳句である。
UFO史の中では、この前年一九五一年八月にアメリカで起きたラボック・ライト事件が知られる。テキサス州ラボックで全翼機(V字)型の未確認飛行物体やV字型に複数のライトが点灯した物体が目撃され、青年がそのブーメラン状の光源を写真に収めた。同様の物体は同時期ニューメキシコ州アルバカーキなどでも目撃され、二十六日早朝にはその目撃の後にワシントン州防空レーダーがUFOを捕捉、F-86セイバーがスクランブル発進している。当時は正に「空飛ぶ円盤」・宇宙人の到来・地球への来訪や侵略といった都市伝説が大ブレイクする直前であった。例えばウエストバージニア州ブラクストン郡フラットウッズで赤い発光体が目撃され、少年七人が森の中でおぞましいモンスターに襲われる本格的な最初の第三種接近遭遇事件として知られるフラットウッズ事件は、実にこの投句の直後の九月十二日のことなのである。因みにウェルズの「宇宙戦争」のジョージ・パルによる映画の公開はこの翌年、一九五三年である。――何、リキんでるんだ? って? そりゃ、こんな句を見れば、エキサイトしますさ、だって私は十代の頃、UFOの研究をしていたんですから。大真面目にね――三島由紀夫も「空飛ぶ円盤」、大好きだったんですぜ――
〇鈴木しづ子 三十三歳 昭和二十七(一九五二)年八月三十日附句稿五十五句より(2) 一句
いつか地球は滅ぶと言へり渦卷くぜんまい
シュールな、いい句じゃないか!――いいや、これは遙か以前に書かれたウルトラセブンの「第四惑星の悪夢」(脚本:川崎高(実相寺昭雄のペンネーム)・上原正三/監督:実相寺昭雄/特殊技術:高野宏一)じゃないか!――何、リキんでるんだ? って? そりゃ、こんな句を見れば、エキサイトしますさ、だって私は未だに特撮オタクなんですから。これから大真面目に特撮評論を書こうと思っているね――あんたが笑うならウルトラセブンに感激して宇宙飛行士になった誰彼もあんたにとっては私と同類の大馬鹿者ってことだわな――
〇鈴木しづ子 三十三歳 昭和二十七(一九五二)年八月三十日附句稿五十五句より(3) 古橋広之進三句
端居して盡くることなき古橋論
古橋敗れたり町に散らばる店舗の燈
古橋敗れたり團扇の風をつと強め
これこそが、あの汗ばんだ夏の、饐えたゴミ箱の漂ってくる、正真正銘の「ALWAYS 三丁目の夕日」の映像ではないか!
昭和二十四(一九四九)年八月に招待された、ロサンゼルスでの全米選手権で世界新記録を樹立し、現地で「フジヤマのトビウオ」“The Flying
Fish of Fujiyama”と呼ばれて戦後日本人の大きな希望の燈となった古橋広之進は、この昭和二十七(一九五二)年七月十九日から八月三日までフィンランドのヘルシンキで開催されたヘルシンキ・オリンピックに出場したが、既に選手としてのピークを過ぎていたことや体調の不良が祟って、四百メートル自由形八位に終わった。参照したウィキの「古橋広之進」によれば、『この時、実況を担当したNHKの飯田次男アナウンサーが涙声で「日本の皆さん、どうか古橋を責めないでやって下さい。古橋の活躍なくして戦後の日本の発展は有り得なかったのであります。古橋に有難うを言ってあげて下さい」と述べたことがあった。帰国中の船内では自殺まで考えていたという』とある。――「盡くることなき古橋論」を展開する人――「古橋敗れたり」の現実をラジオで体感した人々の落胆が点綴される――「町に散らばる店舗の燈」に――敗れた瞬間、その時、日本中の人々が、「つと強め」て団扇をバタつかせた――私はこの時、まだ生を享けていないが――私には確かにその情景と匂いと思いが確かに伝わってくるのである――この句によって――
〇鈴木しづ子 三十三歳 昭和二十七(一九五二)年九月一日附句稿五十四句より 四句
トランクを提げてつまづく枯野中
脚本を書いてみようか枯野すすむ
現の世も夕燒小燒のうたきこゆ
文學の末部の俳句マツチ擦る
既にしてしづ子の失踪は
〇鈴木しづ子 三十三歳 昭和二十七(一九五二)年九月二日附句稿百十句より(1) 二句
稻葉川ほとりの草の旱の陽
わが村の稻葉川てふ涼しき名
これは明らかに固有名詞である。「稻葉川」とはどこか。ネット上で検索する中で、めぼしいところは以下の三つ。
・大分県竹田市稲葉川(大野川に合流)
・兵庫県日豊岡市高町稲葉川(円山川に合流)
・新潟県長岡市稲葉川(信濃川水系)
但し、兵庫県の稲葉川は「いなんばがわ」と読むようである。新潟……
……新潟……川村蘭太氏「しづ子 娼婦と呼ばれた俳人を追って」の最終章「エピローグ 巨湫の遺した謎を追って」で、氏は巨湫がしづ子が突如、昭和三十八(一九六三)年に改題された『きのうみ・樹海』にしづ子の句を投句されたかのように掲載し出した、その雑誌に示されたしづ子の投句先住所『狭河』(県名も市名も示されていないという)を手掛かりに、しづ子の所在を追っておられるのであるが――詳細は当該書をお読み戴きたい――川村氏がそのラスト・シーンで立ったのは……新潟の……とある河畔であった……
〇鈴木しづ子 三十三歳 昭和二十七(一九五二)年九月二日附句稿百十句より(2) 十九句
薊吹き死期が近づく筆の冴え
秋の草の吹かるるこの世惜しむなし
死して吾に殘すものなし鳳仙花
わがからだ失せしののちの鳳仙花
秋めきの雲を詠みしを最后とす
秋の雲ゆくおも子はあ鈴木しづ子之墓
秋の雲いづれは失せるべきからだ
星美しき夜の一遍の愛の詩
夏休み了らむとして得し病
この秋と生命限りし棕梠葉かな
死ぬまいぞ鏡の貌の汗の玉
雪被く明治大正昭和の墓碑
わが墓碑は誰がてに成らむ雪めく空
秋ぞきたる吾が上にこそ自由はあり
梅雨土砂降り日本人たることを忌みにけり
雪めく空生きるることは華やかに
意のままに二十七年夏氷
意のままにわが過去帳に白紙なし
風凪て星天の下河流る
……しづさん……もう、いいんだよ……言わなくたって……六十年後の今も「しづ子」は圧倒的な伝説の中に孤独な女王として君臨している……どんな「女」も……しづさん……あなたには勝てないのさ……永遠に「二十七」で……永遠に「娼婦と呼ばれて」……そうして永遠に私のようにあなたを恋い焦がれる男が……居続けるのだから……しづさん……
◯鈴木しづ子 三十三歳 昭和二十七(一九五二)年九月三日『読売新聞』夕刊文化欄「新人抄」掲載句『雲間の陽』全五句
炎天下首輪くひこむ犬の首 (七月二十四日附投句稿より)
靑蔦のきらめきを壁となし (六月 十六日附投句稿より)
橋わたる七夕さまの夜の電車 (七月二十四日附投句稿より)
腋毛濃しさんさんと湧く雲間の陽 (六月 十五日附投句稿より)
綠蔭に揃ひの椅子を薦めらる (日附不明投句稿より)
これはしづ子の投句によるものではない。川村氏によれば、掲載記事のしづ子肩書は『樹海・同人』となっており、『新聞社との句稿の受け渡しも、すべて松村巨湫経由で行われた』(「しづ子 娼婦と呼ばれた俳人を追って」三八五頁)とある。さすればこの選句も巨湫によるものであると考えてよい。但し、この選句自体は、私にはどれもかなり共感出来るものである。
――それにしてもこの掲載は如何なる経緯によるものか。しづ子が望んだとは私には考えられない。とすれば巨湫しか考えられない。全くたまたま『話題の伝説の俳人しづ子』を興味本位でターゲットとした文化欄編集者が巨湫に話を持ち込んだに過ぎないのか、それを巨湫がしづ子を『引き留めるための最後の手段』となるとでも思ったものか。しかし――しづ子はこの十二日後の投句稿を最後に失踪してしまうのである――私は逆に、この『読売新聞』夕刊文化欄「新人抄」掲載という事実は、しづ子自身にとっては俳句を見限る大きな一つの「事件」ではなかったか、これが失踪にしづ子を駆り立てた、最後のスプリング・ボードではなかったか――と私は疑うのである。
◯鈴木しづ子 三十三歳 『樹海』昭和二十七(一九五二)年八・九月号掲載句全七句
これがしづ子の真の投句の掲載最終号の『樹海』である。しかし実際には巨湫の選句は直近の投句稿からは選んでいないから、これを『しづ子の真の投句の掲載最終号』とすること自体には余り意味はないと思うが、取り敢えず現象的事実として押さえておこう。句の後の括弧書きがあるものは例によって私が調べた投句稿所載のものである。後の五句は現存する投句稿には見出せなかったが、「雪降りをり県庁はいま正午にて」は昭和二十六(一九五一)年十二月十九日の投句稿に「寒月をのぼらしめたり惰性の生」という感懐類型句が見える。
揃えて脱げばスリツパ赤し降誕祭 (一月二日附投句稿より)
こころの疵からだの疵さむざむと在る玻璃の疵 (一月十一日附投句稿より)
綠蔭の樹に凭しやすし凭れば歌ふ
夏の雲ゆく戰爭花嫁といふことば
紫雲英田に立てば山脈高からず
寒月照る着々と死を近づきしめ
雪降りをり県庁はいま正午にて
〇鈴木しづ子 三十三歳 昭和二十七(一九五二)年九月五日附句稿五十四句より 一句
莫迦のような暮しつづくや土の苔
〇鈴木しづ子 三十三歳 昭和二十七(一九五二)年九月五日附句稿五十四句より 一句
秋風の有刺鐵線比内の地
また出て来た。「比内」は固有名詞であろう。であれば秋田県大館市比内町しかない。――そしてやはり、新潟に近い。「有刺鉄線」が分からない。当時の比内に米軍基地があったことは確認出来ないでいる。
〇鈴木しづ子 三十三歳 昭和二十七(一九五二)年九月九日附句稿三十句より 四句
死ぬことをときに懼るや薄荷草
腕時計ばかりは賣らじ赤まんま
自殺者の手記のなかなる星のこと
蟲しじに書きゆく便り遺書めく
〇鈴木しづ子 三十三歳 昭和二十七(一九五二)年九月九日附最終投句稿四十句全句
遂にやってきてしまった。――現存し、期日の明白な、しづ子の最後の投句稿である。――ここは総てを底本の表記そのままに掲載する。――この投句稿を最後として、鈴木しづ子は永遠に我々の前から姿を消した。――鈴木しづ子――現在まで、行方不明――今、二〇一二年一月七日現在、生きておられれば、九十二歳になられるはずである……
簷に葉に二百十のしづかな雨
降るになく吹くにあらざる危日の葉
[やぶちゃん注:「危日」とは
吹きとほす危日ちかづく竹■葉
炊ぐ飯二百十日も過ぎにけり
一匹の蟲鳴きつづく晝の雨
魚燒きて一日ごもりの秋の雨
ひらくとき秋の日傘となりにけり
擦れちがふとき片蔭をゆづられし
秋の陽に双つ腕を燒かしめて
秋の雨夕べのごとくこづかなる
堤防を崩せしほどの梅雨出水
暁より梅雨の濁流橋くぐる
泳ぐよに蜻蛉いできし雨のあと
吾にいたりて■木の家係崩れたり
颱風のありし地上に蚯蚓死す
綠の下にまで秋風があふれゐて
秋風裡手にもてあそぶマッチの箱
つゆ草を踏まじとおもふ草の中
やうやくに暑さうすらぐのぼり蔦
青蔦の葉のいつぱいの西日かな
をりをりはおもはせぶりな雲間の陽
數を教ふどんぐりをもて一つとし
捉へきし蟬を与へて泣くをなだむ
わが坐せば簾むかふの秋の風
秋めく風姉は虚榮に走りけり
[やぶちゃん注:この「姉」とはしづ子を指し、措定される妹は堅実な生を全うした実妹正子(しづ子は彼女の年齢を詐称したと考えられている)のことを念頭に置くものであろう。]
姉妹あり秋の落日けんらんと
小説中つねに嬌るは姉娘
小説においても嬌るは姉娘
死にぎわの蟻が必死に軀を廻す
風ゆれの葉に一匹の蟻を■し
秋燈下にて消しゴムをさがしをり
秋風裡萬年筆にイレワ缺く
[やぶちゃん注:これは万年筆のインク補充のための着脱部分に入っていた、恐らく金属の輪っかがなくなっていることを詠んでいるように私には感じられる。]
とほければ團扇を取りてもらふ
るの裸身金魚のごとしたゆまざる
[やぶちゃん注:「るの裸身」は不審。「この裸身」「かの裸身」「その裸身」「ゐの裸身」又は「ゑの裸身」か。句としては「この」でありたい。]
差出されし朱け色きるき団扇の板
[やぶちゃん注:「きるき」は誤読であろう。「しるき」か。]
みづ色の団扇をつかふ人とゐる
眠るともなく団扇をつかふともなく
ひと夏の裏みこまひたり
[やぶちゃん注:「裏みこまひたり」は不審。「裹みしまひたり」ではなかろうか?]
夏逝くや朱色きつき団扇の板
豪雨とはいへざるまでも標格の雨
[やぶちゃん注:掉尾の句。「標格」不詳。地名ではなさそうである。失礼ながら誤読か。原本が見たい。]
*
……しづさん……あなたは最後の最後まで……謎を残して去ってゆくのですね……でも、私は……川村氏のようには、「もういいよ」というあなたの声が聴こえません……私はあなたを探し続けます……
〇鈴木しづ子 大量投句稿の日附不明百六十四句より 三十八句
貨車過ぎの搖れの名殘りや秋櫻
夏枯れの橋をつくらふ稻葉川
夕燒けや土面水をく一ところ
穗草ふく匂ひを人とおもいけり
人とあるおもひに坐すや穗草吹く
■の齒に古知野の風にわたりけり
[やぶちゃん注:古知野町は、愛知県丹羽郡の旧町名。現在の江南市中心部。]
傳説はいふ滿月の夜のいけにへを
犬を抱く混血のりや虹の下
夏がきて混血のるに父のなし
爐火のまへての白肌ぞ孤りなる
祕めてあればこころ喪に似て爐火燃ゆる
叔母の戀情噺笑ふにもあらず氷柱照る
戀ごころ少年にありや冬すみれ
凍蝶の翅ひといろの白さかな
わが不幸記憶の蝶の失せしより
わが不幸離京の蝶のことさら黃
思慮なくも海へ去りけり冬の蝶
人死なせしかの雪溪も雪崩をらむ
死の谷といはるるところ夏薊
瀧形りに雪墜りつぐや對ふ崖
寒夜飮む藥に致死量思ひけり
百姓の暴君の似て甘藷を掘る
戀過ぎの猫うづくまる祠そと
少女の指花の椿を祕そかに祈る
花吹雪過去と畫する一線あり
滿月の夜のいとなみの女體の手
女體にて滿月の夜の火を捧ぐ
ローレライの乙女とおもふ萬綠に
夜を泳ぐ人魚とおもふ妖めきに
月に泳ぐこの世のいのちおもはざり
暗黑の沖へ沖へと泳ぎて死なむ
きたるべき滿月の夜と決めしなり
滿月の夜を泳ぎてゆきし還るなし
雪溪に死なむいのちともおもふ
この世への訣別の手に月光りぬ
月光と死とかかはりのあらざるも
柿の種投ぐるや風の城ヶ島
戀情や冬甘日藍の重み掌に
[やぶちゃん注:「冬甘日藍」は恐らく、「冬甘藍」で冬キャベツのことであろうと思われる。]
〇鈴木しづ子 大量投句稿の日附不明百六十四句最終句 遊郭へ此の道つづく月の照り
遊郭へ此の道つづく月の照り
不明句のランダムの中なんだから、この句に殊更な感懐を感ずる必要はないのでしょう……が……しづさん……あなたらしい「最後の句」ではありませんか……
◯鈴木しづ子 三十三歳 『樹海』昭和二十七(一九五二)年十月号全掲載句
――以降、我々が見るものは巨湫によって仮構された存在しないしづ子『投句』である。但し、この十月号について言えば締切が八月末日であるとしてぎりぎりしづ子の投句時期内に入るが、選句された句は既に見てきたものと同じく、古い投句稿等から引かれており、その固有性を私は認識しない。――これ以降、我々は巨湫の俳句誌上稀に見る投句詐称史を見ることになる。私はこの『巨湫の犯罪』を最後まで漏らさず見届けたいと思う。
花の穹感激もなく雲流れ (四月十五日附投句稿より)
くわりん咲くいづれは失せるべきわが手 (五月 六日附投句稿より)
手をとりて踊るルンバの螢光燈 (五月 六日附投句稿より)
五月なり山羊は圍はれつつ育ち (五月 六日附投句稿より)
新綠の木曾の急流橋くぐれり (五月 六日附投句稿より)
はつなつや川面ながるる水の泡 (六月十五日附投句稿より)
河越の電車に在りぬ雲の朱け (五月 六日附投句稿より)
風鈴や醉へば唄うてつねのこと (六月十五日附投句稿より)
遠山や五月の竿に衣ほす (六月十五日附投句稿より)
生くるべし蝦夷はまつたき夏みどり (六月十五日附投句稿より)
*
なお、次号『樹海』昭和二十七(一九五二)年十一月号の掲載句五句は総て昭和二十七(一九五二)年九月三日『読売新聞』夕刊文化欄「新人抄」に『雲間の陽』として載った五句と完全に同じものであるから省略する。
◯鈴木しづ子 三十三歳 『樹海』昭和二十七(一九五二)年十二月号しづ子詐称投句全掲載句
しづ子の失踪を、最終投句稿の日附昭和二十七(一九五二)年九月末日と措定し、ここ以降、最後の昭和三十九(一九六四)年七月号『俳句苑』までの実に四十一冊、凡そ十二年間
――但し、途中、
昭和二十八(一九五三)年七月号から翌昭和二十九(一九五四)年一月号までの七ヶ月
昭和三十(一九五五)年十二月号から翌昭和三十一(一九五六)年四月号までの五ヶ月
昭和三十二(一九五七)年三月号から翌昭和三十三(一九五八)年八月号までの六ヶ月
昭和三十四(一九五九)年二月号から六月号までの五ヶ月
昭和三十四(一九五九)年十月号から昭和三十八(一九六三)年五月号まで三年六ヶ月
の『樹海』(後に『きのうみ』に改題)には掲載句がない五ヶ月以上に及ぶ有意なブランクがあり(その間にも一~三ヶ月のブランクは何度もある)、更に「きのうみ」昭和三十八(一九六三)年十月号に掲載されてから最後の『俳句苑』昭和三十九(一九六四)年七月号掲載の間も八ヶ月のブランクがある――
にも及ぶ掲載句を、私は巨湫による『しづ子詐称投句』と呼称することにする。詐称である以上、どの投句稿からのものであるかは、全集でも出版される過程で(そのような企画があるかないかは別として)、全句が自ずとデータベース化されて明らかになるであろう。私は目視によって行っており、時間もかかるし、見落としも出て来る。その労はこれ以降は、今の私にとってあまり価値を認めていない。投句稿にあるものもあり、ないものもあるやに感ぜられるが、淡々と示したい。但し、これがそれらの『樹海』その他を精査された川村氏の編集権を犯すものとならないように、簡単な評は附していきたいと思う。
殊に佳き星をとらへてまぶしめり
男あり鉢卷をして靑田中
蚊遣りの蚊ひとたび堕ちて起ちゆけり
佇ちてあれば柳絮とびゆく水の上
髮梳けばふるさとのごと雪降れり
しづ子の実際の生誕地は東京市神田区(現在の千代田区)三河町である。しかし雪を詠み込んだ最終句の「ふるさと」はそこではない。巨湫によって組み合わされたものであるから前句との関連を問題にするのは意味がないとも言われようが私は「柳絮」が気になる。日本で柳の綿毛が舞うのが見られるのは、大陸からの柳の移入種が多い、北海道である。しづ子の中にあの、大正一四(一九二五)年、しづ子六歳の時、家族と住んだ一時の団欒の幸せな一瞬が、しづ子をして北海道を「ふるさと」と呼ばしめているのではあるまいか。
◯鈴木しづ子 三十三歳 『樹海』昭和二十八(一九五三)年一月号しづ子詐称投句全掲載句
百合瘦せてむかしながらの壕ほとり
旺んなる爐火を見てゐるうちに眠し
まつすぐに生ひて辛夷は蕾むなり
蛇にして全身をもて遁れゆけり
靑嵐北へながるる美濃の鳥
――巨湫先生、遅すぎますよ――「蛇にして」は名吟です――いや――先生――「北へながるる美濃の鳥」――やっぱりしづ子は――「北」へ――渡って行ったのですね?
◯鈴木しづ子 三十三歳 『樹海』昭和二十八(一九五三)年二月号しづ子詐称投句全掲載句
紫陽花の門の裡なる祝ごと
悲劇はこの世だけでいいスクリーンの白雪
光る星以外の星も凍てにけり
この土地の雪に馴染まず牛鳴けり
[やぶちゃん字注:中七は底本では「雪に駒染まず」。ママ注記はないが、如何にもおかしい「馴染まず」(なじまず)の誤植ではないかと感じ、調べたところ、案の定、一月二日附投句稿にあり、「馴」とある。訂した。]
雪つけてゆびきりの指幼なしをさなし
二句目「悲劇はこの世だけでいいスクリーンの白雪」はしづ子の句としては、二冊の句集未収録句ながら、しばしば引用される句である。私は一読の直感であるが、これはマーヴィン・ルロイ監督ヴィヴィアン・リーとロバート・テイラー主演の「哀愁」“Waterloo
Bridge”ではあるまいかと感じている。本映画は一九四〇年製作のアメリカ映画であるが、本邦での公開は敗戦後の昭和二十四(一九四九)年三月である。あの映画のコンセプトは不思議に兵士ケリーとの恋に落ちたしづ子及び娼婦俳人などと呼ばれた「しづ子伝説」と妙に合致する作品なのである。私の好きなヴィヴィアン・リーとしづ子――何よりこの組み合わせが私を惹きつける……
◯鈴木しづ子 三十三歳 『樹海』昭和二十八(一九五三)年三月号しづ子詐称投句全掲載句
しばらくはのぼるにまかす熱き湯氣
仲間はずれの大人の如きふところ手
雪の飛驒より來りし牛のつぶらな眼
この夜の爐火アンネンポルカ愉しく聽く
柿は
「しばらくは」の句は「のぼるにまかす」の表現の面白さなのであろうが、この句は例えば前掲した『指環』所収の「對決やじんじん昇る器の蒸氣」(初出『樹海』昭和二十三(一九四八)年四月号)の後に並べてこそ組写真としてのシーンの面白さが出るのであって、これだけでは最早、喉をやられた風邪ひきが空気を湿らせているみたような愚鈍な景であり、巨湫の選句ポリシーを、私は疑う。
二句目の「ふところ手」をしているのは子供であるが、実は大量投句稿には子供を詠んだ句が想像を絶するほどに多い。伝説のしづ子とは全く異なる母なるしづ子の目線を私はそこに見る(それは何句か既に取り上げてもいる)。今後のしづ子の考察は、未発表の《しづ子伝説如何にもな危険がアブナい句の発掘》ではなく、まず何よりそうした子らを詠唱した等身大のしづ子の母性的優しさから始めるべきであるように私は感じている(次号の選句も同様)。
◯鈴木しづ子 三十三歳 『樹海』昭和二十八(一九五三)年四月号しづ子詐称投句全掲載句
人の子の劇觀て歸る牡丹雪
雪の日の辯論大會少年好し
繪のこと言ふいとしきものよかがよふ雪
子ならずとも春雪を來しかがやく眸
雪中の親しみくるは知らざる犬
雪つけど觸るるべからず御師の眉
前に述べた如く、最初の三句が子らを詠んだもの、四句目は自分の眸の中に子らの童心を見ており、五句目は見知らぬ野良犬に向けるしづ子の優しい眼である。……そして……そして巨湫は、大胆にも昭和二十七(一九五二)年二月十二日句稿から、あの同年二月四日の岐阜駅での、しづ子との数分の再会の一瞬のスカルプティング・イン・タイムの――それもかなり危うい句を……敢えて選んでいる。――あんた、やるね……巨湫さん、よ……
◯鈴木しづ子 三十三歳 『樹海』昭和二十八(一九五三)年五・六月号しづ子詐称投句全掲載句
美濃は好し冬は水邊の歸り花
人間の貌に似てきし老いたる犬
鳰を見るひとにをしふることもなく
この徑の行き盡くまでの蓬とも
本号の選句は明らかに前号までの選句と異なる。しづ子の句は孤愁と死の影を暗示させるものが多いことは事実だが、先の子らを詠唱した作に見るように、その中には小春日のような温もりの句を見出すことは決して困難ではない。勿論、数句を採るにそこに共通のコンセプトを持たせようとするのは、巨湫に限らぬ普通の選句者の教育的立場でもあろう。にしても――である。前号の優しい母性の眼差しを一変させて、語彙も映像もすっかりモノクロームの愁と死のモンタージュに変えたこの選句はどうだ。
そうして――実はこの後、翌昭和二十九(一九五四)年二月号刊行までの、七ヶ月に亙ってしづ子の句は『樹海』に掲載されないのである。――
なお、特にこれ以降の『樹海』に見るように巨湫は詐称投句群に総標題を附し始める。これは今に始まったことではないが、それが顕著になる。しかし私には、これは共時的に投句されたものを掲載しているのではないという真実を隠蔽するための姑息な手段にしか見えないのである。
◯鈴木しづ子 三十四歳 『樹海』昭和二十九(一九五四)年二月号しづ子詐称投句全掲載句
ふたたび
凍蝶に蹤きてさすらひはじまれり
わが不幸東京に見し冬の蝶
玻璃の面の蛾のはばたきを人と思ふ
まん月の夜のいのりぞ女體もて
巨湫よ――何が「ふたたび」だ――お前の中でのみしづ子が復活するとでも言いたいのか?――それがお前の愚劣な犯罪であることを――強迫神経症の如く忘れるためか――そこではしづ子は既に死んでいて――凍蝶や蛾となって――お前を「ふたたび」訪れるとでもおめでたく思ってでもいたのか?……お前が抱いた――いや――誠、抱きたいと思ったが抱けなかった――しづ子が――
◯鈴木しづ子 三十四歳 『樹海』昭和二十九(一九五四)年三月号しづ子詐称投句全掲載句
隱るる如
萬綠の流れ激ぎちこゑを載す
月明の棚に身を凭せ刻過ごす
隱るる如月の片蔭みちをゆく
爐火のまへこの白肌ぞ孤りなる
爐火の燃え祕むるこころの喪さながら
癪だけれど……この五句の撰は美事である――五句全体のソリッドな感覚も素晴らしい。流石は巨湫だ――というより――巨湫は確かにしづ子を愛していた――それだけが分かれば――相愛の二人にもう――僕らは文句は言えないのだ……
◯鈴木しづ子 三十四歳 『樹海』昭和二十九(一九五四)年五月号しづ子詐称投句全掲載句
崖の底
強からぬ爐の燃えゆきを一日とす
風の頭輕く叩く握り拳の手
手をおくや對ふ人なき月夜の餉
惜しむなきいのちをさらす月の前
月光と死とかかはりのあらざるも
堕りし雪の碎け散りなむ崖の底
――選句する巨湫の中に大きな変化が起こっている気がする――どれも、選句する巨湫の側に――ある何やらん不思議な「覚悟」がある――則ち「選句」という作業が、不可思議な――あるしづ子の実相を剔抉しているのだ――そこには二句目のような現実のリアルな実像を挟んで、美事である……私は選句のという行為の「創造性」に今更ながら、気づいたことを告白しておきたい――この憎い「崖の底」という標題も含めて――途轍もなく――素晴らしい――
◯鈴木しづ子 三十四歳 『樹海』昭和二十九(一九五四)年六月号しづ子詐称投句全掲載句
こころぎめ
掌に握る鍵溫し雪しまくなか
秋葵咲きつぐことやここぎめ
風過ぎし穗草匂ふや人あらぬ
「しまく」「繞く」で、取り巻く、取り囲むの意。コスモスは長い期間、開花が続く。「穗草」は穂の出る草や秋に穂花を出している草を指す季語であるが、一般には稲の穂や芒の穂を指すことが多い。ここは後者であろう。
乱舞する雪の中で――
群生し風に揺れるコスモスの中で――
尾花の独特の匂う銀波うねりの中で――
しづ子はいつも――
独りである――
そうしてそこでしづ子は――
必ず埋み火のような心で人知れず一人――
決意をするのだ――
これからも――永遠に――しづ子ひとり――と――
◯鈴木しづ子 三十四歳 『樹海』昭和二十九(一九五四)年八月号しづ子詐称投句全掲載句
穗草
夏涸れの橋つくふや稻葉川
塔下なる疾風の麥明日は刈る
穗草吹く匂ひを人とおもひけり
星霽れのしんしんと濃き樹蔭ゆく
叔母の戀情噺笑ふにもあらず氷柱照る
「夏涸れの」は不審。前掲したようにこれは日附不明の大量投句稿にあるが、そこでは、
夏枯れの橋をつくらふ稻葉川
音数律から見ても『樹海』の誤植であろうと思われるがママ注記もない。これはそのまま表記しておいた。なお、やはり前の昭和二十七(一九五二)年九月二日附句稿で掲げた通り、この「稻葉川」はしづ子にとって意味深長な固有名詞なのである。巨湫がそれをここで敢えて出したこともやはり巨湫にとっても意味深長なのである。
「穗草吹く」は底本「隠草吹く」。これでは標題の意味が分からぬ。「隱草」では意味も分からぬ(私は不学にして「隠草」という、この如何にもいい風雅な熟語を知らない)。『樹海』の誤植なのか、しかしママ注記もない。こちらは私の独断で勝手に訂した。
「叔母」は岐阜在住であった歌人の山田朝子(旧姓鈴木)。その句柄はしかし、絶対零度である。しづ子と叔母との関係は社会的立場及び親族内でのしがらみへの意識の相違による相互不理解と、「アララギ」の正統派と「しづ子伝説」の観念世界のギャップからか、既に冷えきっていた。それが正に低温吸着して肌がべろりと剥けるように、美事に詠まれた句である。
なお、ここまでで気が付くことが一つある。
――三月号の最終句は、
爐火の燃え祕むるこころの喪さながら
次の五月号の巻頭句は、
強からぬ爐の燃えゆきを一日とす
その掉尾は、
堕りし雪の碎け散りなむ崖の底
次の六月号の巻頭句は、
掌に握る鍵溫し雪しまくなか
その掉尾は、
風過ぎし穗草匂ふや人あらぬ
そして次の本八月号の冒頭標題は
「穗草」
である。
これは確信犯の連鎖である。巨湫は何かを考えていた――少なくとも漫然と――しづ子の投句を詐称するためだけに掲載していたのではないことは確かだ。しづ子の失踪の景色は、もしかするとその巨湫の選句の中にこそ、宿命的に暗示的ながら、ぼんやりと姿を現してくるのかも――知れない
◯鈴木しづ子 三十四歳 『樹海』昭和二十九(一九五四)年九月号しづ子詐称投句全掲載句
香ぐはひ
香ぐはふ梅くちにのぼりしひとつこと
なしをへし文の重みぞ香ぐはふ梅
雪つけど觸るるべからずお師の眉
師が手とつむ春雪とすべもなし
香ぐはふ梅かぐはふ
蹴る春雪こころいちづに在りし吾が
風花やむかしのおのれ殘すなし
すべてこと師にぞしたがふ香ぐはふ梅
三句目は、『樹海』昭和二十八(一九五三)年四月号しづ子詐称投句の、
雪つけど觸るるべからず御師の眉
の「御」を「お」に変えて、例外的に再掲されたものである。通常の俳誌の投句選句ではあり得ないことである。詐称している巨湫にしてみれば、これは詐称投句を大疑わせる大きな証左となろう。尚且つ、この九句は巨湫によって組み立てられたと考えられる、「しづ子」の秘めた(いや、もはや赤裸々に露呈された)巨湫自身への恋愛感情を核心としていることを、読者は容易に感じ得たはずである。巨湫はもうどこかで詐称を確信犯として、意識しなくなっていたようにも思われる。そうして見た時、この連作の標題「香ぐはひ」というのは、言わずもがな(と私には感じられる)例の「まぐはひ」という語――しづ子独特の詩語――をも連想させるではないか――梅の香ぐはひ――それは巨湫としづ子の――魂の交接であった――
◯鈴木しづ子 三十四歳 『樹海』昭和二十九(一九五四)年十月号しづ子詐称投句全掲載句
岐阜駅未明
春雪やへだて觸るるお師の胸
曉星や師ならぬ人とし膽む希ひ
春雪やあはれまぎれぬ星とひとつ
つむ春雪その白ら胸を裂かむとす
總べてはすべてあかつき裂きて積む春雪
白ら雪に還し申さむ曉の星
申さずに積む春雪の白かりき
前号に続く確信犯である。尚且つ、これらの句は明らかに例の昭和二十七(一九五二)年二月四日零時の岐阜駅での巨湫としづ子の邂逅を詠んだものであるのだが、精査したわけではないけれども、大量投句稿の中にはなかったように思われるのである。これらの句の感懐は――まさしく、自ら自身の白い胸に爪を立てて血飛沫を白雪に飛ばさんばかりの「熱情」に満ちている。――これらは巨湫が秘かに自身の死とともに葬ったと思われる失われた投句稿から出た稀有の迸りであり、しづ子の巨湫へ宛てた秘められた愛の句群の断片のように私には思われるのである――
いや……それにしても……しづ子の失踪から早二年……失踪以降、巨湫がしづ子の居場所を知っていたのかどうか……知らなかった、とすれば……しづ子は失踪以後の『樹海』を読むことはなかったと思う……私はしづ子は失踪以降……失踪しているはずの自分の句が投句されている『樹海』を……手にしなかったのではないかと考えているのである……そうして……そうしてこうした続けられる巨湫の詐称犯罪を何らかの形で知ったとしても……しづ子にとって何の関心も不満も憤激もなかったであろうと……私は思うのである……しづ子は、巨湫や『樹海』や俳壇という複数の共同正犯になる「しづ子伝説」捏造という特別背任の文芸犯罪社会とは……最早、全く無縁な世界に遮断されてあったように……感ぜられるのである……
◯鈴木しづ子 三十四歳 『樹海』昭和三十(一九五五)年一月号しづ子詐称投句全掲載句
墓
わがことをひとびと言ふや麥の秋
麥秋やつねききながらおのがこと
知人なしやがて花もつ櫻の木
坐すや膝年賀のふみのひとつなく
つよからぬ體臭の衣すらも脱ぐ
ただ墓が穹のましたにならぶのみ
この句群は不思議にいい。それはまさにこの時期にあって――先の前年九月と十月の二号続きの巨湫に私物化された「しづ子」の後では――殊によい。私が当寺の『樹海』同人なら、まさにこの句群に、しづ子は投句を続けている、しづ子節は健在だ、と間違いなく思うであろう。しかし、それも巨湫の完全犯罪なのか。――そうして――確かにしづ子の眼は――死を見据えている――
◯鈴木しづ子 三十四歳 『樹海』昭和三十(一九五五)年二月号しづ子詐称投句全掲載句
近江の葉
脚組むやおほかたの驛雪をつく
吹くすそやつまさき滲みる膳所の雲
一樣に外套黑し旅長く
湖冷えの吹かるるばかり近江の葉
よべ雪のあともなかりし近江の葉
雪冷えのつまさきおろす京都かな
しづ子の句としては極めて稀なソリッドな、しかもスラーのようにブレイクの殆んどない旋律の稀有の羈旅吟を構成している。しかし、その結果として「脚組むや」という冒頭の一句の初五以外には、しづ子らしさが感じられない。しづ子の句と言われなければ、「なるほど、悪くないね」で、暫くすると思い出せなくなる(少なくとも私には)「実に纏まった、それらしい」句群である。
◯鈴木しづ子 三十四歳 『樹海』昭和三十(一九五五)年三月号しづ子詐称投句全掲載句
鹿
雄の鹿のたちてうごかず形り固く
雄鹿たつ吾れに背きてほど遠く
雄の鹿のこころ深げに形りにたつ
水飮みに鹿下りてくるおなじみち
すこし水飮みて足りつつ鹿驅くる
前号の「近江の葉」の京都を読んでいると、あたかもそのまま奈良に向かったしづ子の穏やかな羈旅吟のようにアリバイが作られていはしないか。読者を巧妙に騙す巨湫マジックである。
◯鈴木しづ子 三十四歳 『樹海』昭和三十(一九五五)年五月号しづ子詐称投句全掲載句
母
母が名を洗ひ濡らすや墓石の面
夫戀ひの母が一世や土の苔
幸ちうすくおのれに似かよふ母が貌に
かつては製圖工すそ曳けば紅し
――私の顔は真ん中に鏡を立てると――右の対称は母になり――左の対称は父になる――因みに――私の両親は従兄妹である――
◯鈴木しづ子 三十四歳 『樹海』昭和三十(一九五五)年六月号しづ子詐称投句全掲載句
露散る
ひとり行きひとり歸りぬ木曾の水
露散るや嫌ひつづくるおのが詩
後者の「詩」は「うた」と読ませるのであろう。
◯鈴木しづ子 三十五歳 『樹海』昭和三十(一九五五)年七月号しづ子詐称投句全掲載句
春
焜爐据ふ春あかつきの土の上
春が來て砂面の枯藻焚かれけり
吹きやみの深まる昏らみ燈しけり
三句とも、静謐なタルコフスキイ的な画面で、大いに惹かれる。標題の年齢を、六月九日のしづ子の誕生日を過ぎたので満年齢で三十五歳とした。
◯鈴木しづ子 三十五歳 『樹海』昭和三十(一九五五)年八月号しづ子詐称投句全掲載句
春の夜の膚をつぼめし衣うち
竹吹き葉擲つにひとしき怒り起つ
人の言百里を越えて怒り起つ
花すでに美濃は風起つ水ほとり
この選句には標題がなく、尚且つ底本には『(一般欄)』とある。これは俳誌の同人欄(通常、毎号の掲載が保障される)ではない、格下の一般読者投句欄の謂いであろうか。この号でのこの巨湫の処置には(底本で『(一般欄)』注記があるのはこの号だけである)、何か特殊な意味が隠されているように思われる。巨湫が選んだ三句の句柄も、身「うち」に内向していた激しい「怒り」遂に屹立して「起」ち、それが頬を切る、花を散らす鋭い春一番の疾「風」となって外界へ解き放たれているような、独特の心理的な螺旋状の情念のエネルギを感じさせるものである。――巨湫に何かあったのか――もしくは――巨湫にしづ子に関わる何らかの知らせが齎されたのか――
◯鈴木しづ子 三十五歳 『樹海』昭和三十(一九五五)年九月号しづ子詐称投句全掲載句
徑
郭公や旅了らむとしつつなほ
この徑や人にあはざるいぬふぐり
この二句、芭蕉の
憂きわれをさびしがらせよ閑古鳥
この道やゆく人なしに秋の暮れ
の名句二句を美事にインスパイアしている。特に私は後者の「いぬふぐり」の小花の美しいアップが気に入っている。この二句はしづ子の代表句として残されるべき句であると、本気で思っている。
◯鈴木しづ子 三十五歳 『樹海』昭和三十(一九五五)年十月号しづ子詐称投句全掲載句
足凍てし嬰兒は涕くにこゑもたず
一冬の枯藻みかへることもなし
雨おち來簷したかこふ竿の衣
對ふ屋に雨吹きつくる竹葉かな
三句目「衣」は「きぬ」と読むのであろう。どの句も盤石にして佳品である。しづ子の俳句の基本は、昔々のとっくのとう、とっくのとうの大昔に――出来ていたのだ。
それにしても、ずっと不審なのだが――失踪以前の大量投句稿の句でさえ発表形と原稿に殆んど全く変化がないのは何故だろう? 師匠の朱が全くと言っていい程入っていないのはどうしてだろう? 僕も「層雲」にいた頃にやられて憤慨した経験があるが、俳句結社では元の句が想像出来ない程、朱を入れる師匠が多いのに、だ――
ついでに失礼乍ら――彼女が師と慕った巨湫の――彼の、人口に膾炙した代表句を四句挙げろ――と言われて挙げられる人間が、今、何人いるんだろう?
◯鈴木しづ子 三十五歳 『樹海』昭和三十(一九五五)年十一月号しづ子詐称投句全掲載句
たがひ汽車並行つづく雪の中
雪の汽車つづけきて岐る
ただ凍むのみ北陸線を待つ人ら
離れては雪中の居となりにけり
発表号と句の季節が近く、四句はまごうかたなき強力な組み写真、連作である。にもかかわらず巨湫は標題を附していない。「雪」「北陸線」「雪中の居」――これは私にはしづ子失踪の――そのギミー・シェルターの暗号であるように思われるのである――
◯鈴木しづ子 三十五歳 『樹海』昭和三十一(一九五六)年五月号しづ子詐称投句全掲載句
ここ美濃に封建の麥靑みたり
星とぶやいつさい棄ててはばかるなし
ちらつく雪吉と引きたる紙は仕舞ふ
夏雨やいっぱい叩く葉のおもて
ここではまた美濃に来た頃に戻っている。底本で漫然と読んでいると、前号の句がすぐ右にあるために、それらの前号の句が秘密の暴露でも何でもない岐阜行の、岐阜での日常的嘱目吟のように見えるかも知れない。しかし、前号とは実は半年もブランクがある。そこに連環らしきものを感じる方が、実は不自然である。そもそも岐阜では「北陸線」はおかしい。そしてそうした錯視効果は、言わずもがな、選句者自身が確信犯で行なってもいるのだ――巨湫はしづ子のジグソー・パズルのピースを用いて実は、読者に、しづ子の句の意味する絵とは別な絵を見せているのだと私は思う――
◯鈴木しづ子 三十五歳 『樹海』昭和三十一(一九五六)年六月号しづ子詐称投句全掲載句
寒濤の欲らばこの身をあたふべく
人の言うべなふべきか柿の花
虫鳴く中洋服簞笥まつすぐ立つ
――私は時々、しづ子の句を詠んでいると、マルセル・デュシャンの作品を見ているような錯覚を感ずることがある――最後の――虫鳴く中――SE――洋服簞笥――フレッシュ・ウィドゥ――真新しい未亡人――まつすぐ立つ――
◯鈴木しづ子 三十六歳 『樹海』昭和三十一(一九五六)年七月号しづ子詐称投句全掲載句
方丈記
菊の葉に鎭まりがたき吹雪かな
人の子に慕はれゐたり枯野中
夕燒の失せし地をゆく乳母車
月明の眞中に在りて煽げる火
雪の日の講義續くや方丈記
ここまで付き合って下さっておられる読者には言わずもがな――標題の最終句は、しづ子の高等女学校時代の淡き秘やかな初恋の相手であった国語教師の古文の授業である。巨湫の標題附けは実に上手い。最後の句に辿り着くまで、前の四句は「方丈記」に描かれた貧困と天変地異や火事に荒廃した末法の京の都を髣髴とさせるように選ばれているように思われるのだ。いや、私は巨湫の恣意的選句は絶対にそれを意識していた、と思うのである。
◯鈴木しづ子 三十六歳 『樹海』昭和三十一(一九五六)年八月号しづ子詐称投句全掲載句
東京のからたち芽吹く頃と思ふ
すべて星月ひかりの甍おく
鵙鳴くや沼に棄て來し戀ひとつ
そびらにて春の霜の葉吹かるるか
おのおのの葉のいのちささげて月に光らふ
三句目――鵙鳴くや沼に棄て來し戀ひとつ――SEもロケーションも完璧――泉鏡花の「沼夫人」だ――私好みの句である――
〇鈴木しづ子 三十六歳 『樹海』昭和三十一(一九五六)年九月号しづ子詐称投句全掲載句
からたち
照る月を夫となすかけがへあらぬ
人形に添寢をさせる蒲團かく
炎え出でし梅雨の光りの永からず
楓の葉に梅雨颱風あつさり過ぐ
渦潮の春日のもとの厚みかな
躬を寄せていぶり炭をば見分けむと
なぜか汗が哀れでならぬ書きつつに
「渦潮の」と「躬を寄せて」の二句は――特に伝統俳句の観点から見れば――如何にも渋い名吟と私には映る。少なくとも地に足の着いたしっかりとした句である。
〇鈴木しづ子 三十六歳 『樹海』昭和三十一(一九五六)年十一月号しづ子詐称投句全掲載句
このあたり柿美しく子は早熟
秋の夜の醬油こぼせしひとりごと
ひとの顏野分の中に現れぬ
へだつればいつさい喜劇石榴咲く
ひつそりと彌生の晝を覺めにけり
「へだつれば」と「ひつそりと」の句は大量句稿中の昭和二十七(一九五二)年二月十二日附句稿に認められ、前者は、
經だたればいっさい喜劇柘榴咲く
の句形で、珍しく軽い巨湫による斧正が入っている。
〇鈴木しづ子 三十六歳 『樹海』昭和三十二(一九五七)年一月号しづ子詐称投句全掲載句
傾くやいつさい了へし雪の墓
――フリードリヒの絵を髣髴とさせる寂寥の画面――
〇鈴木しづ子 三十六歳 『樹海』昭和三十二(一九五七)年二月号しづ子詐称投句全掲載句
步をとめて見るまでもなく銀河あり
因みに、ここで私はしづ子と接続する。この月の十五日に私は生まれているのである――
「……銀河を渡ってゆく
〇鈴木しづ子 三十七歳 『樹海』昭和三十三(一九五八)年九月号しづ子詐称投句全掲載句
畫くべくには一樹置きたるこの夏野
わが喰むべき土用鰻を殺さしむ
わが喰むべき土用鰻の殺されけり
『樹海』昭和三十二(一九五七)年二月号の掲載から実に一年七ヶ月のブランクがある。この時点で、私が巨湫の詐称が始まったと考える昭和二十七(一九五二)年十二月号から実に五年九ヶ月が経過している。この大きなブランクはしづ子とは無縁な巨湫の何らかの個人的理由なのかも知れないし、巨湫の中のしづ子への思いへの大きな変化があったのかも知れない。これは最早、明らかにはならないことであるが、この後のしづ子詐称投句の掲載減少と長い途絶を考える時、そこに――しづ子に繋がる巨湫の現実世界や秘められた内心に――我々の知らない、何らかの大きな変化があったことは否めない気がする。
〇鈴木しづ子 三十七歳 『樹海』昭和三十三(一九五八)年十一月号しづ子詐称投句全掲載句
蟬鳴くなか生煮えの菜に塩をふる
月下にて駿柵のひま次第に粗き
詩稿すべて裂きてすてしより落着く
底本、二句目の後に編者により『「駅柵」の誤植』という注記がある。「蟬鳴くなか」の句、何故か一読忘れ難い。
〇鈴木しづ子 三十七歳 『樹海』昭和三十四(一九五九)年一月号しづ子詐称投句全掲載句
體を入れてコスモスを折る驛柵のひま
月下にて驛柵のひま次第に粗き
銀漢の定かならねば滿たされず
手袋の五指を握る凍でゆまじ
儀禮的に手袋をはづせしなり
首をめぐりてマフラの端を背と胸に
底本では「月下にて」の後に編者により『再掲載』の注記がある。これは昭和三十三(一九五八)年十一月号の誤植を受けてのものと思われるが、そうした気の使い方にも、私は巨湫の微妙な心のあるゆらぎのようなものを逆に感じるのである。
〇鈴木しづ子 三十八歳 『樹海』昭和三十四(一九五九)年七月号しづ子詐称投句全掲載句
蟬籠提げ兄に蹤きゆくうたがはず
炎暑の地罐がころがる誰も除かず
やがて蟻つどひくるらむ棄てし菓子
「蟬籠提げ」兄妹の蟬取りの嘱目吟であろう――あろうが――私には少女のしづ子と――少年の巨湫がそこに見える――
〇鈴木しづ子 三十八歳 『樹海』昭和三十四(一九五九)年九月号しづ子詐称投句全掲載句
挑まれてわが甲虫たたかへり
如何樣にしても甲虫たたかはず
甲虫を
しづ子の好きな「欲る」という動詞を以て終わり……この後、凡そ四年、しづ子の句は『樹海』から姿を消す―……
〇鈴木しづ子 四十一歳 『きのうみ』昭和三十八(一九六三)年六月号しづ子詐称投句全掲載句
きょうだいの性異なれる綠雨かな
拭ぐう雨東京の土踏むことなし
書くときも身近かにたもつ蠅叩き
五月雨や流れどおしの木木の膚
萬綠や腰おろすべき石さがす
この時、『樹海』は『きのうみ・樹海』と改称し、通算五十号を数えている。さて、掲載句は総て現存する大量投句稿の、最も古い昭和二十六(一九五一)年六月八日附句稿から採られている。但し、「拭ぐう雨」と「五月雨や」の二句は、投句稿では、
拭う汗東京の土踏むことなし
五月雨の流れどおしの木木の膚
である。後者の斧正は格助詞「の」の畳み掛けを切れ字で断つ方が断然よく、穏当であり正しい(「ぐ」の、この後にも似たように見られる気持ちの悪い送り仮名はいただけないが)。しかし、前者は私から見ると、たとえ師であっても斧正としては全く認められない『操作』である――いや――いいか、どうせ詐称しているんだから、ね……。
そして――この掲載には巨湫の最後の芝居と謎かけがなされている――
まず、川村蘭太氏の「しづ子 娼婦と呼ばれた俳人を追って」の本文(三九四頁)によれば、この詐称投句に虚偽の選評を施し、
ひさかた振りのしづ子さん。俳句のルール(すじみち)を踏まえている。――象徴――てんでゆるぎもありません「格はいく第五詩格旧十七音詩」(乗摘象徴発想)として推します
とあるとする。『「格はいく第五詩格旧十七音詩」(乗摘象徴発想)』とはよく分からないが、恐らく巨湫が「樹海」同人の中で展開した彼の独自の俳論のセオリーの一種であろう。それにしても、ここまで確信犯で詐称を厚塗りする巨湫は、何か見ていて傷ましい気がしてくる。
更に「謎」である。それは、この掲載の作者の住所を示す位置に(底本では一句目「きょうだいの」の後に編者注で示されるが、「鈴木しづ子」という名前がその句の下(若しくは後)に示されてある、その下の位置か?)ある。
狭河
である。謎の地名である、この謎の「狭河」の探訪は「しづ子 娼婦と呼ばれた俳人を追って」の最終章をお読み戴きたい。
――それにしても――巨湫が四年の沈黙を破ってまたしても確信犯の詐称を再開した、その採録投句稿が、例の異様な大量投句稿の最初の日附であることに着目したい。――巨湫はまたしても確信犯でゼロ座標からしづ子投句を始めようとしたのではなかったか? 彼は性懲りもなく――またゼロから詐称を始めたのではなかったか?!……しかし……
〇鈴木しづ子 四十二歳 『きのうみ』昭和三十八(一九六三)年八月号しづ子詐称投句全掲載句
濃靑の葉のため息にて雫りけり
高かき葉の隔日に照る梅雨なりけり
蟻の體にジユッと當てたる煙草の火
梅雨の燈や海を渡たれば近づく駿
梅雨寒むの點もらぬ煙草唇はさむ
前の注で私が「……しかし……」と言った理由は、以下の句の出所からである。
・第一句「濃靑の」(「濃靑」は「こあを」と読む)は第二句集『指環』に所収している句である。但し、これまで『樹海』その他の誌上に掲載されたことはない。しかし、十一年前とはいえ、厳然たる句集の既出句である。
・第二句「高かき葉の」は昭和二十六(一九五一)年『樹海』八月号既掲載句。但し、先行句は不自然な送り仮名「か」はない。
・第三句「蟻の體に」も昭和二十六(一九五一)年『樹海』八月号既掲載句。但し、先行句は歴史的仮名遣いに則り、「ジユツ」で拗音化されていない。
・第四句は、底本編者注もあるが、「駿」は「驛」の誤植で、現存する大量投句稿の、最も古い昭和二十六(一九五一)年六月八日附句稿から採られたものである。但し、句稿では、
梅雨の燈や海を渡れば近づく驛
と、「渡」に奇妙な送り仮名「た」は、ない。
・第五句「梅雨寒むの」も同じく昭和二十六(一九五一)年六月八日附句稿から採られたものだが、これは
梅雨寒むの點さぬ煙草唇はさむ
であり、斧正が入っている。しかしここでも奇妙な送り仮名「も」が入っていることの方が気になる。
以上の内、少なくとも昔からの「樹海」同人にとっては最初の三句は既知の旧句である。特に『樹海』を手に取り、また、部外者でもしづ子を少しでも知る者なら「蟻の體にジユッと當てたる煙草の火」を知らぬ者はなかったはずだ。少なくともしづ子を知っている「樹海」同人であったなら、この号で巨湫がしづ子を詐称していることを、どんな馬鹿でも見抜くであろう。――前号とこの号との二か月の間で、もしかすると巨湫は、「樹海」同人の鋭い誰かからか暗に詐称を指摘されて(それも、あの如何にもな選評が仇となって)、自分の犯罪がバレたことを知ったのかも知れない。――ともかくもこれで、巨湫は遂に詐称を公的に認めてしまったことに他ならない、と私は思う。――その呵責が、無意識的に元の句を変則的に変えるおかしな送り仮名になって表れたのではないか? いや、巨湫にとって詐称は――もうどうでもいいことであったのかも知れない……
〇鈴木しづ子 四十二歳 『きのうみ』昭和三十八(一九六三)年九月号しづ子詐称投句全掲載句
蟻をあわれとおもうことよりおのれをば
蟻のごとおのれの危機に聡とかりせば
とりいだせし扇風機にも過去嚴と
とりいだせし扇風機にも戀哀われ
とりいだせし扇風機にて人はなし
総て昭和二十七(一九五二)年七月二日附大量投句稿から。但し、次の三句は表記が異なり、
蟻をあわれとおもふことよりおのれをば
蟻の如おのれの危機に聡かりせば
次の句はてにをはが異なる。
とりいだせし扇風機にて戀哀われ
なお、これらの選句されたものの原稿は殆ど同一の句稿紙から採られたもので、九句の連続した句稿からこれら五句が選ばれている。
〇鈴木しづ子 四十二歳 『きのうみ』昭和三十八(一九六三)年十月号しづ子詐称投句全掲載句
午後よりは齒醫者へ通う梅雨の照り
炎日の草が吹かるる縣境
短か夜のゆめの白さや水まくら
風鈴や枕に伏してしくしく沸く
最終句の「沸く」はママ。「涕く」の誤植。総て現存する大量投句稿の、最も古い昭和二十六(一九五一)年六月八日附句稿から採られたものである。総てを投句稿の正表記(私の恣意的な旧字化をしていない底本のままの意)で示す。
花舗へ橋越えてゆく梅雨の降り
午後よりは齒醫者へ通ふ梅雨の照り
炎日の草が吹かるる縣界
短夜の夢の白さや水枕
風鈴や枕に伏してしくしく涕く
「花舗」の読みは元にはない。これらも同句稿の連続する十六句の中から採られた五句である。因みに、最後の句は『指環』に所収する句である。
――そしてこれが――鈴木しづ子の『きのうみ・樹海』での詐称掲載の――最後となった――
〇鈴木しづ子 四十三歳 『俳句苑』昭和三十九(一九六四)年七月号しづ子詐称最終投句全掲載句
きょうだいの性異なれる綠雨かな
拭う雨東京の土踏むことなし
書くときと身近にたもつ蠅叩き
五月雨の流れどおしの木木の虜
万綠や腰おろすべき石さがす
「五月雨の」の「木木の虜」はママ。「膚」の誤植。ここだけは総て底本通りの表記で示した。『きのうみ』昭和三十八(一九六三)年六月号しづ子詐称投句全掲載句の再録(「拭ぐう」の「ぐ」がなくなり、「萬」が「万」になっている)であるが、ともかくも、これが最後の巨湫による、本当の最後のしづ子詐称投句ということになる。『俳句苑』は巨湫が関わった同系組織の短詩系結社の転載総合俳句誌といったもので、この『俳句苑』は第二次の再開創刊号にあたる(巨湫は主宰ではなく編集長であった)。――これが最後となったのは――巨湫は本号発刊直前に脳軟化症で倒れ――そして、この昭和三十九(一九六四)年七月二十三日に――亡くなったためである――ともかくも巨湫は――確信犯でしづ子を騙った詐称投句を――死ぬまで貫徹したと言えるのである――
〇附 しづ子大量投句稿日附不明二十枚の内 ノンブル「17」・「18」
川村蘭太氏の「しづ子 娼婦と呼ばれた俳人を追って」の中に判読可能な大きさで画像が示されている句稿が二枚ある。これを見ると、少なくともこの句稿の場合、激しい推敲の後を留めたもの(投句用の清書原稿ではない)であることが分かる。川村氏はこれを用いて、しづ子の作句上の特徴である『連作作法』を明らかにされている。川村氏の言う『連作作法』とは、『最初に得たイメージを連鎖させることによって、自身のテーマを摑んでゆく方法で』、『テーマの確証が固まってくると、しづ子は俄にその主題に埋没し出』し、『彼女はテーマに埋没することによって描くべき人物になり切ってゆく』のだと説明されて、その例をこの二枚を用いて解説なさっておられる。
ただ、ここには私にはやや解せない部分がある。それは三五六頁の書き出しに『最初のイメージを想起させる句』として掲げられた、いわばここで連作作法を説明するプロトタイプの句として、「満月の夜にて女體の恥ずるなり」が示されているのだが、ここを読んでゆくと、この句は「17」よりも前の句稿にあるように書かれているのである(三五七頁冒頭に『これでこの句は完了したのかと思うと、一七枚目には』とある)。ところが、更に読み進め、また挟まれた画像を視認すると、「18」枚目になってまた、先に川村氏が説明したのと全く同じ推敲訂正抹消を施した「満月の夜にて女體の恥ずるなり」がまた現れるのである。同じ推敲訂正末梢を施したものが再度現れることはあり得ないとは言えないが、失礼乍ら私はここには、叙述に何らかの錯綜があるのではないかと疑っているのである。
それはそれとして、私は、本プロジェクトの最後に、この与えられたしづ子の生原稿を私なりの方法で読み取り、活字で再現したい願望に駆られたのである(「しづ子 娼婦と呼ばれた俳人を追って」巻末の「鈴木しづ子 全句」にある句群は推敲の跡を示していない。それはそれで良いのだが、それ以外に、失礼ながら例えば最初の句の下五を「搖らぎかふ」と誤読――これは草書体の「な」を「ふ」と誤読したとしか思われず、実は「鈴木しづ子 全句」の他の箇所にも同じ誤りが散見されるのである――している。更に「全句」では、本文で川村氏がちゃんと読んでいる「祈」の字が「■」で判読不能となっている等々、正直言って「全句」の判読は判読者の能力が疑われ、「全句」と称することの疑義を感じさせるのである)。以下、その作業を、せめてもの私の最後のしづ子への謝意として終わりとしたい。
●大量投句稿日附不明二十枚の内 ノンブル「17」句稿
17[やぶちゃん注:右上に。通常便箋。左右の端の罫は、やや太く且つ上下もやや長い。句は基本一枚の便箋に一行空きで八句書かれており、その間に推敲跡がある。]
臥して見る白木蓮の搖らぎかな
花過ぎの木蓮の葉の靑みけり
足早に樹蔭を過ぐる手の包み
[やぶちゃん注:次の句は激しい推敲の跡がある。画像が小さいので抹消文字の判読は難しいが、推敲課程を私なりの読みで推測しながら示すと、まず最初に、
木蓮の白花をもちし樹蔭なり
と書いたもの全体を波線一本で抹消し、右に一字下げて少し小さく、
花過ぎの白木蓮の茂りかな
と記した上で、更にその下五「茂りかな」を途中で捻じれた一本線で抹消し、左側の空行の「もちし」の「ち」の高さの所に同じ大きさの字で、
木の茂り
と書いて、二行前の「白木蓮の」の「の」の下と曲線で繫げている。従って、次の句が最終推敲句となる。]
花過ぎの白木蓮の木の茂り
[やぶちゃん注:従って、この句の推敲過程は、
木蓮の白花をもちし樹蔭なり
↓
花過ぎの白木蓮の茂りかな
↓
花過ぎの白木蓮の木の茂り
となる。]
[やぶちゃん注:次の句は、本来、以下の記載がしづ子のものである。]
滿月の夜は女體もて祈り遂ぐ
[やぶちゃん注:ところが不思議なことに、この句は「全句」に所収しない。そして、この句稿には鉛筆による書き込みが多数ある。以下、その鉛筆書きを説明する。
まず句の頭に「の」の字状の記号、その下に「レ」字型の記号が重ねて二つ存在する。
そして、
「滿」をぐりぐりと消して右に「まん」
とあり、
「夜は」の「は」をぐりぐりと消して右に「ぞ」
と書き、
「祈り」の「祈」の横に「いの」
と書く。
ところが鉛筆による書き込みはそれで終わらずに、全体の曲線を持った一本線で削除線が延びて、「遂」の字から逆Vの字型に下部に線が引かれて、その中に、右側、判読不明の丸に左に落ちる鍵型の不思議な記号、その下に「?」を〇で囲ったような記号を配し、その左に、「〇レ」のような記号を頭にした、
まん月の夜の
とあって、その更に左に(写真では一部の判読が難しいが川村氏の判読を参考にすれば)、
いのり女ぞ體もて
とある。これをそのまま続けて表記すれば、
まん月の夜のいのりぞ女體もて
と読める。しかし乍ら、これは鉛筆であり、頭の「レ」の記号を見ても、しづ子の書き入れではなく、本文で川村氏も指摘されている通り、巨湫の斧正と見て間違いない。従って、しづ子の句としては、あくまで最初に示した「滿月の夜は女體もて祈り遂ぐ」のみが「全句」として採用されなければならない。]
[やぶちゃん注:次の句も激しい推敲の跡がある。まず最初に、
滿月の夜こそ女體のけがれなし
と記し、恐らくまず、「こそ」を二重線で消去し右に、
にて
と記した。ところがその後に気に入らなくなったしづ子は残りの「滿月の夜」「女體のけがれなし」の部分に波線を引いて末梢、左の空行部に、少し小さな字で、
滿月の夜のいとなみの女人の手
と直した。しかし、下五がやはり気に入らず、「女人の手」を一本線で消去、今度は右の空行部分に、
女體の手
と書いて、「いとなみの」の下に曲線で繋げて、以下の句を決定稿としている。]
滿月の夜のいとなみの女體の手
[やぶちゃん注:則ち、この句の推敲過程は、
滿月の夜こそ女體のけがれなし
↓
滿月の夜にて女體のけがれなし
↓
滿月の夜のいとなみの女人の手
↓
滿月の夜のいとなみの女體の手
となる。]
傳説の満月の夜の捧げもの
滿月の夜はいけにへの女體焚くと
●大量投句稿日附不明二十枚の内 ノンブル「18」句稿
18[やぶちゃん注:右上に。通常便箋。以下、17に同じ。]
滿月の夜は祈りの手ほどかざる
[やぶちゃん注:元は、
滿月の夜は祈りの手摑みしままに
とあったものを、下五字余り七音を波線で消去、「ほどかざる」と右に記したもの。]
女體にて月のみ前に恥づるなし
[やぶちゃん注:頭に巨湫によると思われる鉛筆の「レ」点一つあり。この句は元の、
月み前女體捧げて惜しむなし
を総て波線で消去、その右側にやや小さな字で表記の句を書く。]
滿月の夜にて捧げむ女體かな
[やぶちゃん注:頭に巨湫によると思われる鉛筆の「レ」点一つあり。この句は元の、
滿月の夜こそ捧げむ女體かな
とした「こそ」を二重線で消去、右側に「にて」とする。]
女體にて滿月の夜の火を捧ぐ
[やぶちゃん注:元は、
滿月の夜こそ女體の恥づるなし
であった。まず「こそ」に二重線を引き、右側に「にて」として、
滿月の夜にて女體の恥づるなし
としたが、気に入らず、「にて」を一本線で消去、更に「滿月の夜」「女體の恥づるなり」を波線で消去して、冒頭の句を決定稿としたものと思われる。]
滿月の夜に女體に祈りはなし
萬綠の岩に足立ち髮を梳く
ローレライの乙女とおもふ萬綠に
綠蔭におのが歌ごゑ翳らしむ
[やぶちゃん注:この句、頭に巨湫によると思われる鉛筆の「レ」点二つあり。]
これを以て、私の「鈴木しづ子句抄――雑誌発表句・未発表句を中心にしたやぶちゃん琴線句集」を終了する。
最後に――
我々に鈴木しづ子の全貌を伝えて下さった川村蘭太氏に改めて心より感謝する――
そして――
――しづへ――
――愛を込めて――
“Here's looking at you, kid!”
――君の瞳に乾杯!――
鈴木しづ子句抄――雑誌発表句・未発表句を中心にしたやぶちゃん琴線句集 完