
[島の男]
The Aran Islands
Part Ⅳ
by J. M. Synge
With drawings by Jack B. Yeats
Dublin, Maunsel & Co., Ltd.
[1907]
アラン島
第四部
ジョン・ミリングトン・シング著
ウィリアム・バトラー・イェイツ挿絵
ダブリン マウンセル社刊
姉崎正見訳
附 やぶちゃん注

[島の男]
The Aran Islands
Part Ⅳ
by J. M. Synge
With drawings by Jack B. Yeats
Dublin, Maunsel & Co., Ltd.
[1907]
アラン島
第四部
ジョン・ミリングトン・シング著
ウィリアム・バトラー・イェイツ挿絵
ダブリン マウンセル社刊
姉崎正見訳
附 やぶちゃん注
[やぶちゃん注:本頁は私のブログでの第四部の公開を経て、第四部全文を一括して作成したものである。底本・凡例及び解説は第一部を参照されたい。今回、明らかな脱字と思われる箇所には【 】で字を補った。――以上、シングの「アラン島」全篇をブログ・アクセス360000記念及び、私が一切の社会的拘束から解き放たれて野人となった記念として――そして、私と同じく母を失う聖痕(スティグマ)を受けた友 杉崎知喜君に捧げる――藪野直史――【2011年4月9日】]
第 四 部
此の群島へ二度旅をすれば二度とも變つたことに出遇ふ。今朝、私は五時少し過ぎ、灣の上には星が輝いて空氣の冷い中を汽船で出發した。多くのクラダの漁夫達は港から程遠くない處で夜通し釣に出てゐた。そして彼等は汽船のことを考へずに、恐らく考へることを好まずに、その通る道筋の海峽の中へ網を張つてゐた。出發の直前、運轉手が彼等を警告するために再三、汽笛を鳴らした。鳴らしながら、こんな事を云つた。――
「皆さん、今、灣の中へ出て行くと、素晴らしい祈り聲を聞きますよ。」
少し行くと漁夫の持つてゐる泥炭の火が、波間に見えつ隱れつするのが見え出し、恕つてゐる聲がかすかに聞こえ出した。そのうち大きな漁船の形が闇の中に現はれて來た。甲板に立つてゐる三人の人影が、こちらに向つて、航路を變へてくれと吠えるやうに呶鳴つてゐた。船長は海峽近くに砂洲があるので、脇へそれるのを恐れた。それで機關を止めて網の上をそれを害せぬやうに、靜かに通り過ぎる。船の直ぐ近くを通りながら、船頭達が甲板にゐるのがよく見える。一人は赤い泥炭の鉢を手に持ち、罵る聲ははつきりと聞こえた。それはゲール語の言葉數の多い呪詛から英語で知つてゐる簡單な怨言へ、絶えず變化した。物を云ひながら恕りに身をくねらし、悶えてゐるのが、海の小波の上に次第に明くなり初める光を背景にしてよく見えた。それから直ぐ後も、また幾人かの共に叫ぶ聲が前の方に起り初めたが、薄れ行く星影、曉の靜けさに妙なとり合はせであつた。
その先でも多くの小船に出逢つたが、海峽に網を張つてゐなかつたので、何んとも云はずに通してくれた。それから夜は、寒い時雨と共に明けて行つて、その時雨は、波の谷を面白い透明と明るさで充たす太陽の第一閃の中に金色に變つた。
*
Part IV
NO TWO JOURNEYS to these islands are alike. This morning I sailed with the steamer a little after five o'clock in a cold night air, with the stars shining on the bay. A number of Claddagh fishermen had been out all night fishing not far from the harbour, and without thinking, or perhaps caring to think, of the steamer, they had put out their nets in the channel where she was to pass. Just before we started the mate sounded the steam whistle repeatedly to give them warning, saying as he did so--'If you were out now in the bay, gentlemen, you'd hear some fine prayers being said.'
When we had gone a little way we began to see the light from the turf fires carried by the fishermen flickering on the water, and to hear a faint noise of angry voices. Then the outline of a large fishing-boat came in sight through the darkness, with the forms of three men who stood on the course. The captain feared to turn aside, as there are sandbanks near the channel, so the engines were stopped and we glided over the nets without doing them harm. As we passed close to the boat the crew could be seen plainly on the deck, one of them holding the bucket of red turf, and their abuse could be distinctly heard. It changed continually, from profuse Gaelic maledictions to the simpler curses they know in English. As they spoke they could be seen writhing and twisting themselves with passion against the light which was beginning to turn on the ripple of the sea. Soon afterwards another set of voices began in front of us, breaking out in strange contrast with the dwindling stars and the silence of the dawn.
Further on we passed many boats that let us go by without a word, as their nets were not in the channel. Then day came on rapidly with cold showers that turned golden in the first rays from the sun, filling the troughs of the sea with curious transparencies and light.
[やぶちゃん注:「クラダ」原文“Claddagh”。はゴールウェイ西部海岸地域の呼称。ゲール語“An Cladach”は「石の多い浜」の意。アイルランド最古の漁村の一つであったが、現在はゴールウェイの最高級居住区に変貌してしまった。愛・友情・忠誠のシンボルとされる冠のついたハートを二つの手が握るクラダ・リングはここのクラダの伝統工芸品である(以上はウィキの「クラダ」を参照した)。]
私は村人の興味をつなぐ何か新しい物をと思つて、今年はヴァイオリンを携へて來た。彼等に幾つかの曲を彈いた。併し私のわかる限りでは、現代の音樂はその珍しさのために、熱心には聞くがわからないらしい。愛蘭土の歌「アイリーン・オルーン」[可愛いゝアイリーンの意]のやうな物をより多く喜び、「ブラック・ローグ」――島で知られてゐる――のやうな舞踏曲を彈く時のみ、その調子の意味が彼等にしつくり來るらしい。昨夜、私は島の方方から他の目的で集まつて來た大勢の人達のために演奏した。
六時頃、學校の先生の家へ行く途中で、西の方の道の下にある家の近くで一人の女と一人の男が激しく言ひ合つてゐる聲が聞こえた。それを聞いてゐる間に、幾人かの女が石垣の後からこれも聞きに下りて來た。そして私に語つたが、その爭つてゐた人達は近しい親戚の人で隣同志に住んでゐて、次の日は又もと通りの仲よしになるのだが、些細なことから時時口論するさうである。
聲が餘り激しいので、何か間違ひでも起るかと思つたが、そんな事はないと女達は笑つてゐた。それから一寸中休みとなつたので、遂に終つたやうだと私が云ふと、
「終つたのですつて!」一人の女が云つた。「まだ本當に初まつてないのですよ。まだふざけてゐるだけなのです。」
日沒後で、非常に寒かつた。それで私は家の中にはひり、彼等と別れた。
一時間の後、爺さんが宿から來て、幾人かの少年と「ファル・リーオンタ」(網の男――少年達に網繕ひを教へるアランモアの若い男)が上の家に來てゐて、私が歸つて音樂をすれば踊りたいといふことを告げに彼をよこしたと云つた。
私は直ぐに出かけた。外氣にあたつたと思ふと、喧嘩がまだ西の方で、前より一層激しく行はれてゐるのを聞いた。此のしらせが島中に傳はつて、男女の可愛いい子供連中まで丁度競馬場へ行くやうに、一生懸命に喧嘩の現場の方へ道を驅けて行つた。
私は宿の戸口で一寸立止つて、罵る聲が島の靜けさを通して折重つて起るのに耳傾けた。それから茶の間にはひつて行き、少年達が私の音樂をしきりに待つてゐるので、ヴァイオリンの調子を合はせ初めた。最初立つて彈かうと思つたが、弓を上へ押すと棰木からぶら下つてゐる鹽魚や雨合羽に觸はるので、邪魔にならないやうに、隅のテーブルの上に座を占め、臺を持つてゐなかつたので、音譜を一人の男に支へて貰つた。最初、皆を馴染ますために、また土間と頭の上の藁屋根との間の反響の少い部屋の效果に慣れるために、フランスの曲を彈いた。それから「ブラック・ローダ」を彈き初めた。すると直ぐに、煙突の下の腰掛から背の高い男が躍り出して、獨特な確かさで而かも優しみのある伊達な身振で、茶の間を飛び廻り出した。
革草鞋の輕いために、此の島の踊りは本土では見たこともないほど、輕快でまた敏捷である。また人の純樸なために、歩調に巧まない奔放さを入れることが出來る。これは、人が自意識を持つてゐる處では不可能なことである。
併し速度が激しかつたので、私の練習してない指ではついて行くのに骨が折れ、また演じられてゐる事を見ようと少しの注意をそらす事も出來なかつた。彈き終ると、戸口の處が騷騷しくなつた。喧嘩を見に行つた連中が全部茶の間の中へぞろぞろはひつて來たのである。彼等は壁の周りに列を作り、女達や娘の子は例の如くぎつしりとかたまつて扉の近くに中腰にしやがんだ。
私は今一つの舞踏曲――「バディ起きよ」――を彈き初めた。すると「ファル・リーオンタ」と最初の踊り手が一緒になつて、はひつて來た人たちの前で興奮したやうに、前よりも一層早く且つ優美に、それをやり通した。それから「小さいロージャー」と呼ばれる老人が外にゐると誰云ふともなく云ひ出した。その人は昔島一番の踊り手であつたさうである。
彼は年を取つて踊れないと云つて、長い間はひるのを拒んだが、遂にくどき落されて、中に入り、私の向ひ側に席を占めた。彼を踊らせるにはなかなか時間がかかつたが、踊つた時は大喝采を博した。併し、踊つたのは一寸の間に過ぎなかつた。彼は私の本にあるやうな舞踏曲は知らないと云つた。また知らない音樂に合はせて踊りたくはないと云つた。皆がもう一度と彼を促した時、私の方を向いた。
「ジョン、『ラリー・グロガン』を持つてかるかね? 愉快な曲だがね。」と震へる英語で云つた。
私は持つてゐなかつたので、若い人たちがもう一度、「ブラック・ローグ」に合はせて踊つた。
それから集りは散會した。口論は下の家で、まだやつてゐる。人人はどんなになつたかと、氣をもんでゐた。
十時頃、或る若者が來て、喧嘩は納まつたと知らせた。
「これで四時間やつたんだからね。」彼は云つた。「草臥れてしまつてるよ。草臥れる筈だあね。何しろあのがなり立てる聲を聞くよりは、
踊つたり騷いだりした後なので、私たちは興奮して眠れなかつた。それで長い間、炭火の燃えさしを取圍んで坐りながら、蠟燭の燈の傍で話をしたり、煙草をふかしたりしてゐた。
話は普通の音樂のことから、妖精の音樂のことに移つて行き、私のいくつかの話が終つた後で、次のやうな話を彼等はした。――
或る日、村の向うの端に住んでゐた一人の男が鉄砲を手に入れて、小さな砦の丘近くのしげみの中に兎を探しに出かけた。一匹の兎が木の下に立つてゐるのを見て、それを撃たうと、鐵砲を取り上げたが、丁度狙ひを定めた時、頭の上で音樂のやうな物を聞いたので、空を見上げた。兎はと見返ると影も形も見えなかつた。
その男はその後を追つて行くと、音樂がまた聞こえた。
それで石垣見上げると、一匹の兎がその傍に坐つて、笛のやうなものを口に當てて、二本の指でそれを吹いてゐた。
「どんな兎だつたかね?」話が終ると、お婆さんが聞いた。「どうしたつて、それは本當の兎の筈はないだらう。パット・ディレイン爺さんがいつも云つてたのを憶ひ出すがね。あの人が或る時崖の上に行つたのさ。すると、板石の下の穴の中に、一匹の大きな兎が坐つてゐるのを見たさうだ。連れの男を呼んで、杖の先に鈎を附け、それを穴の中へさし込んだ。するとこんな聲で呼びかけた者があつた。――
『ああ、ファドリック、鈎で私を傷つけるなよ!』
「パットはひどい
『パット、お前の杖に附いてるのは惡魔の角ぢやないかね?』
『何んだかよくは知りませんがね。』パットは言云つた。『これが惡魔の角なら、あんたも生れて生まれてから飮んでるのは惡魔の乳だし、あんたの食つてるのは惡魔の肉だし、あんたのパンに附けるのは惡魔のバターです。何しろ、こんな角は國中のどんな年取つた牝年の頭にもくつ附いてゐますからね。』」
*
This year I have brought my fiddle with me so that I may have something new to keep up the interest of the people. I have played for them several tunes, but as far as I can judge they do not feel modern music, though they listen eagerly from curiosity. Irish airs like 'Eileen Aroon' please them better, but it is only when I play some jig like the 'Black Rogue'--which is known on the island--that they seem to respond to the full meaning of the notes. Last night I played for a large crowd, which had come together for another purpose from all parts of the island.
About six o'clock I was going into the schoolmaster's house, and I heard a fierce wrangle going on between a man and a woman near the cottages to the west, that lie below the road. While I was listening to them several women came down to listen also from behind the wall, and told me that the people who were fighting were near relations who lived side by side and often quarrelled about trifles, though they were as good friends as ever the next day. The voices sounded so enraged that I thought mischief would come of it, but the women laughed at the idea. Then a lull came, and I said that they seemed to have finished at last.
'Finished!' said one of the women; 'sure they haven't rightly begun. It's only playing they are yet.'
It was just after sunset and the evening was bitterly cold, so I went into the house and left them.
An hour later the old man came down from my cottage to say that some of the lads and the 'fear lionta' ('the man of the nets'--a young man from Aranmor who is teaching net-mending to the boys) were up at the house, and had sent him down to tell me they would like to dance, if I would come up and play for them.
I went out at once, and as soon as I came into the air I heard the dispute going on still to the west more violently than ever. The news of it had gone about the island, and little bands of girls and boys were running along the lanes towards the scene of the quarrel as eagerly as if they were going to a racecourse. I stopped for a few minutes at the door of our cottage to listen to the volume of abuse that was rising across the stillness of the island. Then I went into the kitchen and began tuning the fiddle, as the boys were impatient for my music. At first I tried to play standing, but on the upward stroke my bow came in contact with the salt-fish and oil-skins that hung from the rafters, so I settled myself at last on a table in the corner, where I was out of the way, and got one of the people to hold up my music before me, as I had no stand. I played a French melody first, to get myself used to the people and the qualities of the room, which has little resonance between the earth floor and the thatch overhead. Then I struck up the 'Black Rogue,' and in a moment a tall man bounded out from his stool under the chimney and began flying round the kitchen with peculiarly sure and graceful bravado.
The lightness of the pampooties seems to make the dancing on this island lighter and swifter than anything I have seen on the mainland, and the simplicity of the men enables them to throw a naïve extravagance into their steps that is impossible in places where the people are self-conscious.
The speed, however, was so violent that I had some difficulty in keeping up, as my fingers were not in practice, and I could not take off more than a small part of my attention to watch what was going on. When I finished I heard a commotion at the door, and the whole body of people who had gone down to watch the quarrel filed into the kitchen and arranged themselves around the walls, the women and girls, as is usual, forming themselves in one compact mass crouching on their heels near the door.
I struck up another dance--'Paddy get up'--and the 'fear lionta' and the first dancer went through it together, with additional rapidity and grace, as they were excited by the presence of the people who had come in. Then word went round that an old man, known as Little Roger, was outside, and they told me he was once the best dancer on the island.
For a long time he refused to come in, for he said he was too old to dance, but at last he was persuaded, and the people brought him in and gave him a stool opposite me. It was some time longer before he would take his turn, and when he did so, though he was met with great clapping of hands, he only danced for a few moments. He did not know the dances in my book, he said, and did not care to dance to music he was not familiar with. When the people pressed him again he looked across to me.
'John,' he said, in shaking English, 'have you got "Larry Grogan," for it is an agreeable air?'
I had not, so some of the young men danced again to the 'Black Rogue,' and then the party broke up. The altercation was still going on at the cottage below us, and the people were anxious to see what was coming of it.
About ten o'clock a young man came in and told us that the fight was over.
'They have been at it for four hours,' he said, 'and now they're tired.
Indeed it is time they were, for you'd rather be listening to a man killing a pig than to the noise they were letting out of them.'
After the dancing and excitement we were too stirred up to be sleepy, so we sat for a long time round the embers of the turf, talking and smoking by the light of the candle.
From ordinary music we came to talk of the music of the fairies, and they told me this story, when I had told them some stories of my own:--
A man who lives in the other end of the village got his gun one day and went out to look for rabbits in a thicket near the small Dun. He saw a rabbit sitting up under a tree, and he lifted his gun to take aim at it, but just as he had it covered he heard a kind of music over his head, and he looked up into the sky. When he looked back for the rabbit, not a bit of it was to be seen.
He went on after that, and he heard the music again.
Then he looked over a wall, and he saw a rabbit sitting up by the wall with a sort of flute in its mouth, and it playing on it with its two fingers!
'What sort of rabbit was that?' said the old woman when they had finished. 'How could that be a right rabbit? I remember old Pat Dirane used to be telling us he was once out on the cliffs, and he saw a big rabbit sitting down in a hole under a flagstone. He called a man who was with him, and they put a hook on the end of a stick and ran it down into the hole. Then a voice called up to them--
"Ah, Phaddrick, don't hurt me with the hook!"
'Pat was a great rogue,' said the old man. 'Maybe you remember the bits of horns he had like handles on the end of his sticks? Well, one day there was a priest over and he said to Pat--"Is it the devil's horns you have on your sticks, Pat?" "I don't rightly know" said Pat, "but if it is, it's the devil's milk you've been drinking, since you've been able to drink, and the devil's flesh you've been eating and the devil's butter you've been putting on your bread, for I've seen the like of them horns on every old cow through the country." '
[やぶちゃん注:本パートは妖精譚を挟み、有意な行空けが底本及び原文にもあるが、全体が一つのシークエンスとなっているので纏めて採った。
「ヴァイオリン」原文は“fiddle”。以下、ウィキの「フィドル」から引用する。『フィドル(英語 fiddle, ドイツ語 Fiedel)は弓を用いて演奏する擦弦楽器のうち、ヴァイオリンを指す名称である。主にフォークミュージック、民族音楽で使われるヴァイオリンを指す。一方、英語のViolinの俗語でFiddleが使われることがあり、この場合、クラシックで使われるヴァイオリンにも使われる』。『元々イタリアで生まれたとされるヴァイオリンという言葉は、イタリア語から派生した言葉であり、フィドルは英語である』。『ヴァイオリンとフィドルの構造はまったく一緒だが、次の言葉が両者の違いを良く示している。「ヴァイオリンは歌う、しかしフィドルは踊る」「フィドルにビールをこぼしてもだれも泣くものはいない」』。『ソロの演奏が多い。また、二挺のフィドル演奏は多くの北アメリカ、スカンジナビア地方、アイルランド(アイリッシュスタイル)で見られる。フィドルの演奏は、巨大な民族及びフォークミュージックの伝統によって形作られ、各々が特色のある音を持っている』。なお、シングのヴァイオリンを甘く見てはいけない。シングは1888年にトリニティ・カレッジに入学後は主に音楽を学び、1892年に卒業後はプロの音楽家を目指してドイツへ留学しているのである。
「アイリーン・オルーン」“Eileen Aroon”十四世紀に生まれたアイルランド民謡の甘い恋歌であるが、かのバロックの巨匠ヘンデルが絶賛したという。「You tube」などで聴くことが出来る。
「ブラック・ロウグ」“Black Rogue”の“Rogue”は、親しみを込めた「しょうがない奴・悪戯っ子・腕白小僧」、古風に「悪漢・ごろつき・詐欺師」、「浮浪者」、群れを離れた「はぐれもの・はみ出し者」と言った、ある意味、アイルランド人好みのキャラクターを示す語である。それにダメ押しの「黒」であるから、「悪たれ餓鬼んちょ黒っ子」といった感じか。やはり「You tube」などで聴くことが出来る。所謂、典型的な陽性のアイルランド・ジグである。
「バディ起きよ」“Paddy get up”。不詳。私が見つけた「You tube」の“Irish Arsenal Song 'By Jesus said Paddy'”とは別物か。これは軍歌らしく、バーで酔った男連中が只管、シャウトしているばかりで、踊りを合わせられそうなものではない。
「ラリー・グロガン」“Larry Grogan”。不詳。人名である。参考までに、後に、アイルランド共和国軍(IRA)に属し、アイルランド共和党の活動家となった政治家にラリー・グローガン(Labhras Gruagain 1899年~1979年)なる人物がいる。
「ファドリック」原文は“Phaddrick”。これは通称「パット」爺さんの本名である。アイルランドの聖人パトリキウスにちなんでアイルランド人に多い男性名であるが、通常は “Patrick”「パトリック」で、ゲール語でも“Pádraig”と綴る。この“Phaddrick”は極めて特異で、これで検索をかけると正にシングの「アラン島」のこの台詞がごっそり検索にかかってしまう。]
今日、天氣は荒模樣であつたが、午後の初めのうちは、コニマラから泥炭を積んで來る漁船は充分はひつて來られる位に、海は靜かであつた。尤もそれが波止場に泊つてゐる間は、うねりが大きいので、人は海の上を見乘りしてゐて、大きなのが來る度に、船が波に樂に乘やうに錨索を弛めなければならなかつたが。
船の中には、二人の男がゐるばかりだつた。
直ぐ後で激しい夕立が來たので、私は泥炭の積み重ねの下へ幾人かの人達と一緒にもぐり込んだ。此の人達は馬を積んでやつて來る他の漁船を待つて立つてゐた。彼等は昨晩の喧嘩のこと、その騷騷しかつたことを語り出して笑つた。
「くだらないことから一番ひどい喧嘩がおつ始まつたんだ。」隣りにゐた老人が云つた。「ムルティーンか誰かが六十年前、濱でナイフで殺し合つた喧嘩の話をあんたにしたことはなかつたかね?」
「聞かなかつたね。」 私は云つた。
「さて、」彼は云つた。「皆んなが海草刈に出かけようとしてゐた。或る男が出かける前に、ナイフを砥石で研いでゐた。一人の子供が茶の間にはひつて來て、その男に云つた。――
『何んのためにナイフを研いでゐるの?』
『お前のお父さんを殺ためだ。』その男は云つた。彼等はいつも仲のよい友達だつた。子供は家に歸つて、父親にナイフを砥いで殺さうとしてゐる男があると云つた。
『畜生!』父親は云つた。『彼奴がナイフを持つて行くなら、俺も持つて行くぞ。』
それから彼はナイフを研ぎ、皆んなは濱へ下りて行つた。それから二人は互ひにナイフのこと
翌日葬ひをして、みんなが歸つて來ると、みんなの目についたのは、事を起した子供が相手の男の子供と仲よく遊んでゐるところであつた。二人の父親はどちらも墓場の中に埋められてゐるのに。」
彼が語り止めると、一陣の風が來て、近くの乾いた海草の束を私たちの頭上高く、吹き上げた。
今一人の老人が語り出した。
「大風の吹いたことがあつた。」彼は云つた。「忘れもしない、南島に、石垣の角に向つた圍ひの中に羊毛を澤山持つてゐた男があつた。その男が丁度羊毛を洗つたり、乾したり、裏返したり、
『惑魔にでもあたまを治して貰へ!』彼は云つた。『その風にはお前はかなはねえぞ。』
『よし惡魔がゐるなら、』相手の男は云つた。『おれが捕へてやる。』
さう云つたためかどうかは知らないが、それから全部の羊毛が彼の頭の上を越して、島中到る所に吹き飛んだが、後でかみさんがやつて來て紡がうとすると、その量には少しも損はなかつたかのやうに、要るだけのものがすつかりあつた。」
「それには、もつと話があるのだ。」今一人の男が口を出した。「と云ふのは、その前の晩、或る女が此の島の西のはづれで、えらい光景を見た。それは此の島と南島で少し以前に死んだ人が全部ゐて、互ひに話し合つてゐるのを見たのだ。その晩は隣島から一人の男が來てゐて、その男はさつきの女が見た物について話すの聞いてゐた。翌日その男は南島へ歸つたが、恐らくカラハの中は一人きりだつたのだらう。隣島の近くへ來ると、崖で釣をしてゐる人を見かけた。その人が彼に呼びかけた。――
『早く急いで行つて、おツ母の密釀酒を匿せと云へよ。』――母親は密釀酒を賣るのが商賣だつた――『丁度今、此の島ではこれまで見たこともないほど大勢の巡査と郷士の人が、岩の上を通つて行くのを見たんだ』。丁度その時が、上の方で、さつきの男が丘の下の羊毛を持つて行かれた時だつたが、巡査などは一人も島にはゐなかつた。」
それから少したつと、老人連は行つてしまつて、幾人かの二十代の靑年たちが私と一緒に殘つた。此の人達は私にいろいろな事を話した。一人は、私が嘗つて醉拂つた事があるかと聞いたり、また或る者は此の島から嫁を貰ふべきだと云つたりした。島には美人がゐて、よく肥つた娘なら、丈夫で、澤山の子を産み、金を浪費しないと云つた。
馬船が岸に着くと、蟹の罠籠について遠くにゐた一艘のカラハが、大急ぎではひつて來た。それから一人の男が船から降りて砂丘を登つて行つて、一人の娘の子と逢つた。娘の子は晴着の一束を持つて來のであつた。男は砂の上で、それに着替へ、漁船の方へ出かけ、馬を返しにコニマラの方へ向つて出立した。
*
The weather has been rough, but early this afternoon the sea was calm enough for a hooker to come in with turf from Connemara, though while she was at the pier the roll was so great that the men had to keep a watch on the waves and loosen the cable whenever a large one was coming in, so that she might ease up with the water.
There were only two men on board, and when she was empty they had some trouble in dragging in the cables, hoisting the sails, and getting out of the harbour before they could be blown on the rocks.
A heavy shower came on soon afterwards, and I lay down under a stack of turf with some people who were standing about, to wait for another hooker that was coming in with horses. They began talking and laughing about the dispute last night and the noise made at it.
'The worst fights do be made here over nothing,' said an old man next me. 'Did Mourteen or any of them on the big island ever tell you of the fight they had there threescore years ago when they were killing each other with knives out on the strand?'
'They never told me,' I said.
'Well,' said he, 'they were going down to cut weed, and a man was sharpening his knife on a stone before he went. A young boy came into the kitchen, and he said to the man--"What are you sharpening that knife for?"
"To kill your father with," said the man, and they the best of friends all the time. The young boy went back to his house and told his father there was a man sharpening a knife to kill him.
"Bedad," said the father, "if he has a knife I'll have one, too."
'He sharpened his knife after that, and they went down to the strand. Then the two men began making fun about their knives, and from that they began raising their voices, and it wasn't long before there were ten men fighting with their knives, and they never stopped till there were five of them dead.
'They buried them the day after, and when they were coming home, what did they see but the boy who began the work playing about with the son of the other man, and their two fathers down in their graves.'
When he stopped, a gust of wind came and blew up a bundle of dry seaweed that was near us, right over our heads.
Another old man began to talk.
'That was a great wind,' he said. 'I remember one time there was a man in the south island who had a lot of wool up in shelter against the corner of a wall. He was after washing it, and drying it, and turning it, and he had it all nice and clean the way they could card it. Then a wind came down and the wool began blowing all over the wall. The man was throwing out his arms on it and trying to stop it, and another man saw him.
"The devil mend your head!" says he, "the like of that wind is too strong for you."
"If the devil himself is in it," said the other man, "I'll hold on to it while I can."
'Then whether it was because of the word or not I don't know, but the whole of the wool went up over his head and blew all over the island, yet, when his wife came to spin afterwards she had all they expected, as if that lot was not lost on them at all.'
'There was more than that in it,' said another man, 'for the night before a woman had a great sight out to the west in this island, and saw all the people that were dead a while back in this island and the south island, and they all talking with each other. There was a man over from the other island that night, and he heard the woman talking of what she had seen. The next day he went back to the south island, and I think he was alone in the curagh. As soon as he came near the other island he saw a man fishing from the cliffs, and this man called out to him--"Make haste now and go up and tell your mother to hide the poteen"--his mother used to sell poteen--"for I'm after seeing the biggest party of peelers and yeomanry passing by on the rocks was ever seen on the island." It was at that time the wool was taken with the other man above, under the hill, and no peelers in the island at all.'
A little after that the old men went away, and I was left with some young men between twenty and thirty, who talked to me of different things. One of them asked me if ever I was drunk, and another told me I would be right to marry a girl out of this island, for they were nice women in it, fine fat girls, who would be strong, and have plenty of children, and not be wasting my money on me.
When the horses were coming ashore a curagh that was far out after lobster-pots came hurrying in, and a man out of her ran up the sandhills to meet a little girl who was coming down with a bundle of Sunday clothes. He changed them on the sand and then went out to the hooker, and went off to Connemara to bring back his horses.
[やぶちゃん注:原文では、行空けなしで次の段落と繋がっているが、底本に準ずる。
「船の中には、二人の男がゐるばかりだつた。
「郷士」原文“yeomanry”。イギリスでは古くから市民が“militia”(ミリシア:民兵。)を組織することが公的に認められていたが、特に“Yeoman”(ヨーマン:イングランドの富農層である独立自営農民。)は“yeomanry”「ヨーマンリー」と称される義勇騎兵部隊を組織して国家の軍事活動に協力していた。1854年のクリミア戦争勃発によって、イギリス陸軍は常備軍の深刻な兵力不足に見舞われ、その後のフランスとの対立やイタリア統一戦争などの軍事的需要が高まり、大規模な予備軍組織の要請が高まり、1859年、陸軍省管轄下の義勇軍“Volunteer
Force”が創設された。参照したウィキの「国防義勇軍」によれば、『州知事の認可により部隊が設立され、平時には市民生活のかたわら一定の訓練を行い、有事には自弁で武装して動員されて常備軍同様の給与と軍法の適用を受けるものとされた。当初は小規模な部隊が乱立したが、次第に効率的な大隊規模に統一され、1862年には歩兵220個大隊など兵力16万人を数えた。実戦出動の経験もあり、1899年に起きた第二次ボーア戦争がその最後の事例となった』とある。従って、ここは時代背景から国防義勇騎兵隊の一団と訳すべきところか。――そんなことよりも――この話柄の前段から、私には「大勢の巡査と郷士の」一団が、あたかも「ヨハネの黙示録」の邪悪にして亡ぼされる(だってアランの貧農の正義の羊毛も、アランの母さんの密造酒も守られるんだからね)地獄の悪魔の軍団のように見えてくる面白さではないかと思うのであるが、如何?
「蟹の罠籠」原文は“lobster-pots”。これはよろしくない。何故なら、ロブスターは「蟹」ではないからである。敢えて言うならエビそれもザリガニの仲間である。甲殻亜門軟甲綱真軟甲亜綱ホンエビ上目十脚(エビ)目抱卵(エビ)亜目ザリガニ下目アカザエビ科アカザエビ亜科ロブスター属
Homarus で、本種は分布域からヨーロピアン・ロブスター Homarus gammarus と考えてよい。
「馬船が岸に着くと、蟹の罠籠について遠くにゐた一艘のカラハが、大急ぎではひつて來た。それから一人の男が船から降りて砂丘を登つて行つて、一人の娘の子と逢つた。娘の子は晴着の一束を持つて來たのであつた。男は砂の上で、それに着替へ、漁船の方へ出かけ、馬を返しにコニマラの方へ向つて出立した。」という最終段落“When the horses were coming ashore a curagh that was far out after lobster-pots came hurrying in, and a man out of her ran up the sandhills to meet a little girl who was coming down with a bundle of Sunday clothes. He changed them on the sand and then went out to the hooker, and went off to Connemara to bring back his horses.”は、失礼ながら姉崎氏自身分かって訳されているようには思われないのである(但し、私も一部よく分からないのであるが)。まず、馬を積んだ船がやっと入港した丁度その時、“hurrying in”(波止場に大急ぎで)帰ってくるカラハがあったが、それはロブスター獲りのための籠を仕掛けに朝早くに出た漁師のカラハであった。何故、「大急ぎ」なのか? 自分の娘が用意して持ってきた“Sunday clothes”(日曜のミサ用の晴れ着)に着替えるためであり、この「馬を積んだ船」に乗ってコネマラへ向かうためである。何のための「晴れ着」か?――そこが今一つ、分からないのであるが――彼はその馬を積んで入港した船に乗り、どうも“his horses”彼の馬(この一回目の便ではもたらされていない馬。それも複数である)を、コネマラまで直接引き取りに行く“bring back”(連れて戻る)ために――その際に元の馬主と逢うための晴れ着か、それとももっと純粋に新しい栄えある名馬を受け取る晴れの日のためにか、分からないのであるが――正装をしているようなのである。複数の馬を正装で引き取りに行くこの漁師は、島でも相当な金持ちなのか? 英語の苦手な私にはその程度までしか推理出来ない。識者の御教授を乞うものである。]
私が何度も話したことのある若い既婚の女が熱病で死にかけてゐる――チブスださうである。
――それでその夫と兄弟たちは海が荒れてゐるにもかかはらず、北島から醫者と坊さんを呼びに、カラハで出かけた。
此の人達の出立した後、私は砦の丘から長い間、眺めてゐた。風と雨は瀨戸の中へ押し寄せ、波の中をしぶきを立てて苦鬪してゐるその小さな黑いカラハのほかには、舟影も人影も見えなかつた。風が少し收まると私の足下の東の方で人が槌を打つてゐる音が聞こえた。二三週間前、溺死した靑年の死體が今朝岸邊に着き、その友達が、死んだ男の家の庭で、一日中棺を造るのに忙しいのであつた。
少したつと、カラハは霧の中に姿を消した。寒さと慘めさに身ぶるひしながら、私は宿に歸つて來た。
お婆さんは火の傍で、泣唱をしてゐた。
「私は若者の居た家まで待つて來た。」彼女は云つた。「其處から出て來る匂ひのため、私は中へはひれなかつた。頭は全くないさうだが、海に三週間もひたつて居れば、それは無理もない事だね。此の島の者は誰も彼も、こんな危い目や悲しい目に逢はねばならないのかね?」
私は、カラハは坊さんを乘せて直ぐ戻つて來るだらうかと尋ねた。
「直ぐ戻つて來なけりや、今夜は戻つて來ないでせう。」彼女は云つた。「今、風が出た。恐らく此の二三日は此の島へカラハは來ないでせう。氣が
それから、私は、女はどうしたかと尋ねた。
「あの女は、もう大方駄目だらう。」お婆さんは云つた。「明日の朝までは持つまい。棺を造る板がないので、此の下にゐる男が、まだ生きてゐるその母親の葬式のために、此の二年間持つてゐる板を借りたいと云つてゐる。熱を出してゐる女がもう二人と、三つにもならない子供が一人ゐるさうだ。神樣何卒、私達をお惠み下さい!」
私はまた海を眺めに出かけた。併し日はとつぷりと暮れて、疾風は砦の丘の上に吠えてゐた。
私は道を下りて行き、靑年の死んだ家で、泣唱の聲を聞いた。もつと行つて最近チブスにやられた家の戸口の騷騷しいのを見た。それから雨を冒して宿に歸つて來て、お婆さんやかみさんと一緒に爐を圍んで、夜の更けるまで島人の不幸を話し合つた。
*
A young married woman I used often to talk with is dying of a fever--typhus I am told--and her husband and brothers have gone off in a curagh to get the doctor and the priest from the north island, though the sea is rough.
I watched them from the Dun for a long time after they had started. Wind and rain were driving through the sound, and I could see no boats or people anywhere except this one black curagh splashing and struggling through the waves. When the wind fell a little I could hear people hammering below me to the east. The body of a young man who was drowned a few weeks ago came ashore this morning, and his friends have been busy all day making a coffin in the yard of the house where he lived.
After a while the curagh went out of sight into the mist, and I came down to the cottage shuddering with cold and misery.
The old woman was keening by the fire.
'I have been to the house where the young man is,' she said, 'but I couldn't go to the door with the air was coming out of it. They say his head isn't on him at all, and indeed it isn't any wonder and he three weeks in the sea. Isn't it great danger and sorrow is over every one on this island?"
I asked her if the curagh would soon be coming back with the priest. 'It will not be coming soon or at all to-night,' she said. 'The wind has gone up now, and there will come no curagh to this island for maybe two days or three. And wasn't it a cruel thing to see the haste was on them, and they in danger all the time to be drowned themselves?'
Then I asked her how the woman was doing.
'She's nearly lost,' said the old woman; 'she won't be alive at all tomorrow morning. They have no boards to make her a coffin, and they'll want to borrow the boards that a man below has had this two years to bury his mother, and she alive still. I heard them saying there are two more women with the fever, and a child that's not three. The Lord have mercy on us all!'
I went out again to look over the sea, but night had fallen and the hurricane was howling over the Dun. I walked down the lane and heard the keening in the house where the young man was. Further on I could see a stir about the door of the cottage that had been last struck by typhus. Then I turned back again in the teeth of the rain, and sat over the fire with the old man and woman talking of the sorrows of the people till it was late in the night.
[やぶちゃん注:本章は「アラン島」の中でも、モノクロームの、深く昏い、文字通り「死」の臭いのする箇所である。棺作りの釘を打つ音が虚空に響いて一読、忘れ難い。
「チブス」原文は“fever--typhus”。“Typhus”(窒扶斯・チブス・チフス)は高熱や発疹を伴う細菌感染症の一群を言い、異なった以下の三種を総称する。①サルモネラ菌の一種チフス菌“Salmonella
enterica serovar Typhi”に経口感染することによって発症する「腸チフス」。腹胸部のバラ疹が特徴。通常の英語表記“typhoid
fever”。抗菌薬がなかった当時の致死率は、主に調出血や腸穿孔による10~20%。②サルモネラ菌の一種パラチフスA菌 “Salmonella
enterica serovar Paratyphi A”に経口感染することによって発症する「パラチフス」。致死率は腸チフスに比して低く5%程度。通常の英語表記“paratyphoid
fever”。③主にコロモジラミやアタマジラミが媒介する発疹チフス・リケッチア“Rickettsia prowazekii”に感染することによって発症する「発疹チフス」。体幹部の丘疹から広がる全身性発疹が特徴。致死率は10~60%(10歳未満の小児では死亡は稀であるが、加齢により上昇、50歳以上の高齢者では治療不全の場合は60%を越える)。通常の英語表記“typhus”。この場合のアランの「チブス」は致死率が高いから、①か③の何れかであるが、古くは③の「発疹チフス」が“typhus”であった。原文の“fever--typhus”は①の腸チフスの英語名“typhoid
fever”に最も似るが、英文の風土病記事などを検索すると、③の発疹チフスを“Endemic Typhus Fever”と記している記事を見かけるので同定し得ない。但し、私には③のベクター感染では①よりも高く、深刻な島内でのパンデミックが予想されるように思われるので、一応、腸チフスでとっておく。因みに、1898年を一回目とする、この四度目のシングのアラン帰還は1901年9月21日から10月19日(栩木伸明氏訳2005年みすず書房刊の「アラン島」の「訳者あとがき」による)であるが、漱石の「こゝろ」の「先生」の両親は腸チフスのために相次いで亡くなっている。私の推定するその没年は明治28(1895)年頃である(私の『「こゝろ」マニアックス』の『●「先生」の時系列の推定年表』を参照のこと)。]
今夜、爺さんは昔本土で聞いた話をしてくれた。――
或る若い女が居て、一人の子供を持つてゐた。間もなく、その女は死んだので、翌日それを葬つた。その晩、もう一人の女――家のおかみさん――がその子供を膝に載せ、爐の傍に腰掛け、コップから牛乳を飮ませてゐた。すると葬つたばかりの女が戸を開けて、家にはひつて來た。彼女は爐の方へ行き、椅子を取りお内儀きんの前に腰掛けた。それから手を差出して、子供を膝の上に取り乳を與へた。暫くして子供を搖籠の中に置き、料理臺の所へ行つて、牛乳や馬鈴薯を取つて食べ、そして出て行つてしまつた。お内儀さんは驚いて、その事を夫の歸つて來た時告げ、また二人の若者に告げた。皆んな明日の晩は家に居て、彼女が來たら、捉へようと云つた。彼女は翌日の晩も來て、子供に乳房を與へ、料理臺の方へ行かうと立ち上つた所を、主人が捉へたが主人は床に倒れてしまつた。すると二人の若者がそれを捉へて、放さないやうにした。そこで、彼女の物語つた所に依れば、妖精に連れられて行き、その晩は、妖精と共に食物を食べてゐなかつたが、子供の處へ歸られるやうに妖精達は彼女を放した。そして妖精の全部はイーヘ・ホウナ[十一月一日に行はれる愛蘭土の祭で、その宵祭の意、此夜は一年中で幽靈や魔女の最も多く出歩くものと信ぜられる]に、國のその地方を立ち去るだらうこと、その四五百人が馬に騎つて行くであらうこと、彼女自身は或る若者の後に白馬に騎つてゐることを話した。そして彼女はその晩、妖精達が橋を渡るから、その橋まで來て、その袂で待つてゐてくれと賴んだ。さうすれば自分の通る時、自分と若者に何か投げられるやうに、馬をゆるめるであらう。そして自分達が地面に落ちれば、助かるだらうと語つた。
かう云つて、彼女は行つてしまつた。男達はイーヘ・ホウナに行つて、彼女を取り戻した。
彼女はその後、四の子を産み、遂に死んだ。初め葬つたの最女ではなく、妖精が彼女の代りに何か古い着物でもおいたのであらう。
「そんな事は信ぜられないと云ふ人がある。」お婆さんは云つた。「だが不思議といふものはあるもので、そんな人達には、云ひたいやうに云はせておくさ。此の間のことだが、下の村で、或る女がその子供と寢床にはひつた。暫く眠らないでゐると、何者か窓の所へ來て、聲を聞いたやうであつた。その聲はかう云つた。――
『これから、眠り通す時が來た。』
子供の死んでゐたのは、その朝だつた。島でこんな風な死に方をする人は多いのです。」
*
This evening the old man told me a story he had heard long ago on the mainland:--
There was a young woman, he said, and she had a child. In a little time the woman died and they buried her the day after. That night another woman--a woman of the family--was sitting by the fire with the child on her lap, giving milk to it out of a cup. Then the woman they were after burying opened the door, and came into the house. She went over to the fire, and she took a stool and sat down before the other woman. Then she put out her hand and took the child on her lap, and gave it her breast. After that she put the child in the cradle and went over to the dresser and took milk and potatoes off it, and ate them. Then she went out. The other woman was frightened, and she told the man of the house when he came back, and two young men. They said they would be there the next night, and if she came back they would catch hold of her. She came the next night and gave the child her breast, and when she got up to go to the dresser, the man of the house caught hold of her, but he fell down on the floor. Then the two young men caught hold of her and they held her. She told them she was away with the fairies, and they could not keep her that night, though she was eating no food with the fairies, the way she might be able to come back to her child. Then she told them they would all be leaving that part of the country on the Oidhche Shamhna, and that there would be four or five hundred of them riding on horses, and herself would be on a grey horse, riding behind a young man. And she told them to go down to a bridge they would be crossing that night, and to wait at the head of it, and when she would be coming up she would slow the horse and they would be able to throw something on her and on the young man, and they would fall over on the ground and be saved.
She went away then, and on the Oidhche Shamhna the men went down and got her back. She had four children after that, and in the end she died.
It was not herself they buried at all the first time, but some old thing the fairies put in her place.
'There are people who say they don't believe in these things,' said the old woman, 'but there are strange things, let them say what they will. There was a woman went to bed at the lower village a while ago, and her child along with her. For a time they did not sleep, and then something came to the window, and they heard a voice and this is what it said--
"It is time to sleep from this out."
'In the morning the child was dead, and indeed it is many get their death that way on the island.'
[やぶちゃん注:一連の話であるので纏めて採った。
ここに語られる話は蘇生譚として、細部がよく描かれている興味深い民俗伝承である。冒頭部分で思い出すのは本邦の妊娠中若しくは出産時に死んでしまった女性が妖怪化した
「爺さん」は、この時の(恐らくは第三部までと同じ定宿の)民家の主人である。
「そこで、彼女の物語つた所に依れば、妖精に連れられて行き、その晩は、妖精と共に食物を食べてゐなかつたが、子供の處へ歸られるやうに妖精達は彼女を放した。」原文は“She told them she was away with the fairies, and they could not keep her that night, though she was eating no food with the fairies, the way she might be able to come back to her child.”で、文脈に捩じれがあるように思われる。これは素直に順に訳せばよいのではなかろうか。
「そこで、彼女の物語つた所に依れば、」彼女は死んだのではなく、「妖精に連れられて行」ったのだということを語り、その晩」も彼女は、長くここには居られないのだと言い、しかし未だに「妖精と共に」彼らの「食物を食べて」は「ゐな」いから、こうしてこの現世、「子供の處へ歸」ってこられるのだ、と語った。
という意味であろう。中間部の「妖精と共に食物を食べてゐなかつた」というところが「古事記」のイサナキの黄泉国訪問で妻イサナキが「黄泉戸喫」の話をする(異界の食物を口にすることで世界が遮断・変異する)シーンを想起させて興味深い。
「イーヘ・ホウナ[十一月一日に行はれる愛蘭土の祭で、その宵祭の意、此夜は一年中で幽靈や魔女の最も多く出歩くものと信ぜられる]」“Oidhche
Shamhna”は「10月31日の晩という日附でお分かり頂けると思うが、所謂、“Halloween, Hallowe'en”(ハロウィン)のことである。“Oidhche”が「夜」、“Shamhna”が「ハロウィン」の意。以下、ウィキの「ハロウィン」から引用しておく。本来は『ケルト人の行う収穫感謝祭が、他民族の間にも行事として浸透していったものとされて』おり、ヨーロッパを起源とする民族行事で、毎年に行われる。いる。『ケルト人は、自然崇拝からケルト系キリスト教を経てカトリックへと改宗していった』が、『カトリックでは11月1日を諸聖人の日(万聖節)としているが、この行事はその前晩にあたることから、後に諸聖人の日の旧称"All
Hallows"のeve(前夜祭)、Hallowseveが訛って、Halloweenと呼ばれるようになった。そもそもキリスト教の教えと、魑魅魍魎が跋扈するハロウィンの世界は相容れるものではなく、聖と俗との習合がハロウィンという名称のみに痕跡を残している』。なお、ネット上のネイティヴの発音を聴くと「イーハ・ハウナ」と聴こえる。
「白馬」原文は“a grey horse”であるが、これは所謂「葦毛」の馬で、元は灰色でも年をとるに連れて見た目は白と変わらなくなるので訳としては問題ない。
「そして彼女はその晩、妖精達が橋を渡るから、その橋まで來て、その袂で待つてゐてくれと賴んだ。さうすれば自分の通る時、自分と若者に何か投げられるやうに、馬をゆるめるであらう。そして自分達が地面に落ちれば、助かるだらうと語つた。」まずは異界との境界である(従って異界からの帰還のルートともなる)端としての「橋」、霊界との通路である水に関わる「橋」が特異点として描出される。更に「何か投げられる」ことによって妖精世界からの帰還に可能であるという謂いが、例えばイサナキの呪的逃走の成功と近似する。ここで投げられたものが何であったかが語られていないのが如何にも惜しい。しかもこの「自分達が地面に落ちれば、助かるだらう」という部分にも何かが隠されているようだ。女の帰還には「若者」が一緒に地面に落ちる必要があるからである。面白い。実に面白い。]
若者は葬られた。その葬式は、私がかつて見たうちで最も奇妙な光景であつた。朝早くから、その家へ行く人達を見かけた。併し私が老人と一緒に午後の最中に行つた時もまだ戸口の前には棺が置いてあつて、家族の男や女の人がその周りに立ち、人の大勢ゐる中で棺をたたいたり、その上にもたれて泣唱を歌つたりしてゐた。それから少したつて、皆は跪いて、最後の所感を云つた。それから死者の從兄弟達が――家族の者は何も手につかないほど悲しみにしをれてゐたから――二本の櫂、幾本かの繩を用意して、棺をくくりつけ、行列は初まつた。お婆さん等は棺の直ぐ後に隨いて行き、私は偶然にも、その丁度後、第一番目の男達の中にゐることになつた。墓場へ行く道は惡く、東の方へ向つて坂になつてゐる。女達の群は私の前を下りて行く。その赤い着物を着、赤いぺティコートを被る、丁度後から見えるが、その頭に腰帶を卷いてゐる樣は、不思議な效果を出してゐた。それにまた白い棺や一樣な色彩は全く僧院のやうな落着きを加へるのであつた。
前に述べたことのある葬式の時には、何處にも早い羊齒が生えてゐたが、今度は、それに代つて墓場には、枯草や枯蕨が一面に生えてゐた。また今度は、八十の老人ではなく、成人したばかりの若者を葬りに來たのであるから、人人の悲しみはその性質が違つてゐた。從つて、泣唱は一部分、形式的の性質を失ひ、若者の家族の思ひ思ひの激しい悲しみを表はして歌はれた。
棺がこれから、掘られようとする墓の近くに置かれると、岩の中の茨ら二つの長い枝が切られ、岩の上に棺の長さと幅が印された。それから男達は仕事を初め、石や土の薄い層を除いたり、新しい棺を下ろす場所にある古い棺を壞はしたりした。澤山の黑くなつた板や骨のかけらが土と共に堀り出されると、一つの頭蓋骨が上がり、墓石の上に置かれた。すると直ぐに、死者の母親であるお婆さんがそれを取り上げて、一人で持つて行つた。彼女は坐つてそれを――彼女の本當の母親の頭蓋骨であつた――膝の上に置き、激しい悲しみで泣唱と號泣を初めた。
腐つた土の山が墓の近くに段々と高くなると、それから嫌な嗅ひが立ち初めたので、男たちは何度も二つの茨の棒で穴の大きさを計りながら仕事を急いだ。穴が充分に深くなると、お婆さんは立ち上つて、棺へ戻つて來て、頭蓋骨を左手に持ち、茨の棒で棺をたたき初めた。此の最後の悲しみの一時は最も慘めなものであつた。若い女たちは悲しみのため、憔悴して石の間に伏すやうにしてゐた。それでも、時時つと立ち上つて、立派な態度で棺の板をたたいてゐた。若い男たちも憔悴して、泣唱の悲しさのために絶えず聲を嗄らしてゐた。
用意が萬端出來上ると、白布は棺から取り除かれ、その場所へ下ろされた。すると一人の爺さんが、聖水のはひつてゐる木の器と蕨の一束を取り上げた。皆の頭の上に水を振りかける間、人人は周りに群つてゐた。彼等はしきりに成るべく多くを貰はうと思つてゐるらしく、婆さんは幾度も滑稽な聲で叫んでゐた。――
「タラム・プレイォン・エレ・オー・ムールティーン」(ムールティーン、私にもう一滴ください)。
墓が半分ほど、埋まると、私は寄波近くに海豹が二匹追ひかけ合つてゐるのを眺めながら、北の方へぶらぶら出かけた。明るさの薄れかかる頃、「砂の岬」へ着くと、よく知つてゐる幾人かの男が、地引網のやうなもので魚を捕へてゐるのに出逢つた。それは仲仲手間取る仕事であつた。長い間、私は砂の上に坐つて、網が張られてはまた八人の男が一緒にかけ聲を合はせて、そろそろ手繰るのを見てゐた。
彼等は私に話しかけた。私が腹がすいてゐると思つたらしく、少しの密釀酒とパンをくれた。さうやつてゐるうちも、死の宣告を受けてゐる人と語つてゐるやうな氣がして仕方がなかつた。此の人達も數年たてば、海に溺れて裸かのまま岩に打ち上げられるか、または自分の家で死ぬかであらう。そして今、私が墓地へ行つて見て來たばかりの恐ろしい光景で葬られるのであらう。
*
The young man has been buried, and his funeral was one of the strangest scenes I have met with. People could be seen going down to his house from early in the day, yet when I went there with the old man about the middle of the afternoon, the coffin was still lying in front of the door, with the men and women of the family standing round beating it, and keening over it, in a great crowd of people. A little later every one knelt down and a last prayer was said. Then the cousins of the dead man got ready two oars and some pieces of rope--the men of his own family seemed too broken with grief to know what they were doing--the coffin was tied up, and the procession began. The old woman walked close behind the coffin, and I happened to take a place just after them, among the first of the men. The rough lane to the graveyard slopes away towards the east, and the crowd of women going down before me in their red dresses, cloaked with red pethcoats, with the waistband that is held round the head just seen from behind, had a strange effect, to which the white coffin and the unity of colour gave a nearly cloistral quietness.
This time the graveyard was filled with withered grass and bracken instead of the early ferns that were to be seen everywhere at the other funeral I have spoken of, and the grief of the people was of a different kind, as they had come to bury a young man who had died in his first manhood, instead of an old woman of eighty. For this reason the keen lost a part of its formal nature, and was recited as the expression of intense personal grief by the young men and women of the man's own family.
When the coffin had been laid down, near the grave that was to be opened, two long switches were cut out from the brambles among the rocks, and the length and breadth of the coffin were marked on them. Then the men began their work, clearing off stones and thin layers of earth, and breaking up an old coffin that was in the place into which the new one had to be lowered. When a number of blackened boards and pieces of bone had been thrown up with the clay, a skull was lifted out, and placed upon a gravestone. Immediately the old woman, the mother of the dead man, took it up in her hands, and carried it away by herself. Then she sat down and put it in her lap--it was the skull of her own mother--and began keening and shrieking over it with the wildest lamentation.
As the pile of mouldering clay got higher beside the grave a heavy smell began to rise from it, and the men hurried with their work, measuring the hole repeatedly with the two rods of bramble. When it was nearly deep enough the old woman got up and came back to the coffin, and began to beat on it, holding the skull in her left hand. This last moment of grief was the most terrible of all. The young women were nearly lying among the stones, worn out with their passion of grief, yet raising themselves every few moments to beat with magnificent gestures on the boards of the coffin. The young men were worn out also, and their voices cracked continually in the wail of the keen.
When everything was ready the sheet was unpinned from the coffin, and it was lowered into its place. Then an old man took a wooden vessel with holy water in it, and a wisp of bracken, and the people crowded round him while he splashed the water over them. They seemed eager to get as much of it as possible, more than one old woman crying out with a humorous voice--
'Tabhair dham braon eile, a Mhourteen.' ('Give me another drop, Martin.')
When the grave was half filled in, I wandered round towards the north watching two seals that were chasing each other near the surf. I reached the Sandy Head as the light began to fail, and found some of the men I knew best fishing there with a sort of dragnet. It is a tedious process, and I sat for a long time on the sand watching the net being put out, and then drawn in again by eight men working together with a slow rhythmical movement.
As they talked to me and gave me a little poteen and a little bread when they thought I was hungry, I could not help feeling that I was talking with men who were under a judgment of death. I knew that every one of them would be drowned in the sea in a few years and battered naked on the rocks, or would die in his own cottage and be buried with another fearful scene in the graveyard I had come from.
[やぶちゃん注:若いシングは深い悲哀の感染から激しく感傷的になりながらも、野辺の送りから墓掘り、先祖の遺骨の扱いから埋葬と聖水散布に至るまで、非常に緻密にその葬送儀礼を描出して美事である。これは実に稀有のアランに於ける葬送の一部始終のドキュメントなのである。ラストのアザラシの描写から、墓地を下った海辺の地引網のロケーションもコーダとして絶妙である。
「前に述べたことのある葬式の時」とは「第一部」のちょうど中盤に描かれた老婆の葬儀であるから、1898年の五月下旬か六月上旬のことであった。今回は1901年の九月下旬か十月頭の情景である。
「前に述べたことのある葬式の時には、何處にも早い羊齒が生えてゐたが、今度は、それに代つて墓場には、枯草や枯蕨が一面に生えてゐた。」原文は“This time the graveyard was filled with withered grass and bracken instead of the early ferns that were to be seen everywhere at the other funeral I have spoken of,”。ちょっと気になるのは「枯蕨」の部分で、これは“early ferns”、第一部の当該部の描写の“bordered with a pale fringe of early bracken”「早蕨の青く緣取つた平らな墓石」と、まだ葉の開いていない新芽だったものが、今は季節も季節、すっかり開いて濃い青緑のシダとなっていることを言っていよう。「枯蕨」ではない(寒冷なアランとは言え、ワラビが枯れるには少し時期が早いと私には思われる)。栩木氏も『枯れ草と丈高いシダの茂み』と訳されておられる。ここはシングが先の大往生の老婆と若者を意識的に対比させている。そうした対照性を引き立ているものとして、この――莟の「早蕨」――と――開き切った「羊齒」――とは対峙して機能しなくてはならない。
「穴が充分に深くなると、お婆さんは立ち上つて、棺へ戻つて來て、頭蓋骨を左手に持ち、茨の棒で棺をたたき初めた。」“When it was nearly deep enough the old woman got up and came back to the coffin, and began to beat on it, holding the skull in her left hand.”この儀式は、名を呼んだり、着衣を屋根に登ってはためかせるといった死者の再生儀礼を想起させる。叩くことによって蘇生を促す古式である。若しくは魂の抜けた骸に邪悪な悪霊が侵入しないようにするためのやはり古式の葬送儀礼とも取れる。識者の御教授を乞う。このシーンの映像は私には鬼気迫るというよりも、死を悼む、いや「メメント・モリ」(死を忘るべからず)のシンボルとして激しく胸を打つ。
「婆さんは幾度も滑稽な聲で叫んでゐた」原文は“more than one old woman crying out with a humorous voice”。この「婆さんは」は、「会葬者の中にいた一人の老婆などは」としたい。何故なら姉崎氏は、直前で“the old woman, the mother of the dead man,”を――この若者の母を――「死者の母親である婆さん」と訳しているからである(ここは栩木氏の『死んだ若者の老いた母親』がよい/でなくてはだめである)。誤読する可能性は低いかも知れないが(いや、私は三十年前に読んだ時に誤読した)、やはりまずいと思う。
『「タラム・ブレイォン・エレ・オー・ムールティーン」(ムールティーン、私にもう一滴ください)。』“'Tabhair dham braon eile,
a Mhourteen.' ('Give me another drop, Martin.')”。「ムールティーン」は「マーチン」でアイルランド系に多い名であるが、ここが「聖水」であることやその名から、後にシングが発表する戯曲「聖者の泉」を連想させる(主人公の男の名は“Martin”である。リンク先は私の片山廣子(松村みね子)訳「聖者の泉」)。栩木氏は音写して『トゥール・ゴム・ブリーン・エラ・ア・ヴァーチーン』しておられる。姉崎氏の音写は最初の二つの単語“Tabhair
dham”を連声音にしておられるようである。]
今朝、起きると、家の人達は皆彌撒に出かけてしまつて、戸は外から鍵がかけられてあつた。
それで明るくするために戸を開けることが出來なかつた。
こんな小さな家に、たつた一人でゐることになつたらと、妙に考へながら、私は殆んど一時間近くを、火の傍に坐つてゐた。此の家の人達と此處に坐りつけてゐるために、此の部屋がたつた一人人で住んで仕事をすることが出來る場所とは、以前決して考へたことがなかつた。棰木や壁の白さがぼんやり見える位の明るさが煙突からはひつて來る中に、私は暫く待ちながら、何とも云はれない悲しい氣特になつて來た。と云ふのは、此の世界の表面にある小さな片隅にも、またその中に住んでゐる人たちにも、私たちには永久に窺ひ知ることの出來ない平和と尊嚴を持つてゐると思つたからであつた。
うつらうつらしてゐるうちに、お婆さんが非常に
此の中の島と南島を受け持つ副牧師は、骨が折れてまた危險な任務を持つて居る。土曜日の夜――海が穩かな時はいつでも――此の島か或はイニシールにやつて來て、日曜の朝の彌撒を重な仕事とする。それから、食事せずに他の島へ渡り、再び彌撒をする。それゆゑ、二同の渡航に時時荒れて危險な海に出逢つたりして、アランモアに歸る前、急いで食事するのが、正午頃になる。
二週間前の日曜のこと、私が煙草を吹かしながら日のあたる宿の外で休んでゐると、大そう親切さうで愛橋のある副牧師が、濡れて疲れて、最初の食事を取りにやつて來た。暫く私の方を見ゐて、それから頭を振つた。
「ねえ、」彼は云つた。「あなたは今朝聖書をお讀みになりましたか?」
私は讀まないと答へた。
「おや、さうですか、シングさん、」彼は續けて云つた。「あなたがもし天國へ行くやうなら、私たちはひどく笑はれる事でせう。」
*
When I got up this morning I found that the people had gone to Mass and latched the kitchen door from the outside, so that I could not open it to give myself light.
I sat for nearly an hour beside the fire with a curious feeling that I should be quite alone in this little cottage. I am so used to sitting here with the people that I have never felt the room before as a place where any man might live and work by himself. After a while as I waited, with just light enough from the chimney to let me see the rafters and the greyness of the walls, I became indescribably mournful, for I felt that this little corner on the face of the world, and the people who live in it, have a peace and dignity from which we are shut for ever.
While I was dreaming, the old woman came in in a great hurry and made tea for me and the young priest, who followed her a little later drenched with rain and spray.
The curate who has charge of the middle and south islands has a wearisome and dangerous task. He comes to this island or Inishere on Saturday night--whenever the sea is calm enough--and has Mass the first thing on Sunday morning. Then he goes down fasting and is rowed across to the other island and has Mass again, so that it is about midday when he gets a hurried breakfast before he sets off again for Aranmore, meeting often on both passages a rough and perilous sea.
A couple of Sundays ago I was lying outside the cottage in the sunshine smoking my pipe, when the curate, a man of the greatest kindliness and humour, came up, wet and worn out, to have his first meal. He looked at me for a moment and then shook his head.
'Tell me,' he said, 'did you read your Bible this morning?'
I answered that I had not done so.
'Well, begod, Mr. Synge,' he went on, 'if you ever go to Heaven, you'll have a great laugh at us.'
[やぶちゃん注:「と云ふのは、此の世界の表面にある小さな片隅にも、またその中に住んでゐる人たちにも、私たちには永久に窺ひ知ることの出來ない平和と尊嚴を持つてゐると思つたからであつた。」原文は“for I felt that this little corner on the face of the world, and the people who live in it, have a peace and dignity from which we are shut for ever.”。日本語がおかしい。主格なしで「~にも、……にも、――持つてゐる」と続くからである。しかし逆に、その不自然さにこそ気付けば、この訳文の意図は英文がなくてもそこそこ推定で汲むことが出来るのである。宿の狭隘で殆んど奈落の地獄のような暗闇に閉じ込められたシングは、「この世界という広大な地球表面の、そのまた小っぽけなアラン島という片隅には――また、その島の片隅に肩寄せ合って住んでいる人たちには――永久に窺い知ることの出来ない純な平和とまことの尊厳が確かに生きていて――しかしそこから私たち文明界の異邦人は、所詮、遮断されているという感懐であった」というのである。
「大そう親切さうで愛橋のある副牧師」は直前の「副牧師」と同一人物であろう。「同じ副牧師」と入れたい。]
此處の人達はお互ひ同志にもまた子供達にも親切であるが、動物の苦痛には冷淡で、また人が 苦しんでゐても危險でない時は、その苦痛に同情しない。女の子が齒痛で顏を曲げて泣き喚いてゐるのに、母宗は爐の向う側でその子を指しながら、その有樣を面白がるかのやうに、笑つてゐるのを時時見た。
二三日前、マッキンレー大統領の死に就いて語つた時、私は暗殺者を殺すアメリカ式の方法を説明した。すると大の男が、大統領を殺した者はどの位の時間で死ぬだらうかと聞いた。
「お前さんの指を彈くくらゐの間にさ。」 私は云つた。
「なにも」その男は云つた。「電線などでやらなくても、同じやうに首は絞められるだらうがなア。王樣や大統領のやうな人を殺す奴は、自分も殺されることはわかつてゐる筈だから、樂に死ねば儲け物をさせるだけだ。三週間もかかつて死ぬのが當り前だ。さうすれば世の中に、そんなことをする奴は段段となくなるだらう。」
人人が汽船を待つてゐる時、般卸臺で二匹の犬が喧嘩をすると、みんな面白がつて、激しい嚙み合ひを續けさせようとあらゆることをする。
驢馬が動き出さないやうに、頭その蹄に縛りつけるのは、非常な苦痛を起させる仕方に違ひない。又いつか、或る家へ行つた時、其處にゐる女たちがみん膝をついて、生きた鴨や鵞鳥の羽根をむしってゐるのを見たことがあつた。
苦痛のある時、人はその感情を隱したり、抑へようとしたりしない。或る爺さんは、此の冬病氣であつたが、「頭の痛かつた時」その唸り聲が、道の何處まで聞こえたかを教へようと云つて、私を案内した事があつた。
*
Although these people are kindly towards each other and to their children, they have no feeling for the sufferings of animals, and little sympathy for pain when the person who feels it is not in danger. I have sometimes seen a girl writhing and howling with toothache while her mother sat at the other side of the fireplace pointing at her and laughing at her as if amused by the sight.
A few days ago, when we had been talking of the death of President McKinley, I explained the American way of killing murderers, and a man asked me how long the man who killed the President would be dying.
'While you'd be snapping your fingers,' I said.
'Well,' said the man, 'they might as well hang him so, and not be bothering themselves with all them wires. A man who would kill a King or a President knows he has to die for it, and it's only giving him the thing he bargained for if he dies easy. It would be right he should be three weeks dying, and there'd be fewer of those things done in the world.'
If two dogs fight at the slip when we are waiting for the steamer, the men are delighted and do all they can to keep up the fury of the battle.
They tie down donkeys' heads to their hoofs to keep them from straying, in a way that must cause horrible pain, and sometimes when I go into a cottage I find all the women of the place down on their knees plucking the feathers from live ducks and geese.
When the people are in pain themselves they make no attempt to hide or control their feelings. An old man who was ill in the winter took me out the other day to show me how far down the road they could hear him yelling 'the time he had a pain in his head.'
[やぶちゃん注:「マッキンレー大統領」“President McKinley” ウィリアム・マッキンリー・ジュニア(“William McKinley,
Jr.” 1897年~1901年)は第25代アメリカ合衆国大統領。最後の南北戦争従軍経験のある大統領であり、19世紀最後にして20世紀最初の大統領でもある。マッキンリー大統領ニューヨーク州バッファローのテンプル・オブ・ミュージックで、開催されていたパン・アメリカン博覧会に出席した1901年9月6日、無政府主義者“Leon
Czolgosz”(レオン・チョルゴッシュ)に2度銃撃され、狙撃から6日後に容態が急変し、9月14日に死亡した(副大統領セオドア・ルーズベルトが大統領職を継ぐ)。マッキンリーは暗殺されたアメリカ合衆国大統領四人のうちの三人目に当たる。チョルゴッシュの裁判は9日後の9月23日に始まり、弁護士は精神異常を示唆したが、陪審員は一時間半の審議で有罪を評決、9月26日に殺人について有罪が宣告されて10月29日に電気椅子による死刑が執行された。今回のシングのアラン帰還はチョルゴッシュの裁判の始まる直前であるから、死刑の話は推測の段階である(以上はウィキの「ウィリアム・マッキンリー」及び「マッキンリー大統領暗殺事件」を参照した)。]
今朝、ひどい嵐であつた。私は斷崖に登つて行き、打ち上げられた海草の番をする人のために建てた小舍にゐた。その後間もなく、羊の番をしてゐた一人の少年が、西の方から來て、長い間話をした。
彼は先づ、先日起つた事件に就いて私が聞き得た最初のまとまつた話をしてくれた。それは、若者が南島へ行く途中で溺死した事件である。
「南島から來た數人の男がね、」彼は云つた。「此の島へ渡つて來て馬を數匹買ひ、それを漁船に積んで渡らうとした。馬を海岸まで曳いて行くために、一艘のカラハを持つて行かうとした。一人の若者が自分が行くと云ふので、その男に繩をやり、漁船の後へ附けて曳いて行くことになつた。瀨の中へさしかかつた時、風が出て來た。カラハの中の男は漁船に引張られるので、波に乘るやうに向を變へることが出來ないで、水が一杯にはひり出した。
漁船の人達はそれを見て、どうしてよいかわからず、あれよあれよと叫び初めた。一人の男が繩を持つてゐる男に「繩を放してしまへ、さうしなけりや、舟をひつくり返してしまふぞ」と呶鳴つた。
そこで繩を持つてゐた男が、それを水の上に投げたが、カラハはもう水が半分はひり、櫂は一本しかなかつたのであらう。それから一つ波が來て、船は見てゐる前で沈んで行き、若者はそこら中を泳ぎ出した。若者を救はうと、漁船は帆を下ろした。そして下ろしてしまつた時には、餘り遠くへ來過ぎたので、また帆を擧げて、彼の方へ戻つて來た。彼は波の中を泳ぎに泳いだが、船が再び彼に近づくまでに三度目に沈んで、それつきり姿は見えなくなつてしまつた。」
誰か彼の死後出逢つた人があるかと私は聞いた。
「そんな人はない。」彼は云つた。「併し妙な話があるよ。その日、彼が海に行く前、犬が來て岩の上に坐り、彼の傍で鳴き出した。馬が船卸臺に來た時、一人のお婆さんが、以前に溺死した息子が、その中の一匹に乘つてゐるのを見た。お婆さんはその見たことを云はずにゐると、その男は目分の馬を最初に取り、その次にその馬を取つて、それから出かけて行つて、溺れたのさ。二日たつてから、私はこんな夢を見た。それは彼が「キヨーン・ギャネ」(砂の岬)で發見されて、原の家へ運ばれて、革草鞋を脱せられて、それを乾すために釘に掛けたといふ夢だつた。後で彼が見つかつたのは、あなたは聞いたでせうが其處だつたのです。」
「お前さん連は犬の鳴聲を聞くと、いつも怖いかね?」私は云つた。
「いやだね。」彼は答へた。「岩の上で天の方を見て鳴いてるのをよく見かけるでせう。あれは全くいやだね。牡雞か牝雞が家の中で何かを壞はすと誰かが死ぬといふので、あれもいやだね。此の間、此の下の家に始終住んでゐた人が、此の冬死ぬちよつと前に、そのお内儀さんの牡雞が喧嘩を初めたことがあつた。二羽とも料理臺へ跳び上つて、ランプのガラスを倒して、それを床に落して壞した。お内儀さんはその後で、自分の牡雞を捕へて殺したが、もう一羽の牡雞は隣りの家のだつたので、殺せなかつたのさ。それから旦那が病氣になつて、とうとう死んだのだよ。」
私は島で妖精の音樂を聞いたことがあるかと尋ねた。
「此の間、子供たちが學校で、そんなことを話してゐるのを聞いたよ。」彼は云つた。「その兄弟たちがよその伯父さんと、二週前の或る朝、牡雞のまだ鳴かないうちに、漁に出かけたさうだ。その人達が「砂の岬」の近くに降りて來ると、音樂が聞こえた。それが妖精の音樂だつたさうだ。また別の話だが、或る時、三人の男が夜、カラハで出かけた。すると大きな船がこつちの方へやつて來る。みんな驚いて逃げようとしたが、ずんずん近づいて來て、とうとう一人の男が、そつちへ向いて十字を切ると、それつきり見えなくなつたさうだ。」
彼はまた次の問に答へて話し續けた。
「よく妖精にさらはれる人があるよ。一年前に死んだ若者があつたが、彼はその兄弟の寢てる家の窓へ始終やつて來て、夜中にその人達と話をした。彼はその暫く前に結婚してゐたのだが、夜になると、土地を自分の息子に約束しておかなかつたのは、殘念だとか、その土地は息子に行くべきだとかいふことを口癖のやうに云つた。また或る時は牝馬のこと、その蹄のこと、それにはかせる蹄鐵のことを話すこともあつた。少し前に、パッチ・ルアはその男がブローガ・オルダ(革の長靴)をはいて、新しい着物を着て、道を行くのを見た。また二人の男は彼に別の處で逢つた。」
「あの崖の絶壁が見えるでせう?」それから暫く間をおいて、下の方の或る場所を指しながら彼は云ひ續けた。「妖精達がボール遊びをするのはあすこです。朝來ると、足跡があり、線を引くための三つの石や、ボールを跳ねさす大きな石がある。子供たちが時時、その三つの石を取り除けておくが、いつも朝になると、また戻つて來てゐる。此の間、その土地を持つてゐる人が、大きな石まで取り除けて、それを轉がして、崖の下へ落しておいたが、それでも朝には又もとの所へ戻つてゐた。」
*
There was a great storm this morning, and I went up on the cliff to sit in the shanty they have made there for the men who watch for wrack. Soon afterwards a boy, who was out minding sheep, came up from the west, and we had a long talk.
He began by giving me the first connected account I have had of the accident that happened some time ago, when the young man was drowned on his way to the south island.
'Some men from the south island,' he said, 'came over and bought some horses on this island, and they put them in a hooker to take across. They wanted a curagh to go with them to tow the horses on to the strand, and a young man said he would go, and they could give him a rope and tow him behind the hooker. When they were out in the sound a wind came down on them, and the man in the curagh couldn't turn her to meet the waves, because the hooker was pulling her and she began filling up with water.
'When the men in the hooker saw it they began crying out one thing and another thing without knowing what to do. One man called out to the man who was holding the rope: "Let go the rope now, or you'll swamp her."
'And the man with the rope threw it out on the water, and the curagh half-filled already, and I think only one oar in her. A wave came into her then, and she went down before them, and the young man began swimming about; then they let fall the sails in the hooker the way they could pick him up. And when they had them down they were too far off, and they pulled the sails up again the way they could tack back to him. He was there in the water swimming round, and swimming round, and before they got up with him again he sank the third time, and they didn't see any more of him.'
I asked if anyone had seen him on the island since he was dead.
'They have not,' he said, 'but there were queer things in it. Before he went out on the sea that day his dog came up and sat beside him on the rocks, and began crying. When the horses were coming down to the slip an old woman saw her son, that was drowned a while ago, riding on one of them, She didn't say what she was after seeing, and this man caught the horse, he caught his own horse first, and then he caught this one, and after that he went out and was drowned. Two days after I dreamed they found him on the Ceann gaine (the Sandy Head) and carried him up to the house on the plain, and took his pampooties off him and hung them up on a nail to dry. It was there they found him afterwards as you'll have heard them say.'
'Are you always afraid when you hear a dog crying?' I said.
'We don't like it,' he answered; 'you will often see them on the top of the rocks looking up into the heavens, and they crying. We don't like it at all, and we don't like a cock or hen to break anything in the house, for we know then some one will be going away. A while before the man who used to live in that cottage below died in the winter, the cock belonging to his wife began to fight with another cock. The two of them flew up on the dresser and knocked the glass of the lamp off it, and it fell on the floor and was broken. The woman caught her cock after that and killed it, but she could not kill the other cock, for it was belonging to the man who lived in the next house. Then himself got a sickness and died after that.'
I asked him if he ever heard the fairy music on the island.
'I heard some of the boys talking in the school a while ago,' he said, 'and they were saying that their brothers and another man went out fishing a morning, two weeks ago, before the cock crew. When they were down near the Sandy Head they heard music near them, and it was the fairies were in it. I've heard of other things too. One time three men were out at night in a curagh, and they saw a big ship coming down on them. They were frightened at it, and they tried to get away, but it came on nearer them, till one of the men turned round and made the sign of the cross, and then they didn't see it any more.'
Then he went on in answer to another question:
'We do often see the people who do be away with them. There was a young man died a year ago, and he used to come to the window of the house where his brothers slept, and be talking to them in the night. He was married a while before that, and he used to be saying in the night he was sorry he had not promised the land to his son, and that it was to him it should go. Another time he was saying something about a mare, about her hoofs, or the shoes they should put on her. A little while ago Patch Ruadh saw him going down the road with brogaarda (leather boots) on him and a new suit. Then two men saw him in another place.
'Do you see that straight wall of cliff?' he went on a few minutes later, pointing to a place below us. 'It is there the fairies do be playing ball in the night, and you can see the marks of their heels when you come in the morning, and three stones they have to mark the line, and another big stone they hop the ball on. It's often the boys have put away the three stones, and they will always be back again in the morning, and a while since the man who owns the land took the big stone itself and rolled it down and threw it over the cliff, yet in the morning it was back in its place before him.'
[やぶちゃん注:この溺死した若者というのは、先に埋葬シーンが描かれた若者であろう。ここは怪異伝承の記載として素晴らしく、また面白い。
「私は斷崖に登つて行き、打ち上げられた海草の番をする人のために建てた小舍にゐた。」原文は“I went up on the cliff to sit in the shanty they have made there for the men who watch for wrack.”。“shanty”は「掘立小屋」(“they”とあるから、そうした小屋蛾が複数あるのであろう)。“wrack”で、これには「難破船・漂着物・残骸」の意の外に「漂着した海草・ちぎれ雲」の意がある。栩木氏はここを『難破船の破片などが島へ漂着するのを見張るため』と訳されている。漁村ではしばしばこうした物見台があるから、これは如何にも自然な訳ではある。しかし、姉崎氏の訳が誤訳かと言えば、そうともとれない。実際にこれらは海藻灰(ケルプ灰)として商品にする材料でもあり、恐らくはその時期になると、打ち上がった海藻は代々採取の場所が各家で決められていて、その掟を破ってこっそり他人の所有権のある海藻を不法に取る者が出ないように、例えば、村の中のグループ単位で順にここで見張りをすると考えれば、しっくりくる(寧ろ複数あるのはその可能性を示唆するとも言えるかも知れない)。いずれにせよ、そこは海難の際の物見台の役割もしていようから、何れの訳もおかしくはない。但し、栩木氏は“shanty”を『石積みの風除け椅子』と訳されておられ、これは氏の2005年みすず書房刊の「アラン島」の「訳者あとがき」で明らかにされているが、所謂、現在、正に島で「シングの椅子」(カヒール・シング)と呼ばれている場所を同定地としておられるからである。そこに載る氏が撮った「シングの椅子」の写真のキャプションに、『ほぼ円形の石積みのシェルターの内部に入ると、こじんまりと居心地がよく、崖上にあるので眺望絶佳』とある。さすれば、栩木氏は現地でここを見、恐らくそこで誰かからこの「椅子」(岩小屋)の機能を説明されたものと思われ、その点からはやはり、これは海事用・海難用の物見のための岩小屋と理解するのが妥当であろうと思われる。因みにかつてアランを旅した時、私は残念なことにここを訪ねていない。
「馬を海岸まで曳いて行くために、一艘のカラハを持つて行かうとした。」原文は“They wanted a curagh to go with them to tow the horses on to the strand”。これは今までに何度も描写されているように、アラン諸島では海岸や港近くが浅いために、大型の船は入港出来ず、しばしば出て来る小型のカラハで人や荷を運搬する。南島(イニシーア島)に着いた際、そのように馬を陸揚げするために、このカラハが必要なのである。
「一人の若者が自分が行くと云ふので、その男に繩をやり、漁船の後へ附けて曳いて行くことになつた。」空のカラハを曳航することは、恐らく勝手に波に動かされるために出来ないのであろう。そこで縄で漁船と結んだ上、カラハを操舵するために一人の若者が乗った、という意味である。
「繩を放してしまへ、さうしなけりや、舟をひつくり返してしまふぞ」瀬戸の荒波と複雑な流れが、漁船と曳航するカラハの一体性を阻害し、カラハが木の葉のように弄ばれて、ローリングやピッチングを繰り返して、転覆の危険性が高まったため、曳航索を放してカラハを自立させた方が、安定するからである。しかし既に浸水しており、しかも漕ぐために必要な一対の櫂も恐らく流されて一本しかなく、操舵不能に陥り、横波を喰らって転覆したのである。
「船が再び彼に近づくまでに三度目に沈んで」言わずもがなであるが、船が再び彼に近づいていく途中、沈んでは海面に首を出し、出しては沈むというのを二度繰り返したのを彼らは見た。が、三度目は沈んだまま、「それつきり姿は見えなくなつてしまつた。」という意味である。
「誰か彼の死後出逢つた人があるかと私は聞いた」という部分は、面白い。もしかすると、島では、死後、ある程度の時間が経過しないと、霊体は顕在化しないと考えられているのかもしれないことを示唆しているようにも読めるからである。
「併し妙な話があるよ。」以下の少年の語る怪異譚は以下の三つの部分から成り、三番目がこの手の当時の都市伝説としては極めて特異である。何故なら、話者の少年自身の体験談だからである。
①「その日、彼が海に行く前、犬が來て岩の上に坐り、彼の傍で鳴き出した。」“Before he went out on the sea that day his dog came up and sat beside him on the rocks, and began crying.”。その事故が起こった日、この若者が海へ出て行く直前、彼の飼っている犬が、普段は決してそんなことはしないのに、岩の上に立っていた彼の側へやってきて坐ると、しきりに吠え出した事実。この犬の遠吠えを不吉とする伝承は続く少年の語りで、一般的なものであることが示される。これはヨーロッパに限らず、本邦でも犬の遠吠えを不吉とする伝承は一般的にあり、例えば福岡などでは野犬が遠吠えをすると翌日に村から死人が出るという。
②「馬が船卸臺に來た時、一人のお婆さんが、以前に溺死した息子が、その中の一匹に乘つてゐるのを見た。お婆さんはその見たことを云はずにゐると、その男は目分の馬を最初に取り、その次にその馬を取つて、それから出かけて行つて、溺れたのさ。」“When the horses were coming down to the slip an old woman saw her son, that was drowned a while ago, riding on one of them, She didn't say what she was after seeing, and this man caught the horse, he caught his own horse first, and then he caught this one, and after that he went out and was drowned.”。イニシーアへ送る候補の馬が港の船卸台のところまで運ばれてきた時、そこに居た一人の老婆が、少し前に溺死した彼女の息子が、その中の一匹の馬に跨っているのを一瞬見た(ように思ったのであろう)。彼女は縁起でもないからそのことを黙っていたのだけれども、見ていると、その若者は馬を選び出すのに、まず彼の持ち馬を最初に選び、二番目にさっき彼女の死んだ息子が騎っていた馬を、若者は選んだ。そうして海へ出て行って溺れた、という事実。これは老婆によって語られた後日譚であろうから、本怪異譚の中でも後から付随したものであろう。
③「二日たつてから、私はこんな夢を見た。それは彼が「キヨーン・ギャネ」(砂の岬)で發見されて、原の家へ運ばれて、革草鞋を脱せられて、それを乾すために釘に掛けたといふ夢だつた。後で彼が見つかつたのは、あなたは聞いたでせうが其處だつたのです。」“Two days after I dreamed they found him on the Ceann gaine (the Sandy Head) and carried him up to the house on the plain, and took his pampooties off him and hung them up on a nail to dry. It was there they found him afterwards as you'll have heard them say.”。これが本話の極め付けだ。私、則ち話者である少年のオリジナルな怪異譚なのだ。非常にいい。私のオリジナルな邦訳を試みてみる。
「……それから、ですね……彼が行方不明になって、二日後のことなんですけど……僕、不思議な夢を見たんです……その夢は――
……彼の遺体が『砂の岬』にうち揚がっているのが見つかるんです……
……そうして……その遺体は野っ原の彼の
……そうして……画面がアップになって……遺体から革草鞋が脱がされ……
……そうして……それが梁に打ち込まれた一本の大釘にぶら下げられて……
……そうして……それがぶらんぶらんと揺れながら……雫を垂らしながら……乾かされてる……
――っていう、もの凄くリアルな夢だったんです……で……ねえ、シングさん……シングさんは、もう聴いてるでしょうが……それよりずうっと後になって……彼の遺体が揚がったのは……『砂の岬』……だったんですよ……」
“Ceann gaine”の“Ceann ”はネット上のネィティヴの発音を聴くと「キャン」と聴こえる。栩木氏は「キヤン・ガニヤウ」とルビされている(「キャン・ガニャウ」か)。この『砂の岬』は恐らく砂浜海岸のある岬ではなく砂洲か砂嘴ではないかと思われる。また「原の家」“the house on the plain”というのは、実は私は民俗社会の村の中の呼び名(特に同姓の多い村)にしばしば見られる(例:「川曲りの~」「北浜の~」)、地形を以て呼称する固有の地所名ではないかと推測している。
「牡雞か牝雞が家の中で何かを壞はすと誰かが死ぬ」というのは、これは直観であるが、西洋では一般的なものなのかも知れない。タルコフスキイの「鏡」で、そうした映像があり、そこに私は言いようのない不吉さを感じた。本邦ではニワトリが夜間に鬨を挙げると凶事や変事が起こるという伝承は広く知られるが、「家の中で何かを壞はすと」というシチュエーションのジンクスは、私は聞いたことがない。もしあるようならばここに掲げたい。識者の御教授を乞うものである。
「或る時、三人の男が夜、カラハで出かけた。すると大きな船がこつちの方へやつて來る。みんな驚いて逃げようとしたが、ずんずん近づいて來て、とうとう一人の男が、そつちへ向いて十字を切ると、それつきり見えなくなつたさうだ。」これは洋の東西を問わず存在する。幽霊船や本邦では船幽霊の一形態として知られる。
「パッチ・ルア」原文“Patch Ruadh”。ゲール語の“Ruadh”は英語の“red”であるから、「赤毛のパッチ」という綽名である。“Patch”は正式な名で、普通は通称の“Pat”「パット」で呼ばれる。
「ブローガ・オルダ(革の長靴)」“brogaarda (leather boots)”。栩木氏は『ブローガ・アーダ』と音写されている。
「線を引くための三つの石」原文“three stones they have to mark the line”。しかし日本語としてはちょっと奇妙だ。これは彼等独特のボール・ゲームの競技場のラインとしての「境界を示すための三つの置き石」であろう。
「妖精達がボール遊びをする」については、ミユシャ氏のHP「妖精辞典 夜明けの妖精詩」に、“Ganconer”・ゲール語“Gean-cannah”・英語“The Love Talker”・和名「ガンコナー/言い寄り魔/恋を語る人(ラヴ・トーカー)」というアイルランドの妖精を挙げて、この『ガンコナー達は、普通の[群をなす妖精達(トルーピング・フェアリーズ)]と全く同じ様に多勢で現れ、湖の底の町に住み、ボールを投げて遊び、人間の牛を盗んでは、その後に丸太を残していく』とあるから、妖精たちは一般にボール遊びが好きらしい。]
私はまた南島に來て居る。そして驚くほど色色の物語や歌を知つて居る老人たちに出逢つた。それもよく愛蘭土語と英語の兩方で知つてゐる最後の人たちなのである。今日はその一人の家へ、愛蘭土語を書ける土地の學者を連れて立寄つた。そしていくつかを書き留め、他は聞いておいた。此處に老人が、その本筋に熱中して行く前、最初に話した一つの物語がある。それは書き留めなかつたが、意味は次のやうであつた。――
チャリー・ランバートといふ一人の男が居た。彼が競馬で乘る馬は、どれも一番になるのがきまりであつた。
その國の人たちは遂に怒つてしまつて、今後、彼は競馬に出てはならぬこと、若し出たらば、見つけた者は彼を撃つ權利があるといふ法律ができた。それから後、國のその地方から英國へ行つた一人の紳士があつた。或る日、英國の人たちと話をして居る時、愛蘭土の馬が最良だと云つた。英國人は英國の馬が最良だと云ひ、終に競馬をやらうといふことになり、英國の馬がやつ來て、愛蘭土の馬と競走することになつた。紳士はその競馬に、全財産を賭けた。
さて彼は愛蘭土に歸ると、チャリー・ランバートの處へ行き、馬に乘つてくれないかと賴んだ。チャリーは乘りたくないと云つて、紳士に自分の身に迫る危險を話した。そこで紳士は全財産を賭けた次第を話すと、終にチャリーは競馬の行はれる場所と時日を聞いたので、紳士はそれを教へた。
「その當日に、此處から競馬場まで沿道七哩毎に、手綱と鞍をつけた馬を、おいて下さい。」
ランバートは云つた。「さうしたら、其處へ行きませう。」
紳士が行つてしまふと、チャリーは着物を脱いて、寢床にはひつた。それから醫者を呼びに遣り、醫者が來たと聞くと、熱のために脈搏が高いと思はせようと腕を振り廻はし初めた。
醫者はその脈搏を感じ、明日また來るまで安靜にしてゐるやうにと命じた。
次の日も同じやうな状態で、競馬の日まで此のやうだつた。その日の朝、醫者が重態だと思つたほど、チャリーは激しく脈を打たせた。
「チャリー、これから私は競馬に行かうと思ふ。」彼は云つた。「だが、今晩歸つて來たら、また來て診て上げよう。私が來るまで大事にしてゐなさい。」
醫者が行つてしまふと直ぐに、チャリーは床から跳び起きて、馬に乘つた。そして第一の馬が待つてゐる處までで七哩行き、それからその馬で七哩行き、また他の馬で七哩行き、遂に競馬場まで來た。
彼は紳士の馬に乘つて、競馬に勝つた。
群集は大勢見物して居た。彼がやつて來るのを見た時、皆んなチャリー・ランバートだ、若しさうでないなら惡魔だと云つた。何故なら、そんな乘り方のできる者がほかにある筈はなかつたし、足が馬から離れてしまつてゐたが、彼はいつもさうだつたからである。
競馬が濟むと、彼は待つてゐた馬に乘り、その馬で七哩行き、また次の處で七哩、自分の馬で七哩乘つて家に歸ると、着物を脱ぎ捨て、寢床に横になつた。
暫くして、醫者が歸つて來て、素晴らしい競馬を見て來たと云つた。
翌日、馬に乘つた男はチャリー・ランバートだと、人人は言ひ出した。調べられたが、醫者がチャリーは病氣で寢てゐて、競馬の前にも後にも自分が診察したことを誓つたので、例の紳士は財産が助かつたのであつた。
*

[島の騎り手]
I am in the south island again, and I have come upon some old men with a wonderful variety of stories and songs, the last, fairly often, both in English and Irish, I went round to the house of one of them to-day, with a native scholar who can write Irish, and we took down a certain number, and heard others. Here is one of the tales the old man told us at first before he had warmed to his subject. I did not take it down, but it ran in this way:--
There was a man of the name of Charley Lambert, and every horse he would ride in a race he would come in the first.
The people in the country were angry with him at last, and this law was made, that he should ride no more at races, and if he rode, any one who saw him would have the right to shoot him. After that there was a gentleman from that part of the country over in England, and he was talking one day with the people there, and he said that the horses of Ireland were the best horses. The English said it was the English horses were the best, and at last they said there should be a race, and the English horses would come over and race against the horses of Ireland, and the gentleman put all his money on that race.
Well, when he came back to Ireland he went to Charley Lambert, and asked him to ride on his horse. Charley said he would not ride, and told the gentleman the danger he'd be in. Then the gentleman told him the way he had put all his property on the horse, and at last Charley asked where the races were to be, and the hour and the day. The gentleman told him.
'Let you put a horse with a bridle and saddle on it every seven miles along the road from here to the racecourse on that day,' said Lambert, 'and I'll be in it.'
When the gentleman was gone, Charley stripped off his clothes and got into his bed. Then he sent for the doctor, and when he heard him coming he began throwing about his arms the way the doctor would think his pulse was up with the fever.
The doctor felt his pulse and told him to stay quiet till the next day, when he would see him again.
The next day it was the same thing, and so on till the day of the races. That morning Charley had his pulse beating so hard the doctor thought bad of him.
'I'm going to the races now, Charley,' said he, 'but I'll come in and see you again when I'll be coming back in the evening, and let you be very careful and quiet till you see me.'
As soon as he had gone Charley leapt up out of bed and got on his horse, and rode seven miles to where the first horse was waiting for him. Then he rode that horse seven miles, and another horse seven miles more, till he came to the racecourse.
He rode on the gentleman's horse and he won the race.
There were great crowds looking on, and when they saw him coming in they said it was Charley Lambert, or the devil was in it, for there was no one else could bring in a horse the way he did, for the leg was after being knocked off of the horse and he came in all the same.
When the race was over, he got up on the horse was waiting for him, and away with him for seven miles. Then he rode the other horse seven miles, and his own horse seven miles, and when he got home he threw off his clothes and lay down on his bed.
After a while the doctor came back and said it was a great race they were after having.
The next day the people were saying it was Charley Lambert was the man who rode the horse. An inquiry was held, and the doctor swore that Charley was ill in his bed, and he had seen him before the race and after it, so the gentleman saved his fortune.
[やぶちゃん注:「私はまた南島に來て居る。そして驚くほど色色の物語や歌を知つて居る老人たちに出逢つた。それもよく愛蘭土語と英語の兩方で知つてゐる最後の人たちなのである。」原文は“I am in the south island again, and I have come upon some old men with a wonderful variety of stories and songs, the last, fairly often, both in English and Irish,”であるが、この「それもよく愛蘭土語と英語の兩方で知つてゐる最後の人たちなのである。」の「最後の人」というのは一読おかしい気がする。「古伝承や歌を古いゲール語と英語で語れる最後の人々」という意味でとれないとは言えないが、やはりそうした「最後の」と言い切る(言い切れる)のは、最早、そうした人が彼等以外にはいないという意味になり、断定に過ぎるからであり、現実的な謂いとは言い難い。問題は挿入句である“the last”で、これは実は “stories and songs”の「最後のもの」「後者の方の」という指示代名詞で、この後半部は「特に後者の『歌』については、かなりしばしば、アイルランド語と英語の両方で知っている人たちなのである。」という意味なのではあるまいか。栩木氏もそのように訳しておられる。
「土地の學者」“native scholar”。「學者」というのは、ここまでの島の描写からはそぐわない。所謂、アラン島の人の中でも多少の教養を持った「郷土史研究家」といった感じであろう。
「七哩」11キロメートル強。
「何故なら、そんな乘り方のできる者がほかにある筈はなかつたし、足が馬から離れてしまつてゐたが、彼はいつもさうだつたからである。」“for there was no one else could bring in a horse the way he did, for the leg was after being knocked off of the horse and he came in all the same.”。私には英文の後半部がよく分からないが、姉崎氏の訳は少なくとも辻褄の合う日本語ではある。則ち、馬を疾走させる際に、乗った騎手の足が馬の体から殆んど浮いたように見えるのが名騎手チャーリー・ランバートの騎乗の一番の特徴だったから、という謂いである。但し、栩木氏は全く異なった訳をなさっている。氏の2005年みすず書房刊の「アラン島」をお読みあれかし。なお、イェーツによるこの部分の挿絵と思われる“An Island Horseman”を見ると、仰天することに、その騎乗方法は跨るタイプではなく、腰掛けるような横座りである。そうして、その騎手の両足は馬の左手にすっくと伸ばされて文字通り、「足が馬から離れてしまつてゐ」るように見えるのは偶然か?]
その後で、もう一つ同じやうな妖精騎手の話をした。それは彼が一シリングだけ殘して、全財産を失くした紳士に逢ひ、その人にその一シリングをくれと願つた。紳士はそれを與へると、その妖精騎手――小さな赤顏の男――彼のために競馬に出て、賭金が倍になる時に、信號に赤いハンカチを振つて、その紳士を金持にした。
*
After that he told me another story of the same sort about a fairy rider, who met a gentleman that was after losing all his fortune but a shilling, and begged the shilling of him. The gentleman gave him the shilling, and the fairy rider--a little red man--rode a horse for him in a race, waving a red handkerchief to him as a signal when he was to double the stakes, and made him a rich man.
[やぶちゃん注:原文では行空けはないが、独立させた。
「妖精騎手」原文も“fairy rider”であるが、謂いは、妖精のような超常的な能力を持った名騎手という謂いであろう。
「小さな赤顏の男」原文は確かに“a little red man”であるが、これは「小兵の赤毛の男」であろう。]
それから、老人はなみはづれた英語の惡詩を謠つてくれたから私は書き留めたが、今寫してみると、頗る首尾一貫しないものである。此の詩を老人達は吟唱曲のやうに繰り返してゐるが、特に韻の不規則な行に來ると、彼等はそれを無理に朗吟風の型にして本當に樂しんでゐるやうであつた。その老人は吟唱しながら身體をくねくねと動かし續けてゐた。それが吟唱にふさはしく、板についてゐるやうであつた。
*
Then he gave us an extraordinary English doggerel rhyme which I took down, though it seems singularly incoherent when written out at length. These rhymes are repeated by the old men as a sort of chant, and when a line comes that is more than usually irregular they seem to take a real delight in forcing it into the mould of the recitative. All the time he was chanting the old man kept up a kind of snakelike movement in his body, which seemed to fit the chant and make it part of him.
[やぶちゃん注:「惡詩」“doggerel”は「狂詩」のこと。滑稽な内容を旨としたもの。但しこの後に示される「白馬」“THE WHITE HORSE”という詩を見ると、これは所謂、自由形式で民族的や叙事的な内容を表わした古形の朗誦用「狂詩曲」(ラプソディー)であると言ってよい。
「吟唱曲のように」“a sort of chant”。キリスト教の典礼聖歌のような感じの歌い方。同じフレーズを唱和して歌う。
「朗吟風の型」“the mould of the recitative”レシタティーボの型。叙事詩や歌物語の中で叙述や会話の部分に用いられる朗読調の歌唱部分。オペラやオラトリオなどに見られるように、歌い方に一定の類似性や定型がある。]
白馬
私の馬は白馬だ、
初めは栗毛だつたが。
夜でも晝でも旅をして
歩いて行くのが大好きだ。
旅した道は大變だ
半分だけを語つてみても。
アダムを花園で乘せた、
彼が天から落ちた日に。
バビロンの野では、
賞牌目あてに驅けたが、
ハンニンバル大王に
その翌日は狩り立てられた。
それからは狐狩の時に
またしても狩り立てられた。
その時ネブカトネザルは
牛の姿で草を食べてゐた。
*
THE WHITE HORSE
My horse he is white,
Though at first he was bay,
And he took great delight
In travelling by night
And by day.
His travels were great
If I could but half of them tell,
He was rode in the garden by Adam,
The day that he fell.
On Babylon plains
He ran with speed for the plate,
He was hunted next day
By Hannibal the great.
After that he was hunted
In the chase of a fox,
When Nebuchadnezzar ate grass,
In the shape of an ox.
[やぶちゃん注:原詩は最初の一連が御覧の通り、五行である。
「栗毛」黄褐色の毛で覆われる毛色。我々がイメージする一般的なサラブレッドは「
「バビロン」は紀元前のメソポタミア地方の古代都市で、バグダードの南方、ユーフラテス川河畔にあった。ハンニバルが生きた時代はセレウコス朝であるが、ここは超時空で(「翌日」は翌日ではない)、バビロンの栄華の時代の設定であろう。
「賞牌」は「しゃうはい(しょうはい)」と読み、競技の入賞者などに賞として与えるメダル。のこと。但し、ここは競馬であるから、“plate”は近代競馬の賞杯である「金(銀)盃」を意味していよう。
「ハンニバル」Hannibal Barca(ハンニバル・バルカ B.C.247年頃~B.C.183年か182年頃)はカルタゴの将軍。第二次ポエニ戦争でローマ軍に大勝したが、のちにローマの武将スキピオに敗れ、小アジアに亡命、自殺した。
「ハンニンバル大王に/その翌日は狩り立てられた」原文“He was hunted next day/ By Hannibal the great.”で、これは「翌日は狩りに駆り出された/ハンニバル大王様の御騎乗で」という意味である。この訳ではまるでハンニバルに生捕りにされそうになった、という誤読をしてしまう。
「ネブカドネザル」は古代メソポタミアの王の名で、四人の王がこの名を持つが、単に“Nebuchadnezzar”と記す場合はネブカドネザル2世(B.C.604年~B.C.562年)の新バビロニアの王を指す。いずれにせよ、この四人の王は総てハンニバルの時代より遥かに昔であるから、この狂詩の支離滅裂さの真骨頂である。但し、これはネブガドネザルが後世転生して牛(雄牛)となっていた、とも解釈は可能である。ともかくも「その時ネブカトネザルは/牛の姿で草を食べてゐた」という章句には、戯言以外の何らかのネブカトネザルに纏わる民間伝承が隠されているのかも知れないが、調べ切れなかった。識者の御教授を乞うものである。
最後に。ちょいと私も定型狂詩っぽくオリジナルに訳してみたい気になった。
おいらの馬は
ところがどっこい昔は
昼夜を継ぎ
驅けるわ、驅ける、その驅り――
その半分も語れねえ――
昔を言やあ、園エデン、御先祖アダムを乗せ申し、
堕天、韋駄天、それも
バビロンの、その野辺の競馬場、
金杯目あてに驅け抜けて――
さて翌日は狩りに出る、
次に控えし
そいつは狐を追う修行――
さてもその時、ネブカドネザル、
草を食んでる雄牛で御座い――
おあとがよろしいようで――]
次の句では、ノアと箱船にはひつたり、モーゼを乘せて紅海を横切つたりした事があつた。それから――
やつと運が向いて來て
エヂプトではパラオの傍に居て、
王を乘せては堂堂と
花やかなナイルの岸を練つたものだ。
サウル王と居た時は
艱難辛苦を共にした。
ダビテの傍に居た時は
ダビテがゴリアテを殺した。
*
We are told in the next verses of his going into the ark with Noah, of Moses riding him through the Red Sea; then
He was with king Pharaoh in Egypt
When fortune did smile,
And he rode him stately along
The gay banks of the Nile.
He was with king Saul and all
His troubles went through,
He was with king David the day
That Goliath he slew.
[やぶちゃん注:「パラオ」“Pharaoh”はファラオ、古代エジプトの君主の称号。
「サウル」は、旧約聖書「サムエル記」に登場する、B.C.10世紀頃のイスラエル王国最初の王。以下、ウィキの「サウル」から引用する。ユダヤの指導者にして預言者であったサムエルの神託によって王として選ばれた『サウルは息子ヨナタンや家臣たちと共にイスラエルを率いて、ペリシテ人や周辺民族と勇敢に戦った。しかしアマレク人との戦いで「アマレク人とその属するものを一切滅ぼせ」という神の命令に従わなかったため、神の心は彼から離れた』『神の声を伝えていたサムエルもこれ以降サウルに会うことはなかった。サムエルはサウルをあきらめ、神の言葉によってひそかにエッサイの子ダビデに油を注いだ。ダビデはペリシテの勇者ゴリアテ(次注参照)を討って有名になり、竪琴の名手としてサウルに仕えたが、サウルはダビデの人気をねたんで命を狙った。ダビデは逃れ、何度もサウルを殺害するチャンスを得たが、「神の選んだ人に手をかけられない」といってサウルに手を触れなかった』。『ダビデの立琴によってサウルから悪霊が出て行』ったが、後、『サウルはペリシテ軍との戦いの中で、ギルボア山で息子たちと共に追い詰められ、剣の上に身を投げて死んだ』とも、『「重傷だったサウルに頼まれて家臣がとどめをさした」との異なる伝承もある』。『サウルとヨナタンの遺骨は、次の王となったダビデによって、ベニヤミンの地ツェラの父の墓に葬られ』、『サウル王の四男のイシュ・ボシェテがただ一人生き残り、将軍アブネルに支持されて、マハナイムでサウル王朝第2代目の王になった。イシュ・ボシェテが暗殺されるとサウル王朝は滅亡して、ダビデ王朝が始まった』とある。
「ゴリアテ」は(以下、ウィキの「ゴリアテ」から引用)『旧約聖書の「サムエル記」に登場するペリシテ人の巨人兵士。身長は6キュビト半』『(約2.9メートル)、身にまとっていた銅の小札かたびら(鎧)は5000シェケル』『(約57キログラム)、槍の鉄の刃は600シェケル』『(約6.8キログラム)あったという。サウル王治下のイスラエル王国の兵士と対峙し、彼らの神を嘲ったが、羊飼いの少年であったダビデが投石器から放った石を額に受けて昏倒し、自らの剣で首を刎ねられた』。
私の定型狂詩オリジナル訳。
頃はエジプト、ファラオと一緒、
運命の、女神がにっこり、笑みをかけ――
王を騎上に堂堂と、
花のナイルの岸うねる――
サウルの王といた時にゃ、
艱難辛苦をなめ尽くし――
ダビテの王といた時にや、
ゴリアテ殺した日にもいた――
おあとがよろしいようで――]
次の數句の間で、馬はユダやマッカべウス大王に仕へ、クルスに仕へ、またバビロンに戻つて來る。次に、トロイにはひつた馬となつて居る。
( )が喜んでトロイに來た時、
私の馬もそこにゐた。
それは城壁を乘り越えて、
町にはひつたといふことである。
私はスぺインでまた逢つた。
その頃は彼も全盛で、
ハンニンバル大王の乘馬となつて、
アルプスを越えてローマに入つた。
馬も高いしアルプスも高く、
乘手は落ちて、
ハンニンバル大王は、
片目をつぶした。
*
For a few verses he is with Juda and Maccabeus the great, with Cyrus, and back again to Babylon. Next we find him as the horse that came into Troy.
When ( ) came to Troy with joy,
My horse he was found,
He crossed over the walls and entered
The city I'm told.
I come on him again, in Spain,
And he in full bloom,
By Hannibal the great he was rode,
And he crossing the Alps into Rome.
The horse being tall
And the Alps very high,
His rider did fall
And Hannibal the great lost an eye.
[やぶちゃん注:「ユダ」はずっと紀元前の話であることや、次の「マッカべウス大王」から、これはイスラエルの十二部族の一つであるユダ族の祖であるユダのことであろう。
「マッカべウス大王」ユダ・マカバイ(Judas Maccabaeus ?~B.C.160年)。ウィキの「ユダ・マカバイ」によれば旧約聖書外典の一つ「マカバイ記」に現れるB.C.2世紀のユダヤ民族の英雄。『シリアの支配下にあったユダヤの独立を達成することになるマカバイ戦争を指導し、ハスモン朝が開かれる基礎を築いた』とある。
「クルス」“Cyrus”。キュロス2世(Kyros B.C.600年頃~B.C.529年:綴りが異なるが、こうも綴るらしい)はアケメネス朝ペルシアの初代国王。ウィキの「キュロス2世」に、『キュロスは古代エジプトを除く全ての古代オリエント諸国を統一して空前の大帝国を建設した。古代ペルシア語名をクリシュなどといい、ギリシア語名をキュロス(クロス)、ラテン語名をキルス、古典ヘブライ語名をコレシュという。同名の王子小キュロスと区別して「大キュロス」、キュロス大王、同名のアンシャン王と区別してキュロス2世と呼ばれる。現代のイラン人は、キュロスをイランの建国者と称えている』とある。
「( )が喜んでトロイに來た時」の「( )」は、御覧の通り、原文も同じ。シングが老人の詠唱を採録した際、分からなかった単語と思われる。トロイの木馬を考案したオデュッセウスか。
「ハンニンバル大王は、/片目をつぶした」ハンニバルはB.C.218年のローマ攻略のアルプス越えの際、左目を失明している。この詩では落馬による外傷とするが、ネット上の記載には重度の結膜炎を原因とするらしい。
私の定型狂詩オリジナル訳。「( )」はとりあえずオデュッセウスでやってみた。
オデュッセウス、彼がトロイに來た時にゃ、これ幸いに、
おいらがいた、おいらはそん時きゃ、トロイの木馬――
やすやすと、鉄壁城壁何のその、
町の中へと、ずずいずい!――
おいらがよ、
そん時きゃ
大殿さまのハンニンバル、悠々乗せて、
アルプスを、越えてローマへ一目散――
高い高いは馬の丈、
高い高いはアルプスじゃ――、
ああら、あらあら、騎手さん、ドスン!
大殿さまのハンニンバル、片目眇めとなりにけり――
おあとがよろしいようで――]
それから後、少スキピオを乘せたり、ブリアンがデンマルク人を愛蘭土から追ひ出す時に乘せたり、聖ルスがオーリムの戰で斃れた時に乘せたり、サースフィールドをリメリックの攻圍で乘せたりした。
ジェームズ王に仕へては、
愛蘭土の岸にやつて來て、
ボイン河の激戰の終つた時、
到頭ちんばになつちやつた。
名高いヲーターローの戰では、
世界一の人を乘せ、
勇ましいダニエル・オーコンネルが
その脊に乘つたのも嘘ぢやない。
勇ましいダニエルをその脊に乘せて、
再び戰場へと用意して、
王黨を屈服させるまでは、
いつまでも止まることはないだらう。
此の長い詩は奇怪なものではあるが、前いつたやうに、老人がそれを爐邊で低唱すると、一種の存在を持つ。さうして島では、非常に有名である。老人はそれを印刷して欲しいと望んでゐる。
それが世の中から無くなるのはよい事でなく、此處で知つてゐるのは自分だけで、本土では、聞いた人もないからだと云つた。もう二つばかり同じやうな惡詩の見本があつたが、私は書き寫さなかつた。
その歌には英語・愛蘭土語共に此の島の人達にすらわからない言葉が一杯あるので、それをゆつくり云ふ時は記憶が大概覺束なくなる。
*
Afterwards he carries young Sipho (Scipio), and then he is ridden by Brian when driving the Danes from Ireland, and by St. Ruth when he fell at the battle of Aughrim, and by Sarsfield at the siege of Limerick.
He was with king James who sailed
To the Irish shore,
But at last he got lame,
When the Boyne's bloody battle was o'er.
He was rode by the greatest of men
At famed Waterloo,
Brave Daniel O'Connell he sat
On his back it is true.
***
Brave Dan's on his back,
He's ready once more for the field.
He never will stop till the Tories,
He'll make them to yield.
Grotesque as this long rhyme appears, it has, as I said, a sort of existence when it is crooned by the old man at his fireside, and it has great fame in the island. The old man himself is hoping that I will print it, for it would not be fair, he says, that it should die out of the world, and he is the only man here who knows it, and none of them have ever heard it on the mainland. He has a couple more examples of the same kind of doggerel, but I have not taken them down.
Both in English and in Irish the songs are full of words the people do not understand themselves, and when they come to say the words slowly their memory is usually uncertain.
[やぶちゃん注:原文では最後の一連の前には、御覧の通り、“***”が入っているが、底本にはない。このアスタリスクは恐らくそこにあった数連を省略したこと、そしてこの最後に示された連が正真正銘、最後のフレーズであることを示唆するものと私は判断する。なお、私は世界史は苦手である。複数の叙述を勘案しながら注を附したが、誤りがあった場合は、御教授願えれば幸いである。
「少スキピオ」は「小スキピオ」で、プブリウス・コルネリウス・スキピオ・アエミリアヌス・アフリカヌス・ヌマンティヌス(Publius Cornelius
Scipio Aemilianus Africanus Numantinus B.C.185年~B.C.129年)のこと。共和政ローマの軍人政治家。第三次ポエニ戦争の際にはカルタゴの三重防壁を破るために遣わされ、B.C.146年、カルタゴを陥落させ、都市も市民も悉く破壊虐殺した。呼称の「小」は、第二次ポエニ戦争で活躍し、カルタゴの将軍ハンニバルをザマの戦いで破って戦争を終結させた同じく共和政ローマの軍人政治家「大スキピオ」プブリウス・コルネリウス・スキピオ・アフリカヌス・マイヨル(Publius
Cornelius Scipio Africanus Major B.C.236年~B.C.183年頃)と区別するため。小スキピオは大スキピオの妻の甥で義理の孫に当たる(以上は主にウィキの「スキピオ・アエミリアヌス」によった)。
「ブリアン」“Brian”はアイルランドの偉大なる王にして英雄ブライアン・ボル(Brian Boru 941年~1014年 ゲール語:Brian Bóroimhe)。ヴァイキングに兄を殺されて王となった彼は、ヴァイキングへの復讐と、その布石としてのアイルランド全土の政治統一に誠心を傾け、遂に1002年に統一を成し遂げ、ヴァイキングの追放に成功した(但し、その生き残りに暗殺されたという)。
「デンマルク人」“the Danes”は「デーン人」で、古くデンマーク地方に居住していた北方ノルマン人一族。8世紀から11世紀にかけて、海上からイングランドをはじめとしたヨーロッパ各地に侵攻し、スカンディナヴィアの海賊、通称ヴァイキングの主流を成した。キリスト教に改宗後、デンマーク王国として統一国家を創設した。
「聖ルスがオーリムの戰で斃れた時」「聖ルス」はサン・ルース侯爵(Charles Chalmont Marquis of St Ruth 1650 年~1691年)。フランスの将軍。カトリック信者の多いアイルランドが支持していた“Jacobite”( ジャコバイト:イギリスの名誉革命のウィリアム3世支持派の“Williamite”ウィリアマイトに対抗したジェームズ2世支持派の反革命勢力でフランスも支持していた)に組してウィリアマイト戦争をアイルランドで戦ったが、ゴールウェイ州のオーリムの戦いで戦死した。
「サースフィールドをリメリックの攻圍で乘せたりした」Patrick Sarsfield (パトリック・サーズフィールド 1660年~1693年)はウィリアマイト戦争末期、ウィリアマイト軍は1690年にジャコバイトの根拠地である南西部マンスターの都市リムリックでの包囲戦では降伏の最後まで善戦したジャコバイト騎兵隊指揮官であった。
「ジェームズ王」はイングランド・スコットランド・アイルランドの王ジェームズ7世=ジェームズ2世(James VII of Scotland and
James II of England 1633年~1701年 在位:1685年~1688年)のこと。スコットランド王としてはジェームズ7世、イングランド王・アイルランド王としてはジェームズ2世。三ヶ国にとってジェームズは歴史上最後のカトリック信者の国王である。名誉革命によって王位を逐われ、王国はウィリアム3世とメアリー2世による共同統治となった。先に掲げたジャコバイトとはウィリアム・メアリーでなくジェームズこそ正統なる王であるとする人々を指す(以上は、ウィキの「ジェームズ2世(イングランド)」を参照した)。
「ボイン河の激戰」ボイン川の戦いは1690年7月1日にウィリアム3世のイングランド・オランダ連合軍とジェームズ2世のスコットランド軍の間で行われた戦い。アイルランドのレンスター地方ボイン川河畔で行われ、勝利したウィリアムがイングランド王位を決定的なものとした戦争(以上は、ウィキの「ボイン川の戦い」を参照した)。ジェームズ2世は敗残の自軍を置き去りにしてフランスに亡命したため、敗残兵たちからは“Séamus á Chaca(James the
Shit)”「くそったれのジェームズ」という蔑称されたという(ここは、ウィキのウィキの「ジェームズ2世(イングランド)」を参照した)。
「到頭ちんばになつちやつた」は、何かの比喩(若しくは皮肉)が隠されているような気がする。
「ヲーターローの戰」ナポレオンのワーテルローの戦いは1815年であるから、一気に百年、時空が飛ぶ。
「ダニエル・オーコンネル」(1775年~1847年)はアイルランド解放運動の指導者。英国の支配に抵抗し、「カトリック教徒協会」を率いて1829年にカトリック教徒解放法を成立させ、アイルランドの分離独立運動を推進、1841年にはカトリック初のダブリン市長となったアイルランドの英雄である。
「王黨」“the Tories”。“Tory”の原義はイギリスのトーリー党員のこと。17世紀末から1832年頃まで、議会に対する王権の優位を主張した。現在のイギリスの二大政党の一つである「保守党(保守統一党)」の前身。現在でも「保守党」は“Tory”と俗称される。
「その歌には英語・愛蘭土語共に此の島の人達にすらわからない言葉が一杯あるので、それをゆつくり云ふ時は記憶が大概覺束なくなる。」原文は“Both in English and in Irish the songs are full of words the people do not understand themselves, and when they come to say the words slowly their memory is usually uncertain.”。ちょっと分かり難い訳文である。「この爺さんたち(但し、中心の詠唱者は一人の老人)が歌う歌には――それが英語のものであってもアイルランド語のものであっても――どちらにも、遺憾ながら、歌っている本人たちにさえ実はまるで分かっていない(としか思われない)単語が多数含まれている。だから、歌の調子が『……うん? なんだかゆっくらになったなぁ?』と感じられる時には、それは概ね、歌っている彼らの記憶が本当のところは、あやふやな箇所なのであった」という意味である。
私の定型狂詩オリジナル訳。
さても今度はジェームズ王が、海を渡って来なすった、
アイルランドは、その岸辺、すっくと立ったもやっぱり
だけど遂にはボッキリと、折れてちんばになりにける、
ボインの川の、血みどろの、ひでえ戦さの仕舞いにゃね――
それでもまだまだ、
たとえば一人はワーテルロー――
たとえば跨る――ありゃ何と! 我らがダニエル・オコンネル!
***
勇者ダニエルと
おいらの馬はまたしても、あの修羅場へと甦る――
糞保守どもを根絶やすまで、古今東西金輪際、
おあとがよろしいようで――]
朝の間は、岩の上で逢つた子供と、くじやく羊齒を掘つてゐた。その子供は一週間前、心臟麻痺で父親を急に亡くしたので、大へん悲しんでゐた。
「世界中の金に代へても、父を亡くなしたくなかつたよ。」彼は云つた。「家は今、大へん淋しく、賴りなくなつちやつた。」
それから海軍の火夫をしてる一人の兄が、父親の死ぬ少し前に歸つて來て、立派な葬式を出して、澤山の酒を飮んだり、煙草を吸つたりしたので、金を皆使つてしまつたと話した。
「兄は世界中を廻つてね、」彼は云つた。「大そう珍らしい物を見たんだよ。イタリーから來た人や、スペインから來た人や、ポルトガルから來た人のことを話したよ。彼等の話す言葉は英語ではなくて――愛蘭土語みたいな言葉ださうだ。時時わかる言葉がある位だが。」
私たちは岩の深い裂け目だけにある羊齒の根を充分澤山掘り出した時、私はその友達に幾ペンスかを與へて、家へ送り歸した。
*
All the morning I have been digging maidenhair ferns with a boy I met on the rocks, who was in great sorrow because his father died suddenly a week ago of a pain in his heart.
'We wouldn't have chosen to lose our father for all the gold there is in the world,' he said, 'and it's great loneliness and sorrow there is in the house now.'
Then he told me that a brother of his who is a stoker in the Navy had come home a little while before his father died, and that he had spent all his money in having a fine funeral, with plenty of drink at it, and tobacco.
'My brother has been a long way in the world,' he said, 'and seen great wonders. He does be telling us of the people that do come out to them from Italy, and Spain, and Portugal, and that it is a sort of Irish they do be talking--not English at all--though it is only a word here and there you'd understand.'
When we had dug out enough of roots from the deep crannies in the rocks where they are only to be found, I gave my companion a few pence, and sent him back to his cottage.
[やぶちゃん注:原文では、次に行空きがなく繋がっているが、分けた。私は個人的に、伝承歌謡採取の狭間に挿入された、この手に取るような原色の映像のシークエンス(炉辺物語の語り映像部分が視覚に暗いだけに)がたまらなく好きだ。タルコフスキイの「鏡」のワン・シークエンスのようではないか。
「くじやく羊齒」“maidenhair ferns”。シダ植物門シダ綱シダ目ホウライシダ科ホウライシダ属クジャクシダ Adiantum pedatum 。若葉は赤みを帯びるが、夏季に緑色となり、冬季に枯れる。和名の由来は、羽状の複葉になった枝を扇のように広げ、それがクジャクの尾羽を連想させることによる。英名“maidenhair”は「オトメノクロカミシダ(乙女の黒髪羊歯)」である。ここでは根を掘っているが、Siro Kurita氏のHP「草と木と花の博物誌」の「シダの民族植物誌」の「クジャクシダ」の項に、『この孔雀が尾羽を広げたような美しいシダはヒマラヤから極東アジアを経て北アメリカまで分布している。インド・ネパール・中国での薬用の報告はないが、日本ではアイヌの人たちが葉を揉んで止血に使ったという。北アメリカでは原住民の多くの部族がこのシダを薬用している。例えば、ノースカロナイヤ州やジョージア州のチェロキー(Cherokee)は根茎の煎じ汁をリュウマチの腫れや痛みを和らげるために手で暖めて刷り込んだり、全草の絞り汁を悪寒を伴う発熱が出たときに嘔吐剤として飲ませる。また、喘息病みには葉を粉にして嗅ぎタバコのように鼻から吸い込むと効くという。ウイスコンシン州のメノミニー(Menominee)は赤痢の際の下痢止めや婦人病に根茎の煎じ汁を使う。東海岸沿いに居住するイロコイ(Iroquoi)は煎じ汁を肝臓病に、蛇にかまれたときには葉を叩いて潰したものを傷口に湿布する』。『数万年前、ベーリング海峡を渡って北アメリカに移住していった当時のモンゴロイドたちがすでに知っていた医療の知恵だったのだろう』とある。ここでの採取も私は薬用(の商品原料)と見た(特に先にシングはアランにリューマチが多いことを記してもいる)。もし、これが自家製の自宅用の薬用ではなく、薬用商品の原料であるなら、きっと本土からきた商人に言い値で安く叩かれて、二束三文の代金を貰うのではないか――私はかつて中国の安徽省の山里の青年からもっと悲しい実体験を聞いたことがあるから――と思うと、何だかあやしくものぐるほしくもなってくるのである。]
愛蘭土の詩を語つてくれる老人は、私がその中から作つた幾つかの飜譯を妙に喜んでゐる。彼の云ふ處では、私がそれを讀んでゐる間、聞いてゐるにも少しも退屈せず、それ等は古い詩の方よりずつと立派ださうである。
これは、その中の一つだが、私は出來るだけ愛蘭土語に近く飜譯してみた。――
ルカード・モール
私は破滅の悲しみを不運ゆゑと諦める、
否むは不幸となるだらう。
それはわが身につきまとふ、
淋しさゆゑの憂き歎き。
さすらひの身となつたのも、
持ち物すつかり失くしたのも、
みんな妖精達の成した業。
こんなむごい振舞ひが私に爲されたのは、
マニスティル・ナ・ルアイエであつた。
フィン・ヴァラやその一味の妖精が、
私の可愛い馬を鞄の下からつれて行つた。
皮を殘して行つたなら、
殘して行つたものとては、
此の年とつた
可哀さうぢやないか私は?
思ひ切れないあの牝馬、
まだ馬代は拂はれず、
淋しさ辛さ憂き歎き。
山でも谷でも愛蘭土の、
一番高いとりでの上も、
くまなく牝馬を探したが、
私の歎きは盡きはせぬ。
朝は早目に起き出でて、
パイプに赤い火をつけて、
嬉しいことを聞くために
クノック・モイエへ行つてみた。
私の牝馬を取り戻す
よい手立はないものかと
そこの人達に聞いてみた。
なければ考へなほさうと。
「御存じないか、ルカード・モール?
お前の牝馬は此處には居ない。
男の妖精に連れられて、三月前、
グレナスモイルに行つたのだ。」
私は道を大急ぎ
まつすぐ駈けて行つたらば、
お晝にならぬその先に
グレナスモイルに行き着いた。
私の牝馬を取り戻す、
よい手立はないものかと
男の妖精に聞いてみた。
なけれぼ考へなほさうと。
「御存じないか、ルカード・モール?
お前の牝馬は此處には居ない。
笛吹く騎手に連れられて、三月前、
クノック・パワー・ブリシュロ-ンに行つたのだ。」
私は道を大急ぎ
まつすぐ駈けて行つたらば、
日もとつぷりと暮れた頃、
クノック・パワー・ブリシュローンに行き着いた。
其處には大勢人が居て
皆んな手袋編んでゐる
編み手のやうに思はれた。
こんな處で噂を人は聞くだらう。
私の牝馬を取り戻す、
よい手立はないものかと
騎手の男に聞いてみた。
なければ考へなほさうと。
「御存じないか、ルカード・モール?
お前の牝馬は此處には居ない。
クノック・クルーハンの宮殿の
裏のはづれにそれは居る。」
私は道を大急ぎ
まつすぐ駈けて行つたらば、
休みもしないで、私は、
宮殿の前に行き着いた。
其處には大勢人が居て、
男も女も國中の
人が皆んな集まつて、
お祭り騷をやつてゐた。
アーサー・スコイル(?)が立上り、
音頭を取つて初めれば、
皆んな面白さうだ、愉快だ、活潑だ、
私も一緒に踊り出さうとした程に。
足をぱつたり踏み止めて、
皆んなは笑ひ出してゐた。――
「御覧よ、ルカード・モールを、
あいつは小さい牝馬を探してゐるんだ。」
私が話しかけたのは
醜い顏のこぶ男、
牝馬を出さねば肋骨を
折つてやらうと思つてた。
「御存じないか、ルカード・モール?
お前の牝馬は此處には居ない、
私の母に手綱をとられ、
レンスターのアルビンへ行つたのだ。」
私は道を大急ぎ
レンスターのアルビンヘやつて來た。
其處で婆さんに出逢つたが――
私の言葉を聞いて喜ばぬ。
私は婆さんに尋ねたが、
英語でどんどん云ひ出した。
「行つてしまへ、馬鹿野郎、
お前の云ふことが氣に食はぬ」
「これこれもうし、お婆さん、
私に英語はよしてくれ、
誰が聞いてもわかるやうな、
言葉で私に話してくれ。」
「牝馬のことなら教へてもよいが、
お前の來方が遲かつた。――
私は昨日あの馬で、
コナル・カーに鳥打帽子を造つてやつた。」
私は道を大急ぎ
寒い汚い思ひして、
男の妖精に出くはした。
彼はルアイエで寢轉ろんでゐた。
「牛を失くした奴は可哀さう。
羊を失くした奴も可哀さう。
だが、馬を失くした奴だけは
世界の遠くへ行かねばならぬ。」
*
The old man who tells me the Irish poems is curiously pleased with the translations I have made from some of them.
He would never be tired, he says, listening while I would be reading them, and they are much finer things than his old bits of rhyme.
Here is one of them, as near the Irish as I am able to make it:--
RUCARD MOR
I put the sorrow of destruction on the bad luck,
For it would be a pity ever to deny it,
It is to me it is stuck,
By loneliness my pain, my complaining.
It is the fairy-host
Put me a-wandering
And took from me my goods of the world.
At Mannistir na Ruaidthe
It is on me the shameless deed was done:
Finn Bheara and his fairy-host
Took my little horse on me from under the bag.
If they left me the skin
It would bring me tobacco for three months,
But they did not leave anything with me
But the old minister in its place.
Am not I to be pitied?
My bond and my note are on her,
And the price of her not yet paid,
My loneliness, my pain, my complaining.
The devil a hill or a glen, or highest fort
Ever was built in Ireland,
Is not searched on me for my mare;
And I am still at my complaining.
I got up in the morning,
I put a red spark in my pipe.
I went to the Cnoc-Maithe
To get satisfaction from them.
I spoke to them,
If it was in them to do a right thing,
To get me my little mare,
Or I would be changing my wits.
'Do you hear, Rucard Mor?
It is not here is your mare,
She is in Cnoc Bally Brishlawn
With the fairy-men these three months.
I ran on in my walking,
I followed the road straightly,
I was in Glenasmoil
Before the moon was ended.
I spoke to the fairy-man,
If it was in him to do a right thing,
To get me my little mare,
Or I would be changing my wits.
'Do you hear Rucard Mor?
It is not here is your mare,
She is in Cnoc Bally Brishlawn
With the horseman of the music these three months.'
I ran off on my walking,
I followed the road straightly,
I was in Cnoc Bally Brishlawn
With the black fall of the night.
That is a place was a crowd
As it was seen by me,
All the weavers of the globe,
It is there you would have news of them.
I spoke to the horseman,
If it was in him to do the right thing,
To get me my little mare,
Or I would be changing my wits.
'Do you hear, Rucard Mor?
It is not here is your mare,
She is in Cnoc Cruachan,
In the back end of the palace.'
I ran off on my walking,
I followed the road straightly,
I made no rest or stop
Till I was in face of the palace.
That is the place was a crowd
As it appeared to me,
The men and women of the country,
And they all making merry.
Arthur Scoil (?) stood up
And began himself giving the lead,
It is joyful, light and active,
I would have danced the course with them.
They drew up on their feet
And they began to laugh,--
'Look at Rucard Mor,
And he looking for his little mare.'
I spoke to the man,
And he ugly and humpy,
Unless he would get me my mare
I would break a third of his bones.
'Do you hear, Rucard Mor?
It is not here is your mare,
She is in Alvin of Leinster,
On a halter with my mother.'
I ran off on my walking,
And I came to Alvin of Leinster.
I met the old woman—
On my word she was not pleasing.
I spoke to the old woman,
And she broke out in English:
'Get agone, you rascal,
I don't like your notions.'
'Do you hear, you old woman?
Keep away from me with your English,
But speak to me with the tongue
I hear from every person.'
'It is from me you will get word of her,
Only you come too late—
I made a hunting cap
For Conal Cath of her yesterday.'
I ran off on my walking,
Through roads that were cold and dirty.
I fell in with the fairy-man,
And he lying down in the Ruadthe.
'I pity a man without a cow,
I pity a man without a sheep,
But in the case of a man without a horse
It is hard for him to be long in the world.'
[やぶちゃん注:栩木氏は主人公の名を『リカード・モア』と音写されている。本詩ではゲール語の架空と思われる地名が多く出現するが、その殆どが音写されるばかりで分かり難い。以下、地名の意味の多くを栩木氏の訳に頼った。引用部はすべて引用であることを明記した。
「マニスティル・ナ・ルアイエ」原文“Mannistir na Ruaidthe”。栩木氏は『ルア修道院村』と訳されて、ルビで『マナスター・ナ・ルア』と音写されている。英語で男性の修道院は“monastery”で、自動翻訳機にこれを掛けるとゲール語で“mainistir”と出る。“n”がダブっているが、確かにこれである。但し、“Ruaidthe”という地名は同定出来なかった。
「私の可愛い馬を鞄の下からつれて行つた。」原文も“Took my little horse on me from under the bag.”となっているが、この日本語は意味不明だ。これは何かの性的なスラングなのではないか? 栩木氏は『おれのかわいい牝馬
「フィン・ヴァラ」前掲したミユシャ氏のHP「妖精辞典 夜明けの妖精詩」に、アイルランドのコナハト地方の妖精の王とあり、「神様コレクション@wikiフィンヴァラ」には、『ケルト神話の神。ダグザに妖精の王を命じられ、妖精の最高王となった。地方の女王たち(クリオズナ、イーヴィン、アーネ)を従える。キルワン王の妻エタインを誘拐したこともあるが無傷で返し』、『キルワン家の後援者にして守護霊となった』とある。どうもフィン・ヴァラには女性誘拐癖があるらしい(それを配下に用いるためか)。女王たちを統括するとあるが、フィン・ヴァラ自身は男性の妖精である。前の注で述べた通り、最終場面で実際に彼フィン・ヴァラが登場する。彼が妖精の王ならば、やはり最終連の呪言は重いメタファーを含んでいると読むべきである。
「此の年とつた
「思ひ切れないあの牝馬、」“My bond and my note are on her,”。姉崎氏の訳は恐らく、“bond”を絆、“note”を大事な存在の意で採り、意訳したものと思われる。但し、前の一切合財持って行かれてすっからかんという事実の提示と、次のフレーズの『まだ馬代は拂はれず』の極めて現実的な物謂いから考えると、この“bond”は「債券」、“note”は「約束手形」か「紙幣」(有り金)を意味していると考えた方が自然か(栩木氏も『公債証書』と『現金』で訳しておられる。しかし、一読、姉崎氏のセンチメンタルな訳も捨て難くはある。
「クノック・モイエ」原文“Cnoc-Maithe”。現在のアイルランドのメイヨー郡の町“Knock”(クノック)があるが、“Cnoc”は一般名詞で「丘」の意だから、こことは言えない。この町は現在、ゲール語で“Cnoc”“Cnoc Mhuire”と綴る。一見、“Mhuire”は似ているが、「聖母マリア」のことで違う。因みに、メイヨー郡のクノックは1879年8月21日に聖ヨセフ・聖ヨハネそして聖母マリアが顕現したという伝承で知られる町であるが、老人の古歌はもっと古い時代のものと思われる。同定不能。栩木氏は『秤山』とし、『クノック・マー』と音写されている。丘であること、文脈からもこれは妖精の棲む丘なのであろう。
「私の牝馬を取り戻す/よい手立はないものかと/そこの人達に聞いてみた。/なければ考へなほさうと。」は、栩木氏の訳は丘の妖精の中に牝馬を奪った奴がいるという感じで、遙かに指弾的な強い物言いの訳となっている。人と妖精の丁々発止が面白い。是非、比較してお読みあれ。
「ゲレナスモイル」栩木氏は『焼き枯れ谷』と訳し、『グレナスモル』と音写されている。先の「クノック・モイエ」同様、妖精の棲家で、実際の地名ではないのであろう。
「クノック・パワー・ブリシュロ-ン」栩木氏は『昼飯砦山』と訳しておられる。同様に妖精の棲家であるが、ここは世界中の国に散らばっている妖精たちの集合地であるようだ(次注参照)。
「皆んな手袋編んでゐる」該当箇所は三行目の“All the weavers of the globe,”であるが、これは “weavers”の「織工」から“globe”を「手袋」としてしまった誤訳である。これは「全世界」「地球」の「織り手」たち総てが、この「ゲレナスモイル」に集まっている、だからここには私の牝馬の行方を噂として知っている人間が必ずいるはずだと、私が思うシーンである。そうすると「世界中の織り手」というのは、世界のあらゆる国の話の織り手(ストーリー・テラー)の妖精が集まっているということを言うか? 栩木氏もそのように訳されておられる。
「クノック・クルーハン」栩木氏は『焼き入れ山』と訳し、『クノック・クルアハン』と音写されている。これも妖精の棲家であろうが、宮殿とあるから、妖精の王若しくは女王の居る場所らしい。
「アーサー・スコイル(?)」この「?」は“Arthur Scoil (?)”と原文にあるもの。聞き書きの際、若しくは後に「アラン島」を活字化した際に、綴り又は記憶が不確かであったということ示しているようである。
「こぶ男」“humpy”。背むし男。脊椎奇形である。
「レンスターのアルビン」“Alvin of Leinster”「レンスター」(ゲール語 Laighin, Laigin)はアイルランドの東岸に位置し、現在はウィックロー州をはじめとして12の州からなる、アイルランドの産業の中心地。「アルビン」不詳。因みに、アルビンという名(人名)の語源は「妖精の友」である。
「コナル・カー」不詳。妖精にカーという名の者がいるが、これは女性であるので違う。
「牛を失くした奴は可哀さう。/羊を失くした奴も可哀さう。/だが、馬を失くした奴だけは/世界の遠くへ行かねばなちぬ。」“'I pity a man without a cow,/I pity a man without a sheep,/But in the case of a man without a horse/It is hard for him to be long in the world.'”。これは騎馬民族に於ける馬の霊性を示すものであると同時に、不吉な言上げである。牛や羊を亡くしても哀しむばかりで、その内、忘れっちまうが、馬を亡くすと、その激しい悲しみ故に死に至る、というのである。則ち、ルカード・モールは、妖精の言葉を聞いた時、自分が死を免れないことを悟ったのだ――いや、そもそもが妖精の棲家を彷徨した彼は、既にして――愛する牝馬を奪われたその直後に――死んでいるのではなかろうか? だからこそ、牝馬が攫われた後には何もかもが消え去り、残ったのは――ルカード・モールに引導を渡す司祭だけだったのではあるまいか? またここは、ケルトの古形にあっては、死んだ馬は世界の果てへと人を導く霊界の使者であると読み替えることも出来るのではあるまいか。私のこの見解はただの勝手な想像である。大きな誤りがある場合は、是非とも識者の御斧正をお願いしたい。
この長詩もオリジナルに訳したい欲求に駆られるが、栩木氏の謡曲のような「~着きにけり」が現代文に交る独特の名訳を越えることは難しそうなので、涙を呑んでやめる。栩木氏の訳書をお読みあれ(しかし、この全文を謡曲に擬古文化してみたい欲求は抑えられぬ。今度、私だけの手慰みのためだけにやってみようとは思っている)。]
今朝、海近くの岩の上に長い間休んで、幾羽かの冠烏が、岩の上に貝を落しては碎いてゐるのを眺めてゐた。すると一羽が何か白い大きな物をくはへてゐると見えたが、それを幾度落しても壞れなかつた。私は石を取つて、それが落ちて來た時、鳥を追ひ除けようとしたが、いつも鳥の方が早く、それに
それから餘程たつて、現代生活に就いて知りたがつてゐる或る靑年と長い間話した。私は最近聞いた株の取引所に於ける念入りな企みや、買占めやらを説明した。充分、了解をつかせると、彼は面白さうに大聲を立てた。
「さうか、」彼は云つた。「その人達も我我のやうなえらいならず者とは、驚いたことだ。」
*
This morning, when I had been lying for a long time on a rock near the sea watching some hooded crows that were dropping shellfish on the rocks to break them, I saw one bird that had a large white object which it was dropping continually without any result. I got some stones and tried to drive it off when the thing had fallen, but several times the bird was too quick for me and made off with it before I could get down to him. At last, however, I dropped a stone almost on top of him and he flew away. I clambered down hastily, and found to my amazement a worn golf-ball! No doubt it had been brought out in some way or other from the links in County Glare, which are not far off, and the bird had been trying half the morning to break it.
Further on I had a long talk with a young man who is inquisitive about modern life, and I explained to him an elaborate trick or corner on the Stock Exchange that I heard of lately. When I got him to understand it fully, he shouted with delight and amusement.
'Well,' he said when he was quiet again, 'isn't it a great wonder to think that those rich men are as big rogues as ourselves.'
[やぶちゃん注:「冠烏」既出。スズメ目カラス科ハイイロガラス(ズキンガラス)Corvus cornix のこと。ハシボソガラス Corvus corone の亜種とされる。
「驚いたことに、それはすり切れたゴルフ・ボールであつた!」今でこそよく知られる現象であるが、それが実に百十一年も前にここに報告されていることが素晴らしい! カラスのこの行動については、何度も繰り返し同じ行動をとることから、既に食物としての卵の誤認ではなく、ゴルフボールを卵に見立てた遊びをしている可能性が高いとされている。なお、本土からイニシマーンまでは直線距離で最短でも15㎞弱ある。]
老物語師は、鷲と戰つた男を歌つた長い吟唱曲を教へてくれた。それは少し不規則で曖昧な所はあるが、學者と一緒に飜譯した。
[やぶちゃん注:「學者」は既出のアラン島の人の中でも多少の教養を持った「郷土史研究家」の意。以下、底本では物語全体が一字下げである。]
フェリムと鷲
朝早く起きると、困つたことがあつたので、日曜のことだが、靴を穿いて「死者の谷」の中にあるティアニーへ行つた。其處で出建つた大きな鷲は、茨の積重ねのやうに眞黑く、いかめしさうに立つてゐた。
私はそれに呼びかけた。やくざ者よ、馬鹿者よ【、】國で一番偉いならず者の、クラン・クリオパス族の女と馬鹿者の間に生れた息子よ。私の一番よく啼く可愛い牡雞を盜んだお前に、此の呪と私の七つの呪がかかり、好い運には決して逢はないだらうと。
【鷲】「お前の氣が確かなら、私に餘りひどい呪をかけてはならぬ。私は誓つて、お前から家賃を決して取らぬ。燒鳩の小屋に、お前が何を貯めようとも、私は羨まぬ。お前のやうな者は商賣人には打つてつけだ。
【鷲】「だが、家へ行つてノラに聞いてごらん。雞の頭をゆでてゐた若い女の名は何と云ふかと。その肋の羽は竃で燒かれた。そして皆食つちやつたが、そんなに有難くは思つてはゐないよ。」
【フェリム】「お前は嘘つきだ、泥棒だ。皆んなそんなうまい物を食つて、きつと有難からずには居られない。お前はそれを昨日食つたと、ノラが云つたぞ。そしてお前は、私が税を取る迄で、收穫の四分の一も使はないのだらう。」
【鷲】「私はフィアンナに失戀するまではよい男の子であつた。泥棒なんかする事は少しも考へず、始終手品をしたり、ゴル・マック・モルナと力競べをして遊んだりした。そして一生の終りに、お前は私をならず者にしてしまつた。」
【フェリム】「一つの函の、底深く祕めて、私は祖先の本の一部を持つてゐる。それを讀む度毎に、涙が流れ出る。由緒をしらべてわかつたが、假令お前は喧譁が好きで感謝するのが常であつても、お前はダルグ・モールの子孫なのだ。」
鷲は武具と衣服つけて、美しく裝ひ、手には選りすぐつて一番よく切れる劍を持つた。私は大鎌を手に、身にはシャツのほかなんにも着ず、二人は互ひにその日の朝早く出かけて行つた。
私たちは、山の狹間や谷間を切り分け進みながら、二人の巨人のやうだつた。暫く、どちらが偉いともわからず、私たちは取り組んで、互ひにひしめき合ひする物音は、日が暮れて、彼が仕方なく止めるまで聞こえてゐた。
翌朝、私は決鬪の挑戰狀を書き、夜明けの頃に間違ひなく戰ふやうに行くと、云つてやつた。彼に與へた第二の拳で顎の骨を打ちたたき、彼は斃れて氣が付かなくなつたのは噓ぢやない。
鷲は起き上がり、私の手を取つて「お前は一生の中で逢つた一番偉い男だ。さあ、家へ行け、御機嫌よう、さらばだ。お前一人で、永遠に、愛蘭土の名譽を救つたのだ。」
ああ! 皆さん、フェリムの偉さと強さを聞きましたか? どんな大きな猛獸でも、彼が第二の拳を加へて顎を打てば、それはまる二日間、起【き】上れなかつたものだ。
[やぶちゃん注:前半部で話者が今一つ分かり難いので【 】で補った。]
*
PHELIM AND THE EAGLE
On my getting up in the morning
And I bothered, on a Sunday,
I put my brogues on me,
And I going to Tierny
In the Glen of the Dead People.
It is there the big eagle fell in with me,
He like a black stack of turf sitting up stately.
I called him a lout and a fool,
The son of a female and a fool,
Of the race of the Clan Cleopas, the biggest rogues in the land.
That and my seven curses
And never a good day to be on you,
Who stole my little cock from me that could crow the sweetest.
'Keep your wits right in you
And don't curse me too greatly,
By my strength and my oath
I never took rent of you,
I didn't grudge what you would have to spare
In the house of the burnt pigeons,
It is always useful you were to men of business.
'But get off home
And ask Nora
What name was on the young woman that scalded his head.
The feathers there were on his ribs
Are burnt on the hearth,
And they eat him and they taking and it wasn't much were thankful.'
'You are a liar, you stealer,
They did not eat him, and they're taking
Nor a taste of the sort without being thankful,
You took him yesterday
As Nora told me,
And the harvest quarter will not be spent till I take a tax of you.'
'Before I lost the Fianna
It was a fine boy I was,
It was not about thieving was my knowledge,
But always putting spells,
Playing games and matches with the strength of Gol MacMorna,
And you are making me a rogue
At the end of my life.'
'There is a part of my father's books with me,
Keeping in the bottom of a box,
And when I read them the tears fall down from me.
But I found out in history
That you are a son of the Dearg Mor,
If it is fighting you want and you won't be thankful.'
The Eagle dressed his bravery
With his share of arms and his clothes,
He had the sword that was the sharpest
Could be got anywhere.
I and my scythe with me,
And nothing on but my shirt,
We went at each other early in the day.
We were as two giants
Ploughing in a valley in a glen of the mountains.
We did not know for the while which was the better man.
You could hear the shakes that were on our arms under each other,
From that till the sunset,
Till it was forced on him to give up.
I wrote a 'challenge boxail' to him
On the morning of the next day,
To come till we would fight without doubt at the dawn of the day.
The second fist I drew on him I struck him on the hone of his jaw,
He fell, and it is no lie there was a cloud in his head.
The Eagle stood up,
He took the end of my hand:--
'You are the finest man I ever saw in my life,
Go off home, my blessing will be on you for ever,
You have saved the fame of Eire for yourself till the Day of the Judgment.'
Ah! neighbors, did you hear
The goodness and power of Felim?
The biggest wild beast you could get,
The second fist he drew on it
He struck it on the jaw,
It fell, and it did not rise
Till the end of two days.
[やぶちゃん注:原文はご覧のように、分かち書きになっている。「鷲」と「雞」と「鳩」――この伝承は鳥が絡む。直前にインサートされた話にも「冠烏」が出る――シングの書き方はその構成が実は美事に計算されて、澱みなく有機的に文章が続くことに注目したい。
『「死者の谷」の中にあるティアニー』不詳。
「クレオパス」“Cleopas”不詳。新約聖書にイエス・キリストが復活した日の午後、エマオの途上でイエスに出逢った二人の弟子のうちの一人の名前として登場するが、侮蔑の文句の中にあるので無関係か。
「燒鳩の小屋」原文“the house of the burnt pigeons”。中国をはじめ、フランス・イタリア・エジプトでは通常の料理として今でもハトの丸焼きやハト料理がある(丸焼きではないが私もイタリアで食した)。イギリスでも18世紀頃までは普通に食されていた。さすれば、これはフェリムの家(自営業)は鳩の丸焼き食わせる焼き鳥屋であることを意味している。
「燒鳩の小屋に、お前が何を貯めようとも、私は羨まぬ。」“I didn't grudge what you would have to spare/In the house of the burnt pigeons,”という部分、“spare”が分からない。これを姉崎氏は「惜しんで使わない」「節約する」から、金品か何かを「小屋」(店)の中にこっそり溜め込んでいる(家賃も払わないくせに)、という意味で捉えられたようであるが、これは寧ろ、次で「お前のやうな者は商賣人には打つてつけだ」と揶揄するところを見れば、鳩の丸焼き食わせる焼き鳥屋でありながら、実は鳩を「惜しんで使わない」、鳩「なしで済ませ」ている、羊頭狗肉的な皮肉を言っているようにも取れる。そう言えば、前段のフェリムの鷲への非難に出て来るのは「鳩」ではなく、「牡雞」である。するとフェリムは鳩頭鶏肉であったということか? そうすると次の段落の不可解さも少し腑に落ちる。ハトとは真っ赤な偽りで、ニワトリを縊り、頭はこっそりゆで汁にでもし、ばれたら困るニワトリの羽は悉く爐で灰にしている、という訳である。栩木氏もほぼそうした羊頭狗肉的ニュアンスで訳しておられるが、最終行は姉崎氏の「お前のやうな者は商賣人には打つてつけだ」という訳とは全く異なっている。当該書をお読みになられたい。
「そしてお前は、私が税を取る迄で、收穫の四分の一も使はないのだらう。」これもまた、ノストラダムスの大予言並の難解さである。原文は“And the harvest quarter will not be spent till I take a tax of you.'”で、“harvest”は古語廃語で方言の収穫の「秋」で、その一年の1/4の四季支払い期の一つ“harvest quarter”を指していないか? 更に、それを消費させない、というのはそこまで待たないでという意味ではないか? そうして“tax”は税ではなく、口語の「代金」であり、全体で「お前には(鷲)には四季支払い期で、次に迫っている秋の代金請求(が終わる)その時よりも前までに、きっときっちり(お前盗んだ雄鶏の代金を)請求するぞ!」という意味ではあるまいか? 栩木氏の訳もほぼそうしたコンセプトである。
「私はフィアンナに失戀するまではよい男の子であつた。」原文“'Before I lost the Fianna/It was a fine boy I was,”。この“Fianna”は女性の名ではなく、アイルランドの神話フェニアンサイクルに登場する英雄フィン・マックールが率いるフィアナ騎士団のことである。従って姉崎氏の“lost”「失戀」というのも正しくなく、その壮大にして複雑なフェニアン・サイクル神話の最後にフィアナ騎士団が壊滅させられることを指すものと思われる。私自身、この注を附すまで全く知らない神話であったが、ここは従って「私はフィアナ騎士団が亡ぼされるまでは/一個の見目麗しい少年であったのに」という意味であろう。則ち、この老いた荒鷲はかつて伝説中のフィアナ騎士団の騎士の一人であったということであろう。栩木氏が文字通り、正にぴったりくる「若鷲」と訳しておられるのは絶妙である。
「ゴル・マック・モルナ」“Gol MacMorna”。勇者にしてフィアナ騎士団の元団長。後に団長となる英雄フィン・マックールの父は彼に殺されており、宿敵であったが、紆余曲折を経てフィンの配下となった(一説には決闘によって倒したとも)。その辺りの経緯は、参照したウィキの「フィン・マックール」を読まれたい。
「泥棒なんかする事は少しも考へず、始終手品をしたり、ゴル・マック・モルナと力競べをして遊んだりした。そして一生の終りに、お前は私をならず者にしてしまつた。」“It was not about thieving was my knowledge,/But always putting spells,/Playing games and matches with the strength of Gol MacMorna,/And you are making me a rogue/At the end of my life.'”。“my knowledge” 「私の智」「私の能力」は前後に関わる。だから“Playing games”を「手品をしたり」とするのはいただけない。“game”と“match”が対になっているから、その頃の彼(騎士であった頃の「鷲」)は、一人でする勇壮な“game”「狩り」と、例えば最強の力持ちであった勇者ゴル・マック・モルナを相手に互角に「力競べを」する(レスリングや武術試合をする)のが彼の能力発揮の専ら、日常であったと言うのである。そんな孤高にして高潔な過去世を持つ「私を」、「お前は」この期に至って、冤罪である雄鶏の盗人として誹謗中傷し、あろうことか今まさにこの「一生の終りに」、「ならず者」扱いにしやがった、と「鷲」は逆切れしているのである。ここでも栩木氏の訳は絶好調で、「鷲」一人称を「ワシ」(儂)と訳されており、いい感じだ。
「祖先の本の一部」“a part of my father's books”はアイルランド神話が書かれた史伝類のことであろう。ここでそれが「一つの函の、底深く祕めて」(家宝として筐底深く大切にされてきた)事実、「それを讀む度毎に」、フェリムの目から「涙が流れ出る」という事実から、ここでは「鷲」「の由緒」ばかりではなく、フェルムの先祖自身も正当なフェニアン・サイクル神話の中の重要な登場人物であることが分かる。
「假令お前は喧譁が好きで感謝するのが常であつても、お前はダルグ・モールの子孫なのだ。」“That you are a son of the Dearg Mor,/If it is fighting you want and you won't be thankful.'”。「ダルグ・モール」不詳。意味はゲール語で「赤い巨人」である。このフェルムの謂いからはアイルランド古神話に登場する悪役・裏切り者であり、最後には敗者となる人物であろうと思われる。スコットランドの高山に“Carn Mor Dearg Arete”カーン・モア・ジェレック・アレートと呼ばれる馬蹄形の稜線を持った山があるが、これはこの「赤い巨人」が住んだか化したものということか。最終行は「假令お前は喧譁が好きで感謝するのが常であつても、」とあるが、ここは「喧譁が好きで感謝する」と順接で続けたのでは意味が取れない。「鷲よ、意気高々にお前が私に真剣勝負を望んだとしても、しかしな、最後にゃ負けるんだ――これはフェルムの自己肥大や嚇しというより、私(やぶちゃん)には、それが恐らくダルグ・モールの運命の神話上の約束事なのではないかと思う――そうして貴様は、私の前に斃れ這いつくばって、必ずや、感謝の祈りをせざるを得なくなるのさ。」といった意味であろう。どこで「鷲」が「人型」になるのかは、意見の分かれるところであろうが、この次の段からは「鷲」も人型となり、フェルムも巨大化してウルトラ・ファイト(ウルトラ・シリーズの申し子である私は、あの番組は大嫌いである)の様相を呈する。初めっから人型であったとしても文脈上はおかしくはない。但し、私は冒頭に述べた通り、最初は鳥類の「ワシ」でないと、神話的叙事の面白味が半減するように思う。
「二人は互ひにその日の朝早く出かけて行つた。」“We went at each other early in the day.”。翌朝、それぞれが果し合いの場に出向いて互いに対峙した、の意。
「日が暮れて、彼が仕方なく止めるまで聞こえてゐた。」“From that till the sunset,/Till it was forced on him to give up.”は、「日が暮れて」暗くなって互いに相手が見えなくなって「仕方なく止め」た、という意味であるが、栩木氏の訳では、相手は鷲だから『鳥目』で、夜は戦えないという設定で訳されており、実に味な訳である。
「彼は斃れて氣が付かなくなつたのは噓ぢやない。」“He fell, and it is no lie there was a cloud in his head.”であるから、「噓じゃないぜ――暫くの間、鷲は仰向けになったまま、立ち上がることが出来なくなって、彼の頭(顔面)の上を雲が流れてゆくばかりだったのさ。」といった感じか。
「お前一人で、永遠に、愛蘭土の名譽を救つたのだ。」原文は“You have saved the fame of Eire for yourself till the Day of the Judgment.”で省略がある。フェルムは古神「鷲」をうち倒した。負けた「鷲」がそれを
私は此の群島の人達をよく知つてゐるつもりではあるが、彼等の生活の何か新しい原始的な特色に出逢はない日とては一日もない。
昨日、或る家に行つたが、其處の内儀さんは働いてゐて、だらしない
今夜は他の家へ行き、その家の人達と夜遲くまで話してゐた。幼い男の子――その家の獨り子――が眠くなると、お婆さんはその子を膝に載せて歌ひだした。その子がうとうとしてくると、次第にその着物を脱ぎ取つて、その子の身體中をそつと爪で掻いてやつた。それから壺の水を少し取つて足を洗ひ、寢床に寢かせた。
家へ歸つて行く途中、風で砂が顏に吹きつけ、行く手が殆んどわからなかつた。私は帽子で口と鼻を塞ぎ、片手を目に當てて、砂の穴や岩を足で探りながら歩かなければならなかつた。
*
Well as I seem to know these people of the islands, there is hardly a day that I do not come upon some new primitive feature of their life.
Yesterday I went into a cottage where the woman was at work and very carelessly dressed. She waited for a while till I got into conversation with her husband, and then she slipped into the corner and put on a clean petticoat and a bright shawl round her neck. Then she came back and took her place at the fire.
This evening I was in another cottage till very late talking to the people. When the little boy--the only child of the house--got sleepy, the old grandmother took him on her lap and began singing to him. As soon as he was drowsy she worked his clothes off him by degrees, scratching him softly with her nails as she did so all over his body. Then she washed his feet with a little water out of a pot and put him into his bed.
When I was going home the wind was driving the sand into my face so that I could hardly find my way. I had to hold my hat over my mouth and nose, and my hand over my eyes while I groped along, with my feet feeling for rocks and holes in the sand.
[やぶちゃん注:原文では、次に行空きがなく繋がっているが、分けた。]
朝の間中、私は或る爺さんと一緒にゐた。爺さんは家のための藁繩を作つてをり、働きながら私と話した。彼は若い時、船乘であつて、最初、ドイツ人、イタリヤ人、ロシヤ人のことに就き、或ひは港町の有樣に就いて澤山話をした。それから話は中の島のことになつて行き、こんな話をしたが、それは島と島の間にある妙な嫉妬心が覗へる。――
昔、わし等はずつと異教徒だつた。それで教父達が來て、神に就いてまた世界の創造に就いて、わし等に教へるのが慣ひだつた。中の島の人達は一番後までも拜火教の、或はその當時あつた何かの信仰を持ち續けてゐた。だが、結局彼等の中にも教父が來て、その云ふことに耳傾けるやうになつた。尤も、晩には信ずると云つておきながら、その翌朝は信じないと云ふ有樣だつたが。終に教父は彼等を説き伏せ、一軒の教會を建てることになつた。教父は石で仕事をする時、皆と一緒に使ふ道具を持つてゐた。教會が半ば出來上つた時、島の人達は教父が寢てしまふと、ひそかに相談して、本當に信仰して間違ひのないものかどうかを試さうとした。
頭株の男が立ち上つて云ふには、さあ出かけて行かうぢやないか、そして道具を皆、崖から投げ捨ててしまはう。若し神といふやうな者があつて、教父が、その云ふやうに神に知られてゐるなら、我我が道具を投げ捨てたやうに、彼はそれを海から拾ひ上げることが出來るだらうから。
そこでその人達は出かけて行つて、その道具を崖から投げ捨てた。
朝になつて、教父が教會に來ると、仕事する人達は皆石の上に坐つて、仕事をしてゐない。
「何故、お前達は怠けてゐるのか?」教父が尋ねた。
「わし等は道具を持つてゐないのです。」 皆はさう云つて、それから自分達のした事をすつかり話した。
教父は跪いて、道具が出て來るやうにと祈り、また何處の人達も中の島の人達ほど、馬鹿でないやうに、そして神は世の終りまで彼等の愚かな暗い心を守護して下さるやうにと神に祈つた。そのために、あの島の人達は口ごもらずには話を全部云ふことが出來ず、或ひは間違ひなく、どんな仕事でも最後までやり通すことが出來ない。
*
I have been sitting all the morning with an old man who was making sugawn ropes for his house, and telling me stories while he worked. He was a pilot when he was young, and we had great talk at first about Germans, and Italians, and Russians, and the ways of seaport towns. Then he came round to talk of the middle island, and he told me this story which shows the curious jealousy that is between the islands:--
Long ago we used all to be pagans, and the saints used to be coming to teach us about God and the creation of the world. The people on the middle island were the last to keep a hold on the fire-worshipping, or whatever it was they had in those days, but in the long run a saint got in among them and they began listening to him, though they would often say in the evening they believed, and then say the morning after that they did not believe. In the end the saint gained them over and they began building a church, and the saint had tools that were in use with them for working with the stones. When the church was halfway up the people held a kind of meeting one night among themselves, when the saint was asleep in his bed, to see if they did really believe and no mistake in it.
The leading man got up, and this is what he said: that they should go down and throw their tools over the cliff, for if there was such a man as God, and if the saint was as well known to Him as he said, then he would be as well able to bring up the tools out of the sea as they were to throw them in.
They went then and threw their tools over the cliff.
When the saint came down to the church in the morning the workmen were all sitting on the stones and no work doing.
'For what cause are you idle?' asked the saint.
'We have no tools,' said the men, and then they told him the story of what they had done.
He kneeled down and prayed God that the tools might come up out of the sea, and after that he prayed that no other people might ever be as great fools as the people on the middle island, and that God might preserve theft dark minds of folly to them fill the end of the world. And that is why no man out of that island can tell you a whole story without stammering, or bring any work to end without a fault in it.
[やぶちゃん注:「教父は石で仕事をする時、皆と一緒に使ふ道具を持つてゐた。」原文は“the saint had tools that were in use with them for working with the stones.”であるが、妙な直訳である。因みに、ここは語部の爺さんが特に“saint”と使っているので「聖人」と訳したい。素直に「皆が教会造りの石切りに用いる道具はその聖人さまが用意した。」でよいのではなかろうか。
「そのために、あの島の人達は口ごもらずには話を全部云ふことが出來ず、或ひは間違ひなく、どんな仕事でも最後までやり通すことが出來ない。」これを読むと、イニシーアの島民の素朴なイニシマーン島民への嫉妬以前に、私はつくづく神は気まぐれだと、溜め息が出るのである。誰より素朴なイニシマーン島の民の話下手や仕事の貫徹不徹底は、愚かな彼等へのヤーハウェの神罰という解釈が否応なしにもたらされるからである――キリスト教では神を試してはいけないのは分かる――しかし、それ故に神罰をそこいら中にはびこらせる「神」は、叡山の強訴となんら変わらん――と私は思うのである。]
私は彼に、中の島のパット・ディレイン爺さんを知つてゐるか、そして常に話す面白い話を聞いたことがあるか、と聞いた。
「私ぐらゐあの人をよく知つてゐる者はないだらう。」彼は云つた。「私は時時、あの島の人達にカラハを造つてやりに行く事があるから。或る日、私が丁度新しいカラハにタールを塗つて居ると、彼は私の處へやつて來て、ズボンの膝頭に雨がしみないやうに少しタールを塗つてくれないかと云つた。
私は刷毛を取つて、私が何をやつてゐるかわからないうちに、彼の足の所までタールを塗つてしまつた。『さあ、あつちを向いてごらん。何處でも今度は腰掛けられるだらう。』【と】私は云つた。するとタールが肉に熱く感じて來たので、私を怨み出した。惡い事をしちやつたと思つたね。」
此の爺さんは愛蘭土の何處ででも出逢ふ快活な、茶目氣のある型の人で、イニシマーンに目立つた地方的の特質を持つてゐなかつた。
私たちは語り疲れたので、私は手品のいくつかをやつてみせると、いくらか見物人が集まつて來た。皆んな行つてしまふと、今一人の老人が入れ代りにやつて來て、妖精に就いて語り初めた。或る晩のこと、彼が燈臺から家へ歸る途中、後から人が馬に乘つて來るやうな氣がしたので、立止つて待つてゐたが、誰も來ない。それから岩の上で、人が丁度馬を捉へてゐるやうな音が聞こえたが、直ぐ止んでしまつた。後の方でする物音は、行くに從つて段段大きくなつて來た。それは恰かも廿匹位の馬と思へたが、少しすると、百匹或ひは千匹の馬が後から驅足で來るやうであつた。道が盡きて踏段の處へ來ると、何か彼に突き當り、そして彼は岩の上に打ち倒され、手に持つてゐた鐵砲は身體より向うの野原に落ちてゐた。
「私はその當時の受持の坊さんに、それは何だらうと尋ねてみたら、」彼は云つた。「それは墮落した天使だと云つた。さうより他にわからない。」
「又或る時のこと、」彼は續けて云ふ。「私が、崖になつてその下に小さな穴のある處へ來かかると、その傍で或ひはその中で、笛の音が聞こえた。その時は、夜明け前だつたがね。とにかく、不思議なことはあるものだ。三十年前だつたが、或る晩、-人の男が來て、その人のお内儀さんがお産すると云ふので、私の女房を連れて行つた。
その男は燈臺や海上警察署に何か關係を持つてゐて、プロテスタントだつたが、そんな事は何も信じてゐない人たちの一人で、我我を馬鹿にしてゐるのだ。さて、その男が私の女房の支度をしてゐる間に、一クォートの酒を取つて來てもらひたい、若し怖かつたら一緒に行つてやる、と云ふ。
私は怖くないと云つて獨りで出かけた。
その歸り途で、道に何かゐるやうだ。私も馬鹿でなかつたら、砂の上からためつすがめつ行くところだつたが、いきなりその方へ行つて、遂にそれに近よつた――つい餘り近より過ぎた――その時、「デ・ブロフンディス」[聖書の詩篇にある祈りの言葉で此處では魔除けの言葉として用ひる]と云へばこのやうな生き物は向つて來られないと、よく人が云ふのを憶ひ出したので、さう云つてみたら、件の物は砂原を越えて逃げて行つたので、私は家へ歸つた。
道にゐたのは、年取つた牡の驢馬ぢやないかと、よくさう云ふ人もあるが、「デ・ブロフンディス」と云つたからとて、牡の驢馬が逃げて行つたといふ話はまだ聞いたことがない。」
私は、中の島で開いた話であつたが、十字を切つたら消えたといふお化け船の話をした。
「海の上には、不思議なことがある。」彼は云つた。「或る晩のこと、私は貴方にも見えるだらうが、あの下の方の靑くなつた所に居たら、一艘の船がはひつて來るのが見えた。あんなに岩に近づいて來て何をするのだらうと、不思議に思つてゐたが、それはまつ直ぐに私のゐた方へ向いてやつて來る。私はびつくりして、家の方へ逃げて行つたが、船長が私の逃げるのを見ると、進路を變へて、行つてしまつた。
その頃、私は時時船乘りとして出かけることがあつた。――ただ二三囘出かけたに過ぎないが。さうだ、或る日曜のこと、大きな船が瀨戸にはひつて來たと人が云ふ。三人の男と一緒に驅け下りて、カラハに乘つて出かけた。わし等は船の居たといふ處まで來たが、一艘の船も居やしない。日曜で仕事はないし、おまけに晴れて靜かな日ではあるし、わし等は船を探しに遠く漕ぎ出て、遂に後にも先にも行つたことのない遠くまで來てしまつた。漕ぎ返さうと思つて、見ると、海の上に鳥の大群がゐる。それは全部黑い色で、白いのは一羽もゐない。鳥はわし等を少しもお恐れてゐる樣子がない。一緒の男たちは行かうと云ふので、もつと行き、殆んど觸れさうになる迄に近づくと、それがパット飛び立つた。[やぶちゃん注:「ト」はママ。]空が眞黑になるほど澤山だつた。そしてまた百ヤード、或ひは恐らく百廿ヤードも沖に鳥はまた下りた。わし等は又その後を追つかけ、一人の男は一羽を橈栓で殺さうと云ひ、もう一人は漕桿で殺さうと云ふ、私はそれ等はカラハを覆すのではないかと思つたが、他の男は尚追つかけて行きたがる。
殆んど觸れさうになるまで近づくと、一人は櫂栓を投げ、もう一人は漕桿で打つた。すると二羽がカラハの中へ落ちて來て、そして舟は横樣に引つくり返り、若し海が全く靜でなかつたら、わし等は皆溺れただらう。
思ふに、その黑い鷗と船は同じものだつたらう。それから後、私は船乘りとして出かけた事はない。カラハが船まで出かけて、船が居なくなつてしまふ事はよくある事だ。
此の間、大島からカラハが一艘の船へ向つて出かけたが、船は居ず、カラハに居た人は皆溺れた事がある。後でそれを歌つた立派な歌が出來た。私はそれを聞いた事はないが。
また或る日、此の島からだつたが、カラハが漁に出かけた。ところが、さう遠くない處に一艘の船が見えた。その人達はパイプの火を借りようと――その當時はマッチがなかつたので――その大きな船に近づくと、そのゐた場所から船がなくなつてゐたので、大そう恐ろしくなつたさうだ。」
それから、彼は本土で聞いた話をした。それは或る男が夜、馬車を驅つて田舍を通つてゐると、一人の女に逢つた。その女はこつちの方へやつて來て、馬車に乘せてくれと云ふ。怪しい女と思つたので行過ぎて、少し行つてから後を振返つて見ると、一匹の豚が道の上に居て、女の人は誰も居なかつた。
彼は一杯食はされたと思つたが、尚も行き續けた。それから森を通り拔けて尚進んで行くと、二人の男が一人づつ道の南側から出て來て、馬の手綱をしつかりと抑へ、馬を間に挾んで連れて行かうとする。その男と云ふのは粗い羅紗の着物を着、昔風な
*
I asked him if he had known old Pat Dirane on the middle island, and heard the fine stories he used to tell.
'No one knew him better than I did,' he said; 'for I do often be in that island making curaghs for the people. One day old Pat came down to me when I was after tarring a new curagh, and he asked me to put a little tar on the knees of his breeches the way the rain wouldn't come through on him.
'I took the brush in my hand, and I had him tarred down to his feet before he knew what I was at. "Turn round the other side now," I said, "and you'll be able to sit where you like." Then he felt the tar coming in hot against his skin and he began cursing my soul, and I was sorry for the trick I'd played on him.'
This old man was the same type as the genial, whimsical old men one meets all through Ireland, and had none of the local characteristics that are so marked on lnishmaan.
When we were tired talking I showed some of my tricks and a little crowd collected. When they were gone another old man who had come up began telling us about the fairies. One night when he was coming home from the lighthouse he heard a man riding on the road behind him, and he stopped to wait for him, but nothing came. Then he heard as if there was a man trying to catch a horse on the rocks, and in a little time he went on. The noise behind him got bigger as he went along as if twenty horses, and then as if a hundred or a thousand, were galloping after him. When he came to the stile where he had to leave the road and got out over it, something hit against him and threw him down on the rock, and a gun he had in his hand fell into the field beyond him.
'I asked the priest we had at that time what was in it,' he said, 'and the priest told me it was the fallen angels; and I don't know but it was.'
'Another time,' he went on, 'I was coming down where there is a bit of a cliff and a little hole under it, and I heard a flute playing in the hole or beside it, and that was before the dawn began. Whatever anyone says there are strange things. There was one night thirty years ago a man came down to get my wife to go up to his wife, for she was in childbed.
'He was something to do with the lighthouse or the coastguard, one of them Protestants who don't believe in any of these things and do be making fun of us. Well, he asked me to go down and get a quart of spirits while my wife would be getting herself ready, and he said he would go down along with me if I was afraid.
'I said I was not afraid, and I went by myself.
'When I was coming back there was something on the path, and wasn't I a foolish fellow, I might have gone to one side or the other over the sand, but I went on straight till I was near it--till I was too near it--then I remembered that I had heard them saying none of those creatures can stand before you and you saying the De Profundis, so I began saying it, and the thing ran off over the sand and I got home.
'Some of the people used to say it was only an old jackass that was on the path before me, but I never heard tell of an old jackass would run away from a man and he saying the De Profundis.'
I told him the story of the fairy ship which had disappeared when the man made the sign of the cross, as I had heard it on the middle island.
'There do be strange things on the sea,' he said. 'One night I was down there where you can see that green point, and I saw a ship coming in and I wondered what it would be doing coming so close to the rocks. It came straight on towards the place I was in, and then I got frightened and I ran up to the houses, and when the captain saw me running he changed his course and went away.
'Sometimes I used to go out as a pilot at that time--I went a few times only. Well, one Sunday a man came down and said there was a big ship coming into the sound. I ran down with two men and we went out in a curagh; we went round the point where they said the ship was, and there was no ship in it. As it was a Sunday we had nothing to do, and it was a fine, calm day, so we rowed out a long way looking for the ship, till I was further than I ever was before or after. When I wanted to turn back we saw a great flock of birds on the water and they all black, without a white bird through them. They had no fear of us at all, and the men with me wanted to go up to them, so we went further. When we were quite close they got up, so many that they blackened the sky, and they lit down again a hundred or maybe a hundred and twenty yards off. We went after them again, and one of the men wanted to kill one with a thole-pin, and the other man wanted to kill one with his rowing stick. I was afraid they would upset the curagh, but they would go after the birds.
'When we were quite close one man threw the pin and the other man hit at them with his rowing stick, and the two of them fell over in the curagh, and she turned on her side and only it was quite calm the lot of us were drowned.
'I think those black gulls and the ship were the same sort, and after that I never went out again as a pilot. It is often curaghs go out to ships and find there is no ship.
'A while ago a curagh went out to a ship from the big island, and there was no ship; and all the men in the curagh were drowned. A fine song was made about them after that, though I never heard it myself.
'Another day a curagh was out fishing from this island, and the men saw a hooker not far from them, and they rowed up to it to get a light for their pipes--at that time there were no matches--and when they up to the big boat it was gone out of its place, and they were in great fear.'
Then he told me a story he had got from the mainland about a man who was driving one night through the country, and met a woman who came up to him and asked him to take her into his cart. He thought something was not right about her, and he went on. When he had gone a little way he looked back, and it was a pig was on the road and not a woman at all.
He thought he was a done man, but he went on. When he was going through a wood further on, two men came out to him, one from each side of the road, and they took hold of the bridle of the horse and led it on between them. They were old stale men with frieze clothes on them, and the old fashions. When they came out of the wood he found people as if there was a fair on the road, with the people buying and selling and they not living people at all. The old men took him through the crowd, and then they left him. When he got home and told the old people of the two old men and the ways and fashions they had about them, the old people told him it was his two grandfathers had taken care of him, for they had had a great love for him and he a lad growing up.
[やぶちゃん注:「此の爺さんは愛蘭土の何處ででも出逢ふ快活な、茶目氣のある型の人で、イニシマーンに目立つた地方的の特質を持つてゐなかつた。」原文は“This old man was the same type as the genial, whimsical old men one meets all through Ireland, and had none of the local characteristics that are so marked on lnishmaan.”であるが、やや問題があるように思われる。則ち、素直にこの邦訳を読むと、この話者である老人は一般的なアイルランドでは、しばしば頻繁に見受けられるところの「快活な、茶目氣のある型の」よくある老人である。しかし、そういう老人はイニシマーン島では滅多に見当たらない、という謂いにしか採れない。しかし、これは今まで読んできた我々には、それでは奇異に感じられるのである。シングはイニシマーンの人々をこそアランの原型としての素朴な民として称揚していることは最早、明らかだからである。そういう疑義を持って原文を見ると、“genial”と“whimsical”の対称性に気付く。ここは「愛想がいい」⇔「むらっ気のある」で、妙に人懐っこいものの、その実、ぷいっと機嫌が変わるといったかなりいい加減な
「さあ、あつちを向いてごらん。」原文は“"Turn round the other side now,"”で、これは「さあ、ぐるっと回って。反対側にも(塗って)進ぜよう。」で、タールをズボンの反対側(後ろ側)にも塗ろう、という意味である。
「踏段」アランでよく見かける、所有地を示し、また強風から家屋や作物などを守るための人工の石組みの垣根のこと。
「墮落した天使」原文は“the fallen angels”で複数形。
「海上警察署」“the coastguard”。沿岸警備隊。正式には“Her Majesty's Coastguard”、「王立沿岸警備隊」である。
「そんな事は何も信じてゐない」の「そんな事」は悪魔や妖精といった超常的存在や現象を指す。
「一クォートの酒」原文“a quart of spirits”。現在のイギリスの単位1 クォートは1.1365225リットル。約一リットル強。“spirits”で、お産の消毒用の蒸留酒である。
「私も馬鹿でなかつたら、砂の上からためつすがめつ行くところだつたが、」原文は“and wasn't I a foolish fellow, I might have gone to one side or the other over the sand,”。「私が馬鹿な輩でなかったなら、私はその何かのいるところと有意に反対側か、若しくはもっと向こう側にある砂浜を行ったかも知れないが、」で、結果的には「儂は馬鹿で、ずんずんそいつに近づいてっちゃった」のである。「ためつすがめつ」(矯めつ眇めつ)という日本語は「色々な角度からよく観察すること」を意味し、ここの訳としても、民俗学的な習俗としても相応しくなく、逆にこうした場合のタブーでさえある。凝っと見てはいけない。逆に魅入られる、のである。
「デ・ブロフンディス」“De Profundis” ラテン語で“out of the depths”、「深き淵より」の意で、旧約聖書「詩篇」第129番に現われる言葉。古くから死者の典礼を行う際に歌われ、悲しみや絶望などのどん底からの叫びの意を持つ。「主よ、我れ、深き淵より主を呼ばはる。主よ、わが声を聴き容れ給へ。願はくは我が願ひの声に御耳傾け給へ……」と始まる呪言である。
「或る晩のこと、私は貴方にも見えるだらうが、あの下の方の靑くなつた所に居たら、」原文は“'One night I was down there where you can see that green point,”の部分。この“point”は岬で、あそこに「ある夜のことじゃ――ほれ、あの下の方に緑色の岬が見えるじゃろう、あそこに儂は居った――」の意。ここで老人との会話のロケーションの位置が、かなり高い位置で、尚且つ、海と岬の見える場所での聴き取りであることが明らかになる。広角レンズに変えたような上手い効果である。
「船乘り」原文は“a pilot”で、ここは水先案内人と訳したいところだ。
「百ヤード、或ひは恐らく百廿ヤード」91mから110m弱ほど。
「橈栓」は「かいせん」と読み、「櫂栓」と同じい。原文“thole-pin”は“tholepin”で櫂を船端に固定するための器具。櫓べそ。恐らく抜けば固定部分が尖っているものと思われ、それを槍のように投げつけて鳥を射落とすということと推測する。
「漕桿」「さうかん(そうかん)」と読むか。原文“rowing stick”は櫂・オールのことであるが、海事用語としては一般的な表現ではない。
「わし等は又その後を追つかけ、一人の男は一羽を橈栓で殺さうと云ひ、もう一人は漕桿で殺さうと云ふ、私はそれ等はカラハを覆すのではないかと思つたが、他の男は尚追つかけて行きたがる。」以下の部分は、まさに話者の爺さん以外の二人は、完全に魔に魅入られている。海上にあって櫂栓を失えばオールは漕げず、オールを失えば命とりとなるという当たり前のことをこの海の男たちは全く認識出来ていない。ということはまさに幽霊船や不吉な黒鳥の群れの背後にある邪悪なるものに完全に魅入られていると言ってよいのである。命を落とさなかったのは幸いであった。幾分、この話柄には老人だけは正気であったことを自慢するニュアンスが感じられる。
「此の間……後でそれを歌つた立派な歌が出來た。私はそれを聞いた事はないが。」の「此れの間」の原文は“A while ago”で、確かに「少し前に、数分前、先程」という意味であるが、この成句は必ずしも短い時間限定する訳ではなく、歴史的時空間的な大きなレンジでの相対的な、実はもっと長い時間を意味する「暫く前」の方がしっくりくる。何故なら、その幽霊船とカラハの乗組員全員溺死という恐ろしくも哀しい出来事は、民俗的伝承の中に取り込まれて、それを詠んだ名悲歌が作られるまでには、相応の時間が必要だからである。これは「新しい歌」だからまだ聴いたことがないのではなく、寧ろ逆に古い伝承で、最早、そのエレジーを知っていて歌える者がいなくなったということを意味していると考える方が自然ではあるまいかと私は考えるのである。
「大道の市場で賣買をしてゐるやうな人だかりとなつた。而かもその人達は生きてゐる人間ではなかつた。」“When they came out of the wood he found people as if there was a fair on the road, with the people buying and selling and they not living people at all.”は最大の怪談の真骨頂で、これは中国で言う所の、死者たちが商いをする「鬼市」である。]
今夜、旅館の客間で、爐に火をともし、椅子を片隅に寄せて、踊りの會を催した。誰も司會者がなかつた。私はヴァイオリンで二つ三つの舞踏曲やその他の曲を彈いてしまつた時、私は皆が私の音樂をどの位に望んでゐるか、また誰か他に歌ひ或は音樂をする人があるか、わからなくなつたので、中止となつた。一寸の間、行詰まりが來たやうな氣がしたが、私のよく知つてゐる若い娘が此の窮境を見てとつて、會の進行係を引受けた。先づ最初に海上警察署の娘にハーモニカで踊の曲を吹くやうに賴んだ。その娘は直ぐに、それを立派な元氣と音律でやり遂げた。それから、小さな娘は私に何を選んでもよいから又彈いてくれと云つた。此のやうな調子で、彼女は家に歸らなければならないと思つた時まで今夜の進行係を續けてゐた。それから彼女は立上つて、私に愛蘭土語で禮を述べ、誰の方をも見ずに、戸口から外へ出て行つた。そして殆んど直ぐ後から、會衆の全部が續いた。
*
This evening we had a dance in the inn parlour, where a fire had been lighted and the tables had been pushed into the corners. There was no master of the ceremonies, and when I had played two or three jigs and other tunes on my fiddle, there was a pause, as I did not know how much of my music the people wanted, or who else could be got to sing or play. For a moment a deadlock seemed to be coming, but a young girl I knew fairly well saw my difficulty, and took the management of our festivities into her hands. At first she asked a coastguard's daughter to play a reel on the mouth organ, which she did at once with admirable spirit and rhythm. Then the little girl asked me to play again, telling me what I should choose, and went on in the same way managing the evening till she thought it was time to go home. Then she stood up, thanked me in Irish, and walked out of the door, without looking at anybody, but followed almost at once by the whole party.
[やぶちゃん注:以下は、原文では行空きはない。
「今夜、旅館の客間で、爐に火をともし、椅子を片隅に寄せて、踊りの會を催した。」原文は“This evening we had a dance in the inn parlour, where a fire had been lighted and the tables had been pushed into the corners.”である。この直前まで、シングは採録のためにイニシーア島(南島)へ行っていた。しかし、ここに登場するのは「旅館」はどうもイニシーアとは思われない。ここは島を離れる最後の宴の描写であり、本土への船はアランモアのキルローナンから出る。何より、この場面は我々に第一部の最初のシーンを容易に想起させよう。則ち、
『私はアランモアにゐる。泥炭の火にあたり、部屋の下の小さな酒場から聞こえて來るゲール語の話し聲に耳傾けながら。』
この描写は美事にこのエンディングの舞台と一致する。さすれば、この最後の宴の場所は、シングが「アラン島」の最初のシーンとして取り上げた、このアランモアの酒場の二階なのである。何と素晴らしい額縁であろう!
「海上警察署の娘」は注既出の通り、「沿岸警備隊員の娘」。]
皆が行つてしまふと、私は暫く、酒場の椅子に腰掛け、愛蘭土語の新聞を讀んでゐる幾人かの靑年たちと話をした。それから學者と二人の物語師――二人共老人で船乘り――と一緒に物語や詩を書き寫しながら、長い夜を過した。殆んど六時間近くを勉強したが、事柄を段段と調べれば調べるほど、此の老人達は多くを憶ひ出してくるやうであつた。
「私は今夜、漁に出かける筈だつたのだ。」さう云つて一人の若者がはひつて來た。「併し、私はあなたに來ると約束をした。あなたは禮儀正しい人だから、私は約束を破るよりも五ポンドを捨てることにした。さあ、」――ウィスキーの盃を取り上げながら――「あなたの健康を祝します。グスベリの木であなたが棺を造るまで、またお産の床であなたが死ぬまで、生きていらつしやるやうに。」
皆も私の健康を祝つて飮み、また我我の勉強が初つた。
「あなたは詩人のマックスウィニーの話を知つてゐますかね?」と私の傍に坐つて、その男が聞いた。
「ゴルウェーの町で聞いた事がある。」私は答へた。
「さうかね、」彼は云つた。「『盛んな結婚式』といふ一篇をあなたに話してみよう。それは美しい一篇で、知つてゐる人は澤山ないだらうから。田舍に、或る可憐な召使の娘がゐて、その娘が或る可憐な召使の男の子と結婚した。マックスウィニーは二人を知つてゐたが、その時、遠方にゐて、歸るまで一ケ月かかつた。歸つて來ると、彼はペギー・オハラ――娘の名をさう云つた――に逢ひに行き、盛大な結婚を擧げたかと聞いた。ペギーはほんの中位であつたと答へ、矢張りよく忘れずにゐたと見えて、戸棚にウィスキーの瓶をしまつておいた。彼は爐邊に坐り、ウィスキーを飮み初めた。二三杯飮んでしまつて、爐で温かくなると、一つの歌を作り初めた。それがペギー・オハラの結婚式について作つた歌なのだ。」
*
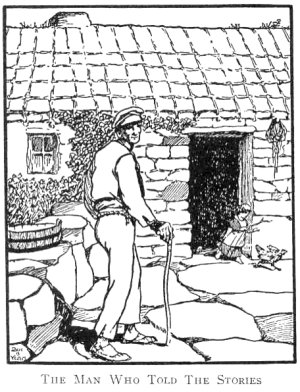
[ストリー・テラーの男]
When they had gone I sat for a while on a barrel in the public-house talking to some young men who were reading a paper in Irish. Then I had a long evening with the scholar and two story-tellers--both old men who had been pilots--taking down stories and poems. We were at work for nearly six hours, and the more matter we got the more the old men seemed to remember.
'I was to go out fishing tonight,' said the younger as he came in, 'but I promised you to come, and you're a civil man, so I wouldn't take five pounds to break my word to you. And now'--taking up his glass of whisky--'here's to your good health, and may you live till they make you a coffin out of a gooseberry bush, or till you die in childbed.'
They drank my health and our work began.
'Have you heard tell of the poet MacSweeny?' said the same man, sitting down near me.
'I have,' I said, 'in the town of Galway.'
'Well,' he said, 'I'll tell you his piece "The Big Wedding," for it's a fine piece and there aren't many that know it. There was a poor servant girl out in the country, and she got married to a poor servant boy. MacSweeny knew the two of them, and he was away at that time and it was a month before he came back. When he came back he went to see Peggy O'Hara--that was the name of the girl--and he asked her if they had had a great wedding. Peggy said it was only middling, but they hadn't forgotten him all the same, and she had a bottle of whisky for him in the cupboard. He sat down by the fire and began drinking the whisky. When he had a couple of glasses taken and was warm by the fire, he began making a song, and this was the song he made about the wedding of Peggy O'Hara.'
[やぶちゃん注:以下、底本では続くが、原文では行空けがある。
「學者」は注既出の通り、「郷土史研究家」。「物語師」は「語部」と訳したい。私は約束を「あなたは禮儀正しい人だから、私は約束を破るよりも五ポンドを捨てることにした。さあ、」原文は“you're a civil man, so I wouldn't take five pounds to break my word to you. And now”で、これは別に彼が漁に出ていれば、その収穫で「五ポンド」を手に入れていた、それを捨てた、という意味では、あるまい。「あんたは礼儀正しい人だ、だからどんなことがあったって――たとえ誰かが俺に五ポンドくれてやると言ったとしたって――俺は約束を破らねえ、さあ、」という意味である。
「グスベリの木であなたが棺を造るまで、またお産の床であなたが死ぬまで、生きていらつしやるやうに。」 “and may you live till
they make you a coffin out of a gooseberry bush, or till you die in childbed.'”「グスベリ」はグース・ベリーでバラ目スグリ科スグリ属セイヨウスグリRibes uva-crispa。漢字では「西洋酸塊」と書く。和名の異名はマルスグリ・オオスグリ。イギリスでは音写すると一般には「グズバリ」。甘い果実をジャムに加工する。3メートルほどの落葉低木でとても棺桶の材料にはなりそうもない。なりそうもないから長寿の祝言となるのではなかろうかと推測する。「お産の床であなたが死ぬまで、生きていらつしやるやうに」とは、あなたが死ぬとすれば――それはあなたが生まれたばかりの時、ベビー・ベッドの中で死ぬまで――あなたの死はやってこない――あなたは今や大の大人になってぴんぴんしている――だからあなたに死はやってこない」という論理矛盾を用いた長寿の祝言と読む。
「詩人のマックスウィニー」“the poet MacSweeny”。シングも知っているからアイルランドでは相応に有名な吟遊詩人なのであろうが、不詳。識者の御教授を乞う。]
彼はその詩の英語と愛蘭土語の兩方を持つてゐたが、それは何處にでもあり、且つ他の通俗詩人の作と看做されるれてゐるので、此處に掲げる必要もないであらう。
私たちもう一遍、黑ビールやウィスキーを一廻りさせた。そしてマックスウィニーの結婚式の詩を持つてゐた老人は酒飮みの歌の一篇を見せてくれた。學者はこれを書き寫し、後で私が彼と一緒に飜譯した。――
*
He had the poem both in English and Irish, but as it has been found elsewhere and attributed to another folk-poet, I need not give it.
We had another round of porter and whisky, and then the old man who had MacSweeny's wedding gave us a bit of a drinking song, which the scholar took down and I translated with him afterwards:--
[やぶちゃん注:以下、底本では行空けがあるが、原文では続く。
「彼はその詩の英語と愛蘭土語の兩方を持つてゐた」は、言わずもがなであるが、「彼はその詩を英語とアイルランド語の両方で歌うことが出来た」という意。「酒飮みの歌の一篇を見せてくれた」も同様に「酒飲み歌の
「お婆さんがベアラカで、のろまな男に出逢ふと、こんな事を云ふ。――
「お前さんは前に、蒸溜所に行つて其處から一杯ひつかけた事があるかね? 葡萄酒でもビールでも、それほどおいしい物はない。だが、飮んだ後、私がスローパーさんの爐の傍で倒れた時、火傷しなかつたのは何よりだつた。
「オーエン・オハーノンを愛蘭土一のお醫者さんと、私は褒める。大麥の中へ水をさし、その中へ藥を入れるのはあの人だ。
「若しその一滴だけでも、杖をついて世の中を歩く婆さんにやつたなら、素晴らしい安息所が出來たと、お婆さんは一週間ぐらゐは考へるだらう。」
*
'This is what the old woman says at the Beulleaca when she sees a man without knowledge--'Were you ever at the house of the Still, did you ever get a drink from it? Neither wine nor beer is as sweet as it is, but it is well I was not burnt when I fell down after a drink of it by the fire of Mr. Sloper.
'I praise Owen O'Hernon over all the doctors of Ireland, it is he put drugs on the water, and it lying on the barley.
'If you gave but a drop of it to an old woman who does be walking the world with a stick, she would think for a week that it was a fine bed was made for her.'
[やぶちゃん注:「ベアラカ」“Beulleaca”不詳。
「オーエン・オハーノン」“Owen O'Hernon”不詳。
「大麥の中へ水をさし、その中へ藥を入れるのはあの人だ。」原文は“it is he put drugs on the water, and it
lying on the barley.”。これは「オオムギの中で寝かせて造る――そんでもって出来たそのヤクは――こっそり仕込むんだ、水ん中――」と言ったニュアンスではなかろうか? また、これは私の直感であるが、オオムギに生じた麦角アルカロイドの抽出とそこから精製した堕胎薬を指しているように思われる。麦角菌はバッカクキン科バッカクキン属
Claviceps に属する子嚢菌の約五十種の菌類の総称。特によく知られる種は Claviceps purpurea でオオムギ・ライ麥・コムギ・エンバクなど多くの穀物に寄生し、本種が作る菌核は黒い角状或いは爪状を呈し、西洋では「悪魔の爪」などとも呼ばれる。この麦角の中には麦角アルカロイドと総称される物質は含まれており、これは麦角中毒という循環器(血管収縮による手足の壊死)や神経系(手足が燃えるような異感覚)に対する様々な毒性を示し、脳への血流の不足による精神異常・痙攣、意識不明から死に至ることもある。子宮収縮による流産なども引き起こすが、そこから古くは微量の麦角が堕胎や出産後の止血剤としても用いられた(以上はウィキの「麦角菌」に依った)とあり、この「藥」はカトリックが厳しく断罪する堕胎のための秘薬の謂いではなかろうか? 更に言えば、最後の歌は一種の姥捨伝説を語っており、精製したアルカロイドを一振り盛れば、免疫機能の低下した老人ならば一週間程度で死に至るということ、麦角アルカロイドによる毒殺を暗に意味しているのではなかろうか? とすれば――この最初の歌は……強いスピリッツを殺したい奴に酔うまで飲ませて、後は暖炉のそばに放置して置けば、過失による焼死で処理される、という完全犯罪のススメの意が隠されているのではなかろうか?! 私のとんでもない誤解かも知れない。識者の御教授を乞うものである。]
その後で私はヴァイオリンを取り出さして、皆がウィスキーを飮んでゐる間、幾つかの曲を彈かねばならなかつた。今朝は、黑ビールの新らしい貯藏品が部屋の下の酒場に出された。私たちの話す合間に、中の島から來た人達をもてなす爲に來てゐる幾人かの男たちが色色の歌を歌つてゐるのが聞こえてゐた。或る者は私の書いたやうな英語であつたが、大概の者は愛蘭土語で歌つてゐた。
暫くして、一行が階下で解散すると、此の老人達は妖精達――それは少し行つた處に住んでゐる――を氣味惡がりながら、砂山を越えて立ち去つた。
その翌日、私は汽船で出發した。
*
After that I had to get out my fiddle and play some tunes for them while they finished their whisky. A new stock of porter was brought in this morning to the little public-house underneath my room, and I could hear in the intervals of our talk that a number of men had come in to treat some neighbors from the middle island, and were singing many songs, some of them in English or of the kind I have given, but most of them in Irish.
A little later when the party broke up downstairs my old men got nervous about the fairies--they live some distance away--and set off across the sandhills.
The next day I left with the steamer.
[やぶちゃん注:これが“The Aran Islands”「アラン島」の掉尾である。栩木氏によれば、この第四回目のアラン離島は1901年10月19日である。実はこれが最後ではなく、シングはこの一年後の1902年10月14日から11月8日まで、五回目のアラン滞在を果たしており、実にシングは27歳の時から30歳になるまでの毎年、アランに「帰って」いたのであった。因みに、シングは最初のアラン訪問(1989年5月10日)の二年前、1897年25歳の時に血液の癌の一種“Hodgkin's
lymphoma”ホジキンリンパ腫を発症していた(白血球中のリンパ球が悪性化する癌で、全身のリンパ節が腫れ、腫瘤が形成される。当時は有効な治療法はなかった。私の愛するルーマニアのピアニスト、“Dinu
Lipatti”ディヌ・リパッテイもこの病いのため、1950年、33歳で夭折している――私にはアランを去って行くシングの乗る汽船のエンディングの映像にリパッティの演奏する、あの“Jesu,
meiner Seelen Wonne”(“Jesus, Joy of Man's Desiring”「主よ、人の望みの喜びよ」)が聴こえる――シングは1909年3月24日、様態が悪化、37歳の若さで帰らぬ人となった……
……アランの島人らが何時も心配していたこと……
……それはいつもシングの結婚のことであった……
……シングはこの亡くなる直前に……
……彼がディレクター兼アドバイザーをしていたダブリンの劇場アベイ座の女優モリー・オールグッドと婚約したのであった……]
The Aran Islands
by J. M. Synge
Part Ⅳ
End
アラン島
ジョン・ミリングトン・シング著
姉崎正見訳
第四部
終
Críoch
[やぶちゃん注:以下、底本岩波文庫の最後に附された訳者姉崎正見氏の「あとがき」及び「復刊にあたりて」を添えて終わりとする。]
あとがき
愛蘭土の劇作者ジョン・ミリングトン・シング(John Millington Synge, 1871―1904)は劇作のほかに、幾つかの散文の作品を殘してゐる。それ等は主に愛蘭土の諸地方を旅行して書いた紀行乃至隨筆であるが、その中でも此の「アラン島」(The Aran Islands)は比較的初期のもので、彼の生涯に於ける重要な轉換期に書かれたといふ點に於いて、また書かれた土地が歐洲の西端にある孤島として近代文化からかけ離れた特殊な風俗人情を持つてゐるといふ點に於いて興味あるスケツチとして珍重される。
彼がアラン島に來たのは先輩イェーツの同情的な勸告に從つたと云はれるが、愛蘭土の一方言ゲール語を習ふこともまた一つの目的であつた。一八九八年五月彼がアランの一島アランモアに來て島民たちと寢食を共にする生活にはひつてみると、その荒涼たる岩石から成る島の間に營まれてゐる彼等の生活の中には、古代ゲール族から殘されて來たと思はれる純樸な風俗、剛健な氣風、古い傳説や迷信などがあるのを發見した。比の發見は又一面に於いて彼自身の藝術的才能の素地を發見したとも云へるので、その後、彼が劇を作るに當つて此のアラン滯在中に得た見聞が如何に役立つたかは、その劇、例へば The Shadow of the Glen や Rider to the Sea 等の中の插話や事件や登場人物までも「アラン島」中の隨所に認められるに依つても明かである。
此の旅行記は全體が四部から出來てゐるが、第一部は最初の滯在、即ち一八九八年の滯在の時の事を、第二部はその翌年、第三部は又その翌年、第四部はそれから更に一年置いて一九〇二年の滯在の時を書いたものである。そして各部は一年乃至三年の後、何れ愛蘭土や英國の雜誌に寄稿され、一九〇七年に一册にまとめられて「アラン島」と題して出版された。
原文中、島民の會話には所謂アングロ・アイリッシュが多く使つてあるが、私は強ひてそれを是の日本の特定地方の方言に寫て表現して見るやうなことをせず、普通の口語に譯するに止めた。殊に民話には背景に傳説が含まれてゐると思はれるものがあるが、それを精細に調べるのは私の力の及ぶ所でなかつたのでそのまま散文體にした所もある。讀者の寛恕を乞ふ。
また此の譯を爲すに當つて、野上豐一郎先生の御世話になり、ゲール語は市河三喜博士、特に勝田孝興氏の御助力を仰いだ事を附記して、此處に感謝の意を表する次第である。
昭和十一年十月 譯 者
[やぶちゃん注:「市河三喜」(いちかわさんき 明治19(1886)年~昭和45(1970)年)は英語学者。東京帝國大学名誉教授。日本英語学の祖と呼ばれる。
「勝田孝興」(かったたかおき 明治19(1886)年~昭和51(1976)年)はアイルランド文学者・語学者。東京帝国大学英文科卒業後、1925年より二年間、文部省から推薦されてアイルランドに留学、後、旧制神奈川県立横須賀中学校(現在の横須賀高等学校であるから、同県の高校教師であった私にとっては先輩に当たる)教諭や旧制山形高等学校(現在の山形大学)の各教授を経て同志社大学教授、戦後は滋賀大学教授、大阪工業大学教授となった。アイルランド文芸復興運動に関わる演劇及びアングロ・アイリッシュの発音に関する研究を専門とした(以上はウィキの「勝田孝興」に基づく)。]
復刊にあたりて
久しく絶版になつていた本書は、戰爭後再び世に現はれた。丁度、今年はシングの死後五十年に當るのも、何かの意義があるような氣がする。
此版で内容は少しも改訂はしなかつた。序文の「アラン島について」の野上先生の文もそのまま載せて頂いた。今は亡き先生の本書に對する御好意の記念として。
昭和三十四年四月廿二日 譯 者
[やぶちゃん最終注:本テクストへの注釈に当たっては、元同僚の英語教師や海外で活躍する元教え子の協力を得た。ここに挙げて感謝の意を表する。……さて、私が底本とした私の所持する岩波文庫版の最後のページの下に、私は本書を買った日附を記している。それは「1979.7.3.」である。私が神奈川県の高等学校教員になって丁度三ヶ月後の夏、私はこの本に出逢ったのであった……
……その頃、私はいまだ22歳であった……
……そして、妻と一緒に44歳の私はアラン島へ行った……
……さても、本書入手の33年の後に……
……まさか、野に下った55歳の私が……
……この姉崎正見氏訳「アラン島」を英語の原文と暴虎馮河のオリジナル注を附して全世界に発信しようなんどとは……
……想像だにし得なかった……
――姉崎先生、心より、ありがとう御座いました。――]
ジョン・ミリングトン・シング著
ウィリアム・バトラー・イェイツ挿絵
「アラン島」
姉崎正見訳 全四部
附 やぶちゃん注
完
Críoch