
[島の男]
The Aran Islands
Part I
by J. M. Synge
With drawings by Jack B. Yeats
Dublin, Maunsel & Co., Ltd.
[1907]
アラン島
第一部
ジョン・ミリングトン・シング著
ウィリアム・バトラー・イェイツ挿絵
ダブリン マウンセル社刊
姉崎正見訳
附 やぶちゃん注

[島の男]
The Aran Islands
Part I
by J. M. Synge
With drawings by Jack B. Yeats
Dublin, Maunsel & Co., Ltd.
[1907]
アラン島
第一部
ジョン・ミリングトン・シング著
ウィリアム・バトラー・イェイツ挿絵
ダブリン マウンセル社刊
姉崎正見訳
附 やぶちゃん注
[やぶちゃん注:アイルランドの劇作家にして詩人であったジョン・ミリントン・シング (John Millington Synge 1871年~1909年)は、1898年から1902年にかけて4度、アイルランド島の西のゴールウェイ湾に浮かぶアラン諸島を訪れた。後に愛情に満ちた筆致でこの島に残るアイルランドの古形的民俗と人々の生活を活写したのが本作である(一冊に纏められた出版は1907年)。底本は一九三七年刊岩波文庫版を用いた。姉崎正見氏は東大附属図書館司書で昭和36(1961)年11月現職で逝去されている。従って著作権法五十一条により亡くなった翌年の1962年1月1日起算50年で、著作権保護期間は2010年1月1日までとなる。姉崎氏の没年については昨年年初に岩波書店に電話で直接確認をとってあるが、ネット上の記載でも確認が出来るので間違いない。冒頭に配された野上豊一郎の『「アラン島」について』も野上は昭和25(1950)年2月に逝去されているので、同じく著作権は消滅している。訳者によるポイント落ちの( )による割注は本文同ポイントで〔 〕示し、一部の踊り字は正字や「々」で示した。原則、底本の行空けのあるパートごとに(後半部には一部例外あり)訳文の後に原文を付し、更に私のオリジナルな注を附した。私は英語は苦手である。誤りや誤解があった場合は、御教授を乞う。底本の「口繪」に配されたシングがアラン島で撮った4枚の写真は底本のものを、原文及びイェイツの挿絵は“Intenet Sacred Text Archive”所収の“The Aran Islands by J. M. Synge”のものをそれぞれ用いた(冒頭の着色の一枚だけはイギリスの個人の方の蔵書から、同書の見開き扉絵の写真からを絵のみを切り取ったものである。万一、着色に著作権が生じている場合には削除する用意がある)。以上の写真と挿絵の配置は私の恣意によるもので(但し、写真については底本のキャプションにある『〇〇頁参照』という指示を勘案した)、挿絵の英語標題の訳は私が現代仮名遣・新字で附した。本頁は私のブログでの第一部の公開を経て、第一部全文を一括して作成したものである。――これを私と同じく母を失う聖痕(スティグマ)を受けた教え子に捧げる――【2011年3月10日
私の最愛の教え子の誕生日に】]
アラン島 シング作 姉崎正見譯
「アラン島」について
「アラン島」(The Aran Islands)はシングの戯曲を讀む人にとつて、興味ある貴重な文獻である。何となれば、イェーツも言つたやうに、シングの藝術の本質を形づくる永遠な高貴なものは、彼がアラン群島のそこここに寄寓して、土地の人たちから古い物語を聞き、それを目の前に見る現實の生活と比較することに依つて體得したものであり、讀者にその製作經過を感じさせないでは措かない素材がその中には豐富に盛られてあるから。
「アラン島」は、同時にまた、シングの戯曲を讀まない人にとつても、一つの興味多い讀物であることを失はない。何となれば、そこには世界の他のどこにも殆ど見られなくなつた傳統ある原始生活がまだ見られてあつたし、その生活の中にはひり込んで、同情と批判を以つて觀察した天才文人の忠實な記録でそれはあるから。
實際アランの岩島はシングに依つて生かされ、シングはまたアランを踏まへて彼の藝術を完成したのであつた。
シングにアランへ行けと忠告したのはイェーツであつた。それは一八九九年、シング二十八歳の時であつた。その七年前、シングはダブリン大學を出て、音樂者にならうと思つてドイツへ行き、作家に轉向しようと思つてフランスへ行き、フランスに三年ほどゐてイタリアヘ行き、捜すものを求め得ないでアイルランドに歸り、イェーツに逢ふ前年、一八九八年、アラン島に最初の訪問を試みて、またフランスへ行き、パリで先輩イェーツに逢ふと、イェーツはシングの天才を生かすにはラシーヌの幽靈を突き放して(當時シングはラシーヌに傾倒してゐたので)郷國の漁民の生活の中へ歸るのが一番だと感じ、それをシングに忠告したのであつた。シングはイェーツの忠告に従つてアランの生活を研究し、それを物にして遂にシェイクスピア以來の劇詩人と言はれるほどの製作をして、一九〇九年、三十八歳で孤獨の生涯を終つた。
シングは純眞で、内氣で、禁慾的で、さうして皮肉屋であつた。言語には殊に敏感で、近代詩の外にヘブライ語と固有アイルランド語をも知つてゐた。彼自身の書くものに彼自身獨自の表現を作り出すことにも成功した。それは彼の描いた性格の多くと共に、アランの漁民の生活觀察から得たものであつた。
私の若い友人姉崎正見君の飜譯が、さういつたシングの特長を生かさうとすることに周到な注意と努力の拂はれてあるのは推賞に値する。
昭和十二年二月 野上豊一郎
アラン島
緒 言
アラン島の地理は甚だ簡單であるが、これに就き一言する必要があらう。それは三つの島から成る。即ち、アランモア、北の島、長さ約九哩。次に、イニシマーン、中央の島、さしわたし約三哩半、形はほぼ圓形。さうして南の畠なるイニシール――愛蘭土語で東の島の意――は中央の島に似てゐるが、稍々小さい。それ等はゴルウェーから約三十哩離れ、その灣の中央に横はる。併し南方では、クレア郡の斷崖から、また北方では、コニマラの一角から程遠くはない。
アランモアの主要村キルロナンは繁華區域役所〔愛蘭土に於いて一八一九年移民に依つて起る借地問題を解決するために創設された役所〕に依つて發展した漁業のために大いに變革が行はれ、今では愛蘭土西岸の漁村と大した差違がなくなつてゐる。他の二島はそれより原始的であるが、其處にも變革は行はれつつある。併し本文中ではそれに就いて論及するほどの必要は感じられなかつた。
以下のページで、私は此の群島に於ける私の生活と、私の遭遇した事柄のありのままを述べ、何物をも創作せず、また本質的なものは何物をも變更しないで置いた。併し、私の語る人人に就いては、その名前を變へたり、引用した手紙を變へたり、また地理的・家族例の關係を變更したりして、成るべくその實體を現はさないやうにした。私は、全然彼等のためにならないやうな事は云はなかつたが、それでも斯く假裝を施したのは、彼等の厚意や友情を餘りに露骨に取扱つたといふ感じを
*
Author's Forword
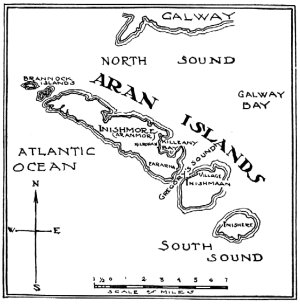
The geography of the Aran Islands is very simple, yet it may need a word to itself. There are three islands: Aranmor, the north island, about nine miles long; Inishmaan, the middle island, about three miles and a half across, and nearly round in form; and the south island, Inishere--in Irish, east island,--like the middle island but slightly smaller. They lie about thirty miles from Galway, up the centre of the bay, but they are not far from the cliffs of County Clare, on the south, or the corner of Connemara on the north.
Kilronan, the principal village on Aranmor, has been so much changed by the fishing industry, developed there by the Congested Districts Board, that it has now very little to distinguish it from any fishing village on the west coast of Ireland. The other islands are more primitive, but even on them many changes are being made, that it was not worth while to deal with in the text.
In the pages that follow I have given a direct account of my life on the islands, and of what I met with among them, inventing nothing, and changing nothing that is essential. As far as possible, however, I have disguised the identity of the people I speak of, by making changes in their names, and in the letters I quote, and by altering some local and family relationships. I have had nothing to say about them that was not wholly in their favour, but I have made this disguise to keep them from ever feeling that a too direct use had been made of their kindness, and friendship, for which I am more grateful than it is easy to say.
[やぶちゃん注:「九哩」1mile は約1.6㎞。14.5㎞弱。
「繁華區域役所〔愛蘭土に於いて一八一九年移民に依つて起る借地問題を解決するために創設された役所〕」とあるが、この姉崎氏の割注の「一八一九年」は「一八九一年」の誤植であろう。原文“Congested
Districts Board”は正確には“Congested Districts Board for Ireland”で、これは時のソールズベリー内閣のスコットランド長官であった保守党政治家アーサー・バルフォア(1848年~1930年)の肝煎りで創設された一種の社会改良団体で、アイルランドの貧困層の特に婦人の雇用促進などを図ったもの(後に首相となるが、彼はアイルランド自治権拡大要求には反対であった)。ネット上では「アイルランド密集地区委員会」などと訳されている。貧困地域を対象としたシステムであるから「繁華」という訳語は違和感がある。]
第 一 部

[桟橋]
私はアランモア〔アランの三島中最北に位する島〕にゐる。泥炭の火にあたり、部屋の下の小さな酒場から聞こえて來るゲール語の話し聲に耳傾けながら。
アランに來る汽船は潮時を見てやつて來る。私たちが深い霧に蔽はれたゴルウェーの波止場を見捨てたのは今朝六時であつた。
最初は右の方、波と霧の動く間に低い丘の連りが見えてゐたが、行くに從つてその影もなくなり、ただ索具にまつはる霧と小さな泡の渦卷のほか何も見えなくなつてしまつた。
乗客は少かつた。袋の中にゆるく小豚を縛りつけてやつて來た二人の男。首をすつぽりと襟卷に包んで船室に坐つてゐた三四人の少女。キルロナンの波止場を修繕に行く一人の大工、此の人は歩きまはつたり、私と話をしたりした。
三時間ばかりすると、アランが見え出した。先づ最初に荒涼たる岩が霧の中に海から盛り立つて現はれ、それから近づくに從つて、水上警察署や村が現はれて來た。
それから少し後、私は島の立派な道路に沿うて、両側の低い石垣越しに裸岩の僅かな平い畑地をのぞき込みながら歩いてゐた。私はこんな荒涼たる樣をかつて見たことがなかつた。灰色の水の溢れは、到る所で石灰岩の上を洗つて、時時道を激湍となしてゐた。それは、絶えず低い丘や岩の凹みの上をうねうねしたり、或ひは馬鈴薯畑や草原の間を通つて、隠れ場となつた隅の方へ失せ去つてゐた。雲が霽れる度ごとに、右手の下の方には海の端が見え、左手には高く島の裸かの隆起が見えた。たまに淋しい禮拜堂や學校の前を通つたり、また上に十字架がついて、祀つてある人の靈魂のために祈りをしてくれと銘を彫つてある石柱の列の前を通つたりもした。
人にはあまり逢はなかつた。ただ時時、キルロナンへ行く背の高い娘たちの群が通り過ぎて、樂しさうないぶかりの気持で私に呼びかけて、ゴルウェーの訛とはかなり違つた聞き馴れぬ抑揚の英語を話した。雨も寒さも物ともせず、彼女たちは元氣に笑ひ、ゲール語で大いにしやべりながら、私の傍を騒け過ぎて行き、濡れた岩の群を前より一層荒涼たらしめた。
正午少し過ぎて歸つて來る途中、一人の半盲の老人が私にゲール語で話しかけたが、大體からいつて、私はその方言の夥多と流暢に驚いた。
午後も雨が降り續いたので、私は此の宿にゐて、霧の中を數人の男がコニマラ〔愛蘭土本島、ゴルウェー州にある町〕から泥炭を積んで來た)
宿の婆さんが會話の教師を見付けてくれると約束してあつたが、少したつと、階段の上に足を引き摺る音がして、今朝話しかけた半盲の老人が部屋の中へ手探りではひつて來た。
彼を爐の所まで連れて行き、私たちは何時間も話した。彼はピートリもサー・ウィリアム・ワイルドも、その他現代の考古學者を知つてゐると云つた。それから、フィンク博士やペダーソン博士に愛蘭土語を教へた事もあれば、アメリカのカーティン氏に昔話を聞かした事もあると云つた。中年を少し過ぎて彼は崖から落ち、その時以來視力を失ひ、手や首が震へるやうになつたのであつた。
話してゐる時に、彼は火の上にのしかかり、震へながら目をつぶつてゐるが、顏は云ふに云はれぬやさしみがあつて、機智や惡意のこもつた話をする時は愉快の絶頂に達して輝き出し、宗教や妖精の事を話す時は暗く淋しくなつてしまつた。
彼は自分の力量と才能にも、自分の話す話が世界中のどの話よりもすぐれてゐることにも大きな自信を持つてゐた。話がカーティン氏の事になつた時、その人はアメリカでアランの物語を本にして、それを賣つて五百ポンド儲けたと云つた。
「それから、どうしたと思いますか?」彼は續けた。「私の話でうんと金を儲けた後、今度は自分で話を作つて本を書いた。そしてそれを出したのですが、半ペンスだつて儲かりませんや。どうです?」
その後、彼は一人の子供が妖精にとられた話をした。
或る日、近所の女が通つてゐた。道ばたで彼女が其奴を見た時、「まあ綺麗な子供」と云つた。
その子の母親が、「神さまお惠みください」と云はうとすると、聲が喉につかへて出なかつた。少したつてその子供の頸に傷のあるのに氣づいた。三日三晩、家の中が騒がしかつた。
「私は夜分シャツを着ないのです。」と彼は云つた。「でも家の騒ぎを聞くと、裸か同然で床から飛び起きて、
すると一人の啞がやつて棺に釘を打ちつける手眞似をした。
次の日は種芋に花が一杯咲いて、子供は母親にアメリカへ行くと云つた。
その晩子供は死んだ。「全くですよ、妖精に取られたのです。」と老人は云つた。
彼が歸つて行くと、小さい跣足の女の子が泥炭と火を起す
その女の子ははにかみやあつたが、話し好きで、立派な愛蘭土語が話せるとか、學校で愛蘭土語を教はつてゐるとか、此處では大人の女でも本土に足を踏み入れたことのない者が澤山あるのに、自分はゴルウェーに二度も行つたことがあるとか話した。
*
Part I
I AM IN Aranmor, sitting over a turf fire, listening to a murmur of Gaelic that is rising from a little public-house under my room.
The steamer which comes to Aran sails according to the tide, and it was six o'clock this morning when we left the quay of Galway in a dense shroud of mist.
A low line of shore was visible at first on the right between the movement of the waves and fog, but when we came further it was lost sight of, and nothing could be seen but the mist curling in the rigging, and a small circle of foam.
There were few passengers; a couple of men going out with young pigs tied loosely in sacking, three or four young girls who sat in the cabin with their heads completely twisted in their shawls, and a builder, on his way to repair the pier at Kilronan, who walked up and down and talked with me.
In about three hours Aran came in sight. A dreary rock appeared at first sloping up from the sea into the fog; then, as we drew nearer, a coast-guard station and the village.
A little later I was wandering out along the one good roadway of the island, looking over low walls on either side into small flat fields of naked rock. I have seen nothing so desolate. Grey floods of water were sweeping everywhere upon the limestone, making at limes a wild torrent of the road, which twined continually over low hills and cavities in the rock or passed between a few small fields of potatoes or grass hidden away in corners that had shelter. Whenever the cloud lifted I could see the edge of the sea below me on the right, and the naked ridge of the island above me on the other side. Occasionally I passed a lonely chapel or schoolhouse, or a line of stone pillars with crosses above them and inscriptions asking a prayer for the soul of the person they commemorated.
I met few people; but here and there a band of tall girls passed me on their way to Kilronan, and called out to me with humorous wonder, speaking English with a slight foreign intonation that differed a good deal from the brogue of Galway. The rain and cold seemed to have no influence on their vitality and as they hurried past me with eager laughter and great talking in Gaelic, they left the wet masses of rock more desolate than before.
A little after midday when I was coming back one old half-blind man spoke to me in Gaelic, but, in general, I was surprised at the abundance and fluency of the foreign tongue.
In the afternoon the rain continued, so I sat here in the inn looking out through the mist at a few men who were unlading hookers that had come in with turf from Connemara, and at the long-legged pigs that were playing in the surf. As the fishermen came in and out of the public-house underneath my room, I could hear through the broken panes that a number of them still used the Gaelic, though it seems to be falling out of use among the younger people of this village.
The old woman of the house had promised to get me a teacher of the language, and after a while I heard a shuffling on the stairs, and the old dark man I had spoken to in the morning groped his way into the room.
I brought him over to the fire, and we talked for many hours. He told me that he had known Petrie and Sir William Wilde, and many living antiquarians, and had taught Irish to Dr. Finck and Dr. Pedersen, and given stories to Mr. Curtin of America. A little after middle age he had fallen over a cliff, and since then he had had little eyesight, and a trembling of his hands and head.
As we talked he sat huddled together over the fire, shaking and blind, yet his face was indescribably pliant, lighting up with an ecstasy of humour when he told me anything that had a point of wit or malice, and growing sombre and desolate again when he spoke of religion or the fairies.
He had great confidence in his own powers and talent, and in the superiority of his stories over all other stories in the world. When we were speaking of Mr. Curtin, he told me that this gentleman had brought out a volume of his Aran stories in America, and made five hundred pounds by the sale of them.
'And what do you think he did then?' he continued; 'he wrote a book of his own stories after making that lot of money with mine. And he brought them out, and the divil a half-penny did he get for them. Would you believe that?'
Afterwards he told me how one of his children had been taken by the fairies.
One day a neighbor was passing, and she said, when she saw it on the road, 'That's a fine child.'
Its mother tried to say 'God bless it,' but something choked the words in her throat.
A while later they found a wound on its neck, and for three nights the house was filled with noises.
'I never wear a shirt at night,' he said, 'but I got up out of my bed, all naked as I was, when I heard the noises in the house, and lighted a light, but there was nothing in it.'
Then a dummy came and made signs of hammering nails in a coffin. The next day the seed potatoes were full of blood, and the child told his mother that he was going to America.
That night it died, and 'Believe me,' said the old man, 'the fairies were in it.'
When he went away, a little bare-footed girl was sent up with turf and the bellows to make a fire that would last for the evening.
She was shy, yet eager to talk, and told me that she had good spoken Irish, and was learning to read it in the school, and that she had been twice to Galway, though there are many grown women in the place who have never set a foot upon the mainland.
[やぶちゃん注:「夥多」は「かた」と読み、甚だ多いこと。
「脚長豚」原文“long-legged pigs”はそういう豚の品種ではないと思われる。所謂、子ブタや若い豚ではなく、親豚のことであろう。
「彼は一人の子供が妖精にとられた話をした。」ちょっとわかりにくいが、後のシャツの附言部分から、以下の、妖精に攫われた子供というのはこの話し手の老人の子であり、この「母親」とは彼の妻であることが分かる。]
雨が上つたので、私は島とその住民たちに眞實の初のお目見得をした。
私はキラニー――アランモアの最も貧しい村――を通り拔けて、南西へ海の中に伸びてゐる砂山の長い頸まで出かけた。其處で草の上に坐ると、コニマラの山には雲が霽れて、しばらくの間靑く起伏する前景は、遠くの山山を背景として、私にローマ近くの田舎を想ひ出させた。その時一艘の
尚行くと、一人の子供と男が隣村から下りて來て、私に話かけた。今度は英語が不完全ながら通用した。私が此の島には
彼等は私をつれて、此の島とイニシマーン――群島の中央の島――を隔ててゐる瀨戸まで行つて、二つの絶壁の間に大西洋から打ち寄せてゐるうねりを見せてくれた。
イニシマーンには愛蘭土語を習ひに來てゐる人が幾人か滯在してゐるさうで、男の子は島の中央に圓く藁の帶の樣に並んでゐる小屋の列を指した。その人たちはそこに住んでゐるのである。そこは殆んど人の住めさうな處とは思へなかつた。靑い物は何も見えず、人のゐるけはひといつては、その蜂の巣の樣な屋根とその上に空の際に屹立した一つの
やがてその道連れが行つてしまふと、ほかの二人の子供が私の直ぐ後からついて來た。たうとう私は振り向いて話をさせた。彼等は先づ自分たちの貧しい事を話し、それからその中の一人が云つた――
「あなたはホテルで一週間に十シリングも拂ふのでせう?」
「もつと。」 私は答へた。
「十二シリング?」
「もつと。」
「十五シリング?」
「まだ、もつと。」
それで彼等は引き下つて、それ以上聞かなかつた。私が彼等の好奇心を止める爲に嘘をついてゐると思つたのか、私の富に恐れてそれ以上續け得なかつたのか知らないが。
キラニーを再び通つてゐると、アメリカに二十年居たと云ふ男に出逢つた。彼はアメリカで健康を害して戻つて來たのだが、餘程以前に英語を忘れてしまつたと見えて、云ふ事が殆んどわからなかつた。見るからに希望もなく、不潔で、喘息氣味であつたが、二三百ヤードもー緒に歩いて行くと、立ち止つて銅貨をくれと云つた。私は持ち合はせてなかつたので煙草をやつた。すると彼は小屋の方へ歸つて居った。
彼が行つてしまふと、代りに二人の小さい娘の子がついて來たので、今度は彼等に話させた。
彼等は優しさのこもつた非常に微妙な異國的な抑揚で話し、夏になると、ladies and gentlemins(御婦人や旦那さんたち)を近所の名所へ案内して、バンプーティーズ〔まだ鞣さない牛皮で造つた一種のスリッパ或は草鞋〕や岩の中に澤山ある孔雀齒朶を賣りつける話を、歌のやうな調子で話した。
さてキルロナンに歸つて來て別れようとすると、二人の娘の子は自分達の履いてゐるバンプーティーズ即ち革草鞋の穴を見せて新しいのを買ふ代償を私にくれと云つた。私は財布が空だと云ふと、彼等は小聲で挨拶をして向うむいて波止場の方へ下りて行つた。
此の歸り道は非常にきれいだつた。愛蘭土にのみ、而かも雨後に限つて見られる烈しい島嶼的な明るさが、海にも空にもあらゆる漣波〔さざなみ〕を描き出し、入江の向うには山山のあらゆる皺襞〔ひだ〕を描き出してゐた。
*
The rain has cleared off, and I have had my first real introduction to the island and its people.
I went out through Killeany--the poorest village in Aranmor--to a long neck of sandhill that runs out into the sea towards the south-west. As I lay there on the grass the clouds lifted from the Connemara mountains and, for a moment, the green undulating foreground, backed in the distance by a mass of hills, reminded me of the country near Rome. Then the dun top-sail of a hooker swept above the edge of the sandhill and revealed the presence of the sea.
As I moved on a boy and a man came down from the next village to talk to me, and I found that here, at least, English was imperfectly understood. When I asked them if there were any trees in the island they held a hurried consultation in Gaelic, and then the man asked if 'tree' meant the same thing as 'bush,' for if so there were a few in sheltered hollows to the east.
They walked on with me to the sound which separates this island from Inishmaan--the middle island of the group--and showed me the roll from the Atlantic running up between two walls of cliff.
They told me that several men had stayed on Inishmaan to learn Irish, and the boy pointed out a line of hovels where they had lodged running like a belt of straw round the middle of the island. The place looked hardly fit for habitation. There was no green to be seen, and no sign of the people except these beehive-like roofs, and the outline of a Dun that stood out above them against the edge of the sky.
After a while my companions went away and two other boys came and walked at my heels, till I turned and made them talk to me. They spoke at first of their poverty, and then one of them said--'I dare say you do have to pay ten shillings a week in the hotel?' 'More,' I answered.
'Twelve?'
'More.'
'Fifteen?'
'More still.'
Then he drew back and did not question me any further, either thinking that I had lied to check his curiosity, or too awed by my riches to continue.
Repassing Killeany I was joined by a man who had spent twenty years in America, where he had lost his health and then returned, so long ago that he had forgotten English and could hardly make me understand him. He seemed hopeless, dirty and asthmatic, and after going with me for a few hundred yards he stopped and asked for coppers. I had none left, so I gave him a fill of tobacco, and he went back to his hovel.
When he was gone, two little girls took their place behind me and I drew them in turn into conversation.
They spoke with a delicate exotic intonation that was full of charm, and told me with a sort of chant how they guide 'ladies and gintlemins' in the summer to all that is worth seeing in their neighbourhood, and sell them pampooties and maidenhair ferns, which are common among the rocks.
We were now in Kilronan, and as we parted they showed me holes in their own pampooties, or cowskin sandals, and asked me the price of new ones. I told them that my purse was empty, and then with a few quaint words of blessing they turned away from me and went down to the pier.
All this walk back had been extraordinarily fine. The intense insular clearness one sees only in Ireland, and after rain, was throwing out every ripple in the sea and sky, and every crevice in the hills beyond the bay.
[やぶちゃん注:「イニシマーンには愛蘭土語を習ひに來てゐる人が幾人か滯在してゐるさうで、男の子は島の中央に圓く藁の帶の樣に並んでゐる小屋の列を指した。その人たちはそこに住んでゐるのである。」の部分は、そうした人々が現にそこに住んでいるとしか読めないのであるが、続く文章を読む限り、どうもそうではなく、嘗て滞在していた、というニュアンスを感じる。原文は“They
told me that several men had stayed on Inishmaan to learn Irish, and the
boy pointed out a line of hovels where they had lodged running like a belt
of straw round the middle of the island.”で“several men had stayed”“they
had lodged”と過去完了であるし、「その人たちはそこに住んでゐるのである。」に相当する独立文はない。訳者は後半部分であまりにも荒涼たる石積みの小屋で人は住めそうにない、人の気配はない、しかし、いるらしいと判断したものか。また、後文で彼らの訛が強烈で性人称なども区別しないとあるから、筆者はここも彼らの謂いの時制上のそうした特異性を出そうとしたものかも知れない。しかしやはり続く描写の人影もない荒涼感からは、ここは素直に例えば『イニシマーンにはアイルランド語を習いに来た人が幾人か滞在していたそうで、男の子は、その人たちが住んでいたという島の中央に円く藁の帯の樣に並んでいる小屋の列を指した。しかし、そこは殆んど人の住めそうな処とは思えなかった。……』とシンプルに続けて読みたくなるところである。
「孔雀齒朶」“maidenhair ferns”シダ植物門シダ目ホウライシダ科ホウライシダ属ホウライシダAdiantum capillus-veneris 若しくはクジャクシダAdiantum pedatum かその近縁種と思われる。一応、現在の“maidenhair ferns”は正式には前者の英名である(但し、植生域からはこれに同定するのはやや疑問か)。この属の種には現在でも観葉植物として高い価値を持つものが多い。]
今夜、一人の老人が私を訪ねて來た。彼は四十三年前、暫く此の島にゐた私の親戚を知つてゐると云つた。
「お前さんが船からやつて來る時、私は波止場の石垣の下で網を繕つてゐた。」と彼は云つた。「シングと云ふ名の人が、若し此の世界に出かけて來るとすれば、あの人こそ其の人だらうと、その時預言を云つた。」
彼は、少年時代を終らないうちに船員となつて、此の島を離れた時から此處に行はれた變遷を妙に短いが品位のある言葉で慨き續けた。
「私は歸つて來て、」と彼は云つた。「妹と一軒の家に住んだが、島は前とは全然變り、現在居る人から私は何のお蔭も蒙らないし、又彼等も私から何の
さういつた話からすると、此の男は一種獨特の
少したつて、茶の間の方へ下りて行くと二人の男がゐた。此の人たちは中の島〔イニシマーン〕から來て、此の島で日が暮れたのである。彼等は此處の人達より純撲で、恐らくより興味ある型の人であらう。念入りな英語で
*
This evening an old man came to see me, and said he had known a relative of mine who passed some time on this island forty-three years ago.
'I was standing under the pier-wall mending nets,' he said, 'when you came off the steamer, and I said to myself in that moment, if there is a man of the name of Synge left walking the world, it is that man yonder will be he.'
He went on to complain in curiously simple yet dignified language of the changes that have taken place here since he left the island to go to sea before the end of his childhood.
'I have come back,' he said, 'to live in a bit of a house with my sister. The island is not the same at all to what it was. It is little good I can get from the people who are in it now, and anything I have to give them they don't care to have.'
From what I hear this man seems to have shut himself up in a world of individual conceits and theories, and to live aloof at his trade of net-mending, regarded by the other islanders with respect and half-ironical sympathy.
A little later when I went down to the kitchen I found two men from Inishmaan who had been benighted on the island. They seemed a simpler and perhaps a more interesting type than the people here, and talked with careful English about the history of the Duns, and the Book of Ballymote, and the Book of Kells, and other ancient MSS., with the names of which they seemed familiar.
[やぶちゃん注:「シングと云ふ名の人が、若し此の世界に出かけて來るとすれば」原文は“if there is a man of the name
of Synge left walking the world”。この訳は「此の世界に出かけて來る」がやや奇異で、「此の世界」をアラン島と取るか、若しくは特殊な宗教観からある別な世界からこの現実世界へやって来るという意味になるが、それを伝えるには如何にも苦しい訳である。寧ろ、“walk
the world”は、“walk”の古語としての意を受けた、世を渡る、この世に生きるの謂いで、『もしシングという名の、今もこの世の中に生き残っている人がいるというなら』という意味であろう。
『「バリモートの書」「ケルスの書」』“Book of Ballymote, and the Book of Kells”はいずれもアイルランド文学の至宝。前者は14世紀の写本でケルトの神話を語るもので、アイルランドのスライゴ州バリモートに由来する。後者は紀元後700~800年にかけて制作された、四種の福音書によるイエス・キリストの生涯を華麗な文字で綴った初期キリスト教芸術の重宝で、ミーズ州ケルズに由来する。現在は「ケルズ」と表記するのが一般的。
「昔の寫本」原文“ancient MSS.”。“MSS.”は“manuscript”(マニュスクリプト)の省略形で手稿・写本のこと。]
到着した日に逢つた半盲の老人、即ち私の教師に心惹かれたにも關らず、私はイニシマーンに移る事にきめた。其處ではゲール語がもつと一般的に使はれ、その生活は、恐らく歐洲に殘つてゐる中で最も原始的な處である。
此の最後の日の一日中、私は半盲の案内人と、島の東部或ひは西北部に多くある古蹟を見物しながら過した。
出かける時、我我の道連れ――ムールティーン爺さんは時鳥と田雲雀の道連れの樣だと云つた――を笑つてゐる一團の娘の中に、際立つて精神的な表情をしてゐる美しい瓜實顏の女を私は見とめた。そんな顏は西部愛蘭土の女の或る型に著しいのである。此の日、後で老人は妖精とそれに騙された女の話を續けざまにしたが、島で信じられてゐる野蠻な神話と女の不思議な美しさの間に、関係がありさうに思へた。
正午ごろ一軒の廢屋の近くに休んでゐると、二人の綺麗な男の子が來て、傍に坐つた。ムールティーン爺さんは子供たちに、廢屋になつた譯、住んでゐた人の事を尋ねた。
「或る金持の百姓が前に建てた。」と彼等は云つた。「だが、二年の後に妖精の群に追ひ立てられてしまつた。」
子供たちは、今でも完全に殘つてゐる古い蜂の巣狀の家の一つを訪ねる爲に、北の方へかなりの道を我我について來た。我我は四つん這ひになつてはひり、内部の眞暗な中で立ち上つた時、ムールティーン爺さんは俗気臭いをかしな空想を考へ、若し彼が靑年であつて、若い女とはひつて來たら、どんな事になつたらうと語り出した。
それから彼は床下の眞ん中に坐つて、昔の愛蘭土の詩を誦し始めた。その音調の美しい純粋さは、意味はよく解らなかつたが、私に涕を催させた。
歸る途中、彼は妖精に就いてカトリック教的な話を聞かせてくれた。
悪魔が鏡で自分の姿を見た時、神と同じであると息つた。それで天主は彼とその家來の天使全部を天界から追ひ出した。天主が彼等を「つまみ出してゐる」最中、大天使が天主に彼等の或る者の赦しを願つた。それで墜落しつつあつた者は今でも空中に住んで、船を難破させたり、世の中に災害を起したりする力を持つてゐる。
それから話は神學の退屈な事柄に分れてゆき、かつて坊さんから聞いた愛蘭土語の説教や祈禱を長長と繰り返し初めた。
少し行くと、スレート葺の家へ來た。私は彼處に誰が住んでゐたのかと聞いた。
「學校の女の先生の樣な人」と彼は答へ、それからその年取つた顔を皺寄らせて、ちらりと異教的ないたづら氣を見せた。
「旦那、」と彼は云つた。「その中へはひつて、彼女に接吻したらよかつたらう。」
此の村から二哩ばかり行つた所で、カハル・オールウィン(美しき四人の人)と云ふ教會の廢墟と、その近くの盲目と癲癇によく效くので有名な靈泉を見物しに立寄つた。
我我がその泉の近くに腰掛けてゐると、道傍の家から一人の非常に年とつた老人が出て來て、泉の有名になつた譯を話した。
「スライゴの或る女が、生れながら盲目の息子を持つてゐた。或る晩、息子の目によく效く泉が、或る島の中にあると云ふ夢を見た。その朝、息子に話すと、或る老人が、彼女の夢にみたのはアランだと教へてくれた。
彼女は息子をゴルウェーの濱沿ひに連れて來て、カラハ〔アランで土人の乘る小船、木の骨組に麻布又は牛皮を張つて造る〕に乘つて出かけ、此の下に少し入江になつて見えるでせう。あすこに上陸した。
その女は當時私の父であつた家に歩いて來た。そして何を探してゐるかを話した。
私の父は、その夢と同じやうな處がある事を云つて、道案内に子供を遣ると云つた。
『少しも、それには及びません。其處はみんな夢で見て知つてゐるのですもの。』と彼女は云つた。
そこで子供と共に出かけ、その泉まで歩いて來て、跪いて祈りを初めた。それから水の方に手を差し伸べて、それを子供の目に當て、觸つたと思ふと、子供は『あッお母さん、美しい花を御覧!』と叫んだ。」
その後でムールティーンは密釀酒の酒盛りや若い時にした喧嘩のことをくはしく話した。それからサムソンに次いで力持であつたダーミッド〔愛蘭土の神話の勇者〕の話、及び島の東方にあるダーミッドとグレーン〔同じ神話の中の女王で、ダーミッドを誘惑したと傳へられる〕の寝床に就いての話となつた。ダーミッドはドルドイ僧に、火のついたシャツを着せられて、殺されたと云つた、――これは野天學校〔愛蘭土の臨時野外學校〕の先生の民謠の「學問」に依るのではないが、ダーミッドとヘルクレスの傳説とを結びつけ得る神話の斷片であらう。
それから我我はイニシマーンに就いて話した。
「あすこに、お前さんの話相手になる爺さんが居るだらう」と彼は云つた。「そして、妖精の話をする。だがあの人は此の十年間、二本の杖を賴りに歩いてゐる。若い時は四本足で、その後二本足で、それから年を取ると三本足で歩く者を知つてゐるかね?」
私は答を與へた。
「おお、旦那、」彼は云つた。「お前さんは利巧だ。神の惠みよ、お前さんの上に。さうだ、私は今三本足、あすこの爺さんは四本足に戻つた。でもどつちの
*
ln spite of the charm of my teacher, the old blind man I met the day of my arrival, I have decided to move on to Inishmaan, where Gaelic is more generally used, and the life is perhaps the most primitive that is left in Europe.
I spent all this last day with my blind guide, looking at the antiquities that abound in the west or north-west of the island.
As we set out I noticed among the groups of girls who smiled at our fellowship--old Mourteen says we are like the cuckoo with its pipit--a beautiful oval face with the singularly spiritual expression that is so marked in one type of the West Ireland women. Later in the day, as the old man talked continually of the fairies and the women they have taken, it seemed that there was a possible link between the wild mythology that is accepted on the islands and the strange beauty of the women.
At midday we rested near the ruins of a house, and two beautiful boys came up and sat near us. Old Mourteen asked them why the house was in ruins, and who had lived in it.
'A rich farmer built it a while since,' they said, 'but after two years he was driven away by the fairy host.'
The boys came on with us some distance to the north to visit one of the ancient beehive dwellings that is still in perfect preservation. When we crawled in on our hands and knees, and stood up in the gloom of the interior, old Mourteen took a freak of earthly humour and began telling what he would have done if he could have come in there when he was a young man and a young girl along with him.
Then he sat down in the middle of the floor and began to recite old Irish poetry, with an exquisite purity of intonation that brought tears to my eyes though I understood but little of the meaning.
On our way home he gave me the Catholic theory of the fairies.
When Lucifer saw himself in the glass he thought himself equal with God. Then the Lord threw him out of Heaven, and all the angels that belonged to him. While He was 'chucking them out,' an archangel asked Him to spare some of them, and those that were falling are in the air still, and have power to wreck ships, and to work evil in the world.
From this he wandered off into tedious matters of theology, and repeated many long prayers and sermons in Irish that he had heard from the priests.
A little further on we came to a slated house, and I asked him who was living in it.
'A kind of a schoolmistress,' he said; then his old face puckered with a gleam of pagan malice.
'Ah, master,' he said, 'wouldn't it be fine to be in there, and to be kissing her?'
A couple of miles from this village we turned aside to look at an old ruined church of the Ceathair Aluinn (The Four Beautiful Persons), and a holy well near it that is famous for cures of blindness and epilepsy.
As we sat near the well a very old man came up from a cottage near the road, and told me how it had become famous.
'A woman of Sligo had a son who was born blind, and one night she dreamed that she saw an island with a blessed well in it that could cure her son. She told her dream in the morning, and an old man said it was of Aran she was after dreaming.
'She brought her son down by the coast of Galway, and came out in a curagh,
and landed below where you see a bit of a cove.
'She walked up then to the house of my father--God rest his soul--and she told them what she was looking for.
'My father said that there was a well like what she had dreamed of, and that he would send a boy along with her to show her the way.
"There's no need, at all," said she; "haven't I seen it all in my dream?"
'Then she went out with the child and walked up to this well, and she kneeled down and began saying her prayers. Then she put her hand out for the water, and put it on his eyes, and the moment it touched him he called out: "O mother, look at the pretty flowers!"
After that Mourteen described the feats of poteen drinking and fighting that he did in his youth, and went on to talk of Diarmid, who was the strongest man after Samson, and of one of the beds of Diarmid and Grainne, which is on the east of the island. He says that Diarmid was killed by the druids, who put a burning shirt on him,--a fragment of mythology that may connect Diarmid with the legend of Hercules, if it is not due to the 'learning' in some hedge-school master's ballad.
Then we talked about Inishmaan.
'You'll have an old man to talk with you over there,' he said, 'and tell you stories of the fairies, but he's walking about with two sticks under him this ten year. Did ever you hear what it is goes on four legs when it is young, and on two legs after that, and on three legs when it does be old?'
I gave him the answer.
'Ah, master,' he said, 'you're a cute one, and the blessing of God be on you. Well, I'm on three legs this minute, but the old man beyond is back on four; I don't know if I'm better than the way he is; he's got his sight and I'm only an old dark man.'
[やぶちゃん注:「田雲雀」は「たひばり」と読む。原文“pipit”。スズメ目セキレイ科タヒバリAnthus pinoletta のこと。正式な英名は“Water Pipit”で、彼らはカッコウ目カッコウ科カッコウ属ホトトギスCuculus poliocephalus の托卵相手である(カッコウ目カッコウ科とホトトギス目ホトトギス科は同じである)。
「野蠻な神話」原文“wild mythology”。『粗野な神話』、『
「ムールティーン爺さんは俗気臭いをかしな空想を考へ」原文“old Mourteen took a freak of earthly humour”で、訳文はやや生硬な印象を受ける。『ムールティーン老師は若い頃のちょっとしたいたずらっ気を発揮して』ぐらいの感じであろう。
「坊さん」“priests”。カトリック教会の司祭たち。
「學校の女の先生の樣な人」“'A kind of a schoolmistress,'”『まあ、言うたら、
「カハル・オールウィン(美しき四人の人)」原文の“Ceathair Aluinn”はゲール語で“Ceathair”は4、“Aluinn”は美しい、の意。但し“Ceathair”はネット上のネイティヴの発音では「カハル」ではなく「エタフェル」と言うように聴こえる。
「カラハ」原文の綴りは“curagh”であるが、現在では一般には“currach”で、ゲール語では“koroko”、しばしば英国風には“curragh”と綴る。但し、スペルでは二つの“r”を一つで済ませるスペルも用いられるらしいので、シングの綴りは誤りではないものと思われる。
以下の盲人を開明させる聖なる泉の話は、後にシングが発表する戯曲「聖者の泉」を髣髴とさせる(リンク先は私の片山廣子(松村みね子)訳「聖者の泉」)。そういえば、あの主人公の男の名は“Martin”――マーチン、この老人の名は“Mourteen”、ムールティーン=マーチーンである。
「その女は當時私の父であつた家に歩いて來た。」ちょっと妙な日本語だなと思って原文を見ると、“She walked up then to the house of my father--God rest his soul--”となっており、これは敬虔なカトリック教徒の習慣が出た直接話法をそのままに写したことが分かった。則ち、死者のことを口にする時のマナーとして、「その亡き人の魂に神の御恵みを!」と添えたのである。だからここは『彼女が私のその頃の父――おぉ、安らかにねむり給え!――の家へとやって来て』といった台詞となる。
「密釀酒」原文は“poteen”で、ゲール語で非合法に蒸留したアイリッシュ・ウイスキーのこと。ポーティン。
「ドルドイ僧」は「ドルイド僧」の錯字。“the druids”は古代ケルト人のドルイド教の神官。聖樹信仰を核に、霊魂不滅・輪廻を中心教義とし、占星術を始めとする各種の占術を駆使した。
『――これは野天學校〔愛蘭土の臨時野外學校〕の先生の民謠の「學問」に依るのではないが、ダーミッドとヘルクレスの傳説とを結びつけ得る神話の断片であらう。』もやや分かり難い。原文は“--a fragment of mythology that may connect Diarmid with the legend of Hercules, if it is not due to the 'learning' in some hedge-school master's ballad.”であるが、訳の後半は問題がない。問題は“if it is not due to the 'learning' in some hedge-school master's ballad.”の部分である。まず、“hedge-school master”『アイルランドの臨時野外学校の先生』である。このヘッジ・スクールというのは、十八世紀初頭から十九世紀前半にかけて、アイルランド全土に広がった非合法の民衆教育組織で、垣根の陰に隠れて教師と子らが集って学校活動が行われたことに由来し、教区聖職者を中心に代書業・測量師等などを副業とした多彩な教師が運営し、そうした貧しい子らの親が授業料を支払って運営されていた独特の民間教育機関である。ペイ・スクールとも言う。このヘッジ・スクールがアイルランドの教育向上に大いに貢献したことは言うまでもない。但し、いわばそうした非公認の「先生」の中には、「先生」とは言うものの大した学識もない、“'learning'”、カッコ書きの 『(にわかハッタリの)学問』の持ち主もいたであろう(今の教師にも私を含めてゴマンといる)。そうした『にわか学問』によってデッチ上げられた“ballad”、バラッド、『民間伝承の物語詩』に“if it is not due to”『基づくものでないないとすれば』という意味であろう。則ち、ここは『――これはダーミッドとヘルクレス伝説とを結びつけ得る神話の断片であろう――但し、これがどこぞのヘッジ・スクールの大先生の「にわか学問」が発祥のバラードによるものでなかったとすれば、の話である。』というピリッと皮肉を込めた附言なのである。]
私は遂にイニシマーンの小さな家に落着いた。私の部屋の方へ開いてゐる茶の間から、絶えずゲール語の單調な聲がはひつて來る。
今朝早く、此の家の男が四挺櫂のカラハ――即ち、四人の漕手が居て、銘銘が二本づつ使へるやうに両側に四つの櫂があるカラハ――で私を迎へに來た。そして正午少し前出立した。
人間が初めて海に乘り出して以來、原始人に使はれた型の粗末な布のカヌーに乘つて、文明から逃れ出てゐると思ふと、私には云ひ知れぬ滿足の一時であつた。
我我は、常に碇泊してゐる
再び出發した時は、小さな帆を船首に揚げて、瀨戸横斷の途に就いた。その跳ぶやうな動搖はボートの重い進行とは餘程違つてゐた。
帆はただ補助として用ひるに過ぎず、帆を揚げた後も男たちは漕ぎ續ける。そして漕手は四つの横渡しの腰掛を占めてゐるので、私は船尾のカンバスの上、掩はれた木の骨組の
出かけた時、四月の朝は晴れ渡つて蒼いキラキラする波がカヌーをその中で押しやつてくれるやうであつたが、島に近づくにつれて、行手の岩の後から雷雨が起つて靜かな大西洋の氣分を一時かき交ぜた。
我我は小さな波止場から上陸した。其處から、アランモアに於けると同じやうに、粗末な路が小さな畑と一面の裸岩の間をねけて、村まで續いてゐる。船頭の中で最も年下の息子の十七歳ぐらゐの男の子は私の教師となり、また道案内人となる筈であるが、此男の子が波止場で私を待つてゐて、家まで案内してくれた。一方、男たちはカラハを片付け、私の荷物を提げてゆるゆる後から附いて來た。
私の部屋は家の一端にあつて、板張の床下と天井、互ひに向き合つた二つの窓がある。また茶の間には土間とむき出しの棰木があり、向き合つて二つの戸が戸外へ開くやうについてゐるが、窓はない。その奥に茶の間の半分ほどの廣さの二つの小さな部屋があるが、こ心れには一つづつの窓がある。
私は大抵の時を茶の間で過す積りだが、其處だけでも多くの美しさがあり、特色がある。爐の周りの椅子に腰掛けて集まる女たちの赤い着物は東洋的な豐かな色彩を出し、また泥炭の煙で軟かい茶褐色に彩られた壁は床下の灰色の土と色のよい配合を作る。いろいろの釣道具、網、男の雨合羽などが壁やむき出しの棰木に懸り、頭の上、草葺の屋根の下には革草鞋を造る剥いだままの年の皮がある。
此の群島のあらゆる品物には殆んど個性的な特色がある。その特色は藝術を全然知らない簡素な生活に、中世生活の藝術的美しさのやうな物を加へる。カラハ、
着物の質素と一樣さは又他の方面で、郷土色に美しさを加へる。女は赤いペティコート〔婦人或は子供の着る上着、普通腰の邊より下袴が下がる。〕や茜で染めた島の羊毛のジャケツを着て、その上に普通格子縞の襟卷を胸に卷いて、背中で結ぶ。雨の日には、顔の周りに腰帶をして、もう一つのペティコートを頭からかぶる。若ければ、ゴルウェーで着るやうな重い襟卷を使ふ。時には他の纏物をする。私が夕立の最中到着した時、數人の女が男の胴着を體の周りにボタンで締めて着てゐるのを見た。裾は餘り膝の下まで届かず、皆用意して持つてゐる濃い紺色の靴下を履いて、逞しい足を見せてゐる。
男は三つの色物を着る、即ち無地の羊毛、紺色の羊毛、無地と紺色の羊毛を互ひ違ひに織り交ぜた灰色のフランネルである。アランモアでは、多くの若い男は普通の漁夫の着るジャージー・ジャケツを用ひるが、此の島ではただ二人だけしか見かけなかつた。
フランネルは安いので――女たちが家の羊の毛から絲を造り、それをキルロナンで一ヤード四ペンスで織子が織るので――、男達は何枚も胴着を着、羊毛のズボンを重ねて穿くらしい。大抵の者は私の着物の輕いのに驚く。波止場で一寸口をきいた老人は私が岸に來ると「私の少しの着物」で寒くはなからうかと尋ねた。
茶の間で着物から水しぶきを乾かしてゐると、私の歩いて來るのを見た數人の人たちは、大抵敷居の所で、「今日は、ようこそ」と云ふやうな挨拶の言葉を、小聲で云ひながら、私と話さうとはひつて來た。
此の家のお婆さんの丁寧なのは非常に人の心を惹く、彼女の云ふ事は――英語を話さないので――大部分解らなかつたが、如何にもしとやかに客を年齡に應じて、或ひは椅子へ或ひは床机へと案内して、英語の會話につり込ませるまで二言三言を言つてゐるのだと見られた。
暫く私の來たことが興味の中心になつて、はひつて來る人たちはしきりに私と話したがる。
或る者は普通の百姓よりずづと正確にその考へを發表し、また或る者は絶えずゲール語の訛を出して、現代の愛蘭土語には中性名詞がないので、it の代りに
she か或は he を使ふ。
中には不思議にも単語を多く知つてゐる者もあるが、また英語の極く普通の言葉だけしか知らず、意味を表はすのに勢ひ巧妙な工夫をしなければならない者もある。我我の話し得る話題の中では戰爭を好むらしく、アメリカとスペインの戰爭は非常な興味を起させた。どの家族にも大西洋を渡らねばならなかつた者を親戚に持ち、また合衆國から來る小麥と燒豚を食べてゐるので、若しアメリカに何か起つたら暮らせなくなるだらうと云ふ漠然たる恐怖を持つてゐた。
外國語も亦好む話題であつて、二國語を使ふ彼等は、いろいろ違つた言葉で表現したり考へたりするのは如何なる意義があるかに就いて正しい考へを持つてゐる。此の島で知る外国人の多くは言語學者であるから、彼等は言語の研究、殊にゲール語の研究が外の世界でやつてゐる重な仕事であると勢ひ思ひ込んでゐる。
「私はフランス人にも、デンマーク人にも、ドイツ人にも逢つたことがある。」と一人の男が云つた。「その人たちは愛蘭土語の本をどつさり持つてゐて、我我よりもよく讀む。此の頃、世界で、金持でゲール語を研究してない人はないですよ。」
或る時は、簡單な文章の佛語を私に要求する。暫くその音調を聞いてゐると、大概の者は見事な正確さで眞似する事が出來た。
*
I am settled at last on Inishmaan in a small cottage with a continual drone of Gaelic coming from the kitchen that opens into my room.
Early this morning the man of the house came over for me with a four-oared curagh--that is, a curagh with four rowers and four oars on either side, as each man uses two--and we set off a little before noon.
It gave me a moment of exquisite satisfaction to find myself moving away from civilisation in this rude canvas canoe of a model that has served primitive races since men first went to sea.
We had to stop for a moment at a hulk that is anchored in the bay, to make some arrangement for the fish-curing of the middle island, and my crew called out as soon as we were within earshot that they had a man with them who had been in France a month from this day.
When we started again, a small sail was run up in the bow, and we set off across the sound with a leaping oscillation that had no resemblance to the heavy movement of a boat.
The sail is only used as an aid, so the men continued to row after it had gone up, and as they occupied the four cross-seats I lay on the canvas at the stern and the frame of slender laths, which bent and quivered as the waves passed under them.
When we set off it was a brilliant morning of April, and the green, glittering waves seemed to toss the canoe among themselves, yet as we drew nearer this island a sudden thunderstorm broke out behind the rocks we were approaching, and lent a momentary tumult to this still vein of the Atlantic.
We landed at a small pier, from which a rude track leads up to the village between small fields and bare sheets of rock like those in Aranmor. The youngest son of my boatman, a boy of about seventeen, who is to be my teacher and guide, was waiting for me at the pier and guided me to his house, while the men settled the curagh and followed slowly with my baggage.
My room is at one end of the cottage, with a boarded floor and ceiling, and two windows opposite each other. Then there is the kitchen with earth floor and open rafters, and two doors opposite each other opening into the open air, but no windows. Beyond it there are two small rooms of half the width of the kitchen with one window apiece.
The kitchen itself, where I will spend most of my time, is full of beauty and distinction. The red dresses of the women who cluster round the fire on their stools give a glow of almost Eastern richness, and the walls have been toned by the turf-smoke to a soft brown that blends with the grey earth-colour of the floor. Many sorts of fishing-tackle, and the nets and oil-skins of the men, are hung upon the walls or among the open rafters; and right overhead, under the thatch, there is a whole cowskin from which they make pampooties.
Every article on these islands has an almost personal character, which gives this simple life, where all art is unknown, something of the artistic beauty of medieval life. The curaghs and spinning-wheels, the tiny wooden barrels that are still much used in the place of earthenware, the home-made cradles, churns, and baskets, are all full of individuality, and being made from materials that are common here, yet to some extent peculiar to the island, they seem to exist as a natural link between the people and the world that is about them.
The simplicity and unity of the dress increases in another way the local air of beauty. The women wear red petticoats and jackets of the island wool stained with madder, to which they usually add a plaid shawl twisted round their chests and tied at their back. When it rains they throw another petticoat over their heads with the waistband round their faces, or, if they are young, they use a heavy shawl like those worn in Galway. Occasionally other wraps are worn, and during the thunderstorm I arrived in I saw several girls with men's waistcoats buttoned round their bodies. Their skirts do not come much below the knee, and show their powerful legs in the heavy indigo stockings with which they are all provided.
The men wear three colours: the natural wool, indigo, and a grey flannel that is woven of alternate threads of indigo and the natural wool. In Aranmor many of the younger men have adopted the usual fisherman's jersey, but I have only seen one on this island.
As flannel is cheap--the women spin the yarn from the wool of their own sheep, and it is then woven by a weaver in Kilronan for fourpence a yard--the men seem to wear an indefinite number of waistcoats and woollen drawers one over the other. They are usually surprised at the lightness of my own dress, and one old man I spoke to for a minute on the pier, when I came ashore, asked me if I was not cold with 'my little clothes.'
As I sat in the kitchen to dry the spray from my coat, several men who had seen me walking up came in to me to talk to me, usually murmuring on the threshold, 'The blessing of God on this place,' or some similar words.
The courtesy of the old woman of the house is singularly attractive, and though I could not understand much of what she said--she has no English--I could see with how much grace she motioned each visitor to a chair, or stool, according to his age, and said a few words to him till he drifted into our English conversation.
For the moment my own arrival is the chief subject of interest, and the men who come in are eager to talk to me.
Some of them express themselves more correctly than the ordinary peasant, others use the Gaelic idioms continually and substitute 'he' or 'she' for 'it,' as the neuter pronoun is not found in modern Irish.
A few of the men have a curiously full vocabulary, others know only the commonest words in English, and are driven to ingenious devices to express their meaning. Of all the subjects we can talk of war seems their favourite, and the conflict between America and Spain is causing a great deal of excitement. Nearly all the families have relations who have had to cross the Atlantic, and all eat of the flour and bacon that is brought from the United States, so they have a vague fear that 'if anything happened to America,' their own island would cease to be habitable.
Foreign languages are another favourite topic, and as these men are bilingual they have a fair notion of what it means to speak and think in many different idioms. Most of the strangers they see on the islands are philological students, and the people have been led to conclude that linguistic studies, particularly Gaelic studies, are the chief occupation of the outside world.
'I have seen Frenchmen, and Danes, and Germans,' said one man, 'and there does be a power a Irish books along with them, and they reading them better than ourselves. Believe me there are few rich men now in the world who are not studying the Gaelic.'
They sometimes ask me the French for simple phrases, and when they have listened to the intonation for a moment, most of them are able to reproduce it with admirable precision.
[やぶちゃん注:「掩はれた木の骨組の
「棰木」は「たるき」と読む。垂木。
「英語の會話につり込ませるまで二言三言を言つてゐるのだと見られた。」この訳文は文字通り“drift”(意味)が分からない。原文を見ると、“and said a few words to him till he drifted into our English conversation.”で、この“him”は直前の“visitor”を指し、『私を訪ねてきた幾分かは英語を喋れる男たちが私との英語の会話に入る前、その彼らにこのお婆さんが、二言三言、ゲール語で声をかけているその雰囲気を見る限り、彼女が丁寧で非常に人の心を惹くものを持った女性であることが感じられる』ということであろう。ここではシング自身も、このお婆さんの訛の強いゲール語は分からないのであって、いわばその雰囲気からお婆さんの人柄を体感しているということではなかろうか。
「アメリカとスペインの戰爭」一八九八年四月に勃発した米西戦争のこと。シングが最初にアラン島を訪問したのは同年五月十日から六月二十五日までであったから、文字通り、アップ・トゥ・デイトな関心事であった。結果的には八月にスペインの敗北で終結し、カリブ海及び太平洋のスペイン旧植民地の管理権はアメリカへ移った。
「燒豚」原文は“bacon”であるから今の感覚では違和感がある。ベーコンは塩漬けの豚肉を燻製にしたものであり、焼豚は豚肉を炙り焼きや煮込んだもので製法も異なる。本書が刊行された昭和十二(一九三七)年ではベーコンは一般的な日本語としては通じ難かったということか。]
今朝、愛蘭土語を私に教へてゐる靑年のマイケルと島を散歩しようと出かけた時、宿の方へ向つて行く一人の老人に出逢つた。彼は本土から來たと見えるみすぼらしい黑い着物を着て、遠くから見れば人間よりは一層蜘蛛に見えるほどにリューマチスのため體が曲つてゐた。
マイケルはあれはあちらの島でムールティーン爺さんが話した物語師のパット・ディレイン爺さんであると語つた。その人は偶然にも私を訪ねて來るらしいので、引返したかつたが、マイケルは聞かなかつた。
「我我が歸つたら火の側に居るでせう」と彼は云つた。「心配はありませんよ。これから少しづつ話す時は充分あるでせう。」
彼の云つた通りであつた。それから何時聞かの後、私が茶の間の方へ下りて行つた時、パット爺さんは炭の爐で目をしばたたかせながら、爐の側にまだ居た。
彼は非常に器用にまた流暢に英語を話す。これは彼が若い時、收穫の爲英國の田舍に數ケ月働きに行つてゐた爲に違ひない。
二三の型の如き挨拶の後、彼はオールド・ヒン(即ち、インフルエンザ)にやられて
お婆さんが私の食事を作つてゐる間、彼は私に物語が好きかどうかを尋ねて、若しゲール語に附いて行けるならよいがと云ひ足しながら、英語で一つの物語をしようと云つた。そして語り始めた。――
*
When I was going out this morning to walk round the island with Michael, the boy who is teaching me Irish, I met an old man making his way down to the cottage. He was dressed in miserable black clothes which seemed to have come from the mainland, and was so bent with rheumatism that, at a little distance, he looked more like a spider than a human being.
Michael told me it was Pat Dirane, the story-teller old Mourteen had spoken of on the other island. I wished to turn back, as he appeared to be on his way to visit me, but Michael would not hear of it.
'He will be sitting by the fire when we come in,' he said; 'let you not be afraid, there will be time enough to be talking to him by and by.'
He was right. As I came down into the kitchen some hours later old Pat was still in the chimney-corner, blinking with the turf smoke.
He spoke English with remarkable aptness and fluency, due, I believe, to the months he spent in the English provinces working at the harvest when he was a young man.
After a few formal compliments he told me how he had been crippled by an attack of the 'old hin' (i.e. the influenza), and had been complaining ever since in addition to his rheumatism.
While the old woman was cooking my dinner he asked me if I liked stories, and offered to tell one in English, though he added, it would be much better if I could follow the Gaelic. Then he began:--
[やぶちゃん注:「それから何時聞かの後、私が茶の間の方へ下りて行つた時、パット爺さんは炭の爐で目をしばたたかせながら、爐の側にまだ居た。」は若干気になる。原文は“As
I came down into the kitchen some hours later old Pat was still in the
chimney-corner, blinking with the turf smoke.”で、“came down”とある。ところが既に読者には分かっている通り、彼の宿は平屋である。これは冒頭前文の“I
met an old man making his way down to the cottage.”を受けるものであろう。則ち、シングとマイケルは島巡りをするために、宿からある小道を伝って登って行った。そのルートとは異なった宿へ下る小道をパット爺さんは降りてきたのであった。シングが「数時間の後」の島巡りを終えて、「下り道を降りて」、宿の、その茶の間へと入った時、パット爺さんは「炭の爐で目をしばたたかせながら、爐の側にまだ居た」ということであろう。この間合いが、アランの神話へと導かれる前哨として美事、と私は思うのである。
「オールド・ヒン(即ち、インフルエンザ)」原文“'old hin' (i.e. the influenza)”。“hin”が分からない。栩木伸明氏訳2005年みすず書房刊の「アラン島」では、『めんどりバーバ』(ルビに『インフルエンザ』)という不思議な訳がなされていた。それを凝っと見ながら――成程!――と合点した。“hin”は“hen”(雌鶏)のパット爺さんの訛なのだ。栩木氏の「バーバ」は「雌鶏の御婆ちゃん」の意ではあるまいか?――それにしても、どうしてインフルエンザをこう呼ぶのだろう。まさか、鳥インフルエンザじゃあなかろうし、くしゃみの声とか、くしゃみをしたときの動作からの老いた雌鶏の連想だろうか?]
クレア郡に二人の百姓がゐた。一人は息子を持ち、もう一人の立派な金持の方は一人の娘を持つてゐた。
若者はその娘を妻に貰ひたかつた。父は彼にあのやうな女を貰ふには金が澤山要るだらうが、よいと思ふならやつてみよと云つた。
「やつてみませう」と若者は云つた。
彼は金のありつたけを袋につめた。さうしてもう一人の百姓の所へ行つて、その前に金を投げ出した。
「たつたそれだけか?」と娘の父は云つた。
「これだけです。」 オーコナーは云つた。(若者の名はオーコナーであつた。)
「それではとても娘と釣り合はない。」 父親が云つた。
「試してみませう。」 オーコナーは云つた。
そこで、片方には娘を、もう片方には金を、秤の上に載せて量つた。娘の方がどつかりと地面に落ちたので、オーコナーは袋をとつて往來へ出た。
歩いて行くと、一人の小男が居て、壁にもたれて立つてゐる所へ來た。
「袋を持つて何處へ行く?」小男が云つた。
「家へ行くのです。」 オーコナーが云つた。
「金が要るのぢやないか」小男が云つた。
「その通りです。」 オーコナーが云つた。
「要るだけお前に遣らう。」小男は云つた。「かう云ふ約束をしよう。一二年たつたら遣つた金を返してくれ。返さなかつたら、お前の肉を五ポンド切り取つて貰ふぞ。」
二人の間にそんな約束が出來た。その男はオーコナーに金の袋を與へ、彼はそれを持ち歸つて娘と結婚した。
彼等は金持になり、クレアの絶壁に妻の爲に大きな屋敷を建て、荒海を直ぐ眺められる窓を付けた。
或る日、彼は妻と登つて行き、荒海を眺めてゐると、一艘の船が岩に乘り上げ、帆もかけてないのを見た。それは岩の上で難破してゐたので、茶と立派な絹が積み込んであつた。
オーコナーとその妻は難破船を見に下りて行き、夫人は絹を見ると、それで着物が作りたいと云つた。
彼等は水夫たちから絹を買つた。船長がその代金を貰ひに來た時、オーコナーは一緒に晩飯を食べに來るやうに言つた。皆んな澤山御馳走を食ひ、その後で酒を飲んで、船長は醉つた。酒盛りの最中に一本の手紙がオーコナーに來た。それは友達の死んだ通知で、彼は長い旅に出かけなければならなかつた。支度をしてゐると、船長は彼の傍へ來た。
「あなたは奥さんが好きですか?」船長は聞いた。
「好きです。」 オーコナーは答へた。
「あなたが旅に出てゐる間、どんな男も奥さんに近づかなかつたら二十ギニ賭けませんか?」
「賭けませう。」 オーコナーはさう言つて、出かけた。
屋敷の近くの道傍でつまらない物を賣つてゐる婆が居た。オーコナーの夫人は彼女を自分の部屋に上らせ、大きな箱の中で寢ることを許した。船長は道傍の婆の所へ行つた。
「いくら出せばお前の箱の中で一晩私を寢かしてくれるか?」と聞いた。
「いくら貰つてもそんな事は駄目です。」と婆は云つた。
「十ギニ?」
「駄目です。」
「十二ギニ?」
「駄目です。」
「十五ギニ?」
「それならよろしい。」
そこで婆はその金を貰ひ、船長を箱の中に隠した。夜になるとオーコナ一夫人は部屋にはひつて來た。船長が箱の穴から見てゐると、彼女は三つの指環を拔き、それを頭の上の爐棚のやうになつた板の上に置き、それから肌着のほか皆着物を脱いで、床にはひつた。
彼女が寢込んでしまふと、船長は早速箱から出て來て、蠟燭に火を
爺さんは一寸休んだ。すると、話の間に茶の間が一杯になるまで集まつて來てゐた男女の口から救はれた重い溜息が洩れた。
船長が箱から出て來るあたりから、英語を知らないらしい女たちも、糸を紡ぐ手を止めて、その先を聞かうと息を凝らしてゐた。
爺さんは續けた――
オーコナーが歸つて來ると、船長は彼に逢つて、一晩奥さんの部屋にはひつたことがあると云つて、二つの指環を渡した。
オーコナーは賭の二十ギニを出した。それから屋敷へ上つて、窓から荒海を眺めようと妻を連れ出し、眺めてゐる間に彼女を後から突くと、彼女は崖の上から海の中へ落ちた。
一人のお婆さんが岸に居て、落ちるのを見てゐた。波の中にはひつて行き、づぶぬれになり狂人のやうになつてゐる夫人を引き上げ、濡れた着物を脱がせ、自分の襤褸を着せた。
オーコナーは妻を窓から突き落すと、陸の方へ逃げた。
暫くして夫人はオーコナーを探しに出かけ、国中を長い間あちこち歩いてゐるうち、彼は畑で六十人の人たちと一緒に刈入れをしてゐると云ふ噂を耳にした。
彼女はその畑にやつて來て、はひらうとしたが門番が門を開けてくれない。その時、畑の持主が通りかかつたので、譯を話して中にはひつた。彼女の夫は其處で刈入れをしてゐたが、彼女を知らないのか、目もくれない。そこで持主に夫を教へて、出して貰ひ、一緒に出かけた。
夫人は馬の居る道へ連れて來て、二人は馬に騎つて立ち去つた。
オーコナーが嘗つて小男に逢つた處へ来ると、その男が目の前に居た。
「私の金を持つて來たのか?」その男が聞く。
「さうぢやありません。」 オーコナーは答へた。
「そんなら、お前の身體の肉を切り取つて、支拂つて貰ひたい」と云ふ。
皆んな家の中にはひると、ナイフが出され、白い綺麗な布がテーブルに敷かれ、オーコナーはその布の上に寢かされた。
そこで小男が小槍で將に突き刺さうとした時、オーコナ一夫人は云つた。
「肉を五ポンド取ると、あなたは約束したのですか?」
「その通りだ。」
「血の
「いや、血は。」と男は云つた。
「肉は切り取つてもよござんす。」オーコナー夫人は云つた。
「併し、一滴たりとも血を流したら、私はあなたをこれで撃ち殺します。」 さういつて夫人はピストルを男の顏へつきつけた。
小男は逃げて行き、それきり行方がわからなかつた。
二人は屋敷へ歸ると、大宴會を開き、船長や婆や、オーコナー夫人を海から引き上げた婆さんを招待した。
皆んな充分食べてしまふと、先づオーコナー夫人は銘銘の物語をしてくれと云つた。さうして彼女は海から救はれた事、夫を見付けた事を語つた。
するとお婆さんは、濡れて狂人のやうになつてゐるオーコナー夫人を見付けて家に連れ歸り、自分の襤褸を着せた話をした。
夫人は船長に話をしてくれと願つたが、彼はどうしても話したくないと云つた。すると彼女はポケットからピストルを出してテーブルの端に置き、自分の話をしない者は撃つぞと云つた。
そこで船長は、箱の中にはひり、彼女には少しも手を觸れずに寢臺の所まで行つて、指環を盗んだ次第を物語つた。
すると婦人はピストルを取つて婆を撃ち貫き、崖の上から海の中へ抛り込んだ。
それでおしまひ。
此の大西洋の濕つた岩に住んでゐる文盲の人の口から歐洲的な聯想の豐かな物語を聞くのは、不思議な感じを私に起させた。
此の貞淑な妻の話は、我我をシムベリン〔沙翁の劇の名〕を通り越して、アルノ河の陽光のほとりに誘ひ、フロレンスから愛の物語をしに出かける陽氣な人達の處へつれて行く。また我我をマイン河畔ブュールツブルヒの低い葡萄棚へつれて行く。其處は中世に、「ルブレヒト・フォン・ヴュールツブルヒ作の二人の商人と貞淑な妻」といふ同じやうな物語が語られた處である。
今一つの肉五ポンドに関する部分はペルシアとエヂプトから「ジュスタ・ロマノルム」の物語やフロレンスの公證人なるセル・ヂォヴァンニの「小説ペコローネ」へかけて今でも廣く流布されてゐる。
此の二つの話の現在一つに合體した物は既にゲール族の中にある。またキャンベルの「西部ハイランドの民間説話」の中にも稍々それに似た話がある。
*
There were two farmers in County Clare. One had a son, and the other, a fine rich man, had a daughter.
The young man was wishing to marry the girl, and his father told him to try and get her if he thought well, though a power of gold would be wanting to get the like of her.
'I will try,' said the young man.
He put all his gold into a bag. Then he went over to the other farm, and threw in the gold in front of him.
'Is that all gold?' said the father of the girl.
'All gold,' said O'Conor (the young man's name was O'Conor).
'It will not weigh down my daughter,' said the father.
'We'll see that,' said O'Conor.
Then they put them in the scales, the daughter in one side and the gold in the other. The girl went down against the ground, so O'Conor took his bag and went out on the road.
As he was going along he came to where there was a little man, and he standing with his back against the wall.
'Where are you going with the bag?' said the little man. 'Going home,' said O'Conor.
"Is it gold you might be wanting?' said the man. 'It is, surely,' said O'Conor.
'I'll give you what you are wanting,' said the man, 'and we can bargain in this way--you'll pay me back in a year the gold I give you, or you'll pay me with five pounds cut off your own flesh.'
That bargain was made between them. The man gave a bag of gold to O'Conor, and he went back with it, and was married to the young woman.
They were rich people, and he built her a grand castle on the cliffs of Clare, with a window that looked out straight over the wild ocean.
One day when he went up with his wife to look out over the wild ocean, he saw a ship coming in on the rocks, and no sails on her at all. She was wrecked on the rocks, and it was tea that was in her, and fine silk.
O'Conor and his wife went down to look at the wreck, and when the lady O'Conor saw the silk she said she wished a dress of it.
They got the silk from the sailors, and when the Captain came up to get the money for it, O'Conor asked him to come again and take his dinner with them. They had a grand dinner, and they drank after it, and the Captain was tipsy. While they were still drinking, a letter came to O'Conor, and it was in the letter that a friend of his was dead, and that he would have to go away on a long journey. As he was getting ready the Captain came to him.
'Are you fond of your wife?' said the Captain.
'I am fond of her,' said O'Conor.
'Will you make me a bet of twenty guineas no man comes near her while you'll be away on the journey?' said the Captain.
'I will bet it,' said O'Conor; and he went away.
There was an old hag who sold small things on the road near the castle, and the lady O'Conor allowed her to sleep up in her room in a big box. The Captain went down on the road to the old hag.
'For how much will you let me sleep one night in your box?' said the Captain.
'For no money at all would I do such a thing,' said the hag.
'For ten guineas?' said the Captain.
'Not for ten guineas,' said the hag.
'For twelve guineas?' said the Captain.
'Not for twelve guineas,' said the hag.
'For fifteen guineas?' said the Captain.
'For fifteen I will do it,' said the hag.
Then she took him up and hid him in the box. When night came the lady O'Conor walked up into her room, and the Captain watched her through a hole that was in the box. He saw her take off her two rings and put them on a kind of a board that was over her head like a chimney-piece, and take off her clothes, except her shift, and go up into her bed.
As soon as she was asleep the Captain came out of his box, and he had some means of making a light, for he lit the candle. He went over to the bed where she was sleeping without disturbing her at all, or doing any bad thing, and he took the two rings off the board, and blew out the light, and went down again into the box.
He paused for a moment, and a deep sigh of relief rose from the men and women who had crowded in while the story was going on, till the kitchen was filled with people.
As the Captain was coming out of his box the girls, who had appeared to know no English, stopped their spinning and held their breath with expectation.
The old man went on--
When O'Conor came back the Captain met him, and told him that he had been a night in his wife's room, and gave him the two rings. O'Conor gave him the twenty guineas of the bet. Then he went up into the castle, and he took his wife up to look out of the window over the wild ocean. While she was looking he pushed her from behind, and she fell down over the cliff into the sea.
An old woman was on the shore, and she saw her falling. She went down then to the surf and pulled her out all wet and in great disorder, and she took the wet clothes off her, and put on some old rags belonging to herself.
When O'Conor had pushed his wife from the window he went away into the land.
After a while the lady O'Conor went out searching for him, and when she had gone here and there a long time in the country, she heard that he was reaping in a field with sixty men.
She came to the field and she wanted to go in, but the gate-man would not open the gate for her. Then the owner came by, and she told him her story. He brought her in, and her husband was there, reaping, but he never gave any sign of knowing her. She showed him to the owner, and he made the man come out and go with his wife.
Then the lady O'Conor took him out on the road where there were horses, and they rode away.
When they came to the place where O'Conor had met the little man, he was there on the road before them.
'Have you my gold on you?' said the man.
'I have not,' said O'Conor.
'Then you'll pay me the flesh off your body,' said the man. They went into a house, and a knife was brought, and a clean white cloth was put on the table, and O'Conor was put upon the cloth.
Then the little man was going to strike the lancet into him, when says lady O'Conor--
'Have you bargained for five pounds of flesh?'
'For five pounds of flesh,' said the man.
'Have you bargained for any drop of his blood?' said lady O'Conor.
'For no blood,' said the man.
'Cut out the flesh,' said lady O'Conor, 'but if you spill one drop of his blood I'll put that through you.' And she put a pistol to his head.
The little man went away and they saw no more of him.
When they got home to their castle they made a great supper, and they invited the Captain and the old hag, and the old woman that had pulled the lady O'Conor out of the sea.
After they had eaten well the lady O'Conor began, and she said they would all tell their stories. Then she told how she had been saved from the sea, and how she had found her husband.
Then the old woman told her story; the way she had found the lady O'Conor wet, and in great disorder, and had brought her in and put on her some old rags of her own.
The lady O'Conor asked the Captain for his story; but he said they would get no story from him. Then she took her pistol out of her pocket, and she put it on the edge of the table, and she said that any one that would not tell his story would get a bullet into him.
Then the Captain told the way he had got into the box, and come over to her bed without touching her at all, and had taken away the rings.
Then the lady O'Conor took the pistol and shot the hag through the body, and they threw her over the cliff into the sea.
That is my story.
It gave me a strange feeling of wonder to hear this illiterate native of a wet rock in the Atlantic telling a story that is so full of European associations.
The incident of the faithful wife takes us beyond Cymbeline to the sunshine on the Arno, and the gay company who went out from Florence to tell narratives of love. It takes us again to the low vineyards of Wurzburg on the Main, where the same tale was told in the middle ages, of the 'Two Merchants and the Faithful Wife of Ruprecht von Wurzburg.'
The other portion, dealing with the pound of flesh, has a still wider distribution, reaching from Persia and Egypt to the Gesta Rornanorum, and the Pecorone of Ser Giovanni, a Florentine notary.
The present union of the two tales has already been found among the Gaels, and there is a somewhat similar version in Campbell's Popular Tales of the Western Highlands.
[やぶちゃん注:「クレア郡」“County Clare”。アイルランドのクレア州。アラン諸島を望むゴールウェイ湾南の本土、マンスター地方の州名。
「オーコナーの夫人は彼女を自分の部屋に上らせ、大きな箱の中で寢ることを許した。」原文は“and the lady O'Conor allowed her to sleep up in her room in a big box.”であるが、気になるのは、この訳ではこの夫が長の留守をすることとなった時点で「許した」と読めてしまうことである。しかし、これは、そうした雑貨商を営む身寄りのない老婆を可哀相に思って、以前からオーコナー夫人は、夜は彼女の部屋の大きな櫃を寝床にすることを許していた、という風に読まないとおかしいように思われる。栩木伸明氏訳「アラン島」でもそのように訳されてある。
「爐棚のやうになつた板の上」原文は“on a kind of a board that was over her head like a chimney-piece”。“chimney-piece”は“mantelpiece”マントルピース、暖炉のことだから、如何にも迂遠な表現である。これは実際にはマントルピースではなく、それに似たような形状の当時の特殊な部屋装飾であることをパット爺さんは暗に言わんとしているように思われる。
「船長が箱から出て來るあたりから、英語を知らないらしい女たちも、糸を紡ぐ手を止めて、その先を聞かうと息を凝らしてゐた。」は“As the Captain was coming out of his box the girls, who had appeared to know no English, stopped their spinning and held their breath with expectation.”であるが、「英語を知らないらしい女たち」が「ほつとし」「息を凝らして」「その先を聞かうと」していたというのは訳としては不自然である。“had appeared to know no English”は、そのちょっと前にシングが話しかけても、『英語はまるで分からないかのような素振りを見せていた女たちも』、の意であろう。突然やって来た若き異邦人シングへの、素朴なアランの女たちの、そのはにかみが伝わってくるシーンだ。
「陸の方へ逃げた。」原文の“he went away into the land.”を逐語的に訳してはいるが、如何か? 妻に裏切られたと思った失意と絶望によって自暴自棄となったオーコナーは、衝動的に『内陸の奥の方へと、彷徨い出でて、城を去ってしまった。』と訳したいところである。
「彼女を知らないのか、目もくれない。」原文“but he never gave any sign of knowing her.”。「彼女を知らないのか」では、日本語としては、単純な仮定疑問文として、本当に彼女のことをもう忘れてしまっているのか、という意味にも(寧ろ積極的にそのように)とれてしまう。そうではあるまい。ここは寧ろ、彼女が裏切ったと信じ込んで絶望し、やけのやんぱちで一介の雇われの農奴に身をやつしてしまっているから、『しかし彼は、彼女のことを知っているというこれっぽちの素振りをもいっかな見せずにいる』という意味であろう。
「シムベリン」“Cymbeline”は古ケルト時代のブリテン王シンベリンの娘イモージェン“Imogen”と愛人ポステュマス“Posthumus”に纏わるシェイクスピアの戯曲。1611年頃には上演されたと推測されている。作中、シンベリンによってイモージェンと引き裂かれて追放されたポステュマスはイタリアに行き(本文の「アルノ河」や「フロレンス」(=フィレンツェ)というイタリア風の陽気な喜劇コンセプトへのシングの連想展開は、このシーンに引っ掛けてあるものと思われる)、そこで知り逢ったヤーキモーなる人物とイモージェンの貞節について賭けをする。ヤーキモーはブリテンに向かうと大きな鞄の中に潜んでイモージェンの部屋に侵入、秘かにイモージェンの胸の痣と部屋の造作とを偸み見てイタリアに帰還すると、ポステュマスにイモージェンを美事に落としたと嘘をつく。絶望したポステュマスはブリテンに残してきた下男にイモージェン殺害を命ずるという、本話前半部と極めて類似したシーンがある(本注はウィキの「シンベリン」を参考にした)。
「マイン河畔ブュールツブルヒ」“Wurzburg on the Main”後の中世伝承譚の方は「ルブレヒト・フォン・ヴュールツブルヒ作の二人の商人と貞淑な妻」“'Two Merchants and the Faithful Wife of Ruprecht von Wurzburg.'”と訳されているから「ブュールツブルヒ」は「ヴュールツブルヒ」の誤植であろう。現在はヴュルツブルクと表記される。
「ジュスタ・ロマノルム」“Gesta Rornanorum”は13世紀から14世紀にかけて編纂されたラテン語民話集。Charles Swan
英訳本(安川晃他編注)「ゲスタ・ロマノールム Gesta Romanorum ローマ人達の行状記」が1992年に弓プレスから出版されている。
『フロレンスの公證人なるセル・ヂォヴァンニの「小説ペコローネ」』原文“the Pecorone of Ser Giovanni, a Florentine notary.”。中世イタリアのジョヴァンニ・フィオレンティーノ“Giovanni Fiorentino”(“ser”が頭につくが“Fiorentino”自体が「フィレンツェの」の意であり、何らかの冠称のようである)が書いた「デカメロン」風の物語集“Il Pecorone”「イル・ペコローネ」(「愚か者」の意)。前の「ゲスタ・ロマノールム」とともに、シェイクスピアの「ヴェニスの商人」の種本とされており、その四日目第一話に本話と共通した例の人肉の裁きの話が載る。
『キャンベルの「西部ハイランドの民間説話」』ケルト民俗学の権威であったJohn Francis Campbell(1821年~1885年)が1860年から1862年にかけて刊行した民間説話集。ゲール語からの翻訳採録。]
マイケルと外出すると、後からついて行けないほど足が早いので、石灰岩に多くある端の尖つた風化石で靴をズタズタにしてしまふ。
宿の人たちは昨夜それに就いて相談して、結局一足の革草鞋を私に作つてくれる事になつた。それを今日は岩の中で履いてゐる。
それは生の牛の革から出來ただけの物で、外側に毛があり、釣糸の両端を以つて爪先の上と踵の周りとで編み合はされ、糸はぐるつと廻つて足の甲の上で結ばれてある。
夜脱いだ時は、それを水桶の中に入れておく。革を硬いままにしておくと足や靴下を切るからである。同じ理由で、足を常に
初め私は、長靴を履く時に自然にするやうに、踵に身體の重みをかけて、かなり傷をした。併し、数時間後には普通の歩き方を覺えて、島の何處へでも案内人について行けるやうになつた。
北の方の、崖下の或る處では、殆んど一哩近くも普通の歩き方では一歩も歩けず、岩から岩へ飛び歩くのである。此處でも私は爪先を自然に使ふのがわかつた。と云ふのは、行手のどんな小さな穴へでも、一生懸命に足先でしがみついて跳ぶことがわかつたからである。そして餘り緊張した爲に足の筋肉全體が痛んだ。
歐洲にある重い長靴の無い事が此島の人たちに野獸のやうな素早い歩き方を保存させ、また一方に於て、彼等の一般的に簡素な生活は肉體上の他のいろいろな點に於いて完成を與へた。彼等の生活の樣式は、その四圍に住んでゐる動物の巣や穴より以上に手の込んだ物に從つて営まれてゐるのでなく、或る意味に於いて、彼等は、野生の馬が駄馬や馬車馬よりは寧ろ完全に育てられた馬に似てゐると同じやうに、勞働者や職人よりは――我我の上流の比較的立派な型に――自然の理想に適ふまでに手をかけて育てられた人人に近いやうに見えるる、これと同じやうな自然發達の種族は、恐らく半ば文化の開けた國に珍らしくないのである。併し此處では、野生的動物の性質の中に際立つて、古代社會の純良な物の片影が交つてゐる。
私がマイケルと散歩してゐる間に、屢々時間を聞きに來る者がある。しかし、さういつた人達は時刻といふ物の約束をぼんやりと理解する以上に充分近代的の時間といふものに慣れてゐない。
私の時計では何時と云つても承知せず、日暮れまでどの位あるかと聞く。
此の島で甚だ妙な事は、一般に時間は風の方向と関係してゐると思つてゐる。殆んどどの家もそんな風に建てられ、向き合つて二つの戸があり、風の當らない方の戸は、家の中に明りを採る爲に一日中開いたままになつてゐる。風が北から吹けば南の戸が開いて居り、茶の間の床の上を戸柱の蔭が横に動いて行くので、時間がわかる。ところが、風が南に變ると、直ぐに北の方の戸があいて、簡單な日時計を作る事さへ知らない人たちは困惑する。
此の戸口の仕組はまた今一つの面白い結果を生ずる。村の往來の片側は、どこの戸口も開いたままになつて、女たちが敷居の上に腰かけたりしてゐるのに、他の方の側の戸口は皆しまつて、人の住んでゐる気配も見えない事がよくある。風が變ると、その瞬間に凡ての物が反對になつてしまふ。一時間の散歩の後歸つてみると、何もかも道の片側から他の側へ移り變つてゐるやうな事が屢々ある。
此の家では戸口が變ると茶の間の樣子ががらつと變つて、庭や小路の眺められる輝かしいまで明るい茶の間は、雄大な海を見わたす薄暗い穴倉のやうになる。
北風の吹く日には、お婆さんはどうにか時間通りに私の食事を作るが、さうでない日には六時のお茶を三時に作る事がある。それを斷はると、三時間も炭火にとろとろ煮て、また六時になつて、充分温かいかどうかを非常に心配しながら持つて來る。
爺さんは、私が去る時には時計を送つてもらひたいと云ふ。私の贈つた物が何か家の中にあると、私のことを忘れないだらうし、時計は他の物のやうに重寶ではなくとも、それを見ればいつでも私を想ひ出すだらう、と彼は云ふ。
一般に正確な時刻を知らない爲に、人人は規則正しい食事をする事が出來ない。
家の人は晩は一緒に食事をするらしい。また時には朝も、夜明け少し後、皆が仕事に思ひ思ひに出かける前に一緒に食事をする事がある。併し晝間は、腹がすけばいつでも、ただ茶を一杯飲んだり、パンを一片食つたり、或ひは芋を食べたりするだけである。
外で働いてゐる者は不思議にあまり食べない。マイケルは時時何も食べないで八九時間も芋畑の草取りをして、外にゐる事がある。歸つて來て手製のパンの幾片かを食べるが、それでいつ誘つても私と一緒に出かけて、島を何時間でも歩き廻るやうに用意が出來てゐる。
彼等は鹽豚・鹽肴のほかには動物質の食物は取らない。お婆さんは生の肉を食べると、大病になると云ふ。
茶や砂糖や小麥が一般に用ひられるやうになつたのは數年前からの事で、その前は鹽肴が今日より以上に食事の重要品であつた。それで皮膚病が、今は此の島にも少くなつたが、以前には隨分多かつたさうである。
*
Michael walks so fast when I am out with him that I cannot pick my steps, and the sharp-edged fossils which abound in the limestone have cut my shoes to pieces.
The family held a consultation on them last night, and in the end it was decided to make me a pair of pampooties, which I have been wearing to-day among the rocks.
They consist simply of a piece of raw cowskin, with the hair outside, laced over the toe and round the heel with two ends of fishing-line that work round and are tied above the instep.
In the evening, when they are taken off, they are placed in a basin of water, as the rough hide cuts the foot and stocking if it is allowed to harden. For the same reason the people often step into the surf during the day, so that their feet are continually moist.
At first I threw my weight upon my heels, as one does naturally in a boot, and was a good deal bruised, but after a few hours I learned the natural walk of man, and could follow my guide in any portion of the island.
In one district below the cliffs, towards the north, one goes for nearly a mile jumping from one rock to another without a single ordinary step; and here I realized that toes have a natural use, for I found myself jumping towards any tiny crevice in the rock before me, and clinging with an eager grip in which all the muscles of my feet ached from their exertion.
The absence of the heavy boot of Europe has preserved to these people the agile walk of the wild animal, while the general simplicity of their lives has given them many other points of physical perfection. Their way of life has never been acted on by anything much more artificial than the nests and burrows of the creatures that live round them, and they seem, in a certain sense, to approach more nearly to the finer types of our aristocracies--who are bred artificially to a natural ideal--than to the labourer or citizen, as the wild horse resembles the thoroughbred rather than the hack or cart-horse. Tribes of the same natural development are, perhaps, frequent in half-civilized countries, but here a touch of the refinement of old societies is blended, with singular effect, among the qualities of the wild animal.
While I am walking with Michael some one often comes to me to ask the time of day. Few of the people, however, are sufficiently used to modern time to understand in more than a vague way the convention of the hours, and when I tell them what o'clock it is by my watch they are not satisfied, and ask how long is left them before the twilight.
The general knowledge of time on the island depends, curiously enough, on the direction of the wind. Nearly all the cottages are built, like this one, with two doors opposite each other, the more sheltered of which lies open all day to give light to the interior. If the wind is northerly the south door is opened, and the shadow of the door-post moving across the kitchen floor indicates the hour; as soon, however, as the wind changes to the south the other door is opened, and the people, who never think of putting up a primitive dial, are at a loss.
This system of doorways has another curious result. It usually happens that all the doors on one side of the village pathway are lying open with women sitting about on the thresholds, while on the other side the doors are shut and there is no sign of life. The moment the wind changes everything is reversed, and sometimes when I come back to the village after an hour's walk there seems to have been a general flight from one side of the way to the other.
In my own cottage the change of the doors alters the whole tone of the kitchen, turning it from a brilliantly-lighted room looking out on a yard and laneway to a sombre cell with a superb view of the sea.
When the wind is from the north the old woman manages my meals with fair regularity; but on the other days she often makes my tea at three o'clock instead of six. If I refuse it she puts it down to simmer for three hours in the turf, and then brings it in at six o'clock full of anxiety to know if it is warm enough.
The old man is suggesting that I should send him a clock when I go away. He'd like to have something from me in the house, he says, the way they wouldn't forget me, and wouldn't a clock be as handy as another thing, and they'd be thinking of me whenever they'd look on its face.
The general ignorance of any precise hours in the day makes it impossible for the people to have regular meals.
They seem to eat together in the evening, and sometimes in the morning, a little after dawn, before they scatter for their work, but during the day they simply drink a cup of tea and eat a piece of bread, or some potatoes, whenever they are hungry.
For men who live in the open air they eat strangely little. Often when Michael has been out weeding potatoes for eight or nine hours without food, he comes in and eats a few slices of home-made bread, and then he is ready to go out with me and wander for hours about the island.
They use no animal food except a little bacon and salt fish. The old woman says she would be very ill if she ate fresh meat.
Some years ago, before tea, sugar, and flour had come into general use, salt fish was much more the staple article of diet than at present, and, I am told, skin diseases were very common, though they are now rare on the islands.
[やぶちゃん注:「完全に育てられた馬」原文“thoroughbred”。言うまでもなく、英国原産種にアラビア馬その他を交配して改良・育成した競走馬のことで、現代ではそのまま「サラブレッド」と訳した方がすんなり意味が落ちる。
「彼等の生活の樣式は、その四圍に住んでゐる動物の巣や穴より以上に手の込んだ物に從つて営まれてゐるのでなく」及び「しかし、さういつた人達は時刻といふ物の約束をぼんやりと理解する以上に充分近代的の時間といふものに慣れてゐない。」の訳語は「以上に」の部分を「以上には」とした方が今の日本語としては分かりよい。則ち、『彼らの生活の様式は自然界の動物の本能的な営巣に従っており、それ以上の、我々が言うところの「近代的な知性」によって営まれた「文明的生活」とは無縁で』、『彼らの時間概念は一日の大まかな自然現象としての変化をぼんやりと理解する程度のものであって、それ以上の、我々が言うところの「近代的な概念」によって縛られた「絶対的時間」には慣れていない』のである、と言っているのである。
「さうでない日には六時のお茶を三時に作る事がある。」原文は“she often makes my tea at three o'clock instead of six.”で確かに“tea”であるが、これは前文で“my meals”を「食事」と訳しており、それを受けての文であるから、これはお婆さんの作る(失礼ながら)大したことのない粗末な「夕食」が、所謂、イングランドの習慣である午後五時頃に紅茶とともに摂る、ディナーを事前に補うところの軽食“afternoon[five-o'clock]tea”(夕食が軽い場合には肉料理附きで“high[meat]tea”と言う)のように感ぜられたことからの“tea”なのではなかろうか。訳としては夕餉をでいいのではないか? 但し、もしかすると実際にこのお婆さんは“afternoon tea”の後、ちゃんとディナーかサパーを出していたのかも知れない。お婆さんの名誉のために附言しておく。
「爺さん」ここまで登場していなかったが、これはどうもシングが泊まっているこの屋の主、「お婆さん」の夫と思われる。]
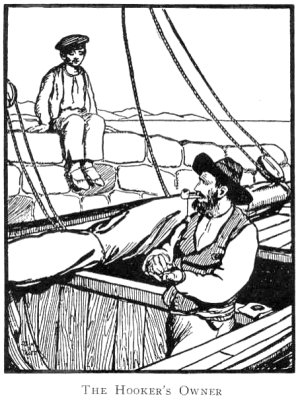
[フッカーの船主]
此の灰色の雲と海の間で幾週間か暮した事のない者には、女の赤い着物が、殊に今朝のやうにたくさん群がつてゐるのを目に止める樂しさはわからないであらう。
若い牛が、近日中に開かれる本土の市場へ船積される筈だと聞いた。それで夜明け少し前、私はそれを見ようと波止揚へ下りて行つた。
灣は催してゐる雨氣に灰色に蔽はれてゐたが、雲の、うすさに海の上には銀のやうな明るさがあり、コニマラの山山には常ならぬ靑さが濃かつた。
私が砂山を越えて行くと、灰色の帆をかけた漁船が滑るやうに靜かに漕ぎ出して行つたり、また波止場へ向つて進んで來たりしてゐた。赤毛の牛の群が、岩と海の境目にある緣の長い草の道でもつて目新しい色の調和を作りながら、大概は女に追はれて方方から集まつて來つつあつた。
波止場その物も牡牛と大勢の人で混み合つてゐた。群集の中にあたりの者たちに威張つてゐるらしい普通の人とは違つた一人の娘が居た。彼女の妙な恰好をした鼻柱や狭い頰は妖精のやうな顏を思はせたが、髮の毛と皮膚の美しさは獨特の魅力であつた。
屋根のない船艙に若い牛を立たせ得るだけぎつしり詰めると、持主は女房や姉妹たちと甲板に飛び下りて出發し初めた。此の女房や姉妹たちは、ゴルウェーで男達の濫費を防ぐ爲に附いて行くのである。直ぐその後で、老いぼれてヨロヨロした一般の漁船がコニマラから泥炭を積んで波止場の方へやつて來た。荷卸をやつてゐる間に、男達がすつかり波止場の緣に腰かけて、持主が怒つて氣が荒くなるまでに木材の腐つてゐる事をとやかく云つた。
さてボートが波止場に來られなくなつた程汐が退いたので、場所を東南の細長い砂地に移し、其處で殘りの牛は寄波の中を船へ積み込まれた。漁船は岸から八十ヤードぐらゐの所に碇泊し、カラハが牛を引張つて漕ぎ去り漕ぎ戻つた。各々の牡牛は順順に捕へられ、革の吊帶を體に廻はされた。その吊帶で牛は船の上に引き揚げられるのである。今一つの綱が角に結ばれて、カラハの艫にゐる人に渡される。それから年は寄波の中へ無理に下ろされ、餘り長く苦しませないやうにして波の深みから出された。少し泳ぐやうになると、漁船の方へ牽いて行き、半ば溺れた狀態で船の中へ引き揚げられた。
砂地では自由がきくので、激しい反抗心を起すらしく、中には危險な取組を冒してやつと捕へられる牛もあつた。最初の一遍で成功するとは限らず、私は三歳の牛が角で二人の男をつり上げ、もう一人を角で五十ヤードも砂地を引きずつて、やつと鎭められたのを見た。
こんな仕事のなされてゐる間中、お内儀さんたちや子供たちの群は岸の緣に集まつて、ひやかしとも賞讃ともつかない事を叫び續ける。
家に歸つてみると、此處のお婆さんの娘も本土へ行つた女の一人で、その九ケ月位の赤ん坊はお婆さんに預けられてあつた。
はひつて行くと、お婆さんは晩飯の用意に忙しく、此の時間にいつもやつて來るパット・ディレイン爺さんが搖加藍を搖つてゐた。その搖藍はみすぼらしい柳細工で、下に
此の家にゐるもう一人の娘もまた市に行つたので、お婆さんが私と赤ん坊の兩人、おまけに爐邊の穴にゐる一群のひよこまでも世話をしなければならなくなつた。茶を賴んだ時や、お婆さんが水汲みに行つた時は、私が搖藍をゆすぶる番になつた。
*
No one who has not lived for weeks among these grey clouds and seas can realise the joy with which the eye rests on the red dresses of the women, especially when a number of them are to be found together, as happened early this morning.
I heard that the young cattle were to be shipped for a fair on the mainland, which is to take place in a few days, and I went down on the pier, a little after dawn, to watch them.
The bay was shrouded in the greys of coming rain, yet the thinness of the cloud threw a silvery light on the sea, and an unusual depth of blue to the mountains of Connemara.
As I was going across the sandhills one dun-sailed hooker glided slowly out to begin her voyage, and another beat up to the pier. Troops of red cattle, driven mostly by the women, were coming up from several directions, forming, with the green of the long tract of grass that separates the sea from the rocks, a new unity of colour.
The pier itself was crowded with bullocks and a great number of the people. I noticed one extraordinary girl in the throng who seemed to exert an authority on all who came near her. Her curiously-formed nostrils and narrow chin gave her a witch-like expression, yet the beauty of her hair and skin made her singularly attractive.
When the empty hooker was made fast its deck was still many feet below the level of the pier, so the animals were slung down by a rope from the mast-head, with much struggling and confusion. Some of them made wild efforts to escape, nearly carrying their owners with them into the sea, but they were handled with wonderful dexterity, and there was no mishap.
When the open hold was filled with young cattle, packed as tightly as they could stand, the owners with their wives or sisters, who go with them to prevent extravagance in Galway, jumped down on the deck, and the voyage was begun. Immediately afterwards a rickety old hooker beat up with turf from Connemara, and while she was unlading all the men sat along the edge of the pier and made remarks upon the rottenness of her timber till the owners grew wild with rage.
The tide was now too low for more boats to come to the pier, so a move was made to a strip of sand towards the south-east, where the rest of the cattle were shipped through the surf. Here the hooker was anchored about eighty yards from the shore, and a curagh was rowed round to tow out the animals. Each bullock was caught in its turn and girded with a sling of rope by which it could be hoisted on board. Another rope was fastened to the horns and passed out to a man in the stem of the curagh. Then the animal was forced down through the surf and out of its depth before it had much time to struggle. Once fairly swimming, it was towed out to the hooker and dragged on board in a half-drowned condition.
The freedom of the sand seemed to give a stronger spirit of revolt, and some of the animals were only caught after a dangerous struggle. The first attempt was not always successful, and I saw one three-year-old lift two men with his horns, and drag another fifty yards along the sand by his tail before he was subdued.
While this work was going on a crowd of girls and women collected on the edge of the cliff and kept shouting down a confused babble of satire and praise.
When I came back to the cottage I found that among the women who had gone to the mainland was a daughter of the old woman's, and that her baby of about nine months had been left in the care of its grandmother.
As I came in she was busy getting ready my dinner, and old Pat Dirane, who usually comes at this hour, was rocking the cradle. It is made of clumsy wicker-work, with two pieces of rough wood fastened underneath to serve as rockers, and all the time I am in my room I can hear it bumping on the floor with extraordinary violence. When the baby is awake it sprawls on the floor, and the old woman sings it a variety of inarticulate lullabies that have much musical charm.
Another daughter, who lives at home, has gone to the fair also, so the old woman has both the baby and myself to take care of as well as a crowd of chickens that live in a hole beside the fire, Often when I want tea, or when the old woman goes for water, I have to take my own turn at rocking the cradle.
此の島の
幸ひなことには天氣がよいので、日向で日を暮す事が出來る。此の石垣の頂から見渡すと、殆んど四方の海が見え、北と南の方は遙かに延びて遠い山脈へ續く。私の足下、東の方には島の人家のある一つの區域が見え、其處には赤い色の人影が小屋の邊をうろついてゐて、時時、きれぎれに話聲や古い島の歌が聞こえて來る。
*
One of the largest Duns, or pagan forts, on the islands, is within a stone's throw of my cottage, and I often stroll up there after a dinner of eggs or salt pork, to smoke drowsily on the stones. The neighbours know my habit, and not infrequently some one wanders up to ask what news there is in the last paper I have received, or to make inquiries about the American war. If no one comes I prop my book open with stones touched by the Fir-bolgs, and sleep for hours in the delicious warmth of the sun. The last few days I have almost lived on the round walls, for, by some miscalculation, our turf has come to an end, and the fires are kept up with dried cow-dung--a common fuel on the island--the smoke from which filters through into my room and lies in blue layers above my table and bed.
Fortunately the weather is fine, and I can spend my days in the sunshine. When I look round from the top of these walls I can see the sea on nearly every side, stretching away to distant ranges of mountains on the north and south. Underneath me to the east there is the one inhabited district of the island, where I can see red figures moving about the cottages, sending up an occasional fragment of conversation or of old island melodies.
[やぶちゃん注:「
赤ん坊は齒が生えつつあるので、此の數日間、泣いてゐる。母が市に行つたので牛乳で養はれ、時時それが酸つぱかつたり、餘計に飲まされたりするらしい。
併し今朝は大へん機嫌が惡かつたので、家の人たちは村に乳母を探しにやり、間もなく東の方へ少し行つた處に住んでゐる若い女が來て、赤ん坊に天然の食物をまたやるやうになつた。
それから數時間たつて、私はパット爺さんと話さうと思つて茶の間にはひつて行くと、また違つた女が同じやうな親切な役を務めてゐたが、今度は妙にむづかしい顏をした女であつた。
パット爺さんは一人の不貞な妻の話をした。それはこれから述べるが、その後でその女と道德上の口論を初めた。話を聞きにやつて來た若者たちはそれを面白がつて聞いてゐたが、生憎ゲール語で早口に言はれたので、私にはその要點の大略さへつかめなかつた。
此の老人はいつも妙に滅入つた口調で自分の病氣の事や自分で近づきつつあるものと感じてゐる死の事などを語るが、北の島のムールティーン爺さんを思ひ出すやうな諧謔を時時弄する。今日、怪奇な二錢人形がお婆さんのゐる近くの床に落ちてゐた。それを爺さんは拾ひ上げ、お婆さんの顏と見較べるやうに眺めた。それからそれをさし上げて、「お内儀さん、こんなものを持ち出したのはお前さんかね?」と云つた。
これからが彼の物語である。――
*
The baby is teething, and has been crying for several days. Since his mother went to the fair they have been feeding him with cow's milk, often slightly sour, and giving him, I think, more than he requires.
This morning, however, he seemed so unwell they sent out to look for a foster-mother in the village, and before long a young woman, who lives a little way to the east, came in and restored him to his natural food.
A few hours later, when I came into the kitchen to talk to old Pat, another woman performed the same kindly office, this time a person with a curiously whimsical expression.
Pat told me a story of an unfaithful wife, which I will give further down, and then broke into a moral dispute with the visitor, which caused immense delight to some young men who had come down to listen to the story. Unfortunately it was carried on so rapidly in Gaelic that I lost most of the points.
This old man talks usually in a mournful tone about his ill-health, and his death, which he feels to be approaching, yet he has occasional touches of humor that remind me of old Mourteen on the north island. To-day a grotesque twopenny doll was lying on the floor near the old woman. He picked it up and examined it as if comparing it with her. Then he held it up: 'Is it you is after bringing that thing into the world,' he said, 'woman of the house?'
Here is the story:--
[やぶちゃん注:「今度は妙にむづかしい顏をした女であつた」原文は“this time a person with a curiously whimsical expression.”。“whimsical”というのは「気まぐれな。むら気のある。酔狂な」が原義で、そこから「変な。妙な。滑稽な。」の意を派生する。この後の不貞な女の話とそこからパット爺さんとこの女が道徳的な議論を展開することを考えると、この女性の印象が「気難しい」感じの顔で、「頑なで保守的な」女性であったとは、私には思われない。寧ろ、普通の若い母親の印象とは違った「気まぐれでむらっ気のある」、「一種独特な雰囲気を持った」顔つきの女であったのではなかったか? 次の話で不貞な女とされる色気のあるタイプに寧ろ属する女性であったからこそ、議論になったとするべきであろう。栩木氏はこの部分を『この女がへんに色っぽい表情をしているのが目についた』と訳されており、私にはこちらの方が如何にも腑に落ちたのであるが、如何?
「怪奇な二錢人形」原文は“grotesque twopenny doll”であるが、後で「お内儀さん、こんなものを持ち出したのはお前さんかね?」という台詞があるからといって、何か意味ありげな宗教的な依代なわけでは毛頭あるまい。赤ん坊のために買ったものであるが、表情や造作が、奇妙で笑いをさそうような、いい加減にデフォルメされたように見える、如何にもな安物の人形であることを言うのであろう。すると、後の「お内儀さん、こんなものを持ち出したのはお前さんかね?」という台詞も、違ったニュアンスで読める。原文は“'Is it you is after bringing that thing into the world,' he said, 'woman of the house?'”である。パット爺さんは「諧謔を時時弄する」のであるから、『「今になって、この世にこんな奴をもたらしちまったのは、あんた」彼は言った、「女将さんかい?」』、即ち、『女将さん、この子は、お前さんが産んじまった哀れな子かね?』という意味であろう。栩木氏も『おや、奥さん、この子はあんたが産んだ子かいな。』と訳しておられる。]
或る日、私はゴルウェーからダブリンへ歩いてゐた。途中で日が暮れて、まだ町まで十哩もあるので、何處か夜を過す處を探してゐた。するとひどく雨が降り出し、私は歩き疲れたので、道の向う側に屋根のない家らしいものが見えたので、壁が雨除けになるだらうと思つて中にはひつた。
一人の死人がテーブルの上に寢てゐて、蠟燭が
「今晩は、お内儀さん」と私は云ふ。
「今晩は、旅の衆。」と女は云ふ。「雨の中にゐないで、おはひりなさい。」
そこでその女は私を中に入れ、亭主に死なれてお通夜をしてゐるところだと云つた。
「だが、お前さん、喉が乾いてゐるでせう。」彼女は云ふ。「客間にいらつしやい。」
そこで私を客間につれて行き――ちよつと立派な家だつた――そしてコップをソーサーに載せ、甘さうな砂糖とパンを添へて、テーブルの上に出した。
お茶がすんだので、私は、死人のゐる茶の間に戻つて來た。彼女はテーブルから立派な新しいパイプにアルコールを一滴垂らして、私にくれた。
「お前さん、」彼女は云ふ。「この人と二人きりになつたら怖かありませんか?」
「ちつとも怖かありませんよ、お内儀さん。」私は云ふ。「死人は何もしやしません。」
すると彼女は亭主の亡くなつた事を近所の人に知らせに行きたいと云つて、出て行き、外から鍵をかけた。
私は煙草を一服吸つて椅子にもたれ、もう一服テーブルから取つて、――さうさう、今あなたがしてゐるやうに――椅子の
「お前さん、怖がらなくてもいいよ。」その死人が云ふ。「私は決して死んでるのぢやないのだ。此處へ來て助け起してくれ、譯を話して上げるから。」
よしとばかり、私は立つて行き、敷布を取つてやつた。すると彼は綺麗なシャツを着て、立派なフランネルのズボンをはいてゐた。
彼は起き上つて、云ふには――
「私は惡い女房を持つたんでね、お前さん。彼奴の振舞を見とどけてくれようと、死んだ眞似をしてるところだ。」
それから女をやつつける爲の二本の手頃な棒切れを取つて來て、それを両脇において、また死んだやうに長長と横になつた。
半時間もたつと彼の妻は歸つて來たが、若い男が一緒に來た。さうしてその男に茶を出し、疲れてゐるだらうから寢室に行つて寢たらよいと云つた。
若者ははひて行き、女は死人の傍に腰掛て見守つてゐた。少したつと彼女は立ち上つて、云ふには、「お前さん、私はちよつと寢室に行つて
すると死人は起ち上つて二本の棒を押つ取り、今一本を私に渡した。私たちがはひつて行くと、女の頭は男の腕にかかへられて寢てゐるのを見た。
死人は棒切れで男に一撃を喰はした。血は迸つて、廊下まではねた。
それでおしまひ。
*
One day I was travelling on foot from Galway to Dublin, and the darkness came on me and I ten miles from the town I was wanting to pass the night in. Then a hard rain began to fall and I was tired walking, so when I saw a sort of a house with no roof on it up against the road, I got in the way the walls would give me shelter.
As I was looking round I saw a light in some trees two perches off, and thinking any sort of a house would be better than where I was, I got over a wall and went up to the house to look in at the window.
I saw a dead man laid on a table, and candles lighted, and a woman watching him. I was frightened when I saw him, but it was raining hard, and I said to myself, if he was dead he couldn't hurt me. Then I knocked on the door and the woman came and opened it.
'Good evening, ma'am,' says I.
'Good evening kindly, stranger,' says she, 'Come in out of the rain.' Then she took me in and told me her husband was after dying on her, and she was watching him that night.
'But it's thirsty you'll be, stranger,' says she, 'Come into the parlour.' Then she took me into the parlour--and it was a fine clean house--and she put a cup, with a saucer under it, on the table before me with fine sugar and bread.
When I'd had a cup of tea I went back into the kitchen where the dead man was lying, and she gave me a fine new pipe off the table with a drop of spirits.
'Stranger,' says she, 'would you be afeard to be alone with himself?'
'Not a bit in the world, ma'am,' says I; 'he that's dead can do no hurt,' Then she said she wanted to go over and tell the neighbours the way her husband was after dying on her, and she went out and locked the door behind her.
I smoked one pipe, and I leaned out and took another off the table. I was smoking it with my hand on the back of my chair--the way you are yourself this minute, God bless you--and I looking on the dead man, when he opened his eyes as wide as myself and looked at me.
'Don't be afraid, stranger,' said the dead man; 'I'm not dead at all in the world. Come here and help me up and I'll tell you all about it.'
Well, I went up and took the sheet off of him, and I saw that he had a fine clean shirt on his body, and fine flannel drawers.
He sat up then, and says he--
'I've got a bad wife, stranger, and I let on to be dead the way I'd catch her goings on.'
Then he got two fine sticks he had to keep down his wife, and he put them at each side of his body, and he laid himself out again as if he was dead.
In half an hour his wife came back and a young man along with her. Well, she gave him his tea, and she told him he was tired, and he would do right to go and lie down in the bedroom.
The young man went in and the woman sat down to watch by the dead man. A while after she got up and 'Stranger,' says she, 'I'm going in to get the candle out of the room; I'm thinking the young man will be asleep by this time.' She went into the bedroom, but the divil a bit of her came back.
Then the dead man got up, and he took one stick, and he gave the other to myself. We went in and saw them lying together with her head on his arm.
The dead man hit him a blow with the stick so that the blood out of him leapt up and hit the gallery.
That is my story.
[やぶちゃん注:「二パーチ」“perch”はイギリスの距離単位。1パーチは約5.03mであるから凡そ十メートル。
「彼女はテーブルから立派な新しいパイプにアルコールを一滴垂らして、私にくれた。」原文は“and she gave me a fine new pipe off the table with a drop of spirits.”。葉巻にウィスキーを湿らせたり、煙草の葉にスピリッツをまぶして吸うことは、習慣として存在し、私もやったことがある。従って私はこの訳を別段、不思議に思わなかったが、ここを栩木氏はパイプ煙草に加えて、『ウィスキーも一杯くれましてな。』と訳しておられる。確かに、この後、雨に降り込まれて冷えた旅人(パット爺さん)をこのような通夜の場に残して、妻が出かけるということを考えれば、これは一杯の酒の方がしっくりくるとは思う。
「廊下まではねた」原文は“hit the gallery”。これを栩木氏は『ランプの
なお、言わずもがなであるが、このパット爺さんの話は後のシングの初期戯曲“In the Shadow of the Glen”(「谷間の影」1903年)の素材となった。]
かういふ話には、彼はいつも一人稱で話す。描かれる場面の中へ實際、自分が出て來るやうに細かい描寫をしながら。
此の話の初めに、彼はその時、ダブリンへ行く途中で自分のもてた事を長長と語り、市中の目拔の町の金持の人たちに逢ひに行つた話をした。
*
In stories of this kind he always speaks in the first person, with minute details to show that he was actually present at the scenes that are described.
At the beginning of this story he gave me a long account of what had made him be on his way to Dublin on that occasion, and told me about all the rich people he was going to see in the finest streets of the city.
[やぶちゃん注:「彼はその時、ダブリンへ行く途中で自分のもてた事を長長と語り」という訳は如何にもさもありなんと感じさせる面白い訳であるが、原文を見る限り、前文の「細かい描寫」“minute details”を受けており、単に「彼はこの話の際にも、そのさわりの部分で、彼がダブリンへ向かうこととなった理由について長々と話をし」というパット爺さんの退屈な前振りを言っているように思われる。
「市中の目拔の町の金持の人たちに逢ひに行つた話をした」は、「ダブリン市内の目抜き通りで彼が出逢った、あらゆる金持ち連中一人ひとりについて、まことにご丁寧に私に説教したもうた」といった意味であろう。これも同様に聴くシングが幾分、内心閉口したことを皮肉っての表現のように思われる。]
吹きまくる霧の一週間は終つたが、私は妙に流し者の淋しい氣持になつた。殆んど毎日島の中を歩き廻つたが、濕つた岩の群と細長い波と荒れ狂ふ波の騒ぎの外には何も見る事は出來ない。
スレート質の石灰岩はその上に滴る水で黑ずみ、どちらを向いても、狹い間に重り合ひ捲き合いひしてゐる同じやうな暗澹たる心のつきまとひ、石垣の荒い岩目に叫び咽ぶ同じやうな悲しい音ばかりである。
初め、人人は周圍の荒涼たる有樣に對しては氣も留めないでゐるが、數日たつと彼等の聲は茶の間でも滅入ってしまひ、豚や牛のことを果しなく話てゐるのが、化け物屋敷で話してゐる人たちの囁き聲のやうに低くなる。
*
A week of sweeping fogs has passed over and given me a strange sense of exile and desolation. I walk round the island nearly every day, yet I can see nothing anywhere but a mass of wet rock, a strip of surf, and then a tumult of waves.
The slaty limestone has grown black with the water that is dripping on it, and wherever I turn there is the same grey obsession twining and wreathing itself among the narrow fields, and the same wail from the wind that shrieks and whistles in the loose rubble of the walls.
At first the people do not give much attention to the wilderness that is round them, but after a few days their voices sink in the kitchen, and their endless talk of pigs and cattle falls to the whisper of men who are telling stories in a haunted house.
[やぶちゃん注:「妙に流し者の淋しい氣持」“strange sense of exile and desolation”。“exile”の「流し者」は「流刑に処せられた者」という意味で、“desolation”は「荒蕪地・荒寥地方」であるから、「荒涼たる地の自然と流刑者の人事といった異様な寂寥の気持ち」といったニュアンスであろう。私は本節の姉崎氏の畳み掛けた有機的な荒々しい日本語表現が好きだ。]
雨は降り續く。併し今夜は若者たちが、網繕いをしながら、茶の間にゐる。そして、密釀酒の壜こつそりと隠し場所から出された。
かういつた崩かかつた斷崖上で葡萄酒を飲む事など思ひも寄らない。併し喜びに血を振ひ立たせる此の灰色の密釀酒こそは、此の霧の世界に忘れられて住んでゐる人たちを氣ちがひにしないやうに定められた物のやうである。
私は、盛んになつて行く陽氣な空氣を味ふ爲に、夜の
*
The rain continues; but this evening a number of young men were in the kitchen mending nets, and the bottle of poteen was drawn from its hiding-place.
One cannot think of these people drinking wine on the summit of this crumbling precipice, but their grey poteen, which brings a shock of joy to the blood, seems predestined to keep sanity in men who live forgotten in these worlds of mist.
I sat in the kitchen part of the evening to feel the gaiety that was rising, and when I came into my own room after dark, one of the sons came in every time the bottle made its round, to pour me out my share.
空は晴れ渡つて暖く照らし、全島を耀かしい寶石の如く光らせ、海と空をば蒼い輝かしい光で充たしてゐる。
私は岩の上に足を投げ出さうとやつて來た。前には北島の緣が黑ずんで見え、右手には餘りの靑さに眺められない位なゴルウェー灣が、左手には大西洋が、脚の下には切り立つた斷崖があり、頭の上には無數の鷗が翼で白い卷雲を作つて、追ひつ追はれつ飛んでゐる。
冠鳥の巣が何處か近くにあるらしく、年取つたのが一羽、頭の上、四十ヤード位の高さから手の届くまで近く、石のやうに絶えず落ちて來ては、私を追ひ立ようとしている。
をさ鳥は時々鯖を追つて、急に飛び下りながら、瀨戸の彼方此方を飛んでゐる。もつと沖の方にはキルロナンを出て西の方の深海に夜釣に出かける漁船の一隊が見える。
此處に何時間も休んでゐると、私も斷崖の野外遊戲に入り交つて、鵜や烏の仲間入りをしてゐるやうな氣がする。
多くの鳥は未開人の虛榮心を以つて私の目前で、これ見よがしに私の姿の見えてゐる間は、不思議な圓を描いてゐるが、私が行つてしまふと、岩の突出しに戻る。或る者は驚くほど巧妙に、長い時間を
東の方、低い一面の岩の上には、赤や灰色の多くの人が忙しさうに働いてゐるのが見える。昨夜の慘めさから今日の輝かしさへ、極りなく變化する此の島の氣候は、藝術家や一種の精神狀態によくある悲喜交々する氣分に類似したものを此處の人たちに植ゑ付けたやうである。とは云ふものの、島の本當の精神は或る文句の音調か、古い歌の斷片に於いてのみつかみ得るに過ぎない。何故なら、概して人人は一緒に腰掛けて、汐の事、魚の事、コニマラに於ける海草灰の値段の事などを盡きる事なく話してゐるからである。
*
It has cleared, and the sun is shining with a luminous warmth that makes the whole island glisten with the splendor of a gem, and fills the sea and sky with a radiance of blue light.
I have come out to lie on the rocks where I have the black edge of the north island in front of me, Galway Bay, too blue almost to look at, on my right, the Atlantic on my left, a perpendicular cliff under my ankles, and over me innumerable gulls that chase each other in a white cirrus of wings.
A nest of hooded crows is somewhere near me, and one of the old birds is trying to drive me away by letting itself fall like a stone every few moments, from about forty yards above me to within reach of my hand.
Gannets are passing up and down above the sound, swooping at times after a mackerel, and further off I can see the whole fleet of hookers coming out from Kilronan for a night's fishing in the deep water to the west.
As I lie here hour after hour, I seem to enter into the wild pastimes of the cliff, and to become a companion of the cormorants and crows.
Many of the birds display themselves before me with the vanity of barbarians, performing in strange evolutions as long as I am in sight, and returning to their ledge of rock when I am gone. Some are wonderfully expert, and cut graceful figures for an inconceivable time without a flap of their wings, growing so absorbed in their own dexterity that they often collide with one another in their flight, an incident always followed by a wild outburst of abuse. Their language is easier than Gaelic, and I seem to understand the greater part of their cries, though I am not able to answer. There is one plaintive note which they take up in the middle of their usual babble with extraordinary effect, and pass on from one to another along the cliff with a sort of an inarticulate wail, as if they remembered for an instant the horror of the mist.
On the low sheets of rock to the east I can see a number of red and grey figures hurrying about their work. The continual passing in this island between the misery of last night and the splendor of to-day, seems to create an affinity between the moods of these people and the moods of varying rapture and dismay that are frequent in artists, and in certain forms of alienation. Yet it is only in the intonation of a few sentences or some old fragment of melody that I catch the real spirit of the island, for in general the men sit together and talk with endless iteration of the tides and fish, and of the price of kelp in Connemara.
[やぶちゃん注:「冠烏」“hooded crows”はスズメ目カラス科ハイイロガラス(ズキンガラス)Corvus cornix のこと。ハシボソガラス Corvus corone の亜種とされる。ウラル山脈以西のロシアや東ヨーロッパ・北部ヨーロッパに広く棲息する。体長約50cmで雑食性、灰色の体に黒ずんだ濃紺の頭・胸と濃青色の翼を持つ。通常は高木の梢に営巣する。
「四十ヤード」約36m 強。
「をさ鳥」“Gannets”。オサドリはカツオドリの別名で、元は小笠原方言とする記載が多い。通常なら英名のこれは確かに和名のペリカン目カツオドリ科カツオドリSula leucogaster を指すのであるが、この「カツオドリ」を逆に調べてみると、英名では“Brown Booby”となっており、やや同定に躊躇する。逆に英語の“Gannet”を調べると、同じカツオドリ科のシロカツオドリMorus bassanus に“Northern Gannet”の英名が与えられている。シロカツオドリの繁殖地域は北大西洋で、現在の主な繁殖地としてアラン島に近いアイルランド南西端がドットされており、また、海を見下ろす崖や小さな岩塊の多い島に大きな集団営巣地を形成することからも、「シロカツオドリ」が有力な正式同定候補となるように思われる。
「海草灰」原文の“kelp”は、通常ならば大型のコンブ類の生体を指すが、ここでは姉崎氏の訳したように海藻を燻して灰にしたものを指している。これはコンブの他、アラメ・カジメ・ホンダワラなどを含む広範な褐藻類を天日干しにした上で、更にそれを蒸し焼きにして作った灰で、当時は農業用のカリウム肥料や西洋人に欠乏しがちなヨードを精製するための原料にした。後にその粗製シーンが描写される。但し、姉崎氏の「海草灰」という訳語は海洋生物愛好家の私にはいただけない。「海草」は水棲種子植物を指し、植物分類学上のケルプ類=海産藻類とは全く異なるからである。]
今朝、
墓が掘られてゐる間、女たちは早蕨の青く緣取つた平らな墓石の間に坐つて激しい泣唱即ち死者の爲の泣き叫びを初めた。お婆さんたちは代る代る朗吟の音頭を取つて、身體を前後に搖り、額を目の前の石の方に曲げながら、暫く深い悲しみに醉つてゐるやうであつた。さうしながら啜り泣きの歌聲を繰り返し繰り返して、死者に呼びかけてゐた。
また墓地の周りには別の皺のよつた婆さんたちがぐるつと取り卷き、赤いペティコートの下から目ばかり出して、同じやうな調子で身體を搖り動かしながら、伴奏のやうに皆んなに附けられて、譯の分らない歌を歌つてゐた。
その朝、天気はよかつたが、棺を下ろす頃、頭の上で雷が鳴り、雹が蕨の中ヘ音立てて落ちた。
イニシマーンに居ると、人と自然の共鳴をどうしても信ずるやうになる。折も折、お婆さんたちの聲より大きく雷が莊嚴な死の轟きを立てた時に、傍に居た人人の顏は感激に緊張し引き釣つてゐるのを私は見た。
棺が墓に納まり、雷がクレアの丘を越えて過ぎ去つた時には、泣唱は前よりも盛んになつた。
此の泣唱の悲しみは、一人の八十を越えた女の死に對する個人的な悲しみではなく、此の島のあらゆる人たちの何處かにひそんでゐる激情の全部であるやうに思はれる。此の悲痛の叫びの中に、人人の心の奧の意識は暫し表面に現はれ、波と風とで戰ふ宇宙に面と向ひつつ孤立を感ずる人たちの氣持を表はしてゐるやうである。彼等は不斷無口であるが、死を前にすると、無頓着と忍耐に見えてゐたものは忘れられ、彼等の凡てが定められた恐ろしい運命の前に、いたましい絶望で泣き叫ぶのである。
棺を蔽ふ前、-人の老婆が墓の傍に跪いて、死者の爲に簡單な祈禱を繰り返した。
此の贖罪の言葉と、異教的な絶望の叫びにまだ嗄れてゐる聲で唱へるカトリック教的信仰の言葉には、一つの皮肉があつた。
墓の少し向うには、屋根のない教會跡の壁蔭に坐りながら、泣唱を歌つてゐる婆さんたちの一列が見えた。彼等はまだ悲しみの爲にすゝり泣き、身體を震はせてゐたが、此の世の恐ろしさを紛らす日常のありなし事を再び語り出してゐた。
皆んな墓地から出てしまひ、二人の男が棺を中へ下ろすための壁の穴を塞いでしまふと、我我は、何やかや語りつつ、また冗談を云ひつつ、恰かも
一人の男は、或る葬式で行はれた密釀酒の酒盛りの話をした。
「此のあひだ」と彼は云つた。「酒盛りの最中に、二人の男が墓地で仆れた。その日は醫者を呼びに行く事が出來ないほど海が荒れてゐた。そしてその中の一人はそれつきり生氣つかずに、その晩死んでしまつた。」
*
After Mass this morning an old woman was buried. She lived in the cottage next mine, and more than once before noon I heard a faint echo of-the keen. I did not go to the wake for fear my presence might jar upon the mourners, but all last evening I could hear the strokes of a hammer in the yard, where, in the middle of a little crowd of idlers, the next of kin laboured slowly at the coffin. To-day, before the hour for the funeral, poteen was served to a number of men who stood about upon the road, and a portion was brought to me in my room. Then the coffin was carried out sewn loosely in sailcloth, and held near the ground by three cross-poles lashed upon the top. As we moved down to the low eastern portion of the island, nearly all the men, and all the oldest women, wearing petticoats over their heads, came out and joined in the procession.
While the grave was being opened the women sat down among the flat tombstones, bordered with a pale fringe of early bracken, and began the wild keen, or crying for the dead. Each old woman, as she took her turn in the leading recitative, seemed possessed for the moment with a profound ecstasy of grief, swaying to and fro, and bending her forehead to the stone before her, while she called out to the dead with a perpetually recurring chant of sobs.
All round the graveyard other wrinkled women, looking out from under the deep red petticoats that cloaked them, rocked themselves with the same rhythm, and intoned the inarticulate chant that is sustained by all as an accompaniment.
The morning had been beautifully fine, but as they lowered the coffin into the grave, thunder rumbled overhead and hailstones hissed among the bracken.
In Inishmaan one is forced to believe in a sympathy between man and nature, and at this moment when the thunder sounded a death-peal of extraordinary grandeur above the voices of the women, I could see the faces near me stiff and drawn with emotion.
When the coffin was in the grave, and the thunder had rolled away across the hills of Clare, the keen broke out again more passionately than before.
This grief of the keen is no personal complaint for the death of one woman over eighty years, but seems to contain the whole passionate rage that lurks somewhere in every native of the island. In this cry of pain the inner consciousness of the people seems to lay itself bare for an instant, and to reveal the mood of beings who feel their isolation in the face of a universe that wars on them with winds and seas. They are usually silent, but in the presence of death all outward show of indifference or patience is forgotten, and they shriek with pitiable despair before the horror of the fate to which they are all doomed.
Before they covered the coffin an old man kneeled down by the grave and repeated a simple prayer for the dead.
There was an irony in these words of atonement and Catholic belief spoken by voices that were still hoarse with the cries of pagan desperation.
A little beyond the grave I saw a line of old women who had recited in the keen sitting in the shadow of a wall beside the roofless shell of the church. They were still sobbing and shaken with grief, yet they were beginning to talk again of the daily trifles that veil from them the terror of the world.
When we had all come out of the graveyard, and two men had rebuilt the hole in the wall through which the coffin had been carried in, we walked back to the village, talking of anything, and joking of anything, as if merely coming from the boat-slip, or the pier.
One man told me of the poteen drinking that takes place at some funerals.
'A while since,' he said, 'there were two men fell down in the graveyard while the drink was on them. The sea was rough that day, the way no one could go to bring the doctor, and one of the men never woke again, and found death that night.'
[やぶちゃん注:「泣唱」“keen”この語は、アイルランドの習俗で、死者に対して哀しみを表すために歌われる泣き叫びを伴った
「通夜」原文“wake”。通常の英語では目覚めている、寝ずにいる、という動詞であるが、アイルランド方言では動詞としては「死者を取り囲んで通夜をする」、名詞としてはアイルランドに於ける「通夜」を意味する特別な意を持つ。
「早蕨」“early bracken”はシダ植物門シダ綱シダ目コバノイシカグマ科ワラビ Pteridium aquilinum の若芽。
「お婆さんたちは代る代る朗吟の音頭を取つて」原文は“Each old woman, as she took her turn in the leading recitative”。これはキーンの始まりに特徴的な語りを重視した(哀悼の意を表明する)叙唱めいた、定型的な触りの悲痛な語りを言うのであろう。
「此の贖罪の言葉と、異教的な絶望の叫びにまだ嗄れてゐる聲で唱へるカトリック教的信仰の言葉には、一つの皮肉があつた。」というのは、キーンを主体としたケルト信仰の葬送儀礼の中に、突如、カトリックの「贖罪」の「祈禱」が行われるということが、排他的で保守的なカトリックの立場から考えれば如何にも皮肉な様相を呈している、というシングの「皮肉」な表現である。
「その中の一人はそれつきり生氣つかずに、その晩死んでしまつた」という叙述からは、彼らの密造酒“poteen”(ポチーン:アイリッシュ・ウィスキー。)の中には、メチルや毒性のある香り付けを添加したような危険なものがあったのではないかということを疑わせる記述ではある。]

[ケルプ灰作り]
此の間、此の家の男たちは新しい畑を造つた。僅かばかり土のある處が、庭の塀際と、もう一つはキャベツ畑の隅にあつた。爺さんと一番上の息子が、金鑛で働いてゐる人のやうに細心に土を掘り出し、マイケルがそれを荷籠に入れて――此の島には車といふものがないので――地所の圍はれた一角にある平たい岩の上に運び、其處で砂と海草を混ぜて石の上に一面に擴げた。
馬鈴薯の栽培は島では大概こんな畑でなされる。――その爲には可成りの金を拂つて。 ――そして季節が全く日照りの時、よい收穫の望みは殆んど常に外れる。
雨がないのは今日で九日である。太陽の熱さはまだひどくはないが、人人は非常に心配してゐる。
日照りはまた水の缺乏の原因となる。島のこちら側にもいくつかの泉はあるが、それも少し遠くから来るに過ぎず、暑い日は當にする事が出来ない。此の家へ水を支給するのは女の手一つで水桶に入れて運ばれる。直ぐに汲めば、味は大して嫌でもないが、時時やられるやうに、桶に何時間も溜めて置かれては嗅ひも色もまた味も堪らない。洗濯の水もまた不足する。そんな時、海の緣を歩いてゐると、ペティコートをたくし上げて、
島の人たちはかういふ乾燥期を利用してケルプ灰を燃し初め、全島は灰色の煙の渦の中に横たはる。今年は、住民が市價の不安定の爲に氣乘がしないのと、利益が確かでない製造の仕事に從事しようとしないので、澤山は出來ないであらう。
一頓のケルプ灰を造るのに要する勞働は大したものである。海草を秋と冬の嵐の後で岩から集め、天気の好い日に乾かし、一山にして積み、六月の初めまでそのままにしておく。
それから海岸で、脊の低い窯で燃す。これは十二時間乃二十四時間の続け樣の激しい勞働である。だが此處の島民は餘り取扱ひが上手でなく、必要以上を燃し過ぎて取れる灰の一部分を駄目にする。
窯は燃えたケルプ灰の二噸位を入れ得るが、それが一杯になると、ゆるく石で蓋をして冷しておく。二三日たつと中の物は石灰岩のやうに硬くなる。それを
アランでは、製造がまた面白い。クリーム色の濃い煙を吐き出してゐる焰に緣取られた低い窯は、その煙つた中に立ち働く赤や灰色の着物の勞働者の一團や、ペティーコートを着て飲み物を持つて來る子供たち女たちと共に、東洋の繪のやうな多種なまた多樣を光景を造る。
男たちは或る意味で、島の名物と思つてゐて、自慢顏にその仕事を私に見せてくれる。一人の男が、昨日私に云ふには、「あなたは、今日までこんな仕事をきつと見なかつたでせう?」
「なるほど」私は答へた。「見た事がなかつた。」
「おやおや、それでは」と彼は云つた。「あなたはフランスやドイツや法王を見たくせに、イニシマーンに來るまでケルプ灰を造つてゐる人を見なかつたとは、不思議なことだ。」
*
The other day the men of this house made a new field. There was a slight bank of earth under the wall of the yard, and another in the corner of the cabbage garden. The old man and his eldest son dug out the clay, with the care of men working in a gold-mine, and Michael packed it in panniers--there are no wheeled vehicles on this island--for transport to a flat rock in a sheltered corner of their holding, where it was mixed with sand and seaweed and spread out in a layer upon the stone.
Most of the potato-growing of the island is carried on in fields of this sort--for which the people pay a considerable rent--and if the season is at all dry, their hope of a fair crop is nearly always disappointed.
It is now nine days since rain has fallen, and the people are filled with anxiety, although the sun has not yet been hot enough to do harm.
The drought is also causing a scarcity of water. There are a few springs on this side of the island, but they come only from a little distance, and in hot weather are not to be relied on. The supply for this house is carried up in a water-barrel by one of the women. If it is drawn off at once it is not very nauseous, but if it has lain, as it often does, for some hours in the barrel, the smell, colour, and taste are unendurable. The water for washing is also coming short, and as I walk round the edges of the sea, I often come on a girl with her petticoats tucked up round her, standing in a pool left by the tide and washing her flannels among the sea-anemones and crabs. Their red bodices and white tapering legs make them as beautiful as tropical sea-birds, as they stand in a frame of seaweeds against the brink of the Atlantic. Michael, however, is a little uneasy when they are in sight, and I cannot pause to watch them. This habit of using the sea water for washing causes a good deal of rheumatism on the island, for the salt lies in the clothes and keeps them continually moist.
The people have taken advantage of this dry moment to begin the burning of the kelp, and all the islands are lying in a volume of grey smoke. There will not be a very large quantity this year, as the people are discouraged by the uncertainty of the market, and do not care to undertake the task of manufacture without a certainty of profit.
The work needed to form a ton of kelp is considerable. The seaweed is collected from the rocks after the storms of autumn and winter, dried on fine days, and then made up into a rick, where it is left till the beginning of June.
It is then burnt in low kilns on the shore, an affair that takes from twelve to twenty-four hours of continuous hard work, though I understand the people here do not manage well and spoil a portion of what they produce by burning it more than is required.
The kiln holds about two tons of molten kelp, and when full it is loosely covered with stones, and left to cool. In a few days the substance is as hard as the limestone, and has to be broken with crowbars before it can be placed in curaghs for transport to Kilronan, where it is tested to determine the amount of iodine contained, and paid for accordingly. In former years good kelp would bring seven pounds a ton, now four pounds are not always reached.
In Aran even manufacture is of interest. The low flame-edged kiln, sending out dense clouds of creamy smoke, with a band of red and grey clothed workers moving in the haze, and usually some petticoated boys and women who come down with drink, forms a scene with as much variety and colour as any picture from the East.
The men feel in a certain sense the distinction of their island, and show me their work with pride. One of them said to me yesterday, 'I'm thinking you never saw the like of this work before this day?'
'That is true,' I answered, 'I never did.'
'Bedad, then,' he said, 'isn't it a great wonder that you've seen France and Germany, and the Holy Father, and never seen a man making kelp till you come to Inishmaan.'
[やぶちゃん注:「リューマチス」現在の知見ではリウマチは自己免疫疾患が原因と考えられている。リウマチ患者にはDR4というタンパク質で作られたHLA遺伝子保持者が健常者に比べて多いという事実が分かっており、このHLA‐DR4遺伝子が免疫システムに何らかの異常を起こしている可能性が指摘されていて、遺伝因子による発症も否定出来ないとされている。
「ペティーコートを着て飲み物を持つて來る子供たち女たちと共に」の部分を、栩木氏は『そこへ、妖精にさらわれないようペチコートを着せられた男の子たちや女たちが飲み物を持ってくる。』と訳しておられる。原文は“and usually some petticoated boys and women who come down with drink,”であるから、現地での着衣の民俗を踏まえた意訳と思われるが、極めて興味深い。]
此處では夏の間、食べさせる草がないので、六月から九月にかけて、全部の馬はコニマラの山の中の草地に送り出される。
その船積み運搬は、牛の場合よりも一層むづかしくさへある。多くはコニマラ産の野生の小馬で、力が強くて臆病なので、狭い波止場では取扱ひに骨が折れる。また一方、船の中でも間に合ふ場所が少いので、それ等を安全に立たせるのが容易な事ではない。取扱ひの仕事は、前に牛の場合に云つたのと同樣あるが、騒はもつと激しく、一匹の馬が波止場から押し出されて、無事にその納まる場所に納つてしまふまで、嵐のやうに起るゲール語は形容が出來ない。二十人の若い男、年とつた男たちが、その間ぢう、譯も分らずに罵つたり、勵したりしつつ、亢奮して喚き叫ぶ。
併し此のやうな原始的な騒ぎは別として、男たちの器用さや、力強さを見るのにこれまでになくよい機會であつた。私は、特に今朝荷を積んで北島からやつて來た漁船の船頭に目を止めた。馬が帆柱の頂きから搖れながら下つてゐる時、自分一人の重さでそれを持ち堪へて、而も熱狂の最中にありながら、面白さうに平靜を保つてゐた。或る時は大き牝馬が他の馬の脊の上に横樣に落ちかかつて來て、そこら中を蹴る。すると、小馬に害を與へまいと男たちが飛び下りて來るので、船艙はセントー〔神話の半神半馬〕たちが一塊となつて暴れ狂ふまでになる。先に入れられた馬の脊中は、時時その上に下りて來る他の馬の蹄でひどく切られる事がある。その他は大した害もないらしい。それ等は市に行くのではないから、どんな狀態で陸上げされようと別に構はない。
島には一つの轡と一つの鞍があるだけである。これは日曜のお勤めをした時、教會から波止場まで騎つて来る坊さんが使ふ。
島の人たちは二筋の手綱と一木の棒切れだけで馬に騎り、大きな島では、無鐵砲な驅足で騎り廻はす事もある。馬は普通荷籠を背負つてゐるので、人は馬の肩骨の上に横騎りをし、荷籠が
アランモアでは、キルロナンから西の方へ荷籠を付けて行く一隊に、私はよく逢つた。彼等の見えて來るずつと前から、蹄の音が聞こえて來る。すると彼等は唯一の止め手綱である細い索を全然無用視して、頭を前の方に突き出し、疾風のやうな速さで角を曲つてやつて來る。大概、前後五六尺の距離をおいて一列となつて來るが、車がないので間違ひの起る心配は少い。
時時、男と女が合乘りしてゐる事がある。此の場合、男は普通の位置に坐り、女はその後に坐り、男の腰をつかまへてゐる。
*
All the horses from this island are put out on grass among the hills of Connemara from June to the end of September, as there is no grazing here during the summer.
Their shipping and transport is even more difficult than that of the homed cattle. Most of them are wild Connemara ponies, and their great strength and timidity make them hard to handle on the narrow pier, while in the hooker itself it is not easy to get them safely on their feet in the small space that is available. They are dealt with in the same way as for the bullocks I have spoken of already, but the excitement becomes much more intense, and the storm of Gaelic that rises the moment a horse is shoved from the pier, till it is safely in its place, is indescribable. Twenty boys and men howl and scream with agitation, cursing and exhorting, without knowing, most of the time, what they are saying.
Apart, however, from this primitive babble, the dexterity and power of the men are displayed to more advantage than in anything I have seen hitherto. I noticed particularly the owner of a hooker from the north island that was loaded this morning. He seemed able to hold up a horse by his single weight when it was swinging from the masthead, and preserved a humorous calm even in moments of the wildest excitement. Sometimes a large mare would come down sideways on the backs of the other horses, and kick there till the hold seemed to be filled with a mass of struggling centaurs, for the men themselves often leap down to try and save the foals from injury. The backs of the horses put in first are often a good deal cut by the shoes of the others that arrive on top of them, but otherwise they do not seem to be much the worse, and as they are not on their way to a fair, it is not of much consequence in what condition they come to land.
There is only one bit and saddle in the island, which are used by the priest, who rides from the chapel to the pier when he has held the service on Sunday.
The islanders themselves ride with a simple halter and a stick, yet sometimes travel, at least in the larger island, at a desperate gallop. As the horses usually have panniers, the rider sits sideways over the withers, and if the panniers are empty they go at full speed in this position without anything to hold to.
More than once in Aranmor I met a party going out west with empty panniers from Kilronan. Long before they came in sight I could hear a clatter of hoofs, and then a whirl of horses would come round a corner at full gallop with their heads out, utterly indifferent to the slender halter that is their only check. They generally travel in single file with a few yards between them, and as there is no traffic there is little fear of an accident.
Sometimes a woman and a man ride together, but in this case the man sits in the usual position, and the woman sits sideways behind him, and holds him round the waist.
[やぶちゃん注:「セントーたちが一塊となつて暴れ狂ふ」“a mass of struggling centaurs”本作中でも最も印象的で劇的なシークエンスである。馬と人が一体となって、そこにかのセントウル(ケンタウルス)の、原初の神々の饗宴が再現されるのである。「無鐵砲な驅足」“a desperate gallop”は無茶苦茶なギャロップ(馬術の全速力)の意。]
パット・ディレイン爺さんは毎日私の處へ話しにやつて來る。私は時時話を彼の妖精の経験談に向ける。
爺さんは、妖精をたくさん島の方方で、殊に船卸臺の北、砂地の處で見たさうである。脊の高さは一ヤード位で、
彼は妖精にさらはれた二人の女を見た。一人は既婚の婦人で、今一人は娘であつた。婦人は塀際に立つてゐた。爺さんは北の方を向きながら、私に丁寧にその場所を説明してくれた。
また或る夜、愛蘭土語で「オー・ウォホイル・ソ・メー・モラヴ」(ああ、お母さん、殺される)といふ叫び聲を彼は聞いたが、朝になつてその家の塀に血がついてゐて、そこから程遠からぬ處に、その家の子供は死んでゐた。
昨日、彼は私を脇へつれて行き、まだ誰にも云はなかつた祕密を教へてやると云つた。
「先の鋭い針を取つて、」彼は云つた。「それをあなたの着物の襟裏にさしとくと、どんな妖精だつてどうすることもできないものだ。」
鐵は未開人にとつて共通の護符であるが、此の場合は先の極く鋭いと云ふ觀念も加はり、また恐らくブリタニーに共通の民間信仰として、仕事の器具を神聖視する感じも出てゐるのであらう。
妖精は他の郡よりも比較的メオ郡に多くゐるが、ゴルウェーの或る地方をも好み、次の話も其處で行はれた。
*
Old Pat Dirane continues to come up every day to talk to me, and at times I turn the conversation to his experiences of the fairies.
He has seen a good many of them, he says, in different parts of the island, especially in the sandy districts north of the slip. They are about a yard high with caps like the 'peelers' pulled down over their faces. On one occasion he saw them playing ball in the evening just above the slip, and he says I must avoid that place in the morning or after nightfall for fear they might do me mischief.
He has seen two women who were 'away' with them, one a young married woman, the other a girl. The woman was standing by a wall, at a spot he described to me with great care, looking out towards the north
Another night he heard a voice crying out in Irish, 'mháthair tá mé marbh' ('O mother, I'm killed'), and in the morning there was blood on the wall of his house, and a child in a house not far off was dead.
Yesterday he took me aside, and said he would tell me a secret he had never yet told to any person in the world.
'Take a sharp needle,' he said, 'and stick it in under the collar of your coat, and not one of them will be able to have power on you.'
Iron is a common talisman with barbarians, but in this case the idea of exquisite sharpness was probably present also, and, perhaps, some feeling for the sanctity of the instrument of toil, a folk-belief that is common in Brittany.
The fairies are more numerous in Mayo than in any other county, though they are fond of certain districts in Galway, where the following story is said to have taken place.
[やぶちゃん注:「一ヤード位」90センチメートル強。
「
「オー・ウォホイル・ソ・メー・モラヴ」原文は“mháthair tá mé marbh”。栩木氏の訳では『ア・ウアハル・ター・メー・マラヴ』というルビが振られている。最後の“marbh”はネイティヴの発音を聴く限りでは、私には「マァラルゥ」と聴こえる。
「ブリタニー」原文“Brittany”。これは“Bretagne”で、フランス北西端の大西洋に突き出たブルターニュ半島を中心としたブルターニュ地方。ドーバー海峡を挟んでイギリスと接する。地名は五世紀頃、ケルト人がブリタニア、現在のイギリスから移住しここを開拓したことに由来し、先史時代のメンヒル・ドルメンといった巨石文化も齎された、ケルト系文化や民族が色濃く残る、フランスでも特異な地域である。
「メオ郡」“Mayo”。メイヨー州。アイルランド北西部、神話にもしばしば登場するコノート地方にある大きな州。]
「或る百姓が收穫は駄目になるし、牛は死んでしまふし、大へん困つてゐた。或る晩、妻に明日の朝までに小麥の新しい立派な袋を作つてくれと云つた。それが出來ると、それを持つて、夜明けを待たないで出發した。
その頃、妖精に連れて行かれた紳士がゐて、妖精の中で大將になり、夜明けと夕方に、白馬に騎つて行くのを人人はよく見かけた。
件の男は、いつも大將に逢ふ處に行き、かれが馬に乘つて通りかかつた時、大へん困つてゐるから、小麥粉を二百五十ほど貸してもらひたいと願つた。
大將は妖精たちを小麥の藏つてある岩穴から呼び出し、望むだけをその男に與へるやうに命じた。そして一年經つたらまた此處へ來て、金を拂つてくれと云つて、馬に乘つて行つてしまつた。
男は家に歸り、その期日を紙に書き留めた。そして翌年のその日に、又もとの所へ行つて、大將に支拂つた。」
此の話を終つた時、爺さんは、妖精は國中の産物全體の十分の一を持つてゐて、それを岩の中に藏つておくのだと云つた。
*
'A farmer was in great distress as his crops had failed, and his cow had died on him. One night he told his wife to make him a fine new sack for flour before the next morning; and when it was finished he started off with it before the dawn.
'At that time there was a gentleman who had been taken by the fairies, and made an officer among them, and it was often people would see him and him riding on a white horse at dawn and in the evening.
'The poor man went down to the place where they used to see the officer, and when he came by on his horse, he asked the loan of two hundred and a half of flour, for he was in great want.
'The officer called the fairies out of a hole in the rocks where they stored their wheat, and told them to give the poor man what he was asking. Then he told him to come back and pay him in a year, and rode away.
'When the poor man got home he wrote down the day on a piece of paper, and that day year he came back and paid the officer.'
When he had ended his story the old man told me that the fairies have a tenth of all the produce of the country, and make stores of it in the rocks.
[やぶちゃん注:老婆心ながら、「藏つて」は「しまつて」と訓じる。]
今日は
今朝は、日曜によくあるやうに、不思議な靜寂が全島を襲つて、兩側の海も禮拜堂のやうな靜けさに充たされてゐる。
此處にある一つの風景は、不思議な力を以つて灰色の光を含んだ雲のある事をはっきりと感じさせる。風もなく、又これといふ光もない。アランモアは鏡の上に眠つてゐるやうである。そしてコニマラの山山は、その前に横たはる灣の廣さの見當がつき難いほど近く見え、灣は今朝、湖に時時見るやうな獨特な表情をしてゐる。
此の草も木も生えず、動物も住まない岩の上では、季節はいつも同じである。此の六月の日も何んとなく、枯葉のそよぎが聞こえるかと思ふほどに秋の氣が充ち充ちてゐる。
禮拜堂からは、先づ最初に男たちの一團が出で、それから續いて女たちの一團が出る。男たちは往來に立ちもとほつて話してゐる間に、女たちは門前で別れ、四方に急ぎ散つて行く。
沈默は破られ、ゲール語の幽かな聲が、恰も海を越えて來る如く、遠くから聞こえる。
*
It is a Holy Day, and I have come up to sit on the Dun while the people are at Mass.
A strange tranquility has come over the island this morning, as happens sometimes on Sunday, filling the two circles of sea and sky with the quiet of a church.
The one landscape that is here lends itself with singular power to this suggestion of grey luminous cloud. There is no wind, and no definite light. Aranmor seems to sleep upon a mirror, and the hills of Connemara look so near that I am troubled by the width of the bay that lies before them, touched this morning with individual expression one sees sometimes in a lake.
On these rocks, where there is no growth of vegetable or animal life, all the seasons are the same, and this June day is so full of autumn that I listen unconsciously for the rustle of dead leaves.
The first group of men are coming out of the chapel, followed by a crowd of women, who divide at the gate and troop off in different directions, while the men linger on the road to gossip.
The silence is broken; I can hear far off, as if over water, a faint murmur of Gaelic.
[やぶちゃん注:「男たちは往來に立ちもとほつて話してゐる間に、」原文“while the men linger on the road to gossip.”。「もとほる」は記紀歌謡に登場する古語で「歩き回る・徘徊する」の意である。「男たちが路上に溜まり込んで、世間話に花を咲かせている間に、」の意。]
午後になつて、陽が出て來た。私はキルロナンへ行くため、船を漕ぎ出して貰つた。
漕ぐ人たちは波止場近くの岬の沖を廻つてカラハを持つて來る途中、暗礁にあてた。そして水を澤山入れたまま岸へ來た。彼等は坊さんに持つて行く馬鈴薯の袋からズックを引裂き、穴に栓をした。それで大西洋と我我の間には、破れた布一枚あるだけで出立したのである。
數百ヤード毎に、漕手の一人は止つて、水を
瀨戸を横切つて半分ほど來た處で、こちらへやつて來る一艘の帆を張つたカラハに出逢つた。
ゲール語で叫び交はしてゐたが、それは私に手紙と煙草の一包みを持つて來たのだといふことがわかつた。我々はうねりと共に、出來るだけ近くすり寄つて、荷物はしぶきに濡れて、私の方へ投げられた。
イニシマーンに於ける數週間の後では、キルロナンは盛んな活動の中心地のやうに見えた。此の大きい島の半ば文明化された漁夫たちは、此處の生活の單純さを輕蔑する傾向がある。私が上陸した時、傍に立つてゐた或る者は、見物するに相應しい漁もなくて一體何をして暮してゐるかと、私に尋ねた。
旅館の老人夫婦と話しに一寸立寄り、それから村の他の處を訪ねるために、出かけた。
タ方遅く、私は北の方の道に沿うて散歩に出かけた。その道では、祝祭日にキルロナンへ集る遠い村の人たちが、三々五々群を爲して、移動家庭となつて來るのに出逢つた。
女たちや娘たちは、男の連れがゐない時は大概私をからかつて行く。
「疲れたんですか?」と一人の娘は云つた。私は東の方へ歸る前、時間をつぶすために、のろのろ歩いてゐた。
「なあに、さうぢやないよ、娘さん。私は淋しいのだ。」と私はゲール語で返事をした。
「これ私の妹よ。腕を貸して上げるでせう。」
こんな調子であつた。これ等の女たちは不斷はおとなしいが、祭日の晴着を着て襟卷をして、二三人一緒になると、都會の女たちのやうにはしやいで氣紛れになる。
七時頃、キルロナンへ戻り、私は入江近くの酒場から船頭たちを追ひ立てた。彼等の無頓着はいつもの事であるが、カラハの中に漏口のある事も、また櫂栓〔櫂を船緣に固定するための釘〕の失くなつてゐる事も氣づかず、足下に段段と深くなる水溜りを持ちながら、途方もないのろい速度で瀨戸横斷の途についた。
島の上には見事な夕燒が懸かり、遅れたのが却つて嬉しかつた。振り向くと、岩の鋭い切先の後には金色の靄があり、太陽の殘照が長く引いて、櫂に依つて殘される泡を寶石にしてゐた。
みんな黑ビールを飲んで、常ならず口數が多くなり、見て來た物を私に指し示したり、時時漕ぐのを止めて、波から跳ねる鯖の油ぽい匂を私に注意したりした。
彼等は取り立ての一行が明日の朝、島へ來るのだと告げ、私に長長と彼等がその年に儲けた事、費した事、また家賃に就いての心配を語つた。
「家賃は貧乏人にとつては實に辛い。」その中の一人が云つた。「今度我我は拂はなかつたんだ。そこで皆んなに令狀を突きつけて來たんだ。今度は家賃を拂はなくちやならぬ。それから令狀に對してもうんと取られる。大方の役人は、その令狀で自分の、女中や下男に一年分支拂ふ位の金は充分貰ふのだらう。」
私はその後で、此の島は誰の物なのかと尋ねた。
「なあに、」彼等は云つた。「何とか孃の物だと聞いてゐたが、その女はもう死んだ。」
太陽が菱形の金色の光芒のやうに海に沈むと、寒さが激しくなつて來た。男たちは彼等同志で話し出し、私は話の緒がなくなつたので、半ば夢見心地に、周りの蒼い油のやうな海や、村を越えて立つてゐる島の低い斷崖などを眺めながら、横になつた。村の炊煙の環はコノール
*
the afternoon the sun came out and I was rowed over for a visit to Kilronan.
As my men were bringing round the curagh to take me off a headland near the pier, they struck a sunken rock, and came ashore shipping a quantity of water, They plugged the hole with a piece of sacking torn from a bag of potatoes they were taking over for the priest, and we set off with nothing but a piece of torn canvas between us and the Atlantic.
Every few hundred yards one of the rowers had to stop and bail, but the hole did not increase.
When we were about half way across the sound we met a curagh coming towards us with its sails set. After some shouting in Gaelic, I learned that they had a packet of letters and tobacco for myself. We sidled up as near as was possible with the roll, and my goods were thrown to me wet with spray.
After my weeks in Inishmaan, Kilronan seemed an imposing centre of activity. The half-civilized fishermen of the larger island are inclined to despise the simplicity of the life here, and some of them who were standing about when I landed asked me how at all I passed my time with no decent fishing to be looking at.
I turned in for a moment to talk to the old couple in the hotel, and then moved on to pay some other visits in the village.
Later in the evening I walked out along the northern road, where I met many of the natives of the outlying villages, who had come down to Kilronan for the Holy Day, and were now wandering home in scattered groups.
The women and girls, when they had no men with them, usually tried to make fun with me.
'Is it tired you are, stranger?' said one girl. I was walking very slowly, to pass the time before my return to the east.
'Bedad, it is not, little girl,' I answered in Gaelic, 'It is lonely I am.'
'Here is my little sister, stranger, who will give you her arm.'
And so it went. Quiet as these women are on ordinary occasions, when two or three of them are gathered together in their holiday petti-coats and shawls, they are as wild and capricious as the women who live in towns.
About seven o'clock I got back to Kilronan, and beat up my crew from the public-houses near the bay. With their usual carelessness they had not seen to the leak in the curagh, nor to an oar that was losing the brace that holds it to the toll-pin, and we moved off across the sound at an absurd pace with a deepening pool at our feet.
A superb evening light was lying over the island, which made me rejoice at our delay. Looking back there was a golden haze behind the sharp edges of the rock, and a long wake from the sun, which was making jewels of the bubbling left by the oars.
The men had had their share of porter and were unusually voluble, pointing out things to me that I had already seen, and stopping now and then to make me notice the oily smell of mackerel that was rising from the waves.
They told me that an evicting party is coming to the island tomorrow morning, and gave me a long account of what they make and spend in a year and of their trouble with the rent.
'The rent is hard enough for a poor man,' said one of them, 'but this time we didn't pay, and they're after serving processes on every one of us. A man will have to pay his rent now, and a power of money with it for the process, and I'm thinking the agent will have money enough out of them processes to pay for his servant-girl and his man all the year.'
I asked afterwards who the island belonged to.
'Bedad,' they said, 'we've always heard it belonged to Miss - and she is dead.'
When the sun passed like a lozenge of gold flame into the sea the cold became intense. Then the men began to talk among themselves, and losing the thread, I lay half in a dream looking at the pale oily sea about us, and the low cliffs of the island sloping up past the village with its wreath of smoke to the outline of Dun Conor.
[やぶちゃん注:「家賃」原文“rent”。土地貸借料。地代のこと。18世紀中頃からアラン島はキルデア県のディグビー一族が島の地主となったが、彼ら一族は島には殆んど居住することなく定期的な定額地代を徴収し、貧しかった多くの島民が地代を払えずに強制的な立ち退きを余儀なくされていたという。19世紀になると慢性的な主食のジャガイモの供給不足に陥り、大数の島民が国外への移民を選んだ(因みに島の人口は1841年で3,521人、1976年で1,496人、2010年現在は1,300人)。ディグビー・セント・ローレンス一族が島の所有権を売り渡し、彼らが自分達の土地としてそこに住めるようになったのは、実にシングが訪れた後の凡そ20年後、1922
年のことであった(以上はアイルランド現地旅行会社“ewe tours”のHPの「アラン島の歴史」を主に参照させて頂いた。
「コノール
家に歸ると、パット爺さんが來てゐて、晩飯の後に長い物語をしてくれた。――
*
Old Pat was in the house when I arrived, and he told a long story after supper:--
昔、森の中に後家さんが一人息子と一緒に住んでゐた。息子は毎朝、森に薪木を拾ひに出かけた。或る日、地面に寢ろんでゐると、牛が後に殘していつた物の上に蠅が一杯飛んでゐるのを見た。彼は斧を取つて、それを打つと、一匹も餘さずに打てた。
その晩、息子は母親に向ひ、たかつてゐた蠅を一撃で殺すことが出來たから幸福を求めに世の中へ出かけるのによい時と思はれると云ひ、明朝持つて行けるやうに菓子を三つ作つてくれと賴んだ。
翌日、その三つの菓子を袋に入れて、夜が明けると直ぐ出立した。そして十時ごろ三つの菓子のうち一つを食べた。
おひるになるとまた腹がすいたので、二つ目を食べ、夕方三つ目を食べた。その後で、一人の男に出逢つたら、その男は何處へ行くのかと聞いた。
「
「私について來い。」その男は云つた。「ぢや今夜は、納屋に寢なさい、明日お前に何が出來るかを見るために、仕事を與へよう。」
翌朝、その百姓は彼を連れ出し、牛を見せて、此の牛を丘で草を食べさせるために外へ出し、誰も牛乳を取りに來ないやうに、よく番をしてをれと云ひつけた。若者は牛を野原に連れ出し、日が暑くなると、仰向けに寢て空を眺めてゐた。暫くすると西北の方に一つの黒い點が見え、それが近づくに従ひ段段大きくなり、遂に一人の恐ろしい巨人となつてやつて來た。
彼は立ち上つて、両腕で巨人の脚をしつかりと抱へた。そして動けないやうに、くるぶしを下にして堅い地面にたたきつけた。すると巨人は何も悪い事はしないからと云ひ、魔法の棒を渡し、岩を叩くと美しい黑馬と劍と立派な服が出ると教へた。
若者は岩を叩くと、見てゐる間に岩が開いて、一匹の美しい黑馬と巨人の劍と服が目の前に出た。彼は劍だけを取つて、それを一振りして巨人の首を打ち落した。それからその劍を岩に戻して、再び牛の處へ行き、百姓の處へそれ等を連れ歸つた。
乳を搾ると、澤山の乳が牛から出た。そこで百姓は、他の牧童は年を連れ歸つて一滴も乳が出なかつたが、丘で何か見かけなかつたかと尋ねた。若者は何も見かけなかつたと答へた。
次の日、また牛を連れて出かけた。日が暑くなると仰向けに寢た。すると少し經つて、西北の方に一つの黑い點が見え、それが近づいて來るに從ひ段段大きくなり、遂に一人の巨人が彼の方へやつて來て、襲ひかからうとした。
「貴樣はおれの兄貴を殺したな。さあ、貴樣をのしちまふまではおかないぞ」と巨人は云つた。
若者は彼の方へ進んで行つて、両腕でその脚を抱へ、くるぶしを下にして巨人を大地にたたきつけた。
それから棒で岩を叩き、劍を取り出し、巨人の首を切り落した。
その晩、百姓は牛に前の晩より二倍の乳のあるのがわかつた。そこで何か見かけなかつたかと尋ねた。若者は何も見かけなかつたと答へた。
第三日目には三番目の巨人が來て、「貴樣はおれの二人の兄貴を殺した。さあ來い、貴樣をのしちまふまではおかないぞ」と言つた。
そこで此の巨人をも前の二人をやつつけたやうにやつつけた。その晩は、乳が牛の乳房から道に溢れるほど澤山出た。
次の日、百姓は若者を呼び、今日は牛を牛舍に繫いでおいてもよい。美しい王女が、若し助ける者がなかつたら、大魚に食はれてしまふといふ大へん面白い
鯨より大きく脊に二つの翼のある大魚が海から現はれると、若者は波の中に躍り込んで劍でそれを打ち、その翼の一つを切り取つた。海の中はその流れ出た血で眞赤になり、遂に大魚は泳ぎ去つて、若者は岸に殘された。
それから馬をめぐらして、疾風のやうに馬を驅けらし、遂に岩の處まで來て服を脱ぎ、巨人の劍と黑馬と一緒にもとの岩の中にしまひ、牛を追つて農場に歸つた。
百姓は彼の前に來て、今日お前は未だ嘗つてない大した不思議を見損なつた。それは或る貴公子が立沢な服をつけて來て、大魚の翼の一つを切り取つた事だがと云つた。
「これからも二朝續いて、王女は同じ運命に逢ふ」と百姓は云つた。「行つてそれを見物したらよからう。」
併し若者は行きたくないと云つた。
次の朝、牛を連れて出かけ、岩から劍と服と黑馬とを取り出して、疾風のやうに馬を驅けらし、王女が海岸で金の椅子に腰掛けてゐる處まで來た。人が彼の來るのを見た時、前日に見た男と同じかどうか、大いに怪んだ。王女は彼を呼んで、跪いて禮をするやうに命じた。彼が跪いてゐた時、王女は鋏でその頭の後から一房の髮の毛を切り取り、着物の中に隠した。
それから大魚が海から現はれると、彼は波の中に躍り入り、そのもう一つの翼を切り落した。海は流れ出る血ですつかり眞赤になつたが、それは遂に皆を後に殘して逃げた。
その晩、百姓は彼の前に來て、お前は非常な不思議を見損なつた。明日は行つてみるかと聞いた。若者は行きたくないと云つた。
三日目、再び彼は黑馬に騎り、王女が金の椅子に腰掛けて大魚を待つてゐる處へ來た。大魚が海から現はれると、若者はそれを目がけて進んで行き、口を開けて食べようとするのを何度も何度も、口の中を刺して、遂に劍で頸を突き通したので、大魚は腹を上にして死んだ。
そこで、彼は疾風の如くに馬を驅けらし、服と劍と黑馬を岩の中にしまひ、牛を追つて家へ歸つた。
百姓は彼の前に來て、三旦間、婚禮の大宴會が催され、三日日には王女が大魚を殺した男を見つけたら、その男と結婚するだらうと告げた。
大宴會は催され、力持の男たちが集まつて來て、大魚を殺したのは自分だと云つた。
併し三日目に若者は服をつけ、將軍のやうに劍を佩き、黑馬に騎つて、疾風のやうに馬を驅けらしその宮殿に來た。
王女は彼は見ると、呼び入れて前に跪かせ、そしてその頭の後を見ると彼女自身の手で切取つた一房の髮の毛の跡があつた。王女は彼を王樣に引き合はせ、そして二人は結婚し、若者は領地全部を貰つた。
それでおしまひ。
*
There was once a widow living among the woods, and her only son living along with her. He went out every morning through the trees to get sticks, and one day as he was lying on the ground he saw a swarm of flies flying over what the cow leaves behind her. He took up his sickle and hit one blow at them, and hit that hard he left no single one of them living.
That evening he said to his mother that it was time he was going out into the world to seek his fortune, for he was able to destroy a whole swarm of flies at one blow, and he asked her to make him three cakes the way he might take them with him in the morning.
He started the next day a while after the dawn, with his three cakes in his wallet, and he ate one of them near ten o'clock.
He got hungry again by midday and ate the second, and when night was coming on him he ate the third. After that he met a man on the road who asked him where he was going.
'I'm looking for some place where I can work for my living,' said the young man.
'Come with me,' said the other man, 'and sleep to-night in the barn, and I'll give you work to-morrow to see what you're able for.'
The next morning the farmer brought him out and showed him his cows and told him to take them out to graze on the hills, and to keep good watch that no one should come near them to milk them. The young man drove out the cows into the fields, and when the heat of the day came on he lay down on his back and looked up into the sky. A while after he saw a black spot in the north-west, and it grew larger and nearer till he saw a great giant coming towards him.
He got up on his feet and he caught the giant round the legs with his two arms, and he drove him down into the hard ground above his ankles, the way he was not able to free himself. Then the giant told him to do him no hurt, and gave him his magic rod, and told him to strike on the rock, and he would find his beautiful black horse, and his sword, and his fine suit.
The young man struck the rock and it opened before him, and he found the beautiful black horse, and the giant's sword and the suit lying before him. He took out the sword alone, and he struck one blow with it and struck off the giant's head. Then he put back the sword into the rock, and went out again to his cattle, till it was time to drive them home to the farmer.
When they came to milk the cows they found a power of milk in them, and the farmer asked the young man if he had seen nothing out on the hills, for the other cow-boys had been bringing home the cows with no drop of milk in them. And the young man said he had seen nothing.
The next day he went out again with the cows. He lay down on his back in the heat of the day, and after a while he saw a black spot in the north-west, and it grew larger and nearer, till he saw it was a great giant coming to attack him.
'You killed my brother,' said the giant; 'come here, till I make a garter of your body.'
The young man went to him and caught him by the legs and drove him down into the hard ground up to his ankles.
Then he hit the rod against the rock, and took out the sword and struck off the giant's head.
That evening the farmer found twice as much milk in the cows as the evening before, and he asked the young man if he had seen anything. The young man said that he had seen nothing.
The third day the third giant came to him and said, 'You have killed my two brothers; come here, till I make a garter of your body.'
And he did with this giant as he had done with the other two, and that evening there was so much milk in the cows it was dropping out of their udders on the pathway.
The next day the farmer called him and told him he might leave the cows in the stalls that day, for there was a great curiosity to be seen, namely, a beautiful king's daughter that was to be eaten by a great fish, if there was no one in it that could save her. But the young man said such a sight was all one to him, and he went out with the cows on to the hills. When he came to the rocks he hit them with his rod and brought out the suit and put it on him, and brought out the sword and strapped it on his side, like an officer, and he got on the black horse and rode faster than the wind till he came to where the beautiful king's daughter was sitting on the shore in a golden chair, waiting for the great fish.
When the great fish came in on the sea, bigger than a whale, with two wings on the back of it, the young man went down into the surf and struck at it with his sword and cut off one of its wings. All the sea turned red with the bleeding out of it, till it swam away and left the young man on the shore.
Then he turned his horse and rode faster than the wind till he came to the rocks, and he took the suit off him and put it back in the rocks, with the giant's sword and the black horse, and drove the cows down to the farm.
The man came out before him and said he had missed the greatest wonder ever was, and that a noble person was after coming down with a fine suit on him and cutting off one of the wings from the great fish.
'And there'll be the same necessity on her for two mornings more,' said the farmer, 'and you'd do right to come and look on it.'
But the young man said he would not come.
The next morning he went out with his cows, and he took the sword and the suit and the black horse out of the rock, and he rode faster than the wind till he came where the king's daughter was sitting on the shore. When the people saw him coming there was great wonder on them to know if it was the same man they had seen the day before. The king's daughter called out to him to come and kneel before her, and when he kneeled down she took her scissors and cut off a lock of hair from the back of his head and hid it in her clothes.
Then the great worm came in from the sea, and he went down into the surf and cut the other wing off from it. All the sea turned red with the bleeding out of it, till it swam away and left them.
That evening the farmer came out before him and told him of the great wonder he had missed, and asked him would he go the next day and look on it. The young man said he would not go.
The third day he came again on the black horse to where the king's daughter was sitting on a golden chair waiting for the great worm. When it came in from the sea the young man went down before it, and every time it opened its mouth to eat him, he struck into its mouth, till his sword went out through its neck, and it rolled back and died.
Then he rode off faster than the wind, and he put the suit and the sword and the black horse into the rock, and drove home the cows.
The farmer was there before him and he told him that there was to be a great marriage feast held for three days, and on the third day the king's daughter would be married to the man that killed the great worm, if they were able to find him.
A great feast was held, and men of great strength came and said it was themselves were after killing the great worm.
But on the third day the young man put on the suit, and strapped the sword to his side like an officer, and got on the black horse and rode faster than the wind, till he came to the palace.
The king's daughter saw him, and she brought him in and made him kneel down before her. Then she looked at the back of his head and saw the place where she had cut off the lock with her own hand. She led him in to the king, and they were married, and the young man was given all the estate.
That is my story.
[やぶちゃん注:アイルランド口承の豊穣の牝牛(Glas Gaibhnenn グラス・ガヴナン)、神聖数3、アイルランド先住民族の形象化ともされる巨人(彼等“Fomoire”フォモール一族は戦いに敗れて後に海の怪物ロックランとなったともされる。巨人定番の足元の秘密の弱点もしっかり出現)、アーサー王伝説の“Excalibur”(エクスカリバー)を髣髴とさせる剣、岩礁に囚われた姫と翼を持った海の怪物(化け鯨)とその救済という英雄ペルセウスと王女アンドロメダ型の神話などなど、比較神話学的には頗る面白い内容である。]

[取り立て]
最近二囘に亙つて、取り立てが行はれようとしたが、二囘とも急に嵐が起つて失敗に終つた。これは船が近づくと、上陸させないやうに土地の妖精たちの力に依つて起つたと云はれてゐる。
流石に今朝は、六月の澄んだ空の下に夜は明けた。外へ出て來た時には、海鳥も素晴しく光り輝いてゐた。晴着を着た人たちの羣は、怒つたり怖れたりしつつしやべりながら立つてゐるが、海の靜けさを破るであらう目ざましい見物を思つて、何處かに祕かな嬉しさを現してゐる。
九時半頃、灣の中央に見える狹い水平線の上に、汽船が見えて來た。すると、大部分負債になつてゐる家家の牛や羊を隱さうとする最後の努力が試みられた。
今年まで、此の島で誰も執達吏を務めるのを承知しなかつたから、滯納者の牛を確める事は出來かつた。然るに、近頃、パトリックと云ふ男が自分の名譽を賣つてしまつたので、隱さうとしても事實上無駄なことになつた。
此の島の古い節義の失はれて行く事は非常な憤りを起させ、昨日朝早く、私が
「極惡人、パトリック、ピストルを覺悟してをれ。たとへ、一發が外れても、續いて五發が汝を打つべし。また汝と口をきく者、共に働く者、汝の店で黑ビールの少量を飮む者は、何人と雖も同刑に處せらるべし。」
汽船が近づいて來ると、私は此の到着を見物しようとする人人と共に、下りて行つた。併し誰も岸から約一哩より先の方へは、行かうとしなかつた。
戸別調査を援助すべき一人の男と醫者と貧民救助吏の乘つてゐるキルロナンから來た二艘のカラハは、大部隊を賴まなければ上陸を欲せず、汐に漂つてゐた。錨が投げられ、ボートが下ろされ、それにドヤドヤと乘り込む警察官の綫條銃やヘルメット帽が陽に閃くのを見ると、私に不思議な心痛の動悸を感ぜしめた。
上陸すると、男たちは密集せる行進隊形に列べられ、命令が發せられた。彼等の長靴の重さうなリズムは岩を越えてやつて來る。揉み合ひながら、道路の兩側に二列に竝んでゐると、少し經つて堂堂と武裝した一隊が間近を通り過ぎる。その後に賤民たちが隨いて行く。此の人たちは郡執行官のため、追手の役を務めるために送られたのである。
原始的な人たちの中で數週間暮した後、かういつた人間の新しい型を見ることは賴もしいものではなかつた。併し此の機械的な警官たちは、平凡な役人や郡執行官やその傭つた賤民たちと共に、よく文明を代表してゐた。その文明のために此の島の家庭の神聖は穢されるのではあるが。
止れの號令が村の最初の家でかけられて、此の日の仕事が初まつた。併し此處でもまた次の家でも、最後の瞬間に親類の人が來て處刑猶豫に必要な金を貸したので、妥協が成立した。
次の場合には女の子が病氣で、醫者が仲にたち、家人はただ形式的の取り立ての後、家にゐる事を許された。然るに、正午頃來た或る家では、如何なる情けもかけられず、また金も處辨されなかつた。郡執行官の合圖で、寢臺や家具を持出す作業が、大勢の土地の人が全く物一つ云はずに見てゐる中で初まつた。沈默はただ家の内儀さんの亂暴な呪ひの言葉で破られるのみであつた。
彼女は島で最も舊い家の人であつた。彼女は、その云ふことはわからないが、三十年間住み慣れた爐邊から追ひ立てようとする此の奇妙な武裝した人たちを見ながら、耐へられぬ怒りに震へてゐた。此の人たちにとつて爐邊を荒されることは此の上もない悲慘事であつた。彼等は一年中、每週のやうにすさまじい雨と霧のやつて來る此の無趣味な世界に住み、子供たちや女たちの一ぱい集る此の暖い爐邊は、文明國では想像も出來ないほどに各の家族の人の心に深くしみ込んでゐた。
支那に於いて墓を荒されることは、支那人にとつては大いなる苦痛であらうが、それにも劣らずイニシマーンに於いても、爐邊を荒されることは住民にとつて大いなる苦痛であらう。
いくつかつまらない物が外に出され、戸口が石で鎖されてしまふと、老婆は敷居に腰掛けて、肩掛で顏を包んでしまつた。
近くに住んでゐた他の五六人の女は、同情して何も云はずに、彼女の周りを固く取り卷いた。それから群集は警官たちと共に他の家に移り、其處でも同じやうな場面が展開され、後には小屋の傍に腰掛けてゐる見捨てられた女たちの群を殘した。
空にはいまだに雲もなく、暑さが激しい。警官たちは活動してゐない時は、肌着のボタンを外し、塀際で汗を流しつつ又喘ぎつつ休んでゐた。彼等は感じのよいものではない。私は始終その人たちと、鷗のやうに涼しい顏をして、あちこち步き廻つてゐる島の人たちとを見較べてゐた。
最初の取り立てが濟むと、隊が二つに別れた。一半は朝の間に匿された年を探しに、奧の方へ執達吏と共に行き、他の半分は既に取つてある豚を見守るために村の往來に殘つた。
それから少し經つて、これ等の豚の二匹が追手から逃れて、狹い道を登つたり下つたり激しい競走を初めた。人人は喚き叫ぶので、豚は益々怖がるばかりであつた。或る者が餘り熱狂したので、遂に警官は干涉するのは此の時と考へた。彼等はそれを追ひ込まうと行詰まりの道の口に向つて二重の列を敷いた。暫く經つと再び西の方で喚聲が擧がり、二匹の豚が道の眞ん中を追手を尻目に一目散に走つて來るのが見え出した。
警戒線に達した。一寸もみ合つたが、三人の警官を砂塵の中に殘して、尚も東の方へ向つて遮二無二の突貫を續けた。
人人の喜びは大した物であつた。喜んで大聲を擧げたり、抱き合つたり、此の動物を島代代の語り草に特筆せんとするもののやうであつた。
二時間の後、他の隊は瘦せた二匹の牝牛を追ひながら戾つ來た。そして船卸臺の方へ向つて出かけ初めた。酒場で警官に酒が出され、その閒、後から隨いて來た一杯の群集は道傍で待つてゐた。偶然直ぐ苧の野に島の牡牛がゐたが、牝牛の姿を見、また妙な服裝をした人たちを見ると、非常に興奮した。すると直ぐに二人の島の若者が石垣の下に休んでゐる私の傍ににじり寄つて來て、その中の一人が、
「奴等の中へ牡牛を放つたら罰金を取られるだらうか」と私の耳下で囁いた。
女たちや子供の面前であつたので、私は「取られるだらう」とだけ答へた。すると二人遠げるやうに行つてしまつた。
船卸臺で多くの談判が行はれてゐたが、皆結局、牛は飼主に戾される事になつた。牛は一文にもならないから、持つて行つても明かに無駄であつた。
警官たちがすつかり船に乘つてしまふと、群集の中から一人の婆さんが進み出て、船卸臺近くの岩に上りその執達吏を指し、非常な怒りに瘦腕を振り上げながら口から出るままに、毒舌を吐き初めた。
「あれは私の息子だ。」彼女は云つた。「私があれのことは一番よく知つてゐる。世界中で一番の惡者だ。」
それから形容のできないほどに復讐心に顏色を變へてその男のことを語り出した。彼女は語り進むにつれて興奮が強くなつて行くので、その男は家へ戾らないうちに石を投げられるだらうと思つた程であつた。
此の島では女はただ子供たちのためにばかり生きてゐるのであるが、此の老婆をして斷然と立つて息子を呪はしめたその感情の激しさは殆んど量り知る事が出來ない。
彼女の怒りを含んだ言葉の中に、私は、此の島の人たちの妙に控へ目な氣質のくせに、ただ何かのはずみで、その熱し易い精神が起り立つと、素晴らしい言葉となり身振りとなつて現れる事がわかつたやうである。
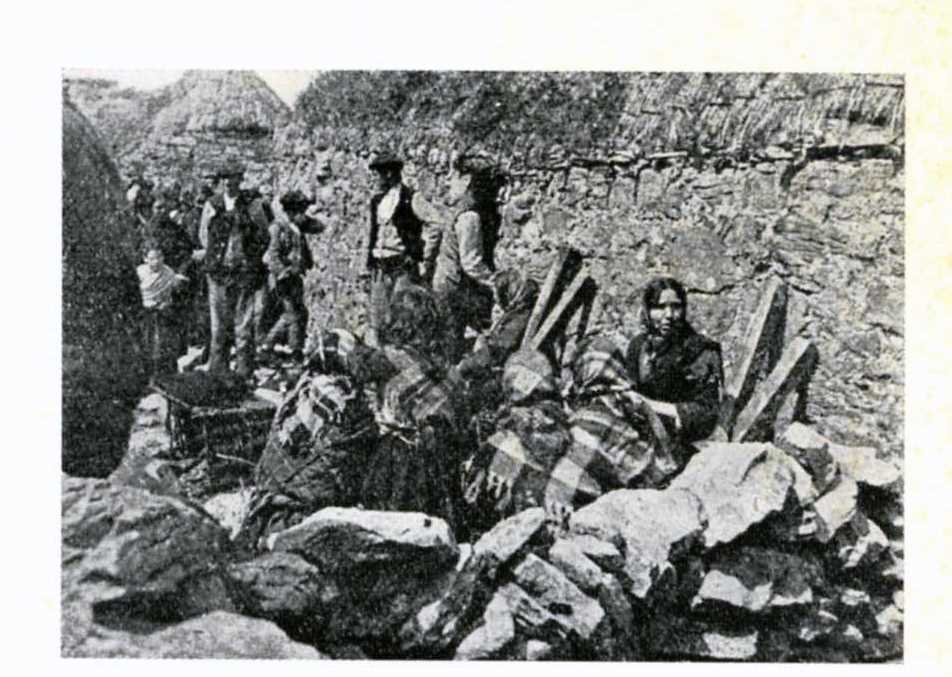

*
Two recent attempts to carry out evictions on the island came to nothing, for each time a sudden storm rose, by, it is said, the power of a native witch, when the steamer was approaching, and made it impossible to land.
This morning, however, broke beneath a clear sky of June, and when I came into the open air the sea and rocks were shining with wonderful brilliancy. Groups of men, dressed in their holiday clothes, were standing about, talking with anger and fear, yet showing a lurking satisfaction at the thought of the dramatic pageant that was to break the silence of the seas.
About half-past nine the steamer came in sight, on the narrow line of sea-horizon that is seen in the centre of the bay, and immediately a last effort was made to hide the cows and sheep of the families that were most in debt.
Till this year no one on the island would consent to act as bailiff, so that it was impossible to identify the cattle of the defaulters. Now however, a man of the name of Patrick has sold his honour, and the effort of concealment is practically futile.
This falling away from the ancient loyalty of the island has caused intense indignation, and early yesterday morning, while I was dreaming on the Dun, this letter was nailed on the doorpost of the chapel:--
'Patrick, the devil, a revolver is waiting for you. If you are missed with the first shot, there will be five more that will hit you.
'Any man that will talk with you, or work with you, or drink a pint of porter in your shop, will be done with the same way as yourself.'
As the steamer drew near I moved down with the men to watch the arrival, though no one went further than about a mile from the shore.
Two curaghs from Kilronan with a man who was to give help in identifying the cottages, the doctor, and the relieving officer, were drifting with the tide, unwilling to come to land without the support of the larger party. When the anchor had been thrown it gave me a strange throb of pain to see the boats being lowered, and the sunshine gleaming on the rifles and helmets of the constabulary who crowded into them.
Once on shore the men were formed in close marching order, a word was given, and the heavy rhythm of their boots came up over the rocks. We were collected in two straggling bands on either side of the roadway, and a few moments later the body of magnificent armed men passed close to us, followed by a low rabble, who had been brought to act as drivers for the sheriff.
After my weeks spent among primitive men this glimpse of the newer types of humanity was not reassuring. Yet these mechanical police, with the commonplace agents and sheriffs, and the rabble they had hired, represented aptly enough the civilisation for which the homes of the island were to be desecrated.
A stop was made at one of the first cottages in the village, and the day's work began. Here, however, and at the next cottage, a compromise was made, as some relatives came up at the last moment and lent the money that was needed to gain a respite.
In another case a girl was ill in the house, so the doctor interposed, and the people were allowed to remain after a merely formal eviction. About midday, however, a house was reached where there was no pretext for mercy, and no money could be procured. At a sign from the sheriff the work of carrying out the beds and utensils was begun in the middle of a crowd of natives who looked on in absolute silence, broken only by the wild imprecations of the woman of the house. She belonged to one of the most primitive families on the island, and she shook with uncontrollable fury as she saw the strange armed men who spoke a language she could not understand driving her from the hearth she had brooded on for thirty years. For these people the outrage to the hearth is the supreme catastrophe. They live here in a world of grey, where there are wild rains and mists every week in the year, and their warm chimney corners, filled with children and young girls, grow into the consciousness of each family in a way it is not easy to understand in more civilised places.
The outrage to a tomb in China probably gives no greater shock to the Chinese than the outrage to a hearth in Inishmaan gives to the people.
When the few trifles had been carried out, and the door blocked with stones, the old woman sat down by the threshold and covered her head with her shawl.
Five or six other women who lived close by sat down in a circle round her, with mute sympathy. Then the crowd moved on with the police to another cottage where the same scene was to take place, and left the group of desolate women sitting by the hovel.
There were still no clouds in the sky and the heat was intense. The police when not in motion lay sweating and gasping under the walls with their tunics unbuttoned. They were not attractive, and I kept comparing them with the islandmen, who walked up and down as cool and fresh-looking as the sea-gulls.
When the last eviction had been carried out a division was made: half the party went off with the bailiff to search the inner plain of the island for the cattle that had been hidden in the morning, the other half remained on the village road to guard some pigs that had already been taken possession of.
After a while two of these pigs escaped from the drivers and began a wild race up and down the narrow road. The people shrieked and howled to increase their terror, and at last some of them became so excited that the police thought it time to interfere. They drew up in double line opposite the mouth of a blind laneway where the animals had been shut up. A moment later the shrieking began again in the west and the two pigs came in sight, rushing down the middle of the road with the drivers behind them.
They reached the line of the police. There was a slight scuffle, and then the pigs continued their mad rush to the east, leaving three policemen lying in the dust.
The satisfaction of the people was immense. They shrieked and hugged each other with delight, and it is likely that they will hand down these animals for generations in the tradition of the island.
Two hours later the other party returned, driving three lean cows before them, and a start was made for the slip. At the public-house the policemen were given a drink while the dense crowd that was following waited in the lane. The island bull happened to be in a field close by, and he became wildly excited at the sight of the cows and of the strangely-dressed men. Two young islanders sidled up to me in a moment or two as I was resting on a wall, and one of them whispered in my ear--'Do you think they could take fines of us if we let out the bull on them?'
In face of the crowd of women and children, I could only say it was probable, and they slunk off.
At the slip there was a good deal of bargaining, which ended in all the cattle being given back to their owners. It was plainly of no use to take them away, as they were worth nothing.
When the last policeman had embarked, an old woman came forward from the crowd and, mounting on a rock near the slip, began a fierce rhapsody in Gaelic, pointing at the bailiff and waving her withered arms with extraordinary rage.
'This man is my own son,' she said; 'it is I that ought to know him. He is the first ruffian in the whole big world.'
Then she gave an account of his life, coloured with a vindictive fury I cannot reproduce. As she went on the excitement became so intense I thought the man would be stoned before he could get back to his cottage.
On these islands the women live only for their children, and it is hard to estimate the power of the impulse that made this old woman stand out and curse her son.
In the fury of her speech I seem to look again into the strangely reticent temperament of the islanders, and to feel the passionate spirit that expresses itself, at odd moments only, with magnificent words and gestures.
[やぶちゃん注:「取り立てが行はれようとした」“to carry out evictions”の“eviction”とは以下の描写によって、行政による地代の支払いを行わない島民への違約罰金を含む徴収(そこには後掲されるような既に抵当物件となっている豚や牛などの家畜類の現物をも含む)としての「取り立て」や、それを支払えない場合の居住地からの「追い立て」を意味し、所謂、現在の日本の警察部隊を伴った行政代執行に相当するものである。
「執達吏」“bailiff”。執行官補佐人。恐らくは地主から形式上の島全体の土地管理監督者として命ぜられた現地の者で、このような行政代執行の際には準公務員格で令状の送達や差し押さえ・追い立ての執行、それに伴う地主側の裁判関係業務等を補佐する者である。この単語、古フランス語が元で、“bail”(監禁)+“-ive”(~する人)と語源も厭らしい。
「極惡人」現文は“devil”。張り紙されているのが教会であるから、ここは「悪魔」と訳したいところ。更に言えば、この男の名は“Patrick”で、これはキリスト教徒でなくても我々日本人でさえ名前ぐらいは知っている、「アイルランドの使徒」と呼ばれたアイルランドでのキリスト教布教に功あった司教にして聖人“Saint Patrick”聖パトリック(“Patricius” パトリキウス 387年?~461年)に基づくから、強烈な皮肉としても機能していると考えてよいであろう。
「ピストル」“a revolver”。リボルバー。知られた回転式拳銃のことで、シリンダーへの装弾数で五発と六発のものに大別される。ここは勿論、後者。
「黑ビール」“porter”。ポーター。ポーター・ビール。焦がした麦芽を使った、“stout”(スタウト)よりも弱い黒ビールのこと。原義は荷役人夫(ポーター)らが愛飲したことに由来する。
「綫條銃」“the rifles”。「せんじょうじゅう」と読む。小銃(銃剣を装着して白兵戦が可能な銃)。ライフル。この名称は銃身内に螺旋状の浅い溝である“rifling”(ライフリング)を有する銃という意である。この旋条銃身から撃ち出されると、弾丸はこのライフリングに浅く食い込みながら発射され、それによって得られる回転運動によるジャイロ効果で弾軸が安定し、ライフリングのない滑腔銃身よりも遥かに高い直進性と低伸性(弾道の直線性と着弾時間の短かさ)が与えられ、命中精度が高まる。ライフリングは日本語では「施条」「綫条」「腔線」「腔綫」等と言う。「綫」は筋の意。
「郡執行官」“the sheriff”。主に英国で「州長官」の意で用いられた。“county (or shire)”(州)の執政長官。
「處辨されなかつた」の「処弁」は、方針を取り決めて適切に取り計らう、処理することをいう。原文は“no money could be procured”であるから、前掲の事例のようには金を工面出来なかったという意味である。
「無趣味な世界」原文“a world of grey”。そのままの「灰色の世界」の方が分かりがよい。また、この前後は日本語としては「無趣味な世界に住み、~」ではなく、「灰色の世界に在っては、~」の方がよい。
『女たちや子供の面前であつたので、私は「取られるだらう」とだけ答へた』のは、無論、シングはその悪戯を面白いと思ったものの、女子供がいるので、その際の牛の暴走による万一の怪我などを考えて、という含みである。
「すると二人は逃げるやうに行つてしまつた」原文は“and they slunk off”。私なら「すると二人は、つまらないと言った感じで、こそこそっと出て行ってしまった」と訳したい。
「船卸臺で多くの談判が行はれてゐたが、皆結局、牛は飼主に戾される事になつた。牛は一文にもならないから、持つて行つても明かに無駄であつた」とあるが、原文を見ると“all the cattle”とあり、ここで返還されたのは牛だけではなく、収用された豚も含む家畜類である。後半部分(原文は“It was plainly of no use to take them away, as they were worth nothing.”)で「一文にもならない」とするのは、それらの家畜類が恐らくは瘦せているか、品質も低級で、更に本土にわざわざ船移送し、市場へ運ぶその手間賃を考えると殆ど割に合わないからであろう。もしかすると執達吏のこの収用と返戻は島民への脅しや恩着せがましさを含んだ、嫌がらせのポーズででもあったのかも知れない。
「一番の惡者」“the first ruffian”。「大悪党」「極め付けのならず者」「最下劣漢」といった意。“ruffian”は古語で、元はドイツ語かオランダ語らしい。
「彼女は語り進むにつれて興奮が強くなつて行くので、その男は家へ戾らないうちに石を投げられるだらうと思つた程であつた。」原文は“As she went on the excitement became so intense I thought the man would be stoned before he could get back to his cottage.”。栩木氏はここを『石になってしまうのじゃないかと』訳しておられる。妖精が跳梁するアラン島ならではのファンタジックな訳ではあるが、先輩の英語教師にも読んで戴いたがやはり「石を投げられるであろう」と訳すとされた。前後の文脈から見ても、ここは素直に「石を投げられるだらう」が穏当であるように思われるが、如何?]
パット爺さんは、彼が不死鳥と呼んでゐる、金の卵を生んだ鵞鳥の話をした。
或る貧しい後家さんが三人の息子と一人の娘を持つてゐた。或る日、息子たちは森に薪木を拾ひに行つて、美しい縞のある鳥が木の間を飛んでゐるのを見た。その次の日もまた見た。一番上の兄は自分が鳥を追ふから、お前たちだけで薪木を採りに行けと弟たちに告げた。
彼は鳥の後を追つて行き、晩に家に歸つて來た時、それを手に持つてゐた。皆んなはそれを古い
その晩、それは籠の中で一つの美しい斑點のある卵を生んだ。次の晩もまた生んだ。
當時、そのことが新聞に出て、生んだ卵が金色をしてゐたので、金の卵を生んだ鳥と書かれて評判だつた。それは嘘ぢやない。
翌日、子供たちが
それから後、子供たちの一人はその鳥の卵を田舍にゐた或る紳士へ賣つた。紳士は鳥はまだ持つてゐるかと尋ねるので、姉を妻に貰つてくれた人にやつた所だと答へた。
「さうか」と紳士は云つた。「その鳥の心臟を食ふと、每朝自分の下から金の財布が見つかり、肝臟を食ふと、愛蘭土の王になるだらう。」
子供は出かけた。――彼は可哀さに人のよい子供であつた。そして店の夫に話した。
店の主人は鳥を持つて來て、それを殺し、自分は、心臟を食べ、肝臟は妻に與へた。
子供はそれを見ると、大いに怒つて、紳士にその事を云ひつけた。
「私の云ふ通りにしなさい。」紳士は云つた。「今夜、私は淋しいから、トランプをしに來ないかと、店の主人とその妻に云ひに行きなさい。」
子供が出て行くと、彼は嘔吐劑を調合してウィスキーの幾ナギンかの中へうんと交ぜ、カードを置くテーブルに丈夫な布をかけた。
店の主人は妻とやつて來て、トランプを初めた。
店の主人は最初の勝負に勝ち、紳士からウィスキーの一啜を飲せられた。
再びやつたが二囘日も主人が勝つた。それで紳士は彼にまたウィスキーを飮ませた。
三囘目をやつてゐる時、主人夫妻は布の上に吐いた。そこで子供は、紳士に敎へられてゐた通り、それを拾ひ上げて、庭に持ち出したら果して鳥の心臟があつたので、それを食べた。翌朝、寢床の中で寢返りすると、身體の下から金の財布が出て來た。
それでおしまひ。
*
Old Pat has told me a story of the goose that lays the golden eggs, which he calls the Phoenix:--
A poor widow had three sons and a daughter. One day when her sons were out looking for sticks in the wood they saw a fine speckled bird flying in the trees. The next day they saw it again, and the eldest son told his brothers to go and get sticks by themselves, for he was going after the bird.
He went after it, and brought it in with him when he came home in the evening. They put it in an old hencoop, and they gave it some of the meal they had for themselves;--I don't know if it ate the meal, but they divided what they had themselves; they could do no more.
That night it laid a fine spotted egg in the basket. The next night it laid another.
At that time its name was on the papers and many heard of the bird that laid the golden eggs, for the eggs were of gold, and there's no lie in it.
When the boys went down to the shop the next day to buy a stone of meal, the shopman asked if he could buy the bird of them. Well, it was arranged in this way. The shopman would marry the boys' sister--a poor simple girl without a stitch of good clothes--and get the bird with her.
Some time after that one of the boys sold an egg of the bird to a gentleman that was in the country. The gentleman asked him if he had the bird still. He said that the man who had married his sister was after getting it.
'Well,' said the gentleman, 'the man who eats the heart of that bird will find a purse of gold beneath him every morning, and the man who eats its liver will be king of Ireland.'
The boy went out--he was a simple poor fellow--and told the shopman.
Then the shopman brought in the bird and killed it, and he ate the heart himself and he gave the liver to his wife.
When the boy saw that, there was great anger on him, and he went back and told the gentleman.
'Do what I'm telling you,' said the gentleman. 'Go down now and tell the shopman and his wife to come up here to play a game of cards with me, for it's lonesome I am this evening.'
When the boy was gone he mixed a vomit and poured the lot of it into a few naggins of whiskey, and he put a strong cloth on the table under the cards.
The man came up with his wife and they began to play.
The shopman won the first game and the gentleman made them drink a sup of the whiskey.
They played again and the shopman won the second game. Then the gentleman made him drink a sup more of the whiskey.
As they were playing the third game the shopman and his wife got sick on the cloth, and the boy picked it up and carried it into the yard, for the gentleman had let him know what he was to do. Then he found the heart of the bird and he ate it, and the next morning when he turned in his bed there was a purse of gold under him.
That is my story.
[やぶちゃん注:「美しい縞」原文は“a fine speckled bird”。鮮やかで美しい色の小さな
「鷄籠」は原文“an old hencoop”で、これはわざわざ古いと言っている以上、日本の農家にあったような伏せ籠をイメージすべきであろう。
「碾割粉」原文“the meal”。ミール自体は広義に食事、狭義にはトウモロコシ・麦・豆等の穀類を挽き割って粗い粉にした食用加工品を言うが、ここは欧米で一般的な、カヤツリグサ目イネ科カラスムギ属エンバク(燕麦) Avena sativa を脱穀して粗く製粉した “oatmeal”(オートミール)と考えてよいであろう。
「翌日、子供たちが碾割の石を買ひに行くと、」これは明らかな誤訳である。原文は“When the boys went down to the shop the next day to buy a stone of meal,”で、“a stone of meal”はオートミール1ストーン(1ストーン=14ポンド≒6.35キログラム)のこと。「翌日、兄弟たちが売店にオートミールを1ストーン買いに行くと、」である。オートミールの量が多いようにも見えるが、肉体労働者の三兄弟の若者に一人娘と未亡人に(食ったかどうか分からないとは言うものの)金の卵を産むカモのフェニックスの主食の食い分としては、そして金の卵を手に入れた彼らとしては、決しておかしくはあるまい。
「それはかういふ魂膽であつた。」原文は“Well, it was arranged in this way.”で、「で、まあ、その魂胆は簡潔に纏めるなら次のような次第で。」の意か。栩木氏は『で、話をはしょれば、こんなふうに話がまとまったわけです。』と訳しておられる。ここはこの後の原文が願望形になっているために姉崎氏・栩木氏の両訳とも苦心しておられる。要は次の段落では時間が経って、この通りに店屋の主が、策略通り、この娘とフェニックスをまんまと手に入れていることを聴く者に、わざと「知らせない」(推測させる余地と同時に吃驚させようとする効果を持った)ような時制構造となっているように思われる。
「その鳥の心臟を食ふと、每朝自分の下から金の財布が見つかり、」原文は“the man who eats the heart of that bird will find a purse of gold beneath him every morning,”。“beneath him”だから、「毎朝、彼が起きるたびに彼の体の下に」ということである。一見生硬に見えるが私はそうは採らない。姉崎氏の訳は逆に『「下に」ってどういうこと?』という、本話の最後のシーンの映像をわざと隠すように逐語訳されているのであって、そもそも、この後半の途方もない“the man who eats its liver will be king of Ireland”に至っては、『どうやって?』という民話の常套的なワクワク感が醸成されているのであってみれば(それは語られないのであるが)、私は楽しい面白い訳であると思うのである。
「嘔吐劑」“a vomit”。
「ウィスキーの幾ナギンか」原文は“a few naggins of whiskey”。この“naggins”は“noggin”の訛か。発音は正に【nάgɪn】で、原義は小さなコップのことで、そこから少量の酒、一般には“1/4pint”で142ml。これは小さめのワイン・グラスに普通に注いだ量である。
「主人夫妻は布の上に吐いた」とあるが、妻は訳文でも原文でも薬を混入したウィスキーを飲んではいない。しかし吐いているからであろう、栩木氏は一回目の勝利のところで『紳士は夫婦にウィスキーを一杯勧めました。』と訳しておられる。しかし、すると妻はどうして肝臓を吐かなかったのか、という素朴な疑問が生じる。吐いたのか? ではアイルランドの王になれるそれは誰のものになったのか? 無粋と言えば無粋なのかも知れぬ。しかし私は気になってしょうがないのである。]
汽船の來る筈の日には、私は船卸臺へ行くことを滅多に缺かしたことはない。汽船が沖に見えると、人人はいつも集まつて來るからである。そして汽船が南島に立ち寄つて、こちらへ向つて來るまで、彼等はカラハの置いてある中で話をしながら休んでゐる。
今朝、或る老人と長く話をしたが、その人は此の土地が、此の十年間乃至十五年間に改造の行はれた事を喜んでゐた。
極く最近まで本土とは漁船に依る他は何等の交通もなかつた。その漁船も普通はのろく、可成り長い天氣の日に通ふのみであつた。それで島の人が市場に行くと、歸るまでには三週間かかる事があつた。併し今では汽船が一週に二囘來て、而かも三四時閒で行けるやうになつた。
此の島の波止場もまた新しい物の一つで、自慢物である。今でも泥炭や牛を運んで來る漁船が荷を下ろしたり、岸から直接に荷を積んだりする事が出來るからである。併しその附近の海は潮が一杯に充ちた時だけ漁船がやつとはひられる位の撫深さであるから、汽船はどうしても來られない。それゆ來客は今でもカラハに乘つて上陸しなければならない。南島に最も近く、角にある船卸臺は靜かな日には非常に役立つが、南からの大波を避ける物がなく、且つ狹いゆゑに、カラハが立ち騷ぐ波の中に船卸臺を見失ふ危險がある。
惡い天氣の日には、四人の男がカラハを手に持つたまま、南の方に向つて、はひつて來る波の強さのわかる岩の印しを見つめながら、船卸臺の上の方で殆んど一時間も立つてゐる事がある。
波の破れが見えた瞬間、彼等は急に寄波の中に飛び下りて、カラハを下し、目にも止まらない速さで海へ漕ぎ出して行く。陸の方へ來るにも同じやうな危險が伴ふ。一寸でも時期が惡かつたら、橫樣に波に洗はれて、岩の中に乘り入れるであらう。
身體の非常な敏捷さに依つてのみ避けられる此の絶え間なき危險は、地方的特色の上に大き影響を及ぼす。それは、不器用な向う見ずなまた臆病な男をば、波が此の島で生活する事を不可能にせしめるからである。
汽船が船卸臺から一哩以内に近づくと、カラハが出され、カラハは通常四艘から十二艘であるが――そして岸から或る距離の處に二列に出ぶ。
汽船がその間にはひつて來ると、船側によい位置を取らうと、短時閒ではあるが、必死の競爭が初まる。男たちは櫂に凭れながらだるさうな聲で話をしてゐる。それが波の搖れと共に聞こえて來る。汽船が橫付けになると、瞬間に彼等の顏は血氣にゆがみ、櫂は張り切つて曲り震へる。暫くは自分の安全も、友達や兄弟の安全も全然構はないやうである。やがて順位が決定され、彼等はいつものだるさうな調子で再び話を初め、カラハを繫いで汽船に攀ぢ上つて行く。
カラハが出てゐる間、私は數人の女たちと漕ぐ事の出來ない非常に年取つた人たちと共に殘されてゐる。その中の一人の爺さんとはよく話すことがあるが、
*
When the steamer is expected I rarely fail to visit the boat-slip, as the men usually collect when she is in the offing, and lie arguing among their curaghs till she has made her visit to the south island, and is seen coming towards us.
This morning I had a long talk with an old man who was rejoicing over the improvement he had seen here during the last ten or fifteen years.
Till recently there was no communication with the mainland except by hookers, which were usually slow, and could only make the voyage in tolerably fine weather, so that if an islander went to a fair it was often three weeks before he could return. Now, however, the steamer comes here twice in the week, and the voyage is made in three or four hours.
The pier on this island is also a novelty, and is much thought of, as it enables the hookers that still carry turf and cattle to discharge and take their cargoes directly from the shore. The water round it, however, is only deep enough for a hooker when the tide is nearly full, and will never float the steamer, so passengers must still come to land in curaghs. The boat-slip at the corner next the south island is extremely useful in calm weather, but it is exposed to a heavy roll from the south, and is so narrow that the curaghs run some danger of missing it in the tumult of the surf.
In bad weather four men will often stand for nearly an hour at the top of the slip with a curagh in their hands, watching a point of rock towards the south where they can see the strength of the waves that are coming in.
The instant a break is seen they swoop down to the surf, launch their curagh, and pull out to sea with incredible speed. Coming to land Is attended with the same difficulty, and, if their moment is badly chosen, they are likely to be washed sideways and swamped among the rocks.
This continual danger, which can only be escaped by extraordinary personal dexterity, has had considerable influence on the local character, as the waves have made it impossible for clumsy, foolhardy, or timid men to live on these islands.
When the steamer is within a mile of the slip, the curaghs are put out and range themselves--there are usually from four to a dozen--in two lines at some distance from the shore.
The moment she comes in among them there is a short but desperate struggle for good places at her side. The men are lolling on their oars talking with the dreamy tone which comes with the rocking of the waves. The steamer lies to, and in an instant their faces become distorted with passion, while the oars bend and quiver with the strain. For one minute they seem utterly indifferent to their own safety and that of their friends and brothers. Then the sequence is decided, and they begin to talk again with the dreamy tone that is habitual to them, while they make fast and clamber up into the steamer.
While the curaghs are out I am left with a few women and very old men who cannot row. One of these old men, whom I often talk with, has some fame as a bone-setter, and is said to have done remarkable cures, both here and on the mainland. Stories are told of how he has been taken off by the quality in their carriages through the hills of Connemara, to treat their sons and daughters, and come home with his pockets full of money.
[やぶちゃん注:ここは底本では次の段落と繋がっているが、原文では行空けが行われているので、ここで切った。
「それは、不器用な向う見ずなまた臆病な男をば、波が此の島で生活する事を不可能にせしめるからである。」私はこの訳が好きだ。アランの人々の生死を支配している主体は、正に、この“the waves”「波」だからである。]
もう一人の爺さんは、島で第一の年寄であつたが、彼の生涯中で此の島に起つた實話――傳説ではなく――を好んで話した。
彼は私によくコンノートの男のことを話した。その男は一時の怒りで鋤で父を打ち殺したのであるが、此の島に逃げて來て、親戚と云はれた島の或る人の情に縋つた。その男は一つの穴に匿まはれ――爺さんが私に見せたことがある――巡査が探しに來て、頭の上で長靴の石を踏み付ける音を聞いたが、數週間無事に忍んだ。報酬が出されたが、島の人は買收されず、その男は多くの苦心の後、アメリカへ向けて無事に船に乘せられた。
此のやうに罪人を保護する氣風は西部では一般的である。これは一面に於いては正義と恨むべき英國司法權とを併せ考へることにも困るが、もつと直接的には、決して犯罪はしないが犯罪の可能性は常に持つてゐる此の島の人たちの原始的な感情に因るものである。卽ち人間は海の荒れのやうにどうしやうもなくなる一時の血氣に驅られない限りは惡い事はしないと云ふ感情に因るのである。たとへ父を殺しても、既に後悔して身も心も弱り果ててゐる者を引張つて行き、法律に依つて殺すべき理由はないと考へるのである。
彼等の説では、かういつた人は殘りの生涯を靜かにさせておくべきであると云ふ。若し見せしめの必要があると云ふ人があれば、彼等は「誰がすき好んで父を殺すものか?」と問ふであらう。
警察がはひつて來ない數年前までは、此の群島の住民全部は今日まで此處に殘留してゐる人たちのやうに罪を知らなかつた。その當時、北島を支配する地主でありまた長官であつた人が、惡事をした者にはゴルウェーの獄吏に宛てて手紙を持たせ、懲役に服させるために一人で送り出す習慣があつたさうである。
汽船がなかつたので、犯罪者は便のあり次第の漁船に乘つて、本土に最も近い處へ渡る許可が與へられた。それから何哩も荒れ果てた岸に沿うて步いて行き、遂に町に着く。年期が終へると、彼は弱弱しく瘦せ衰へて、もと來た道を辿つて來る。そして時には何週間も待たなければ再び島を踏む事は出來ない。これが話の大體である。
そんな法律を、此處の住民や都會の犯罪人階級に適用するのは無理のやうに思はれる。イニシマーンの最も心ある人は法律を輕蔑してゐる事と、またアランモアに警察が出來て犯罪が多くなつた事を屢々私に語つた。その島では人が一寸した不和や毆り合ひをすれば、友達が餘りひどくならないやうに注意する。そして暫くすると忘られてしまふとの事である。キルロナンでは自分自身の手で事件を解決するために、金で傭はれてゐる一團の人たちがある。毆打事件が初まれば直ぐその人たちがやつて來て、毆打した人を檢束する。喧嘩を賣られた方の人は相手に反對な證據を出す。全家族の者が法廷に來て、互ひに反對の誓言をして、仇同士になつてしまふ。宣告が下れば宣告された人は決して服しない。彼はその時を待つて、その年の終らないうちに、反對の召喚が來る。すると今度は、相手の方が決して服さない。爭ひは段段と大きくなつていつて、一年間、強制し合つた後で、遂に髮の毛の色がどうのかうのといつたやうな論爭が殺人沙汰にまでなる。島では信賴すべき證據が得られないと云ふだけの事實で――これは島の人が不正直だといふわけではなく、血族の主張の方が抽象的な眞實より神聖だと考へてゐるために――誓約した證言の全組織も一つの人騷がせの狂言となつてしまふ。そして此の間違つた基礎の上に於ける法律的處置は、あらゆる不正を生ずるに至るべき事は容易に信ぜられる。
私がそんな問題を老人たちと論じてゐるうちに、カラハは鹽、麥粉、黑ビールの積荷を載せて戾つて來だした。
今日はニュー・ヨークに五年居た土地の人が歸つて來たと云ふので大騷ぎである。その男は本土へ買物に行つた五六人の人たちと一緖に上陸した。生れ故鄕では珍らしい小ざつばりした服をつけて、船卸臺をあちこち步いてゐた。すると、彼の八十五歳の年取つた母親は、喜びで半ば狂氣のやうになつて、その知らせを皆に告げながら、ぬるぬるした海草の上を走り廻つてゐた。
カラハが片向けられると、人人は歡迎の挨拶を云ひに、その周りに集つた。彼は萬遍なく握手をしてゐたが、見知り顏を認めた微笑はなかつた。
彼は死にかけてゐるさうである。
*
Another old man, the oldest on the island, is fond of telling me anecdotes--not folktales--of things that have happened here in his lifetime.
He often tells me about a Connaught man who killed his father with the blow of a spade when he was in passion, and then fled to this island and threw himself on the mercy of some of the natives with whom he was said to be related. They hid him in a hole--which the old man has shown me--and kept him safe for weeks, though the police came and searched for him, and he could hear their boots grinding on the stones over his head. In spite of a reward which was offered, the island was incorruptible, and after much trouble the man was safely shipped to America.
This impulse to protect the criminal is universal in the west. It seems partly due to the association between justice and the hated English jurisdiction, but more directly to the primitive feeling of these people, who are never criminals yet always capable of crime, that a man will not do wrong unless he is under the influence of a passion which is as irresponsible as a storm on the sea. If a man has killed his father, and is already sick and broken with remorse, they can see no reason why he should be dragged away and killed by the law.
Such a man, they say, will be quiet all the rest of his life, and if you suggest that punishment is needed as an example, they ask, 'Would any one kill his father if he was able to help it?'
Some time ago, before the introduction of police, all the people of the islands were as innocent as the people here remain to this day. I have heard that at that time the ruling proprietor and magistrate of the north island used to give any man who had done wrong a letter to a jailer in Galway, and send him off by himself to serve a term of imprisonment.
As there was no steamer, the ill-doer was given a passage in some chance hooker to the nearest point on the mainland. Then he walked for many miles along a desolate shore till he reached the town. When his time had been put through he crawled back along the same route, feeble and emaciated, and had often to wait many weeks before he could regain the island. Such at least is the story.
It seems absurd to apply the same laws to these people and to the criminal classes of a city. The most intelligent man on Inishmaan has often spoken to me of his contempt of the law, and of the increase of crime the police have brought to Aranmor. On this island, he says, if men have a little difference, or a little fight, their friends take care it does not go too far, and in a little time it is forgotten. In Kilronan there is a band of men paid to make out cases for themselves; the moment a blow is struck they come down and arrest the man who gave it. The other man he quarreled with has to give evidence against him; whole families come down to the court and swear against each other till they become bitter enemies. If there is a conviction the man who is convicted never forgives. He waits his time, and before the year is out there is a cross summons, which the other man in turn never forgives. The feud continues to grow, till a dispute about the colour of a man's hair may end in a murder, after a year's forcing by the law. The mere fact that it is impossible to get reliable evidence in the island--not because the people are dishonest, but because they think the claim of kinship more sacred than the claims of abstract truth--turns the whole system of sworn evidence into a demoralising farce, and it is easy to believe that law dealings on this false basis must lead to every sort of injustice.
While I am discussing these questions with the old men the curaghs begin to come in with cargoes of salt, and flour, and porter.
To-day a stir was made by the return of a native who had spent five years in New York. He came on shore with half a dozen people who had been shopping on the mainland, and walked up and down on the slip in his neat suit, looking strangely foreign to his birthplace, while his old mother of eighty-five ran about on the slippery seaweed, half crazy with delight, telling every one the news.
When the curaghs were in their places the men crowded round him to bid him welcome. He shook hands with them readily enough, but with no smile of recognition.
He is said to be dying.
[やぶちゃん注:ここは底本も原文も次の段落と繋がっているが、最後の一節から、私の心情としてはここで切りたい。栩木氏の訳もここに行空けを行っておられる。
「コンノートの男のこと」以下の話柄がヒントとなって、後にシングの名作にして問題作となる“The Playboy of the Western World”「西部の人気者」(1907年)が生み出された
「北島を支配する地主でありまた長官であつた人」原文“the ruling proprietor and magistrate of the north island”。“ruling proprietor”は「土地統治所有権者」で「地主」と訳したくなるが、先に示したようにアラン島は18世紀中頃からキルデア県のディグビー一族が島の地主となったものの、殆ど島には居住していなかったから、ここは土地所有権者から命ぜられた実質的統治と土地管理人を兼ねた職分を謂うものと思われる。“magistrate”はイギリスで比較的軽い犯罪を扱う裁判官である治安判事。従ってこことは「北島を支配するアラン諸島全体の実質統括権を賦与された土地管理人兼治安判事であった人」という意味である。
「獄吏」“jailer”は看守。ここは、ちっぽけな島の、裁判でもなんでもこなした村長から、刑務所の(所長ではない)一介の牢番宛の一通の判決文を、刑の確定した被告人渡して、お前ひとりで刑務所に行って服役してこいと命じ、被告人はそれに従順に従って苦難の末に刑務所に入り、刑期満了後は同じように苦難を乗り越えて共同体の島アランへと帰還し、再び受け入れられるという古典的運命共同体の素晴らしさが眼目なのである。
「そんな法律を、此處の住民や都會の犯罪人階級に適用するのは無理のやうに思はれる。」これは誤訳と言わざるを得ない。原文は“It seems absurd to apply the same laws to these people and to the criminal classes of a city.”で、ここは「(今、述べたような、これら(アラン島)の人々と、都会の犯罪人階層とに、同じ法律を適用するということは不条理に思われる。」と言っているのである。
「誓約した證言の全組織も一つの人騷がせの狂言となつてしまふ。」原文“turns the whole system of sworn evidence into a demoralising farce”。この「全組織」は注意深く読まないと意味が分からない。ここのポイントは“sworn evidence”「誓約した證言」、則ち、虚偽でない旨の宣誓による証言によって、揺るぎない真理性が支えられているところの“the whole system”「全組織」、全てのシステム、則ち厳粛たるべき裁判の公判が、“demoralising farce”となる、則ち、壊滅的な混乱と麻痺の様相を呈するに至る、という意味である。日本語としては、せめて「誓約した證言によって厳粛たるべき全公判も、あっという間にただの人騷がせな狂言となってしまう。」ぐらいの嚙み砕きが欲しいところである。]
昨日――日曜――三人の若者が私を群島中の南の島なる、イニシールまで私を乘せて行つてくれた。
カラハの船尾の席は塞がつてゐたので、私は船尾に置かれて、頭を船緣と水平にした。瀨戸には非常な潮流が流れてゐたので、島陰から出ると、名狀し難い搖れたり跳び上つたりした。
或る瞬間、我我は谷底に下つて行くと、綠色の波が頭上に渦卷き、
男たちは興奮して落付かないやうであつた。一時は沈沒するのではないかと思つたが、少し經つてカラハは波の中で頭を上げ得る性質のあることがわかつた。進行は不思議にも輕快になつた。たとへ波の靑い割目に沈んで行くとしても、此の死は口に心地よい鹽水をくくむのであるから、普通の死に方よりは愉快であらうと私は考へた。
隣島に着いた時、雨がひどく降つてゐたので古跡も住民も見る事は出來なかつた。
午後の大半を、我我は酒場の空樽の上に腰掛けて、ゲール語の運命に就いて語つた。我我は旅人として中に入れられた。後には店の鎧戸は鎖されて、僅かに衣色の光が漏れ、嵐の音が聞こえるのみであつた。夕方近くなつて空は少し晴れ、靜かになつた海を歸途についた。併し眞正面の迎ひ風なので漕手は全力を盡した。
*
Yesterday--a Sunday--three young men rowed me over to Inisheer, the south island of the group.
The stern of the curagh was occupied, so I was put in the bow with my head on a level with the gunnel. A considerable sea was running in the sound, and when we came out from the shelter of this island, the curagh rolled and vaulted in a way not easy to describe.
At one moment, as we went down into the furrow, green waves curled and arched themselves above me; then in an instant I was flung up into the air and could look down on the heads of the rowers, as if we were sitting on a ladder, or out across a forest of white crests to the black cliff of Inishmaan.
The men seemed excited and uneasy, and I thought for a moment that we were likely to be swamped. In a little while, however I realised the capacity of the curagh to raise its head among the waves, and the motion became strangely exhilarating. Even, I thought, if we were dropped into the blue chasm of the waves, this death, with the fresh sea saltness in one's teeth, would be better than most deaths one is likely to meet.
When we reached the other island, it was raining heavily, so that we could not see anything of the antiquities or people.
For the greater part of the afternoon we sat on the tops of empty barrels in the public-house, talking of the destiny of Gaelic. We were admitted as travellers, and the shutters of the shop were closed behind us, letting in only a glimmer of grey light, and the tumult of the storm. Towards evening it cleared a little and we came home in a calmer sea, but with a dead head-wind that gave the rowers all they could do to make the passage.
[やぶちゃん注:「カラハの船尾の席は塞がつてゐたので、私は船尾に置かれて、頭を船緣と水平にした。」お分かりと思うが二番目の「船尾」は「船首」の誤訳(誤植か)。原文は“The stern of the curagh was occupied, so I was put in the bow with my head on a level with the gunnel.”。“stern”が「船尾」、“bow”が「船首」、“gunnel”は“gunwale”とも書き、海事用語でガンネル・舷縁・船べりのこと。
「たとへ波の靑い割目に沈んで行くとしても、此の死は口に心地よい鹽水をくくむのであるから、普通の死に方よりは愉快であらうと私は考へた。」この「くくむ」は「ふくむ」の誤植ではない。「銜む・含む」と書いて、「くくむ」と訓じ、口の中に含むの意である。四段活用の古語であるが、五段化して明治以降も用いられた。いい響きである。――いや、私はこのシングの謂いに――限りないこの不思議なグラン・ブルーの美しさに――心うたれるのだ――“Even, I thought, if we were dropped into the blue chasm of the waves, this death, with the fresh sea saltness in one's teeth, would be better than most deaths one is likely to meet.”(“chasm”は【kǽzm】と発音し、「深い裂け目」の意)――いい台詞だ――]
靜かな日には、マイケルと一緒に、時時釣に出かける。岩の上にカラハが腹を上にして支へられてゐる船卸臺の上の墓地まで行くと、マイケルは乘らうと思ふ一艘の舳先を持ち上げる。私はその下へはひり一番前の席の眞ん中を首の上に載せる。すると彼は船尾に這ひ込んで、最後の席を肩に擔いで立ち上り、我我は海の方へ步き出す。長い舳先が私の目の前に下つてゐるので、足下の小石のある數ヤードの外は何も見えない。震ひつくやうな痛みが、背骨の頂上から私の革草履鞋の中へ入つて踝にギシギシこすりつけられてゐる尖んがつた小石まで傳はつて行く。我我は重荷の下でよろめき唸る。併し遂に足が船卸臺にとどくと跣足の子供のやうな足取で、半ば小走りで驅け下りて行く。
海から一ヤードの所で止まり、カラハを右へ下ろす。靜かに下ろさなければならない。――緊張して痛む筋肉にはこたへる動作である。――船緣が船卸臺につく時、私は平衡を失つて座席の中に轉がり込む事がよくある。
昨日乘つたのは、キルロナンへ行つた時に破損したカラハであつた。それで櫂を中へ入れてゐると、新らしくタールを塗つて繕つた處が日光で熱した船卸臺に附着した。我我は
繕ひの場所が間違つてゐた。今度は麻布がない。マイケルは私のポケット鋏を借りて、驚くほど手際よくフランネルを自分のシャツの裾から四角に切り取り、櫂から切つた木片にしつかり結びつけて、その穴へ押し入れた。
こんな騷ぎの間に我我は岩の緣まで汐に流されてゐた。すると彼は櫂を水に入れて、波に乘るやうに向きを變へた。さもなければ我我は波に擲げられて沈んでしまつたであらう。彼の此の巧妙さを私は再び賞讚した。
カラハが傷ついたので、岸から餘り遠くへは行かなかつた。少し經つて、私は長い間代り合つて櫂を漕いだ。扱ひ難い物であるが、少しは巧くなつた。兩方の櫂の柄は端が六インチほど重なり合ふ。――カラハが狹いので、挺の作用を増すために。――それで初めは上の方の櫂を自分の指節にあてる事は殆んど避けられない。櫂は端を除いては、ザラザラして角があるから、無難ではどうしても漕げない。それに、二人の輕い人を乘せたカラハは水に浮いてゐる胡桃の穀のやうで、一漕ぎのうちで少し均衡が破れても、船首は進む方向から少くとも直角だけはそれる。最初の半時間は、私は度度出かけた方向へ進んでゐたので、マイケルは非常に喜んだ。
今朝も我我は島の北側にある波止場近くに出かけた。鱈を釣りながら、汐に從つて靜かに櫂を浸して行くと、重さうにケルプ灰を船緣まで積んでキルロナンへ行く幾艘かのカラハとすれちがつた。
一人のお婆さんが赤いペティコートにくるまつて、海に突き出た岩の緣に立つてゐた。其處はカラハが南からよく通る處で、婆さんはキルロナンへ渡してくれと震へるゲール語で大聲で叫んでゐた。積荷を持たずに來た最初の船が、少し離れた處から寄つて來て、彼女を連れて行つた。
今朝は、雨催ひの日によく島を襲ふ不思議な美しさは少しもなかつた。それで我我は海上の殺風景さと不思議な對照をなしてゐる海底の植物の自然の絢爛たる樣を見下ろしながら、ぼんやりと日光浴を樂しんだ。
*
On calm days I often go out fishing with Michael. When we reach the space above the slip where the curaghs are propped, bottom upwards, on the limestone, he lifts the prow of the one we are going to embark in, and I slip underneath and set the centre of the foremost seat upon my neck. Then he crawls under the stern and stands up with the last seat upon his shoulders. We start for the sea. The long prow bends before me so that I see nothing but a few yards of shingle at my feet. A quivering pain runs from the top of my spine to the sharp stones that seem to pass through my pampooties, and grate upon my ankles. We stagger and groan beneath the weight; but at last our feet reach the slip, and we run down with a half-trot like the pace of bare-footed children.
A yard from the sea we stop and lower the curagh to the right. It must be brought down gently--a difficult task for our strained and aching muscles--and sometimes as the gunnel reaches the slip I lose my balance and roll in among the seats.
Yesterday we went out in the curagh that had been damaged on the day of my visit to Kilronan, and as we were putting in the oars the freshly-tarred patch stuck to the slip which was heated with the sunshine. We carried up water in the bailer--the 'supeen,' a shallow wooden vessel like a soup-plate--and with infinite pains we got free and rode away. In a few minutes, however, I found the water spouting up at my feet.
The patch had been misplaced, and this time we had no sacking. Michael borrowed my pocket scissors, and with admirable rapidity cut a square of flannel from the tail of his shirt and squeezed it into the hole, making it fast with a splint which he hacked from one of the oars.
During our excitement the tide had carried us to the brink of the rocks, and I admired again the dexterity with which he got his oars into the water and turned us out as we were mounting on a wave that would have hurled us to destruction.
With the injury to our curagh we did not go far from the shore. After a while I took a long spell at the oars, and gained a certain dexterity, though they are not easy to manage. The handles overlap by about six inches--in order to gain leverage, as the curagh is narrow--and at first it was almost impossible to avoid striking the upper oar against one's knuckles. The oars are rough and square, except at the ends, so one cannot do so with impunity. Again, a curagh with two light people in it floats on the water like a nut-shell, and the slightest inequality in the stroke throws the prow round at least a right angle from its course. In the first half-hour I found myself more than once moving towards the point I had come from, greatly to Michael's satisfaction.
This morning we were out again near the pier on the north side of the island. As we paddled slowly with the tide, trolling for pollock, several curaghs, weighed to the gunnel with kelp, passed us on their way to Kilronan.
An old woman, rolled in red petticoats, was sitting on a ledge of rock that runs into the sea at the point where the curaghs were passing from the south, hailing them in quavering Gaelic, and asking for a passage to Kilronan.
The first one that came round without a cargo turned in from some distance and took her away.
The morning had none of the supernatural beauty that comes over the island so often in rainy weather, so we basked in the vague enjoyment of the sunshine, looking down at the wild luxuriance of the vegetation beneath the sea, which contrasts strangely with the nakedness above it.
[やぶちゃん注:ここは原文は次の段落と繋がっているが、次の夢との有意な切れ目であるから切る。
「淦」船板の隙間から染み出て船底に溜まった水のこと。漁夫の忌み詞で、仏前に備える「
「六インチ」約25㎝強。
「鱈」原文は“pollock”。タラ科コダラ Melanogrammus aeglefinus の近縁種であるようだが和名はない。条鰭綱タラ目タラ科 Pollachius 属の魚で、英語版Wiki“pollock”には Pollachius pollachius と Pollachius virens の二種を載せる。形状はコダラに似るが、そっくりである。成魚の体長は1m程になり、コダラが白い体に黒い側線が走るのに対して逆に黒い体に白い側線を持つと日本版ウィキの「コダラ」にある。但し、英語版には他種を“pollock”と呼称する記載があり、例えば“Alaska pollock”タラ科スケトウダラ Theragra chalcogramma をもこう呼ぶとある。]
私が此の宿で見たいくつかの夢は、一定の環境に附隨した心靈上の記憶があると云ふ學説に寄與する所があるやうに思へる。
昨夜、夢の中で、私は、妙に強い光のあたつてゐる建物の間を步いた後で、何かの弦樂器から來るらしい幽かな靑紫のリズムが遠くから起つて來るのを聞いた。
それは紛ふかたなく正確な進行を以つて速度を増し、音量を増して段段と近づいて來た。それが直ぐ側に來た時、その昔は私の神經の中や血管の中で動き出し、その調子につれて私を踊らせようとしだした。
私は若しこれに負けたら、直ぐにも恐ろしい苦悶の瞬間に陷るだらうと思つたので、一生懸命に膝を手で抑へてぢつとこらへてゐた。
音樂は、竪琴の絃のやうな音を出して、或る忘れられた音階に調子を合せ、ツェロの絃のやうに徹る響を出しながら、絶えず大きくなつて行つた。
魅惑する力は私の意志ではどうする事も出來ないほど、段段に強くなつて行き、手足は我知らず動き出した。
忽ち、渦卷く音の中に私は卷き込まれてしまつた。私の呼吸、思考、身體のあらゆる衝動が皆躍りの形となつて、遂に樂器と音律と自分の身鮭或は意識との聞の宙別がわからなくなつた。
暫くは喜びに溢れる感激のやうであつた。それから、法悅の狀態になり、あらゆる物が連動の渦の中に失はれてしまつた。私は踊り狂ふ外に人生があるとは思へなくなつた。
するとはつと思ふ間に、法悅は苦悶となり怒りとなつた。自由になりたいと悶えたが、步き出さうとする情熱を増すばかりであつた。聲を立ててみるが、リズムの調子を眞似て云へるばかりであつた。
逐にどうにも仕方なく悶えた瞬間に氣がついて、目が醒めた。
震へながら家の窓まで足を引きずつて行き、外を眺めた。月が灣の彼方に輝いてゐて、島の上には何の物音もなかつた。
*
Some dreams I have had in this cottage seem to give strength to the opinion that there is a psychic memory attached to certain neighbourhoods.
Last night, after walking in a dream among buildings with strangely intense light on them, I heard a faint rhythm of music beginning far away on some stringed instrument.
It came closer to me, gradually increasing in quickness and volume with an irresistibly definite progression. When it was quite near the sound began to move in my nerves and blood, and to urge me to dance with them.
I knew that if I yielded I would be carried away to some moment of terrible agony, so I struggled to remain quiet, holding my knees together with my hands.
The music increased continually, sounding like the strings of harps, tuned to a forgotten scale, and having a resonance as searching as the strings of the cello.
Then the luring excitement became more powerful than my will, and my limbs moved in spite of me.
In a moment I was swept away in a whirlwind of notes. My breath and my thoughts and every impulse of my body, became a form of the dance, till I could not distinguish between the instruments and the rhythm and my own person or consciousness.
For a while it seemed an excitement that was filled with joy, then it grew into an ecstasy where all existence was lost in a vortex of movement. I could not think there had ever been a life beyond the whirling of the dance.
Then with a shock the ecstasy turned to an agony and rage. I Struggled to free myself, but seemed only to increase the passion of the steps I moved to. When I shrieked I could only echo the notes of the rhythm.
At last with a moment of uncontrollable frenzy I broke back to consciousness and awoke.
I dragged myself trembling to the window of the cottage and looked out. The moon was glittering across the bay, and there was no sound anywhere on the island.
[やぶちゃん注:アイリッシュ・ステップ・ダンスの音楽夢。――羨ましいドゥエンデの舞踏――]
私は、二日したら出發しようとしてゐる。パット・ディレイン爺さんは、私に別れを告げた。今朝、彼は村で私と逢ひ、彼が夜を過すみすぼらしい小屋である、「彼の小さなティント(テント)」に私を連れて行つた。
私は長い間、入口に腰掛けて居り、彼は、その間、私の後の寢床近くの腰掛に凭れてゐた。そして彼から聞く最後であらう話――書く價値もない露骨な實話――をしてくれた。それから若い時、漂浪して、立派な學校に住んで若い坊さんに愛蘭土語を敎へた事を特に力をこめて話した。
彼は四人分も噓をつけると云ふ島の噂である。恐らく覺えた物語で彼の想像力が強くなつたのだらう。
彼に別れを告げて、戸口の處に立つと、彼は寢床を形造つてゐる藁にもたれて、涙を流した。それから又こちらの方を振り向き、震へる片方の手を擧げた。その手には、撞木杖のこすれから掌に穴があくほど破れてゐる手袋をはめてゐた。
「もうあんたには逢へないだらう。」彼は顏に涙を流して云つた。「あんたは親切な人だつた。來年、戾つて來ても、私はもう此の世には居ないだらう。私は此の冬は越せないだらう。だが、今私の云ふことを聞きなさい。それはあんたがダブリンの町で私に保險をかけるのです。さうするとあんたは私の葬式の時、五百ポンド手に入るだらう。」
此の島の最後の晩なる今夜はまたパターン祭〔愛蘭土に於ける守護の聖人を祭る日で、色色の餘興が催される〕――ブリタニー地方のパードン〔佛國ブルターニュに行はれる教會及び民間の祭で、一般の無禮講が許される〕に似た祭――の宵祭である。
私は特にそれを見ようと待つてゐたが、來る筈であつた
いつか笛吹が來た時は、ダンスやお祭り騷ぎで賑やかであるに違ひない。併し、ゴルウェーの笛吹も年を取つて、容易にやつて來るといふわけに行かない。
昨夜はセント・ヂョーンの祭〔洗禮者ヨハネの誕生を祝ふ祭日、六月二十四日、その前夜は大篝火を焚き男女がその周りを躍る〕の宵祭で、篝火が焚かれ、子供たちは火のついた一片の泥炭を手に持つて步き廻つた。併し大篝火から家の火をつける考へは、今でも島に存在してゐるかどうか見ることは出來なかつた。
*
I am leaving in two days, and old Pat Dirane has bidden me goodbye. He met me in the village this morning and took me into 'his little tint,' a miserable hovel where he spends the night.
I sat for a long time on his threshold, while he leaned on a stool behind me, near his bed, and told me the last story I shall have from him--a rude anecdote not worth recording. Then he told me with careful emphasis how he had wandered when he was a young man, and lived in a fine college, teaching Irish to the young priests!
They say on the island that he can tell as many lies as four men: perhaps the stories he has learned have strengthened his imagination. When I stood up in the doorway to give him God's blessing, he leaned over on the straw that forms his bed, and shed tears. Then he turned to me again, lifting up one trembling hand, with the mitten worn to a hole on the palm, from the rubbing of his crutch.
'I'll not see you again,' he said, with tears trickling on his face, 'and you're a kindly man. When you come back next year I won't be in it. I won't live beyond the winter. But listen now to what I'm telling you; let you put insurance on me in the city of Dublin, and it's five hundred pounds you'll get on my burial.'
This evening, my last in the island, is also the evening of the 'Pattern'--a festival something like 'Pardons' of Brittany.
I waited especially to see it, but a piper who was expected did not come, and there was no amusement. A few friends and relations came over from the other island and stood about the public-house in their best clothes, but without music dancing was impossible.
I believe on some occasions when the piper is present there is a fine day of dancing and excitement, but the Galway piper is getting old, and is not easily induced to undertake the voyage.
Last night, St. John's Eve, the fires were lighted and boys ran about with pieces of the burning turf, though I could not find out if the idea of lighting the house fires from the bonfires is still found on the island.
[やぶちゃん注:「撞木杖」“crutch”。本邦ではT字型が鉦叩きの撞木の似ていることから、かく言う。
「パターン祭」原文は“'Pattern'”であるが、この綴りではゲール語でも検索出来なかった。この綴りは、アイルランドの守護聖人として有名な聖パトリック“Patrick”と似ている(但し、ゲール語では“Pádraig”)が、聖パトリックの祭日は3月17日で、シングの第一回目のアラン島訪問期間(1898年5月10日から6月25日。栩木氏の「アラン島」の「訳者あとがき」による)とは合わない。この6月25日に最も近いアイルランドの聖人の祭日は、アイルランド三守護聖人にしてアイルランドノ十二使徒の一人である“St Columba”聖コルンバの祭日で、6月9日である。但し、彼の名もゲール語では“St Colm Cille”(コルム・キル)で“Pattern”とは一致しないし、日附に有意なタイム・ラグがあるから違う。識者の御教授を乞うものである。
「昨夜はセント・ヂョーンの祭〔洗禮者ヨハネの誕生を祝ふ祭日、六月二十四日、その前夜は大篝火を焚き男女がその周りを躍る〕の宵祭」はラテン語名“Ioannes Baptista”(英語名“John the Baptist”)で、言わずもがな「サロメ」で知られた、「新約聖書」に登場するヨルダン川でイエスに洗礼を授けたユダヤの大預言者である。現在もヨハネの誕生日とされる6月24日はカトリックなどで彼の聖名祝日となっている。但し、ヨハネのゲール語も“Eoin Baiste”で“Pattern”には全然似ていない。……按ずるに、彼が離島したのが6月25日なら、この謂いでは「昨夜」は、シングの島での最後の夜の24日、文字通り聖ヨハネの祭日の前の晩、23日の夜ということになる。連続で24日のSt. John's dayと25日の“'Pattern'”があるということになるが、そもそもが類似した異なった起源の祭祀であってもそれが同時期にリンクして習合して、毎日がイヴと祭日の連続となっても別段おかしくはないのである(私がかつて住んでいた富山では季節の節目になると毎日どこかで祭りがあった。驚くべきことに、中学生の頃の秋祭りなどでは祭りに参加するために、学校が公欠扱いとしていた同級生さえいた。古き良き時代の名残りであった)。……しかし、にしても“Pattern”が謎であることには変わりがない……私は……やはり“Patrick”との類似が気になるのである。もしかするとアラン島では複数の聖人たちの祭日を、彼らが最も尊崇する守護聖人のチャンピオン聖パトリックに代表させて、かく呼んでいたのではなかろうか? 識者の御教授を乞うものである。
「ブリタニー地方のパードンに似た祭」“'Pardons' of Brittany”。ウィキの「パルドン祭り」によれば、フランスのブルターニュ地方に典型的な巡礼行事の一つで、『庶民のカトリック信仰に根付く伝統的な行事である』が、その起源は『ケルト人のキリスト教化がキリスト教聖職者によって行われた時代に遡ると』され、アイルランドの『セント・パトリック・デーのパレードと比較される』とあるから、これは同起源の祭りである。フランス語の“pardon”は「許し」であり、告解による神の容赦を意味する。『信者たちは聖人の墓や聖人に献げられた場所に向けて巡礼する。その場所は、ケリアン(フィニステール県のコミューン)のように、奇跡の出現と関係している場合もあるし、聖遺物と関係している場合もある。告解者の旅行は教区ごとの集団、信徒団体、その他の団体で、旗印、十字架、その他巡礼を表すものを掲げ、どの団体も華麗さ・高潔さのため他者と競い合う』。『巡礼行進のように、指定された場所で落ち合うまで巡礼は解散せず、信仰のなせるわざとして旅する努力を提供することで、名高い聖人から取りなしを得ようとする願望を象徴しているのである。これは、地上の人間たちは天上の王国か新たな約束された地へ向かって旅を続ける状況にある、とみなす、キリスト教徒の考えを反映している。この説に従うと、巡礼者たちはミサに出席する前に聖職者に対して罪を告白するよう勧められている。そしてその後に厳粛な夕べの祈りがしばしば続く。彼らは免罪を授かり、集団はキリスト教徒の救済を喜ぶためにコミュニティの祝宴に加わる。これは村祭りか移動遊園地にすら似ている体系をとる』とある。
「篝火が焚かれ、子供たちは火のついた一片の泥炭を手に持つて步き廻つた。併し大篝火から家の火をつける考へは、今でも島に存在してゐるかどうか見ることは出來なかつた。」は、聖ヨハネの祝祭とは違う、バルト神話の太陽神サウレ(リトアニア語“Saulė”・ラトビア語“Saule”)等に基づくものではなかろうか。例えばウィキの「サウレ」によれば『サウレの祭である夏至祭を起源に持つリトアニアのRasos(キリスト教によって聖ヨハネ祭とされた)およびラトビアのLīgo(同じく聖ヨハネ祭)は、花輪を作り、不思議なシダの花(en)を探し、篝火を燃やしてその周りで踊り、火を飛び越え、そうして翌朝の午前4時頃の日の出を迎えるということを要件とする祭り』であり、『それは最も喜びに満ちた伝統的な休日である』とあり、本記載と酷似する。夏至は6月22日頃に当たり、聖ヨハネの祝日の前日に当たる6月23日に近く、信仰行事として習合し易かったものとも思われる。考えるに、これは古形の太陽再生儀礼が元ではなかろうか。篝火はそのシンボルであり、記されなかったパット爺さんの昔話の中などで恐らく、アラン島の古伝承ではそれを各家庭の竈の火種として移し、一年の太陽の恵みと豊穣を祈願して保守したのではなかったか。]
私はゴルウェー灣のふちに沿うて散步しようと、旅客や旅商人で混み合つてゐる旅館を出て來た。そして島島の方を眺めやる。あの淋しい岩の島へ對して感ずる一種の憧憬は云ふに云はれず強い。野生的な人間の面白さは常に到る處にある此の町も、今の私の氣持には、現代生活の最もあからさまなあらゆる物のけばけばしい交ぜ合はせに見える。金持の無禮も貧民の不潔も、共に不思議な嫌さで私の胸を痛ましめる。併し島島は、既に影が薄れて行きつつある。其處に今でも漂つてゐる海草の香も、大西洋の波の轟も、私には殆んど實感する事は出來なくなつてしまつた。
島の友達の一人からこんな手紙が來た。
親愛なるヂョン・シング――私は長い間、あなたからの手紙を待つてゐます。あなたは全く此の島を忘れたのでせう。
――君は餘程前に大島で死にました。彼のボートは港に繫がれてゐましたが、その死後、風がそれをブラック岬へ吹き流し微塵に碎いてしまひました。
そちらでも、愛蘭土語をやつておいででせうね。我我は此の頃、此處にゲーリック聯盟の支部を造つて、愛蘭土語と讀書を一心にやつてゐます。
次の手紙は愛蘭土語で書きませう。貴方は來年はこちらへお出ででせうね。若しお出でならば、その前に手紙を下さい。貴方の愛する友達は皆達者でゐます。――末長く、貴方の友より。
私が少し魚の餌を送つてやつたもう一人の少年からも、初めは愛蘭土語で、終りは英語で、手紙が來た。――
親愛なるヂョン、――四日前、貴方のお手紙を受け攻りました。愛蘭土語でお書きになつてあつたので、私は肩身が廣く、嬉しく思ひました。立派な氣持のよいお手紙でした。送つて下さつた餌は大へん結構でした。併しその中の二つをなくし、また釣糸の半分をなくしました。大きな魚が來て餌にかかりましたが、釣糸が惡く、釣糸の半分と餌を持つて行かれました。姉がアメリカから歸つてゐます。併し彼女は此の頃、島を淋しくみすぼらしく感じ出したので、間もなく又歸つて行くでせう。――御機嫌よく……
早く御返事を、そして愛蘭土語で下さい。さうでないと、私は讀む氣がしません。
*
I have come out of an hotel full of tourists and commercial travelers, to stroll along the edge of Galway bay, and look out in the direction of the islands. The sort of yearning I feel towards those lonely rocks is indescribably acute. This town, that is usually so full of wild human interest, seems in my present mood a tawdry medley of all that is crudest in modern life. The nullity of the rich and the squalor of the poor give me the same pang of wondering disgust; yet the islands are fading already and I can hardly realise that the smell of the seaweed and the drone of the Atlantic are still moving round them.
One of my island friends has written to me:--
DEAR JOHN SYNGE,--I am for a long time expecting a letter from you and I think you are forgetting this island altogether.
Mr. - died a long time ago on the big island and his boat was on anchor in the harbour and the wind blew her to Black Head and broke her up after his death.
Tell me are you learning Irish since you went. We have a branch of the Gaelic League here now and the people is going on well with the Irish and reading.
I will write the next letter in Irish to you. Tell me will you come to see us next year and if you will you'll write a letter before you. All your loving friends is well in health.--Mise do chara go huan.
Another boy I sent some baits to has written to me also, beginning his letter in Irish and ending it in English:--DEAR JOHN,--I got your letter four days ago, and there was pride and joy on me because it was written in Irish, and a fine, good, pleasant letter it was. The baits you sent are very good, but I lost two of them and half my line. A big fish came and caught the bait, and the line was bad and half of the line and the baits went away. My sister has come back from America, but I'm thinking it won't be long till she goes away again, for it is lonesome and poor she finds the island now.--I am your friend ...
Write soon and let you write in Irish, if you don't I won't look on it.
[やぶちゃん注:以上が第一部の最後となる。
「――君は餘程前に大島で死にました。彼のボートは港に繫がれてゐましたが、その死後、風がそれをブラック岬へ吹き流し微塵に碎いてしまひました。」原文を見てみよう。“Mr. - died a long time ago on the big island and his boat was on anchor in the harbour and the wind blew her to Black Head and broke her up after his death.”「――君」のダッシュは個人名を伏せた意識的欠字。「大島」“big island”はイニシュモア(アランモア)島。栩木氏は「
「ゲーリック聯盟」“the Gaelic League”。現在は「ゲール語連盟」と訳される。ゲール語では“Conradh na Gaeilge”。以下、ウィキの「ゲール語連盟」より。『8世紀末から19世紀にかけてアイルランド語とゲール文化の復興を掲げてアイルランドで活動した団体。1893年7月31日にロスコモン州出身のプロテスタントであるダグラス・ハイドらによってダブリンで設立された』もので、『ゲール語復興運動の中心となり、イースター蜂起などのアイルランド独立運動にも大きな影響を与えた』とある。
「貴方の愛する友達は皆達者でゐます。――末長く、貴方の友より。」原文“All your loving friends is well in health.--Mise do chara go huan.”。ネットで調べると最後のゲール語は、“Mise”が「小生」、“do”は「あなた」、“chara”は「親愛なる」、“go”は「~よ」という感嘆詞か、「その」という指示語か、「~へ」という前置詞か? “huan”も分からない。一部の英語圏のページには英語の“hound”とあり、それだと「熱中者」「~狂」に相当するが、アイルランド語と日本語の自動翻訳機にかけると、“huan”は「ラム」(小羊)と出る(但し、全文をかけると「私の友達子羊へ」となり、これは少々疑問である)。するとこれは神の子羊(イエス)の謂いで、「神の子羊イエス様の御名にかけて――永遠に変わらぬ愛を――あなたへ――友より」という謂いであろうか? 識者の御教授を乞う。栩木氏は『わたしはあなたの変わらぬ友達』と訳され、更にここにゲール語の発音で『ミシャ・ド・ハラ・ゴ・ブアン』(底本では「ミシヤ」であるが拗音化した)とルビを振られておられる。――姉崎先生、ここにはゲール語のルビが、やっぱり、欲しかったです。
「もう一人の少年」“Another boy”という表現から、第一の手紙の主も当時のシング(27歳)より、恐らくは遥かに、年少の青年であったことが分かる。
「魚の餌」原文“baits”。これは後の少年の手紙から、“artificial bait”(擬似餌)であることが分かる。この少年の手紙は事実を一生懸命綴った素直なものである。そして、きっとシングは――少年への返事と一緒に――新しいルアーいくたりかと、そして丈夫なテグスを送ったに違いない。――]
The Aran Islands
by J. M. Synge
Part I
End
アラン島
ジョン・ミリングトン・シング著
姉崎正見訳
第一部
終
Críoch
第二部