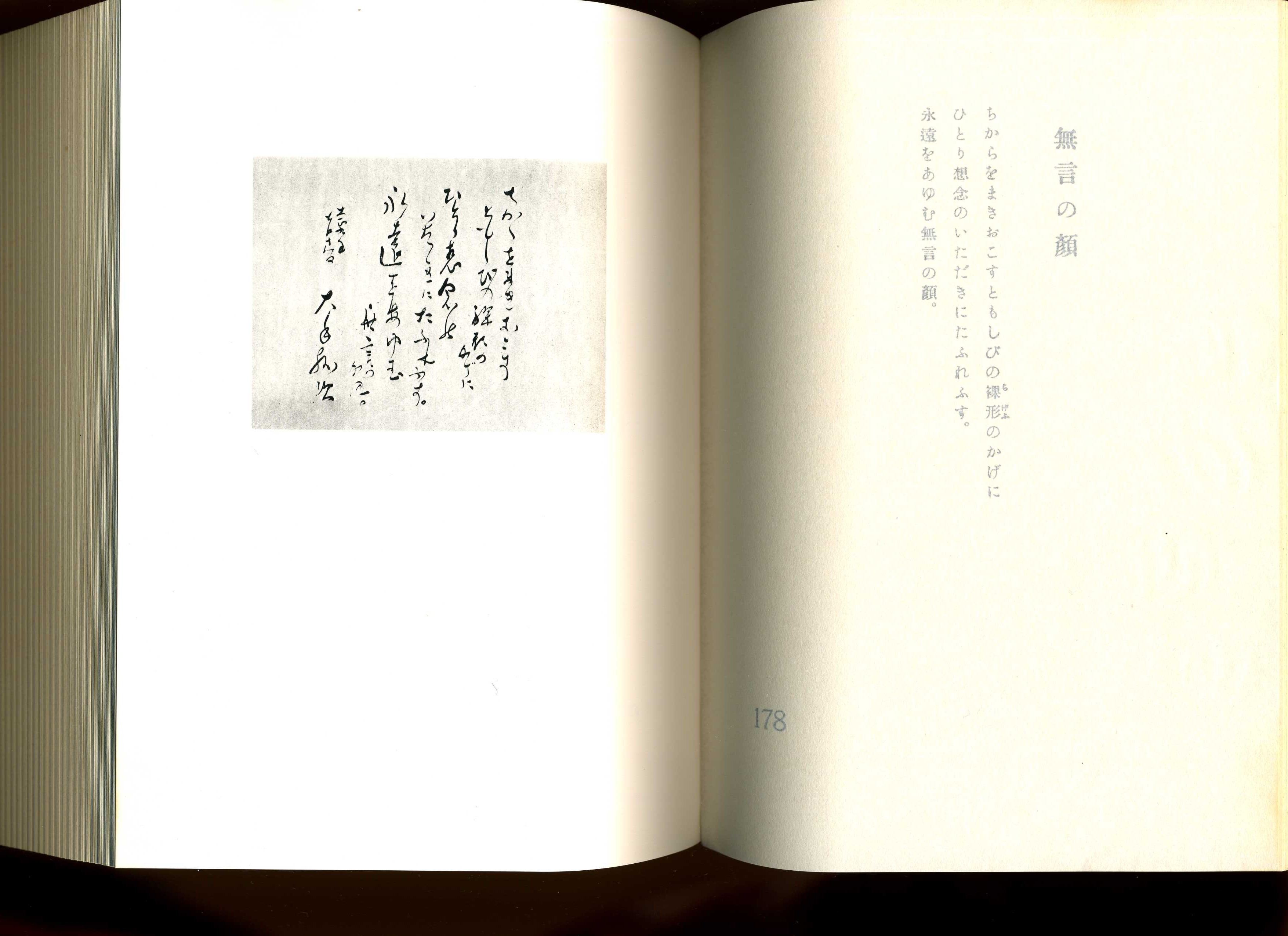心朽窩 新館へ
鬼火へ
藍色の蟇 大手拓次 (やぶちゃん注附初版再現版)
☞縦書版へ
[やぶちゃん注:本詩集は大手拓次の死(昭和九(一九三四)年四月十八日)の後二年八ヶ月後処女詩集にして追悼詩集の如きものとしてアルスより昭和一一(一九三六)年十二月に刊行された。菊判変型、丸背情勢革装、天金、包み函附。所収詩篇二百五十五篇、印刷部数五百部。
底本は昭和五八(一九八三)年ほるぷ刊行の「名著復刻詩歌文学館 紫陽花セット」の「藍色の蟇」に拠った。本書は復刻本乍ら、僕の所持する書籍の中で、というより、私の知る近現代のあらゆる出版物の中でもすこぶる附きで偏愛する装幀である。
原本に従ってなるべく忠実に再現することを心掛けたが、標題の字配は原則これを無視し、その他の細部の字配及びポイントの違いも一部を無視している。
疑義のある箇所は昭和二六(一九四一)年創元社刊創元文庫「大手拓次詩集」、昭和五〇(一九七五)年現代思潮社刊現代詩人文庫「大手拓次詩集」及び平成三(一九九一)年岩波書店刊岩波文庫原子朗編「大手拓次詩集」を適宜参考にした(なお、大手拓次の第一人者である岩波版編者の原氏は、本詩集「藍色の蟇」について、編集過程で製作順列が変更された上に、晩年の作品も恣意的に加えられており、大手拓次の『四半世紀にもわたる詩業を整理もせず一冊に盛りつけている』『内容自体に問題がある』詩集として強く批判され、岩波版編集の際もその『作品選択は、既刊本『藍色の蟇』の内容に左右されていない』とわざわざ解説で述べられているほどに評価されておられぬことを書誌学的学術的には重要な事実及び見解として書き添えておくことにする。また、底本の総解説の本書のパートも原氏が担当されておられるが、そこには、本書出版の『費用はすべて拓次の退職金でまかなわれ』、『実質は自費出版であ』り、『この空前の豪華版詩集のコストは、しめて二千五百円。当時としては破格の費用であ』ったともある)。
本サイト版はブログ・アクセス540000突破記念として昨年完成したブログ版に更に手を加えた私のサイト決定版である。藪野直史【2014年1月27日】]
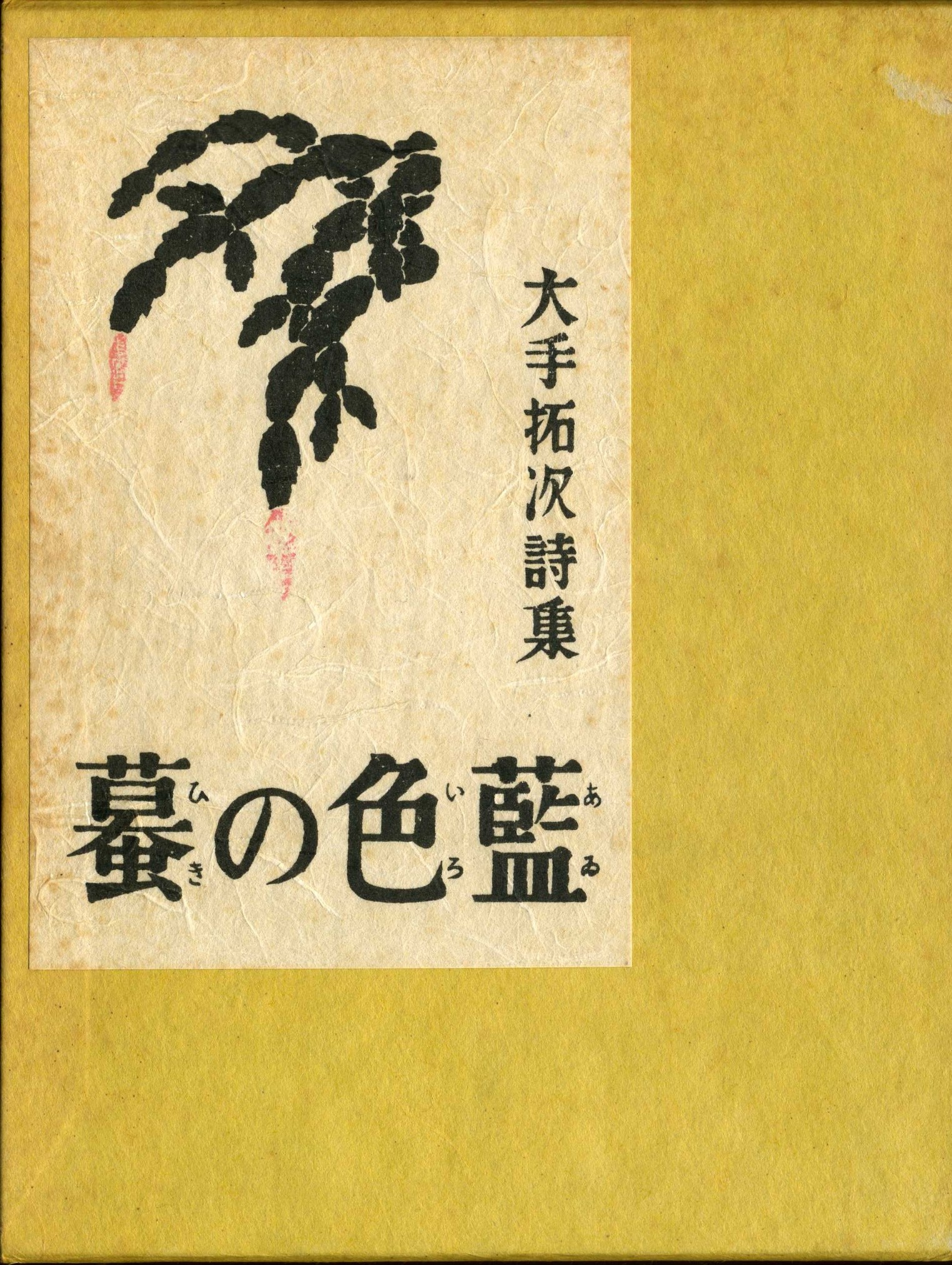
[やぶちゃん注:大手拓次詩集「藍色の蟇」箱(表)。絵はナデシコ目サボテン科ハシラサボテン亜科葦サボテン連スクルンベルゲラ属 Schlumbergera シャコバサボテン(カニサボテン)(同タイプ種は Schlumbergera russelliana)。汚損は私の入手(一九八三年八月二十日の復刻版刊行と同時に購入)以降に発生したもの。]

[やぶちゃん注:同箱(背)。]
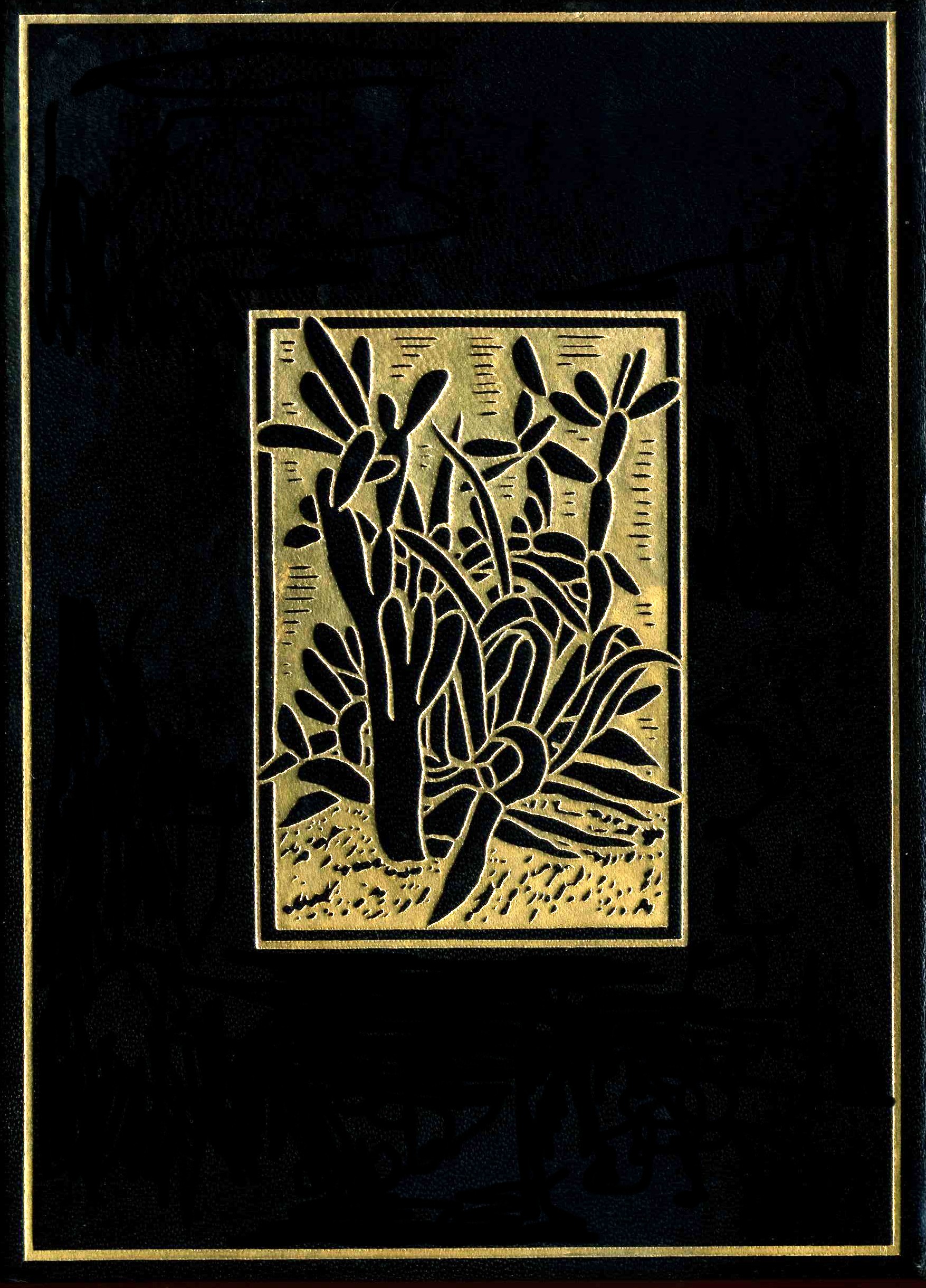
[やぶちゃん注:大手拓次詩集「藍色の蟇」本体表紙。私は植物に疎い。絵はサボテンの一種かとも思われるが、この表紙画の種についてご存知の方、是非ともご教授を乞うものである。]
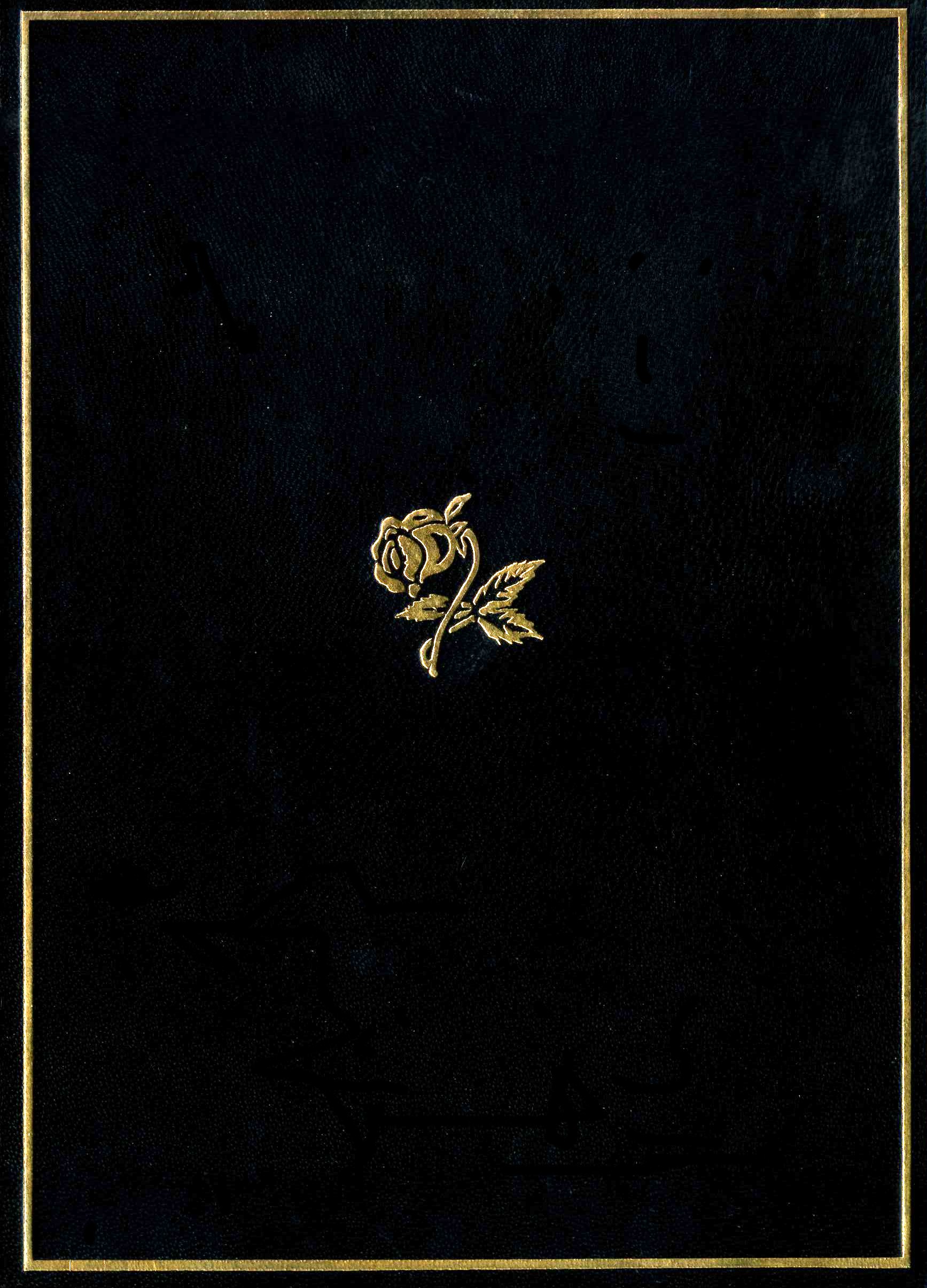
[やぶちゃん注:同裏表紙。ポイントのデザインは拓次の好きだった薔薇の花。]

[やぶちゃん注:同背表紙。ポイントのデザインは上から女神(?)・蟇・サボテン・蛇。如何にも拓次好みのシンボルである。なお、背の部分だけの金の質感を出すために私が補正を加えている。]
[やぶちゃん注:以下、標題紙前にある献辞。]
わたしのひかりである
北原白秋氏に獻ぐ
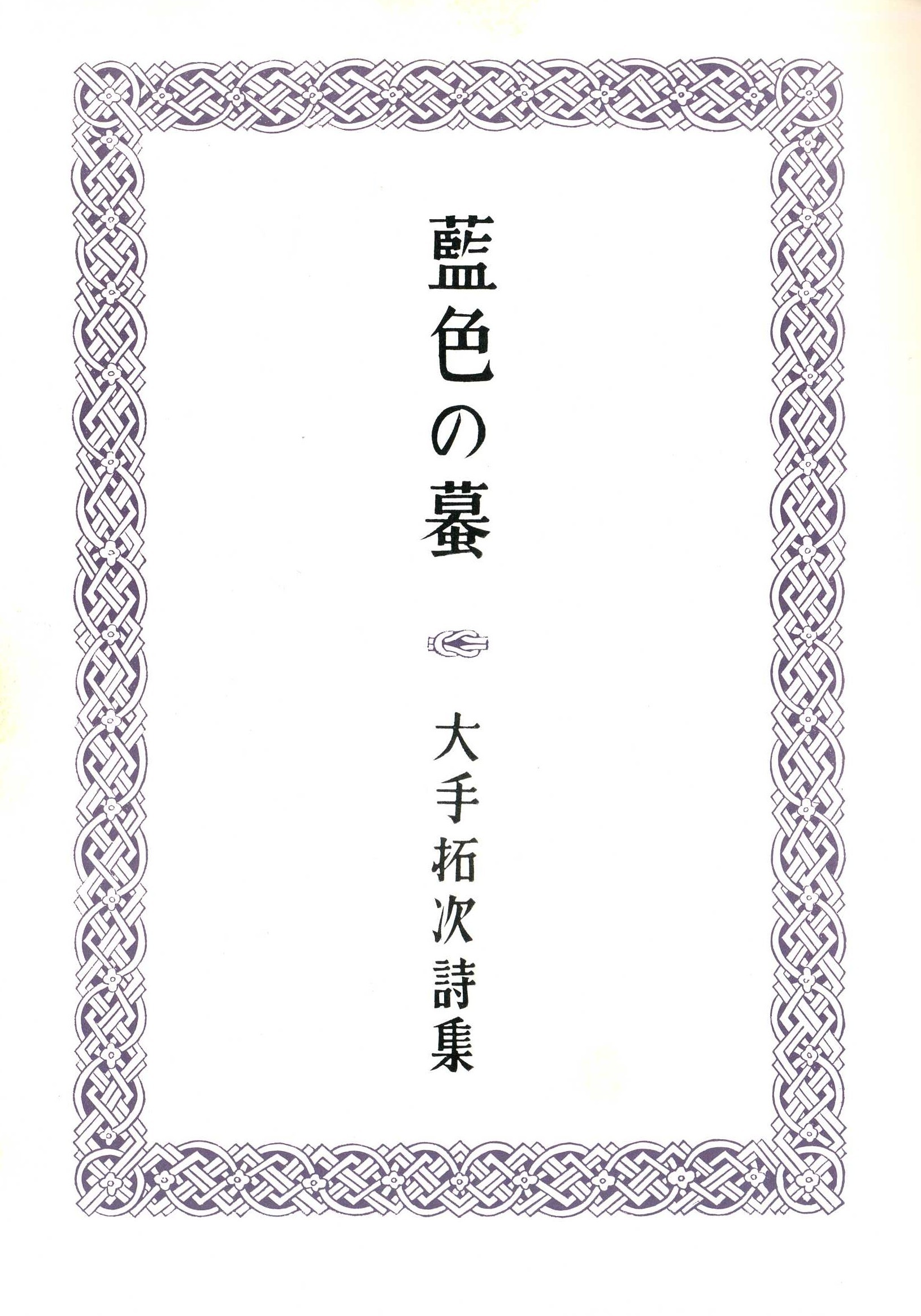
[やぶちゃん注:同表題紙。]
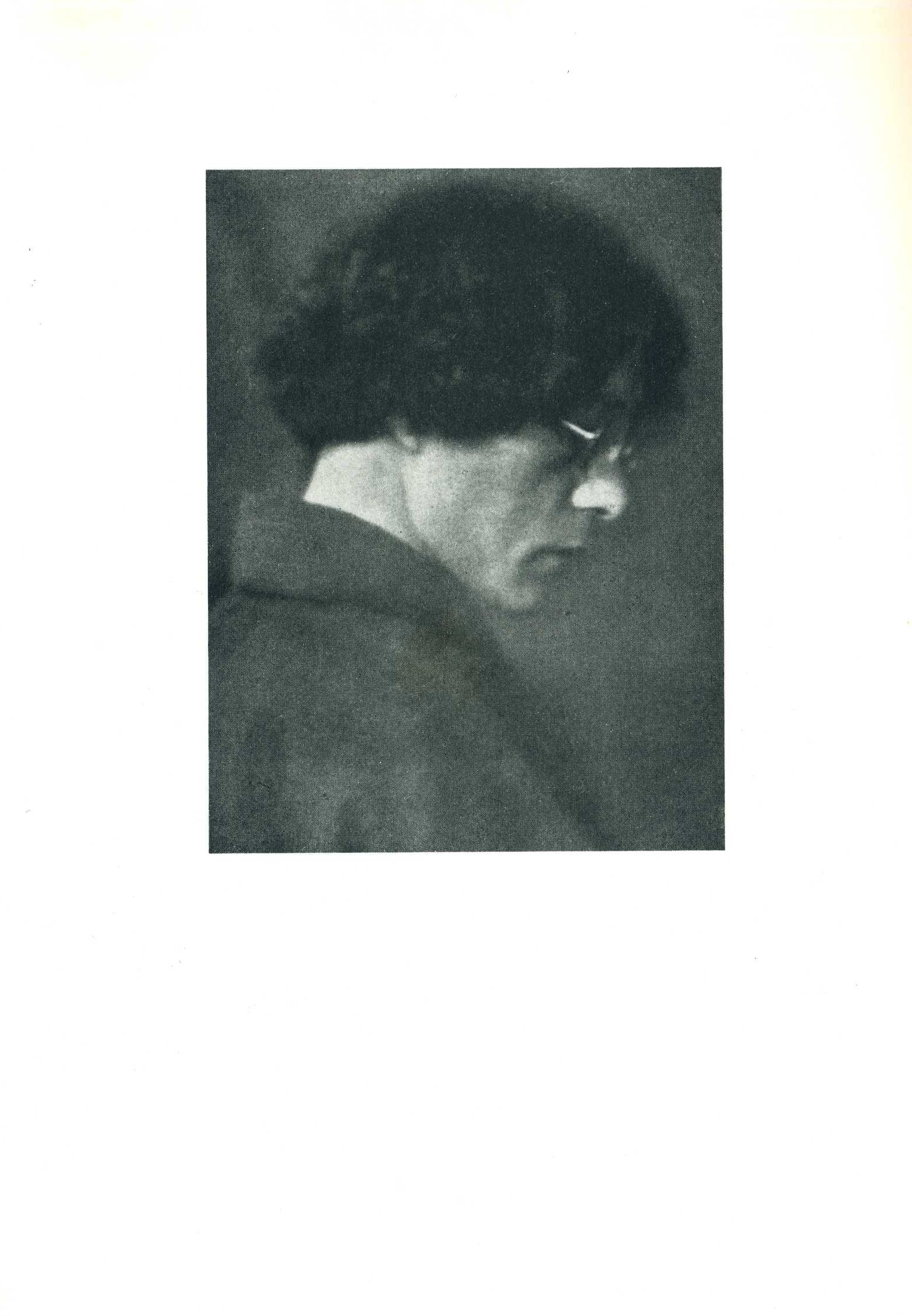
[やぶちゃん注:上記標題紙の次に挟まれてある平野次郎氏撮影になる著者肖像写真。平野次郎氏は没年の確認が出来ない。従って著作権が存続している可能性がないとは言えない。その場合は写真は撤去する。この方の没年や事蹟を御存知の方、御教授をお願いしたい。]
[やぶちゃん注:以下、著者遺影の次に挟まれてある序と跋の目次(ノンブル表示はなし)。]
『藍色の蟇』の詩人に(序)・北原白秋
大手拓次君の詩と人格(跋)・萩原朔太郞
[やぶちゃん注:上記の裏頁。]
装幀 逸見 享
[やぶちゃん注:「装幀 逸見 享」の次頁。見開き左頁でここと裏が都合、本文頁の1と2に当たるがノンブルはない。]
序
[やぶちゃん注:改頁二回で、次の見開き左頁から序本文開始。章段数字「1」~「5」は底本では半角。本詩集特有の印象的な大きなノンブルもここから始まる。これは私には現在の欧文フォント“University Roman LET”の数字に最も近いように見受けられる。美しい私の偏愛する字体である。このノンブルはまた配置も得意で、総てが各ページののどの部分(右頁では内側左下・左頁では内側右下)に配されている。以下の「無言の顏」の後にある同詩の肉筆画像の半分映っている前頁左下の画像を参照されたい。]
『藍色の蟇』の詩人に
北 原 白 秋
1
大手君。
君の在天の靈に獻ぐる此の私の言葉は、既に遲きに過ぎた。しかしながら到るべき時が滿ちなければどうにも輝かぬ機會がある。かうした自然の推移を推移として、今日の光榮があらためて君の上に俟たれたのである。とは云つてもこの事は決して私の爲に自身の懈怠をうち消す理由にはならぬ。深くお詑びをする。
かう言へば、君は却つて虔しく微笑されるであらう。君は私を識り、私もよく君を知つてゐる。幽明所を異にしようと私たちには必ず靈犀相通ずるものがあると思へる。時は到り道は愈々に開けて來た。大手拓次詩集『藍色の蟇』が燦然として今こそ梓に上るのである。
大手君。
君の詩を私が識つてから幾年になるであらう。『朱欒』の昔、明治大正の初頭に吉川惣一郞の筆名を以て突如として現れた新人の君は、室生犀星、萩原朔太郞の兩君と共に、一に金線につながる連星として光つて來た。以來、君の純情と節義とは私をして常に敬愛せしめた。私の行くところ常に步みを同うして君は君の香韻を鳴り響かした。時として私が步を停むれば君も亦幽かに、潔くして隱れた。『地上巡禮』“ARS”『詩と音樂』『日光』『近代風景』、さうした私の詩歌史に於ける諸誌を通じて、主として君の詩業は公にされ、ただ一道に眞實を傾け盡したのであつた。なみなみならぬ結緣といふ外はない。世に稀な忝さとはかうした魂の共鳴りであらうか。
大手君。
君の詩集『藍色の蟇』は、室生君の『愛の詩集』萩原君の『月に吠える』と雁行して、少くとも大正の中葉には輝かしく出世すべきであつた。謙讓であり、非社交的であり、私行の上に極めて扣へ目がちであつた君は幾度かその機を逸した。此の事は詩友としての私にも責任が無いとは言へない。君の詩は君獨自の香氣と語感と韻律とを以て、知るかぎりの人には驚目されてゐた。いみじき寶玉の凾はいつよりか獵奇の手に開かれてあり、決して巖窟の闇に埋もれてあつたといふ譯でもなかつた。運不運といふ事があるとしたら、君は不運の星から永らく見守られてゐたと云へる。この頃の新詩人の間には、吉川惣一郞と云ひ大手拓次とは云つても、或は見知らぬ世界の「球形の鬼」のやうにも見定め難いであらう。しかしながら大正より昭和にかけて君が成就された個の詩風は蕩然として實在し、此の『藍色の蟇』一卷の重量と柔かみとは、その掌に戴く人々をして、稀有の新詩集として讚歎せしむるであらう。年代を追ひ、その生長の跡を辿り、今更に、私は外ならぬ君の息吹を感じ、その詩句のひとつひとつに寧ろ自身の手澤をさへ嗅いで、この兩者の愛と深い魂の交流を聽きつつある。何よりも遺憾に思ふことは、今は遂に君の最後だといふことである。
君の親友逸見享君は、進んで裝幀した此の金を鏤むる『藍色の蟇』を獻げて、何は措いても君の墓前に額づかれるであらう。それにしても、澄明な冬の大氣に、此の濃い藍色の詩集が燻らす香煙の匂やかさを偲ぶ時、私はつくづくと熱い我が眼がしらのふるへを痛感する。
2
大手君。
君はその初期の詩「藍色の蟇」「陶器の鴉」等によつて早くも一家の淸新體を風騷した。想念に於ても感覺に於ても、または語音の舌觸、韻律の蕩搖に於ても、殆ど前人の影響を受けず、日本詩歌の傳統以外に、個の吉川惣一郞の詩を創成した。異數の事であり、まことに佛蘭西風の開花でもあつた。その獨自の香氣と粘りある柔軟性とは、怪奇な雜多の主題と共に、その觀る人々に一種のえならぬ甘い戰慄をさへも與へた。
稟質の特異性といふ點に於ては、神經の詩人『月に吠える』の著者と時代を同じくして、或は好き一對を成すものであらうか。しかしながら、此の『藍色の蟇』の世界はまた別種の惱氣ある幻夢を吐いて、寧ろ放埓なまでに黃色い空想の噴霧を羽ばたかした。空想の獵人と云ひ、麻醉の風車と云ひ、鳥の毛の鞭と云ひ、茴香色の性慾と云ひ、紅い羊皮を着た召使と云ひ、草色の瘤の生えた幽靈の足と云ふごとき、ただに五六の詩句を拾つたのみで、暗鬱の胸板をかき撫でられるむづ痒ゆさや柔かい怪しい七色の祕密の呪文をその「香料の顏寄せ」の中に感じられるであらう。もやもやした、のろのろした、ねばねばした、ふはふはした、よろよろした、ゆらゆらした、めらめらした、によろによろした、うとうと、うねうね、うつうつとした、或はぴらぴらした、ちろちろした、べろべろした、ほやほやとした、何といふ不思議なこぐらかつた肉的觸感であらう。聲、色、香、味、觸、之等の中で、君は最も觸の一面を高い藝術にまで、視覺や嗅覺と織り交ぜたのではなかつたか。
時としては蒼白の面に、而も一脈の妖美をひそめた尼僧のやうに羞かみ、或は緬羊の衣を著て、春の夕映の下によろばふ托鉢僧のやうに吐息した君は又、白い狼をその背に吼えさしたり、ぽうぽうと手にも足にも草を生やしたりしてつぶやいた。さうして君は獨身で生涯を畢つた。言葉をかへて云へば、君の詩は獨身の肉體に咲いた幻想の華であつた。
何故かなら、君の藍色の蟇は夜と毒氣を雜草の奧に吐き出だすそれではなかつた。森の寶庫の寢間にうづくまつて、あの陰濕な暗い暖爐の中にさへも、或る朱の更紗の繪模樣を描いた。
君にボオドレエルの影響が無いとは言へないであらう。しかしながら君の詩はかの惡の華とも色合を異にしてゐた。孤燭で内氣な肉體の華、陰鬱と情念のラムプの舌、とりとめない幻感と連禱、乳黃と綠の羽ばたき、さうしたもだもだとした雜光の霞に陶醉した君は何といふ不思議な存在であつたらう。
君は詩の使徒にはちがひなかつたが、より苦行する以上により哀樂した。寧ろ淫するほどに溺沒した畸體の詩魔であつた。さうして君の言葉に從へば、その一篇の詩を得る時には、病床に餅菓子の粘りを舌なめづる餓鬼の嗜慾をも感傷した。
君は十年一日のごとく、夜は近代映畫館の電飾と騷音とを眼前にして、陰濕な暗いその空を閉して、その己れの肺臟を刻々と蝕ませて行つた。
3
大手君。
君の書かれた詩を見ること二十數年に及ぶ間に、君の書體はいつも變らなかつた。君は一頁十行の原稿紙に、その一頁と次の頁の二三行とを、君獨自の圓みと粘りとを持つた細い曲線で書いて收めた。さしてそれ以上に詩は長くもなく、又、以内に短くもなかつた。
君は迫らなかつた。その爲に行の運びによる詩の韻律は常に緩調の樂曲であつた。ただ解體する縞蛇の群の四方への匍匐のやうに、行と行とがその想念情癡の綰ねから放れ、ぬらぬらと、而も未だ夢見る色と香ひとのとろみを、かの妖しい季節の首玉に一條一條とうねらすかのごとくであつた。さうして遂に雅味多き平假名の美しい連鏁となつた。是の平假名をかくばかり生きた波狀のやうにぬめりにぬめらした君の詩の姿は、日本の詩により新らしい匂と煙とを縺れさせ、さうして日本のものといふよりは寧ろ十九世紀あたりの舶來の氣色をも想見せしめた。君が日本文學の何ものの傳統にも殆ど囚へられなかつたのは、君にとつては知らぬが幸であつたとも云へよう。それだけにほしいままにも樂しめた自由さであつたか。私のごときは古典と先人の重壓の下に、苦しみに苦しみとほして來た。結縛と不自由との中にあらためて己れを鍛錬し、己れを解放することに惱みぬいて來た。何れが幸であり禍であるかといふことはその人の分にある。私は私でよく、君は君でよろしかつた。それにしても、君は藍色の捲毛に眼は碧い洋種の詩人として、この祖國の民俗とは甚しくかけはなれた海の外から、提琴を爪ぐつて來たかのごとくにその詩句を操つた。近代日本の口語體に移したよき飜譯調のやうでもあり、血脈の相違をも疑はせた。君は易々として樂しかつたであらう。その爲にまた、日本の言葉に新味の感情を附與し、香色の排列を光闡した。
君の詩が如何に幻想に豐かであつたかといふことは、日常に君を夢遊せしめた詩魂の音樂に就いて聽けばよき理解が匂ふであらう。ただ君の韻律の流動にはさして多種多樣の變化は看られなかつた。概して相似の音波の連續であり、音の强弱が度に於てほぼ同じく絕えず遠心的に蒼茫とした空氣を顫はして行つた。内に寵る極度の緊縮や、詩型の整齊や、時にとつての動顚や、野性の咆吼、人間群落の亂聲といふ風のものは、その詩興の五線譜には綴られなかつた。少年の羞耻にも近い潔癖や、厭人的孤高性や、また穩かな女人の白い手の香炎にも似た性情が、さう常にあらしめたであらう。
君はまことに詩に隱れて、ただ獨の幻感と連想とに昏醉した人ではあつた。此の『藍色の蟇』の詩は、君が作るところの一部の選抄にしか過ぎない。その類型の爲に、現像の稀薄、或は喪れた想像の翼の爲に、或は餅菓子を食べ過ぎたが爲に、そのまま筐底に葬られたものは實に顆しい蝶の數に堆積した。君は君の藍色の夜を、ただに黃いろいラムプの中にあつめて、詩を吐き、炎を瞬かしてゐればよかつたのだ。
或は、そのせいでもあつたか、晩年にはいくらか根が疲れ、聲色の衰へと香の火の白いくづれとが見えないではなかつた。何にしろ初期の詩がすぐれて妖しく炎を點してゐる。
大手君。
君の情感は翼の生えたわかわかしい黃ろい薔薇の花のやうであつた。色も香ひも、その繞りの空氣もすべてがゆらゆらと新らしく、そこには古めかしい何の文獻の關りもなかつた。再び云ふが、君の言葉は君によつて選まれたところの此の近代の日本の言葉のみであり、その口語脈の詩句のひびきは君自身に内より外へ釀し出された薰りの音波であつた。これほど物の見事に我が古典を雲霧の彼方に忘却し得た今日の詩人は他にはあるまいと思はれる。强ひても赤外線によつてでも、原始日本を身の眞近に映寫しようとする私ごときにとつては、全く不審にすら思はれる。
詩人の一生にも風雪と境涯の推移によつて、幾許かの轉身はある。この私の詩風にも、君が觀られたとほり幾度かの變貌がひとりでに來た。然るに君はその背中の美しい翅ばたきを休止するまで、失張り同じ語韻の同じ姿體の持主であつた。而もその精神に於ては永遠の浪曼人であつた。
君がありのままの自然の觀照家でもなく、活きた人生の現實主義者でも末世の思想家でもないといふことは、君の詩人としでの價値を上下する理由にはならぬ。君は君としての個の匂のふかい世界を夢から夢へと織り續けて行つたのだから、それでよいではないか。
思ふに君の詩は君の謂ふ黃ろい馬の耳元や、柔かいカンガルウの編靴の傍、或は陶器製の靑い鴉のまへ、あかい假面の上の雜草の中、或は月を眺むる靑狐の足のうしろ、白い髯を生やした蟹のかたへ、さうした位置に、君と同じに心を据ゑて、それらの一句一句を味わふべきものかと思はれる。君の怪奇な曼陀羅圖は濛々とし惱氣と、さだかならぬ啾々たる鬼哭とを以て私たちを吸ひ寄せる。一氣に、或は東洋風の簡約に、頸根つこや生膽をがしと摑むそれらでもなく、徹りきつた直觀で錐揉みに揉むそれらでもないやうである。ともすれば放恣に空想の蛾が鱗粉を散らし、金の吹雪が卵をたぎらせる。どうともせよと焦燥したくなつても中々に見えて來ぬ幽靈の手ぶりもあれば、さだかにはわきがたい銀の捕繩の響もする。君は獨だけで考へ、獨だけでつぶやきつづけた。
しかもまた、解體しつつある縞蛇の塊りとも、私は君の鬱憂の匍匐狀態を云つたが、角の神經を持つた雲丹型の紅い球形の鬼が君の腦髓には棲んでゐたらしい。君の蛇はぬらぬらとしても溫かく、君の鬼は陰鬱でも明るくしやくつてゐた。南方の詩であり、北方のそれではなかつた。全く、あの色も響も無くしんしんと押し迫る寒波の凄まじさは、たとひ妖氣の獵奇者の君にも堪へられなかつた筈だ。眞空鐘の中では音韻が微動だにせぬがごとく、光と薰と空氣無しには、君は一瞬も生きられさうになかつた。
それであるから君は決して惡の詩人ではなかつたのである。
4
大手君。
君の風貌に就いては、君の詩を識つて以來、十數年の後に至るまで、私は全く知るところがなかつた。それは此の集の君のおぼえがき「孤獨の箱のなかから」に君が書かれたとほりであつた。君はその永い歳月の間にただの一度も私を訪れては見えなかつた。
ただ、私は、君より入手するや詩と書體をとほして、私の恣な想像を樂しむのみであつた。初めて君の魔女作「藍色の蟇」を發見した當時の私の悦びは、今にしても光りかがやく私の頰を感ずる。室生、萩原兩君の出現に私の眉もうちあがつたあの『朱欒』の開花時が思ひ出される。
吉川惣一郞、その人の名を以て、私に寄せられた折々の書簡は、大手拓次となつても、まだ秋の香爐の煙のやうに匂はしく、何か内氣な女手のやうな色めきや優しみが殘つてゐた。その細みの圓い曲線に縺れた淚ぐましい風のそよめきが時として些か私を戚傷の囹とした。謂ふところの未知の戀人のやうに私を遠くより觀る瞳の若さが偲ばれた。
大手君。
さうであつた。たまたま詩誌『近代風景』の創刊に際して、谷中天王寺の私の假寓に、君と初めて會見したのはまさしく大正十五年の冬であつた。
私は驚いて目を瞠つた。
蓬々として捲いてちぢれた肩をうつ長髮、鼻も高く、鬱屈した逞しい顏、筋骨の嚴つい中年の偉丈夫が、何と私の前に端坐してゐたのではないか。豫想とは全くちがつた、諧謔して云へば歷山大王のやうな風姿の君ではあつた。
それにも關らず。君はまた寡默の、極めて羞かみ屋の、切長の眼の潤んだ、事ごとに頰を赤める少年の純情を以て、おどおどとした、その詩や書體に見るやうな人でもあつた。
私たちは何を語つたであらう。おほかたはあの墓地の落葉のやうに記憶も飛び散つて了つたが、雲は細く、玉蘭の高い枝には朱の寂びた奇異な瘤形の果の幾つかが、くくれて、共に步いて見上げた、私の眼底に灼きついてゐる。
君の詩に就き、性情に就き、私生活に就き、樣々に思ひ惑つた私は、君の死後に、それとなく聽きもし、日記類なとも散見もして、漸くに氷釋した數々があつた。
書いてもいいかと思ふが、君の詩はまさしく、君の鬱悶が、神經が、生活が書かせたものにちがひなかつた。異常の君にしてよくもライオン齒磨の廣告部に二十年近くも日々勤務しおほせたと思へるが、それ故にまた、牛込袋町の下宿の一室に机の向も變へずに、夜々を坐りとほした忍苦と奇怪な不精とを肯き得るのである。
限りのない戀慕と詩と空想と美の耽溺は、君の命を糸で編んだラムプの蕊のやうにぢりぢりと縮めては行つたらうが、君自身には、それが炎の祭でもあり、好もしく吸ひあぐる紫の燈油のにじみでもあり、如何ともするすべはなかつたであらう。
書いてはわるいかとも思ふが、君の詩の世界の相手は、多くは君ほどの優れた詩人の戀する相手としてはあまりに價値の無い市井の少年少女であつたらしい。君の書き贈る切々とした戀の詩の美しさや消息の細々しさに對して、手まはり香料や化粧液を嗅ぎ分けるほどの敏感さを果して彼等は所有してゐたであらうか。君の心の鳴咽はかの母韻のごとくに、常に子韻のかげに隱れて五色の光線を顫はしたが、彼等は遂に知るところも啄むところも無かつたらしい。綿々たる情熱を祕めた幽婉な愛の言葉の末には、必ず「朝な朝な、その淨き齒を磨きたまへかし。」と書き添へることを忘れなかつた君の純情はさることながら、如何ほどに彼等の口中は牝牛の舌や腐れた赤茄子からの唾液を厭はしく淸掃したであらうか。
いつもいつも恐ろしい幻滅が、君を蝕ませたといふそのことそれ自らが、非現實な幻想家の收穫すべき冬の日の柿の蔕ではなかつたか。
永い間の君の獨身が、夢にのみ華やかなその木の根の石の上には、いつもいつも怯儒な蒼い影ばかりをこびらつかせたのだ。
大手君。
許してもらへるならば、私は、君の詩生活の豐潤と、虛妄とも見えて君には眞實であつた香炎の羽ばたきとを、更に裏書すべき詩文集の一卷を編纂さしてほしいと思ふ。詩の殘闕と、日記、書簡、その他の類聚である。此の一卷こそ、君の裸形の背後から射透す紫外線の火花でなくして何であらう。
私は密かに見た。君が戀する女の足に就いてあの幻感と連禱とを恣にした日記の詩文を、さうして、その二つの白い素足をそれぞれの中心として縱橫十方に放射する理性と神經と情念との道路圖を。
私は知つてゐる。私の義弟山本鼎の近親であつて、同じく畫家であり、未完成ながら天才の俤を多分に示した村山槐多の遺稿集『槐多の歌へる』のあの暴露の凄まじさを。おそらく君のこれとは、色こそちがへ、同じ光度に於て世を驚倒せしめるであらう。
5
大手君。
私は君に就いて些か鵞鳥の筆を以てして書き過ぎたかもしれぬ。切口が今でもきちきちするこの羽根で。
しかし、君はきつと私が君の詩をかう觀て讚歎もし微笑もしてゐたことを知つてゐられたにちがひない。それほどの知己の間の私たちであつたから。君の死後に私が處置すべきことの何であるかも私は知つてゐる。
昭和九年四月十八日、茅ケ崎の南湖院からの急電を受けて、私たち夫妻が駈けつけた時は、すでに君の命脈は止つてゐた。その一二年がほどは、君からの消息も無く、病患に就いても、再度の轉地療養のことも、少しも知らなかつた私たちであつた。
春と言つても、雲と波の音は薄ら寒く、風は砂をけぶらして、したたか群生の小松に吹きあげてゐた。
しみじみと合掌しながら、私は君の死顏の高貴さに撲れた。透きとほり、淨く緊り、蒼白く光をさめ、日の長い薄明の中に、君は幽かに仰向いてゐられた。
愈々起たずと知つて、白秋この私には必ずその臨終後の通知を打電つやうにと、そのただ一人の附添ひの看護婦に密かに云ひ含めてあつたと聽いた。
さうであつたか。
私は君が、大福餅のみを、その少しく前よ朝夕に一つづつ幼童のごとく嗜好されたといふことも聽いた。
電燈が黃ろく點つた。コードの紐の影がいくらか搖れたやうであつたが、君の閉した眶には何の微動も無かつた。
二十日、故郷の上州磯部へ君の遺骨が還られる日、私は、室生犀星、萩原朔太郞、大木惇夫諸君その他私の周圍の新人達と上野驛に謹んで參集した。詩の交友も殆どそれだけに限られた君であつた。發車の汽笛が鳴り、私たちは聲を呑んで禮拜した。私の腸はちぎれさうになつた。
大手君。
君は生前に、此の新詩集『藍色の蟇』を自身の手で明るく上梓するよい機會とよい條件に惠まれなかつた。大正の十五年に一旦編纂して、卷末のおぼえ書を書き添へまでした君ではあつたが、委托された私ではあつたが、二人の前にはただに大きな障碍のみが暗い翼を張つた。今漸くにして、ここに、その後の詩品を逸見君と更に收錄し補綴して、この出版の日の目を見ることとなつた。しかし、君の圓寂後、その多年の事務的勤勞の餘情として得られたものから、乃ち死後の君自身によつて刊行されるのである。謝するに言葉の無い私たちを君はまことに、虔ましく、弱々と微笑されてゐるであらう。
それでよいのであらうか。否々、君にはもつともつと世の耀かしい酬が莊巖されねばならぬ。
君はまことに、明治大正昭三代に亘つての數少い優れた詩人の中の一人であつた。 昭和十一年十二月十五日拂曉
[やぶちゃん注:以下、白秋の序の最終(右頁で終わり)の見開き左頁にある、作者の自序代わりの序詩。]
宿命の雪
自序に代へて
ほのほはそのかげをおかしてたたずみ、
みどりの犬をはなち、
合掌し 合掌し みづにおぼれる。
大正十五年九月 拓 次
[やぶちゃん注:この「宿命の雪(自序にかへて)」は最後の逸見享氏の「編者の言葉」によれば、大正一五(一九二六)年に彼が書いたものをそのまま用いたとある。
次の次の頁に拓次の死の翌日の死顔の逸見享によるデッサン画。左下に「昭和九年 四月十九日 享」とある。これは画家逸見享氏(明治二八(一八九五)年~昭和一九(一九四四)年)で、和歌山県出身。中央大学卒業後、ライオン歯磨意匠部に勤務する傍ら、木版画を始め、大正八(一九一九)年の第一回日本創作版画協会展に入選、日本版画協会でも活躍した。「新東京百景」を分担制作、友人であった大手拓次の詩集の装丁・編集も彼が手がけた(講談社「日本人名大辞典」の解説に拠る)。本詩集の編集・装幀も彼の手になる。]
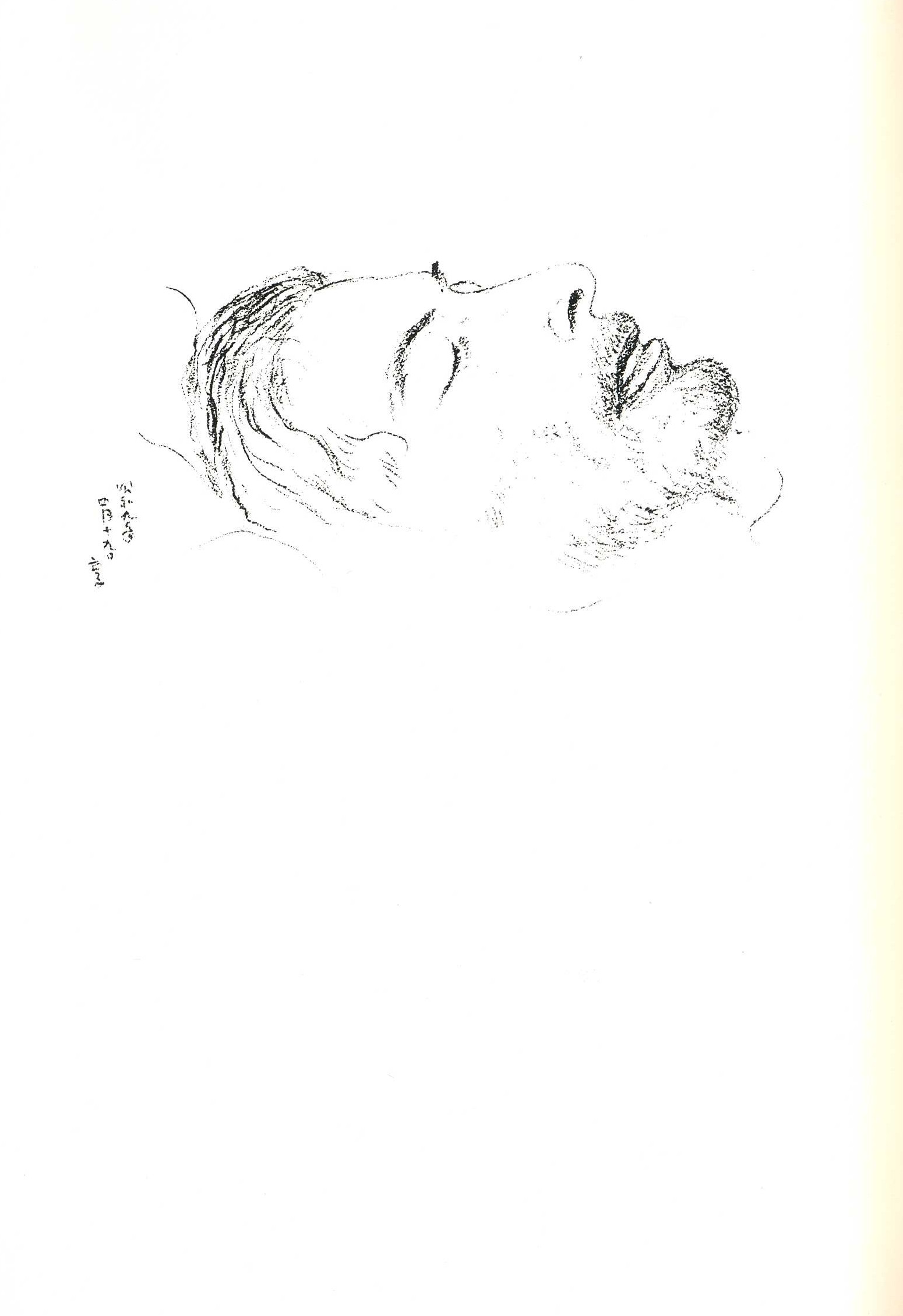
[やぶちゃん注:「宿命の雪 自序に代へて」の次に挟まれてある大手拓次の死顔のデッサン(逸見亨画)。左端に、
昭和九年
四月十九日
享
という署名がある。逸見亨(明治二八(一八九五)年~昭和一九(一九四四)年)は画家。和歌山県出身で中央大学卒業後、ライオン歯磨意匠部に勤務する傍ら、木版画を始め、大正八(一九一九)年の第一回日本創作版画協会展に入選、日本版画協会でも活躍した。「新東京百景」を分担制作、友人であった大手拓次の詩集の装丁・編集も彼が手がけた(講談社「日本人名大辞典」の解説に拠る)。彼の作品はパブリック・ドメインである。]
[やぶちゃん注:以下、本文標題紙。「詩集」は横組。]
詩集 藍色の蟇
陶器の鴉
藍色の蟇
森の寶庫の寢閒に
藍色の蟇は黃色い息をはいて
陰濕の暗い暖爐のなかにひとつの繪模樣をかく。
太陽の隱し子のやうにひよわの少年は
美しい葡萄のやうな眼をもつて、
行くよ、行くよ、いさましげに、
空想の獵人はやはらかいカンガルウの編靴に。
陶器の鴉
陶器製のあをい鴉、
なめらかな母韻をつつんでおそひくるあをがらす、
うまれたままの暖かさでお前はよろよろする。
嘴の大きい、眼のおほきい、わるだくみのありさうな靑鴉、
この日和のしづかさを食べろ。
しなびた船
海がある、
お前の手のひらの海がある。
苺の實の汁を吸ひながら、
わたしはよろける。
わたしはお前の手のなかへ捲きこまれる。
逼塞した息はお腹の上へ墓標をたてようとする。
灰色の謀叛よ、お前の魂を火皿の心にささげて、
淸淨に、安らかに傳道のために死なうではないか。
黃金の闇
南がふいて
鳩の胸が光りにふるへ、
わたしの頭は釀された酒のやうに黴の花をはねのける。
赤い護謨のやうにおびえる唇が
力なげに、けれど親しげに内輪な步みぶりをほのめかす。
わたしは今、反省と悔悟の闇に
あまくこぼれおちる情趣を抱きしめる。
白い羽根蒲團の上に、
產み月の黃金の闇は
惱みをふくんでゐる。
槍の野邊
うす紅い晝の衣裳をきて、お前といふ異國の夢がしとやかにわたしの胸をめぐる。
執拗な陰氣な顏をしてる愚かな乳母は
うつとりと見惚れて、くやしいけれど言葉も出ない。
古い香木のもえる煙のやうにたちのぼる
この紛亂した人間の隱遁性と何物をも恐れない暴逆な復讎心とが、
溫和な春の日の箱車のなかに狎れ親しんで
ちやうど麝香猫と褐色の栗鼠とのやうにいがみあふ。
をりをりは麗しくきらめく白い齒の爭鬪に倦怠の世は旋風の壁模樣に眺め入る。
象よ步め
赤い表紙の本から出て、
皺だみた象よ、口のない大きな象よ、のろのろあゆめ、
ふたりが死んだ床の上に。
疲勞ををどらせる麻醉の風車、
お前が黃色い人間の皮をはいで
深い眞言の奧へ、のろのろと秋を背に負うて象よあゆめ
おなじ眠りへ生の嘴は動いて、
ふとつた老樹をつきくづす。
鷲のやうにひろがる象の世界をもりそだてて、
夜の噴煙のなかへすすめ、
人生は垂れた通草の頸のやうにゆれる。
枯木の馬
神よ、大洋をとびきる鳥よ、
神よ、凡ての實在を正しくおくものよ、
ああ、わたしの盲の肉體よ滅亡せよ、
さうでなければ、神と共に燃えよ、燃えよ、王城の炬火のやうに燃えよ、
ああ、わたしの取るに足りない性の遺骸を棄てて、
暴風のうすみどりの槌のしたに。
香枕のそばに投げだされたあをい手を見よ、
もはや、深淵をかけめぐる枯木の馬にのつて、
わたしは懷疑者の冷たい着物をきてゐる。
けれど神樣よ、わたしの遺骸には永遠に芳烈な花を飾つてください。
鳥の毛の鞭
尼僧のおとづれてくるやうに思はれて、なんとも言ひやうのない寂しさ いらだたしさに張りもなくだらける。
嫉妬よ、嫉妬よ、
やはらかい濡葉のしたをこごみがちに迷つて、
鳥の毛の古甕色の悲しい鞭にうたれる。
お前はやさしい惱みを生む花嫁、
わたしはお前のつつましやかな姿にほれる。
花嫁よ、けむりのやうにふくらむ花嫁よ、
わたしはお前の手にもたれてゆかう。
道心
七頭の怪物のやうな形をして、わたしの道心は呼吸してゐる。
洪水の喧囂、洪水の騷亂、
わたしは死骸となつた童貞のそばに、
白い布に包まれて母の嘆きをおびてゐる。
たはむれに水蛇は怪しい理智の影に逃げまはる。
世界は黃昏の永遠を波立たせる。
[やぶちゃん注:「喧囂」は「けんがう(けんごう)」で、喧喧囂囂。がやがやとやかましいこと、そうすること、また、そのさま。
私はこの、
わたしは死骸となつた童貞のそばに、
白い布に包まれて母の嘆きをおびてゐる。
のシークエンスが好きで堪らない。]
漁色
あを海色の耳のない叢林よ、
たまごなりの媒酌のうつたうしい気分、
おとなしい山羊の曲り角に手をかけて、子供たちの空想の息をついてみよう。
夜よ、夜よ、夜の船のなかに
茴香色の性慾はこまやかに泡だつて、
花粉の霧のやうに麥笛をならす。
撒水車の小僧たち
お前は撒水車をひく小僧たち、
川ぞひのひろい市街を悠長にかけめぐる。
紅や綠や光のある色はみんなおほひかくされ、
Silence と廢滅の水色の色の行者のみがうろつく。
これがわたしの隱しやうもない生活の姿だ。
ああわたしの果てもない寂寥を
街のかなたこなたに撒きちらせ、撒きちらせ。
撒水車の小僧たち、
あはい豫言の日和が生れるより先に、
つきせないわたしの寂寥をまきちらせまきちらせ。
海のやうにわきでるわたしの寂寥をまきちらせ。
[やぶちゃん注:「撒水車」は「さつすいしや(さっすいしゃ)」と読む。散水車に同じであるが、読みに注意されたい。]
羊皮をきた召使
お前は羊皮をきた召使だ。
くさつた思想をもちはこぶおとなしい召使だ。
お前は紅い羊皮をきたつつましい召使だ。
あの ふるい手なれた鎔爐のそばに
お前はいつも生生した眼で待つてゐる。
ほんたうにお前は氣の毒なほど新らしい無智を食べてゐる。
やはらかい羊の皮のきものをきて
すずしい眼で御用をきいてゐる。
すこしはなまけてもいいよ、
すこしはあそんでもいいよ、
夜になつたらお前自身の考をゆるしてやる。
ぬけ羽のことさへわすれた老鳥が
お前のあたまのうへにびつこをひいてゐる。
海鳥の結婚
大きな緋色の扇をかざして
空想の海は大聲にわらふ。
濃い綠色の海鳥の不具者、
命の前にかぎりない祈禱をささげ、
眞夏の落葉のやうに不運をなげく。
命はしとやかに馬の蹄をふんで西へ西へとすすみ、
再現のあまい美妙はいんいんと鳴る。
眠りは起き、狂氣はめざめ、
嵐はさうさうと神の額をふく。
永劫は臥床から出て信仰の笑顏に親しむ。
空想の海は平和の祭禮のなかに
可憐な不具者と異樣のものの媒介をする。
寂寥の犬、病氣の牛、
色大理石の女の彫像に淫蕩な母韻の泣き聲がただよふ。
唇に秋を思はせる姦淫者のおとなしい群よ、
惡の花の咲きにほふひと閒をみたまへ、
勝利をほころばす靑い冠、
女の謎をふせぐ黃金の圓楯よ、
戀の姿をうつす象牙の鏡、
寶玉と薰香と善美をつくした死の王衣よ。
海鳥の不具者は驚異と安息とに飽食し、
淚もろい異樣のものを抱へてひざまづく。
慰安
惡氣のそれとなくうなだれて
慰安の銀綠色の塔のなかへ身を投げかける。
なめらかな天鵞絨色の魚よ、
忍從の木陰に鳴らす timbale
祕密はあだめいた濃化粧して溫順な人生に享樂の罪を贈る。
わたしはただ、空に鳴る鞭のひびきにすぎない。
水色の神と交遊する鞭にすぎない。
[やぶちゃん注:底本では「天鵞絨色」のルビは「ろうどいろ」であるが、意味からも、ルビの植字の割付位置からも、「び」の脱字であることが明白であるので補った。「timbale」はフランス語で打楽器のティンパニのこと。ティンパニは英語では“timpani”、本来の語源であるイタリア語では“timpani ”又は“timpano”と綴る。]
蛇の道行
わたしの眼を、ふところに抱いた眞珠玉のやうに暖めて、
懶惰の考へ深い錆色をした蛇めが
若いはちきれるやうな血をみなぎらして蠟色の臥床にありながら、
おほやうな空の叢に舞ふ光の魂を招いたのだ。
それも無理もない話だ。
見たまへ、お互ひが持つてゐる慾の火壺のなかには可愛らしい子蛇と光りの卵が無心にふざけてる。
だんだんに子供たちの眼がふくらんできて、
ありもしない翅をはたつかせた。
そのたびに幻影はいきほひよくをどつた。
いたづらな神樣は
かうして二人に罪と惠みの樂しみを料理してくれた。
なまけものの幽靈
ある日なまけものの幽靈が
感奮して魔王の黑い黑い殿堂の建築に從事した。
ひとあたり手をつけてみると
妙にをかしくてつてきて、またどうやら倦き倦きしてしまつた。
しかし、仕事をつづけるといふことが怪しく殘りをしかつたので
靑い斧をふりあげては働いた。
そして、炎のやうに冥想の遺骸が質朴な木造車にのせられて通る。
黑い殿堂は休むことなく
ふだんの事のやうに工事が進められてゐる。
なまけものの幽靈は今更のやうにあたり前の誇りをみせびらかしたくなつた。
――みると幽靈の足には草色の瘤が出來てゐた。
泡立つ陰鬱
女のかひなのやうに泡だつてくる
むさぼり好きの陰鬱よ、
あの黑い いつもよくかしこまつてゐる小魚が
空が絹をひいたやうにあまいので、
今日は なだめやうもないほどむづかつてゐる。
長い耳の亡靈
うこん色にひかる遊戲のなかに
追ひたてられた亡靈はつまづいてたふれる。
きらびやかな荊棘の杖をついて
足のすわらない生活がせまつてくる。
くるしい、そしてつんぼの窓には
亡靈のうとい耳がひつかかつてゐる。
灰色のだらつとたれた長い耳は
あへぎあへぎ空想をはらんでゐる。
目をあいた過去
この放埒な空想は
行きつまつて 自らのからだのうちへ沈んだ。
みづからをとめどもなく掘りくづす旅わたりの金鑛夫、
わたしの過去はなまなましくくづれてくる。
過去よ、決して聲をあげるな、
お前は隱呪の箱のやうにただ暗く恐ろしくあれ。
[やぶちゃん注:「隱呪」不詳。「おんじゆ(おんじゅ)」と読んでいるか。これはもしかすると、呪術を用いて自分の姿を隠して見えなくする「隠形」の謂いか? 識者の御教授を乞うものである。]
なりひびく鉤
年のわかい蛭のやうに
みづみづとふくらんだ眼から眼へ、
はなやかな隱者の心が點つてゆき、
わけ知らずの顏の白いけものたち、
お前は幽靈のやうにわたしのまはりに坐つてゐる。
そら、海が女のやうに媚びてねむるとき、
絲をはなれて、はればれと鳴る黑い鉤の音をきいてごらん、
やはらかい魚はだまつてききとれてゐるだらう。
のびてゆく不具
わたしはなんにもしらない。
ただぼんやりとすわつてゐる。
さうして、わたしのあたまが香のけむりのくゆるやうにわらわらとみだれてゐる。
あたまはじぶんから
あはうのやうにすべての物音に負かされてゐる。
かびのはえたやうなしめつぽい木靈が
はりあひもなくはねかへつてゐる。
のぞみのない不具めが
もうおれひとりといはぬばかりに
あたらしい生活のあとを食ひあらしてゆく。
わたしはかうしてまいにちまいにち、
ふるい灰塚のなかへうもれてゐる。
神さまもみえない、
ふるへながら、のろのろしてゐる死をぬつたり消しぬつたり消ししてゐる。
やけた鍵
だまつてゐてくれ、
おまへにこんなことをお願ひするのは面目ないんだ。
この燒けてさびた鍵をそつともつてゆき、
うぐひす色のしなやかな紙鑪にかけて、
それからおまへの使ひなれた靑砥のうへにきずのつかないやうにおいてくれ。
べつに多分のねがひはない。
ね、さうやつてやけあとがきれいになほつたら、
またわたしの手へかへしてくれ、
それのもどるのを專念に待つてゐるのだから。
季節のすすむのがはやいので、
ついそのままにわすれてゐた。
としつきに焦げたこのちひさな鍵も
またつかひみちがわかるだらう。
[やぶちゃん注:「紙鑪」の「鑪」は、囲炉裏・火鉢・香炉・大甕・酒甕といった意味でヤスリの意はない。ヤスリは「鑢」と書き、「鑪」に非常に似ているので、作者自身の誤字か、植字ミスの可能性が疑われる。]
美の遊行者
そのむかし、わたしの心にさわいだ野獸の嵐が、
初夏の日にひややかによみがへつてきた。
すべての空想のあたらしい核をもとめようとして
南洋のながい髮をたれた女鳥のやうに、
いたましいほどに狂ひみだれたそのときの一途の心が
いまもまた、このおだやかな遊惰の日に法服をきた昔の知り人のやうにやつてきた。
なんといふあてもない寂しさだらう。
白磁の皿にもられたこのみのやうに人を魅する冷たい哀愁がながれでる。
わたしはまことに美の遊行者であつた。
苗床のなかにめぐむ憂ひの芽望みの芽、
わたしのゆくみちには常にかなしい雨がふる。
[やぶちゃん注:「女鳥」不詳。叙述からみると、所謂、雄の成鳥が美しい飾り羽を持つ極楽鳥、スズメ目スズメ亜目カラス上科フウチョウ科 Paradisaeidae に属するフウチョウ(風鳥)の仲間を指しているように読める(人口に膾炙しているゴクラクチョウという名は正式和名ではない)。識者の御教授を乞う。]
秋
ものはものは呼んでよろこび、
さみしい秋の黃色い葉はひろい大樣な胸にねむる。
風もあるし、旅人もあるし、
しづんでゆく若い心はほのかな化粧づかれに遠い國をおもふ。
ちひさな傷のあるわたしの手は
よろけながらに白い狼をおひかける。
ああ 秋よ、
秋はつめたい霧の火をまきちらす。
[やぶちゃん注:一行目、不審。校合すべき所載本がないのではっきりとは言えないが、これは、
ものはものを呼んでよろこび、
の誤植ではなかろうかと思われる。
ネット上で検索をかけた結果、「日本詩人愛唱歌集 詩と音楽を愛する人のためのデータベース」内に「藍色の蟇」(白鳳社版「大手拓次全集」の第一巻及び第二巻)があり、そこでは「ものを」となっているのを見出した。以下に「ものを」とした形で全詩を再度、掲げておく。
秋
ものはものを呼んでよろこび、
さみしい秋の黃色い葉はひろい大樣な胸にねむる。
風もあるし、旅人もあるし、
しづんでゆく若い心はほのかな化粧づかれに遠い國をおもふ。
ちひさな傷のあるわたしの手は
よろけながらに白い狼をおひかける。
ああ 秋よ、
秋はつめたい霧の火をまきちらす。
但し、私は白鳳社版「大手拓次全集」を所持しておらず、現時点では確認したわけでもないことは断っておく。]
裸體の森
鏡の眼をもつた糜爛の蛇が、
羚羊の腹を喰ひやぶる蛇が、
凝力の强い稟性の痴愚を煽つて
炎熱の砂漠の上にたたきつぶす。
冷笑の使をおびた駝鳥が奇怪なづうたいをのさばらす。
死ね……
淫縱の智者よ、
芳香ある裸体の森へゆかう。
なめらかな氈の上に 化粧の蛇は媚をあふれこぼす。
[やぶちゃん注:「稟性」生得の性質。天賦の質。天性。]
罪の拜跪
ぬしよ、この「自我」のぬしよ、
空虛な肉體をのこしてどこへいつたのか。
ぬしの御座は紫の疑惑にけがされてゐる。
跳梁をほしいままにした罪の淚もろい拜跪は
祈れども祈れども、
ああ わたしの生存の標たるぬしはみえない。
ぬしよ、囚人の悲しい音樂をきけ。
據りどころのない亡命の鳥の歌をきけ。
ぬしよ、
罪の至純なる懺悔はいづこまでそなたの影を追うてゆくのか。
ぬしよ、信仰の火把に火はつけられんとする。
死は香爐の扉のやうににほうてくる。
[やぶちゃん注:底本、八行目は、
據りどころ亡命の鳥の歌をきけ。
であるが、意味が通らないため、昭和二六(一九四一)年創元社刊創元文庫「大手拓次詩集」、昭和五〇(一九七五)年現代思潮社刊現代詩人文庫「大手拓次詩集」に拠って訂した。]
肉色の薔薇
うまれでた季節は僞らずに幸福をおくる。
おお はづかしげに裸になつた接吻よ、
五月はわたし達に果てもない夢である。
此汎愛の思想のよわよわしい芽生えは
旅の空をうろついてあるく女藝人のやうに人知れず淚をながしてゐる。
今、偏狹者の胸に咲いた肉色の薔薇よ、
今、惡執者の腕に散る肉色の薔薇よ、
遍在の神は吾等の上に楽しい訪れをささやく。
歡びにみちた季節は悲哀の種をまく。
うれはしげに鎧を着た接吻よ、
戦闘は白く白く波をうつてゐる。
[やぶちゃん注:創元社刊創元文庫「大手拓次詩集」及び現代思潮社刊現代詩人文庫「大手拓次詩集」では、二行目を、
おお はづかしげに裸になつた接吻よ。
と読点ではなく、句点とする。また、後者現代詩人文庫版では、更に最後の三行を独立連(第二連)としている。正字で以下に現代詩人文庫版の詩形全文を示しておく。
肉色の薔薇
うまれでた季節は僞らずに幸福をおくる。
おお はづかしげに裸になつた接吻よ。
五月はわたし達に果てもない夢である。
此汎愛の思想のよわよわしい芽生えは
旅の空をうろついてあるく女藝人のやうに人知れず淚をながしてゐる。
今、偏狹者の胸に咲いた肉色の薔薇よ、
今、惡執者の腕に散る肉色の薔薇よ、
遍在の神は吾等の上に楽しい訪れをささやく。
歡びにみちた季節は悲哀の種をまく。
うれはしげに鎧を着た接吻よ、
戦闘は白く白く波をうつてゐる。]
つんぼの犬
だまつて聽いてゐる、
あけはなした恐ろしい話を。
むくむくと太古を夢見てる犬よ、
顏をあげて流れさる潮の
はなやかな色にみとれてるのか。
お前の後足のほとりには、いつも
ミモザの花のにほひが漂うてゐる。
野の羊へ
野をひそひそとあゆんでゆく羊の群よ、
やさしげに湖上の夕月を眺めて
嘆息をもらすのは、
なんといふ瞑合をわたしの心にもつてくるだらう。
紫の角を持つた羊のむれ、
跳ねよ、跳ねよ、
夕月はめぐみをこぼす…………
わたし達すてられた魂のうへに。
[やぶちゃん注:「瞑合」は「みやうがふ(みょうごう)」で、恐らくは、知らず知らず一つになることという「冥合」の謂いであろう。]
威嚇者
わたしの威嚇者がおどろいてゐる梢の上から見おろして、
いまにもその妙に曲つた固い黑い爪で
冥府から來た響の聲援によりながら
必勝を期してわたしの魂へついてゐるだらう。
わたしはもう、それを恐れたり、おびえたりする餘裕がない。
わたしは朦朧として無限とつらなつてゐるばかりで、
苦痛も慟哭も、哀れな世の不運も、據りどころない風の苦痛にすぎなくなつた。
わたしは、もう永遠の存在の端へむすびつけられたのだ。
わたしの生活の盛りは、空氣をこえ、
萬象をこえ、水色の奧祕へひびく時である。
憂はわたしを護る
憂はわたしをまもる。
のびやかに此心がをどつてゆくときでも、
また限りない瞑想の朽廢へおちいるときでも、
きつと わたしの憂はわたしの弱い身體を中庸の微韻のうちに保つ。
ああ お前よ、鳩の毛竝のやうにやさしくふるへる憂よ、
さあ お前の好きな五月がきた。
たんぽぽの實のしろくはじけてとぶ五月がきた。
お前は この光のなかに悲しげに浴みして
世界のすべてを包む戀を探せ。
河原の沙のなかから
河原の沙のなかから
夕映の花のなかへ むつくりとした圓いものがうかびあがる。
それは貝でもない、また魚でもない、
胴からはなれて生きるわたしの首の幻だ。
わたしの首はたいへん年をとつて
ぶらぶらとらちもない獨りあるきがしたいのだらう。
やさしくそれを看とりしてやるものもない。
わたしの首は たうとう風に追はれて、月見草のくさむらへまぎれこんだ。
球形の鬼
雪をのむ馬
自然をつくる大神よ、
まちの巷をくらうする大氣のおほどかなる有樣、
めづらしい幽闇の景色をゑがいて、
その したしたとしたたる碧玉のつれなさにしづみ、
ゆたかにも企畫をめぐらすものは、
これ このわたしといふ
靑白い幻の雪をのむ馬。
[やぶちゃん注:最終行、「靑白い/幻の//雪をのむ馬」と詠む時、恐ろしいまでに私の琴線が倍音となって鳴り響く。]
假面の上の草
そこをどいてゆけ。
あかい肉色の假面のうへに生えた雜草は
びよびよとしてあちらのはうへなびいてゐる。
毒鳥の嘴にほじられ、
髮をながくのばした怪異の托僧は こつねんとして姿をあらはした。
ぐるぐると身をうねらせる忍辱は
黑いながい舌をだして身ぶるひをする。
季節よ、人閒よ、
おまへたちは橫にたふれろ、
あやしい火はばうばうともえて、わたしの進路にたちふさがる。
そこをどいてゆけ、
わたしは神のしろい手をもとめるのだ。
香爐の秋
むらがる鳥よ、
むらがる木の葉よ、
ふかく、こんとんと冥護の谷底へおちる。
あたまをあげよ、
さやさやとかける秋は いましも伸びてきて、
おとろへた人人のために
音をうつやうな香爐をたく。
ああ 凋滅のまへにさきだつこゑは
無窮の美をおびて境界をこえ、
白い木馬にまたがつてこともなくゆきすぎる。
木立の相
物語のおくに
ちひさな春の悔恨をうめたてて、
あをいあをい小蜂の羽なりの狼煙をみまもり、
ふりしきる木立の怪相ををがむ。
ふるひをののく心の肌にすひついて
その銀の牙をならし、
天地しんごんとしてとけるとき、
幻化の頌を誦す。
木立は紫金の蛇をうみ、
おしせまる海浪まんまんとして胎盤のうへに芽ぐむとき、
惡の寶冠はゆめをけちらして神を抱く。
ことばなく、こゑなく、陸に、海に、
ながれる存在の腹部は紅爛のよろこびをそだてて屈伸する。
[やぶちゃん注:現代思潮社刊現代詩人文庫「大手拓次詩集」では、「幻化の頌を誦す。」の「誦す」には「誦す」とルビを振る。]
武裝した痙攣
武裝した痙攣がおこる、
ぐわうぜんたる破壞にむかふ努力がうなりごゑをだす。
わたしはたちあがる、生活の顔面へ。
わたしはみづばれになつた足や膝をだしてあるくのだ。
濕氣の膓をひきだす幻想は姦淫されて、のら犬のやうに死んでゐる。
けれどそんなことは意としない。
くさつた鐵の壁は、わたしのうなりごゑをきいてしかみづらをしてゐる。
それは大きな象をうむ陣痛だ。
ぢつと旋行する凝視のクラリオネツトが鳴ると、
だんだんに夜がしらみががつてゆく。
[やぶちゃん注:「しかみづら」は無論、「顰み面」で、「顰めっ面」に同じい。]
創造の草笛
あなたはしづかにわたしのまはりをとりまいてゐる。
わたしが くらい底のない闇につきおとされて、
くるしさにもがくとき、
あなたのひかりがきらきらとかがやく。
わたしの手をひきだしてくれるものは、
あなたの心のながれよりほかにはない。
朝露のやうにすずしい言葉をうむものは、
あなたの身ぶりよりほかにはない。
あなたは、いつもいつもあたらしい創造の草笛である。
水のおもてをかける草笛よ、
また とほくのはうへにげてゆく草笛よ、
しづかにかなしくうたつてくれ。
[やぶちゃん注:小さな頃、私の母は、私のために、よく草笛を鳴らしてくれたものだった――私は今も――草笛を鳴らせない――。]
球形の鬼
あつまるものをよせあつめ、
ぐわうぐわうと鳴るひとつの箱のなかに、
やうやく眼をあきかけた此世の鬼は
うすいあま皮に包まれたままでわづかに息をふいてゐる。
香具をもたらしてゆく虛妄の妖艷、
さんさんと鳴る銀と白蠟の燈架のうへのいのちは、
ひとしく手をたたいて消えんことをのぞんでゐる。
みよ、みよ、
世界をおしかくす赤いふくらんだ大足は
夕燒のごとく影をあらはさうとする。
ああ、力と闇とに滿ちた球形の鬼よ、
その鳴りひびく胎期の長くあれ、長くあれ。
[やぶちゃん注:ここまで再読して私は「藍色の蟇」のイメージに最も近い画家は、かの私の偏愛するルドンであるように思えてならなくなってきたことをここに告白する。]
ふくろふの笛
とびちがふ とびちがふ暗闇のぬけ羽の手、
その手は丘をひきよせてみだれる。
そしてまた 死の輪飾りを
薔薇のつぼみのやうなお前のやはらかい肩へおくるだらう。
おききなさい、
今も今とて ふくろふの笛は足ずりをして
あをいけむりのなかにうなだれるお前のからだを
とほくへ とほくへと追ひのける。
くちなし色の車
つらなつてくる車のあとに また車がある。
あをい背旗をたてならべ、
どこへゆくのやら若い人たちがくるではないか、
しやりしやりと鳴るあらつちのうへを
うれひにのべられた小砂利のうへを
笑顏しながら羽ぶるひをする人たちがゆく。
さうして、くちなし色の車のかずが
河豚のやうな闇のなかにのまれた。
春のかなしみ
かなしみよ、
なんともいへない 深いふかい春のかなしみよ、
やせほそつた幹に春はたうとうふうはりした生きもののかなしみをつけた。
のたりのたりした海原のはてしないとほくの方へゆくやうに
ああ このとめどもない悔恨のかなしみよ、
溫室のなかに長いもすそをひく草のやうに
かなしみはよわよわしい賴り氣をなびかしてゐる。
空想の階段にうかぶ鳩の足どりに
かなしみはだんだんに虛無の宮殿にちかよつてゆく。
生きたる過去
とりかへしのつかない、あの生きたる過去は
ひたひの傷をおさへながらあるきまはる。
だらだらとよみがへつた生血はひたひからおちて、
牡熊のやうにくるしさをしのんでゐる。
過去は永遠のとびらをふさがうとする。
過去はたましひのほとりに黃金のくさりを鳴らす。
わたしのもえあがる戀の十字架のうへにうつくしい棺衣と灰の白刃とを與へる。
かなしい過去のあゆみは
わたしのからだを泥海のやうにふみあらす。
[やぶちゃん注:現代思潮社刊現代詩人文庫「大手拓次詩集」では、
わたしのもえあがる戀の十字架のうへにうつくしい棺衣と灰の白刃とを與へる。
の一行を、
わたしのもえあがる戀の十字架のうへに
うつくしい棺衣と灰の白刃とを與へる。
と二行に分かつが、採らない。]
輝く城のなかへ
みなとを出る船は黃色い帆をあげて去つた。
嘴は木の葉の群をささやいて
海の鳥はけむりを焚いてゐる。
磯邊の草は亡靈の影をそだてて、
わきかへるうしほのなかへわたしは身をなげる。
わたしの身にからまる魚のうろこをぬいで、
泥土に輝く城のなかへ。
咆える月暈
わたしは街にほえる、
ひとびとのくらいおくそこに。
ひややかな木のこずゑをはなれ、
さまざまの呪ひの銃聲のながれる街のなかに、
瀲灔とたたへられた水のやうに
わたしは手づくりの網をまいて、
はるかなる死の慰安をほえてゐる。
[やぶちゃん注:「瀲灔」水の満ち溢れるさま。また、漣が光り煌めくさま。「瀲灩」とも書く。]
銀の足鐶
――死人の家をよみて――
囚徒らの足にはまばゆい銀のくさりがついてゐる。
そのくさりの鐶は しづかにけむる如く
呼吸をよび 嘆息をうながし、
力をはらむ鳥の翅のやうにささやきを起して、
これら 憂愁にとざされた囚徒らのうへに光をなげる。
くらく いんうつに見える囚徒らの日常のくさむらをうごかすものは、
その、感觸のなつかしく 强靱なる銀の足鐶である。
死滅のほそい途に心を向ける これらバラツクのなかの人人は
おそろしい空想家である。
彼等は精彩ある巢をつくり、雛をつくり、
海をわたつてとびゆく候鳥である。
[やぶちゃん注:「死人の家」は、恐らくドストエフスキイの「死の家の記録」(原題“Записки из Мёртвого дома”一八六二年作)である。かれが読んだのは片上伸訳の大正三(一九一四)年博文館刊の「近代西洋文芸叢書」第六冊に所収されたものであろう。この時の邦題は「死人の家」である。]
ひろがる肉體
わたしのこゑはほら貝のやうにとほくひろがる。
わたしはじぶんの腹をおさへてどしどしとあるくと、
日光は緋のきれのやうにとびちり、
空氣はあをい胎壁の息のやうに泡をわきたたせる。
山や河や丘や野や、すべてひとつのけものとなつてわたしにつきしたがふ。
わたしの足は土となつてひろがり
わたしのからだは香となつてひろがる。
いろいろの法規は屑肉のやうにわたしのゑさとなる。
かくして、わたしはだんまりのほら貝のうちにかくれる。
つんぼの月、めくらの月、
わたしはまだ滅しつくさなかつた。
[やぶちゃん注:非常に珍しく題名の「肉體」及び、本文は「緋」を除いて総てにルビが振られている。寧ろ、「緋」は本文総ルビの脱落のようにしか思われない。]
躁忙
ひややかな火のほとりをとぶ蟲のやうに
くるくるといらだち、をののき、おびえつつ、さわがしい私よ
野をかける仔牛のおどろき、
あかくもえあがる雲の眞下に慟哭をつつんでかける毛なみのうつくしい仔牛のむれ。
鉤を產む風は輝く寶石のごとく私をおさへてうごかさない。
底のない、幽谷の闇の曙にめざめて偉大なる茫漠の胞衣をむかへる。
つよい海風のやうに烈しい身づくろひした接吻をのぞんでも、
すべて手だてなきものは欺騙者の香餌である。
わたしの躁忙は海の底に
さわがしい太鼓をならしてゐる。
[やぶちゃん注:「躁忙」は「そうばう(そうぼう)」で「怱忙」と同義であろう。忙しくて落ち着かないことを言う。「欺騙者」は「きへんしや(きへんしゃ)」と読み、「欺騙」は「欺瞞」と同義で、欺き騙す者。]
走る宮殿
紺色にまたみどり色にあかつきの空を手でかなでる、
このみごもりの世界に滿ちた悉くの蛇よ、
おまへたちの その女のへそのやうなやはらかな金のうろこをうごかして、
さびしいこのふるい靈像のまはりをとりまけ、
うろこからでる靑銅の焰はをどる、
なみだをたれてゆく化生の罪は
霧のやうに消えさる。
あかつきは生長して紅の彩光をなげあたへ、
ひとつひとつの住居はとびらをひらいて念じ、
さて、わたしたち精靈の宮は
あけぼののやさしい Chorus のなかへとはしる。
[やぶちゃん注:「Chorus」表面上は、コーダで「わたしたち」である「精靈の宮」は、目に見えぬ流体としての合唱の歌声の奔流の中へと走り入ってゆくのであるが、私は拓次がこれをわざわざ英文で表記したことに拘る。これは合唱の声であると同時にこの「走る宮殿」という名の野外劇に於ける、そのコロス(“choros”。古代ギリシャ語由来で“chorus”の語源、古代ギリシア劇に於ける合唱隊)の中へと走り去るように思われてならない。ウィキの「コロス」によれば、『コロスは観客に対して、観賞の助けとなる劇の背景や要約を伝え、劇のテーマについて注釈し、観客がどう劇に反応するのが理想的かを教える。また、劇によっては一般大衆の代わりをすることもある。多くの古代ギリシア劇の中で、コロスは主要登場人物が劇中語れなかったこと(たとえば恐怖、秘密とか)を登場人物に代わって代弁する。コロスは通常、歌の形式を採るが、時にはユニゾンで詩を朗読する場合もある』とある。]
耳のうしろの野
わたしの耳のうしろにある黃色い野は
僞笑をふくんであでやかに化粧する。
その野のなかにはみどり色の眼をもつた自働車がうごき
いうれいのやうにひるがへる女たちはゆききする。
ただ そこに荒武者のやうに
ひとりの男は銀の穗先の槍をもつてたはむれる。
ふたつの手をもつ世のひとびとよ、
耳のおくにある幻の伶樂をきけ、
美裝をこらした惡魔どもは
あまい毒刃のゆめよりさめて、
騷然たる神前の吹笛にふける。
かくして、
耳のうしろにある黃色い野は死の頭上にしづかにもえてゐる。
笛をふく墓鬼
もぢやもぢやとたれた髮の毛、
あをいあばたの鼻、
ほそい眼が奥からのぞいてゐる。
つちのうへをぺたぺたとあるいて、
すすいろのやせた手をだしては笛をふく。
ものをすひこむやうなねいろである。
ふるへるやうなまやかしである。
[やぶちゃん注:「墓鬼」というのは拓次の造語と思われる。この辺り、まさに大手拓次版「稲生物怪録」張りである。]
あをい狐
さかしい眼をするあをい狐よ、
夏葦のしげるなかに
おまへの足をやすめて、
うららかに光明の心をきる。
草間の風を、
その豊麗な背にうけよ、背にうけよ。
老人
わたしのそばへきて腰をかけた、
ほそい杖にたよつてそうつと腰をかけた。
老人はわたしの眼をみてゐた。
たつたひとつの光がわたしの背にふるへてゐた。
奇蹟のおそはれのやうに
わらひはじめると、
その口がばかにおほきい。
おだやかな日和はながれ、
わたしの身がけむりになつてしまふかとおもふと、
老人は白いひげをはやした蟹のやうにみえた。
紫の盾
あをい環をつみかさねる銅鑼の遠音はうかび、
金衣の僧侶はいでて祈禱をさづけ、
階段のうへに秋はさめざめとうろついてゐるなかを、
紫の縞目をうつした半月の盾をだいて
憔悴した惡徒は入りきたる。
哀音は友をよんで部屋部屋にうつりゆき、
自戒の念にとりまかれた朝はやぶれる。
地をかきたてるかなしい銅鑼がなれば、
角ある鳥をゑがいた紫の盾はやすやすともたげられて、
死のまへにみじろぐ惡徒の身をかくす。
紫の盾よ さちあれ、
生をよびかへす白痴の胸にも花よかをれ。
白い髯をはやした蟹
おまへはね、しろいひげをはやした蟹だよ、
なりが大きくつて、のさのさとよこばひをする。
幻影をしまつておくうねりまがつた迷宮のきざはしのまへに、
何年といふことなくねころんでゐる。
さまざまな行列や旗じるしがお前のまへをとほつていつたけれど、
そんなものには眼もくれないで、
おまへは自分ひとりの夢をむさぼりくつてゐる。
ふかい哄笑がおまへの全身をひたして、
それがだんだんしづんでゆき、
地軸のひとつの端にふれたとき、
むらさきの光をはなつ太陽が世界いちめんにひろがつた。
けれどもおまへはおなじやうにふくろふの羽ばたく晝にかくれて、
なまけくさつた手で風琴をひいてゐる。
みどりの狂人
そらをおしながせ、
みどりの狂人よ。
とどろきわたる媢嫉のいけすのなかにはねまはる羽のある魚は、
さかさまにつつたちあがつて、
齒をむきだしていがむ。
いけすはばさばさとゆれる、
魚は眼をたたいてとびださうとする。
風と雨との自由をもつ、ながいからだのみどりの狂人よ、
おまへのからだが、むやみとほそくながくのびるのは、
どうしたせゐなのだ。
いや………‥魚がはねるのがきこえる。
おまへは、ありたけのちからをだして空をおしながしてしまへ。
[やぶちゃん注:「媢嫉」妬み憎むこと、忌み嫌う、の意。「媢」は、ねたむ・そねむ・忌む及び憎むの意を持つ。終わりから二行目のリーダ部は、底本では等間隔で十一ポイントある。]
よれからむ帆
ひとつは黃色い帆、
ひとつは赤い帆、
もうひとつはあをい帆だ。
その三つの帆はならんで、よれあひながら沖あひさしてすすむ。
それはとほく海のうへをゆくやうであるが、
じつはだんだん空のなかへまきあがつてゆくのだ。
うみ鳥のけたたましいさけびがそのあひだをとぶ。
これらの帆ぬのは、
人間の皮をはいでこしらへたものだから、
どうしても、内側へまきこんできて、
おひての風を布いつぱいにはらまないのだ。
よれからむ生皮の帆布は翕然としてひとつの怪像となる。
[やぶちゃん注:四行目の「沖あひさしてすすむ」の部分、底本は「沖あひさしですすむ」でと格助詞が「て」ではなく、「で」の濁音ある(印字の汚れではなく、確かな植字「で」である)。「沖合指し」という特異な名詞形もあり得ない訳ではないが、ここは創元文庫版「大手拓次詩集」の表記を採用した。
「翕然」「翕」は聚まるの意で、多くのものが一つに合う、一致する、集まるさま。]
みどり色の蛇
假面のいただきをこえて
そのうねうねしたからだをのばしてはふ
みどり色のふとい蛇よ、
その腹には春の情感のうろこが
らんらんと金にもえてゐる。
みどり色の蛇よ、
ねんばりしたその執著を路ばたにうゑながら、
ひとあし ひとあし
春の肌にはひつてゆく。
うれひに滿ちた春の肌は
あらゆる芬香にゆたゆたと波をうつてゐる。
みどり色の蛇よ、
白い柩のゆめをすてて、
かなしみにあふれた春のまぶたへ
つよい戀をおくれ、
そのみどりのからだがやぶれるまで。
みどり色の蛇よ、
いんいんとなる戀のうづまく鐘は
かぎりなく美の生立をときしめす。
その齒で咬め、
その舌で刺せ、
その光ある尾で打て、
その腹で紅金の焰を焚け、
春のまるまるした肌へ
永遠を產む毒液をそそぎこめ。
みどり色の蛇よ、
そしてお前も
春とともに死の前にひざまづけ。
[やぶちゃん注:「芬香」は「ふんかう(ふんこう)」で、よい匂い、芳香。]
死の行列
こころよく すきとほる死の透明なよそほひをしたものものが
さらりさらり なんのさはるおともなく、
地をひきずるおともなく、
けむりのうへを匍ふ靑いぬれ色のたましひのやうに
しめつた脣をのがれのがれゆく。
名も知らない女へ
名も知らない女よ、
おまへの眼にはやさしい媚がとがつてゐる、
そして その瞳は小魚のやうにはねてゐる、
おまへのやはらかな頰は
ふつくりとして色とにほひの住處、
おまへのからだはすんなりとして
手はいきもののやうにうごめく。
名もしらない女よ、
おまへのわけた髮の毛は
うすぐらく、なやましく、
ゆふべの鐘のねのやうにわたしの心にまつはる。
「ねえおつかさん、
あたし足がかつたるくつてしやうがないわ」
わたしはまだそのこゑをおぼえてゐる。
うつくしい うつくしい名もしらない女よ
濕氣の小馬
黃色い馬
そこからはかげがさし、
ゆふひは帶をといてねころぶ。
かるい羽のやうな耳は風にふるへて、
黃色い毛竝の馬は馬銜をかんで繫がれてゐる。
そして、パンヤのやうにふはふはと舞ひたつ懶惰は
その馬の繫木となつてうづくまり、
しき藁のうへによこになれば、
しみでる汗は祈禱の糧となる。
[やぶちゃん注:「パンヤ」双子葉植物綱アオイ目アオイ科(新エングラー体系及びクロンキスト体系ではパンヤ科)パンヤ亜科セイバ属カポック Ceiba pentandra などのパンヤ類の植物の種子から繊維として採取される、紡ぐことが出来ない綿のような長毛。クッション・救命胴衣・ソフトボールの詰め物などに用いられる。ポルトガル語“panha”を語源とする。]
朱の搖椅子
岡をのぼる人よ、
野をたどる人よ、
さてはまた、とびらをとぼとぼとたたく人よ、
春のひかりがゆれてくるではないか。
わたしたちふたりは
朱と金との搖椅子のうへに身をのせて、
このベエルのやうな氛氣とともに、かろくかろくゆれてみよう、
あの溫室にさくふうりん草のくびのやうに。
[やぶちゃん注:「氛氣」空中に見えるクモや、かすみのような気。なお古くは空気・大気の原義である「雰囲気」を「氛圍氣」とも書いた。
「ふうりん草」我々に馴染みの双子葉植物綱キキョウ目キキョウ科ホタルブクロ属 Campanula のホタルブクロ(螢袋)のことか、若しくは狭義の同属のフウリンソウ Campanula medium を指している。現在は改良品種が学名のラテン名「小さな鐘」をそのまま用いてカンパニュラ(カンパヌラ)などとも呼ばれる。フウリンソウ Campanula medium は園芸では正式和名のフウリンソウよりもツリガネソウ(釣鐘草)と呼ぶことの方が多いらしい。ウィキの「カンパニュラ」の「ふうりんそう」の項(画像あり)には(アラビア数字を漢数字に代え、記号の一部を変更した)、『この仲間では最もポピュラーな植物。草丈二メートルくらいになる二年草だが、秋まきで翌春開花する一年草に改良された品種もある。花色には青紫・藤色・ピンク・白などがあり、上手に育てると、花径一〇センチメートル近い花が数十輪咲き、花壇の背景などに植えると見事である』とある。ここは「溫室」とするので、後者で採ってよかろう。]
法性のみち
わたしはきものをぬぎ、
じゆばんをぬいで、
りんごの實のやうなはだかになつて、
ひたすらに法性のみちをもとめる。
わたしをわらふあざけりのこゑ、
わたしをわらふそしりのこゑ、
それはみなてる日にむされたうじむしのこゑである。
わたしのからだはほがらかにあけぼのへはしる。
わたしのあるいてゆく路のくさは
ひとつひとつをとめとなり、
手をのべてはわたしの足をだき、
唇をだしてはわたしの膝をなめる。
すずしくさびしい野邊のくさは、
うつくしいをとめとなつて豐麗なからだをわたしのまへにさしのべる。
わたしの靑春はけものとなつてもえる。
[やぶちゃん注:「法性」辞書的な意味を示しておく。仏教用語で一切の存在・現象の真の本性。万有の本体。「真如」「実相」「法界」とも言う。「ほっしょう」と読むことが多い。]
曼陀羅を食ふ縞馬
ゆきがふる ゆきがふる。
しろい雪がふる。
あをい雪がふる。
ひづめのおとがする、
樹をたたく啄木鳥のやうなおとがする。
天馬のやうにひらりとおりたつたのは
茶と金との縞馬である。
若草のやうにこころよく その鼻と耳とはそよいでゐる。
封じられた五音の丘にのぼり、
こゑもなく 空をかめば、
未知の曼陀羅はくづれ落ちようとする。
おそろしい縞馬め!
わたしの舌から、わたしの胸からは鬼火がもえる。
ゆきがふる ゆきがふる。
赤と紫とのまだらの雪がふる。
[やぶちゃん注:「五音」は狭義には中国・日本の音楽の理論用語で音階や旋法の基本となる五つの音を指す。各音は低い方から順に宮・商・角・徴・羽と呼ばれ、基本型としては洋楽のドレミソラと同様の音程関係になる。「ごおん」とも読む。但し、広義には広く音声の調子・音色の意としても用いられる。ここで拓次は架空の、例えば古代ケルトの遺跡のようなイメージを飛ばして、神聖不可侵の楽の音の封じ込まれた丘を想起しているように思われる。]
金屬の耳
わたしの耳は
金絲のぬひはくにいろづいて、
鳩のにこ毛のやうな痛みをおぼえる。
わたしの耳は
うすぐろい妖鬼の足にふみにじられて、
石綿のやうにかけおちる。
わたしの耳は
祭壇のなかへおひいれられて、
そこに隱呪をむすぶ金物の像となつた。
わたしの耳は
水仙の風のなかにたつて、
物の招きにさからつてゐる。
[やぶちゃん注:「隱呪」この熟語は辞書に見えないが、密教にあって印を結び、真言を唱えることを「印呪」と言い、また、神道を始め多くの宗教や信仰の中には、秘かに人に見えぬように体の蔭や手の内に隠して印を結ぶことが普通に行われるから、奇異な熟語には私には見えない。すこぶる腑に落ちる用字である。]
妬心の花嫁
このこころ、
つばさのはえた、角の生えたわたしの心は、
かぎりなくも溫熱の胸牆をもとめて、
ひたはしりにまよなかの闇をかける。
をんなたちの放埓はこの右の手のかがみにうつり、
また疾走する吐息のかをりはこの左の手のつるぎをふるはせる。
妖氣の美僧はもすそをひいてことばをなげき、
うらうらとして銀鈴の魔をそよがせる。
ことなれる二つの性は大地のみごもりとなつて、
谷間に老樹をうみ、
野や丘にはひあるく二尾の蛇をうむ。
[やぶちゃん注:「胸牆」敵の矢玉からの防備及び敵に対する射撃の便のために胸の高さほどに築いた盛り土のこと。胸壁。「胸墻」とも書く。]
白い象の賀宴
香氣をはく無言のとき、
晝閒は羽團扇のやうに物のかげをおひたてて、
なにごともひとつらに足のあゆみを忍ばせる。
この隱密の露臺のみどりのうへに、
年とつた白い象は謙讓の姿をあらはして、
手もない牙の樂器をかなでる。
女象の足は地をふんで、
あやしい舞踏にふけり、
角笛の麻睡はとほくよりおとづれて、
たのしい賀宴の誇りをちらす。
[やぶちゃん注:「麻睡」はママ。
「ひとつら」「一連・一行」で、ひと続きに並ぶさま。一連なり。一列。
「手もない」特異な用法である。文字通りなら、容易にとか難なくたやすく、若しくはそのままの意の「手も無く」を形容詞とした連体形であるが、用法としては特異で、私は寧ろ、同語又は類似した意味の動詞を並べて強く否定する表現の「ても…ない」の常套例「似ても似つかない」の省略形で、見たこともないような、の意をも(の方を)強く感じる。]
蛙にのつた死の老爺
灰色の蛙の背中にのつた死が、
まづしいひげをそよがせながら、
そしてわらひながら、
手をさしまねいてやつてくる。
その手は夕暮をとぶ蝙蝠のやうだ。
年をとつた死は
蛙のあゆみののろいのを氣にもしないで、
ふはふはとのつかつてゐる。
その蛙は橫からみると金色にかがやいてゐる、
まへからみると二つの眼がとびでて黑くひかつてゐる。
死の顏はしろく、そして水色にすきとほつてゐる。
死の老爺はこんな風にして、ぐるりぐるりと世界のなかをめぐつてゐる。
日輪草
そらへのぼつてゆけ、
心のひまはり草よ、
きんきんと鈴をふりならす階段をのぼつて、
おほぞらの、あをいあをいなかへはひつてゆけ、
わたしの命は、そこに芽をふくだらう。
いまのわたしは、くるしいさびしい惡魔の羂につつまれてゐる。
ひまはり草よ、
正直なひまはり草よ、
鈴のねをたよりにのぼつてゆけ、のぼつてゆけ、
空をまふ魚のうろこの鏡は、
やがておまへの姿をうつすだらう。
[やぶちゃん注:「日輪草」拓次は標題にはルビを振らない。従ってこれを「にちりんさう」と「ひまはりさう」の孰れで読んでいるかは不明である。詩中で一貫して「ひまはりさう」と読んでおり、その可能性の方が強いとは言える。「羂」は罠に同じ意で用いている。狭義に言えば、本字は網や紐のようなもので括る罠という意である。]
ふくらんだ寶玉
ある夕方、一疋のおほきな蝙蝠が、
するどい叫びをだしてかけまはつた。
茶と靑磁との空は
大口をあいてののしり、
おもい憎惡をしたたらし、
ふるい樹のうつろのやうに蝙蝠の叫びを抱きかかへた。
わたしは眺めると、
あなたこなたに、ふさふさとした神のしろい髮がたれてゐた。
幻影のやうにふくらんだ寶玉は、
水蛭のやうにうごめいて、
おたがひの身をすりつけた。
ふくらんだ寶玉はおひおひにわたしの腦をかたちづくつた。
[やぶちゃん注:「水蛭」環形動物門ヒル綱ヒルド科ウマビル(馬蛭) Whitmania pigra のこと。日本全国の水田・池や沼などに広く分布する。体は扁平で長さ一〇~一五センチメートル、幅は体幹の最も広い箇所で一七~二五ミリメートルで背面はオリーブ色、五本の縦線模様が入る。体側縁は淡黄色、腹面は淡色で小さい暗色の斑点が縦に並ぶ。体環は明瞭で体の中央部では一体節に五体環を有する。前吸盤は小さく、その底に口が開く。口には三つの顎があるが小さく、名前からもしばしば吸血蛭として誤解されているが(但し、この「馬」も恐らくは大きいの謂いであろう)、動物の体に傷をつけて吸血することは出来ず、タニシなどの淡水産腹足類などを捕食している(以上は平凡社「世界大百科事典」の記載を参考にした)。]
足をみがく男
わたしは足をみがく男である。
誰のともしれない、しろいやはらかな足をみがいてゐる。
そのなめらかな甲の手ざはりは、
牡丹の花のやうにふつくりとしてゐる。
わたしのみがく桃色のうつくしい足のゆびは、
息のあるやうにうごいて、
わたしのふるへる手は淚をながしてゐる。
もう二度とかへらないわたしの思ひは、
ひばりのごとく、自由に自由にうたつてゐる。
わたしの生の祈りのともしびとなつてもえる見知らぬ足、
さわやかな風のなかに、いつまでもそのままにうごいてをれ。
夜會
わたしの腹のなかでいま夜會がある。
壁にかかる黃色と樺とのカアテンをしぼつて、
そのなかをのぞいてみよう。
まづ第一におほきな眼をむきだして今宵の主人役をつとめてゐるのは焦茶色の年とつた蛇である。
そのわきに氣のきいた接待ぶりをしめしてゐるのは白毛の猿である、
(猿の眼からは火花のやうな眞赤な閃光がちらちら走る)
それから、古びた頭巾をかぶつた片眼の法師、
秋のささやきのやうな聲をたてて泡をふく白い髯をはやした蟹、
半月の影をさびしくあびて、ひとりつぶやいてゐる金の眼のふくろふ、
ゐざりながらだんだんこつちへやつてくるのは足をきられた鰐鮫だ。
するとそよそよとさわだつて、くらいなかからせりあがるのはうす色の幽靈である、
幽靈はかろく會釋して裾をひくとあやしい樂のねがする。
かたりかたりといふ扉のおと、
ちひさな蛙ははねこみ、
すばしつこい蜥蝪はちよろりとはひる。
またしても、ぼさぼさといふ音がして、
鼬めが尻尾でおとづれたのである。
やがて車のかすれがきこえて、
しづかに降りたつてきたのは、あをじろい顏の少女である、
この少女こそ今宵の正客である。
少女はくちをひらいて、おそなはつた詫をいふ。
その馬車の馬のいななきが霧をよんで、ますます夜はくらくなる。
さて何がはじまるのであらう。
[やぶちゃん注:「おそなはつた」は「遅なわった」で、「おそなはつ」はラ行五段活用「おそなはわる(おそなわる)」(古語「おそなはる」は四段)の、「遅くなる」の意の自動詞「遅なはる」の連用形である「おそなわり」の促音便である。]
むらがる手
空はかたちもなくくもり、
ことわりもないわたしのあたまのうへに、
錨をおろすやうにあまたの手がむらがりおりる。
街のなかを花とふりそそぐ亡靈のやうに
ひとしづくの胚珠をやしなひそだてて、
ほのかなる小徑の香をさがし、
もつれもつれる手の愛にわたしのあたまは野火のやうにもえたつ。
しなやかに、しろくすずしく身ぶるひをする手のむれは、
今わたしのあたまのなかの王座をしめて相姦する。
[やぶちゃん注:私はこの最終行を無類に偏愛する。]
靑白い馬
いちはやく草は手をたれて祈りをささげた。
靑白い馬は水にうつる頭の角に恐れて、草のなかをかけめぐり、
そのあへぐ鼻息は死人の匂ひのやうに萬物をくさらせる。
眼は沼のをどみのやうにいきれて泡だち、
足は銀の細工のやうにうすぐもる光をはなつ。
靑白い馬は
黑の馬よろひをつけて、ふたたび水のうへに嘆息をふきかける。
その あたまのうへに芽をだした角は
惡のよろこびにいきいきとして 食物をとる。
怪物
からだは翁草の髮のやうに亞麻色の毛におほはれ、
顏は三月の女鴉のやうに憂鬱にしづみ、
四つの足ではひながらも
ときどきうすい爪でものをかきむしる。
そのけものは ひくくうめいて寢ころんだ。
曇天の日沒は銀のやうにつめたく火花をちらし、
けもののかたちは 黑くおそろしくなつて、
微風とともにかなたへあゆみさつた。
[やぶちゃん注:「翁草」双子葉植物綱キンポウゲ目キンポウゲ科オキナグサ Pulsatilla cernua。葉や花茎など全体的に白い長い毛に被われており。花茎の高さは花期の頃で一〇センチメートル程。花後の種子が付いた白い綿毛が附く頃には三〇~四〇センチメートルになる。花期は四~五月で、暗赤紫色の花を花茎の先端に一個宛附ける。開花の頃はうつむいて咲くが、後に上向きに変わる。花弁に見えるのは萼片で、その外側はやはり白い毛で被われる。白く長い綿毛がある果実の集まった姿を老人の頭に譬え、和名をオキナグサ(翁草)とする。ネコグサという異称もある。全草にプロトアネモニン・ラナンクリンなどを含む有毒植物で、植物体から分泌される汁液に触れれば皮膚炎を引き起こすこともあり、誤食して中毒すれば腹痛・嘔吐・血便のほか痙攣・心停止(プロトアネモニンは心臓毒)に至る可能性もある。漢方においては根を乾燥させたものが白頭翁と呼ばれ、下痢・閉経などに用いられる。本邦では北海道を除く各地に普通に自生していたが、農家によって手入れされていた植生する草地が荒廃したことや開発の進行・山野草としての栽培目的の採取によって各地で激減、現在、環境省レッドリスト絶滅危惧Ⅱ類(VU)に指定されている。(以上はウィキの「オキナグサ」に拠った)。]
花をひらく立像
手をあはせていのります。
もののまねきはしづかにおとづれます。
かほもわかりません、
髮のけもわかりません、
いたいたしく、ひとむれのにほひを背おうて、
くらいゆふぐれの胸のまへに花びらをちらします。
めくらの蛙
闇のなかに叫びを追ふものがあります。
それはめくらの蛙です。
ほのぼのとたましひのほころびを縫ふこゑがします。
あたまをあげるものは夜のさかづきです。
くちなし色の肉を盛る夜のさかづきです。
それはなめらかにうたふ白磁のさかづきです。
蛙の足はびつこです。
蛙のおなかはやせてゐます。
蛙の眼はなみだにきずついてゐます。
窓わく
あをい菊、
きいろい菊、
菊は影のいのちである。
菊はふとつてゆく、
菊は裂けてゆく、
菊は死人の魂をよんで、
おほきな窓わくをつくる。
その窓わくに鳥がきてとまる。
窓わくは鳥と共寢する。
鳥は足をたて、
羽をたて、
くちばしをたてたが、
眼のさきがくらいので、そこにぢつとしてゐる。
永遠は大地の鐘をならしてすぎてゆく。
[やぶちゃん注:これはアンドレイ・タルコフスキイの「鏡」(Зеркало 1975 私はタルコフスキイの、映画のベスト1をと言われれば躊躇なく「鏡」を挙げる)や、つげ義春の「窓の手」(私はつげ義春の、忘れ難い近年の作品――それでも一九八〇年である。彼は一九八七年の「別離」以降、筆を執っていない――の一本をと言われれば躊躇なく「窓の手」を挙げる)……でも……なく……寧ろ、さえも……これはマルセル・デシャンの「フレッシュ・ウィドウ」(Fresh Widow 1920)である、とさえ……]
黑い手を迎へよ
小雨をふらす老樹のうつろのなかに
たましひをぬらすともしびうまれ、
野のくらがりにゐざりゆく昆蟲の羽音をつちかふ。
かなしげに身をふるはせる老樹よ、
しろくほうけたる髮もなく、
風のなかによそほひをつくる形もなく、
ただ、つみかさなる言葉のみがのつかつてゐる。
老樹はめしひの手をあげてものをささげる。
その手はふくろふの眼のやうにうすぐらく、時として金光をおび、
さわだてる梢のいただきにかがやく。
つめたい春の憂鬱
にほひ袋をかくしてゐるやうな春の憂鬱よ、
なぜそんなに わたしのせなかをたたくのか、
うすむらさきのヒヤシンスのなかにひそむ憂鬱よ、
なぜそんなに わたしの胸をかきむしるのか、
ああ、あの好きなともだちはわたしにそむかうとしてゐるではないか、
たんぽぽの穗のやうにみだれてくる春の憂鬱よ、
象牙のやうな手でしなをつくるやはらかな春の憂鬱よ、
わたしはくびをかしげて、おまへのするままにまかせてゐる。
つめたい春の憂鬱よ、
なめらかに芽生えのうへをそよいでは消えてゆく
かなしいかなしいおとづれ。
ヒヤシンスの唄
ヒヤシンス、ヒヤシンス、
四月になつて、わたしの眠りをさましてくれる石竹色のヒヤシンス、
氣高い貴公子のやうなおもざしの靑白色のヒヤシンスよ、
さては、なつかしい姉のやうにわたしの心を看まもつてくれる紫のおほきいヒヤシンスよ、
とほくよりクレーム色に塗つた小馬車をひきよせる魔術師のヒヤシンスよ、
そこには、白い魚のはねるやうな鈴が鳴る。
たましひをあたためる銀の鈴が鳴る。
わたしを追ひかけるヒヤシンスよ、
わたしはいつまでも、おまへの眼のまへに逃げてゆかう。
波のやうにとびはねるヒヤシンスよ、
しづかに物思ひにふけるヒヤシンスよ。
ジヤスミンのゆめ
うすあをいふぢいろのはだへのもや、
うつとりと上気した女へびの眼のやうに
みだらにしたたる香氣をはく。
つよいつよいジヤスミンのねむりの香氣、
ちやうどそれはひたひをおさへてうなだれる尼僧のひとりごと、
ああ つよいつよいねむりの香氣。
母韻の秋
ながれるものはさり、
ひびくものはうつり、
ささやきとねむりとの大きな花たばのほとりに
しろ毛のうさぎのやうにおどおどとうづくまり、
寶石のやうにきらめく眼をみはつて
わたしはかぎりなく大空のとびらをたたく。
濕氣の小馬
かなしいではありませんか。
わたしはなんとしてもなみだがながれます。
あの うすいうすい水色をした角をもつ、
小馬のやさしい背にのつて、
わたしは山しぎのやうにやせたからだをまかせてゐます。
わたしがいつも愛してゐるこの小馬は、
ちやうどわたしの心が、はてしないささめ雪のやうにながれてゆくとき、
どこからともなく、わたしのそばへやつてきます。
かなしみにそだてられた小馬の耳は、
うゐきやう色のつゆにぬれ、
かなしみにつつまれた小馬の足は
やはらかな土壤の肌にねむつてゐる。
さうして、かなしみにさそはれる小馬のたてがみは、
おきなぐさの髮のやうにうかんでゐる。
かるいかるい、枯草のそよぎにも似る小馬のすすみは、
あの、ぱらぱらとうつ Timbale のふしのねにそぞろなみだぐむ。
[やぶちゃん注:「うゐきやう色」「うゐきやう」はフェンネル(Fennel)。セリ目セリ科ウイキョウ Foeniculum vulgare。茴香。花は黄白色であるが、この場合、生薬として知られる実の薄い茶褐色を指しているように私は思われる。
「Timbale」先行する「慰安」に既出。フランス語で打楽器のティンパニのこと。ティンパニは英語では“timpani”、本来の語源であるイタリア語では“timpani ”又は“timpano”と綴る。]
森のうへの坊さん
坊さんがきたな、
くさいろのちひさなかごをさげて。
鳥のやうにとんできた。
ほんとに、まるで鴉のやうな坊さんだ、
なんかの前じらせをもつてくるやうな、ぞつとする坊さんだ。
わらつてゐるよ。
あのうすいくちびるのさきが、
わたしの心臟へささるやうな氣がする。
坊さんはとんでいつた。
をんなのはだかをならべたやうな
ばかにしろくみえる森のうへに、
ひらひらと紙のやうに坊さんはとんでいつた。
草の葉を追ひかける眼
ふはふはうかんでゐる
くさのはを、
おひかけてゆくわたしのめ。
いつてみれば、そこにはなんにもない。
ひよりのなかにたつてゐるかげろふ。
おてらのかねのまねをする
のろいのろい風あし。
ああ くらい秋だねえ、
わたしのまぶたに霧がしみてくる。
喪服の魚
透明の水はうすあをい魚をはらみました。
ともしびはゆらゆらとして星のまばたく路をあゆみつづける。
こがねいろの波は香氣をふき、
あさみどりの葉はさびしいこゑをあげる。
ゑみわれる微笑の淵におぼれる魚のむれは、
たたまれてゐる秋の陶醉のなかににげてゆきます。
黃色い帽子の蛇
曉の香料
みどりの毛、
みどりのたましひ、
あふれる騷擾のみどりの笛、
木の閒をけむらせる鳥の眼のいかり、
あけぼのを吹く地のうへに匍ひまはるみどりのこほろぎ、
波のうへに祈るわたしは、
いま、わきかへるみどりの香料の鐘をつく。
魚の祭禮
人間のたましひと蟲のたましひとがしづかに抱きあふ五月のゆふがた、
そこに愛につかれた老婆の眼が永遠にむかつてさびしい光をなげかけ、
また、やはらかなうぶ毛のなかににほふ處女の肌が香爐のやうにたえまなく幻想を生んでゐる。
わたしはいま、窓の椅子によりかかつて眠らうとしてゐる。
そのところへ澤山の魚はおよいできた、
けむりのやうに また あをい花環のやうに。
魚のむれはそよそよとうごいて、
窓よりはひるゆふぐれの光をなめてゐる。
わたしの眼はふたつの雪洞のやうにこの海のなかにおよぎまはり、
ときどき その溜塗のきやしやな椅子のうへにもどつてくる。
魚のむれのうごき方は、だんだんに賑かさを増してきて、
まつしろな音樂ばかりになつた。
これは凡てのいきものの持つてゐる心靈のながれである。
魚のむれは三角の帆となり、
魚のむれはまつさをな森林となり、
魚のむれはまるのこぎりとなり、
魚のむれは亡靈の形なき手となり、
わたしの椅子のまはりに いつまでもおよいでゐる。
[やぶちゃん注:「溜塗」漆塗りの一種で、朱またはベンガラで漆塗りをして乾燥させた後、透漆でさらに上塗りしたものをいう。半透明の美しさがある。「花塗」ともいう。]
黃色い帽子の蛇
ながいあひだ、
草の葉のなかに笛をふいてゐたひとりの蛇、
草の葉の色に染められて化粧する蛇のくるしみ、
夜の花をにほはせる接吻のうねりのやうに、
火と焰との輪をとばし、
眞黃色な、靑ずんだ帽子のしたに、
なめらかな銀のおもちやのやうな蛇の顏があらはれた。
きれをくびにまいた死人
ふとつてゐて、
ぢつとつかれたやうにものをみつめてゐる顏、
そのかほもくびのまきものも、
すてられた果實のやうにものうくしづまり、
くさかげろふのやうなうすあをい息にぬれてゐる。
ながれる風はとしをとり、
そのまぼろしは大きな淵にむかへられて、
いつとなくしづんでいつた。
さうして あとには骨だつた黑いりんかくがのこつてゐる。
手のきずからこぼれる花
手のきずからは
みどりの花がこぼれおちる。
わたしのやはらかな手のすがたは物語をはじめる。
なまけものの風よ、
ものぐさなしのび雨よ、
しばらくのあひだ、
このまつしろなテエブルのまはりにすわつてゐてくれ、
わたしの手のきずからこぼれるみどりの花が、
みんなのひたひに心持よくあたるから。
はにかむ花
黃金の針のちひさないたづら、
はづかしがりのわたしは、
りやうはうのほほをほんのりそめて、
そうつとかほをたれました。
黃金の針のちひさないたづら、
わたしは、わたしは、
ああ やはらかいにこげのなかに顔をうめるやうに、
だんだんに顔がほてつてまゐります。
[やぶちゃん注:「にこげ」「和毛」「毳」で、鳥獣の柔らかい毛。また、人の柔らかい毛。産毛のこと。私は個人的にこの言葉が大好きだが、かつて亡き母にそれを言ったら「鍋の煮焦げみたいで厭だわ」と切り返され、何だか、妙に淋しくなったのを思い出す。]
蛙の夜
いつさいのものはくらく、
いつさいのおとはきえ、
まんまんたる闇の底に、
むらがりつどふ蛙のすがたがうかびでた。
かずしれぬ蛙の口は、
ぱく、ぱく、ぱく、ぱく、…… とうごいて、
その口のなかには一つ一つあをい星がひかつてゐる。
年寄の馬
わたしは手でまねいた、
岡のうへにさびしくたつてゐる馬を、
岡のうへにないてゐる年寄の馬を。
けむりのやうにはびこる憂鬱、
はりねずみのやうに舞ふ苦悶、
まつかに燒けただれたたましひ、
わたしはむかうの岡のうへから、
やみつかれた年寄の馬をつれてこようとしてゐる。
やさしい老馬よ、
おまへの眼のなかにはあをい水草のかげがある。
そこに、まつしろなすきとほる手をさしのべて、
水草のかげをぬすまうとするものがゐる。
無言の顏
ちからをまきおこすともしびの裸形のかげに
ひとり想念のいただきにたふれふす。
永遠をあゆむ無言の顏。
[やぶちゃん注:当該詩は「178」右頁で左頁に以下のように、ハトロン紙を挟んで末尾の「目次」で『筆蹟(グラブア版)・大手拓次筆』とある本詩(題名はなし)の自筆画像が入る(頁としては数えられておらず、次の「毛がはえる」は左頁で「179」とノンブルが振られる)。以下に示す。拓次の筆跡は一見、優しい柔らかで優しい、少し可愛い嫋やかささえ感じさせる筆遣いで、私は非常に好きである。
ちからをまきおこす
ともしびの裸形の
かげに
ひとり想念の
いただきにたふれ
ふす。
永遠をあゆむ
無言の
かを
とあり、クレジットと署名は、
大正九年
七月十八日 大手拓次
と思われる。]
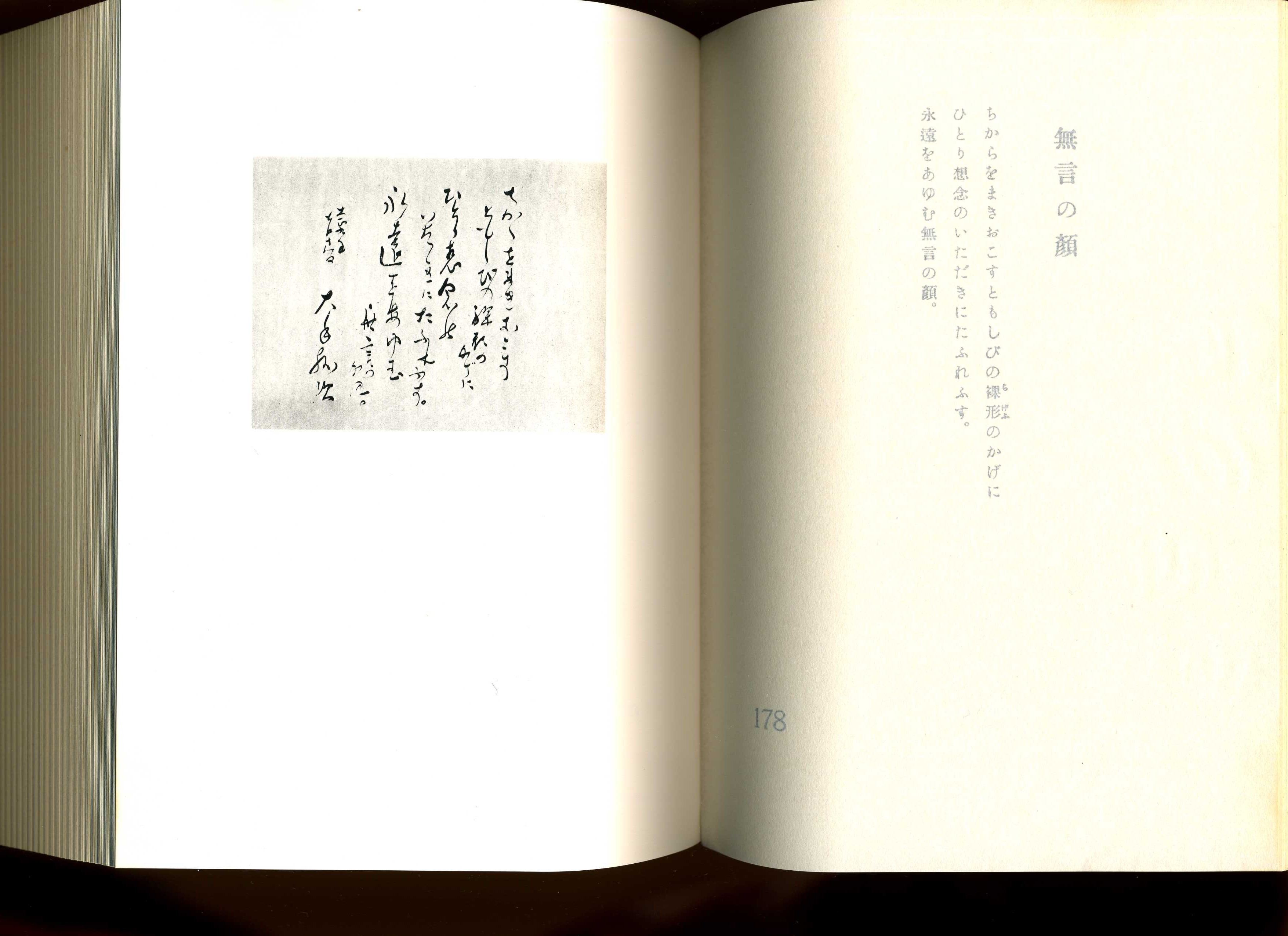
毛がはえる
あたまに毛がはえる。
手にも毛がはえる。
あたまのなかのはらんでゐる水母に、
ぼうつとした月がさす。
舌なめづりをする妄念が
うわうわとうかみだす。
雜草の脣
たふれて手をなげだし、
いぎたなくねそべつて、
こゑをひそめ、かたちをひそめ、
まるく ぐねぐねと海蛇のやうにねむりをむさぼる、
この定身のものをこふ憂ひのねがひ、
秋の日の空をかける小鳥のながい口笛、
雜草の手のひらは雲のやうにのびあがり、
蜘蛛手のやうにたぎりたつあをい花びらのうへにおほひかさぶる。
くろくのびちぢむ雜草の脣は、
まるまるとゆたかな笑ひをたたへて、
なまめかしくおきあがり、
あたりにはびこるともがらのために水をぬらす。
[やぶちゃん注:「定身」はママ。正しくは「ぢやうしん」である。但しそれでも、この行は意味が採りにくい。何故なら「定身」という一般的な熟語はないからである。真言宗では弘法大師の遺体のことをかく呼称するのは聴いたことがあるから、少なくとも私は初読時、亡くなった聖人の遺体を想像した(それは大手拓次の詩想にもたまたま合致したから)。従って私は勝手にこの行を、
この雑草が孕んでいる、この、聖者の御遺体を乞うという、病みついた愁いの希求
という意味で採っている。大方の御批判を俟つものである。]
小用してゐる月
濃いみどりいろの香水のびん、
きもちのいい細長いこのびんのほとりに、
すひよせられてうつとりとゆめをみるなまけもの。
びんのあをさは月のいろ、
びんのあをさは小用してゐる月のしかめづら、
びんのあをさは野菜畑の月のいろ、
ねむさうなあかい眼をしてあるく月のいろ、
びんのあをさは胡弓のねいろ、
びんのあをさは小魚の背につく虫のうた、
びんのなかには Jacinthe の
つよいかをりが死のをどりををどつてゐる。
[やぶちゃん注:「Jacinthe」フランス語でヒヤシンスのこと。女性名詞。単子葉植物綱ユリ目ユリ科ヒヤシンス Hyacinthus orientalis。ヒアシンスの名はギリシャ神話の美青年ヒュアキントスに由来する。同性愛者であった彼は、愛する医学の神アポロンと一緒に円盤投げに興じていたが、その楽しそうな様子を見ていた、やはりヒュアキントスに恋慕していた西風の神ゼピュロスが嫉妬して風を起こし、アポロンが投げた円盤はそれに煽られてヒュアキントスの額を直撃、亡くなってしまう。その時、流れた大量の血からヒヤシンスは生まれたとされる。花言葉は「悲しみを超えた愛」(以上はウィキの「ヒアシンス」に拠った)。]
水草の手
わたしのあしのうらをかいておくれ、
おしろい花のなかをくぐつてゆく花蜂のやうに、
わたしのあしのうらをそつとかいておくれ。
きんいろのこなをちらし、
ぶんぶんとはねをならす蜂のやうに、
おまへのまつしろいいたづらな手で
わたしのあしのうらをかいておくれ、
水草のやうにつめたくしなやかなおまへの手で、
思ひでにはにかむわたしのあしのうらを
しづかにしづかにかいておくれ。
彫金の盗人
おめおめとたちさわぐあをい蓮華の花びら、
かぎりなく耳をふさいでをれば、
あをさびた彫金のちひさな花びらは、
餌をもとめる魚のやうにさびしさにおとろへる。
わたしは形のよいわたしの耳をおさへて、
たましひの寂びのとほのくのを待つてゐる。
あをくさびた佛の眼のやうなこの花びらは、
蘆の葉のなかに浮く木精のやうに巢をもとめてゐる。
わたしの耳はかなしみの泡をふき、
おとろへなげく花びらのたましひを盗みかくす。
三本足の顏
闇がわらふ、
闇がわらふ、
くつ くつ くつとわらふ。
しわくちやなわらひ、
まつしろい、けれど靑みのどんどんながれこむおまへの顏、
まるで三本の足からできてゐるやうだ。
まつくろい きれいなおまへの髮のなかでは、
しじゆうさびしさうな松蟲がないてゐる。
やがて、おまへの眼が
顏いつぱいに大きくなりかかつてきたから、
わたしはこつそりと逃げてしまつた。
[やぶちゃん注:「日本詩人愛唱歌集 詩と音楽を愛する人のためのデータベース」内の「藍色の蟇」(白鳳社版「大手拓次全集」の第一巻及び第二巻)では、五行目と六行目の間に「おまへの顔は、」と入っている。以下にそれを正字化して、総ルビの関係からルビを入れて挿入した全詩を示しておく。
三本足の顏
闇がわらふ、
闇がわらふ、
くつ くつ くつとわらふ。
しわくちやなわらひ、
まつしろい、けれど靑みのどんどんながれこむおまへの顏、
おまへの顏は、
まるで三本の足からできてゐるやうだ。
まつくろい きれいなおまへの髮のなかでは、
しじゆうさびしさうな松蟲がないてゐる。
やがて、おまへの眼が
顏いつぱいに大きくなりかかつてきたから、
わたしはこつそりと逃げてしまつた。
私の所持する抜粋版諸本にはこの「三本足の顏」が所収しないので確認不能であるが、ここは「おまへの顏は、」がないとジョイントがすこぶる悪い。これが正しいように私には思われる。]
鼻を吹く化粧の魔女
水仙色のそら、
あたらしい智謀と靈魂とをそだてる暮方の空のなかに、
こころよく水色にもえる眼鏡、
その眼鏡にうつる向うのはうに
豐麗な肉體を持つ化粧の女、
しなやかに ぴよぴよとなくやうな女のからだ、
ほそい にほはしい線のゆらめくたびに、
ぴよぴよとなまめくこゑの鳴くやうなからだ、
ねばねばしたまぼろしと
つめたくひかる放埓とが、
くつきりとからみついて、
あをくしなしなと透明にみえる女のからだ、
ものごしの媚びるにつれて、
ものかげの夜の鳥のやうに、
ぴよぴよと鳴くやうな女のからだ、
やさしいささやきを賣る女の眼、
雨のやうに情念をけむらせる女の指、
闇のなかに高い香料をなげちらす女の足の爪、
濃化粧の魔女のはく息は、
ゆるやかに輪をつくつて、
わたしのつかれた眼をなぐさめる。
あをざめた僧形の薔薇の花
もえあがるやうにあでやかなほこりをつつみ、
うつうつとしてあゆみ、
うつうつとしてわらつてゐた
僧形のばらの花、
女の肌にながれる乳色のかげのやうに
うづくまり たたずみ うろうろとして、
とかげの尾のなるひびきにもにて、
おそろしいなまめきをひらめかしてうかがひよる。
すべてしろいもののなかに
かくれふしてゆく僧形のばらの花、
ただれる憂鬱、
くされ とけてながれる惱亂の花束、
美貌の情欲、
くろぐろとけむる叡智の犬、
わたしの兩手はくさりにつながれ、
ほそいうめきをたててゐる。
わたしのまへをとほるのは、
うつくしくあをざめた僧形のばらの花、
ひかりもなく つやもなく もくもくとして、
とほりすぎるあをざめたばらの花。
わたしのふたつの手は
くさりとともにさらさらと鳴つてゐる。
嫉妬の馬
かかへるやうな大きな幻想樂、
わたしのからだは いま つぶやきの色をかへ、
あてどもなく夢の穴をほる。
濃いむらさきの細い角と
眞黃色な蹄とをもつた女體の馬は、
わたしの魂をおしつぶしおしつぶし、
絹のきもののなかをかけめぐる。
おまへは毛虫のやうな妖怪だ!
うつくしいふにやふにやした妖怪だ!
僧衣の犬
くちぶえのとほざかる森のなかから、
はなすぢのとほつた
ひたひにしわのある犬が
のつそりとあるいてきた。
犬は人間の年寄のやうに眼をしめらせて、
ながい舌をぬるぬるとして物語つた。
この犬は、
その身にゆつくりとしたねずみいろの僧衣をつけてゐた。
犬がながい舌をだして話しかけるとき、
ゆるやかな僧衣のすそは閑子鳥のはねのやうにぱたぱたした。
あかい あかい 火のやうな空のわらひ顏、
僧衣の犬はひとこゑもほえないで默つてゐた。
罪惡の美貌
めんめんとしてつながりくる火の柱、
異形のくろい人かげは火のなかにみだれあうて、
犬の遠吠のやうにうづまく。
くろいからだに
眞珠の環をかざり、
あをいサフィイルの頸環をはめ、
くちびるに眞紅の眼をにほはせ、
とろ火のやうにやうやうともえる火の柱のなかに、
あるひは めらめらとはひのめる火の蛇のうそぶきに、
罪の美貌の海鼠は
いよいよくさり、
いよいよかがやき
いよいよ美しく海にしづむ。
[やぶちゃん注:視認可能な句読点を表記した。「眞珠の環をかざり、」の読点は他と異なり、殆んどカンマそっくりでしかも有意に薄く掠れているが、読点として採った。「サフィイル」サファイア。青玉。フランス語の“saphir”忠実な音訳(英語は“sapphire”)。]
手の色の相
手の相は暴風雨のきざはしのまへに、
しづかに物語りをはじめる。
赤はうひごと、
黃はよろこびごと、
紫は知らぬ運動の轉回、
靑は希望のはなれるかたち、
さうして銀と黑との手の色は、
いつはりのない狂氣の道すぢを語る。
空にかけのぼるのは銀とひわ色のまざつた色、
あぢさゐ色のぼやけた手は扉にたつ黃金の王者、
ふかくくぼんだ手のひらに、
星かげのやうなまだらを持つのは死の豫言、
栗色の馬の毛のやうな艷つぽい手は、
あたらしい僞善に耽る人である。
ああ、
どこからともなくわたしをおびやかす
ふるへをののく靑銅の鐘のこゑ。
香料の顏寄せ
月下香(Tubereuse)の香料
手をひろげてものを抱く、
しろく匍ひまはる化生のもの。
それは舟のうへのとむらひの歌、
あたらしい憂ひをのせてながれゆく、
身重の夜の化生のもの。
[やぶちゃん注:「月下香(Tubereuse)」「げつかかう(げっかこう)」と読むが、ここはフランス語を附してあるので「チュべローゼ」と読むべきか。但し、綴りは“Tubéreuse”が正しい(創元文庫版はアクサンテギュなし、岩波文庫版はあり)。単子葉植物クサスギカズラ目クサスギカズラ科リュウゼツラン亜科チューベローズ Polianthes tuberosa 。メキシコ原産。晩春に鱗茎から発芽、草丈は一メートルほどまで伸びる。八月頃、白い六弁花からなる穂状花序をつける。花穂は四五センチメートルにも達し、エキゾチックな甘いフローラル系の強い香りを放つ。特に夜間に香りが強くなる。園芸種は八重咲きのものが多いが、一重咲きの方が香りが高い(戦中に流行った中国の歌謡曲「夜来香」で知られたものと混同されたが、あれは蔓性植物であるガガイモ科テロスマ属 Telosma cordata で別種である)。抽出物を香水に用いるため、ハワイや熱帯アジアなどで栽培され、現在も現地ではレイや宗教行事用に用いられている。ヴィクトリア朝時代のハワイでは葬儀花とされた。種小名“tuberosa”はラテン語で「ふくらんだ・塊根状の」の意で、球根を形成することに由来する。異名にオランダ水仙(私の所持する仏和辞典は意味にそう書く)があるが、これは正統な単子葉類クサスギカズラ目ヒガンバナ科ヒガンバナ亜科スイセン属
Narcissus の、ある複数の種を通称する異名でもあり、また、この「月下香」という和名も現在では殆んど使われないものと思われる(以上は主にウィキの「チューベローズ」に拠った)。]
ベルガモツトの香料
ほろにがい苦痛の滋味をあたへる愛戀、
とびらはそこに閉ざされ、
わたしの步みをしぶりがちにさせる。
はりねずみの刺に咲く美貌の花のように
戀情のうろこをほろほろとこぼしながら、
かぎりなくあまい危ふさのなまめかしさを强ひてくる。
[やぶちゃん注:「ベルガモツト」双子葉植物綱ムクロジ目ミカン科ミカン属ベルガモット Citrus × bergamia (学名では自然(交)雑種の場合、自然(交)雑種は(交)雑種の印である小文字の乗法記号 × 印を附し、種間雑種の場合はこの例のように種の前に、属間雑種の場合は属の前に附す)。以下、ウィキの「ベルガモット」によれば、ミカン科の常緑高木樹の柑橘類で主産地はイタリア・モロッコ・チュニジア・ギニア。「ベルガモット」の名はイタリアのベルガモからとも、また、トルコ語で「梨の王」の意となる“Beg armudi”からとも言われる。コロンブスがカナリア諸島で発見してスペイン・イタリアに伝えたとされる。近年のDNA解析によってダイダイ(Citrus aurantium)とマンダリンオレンジ(Citrus reticulata)の交雑種であると推定されている。ベルガモットの果実は生食や果汁飲料には使用されず、専ら精油を採取し、香料として使用される。紅茶のアールグレイはベルガモットで着香した紅茶であり、フレッシュな香りをもつためにオーデコロンを中心に香水にもしばしば使用される。なお、シソ科に同名のベルガモット(Monarda didyma。和名タイマツバナ)というハーブがある。これは葉がベルガモットの精油と良く似た香りを持つことから同じ名前を持っている。樹高は2~5メートル程になり、葉は他の柑橘類と同様、表面に光沢があり、他の柑橘類よりもやや細長い形をしていて先が尖っている。夏に芳香のある五枚の花びらを持つ白い花を咲かせる。果実は蔕の部分が出っ張った洋ナシ形か若しくはほぼ球形を成し、凹凸がある。果実の色は最初は緑色であるが、熟すにつれて徐々に黄色・橙色へと変化する。果実の果皮から精油が得られ、これを香料として使用する。果実はまだ果皮が緑色をしている十一月から黄色く熟す三月にかけて収穫され、圧搾法で抽出、黄色を帯びた精油を得る。ほかの柑橘類の精油がd-リモネンを主成分としているのと大きく異なり、ベルガモットの精油はl-リナロールとl-酢酸リナリルを主成分とする。心理効果(鎮静と高揚の両方の効果を持つ)・消化器系不調改善・皮膚殺菌作用・防虫効果を持つが、強い皮膚刺激性と光毒性を有するため日中の使用は注意が必要である、とある。総ての点でこの詩に相応しい印象を私は受ける。]
ナルシサスの香料
くらやみを裂くひびきのやうに、
絹のすれあふささやきのやうに、
わたしの心を驚きと祕密へひきこむ手管、
そこにちひさなまつしろい小犬がゐて、
にこにこわらひながら、
迷ひ入るわたしの背中に黃色い息をはきかけた。
わたしはぶるぶるとふるへた。
[やぶちゃん注:「ナルシサス」単子葉植物クサスギカズラ目ヒガンバナ科ヒガンバナ亜科スイセン連スイセン属 Narcissus に属するスイセン類の総称。狭義には和水仙の基本種であるスイセン Narcissus tazetta(ナルシサス・タゼッタ)や、その変種であるニホンズイセン Narcissus tazetta var. chinensis (ナルシサス・タゼッタ・キネンシス:“chinensis”は「中国原産の」の意。)を単にスイセンと呼称する。中でも、スイセン(房咲き水仙) Narcissus tazetta やクチベニズイセン Narcissus poeticus(ギリシア神話では学名の由来ともなっているナルキッソスの生まれ変わりとされる種で、種小名“poeticus”は「詩人の」の意)やジョンキルスイセン(Narcissus jonquilla cv.:“cv.”は“cultivar”(栽培変種植物)の略で園芸品種であることを示す。種小名“jonquilla”はフランス語(若しくは近世ラテン語)で黄水仙を指す“jonquille”に由来する。)などの香りは実際に抽出されて香水の原料にもなっており、知られた“Narcisse Noir”(「ナルシス・ソワール」:一九一一年発売。調香師エルネスト・ダルトロフ。本邦では「黒水仙」の名で知られる。)や Chanel“No.5”(一九二一年発売。調香師エルネスト・ボー。)にも用いられている。さらにその甘い香りには優れた鎮静作用があるとも言われる。]
鈴蘭の香料
みどりのくものなかにすむ魚のあしおと、
過去のとびらに名殘の接吻をするみだれ髮、
うきあがる紫紺のつばさ、
思ひにふける女鳥はよろめいた。
まつさをな鉤をひらめかし、
とほくたましひの宿をさそふ女鳥、
もやもやとしたなやましいおまへの言葉の好ましさ、
しろい月のやうにわたしのからだをとりまくおまへのことば、
霧のこい夏の夜のけむりのやうに、
つよくつよくからみつく香のことばは、
わたしのからだにしなしなとふるへついてゐる。
[やぶちゃん注:太字「しなしな」は底本では傍点「ヽ」。]
香料のをどり
木立をめぐる鬼面の闇、
河豚のやうなうめきをそよりたてて、
ものしづかにのぼる新月、
饐えたるものかげは草のやうに生ひたち、
ふりみだす髮、
かきならす髮、
よろこびにおどろく髮、
野生の馬のやうに香氣ある肢體をながして
うつりゆく影のすがたは、
いよいよふくらみ形をこめてつぶやく。
香料の寶石、
香料の寢間、
地のうへをはふ祕密の息のやうに、
あでやかにをどりながら、
墓石に巢くふ小鳥のかげをひらめかす。
[やぶちゃん注:「そよりたてて」やや特異な用法である。「そより」は副詞で、多く「と」を伴って、物が軽く触れあって立てる、幽かな音を表わす語である。一般には「一叢の修竹が、そよりと夕風を受けて、余の肩から頭を撫でたので」(夏目漱石「草枕」のように、風が静かに吹き過ぎていくさまをいうことが多い。ここではフグの絞り立てるような鳴き声(フグは釣り上げた時など危険を感じると威嚇のためにグーっと鳴く)を表現しているものらしい。水泳中に、怒って鳴きながらパンパンに膨れ上がったクサフグ(恐らくは子を守るために)に腰を嚙みつかれた経験のある(こういう経験者は多くはないと思われる)私にはすこぶる自然な表現に読めるのである。]
すみれの葉の香料
ものすごくしめりをおびて
わきおこる惱亂の靑蜘蛛、
柩車のすべりゆくかげとかたちと、
よりそひ かさなりあつて、
ながい吐息をもらす。
時をたべつくし、
亡びをよみがへらせる思ひでの牝犬。
[やぶちゃん注:「靑蜘蛛」単なる大手拓次のイメージの産物であるのかもしれないが、イメージ対象としては実在する。クモ綱クモ目オオツチグモ科コバルトブルー(コバルトブルータランチュラ) Haplopelma lividum Smith, 1996 である。ウィキの「コバルトブルータランチュラ」によれば、体長は♂で四センチメートル、♀で六センチメートル、脚を含めた全長(レッグ・スパン)は♂が八センチメートル、♀は十二センチメートル。体色は金属光沢のある青・緑青色などの変異がある。地中に棲む。現在はペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されているが、性質が荒い上に動きが非常に素早く、毒性も強いため扱いには注意が必要、とある(画像が見たい方のみ自己責任で以下をクリック。グーグルの「Haplopelma lividum」の画像検索。確かに怪しくソソる色ではある)。]
佛蘭西薔薇の香料
まつしろな毛なみをうたせて
はひまはる秋の小兎、
うさぎの背にのびる美貌のゆめ、
ふむちからもなくうなだれてあゆみ、
つつしみの嫉妬をやぶり、
雨のやうにふる心のあつかましさに
いろどりの種をまいて、
くる夜の床のことばをにほはせる。
[やぶちゃん注:「佛蘭西薔薇」フランス原産の薔薇であるラ・フランス“La France”のこと。ピンクの花弁は四十五枚とも言われ、幾重にも重なる大輪である。フルーティーな香りが強い。一八六七年にリヨンの育種家ジャン=バティスト・ギヨ・フィス(Jean-Baptiste Guillot fils 一八二七年~一八九三年)により発表されたハイブリッド・ティーローズ(四季咲きで大輪一輪咲きの品種のこと。現代のバラの切り花一輪咲きは、殆んどがこの系統)第1号のバラである。本邦では明治から大正時代にかけては「天地開」と呼ばれていた。因みに、このラ・フランス誕生以前のバラを「オールドローズ」(Old Roses)、誕生以降のバラを「モダンローズ」(Modern Roses)と呼称するのだそうである。以上はウィキの「ラ・フランス(バラ)」に拠った。

上の画像は同ウィキにある Kurt Stüber 氏の、
Species: Rosa sp.
Family: Rosaceae
Cultivar: La France, Guillot Fils 1867 Image No. 165
の写真でクリエイティブ・コモンズ利用許諾作品である。また、グーグル画像検索「La France rose」も参照されたい。]
香料の墓場
けむりのなかに、
霧のなかに、
うれひをなげすてる香料の墓場、
幻想をはらむ香料の墓場、
その墓場には鳥の生き羽のやうに亡骸の言葉がにほつてゐる。
香料の肌のぬくみ、
香料の骨のきしめき、
香料の息のときめき、
香料のうぶ毛のなまめき、
香料の物言ひぶりのあだつぽさ、
香料の身振りのながしめ、
香料の髮のふくらみ、
香料の眼にたまる有情の淚、
雨のやうにとつぷりと濡れた香料の墓場から、
いろめくさまざまの姿はあらはれ、
すたれゆく生物のほのほはもえたち、
出家した女の移り香をただよはせ、
過去へとびさる小鳥の羽をつらぬく。
Wistaria の香料
銀のはりねずみをあそばせて、
なめらかな象牙の珠をころがすやうに、
孤獨な物思ひはすることもなくたたずんでゐる。
いううつはくものあゆみのやうにひろがり、
竹笛をならすうたがひがしのびよる。
[やぶちゃん注:「Wistaria」藤の花。真正バラ類であるマメ目マメ科マメ亜科フジ連フジ Wisteria floribunda である。標準和名はノダフジ(野田藤)とも。フランスのファッション・ブランド LANVIN(ランバン:一八八九年創業。)の“ÉCLAT D’ARPÈGE”(エクラ・ドゥ・アルページュ:「アルペジオ(分散和音)の華麗さ」といった意味か。)などには、このウィステリアの香料が使われているそうである。今度、買ってみよっと!]
香料の顏寄せ
とびたつヒヤシンスの香料、
おもくしづみゆく白ばらの香料、
うづをまくシネラリヤのくさつた香料、
夜のやみのなかにたちはだかる月下香の香料、
身にしみじみと思ひにふける伊太利の黑百合の香料、
はなやかな著物をぬぎすてるリラの香料、
泉のやうに淚をふりおとしてひざまづくチユウリツプの香料、
年の若さに遍路の旅にたちまよふアマリリスの香料、
友もなくひとりびとりに戀にやせるアカシヤの香料、
記憶をおしのけて白いまぼろしの家をつくる絲杉の香料、
やさしい肌をほのめかして人の心をときめかす鈴蘭の香料。
[やぶちゃん注:「シネラリヤ」キク亜綱キク目キク科キク亜科ペリカリス属シネラリア Pericallis × hybrida。北アフリカ・カナリヤ諸島原産。冬から早春にかけて開花、品種が多く、花の色も白・靑・ピンクなど多彩。別名フウキギク(富貴菊)・フキザクラ(富貴桜)。英名を“Florist's Cineraria”と言い、現在、園芸店などでサイネリアと表示されるのは英語の原音シネラリアが「死ね」に通じることから忌まれるためである。しかし乍ら、“Cineraria”という語自体が“cinerarium”、実に「納骨所」の複数形であるから、“Florist's Cineraria”とは英名自体が「花屋の墓場」という「死の意味」なのである――余りに美しすぎて他の花が売れなくなるからか? グーグル画像検索「Cineraria」。
「月下香」「月下香(Tubereuse)の香料」に既注。
「伊太利の黑百合」これは私の憶測であるが(私はフローラ系は守備範囲でない)、所謂、我々の知っているクロユリ(単子葉植物綱ユリ目ユリ科バイモ属クロユリ
Fritillaria camschatcensis)とは、別な種を指しているように思われる(分布域からみてイタリアには植生しないのではないか)。識者の御教授を乞う。
「絲杉」裸子植物門マツ綱マツ目ヒノキ科イトスギ属 Cupressus。ギリシア神話では美少年キュパリッソスが姿を変えられたのがこの木とされ、また、イエス・キリストが磔にされた十字架はイトスギで作られたものという伝説がある。花言葉は死・哀悼・絶望。欧米では上記のキュパリッソスの逸話から、死や喪の象徴とされる。文化や宗教との関係が深く、古代エジプトや古代ローマでは神聖な木として崇拝されていたほか、キプロス(英語:Cyprus)島の語源になったともされる。イタリアイトスギ Cupressus sempervirens から精製した香料はウッディーで軽いスパイシー感を持ち、主に男性用香水として用いられる(ウィキの「イトスギ」を一部参照した)。]
白い狼
湖上をわたる狐
みなぎる湖上のうへに
爪をといで啼きわたる狐、
まどろみの窓をひらいて
とほく冬の國へ啼いてゆく狐、
その肌に刺の花をうゑつけて、
ゆたかに蒼茫の衣をぬぎかへす。
[やぶちゃん注:「蒼茫」は、ここでは即物的には、ほの蒼暗く妖しいものである妖狐の銜えた衣のイマージュであろうが、同時に、そこを透けて対岸も見えぬ妖しい幻想の湖水の、見渡す限り青々と広がるそれをも、同時にそこに重層化させているのであろう。]
灰色の蝦蟇
ちからなくさめざめとうかみあがり、
よれからむ祕密のあまいしたたりをなめて、
ひかげのやうなうすやみに、
あをい灰色の蝦蟇はもがもがとうごいた。
おほきなこぶしのやうな蝦蟇だ、
うみのなかのなまこのやうな
どろどろにけむりをはきだす蝦蟇だ、
たましひのゆめを縫つてとびあるく蝦蟇だ。
その肌は ざらざらで、
そのくちびるはくろくただれ、
しじゆうびつしよりとぬれてゐる。
まよなかに黃色い風がふくと、
この灰色の蝦蟇は
みもちのやうにふくらんでくるのだ。
蝦蟇よ おまへのからだを大事にして
そのくるしみをたへしのんでくれ。
さよなら さよなら
わたしのすきなおほきな蝦蟇よ。
[やぶちゃん注:「みもち」身持ち。妊娠すること。]
舞ひあがる犬
その鼻をそろへ、
その肩をそろへ、
おうおうとひくいうなりごゑに身をしづませる二疋の犬。
そのせはしい息をそろへ、
その眼は赤くいちごのやうにふくらみ、
さびしさにおうおうとふるへる二ひきの犬。
沼のぬくみのうちにほころびる水草の肌のやうに、
なんといふなめらかさを持つてゐることだらう、
つやつやと月夜のやうにあかるい毛なみよ、
さびしさにくひしばる犬は
おうおうとをののきなきさけんで、
ほの黃色い夕闇のなかをまひあがるのだ。
しろい爪をそろへて、
ふたつの犬はよぢのぼる蔓草のやうに
ほのきいろい夕闇の無言のなかへまひあがるのだ。
そのくるしみをかはしながら、
さだめない大空のなかへゆくふたつの犬よ、
やせた肩をごらん、
ほそいしつぽをごらん、
おまへたちもやつぱりたえまなく消えてゆくものの仲閒だ。
ほのきいろい夕空のなかへ、
ふたつのものはくるしみをかはしながらのぼつてゆく。
靑狐
あをぎつねはあしをあげた、
うすねずみいろの毛ばだつた足をふうはりとあげた、
そのあしのゆびにもさだめなくみなぎる
いきもののかなしみ。
あをぎつねはしらじらとうす眼をあけて、
あけがたの月をながめた。
林檎料理
手にとつてみれば
ゆめのやうにきえうせる淡雪りんご、
ネルのきものにつつまれた女のはだのやうに
ふうはりともりあがる淡雪りんご、
舌のとけるやうにあまくねばねばとして
嫉妬のたのしい心持にも似た淡雪りんご、
まつしろい皿のうへに
うつくしくもられて泡をふき、
香水のしみこんだ銀のフオークのささるのを待つてゐる。
とびらをたたく風のおとのしめやかな晩、
さみしい秋の
林檎料理のなつかしさよ。
まるい鳥
をんなはまるい線をゑがいて
みどりのふえをならし、
をんなはまるい線をひいて
とりのはねをとばせる。
をんなはまるい線をふるはせて
あまいにがさをふりこぼす。
をんなは鳥だ、
をんなはまるい鳥だ。
だまつてゐながらも、
しじゆうなきごゑをにほはせる。
白い狼
白い狼が
わたしの背中でほえてゐる。
白い狼が
わたしの胸で、わたしの腹で、
うをう うをうとほえてゐる。
こえふとつた白い狼が
わたしの腕で、わたしの股で、
ぼう ぼうとほえてゐる。
犬のやうにふとつた白い狼が
眞赤な口をあいて、
なやましくほえさけびながら、
わたしのからだぢゆうをうろうろとあるいてゐる。
疾患の僧侶
みつめればみつめるほど深い穴のなかに、
凝念の心をとかして一心にねむりにいそぐ僧侶、
僧侶の肩に木の葉はさらさらと鳴り、
かげのやうにもうろうとうごく姿に、
闇をこのむ蟲どもがとびはねる。
合掌の手のひらはくづれて水となり、
しづかにねむる眼は神殿の寶石のやうにひかりかがやき、
僧侶のゆくはれやかな道路のまうへに白い花をつみとる。
底のない穴のなかにそのすみかをさだめ、
ふしぎの路をたどる病氣の僧侶は、
眼もなく、ひれもなく、尾もあぎともない
深海の魚のすがたに似て、
いつとなくあをじろい扁平のかたまりとなつてうづくまる。
僧侶のみちは大空につながり、
僧侶の凝念は滿開の薔薇となつてこぼれちる。
盲目の鴉
うすももいろの瑪瑙の香爐から
あやしくみなぎるけむりはたちのぼり、
かすかに迷ふ茶色の蛾は
そこに白い腹をみせてたふれ死ぬ。
秋はかうしてわたしたちの胸のなかへ
おともないとむらひのやうにやつてきた。
しろくわらふ秋のつめたいくもり日に、
めくら鴉は枝から枝へ啼いてあるいていつた。
裂かれたやうな眼がしらの鴉よ、
あぢさゐの花のやうにさまざまの雲をうつす鴉の眼よ、
くびられたやうに啼きだすお前のこゑは秋の木の葉をさへちぢれさせる。
お前のこゑのなかからは、
まつかなけしの花がとびだしてくる。
うすにごる靑磁の皿のうへにもられた兎の肉をきれぎれに嚙む心地にて、
お前のこゑはまぼろしの地面に生える雜草である。
羽根をひろげ、爪をかき、くちばしをさぐつて、
枝から枝へあるいてゆくめくら鴉は、
げえを げえを とおほごゑにしぼりないてゐる。
無限につながる闇の宮殿のなかに、
あをじろくほとばしるいなづまのやうに
めくら鴉のなきごゑは げえを げえを げえをとひびいてくる。
蜘蛛のをどり
あらあらしく野のをかに步みをはこぶ
ゆふぐれのさびれたたましひのおともないはばたき、
うすぐらいともしびのゆらめくたのしさにも似て、
さそはれる微笑の釣針のうつくしさ。
うちつける壁も扉も窓もなく、
むなしくあを空のふかみの底に身をなげ、
世紀のあをあをとながれるうれひ顏のうへに、
こともなげに、ひそかにも、
うつりゆく香料のたいまつをもやしつづけた。
いつぴきの黃色い大蜘蛛は
手品のやうにするすると絲をたれて、
そのふしぎな心の運命を織る。
ああ、
ゆふぐれの野のはてにひとりつぶやく太陽の
かなしくゆがんだわらひ顏、
黃色い蜘蛛はた・た・たと織りつづける。
女のやうにべつたりとしたおほきな蜘蛛は、
くたびれるのもしらないで、
足も 手も ぐるぐるする眼も
葉ずれの蘆のやうに、するどくするどくうごいてゐる。
鏡にうつる裸體
鏡のおもてに
魚のやうに ゆらゆらとうごくしろいもの、
まるいもの、ふといもの、ぬらぬらするもの、べつたりとすひつきさうなもの、
夜の花びらのやうに なよなよとおよぐもの、さては、うすあかいけもののやうに
のつぺりとしてわらひかけるもの。
ひろい鏡のおもてに
ゆきちがひ、すれちがひ、からみあふもの、
くづれちる もくれんの花のやうに
どろどろに みだれて悲しさをいたはり、
もうもうとのぼるかげろふの靑みのなかに、
つつみきれない肉のよろこびを咲きほこらせる。
ああ、みだれみだれて うつる白いけむりの肉、
ぼつてりとくびれて、ふくふくともりあがる肉の雨だれ、
ばらいろの蛇、みどり色の犬、
ぬれたやうにひかるあつたかい女のからだ、
ぷつくりとゑみわれる ぼたんの花、
かげはかげを追ひ、
ひかりはひかりをはしらせ、
つゆをふくんでまつくろなゆめをはらませるもの
につちやりと、うたれたやうな音をたてて、
なまめかしいこゑをもらす白いおもいもの、
あのふくれた腹をごらんなさい、
うう、ううとけもののうめきにも似て命をさそふ嘆息のエメロード、
まるくつて、まるくつて、
こりこりと すばやく あけぼのの霧をよぶやうなすずしいもも、
よれよれにからみつく乳房のあはあはしさ、
こほろぎのなくやうに 溶けてゆく
足の指のうるはしさ、
…………………………。
くるぶしはやはらかくゆらめいて
あまく、あまくわたしの耳をうつ。
[やぶちゃん注:「エメロード」フランス語“emeraude”。エメラルド、エメラルド色のことであるが、ここでは鮮緑色の色のイメージと読む。
後ろから三行目のリーダ数は二十七。但し、底本の見た目の配置(両行と比較した長さ)に近づけるためにポイント数を落として示してある。
さりながら、私はこの詩をデユシャンに読ませたい気がする、さえも……]
指頭の妖怪
あをじろむ指のさきから、
小鳥がまひたつてゆく。
ぎらぎらにくもる地面の床のうへに、
片足でおとろへはてながら、
うづまきながらのしかかつてくる。
まつくろな蛇の腹のやうな太鼓のおとが
ぼろんぼろんとなげくのだ。
わたしのあをじろむ指のさきからにげてゆく月夜の雨、
毛ばだつた秋の果物のやうな
ふといぬめぬめとした頸をねぢらせ、
なまめく頸をねぢらせ、
秋のこゑをつぶやき、
秋のつめたさをおさへつける。
ぼろんぼろんとやぶれた魂の絲をかきならし、
熱く、ものうく、身をかきむしつて、
さびしい秋のつめたさをおさへつける。
まがりくねつた この秋のさびしさを、
あやしくふりむけるお前のなまなましい頸のうめきに、
たよりなくもとほざけるのだ。
しろくひかる粘液をひいて、
うねりをうつお前の頸に
なげつけられた言葉の世にも稀なにほひ。
ぼろんぼろんと
わたしの遠耳にきこえてくるあやしい太鼓のおと。
木製の人魚
をとめの顏
あなたのかほは けだかい佛像のやうに
そうそうとしたひかりのわなにかこまれ、
おもはゆげにふしめして、
あかるくわたしの腕をてらす。
わかれることの寂しさ
あの人はわたしたちとわかれてゆきました。
わたしはあの人を別に好いても嫌つてもゐませんでした。
それだのに、
あの人がわたしたちからはなれてゆくのをみると、
あの人がなじみのやせた顏をもつて去つてゆくのをおもふと、
わけもないものさびしさが
あはくわたしの胸のそこにながれてゆきます。
人の世の 生きてわかれてゆくながれのさびしさ。
あの人のほのじろい顏も、
なじみの調度のなかにもう見えなくなるのかと思ふと、
さだめなくあひ、さだめなくはなれ、
わづかのことばのうちにゆふぐれのささやきをにごした
そのふしぎの時間は、
とほくきえてゆくわたしの足あとを、
鳥のはねのやうにはたはたと羽ばたきをさせるのです。
わらひのひらめき
あのしめやかなうれひにとざされた顏のなかから、
をりふしにこぼれでる
あはあはしいわらひのひらめき。
しろくうるほひのあるひらめき、
それは誰にこたへたわらひでせう。
きぬずれのおとのやうなひらめき、
それはだれをむかへるわらひでせう。
うれひにとざされた顏のなかに咲きいでる
みづいろのともしびの花、
ふしめしたをとめよ、
あなたの肌のそよかぜは誰へふいてゆくのでせう。
水母の吸物
しどろもどろにかくれ、
ちひさくほころびるうたがひのかねをならし、
熱い皿のうへに夜となくひるとなくおちてくる影をあつめ、
なみのあひだによろめきわらふ
いとくらげをすくひとり、
死のあまみをいろづけて、
たましひの椀のなかにぽつたりとおとす。
みづおとはこいでゆく、
みづおとは言葉をなげすててこいでゆく。
さびしいくらげの吸物は
わたしのゆびにゆれてくる。
[やぶちゃん注:私はクラゲ・フリークであるが、この詩は世界的にも歴史的にも突出して特異で美事なクラゲの詩であると思う。金子光晴の「くらげの唄」なんぞより遙かにクラゲ的である。なお「いとくらげ」という種は残念ながらいない。無論、拓次の幻想世界のクラゲの名である訳だが、私なら、小型の透明でしかも刺胞毒の強い、刺胞動物門箱虫綱箱虫目アンドンクラゲ科アンドンクラゲ
Carybdea rastoni の、あの傘の四方に下がった四本の鞭状の恐ろしい触手(凡そ二〇センチメートル)をイメージする。舌が赤黒く爛れて痙攣する……慄っとするほど素敵な眩暈じゃないか!……]
眞黑な水の上の月
不安に滿ちた心を化粧する惡魔、
善と美との妖精、
孤獨の繩梯子をのぼつてゆく道心、
生きた毛皮のうへに魂の菓子をつくる世相、
わたしは空を舞ふミイラのやうに
茫漠とした木盃をうかべて、
奇蹟の榮光に身をかがませ、
うつむきながら、
手足をもぎとられたひとつの流れのなかに、
まつくろなかげをおとしてしづむ眞夜中の月。
きものをきた月
月はちひさなきものをきて、わたしのまへにあらはれた。
それは、カナリヤをくはへたくろい蛇がするするととほるやうに、
微妙な疾風のおももちをながして、
たちさわぐ風景のなかに生きものをうみおとした。
月はひかりの小模樣のあるまだらのきものをきて、
わたしのまへにあらはれた。
夏の夜の薔薇
手に笑とささやきとの吹雪する夏の夜、
黑髮のみだれ心地の眼がよろよろとして、
うつさうとしげる森の身ごもりのやうにたふれる。
あたらしいされかうべのうへに、
ほそぼそとむらがりかかるむらさきのばらの花びら、
夏の夜の銀色の淫縱をつらぬいて、
よろめきながれる薔薇の怪物。
みたまへ、
雪のやうにしろい腕こそは女王のばら、
まるく息づく胴は黑い大輪のばら、
ふつくりとして指のたにまに媚をかくす足は鬱金のばら、
ゆきずりに祕密をふきだすやはらかい肩は眞赤なばら、
帶のしたにむつくりともりあがる腹はあをい臨終のばら、
こつそりとひそかに匂ふすべすべしたつぼみのばら、
ひびきをうちだすただれた老女のばら、
舌と舌とをつなぎあはせる絹のばらの花。
あたらしいふらふらするされかうべのうへに
むらむらとおそひかかるねずみいろの病氣のばら、
香料の吐息をもらすばらの肉體よ、
芳香の淵にざわざわとおよぐばらの肉體よ、
いそげよ、いそげよ、
沈默にいきづまる歡樂の祈禱にいそげよ。
[やぶちゃん注:「淫縱」の「ん」の部分は、底本では植字ミスで空白。訂した。
「胴」」フランス語“torse”(但し、この語自体がイタリア語“tourso”語源)の音写。]
木製の人魚
こゑはとほくをまねき、
しづかにべにの鳩をうなづかせ、
よれよれてのぼる火繩の秋をうつろにする。
こゑはさびしくぬけて
うつろを見はり、
ながれる身のうへににほひをうつす。
くちびるはあをくもえて、
うみのまくらにねむり、
むらがりしづむ藻草のかげに眼をよせる。
洋裝した十六の娘
そのやはらかなまるい肩は、
まだあをい水蜜桃のやうに媚の芽をふかないけれど、
すこしあせばんだうぶ毛がしろい肌にぴちやつとくつついてゐるやうすは、
なんだか、かんで食べたいやうな不思議なあまい食欲をそそる。
戀
わたしの戀は水のなかにある夕日のかほ、
わたしの戀は眞夜中のおちばのおもひ、
ことばも こゑも かげもなく。
山のうへをゆくこゑ
しろい花、しろいつぼみ、
しろいにほひのこころ、
あなたのこゑはまひるのゆめをゑがいて、
めにもみえない、かなたの山のうへをしづかにとほつてゆきます。
うみのなみのやうにゆれてはしづむわたしのさびしい心に、
きこえないあなたのこゑは、
かすかな月見草のやうに咲いてゐます。
窓をあけてください
窓をあけてください。
あなたののこした影のにほひのしたはしさに、
わたしはひともとの草のやうに生ひそだち、
わたしはねむりのそこにひたつて、そのにほひに追ひすがる。
花のにほひに死ににゆく
羽蟲のやうに惱みのあまさにおぼれて、
そぞろに そぞろに 悲しみの夕化粧する。
窓をあけてください、
ほのかなわたしの戀びとよ。
十四のをとめ
そのすがたからは空色のみづがながれ、
きよらかな、ものを吸ふやうな眼、
けだかい鼻、
つゆをやどしてゐるやうなときいろの頰、
あまい唾をためてゐるちひさい脣。
黃金のランプのやうに、
あなたのひかりはやはらかにもえてゐる。
月の麗貌
月は窓のほとりに
羽根をかくしてしのびより、
こゑもださず、眼もひらかず
ゆく舟のそよぎのやうに
黃金の吹雪の芽をのばす。
椅子に眠る憂鬱
はればれとその深い影をもつた橫顏を
花鉢のやうにしづかにとどめ、
搖椅子のなかにうづくまる移り氣をそそのかして、
死のすがたをおぼろにする。
みどりいろの、ゆふべの搖椅子のなやましさに、
みじかい生の花粉のさかづきをのみほすのか。
ああ、わたしのほとりに匍ひよるみどりの椅子のささやきの小唄、
憂鬱はながれる魚のかなしみにも似て、ゆれながら、ゆれながら、
かなしみのさざなみをくりかへす。
水のおもてのこゑ
水のおもてをさかしげにとぶ よみがへりのこゑ、
よわよわしく光にねむるこゑ、
かげよりかげへ おもひよりおもひへ
なよなよとひそみかくれるわたしのこゑ。
水のおもてをかなしげに
よろめいてゆく月いろのこゑ。
みどりの薔薇
あをざめた薔薇
ぬれてたはむれる亡魂の月しろ、
燭臺のうへにあをじろむほのほの姿、
化生の猫の尾のやうにかをる寂光のばら。
うづまく花
そらよりみだれかかる紫琅玕のうはこと、
あかつきの鳥のきもののひだに悲しみのうれひをのせ、
とほざかりゆくこのふかいもののかなしみは、
はなれ、とびはなれ、うなだれ、
さて たよりなくそぞろあるきし、
水底におもかげをうつし、
しづまるこゑの柩に
あをじろい漿果の酒をかもしては、
ところもしらぬひとすぢの國へといそぎゆく。
ああ うれひは風、うれひは鳥、
あをざむい春の日のほとりに
うつりつつ消えてゆく心のまぼろし。
[やぶちゃん注:「紫琅玕」「琅玕」は、希少性の高い高品質の、特別な翡翠(Jadeite ジェダイト・硬玉)の中国名で(「琅玕」とは元来は中国語で「青々とした美しい竹」を意味する語である)、英語では“Imperial Jade”(インぺリアル・ジェイド)と呼ばれる。この英語名は西太后が熱狂的な収集家であったことに由来すると言われる。但し、こうした超高級の「琅玕翡翠」の原産国は、実は中国ではなく、ミャンマーである。]
まぼろしの薔薇
1
まよなかにひらくわたしの白ばらよ、
あはあはとしたみどりのおびのしろばらよ、
どこからともなくにほうてくる
おまへのかなしいながしめのさびしさ、
夜ごと夜ごとまぼろしに咲くわたしのしろばらの花。
[やぶちゃん注:章番号は底本では半角である。本詩に就いては、昭和五〇(一九七五)年現代思潮社刊現代詩人文庫「大手拓次詩集」の当該詩を見ると、
1
まよなかにひらくわたしの白ばらよ、
あはあはとしたみどりのおびのしろばらよ、
どこからともなくにほうてくる
おまへのかなしいながしめのさびしさ、
ああ、
夜ごと夜ごとまぼろしに咲くわたしのしろばらの花。
と、「ああ、」という一行が五行目に存在しており(「咲く」にルビもあり)、これが正しい詩形と思われる。]
2
はるはきたけれど、
わたしはさびしい。
ひとつのかげのうへにまたおもいかげがかさなり、
わたしのまぼろしのばらをさへぎる。
ふえのやうなほそい聲でうたをうたふばらよ、
うつくしい惱みのたねをまくみどりのおびのしろばらよ、
うすぐもりした春のこみちに、
ばらよ、ばらよ、まぼろしのしろばらよ、
わたしはむなしくおまへのかげをもとめては、
こころもなくさまよひあるくのです。
3
かすかな白鳥のはねのやうに
まよなかにさきつづく白ばらの花、
わたしのあはせた手のなかに咲きいでるまぼろしの花、
さきつづくにほひの白ばらよ、
こころをこめたいのりのなかに咲きいでるほのかなばらよ、
ああ、なやみのなかにさきつづく
にほひのばらよ、にほひのばらよ、
おまへのながいまつげが
わたしをさしまねく。
4
まつしろいほのほのなかに、
おまへはうつくしい眼をとぢてわたしをさそふ。
ゆふぐれのこみちにうかみでるしろばらよ、
うすやみにうかみでるみどりのおびのしろばらよ、
おまへはにほやかな眼をとぢて、
わたしのさびしいむねに花をひらく。
5
なやましくふりつもるこころのおくの薔薇の花よ、
わたしはかくすけれども、
よるのふけるにつれてまざまざとうかみでるかなしいしろばらの花よ、
さまざまのおもひをこめたおまへの祕密のかほが、
みづのなかの月のやうに
はてしのないながれのなかにうかんでくる。
6
ひとひら、またひとひら、ふくらみかけるつぼみのばらのはな、
そのままに、ゆふべのこゑをにほはせるばらのかなしみ、
ただ、まぼろしのなかへながれてゆくわたしのしろばらの花よ、
おまへのまつしろいほほに、
わたしはさびしいこほろぎのなくのをききます。
7
朝ごとにわたしのまくらのそばにひらくばらのはな、
きえてゆくにほひをとどめて、
しづかにうれひをひろげるしろばらのはな、
みどりの葉はひとつひとつのことばをのこして、
とほくきえてゆくまぼろしの白ばらのはな。
8
ゆふぐれのかげのなかをあるいてゆくしめやかなこひびとよ、
こゑのないことばをわたしのむねにのこしていつた白薔薇の花よ、
うすあをいまぼろしのぬれてゐるなかに
ふたりのくちびるがふれあふたふとさ。
ひごとにあたらしくうまれでるあの日のばらのはな、
つめたいけれど、
ひとすぢのゆくへをたづねるこころは、
おもひでの籠をさげてゆきます。
うしろをむいた薔薇
ばらよ、
おまへはわたしのしらないまにさいてしまつた。
わたしのむねにありともしない息をふきかけて、
おまへはつつましくさいてしまつた。
にほひのきえようとするはるかなばらのいとほしさよ、
もつとわたしへ手をのばしてください、
ふしめして、うなだれて、うしろをむいた白ばらの花よ。
薔薇のもののけ
あさとなく ひるとなく よるとなく
わたしのまはりにうごいてゐる薔薇のもののけ、
おまへはみどりのおびをしゆうしゆうとならしてわたしの心をしばり、
うつりゆくわたしのからだに、
たえまない火のあめをふらすのです。
手をのばす薔薇
ばらよ おまへはわたしのあたまのなかで鴉のやうにゆれてゐる。
ふしぎなあまいこゑをたててのどをからす野鳩のやうに
おまへはわたしの思ひのなかでたはむれてゐる。
はねをなくした駒鳥のやうに
おまへは影をよみながらあるいてゐる。
このやうにさびしく ゆふぐれとよるとのくるたびに
わたしの白薔薇の花はいきいきとおとづれてくるのです。
みどりのおびをしめて まぼろしによみがへつてくる白薔薇の花、
おまへのすがたは生きた寶石の蛇、
かつ かつ かつととほいひづめのおとをつたへるおまへのゆめ、
薔薇はまよなかの手をわたしへのばさうとして、
ぽたりぽたりちつていつた。
ばらのあしおと
ばらよ おまへのあしおとをきかしておくれ、
さわがしい雨のみづおとのするまよなかに、
このかきむしられるわたしの胸のなかへ
おまへのやさしいあしおとをきかしておくれ。
ちひさく しろく さびしいかほのばらのはなよ、
わたしのたよりない耳へ、
おまへのやはらかなあしおとをきかしておくれ。
とほく とほく ゆらめいてゐるばらのはなよ、
おまへのまぼろしのあしおとを
おとろへてゆくわたしの胸へきかしておくれ。
薔薇の誘惑
ただひとつのにほひとなつて
わたり鳥のやうにうまれてくる影のばらの花、
絲をつないで墓上の霧をひきよせる影のばらの花、
むねせまく ふしぎなふるい甕のすがたをのこしてゆくばらのはな、
ものをいはないばらのはな、
ああ
まぼろしに人閒のたましひをたべて生きてゆくばらのはな、
おまへのねばる手は雜草の笛にかくれて
あたらしいみちにくづれてゆきます。
ばらよ ばらよ
あやしい白薔薇のかぎりないこひしさよ。
ひびきのなかに住む薔薇よ
ひびきのなかにすむ薔薇よ、
おまへはほそぼそとわだかまるみどりの帶をしめて、
雪のやうにしろいおまへのかほを
うすい黃色ににほはせてゐるのです。
ふるへる幽靈をそれからそれへと生んでゆくおまへの肌は、
ひとつのふるい柩のまどはしに似てゐるではありませんか。
ひびきのなかにすむふくらんだおほきな薔薇よ、
おまへは あの水の底に鐘をならす魚の心ではないでせうか。
薔薇よ、
ひびきのなかにうろこをおとす妖性の薔薇よ、
おまへはわたしのくちびるをよぶ、
わたしのくちびるをまじまじとよんで、
月のひかりをくらくするのです。
うすく黃色い薔薇の花よ、
ぷやぷやとはなびらをかむ羽のある蛇が
いたづらな母韻の手をとつて、
あへいでゐるわたしのこころに
亡靈のゆくすゑをうたはせるのです。
ああ
しろばらよ しろばらよ しろばらよ、
おまへはみどりのおびをしめて、
うすきいろく うすあをく にほつてきました。
なやめる薔薇
おぼろの犬の影はこほり、
つめたくひかりの閨をゑがく………
ふゆのひの鬱金のばらは鐘のねをひらいてうたふ。
おまへのなやめる身ぶるひのささやきは、
あわだつみどりの鑰を示して、
こもごもに奇蹟の淵におぼれ死ぬ。
さびしい戀
戀のこころは やみのなかのひなどりのこゑ、
戀のこころは ゆく雲のおとすおもかげ、
戀のこころは 水に生え 水に浮き 水にかくれる盲目魚、
ああ さまよへばとて ゆけばとて、
戀のこころは みづすまし、
戀のこころは くれがたのすゐせんのはな。
かなしみ
まどにちかづく日のかなたから、
夜はあをいいろどりの鳥をよび、
ほのかにも ほのかにも しめる眼をおほふ。
わかれ
さびしさはぬれてゆきます。
しと しと しととおちる雪のやうにぬれてゆきます。
うすずみいろのおちば、
わかれて わかれて ゆくみのさびしさ。
風のなかに巢をくふ小鳥
幻影
ひとつの水甕のなかにかげをうゑ、
またひとつの水甕のなかにかげをうゑ、
ゆくりなくも いのちのいただきに花をうつす。
祕密の花
あなたにあへば祕密の花がこぼれる。
にほひかなしく
ゆきくれたひとつの あげはのてふのやうに、
こもれるあをと、
ながれながれの黑と黃と、
しだれざくらのやうなべにとむらさきとが、
眼のおほきい絹の花となつて、
わたしのまへにぼんやりとおちる。
こびひとよ、
わたしのにげようとする手をよんでください。
悲しみの枝に咲く夢
こひびとよ、こひびとよ、
あなたの呼吸は
わたしの耳に靑玉の耳かざりをつけました。
わたしは耳がかゆくなりました。
こひびとよ、こひびとよ、
あなたの眼が星のやうにきれいだつたので、
わたしはいくつもいくつもひろつてゆきました。
さうして、わたしはあなたの眼をいつぱい胸にためてしまひました。
こひびとよ、こひびとよ、
あなたのびろうどのやうな小指がむずむずとうごいて、
わたしの鼻にさはりました。
わたしはそのまま死んでもいいやうなやすらかな心持になりました。
[やぶちゃん注:既出であるが、「靑玉」はサファイア。青玉。フランス語の“saphir”忠実な音訳(英語は“sapphire”)である。なお、底本ではこのルビは「サフイイル」であるが、既出本文表記から促音化して訂した(ご存知の通り、本邦では現在も続いているが、永くルビの促音表記はなされない(初期は植字の関係上、出来なかったというか、面倒であったというのが正しいかとも思われる)のが常識であったことを多くの人が知っているようには思われないので特に注しておく)。]
風のなかに巢をくふ小鳥
――十月の戀人に捧ぐ――
あなたをはじめてみたときに、
わたしはそよ風にふかれたやうになりました。
ふたたび みたび あなたをみたときに、
わたしは花のつぶてをなげられたやうに
たのしさにほほゑまずにはゐられませんでした。
あなたにあひ、あなたにわかれ、
おなじ日のいくにちもつづくとき、
わたしはかなしみにしづむやうになりました。
まことにはかなきものはゆくへさだめぬものおもひ、
風のなかに巢をくふ小鳥、
はてしなく鳴きつづけ、鳴きつづけ、
いづこともなくながれゆくこひごころ。
足
うすいこさめのふる日です、
わたしのまへにふたりのむすめがゆきました。
そのひとりのむすめのしろい足のうつくしさをわたしはわすれない。
せいじいろの爪かはからこぼれてゐるまるいなめらかなかかとは、
ほんのりとあからんで、
はるのひのさくらの花びらのやうになまめいてゐました。
こいえびちやのはなをがそのはなびらをつつんでつやつやとしてゐました。
ああ うすいこさめのふる日です。
あはい春のこころのやうなうつくしい足のゆらめきが、
ぬれたしろい水鳥のやうに
おもひのなかにかろくうかんでゐます。
秋
ひとつのつらなりとなつて、
ふけてゆくうす月の夜をなつかしむ。
この みづにぬれたたわわのこころ、
そらにながれる木の葉によりかかり、
さびしげに この憂鬱をひらく。
遠い枝枝のなかに
はひまつはる微笑のかたかげに
わたしは さむいあをざめたきものをきて、
さびしさにぬれてひたりながら、
巢をうばはれた野のはだか鳥のやうに
羽ばたいてはおち、羽ばたいてはきずつき、
遠い枝枝のなかに、
うしなはれたあなたの心をさがしてゐます。
思ひ出はすてられた舞踏靴
それは わたしの心にくろいさくらの咲きつづく
うすぐもりした春の日でした。
みどりの小石をつづつて
しろい小羽根のしたにあたためてゐたのに、
おともなく
あらしのまへのそよかぜのやうに、
あなたのすがたはみえなくなつてしまひました。
あなたの白文鳥のやうなみぶりが、
きえたわたしの橋のうへに
たえだえにすぎてゆきます。
さきこぼれるしろばらのゆふやみのやうなあなたのかほは
わたしの手鏡のなかに
ふしぎな春のぼんぼりをともしてゐます。
まどろみからさめたあなたの指が
みがかれた象牙のやうにあをじろんで、
ほろにがい沈丁花のにほひをうつしてゐます。
ああ 思ひではすてられた銀の舞踏靴のやうに
くさむらのなかによろけながら、
月のかげをおしつぶしてゐます。
ただ あなたの指にふれたばかりで
はかなくわかれてしまつた戀人よ、
わたしは蜘蛛のやうにきずつけられて、
まだらのみを
風のなかにうごかしてゐるのです。
[やぶちゃん注:「白文鳥」スズメ目スズメ亜目カエデチョウ科ブンチョウ Padda oryzivora のアルビノの品種。ハクブンチョウとも呼ぶ。ブンチョウはジャワ島やバリ島が原産地であるが、本種は江戸期に中国から輸入されたブンチョウが明治期に突然変異して風切り羽の白い文鳥が生まれ、その後それが固定化されたものである(愛知県弥富市が「ハクブンチョウ」発祥の地とされる)。全身が白く、嘴と目の周囲が赤く、身体に丸みがある(「帯広どうぶつ園の鳥 鳥図鑑」のハクブンチョウ(白文鳥)の記載やウィキの「ブンチョウ」を参照した)。
「舞踏靴」“escarpin”フランス語。現在は専ら婦人用パンプスを指す。]
あなたの一言にぬれて
まどはひかりをよびかはして、
ことごとにかなしみのうつりがを消し、
あゆみもおそく たそがれをあはくぼかして、
うるはしくながれのなかにとけてゆく。
戀人を抱く空想
ちひさな風がゆく、
ちひさな風がゆく、
おまへの眼をすべり、
おまへのゆびのあひだをすべり、
しろいカナリヤのやうに
おまへの乳房のうへをすべりすべり、
ちひさな風がゆく。
ひな菊と さくらさうと あをいばらの花とがもつれもつれ、
おまへのまるい肩があらしのやうにこまかにこまかにふるへる。
西藏のちひさな鐘
むらさきのつばきの花をぬりこめて、
かの宗門のよはひのみぞにはなやかなともしびをかかげ、
憂愁のやせさらぼへた馬の背にうたたねする鐘よ、
そのほのぐらい銀色のつめたさは
さやさやとうすじろく、うすあをく、
嵐氣にかくされたその風貌の刺のなまなましさ。
鐘は僧形のあしのうらに疑問のいぼをうゑ、
くまどりをおしせまり、
笹の葉のとぐろをまいて、
わかれてもわかれてもつきせぬきづなの魚を生かす。
[やぶちゃん注:「西藏のちひさな鐘」とはチベット仏教で用いられる仏具マニ車(摩尼車)のことである。]
さびしいかげ
この ひたすらにうらさびしいかげはどこからくるのか、
きいろい木の實のみのるとほい未來の木立のなかからか、
ちやうど 胸のさやさやとしたながれのなかに、
すずしげにおよぐしろい魚のやうである。
あなたのこゑ
わたしの耳はあなたのこゑのうらとおもてもしつてゐる。
みづ苔のうへをすべる朝のそよかぜのやうなあなたのこゑも、
グロキシニヤのうぶげのなかにからまる夢のやうなあなたのこゑも、
つめたい眞珠のたまをふれあはせて靄のなかにきくやうなあなたのこゑも、
銀と黃金の太刀をひらひらとひらめかす幻想の太陽のやうなあなたのこゑも、
月をかくれ、
沼の水をかくれ、
水中のいきものをかくれ、
ひとりけざやかに雪のみねをのぼるやうな澄んだあなたのこゑも、
つばきの花やひなげしの花がぽとぽととおちるやうなひかりあるあなたのこゑも、
うすもののレースでわたしのたましひをやはらかくとりまくあなたのこゑも、
まひあがり、さてしづかにおりたつて、
あたりに氣をかねながらささやく河原のなかの雲雀のやうなあなたのこゑも、
わたしはよくよく知つてゐる。
とほくのはうからにほふやうにながれてくるあなたのこゑのうつりがを、
わたしは夜のさびしさに、さびしさに、
いま、あなたのこゑをいくつもいくつもおもひだしてゐる。
[やぶちゃん注:本詩は本詩を所収する詩集類で、極めて有意な異同がある。
一つは昭和二六(一九四一)年創元社刊創元文庫「大手拓次詩集」で、初行が、
わたしの耳はあなたのこゑのうらもおもてもしつてゐる。
となり(下線部やぶちゃん)、終曲部は、
とほくのはうからにほふやうにながれてくるあなたのこゑのうつりがを、
わたしは夜のさびしさに、さびしさに、いま、あなたのこゑをいくつもいくつもおもひだしてゐる。
で、「うつりか」と清音になり、最終行は前行に連続してしまっている。
次に昭和五〇(一九七五)年現代思潮社刊現代詩人文庫「大手拓次詩集」であるが、創元文庫と同じ箇所を見ると、初行は何と、
わたしの耳はあなたのこゑのうらとおもてをしつてゐる。
となって(「みみ」は踊り字が正字化している)、終曲部は、
とほくのはうからにほふやうにながれてくるあなたのこゑのうつりがを、
わたしは夜のさびしさに、さびしさに、
いま、あなたのこゑをいくつもいくつもおもひだしてゐる。
最終行が改行されている代わりに、底本のような一字下げは行われていない(「よる」のルビもない)。
前者の創元文庫版は私の底本を底本としている旨の記載があるから、総てを誤植と判断してよいかも知れない。
また、底本の最終行一字下げというのは、同詩集の他の詩では見られない特異なもので、底本自体の組み誤りともとれないことはない(その可能性は大であるとさえ言い得る)。
現代思潮社刊現代詩人文庫は、これ、私はかねがね、同書に対してすこぶる不満を持っているのであるが、同詩集はその総てに亙って何を底本にしたかが、どこにも注記されていないのである。従ってこの詩形を正しいとする根拠が私にはない。これだけ大きな違いが認められるということは、恐らくは最も信用に足るはずの白鳳社版「大手拓次全集」に拠ったものとは推測出来るが、以上のような杜撰さによって(私が白鳳社版「大手拓次全集」を所持しないことも手伝って)、今はこの詩形を正当と支持し得る立場にない。
しかし乍ら、敢えて言わせてもらうならば、私は、
あなたのこゑのうらとおもてもしつてゐる(詩集「藍色の蟇」)
うらもおもてもしつてゐる(創元文庫)
うらとおもてをしつてゐる(思潮社現代詩文庫)
の三つを並べられたならば、これが恋い焦がれた女へ語りかける切ない言葉であるとするなら、私なら
「うらとおもてをしつてゐる」
という冷静で論理的な語り掛けは、絶対にしない。そしてまた
「うらもおもてもしつてゐる」
という畳み掛けて追い詰めるストーカーのような脅迫も、せぬ。……私だったなら……
……私は……あなたの透き通った芳しい声の……その「うらとおもて」の……微妙でいて……それでいて……真実の吐息の……その幽かな違い「も」「しつてゐる」……
と声かけるであろう……と思うのである。――これは私の勝手な空想である―― Maison le crapaud indigo (藍蟇邸)の下男なる私の…………
「グロキシニヤ」双子葉植物綱ゴマノハグサ目イワタバコ科オオイワギリソウ(大岩桐草) Sinningia speciosa。以下、ウィキの「グロキシニア」によれば、ブラジル原産で園芸植物として鉢植えなどで温室栽培される。熱帯雨林の下草として自生していた植物を改良した種で、不定形の塊茎をもち、草丈は二〇センチメートル程度、ロゼット(根生葉:地面からいきなり出ているように見える葉。)は大きな箆状又は倒卵状で、茎に対生する葉は長楕円形をなし、天鵞絨(ビロード)のような柔毛が密生している。花は適温が維持できれば常時咲くが、通常は六月から九月頃を開花期とする。花径五~七センチメートルの漏斗形、花色は紅・藍色・紫・ピンクなどで、星が散ったり縁取りを持ったりするバリエーションも多く、近年は八重咲品種も多く出回っている、とある。専ら花が画像の中心ではあるが、グーグル画像検索「Sinningia speciosa」で「グロキシニヤのうぶげのなかにからまる夢のやうな」彼女の幽玄な声を、お聴きあれ。……]
盲目の寶石商人
わたしは 十二月のきりのこいばんがたに、
街のなかをとぼろとぼろとあるいてゆくめくらの商人です。
わたしの手も やはり霧のやうにあをくばうばうとのびてゆくのです。
ゆめのおもみのやうなきざはしがとびかひ、
わたしは手提の革箱のなかに、
ぬめいろのトルコ玉をもち、
蛇の眼のやうなトルマリン、
おほきなひびきを人形師の絲でころがすザクロ石、
はなよめのやはらかい指にふさはしいうすむらさきのうすダイヤ、
わたしは空からおりてきた鉤のやうに、
つつまれた柳のほそい枝のかげにゆれながら
まだらにうかぶ月の輪をめあてに、
さても とぼろとぼろとあるいてゆきます。
莟から莟へあるいてゆく
馬にゆられて
すべてのよは
いただきのうつろからのがれ、
おひすがる雪をはらひ、
なめらかに靑いほのほをうつす馬にゆられて、
砂原のとほきをとぼろとぼろとゆく。
十六歳の少年の顏
―思ひ出の自畫像―
うすあをいかげにつつまれたおまへのかほには
五月のほととぎすがないてゐます。
うすあをいびろうどのやうなおまへのかほには
月のにほひがひたひたとしてゐます。
ああ みればみるほど薄月のやうな少年よ、
しろい野芥子のやうにはにかんでばかりゐる少年よ、
そつと指でさはられても眞赤になるおまへのかほ、
ほそい眉、
きれのながい眼のあかるさ、
ふつくらとしたしろい頰の花、
水草のやうなやはらかいくちびる、
はづかしさと夢とひかりとでしなしなとふるへてゐるおまへのかほ。
水中の薔薇
―「風・光・木の葉」を讀みて―
あなたの指をうごかしてください。
薄明の霧のなかに
やはらかくまばたくもの、
しろくかすかにまばたくもの、
さざなみするみづのなかに
ほそぼそとまばたくもの、
あをくほのかにひかりあるもの。
あなたの指をうごかしてください。
薔薇はひとつの鳥のやうに
早春の水氣のなかに
かろくまばたいてゐます。
[やぶちゃん注:副題「風・光・木の葉」は底本では「風 光・木の葉」。誤植と見て、中黒を打った。「風・光・木の葉」は白秋門下の詩人で作詞家としても知られた大木篤夫(明治二八(一八九五)年~昭和五二(一九七七)年)が大正一四(一九二四)年に出した処女詩集。この後の大木は、一九三〇年代後半頃から歌謡曲の作詞も手がけるようになり、東海林太郎の「国境の町」は一世を風靡した。太平洋戦争の開戦と同時に徴用され、海軍宣伝班の一員としてジャワ作戦に配属、バンダム湾敵前上陸の際には乗っていた船が沈没したため、同行の大宅壮一や横山隆一と共に海に飛び込み漂流した。この時の経験を基に作られた詩集「海原にありて歌へる」(アジアラヤ出版部昭和一七(一九四二)年刊)をジャカルタで現地出版したが、この詩集には日本戦争文学の最高峰とも称せられる「戦友別盃の歌-南支那海の船上にて。』(「言ふなかれ、君よ、別れを、世の常を、また生き死にを、-」)が掲載されており、この詩は前線の将兵にも愛誦された。この詩集で日本文学報国会大東亜文学賞を受賞するとともに従軍記・軍歌・愛国詩等の原稿依頼が殺到したが、戦後は一転、戦争協力者として文壇からは疎外された(以上はウィキの「大木惇夫」に拠った)。]
雪のある國へ歸るお前は
風のやうにおまへはわたしをとほりすぎた。
枝にからまる風のやうに、
葉のなかに眞夜中をねむるのやうに、
みしらぬおまへがわたしの心のなかを風のやうにとほりすぎた。
四月だといふのにまだ雪の深い北國へかへるおまへは、
どんなにさむざむとしたよそほひをしてゆくだらう。
みしらぬお前がいつとはなしにわたしの心のうへにちらした花びらは、
きえるかもしれない、きえるかもしれない。
けれども、おまへのいたいけな心づくしは、
とほい鐘のねのやうにいつまでもわたしをなぐさめてくれるだらう。
焦心のながしめ
むらがりはあをいひかりをよび、
きえがてにゆれるほのほをうづめ、
しろく しろく あゆみゆくこのさびしさ。
みづのおもての花でもなく、
また こずゑのゆふぐれにかかる鳥のあしおとでもなく、
うつろから うつろへとはこばれる焦心のながしめ、
鬱金香の花ちりちりと、
こころは 雪をいただき、
こころは みぞれになやみ、
こころは あけがたの細雨にまよふ。
[やぶちゃん注:「鬱金香」単子葉植物綱ユリ目ユリ科チューリップ属 Tulipa の和名。花の埃臭い香りがスパイスのウコン(ターメリック)に似ることに由来する。]
四月の顏
ひかりはそのいろどりをのがれて、
あしおともかろく
かぎろひをうみつつ、
河のほとりにはねをのばす。
四月の顏はやはらかく、
またはぢらひのうちに溶けながら
あらあらしくみだれて、
つぼみの花の裂けるおとをつらねてゆく。
こゑよ、
四月のあらあらしいこゑよ、
みだれても みだれても
やはらかいおまへの顏は
うすい絹のおもてにうつる靑い蝶蝶の群れ咲き。
流れの花
風がいたいのです、
わたしの心にいばらの花がさきます。
眼をかすかにして
おとづれをのぞんでゐるのです。
ふるへる花です。
まつげのなげきのやうにふるへる
さみしい花です。
いちまいの靑葉のやうに
かろくよりそうて
息もつかない花です。
とげとげの
そよろそよろする
よりどころない流れの花です。
季節の色
たふれやうとしてたふれない
ゆるやかに
葉と葉とのあひだをながれるもの、
もののみわけもつかないほど
のどかにしなしなとして
おもてをなでるもの、
手のなかをすべりでる
かよわいもの、
いそいそとして水にたはむれる風の舌、
みづいろであり、
みどりであり、
そらいろであり、
さうして 絕えることのない遙かな銀の色である。
わたしの身はうごく、
うつりゆくいろあひのなかに。
四月の日
日は照る、
日は照る、
四月の日はほのほのむれのやうに
はてしなく大空のむなしさのなかに
みなぎりあふれてゐます。
花は熱氣にのぼせて、
うはごとを言ひます。
傘のやうに日のゆれる軟風はたちはだかり、
とびあがる光の槍をむかへます。
日は照る、
日は照る、
あらあらしく紺靑の布をさいて、
らんまんと日は照りつづけます。
呪ひに送られる薔薇
月色の霧はくさむらにせまり、
おとさへもないひそみのなかに
ばらはひとつ
はねをおとし、
ばらはひとつ
あしをみがき、
ばらはひとつ
くちびるをうながす。
のろひにおくられる薔薇のつぼみは
ひらかうとして ひらかうとして
息をなげかはす。
うすあをと ときいろと うこんの薔薇、
はつなつの日はとほい雪にさそはれて、
しろい しろい あこがれのなやみをはき、
みどりのなかに その金のとびらをとざさうとする。
三つの薔薇は肌もあらはに、
ひとびとのおもひのうしろに
ときもなく にほひをはなたうとして、
その刺のひとみをおづおづとこらす。
マリイ・ロオランサンの杖
―ロオランサンのある畫を思ひて―
空にいつぽんのとかげをさがし、
あをみをはぎ、
霧をはきかけ、
たちのぼる香爐のなかに三年のいのちをのばし、
さて 春のそよかぜにひとつの眼をひらかせ、
秋の日だまりにもうひとつの眼をあかせ、
月をわり、日をふりこぼして、
鐘のねの咲きにほふ水のなかにときはなす。
うしなはれた情景はこゑをつみたて、
顏をみがき、
ひとり ひとり 息をはく、
その草の芽のやうな角をおとして。
[やぶちゃん注:本作がローランサンのどの絵に触発されたいものか、捜しあぐねているが、残念なことに私は個人的に彼女の絵は好きではないので、どうも探索の手が鈍る。識者の御教授を乞うものである。]
月に照らされる年齡
あめいろにいろどられた月光のふもとに
ことばをさしのべて空想の馬にさやぐものは、
わきたつ無數のともしびをてらして ひそみにかくれ、
闇のゆらめく舟をおさへて
ふくらむ心の花をゆたかにこぼさせる。
かはりゆき、
うつりゆき、
つらなりゆき、
まことに ひそやかに 月のながれに生きる年頃。
月をあさる花
そのこゑはなめらかな砂のうへをはしる水貝のささやき、
したたるものはまだらのかげをつくつてけぶりたち、
はなびらをはがしてなげうち、
身をそしり、
ほのじろくあへぐ指環のなかに
かすみゆく月をとらへようとする。
ひらいてゆけよ、
ひとり ものかげにくちびるをぬらす花よ。
[やぶちゃん注:「水貝」大手拓次は単なる漠然とした貝類をかく表現したものかも知れない(言わずもがなであるが、料理の水貝なんどではない)が、私はこれが本州以南の潮下線下の砂上に棲息する腹足網後鰓亜網頭楯目オオシイノミガイ上科ミスガイ科ミスガイ(御簾貝)
Hydatina physis のように思われてならない。ウミウシの一種として人気が高いが、私は薄い大型の貝殻も好きである(私は高校時代、秘かに好きだった二つ年上の学校の事務員の女性に、この貝殻を赤のリボンでくくってプレゼントしたのを今、思い出した)。殻表には多数の黒色螺帯があり、一般にはそこに不透明な淡褐色の縦線を有するが個体によってはほとんど見えないものもある。貝殻の中に格納しきれない大きな褐色を帯びたピンク色の軟体部を持ち、フリル状の外套膜の辺縁は青白色を呈し、蛍光する。参照した“The Opisthobranchs of Philippine Sea”の「ミズガイ」のブログ記事に、非常に素早く砂に潜るという記載もあり、こちら「ウミウシ図鑑」の画像を見て頂いても、まさに拓次好みの絢爛さと眩暈的な美しさを持っていることがお分かり戴けるはずである。そして何より、しばしばこの貝は「ミズガイ」と誤記されるのである。……同定というよりも寧ろ、この貝であることを私が切望している――と言った方がよい。]
しろいものにあこがれる
このひごろの心のすずしさに
わたしは あまたのしろいものにあこがれる。
あをぞらにすみわたつて
おほどかにかかる太陽のしろいひかり、
蘆のはかげにきらめくつゆ、
すがたとなく かげともなく うかびでる思ひのなかのしろい花ざかり、
熱情のさりはてたこずゑのうらのしろい花、
また あつたかいしろい雪のかほ、
すみしきる十三のをとめのこころ、
くづれても なほたはむれおきあがる靑春のみどりのしろさ、
四月の夜の月のほほゑみ、
ほのあかい紅をふくんだ初戀のむねのときめき、
おしろいのうつくしい鼻のほのじろさ ほのあをさ、
くらがりにはひでる美妙な指のなまめかしい息のほめき、
たわわなふくらみをもち ともしびにあへぐあかしや色の乳房の花、
たふれてはながれみじろぐねやの祕密のあけぼののあをいいろ、
さみだれに ちらちらするをんなのしろくにほふ足。
それよりも 寺院のなかにあふれる木蓮の花の肉、
それよりも 色のない こゑのない かたちのない こころのむなしさ、
やすみをもとめないで けむりのやうにたえることなくうまれでる肌のうつりぎ、
月はしどろにわれて生物をつつみそだてる。
[やぶちゃん注:「木蓮」のルビは底本では「もくれ 」。脱字と見て訂した。
「うつりぎ」は「移り氣」で、ここは不図した弾みで生じる感情、特に異性に惹かれる思い、出来心の謂いであろう。]
みちのほとりをゆく
わたしは みちのほとりをあるいてゆく、
むなしさをとらへて
そこはかとなくかくれるしのびねのやうに、
わたしは とほいくらさに咲きながら、
みちのほとりを日ごと日ごとにあるいてゆく。
うつり氣の薔薇
としごろのほてりをもつ絹のばら、
うつり氣はとほくにあるけれど
靄のやうにふくらんでこぼれちり、
ささやくよ ささやくよ
うすべにいろの絹のばら、
おまへは今夜、
ほんとによく咲いて こんもりしてゐるのねえ。
[やぶちゃん注:底本は二行目「うつり氣」の「氣」のルビが「き」に見える。「き」でも問題ないが、朗読の印象から創元文庫版の「ぎ」を採った。]
夢をうむ五月
粉をふいたやうな みづみづとしたみどりの葉つぱ、
あをぎりであり、かへでであり、さくらであり、
やなぎであり、すぎであり、いてふである。
うこんいろにそめられたくさむらであり、
まぼろしの花花を咲かせる晝のにほひであり、
感情の絲にゆたゆたとする夢の餌をつける五月、
ただよふものは ときめきであり ためいきであり かげのさしひきであり、
ほころびとけてゆく香料の波である。
思ひと思ひとはひしめき、
はなれた手と手とは眼をかはし、
もすそになびいてきえる花粉の蝶、
人人も花であり、樹樹も花であり、草草も花であり、
うかび ながれ とどまつて息づく花と花とのながしめ、
もつれあひ からみあひ くるしみに上氣する むらさきのみだれ花、
こゑはあまく 羽ばたきはとけるやうに耳をうち、
肌のひかりはぬれてふるへる朝のぼたんのやうにあやふく、
こころはほどのよい濕りにおそはれてよろめき、
みちもなく ただ そよいでくるあまいこゑにいだかれ、
みどりの泡をもつ このすがすがしいはかない幸福、
ななめにかたむいて散らうともしない迷ひのそぞろあるき、
恐れとなやみとの網にかけられて身をほそらせる微風の卵。
莟から莟へあるいてゆく人
まだ こころをあかさない
とほいむかうにある戀人のこゑをきいてゐると、
ゆらゆらする うすあかいつぼみの花を
ひとつひとつ あやぶみながらあるいてゆくやうです。
その花の
ひとの手にひらかれるのをおそれながら、
かすかな ゆくすゑのにほひをおもひながら、
やはらかにみがかれたしろい足で
そのあたりをあるいてゆくのです。
ゆふやみの花と花とのあひだに
こなをまきちらす花蜂のやうに
あなたのみづみづしいこゑにぬれまみれて、
ねむり心地にあるいてゆくのです。
名もよばないでゐるけれど
名もよばないでゐるけれど、
こころはふしぎのいろどりにそめられてゐるのです。
かげではないでせうとおもひます。
かげの心
あなたのそばに
それとなく生ひしげつた
つるくさの葉のやうに、
わたしは よそごころをよそほつて、
あちらにも こちらにも
むらがりさいてゐます。
六月の雨
六月はこもるあめ、くさいろのあめ、
なめくぢいろのあめ、
ひかりをおほひかくして窻のなかに息をはくねずみいろのあめ、
しろい顏をぬらして みちにたたずむひとのあり、
たぎりたつ思ひをふさぐぬかのあめ、みみずのあめ、たれぬののあめ、
たえまないをやみのあめのいと、
もののくされであり、やまひであり、うまれである この霖雨のあし、
わたしはからだの眼といふ眼をふさいでひきこもり、
うぶ毛の月のほとりにふらふらとまよひでる。
[やぶちゃん注:「霖雨」は底本ルビでは「な あめ」。創元文庫版で訂した。]
卵の月
そよかぜよ そよかぜよ、
わたしはあをいはねの鳥、
みづはながれ、
そよかぜはむねをあたためる。
この しつとりとした六月の日は
ものをふくらめ こころよくたたき、
まつしろい卵をうむ。
そよかぜのしめつたかほも
なつかしく心をおかし、
まつしろい卵のはだのなめらかなかがやき、
卵よ 卵よ
あをいはねをふるはして卵をながめる鳥、
まつしろ 卵よ ふくらめ ふくらめ、
はれた日に その肌をひらひらとふくらませよ。
[やぶちゃん注:「おかし」はママ。「日本詩人愛唱歌集 詩と音楽を愛する人のためのデータベース」内の「藍色の蟇」(白鳳社版「大手拓次全集」の第一巻及び第二巻)に基づいて表記すると、、
卵の月
そよかぜよ そよかぜよ、
わたしはあをいはねの鳥、
みづはながれ、
そよかぜはむねをあたためる。
この しつとりとした六月の日は
ものをふくらめ こころよくたたき、
まつしろい卵をうむ。
そよかぜのしめつたかほも
なつかしく心ををかし、
まつしろい卵のはだのなめらかなかがやき、
卵よ 卵よ
あをいはねをふるはして卵をながめる鳥、
まつしろい卵よ ふくらめ ふくらめ、
はれた日に その肌をひらひらとふくらませよ。
と「おかし」が正しく「をかし」と表記されている上、十三業行目も「まつしろ 卵よ」ではなく、「まつしろい卵よ」となっており、ここも七行目の「まつしろい卵をうむ。」で有意な休止が入った後、十一行目以降総てが呼びかけと命令形に雪崩れ込む構造からも、「まつしろ 卵よ」という呼びかけはリズムを崩すように思われ、脱字の可能性が高いように思われる。諸本に本詩は掲載されておらず、白鳳社版全集を所持していないため、私個人では今は校合不能である。]
黃色い接吻
夜 の 時
ちろ そろ ちろそろ
そろ そろ そろ
そる そる そる
ちろちろちろ
され され されされされされされ
びるびるびるびる びる
[やぶちゃん注:音声詩若しくは表音詩として活字や字配が有意に意味を持っていると考え、ここに限って標題の字配を再現した。]
春の日の女のゆび
この ぬるぬるとした空氣のゆめのなかに、
かずかずのをんなの指といふ指は
よろこびにふるへながら かすかにしめりつつ、
ほのかにあせばんでしづまり、
しろい丁字草のにほひをかくして のがれゆき、
ときめく波のやうに おびえる死人の薔薇をあらはにする。
それは みづからでた魚のやうにぬれて なまめかしくひかり、
ところどころに眼をあけて ほのめきをむさぼる。
ゆびよ ゆびよ 春のひのゆびよ、
おまへは ふたたびみづにいらうとする魚である。
[やぶちゃん注:「丁字草」リンドウ目キョウチクトウ科チョウジソウ Amsonia elliptica。他のキョウチクトウ科植物と同様に全草にアルカロイドを含み、有毒。五~六月に茎の頂きに集散花序を出し、薄青色の花を多数咲かせる(以上はウィキの「チョウジソウ」に拠る)。拓次は「にほひ」と述べているが、ネット上の記載では確かな香りを記載したものは見当たらない。個人のサイト「かわちのいろいろ見てある記」のこちらのページによると、『姿だけを見ていると良い香りがしそうですが、何となく青臭い感じのにおいがしていました』とある。]
黃色い接吻
もう わすれてしまつた
葉かげのしげりにひそんでゐる
なめらかなかげをのぞかう。
なんといふことなしに
あたりのものが うねうねとした宵でした。
をんなは しろいいきもののやうにむづむづしてゐました。
わたしのくちびるが
魚のやうに をんなのくちのうへにねばつてゐました。
はを はを はを はを はを
それは それは
あかるく きいろい接吻でありました。
[やぶちゃん注:創元文庫版は本詩形と同じであるが、思潮社版及び岩波文庫版では以下のように載る。
黄色い接吻
もう わすれてしまつた
葉かげのしげりにひそんでゐる
なめらかなかげをのぞかう。
なんといふことなしに
あたりのものが うねうねとした宵でした。
をんなは しろいいきもののやうに むづむづしてゐました。
わたしのくちびるが
魚のやうに をんなのくちのうへにねばつてゐました。
はを はを はを はを はを
それは それは
あかるく きいろい接吻でありました。
即ち、
・六行目の「をんなは しろいいきもののやうにむづむづしてゐました。」の「しろいいきもののやうに」の後の一字空け。
・八行目の「魚のやうに」の後に一字空けで完結する詩句存在すること。
である。特に後者は底本を読んでいても意味が通じ難く、明らかな脱文が疑われることからも、正当な補訂であると考えてよいとは思われるが、本文は敢えてそのままで出した。]
ひとすぢの髮
うつくしいひとよ、
あなたから
わたしは けふ 髮の毛をひとすぢもらひました。
それをくるくると小指にまいて、
しばらくは 月の夜をあゆむやうな心持になりました。
あなたの ややさびしみをおびたうるはしさが、
旅人のうへをながれる雲のやうに
わたしのほとりにうかんでゐるのです。
蛇行する蝶
月しろをながして 人人のたましひをとむらふ
はてしなくひろがる 冥闇の肋骨に
うねうねと ゐざりよる毒氣の花のなまめかしさ、
あたまを三角にうちのめして
黑い旗をたてようとする くるしい癡笑のかげに
わたしは 大翅翼の蝶のやうに ひらひらとうごめいた。
[やぶちゃん注:「肋骨」のルビの「ば」は底本では脱字で空白。一般通念で補訂した(後発の諸本は本詩をどれも引かない)。]
合掌する縊死者の群
雪のやうに降りつもる苦しさに
身をくねらせて 爪立ち、
ひとつらに合掌する人人の群。
みなひとしく靑蛇のやうな太紐にくびをしめくくられ、
ガラス玉の眼がうすくともり、
恐怖にふるへながらも 手はおのづと合ひ、
ひたすらに祈りのなかに沒する。
たれさがつた人閒の果物のやうに腐りかけ、
この 幻影の洪水をゆりうごかす おびただしい縊死者の群、
わたしは 大空に�廻轉する白い鴉をつかみ殺さう。
頸をくくられる者の歡び
指をおもうてゐるわたしは
ふるへる わたしの髮の毛をたかくよぢのぼらせて、
げらげらする怪鳥の寢聲をまねきよせる。
ふくふくと なほしめやかに香氣をふくんで霧のやうにいきりたつ
あなたの ゆびのなぐさみのために、
この 月の沼によどむやうな わたしのほのじろい頸をしめくくつてください。
わたしは 吐息に吐息をかさねて、
あなたのまぼろしのまへに さまざまの死のすがたをゆめみる。
あつたかい ゆらゆらする蛇のやうに なめらかに やさしく
あなたの美しい指で わたしの頸をめぐらしてください。
わたしの頸は 幽靈船のやうにのたりのたりとして とほざかり、
あなたの きよらかなたましひのなかにかくれる。
日毎に そのはれやかに陰氣な指をわたしにたはむれる
さかりの花のやうにまぶしく あたらしい戀人よ、
わたしの頸に あなたの うれはしいおぼろの指をまいてください。
[やぶちゃん注:終わりから三行目の「指をわたしにたはむれる」の「指」のルビは「び」がカスれている。諸本確認の上で訂した。]
乳白色の蛇
みじろく冷氣に絕望の垣根をおしくづし、
曉闇にひかる眞靑な星のやうに燃える眼をはびこらして
乳白色のぢろぢろする小蛇は 空間の壁を匍ひまはる。
美しい女の呼吸の動くやうな
むせかへる鈍重な香氣の花束だ!
この怪奇な 昏迷する瞬閒に
傾きかけた肉體は扮裝をこらして憤る。
死は羽團扇のやうに
この夜の もうろうとした
みえざる さつさつとした雨のあしのゆくへに、
わたしは おとろへくづれる肉身の
あまい怖ろしさをおぼえる。
この のぞみのない戀の毒草の火に
心のほのほは 日に日にもえつくされ、
よろこばしい死は
にほひのやうに その透明なすがたをほのめかす。
ああ ゆたかな 波のやうにそよめいてゐる やすらかな死よ、
なにごともなく しづかに わたしのそばへ やつてきてくれ。
いまは もう なつかしい死のおとづれは
羽團扇のやうにあたたかく わたしのうしろにゆらめいてゐる。
[やぶちゃん注:「羽團扇」鳥の羽で作った団扇。
「颯颯」は「さっさつ」(古語にあっても最初のそれは拗音化する)は風が音を立てて吹くさまを指すが、ここは「雨のあし」で、「あし」は雨・雲・風などの動く様子を足に見立てていう語であり、加えてそ「のゆくへ」を描出するのであるから、風に吹かれて斜に降る雨が、ある彼方へとゆっくりと抜けてゆくような動的な感覚描写(「みえざる」である)として違和感はない。]
夜の脣
こひびとよ、
おまへの 夜のくちびるを化粧しないでください、
その やはらかいぬれたくちびるに
なんにもつけないでください、
その あまいくちびるで なんにも言はないでください、
ものしづかに とぢてゐてください、
こひびとよ、
はるかな 夜のこひびとよ、
きれぎれの かげのあつまりである。
おもひは ふかい地のしたにうもれる。
こひびとよ、
わかばは うすあかくひらくけれど、
わたしの さらぼふこころは 地のしたにうもれる。
[やぶちゃん注: 「なんにもつけないでください、」の一字下げはママ。本詩集のここまでの編集コンセプトでは、これは一行で表記が足らなくなった場合に続いている一行であること示すものである。次の行との対句的表現からもここは、
その やはらかいぬれたくちびるに なんにもつけないでください、
その あまいくちびるで なんにも言はないでください、
とするべきところを文選工か植字工が誤ったものではあるまいか。実際、創元文庫版では、かくなっている。なお、創元文庫版では以下に見るように、二連ではなく全体一連で構成されている。
夜の脣
こひびとよ、
おまへの 夜のくちびるを化粧しないでください、
その やはらかいぬれたくちびるに なんにもつけないでください、
その あまいくちびるで なんにも言はないでください、
ものしづかに とぢてゐてください、
こひびとよ、
はるかな 夜のこひびとよ、
きれぎれの かげのあつまりである。
おもひは ふかい地のしたにうもれる。
こひびとよ、
わかばは うすあかくひらくけれど、
わたしの さらぼふこころは 地のしたにうもれる。
なお、「さらぼふ」は現在の「老いさらばう」の「さらばう」の古語で、風雨に曝され、骨と皮ばかりに瘦せ衰えるの意。
ところが実は、この詩は思潮社版では、後半の凡そ三分の一が全く異なっている。以下に示す。
夜の脣
こひびとよ、
おまへの 夜のくちびるを化粧しないでください、
その やはらかいぬれたくちびるに なんにもつけないでください、
その あまいくちびるで なんにも言はないでください、
ものしづかに とぢてゐてください。
こひびとよ、
はるかな 夜のこひびとよ、
おまへのくちびるをつぼみのやうに
ひらかうとして ひらかないでゐてください、
あなたを思ふ わたしのさびしさのために。
この思潮社版は選詩集でありながら編集方針や底本が示されていない非常に困ったものものであるが、これが現在、大勢に於いて正しいと考えられている「夜の脣」の詩形であるものらしい。とのみ述べるに留めておく。]
お前の耳は新月
おまへの耳は新月のやうである。
おしろいにいろどられ、
ほのあをく さみしく かなしく
また つつましく 媚にあふれ、
しめやかに なよなよとして、
みなつきの ゆふべのなかにうかんでゐる。
齒
こひびとよ、
おまへの齒は 五月のゆふべの月しろです。
ちひさな みつばちが
とほくから のぞいてゐますよ、
はねをならしてゐますよ。
[やぶちゃん注:「月しろ」月代・月白で月のこと。別に月の出際に東の空が白んで明るく見えることも言うが、採らない。]
雪が待つてゐる
そこには雪がまつてゐる、
そこには靑い透明な雪が待つてゐる、
みえない刃をならべて
ほのほのやうに輝いてゐる。
船だねえ、
雪のびらびらした顏の船だねえ、
さういふものが、
いつたり きたりしてうごいてゐるのだ。
だれかの顏が だんだんのびてきたらしい。
髮
おまへのやはらかい髮の毛は
ひるの月である。
ものにおくれる はぢらひをつつみ、
ちひさな さざめきをふくみ、
あかるいことばに 霧をまとうてゐる。
おまへのやはらかい髮の毛は
そらにきえようとする ひるの月である。
空にひらく花
みしらぬ影の そこはかとなくゆれうごき、
すべてのものごとの ただ遠くおもはれる
ゆきゆきて かへらぬことのは。
みじろくものは そばにあり、
空いつぱいにひらく れんげうのはな。
靑い紙の上に薔薇を置く
おまへは法體をした薔薇である、
呼吸をながながとかよはせ、
あらゆる生物のうへにとけくづれる。
月のひかりをしりぞけ、
あをくあをく こゑのない吹雪のいただきをもとめる。
みづはなく、
みづはなく、
この世のみちに消されてしまふ。
ただ
あをあをとする薔薇の花。
八つの指を持つ妬心
金屬盤のうへに
遠くおとづれてくる鐘のねをうつしうゑて
まどろみをつのぐませ、
失心した やけただれた妬心の裸身を船にのせて彫刻する。
これは 變轉する相の洪水だ!
微笑の丘をつらぬく黄金の留針だ!
むらさき色を帶びた八つの指の姿は 馬にのつて
びうびうと 狂ひ咲いてゐる。
さうして 白眼を凝らした夜の蛙が
空閒をよぎつて呼吸をしぼりだしてゐる。
[やぶちゃん注:「つのぐませ」「つのぐむ」は「角ぐむ」(「ぐむ」は体言に附いて、その様子が見え始めるという意に動詞化する接尾語)目が角のように出始めるの意。通常は葦・薄・菰などの鋭利な植物の芽吹きに対して用いる。]
夕暮の會話
おまへは とほくから わたしにはなしかける、
この うすあかりに、
この そよともしない風のながれの淵に。
こひびとよ、
おまへは ゆめのやうに わたしにはなしかける、
しなだれた花のつぼみのやうに
にほひのふかい ほのかなことばを、
ながれぼしのやうに きらめくことばを。
こひびとよ、
おまへは いつも ゆれながら、
ゆふぐれのうすあかりに
わたしとともに ささめきかはす。
道化服を着た骸骨
この 槍衾のやうな寂しさを のめのめとはびこらせて
地面のなかに ふしころび、
野獸のやうにもがき つきやぶり わめき をののいて
颯爽としてぎらぎらと化粧する わたしの艷麗な死のながしめよ、
ゆたかな あをめく しかも純白の
さてはだんだら縞の道化服を着た わたしの骸骨よ、
この人間の花に滿ちあふれた夕暮に
いつぴきの孕んだ蝙蝠のやうに
ばさばさと あるいてゆかうか。
あをい馬
なにかしら とほくにあるもののすがたを
ひるもゆめみながら わたしはのぞんでゐる。
それは
ひとひらの芙蓉の花のやうでもあり、
ながれゆく空の 雲のやうでもあり、
わたしの身を うしろからつきうごかす
よわよわしい しのびがたいちからのやうでもある。
さうして 不安から不安へと、
砂原のなかをたどつてゆく
わたしは いつぴきのあをい馬ではないだらうか。
そらいろの吹雪
この ふかまりゆく憂愁の犬のまへに
こころをふるはせ、
わたしは 季節のまばたきにやせてゆく。
おもふひとのすがたは、
うすい そらいろの吹雪のやうに
なきしづむ 心の背にたはむれる。
うつくしい脣
ふるへるぼたんのやうに
おまへのくちびるはひそひそと、
ひとめをはばかるおとをきき、
とほくのもののすがたをひきよせる。
謎のやうな
おほきな謎のやうなひかりをもつて、
おまへは このしづかなまよなかに
まへぶれもなしに わたしの身のなやみのなかへはひつてきた。
謎のやうなひかりをもつて
いんうつな鶺鴒のやうに
わたしのほとりへ あるいてきた。
癡愚
さけびのなかにいろどられ
ほのほを銀のうぶげのやうにはやす
わびしれた くせものよ、
のろひは つきのひかりをよぢて
ぎざぎざに 幕をおとす。
煙のなかに動く幻影
ひかりは おとをたて
みえない きこえない しはぶきをうみおとし、
みだれををさめる叢林のうちに羽ばたき、
鳥はひといろのかぎろひをそばだて
はるかに 現のかなたに なみだつ死をかざる。
夜の光の日向の花
よるのひかりのひなたの花、
おほくの窻窻に ひそかに脣をつける。
つねに わたしの思ひの裏にある
よるのひかりのひなたの花、
みづくろひする心を撫でて遠吠えし、
はぢらひを かなたにかくして
銀のなげきの ささやきをこもらせる。
落葉のやうに
わすれることのできない
ひるのゆめのやうに むなしさのなかにかかる
なつかしい こひびとよ、
たとひ わたしのかなしみが
おまへの こころのすみにふれないとしても、
わたしは 池のなかにしづむ落葉のやうに
くちはてるまで おもひつづけよう。
ひとすぢの髮の毛のなかに
うかびでる はるかな日のこひびとよ、
わたしは たふれてしまはう、
おまへの かすかなにほひのただよふほとりに。
おまへの息
こひびとよ、
おまへの息のかよふところに
わたしはびつしよりとぬれてゐたい。
おまへの息は
はるの日の あさのすずかぜ、
また うつろひのかげをめぐる
うすむらさきのリラのはな。
こひびとよ、
あをい花のやうに とけるここちの おまへの息は
かぎりない絲をつないで めぐります、
また 鏡のやうに わたしのこころをうつします。
靑い吹雪が吹かうとも
おまへのそばに あをい吹雪が吹かうとも
おまへの足は ひかりのやうにきらめく。
わたしの眼にしみいるかげは
二月の風のなかに實をむすび、
生涯のをかのうへに いきながらのこゑをうつす。
そのこゑのさりゆくかたは
そのこゑのさりゆくかたは、
ただしろく 祈りのなかにしづむ。
みづのほとりの姿
ふりつづく思ひ
みづのうへにふる雪のやうに
おもひはふりかかり ふりかかりするけれど
ながれるもののなかに きえてゆく。
たえまなく ふりつづくおもひは またしても
みづのおもてに おともなくうかんでは きえてゆく。
朝 の 波
― 伊豆山にて ―
なにかしら ぬれてゐるこころで
わたしは とほい波と波とのなかにさまよひ、
もりあがる ひかりのはてなさにおぼれてゐる。
まぶしいさざなみの草、
おもひの緣に くづれてくる ひかりのどよもし、
おほうなばらは おほどかに
わたしのむねに ひかりのはねをたたいてゐる。
[やぶちゃん注:「伊豆山」〈いづさん(いずさん)〉は静岡県熱海市伊豆山(湯河原と熱海の間)にある海縁りの温泉地。これは当地の高みにある古社伊豆山神社からの眺めと読みたい。大手拓次の詩の中に固有地名が出現するのは極めて例外的で具体な眺望をもとにした叙景という点でもすこぶる特異な詩と言えよう。]
白い階段
かげは わたしの身をさらず、
くさむらに うつろふ足長蜂の羽鳴のやうに、
火をつくり、 ほのほをつくり、
また うたたねのとほいしとねをつくり、
やすみなくながれながれて、
わたしのこころのうへに、
しろいきざはしをつくる。
靑靑とよみがへる
わたしの過去は 木の葉からわかれてゆく影のやうに
よりどころなく ちりぢりに うすれてゆくけれど、
その笛のねのやうな はかない思ひでは消えることなく、
ゆふぐれごとに、
小雨する春の日ごとに、
月光のぬれてながれる夜夜に、
わたしの心のなかに
あをあをと よみがへる。
日はうつる
手のなかに 日はうつり、
あゆみを うつす、
にほひのひらく とほぞらのかほへ。
しろい火の姿
わたしは 日のはなのなかにゐる。
わたしは おもひもなく こともなく 時のながれにしたがつて、
とほい あなたのことに おぼれてゐる。
あるときは ややうすらぐやうに おもふけれど、
それは とほりゆく 昨日のけはひで、
まことは いつの世に消えるともない
たましひから たましひへ つながつてゆく
しろい しろい 火のすがたである。
月にぬれた鳥
月にぬれた鳥のやうに
おまへは くさのしげみに のがれ、
すぎゆく風を ながめる。
とぢた眼に
うすうすにとぢた わたしの眼に、
とほい日の あなたのすがたがうつる。
かげになりゆく とほい日の
そらいろのすがたが うつる。
こゑををさめた 小鳥のやうに
そよかぜに ながれさる。
みづいろの風よ
かぜよ、
松林をぬけてくる 五月の風よ、
うすみどりの風よ、
そよかぜよ、そよかぜよ、ねむりの風よ、
わたしの髮を なよなよとする風よ、
わたしの手を わたしの足を
そして 夢におぼれるわたしの心を
みづいろの ひかりのなかに 覺まさせる風よ、
かなしみとさびしさを
ひとつひとつに消してゆく風よ、
やはらかい うまれたばかりの銀色の風よ、
かぜよ、かぜよ、
かろくうづまく さやさやとした海邊の風よ、
風は おまへの手のやうにしろく つめたく
薔薇の花びらのかげのやうに ふくよかに
ゆれてゐる ゆれてゐる、
わたしの あはいまどろみのうへに。
睫毛のなかの微風
そよかぜよ、
こゑをしのんでくる そよかぜよ、
ひそかのささやきにも似た にほひをうつす そよかぜよ、
とほく 旅路のおもひをかよはせる そよかぜよ、
しろい 子鳩の羽のなかにひそむ そよかぜよ、
まつ毛のなかに 思ひでの日をかたる そよかぜよ、
そよかぜよ、そよかぜよ、ひかりの風よ、そよかぜは
胸のなかにひらく 今日の花 昨日の花 明日の花。
よりかかる鐘の音
また いつとなく
鐘は こころのなかの とびらをたたき、
しろく よりかかる。
おもひでの ほたるぶくろの花のゆれるやうに
鐘のねは すがたもなく、
遠遠に こころの窗によりかかり、
しづけさの かぜのおもてに 手をのべる。
[やぶちゃん注:「遠遠」のルビはママ。正しくは歴史的仮名遣「とほどほ」、現代仮名遣「とおどお」であるが、私にはこれですこぶる自然に響く。]
雪色の薔薇
またしても 五月のゆふぐれにきてわたしの胸にさくばらのはな、
ひとつの影を ともなひ、
ひといろの にほひをこめて、
さよさよと咲く ばらのはな。
ゆふぐれの あをいしづけさのなかに咲く
しろい雪色のばらのはな、
こころのなかに 咲きいでる
さざめ雪色のばらのはな。
あはれな あはれな 雪色のばらのはな、
ことばをなくした こゑをなくした
ちらちらする おもひにふける ばらのはな。
ひとりのひとりの ばらのはな、
眼をとぢた 雪色の あをあをとするばらのはな。
[やぶちゃん注:「さざめ雪」細雪に同じい。こまかい雪、また、まばらに降る雪。水を含んだ細い真っ直ぐに静かに降る雪。]
みづのほとりの姿
すがたはみづのほとりにうかぶけれど、
それはとらへがたない
とほのいてゆく ひとときの影にすぎない。
わたしの手のほそぼそとのびてゆくところに
すがたは ゆらゆらとただよふけれど
それは みづのなかにおちた鳥のこゑにすぎない。
とほざかる このはてしない心のなかに
なほ やはやはとして たたずみ、
夜も晝も ながれる霧のやうにかすみながら、
もとめてゆく もとめてゆく
みづのほとりのゆらめくすがたを。
そよぐ幻影
あなたは ひかりのなかに さうらうとしてよろめく花、
あなたは はてしなくくもりゆく こゑのなかのひとつの魚、
こころを したたらし、
ことばを おぼろに けはひして、
あをく かろがろと ゆめをかさねる。
あなたは みづのうへに うかび ながれつつ
ゆふぐれの とほいしづけさをよぶ。
あなたは すがたのない うみのともしび、
あなたは たえまなく うまれでる 生涯の花しべ、
あなたは みえ、
あなたは かくれ、
あなたは よろよろとして わたしの心のなかに 咲きにほふ。
みづいろの あをいまぼろしの あゆみくるとき、
わたしは そこともなく ただよひ、
ふかぶかとして ゆめにおぼれる。
ふりしきる さざめゆきのやうに
わたしのこころは ながれ ながれて、
ほのぼのと 死のくちびるのうへに たはむれる。
あなたは みちもなくゆきかふ むらむらとしたかげ、
かげは にほやかに もつれ、
かげは やさしく ふきみだれる。
薔薇の散策
[やぶちゃん注:以下の連作の章番号は、底本では頗るポイントが小さい半角である。]
序
こゑはこゑをよんで、とほくをつなぎ、香芬のまぶたに羽ばたく過去を塗り、靑く吹雪する想ひの麗貌を象る。
舟はしきりにも噴水して、ゆれて、空に微笑をうゑる。みえざる月の胎兒よ。時のうつろひのおもてに 鏡を供へよう。
1
地上のかげをふかめて、昏昏とねむる薔薇の脣。
2
白熱の俎上にをどる薔薇、薔薇、薔薇。
3
しろくなよなよとひらく、あけがた色の勤行の薔薇の花。
4
刺をかさね、刺をかさね、いよいよに にほひをそだてる薔薇の花。
5
翅のおとを聽かんとして、水鏡する 喪心の あゆみゆく薔薇。
6
ひひらぎの葉のねむるやうに ゆめをおひかける 霧色の薔薇の花。
7
いらくさの影にかこまれ 茫茫とした色をぬけでる 眞珠色の薔薇の花。
8
默禱の禁忌のなかにさきいでる 形なき蒼白の 法體の薔薇の花。
9
鬱金色の月に釣られる 盲目の ただよへる薔薇。
10
ひそまりしづむ木立に 鐘をこもらせるうすゆきいろの薔薇の花。
11
すぎさりし月光にみなぎる 雨の薔薇の花。
12
吐息をひらかせる ゆふぐれの 喘ぎの薔薇の花。
13
ひねもすを嗟嘆する 南の色の薔薇の花。
14
火のなかにたはむれる 眞晝の靴をはいた黑耀石の薔薇の花。
15
くもり日の顏に映る 大空の窗の薔薇の花。
16
掌はみづにかくれ 微風の夢をゆめみる 未生の薔薇の花。
17
鵞毛のやうにゆききする 風にさそはれて朝化粧する薔薇の花。
18
みどりのなかに 生ひいでた 手も足も風にあふれる薔薇の花。
19
眼にみえぬ ゆふぐれのなみだをためて ひとつひとつにつづりあはせた 紅玉色の薔薇の花。
20
現なるにほひのなかに 現ならぬ思ひをやどす 一輪のしづまりかへる薔薇の花。
21
眼と眼のなかに 空色の時をはこぶ ゆれてゐる 紅と黄金の薔薇の花。
22
朝な朝な ふしぎなねむりをつくる わすられた耳朶色のばらのはな。
23
かなしみをつみかさねて みうごきもできない 影と影とのむらがる 瞳色のばらのはな。
24
ゆたゆたに にほひをたたへ 靑春を羽ばたく 風のうへのばらのはな。
25
陽の色のふかまるなかに 突風のもえたつなかに なほあはあはと手をひらく 薄月色の薔薇の花。
26
またたきのうちに 香をこめて みちにちらばふ むなしい大輪のばらのはな。
27
はだらの雪のやうに 傷心の夢に刻まれた 類のない美貌のばらのはな。
28
悔恨の虹におびえて ゆふべの星をのがれようとする 時をわすれた 内氣な内氣な ばらのはな。
29
魚のやうにねむりつづける 瀲灔としたみづのなかの かげろふ色のばらの花。
30
白鳥をよんでたはむれ 夜の霧にながされる 盲目のばらのはな。
31
あをうみの 底にひそめる薔薇の花 とげとげとしてやはらかく 香氣の鐘をうちならす薔薇の花。
32
けはひにさへも 心ときめき しぐれする ゆふぐれの 風にもまれるばらのはな。
33
あをぞらのなかに 黄金色の布もて めかくしをされた薔薇の花。
34
微笑の砦もて 心を奥へ奥へと包んだ 薄倖のばらのはな。
35
鬱積する笛のねに 去りがての思慕をつのらせる 靑磁色のばらのはな。
36
さかしらに みづからをほこりしはかなさに くづほれ 無明の淚に さめざめとよみがへる薔薇の花。
[やぶちゃん注:章番号「29」は底本ではナンバー落ち(脱字)であるが補った。その一節にある「瀲灔」は波が光にきらめくさまをいう。]
散文詩
綠の暗さから
時計が朝の十時を打つといふのに、どうしたものか、ほんとにさびしい蛙めが、くる、くる、くる、くる、とないてゐる。
古くさい小池の綠には、薄紫のつつじ、生々とした笹の葉、楓や松や檜や、石菖や、がある。
蛙めが、ごうる、ごうると鳴く。
昨日植ゑたばかりの石竹の鉢がいくつも石燈籠の側の日かげにある。
五月のあつたかい日光にあつたまつて、あのぶ樣な蛙めが一生一度の喉笛をならして吹く……てるてる、くるくる、…… がをうるぐうる。
わたしは、うつとりとして蛙に感謝してゐました。
げつ、げつげつ、いや滅法もない陰氣な音。
琅玕の片足
私は過去を顧る。私は抑壓せられて、苦しい殘虐の中から、暗い星穴の過去へ逃れた。過去を抱かうとしたが、過去も亦ちぢれちぢれの蜘蛛の絲にからまれてゐる。褐色の煤が玉をなしてゐる。
その過去は細つたなりをしてふらふらと宙に迷つてゐる。私はそれを死人の手のやうな力のない鉤で搔き寄せようとしてゐる。私は決して過去を讃美しようとはしない。むしろそんな芳烈な香の無い過去をしげしげと嫌つてゐた。その過去を引きよせて、その中に慰めを求めようとする今の心は、目もあてられないほどに腐爛してゐる。悲しみは古い沼のなかに浮く靑い藻のやうに陰氣に溫かい。嫉妬の白い鬼はいぶかしく坐つてゐる。
紫藍色の車はせはしく過去へきしる。
わたしの過去は醜い蟹のやうにあゆんでゐる。折れて曲つた足にはいろんな物がくつついてゐる。
過去は香箱のなかにうたたねをしてゐる。
こはれ易いその飾りのなかに果敢ない私語をもらしてゐる。
[やぶちゃん注:「琅玕」は「らうかん(ろうかん)」と読み、 暗緑色または青碧色の半透明の硬玉の名。転じて美しいものの譬えにも用い、色がその鉱物に似るところから青々とした美しい竹の謂いでもあるが、無論ここはその鉱物、英語で“Imperial Jade”(インペリアル・ジェイド)と呼ばれる最高級品の翡翠のことを指す。思潮社版「大手拓次詩集」では第一段落の「ちぢれちぢれの蜘蛛の絲」を、
過去を抱かうとしたが、過去も亦ちぎれちぎれの蜘蛛の絲にからまれてゐる。
とし(「絲」は底本では「糸」)、「紫藍色の車はせはしく過去へきしる。」の後の一行空きはなく、しかも、最後の二つの段落は変則的に二字下げとなって,
しかも「私語」に「ささやき」のルビを振っている。
過去は香箱のなかにうたたねをしてゐる。
こはれ易いその飾りのなかに
果敢ない私語をもらしてゐる。
この部分の詩形が異様に異なるので、思潮社版の全詩を再度本テクストの正字表記に準じて表示しておく。
琅玕の片足
私は過去を顧る。私は抑壓せられて、苦しい殘虐の中から、暗い星穴の過去へ逃れた。過去を抱かうとしたが、過去も亦ちぎれちぎれの蜘蛛の絲にからまれてゐる。褐色の煤が玉をなしてゐる。
その過去は細つたなりをしてふらふらと宙に迷つてゐる。私はそれを死人の手のやうな力のない鉤で搔き寄せようとしてゐる。私は決して過去を讃美しようとはしない。むしろそんな芳烈な香の無い過去をしげしげと嫌つてゐた。その過去を引きよせて、その中に慰めを求めようとする今の心は、目もあてられないほどに腐爛してゐる。悲しみは古い沼のなかに浮く靑い藻のやうに陰氣に溫かい。嫉妬の白い鬼はいぶかしく坐つてゐる。
紫藍色の車はせはしく過去へきしる。
わたしの過去は醜い蟹のやうにあゆんでゐる。折れて曲つた足にはいろんな物がくつついてゐる。
過去は香箱のなかにうたたねをしてゐる。
こはれ易いその飾りのなかに
果敢ない私語をもらしてゐる。
個人的には散文詩である以上、「ささやき」のルビ以外、思潮社版詩形を私は支持しない。]
帽子の谷
固く四角の黑の大理石で作つた柩のやうに緘默を守つてる街のなかを、一本足の靑灰色の帽子をかぶつた男が步いて居る。暗黃色と漆黑との煉つたやうに交つてる珊瑚珠の太い杖をついて、右の足には草の乾いた褐色の大きい赤靴をはめて、敷石の上をむささびの羽のやうにぱつぱつと抱へては動いてる。そのあとから黑い沈んだ僧服をきた男がゆく。墓標の陰からのぼる淡黄の息のやうに太陽は、なめらかな調子の好い女唄うたひの橫腹をたたく。
殘虐は街の森林に住むリスだ。敏捷にかけめぐつてその眼のなかにある靑い觸角に生々しくふるへる欺瞞を誇示する。此の栗鼠は、流星のやうに大河の底に飛翔する勞れた魂を追ひすがつては乳色の齒をたてる。街の森林は漠々とおびえて、ますます固凍した柩の姿にあらはれる。
黄金の卵をつらねて作つた頸飾りをかけて、女體の妖精が、此の吐息する闇の宮殿に一群の異形をおくつた。
靑灰色の帽子と黑い僧服とは、ある廣い橋の上でお互ひに面を合せた。二人は知つた仲であつた。かろく手を握つて微笑をとりかはせた。二人の頭の上に小さい暗い鳥がキイと妙に鳴いてとんだ。河の水はゆるく濁つて流れてゐる。
[やぶちゃん注:これはもうマグリット(René François Ghislain Magritte 一八九八年~一九六七年)と共時的に(大手拓次の生没年は明治二〇(一八八七)年~昭和九(一九三四)年)にマグリットである(マグリットの最初のシュールレアリスム的作品は一九二六年作の“Le Jockey perdu”(迷える騎手)とされる。]
二ひきの幽靈
黑の黄との交つてる鳥の毛のやうな林のなかにうごめいてるものがある。呼吸がミモザの花の香のやうにもつれて空にあがる。誰が見ても之は分らないのだ。誰でも感ずることも出來ないのだ。誰でもそこに興味を起すこともないのだ。それは平凡で、ありふれた、世の常の事にすぎないからだ。誰でもかひなでの魂ばかり持つてるものだから、ずんずんと通りすぎて行くのだ。路行く人々はおどけた話に興じながら老いた馬の背中によろよろとゆられて、知らず知らずのうちに陷穽の美しく飾つた入口の前へ來て動けなくなるのだ。可笑しい有樣になつて、丁度蟲かなんぞのやうに匍ひまはつてゐるが、さてなかなか思ふやうに足も動かない手も動かない、頭は勿論働かないでだらけてゐる。聲はしはがれてしまつて腐つた木馬の咆えるやうだ。
わたしはこんな人を見るとあはれまずにはゐられなくなる。けれど此の人々は一向に不思議も何にも知らないかのやうに、どれも假面のやうに平氣の固い顏をしてゐる。そんな妙にこはばつた顏を見ると、なぐつてやりたくなるが、又その眼が一種の鬱悶を湛へてゐるやうで、それを打たうとする私自身の魂が舞ひ上つて後の方へ翔けり去る。
しばらくすると、殷殷と羽打の響をまきちらしながら、もりかへしてくる。ぐるぐると舞ひめぐつて顏をかくした。
今度は翼の空鳴りが聞える。聞える。
翼の幻影が環舞ひをする。
幻影が消える。幻影が消える。
黑曜石のやうに光る珠が驟雨のやうに降つて來た。
しつかりとした死骸の骨がかちかちと鳴るのが聞えはじめた。
わたしは、此の時に歡喜の頂上に達して人生を腹のなかに吸ひ込んだ。
[やぶちゃん注:「かひなで」は「搔い撫で」で、表面を撫ぜただけの、ものの深奥の核心を知らぬこと、通り一遍の意であると思われるが、その場合は本来がこれは「掻き撫で」の音変化であるから「かいなで」が正しい。思潮社版では正しく「かいなで」となっている。]
木造車の旅
くらいなかに大きなテーブルがある。その上には黴の花のやうにぽつとした鱗が浮いてゐる。うう、ううといふ呻りごゑがして物すごい脅迫がはひ出して來る。くらいくらい此の一室のなかに飆風のやうに悽愴の氣がみなぎつた。見ると半身血みどろになつた物がうごき出した。まるで、けしの花をつけたやうに肉がただれてひらひらしてゐる。ばたりといふ音がして、それがテーブルの上にたふれた。赤い花がぱつとくづれて、黑い征矢がほとばしつた。テーブルがむくむくとしたかと思ふと、地鳴りのやうに、力强い洞あなから出る音のやうな、ぼうつとした空漠のひびきがわき出した。そして靑白い赤味をおびた焰がぐるぐるととりまいて、恰も舞踏するかの如くに見えた。妖音と怪焰とが交互に消長していつまでも絕えなかつた。
けれど、此の室は身を刺すやうな寒さであつた。
扉がぎいとあいて、一人の老婆がしづかにはひつて來た。肥つた豚の母親のやうな顏付をした老婆である。その眼ばかりが物欲しげにうごいてゐる。
餘りの寒さにはつとおどろいて身じろいた。焰のもえてるなかへ手をさし入れてその亡骸を撫でた。すると焰はおひおひに靑白く、うすぼんやりと消えて行つた。同時にひびきもしづまつた。にやにやと笑ひながら、その太い腕で血のついてる皮をいぢつてる。
それはうら若い少女の身體である。
老婆は悲しげに獨語しながら、その髮をなで、傷口をしらべ、その美しい額や掌に接吻した。さも滿足らしくあきらめの思ひがただようて見えた。ふところから小さい匣を出して、ぢつと眺めた。その匣は暗いなかにぎらぎらと光つた。老婆のふるへる手がその蓋をとつて、なかからカードのやうな黑い札を出しはじめた。その一枚がチンとテーブルの上におちて音がすると、靑白い怪火が復たもえ立ち、ぱつと急に消えた。そしてテーブルの緣がぼろぼろと缺けおちたかと思ふと、あたり一面に小さな黑ん坊が立ちはだかつてゐた。丁度手の指位の大きさの黑ん坊である。それがじりじりと老婆の手に集つてきた。老婆はそつと拂ひのけると、さらさらと金屑のやうな音がして散つてしまふ。老婆の手が少女の身體をあたためるほどになると、じりじりと黑ん坊の化生がよりはじめる。うるささうにはらひのけると、さらさらとちる。
老婆はざらつと小匣をまけると、黑い札が澤山に出た。その一枚を少女の亡骸の額に、一枚を唇に、一枚を鳩尾に、一枚を腹に、又一枚づつを兩足に、兩手にのせた。それが了ると、しとやかに跪いて、長い祈禱をした。實に長い長いおいのりであつた。
その間黑ん坊の化生はテーブルの緣に復歸してしまつてゐた。
長い熱心な祈禱が了ると、その神樣の札を匣のなかへもどし、安堵したやうにうやうやしくおじぎをして、そろそろと此の室を去つた。
老婆が去ると、またあとに焰がもえはじめた。初のは以前のやうに黑くただれたやうに廻轉したが、それもしばらくの閒で、今度は美しいばら色に變化した。それと共に、室はあかるく、はなやかに、はればれしくなつた。そのばら色の焰のなかには、をりをり神々しい瞳がうつつた。
「幸あるものよ、迷ふなかれ。」一つの聲がいつた。
「世はすすむなり、さざめきつつ、くるめきつつ、」ほかの聲がいつた。
薔薇色の焰はいろいろの物の形にもなる。
ばらの花、裸體、紅の盃、男の姿。
時として劍をたづさへた古の騎士ともなる。
「力なき美のなきがらよ、さむるなかれ、
歌はいましの魂を飾らんず、
行け、ともしびの國、いのりの國」
ささやかな遠い聲が呼んだ。
餓ゑたるものは鐵壁をも破壞し、凛々とつきざる河床をつくつて流れる。しかも、その希望はうづくまり、命はうたたねに耽り、情熱は瀕死の吐息をもらしてゐる。つめたい夜の香をあふつて渦卷をなし、懶惰に伸びてゆく乳白色の魂を惑はし、欺き、抱擁の墓標の頂きに置き去りにする。うゑたる者は輾轉として盲目の世界のなかへ突き進んでゆく。
永遠の調べよい面帕は妖言の囃子につれて空といはず、地といはず、闇といはず、明るみといはず飜りとぶ。雨のうろつきもの、風の道化者、凡ての生物は恐ろしい期待の笑を交して端坐してゐる。典麗の亡魂はまだ暮れやらぬ秋の凋落を拾ひつつ野をあるき、山をたどり、谿をあさり、とどまりなく欲念の襲ひにかられてゐる。
餓ゑたるものは淚もなく佇んでゐる。
暴風は帆舟をからんでさわいでゐる。
嘴の折れた鳥は水の上に狂亂して落ちて來た。
海の怒號は萬象を席捲して十重二十重にうねりをうつ。變幻極まりない長嘯と呻吟とがとこしなへの微動をあらはす。
[やぶちゃん注:「間」と「閒」の混在はママ。
「飆風」は飄風とも書き、急に激しく吹く風で、旋風・疾風の謂い。音は「へうふう(ひょうふう)」であるが、ここは「つむじかぜ」か「はやて」と読んでいるようには感じられる。
「面帕」被きで、私はここは死者の面を蔽う、顔かけ・面布・打ち覆いなどとも呼ぶ白布をイメージした。
なお、この詩は思潮社「大手拓次詩集」では後半に有意に大きな異同がある(特に一行空きと表現の大きな違い一箇所と、最後の三行の消失である)。本詩での表記に準じて正字化して全詩を示し、ルビの有無も含め、異なる箇所(最低で単語単位)に下線を引いた(欠損部の場合はその欠損のある一文全体に引いた。「閒」は「間」で揃えた。なお、こちらでは直接話法の頭が明らかに一字下げになっているのも異なる)。
*
木造車の旅
くらいなかに大きなテーブルがある。その上には黴の花のやうにぽつとした鱗が浮いてゐる。うう、ううといふ呻りごゑがして物すごい脅迫がはひ出して來る。くらいくらい此の一室のなかに飆風のやうに悽愴の氣がみなぎつた。見ると半身血みどろになつた物がうごき出した。まるで、けしの花をつけたやうに肉がただれてひらひらしてゐる。ばたりといふ音がして、それがテーブルの上にたふれた。赤い花がぱつとくづれて、黑い征矢がほとばしつた。テーブルがむくむくとしたかと思ふと、地鳴りのやうに、力强い洞あなから出る音のやうな、ぼうつとした空漠のひびきがわき出した。そして靑白い赤味をおびた焰がぐるぐるととりまいて、恰も舞踏するかの如くに見えた。妖音と怪焰とが交互に消長していつまでも絕えなかつた。
けれど、此の室は身を刺すやうな寒さであつた。
扉がぎいとあいて、一人の老婆がしづかにはひつて來た。肥つた豚の母親のやうな顏付をした老婆である。その眼ばかりが物欲しげにうごいてゐる。
餘りの寒さにはつとおどろいて身じろいた。焰のもえてるなかへ手をさし入れてその亡骸を撫でた。すると焰はおひおひに靑白く、うすぼんやりと消えて行つた。同時にひびきもしづまつた。にやにやと笑ひながら、その太い腕で血のついてる皮をいぢつてる。
それはうら若い少女の身體である。
老婆は悲しげに獨語しながら、その髮をなで、傷口をしらべ、その美しい額や掌に接吻した。さも滿足らしくあきらめの思ひがただようて見えた。ふところから小さい匣を出して、ぢつと眺めた。その匣は暗いなかにぎらぎらと光つた。老婆のふるへる手がその蓋をとつて、なかからカードのやうな黑い札を出しはじめた。その一枚がチンとテーブルの上におちて音がすると、靑白い怪火が復たもえ立ち、ぱつと急に消えた。そしてテーブルの緣がぼろぼろと缺けおちたかと思ふと、あたり一面に小さな黑ん坊が立ちはだかつてゐた。丁度手の指位の大きさの黑ん坊である。それがじりじりと老婆の手に集つてきた。老婆はそつと拂ひのけると、さらさらと金屑のやうな音がして散つてしまふ。老婆の手が少女の身體をあたためるほどになると、じりじりと黑ん坊の化生がよりはじめる。うるささうにはらひのけると、さらさらとちる。
老婆はざらつと小匣をまけると、黑い札が澤山に出た。その一枚を少女の亡骸の額に、一枚を唇に、一枚を鳩尾に、一枚を腹に、又一枚づつを兩足に、兩手にのせた。それが了ると、しとやかに跪いて、長い祈禱をした。長い長いおいのりであつた。
その間黑ん坊の化生はテーブルの緣に復歸してしまつてゐた。
長い熱心な祈禱が了ると、その神樣の札を匣のなかへもどし、安堵したやうにうやうやしくおじぎをして、そろそろと此の室を去つた。
老婆が去ると、またあとに焰がもえはじめた。初めは以前のやうに黑くただれたやうに廻轉したが、それもしばらくの間で、今度は美しいばら色に變化した。それと共に、室はあかるく、はなやかに、はればれしくなつた。そのばら色の焰のなかには、をりをり神神しい瞳がうつつた。
「幸あるものよ、迷ふなかれ。」一つの聲がいつた。
「世はすすむなり、さざめきつつ、くるめきつつ」ほかの聲がいつた。
薔薇色の焰はいろいろの物の形にもなる。
ばらの花、裸體、紅の盃、男の姿。
時として劍をたづさへた古の騎士ともなる。
「力なき美のなきがらよ、さむるなかれ、
歌はいましの魂を飾らんず、
行け、ともしびの國、いのりの國」
ささやかな遠い聲が呼んだ。
餓ゑたるものは鐵壁をも破壞し、凛凛とつきざる河床をつくつて流れる。しかも、その希望はうづくまり、命はうたたねに耽り、情熱は瀕死の吐息をもらしてゐる。つめたい夜の香をあふつて渦卷をなし、懶惰に伸びてゆく乳白色の魂を惑はし、欺き、抱擁の墓上の女標の頂に置き去りにする。うゑたる者は輾轉として盲目の世界のなかへ突き進んでゆく。
永遠の調べよい面帕は妖言の囃子につれて空と云はず、地と云はず、闇と云はず、明るみと云はず飜りとぶ。雨のうろつきもの、風の道化者、凡ての生物は恐ろしい期待の笑を交して端坐してゐる。典麗の亡魂はまだ暮れやらぬ秋の凋落を拾ひつつ野をあるき、山をたどり、谿をあさり、とどまりなく欲念の襲ひにかられてゐる。
餓ゑたるものは淚もなく佇んでゐる。
*
私は「女標」という単語を不学にして知らない。識者の御教授を乞うものである。。――抱擁した墓の上の女を、その墓の墓標の頂きに置き去りにする」と読むのかい?……しかしそれは美事な悪文以外の何ものでもないし、大手拓次が使う詩語とも思われないがね……]
狂人の音樂
ぐいぐい曳つぱつてみると、ちやうど眞赤にただれた花がくづれるやうにほかりほかり落ちた。それが今のわたしの、影ばかりを食べてゐる魂の埃だ。野鼠の毛のやうに荒だつてゐながら、また其の外貌にしたしみを持つてゐた。うす白い、すすばんだ埃は强い日光のなかに好んで落ちた。もえ上るほど熱い光線はいよいよ此の怠けた魂の埃を掃きおとす。黄金の無數の破片が一種の、凋落を偲ばせる澁滯調をやりだしたので、魂はこつそりと、ひろい悲しい張幕のかげにかくれた。
「おい待つてくれ、待つてくれ。」わたしが大空に向けて祈りをささげてゐると、暗い地の底からこんな聲ををりをりきいた。しかし、わたしは他人の干渉などに耳をかす暇はないので、一心をこめて祈りをつづけた。しばらくすると、ひどく混亂したうめきや物音が川の流れのやうに足元にひろがつてゐた。
あをい冠をつけて
こんこんと流れゆく水の行くへの彼方にはみづみづしい漿果のたわわにかをる綠の野がある。力なく、たよりなく、かすかに燃える火の空色を抱きながら、わたしは恍惚とおぼろにさまよひあるくのである。わたしは灰色にけぶる靑い冠をつけてながいながい裾をひいて無言をまもつてゐる。
みたまへ、金褐色の大鳥はあやしげな叫びをひびかし黑い小さな渡り鳥のむれは幻のやうに集合離散してはてしがない。絹の絲のやうにいましめの綱のすがたがふかい空のなかに媚をしたたらしてゐる。
わたしはすすまう。手をしばられても、足をしばられても、顏も背中もしばられても、わたしの魂を迎へてくれるみどりの里へゆかう。うちつれてならす幻怪の太鼓のおとよ、いつまでも、わたしのこの淸純な憧憬の社をめぐれ。
惡の花のあまく咲きこぼれ、みだれさわぐ豐麗なからだのうちにわたしの芽はたえまもなく生長する。
[やぶちゃん注:思潮社「大手拓次詩集」では、二・三段落が(漢字は本表記に準じて正字化した。相違部分に私が下線を引いた)、
みたまへ、金褐色の大鳥はあやしげな叫びをひびかし、黑い小さな渡り鳥のむれは幻のやうに集合離散してはてしがない。絹の絲のやうにいましめの網のすがたがふかい空のなかに媚をしたたらしてゐる。
わたしはすすまう。手をしばられても、足をしばられても、顏も背中もしばられても、わたしの魂を迎へてくれるみどりの野へゆかう。うちつれてならす幻怪の太鼓のおとよ、いつまでも、わたしのこの淸純な憧憬の社をめぐれ。
となっている。鳥という点では「網」、「いましめ」という点では「綱」、畳み懸ける条件句の荒寥感からは「みどりの野」、「わたしの魂を迎へてくれる」という期待感からは「みどりの里」といった印象を受ける。]
暗のなかで
くらい倉庫のなかに、ひとりではひつていつた。そこには、銀の槍のやうなものが、ぴかりぴかりと光つてゐた。私の背中には、おもい、幅のひろい光の板のやうなものがのしかかつてゐる。私は疲れた足をやすめようとして、そばの箱のうへに腰をのせた。それは非常につめたい物であつた。私は自分の足がその冷たい物に吸ひとられてしまふやうに感じた。
いつとなく私は腕をくんでゐた。二本の足は、ぴくぴくうごいて物におそはれてゐた。私の過去が生き返つてきて足にくつついてゐたのである。あをいあばた顏の過去が、らんぐひ齒でがりがりと足にかみついてふるへてゐたのである。過去は煙となつてもえたち、ゆるやかに身のまはりにひろがつて、とほいほのかな笛の音をふいてゐる。私は、その濃い深い霧のなかにつかつてしまつてゐたのだ。
愛戀する惡の華
―逸見享におくりて―
泉のごとく永遠の幻想を涌出し、淸淨無比たる跪拜の淚をさそふものは、妖艷なる惡の華よりたちのぼる一道の香氣である。その香氣は縷縷としてひびきを鳴らし、白顏なる死の面上にたつ吾等の肉身に悠久の生命をあたへる。
みたまへ、
われらの愛戀する惡の華は、地獄の花、天國の花、人閒の花、神の花、人倫の花、藝術の花、
しかして、淚の花、愛の花、惠みの花、悦びの花、熱の花、力の花、
また闇の花、光明の花、苦悶の花、享樂の花、擾亂の花、平和の花、破壞の花、創造の花、
われらの同じく美しきこの惡の華を愛戀する思ひ若き人々よ、したしく手を結んで、この惡の華のさんらんたる藝術の園にわれらの白い足を入れようではありませんか。
わたしの手をきつて下さい。
わたしの腕をきつて下さい。
わたしの足をきつて下さい。
さうするとき、
銀色の瞳はあつたかに、ゆるやかになりだします。
さうざうしい血の海から、ほそくすんなりとのびあがつて咲く惡の華は、
美しさかぎりなく、
神のベエゼのなかにその花粉をちらします。
[やぶちゃん注:六段落目「われらの同じく美しきこの惡の華を愛戀する思ひ若き人々よ、したしく手を結んで、この惡の華のさんらんたる藝術の園にわれらの白い足を入れようではありませんか。」の「この惡の華のさんらんたる藝術の園」の「この」は底本では「二の」となっている。これでは意味も不通であり、見るからに誤植が疑われる。唯一これを採録している思潮社版「大手拓次詩集」によって訂した。
また、次の「わたしの手をきつて下さい。/わたしの腕をきつて下さい。/わたしの足をきつて下さい。」は底本では明らかに有意な二字下げで、そこで「491」頁が終わっており、頁を捲って「462」頁では、明らかに二字下げの位置から「さうするとき、」以下の五行が分かち書きになっている。ところが前に掲げた思潮社版ではこれらが総て一字下げ位置まで上がって、前の散文と変わらぬ書式で続いている。そして、ここが大事な(私が恣意的に変更を加えた)ところであるが、「わたしの足をきつて下さい。」と「さうするとき、」の間に行空けはない。確かに、「わたしの足をきつて下さい。」と「さうするとき、」は他の頁の版組から考えると「わたしの足をきつて下さい。」は「491」頁の最終行であり、「さうするとき、」は「492」頁の第一行目に当たっていることが分かる。しかし、これは単に物理的な見かけの位置であって、私は詩想からもこの間に行空きが存在するとしてしかこの詩を読めない(読まない)。しかも改頁の効果がそれを増幅する。恐らくは私の勝手な恣意的な仕儀としてこれは認められないであろうが、私は敢えて私が読む印象をここでは大事にして示したいと考えた。大方の御批判を俟つものである。
「逸見享」既注であるが再注しておく。大手拓次の盟友で本詩集の編者・装幀者でもある画家逸見享(明治二八(一八九五)年~昭和一九(一九四四)年)。和歌山県出身。中央大学卒業後、ライオン歯磨意匠部に勤務する傍ら、木版画を始め、大正八(一九一九)年の第一回日本創作版画協会展に入選、日本版画協会でも活躍した。「新東京百景」を分担制作、友人であった大手拓次の詩集の装丁・編集も彼が手がけた(講談社「日本人名大辞典」の解説に拠る)。本詩集の編集・装幀も彼の手になる。]
言葉の香氣
ことばは、空のなかをかけりゆく香料のひびきである。ゆめと生命とをあざなはせて、ゆるやかにけぶりながら、まつしろいほのほの肌をあらはに魂のうへにおほひかぶせるふしぎのいきものである。かはたれのうすやみにものの姿をおぼろめかす小鳥のあとのみをである。まぼろしは手に手をつないで河のながれをまきおこし、ものかげのさざめきを壺のなかに埋めていきづまらせ、あをじろいさかづきのなかに永遠の噴水をかたちづくる。
ことばのにほひは、ねやのにほひ、沈默のにほひ、まなざしのにほひ、かげのにほひ、消えうせし樂のねのにほひ、かたちなきくさむらのにほひ、ゆめをふみにじる髮ひとすぢのにほひ、あへども見知らずにゆきすぎる戀人のうつりが、神のうへにむちうつ惡魔のにほひ、火のなかに月をかくすおちばのにほひ、ただれた雜草のくちびるに祈をうつす祕密のにほひ、女のほぞに秋の手のひらを通はせる微笑のにほひ、とらへがたい枝枝のなかをおよぐ光のにほひ、肉親相姦の罪の美貌のにほひ、忘却の塔のいただきにふりかかる候鳥の糞のにほひ、人人を死にさそふ蘭の怪花のにほひ、ひといろにときめきあからむ處女のほほのゆふべのにほひ、荒鷲のくちばしにからまる疾風のにほひ、天上する蛇のうろこに想念の月光を被せる僧門のにほひ、窓より窓に咲いてゆくうすずみいろの、あをいろの、べにのしまある風のにほひ、欲情のもすそにほえる主なきこゑのにほひ、五月のみどりばのきらきらとそよぐもののけのにほひ、うまれいでざる胎兒のおほはれた瞼のにほひ、大地の底にかきならす湖上の笛のにほひ、はびこる動亂の霧に武裝をほどく木馬のにほひ。
まことに、ことばはたましひのつくるそよかぜのながれである。
[やぶちゃん注:岩波文庫版の原子朗編「大手拓次詩集」では異同がある。以下に本底本に従いながら正字化したものを示す。相違箇所(ルビの有無を含む)の下線は私が引いた。
言葉の香氣
ことばは、空のなかをかけりゆく香料のひびきである。ゆめと生命とをあざなはせて、ゆるやかにけぶりながら、まつしろいほのほの肌をあらはに魂のうへにおほひかぶせるふしぎのいきものである。かはたれのうすやみにものの姿をおぼろめかす小鳥のあとのみをである。まぼろしは手に手をつないで河のながれをまきおこし、ものかげのさざめきを壺のなかに埋めていきづまらせ、あをじろいさかづきのなかに永遠の噴水をかたちづくる。
ことばのにほひは、ねやのにほひ、沈默のにほひ、まなざしのにほひ、かげのにほひ、消えうせし樂のねのにほひ、かたちなきくさむらのにほひ、ゆめをふみにじる髮ひとすぢのにほひ、はるかなるうしろすがたのにほひ、あへども見知らずにゆきすぎる戀人のうつりが、神のうへにむちうつ惡魔のにほひ、火のなかに月をかくすおちばのにほひ、ただれた雜草のくちびるに祈をうつす祕密のにほひ、女のほぞに秋の手のひらを通はせる微笑のにほひ、とらへがたい枝枝のなかをおよぐ光のにほひ、肉親相姦の罪の美貌のにほひ、忘却の塔のいただきにふりかかる候鳥の糞のにほひ、人人を死にさそふ蘭の怪花のにほひ、ひといろにときめきあからむ處女のほほのゆふべのにほひ、荒鷲のくちばしにからまる疾風のにほひ、天上する蛇のうろこに想念の月光を被せる僧門のにほひ、窓より窓に咲いてゆくうすずみいろの、あをいろの、べにのしまある風のにほひ、欲情のもすそにほえる主なきこゑのにほひ、五月のみどりばのきらきらとそよぐもののけのにほひ、うまれいでざる胎兒のおほはれた瞼のにほひ、大地の底にかきならす湖上の笛のにほひ、はびこる動亂の霧に武裝をほどく木馬のにほひ。
まことに、ことばはたましひのつくるそよかぜのながれである。
以下は私藪野直史の勝手な空想である。……「ことばは、」「かはたれのうすやみにものの姿をおぼろめかす小鳥のあとのみ」「である」――「ことばのにほひは、ねやのにほひ、沈默のにほひ、まなざしのにほひ、かげのにほひ、消えうせし樂のねのにほひ、かたちなきくさむらのにほひ、ゆめをふみにじる髮ひとすぢのにほひ、」そして、つい逢はざりし人の面影、「あへども見知らずにゆきすぎる戀人のうつりが」である――そしてまたそれは、「女のほぞに秋の手のひらを通はせる微笑のにほひ」であり、「肉親相姦の罪の美貌のにほひ、忘却の塔のいただきにふりかかる候鳥の糞のにほひ、人人を死にさそふ蘭の怪花のにほひ、ひといろにときめきあからむ處女のほほのゆふべのにほひ、荒鷲のくちばしにからまる疾風のにほひ」なのだ――その形象は遂に「窓より窓に咲いてゆくうすずみいろの、あをいろの、べにのしまある風のにほひ」となり、「欲情のもすそにほえる主なきこゑのにほひ」となり、「五月のみどりばのきらきらとそよぐもののけのにほひ」からヒラニア・ガルパ、黄金の胎児、「うまれいでざる胎兒のおほはれた瞼のにほひ」へ翔び、「大地の底にかきならす湖上の笛のにほひ」として舞い上がったかと思うと、一瞬にして「はびこる動亂の霧に武裝をほどく木馬のにほひ」へと堕ちてゆく。――「まことに、ことばはたましひのつくるそよかぜのながれ」なの「である。」……この拓次節ともいうべき波状的に畳み掛ける、恐るべき粘性のめくるめく変化のフェテイシズムは慄っとするほど素敵だ。……この詩は個人的にすこぶる附きで偏愛する詩なのである。]
白い鳥の影を追うて
わたしの感覺の窓がすつかりととぢられてしまふ。さうして、ばうばくとしたひとつの羽音がきこえる。その羽音は香料をふくみ、音樂をわきたたせ、舞踊をはしらせるのである。わたしはしづんでゆく、しづんでゆく、かぎりない地軸のなかへ、黃金の針のやうにきりきりきりきりとしづんでゆく。なほ、わたしはおそろしい靜かさと激動との追迫によつて、さらにはてしない混沌のなかへしづんでゆく。もはや、わたしの身のほとりには、四季の幻影は咲きこぼれ、意慾の發端は八面の舌をもやし淸麗な神體はそよかぜのやうにやはらかくそよいでゐる。
わたしは噴水をのぞみながら、しばられた孤獨のわなにかけられて、ふかくふかく世紀をながれゆく驅橋をわたり、破滅のうへにれいろうとした芽をふく墓標をいだくのである。
水晶色の感情はなげられた母體の腹をさいてさけびをあげ、蛇をよみがへらせ、蛙をまねき、犬をいつくしみ、なめくぢを吸ひ、馬をそだて、狼と接吻するのである。
月のあかりのほのかにさすやうに、たえまなくしづんでゆくわたしの身に、いつとはなしにささめ雪ふりしきり、たそがれの風みだれ、海原の波舞ひあがり、曠野のくさむらにゆく白狐のあしおとがきこえる。
太古の銅盤のさざらさざらとひしめく騷音のかなたに、水邊の蘆のやうにあでやかにしなづくり、ほのめく微音の化粧してとびゆくもの。はツとしてみれば、わかき一羽の白鳩である。幻影は洪水のやうにあふれてきはまりなく、鳩のゆくへに追ひせまるのである。鳩はすずしくまひあがり、かろくめぐり、いなづまの爪のやうに消えさる。鳩は白い尾のかげをのこし、うすあかい指のかげをのこし、みづのながれをひきおこし、ふしぎにも傳統のゆめのそびらをたたいて靑空へかけり、あたらしい癡人の手をみちびくのである。
このとき、わたしの足は薔薇の噴水となり、わたしの肌は薰香にむせぶ眞珠のたまとなる。
香水夜話
まつくらな部屋のなかにひとりの女がたつてゐた。
部屋はほのあたたかく、うすい霧でもただよつてゐるやうで、もやもやとして、いかにもかろく、しかも何物かの息かがさしひきするやうに、やはらかなおもみにしづまりかへつてゐる。
をんなは、すはだかである。ひとつのきれも肌にはつけてゐない。ひとつの裝飾品も身につけてはゐない。
髮はときながしたままである。油もくしもつけてはゐない。
顏にも手にも足にも、からだのすべてに何ひとつとして色づけるもののかげもないのである。
女は、いきたまま、まつたくの生地のままの姿である。肌の毛あなには闇がすひこまれてゐる。べにいろの爪には闇の舌がべろべろとさはつてゐる。ふくよかなももには、しどけない闇のうづまきがゆるくながれてゐる。
まつしろい女のからだは、あつたかい大きな花のやうにわらつてゐる。手もわらつてゐる。足の指もわらつてゐる。しろくけぶるやうな女のまるいからだは、むらさきのやみのなかに、うごくともなくさやさやとおよいで、かすかな吐息をはいてゐる。
女は白いふくろふだ。その足はしろいつばめだ。
闇は、きり、きり、きり、きりと底へしづみ、女の赤いくちびるは、白く、あをじろく、こころよいふるへをかみしめて、ほそい影をはいてゐる。
女の眼は、朝の蛇のやうにうす赤く黑ずんできて、いつぴきの蝙蝠がにげだした。
女のからだは水蛭のやうによぢれて、はては部屋いつぱいにのびひろがらうとしてゐる。
あへぎ、あへぎ、息がたえだえにならうとしてゐる。
このとき、女の左の乳房にリラの花の香水を一滴たらす。香水のにほひは、さくらのつぼみのやうなぽつちりとした乳房にくひついて、こゑをあげてゐる。
噴水の上に眠るものの聲
ひとつの言葉を抱くといふことは、ものの頂を走りながら、ものの底をあゆみゆくことである。
ひとつの言葉におぼれて、そのなかに火をともすことは、とりもなほさず、窓わくのなかに朝と夕の鳥のさへづりを生きのままに縫箔することである。
ひとつの言葉に、もえあがる全存在を髣髴させることは、はるかな神の呼吸にかよふ刹那である。
ひとつの言葉を聽くことは、むらがる雨のおとを聽くことである。數限りない音と色と姿とけはひとを身にせまるのである。
ひとつの言葉に舌をつけることは、おそろしい鐘のねの渦卷に心をひたすことである。空々寂々、ただひそかに逃れんとあせるばかりである。
ひとつの言葉に身を投げかけることは、恰も草木の生長の貌である。そこに芽はひらき、葉はのびあがり、いそいそと地に乳をもとめるのである。この幸福は無限の芳香をもつ。
ひとつの言葉を眺めれば、あまたの人の顏であり、姿であり、身振であり、そして消えてゆかうとするあらゆるものゝ別れである。含まれたる情熱の器は、細い葉のそよぎにゆらめいて、現を夢ににほはせるのである。
ひとつの言葉に觸れることは、うぶ毛の光るももいろの少女の肌にふるへる指を濡れさせることである。指はにほひをきゝ、指はときめきを傳へ、指はあらしを感じ、指はまぼろしをつくり、指は焰をあふり、指はさまざまの姿態にあふれる思ひを背負ひ、指は小徑にすゝり泣き、なほさらに指は芬香の壺にふかぶかと沈みてあがき、壺のやうな執著のころもに自らを失ふのである。
ひとつの言葉を嗅ぐことは、花園のさまよふ蜂となることである。觀念は指をきり、わきたつ噴水に雨をふらし、をののく曙は闇のなかに身をひるがへし、やはやはとし、すべてはほのかなあかるみの流れに身ぶるひをしてとびたつのである。
ひとつの言葉は、影となり光となり、漾うてはとどまらず、うそぶきをうみ、裂かれては浮み、おそひかかる力の放散に花をおしひらかせる。
ひとつの言葉は空中に輪をゑがいて星くづをふくみ、つぶさにそのひびきをつたへ、ゆふべのおとづれを紡ぐのである。
ひとつの言葉は草の葉である。その上の螢である。その光である。光のなかの色である。色のまばたきである。まばたきの命である。消なば消ぬがのたはむれに似てゆらびく遠い意志である。
ひとつの言葉はしたたりおちる木の實であり、その殼であり、その果肉であり、その核であり、その汁である。さうして、木の實の持つすべてのうるほひであり、重みであり、動きであり、ほのほであり、移り氣である。
ひとつの言葉を釣らんとするには、まづ倦怠の餌を月光のなかに投じ、ひとすぢの絲のうへをわたつてゆかなければならぬ。そのあやふさは祈りである。永遠の窓はそこにひらかれる。
ひとつの言葉は跫音である。くさむらのなかにこもる女の跫音である。とほのいては消えがてに、またちかづくみづ色の跫音である。そのよわよわしさは、ながれる蝶のはねである。おさへようとすればくづれてしまふ果敢なさである。
ひとつの言葉はみえざるほのほである。闇である。明るみである。眠りである。ささやきである。圓である。球體である。處女である。絲につながれた魚である。咲かうとする白いつぼみである。常春の年齡である。流れであり、風であり、丘であり、吹きならす口笛の蜘蛛である。
ひとつの言葉にひとつの言葉をつなぐことは花であり、笑ひであり、みとのまぐはひである。白い言葉と黑い言葉とをつなぎ、黃色い言葉と黑い言葉とをつなぎ、靑の言葉と赤の言葉とを、みどりの言葉と黑い言葉とを、空色の言葉と淡紅色の言葉とをつなぎ、或は朝の言葉と夜の言葉とをつなぎ、晝の言葉と夕の言葉とをむすび、春の言葉と夏の言葉とを、善と惡との言葉を、美と醜との言葉を、天と地との言葉を、南と北との言葉を、神と惡魔との言葉を、可見の言葉と不可見の言葉とを、近き言葉と遠き言葉とを、表と裏との言葉を、水と山との言葉を、指と胸との言葉を、手と足との言葉を、夢と空との言葉を、火と岩との言葉を、驚きと竦みとの言葉を、動と不動の言葉を、崩壞と建設の言葉を……つなぎ合せ、結びあはせて、その色彩と音調と感觸とあらゆる混迷のなかに手探りするいんいんたる微妙の世界の開花。
まことに言葉はひとつの生き物である。それは小兒の肌ざはりである。やはらかく、あたたかく、なめらかに、ふしぎにうごめき、もりあがり、けむりたち、びよびよとしてとどまらず、こゑをしのび、ほほゑみをかくし、なまなまとして夢をはらみ、あをくはなやぎ、ほそくしなやかに、風のやうにかすかにみだれ、よびかはし、よりかかり、もたれかかり、夜毎にふくらみ、ほのかに赤らみ、すべすべとしてねばり、はねかへり、ぴたぴたと吸ひつき、絕えず生長し、ひかりかがやき、よろこびを吹き、感じやすく、響きやすく、ことごとくの音をきき色をうつし、時とともにとびさる感情の繪をゑがき、日とともに新しく、唄の森林をはびこらせる。
ひとつの言葉をえらぶにあたり、私は自らの天眞にふるへつつ、六つの指を用ゐる。すなはち、視覺の指、聽覺の指、嗅覺の指、味覺の指、觸覺の指、溫覺の指である。さらに、私はあまたの見えざる指を用ゐる。たとへば年齡の指、方角の指、性の指、季節の指、時間の指、祖先の指、思想の指、微風の指、透明な毛髮の指、情慾の指、飢渇の指、紫色の病氣の指、遠景の指、統覺の指、感情の生血の指、合掌の指、神格性の指、縹渺の指、とぎすまされてめんめんと燃える指、水をくぐる釣針の指、毒草の指、なりひびく瑪瑙の指、馬の指、蛇の指、蛙の指、犬の指、きりぎりすの指、螢の指、鴉の指、蘆の葉の指、おじぎさうの指、月光の指、太陽のかげの指、地面の指、空間の指、雲の指、木立の指、流れの指、黃金の指、銀の指……指。私の肉體をめぐる限りない物象の香氣の幕に魅せられて、これらの指といふ指はむらがりたち、ひとつの言葉の選びに向ふのである。その白熱帶は無心の勤行である。
[やぶちゃん注:第六連の「いそいそ」の後半は底本では踊り字「〱」。
第八連の「芬香」は「ふんかう(ふんこう)」と読む。よい匂い。芳香に同義。
第十二連の「ゆらびく」は「搖ら曳く」で、ゆれて棚引くの意。
第十三連と第十四連は底本では行空きなしで連結しているが、諸本を参照に分離した。
第十七連の「淡紅色」には、思潮社版及び岩波版では「ときいろ」とルビが振られている。
最終第十九連の「嗅覺の指、味覺の指、」は底本では「嗅覺の指味覺の指、」となっている。諸本と校合、脱字として訂した。]
日食する燕は明暗へ急ぐ
このみちはほがらかにして無である。
ゆるぎもなく、恍惚としてねむり、まさぐる指にものはなく、なお髣髴としてうかびいづるもののかたち。それは明暗のさかひに咲く無爲の世界である。はてしなく續きつづきゆく空である。
それは、放たれる佛性の眼である。
みづからのものをすてよ。
みづからをすてよ。
そこにかぎりない千年の眼はうつつとなく空靈の世界を通觀する。
うごくもの
ながれるもの、
とどまるもの、
そのいづれでもなく、いづれでもある繩繩たる大否定の世界にうつりすむのである。
萬物は一如として光被され、すべては mortal と immortal の境を撤しさるのである。
あらゆる相對を離れた絕對無絕對空の世界にうつりすむのである。
すべてをはなれて門に入るのである。
なほ、この相對とまみえる絕對をもこえて、いやさらに不可測の、思惟のゆるされざる虛無のなかにうつりすむのである。
みだれたる花のよびごゑである。客觀的統體として絕えざる轉位に向ふのである。
それは靑面の破壞である。
あらゆるものの否定である。
あらゆるアプリオリとアポステリオリとの全的否定である。冥闇闇である。
美そのものに對しての惡魔的挑戰である。わたしは私自身の有する律動を破壞して泥土に埋めてしまはうとするのである。
破壞である。否定である。
さらに破壞である。否定である。
なほさらに、このふたつのものの果てしない持續は、靑色帶をなして未知へすすみゆくのである。
無韻の雷鳴である。
窻外の私語は、唯美主義の自縛を延長した風葬のさけびである。
虛無の白い脚に飾られるガアタア勳章こそ階段をのぼる SOLLEN である。
この néant の世界にあつて、私はみたされ、ひろげられ、微風のやうな香油に足を沒するのである。
言葉の圓陣にわたしは空閒を虐殺して、遲遲とする。
この表現の飛翔する危機をむすんで、逸し去らうとする魚は影の客である。
かたちももとめず、
かげももとめず、
けはひももとめず、
にほひももとめず、
こゑももとめず、
おもひももとめず、
わたしは、みづからを寸斷にきりさいなみ、ふみにじり、やぶりすてて、うららかに消えうせ、
ひとつの草となり、
ひとつの花となり、
ひとつの蟲となり、
ひとつの光となり、
ひとつの水となり、
ひとつの土となり、
ひとつの火となり、
ひとつの風となり、
ひとつの石となり、
この必然の、しかも偶然の生長に對して、わたしは新しい生命をむさぼり得つつ流れゆくのである。
螢のやうにひかる十二頭の蛇の眼がぢれぢれとする。
わたしは、そこにはてしない森林をひろげる怪物料理をゆめみる。
太陽のラムプが足をぶらさげてでてきたのである。
靑狐は、はらわたをだしてべろべろとなめる。
あたらしい DIABOLISME のこころよい花園である。
ブレエクより、ビアヅレエより、モロオより、ロオトレエクより、ドオミエより、ベツクリンより、ゴヤより、クリンゲルより、ロツプスより、ホルバインより、ムンクより、カムペンドンクより、怪奇なる幻想のなまなまと血のしたたるクビンである。
鬼火はうづまいて、鴉は連れ啼き、もろもろの首は、疾風のやうにおよいでゆき、水中に眼をむく角をもつ魚、死體の髮をねぶる異形なる軟體動物、熱帶林の怪相、蛇とたはむれる微笑の首は睡蓮の咲く池のうへに舞ひ、女體の頭部に鑿をうつ化物、寢室の女怪、のつぺりの淫戲、髑髏と接吻する夫人、昆蟲と狎れあそぶ巨人、空腹にみづからの腕をかむ乞食、酒のごとく香水を愛する襤褸の貴族、桃色大理石のやうな肌をもつ片眼の娘、あをい泡を鼻から吹きだす白馬の沈默、足におほきな梵鐘をひきずる男…………
迷路に鳥はわたり、かすかな遠啼きのなかに心は蟬脱する。
光はうちにやぶれ、闇はそとにひらき、ひたすらなる渾沌に沿うて風は木の實をうむのである。
それら怪奇なる肉身の懊惱にぎらぎらと鱗を生やす心靈は、解體して、おぞおぞとし、わたしの足は地をつらぬき、わたしの手は天をつらぬき、わたしの身は空閒にみちあふれる。
すべてはうしなはれるのである。
すべてはきえさるのである。
すべては虛無である。
この虛無にうつりすむにあたり、はじめてわたしは生れるもののすがたにうつりゆくのである。ひろがりは、わたしにきたるのである。充たされも、わたしにきたるのである。まことの創造の世界にうつるのである。
なにものかが、わたしの手をひくのである。なにものかが、わたしのなかにあふれるのである。それは不死の死である。不滅の滅である。永遠の瞬閒である。
わたしは、白い蛙となつて水邊にうかぶ。
雨はほそくけぶり、
時はながれる。
わたしの足は月かげのたむろである。
わたしの足は靑蛇のぬけがらである。
わたしの足は女の唾である。
わたしの足は言葉のほとぼりである。
わたしの足は思ひのたそがれである。
わたしの足は接吻のほそいしのびねである。
わたしの足は相對の河である。
わたしの足はりんご色の肌のいきれである。
わたしの足はみほとけの群像である。
わたしの足は飛ぶ鳥の糞である。
わたしの足はものおとのうへをすべる妖言である。
わたしの足は嘴をもつ地獄の狂花である。
わたしの足は陰性のもののすべてである。
わたしの足をおまへの腕にうめて、もだえるくるしみは、つやめく疾患である。
みしらぬ人人のために路をひらく。
それは眞珠に飾られたみちである。
夢を食む白い狼は風をきつてそばだち、すみれいろの卵をうみおとすのである。
心はうしなはれ、からだはうしなはれ、思ひはうしなはれ、ひとりたたずむほとりに、動きはつたはりきたるのである。
あだかも花のにほひのやうになかだちを越えて、いそいそとくるのである。
たたずみはたふれる。
すすみもたふれる。
とどまりもたふれる。
まつたき失ひのうちに、おほきなるもののみちあふれてくるのである。
すがたは抽象をないがしろにして、いきいきとあらはれ、とぶがごとく楚楚として現じきたるのである。
やすみなく光をむかへつつ、庭園のなかにほころびかける花である。
たわわにみのる樹はゆれながら步みをうつして、まどろむのである。
その さやぐ葉のむらがりのなかにやどるすがたはもとほり、世にあらたなるさびしみを追ひたてるのである。
花びらは顏を照らして、ひそみをあらはにし、たえざる薰風をそよがせるのである。
あをいものは、さそはれることなく、みづからのうごきに生きて、さよさよとそだちゆくのである。
かをりあるそよかぜは、とほくのみちに夢をひらかせ、ただよふ舟のなかに魂の土產をのこし、ひとびとのうしろかげに柑子色の言葉をはるばるとかざるのである。
わたしは、ゆれゆれる風のなかに、風のとがりに、ふかぶかとゆめみるのである。
[やぶちゃん注:画家については、私が作品を思い浮かべることが出来なかった二人についてのみ注したので悪しからず。
「うごくもの」岩波版「大手拓次詩集」では最後に読点がある。脱字かとも思われるが、敢えてママとする。
「繩繩たる」久遠に続き絶えぬさま。
「mortal と immortal の境」特に特殊な意味合いを附加する気はしない。――「厳然たる死」と「永遠の不死」の境――の謂いと採る。
「撤しさる」その場から永久に除き去る。
「ガアタア勳章」(The Order of the Garter:正式には“The Most Noble Order of the Garter”という。)は一三四八年にエドワード三世によって創始されたイングランドの最高勲章の名称。グレートブリテン及び北アイルランド連合王国の栄典において騎士団勲章(order)の最高位とされる。勲章にはそのモットー“Honi soit qui mal y pense”(イングランドの古語アングロ・ノルマン語で「思い邪なる者に災いあれ」の意)と刻印されてある。勲章の大綬の色がブルーであることから「ブルーリボン」とも呼ばれる(以上はウィキの「ガーター勲章」に拠る)。
「SOLLEN」(ドイツ語)当為。ゾルレン。
「この néant の世界にあつて、私はみたされ、ひろげられ、微風のやうな香油に足を沒するのである。
言葉の圓陣にわたしは空閒を虐殺して、遲遲とする。」以上の詩句は岩波版「大手拓次詩集」では、二つの行の間に一行空きが施されてある。底本では見開きの改頁であるが、組から考えて一行空きはない。また、私自身一行空きを求めない。従って、連続させた。
・「néant」(フランス語)無。虚無。空。
・「DIABOLISME」(英語)①魔術・妖術。②悪魔のような仕業。魔性。③悪魔主義。悪魔崇拝。私は③の「悪魔崇拝」の意で採る。
「クリンゲル」マックス・クリンガー(Max Klinger 一八五七年~一九二〇年)。ドイツの画家(グーグル画像検索「Max Klinger」)。
「カムペンドンク」ハインリヒ・カンペンドンク(Heinrich Campendonk 一八八九年~一八五七年)。ドイツ(後にオランダに帰化)の画家(グーグル画像検索「Heinrich Campendonk」)。
「なにものかが、わたしの手をひくのである。なにものかが、わたしのなかにあふれるのである。それは不死の死である。不滅の滅である。永遠の瞬閒である。
わたしは、白い蛙となつて水邊にうかぶ。」この詩句は岩波版「大手拓次詩集」では、二つの行の間に一行空きはない。
「その さやぐ葉のむらがりのなかにやどるすがたはもとほり、……」の「その」の後の一字空けはママ。岩波版も同じ。]
綠色の馬に乘つて
彼には空にとどく眼があつた。生成のまへのものに觸れる指と齅覺とを持つてゐた。フランソア・ギヨンの漾ふ姿は繫縛のうちに動き、羽ばたき、生きのびる帆のひらめきを敎へる。
卵はいろづいて凡てを魅了する。
影のなかにある影の芽、未生の世界に泳ぐ大噴水塔の鴉は木の葉の黃昏に呼吸をしたたらしてゐる。門柱の鐘を鳴らす一人の訪客は、その步道のかたはらに莟をもつてわらひかける微風の毛を意識してゐるけれど、その足は限りなくしばられてゐるのである。あの夜の虹の私語にしばられてゐるのである。
ひそかに、しかも渾身の力の動きに押しすすめられてゆく路は、昏迷の落日の丘ではないか。大旋風の滿開の薔薇のごとく咲きみだれてゐる眞鍮製の圓錐體である。そこに盲目の手をいだして闇の砲彈をさぐりあて、全身のうつろに植ゑこみ、蓮華の花祭のやうに童貞を點火するのである。あらゆる無意識は機構の深淵に溺れて死に瀕しつつ綠色光を放つて世界をこえる。手負の魂は白い假面をかぶつて路の側にたたずみ、泥濘の皿に朝の髯をきつてゐる。幻想のなかに浮ぶ靑い耳はおそはれる火のもとである。それは廢滅の武器ではなく、盛りあがる愛の花束の散步ではないか。
MARIA UHDEN の奇怪なる繪を見よ。ひとつの心の心靈現象のやうなゆがめられた人間のあへぎが、べつとりと血をはいてゐる。十六本の指に電光をともして蛙の小徑をゆけ。悲しみの繁吹は軟風にたはむれる馬と馬とのひろがりをとつて、その生成の水のうへにそそりたつのである。
掌を彌縫する雷鳴はしきりに曉の舌をだして、連翹の笑ひをしてゐる。この癡笑の糞は裸形の香炎をふみつぶして焦燥する一羽の白鳥である。逆行する空間に蠱惑の螢をとばし、念念として凝固し、雲散霧消する。この未發の風景に遠吠する消息は靑い牢獄である。表現からかくされた存在の胎動に味到し、屈伸自在の埒外にひるがへるもの、黑布をつけた群盲の永遠の音なき葬列である。
いつさいは暗くとどろき、ひれふして、將に發せんとするものの危機を持續するのである。
わたしは自らを俎上にのせ、昏昏として胚珠のごとく靜觀する。震動體の月光を織り紡いで吹く彼の佛蘭西象徴派のひとむれと、水に浮く百合の花をこもごもに取りあひ、華麗なる臥床にゆらめく影をくゆらせたのである。しかしながら、いま私は不思議なる門扉のまへにたつ。怖ろしい地鳴は悉く直立の白刃を私に擬してゐる。そしてわたしの背後に啼きつづける蒼白の「抒情の鳥」を刺し殺さうとしてゐる。この陰慘にして快適なる風景の脚は破れざる殼をつけたるまま、黑と金との宗敎の庭園に漫步する不行跡をあへてする。
盲目こそ境を絕したる透徹の明である。
やぶれざる前の破れこそ聲である。
うごかざる前の動きこそ行ひである。
波動の全圓に影はせまりきて、ひたりしづみ、觸れえざる生身の肌に恍惚としておよがせる魚の姿である。
[やぶちゃん注:「MARIA UHDEN」マリア・アーデン(一八九二年~一九一八年)。ドイツの女流版画家(グーグル画像検索「Maria Uhden」)。
「繁吹」は「しぶき」と読む。飛沫。水滴。
「彌縫」は「びほう」と読む。(一般には失敗や欠点を一時的に)とりつくろうことをいう。
「味到」は「みたう(みとう)」と読み、内容を十分に味わい知ることをいう。
「盲目こそ境を絕したる透徹の明である。」の「明」は思潮社版「大手拓次詩集」では「卵」である。誤植とも思われるがママとした。「盲目」と「明」は寧ろ、詩句としてしっくりくるからである。]
無爲の世界の相について
ながいあひだ私は寢てゐる。
何事もせず、何物も思はない、心の無爲の世界は、生き生きとして花のさかりの如く靜かであつた。
わたくしは日頃から、眼に見えないものへ、また形のないものへのあこがれを抱いてゐたのであつた。この願ひはいつ果されるともなく、わたくしの前に白く燃え續けてゐた。
偶然にとらへられてその白く燃えてゐる思念が、この無爲の世界のなかに此上もなくふさはしく現はれてきたのであつた。
その時、心の「外へのよそほひ」は凡てとりさられ、心は心みづからの眞の姿にかへつて、ほがらかに動きはじめたのであつた。
心は表面の影を失ひ、内面の自由な動きの流れへ移つたのである。
わたくしは見知らぬ透明な路をあるいてゆくのである。
心のおもては閉ざされて暗い。けれど形よりはなれようとする絕えざる内心の窓はらうらうとして白日よりもなほ明らかである。
感情は靑色の僧衣をきてかたはらに佇んでをり、たえず眠りの橫ぶえをふいてなぐさめてゐるではないか。
[やぶちゃん注:本詩を以って詩集「藍色の蟇」の詩本篇が終わる。因みに、本詩題は岩波版「大手拓次詩集」では、
病間錄
――無爲の世界の相に就て――
となっており(正字化して示した)、二段落目の「この願ひはいつ果されるともなく」の部分は同岩波版では、
この願ひは、いつ果されるともなく
と読点が入っている。]
孤獨の箱のなかから
おぼえがき
大 手 拓 次
わたしは ながいあひだ蝸牛のやうにひとつの箱のなかにひそんでゐた。ひとりで泡をふいてゐた。さうして、わたしのべとべとな血みどろの手が、ただひとり人 北原白秋氏にむかつて快くさしのべられた。白秋氏のみえない手がつねにわたしの指にさはつた。「ザムボア」に、「地上巡禮」に「ARS」に、「詩と音樂」に、そしてまた「近代風景」に、ちやうど大正元年から今まで十五年といふ長い間、わたしは常に白秋氏のあたたかき手のうちにあつた。そのあたたかき手にわたしは育てられたのである。
しかも、このながい十五年のとしつきのあひだ、わたしはただの一度も白秋氏をおとづれはしなかつた。未知の戀人をおもふやうにたえず氏を思ひつつ、一度もおとづれることができなかつた。なんといふ内氣な、はにかみやの、氣むづかしい、けつぺきな、ぴりぴりとあをじろい神經のふるへるわがまま者だつたのであらう。けれども、わたしの心のすべては私の詩を通じて氏にひらかれてゐたのである。
わたしは淚のあふれるやうな敬愛の情をたたへながらも、さびしくものおとのしない孤獨の箱のなかにとぐろをまいてゐた。
いんうつな心、くらい心、はげしい情熱のもどかしさ。まつたくその頃のわたしは、耳ののびる亡靈であつた。みどりの蛇であつた。めくらの蛙であつた。靑白い馬であつた。つんぼの犬であつた。笛をふく墓鬼であつた。しばられた鳥であつた。
わたしの憂鬱は本質的でどうともすることが出來なかつた。自然にこのうすぐらい花が散つてゆくのを待つよりほかはなかつた。
白秋氏のやはらかい手はどんなに私にとつてうれしかつたか。
うれしくなればなるほど蝸牛は角をかくし、蛇はとぐろをまいた。
まだごのあひだにあつて、萩原朔太郞氏は、ときどき火花のやうな熱情のこもつた友愛を私にしめしてくだすつた。
さらに、大木惇夫氏にはなにやかやいろいろおほねをりにあづかつてゐる。こんど、白秋氏をおたづねするやうになつたのも、氏があつたればこそである。
わたしボオドレエルといふ古風な黃色いランプをともして、ひとりとぼとぼとあるいてきたのであつた。その孤獨の道に、みどり色のあかるいみちびきの光をともして下すつたのが白秋氏である。十五年といふ長いあひだである。おもふさへ、うれしくなる。ありがたくなる。
この詩集の刊行は、白秋氏のひとかたならぬ御配慮にあづかつたたまものである。ここに護しんで御禮申上げます。
詩の選擇も、自分としてはすゐぶん思かきつてしたつもりである。私の初期に屬する吉川惣一郞の名で發表したものは大部分とり、「詩と音樂」時代のものは、駄作が多いので、四分の一ぐらゐにすててしまつた。また、をりがあつたら、惡いのをすててゆかうと思つてゐる。詩の排列は凡て年代順にしてある。
[やぶちゃん注:以下の詩群の後の解説は底本ではポイント落ちで全体が二字下げである。詠み易くするために各詩群の間に一行空きを入れた。]
陶器の鴉
大正元年秋から大正二年末までの作品で、吉川惣一郞の名のもとに「ザムボア」及び「創作」に載つたものである。
球形の鬼
私の最も窮迫した時代大正三年頃の作で、やはり吉川惣一郞の名で、「地上巡禮」に載つたものである。
濕氣の小鳥
大正四、五、六年頃の作品で、そのうち「朱の搖椅子」から「むらがる手」までは「ARS」に載つたものである。
黃色い帽子の蛇
大正七、八、九年頃の作品で、「無言の歌」及び「あをちどり」に載つたもの、「詩と音樂」に載つたものである。
香料の顏寄せ
大正九、十年頃の作品で、「詩と音樂」に載つたほかは、未發表のものである。
白い狼
大正十年の作品、即ち私の病氣中の作である。「詩と音樂」に載つたもののほかは、未發表のものである。
木製の人魚
大正十年、十二年の作品で、すべて「詩と音樂」に載つたもののみである。
みどりの薔薇
大正十二年の作品で、うち四、五篇をのぞいて、他は凡て「詩と音樂」に載つたものである。
風のなかに巢をくふ小鳥
大正十二年の作品で、「詩情」及び「日光」に載つたものなどがある。
莟から莟へあるいてゆく
大正十四、五年の作品で、「詩と音樂」「日光」「アルス・グラフ」「近代風景」に載つたものである。
黃色い接吻
昭和二、三、四年の作品で、「近代風景」に載つたものである。
みづのほとりの姿
昭和七年病氣療養のため伊豆山溫泉に行つた前後及び八年南湖院に入院して書いたもの、このうち「そよぐ幻影」が八年八月の「中央公論」に載つたほかは未發表のものである。
薔薇の散策
作品として最後のものである。
散文詩
綠の暗さから・琅玕の片足・帽子の谷 は大正元年の作で未發表のものである。
二ひきの幽靈・木造車の旅 は大正二年の作で未發表のものである。
狂人の音樂・あをい冠をつけて は大正三年の作で、未發表のものである。
暗のなかで は大正四年の作で、未發表のものである。
愛戀する惡の華 は大正六年作で、未發表のものである。
言藁の香氣・白い鳥の影を追うて・香水夜話 は以上大正三年の作で、未發表のものである。
噴水の上に眠るものの聲 は大正十五年の作、「近代風景」に載つたものである。
日食する燕は明暗へ急ぐ は昭和二年の作で、「近代風景」に載つたものである。
綠色の馬に乘つて は昭和三年の作で、「近代風景」に載つたものである。
無爲の世界の相に就いて は昭和五年の作で、未發表のものである。
[やぶちゃん注:「散文詩」の項の二行目は底本では「二ひきの幽靈・木造車の旅は 大正二年の作で未發表のものである。となっているが誤植として訂した。
「大木惇夫」(おおきあつお 明治二八(一八九五)年~昭和五二(一九七七)年)は翻訳家・詩人。既注であるが再注しておく。昭和七(一九三二)年までは大木篤夫と名乗っていた。広島生。太平洋戦争中の各種戦争詩や軍歌・戦時歌謡で有名だが、児童文学作品の他、「国境の町」などの歌謡曲や「大地讃頌」を始めとした合唱曲及び社歌・校歌・自治体歌等の作詞も多く手掛けた。青年期に文学者を志し、広島商業学校(現在の広島県立広島商業高等学校)の学生時代より与謝野晶子・吉井勇・若山牧水らの短歌に感化されて短歌を始めが、その後、三木露風や北原白秋の詩を知り、特に白秋に深い感銘を受けたという。学校卒業後は一時、銀行に勤めたが文学への志向止み難く、二十歳で上京、博文館で働きながら文学活動を行った。またこの頃、キリスト教の受洗も受けている。その後、同棲している女性の肺結核療養のため、博文館を辞めて小田原に引っ越し、文筆活動に専念したが、これが契機となって、当時、小田原に在住していた北原白秋の知遇を得、大正一一(一九二二)年に、大手拓次の詩の発表の舞台ともなった白秋・山田耕筰編の雑誌『詩と音楽』創刊号に初めて詩を発表した。大正一四(一九二四)年にはジョバンニ・パピーニ「基督の生涯」の翻訳をアルスから出版してベスト・セラーになるとともに、処女詩集「風・光・木の葉」を白秋序文附きで同じくアルスから出版、その後も一貫して詩人として白秋と行動をともにした。昭和一〇~一五(一九三〇年代後半)から歌謡曲の作詞も手掛けるようになり、一世を風靡した東海林太郎の「国境の町」の他、「夜明けの唄」「隣の八重ちゃん」「八丈舟唄」「雪のふるさと」などを作詞、また知られたスコットランド民謡「麦畑」(誰かさんと誰かさんが)(伊藤武雄共訳)他の訳詞から軍歌・社歌、山田とのコンビで多くの校歌も多数残す。太平洋戦争が始まると徴用を受け、海軍宣伝班の一員としてジャワ作戦に配属された。バンダム湾敵前上陸の際には乗っていた船が沈没したため、同行の大宅壮一や横山隆一と共に海に飛び込み漂流するという経験もした。この際の経験を基に作られた詩を集めてジャカルタで現地出版された詩集「海原にありて歌へる」(昭和一七(一九四二)年アジアラヤ出版部刊)に日本の戦争文学の最高峰とも称され、前線の将兵に愛誦された「言ふなかれ、君よ、別れを、世の常を、また生き死にを……」の詩句で知られた「戦友別盃の歌-南支那海の船上にて。」が掲載されている。彼はこの詩集で日本文学報国会の大東亜文学賞を受賞、同時に作品の依頼が殺到した。この国家的要請に対して大木は誠実に応じ、詩集「豊旗雲」「神々のあけぼの」「雲と椰子」や従軍記・国策映画用音曲の作詞・各新聞社が国威発揚のためにこぞって作成した歌曲の作詞等をも行ったが(その一方で序文以外には殆ど戦時色の感じられぬ詩集「日本の花」も編集している)、戦争末期になると過労が祟って身体精神共に不調となり、福島に疎開して終戦を迎えた。戦後は一転、戦時中の愛国詩などによって非難を浴びて戦争協力者として文壇から疎外された。参照したウィキの「大木惇夫」によれば、『戦争中、大木をもてはやした文学者やマスコミは彼を徹底的に無視し、窮迫と沈黙の日が続いた。そのため、戦後は一部の心ある出版社から作品を出版しながら、校歌の作詞等をして生涯を過ごした』。『ただ、石垣りんの項目にあるように、新日本文学会の重鎮のひとりであった壺井繁治とともに、銀行員の詩集の選者をつとめているということもあるので、戦後の活動の全体像についてはなおも検証が必要である』とし、『大木惇夫は太平洋戦争(大東亜戦争)中、海軍の徴用を受けて従軍し、その経験を基に作詩をした。また、帰国後も国家やマスコミの要請に応じて、多数の作品を作った。このような戦争協力は大木だけでなく、当時の文学者や芸術家の多くが当然の行為として行ったことである。また、大木は戦争詩を作ったことで多数の栄誉を受けているが、これは純粋に作品が評価されたためのことであり、これは今日でもその戦争詩の一部が高い評価を受けていることでも証明される。また、大木自身が戦時中に特権を求めるような行為をした形跡は無く、むしろ、終戦前には過労からノイローゼに近い状態にすらなっている』。『終戦後の文壇やマスコミは大木を徹底して無視、疎外し、反論の機会すら与えずに詩壇から抹殺しようとした』。『大木自身も戦争中の活動を『はりきり過ぎた』と指摘されたことに対し『顔から火が出るほど恥ずかしかった。』としているが、これは自分の行為や詩そのものを否定するものではない。『(前略)堂々とわたしをやっつける人がなくて、すべて私を黙殺してゐるから、その向きに対しても、私は答へる術を知らないのである。』と述べている』。『戦後の一時期、著しく左傾化した文壇で行われた迫害行為から、大木は完全に復権したとはいえない。このことはソビエトでボリス・パステルナークが政府から迫害された際に、自由主義の各国で非難の声が上がったにもかかわらず、日本では文壇が全く反応をしなかったことなどと共に、戦後日本文学史の政治的な汚点の一つともされる』。しかし、昭和三六(一九六一)年には『依頼により作成した「鎮魂歌・御霊よ地下に哭くなかれ」の詩碑が故郷である広島市の平和記念公園に建てられるなど、日本国民の評価は文壇やマスコミとは明らかに異なっていた』とある。なかなか骨のあるウィキ記載であると私は思う。
なお、最後の逸見享氏の「編者の言葉」によれば、この文章の内、「莟から莟へあるいてゆく」の解説部分までは、大正一五(一九二六)年に大手拓次自身が書いたもの、次の「黃色い接吻」以下の解説は逸見氏が追記したものであると記されてある。]
跋
大手拓次君の詩と人物
萩原朔太郞
昭和九年の春であつた。遲櫻の散つた上野の停車場へ、白骨となつた一詩人を送つて行つた。その詩人の遺骨は、汽車に乘せて故郷の上州へ送られるのであつた。
停車場のホームには、大勢の見送人が集つて居た。それらの會葬者は、いづれもモーニングやフロックコートを着、腕に喪章の黑布を卷いてた。彼等の全部は會社員であつた。遺骨が汽車に乘せられ、窓から恭々しく出された時、ホームの人々は帽子を脱いだ。一人の中年の紳士が、簡單に告別の演說をした。その演說の内容は、我々の會社に於て、多年忠實に勤めてくれた模範店員の一人を、今日遺骨として此所に送ることは、如何にも哀悼の情に耐へないといふのであつた。汽笛が鳴つた。そして信越線行の長い列車が、徐々に少し宛プラットホームを離れて行つた。
一人の平凡な會社員が、かうして平凡な一生を終つたのである。彼が内證で詩を書いて居たこと、しかも秀れた詩人であつたことなど、會葬者のだれも知つては居ないのだつた。ただその群集の中に混つて、四人の人だけが彼を知つてた。北原白秋氏と、室生犀星君と、大木惇夫君と、それから私であつた。そしてこの四人だけが、彼の生前に知りた一切の文壇的交友だつた。
「寂しいね。」
見送りをすなした後で、私は室生君と顏を見合せて言つた。
上野驛に遺骨を送つて、歸つて來や日の翌日だつた。詩を作る若い人が訪ねて來たので、昨日の新しい記憶を話した。
「大手拓次? 大手拓次?」
暫らく考へた後で、その若い詩人が言つた。
「あ、知つてます。知つてます。前に白秋氏の難詰で詩を書いて居ましたね。貴方の模倣みたいな詩を。」
「反對ですよ。僕が模倣をしたのだよ。」
と言つたら
「アハヽヽヽ」
と靑年が笑ひ出した。私が諧謔を弄して、何かの逆說を言ふのだと思つたのである。だが諧謔でも逆說でもない。私は實際、大手君の詩から多くを學んだ。特に「靑猫」のスタイルは、彼から啓示されたところが多い。尤も後には、大手君の方でも私から取つたものがあるらしく、兩方混線になつてしまつたけれども、私の方で學んだ部分が、たしかに多いことは事實である。その意味で大手君は、私より一日の先輩である。
と、これだけ話をしても、まだその靑年は腑に落ちないやうな顏をして、
「でも貴方などより、ずつと新しく詩壇に出た、若いグループぢやありませんか。」
と言つた。
大手拓次! この名は實際新しく、詩壇の人に耳慣れない。今の詩壇の人々は、だれもおそらくこの名の詩人を、あまり記憶して居ないであらう。稀れに記憶してゐる人々も、その靑年と同じやうに、若い時代の新進詩人――しかもあまりぱッとしない新進詩人――として忘れかかつた記憶の一部に、ぼんやり名を止めて居るに過ぎないだらう。然るに實際の大手君は、私よりも少し早く、室生犀星君等と前後して詩壇に出、大に活躍した詩人なのである。
その頃の大手君は、吉川惣一郞のぺンネームで詩を書いて居た。と言つたら、昔の「ザムボア」などを讀んでた人には、初めて記憶が確實になり、一切の經過が解るであらう。大手拓次の本名に歸つたのは、後に北原白秋氏が、アルスから詩の雜誌を出すやうになつてから極めて最近のことに屬してゐる。大手君の花々しい詩人的活躍時代は、その短かい本名時代に無くして、實に過去の吉川惣一郞時代にあつたのである。
私が初めて大手拓次、即ち吉川惣一郞の名を知つたのは、北原白秋氏の雜誌「ザムボア」の誌上であつた。常時その同じ誌上に、室生犀星も詩を發表し、少し遲れて私もまたこれに加はつた。この室生、吉川、萩原の三人組は、その後も常に發表の機關を一にし、後に「地上巡禮」から「ARS」、「ARS」から「近代風景」へと、常に白秋氏の雜誌を追つて轉々とつつ、詩人としての共同經歷を一にして居た。單にまたそればかりでなく、三人共に白秋氏を私淑し、且つ白秋氏の推選によつて詩壇に出た。そのため世間では、私等のトリオを稱して「白秋旗下の三羽鴉」と呼んだ。
藝術的經歴に於て、かくも親しく兄弟のやうな閒でありながら、人間としての大手君には殆んど友誼を結ぶ機緣がなかつた。私が大手君に逢つたのは、前後を通じて僅か三度しか無かつた。最初は室生君と共に牛込の下宿を訪ねた。二度目は白秋氏の家のパーチイで一所になつた。そして三度目は、既に遺骨となつて居た大手君を上野に送つた。それほど實に寂しく、墓ない友誼であつた。だがそれにもかかはらず、大手君が常に私のことを心に思ひ、白秋氏と共に深い愛情をよせてをられたことを、この事の卷尾にある同君の覺え書によつて知り、今更また故人への追憶を新たに深くするのみである。
大手拓次君の藝術は、一言で言へば實にユニイクなものである。新體詩以來今日に至るまで、日本の全詩壇の歷史を通じて私は他にこんなユニイクの詩と詩人とを見たことがない。第一にその言葉と内容とが、過去の詩人のどんな影響も受けて居ないのである。たいていその頃の詩人たちは、當時の詩壇の流行であつた類型的自由詩の形態を學んで居た。さうでないものは、蒲原有明氏以來の文章語詩形を襲統して居た。然るに大手君(當時の吉川惣一郞君)の詩には、當時のどんな類型もなく、過去のいかなる襲統もなく、全く別個の珍らしいものであつた。單にフオルムやスタイルばかりでなく、詩の情操する内容がまた特殊であつた。
しかしその「詩」を語る前に、私は先づその「詩人」を語らねばならぬ。なぜなら大手君のすべての詩は、實にその特殊な人間と生活とを根據にして居り、その「人」に對する理解なしにその藝術を味ふことが出來ないほど、人と作品とが密接に結ばれてゐるからである。そしてしかも大手君の人間と生活とが、その藝術以上にまた特殊であり、他に全く類型を見ないほどの、絕對ユニイクの存在なのである。
私が室生君と共に、初めてその下宿屋に大手君を訪ねたのは、今から約二十年近くも昔のことであつた。(その牛込の下宿屋に、大手君はその後二十年も住んで居た。その間に下宿屋の主人が死んで、代が變つても依然として住んで居た。)第一印象に映じた大手君は、蒼白く情熱的な顏をしながら、寂しい憂鬱を漂はせてゐるやうな人であつた。どこか生田春月君に似たやうなところもあり、全くまた別の風貌にも屬して居た。そして要するに、その抒情詩そつくりの人物を感じさせた。
下宿の狹い部屋は淸潔に掃除されて、萬事が几帳面に整理されてた。室の一隅に書架があつて、佛蘭西語の詩集や雜誌がぎつちり積まれて居た。話をして驚いたことは、佛蘭西語の書物以外に、日本語の本を殆んど讀んで居ないことであつた。特に意外であつたのは、北原白秋氏一人を除いて、他の如何なる日本の詩人の存在さへも全く知らずに居ることだつた。當時詩壇には、白秋氏の外に三木露風、川路柳虹、高村光太郞、富田碎花、福士幸次郞、西條八十等、既に一家の名を成してる多くの詩人が活躍してゐた。私と室生君とは、常に此等の先輩詩人を對象にして語つて居たので、大手君に逢ふと同時に、先づかうした詩壇の現狀を話しかけた。然るに驚いたことは大手君は全くその人々の名前さへも知らないのである。況んや詩壇のことなど、全く風馬牛に無關心で、私等の話を迷惑さうに默つて聞いて居た。
「佛蘭西の詩、ボードレエルとサマンより外、少しも讀んで居ませんから。」と言ふのを聽いた時、私は室生君と顏を見合せた。そして世にも尊大なペダンチックの奴が居るものだと思ひ、一種の侮辱を感じて腹を立てた。しかし大手君の表情に少しの尊大な倨傲もなく、却つて内氣に恥かしがつて居るのを見た時、すつかりこの人の詩人的天質が了解された。つまりこの純一の詩人は、自己の詩情に驅りたてられて、自己の悦樂のためにのみ詩を書いてるので、文壇的に地位や名聲を克ち得ようとする野心――それが昔時の私たちには充分あつた――を全く所有して居ないのである。したがつて詩壇の現狀や詩人の名を、殆んど知らずに居るのも當然である。大手君としては、ただその愛誦するボードレエルとサマンだけを、佛蘭西語の原詩で讀んで居れば足りたわけだ。此所で一つ詩を紹介しよう。
[やぶちゃん注:長いので途中に注を挟む。
「サマン」アルベール―ヴィクトール・サマン(Albert‐Victor Samain 一八五八年~一九〇〇年)はフランスの詩人。北フランスのリール生。一八八〇年にパリに出、翌年の『メルキュール・ド・フランス』誌の創刊に参加したが、小身の公吏として病弱のうちに母子二人暮しの孤独な生涯を送った。処女詩集「王女の庭にて」(一八九三年)の甘美でもの憂く漠とした悲哀感を漂わす詩風によって象徴派の一人とも目されるが、第二詩集「花瓶の胴に」(一八九八年)では寧ろ高踏派的な形式美を志向して諧調に富む異教的雰囲気を醸し出している(以上は平凡社「世界大百科事典」に拠る)。本詩の最後に大手拓次訳のサマンの詩を掲げておく。]
枯木の馬
神よ、大洋をとびきる鳥よ、
紳よ、凡ての實在を正しくおくものよ、
ああ、わたしの盲の肉體を滅亡せよ、
さうでなければ、神と共に燃えよ、燃えよ。王城の炬火のやうに燃えよ、
ああ、わたしの取るにも足らない性の遺骸を棄てて
暴風のうすみどりの槌の下に。
香枕のそばに投げだされたあをい手を見よ、
もはや、深淵をかけめぐる枯木の馬にのつて、
わたしは懷疑者の冷たい着物をきてゐる。
けれど神樣よ、わたしの遺骸には永遠に芳烈な花を飾つてください。
「神」「信仰」「忍從」「罪」「實在」「道心」「尼僧」「惡魔」「僧形」「祈禱」「香爐」「紫※」等々の言葉は、實に大手君の詩の主調を成してるイメーヂである。全卷の詩篇を通じて、話者はあのカトリツク敎寺院の聖壇から立ちこめてる、乳香や煉香の腹々とした煙の匂ひを感ずるだらう。かうした大手君の詩想は、おそらくボードレエルから影響されてる。しかしこの詩人の學んだものは、ボードレエルの中のカトリック敎的部分であり、單にその部分の「香氣」にすぎなかつた。詩人としての本質から言へば、大手君は決してあの異端的、叛逆的の懷疑を抱いた「惡の花」の詩人ではなく、むしろそれと正反對なリリシズムをもつた純情の詩人であつた。彼の場合は、むしろサマンの方に接近してゐるやうに思はれる。
[やぶちゃん注:「紫※」(「※」=「袍」-「礻」+「糸」)。筑摩書房版萩原朔太郞全集第十四巻に所収するそれでは編者によって「紫袍」に書き変えられている(同全集は一貫して編者による恣意的な『誤字訂正』が行われてある)。「紫袍」とは「紫色の上着」の謂いであるが、私はこれは本当に正しく『訂正』していると言えるとは思っていない。以下にその理由を示す。まず、ここに朔太郎が並べた十二に語句であるが、この内、「香爐」までの総ては詩集「藍色の蟇」の中にどれも複数回使用されている単語である。ところがこの「紫※」「紫袍」の孰れも使用例がない(無論、「藍色の蟇」に限って朔太郎が述べたのではなく、広義の大手拓次の詩語として述べたのだと考えることも可能であるが、この文脈の中で一つだけそういう単語を選んで入れるということは実質上考えにくいと私は断ずる)。では、「紫」及びを「紫」を含む単語を「藍色の蟇」の中での使用例を見てみる。以下が「藍色の蟇」に於けるその総てである。
ぬしの御座は紫の疑惑にけがされてゐる。(「罪の拜跪」より)
紫の角を持つた羊のむれ、(「野の羊へ」より)
木立は紫金の蛇をうみ、(「木立の相」より)
紫の縞目をうつした半月の盾をだいて
*
角ある鳥をゑがいた紫の盾はやすやすともたげられて、
*
紫の盾よ さちあれ、(三つとも「紫の盾」より)
赤と紫とのまだらの雪がふる。(「曼陀羅を食ふ縞馬」より)
さては、なつかしい姉のやうにわたしの心を看まもつてくれる紫のおほきいヒヤシンスよ、(「ヒヤシンスの唄」)
紫は知らぬ運動の轉回、(「手の色の相」より)
うきあがる紫紺のつばさ、(「鈴蘭の香料」より)
そらよりみだれかかる紫琅玕のうはこと、(「うづまく花」より)
古くさい小池の綠には、薄紫のつつじ、生々とした笹の葉、楓や松や檜や、石菖や、がある。(「綠の暗さから」より)
紫藍色の車はせはしく過去へきしる。(「琅玕の片足」)
紫色の病氣の指(「噴水の上に眠るものの聲」最終連より)
この孰れを見ても紫色の衣服、紫衣、「紫袍」の人物や表象は出現しない。従って私は「紫袍」という筑摩版全集の『訂正』は『誤り』と断ずるものである。但し、「廣漢和辭典」にも出ない「※」は明らかに誤字である。敢えて言うならこれは一例の使用例が出現し、それ以外にも頻繁に現われるところの紫色、それは紺がかった紫色や濃い紫色であるところの紫の色調を局限するもの――「紫紺」の誤りである――とすべきだと私は考えるものである。大方の批判を俟つ。]
撒水車の小僧たち
お前は撒水車をひく小僧たち、
川ぞびのひろい市街を悠長にかけめぐる。
紅や綠や光のある色はみんなおほびかくされ、
Silenceと廢滅の水色の色の行者のみがうろつく。
これがわたしの隱しやうもない生活の委だ。
ああわたしの果てもない寂寥を、
街のかなたこなたに撒きちらせ、撒きちらせ。
撒水車の小僧たち、
あはい豫言の日和が生れるより先に、
つきせないわたしの寂蓼をまきちらせ、まきちらせ。
海のやうにわきでるわたしの寂蓼をまきちらせ。
[やぶちゃん注:七行目は底本では「街のかなたこなたに撒きちらせ。」「撒きちらせ」のリフレインがないが、本文の詩形で訂正した。]
これにはサマンの影響が感じられる。そして尚、少しばかり白秋氏の影響も感じられる。しかし本來言つて、大手君はサマンでもなく、白秋でもなく、況んやボードレエルのやうな型の詩人でもない。この特異な詩人の本領は、性の惱ましいエロチシズムと、或る妖しげな夢をもつたプラトニツクの戀愛詩に盡きるのである。童貞のやうに純潔で、少女のやうに夢見がちなこの詩人は、彼の幻想の部屋の中で、人に隱れた祕密をいたはり育てて居た。彼のエロチシズムと戀愛詩は、いつも阿片の夢の中で、夢魔の月光のやうに縹渺して居た。それは全く常識の理解できない、不思議な妖氣にみちたポエヂイである。彼の詩について語る前に、生活について語らなければならないのである。
以下私が話すことは、故人の親友であつた所の、畫家逸見享氏から聞いた事實である。そしてこの逸見氏だけが、大手拓次の生活を知つてる唯一の人であつた。それほど大手君には全く他に友人と言ふものがなかつた。
詩人といふ人種は、元來非社交的の人種であり、宿命的に孤獨を愛するやうに生まれついてる。しかし大手拓次のやうな詩人は、私の知つてる範圍で類例がなく、全く無人島的な生活をした孤獨者だつた。彼はその生計のために、ライオン齒磨の廣告部に勤め、會社員としての日課を續けて居た。しかし會社では、殆んどだれとも口を利かずに、默々とし啞のやうに仕事をして居た。かうした不思議な人間が、如何にその同僚から氣味惡しく、變人扱ひに嫌厭されるかは、充分想像できるであらう。仲間はづれにされてる孤獨の椅子で、この氣の弱い内氣な詩人は、いつも情熱的な戀愛詩を書き續けて居た。それは同じ會社に勤めて居るところの、若い女事務員に對する殉情だつた。しかしこの詩人の内氣さと羞かしがりは、少女より尚いぢらしく、戀を打明けることが出來ないのである。そして人の知らない祕密の思ひに、情熱の胸を焦しながら、悲しい嘆息ばかり續けて居た。或る時は忍びあまつて、歸途を急ぐ女の袂に、そつと一片の紙片を入れたりした。その小さな紙片には、彼の思ひあまつた詩が書いてあつた。しかしモダンガールの少女店員は、古風な抒情詩に興味がなく、意味を理解することもできなかつた。その上に作者の名前が書いてなかつた。彼女はけげんの顏をしながら、不思議な紙片を破いてしまつた。
かうした悲しい生活が、四十八歳になる迄も續いて居た。彼は幾人かの少女を戀し、幾篇かの抒情詩を書き、そして終生幻影の戀を迫つて生活して居た。さうした彼の生活は、純情の若い處女たちが、小箱の中に祕密をこめ、人の知らない不思議な言葉で、人形と會話して居るやうなものであつた。それこそは本當に「胸に祕めたる」純情のリリシズムであつた。古今東西の詩人を通じて、私は彼のやうに美しく純潔な詩人を知らない。その四十八歳の童貞生涯は、全くミユーゼに捧げた加特力敎的の獻身だつた。彼は一度も結婚せず、女の肉體に就いて知らなかつた。四十八歳で死ぬ時まで、眞に淸淨な童貞で身を保つた。それは現實の世に有り得ないほど、加特力敎的天國の物語に類して居る。
後年肺を患つてから、彼は茅ケ崎の病院に一人で臥て居た。そして毎日、海鳴りの音を聽きながら詩を書いて居た。私はその遺稿を見て悲しくなつた。それは女の子の小箱に張る千代紙で、手製の表裝をした和紙の本に、細い紅筆のやうなもので詩が書いてあつた。その詩は皆短かい小曲で
今日もまた便りが來ない
もう何もかも夢のやうに消えてしまつた。
殘るものは淚ばかりだ。
淚ばかりが殘つてゐるのだ。
といふ風な歌が、いくつもいくつも繰返して書いてあつた。ノートは十册位もあつたが、詩は皆同じやうなことを繰返し、同じ一つの切ない思ひを、盡きずに綿々と歌つてゐるのであつた。一人の友人もなく、見舞客もなく、病氣を看護する者さへもなく、眞に天涯孤獨の身で、病院の一室に寂しく臥て居た彼は、ベツドの中で、毎日遠い戀人を思ひ續けてゐたのであつた。しかもその戀人の方では、彼の存在さへも忘れて知らずに居るのである。こんな悲しく寂しい人生はない。そしてまた、こんなに純潔で美しい詩人の生涯もない。彼はおそらく、胸に祕めた永遠のリリツクを抱きながら、安らかに微笑して死んだであらう。逸見氏がスケツチした彼の死顏は、天使のやうに純潔で美しかつた。五十歳に近い彼の顏には、少しも中年者の穢れがなく、永遠の童貞として生活した、聖畫の基督が輪光して居た。
[やぶちゃん注:この前に示された詩は引用せぬ方がよい部類のものである。私はこれはまさに直後で「といふ風な歌」と朔太郎自身が述べている如く、大手拓次自身の詩句の忠実な引用とは思われないからである。詩想からは死後の編纂になる詩集「蛇の花嫁」所収の文語定型様短詩群の主意とは似ているように思われるものの、私は現存するそれを突き付けられでもしない以上はこれを大手拓次の詩として肯んずることを断固として拒否する者である。]
かうした特殊の生活を背景として、彼の特殊な藝術が作られて居た。讀者にして彼の生活を知つたならば、彼の詩について言ふ必要はなく、すつかり解つてしまふであらう。一言にして言へば、それは純粹に加特力敎的精神の抒情詩である。しかしながら彼の加特力敎は、ボードレエルやヱルレーヌやと同じく、多分に肉情的の感覺を持つたところの、近代的異端趣味の加特力であつた。彼の詩に於ける特殊な言葉、例へば「球形の鬼」「輝く城」「紫の盾」「金屬の耳」「盲目の蛙」「僧衣の犬」「道化の骸骨」「法相の像」「幻の薔薇」「嫉妬の馬」等のものは、すべてかうした異端趣味の、彼の心象に浮んだイメーヂであり、香爐の煙の中に漂ふところの、妖しい僧院の幻想だつた。それらの不思議な妖しい言葉は、作者の意味に於てすべて性慾を表象して居る。即ち「犬」とい毒藥、「僧」といふ言葉、「城」といふ言葉などが、作者のイメーヂの中では、すべて女性の肉體(胴や、臍や、胸や、乳質)を表象して居るのである。詩人は此等の言葉の中に、妖しい性慾の惱みをこめて歌つて居る。その抒情への切ない悶えは、作者と言葉とが一つに重なり、離すことが出來ないほどに食い付いてる。眞にこの詩人の場合に於ては、言葉と詩とが一つの紐で結びつけられ、互に抱き合つて情死して居るといふ感じがする。かつて日本の詩壇に於て、これほど純粹に藝術的であつた詩人はなく、これほどまた純粹に詩人であつた作家も無かつた。
この加持力數的な不思議な詩人は、三十歳を過ぎる迄も、異性に對する眞の sex も知らずに居た。初期の靑年期に作つた詩は、たいてい皆美少年を對象にして歌つて居た。その同性の少年等は、彼にとつて全く女のやうに思はれて居た。それは集中の詩に歌はれてゐるやうに、少女に對する如き愛撫であつた。それらの詩の中で、彼は美少年の手足を撫で、胴をさすり、足の指を弄んで樂しんで居る。しかもその感覺遊戲は、少し邪淫的なものでなくつて、宗敎的に純粹な祈りとロマンチシズムを本質してゐるものであつた。つまりこの詩人は思春期に近い少女のやうに、純粹な感傷性とロマンチシズムとで、同性への愛と思慕とを求めたのである。そして彼の詩篇の中では、この初期時代の作品が一番よく、藝術としての最も高い香氣を持つて居た。後に異性への愛に轉向してから、彼の詩はげつそり色彩を落してしまつた。つまりその時代からして、彼は藝術創造的野心を無くして、ひとへに自己の感傷性の中に溺れてゐたのである。そして詩人が感傷性に溺れる場合、もはや文化上の建設價値を喪失して、自己慰安の作者に墮してしまふのである。彼の後年の日課は、毎日その戀人のために詩を作り、それを無記名にして送るのだつた。逸見氏の話によれば彼はそのために詩の調子を下げ、少女の戀人にも解るやうに、わざと通俗にして書いたといふことであつた。かうした悲しい詩人に對して、私はもはや言ふ言葉がなく、批判の必要さへないのである。(吉川惣一郞といふペンネームは、彼の愛した二人の少年の姓と名とを、一語につづつたものださうである。)
彼はいつも孤獨の部屋で、默つて一人で詩を書いて居た。そして時々、恥かしさうにそれを取り出し、白秋氏の雜誌にだけ送つて居た。詩を公表することさへが、彼にとつては恥かしく、處女のやうに顏を赤らめることであつた。(彼の性格が、如何に女性的であり、基督敎尼僧的であつたかは、本書の自傳に書いてる白秋氏への彼の心情と、その女らしい思慕の純情とによく現れて居る。)
かうした箱入娘のやうな内氣の男が、文壇や詩壇に立つて活躍するのは、あまりに周圍の空氣が粗野にすぎて荒々しく、不適當に傷ましいやうな感じがする。彼も自らそれを意識して居たらしく生涯一册の詩集も出さず、詩壇的に無記名のままで死んでしまつた。この遺稿詩集でさへも、逸見氏の如き書き友人が居なかつたら、おそらく世に出る機會が無かつたであらう。何等賣名的野心がなく、文壇的功名心もなかつた詩人は、それで地下に滿足して居るかも知れない。しかし十八歳から詩に志し、四十八歳で死ぬ時まで、三十年も詩作に專念して、その上にも數々の秀れた作品――それらの作品の價値は、日本詩壇の歴史的過程を通じて、第一流の最高位に列せらるべきものである。――を残した詩人が、一册の詩集も出さず無記名のままで葬られて居ることは、私等にとつてあまりに寂しく、且つ良心が許さないことである。況んや今日の詩壇には、昨日今日の馳出し作家や、人眞似事で駄詩を書いてるやうな連中さへが、堂々とした詩集を出し、相當に名を賣つてるのである。批判の公平と正義の爲にも、私は大手拓次君を紹介して、詩壇に推賞しなければならない義務を持つてる。この不思議な妖術を持つた變化の詩人。加特力敎寺院の密室から、香煙の煙に漂ふ異形な幻影を見せる詩人。純情無比なリリシズムと、プラトニツクな夢を持つてる浪漫詩人。しかしまた性のやるせない惱みを歌ひ、官能の爛れる情痴を歌ふエロチシズムの大詩人を、私は自分の「私淑する先輩」として、廣く日本の詩壇に廣告紹介したいのである。
[やぶちゃん注:この「この遺稿詩集でさへも、逸見氏の如き書き友人が居なかつたら、おそらく世に出る機會が無かつたであらう」という言葉を記憶してもらいたい。則ち、この期(大手拓次の死後)に至っても、実は永く詩集原稿を握っていた北原白秋ではなくて、唯一人の親友逸見享の尽力(その熱意が並々ならぬ驚くべきものであることはこの詩集を実際に手にとって見ればずしりと分かる)なしには詩集「藍色の蟇」の出版は覚束なかったことを意味している。私は以前にも述べた通り、白秋に対して本詩集が生前に出なかったことへのある種の深い疑惑を持っているが、それを強く裏付ける言葉として私は受け取っていることをここに表明しておく。白秋は拓次の生前に於いて、正しく優れたこの弟子を導く師たる詩人では実はなかったと私は思っているのである。]
大手君の詩は、言葉の音韻上に於ける使用法で、佛蘭西語の詩と類似した所があるといふ人がある。佛蘭西語の詩以外に、他のどんな文學も讀んで居なかつた大手君のことであるから、或はたしかに、さうした自然的の類似があるかも知れない。とにかく彼の詩の言葉は、非常に美しく抒情的で、その上に全く音樂的である。私は詩集「靑猫」に於て、彼の影響を多分に受けてゐることも、此所で再度正直に告白しておかねばならない。その同じことは、一方で大手君の方からも言ふであらうが、私としては心密かに、常に彼を一日の長者として自分の及ばない先輩詩人として畏敬して居た。そしてこの畏敬の情は、彼の故人となつた今に於て、一層深く眞實に感じられるものがある。私が心から畏敬し、眞に頭を下げるところの詩人は、北原白秋氏以後に於て、ただ吉川惣一郞の大手拓次君あるのみである。
最後にこの稀有の詩人が、私と同郷の上州に生れたといふことにも、私はまたささやかな血縁的愛情を感じて居る次第である。 (一九三五・八・二〇)
[やぶちゃん注:以下のアルベール・サマンの訳詩は岩波文庫版原子朗氏編「大手拓次詩集」に所収するものを恣意的に正字化して示す。原詩“Automne”はこちらで読める。
秋 アルベール・サマン
うづまく風は扉をたふし、
そのしたに森は髮のやうに身をもだえる。
かちあふ木木の幹は砂の輾轉する海のびびきのやうに、
はげしい風鳴りをたかめてゐる。
おぼろな丘におりてくる秋は、
重い步みのうちにわたし達の心をふるへさせる。
そしてどんなにいたはしく萎れた薔薇のめめしい失望を、
かなしんでやるかをごらんなさい。
休みなくぶんぶいつた黃金色の蜂の翔けりも沈默した。
閂は錆のついた門格子にきりきりとなる。
あを蔦の棚はふるへ、地はしめつてきた。
そして白いリンネルは圍ひ地のなかに、うろたへてかさかさとする。
さびれた庭は微笑する、
死がくるときに、ながながとお前に別れをいふやさしい顏のやうに。
ただ鐵砧のおとか、それとも、犬のなきごゑか、
うつたうしくしめきつた窓ガラスにやつてくる。
母子草と黃楊の樹の瞑想をさましつつ、
鐘はひくいねに檀家の人の心になりいでる、
また光りは苦悶のはてしない身ぶるびをして、
空のふかみに、ながいながい夜のくるのをきいてゐる。
このものあはれな長夜も明日になつたらかはるだらう、
すがすがしい朝とびややかな又うつけな朝と、
たくさんの白い蝶は葉牡丹のなかにひらめきながら、
また物音はこころよい微風の中にさはやかになりながら。
それはさておき、この家はお前のことを嘆きもしないで、
その木蔦と燕の巢とでお前をもてなしてくれる、
そして自分のわきに放蕩者のかへるのを待ちうけて、
ながい藍色の屋根の波にけむりをのぼらせる。
命がやぶれ、ながれいで、もえあがるとき、
うき世のつよい酒にゑひしれて、
血の盃のうへにおもい髮の毛がたれかかれば、
よごれた魂はちやうど遊女のやうである。
けれども、鴉は空のなかに數しれずむらがる、
そしてもはや、さわがしい狂氣をすてて、
その魂は、旅人が歸り旅のみちすがら、
なじみの調度にめぐりあふたのしい嘆息をおしのける。
夏の花びらは花梗のうへに黑くしをれてゐる。
おまへの室にまたはひり おまへのマントを釘にかける。
水のなかの薔薇のやうなお前のゆめは、
仲のよいランプのあまい太陽にひらいてくる。
思ひにしつんでゐる時計では、
知らせの鈴がひそかに沈默の心をうつ、
窓ぎはの孤獨はその氣づかひをひろめてゆき、
かがみながら姉のやうにおまへの額に接吻する。
これは申分のない隱れ家だ、これは氣持のよい住居だ。
あつたかい壁の密室、ひまもない竃、
そこで極めて稀なる越粟幾失兒のやうに、
内心の生命のうつくしい本質をつくりあげる。
そこに、お前は假面と重荷とをとりのけることが出來る。
騷擾からはなれて、いな虛飾から遠くのがれて、
いとしいものの匂ひを、カーテンの襞のなかにあらはになつてゐる。
おまへの胸にばかりただよはせるために。
このときこそ、心おきなく仕事にいそしんでまことの神を禮拜し、
神神しい身ぶるひがお前の年若さと淸らかさとを、
はればれとあらはすやうになつてくる。
秋はこのためにたぐびないよい季節である。
すべてのものはしづかに、風は廊下の奧にすすりなき、
お前の精神はおろかなる鎖をたちきつた。
そしてうごかない時の水のうへに裸のままうなだれて、
そのふさはしい鏡のきれいな水晶に自分の姿をうつす。
それは消えかかつた火のわきの裸の女神である、
あたらしい空氣のなかに船出するぼんやりとした大きな船である、
肉感的な、また物思はしい接吻のするどい液と、
人に知られない水のうへの日沒である………
「母子草」知られた「ははこぐさ」、キク目キク科キク亜科ハハコグサ連ハハコグサ Gnaphalium affine(別名ホウコグサ)であるが、実は原文は“immortelle”であって、これは双子葉植物綱キク目キク科ムギワラギク Helichrysum bracteatum を指す(因みに属名“Helichrysum”(ヘリクリサム)はラテン語で「太陽の黄金」を意味し、花に独特の金属光沢があることに由来するとウィキの「ムギワラギク」にある。フランス語の「不滅のもの」「神」を意味する“immortelle”がこの花を指すのはそれと関係するか)。何れにせよ、聞き慣れぬ本種を日本人に馴染みのある「母子草」に変えたことは首肯出来ないことはなく、また「母子草」を選んだ拓次の深層も興味深い。
「花梗」「くわかう(かこう)」と読む。原文は“hampe”で花茎の意。これは花柄で花軸(花をつける枝)がさらに分枝し、その先端に花をつけるところの小さな枝のことをいう。
「越栗幾失兒」原文“élixir”。音訳はエリクサー・エリクシャー・エリクシール・エリクシア・イリクサ・エリクシル・エリキシルなど。錬金術で不老不死の霊薬を指す。賢者の石と同一物と考えてよい。参照したウィキの「エリクサー」によれば、アイザック・アシモフの「化学の歴史」の「第二章 錬金術 アラビア人達」によれば、語源は、これが乾いた粉の形状をなしていると考えられていたことから、ギリシア語の
“xerion”(乾いたの意)がアラビア語に翻訳され“al iksir”とあり、『錬金術の至高の創作物である賢者の石と同一、或いはそれを用いて作成される液体であると考えられている。服用することで如何なる病も治すことができる・永遠の命を得ることができる等、主に治療薬の一種として扱われており、この効果に則する確立された製造方法は今もって不明とされている』とある。この漢字の当て字は拓次の独創かと思われる。]
蟇 の 足 跡
拓 次 の 生 涯
逸 見 享
彼は逝いた、しかも忽然と。
あの神樂坂の下宿都館に、二十年も詩に瘠せ、戀に蝕まれてつひに最も恐れてゐた茅ヶ崎南湖院の一室に、看護婦ひとりに看取られながら死んでいつた。
思へばあの鬱蒼とした相貌と、異常なる神經との作つた彼の生涯こそはまことに異風景である。
ちひさい時分に兩親をなくした彼は、上州磯部溫泉を拓いた祖父の大手萬平翁と祖母との愛を一身に集めて成長した。あの我儘はこの閒に培はれたものであらうか。臆病で、おこりっぽく、はにかみやで、少年時代から孤獨に慣れ、それを樂むやうにさへなつてゐた。よく手を嗅ぐ癖があつで、熊だ熊だといはれたさうである。病氣で耳をわるくしてゐたが、鼻はかなり敏感でいろんな香水を嗅ぎわける癖は晩年までつゞいてゐた。
高崎中學を卒業して、早大英文科に入學した頃から彼の詩作生活がはじめられた。が我儘に育てられた彼には、月々のきめられた送金と、不自由な下宿生活がかなり憂鬱なものだつたらしい。
當時は詩壇の華やかな頃で、白秋氏の芳醇に醉ひ、ボオドレエルの惡の華に魅せられて、この若き詩人の鬼火のやうな魂は怪しく燃えさかつた。そして新鮮で特異な詩があふれるやうに生れた。
彼のどの詩を讀んでもわかるやうに、あの言葉は得難いものであるが、その研究はまことに深いものがあつた。「花野」と題する三十餘册のノオトに印されたいろんな言葉、それ等はいつのまにか彼に吸收され、その血管をめぐつで詩の中に生きてゐるやうに思はれるのである。
大學を出た頃はあの下宿で明け暮れ詩に浸つでゐた。ちやうど白秋氏が「ザムボア」「地上巡禮」などを出され頃で、そのザムボアに始めて吉川惣一郞のペンネエムで詩を發表した。この頃が彼の生涯でのもつとも華やかな、樂しい思ひ出の頃だつたであらう。
だがいつまでも下宿に夢を追うてばかりはゐられなかつた。彼のいふ窮迫時代がこの若き詩人のうへにもひしひしと押し寄せてゐた。彼は鬱憂の日々を故郷にまた神樂坂に妖気を吐きつづけてゐた。
その内にライオン齒磨廣告部にはひることになつて、自活の道がひらけた。大正五年五月のことである。私と知合つたのもその頃で、うつろの眼をしばたたきながら、腕を組んで何かを追ひかけてゐる彼が思ひ出される。彼の詩的敎養はその廣告文案に現はれて、一種の淸新味を漾はせた。けれどやはり彼は詩人であつた。ひたすらに詩をつくり、孤獨を守ら續けた彼には、あの二十年近い社員生活もつひに空虛なものだつたに違ひない。他と十分解けあはぬのみか、むしろ多くの人のなかにあつてその孤獨癖は一層深められて行つた。
私はそのころ毎日のやうに彼と詩歌や畫の話をした。これはもつとも彼を喜ばせた。あのきれの長い眠が輝き、細長いその手が紅潮して別人のやうに潑溂として見えた。話の高潮する時は掌を眞直ぐに上にあげ、眼をおもむろにつむつて新作の詩を歌ふこともめづらしくなかつた。その頃彼の發表する雜誌がなかつたので、私がすすめて數人の同志と詩歌誌「異香」を發行した。
萩原朔太郞氏の「月に吠える」がそれと前後して發行され、詩壇に大反響を呼び起した。氏から贈られた詩集を見て彼は何と思つたであらうか。「朱欒」「地上巡禮」「ARS」など白秋氏の發行された詩誌には常に發表しあつて來たふたり、互に十分の信賴をもちあつてゐた氏の詩集は後に非常な感動を與へずにはおかなかつた。私は彼に一脈のさびしさを見た。そして祕に愛讀してゐた彼からこの詩集についてつかに何も聞いたことがない。
その後幾度か彼と二人で詩畫集を出したが、以前に見る情熱がだんだんうすれて行くやうに思はれた。
ちやうどあの大震災後、ある少女に熱烈な戀をした。彼にあつては、戀愛によつて詩が高潮するよりも哀しき調べに終つてゐる。そしてこの戀は通り魔のやうに過ぎて行つた。昭和に入つてこの四十過ぎた寂しい詩人は現實の、また幻の戀人を慕ひ步いた。その度に少年のやうな純な性情と、弱氣の彼がまざまざと見られで、私は彼の心情に祕に淚したものである。そしてその詩に於ても實にやさしく淚ぐましい抒情詩が作られてゐる。當時白秋氏の發行された「近代風景」に發表された多くの詩のほとんど總てがその哀唱である。
その内昭和二年の初め頃からほのかにある異性を想ひ初めてゐたが、年を追うて深められて行つた。そして昭和七年頃の日記には絕え入るばかりのせつなさを書き綴つてゐる。
……戀するものにとつて夕暮こそこよなき樂園である。あのうす靑い光こそなんといふなぐさめとゆめとを私にあたへてくれるでせう。
といつてゐる。また
……たゞやすらかな美しき死をば願へり。
……たとひいのちはむなしくなるともこのおもひはつきざらむ。
ともいつてゐる。
そしてつひに病臥する日が多くなつて行つた。
その年の十一月、たうとう伊豆山溫泉に療養することになり、私が送つて行つた。その夜旅館の二階の一室に彼と蒲團を竝べたが、私はまことにねぐるしかつた。うちよせる窓下の波の音、その絕え閒に浮ぶ遠き彼のことども、近きその橫顏の疲れをうすあかりに見て獨り平復を祈つた。この年は其處で越して八年に入つた。病氣はあまりはかばかしくなかつた。日々の單調さと同じ食物に耐へきれなくなつた彼は、其處を引上げて寂しく神樂坂に歸つて來た。そして醫師のすすめで茅ケ崎南湖院に入院した。三月のことである。
彼は此處でも詩を書いたがそれも六月で終つてゐる。その頃の詩を讀んで見ると深い寂しさに襲はれ、そのままあの幻を追ひつつ、自分も死の淵へ吸ひ込まれるやうに思はれて來る。
南湖院の彼の窓からは小松林が續いでゐた。
彼の好きな五月のそよ風のわたる時、葉梢に澄みわたる十月の靑空を仰ぐ時など、ふと便りなど書く氣にもなつたらしいが、それも極く稀になつて、遠ざかりゆく戀人のうへをのみ思ひつづけてゐたらしいのである。がたまさかに見舞ふ私を迎へてやはりうれしさうであつた。病院の食物の不平を訴へたり、家族の安否を聞いてくれたりした。好きな大福餅ばかり食つて一日過したなどとも聞いたので、好物の豆を煮て持つて行つたこともあつたが、彼は非常に喜んでくれた。
その頃から病氣もかなら順調のやうに醫者から聞いてゐたので、九年の春には彼を東京に迎へることが出來るものとばかり思つてゐたが、ここにも彼の我儘が出てかなり無理をしたらしく、つひに命を縮めてしまつた。
彼は逝いた。しかも忽然と。
あの小兒のやうに純眞な彼、實に得難いこの本質的な詩人は、一生獨身のその生涯を寂しく閉じた。彼は日頃北原白秋氏、萩原朔太郞氏、大木惇夫氏などの敬愛する詩人達と私とのほかには殆んど交遊がなかつた。彼が死の床に見たものは、看護婦のつめたい白衣のみであつた。
作品に不滿を感じつつ新境地を拓くこともなく、失戀に失戀を重ねてつひに病床に瘠せせ衰へて行つた彼、彼はいかに寂しかつたであらう。
いや私はさう思かたくない。詩を愛し、戀人を愛し、孤獨に、寂しさに徹し、一切空の心境にあつて、親しければこそ友にその臨終を示さず、むしろ安らかに眠つて逝つたに違ひないのである。
あの死顏に見た崇高さ、靜けさ、彼は今もなほ薔薇の足音を聞きながら幻を追ひつゞけてゐるであらう。 昭和十年四月十八日夜
大手拓次略年譜
[やぶちゃん注:底本では記事部分は六字下げとなっている。]
明治二十年 (一歳)
十二月三日群馬県碓氷郡磯部溫泉寶來館大手宇佐吉の次男として生る。祖父萬平は同溫泉の開拓者として郷黨の尊敬を集む。
明治二十二年 (三歳)
弟秀男(後、櫻井家の養子となり、現磯部館主)出生。
明治二十七年 (八歳)
二月父字作吉三十一歳にて夭逝す。
四月磯部小學校に人學す。
明治二十九年 (十歳)
母のぶ三十四歳にて死す。
明治三十三年 (十四歳)
縣立安中中學校に入學す。
明治三十七年 (十八歳)
十月腦を病み、中學五年を退學、此時より一方の耳遠くなる。
詩人として立つ希望を抱く。
明治三十八年 (十九歳)
病氣快復し高崎中學五年生に編入。
明治三十九年 (二十歳)
高崎中學卒業。同年兄孫平、或目的のため家を出しため、家督をつぐこととなりしも、詩人となる希望を捨てず、弟秀男に讓つて、十月早瀨田大學豫科に入學す。
明治四十年 (二十一歳)
同大學英文科に入學。
明治四十五年 (二十六歳)
同大學英文科卒業。
大正元年 (二十六歳)
白秋氏主宰の雜誌「ザムボア」にはじめて詩を發表す。
大正二年 (二十七歳)
「ザムボア」及び「地上巡禮」に詩を發表す。
大正三年 (二十八歳)
一時郷里に歸りしも再度上京、此閒多數詩作す。
大正五年 (三十歳)
ライオン齒磨本舖(廣告部)に入社。
大正六年 (三十一歳)
詩歌・版畫誌「異香」を發行す。
大正七年 (三十二歳)
祖父ふさ九十歳にて逝去。
逸見享と詩畫集「黃色い帽子の蛇」を發行。
大正八年 (三十三歳)
十二月、祖父萬平九十一歳にて逝去。
逸見享と「無言の歌」を發行。
大正九年 (三十四歳)
逸見享と詩・版畫集「あをちどり」を發行す。
大正十年 (三十五歳)
「詩と音樂」に詩を發表。
大正十一年 (三十六歳)
「詩と音樂」に詩を發表。
大正十二年 (三十七歳)
「詩と音樂」に詩を發表。
大正十三年 (三十八歳)
逸見享と詩・版畫集「詩情」を發行。
「日光」に詩を發表。
大正十四年 (三十九歳)
「詩と版畫」「日光」「アルス・グラフ」「近代風景」に詩を發表。
大正十五年 (四十歳)
「近代風景」に詩を發表。
昭和二年 (四十一歳)
「近代風景」に詩及散文詩を發表。
昭和三年 (四十二歳)
「近代風景」に詩及散文詩を發表。
昭和七年 (四十六歳)
病臥すること多し。十一月伊豆山溫泉に療養のため赴く。
昭和八年 (四十七歳)
伊豆山にて正月を迎へ、一度歸京、三月廿三日茅ヶ崎南湖院に入院。
詩「そよぐ幻影」を「中央公論」に寄稿す。
昭和九年 (四十八歳)
四月十八日午前六時三十分南湖院にて死去、十九日茶毘に附し、二十日郷里磯部に遺骨到着、二十四日葬儀を營み、同日大手家墓地に埋葬さる。
[やぶちゃん注:この左頁のノンブルは「581」で、次の次の左頁から始まる「目次」は新たに「1」からノンブルが始まり(文字タイプは同一)、「編者の言葉」の最終頁「25」で終っている。
なお、以下の目次はリーダと頁数は煩瑣で必要性もないと判断し、省略した。詩群の間は見易くするために、底本より有意に空けてある。]
詩集 藍色の蟇
陶器の鴉
藍色の蟇
陶器の鴉
しなびた船
黃金の闇
槍の野邊
象よ步め
枯木の馬
鳥の毛の鞭
道心
漁色
撒水車の小僧たち
羊皮をきた召使
海鳥の結婚
慰安
蛇の道行
なまけものの幽靈
泡立つ陰鬱
長い耳の亡靈
目をあいた過去
なりひびく鉤
のびてゆく不具
やけた鍵
美の遊行者
秋
裸體の森
罪の拜跪
肉色の薔薇
つんぼの犬
野の羊へ
威嚇者
憂はわたしを護る
河原の沙のなかから
球形の鬼
雪をのむ馬
假面の上の草
香爐の秋
木立の相
武裝した痙攣
創造の草笛
球形の鬼
ふくろふの笛
くちなし色の車
春のかなしみ
生きたる過去
輝く城のなかへ
咆える月暈
銀の足鐶
ひろがる肉體
躁忙
走る宮殿
耳のうしろの野
笛をふく墓鬼
あをい狐
老人
紫の盾
白い髯をはやした蟹
みどりの狂人
よれからむ帆
みどり色の蛇
死の行列
名も知らない女へ
濕氣の小馬
黃色い馬
朱の搖椅子
法性のみち
曼陀羅を食ふ縞馬
金屬の耳
妬心の花嫁
白い象の賀宴
蛙にのつた死の老爺
日輪草
ふくらんだ寶玉
足をみがく男
夜會
むらがる手
靑白い馬
怪物
花をひらく立像
めくらの蛙
窓わく
黑い手を迎へよ
つめたい春の憂鬱
[やぶちゃん注:底本は「春」が「帶」となっているが、誤植であるから訂した。]
ヒヤシンスの唄
ジヤスミンのゆめ
母韻の秋
濕氣の小馬
森のうへの坊さん
草の葉を追ひかける眼
喪服の魚
黃色い帽子の蛇
曉の香料
[やぶちゃん注:底本は「曉の香」であるが、脱字であるから訂した。]
魚の祭禮
黃色い帽子の蛇
きれをくびにまいた死人
手のきずからこぼれる花
はにかむ花
蛙の夜
年寄の馬
無言の顏
毛がはえる
雜草の脣
小用してゐる月
水草の手
彫金の盗人
三本足の顏
鼻を吹く化粧の魔女
あをざめた僧形の薔薇の花
嫉妬の馬
僧衣の犬
罪惡の美貌
手の色の相
香料の顏寄せ
月下香(Tubereuse)の香料
ベルガモツトの香料
ナルシサスの香料
鈴蘭の香料
香料のをどり
すみれの葉の香料
佛蘭西薔薇の香料
香料の墓場
Wistaria の香料
香料の顏寄せ
白い狼
湖上をわたる狐
灰色の蝦蟇
舞ひあがる犬
靑狐
林檎料理
まるい鳥
白い狼
疾患の僧侶
盲目の鴉
蜘蛛のをどり
鏡にうつる裸體
指頭の妖怪
木製の人魚
をとめの顏
わかれることの寂しさ
わらひのひらめき
水母の吸物
眞黑な水の上の月
きものをきた月
夏の夜の薔薇
木製の人魚
洋裝した十六の娘
戀
山のうへをゆくこゑ
窓をあけてください
十四のをとめ
月の麗貌
椅子に眠る憂鬱
[やぶちゃん注:底本では「憂欝」で異体字を用いているが、詩の用いている正字で訂した。]
水のおもてのこゑ
みどりの薔薇
あをざめた薔薇
うづまく花
まぼろしの薔薇
うしろをむいた薔薇
薔薇のもののけ
手をのばす薔薇
ばらのあしおと
薔薇の誘惑
ひびきのなかに住む薔薇よ
なやめる薔薇
さびしい戀
かなしみ
わかれ
風のなかに巢をくふ小鳥
幻影
祕密の花
悲しみの枝に咲く夢
風のなかに巢をくふ小鳥
足
秋
遠い枝枝のなかに
思ひ出はすてられた舞踏靴
あなたの一言にぬれて
戀人を抱く空想
西藏のちひさな鐘
さびしいかげ
あなたのこゑ
盲目の寶石商人
莟から莟へあるいてゆく
馬にゆられて
十六歳の少年の顏
水中の薔薇
雪のある國へ歸るお前は
焦心のながしめ
四月の顏
流れの花
季節の色
四月の日
呪ひに送られる薔薇
マリイ・ロオランサンの杖
月に照らされる年齡
月をあさる花
しろいものにあこがれる
みちのほとりをゆく
うつり氣の薔薇
夢をうむ五月
莟から莟へあるいてゆく人
名もよばないでゐるけれど
かげの心
六月の雨
卵の月
黃色い接吻
夜の時
春の日の女のゆび
黃色い接吻
ひとすぢの髮
蛇行する蝶
合掌する縊死者の群
頸をくくられる者の歡び
乳白色の蛇
死は羽團扇のやうに
夜の脣
お前の耳は新月
齒
雪が待つてゐる
髮
靑い紙の上に薔薇を置く
八つの指を持つ妬心
夕暮の會話
道化服を着た骸骨
あをい馬
そらいろの吹雪
うつくしい脣
謎のやうな
癡愚
煙のなかに動く幻影
夜の光の日向の花
落葉のやうに
おまへの息
靑い吹雪が吹かうとも
みづのほとりの姿
ふりつづく思ひ
朝の波
白い階段
靑靑とよみがへる
日はうつる
しろい火の姿
月にぬれた鳥
とぢた眼に
みづいろの風よ
睫毛のなかの微風
よりかかる鐘の音
雪色の薔薇
みづのほとりの姿
そよぐ幻影
薔薇の散策
薔薇の散策
[やぶちゃん注:総標題が「嗇薇の散策」、個別詩題が「薔薄の散策」となっているが、誤植であるから訂した。なお、この「薔薇の散策」は本文を見て戴ければ分かる通り、個別詩題は本文では示されていない。]
散文詩
綠の暗さから
琅玕の片足
帽子の谷
二ひきの幽靈
木造車の旅
狂人の音樂
あをい冠をつけて
暗のなかで
愛戀する惡の華
言葉の香氣
白い鳥の影を追うて
香水夜話
噴水の上に眠るものの聲
日食する燕は明暗へ急ぐ
綠色の馬に乘つて
無爲の世界の相について
肖像 (寫眞版) ・ 平野次郞寫
死顏 (グラビア版) ・ 逸見 享畫
筆蹟 (グラビア版) ・ 大手拓次筆
[やぶちゃん注:平野次郎氏は不詳。冒頭の写真キャプションに記した通り、著作権が存続している可能性がないとは言えない。その場合は写真は撤去する。この方の没年や事蹟を御存知の方、御教授をお願いしたい。]
編者の言葉
一昨年の四月十八日、拓次危篤の報をうけて、南湖院に着いた時には、もう死室に移されてゐた。私は誰にともない腹立たしさで胸がいつぱいになりながら、やうやく死室に案内されたが、其處ではじめて彼が生前最も敬慕してゐた白秋氏にお目にかかることが出來た。それは全く思ひがけない、なによりも有難いことだつた。
お通夜は近親の外には白秋氏夫妻と、私とだけで營まれたが、詩集發行の計畫はこのしめやかな雰圍氣のうちに胚胎したのである。その時の氏の暖い心情と、さびしくも明るい安堵の氣配とを忘れることが出來ない。そして私は編輯一切をなにげなくお引受けしたが、不馴な自分にはかなりの重荷に相違なかつた。さいはひ本人が大正十五年に詩集出版の計畫をたて、それまでの原稿を整理してあつたので、その後の分を輯めればよかつた。けれどもほとんど日記のやうに書き綴られた多數の詩篇を見て一時は迷つてしまつた。が彼自身編輯すれば多分この程度であらうと思はれるまでに多くの詩を割愛した。このきびしい態度も詩集にゆるみを見せたくなかつたためである。
思へば今までに一册の詩集もなかつたのは、彼の性情による結果とはいへ、あまりにもさびしいことである。せめて生前この詩集を見せたかつた。あの大きな掌にのせて、無言のままほほゑむであらう彼の姿を見たかつた。
この書のうち、宿命の雪(自序にかへて)及び孤獨の箱のなかから(おぼえがき)は、大正十五年に彼が書いたもので、そのまま用ひた。(おぼえがきのうち黃色い接吻以下の解說は私が追記した)
散文詩は代表作といふよりも各年代をうかがへるやうに集めた。
この外、數十篇の譯詩と、抒情小曲が澤山あり、日記、手紙にも面白いものが殘されてゐるが、これは他日私の手でまとめて、發行の豫定故ここに集めないこととした。
裝幀は彼の日頃の意を汲んで皮表紙金刷とし、生前見たがつてゐた私の版畫「サボテンのある風景」の縮められたものを用ひて、彼への踐とした。
又彼を偲ぶよすがにもと、彼の肖像・死顏・筆蹟を各一枚づつ插入しておいた。
編輯にあたつて、北原白秋氏はその序文に見られる通りの、あのあたたかい心を常に私にも寄せられ、編輯上の御注意はもとより、徹夜までされて無理な執筆をして下すつた。
また萩原朔太郞氏はその跋に見るごとく、もつともよき理解者の一人として、いろいろ御氣づきの顚點を話して下すつた。その話されるのを聞いてゐると、時々拓次に接してゐるやうな錯覺を起すことすらもあつた。
彼の交遊はまことに狹かつたが、最も尊敬するふたりの詩人から、かくまで暖い心づかひをうけつつ死んで行つた彼もまた幸福な詩人であつたと思ふ。序と跋とは兩氏とも多忙を極められた時機にお願ひせねばならなかつたにもかかはらず、かくまで心のこもつたものを頂けたことは、編者として特に嬉しく誇らしいことである。玆に深く探く感謝致します。
尚この面倒な出版をお引受け下すつた北原鐡雄氏、完成するまでにいろいろお骨折を願つた、アルスの中村正爾氏及び其他の方々、種々御便宜を與へられた大木惇夫氏、恩地孝四郞氏、絕えず熱意をもつて私をはげまされた、故人の令弟櫻井秀男氏とその令息達に厚く御禮申上げる次第であります。
(昭和十一年十二月十五日深夜・逸見 享)
[やぶちゃん注:「この外、數十篇の譯詩と、抒情小曲が澤山あり、日記、手紙にも面白いものが殘されてゐるが、これは他日私の手でまとめて、發行の豫定故ここに集めないこととした」後に逸見が編纂した詩画集「蛇の花嫁」(龍星閣昭和一五(一九四〇)年刊)・訳詩集「異国の香」(龍星閣昭和一六(一九四一)年刊)及び「詩日記と手紙」(龍星閣昭和一八(一九四三)年刊)を指す。但し、これらの作品(私は未見)について、原子朗氏は「定本大手拓次研究」(牧神社一九七八年刊)で、逸見の『拓次個人への友情の厚さや熱意』及び逸見の一連の拓次関連書刊行への『努力には私も素直に敬意を表したい』としながらも、逸見は『文学のヂレッタントであり、しろうとであった。拓次の詩をどの程度理解していたか疑わしい』と述べ、本詩集は勿論、これら「蛇の花嫁」や「詩日記と手紙」などは、『どちらかといえば俗受けをねらった編集、改竄ぶりは甚だしい』と、手厳しく批判されておられる。
「踐」「セン」と音読みしているか。この語には先人の行跡に従う、(約束を)履行するといった意味はあるが、どうも「彼への踐とした」という謂いとは馴染まない。私の勝手な憶測であるが、これは「餞」の誤植で、「はなむけ」と読んで――彼(の死出の旅路)への餞とした――という謂いではあるまいか?
「北原鐡雄」(明治二〇(一八八七)年~昭和三二(一九五七)年)は写真・文学を専門とする出版社「アルス」を設立し、代表を務めた人物で、北原白秋の弟(三男)に当たる(ウィキの「北原鉄雄」に拠る)。
「中村正爾」(なかむらしょうじ 明治三〇(一八九七)年~昭和三九(一九六四)年は歌人で編集者。新潟生。新潟師範学校卒業後、小学校教員を経て、大正一一(一九二二)年北原白秋を頼って上京、出版社「アルス」に入社、昭和一〇(一九三五)年に白秋が創刊した『多磨』に参加して終刊まで編集に当たった。昭和二八(一九五三)年には『中央線』を創刊して主宰となった(講談社「日本人名大辞典」に拠る)。
「恩地孝四郞」(明治二四(一八九一)年~昭和三〇(一九五五)年)版画家・詩人。東京生。東京美術学校中退。竹久夢二に私淑してドイツ表現派・ムンク・カンディンスキーの影響を受ける。大正三(一九一四)年に詩と版画の同人誌『月映』を創刊、同誌上に抽象木版画を発表して以来、日本の抽象絵画の先駆者として活躍した。大正六(一九一七)年に刊行された萩原朔太郎の詩集「月に吠える」の挿絵・装丁を手掛けて以後、多数の装本をも生業とし、昭和五(一九三〇)年のアルス社版「北原白秋全集」の装幀によって装本家の地位を確立した。日本創作版画協会や日本版画協会の創立に参加、大正・昭和期を通じて日本の近代版画の確立と普及、版画家の育成と国際美術展への参加等、版画界の発展に尽力した(平凡社「世界大百科事典」に拠る)。]
[やぶちゃん注:以下、奥付。周囲に箱と同じシャコバサボテンを模様のように配した多色刷りの非常に豪華なものである(近代出版物の洒落た奥付の三本指に入ると私は思っている)。なるべく似せたが、正式な配置は最後に配した画像で確認されたい。]
昭和十一年十二月二十六日印刷 藍 色 の 蟇
昭和十一年十二月 三十日發行 定價三圓八十錢
著作者 大 手 拓 次
編纂者 逸 見 享
東京市中野區宮前二五
販 權 發行者 北 原 鐡 雄
(逸見印) ・ 東京市神田區神保町三丁目
所 有 印刷者 山 本 英次郞
東京市牛込區東五軒町四〇
印刷所 山本源太郞印刷所
東京市牛込區東五軒町四〇
東京市 神田區 神保町三丁目 發行所
振替 東京 二四八八八番 ア ル ス
電話九段二一七五・二一七六